複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (86)
かしこ【恐・畏・賢】🔗⭐🔉
かしこ【恐・畏・賢】
(カシコシの語幹)
①おそれおおいこと。慎むべきこと。源氏物語若紫「あな―や、ひと日召し侍りしにやおはしますらむ」
②巧妙であるさま。うまいさま。源氏物語葵「草にも真名にも、さまざま、めづらしきさまに書きまぜ給へり。―の御手やと、空を仰ぎて、眺め給ふ」
③賢明なこと。利口。紫式部日記「われ―に思ひたる人」。東海道中膝栗毛6「こちやあほうじやない。―じやわい」
④手紙の末尾に書く語。恐惶謹言などと同意。「かしく」とも。多く、女性が用いる。
かしこ
 ⇒かしこ‐あらそい【賢争い】
⇒かしこ‐がお【賢顔】
⇒かしこ‐だて【賢立て】
⇒かしこ‐あらそい【賢争い】
⇒かしこ‐がお【賢顔】
⇒かしこ‐だて【賢立て】
 ⇒かしこ‐あらそい【賢争い】
⇒かしこ‐がお【賢顔】
⇒かしこ‐だて【賢立て】
⇒かしこ‐あらそい【賢争い】
⇒かしこ‐がお【賢顔】
⇒かしこ‐だて【賢立て】
かしこ‐あらそい【賢争い】‥アラソヒ🔗⭐🔉
かしこ‐あらそい【賢争い】‥アラソヒ
知恵をくらべあうこと。
⇒かしこ【恐・畏・賢】
かしこ・い【賢い】🔗⭐🔉
かしこ・い【賢い】
〔形〕[文]かしこ・し(ク)
(「畏かしこし」の転義)
①おそろしいほど明察の力がある。源氏物語桐壺「―・き相人」
②才知・思慮・分別などがきわだっている。源氏物語藤袴「さすがに―・くあやまちすまじくなどして」。「―・い判断」「―・い子」
③(生き物や事物の)性状・性能がすぐれている。すばらしい。大和物語「磐手の郡より奉れる御鷹よになく―・かりければ」。落窪物語1「―・き物をも買ひてけるかな。この箱の様に、今の世の蒔絵こそ更にかくせね」
④抜け目がない。巧妙である。利口だ。源氏物語帚木「また並ぶ人なくあるべきやうなど―・く教へ立つるかなと思ひ給へて」。「―・く立ち回る」
⑤尊貴である。たいそう大事である。源氏物語若菜上「―・き筋と聞ゆれど」。源氏物語若紫「うちに奉らむと―・ういつき侍りしを」→かしこきあたり。
⑥(めぐりあわせなどが)望ましい状態である。よい具合である。源氏物語若菜上「風吹かず、―・き日なりと興じて」
⑦(連用形を副詞的に用いて)非常に。はなはだしく。土佐日記「これかれ―・くなげく」
かしこ‐がお【賢顔】‥ガホ🔗⭐🔉
かしこ‐がお【賢顔】‥ガホ
①賢そうな顔つき。
②利口ぶる顔つき。
⇒かしこ【恐・畏・賢】
かしこ‐が・る【賢がる】🔗⭐🔉
かしこ‐が・る【賢がる】
〔自五〕
自分で賢いと思う。賢そうな態度をとる。
かしこ‐じま【賢島】🔗⭐🔉
かしこ‐じま【賢島】
三重県東部、志摩半島の南岸、英虞あご湾内の小島。橋で半島と結ばれ、志摩観光の拠点。
賢島
撮影:的場 啓


かしこ‐だて【賢立て】🔗⭐🔉
かしこ‐だて【賢立て】
賢いさまをよそおうこと。利口ぶること。さかしら。
⇒かしこ【恐・畏・賢】
かしこ‐どころ【賢所】🔗⭐🔉
かしこ‐どころ【賢所】
(恐れ多く、もったいない所の意)
①宮中で、天照大神の御霊代みたましろとして神鏡の八咫鏡やたのかがみを模した別の神鏡を祀ってある所。内侍所ないしどころともいった。平安時代は温明殿うんめいでんに、鎌倉時代以後は春興殿にあった。現在は皇居吹上地区にあり、神殿・皇霊殿と共に宮中三殿という。けんしょ。
②神鏡を指す称。平家物語11「如法夜半の事なれば…―をいだし奉るにも及ばず」
⇒かしこどころ‐おおまえ‐の‐ぎ【賢所大前の儀】
⇒かしこどころ‐みかぐら【賢所御神楽】
かしこどころ‐おおまえ‐の‐ぎ【賢所大前の儀】‥オホマヘ‥🔗⭐🔉
かしこどころ‐おおまえ‐の‐ぎ【賢所大前の儀】‥オホマヘ‥
即位礼に際し、天皇が即位したことを自ら賢所に告げる儀式。
⇒かしこ‐どころ【賢所】
かしこどころ‐みかぐら【賢所御神楽】🔗⭐🔉
かしこどころ‐みかぐら【賢所御神楽】
宮中の小祭の一つ。毎年12月中旬、賢所の前庭で庭燎にわびをたいて行われる神楽。
⇒かしこ‐どころ【賢所】
けん【賢】🔗⭐🔉
けん【賢】
①かしこいこと。学才・徳行のすぐれた人。
②(「聖」が清酒を意味するのに対していう)にごり酒。
③相手に対して敬意をあらわす語。「諸―」
けん‐おう【賢王】‥ワウ🔗⭐🔉
けん‐おう【賢王】‥ワウ
賢明な君主。
けん‐ぐ【賢愚】🔗⭐🔉
けん‐ぐ【賢愚】
賢いことと愚かなこと。賢者と愚者。
けんぐ‐きょう【賢愚経】‥キヤウ🔗⭐🔉
けんぐ‐きょう【賢愚経】‥キヤウ
(ゲングキョウとも)北魏の慧覚えかくらの訳した経。13巻。仏教比喩文学の代表的経典で、賢者・愚者に対する69の説話を説く。詳しくは「賢愚因縁経」。
けん‐くん【賢君】🔗⭐🔉
けん‐くん【賢君】
賢い君主。
けん‐けい【賢兄】🔗⭐🔉
けん‐けい【賢兄】
①他人の兄の尊敬語。
②手紙などで、同輩または年上の男子を敬って呼ぶ語。
けん‐ごう【賢豪】‥ガウ🔗⭐🔉
けん‐ごう【賢豪】‥ガウ
賢くてすぐれていること。また、その人。
げん‐ごう【賢劫】‥ゴフ🔗⭐🔉
げん‐ごう【賢劫】‥ゴフ
(ケンゴウとも)〔仏〕現在の住劫。今の世。千仏などの賢人がこの世に出現し衆生しゅじょうを救うからいう。
けん‐さ【賢佐】🔗⭐🔉
けん‐さ【賢佐】
かしこい補佐。良佐。
けん‐さい【賢才】🔗⭐🔉
けん‐さい【賢才】
すぐれた才知。また、その才知ある人。
けん‐さい【賢妻】🔗⭐🔉
けん‐さい【賢妻】
かしこい妻。
けん‐さい【賢宰】🔗⭐🔉
けん‐さい【賢宰】
賢明な宰相。賢相。
けん‐さつ【賢察】🔗⭐🔉
けん‐さつ【賢察】
相手の推察の尊敬語。お察し。高察。
けん‐し【賢士】🔗⭐🔉
けん‐し【賢士】
賢い人士。すぐれた人。
けん‐じゃ【賢者】🔗⭐🔉
けん‐じゃ【賢者】
(ケンシャとも)
①かしこい人。賢人。
②仏道を修行して、いまだ悟りを得るまでにはいたっていない人。↔聖者しょうじゃ。
⇒けんじゃ‐だて【賢者立て】
⇒けんじゃ‐の‐いし【賢者の石】
⇒賢者ひだるし伊達寒し
けんじゃ‐だて【賢者立て】🔗⭐🔉
けんじゃ‐だて【賢者立て】
賢者ぶること。かしこそうにふるまうこと。
⇒けん‐じゃ【賢者】
けんじゃ‐の‐いし【賢者の石】🔗⭐🔉
けんじゃ‐の‐いし【賢者の石】
物質を金に化したり、万病を癒したりする力をもつと信じられた物質。西洋中世の錬金術師たちの探し求めたもの。「哲学者の石」ともいう。
⇒けん‐じゃ【賢者】
○賢者ひだるし伊達寒しけんじゃひだるしだてさむし
賢者は俗人と協調しないために飢え、伊達者だてしゃはみえを張るために薄着して寒い思いをする。世俗と違った行いをする人はつらい目にあうの意。また、やせがまんは愚であるの意。
⇒けん‐じゃ【賢者】
○賢者ひだるし伊達寒しけんじゃひだるしだてさむし🔗⭐🔉
○賢者ひだるし伊達寒しけんじゃひだるしだてさむし
賢者は俗人と協調しないために飢え、伊達者だてしゃはみえを張るために薄着して寒い思いをする。世俗と違った行いをする人はつらい目にあうの意。また、やせがまんは愚であるの意。
⇒けん‐じゃ【賢者】
げんしゃ‐ほう【現写法】‥ハフ
(→)現在法に同じ。
けん‐しゅ【巻鬚】
⇒まきひげ
けん‐しゅ【拳酒】
⇒けんざけ
けん‐しゅ【堅守】
かたく守ること。
けん‐しゅ【賢主】
賢明な君主。賢君。
けん‐しゅ【賢酒】
にごり酒の異称。→賢人
けん‐しゅ【黔首】
[史記秦始皇本紀](「黔」は黒色。昔、中国で人民は冠物かぶりものをせず、黒髪を出していたからいう)人民。庶民。黎民。たみくさ。→黔黎けんれい
けん‐しゅ【懸珠】
[漢書東方朔伝]目の光の明らかなことのたとえ。珠飾りのような美しい目。
けん‐じゅ【剣樹】
〔仏〕枝葉・花果がすべて刀剣から成るという地獄の樹木。
⇒けんじゅ‐じごく【剣樹地獄】
けん‐じゅ【献寿】
長寿を祝って品物や言葉を贈ること。
けん‐じゅ【賢首】
①(仏典で)敬意をもった呼びかけの語。
②(ゲンジュとも)法蔵ほうぞうの大師号。
けん‐じゅ【賢衆】
賢聖けんじょうの人々。高僧の称。賢聖衆。
げん‐しゅ【元首】
一国を代表する資格をもった首長。君主国では君主、共和国では大統領あるいは最高機関の長など。
⇒げんしゅ‐せいじ【元首政治】
げん‐しゅ【玄趣】
幽玄なおもむき。
げん‐しゅ【原酒】
①醪もろみを圧搾した後、加水調整をしていない清酒。
②蒸留のすんだあと、熟成させるため一定期間樽詰にして貯蔵したウィスキーなどの原液。
げん‐しゅ【原種】
①種を取るためにまく種。育成種の種子。
②品種改良以前の、原型である動植物。
げん‐しゅ【厳守】
きびしく守ること。「時間―」
けん‐しゅう【研修】‥シウ
①学問や技芸などをみがきおさめること。
②現職教育。「―生」
けん‐しゅう【兼修】‥シウ
二つ以上のことをかねおさめること。兼学。
けん‐しゅう【検収】‥シウ
納品された品が注文通りであることを確かめた上で受け取ること。
けん‐しゅう【献酬】‥シウ
盃をやりとりすること。夏目漱石、こゝろ「空の盃でよくああ飽きずに―が出来ると思ひますわ」
けん‐しゅう【顕宗】
〔仏〕(→)顕教けんぎょうに同じ。↔密宗
けんじゅう【犬戎】
周代、中国の北西辺境に住んだ異民族。→玁狁けんいん
けん‐じゅう【拳銃】
ピストル。
けん‐じゅう【傔従】
おそばつきの家来。従者。
げん‐しゅう【玄宗】
玄妙な宗旨。奥深い宗門。
げん‐しゅう【現収】‥シウ
現在の収入。
げん‐しゅう【減収】‥シウ
収入や収穫の減ること。「―減益」↔増収
げん‐じゅう【幻獣】‥ジウ
竜・鵺ぬえ・一角獣などの空想上の生物。
げん‐じゅう【現住】‥ヂユウ
①現在そこに居住すること。また、その住居。「―地」
②〔仏〕
㋐現世。
㋑寺の現在の住職。現住職。
⇒げんじゅう‐しょ【現住所】
⇒げんじゅう‐みん【現住民】
げん‐じゅう【還住】‥ヂユウ
もとの地にかえって住むこと。〈日葡辞書〉
げん‐じゅう【厳重】‥ヂユウ
①⇒げんじょう。
②きびしいこと。「―な警戒」
げんじゅう‐あん【幻住庵】‥ヂユウ‥
蕉門の俳人菅沼曲水の伯父幻住老人が、今の大津市国分に結んだ草庵。
⇒げんじゅうあん‐の‐き【幻住庵記】
げんじゅうあん‐の‐き【幻住庵記】‥ヂユウ‥
俳文。芭蕉作。元禄3年(1690)4月から7月まで滞在した幻住庵についての記。一所不住の議論で結ぶ。同年8月成る。翌年刊「猿蓑」所収。
→文献資料[幻住庵記]
⇒げんじゅう‐あん【幻住庵】
げんじゅう‐しょ【現住所】‥ヂユウ‥
現在居住している所。
⇒げん‐じゅう【現住】
けんしゅう‐じょちょく【建州女直】‥シウヂヨ‥
明代満州南東部に住んだ女直の一部。女真族の後裔。明末ヌルハチが出て女直諸部を統一、後金国(後の清)を建てた。→女直
げんじゅう‐みん【現住民】‥ヂユウ‥
現在その土地に住んでいる人。
⇒げん‐じゅう【現住】
げんじゅう‐みん【原住民】‥ヂユウ‥
その土地に、もとから住んでいた民。
けんじゅ‐がくは【犬儒学派】
キニク学派の別称。キニクはギリシア語で「犬のような」の意のkynikosに基づいた語で、犬のような乞食生活をしたことからの称。
げん‐しゅく【減縮】
減らしちぢめること。減りちぢまること。
げん‐しゅく【厳粛】
①おごそかで、心が引きしまるさま。厳格で静粛なこと。「式は―に執り行われた」「―な雰囲気」
②それを真剣に受け取らなければならないさま。厳として動かしがたいこと。「―に受けとめる」「―な事実」
⇒げんしゅく‐しゅぎ【厳粛主義】
げんしゅく‐しゅぎ【厳粛主義】
〔哲〕(rigorism)道徳法則を厳格に守る態度。ストア学派のように、義務を至上として欲望をおさえ、快楽や幸福を拒む立場。カントの倫理学では、道徳的意志の動機として幸福や快楽を認めない。厳格主義。リゴリズム。
⇒げん‐しゅく【厳粛】
けんしゅくりょうこしゅう【蜆縮涼鼓集】‥リヤウ‥シフ
仮名遣書。2冊。鴨東蔌父と自称する者の著。1695年(元禄8)成る。「しじみ」「ちぢみ」「すずみ」「つづみ」の「じ」「ぢ」「ず」「づ」、いわゆる四つ仮名の使い方を示す。仮名文字使蜆縮涼鼓集。→四つ仮名
けんじゅ‐じごく【剣樹地獄】‥ヂ‥
(→)剣林地獄に同じ。
⇒けん‐じゅ【剣樹】
げんしゅ‐せいじ【元首政治】‥ヂ
(principatus ラテン)古代ローマの共和精神を加味した帝政。アウグストゥスから3世紀に至る時代の政治制度で、専制政治とは区別される。プリンキパトゥス。
⇒げん‐しゅ【元首】
けん‐しゅつ【検出】
検査して見つけ出すこと。「大量の菌が―される」
けん‐じゅつ【剣術】
刀剣を手にして敵に当たる技術。練習には多く木剣を用いる。剣法。撃剣。→剣道。
⇒けんじゅつ‐つかい【剣術使い】
げん‐しゅつ【幻出】
まぼろしのように現れること。
げん‐しゅつ【現出】
あらわれ出ること。あらわし出すこと。出現。「珍しい光景が―する」
げん‐じゅつ【幻術】
①人の目をくらます妖術。浄瑠璃、傾城島原蛙合戦「―自在の四郎雲霧にまぎれて失せにけり」
②手品。
げん‐じゅつ【言述】
ことばで述べること。言説。
げん‐じゅつ【験術】
不思議な霊験をあらわす術。
けんじゅつ‐つかい【剣術使い】‥ツカヒ
剣術に巧みな人。
⇒けん‐じゅつ【剣術】
けん‐しゅん【険峻・嶮峻】
山の高くてけわしいこと。また、その場所。
けん‐しゅん【賢俊】
賢くすぐれていること。また、その人。
げん‐しゅん【厳峻】
おごそかできびしいこと。
けんしゅん‐もん【建春門】
平安京内裏の外郭門の一つ。東面中央、内郭の宣陽門に対する。外記門げきもん。左衛門の陣。→内裏(図)
けんしゅん‐もんいん【建春門院】‥ヰン
後白河天皇の女御平滋子。高倉天皇の母。1169年(嘉応1)院号宣下。(1142〜1176)
⇒けんしゅんもんいんちゅうなごん‐にっき【建春門院中納言日記】
けんしゅんもんいんちゅうなごん‐にっき【建春門院中納言日記】‥ヰン‥
藤原俊成の女むすめ、建春門院中納言(1157〜 )が63歳のとき、かつて宮仕えをした日々を回想したもの。奥書の後に定家が反故から拾い集めた補遺部がある。別名、たまきはる・健寿御前日記。
⇒けんしゅん‐もんいん【建春門院】
けん‐しょ【見所】
(ケンジョとも)
①見物の場所。また、見物人。風姿花伝「―の御意見を待つべき」
②能楽で、みどころ。花鏡「目ききの見出す―にあるべし」
けん‐しょ【券書】
契約の証文。手形。証書。券状。
けん‐しょ【険所・嶮所】
けわしい場所。
けん‐しょ【賢所】
⇒かしこどころ
けん‐じょ【見証・見所】
⇒けんぞ
けん‐じょ【建除】‥ヂヨ
暦注の十二直じゅうにちょくのこと。建除十二神。
けん‐じょ【巻舒】
①巻いたりのばしたりすること。
②才徳をかくすこととあらわすこと。また、進退、屈伸。
けん‐じょ【慊如】
あきたらなく思うさま。慊焉けんえん。
けん‐じょ【賢女】‥ヂヨ
かしこい女。徒然草「もし―あらば、それもものうとく、すさまじかりなん」
⇒けんじょ‐ごかし【賢女倒し】
⇒けんじょ‐だて【賢女立て】
げん‐しょ【原初】
いちばん初め。おおもと。「―形態」
⇒げんしょ‐じょうたい【原初状態】
げん‐しょ【原書】
書写本・翻訳書などに対して、もとの書籍。原本。特に、欧文の書物。洋書。三遊亭円朝、英国孝子之伝「―をお読み遊ばした方は御存じのことで御座いませうが」。「―講読」
げん‐しょ【厳暑】
きびしい暑さ。
けん‐しょう【見性】‥シヤウ
(禅宗の語)自己の本来の心性を見極めること。→直指人心見性成仏じきしにんしんけんしょうじょうぶつ。
⇒けんしょう‐じょうぶつ【見性成仏】
けん‐しょう【見証】
⇒けんぞ
けん‐しょう【肩章】‥シヤウ
有爵者および文武官の制服の肩に飾りつけるしるし。官職・等級によって区別がある。
けん‐しょう【兼掌】‥シヤウ
二つ以上の事を兼ねつかさどること。
けん‐しょう【剣匠】‥シヤウ
刀鍛冶かたなかじ。
けん‐しょう【健訟】
[易経訟卦]好んで訴訟をすること。公事くじ好き。好訟。
けん‐しょう【健勝】
(相手の)健康がすぐれてすこやかなこと。「先生には御―の御事とお慶び申し上げます」
けん‐しょう【検証】
(verification)
①実際に調べて証明すること。
②〔論〕ある仮説から論理的に導き出された結論を、事実の観察や実験の結果と照らし合わせて、その仮説の真偽を確かめること。
③〔法〕証拠資料たる事物・場所の在否および状態を裁判官や捜査機関が直接確かめる行為。「現場―」
⇒けんしょう‐ぶつ【検証物】
けん‐しょう【腱鞘】‥セウ
腱の外囲を筒状に包む結合組織性の鞘さや。手や足に見られる。
⇒けんしょう‐えん【腱鞘炎】
けん‐しょう【憲章】‥シヤウ
①重要なおきて。原則的なおきて。「児童―」
②憲法の典章。
けん‐しょう【縑緗】‥シヤウ
書物を表装するのに用いる薄い絹。転じて、書物。
けん‐しょう【賢相】‥シヤウ
賢明な宰相。すぐれた大臣。
けん‐しょう【賢将】‥シヤウ
賢明な将軍。
けん‐しょう【謙称】
相手に対してへりくだった言い方。「小生」「愚息」の類。
けん‐しょう【顕正】‥シヤウ
〔仏〕正しい真理をあらわし示すこと。「破邪―」
けんしょう【顕昭】‥セウ
平安末〜鎌倉初期の歌人・歌学者。藤原顕輔の猶子。僧位は法橋。博覧宏識、六条家歌学の大成者。考証注釈に長じ、その歌風には理知の冴えが見える。著「古今集註」「袖中抄」など。(1130頃〜1210頃)
けん‐しょう【顕証】
⇒けそう
けん‐しょう【顕彰】‥シヤウ
明らかにあらわれること。明らかにあらわすこと。功績などを世間に知らせ、表彰すること。「―碑」
けん‐しょう【顕賞】‥シヤウ
功を明らかにし賞すること。
けん‐しょう【懸章】‥シヤウ
陸軍の副官・週番士官・巡察将校などが、右肩から左脇にかけて佩用した飾りじるし。
けん‐しょう【懸賞】‥シヤウ
(ある物を募り、また人や物を探すために)賞品や賞金をかけること。また、その賞。「―小説」
けん‐じょう【券状】‥ジヤウ
手形。証文。券書。
けん‐じょう【傔仗】‥ヂヤウ
奈良・平安時代、鎮守府将軍・大宰帥・按察使あぜち・陸奥出羽国守など、辺境の官人につけられた護衛の武官。
けん‐じょう【喧擾】‥ゼウ
さわぎ乱れること。騒擾。
けん‐じょう【堅城】‥ジヤウ
防備の堅固な城。
けん‐じょう【勧賞】‥ジヤウ
(カンショウ・カンジョウとも)功労を賞して官位を授け、または物を賜ること。今昔物語集14「阿闍梨に―を給はる事」
けん‐じょう【献上】‥ジヤウ
①さしあげること。たてまつること。〈文明本節用集〉。「特産品を―する」
②献上博多の略。
⇒けんじょう‐がし【献上菓子】
⇒けんじょう‐の‐かも【献上の鴨】
⇒けんじょう‐はかた【献上博多】
⇒けんじょう‐もの【献上物】
けん‐じょう【賢聖】‥ジヤウ
(ゲンジョウとも)
①賢人と聖人。知徳のすぐれた人。けんせい。
②〔仏〕悪を離れて良い行いはできるが、まだ悟りの開けない凡夫ぼんぶを賢、悟りを開いた者を聖とする。三賢十聖、四十二賢聖、二十七賢聖などがある。
⇒けんじょう‐の‐そうじ【賢聖障子】
けん‐じょう【謙譲】‥ジヤウ
へりくだりゆずること。謙遜。「―の美徳」
⇒けんじょう‐ご【謙譲語】
げん‐しょう【元宵】‥セウ
陰暦正月15日の夜。元夕。
⇒げんしょう‐せつ【元宵節】
げん‐しょう【言笑】‥セウ
物を言うことと笑うこと。うちとけて笑いながら物を言うこと。
げん‐しょう【弦誦・絃誦】
弦歌と誦読。琴をひき、詩をうたうこと。転じて、学芸に励むさま。
げん‐しょう【現生】‥シヤウ
(→)現世げんせに同じ。
げん‐しょう【現象】‥シヤウ
〔哲〕(phenomenon)
①観察されうるあらゆる事実。「自然―」
②本質との相関的な概念として、本質の外面的な現れ。↔本質↔本体。
③カントの用法では、時間・空間やカテゴリーに規定されて現れているもの。これは主観の構成が加ったもので、構成される以前の物自体は認識されえないとした。↔物自体。
④フッサール現象学では、純粋意識の領野に現われる志向的対象としての世界。
⇒げんしょう‐がく【現象学】
⇒げんしょうがくてき‐かんげん【現象学的還元】
⇒げんしょうがくてき‐しゃかいがく【現象学的社会学】
⇒げんしょう‐くうかん【現象空間】
⇒げんしょう‐しゅぎ【現象主義】
⇒げんしょう‐ろん【現象論】
げん‐しょう【舷墻】‥シヤウ
波浪や風から旅客・船員を保護するため、甲板の舷側に設けた鋼板の囲い板。ブルワーク。
げん‐しょう【減少】‥セウ
減って少なくなること。減らして少なくすること。「人口が―する」↔増加。
⇒げんしょう‐かんすう【減少関数】
げん‐しょう【減省】‥シヤウ
減らしはぶくこと。げんせい。
げんし‐よう【原子容】
単体の原子1モルが占める体積。
⇒げん‐し【原子】
げんじょう【玄奘】‥ジヤウ
唐代の僧。法相宗・倶舎宗の開祖。河南の人。629年長安を出発し、天山南路からインドに入り、ナーランダー寺の戒賢らに学び、645年帰国後、「大般若経」「倶舎論」「成唯識論」など多数の仏典を翻訳。玄奘以前の訳を旧訳くやくとし、玄奘以後の新訳と区別する。「大唐西域記」はその旅行記。「西遊記」はこの旅行記に取材したもの。玄奘三蔵。三蔵法師。(602〜664)
げんじょう【玄象・玄上】‥ジヤウ
①琵琶の名器の名。比類ない霊物と称せられ、逸話に富む。枕草子93「御琴も笛も、みなめづらしき名つきてぞある。―・牧馬・井手…など」
②(「絃上」とも書く)能。藤原師長が琵琶の奥義を究めるため入唐しようとするのを、村上天皇の霊が現れてとどめ、玄象と並ぶ琵琶の名器獅子丸を竜宮から持参させて授ける。けんじょう。
げん‐じょう【原状】‥ジヤウ
もとのままのありさま。以前の形。
⇒げんじょう‐かいふく【原状回復】
げん‐じょう【現成・見成】‥ジヤウ
〔仏〕実現すること。または、実現されて眼前に提示されていること。
⇒げんじょう‐こうあん【現成公案】
⇒げんじょう‐はん【現成飯】
げん‐じょう【現状】‥ジヤウ
現在の状態。現況。「―維持」
げん‐じょう【現場】‥ヂヤウ
物事の現に行われ、または既に行われた場所。げんば。
⇒げんじょう‐ふざい‐しょうめい【現場不在証明】
げん‐じょう【眼象】‥ジヤウ
(→)牙象げじょうに同じ。
げん‐じょう【還昇】
(カンジョウ・ゲンジョとも)(→)還殿上かえりてんじょう1に同じ。
げん‐じょう【厳重】‥ヂヨウ
おごそかなこと。いかめしいこと。増鏡「臨幸の―なる事も侍らんに参りあへらば」
けんしょう‐えん【腱鞘炎】‥セウ‥
腱鞘の炎症。細菌感染、機械的刺激、手や指の過労などによって起こり、疼痛・腫脹を主徴とする。キー‐パンチャー・プログラマー・ピアニストなどの職業病としても知られる。
⇒けん‐しょう【腱鞘】
げんじょう‐かいふく【原状回復】‥ジヤウクワイ‥
〔法〕結果として生じている現在の状態を、それを生じさせた原因以前の状態に戻すこと。
⇒げん‐じょう【原状】
げんしょう‐がく【現象学】‥シヤウ‥
(Phänomenologie ドイツ)古くは本体と区別された現象の学という意味に用いられた語。今日行われているのはヘーゲルとフッサールの用法。
①ヘーゲルは精神の最も単純直接な現われとしての感覚的確実性から最高の現われとしての絶対知に到達するまでの、精神の弁証法的発展を論じた彼の著作を「精神現象学」と名づけた。
②哲学や科学の確実な基礎をすえるために、一切の先入見を排して意識に直接に明証的に現れている現象を直観し、その本質を記述するフッサールの方法。彼はそれに到達するため日常的見方の土台にある外界の実在性について判断停止を行い、そのあとに残る純粋意識を分析し記述した。以後、ケルゼンの法現象学、ミュンヘン現象学派やインガルデン(R. Ingarden1893〜1970)・デュフレンヌ(M. Dufrenne1910〜1995)らの美学、ハイデガーからサルトルへ至る現象学的存在論、メルロ=ポンティの身体性の現象学など、20世紀哲学・美学の主潮流の一つ。
⇒げん‐しょう【現象】
げんしょうがくてき‐かんげん【現象学的還元】‥シヤウ‥クワン‥
フッサール現象学の基本的方法。世界に対するわれわれの認識態度を根本的に変更する方法的手続きをいう。世界の存在を素朴に前提にする自然的態度をやめ、世界の存在意味が構成される場(純粋意識)へと眼差しを向け変えて超越論的態度へ移行すること。
⇒げん‐しょう【現象】
げんしょうがくてき‐しゃかいがく【現象学的社会学】‥シヤウ‥クワイ‥
フッサールの現象学の方法や概念・発想を取り入れようとする社会学の立場。フィーアカント(A. Vierkandt1867〜1953)やリット(T. Litt1880〜1962)のように、演繹的でア‐プリオリな内的直観によって社会結合の本質を捉えようとする立場と、シュッツに代表される、人が日常生活の現実を構成する仕方を捉えようとする立場とがある。
⇒げん‐しょう【現象】
けんじょう‐がし【献上菓子】‥ジヤウグワ‥
室町時代、白砂糖を用いた上等な菓子。雑菓子ぞうがしに対していう。
⇒けん‐じょう【献上】
げんしょう‐かんすう【減少関数】‥セウクワン‥
変数の値が増加すると、値が減少する関数。
⇒げん‐しょう【減少】
げんしょう‐くうかん【現象空間】‥シヤウ‥
(phenomenal space)物理的空間と異なり、客観的にではなく、主観的に心的活動者たる個人に把握される空間。
⇒げん‐しょう【現象】
けんじょう‐ご【謙譲語】‥ジヤウ‥
(通例の分類による)敬語の一つ。話し手(書き手)が、自身および自身の側の事物や動作を、他に対する卑下謙譲を含ませて表現する語。「見る」を「拝見する」、「行く」を「参る」、「言う」を「申し上げる」という類。→敬語
⇒けん‐じょう【謙譲】
げんじょう‐こうあん【現成公案】‥ジヤウ‥
①禅語。眼前に提示された公案。目の前に突きつけられた問題。道元においては、この世界の一切の現象がそのまま絶対の真理であることが現成公案と呼ばれる。
②「正法眼蔵」の巻名。
⇒げん‐じょう【現成・見成】
げんしょう‐こうい【玄裳縞衣】‥シヤウカウ‥
[蘇軾、後赤壁賦]黒いはかまと白い上衣。白黒の羽を衣裳にたとえた、鶴の姿の形容。
けんしょう‐しつ【顕晶質】‥シヤウ‥
岩石を構成する鉱物の粒の大きさが、肉眼または虫眼鏡で見える程度に大きいことを示す語。深成岩はすべて顕晶質。
けんじょう‐しゃ【健常者】‥ジヤウ‥
(障害者に対して)障害がなく健康な人。
げんしょう‐しゅぎ【現象主義】‥シヤウ‥
(phenomenalism)物の本体は認識できないと考え、感覚的に知覚された現象のみで満足するか、または現象の背後の本体という考えをも否定して、意識に直接与えられているものだけを実在と認める立場。唯現象論。
⇒げん‐しょう【現象】
けんしょう‐じょうぶつ【見性成仏】‥シヤウジヤウ‥
自己の本性である本来清浄な心を見得して悟りを得ること。禅宗の主張。
⇒けん‐しょう【見性】
げんしょう‐せつ【元宵節】‥セウ‥
中国で元宵に行われる祭。その夜美しく飾った灯籠を見物し、だんごを食べる。
⇒げん‐しょう【元宵】
げんしょう‐てんのう【元正天皇】‥シヤウ‥ワウ
奈良時代前期の女帝。草壁皇子の第1王女。母は元明天皇。名は氷高ひだか。(在位715〜724)(680〜748)→天皇(表)
けんじょう‐の‐かも【献上の鴨】‥ジヤウ‥
(江戸時代に、将軍へ献上する鴨の脚を白紙で巻き包んだからいう)着物がきたないのに、足や足袋ばかりが新しく白いのをあざけっていう語。
⇒けん‐じょう【献上】
けんじょう‐の‐そうじ【賢聖障子】‥ジヤウ‥サウ‥
紫宸殿の母屋と北廂きたびさしとを隔てる障子しょうじ。東西各4間あり、中国の三代から唐までの聖賢・名臣32人の肖像を描く。東方に馬周・房玄齢・杜如晦・魏徴・諸葛亮・蘧伯玉きょはくぎょく・張良・第五倫・管仲・鄧禹とうう・子産・蕭何しょうか・伊尹いいん・傅説ふえつ・太公望・仲山甫、西方に李勣りせき・虞世南・杜預・張華・羊祜ようこ・揚雄・陳寔ちんしょく・班固・桓栄・鄭玄・蘇武・倪寛げいかん・董仲舒とうちゅうじょ・文翁・賈誼かぎ・叔孫通。
⇒けん‐じょう【賢聖】
けんじょう‐はかた【献上博多】‥ジヤウ‥
(黒田藩主から江戸幕府に献上したからいう)福岡県博多で織られてきた独鈷華皿どっこはなざらと呼ばれる幾何文様に縞文様を織り出した帯地。細い経糸たていとで文様を織り出すのが特徴。献上。
⇒けん‐じょう【献上】
げんじょう‐はん【現成飯】‥ジヤウ‥
〔仏〕できあいの飯。
⇒げん‐じょう【現成・見成】
げんじょう‐ふざい‐しょうめい【現場不在証明】‥ヂヤウ‥
(→)アリバイのこと。
⇒げん‐じょう【現場】
けんしょう‐ぶつ【検証物】
検証の対象となる人または物。
⇒けん‐しょう【検証】
けんじょう‐もの【献上物】‥ジヤウ‥
献上する品物。特に、江戸時代、将軍から朝廷へ、また、諸侯から将軍に奉った品物。
⇒けん‐じょう【献上】
げんじょう‐らく【還城楽】‥ジヤウ‥
(見蛇楽けんじゃらくの転ともいう)雅楽。唐楽に属する林邑楽りんゆうがく系で、太食たいしき調の曲。舞楽にも管弦にも用いる。一説に西域の胡人が蛇を見つけて歓喜勇躍する様を表すという。一人舞。赤顔・深目で釣顎つりあごの仮面をつけ、1尺1寸の桴ばちを持ち、途中から舞台に置かれた金色の木製の蛇を持って躍る。
還城楽
 げんしょう‐ろん【現象論】‥シヤウ‥
①現象主義。
②実際に現象として現れたことのみに基づいて論ずること。「―としては間違っていない」
⇒げん‐しょう【現象】
けん‐しょく【兼職】
本職以外に他の職を兼ねること。また、兼務の職。
けん‐しょく【顕職】
位の高い官職。高官。要職。
けん‐じょく【見濁】‥ヂヨク
〔仏〕五濁の一つ。末世になり、邪見が盛んになり、世を濁乱すること。
げん‐しょく【言色】
ことばつきと顔色。
げん‐しょく【言職】
言論を以て仕える職。諫言かんげんまたは建言を役目とする職務。
げん‐しょく【原色】
①他の色を生み出すもととなる色。適当な割合に混ぜることによってすべての色を表せる三つの異なった色。その一つが他の二つの混合で生じ得ない限り、任意に選ぶことができるが、実用的には赤・緑・青(青紫)の三つ(光の三原色)が選ばれる。絵具のような吸収媒質を混ぜるときはシアン(青緑)・マゼンタ(赤紫)・黄の3色が選ばれる。(絵具の三原色)
②三原色またはそれに近いはっきりした色。あざやかで派手な色。
③印刷などで、もとのままの色。「―に近い色を出す」「―植物図鑑」
⇒げんしょく‐ばん【原色版】
げん‐しょく【原職】
一時的に離れていた、もとの職務。
げん‐しょく【現職】
現在ついている職務・職業。また、ある職務に現についていること。「―にとどまる」
⇒げんしょく‐きょういく【現職教育】
げん‐しょく【減食】
①食事の量・回数をへらすこと。
②〔法〕受刑者などに対する懲罰として、7日以内の食糧の分量を減ずる制裁。2005年監獄法改正により廃止。
げんしょく‐きょういく【現職教育】‥ケウ‥
現に職業に従事している者に対して現職のまま行われる教育。研修。
⇒げん‐しょく【現職】
げんしょく‐ばん【原色版】
カラー印刷法の一つ。三原色(シアン・マゼンタ・黄)と黒の4色のインクを用いて原画と同じような色彩を出す網目凸版印刷。また、その印刷物。原画を4色に分解撮影した4枚のネガから、おのおの網版を作り、それぞれの色インクで刷り重ねる。高級美術印刷に使用。四色版。
⇒げん‐しょく【原色】
げんしょく‐ほう【減色法】‥ハフ
減法混色法の略。シアン・マゼンタ・黄の三原色を適当に混ぜるか重ね合わせることにより、目的とする色を作りだす方法。カラー写真・映画、カラー印刷などに応用。
けんじょ‐ごかし【賢女倒し】‥ヂヨ‥
相手を賢女だと言いはやすこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
げんしょ‐じょうたい【原初状態】‥ジヤウ‥
〔哲〕ロールズの用語。社会契約説における自然状態を、正義の基本原理を合意によって採択するための平等な討議の場として読み替えたもの。討議の参加者は自分の社会的地位・資産・能力などについて知らない(無知のベール)とされる。
⇒げん‐しょ【原初】
けんじょ‐だて【賢女立て】‥ヂヨ‥
賢女らしくふるまうこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
げん‐しょろう【現所労】‥ラウ
現在病気であること。平家物語4「典薬頭定成こそ…―とて参らず」
げんし‐りょう【原子量】‥リヤウ
天然の元素の原子の相対的な質量を一定の基準に基づいて表したもの。以前は天然の酸素を基準にとり、その原子量を16とした。1961年以降は質量数12の炭素原子を基準にとり、その原子質量を12として他の元素の原子の質量を表す。
⇒げん‐し【原子】
げんし‐りょく【原子力】
(→)核エネルギーに同じ。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐いいんかい【原子力委員会】‥ヰヰンクワイ
(Atomic Energy Commission)原子力の軍事的利用を管理し平和的開発を促進する目的をもつ委員会。国連内に1946年1月発足、52年1月国連軍縮委員会に吸収。これとは別に、各国にもそれぞれ設置され、日本では、平和利用に限るものが、56年に設立された。AEC →国際原子力機関。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐きほんほう【原子力基本法】‥ハフ
原子力に対する日本の基本的な考え方を法制化したもの。原子力の研究・開発やエネルギー資源の確保などについて定める。1955年制定。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐さんげんそく【原子力三原則】
日本における原子力の研究・開発・利用に関する自主・民主・公開の三つの原則。1954年の日本学術会議総会で決議され、原子力基本法に採り入れられた。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐せん【原子力船】
原子力を動力とする船。日本船としては「むつ」があった。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐せんすいかん【原子力潜水艦】
原子力を動力とする潜水艦。原潜。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐でんち【原子力電池】
放射性同位体から発生する放射線のエネルギーを利用した電池。ストロンチウム90のように長い半減期をもつ同位体を用いることにより寿命の長い安定した電源が得られる。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐はつでん【原子力発電】
原子炉で発生する熱エネルギーを利用した発電。
⇒げん‐し【原子】
げんし‐りん【原始林】
(→)原生林に同じ。
⇒げん‐し【原始】
けん・じる【献じる】
〔他上一〕
(→)「献ずる」に同じ。
げん・じる【減じる】
〔自他上一〕
(→)「減ずる」に同じ。
げんし‐ろ【原子炉】
ウラン235・プルトニウム239などの原子核分裂の連鎖反応を、制御しながら持続させるようにした装置。天然ウラン黒鉛型と軽水型に大別され、後者には加圧水型(PWR)と沸騰水型(BWR)とがある。目的により、研究用・発電用・医療用などがある。
原子炉
げんしょう‐ろん【現象論】‥シヤウ‥
①現象主義。
②実際に現象として現れたことのみに基づいて論ずること。「―としては間違っていない」
⇒げん‐しょう【現象】
けん‐しょく【兼職】
本職以外に他の職を兼ねること。また、兼務の職。
けん‐しょく【顕職】
位の高い官職。高官。要職。
けん‐じょく【見濁】‥ヂヨク
〔仏〕五濁の一つ。末世になり、邪見が盛んになり、世を濁乱すること。
げん‐しょく【言色】
ことばつきと顔色。
げん‐しょく【言職】
言論を以て仕える職。諫言かんげんまたは建言を役目とする職務。
げん‐しょく【原色】
①他の色を生み出すもととなる色。適当な割合に混ぜることによってすべての色を表せる三つの異なった色。その一つが他の二つの混合で生じ得ない限り、任意に選ぶことができるが、実用的には赤・緑・青(青紫)の三つ(光の三原色)が選ばれる。絵具のような吸収媒質を混ぜるときはシアン(青緑)・マゼンタ(赤紫)・黄の3色が選ばれる。(絵具の三原色)
②三原色またはそれに近いはっきりした色。あざやかで派手な色。
③印刷などで、もとのままの色。「―に近い色を出す」「―植物図鑑」
⇒げんしょく‐ばん【原色版】
げん‐しょく【原職】
一時的に離れていた、もとの職務。
げん‐しょく【現職】
現在ついている職務・職業。また、ある職務に現についていること。「―にとどまる」
⇒げんしょく‐きょういく【現職教育】
げん‐しょく【減食】
①食事の量・回数をへらすこと。
②〔法〕受刑者などに対する懲罰として、7日以内の食糧の分量を減ずる制裁。2005年監獄法改正により廃止。
げんしょく‐きょういく【現職教育】‥ケウ‥
現に職業に従事している者に対して現職のまま行われる教育。研修。
⇒げん‐しょく【現職】
げんしょく‐ばん【原色版】
カラー印刷法の一つ。三原色(シアン・マゼンタ・黄)と黒の4色のインクを用いて原画と同じような色彩を出す網目凸版印刷。また、その印刷物。原画を4色に分解撮影した4枚のネガから、おのおの網版を作り、それぞれの色インクで刷り重ねる。高級美術印刷に使用。四色版。
⇒げん‐しょく【原色】
げんしょく‐ほう【減色法】‥ハフ
減法混色法の略。シアン・マゼンタ・黄の三原色を適当に混ぜるか重ね合わせることにより、目的とする色を作りだす方法。カラー写真・映画、カラー印刷などに応用。
けんじょ‐ごかし【賢女倒し】‥ヂヨ‥
相手を賢女だと言いはやすこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
げんしょ‐じょうたい【原初状態】‥ジヤウ‥
〔哲〕ロールズの用語。社会契約説における自然状態を、正義の基本原理を合意によって採択するための平等な討議の場として読み替えたもの。討議の参加者は自分の社会的地位・資産・能力などについて知らない(無知のベール)とされる。
⇒げん‐しょ【原初】
けんじょ‐だて【賢女立て】‥ヂヨ‥
賢女らしくふるまうこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
げん‐しょろう【現所労】‥ラウ
現在病気であること。平家物語4「典薬頭定成こそ…―とて参らず」
げんし‐りょう【原子量】‥リヤウ
天然の元素の原子の相対的な質量を一定の基準に基づいて表したもの。以前は天然の酸素を基準にとり、その原子量を16とした。1961年以降は質量数12の炭素原子を基準にとり、その原子質量を12として他の元素の原子の質量を表す。
⇒げん‐し【原子】
げんし‐りょく【原子力】
(→)核エネルギーに同じ。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐いいんかい【原子力委員会】‥ヰヰンクワイ
(Atomic Energy Commission)原子力の軍事的利用を管理し平和的開発を促進する目的をもつ委員会。国連内に1946年1月発足、52年1月国連軍縮委員会に吸収。これとは別に、各国にもそれぞれ設置され、日本では、平和利用に限るものが、56年に設立された。AEC →国際原子力機関。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐きほんほう【原子力基本法】‥ハフ
原子力に対する日本の基本的な考え方を法制化したもの。原子力の研究・開発やエネルギー資源の確保などについて定める。1955年制定。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐さんげんそく【原子力三原則】
日本における原子力の研究・開発・利用に関する自主・民主・公開の三つの原則。1954年の日本学術会議総会で決議され、原子力基本法に採り入れられた。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐せん【原子力船】
原子力を動力とする船。日本船としては「むつ」があった。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐せんすいかん【原子力潜水艦】
原子力を動力とする潜水艦。原潜。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐でんち【原子力電池】
放射性同位体から発生する放射線のエネルギーを利用した電池。ストロンチウム90のように長い半減期をもつ同位体を用いることにより寿命の長い安定した電源が得られる。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐はつでん【原子力発電】
原子炉で発生する熱エネルギーを利用した発電。
⇒げん‐し【原子】
げんし‐りん【原始林】
(→)原生林に同じ。
⇒げん‐し【原始】
けん・じる【献じる】
〔他上一〕
(→)「献ずる」に同じ。
げん・じる【減じる】
〔自他上一〕
(→)「減ずる」に同じ。
げんし‐ろ【原子炉】
ウラン235・プルトニウム239などの原子核分裂の連鎖反応を、制御しながら持続させるようにした装置。天然ウラン黒鉛型と軽水型に大別され、後者には加圧水型(PWR)と沸騰水型(BWR)とがある。目的により、研究用・発電用・医療用などがある。
原子炉
 ⇒げん‐し【原子】
げんしろう【源四郎】‥ラウ
(「げんしろ」とも)金銭・数などをごまかすこと。ものを盗むこと。また、盗人。東海道中膝栗毛8「おまへさんがたの―してじや」
げんしろく【言志録】
漢文の語録の体裁で自己の思想を述べた書。佐藤一斎著。1824年(文政7)刊。「言志後録」「言志晩録」「言志耋てつ録」と共に「言志四録」という。
→文献資料[言志録]
げんし‐ろん【原子論】
(atomism)物質は原子によって構成され、自然現象は原子の離合集散によって説明されるという説。ギリシアの哲学者レウキッポス・デモクリトスらによってこれ以上分割し得ないものとしてアトムという概念が思弁的に提唱された。その後、19世紀初めにドルトン・アボガドロらによって原子・分子の概念が確立され、20世紀初頭には実験的にも証明された。また、より広く物事に最小単位を仮定する学説についても用いられ、要素主義・要素論とも呼ばれる。例えば、論理的原子論。
⇒げん‐し【原子】
けんじ‐わく【見思惑】
〔仏〕見惑と思惑しわく。天台宗で立てる三惑の一つで、道理を誤って分別して起こす惑いと世間の事物に対して起こす惑い。倶舎くしゃ論では見惑は見道の段階で、思惑は修道の段階で断ぜられるとされる。
⇒けん‐じ【見思】
けん‐しん【欠伸】
あくびと背のび。
けん‐しん【見神】
神の示現を心中に感知すること。神の本体を感知すること。
けん‐しん【健診】
健康診断の略。
けん‐しん【堅信・堅振】
〔宗〕(confirmation)キリスト教で受洗後、聖霊の賜物によって信仰を強める秘跡。
けん‐しん【検真】
民事訴訟で、筆跡または印影の対照などにより文書の成立の真否を証明すること。
けん‐しん【検針】
電力・水道・ガスなどの使用量を知るために、計量器の目盛りをしらべること。
けん‐しん【検診】
病気にかかっているかどうかを検査するために診察すること。「胸部―」
けん‐しん【献身】
一身を捧げて尽くすこと。自己の利益を顧みないで力を尽くすこと。自己犠牲。
⇒けんしん‐てき【献身的】
けん‐しん【献進】
さしあげること。たてまつること。献上。献呈。
けん‐しん【権臣】
権力を持った家来。
けん‐しん【賢臣】
賢明な家来。すぐれた臣下。
けん‐しん【懸針】
筆法の一つ。縦に引く画かくの終筆をはらい、針のように尖らすこと。懸鍼けんしんともいう。↔垂露すいろ
けん‐じん【研尋】
きわめたずねること。研究。研鑽。
けん‐じん【県人】
その県に住んでいる人。また、その県の出身者。
⇒けんじん‐かい【県人会】
けん‐じん【涓人】
①宮中の掃除をつかさどる人。
②去勢されて後宮に仕える人。
けん‐じん【堅陣】‥ヂン
防備が堅くて破りがたい陣営。太平記4「呉王の―に懸け入り」。「―を抜く」
けん‐じん【堅靱・堅韌】
かたく、ねばり強いさま。強く、しなやかなさま。
けん‐じん【賢人】
①かしこい人。また、聖人に次ぐ徳のある人。
②(清酒を聖人というのに対して)にごり酒の異称。賢酒。
⇒けんじん‐ごかし【賢人倒し】
⇒けんじん‐だて【賢人立て】
げん‐しん【元稹】
(ゲンジンとも)中唐の詩人・政治家。字は微之。河南洛陽の人。官は宰相に至る。白居易と親交あつく、相携えて平易な詩風を唱え、元白と並称された。詩文集「元氏長慶集」、伝奇小説「鶯鶯伝」。(779〜831)
げん‐しん【原審】
上訴審において上訴前の裁判。また、その裁判所。原裁判所。「―差戻し」
げん‐しん【現身】
①現世にある、この身。現在の姿の体。うつしみ。
②〔仏〕(→)応身おうじんに同じ。
げんしん【源信】
平安中期の天台宗の学僧。通称、恵心えしん僧都。大和の人。良源に師事し、論義・因明学を以て知られたが、横川よかわに隠棲。二十五三昧会を主導し、「往生要集」を著して浄土教の理論的基礎を築いた。ほかに著「一乗要決」など。(942〜1017)
→著作:『往生要集』
→著作:『横川法語』
げん‐しん【厳親】
父親。厳君。厳父。
げん‐じん【玄参】
ゴマノハグサの漢名。また、その根の生薬名。
げん‐じん【原人】
更新世前期・中期に生存した化石人類。ピテカントロプス‐エレクトゥスや北京原人など。人類進化の上で、猿人に次ぎ、旧人・新人の前に位置づけられ160万年前頃に出現。脳の大きさは現生人類の3分の2くらいで、直立歩行に習熟、簡単な石器を用いた。→ホモ‐エレクトゥス
げん‐じん【原腎】
〔生〕(→)中腎のこと。
⇒げんじん‐かん【原腎管】
げん‐じん【減尽】
減ってなくなること。減らしてなくすること。
けんじん‐かい【県人会】‥クワイ
他の府県または他国に行っている同県人の会合。
⇒けん‐じん【県人】
げんじん‐かん【原腎管】‥クワン
後生動物の排泄器官のうち、最も原始的なもの。扁形・紐形・輪形動物の幼生や成体、環形・軟体動物の幼生に見られる。浸透圧調節器官としても重要。水脈管。
⇒げん‐じん【原腎】
けんじん‐ごかし【賢人倒し】
相手を賢人だとはやし立てること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんしん‐だいし【見真大師】
親鸞しんらんの諡号しごう。
けんじん‐だて【賢人立て】
賢人らしく見せかけること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんしん‐てき【献身的】
自己を犠牲にしてでも他のために尽くすさま。「―な看護」
⇒けん‐しん【献身】
けん・す【兼す】
〔他サ変〕
兼ねる。平家物語2「右衛門督を―・して検非違使の別当になり給ふ」
けん・す【鈐す】
〔他サ変〕
①錠をおろす。
②印をおす。
けん・ず【見ず】
〔他サ変〕
見る。見て察する。花鏡「為手しての感より―・ずる際きわなり」
げん・す【眩す】
〔自他サ変〕
目がくらむ。めまいがする。目をくらませる。
げん‐ず【原図】‥ヅ
模写・複製などのもとになった図。
げん‐ず【現図】‥ヅ
船体の設計図に基づき、船体を構成する材料の一つ一つを現尺で描いた図。
⇒げんず‐さぎょう【現図作業】
⇒げんず‐まんだら【現図曼荼羅】
げん・ず【験ず】
〔自他サ変〕
霊験が現れる。今昔物語集26「この国に―・じ給ふ神」
けん‐すい【建水】
(「建」は覆す意)茶道具の一つ。点茶の際、茶碗をすすいだ水を捨てる具。木地の綰物わげもの、陶器、金属器などがある。水こぼし。こぼし。
けん‐すい【硯水】
①すずりの水。
②⇒けんずい(間水)
けん‐すい【懸垂】
①まっすぐにたれさがること。たれさげること。
②器械体操で、両手を鉄棒・平行棒などにかけて身体を垂下し、また、肘ひじを屈伸する技。
⇒けんすい‐かこう【懸垂下降】
⇒けんすいしき‐てつどう【懸垂式鉄道】
⇒けんすい‐せん【懸垂線】
けん‐ずい【間水・硯水・建水】
(間食けんしいの訛か)
①(上方語)定まった食事時以外の飲食。特に、昼食と夕食との間の飲食。おやつ。小昼こびる。
②(大工の隠語)酒。物類称呼「酒…畿内の番匠の詞に―といふ。今はけづりともいふ」
げん‐すい【元帥】
①将軍の統率者。総大将。
②元帥府に列せられた陸海軍大将の称号。
⇒げんすい‐ふ【元帥府】
げん‐すい【玄水】
僧家で酒の異称。
げん‐すい【減水】
水量が減ること。「貯水池が―する」↔増水
げん‐すい【減衰】
次第に減少してゆくこと。
⇒げんすい‐しんどう【減衰振動】
げんすい【源水】
(松井源水が始めたからいう)大道で、居合抜いあいぬき・曲独楽きょくごまなどの技を演じて人を集め、歯磨粉や歯の薬を売る人。
⇒げんすい‐ごま【源水独楽】
けんすい‐かこう【懸垂下降】‥カウ
登山で、岩壁や急斜面をザイルに身を託して下降する技術。アプザイレン。ラペリング。
⇒けん‐すい【懸垂】
げん‐すい‐きょう【原水協】‥ケフ
原水爆禁止日本協議会の略称。1954年ビキニ水爆実験で第五福竜丸が被災した事件をきっかけに起こった原水爆禁止署名運動が全国的に発展してできた団体。55年8月第1回原水爆禁止世界大会が広島で開かれた直後に結成。65年の原水禁組織分裂後は共産党系となる。→原水禁
焼津港に戻った第五福竜丸
提供:毎日新聞社
⇒げん‐し【原子】
げんしろう【源四郎】‥ラウ
(「げんしろ」とも)金銭・数などをごまかすこと。ものを盗むこと。また、盗人。東海道中膝栗毛8「おまへさんがたの―してじや」
げんしろく【言志録】
漢文の語録の体裁で自己の思想を述べた書。佐藤一斎著。1824年(文政7)刊。「言志後録」「言志晩録」「言志耋てつ録」と共に「言志四録」という。
→文献資料[言志録]
げんし‐ろん【原子論】
(atomism)物質は原子によって構成され、自然現象は原子の離合集散によって説明されるという説。ギリシアの哲学者レウキッポス・デモクリトスらによってこれ以上分割し得ないものとしてアトムという概念が思弁的に提唱された。その後、19世紀初めにドルトン・アボガドロらによって原子・分子の概念が確立され、20世紀初頭には実験的にも証明された。また、より広く物事に最小単位を仮定する学説についても用いられ、要素主義・要素論とも呼ばれる。例えば、論理的原子論。
⇒げん‐し【原子】
けんじ‐わく【見思惑】
〔仏〕見惑と思惑しわく。天台宗で立てる三惑の一つで、道理を誤って分別して起こす惑いと世間の事物に対して起こす惑い。倶舎くしゃ論では見惑は見道の段階で、思惑は修道の段階で断ぜられるとされる。
⇒けん‐じ【見思】
けん‐しん【欠伸】
あくびと背のび。
けん‐しん【見神】
神の示現を心中に感知すること。神の本体を感知すること。
けん‐しん【健診】
健康診断の略。
けん‐しん【堅信・堅振】
〔宗〕(confirmation)キリスト教で受洗後、聖霊の賜物によって信仰を強める秘跡。
けん‐しん【検真】
民事訴訟で、筆跡または印影の対照などにより文書の成立の真否を証明すること。
けん‐しん【検針】
電力・水道・ガスなどの使用量を知るために、計量器の目盛りをしらべること。
けん‐しん【検診】
病気にかかっているかどうかを検査するために診察すること。「胸部―」
けん‐しん【献身】
一身を捧げて尽くすこと。自己の利益を顧みないで力を尽くすこと。自己犠牲。
⇒けんしん‐てき【献身的】
けん‐しん【献進】
さしあげること。たてまつること。献上。献呈。
けん‐しん【権臣】
権力を持った家来。
けん‐しん【賢臣】
賢明な家来。すぐれた臣下。
けん‐しん【懸針】
筆法の一つ。縦に引く画かくの終筆をはらい、針のように尖らすこと。懸鍼けんしんともいう。↔垂露すいろ
けん‐じん【研尋】
きわめたずねること。研究。研鑽。
けん‐じん【県人】
その県に住んでいる人。また、その県の出身者。
⇒けんじん‐かい【県人会】
けん‐じん【涓人】
①宮中の掃除をつかさどる人。
②去勢されて後宮に仕える人。
けん‐じん【堅陣】‥ヂン
防備が堅くて破りがたい陣営。太平記4「呉王の―に懸け入り」。「―を抜く」
けん‐じん【堅靱・堅韌】
かたく、ねばり強いさま。強く、しなやかなさま。
けん‐じん【賢人】
①かしこい人。また、聖人に次ぐ徳のある人。
②(清酒を聖人というのに対して)にごり酒の異称。賢酒。
⇒けんじん‐ごかし【賢人倒し】
⇒けんじん‐だて【賢人立て】
げん‐しん【元稹】
(ゲンジンとも)中唐の詩人・政治家。字は微之。河南洛陽の人。官は宰相に至る。白居易と親交あつく、相携えて平易な詩風を唱え、元白と並称された。詩文集「元氏長慶集」、伝奇小説「鶯鶯伝」。(779〜831)
げん‐しん【原審】
上訴審において上訴前の裁判。また、その裁判所。原裁判所。「―差戻し」
げん‐しん【現身】
①現世にある、この身。現在の姿の体。うつしみ。
②〔仏〕(→)応身おうじんに同じ。
げんしん【源信】
平安中期の天台宗の学僧。通称、恵心えしん僧都。大和の人。良源に師事し、論義・因明学を以て知られたが、横川よかわに隠棲。二十五三昧会を主導し、「往生要集」を著して浄土教の理論的基礎を築いた。ほかに著「一乗要決」など。(942〜1017)
→著作:『往生要集』
→著作:『横川法語』
げん‐しん【厳親】
父親。厳君。厳父。
げん‐じん【玄参】
ゴマノハグサの漢名。また、その根の生薬名。
げん‐じん【原人】
更新世前期・中期に生存した化石人類。ピテカントロプス‐エレクトゥスや北京原人など。人類進化の上で、猿人に次ぎ、旧人・新人の前に位置づけられ160万年前頃に出現。脳の大きさは現生人類の3分の2くらいで、直立歩行に習熟、簡単な石器を用いた。→ホモ‐エレクトゥス
げん‐じん【原腎】
〔生〕(→)中腎のこと。
⇒げんじん‐かん【原腎管】
げん‐じん【減尽】
減ってなくなること。減らしてなくすること。
けんじん‐かい【県人会】‥クワイ
他の府県または他国に行っている同県人の会合。
⇒けん‐じん【県人】
げんじん‐かん【原腎管】‥クワン
後生動物の排泄器官のうち、最も原始的なもの。扁形・紐形・輪形動物の幼生や成体、環形・軟体動物の幼生に見られる。浸透圧調節器官としても重要。水脈管。
⇒げん‐じん【原腎】
けんじん‐ごかし【賢人倒し】
相手を賢人だとはやし立てること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんしん‐だいし【見真大師】
親鸞しんらんの諡号しごう。
けんじん‐だて【賢人立て】
賢人らしく見せかけること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんしん‐てき【献身的】
自己を犠牲にしてでも他のために尽くすさま。「―な看護」
⇒けん‐しん【献身】
けん・す【兼す】
〔他サ変〕
兼ねる。平家物語2「右衛門督を―・して検非違使の別当になり給ふ」
けん・す【鈐す】
〔他サ変〕
①錠をおろす。
②印をおす。
けん・ず【見ず】
〔他サ変〕
見る。見て察する。花鏡「為手しての感より―・ずる際きわなり」
げん・す【眩す】
〔自他サ変〕
目がくらむ。めまいがする。目をくらませる。
げん‐ず【原図】‥ヅ
模写・複製などのもとになった図。
げん‐ず【現図】‥ヅ
船体の設計図に基づき、船体を構成する材料の一つ一つを現尺で描いた図。
⇒げんず‐さぎょう【現図作業】
⇒げんず‐まんだら【現図曼荼羅】
げん・ず【験ず】
〔自他サ変〕
霊験が現れる。今昔物語集26「この国に―・じ給ふ神」
けん‐すい【建水】
(「建」は覆す意)茶道具の一つ。点茶の際、茶碗をすすいだ水を捨てる具。木地の綰物わげもの、陶器、金属器などがある。水こぼし。こぼし。
けん‐すい【硯水】
①すずりの水。
②⇒けんずい(間水)
けん‐すい【懸垂】
①まっすぐにたれさがること。たれさげること。
②器械体操で、両手を鉄棒・平行棒などにかけて身体を垂下し、また、肘ひじを屈伸する技。
⇒けんすい‐かこう【懸垂下降】
⇒けんすいしき‐てつどう【懸垂式鉄道】
⇒けんすい‐せん【懸垂線】
けん‐ずい【間水・硯水・建水】
(間食けんしいの訛か)
①(上方語)定まった食事時以外の飲食。特に、昼食と夕食との間の飲食。おやつ。小昼こびる。
②(大工の隠語)酒。物類称呼「酒…畿内の番匠の詞に―といふ。今はけづりともいふ」
げん‐すい【元帥】
①将軍の統率者。総大将。
②元帥府に列せられた陸海軍大将の称号。
⇒げんすい‐ふ【元帥府】
げん‐すい【玄水】
僧家で酒の異称。
げん‐すい【減水】
水量が減ること。「貯水池が―する」↔増水
げん‐すい【減衰】
次第に減少してゆくこと。
⇒げんすい‐しんどう【減衰振動】
げんすい【源水】
(松井源水が始めたからいう)大道で、居合抜いあいぬき・曲独楽きょくごまなどの技を演じて人を集め、歯磨粉や歯の薬を売る人。
⇒げんすい‐ごま【源水独楽】
けんすい‐かこう【懸垂下降】‥カウ
登山で、岩壁や急斜面をザイルに身を託して下降する技術。アプザイレン。ラペリング。
⇒けん‐すい【懸垂】
げん‐すい‐きょう【原水協】‥ケフ
原水爆禁止日本協議会の略称。1954年ビキニ水爆実験で第五福竜丸が被災した事件をきっかけに起こった原水爆禁止署名運動が全国的に発展してできた団体。55年8月第1回原水爆禁止世界大会が広島で開かれた直後に結成。65年の原水禁組織分裂後は共産党系となる。→原水禁
焼津港に戻った第五福竜丸
提供:毎日新聞社
 第1回原水禁世界大会会場 1955年(広島)
提供:毎日新聞社
第1回原水禁世界大会会場 1955年(広島)
提供:毎日新聞社
 第1回原水爆禁止世界大会
提供:NHK
げん‐すい‐きん【原水禁】
①原水爆禁止の略。「―運動」
②原水爆禁止日本国民会議の略称。部分的核実験停止条約の評価をめぐる対立から原水協より脱退した社会党・総評などが1965年に結成。
けんすい‐コック【験水コック】
ボイラーの缶水が規定外に減少するのを防ぎ、また缶水の有無を検査するため、缶の前面に取り付けたコック。
げんすい‐ごま【源水独楽】
(松井源水が曲独楽に用いたからいう)心棒の長い博多独楽。
⇒げんすい【源水】
けんずい‐し【
第1回原水爆禁止世界大会
提供:NHK
げん‐すい‐きん【原水禁】
①原水爆禁止の略。「―運動」
②原水爆禁止日本国民会議の略称。部分的核実験停止条約の評価をめぐる対立から原水協より脱退した社会党・総評などが1965年に結成。
けんすい‐コック【験水コック】
ボイラーの缶水が規定外に減少するのを防ぎ、また缶水の有無を検査するため、缶の前面に取り付けたコック。
げんすい‐ごま【源水独楽】
(松井源水が曲独楽に用いたからいう)心棒の長い博多独楽。
⇒げんすい【源水】
けんずい‐し【
 げんしょう‐ろん【現象論】‥シヤウ‥
①現象主義。
②実際に現象として現れたことのみに基づいて論ずること。「―としては間違っていない」
⇒げん‐しょう【現象】
けん‐しょく【兼職】
本職以外に他の職を兼ねること。また、兼務の職。
けん‐しょく【顕職】
位の高い官職。高官。要職。
けん‐じょく【見濁】‥ヂヨク
〔仏〕五濁の一つ。末世になり、邪見が盛んになり、世を濁乱すること。
げん‐しょく【言色】
ことばつきと顔色。
げん‐しょく【言職】
言論を以て仕える職。諫言かんげんまたは建言を役目とする職務。
げん‐しょく【原色】
①他の色を生み出すもととなる色。適当な割合に混ぜることによってすべての色を表せる三つの異なった色。その一つが他の二つの混合で生じ得ない限り、任意に選ぶことができるが、実用的には赤・緑・青(青紫)の三つ(光の三原色)が選ばれる。絵具のような吸収媒質を混ぜるときはシアン(青緑)・マゼンタ(赤紫)・黄の3色が選ばれる。(絵具の三原色)
②三原色またはそれに近いはっきりした色。あざやかで派手な色。
③印刷などで、もとのままの色。「―に近い色を出す」「―植物図鑑」
⇒げんしょく‐ばん【原色版】
げん‐しょく【原職】
一時的に離れていた、もとの職務。
げん‐しょく【現職】
現在ついている職務・職業。また、ある職務に現についていること。「―にとどまる」
⇒げんしょく‐きょういく【現職教育】
げん‐しょく【減食】
①食事の量・回数をへらすこと。
②〔法〕受刑者などに対する懲罰として、7日以内の食糧の分量を減ずる制裁。2005年監獄法改正により廃止。
げんしょく‐きょういく【現職教育】‥ケウ‥
現に職業に従事している者に対して現職のまま行われる教育。研修。
⇒げん‐しょく【現職】
げんしょく‐ばん【原色版】
カラー印刷法の一つ。三原色(シアン・マゼンタ・黄)と黒の4色のインクを用いて原画と同じような色彩を出す網目凸版印刷。また、その印刷物。原画を4色に分解撮影した4枚のネガから、おのおの網版を作り、それぞれの色インクで刷り重ねる。高級美術印刷に使用。四色版。
⇒げん‐しょく【原色】
げんしょく‐ほう【減色法】‥ハフ
減法混色法の略。シアン・マゼンタ・黄の三原色を適当に混ぜるか重ね合わせることにより、目的とする色を作りだす方法。カラー写真・映画、カラー印刷などに応用。
けんじょ‐ごかし【賢女倒し】‥ヂヨ‥
相手を賢女だと言いはやすこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
げんしょ‐じょうたい【原初状態】‥ジヤウ‥
〔哲〕ロールズの用語。社会契約説における自然状態を、正義の基本原理を合意によって採択するための平等な討議の場として読み替えたもの。討議の参加者は自分の社会的地位・資産・能力などについて知らない(無知のベール)とされる。
⇒げん‐しょ【原初】
けんじょ‐だて【賢女立て】‥ヂヨ‥
賢女らしくふるまうこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
げん‐しょろう【現所労】‥ラウ
現在病気であること。平家物語4「典薬頭定成こそ…―とて参らず」
げんし‐りょう【原子量】‥リヤウ
天然の元素の原子の相対的な質量を一定の基準に基づいて表したもの。以前は天然の酸素を基準にとり、その原子量を16とした。1961年以降は質量数12の炭素原子を基準にとり、その原子質量を12として他の元素の原子の質量を表す。
⇒げん‐し【原子】
げんし‐りょく【原子力】
(→)核エネルギーに同じ。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐いいんかい【原子力委員会】‥ヰヰンクワイ
(Atomic Energy Commission)原子力の軍事的利用を管理し平和的開発を促進する目的をもつ委員会。国連内に1946年1月発足、52年1月国連軍縮委員会に吸収。これとは別に、各国にもそれぞれ設置され、日本では、平和利用に限るものが、56年に設立された。AEC →国際原子力機関。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐きほんほう【原子力基本法】‥ハフ
原子力に対する日本の基本的な考え方を法制化したもの。原子力の研究・開発やエネルギー資源の確保などについて定める。1955年制定。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐さんげんそく【原子力三原則】
日本における原子力の研究・開発・利用に関する自主・民主・公開の三つの原則。1954年の日本学術会議総会で決議され、原子力基本法に採り入れられた。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐せん【原子力船】
原子力を動力とする船。日本船としては「むつ」があった。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐せんすいかん【原子力潜水艦】
原子力を動力とする潜水艦。原潜。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐でんち【原子力電池】
放射性同位体から発生する放射線のエネルギーを利用した電池。ストロンチウム90のように長い半減期をもつ同位体を用いることにより寿命の長い安定した電源が得られる。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐はつでん【原子力発電】
原子炉で発生する熱エネルギーを利用した発電。
⇒げん‐し【原子】
げんし‐りん【原始林】
(→)原生林に同じ。
⇒げん‐し【原始】
けん・じる【献じる】
〔他上一〕
(→)「献ずる」に同じ。
げん・じる【減じる】
〔自他上一〕
(→)「減ずる」に同じ。
げんし‐ろ【原子炉】
ウラン235・プルトニウム239などの原子核分裂の連鎖反応を、制御しながら持続させるようにした装置。天然ウラン黒鉛型と軽水型に大別され、後者には加圧水型(PWR)と沸騰水型(BWR)とがある。目的により、研究用・発電用・医療用などがある。
原子炉
げんしょう‐ろん【現象論】‥シヤウ‥
①現象主義。
②実際に現象として現れたことのみに基づいて論ずること。「―としては間違っていない」
⇒げん‐しょう【現象】
けん‐しょく【兼職】
本職以外に他の職を兼ねること。また、兼務の職。
けん‐しょく【顕職】
位の高い官職。高官。要職。
けん‐じょく【見濁】‥ヂヨク
〔仏〕五濁の一つ。末世になり、邪見が盛んになり、世を濁乱すること。
げん‐しょく【言色】
ことばつきと顔色。
げん‐しょく【言職】
言論を以て仕える職。諫言かんげんまたは建言を役目とする職務。
げん‐しょく【原色】
①他の色を生み出すもととなる色。適当な割合に混ぜることによってすべての色を表せる三つの異なった色。その一つが他の二つの混合で生じ得ない限り、任意に選ぶことができるが、実用的には赤・緑・青(青紫)の三つ(光の三原色)が選ばれる。絵具のような吸収媒質を混ぜるときはシアン(青緑)・マゼンタ(赤紫)・黄の3色が選ばれる。(絵具の三原色)
②三原色またはそれに近いはっきりした色。あざやかで派手な色。
③印刷などで、もとのままの色。「―に近い色を出す」「―植物図鑑」
⇒げんしょく‐ばん【原色版】
げん‐しょく【原職】
一時的に離れていた、もとの職務。
げん‐しょく【現職】
現在ついている職務・職業。また、ある職務に現についていること。「―にとどまる」
⇒げんしょく‐きょういく【現職教育】
げん‐しょく【減食】
①食事の量・回数をへらすこと。
②〔法〕受刑者などに対する懲罰として、7日以内の食糧の分量を減ずる制裁。2005年監獄法改正により廃止。
げんしょく‐きょういく【現職教育】‥ケウ‥
現に職業に従事している者に対して現職のまま行われる教育。研修。
⇒げん‐しょく【現職】
げんしょく‐ばん【原色版】
カラー印刷法の一つ。三原色(シアン・マゼンタ・黄)と黒の4色のインクを用いて原画と同じような色彩を出す網目凸版印刷。また、その印刷物。原画を4色に分解撮影した4枚のネガから、おのおの網版を作り、それぞれの色インクで刷り重ねる。高級美術印刷に使用。四色版。
⇒げん‐しょく【原色】
げんしょく‐ほう【減色法】‥ハフ
減法混色法の略。シアン・マゼンタ・黄の三原色を適当に混ぜるか重ね合わせることにより、目的とする色を作りだす方法。カラー写真・映画、カラー印刷などに応用。
けんじょ‐ごかし【賢女倒し】‥ヂヨ‥
相手を賢女だと言いはやすこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
げんしょ‐じょうたい【原初状態】‥ジヤウ‥
〔哲〕ロールズの用語。社会契約説における自然状態を、正義の基本原理を合意によって採択するための平等な討議の場として読み替えたもの。討議の参加者は自分の社会的地位・資産・能力などについて知らない(無知のベール)とされる。
⇒げん‐しょ【原初】
けんじょ‐だて【賢女立て】‥ヂヨ‥
賢女らしくふるまうこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
げん‐しょろう【現所労】‥ラウ
現在病気であること。平家物語4「典薬頭定成こそ…―とて参らず」
げんし‐りょう【原子量】‥リヤウ
天然の元素の原子の相対的な質量を一定の基準に基づいて表したもの。以前は天然の酸素を基準にとり、その原子量を16とした。1961年以降は質量数12の炭素原子を基準にとり、その原子質量を12として他の元素の原子の質量を表す。
⇒げん‐し【原子】
げんし‐りょく【原子力】
(→)核エネルギーに同じ。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐いいんかい【原子力委員会】‥ヰヰンクワイ
(Atomic Energy Commission)原子力の軍事的利用を管理し平和的開発を促進する目的をもつ委員会。国連内に1946年1月発足、52年1月国連軍縮委員会に吸収。これとは別に、各国にもそれぞれ設置され、日本では、平和利用に限るものが、56年に設立された。AEC →国際原子力機関。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐きほんほう【原子力基本法】‥ハフ
原子力に対する日本の基本的な考え方を法制化したもの。原子力の研究・開発やエネルギー資源の確保などについて定める。1955年制定。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐さんげんそく【原子力三原則】
日本における原子力の研究・開発・利用に関する自主・民主・公開の三つの原則。1954年の日本学術会議総会で決議され、原子力基本法に採り入れられた。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐せん【原子力船】
原子力を動力とする船。日本船としては「むつ」があった。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐せんすいかん【原子力潜水艦】
原子力を動力とする潜水艦。原潜。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐でんち【原子力電池】
放射性同位体から発生する放射線のエネルギーを利用した電池。ストロンチウム90のように長い半減期をもつ同位体を用いることにより寿命の長い安定した電源が得られる。
⇒げん‐し【原子】
げんしりょく‐はつでん【原子力発電】
原子炉で発生する熱エネルギーを利用した発電。
⇒げん‐し【原子】
げんし‐りん【原始林】
(→)原生林に同じ。
⇒げん‐し【原始】
けん・じる【献じる】
〔他上一〕
(→)「献ずる」に同じ。
げん・じる【減じる】
〔自他上一〕
(→)「減ずる」に同じ。
げんし‐ろ【原子炉】
ウラン235・プルトニウム239などの原子核分裂の連鎖反応を、制御しながら持続させるようにした装置。天然ウラン黒鉛型と軽水型に大別され、後者には加圧水型(PWR)と沸騰水型(BWR)とがある。目的により、研究用・発電用・医療用などがある。
原子炉
 ⇒げん‐し【原子】
げんしろう【源四郎】‥ラウ
(「げんしろ」とも)金銭・数などをごまかすこと。ものを盗むこと。また、盗人。東海道中膝栗毛8「おまへさんがたの―してじや」
げんしろく【言志録】
漢文の語録の体裁で自己の思想を述べた書。佐藤一斎著。1824年(文政7)刊。「言志後録」「言志晩録」「言志耋てつ録」と共に「言志四録」という。
→文献資料[言志録]
げんし‐ろん【原子論】
(atomism)物質は原子によって構成され、自然現象は原子の離合集散によって説明されるという説。ギリシアの哲学者レウキッポス・デモクリトスらによってこれ以上分割し得ないものとしてアトムという概念が思弁的に提唱された。その後、19世紀初めにドルトン・アボガドロらによって原子・分子の概念が確立され、20世紀初頭には実験的にも証明された。また、より広く物事に最小単位を仮定する学説についても用いられ、要素主義・要素論とも呼ばれる。例えば、論理的原子論。
⇒げん‐し【原子】
けんじ‐わく【見思惑】
〔仏〕見惑と思惑しわく。天台宗で立てる三惑の一つで、道理を誤って分別して起こす惑いと世間の事物に対して起こす惑い。倶舎くしゃ論では見惑は見道の段階で、思惑は修道の段階で断ぜられるとされる。
⇒けん‐じ【見思】
けん‐しん【欠伸】
あくびと背のび。
けん‐しん【見神】
神の示現を心中に感知すること。神の本体を感知すること。
けん‐しん【健診】
健康診断の略。
けん‐しん【堅信・堅振】
〔宗〕(confirmation)キリスト教で受洗後、聖霊の賜物によって信仰を強める秘跡。
けん‐しん【検真】
民事訴訟で、筆跡または印影の対照などにより文書の成立の真否を証明すること。
けん‐しん【検針】
電力・水道・ガスなどの使用量を知るために、計量器の目盛りをしらべること。
けん‐しん【検診】
病気にかかっているかどうかを検査するために診察すること。「胸部―」
けん‐しん【献身】
一身を捧げて尽くすこと。自己の利益を顧みないで力を尽くすこと。自己犠牲。
⇒けんしん‐てき【献身的】
けん‐しん【献進】
さしあげること。たてまつること。献上。献呈。
けん‐しん【権臣】
権力を持った家来。
けん‐しん【賢臣】
賢明な家来。すぐれた臣下。
けん‐しん【懸針】
筆法の一つ。縦に引く画かくの終筆をはらい、針のように尖らすこと。懸鍼けんしんともいう。↔垂露すいろ
けん‐じん【研尋】
きわめたずねること。研究。研鑽。
けん‐じん【県人】
その県に住んでいる人。また、その県の出身者。
⇒けんじん‐かい【県人会】
けん‐じん【涓人】
①宮中の掃除をつかさどる人。
②去勢されて後宮に仕える人。
けん‐じん【堅陣】‥ヂン
防備が堅くて破りがたい陣営。太平記4「呉王の―に懸け入り」。「―を抜く」
けん‐じん【堅靱・堅韌】
かたく、ねばり強いさま。強く、しなやかなさま。
けん‐じん【賢人】
①かしこい人。また、聖人に次ぐ徳のある人。
②(清酒を聖人というのに対して)にごり酒の異称。賢酒。
⇒けんじん‐ごかし【賢人倒し】
⇒けんじん‐だて【賢人立て】
げん‐しん【元稹】
(ゲンジンとも)中唐の詩人・政治家。字は微之。河南洛陽の人。官は宰相に至る。白居易と親交あつく、相携えて平易な詩風を唱え、元白と並称された。詩文集「元氏長慶集」、伝奇小説「鶯鶯伝」。(779〜831)
げん‐しん【原審】
上訴審において上訴前の裁判。また、その裁判所。原裁判所。「―差戻し」
げん‐しん【現身】
①現世にある、この身。現在の姿の体。うつしみ。
②〔仏〕(→)応身おうじんに同じ。
げんしん【源信】
平安中期の天台宗の学僧。通称、恵心えしん僧都。大和の人。良源に師事し、論義・因明学を以て知られたが、横川よかわに隠棲。二十五三昧会を主導し、「往生要集」を著して浄土教の理論的基礎を築いた。ほかに著「一乗要決」など。(942〜1017)
→著作:『往生要集』
→著作:『横川法語』
げん‐しん【厳親】
父親。厳君。厳父。
げん‐じん【玄参】
ゴマノハグサの漢名。また、その根の生薬名。
げん‐じん【原人】
更新世前期・中期に生存した化石人類。ピテカントロプス‐エレクトゥスや北京原人など。人類進化の上で、猿人に次ぎ、旧人・新人の前に位置づけられ160万年前頃に出現。脳の大きさは現生人類の3分の2くらいで、直立歩行に習熟、簡単な石器を用いた。→ホモ‐エレクトゥス
げん‐じん【原腎】
〔生〕(→)中腎のこと。
⇒げんじん‐かん【原腎管】
げん‐じん【減尽】
減ってなくなること。減らしてなくすること。
けんじん‐かい【県人会】‥クワイ
他の府県または他国に行っている同県人の会合。
⇒けん‐じん【県人】
げんじん‐かん【原腎管】‥クワン
後生動物の排泄器官のうち、最も原始的なもの。扁形・紐形・輪形動物の幼生や成体、環形・軟体動物の幼生に見られる。浸透圧調節器官としても重要。水脈管。
⇒げん‐じん【原腎】
けんじん‐ごかし【賢人倒し】
相手を賢人だとはやし立てること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんしん‐だいし【見真大師】
親鸞しんらんの諡号しごう。
けんじん‐だて【賢人立て】
賢人らしく見せかけること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんしん‐てき【献身的】
自己を犠牲にしてでも他のために尽くすさま。「―な看護」
⇒けん‐しん【献身】
けん・す【兼す】
〔他サ変〕
兼ねる。平家物語2「右衛門督を―・して検非違使の別当になり給ふ」
けん・す【鈐す】
〔他サ変〕
①錠をおろす。
②印をおす。
けん・ず【見ず】
〔他サ変〕
見る。見て察する。花鏡「為手しての感より―・ずる際きわなり」
げん・す【眩す】
〔自他サ変〕
目がくらむ。めまいがする。目をくらませる。
げん‐ず【原図】‥ヅ
模写・複製などのもとになった図。
げん‐ず【現図】‥ヅ
船体の設計図に基づき、船体を構成する材料の一つ一つを現尺で描いた図。
⇒げんず‐さぎょう【現図作業】
⇒げんず‐まんだら【現図曼荼羅】
げん・ず【験ず】
〔自他サ変〕
霊験が現れる。今昔物語集26「この国に―・じ給ふ神」
けん‐すい【建水】
(「建」は覆す意)茶道具の一つ。点茶の際、茶碗をすすいだ水を捨てる具。木地の綰物わげもの、陶器、金属器などがある。水こぼし。こぼし。
けん‐すい【硯水】
①すずりの水。
②⇒けんずい(間水)
けん‐すい【懸垂】
①まっすぐにたれさがること。たれさげること。
②器械体操で、両手を鉄棒・平行棒などにかけて身体を垂下し、また、肘ひじを屈伸する技。
⇒けんすい‐かこう【懸垂下降】
⇒けんすいしき‐てつどう【懸垂式鉄道】
⇒けんすい‐せん【懸垂線】
けん‐ずい【間水・硯水・建水】
(間食けんしいの訛か)
①(上方語)定まった食事時以外の飲食。特に、昼食と夕食との間の飲食。おやつ。小昼こびる。
②(大工の隠語)酒。物類称呼「酒…畿内の番匠の詞に―といふ。今はけづりともいふ」
げん‐すい【元帥】
①将軍の統率者。総大将。
②元帥府に列せられた陸海軍大将の称号。
⇒げんすい‐ふ【元帥府】
げん‐すい【玄水】
僧家で酒の異称。
げん‐すい【減水】
水量が減ること。「貯水池が―する」↔増水
げん‐すい【減衰】
次第に減少してゆくこと。
⇒げんすい‐しんどう【減衰振動】
げんすい【源水】
(松井源水が始めたからいう)大道で、居合抜いあいぬき・曲独楽きょくごまなどの技を演じて人を集め、歯磨粉や歯の薬を売る人。
⇒げんすい‐ごま【源水独楽】
けんすい‐かこう【懸垂下降】‥カウ
登山で、岩壁や急斜面をザイルに身を託して下降する技術。アプザイレン。ラペリング。
⇒けん‐すい【懸垂】
げん‐すい‐きょう【原水協】‥ケフ
原水爆禁止日本協議会の略称。1954年ビキニ水爆実験で第五福竜丸が被災した事件をきっかけに起こった原水爆禁止署名運動が全国的に発展してできた団体。55年8月第1回原水爆禁止世界大会が広島で開かれた直後に結成。65年の原水禁組織分裂後は共産党系となる。→原水禁
焼津港に戻った第五福竜丸
提供:毎日新聞社
⇒げん‐し【原子】
げんしろう【源四郎】‥ラウ
(「げんしろ」とも)金銭・数などをごまかすこと。ものを盗むこと。また、盗人。東海道中膝栗毛8「おまへさんがたの―してじや」
げんしろく【言志録】
漢文の語録の体裁で自己の思想を述べた書。佐藤一斎著。1824年(文政7)刊。「言志後録」「言志晩録」「言志耋てつ録」と共に「言志四録」という。
→文献資料[言志録]
げんし‐ろん【原子論】
(atomism)物質は原子によって構成され、自然現象は原子の離合集散によって説明されるという説。ギリシアの哲学者レウキッポス・デモクリトスらによってこれ以上分割し得ないものとしてアトムという概念が思弁的に提唱された。その後、19世紀初めにドルトン・アボガドロらによって原子・分子の概念が確立され、20世紀初頭には実験的にも証明された。また、より広く物事に最小単位を仮定する学説についても用いられ、要素主義・要素論とも呼ばれる。例えば、論理的原子論。
⇒げん‐し【原子】
けんじ‐わく【見思惑】
〔仏〕見惑と思惑しわく。天台宗で立てる三惑の一つで、道理を誤って分別して起こす惑いと世間の事物に対して起こす惑い。倶舎くしゃ論では見惑は見道の段階で、思惑は修道の段階で断ぜられるとされる。
⇒けん‐じ【見思】
けん‐しん【欠伸】
あくびと背のび。
けん‐しん【見神】
神の示現を心中に感知すること。神の本体を感知すること。
けん‐しん【健診】
健康診断の略。
けん‐しん【堅信・堅振】
〔宗〕(confirmation)キリスト教で受洗後、聖霊の賜物によって信仰を強める秘跡。
けん‐しん【検真】
民事訴訟で、筆跡または印影の対照などにより文書の成立の真否を証明すること。
けん‐しん【検針】
電力・水道・ガスなどの使用量を知るために、計量器の目盛りをしらべること。
けん‐しん【検診】
病気にかかっているかどうかを検査するために診察すること。「胸部―」
けん‐しん【献身】
一身を捧げて尽くすこと。自己の利益を顧みないで力を尽くすこと。自己犠牲。
⇒けんしん‐てき【献身的】
けん‐しん【献進】
さしあげること。たてまつること。献上。献呈。
けん‐しん【権臣】
権力を持った家来。
けん‐しん【賢臣】
賢明な家来。すぐれた臣下。
けん‐しん【懸針】
筆法の一つ。縦に引く画かくの終筆をはらい、針のように尖らすこと。懸鍼けんしんともいう。↔垂露すいろ
けん‐じん【研尋】
きわめたずねること。研究。研鑽。
けん‐じん【県人】
その県に住んでいる人。また、その県の出身者。
⇒けんじん‐かい【県人会】
けん‐じん【涓人】
①宮中の掃除をつかさどる人。
②去勢されて後宮に仕える人。
けん‐じん【堅陣】‥ヂン
防備が堅くて破りがたい陣営。太平記4「呉王の―に懸け入り」。「―を抜く」
けん‐じん【堅靱・堅韌】
かたく、ねばり強いさま。強く、しなやかなさま。
けん‐じん【賢人】
①かしこい人。また、聖人に次ぐ徳のある人。
②(清酒を聖人というのに対して)にごり酒の異称。賢酒。
⇒けんじん‐ごかし【賢人倒し】
⇒けんじん‐だて【賢人立て】
げん‐しん【元稹】
(ゲンジンとも)中唐の詩人・政治家。字は微之。河南洛陽の人。官は宰相に至る。白居易と親交あつく、相携えて平易な詩風を唱え、元白と並称された。詩文集「元氏長慶集」、伝奇小説「鶯鶯伝」。(779〜831)
げん‐しん【原審】
上訴審において上訴前の裁判。また、その裁判所。原裁判所。「―差戻し」
げん‐しん【現身】
①現世にある、この身。現在の姿の体。うつしみ。
②〔仏〕(→)応身おうじんに同じ。
げんしん【源信】
平安中期の天台宗の学僧。通称、恵心えしん僧都。大和の人。良源に師事し、論義・因明学を以て知られたが、横川よかわに隠棲。二十五三昧会を主導し、「往生要集」を著して浄土教の理論的基礎を築いた。ほかに著「一乗要決」など。(942〜1017)
→著作:『往生要集』
→著作:『横川法語』
げん‐しん【厳親】
父親。厳君。厳父。
げん‐じん【玄参】
ゴマノハグサの漢名。また、その根の生薬名。
げん‐じん【原人】
更新世前期・中期に生存した化石人類。ピテカントロプス‐エレクトゥスや北京原人など。人類進化の上で、猿人に次ぎ、旧人・新人の前に位置づけられ160万年前頃に出現。脳の大きさは現生人類の3分の2くらいで、直立歩行に習熟、簡単な石器を用いた。→ホモ‐エレクトゥス
げん‐じん【原腎】
〔生〕(→)中腎のこと。
⇒げんじん‐かん【原腎管】
げん‐じん【減尽】
減ってなくなること。減らしてなくすること。
けんじん‐かい【県人会】‥クワイ
他の府県または他国に行っている同県人の会合。
⇒けん‐じん【県人】
げんじん‐かん【原腎管】‥クワン
後生動物の排泄器官のうち、最も原始的なもの。扁形・紐形・輪形動物の幼生や成体、環形・軟体動物の幼生に見られる。浸透圧調節器官としても重要。水脈管。
⇒げん‐じん【原腎】
けんじん‐ごかし【賢人倒し】
相手を賢人だとはやし立てること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんしん‐だいし【見真大師】
親鸞しんらんの諡号しごう。
けんじん‐だて【賢人立て】
賢人らしく見せかけること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんしん‐てき【献身的】
自己を犠牲にしてでも他のために尽くすさま。「―な看護」
⇒けん‐しん【献身】
けん・す【兼す】
〔他サ変〕
兼ねる。平家物語2「右衛門督を―・して検非違使の別当になり給ふ」
けん・す【鈐す】
〔他サ変〕
①錠をおろす。
②印をおす。
けん・ず【見ず】
〔他サ変〕
見る。見て察する。花鏡「為手しての感より―・ずる際きわなり」
げん・す【眩す】
〔自他サ変〕
目がくらむ。めまいがする。目をくらませる。
げん‐ず【原図】‥ヅ
模写・複製などのもとになった図。
げん‐ず【現図】‥ヅ
船体の設計図に基づき、船体を構成する材料の一つ一つを現尺で描いた図。
⇒げんず‐さぎょう【現図作業】
⇒げんず‐まんだら【現図曼荼羅】
げん・ず【験ず】
〔自他サ変〕
霊験が現れる。今昔物語集26「この国に―・じ給ふ神」
けん‐すい【建水】
(「建」は覆す意)茶道具の一つ。点茶の際、茶碗をすすいだ水を捨てる具。木地の綰物わげもの、陶器、金属器などがある。水こぼし。こぼし。
けん‐すい【硯水】
①すずりの水。
②⇒けんずい(間水)
けん‐すい【懸垂】
①まっすぐにたれさがること。たれさげること。
②器械体操で、両手を鉄棒・平行棒などにかけて身体を垂下し、また、肘ひじを屈伸する技。
⇒けんすい‐かこう【懸垂下降】
⇒けんすいしき‐てつどう【懸垂式鉄道】
⇒けんすい‐せん【懸垂線】
けん‐ずい【間水・硯水・建水】
(間食けんしいの訛か)
①(上方語)定まった食事時以外の飲食。特に、昼食と夕食との間の飲食。おやつ。小昼こびる。
②(大工の隠語)酒。物類称呼「酒…畿内の番匠の詞に―といふ。今はけづりともいふ」
げん‐すい【元帥】
①将軍の統率者。総大将。
②元帥府に列せられた陸海軍大将の称号。
⇒げんすい‐ふ【元帥府】
げん‐すい【玄水】
僧家で酒の異称。
げん‐すい【減水】
水量が減ること。「貯水池が―する」↔増水
げん‐すい【減衰】
次第に減少してゆくこと。
⇒げんすい‐しんどう【減衰振動】
げんすい【源水】
(松井源水が始めたからいう)大道で、居合抜いあいぬき・曲独楽きょくごまなどの技を演じて人を集め、歯磨粉や歯の薬を売る人。
⇒げんすい‐ごま【源水独楽】
けんすい‐かこう【懸垂下降】‥カウ
登山で、岩壁や急斜面をザイルに身を託して下降する技術。アプザイレン。ラペリング。
⇒けん‐すい【懸垂】
げん‐すい‐きょう【原水協】‥ケフ
原水爆禁止日本協議会の略称。1954年ビキニ水爆実験で第五福竜丸が被災した事件をきっかけに起こった原水爆禁止署名運動が全国的に発展してできた団体。55年8月第1回原水爆禁止世界大会が広島で開かれた直後に結成。65年の原水禁組織分裂後は共産党系となる。→原水禁
焼津港に戻った第五福竜丸
提供:毎日新聞社
 第1回原水禁世界大会会場 1955年(広島)
提供:毎日新聞社
第1回原水禁世界大会会場 1955年(広島)
提供:毎日新聞社
 第1回原水爆禁止世界大会
提供:NHK
げん‐すい‐きん【原水禁】
①原水爆禁止の略。「―運動」
②原水爆禁止日本国民会議の略称。部分的核実験停止条約の評価をめぐる対立から原水協より脱退した社会党・総評などが1965年に結成。
けんすい‐コック【験水コック】
ボイラーの缶水が規定外に減少するのを防ぎ、また缶水の有無を検査するため、缶の前面に取り付けたコック。
げんすい‐ごま【源水独楽】
(松井源水が曲独楽に用いたからいう)心棒の長い博多独楽。
⇒げんすい【源水】
けんずい‐し【
第1回原水爆禁止世界大会
提供:NHK
げん‐すい‐きん【原水禁】
①原水爆禁止の略。「―運動」
②原水爆禁止日本国民会議の略称。部分的核実験停止条約の評価をめぐる対立から原水協より脱退した社会党・総評などが1965年に結成。
けんすい‐コック【験水コック】
ボイラーの缶水が規定外に減少するのを防ぎ、また缶水の有無を検査するため、缶の前面に取り付けたコック。
げんすい‐ごま【源水独楽】
(松井源水が曲独楽に用いたからいう)心棒の長い博多独楽。
⇒げんすい【源水】
けんずい‐し【けん‐しゅ【賢主】🔗⭐🔉
けん‐しゅ【賢主】
賢明な君主。賢君。
けん‐じゅ【賢首】🔗⭐🔉
けん‐じゅ【賢首】
①(仏典で)敬意をもった呼びかけの語。
②(ゲンジュとも)法蔵ほうぞうの大師号。
けん‐じゅ【賢衆】🔗⭐🔉
けん‐じゅ【賢衆】
賢聖けんじょうの人々。高僧の称。賢聖衆。
けん‐しゅん【賢俊】🔗⭐🔉
けん‐しゅん【賢俊】
賢くすぐれていること。また、その人。
けん‐じょ【賢女】‥ヂヨ🔗⭐🔉
けん‐じょ【賢女】‥ヂヨ
かしこい女。徒然草「もし―あらば、それもものうとく、すさまじかりなん」
⇒けんじょ‐ごかし【賢女倒し】
⇒けんじょ‐だて【賢女立て】
けん‐しょう【賢相】‥シヤウ🔗⭐🔉
けん‐しょう【賢相】‥シヤウ
賢明な宰相。すぐれた大臣。
けん‐しょう【賢将】‥シヤウ🔗⭐🔉
けん‐しょう【賢将】‥シヤウ
賢明な将軍。
けん‐じょう【賢聖】‥ジヤウ🔗⭐🔉
けん‐じょう【賢聖】‥ジヤウ
(ゲンジョウとも)
①賢人と聖人。知徳のすぐれた人。けんせい。
②〔仏〕悪を離れて良い行いはできるが、まだ悟りの開けない凡夫ぼんぶを賢、悟りを開いた者を聖とする。三賢十聖、四十二賢聖、二十七賢聖などがある。
⇒けんじょう‐の‐そうじ【賢聖障子】
けんじょう‐の‐そうじ【賢聖障子】‥ジヤウ‥サウ‥🔗⭐🔉
けんじょう‐の‐そうじ【賢聖障子】‥ジヤウ‥サウ‥
紫宸殿の母屋と北廂きたびさしとを隔てる障子しょうじ。東西各4間あり、中国の三代から唐までの聖賢・名臣32人の肖像を描く。東方に馬周・房玄齢・杜如晦・魏徴・諸葛亮・蘧伯玉きょはくぎょく・張良・第五倫・管仲・鄧禹とうう・子産・蕭何しょうか・伊尹いいん・傅説ふえつ・太公望・仲山甫、西方に李勣りせき・虞世南・杜預・張華・羊祜ようこ・揚雄・陳寔ちんしょく・班固・桓栄・鄭玄・蘇武・倪寛げいかん・董仲舒とうちゅうじょ・文翁・賈誼かぎ・叔孫通。
⇒けん‐じょう【賢聖】
けんじょ‐ごかし【賢女倒し】‥ヂヨ‥🔗⭐🔉
けんじょ‐ごかし【賢女倒し】‥ヂヨ‥
相手を賢女だと言いはやすこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
けんじょ‐だて【賢女立て】‥ヂヨ‥🔗⭐🔉
けんじょ‐だて【賢女立て】‥ヂヨ‥
賢女らしくふるまうこと。
⇒けん‐じょ【賢女】
けん‐しん【賢臣】🔗⭐🔉
けん‐しん【賢臣】
賢明な家来。すぐれた臣下。
けん‐じん【賢人】🔗⭐🔉
けん‐じん【賢人】
①かしこい人。また、聖人に次ぐ徳のある人。
②(清酒を聖人というのに対して)にごり酒の異称。賢酒。
⇒けんじん‐ごかし【賢人倒し】
⇒けんじん‐だて【賢人立て】
けんじん‐ごかし【賢人倒し】🔗⭐🔉
けんじん‐ごかし【賢人倒し】
相手を賢人だとはやし立てること。
⇒けん‐じん【賢人】
けんじん‐だて【賢人立て】🔗⭐🔉
けんじん‐だて【賢人立て】
賢人らしく見せかけること。
⇒けん‐じん【賢人】
けん‐そく【賢息】🔗⭐🔉
けん‐そく【賢息】
他人の子息の尊敬語。令息。賢郎。
けん‐だい【賢台】🔗⭐🔉
けん‐だい【賢台】
手紙などで、同輩あるいは目上の相手を敬っていう語。賢兄。
けん‐ち【賢智】🔗⭐🔉
けん‐ち【賢智】
かしこくて知恵のある人。〈伊呂波字類抄〉
けん‐てい【賢弟】🔗⭐🔉
けん‐てい【賢弟】
①かしこい弟。「愚兄―」
②相手の弟、年下の男子を敬って呼ぶ語。
けん‐てつ【賢哲】🔗⭐🔉
けん‐てつ【賢哲】
①賢人と哲人。
②かしこくさといこと。賢明で道理をわきまえた人。
けん‐とう【賢答】‥タフ🔗⭐🔉
けん‐とう【賢答】‥タフ
①賢明な答え。
②相手の答えの尊敬語。
けん‐とく【賢徳】🔗⭐🔉
けん‐とく【賢徳】
①かしこく徳あること。
②(「見徳」とも書く)狂言面。視線がはずれ、歯をあらわにした異様な相で、牛・馬・犬・茸の精などに用いる。
賢徳
 賢徳
撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)
賢徳
撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

 賢徳
撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)
賢徳
撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

けん‐のう【賢能】🔗⭐🔉
けん‐のう【賢能】
賢くて才能あること。また、その人。
けん‐ぴ【賢否】🔗⭐🔉
けん‐ぴ【賢否】
賢いことと賢くないこと。賢愚。
けん‐ぷ【賢婦】🔗⭐🔉
けん‐ぷ【賢婦】
かしこい婦人。賢婦人。
けん‐ぷじん【賢夫人】🔗⭐🔉
けん‐ぷじん【賢夫人】
賢明な夫人。
けん‐ぼ【賢母】🔗⭐🔉
けん‐ぼ【賢母】
かしこい母。賢明な母。「良妻―」
けん‐ぽ【賢輔】🔗⭐🔉
けん‐ぽ【賢輔】
かしこい輔佐。賢佐。
けん‐ぼう【賢髦】🔗⭐🔉
けん‐ぼう【賢髦】
名士の中でも特に傑出した人物。賢俊。
けん‐めい【賢明】🔗⭐🔉
けん‐めい【賢明】
賢くて道理に明らかなこと。適切な判断や処置が下せるさま。「―な処置」「まっすぐ帰宅したのは―だった」
けん‐らん【賢覧】🔗⭐🔉
けん‐らん【賢覧】
相手の見ることの尊敬語。高覧。
けん‐り【賢吏】🔗⭐🔉
けん‐り【賢吏】
賢明な役人。
けん‐りょ【賢慮】🔗⭐🔉
けん‐りょ【賢慮】
①賢明な考え。
②相手の考えの尊敬語。
けん‐りょう【賢良】‥リヤウ🔗⭐🔉
けん‐りょう【賢良】‥リヤウ
①賢くて善良なこと。また、その人。
②中国漢代に、官吏登用の目的で地方から推挙された学問・才徳ある者。賢良方正。
けん‐ろう【賢郎】‥ラウ🔗⭐🔉
けん‐ろう【賢郎】‥ラウ
相手のむすこの尊敬語。御子息。令息。賢息。
○賢路を塞ぐけんろをふさぐ🔗⭐🔉
○賢路を塞ぐけんろをふさぐ
賢者の昇進する邪魔となるのも顧みず、不徳不才の者が官職にとどまっていること。
⇒けん‐ろ【賢路】
げん‐ろん【言論】
言語や文章によって思想を発表して論ずること。また、その意見。「―統制」
⇒げんろん‐の‐じゆう【言論の自由】
げん‐ろん【原論】
根本になる理論。また、それを論じたもの。「経済―」
げんろん‐の‐じゆう【言論の自由】‥イウ
(freedom of speech)個人が思想を言論により発表することの自由。近代民主主義の基礎をなす権利の一つで、日本国憲法は第21条でこれを保障。
→参照条文:日本国憲法第21条
⇒げん‐ろん【言論】
げんわ【元和】
(年号)
⇒げんな
げん‐わ【原話】
ある作品のもととなった説話・物語。
けん‐わく【見惑】
(ケンナクとも)〔仏〕思想的な迷い。三道のうち見道で断ぜられる。↔思惑しわく
げん‐わく【幻惑】
目さきをまどわすこと。「トリックに―される」
げん‐わく【眩惑】
目がくらみまどうこと。目をくらましまどわすこと。「目先の華やかさに―される」
げん‐わたし【現渡し】
信用取引や先物さきもの取引で、取引最終日までに買戻しを行うことなく、現物を引き渡して取引を完了すること。特に株式の信用取引で、株式の貸付を受けていた者が、同種同等の株式を返済し、取引を完了すること。
けん‐わん【懸腕】
執筆法の一つ。筆をまっすぐに持ち、腕をあげ肘を脇の下につけないで、字を書くこと。運筆が自由であるため大字を書くのに適する。→枕腕ちんわん→提腕ていわん
さかき【榊・賢木】🔗⭐🔉
さかき【榊・賢木】
①(境さか木の意か)常緑樹の総称。特に神事に用いる木をいう。万葉集3「奥山の―の枝に白香しらかつけ木綿ゆうとりつけて」
②ツバキ科の常緑小高木。葉は厚い革質、深緑色で光沢がある。5〜6月頃、葉のつけ根に白色の細花をつけ、紫黒色の球形の液果を結ぶ。古来神木として枝葉は神に供し、材は細工物・建築などに用いる。「榊の花」は〈[季]夏〉。
さかき
 ③ヒサカキの通称。
④源氏物語の巻名。
⇒さかき‐かき【榊かき】
③ヒサカキの通称。
④源氏物語の巻名。
⇒さかき‐かき【榊かき】
 ③ヒサカキの通称。
④源氏物語の巻名。
⇒さかき‐かき【榊かき】
③ヒサカキの通称。
④源氏物語の巻名。
⇒さかき‐かき【榊かき】
さか‐さか・し【賢賢し】🔗⭐🔉
さか‐さか・し【賢賢し】
〔形シク〕
いかにも賢い。大鏡道長「―・しくおはしまさば」
さか・し【賢し】(形シク)🔗⭐🔉
さか・し【賢し】
〔形シク〕
⇒さかしい
さかし・い【賢しい】🔗⭐🔉
さかし・い【賢しい】
〔形〕[文]さか・し(シク)
①かしこく、すぐれている。聡明だ。万葉集3「古の七の―・しき人どもも欲りせしものは酒にしあるらし」。大鏡序「昔―・しきみかどの御まつりごとのをりは」
②しっかりとゆるぎなく、よくととのっている。また、丈夫で達者である。宇津保物語国譲下「―・しき世ならば、これも坊の親ともなり、高き位にもなるべき人なり」。蜻蛉日記上「おのが―・しからむ時こそ、いかでもいかでもものし給はめ」
③心がしっかりしている。自分を失わない判断力がある。容易になびかぬ抵抗力を持っている。竹取物語「心―・しきもの念じて射むとすれども」。古本説話集下「など―・しうはあるぞ。ただ給はむ物をばたまはらで、かく返し参らする」
④気がきいている。才覚がある。土佐日記「こと人人のもありけれど、―・しきもなかるべし」。源氏物語若菜上「大方の御心おきてに従ひきこえて、―・しき下人もなびきさぶらふこそ」
⑤なまいきだ。さしでがましい。こざかしい。源氏物語総角「例の―・しき女ばら」
さかし‐がお【賢し顔】‥ガホ🔗⭐🔉
さかし‐がお【賢し顔】‥ガホ
自分でかしこいと思っている顔つき。栄華物語日蔭のかづら「いと―にとぶらひ参らする人々などあるを」
⇒さかし【賢し】
さかし‐が・る【賢しがる】🔗⭐🔉
さかし‐が・る【賢しがる】
〔自四〕
かしこそうにふるまう。利口ぶる。さかしだつ。さかしらがる。枕草子121「すずろなるもの恨みし、われ―・る」
さかし‐だ・つ【賢し立つ】🔗⭐🔉
さかし‐だ・つ【賢し立つ】
〔自四〕
(→)「さかしがる」に同じ。
さかし‐びと【賢し人】🔗⭐🔉
さかし‐びと【賢し人】
①かしこい人。けんじん。推古紀「五百いおとせにして乃今いましいま賢さかしひとに遇ふ」
②しっかり者。源氏物語帚木「この―はた軽々しき物怨じすべきにもあらず」
⇒さかし【賢し】
さかし‐め【賢し女】🔗⭐🔉
さかし‐め【賢し女】
賢くすぐれた女。古事記上「こしの国に―をありと聞かして」
⇒さかし【賢し】
さかし‐ら【賢しら】🔗⭐🔉
さかし‐ら【賢しら】
①かしこそうにふるまうこと。利口ぶること。万葉集3「黙もだをりて―するは」。「―な口をきく」「―を言う」
②自分から進んで行動するさま。万葉集16「大君の遣はさなくに―に行きし荒雄ら」
③差し出たふるまい。お節介。また、差し出口。賢しら口。伊勢物語「―する親ありて、思ひもぞつくとて、この女をほかへおひやらむとす」。古今著聞集10「越前房といふ僧来りて見証けんじょすとて、さまざまの―をしけるを」
⇒さかしら‐ぐち【賢しら口】
⇒さかしら‐ごころ【賢しら心】
⇒さかしら‐びと【賢しら人】
さかしら‐が・る【賢しらがる】🔗⭐🔉
さかしら‐が・る【賢しらがる】
〔自四〕
(→)「さかしがる」に同じ。
さかしら‐ぐち【賢しら口】🔗⭐🔉
さかしら‐ぐち【賢しら口】
利口ぶった口ぶり。さしでがましい言動。
⇒さかし‐ら【賢しら】
○座が白けるざがしらける
その座の興が醒める。
⇒ざ【座】
さかしら‐ごころ【賢しら心】🔗⭐🔉
さかしら‐ごころ【賢しら心】
利口ぶった心。源氏物語若紫「なかなかの―なくうち語らひて心のままに教へ」
⇒さかし‐ら【賢しら】
さかしら‐びと【賢しら人】🔗⭐🔉
さかしら‐びと【賢しら人】
さしでがましい人。利口ぶった人。源氏物語蛍「親にはあらでむつかしき御―の」
⇒さかし‐ら【賢しら】
[漢]賢🔗⭐🔉
賢 字形
 筆順
筆順
 〔貝部9画/16画/常用/2413・382D〕
〔音〕ケン(漢) ゲン(呉)
〔訓〕かしこい (名)さとし・さとる・まさる・かた・さか
[意味]
才知や徳がすぐれている。かしこい(人)。「賢者・賢明・聖賢・遺賢・賢夫人」▶相手に敬意を表す語としても用いる。「賢台・賢兄・賢慮」
[解字]
形声。「貝」+音符「
〔貝部9画/16画/常用/2413・382D〕
〔音〕ケン(漢) ゲン(呉)
〔訓〕かしこい (名)さとし・さとる・まさる・かた・さか
[意味]
才知や徳がすぐれている。かしこい(人)。「賢者・賢明・聖賢・遺賢・賢夫人」▶相手に敬意を表す語としても用いる。「賢台・賢兄・賢慮」
[解字]
形声。「貝」+音符「 」(=かたい)。かたい良質の貝の意。転じて、まさる、かしこい、の意。[
」(=かたい)。かたい良質の貝の意。転じて、まさる、かしこい、の意。[ ]は異体字。
[下ツキ
遺賢・七賢・諸賢・聖賢・先賢・前賢・大賢・普賢ふげん
]は異体字。
[下ツキ
遺賢・七賢・諸賢・聖賢・先賢・前賢・大賢・普賢ふげん
 筆順
筆順
 〔貝部9画/16画/常用/2413・382D〕
〔音〕ケン(漢) ゲン(呉)
〔訓〕かしこい (名)さとし・さとる・まさる・かた・さか
[意味]
才知や徳がすぐれている。かしこい(人)。「賢者・賢明・聖賢・遺賢・賢夫人」▶相手に敬意を表す語としても用いる。「賢台・賢兄・賢慮」
[解字]
形声。「貝」+音符「
〔貝部9画/16画/常用/2413・382D〕
〔音〕ケン(漢) ゲン(呉)
〔訓〕かしこい (名)さとし・さとる・まさる・かた・さか
[意味]
才知や徳がすぐれている。かしこい(人)。「賢者・賢明・聖賢・遺賢・賢夫人」▶相手に敬意を表す語としても用いる。「賢台・賢兄・賢慮」
[解字]
形声。「貝」+音符「 」(=かたい)。かたい良質の貝の意。転じて、まさる、かしこい、の意。[
」(=かたい)。かたい良質の貝の意。転じて、まさる、かしこい、の意。[ ]は異体字。
[下ツキ
遺賢・七賢・諸賢・聖賢・先賢・前賢・大賢・普賢ふげん
]は異体字。
[下ツキ
遺賢・七賢・諸賢・聖賢・先賢・前賢・大賢・普賢ふげん
大辞林の検索結果 (64)
かしこ【賢・畏】🔗⭐🔉
かしこ [1] 【賢・畏】
(形容詞「かしこし」の語幹)
□一□〔おそれ慎む意〕
女性が手紙の末尾に書いて敬意を表す語。あらかしこ。あらあらかしこ。かしく。
〔中古には仮名文の消息で男女共に用いた。近世頃から女性のみが用いる〕
□二□
(1)おそれ多いこと。はばかられること。
→あなかしこ
(2)頭がよく知能がすぐれていること。「われ―に思ひたる人/紫式部日記」
(3)技能がすぐれていること。「―の御手やと空を仰ぎてながめ給ふ/源氏(葵)」
かしこ-だて【賢立て】🔗⭐🔉
かしこ-だて 【賢立て】
賢そうにふるまうこと。「多分,人ワ―ヲシテシソコナウモノヂャ/天草本伊曾保」
かしこ・い【賢い・畏い】🔗⭐🔉
かしこ・い [3] 【賢い・畏い】 (形)[文]ク かしこ・し
□一□
(1)頭の働きがよく知恵がすぐれている。賢明だ。《賢》「―・い子」「犬は―・い動物だ」
(2)要領がよい。抜け目がない。《賢》「―・い男だから,その辺はうまく処理するだろう」「―・く立ち回る」
□二□
(1)自然や神など威力・霊力を備えているものに対して脅威を感ずるさま。恐ろしい。畏怖の念に堪えない。「海人娘子(アマオトメ)玉求むらし沖つ波―・き海に船出せり見ゆ/万葉 1003」
(2)高貴な者に対する畏敬の気持ちを表す。おそれ多い。もったいない。「勅なればいとも―・し鶯の宿はと問はば/拾遺(雑下)」
(3)身分・血筋などがきわめてすぐれている。高貴だ。「―・き筋と聞ゆれど/源氏(若菜上)」
(4)立派だ。素晴らしい。「―・き玉の枝をつくらせ給ひて/竹取」
(5)都合がよい。具合がよい。「―・くも(良イ婿ヲ)取りつるかな/落窪 2」
(6)(連用形を副詞的に用いて)はなはだしく。ひどく。「これかれ―・く嘆く/土左」
〔「かしこまる」と同源で,恐るべき威力に対して身のすくむような思いがするさまを表す□二□(1)が原義。そこから恐れ敬う意が生じ,さらに畏敬すべき性質や能力が備わっているさまを表す意ともなった〕
[派生] ――げ(形動)――さ(名)
かしこ・し【賢し・畏し】🔗⭐🔉
かしこ・し 【賢し・畏し】 (形ク)
⇒かしこい
かしこ-じま【賢島】🔗⭐🔉
かしこ-じま 【賢島】
三重県東部,英虞(アゴ)湾北部にある小島。志摩観光の一中心。
かしこ-どころ【賢所】🔗⭐🔉
かしこ-どころ [4] 【賢所】
(1)宮中で天照大神の御霊代(ミタマシロ)として神鏡八咫鏡(ヤタノカガミ)を安置している所。平安時代には内裏の温明殿(ウンメイデン)の南側にあり,内侍が奉仕したので内侍所(ナイシドコロ)ともいった。現在は皇居の吹上御苑にある。けんしょ。
(2)神鏡。「―をいだし奉るにも及ばず/平家 11」
かしこどころ-おおまえ-の-ぎ【賢所大前の儀】🔗⭐🔉
かしこどころ-おおまえ-の-ぎ ―オホマヘ― 【賢所大前の儀】
即位礼に際して,天皇が即位したことを賢所に告げる儀式。
かしこどころ-みかぐら【賢所御神楽】🔗⭐🔉
かしこどころ-みかぐら [8] 【賢所御神楽】
皇室の小祭の一。毎年12月中旬,賢所の前庭で行われる神楽。内侍所御神楽。
けん【賢】🔗⭐🔉
けん [1] 【賢】 (名・形動)[文]ナリ
学徳がすぐれかしこい・こと(さま)。「彼れ美にして且つ―なり/花柳春話(純一郎)」
けん-おう【賢王】🔗⭐🔉
けん-おう ―ワウ [0][3] 【賢王】
賢明な君主。才知と徳を兼ね備えた立派な君主。
けん-ぐ【賢愚】🔗⭐🔉
けん-ぐ [1] 【賢愚】
賢いことと愚かなこと。賢者と愚者。
けん-くん【賢君】🔗⭐🔉
けん-くん [0] 【賢君】
賢明な君主。
けん-けい【賢兄】🔗⭐🔉
けん-けい [0] 【賢兄】
■一■ (名)
かしこい兄。また,他人の兄を敬っていう語。「―愚弟」
■二■ (代)
二人称。男子が手紙などで同輩を敬っていう語。大兄。貴兄。
けん-さい【賢才】🔗⭐🔉
けん-さい [0] 【賢才】
すぐれた才能。賢明な人。
けん-さい【賢妻】🔗⭐🔉
けん-さい [0] 【賢妻】
かしこい妻。「―ぶりを発揮する」
けん-さつ【賢察】🔗⭐🔉
けん-さつ [0] 【賢察】 (名)スル
他人が推察することを敬っていう語。高察。お察し。「御―の通りです」
けん-し【賢士】🔗⭐🔉
けん-し [1] 【賢士】
かしこい人。賢人。
けんじゃ=ひだるし伊達(ダテ)寒し🔗⭐🔉
――ひだるし伊達(ダテ)寒し
賢者は世俗に妥協しないために飢え,伊達者は薄着をするので寒い。俗人とちがった生き方をするものはつらい目にあうというたとえ。
けんじゃ-の-いし【賢者の石】🔗⭐🔉
けんじゃ-の-いし 【賢者の石】
中世ヨーロッパの錬金術師たちが,あらゆる物を金に変え,またあらゆる病気を治す力があると信じて探し求めた物質。哲学者の石。
けん-しゅ【賢主】🔗⭐🔉
けん-しゅ [1] 【賢主】
賢明な君主。
けん-しょ【賢所】🔗⭐🔉
けん-しょ [1] 【賢所】
⇒かしこどころ(賢所)
けん-じょ【賢女】🔗⭐🔉
けん-じょ ―ヂヨ [1] 【賢女】
かしこい女。
けんじょ-だて【賢女立て】🔗⭐🔉
けんじょ-だて ―ヂヨ― 【賢女立て】
賢女らしく振る舞うこと。「おのれが縁を切らずんば,―して我心に従ふまじと思うて/浄瑠璃・井筒業平」
けん-しょう【賢相】🔗⭐🔉
けん-しょう ―シヤウ [0] 【賢相】
賢明な宰相。賢宰。
けん-しょう【賢将】🔗⭐🔉
けん-しょう ―シヤウ [0] 【賢将】
かしこくすぐれた将軍。
けん-じょう【賢聖】🔗⭐🔉
けん-じょう ―ジヤウ [0] 【賢聖】
(1)〔仏〕
〔「げんじょう」とも〕
(ア)悪を去ったが凡夫にとどまっている者(=賢)と,真理をさとった者(=聖)。けんせい。
→見道(ケンドウ)
(イ)仏道修行を積んだ高徳の僧。
(2)「賢聖(ケンセイ){(1)}」に同じ。
けんじょう-の-そうじ【賢聖の障子】🔗⭐🔉
けんじょう-の-そうじ ―ジヤウ―サウジ 【賢聖の障子】
紫宸殿(シシンデン)の母屋と北廂(キタビサシ)を隔てる障子。九枚あり,中央には獅子・狛犬と文書を負った亀を,左右各四枚には中国唐代までの聖賢・名臣を一枚に四人ずつ三二人の肖像を描く。
けん-しん【賢臣】🔗⭐🔉
けん-しん [0] 【賢臣】
かしこい臣下。「―二君に仕えず」
けん-じん【賢人】🔗⭐🔉
けん-じん [0] 【賢人】
(1)知識が豊かで徳のある人。聖人に次いで徳のある人。「竹林の七―」
(2)(清酒を聖人というのに対して)濁り酒。賢酒。
けんじん-だて【賢人立て】🔗⭐🔉
けんじん-だて 【賢人立て】
賢人らしく見せかけること。「ただ一人まじりたまはざりつれば,―かと思ひて侍つるに/著聞 12」
けん-せい【賢聖】🔗⭐🔉
けん-せい [0] 【賢聖】
(1)賢人と聖人。また,知恵と徳を兼ねそなえた人。聖賢。けんじょう。
(2)〔仏〕「賢聖(ケンジヨウ){(1)}」に同じ。
(3)にごり酒(=賢)と清酒(=聖)。
けん-そく【賢息】🔗⭐🔉
けん-そく [0] 【賢息】
他人を敬ってその子息をいう語。また,かしこい子息。
けん-だい【賢台】🔗⭐🔉
けん-だい [1][0] 【賢台】 (代)
二人称。男子が手紙などで,同輩または先輩を敬っていう語。貴兄。貴台。
けん-ち【賢智】🔗⭐🔉
けん-ち [1] 【賢智】
賢く知恵のあること。また,その人。
けん-てい【賢弟】🔗⭐🔉
けん-てい [0] 【賢弟】
■一■ (名)
かしこい弟。また,他人の弟に対する敬称。「愚兄―」
■二■ (代)
二人称。男子が手紙などで,年下の男子を敬っていう語。
けん-てつ【賢哲】🔗⭐🔉
けん-てつ [0] 【賢哲】 (名・形動)[文]ナリ
(1)賢人と哲人。
(2)賢明で道理に通じていること。また,そうした人やさま。「―なる者其信ずる所を明かにして/明六雑誌 8」
けん-とう【賢答】🔗⭐🔉
けん-とう ―タフ [0] 【賢答】
(1)賢明な答え。立派な答え。「愚問―」
(2)相手を敬ってその答えをいう語。
けん-とく【賢徳】🔗⭐🔉
けん-とく [0] 【賢徳】
狂言面の一。鬼畜面で,「犬山伏」の犬,「止動方角」の馬,また蟹(カニ)・蛸(タコ)などに用いる。
賢徳
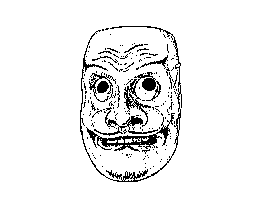 [図]
[図]
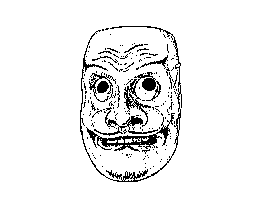 [図]
[図]
けん-のう【賢能】🔗⭐🔉
けん-のう [0] 【賢能】
賢くて才能のあること。また,その人。
けん-ぷ【賢婦】🔗⭐🔉
けん-ぷ [1] 【賢婦】
かしこくしっかりした婦人。賢婦人。
けん-ぷじん【賢夫人】🔗⭐🔉
けん-ぷじん [3] 【賢夫人】
かしこくてしっかりした夫人。
けん-ぼ【賢母】🔗⭐🔉
けん-ぼ [1] 【賢母】
賢明な母。かしこい母。「良妻―」
けん-めい【賢明】🔗⭐🔉
けん-めい [0] 【賢明】 (名・形動)[文]ナリ
賢くて,適切な判断を下せる・こと(さま)。「―な判断」
[派生] ――さ(名)
けん-らん【賢覧】🔗⭐🔉
けん-らん [0] 【賢覧】
相手が見ることを敬っていう語。高覧。「―を願う」
けん-りょ【賢慮】🔗⭐🔉
けん-りょ [1] 【賢慮】
(1)賢い考え。賢明な思慮。
(2)相手の考え・判断などを敬っていう語。
けん-りょう【賢良】🔗⭐🔉
けん-りょう ―リヤウ [0] 【賢良】 (名・形動)[文]ナリ
(1)賢くて善良なこと。また,その人やさま。「君主宰臣の―なりしを/日本開化小史(卯吉)」
(2)中国漢代,官吏登用試験の科目の名。また,それに推挙された才学のある者。
けん-ろ【賢路】🔗⭐🔉
けん-ろ [1] 【賢路】
賢者の昇進するみち。
けんろ=を塞(フサ)ぐ🔗⭐🔉
――を塞(フサ)ぐ
〔潘岳(「河陽県作」)〕
不徳不才の者が官職にとどまって,賢者の昇進の邪魔になること。
さか-き【榊・賢木】🔗⭐🔉
さか-き [0] 【榊・賢木】
〔栄える木の意〕
(1)神域に植える常緑樹の総称。また,神事に用いる木。
(2)ツバキ科の常緑小高木。暖地の山中に自生。高さ約10メートル。葉は互生し,長楕円状倒卵形。濃緑色で質厚く光沢がある。六,七月,白色の小花を開く。枝葉を神事に用いる。
〔「榊の花」は [季]夏〕
→ひさかき
(3)源氏物語の巻名。第一〇帖。
さかさか・し【賢賢し】🔗⭐🔉
さかさか・し 【賢賢し】 (形シク)
〔「さかざかし」とも〕
機転がきく。しっかりしている。「奴は合戦におきては,以ての外―・しき者にて候/保元(上)」
さかし・い【賢しい】🔗⭐🔉
さかし・い [3] 【賢しい】 (形)[文]シク さか・し
(1)かしこい。利口だ。「それが―・い生き方というものなのだろう」
(2)小利口で,なまいきだ。こざかしい。「へんに―・いところが人に嫌われる」
(3)盛んである。栄えている。「斑鳩のなみきの宮にたてし憲法(ノリ)今の―・しき御代にあふかな/日本紀竟宴和歌」
(4)気が強い。勇ましい。心がしっかりしている。「中に心―・しき者,念じて射むとすれども/竹取」
(5)すぐれている。巧みだ。じょうずだ。「ことひとびとのもありけれど,―・しきもなかるべし/土左」
(6)健康だ。じょうぶだ。「をのが―・しからむときこそ,いかでもいかでもものしたまはめ/蜻蛉(上)」
[派生] ――げ(形動)
さかし-だ・つ【賢し立つ】🔗⭐🔉
さかし-だ・つ 【賢し立つ】 (動タ四)
かしこそうに振る舞う。利口ぶる。さかしがる。「さばかり―・ち真名書き散らして侍るほども/紫式部日記」
さかし-ら【賢しら】🔗⭐🔉
さかし-ら [0] 【賢しら】 (名・形動)[文]ナリ
〔「ら」は接尾語〕
(1)利口ぶること。いかにもわかっているというふうに振る舞うこと。また,そのさま。「―を言う」「―をする」「―な顔つき」
(2)自分の考えで行動すること。「大君の遣はさなくに―に行きし荒雄ら沖に袖振る/万葉 3860」
(3)差し出口をきくこと。「―する親ありて,思ひもぞつくとて,この女をほかへ追ひやらむとす/伊勢 40」
(4)でしゃばる・こと(さま)。「まだ夜は深からむものを。葛城の神の―にや/狭衣 4」
さかしら-ぐち【賢しら口】🔗⭐🔉
さかしら-ぐち [4] 【賢しら口】
利口ぶった口ぶり。「―をきく」
さかしら-びと【賢しら人】🔗⭐🔉
さかしら-びと 【賢しら人】
でしゃばる人。利口ぶった人。「―すくなくて良き折りにこそ,と思へば/源氏(手習)」
かしこい【賢い】(和英)🔗⭐🔉
かしこさ【賢さ】(和英)🔗⭐🔉
けんじゃ【賢者】(和英)🔗⭐🔉
けんじゃ【賢者】
⇒賢人.
けんじん【賢人】(和英)🔗⭐🔉
けんじん【賢人】
a wise man;a sage.→英和
広辞苑+大辞林に「賢」で始まるの検索結果。