複数辞典一括検索+![]()
![]()
たち【達】🔗⭐🔉
たち 【達】 (接尾)
名詞・代名詞に付いて,それらが複数であることを表す。「きみ―のせいだ」「わたし―も頑張る」「森の小鳥―」
〔古くは敬意を含み,神や貴人にだけ付いた。現在では「ども」「ら」のような見下した感じはないが,「かた」ほどの敬意はなく,普通,尊敬すべき人にはつけない〕
たつ-い【達意】🔗⭐🔉
たつ-い [1] 【達意】
言わんとする事柄を十分にわからせること。「―の文章」
たっ-かん【達観】🔗⭐🔉
たっ-かん ―クワン [0] 【達観】 (名)スル
(1)細かい事にこだわらず,物事の本質を見通すこと。また,物事に超然として,悟りの心境に達すること。「人生を―する」
(2)広い視野で物事を見ること。全体を見渡すこと。「若し―する時は世界は罪を持ちながらに美である/善の研究(幾多郎)」
たつ-がん【達眼】🔗⭐🔉
たつ-がん [0] 【達眼】
物事の本質を見抜く鋭い眼力。「―の士」
たっ-けん【達見】🔗⭐🔉
たっ-けん [0] 【達見】
広い見通しをもった,優れた見解。
たっ-さい【達才】🔗⭐🔉
たっ-さい [0] 【達才】
広く物事に通じている優れた才能。また,その人。達材。
たっ-し【達し】🔗⭐🔉
たっ-し [0] 【達し】
(1)官庁から一般人民,または上級官庁から下級官庁へ通知が出されること。また,その文書。ふれ。「その筋からお―があった」
(2)(「達示」とも書く)上司から部下に出される通知。
(3)江戸幕府で,老中または諸役の上司から下司の者に発した命令。
たっし-がき【達し書き】🔗⭐🔉
たっし-がき [0] 【達し書き】
達しを書いた文書。ふれがき。達し文(ブミ)。
たっ-し【達士】🔗⭐🔉
たっ-し [1] 【達士】
ある物事によく通じている人。達人。
たっ-しき【達識】🔗⭐🔉
たっ-しき [0] 【達識】
物事の全体を広く見通す,優れた見識。達見。
たっ-しゃ【達者】🔗⭐🔉
たっ-しゃ [0] 【達者】
■一■ (名)
ある道をきわめた人。達人。「弓の―」
■二■ (形動)[文]ナリ
(1)ある事に熟達しているさま。上手であるさま。「英語が―だ」「口の―なやつ」「―な筆づかい」
(2)体の各部の働きが優れているさま。また,体が丈夫で健康であるさま。「年はとっても目は―だ」「祖母は―にしております」
(3)物事をするのにしたたかで抜け目のないさま。「その方面にかけては―な男」
〔■一■の意が原義〕
たっしゃ-もの【達者者】🔗⭐🔉
たっしゃ-もの [0] 【達者者】
(1)ある事柄に熟達している者。また,体の丈夫な者。
(2)経験豊かな,したたか者。
たっ・しる【達しる】🔗⭐🔉
たっ・しる 【達しる】 (動サ上一)
〔サ変動詞「達する」の上一段化〕
「達する」に同じ。「総て砲器の筒先を後ろへ向けると―・しらるれば/近世紀聞(延房)」
たつ-じん【達人】🔗⭐🔉
たつ-じん [0] 【達人】
豊富な経験と長年の鍛練により,その道の真髄を体得した人。「―の境地に入る」「剣道の―」
たつじん=は大観す🔗⭐🔉
――は大観す
〔「 冠子(世兵)」,賈誼「
冠子(世兵)」,賈誼「 鳥賦」〕
達人は一部分にとらわれず全体を見通すので判断を誤らない。
鳥賦」〕
達人は一部分にとらわれず全体を見通すので判断を誤らない。
 冠子(世兵)」,賈誼「
冠子(世兵)」,賈誼「 鳥賦」〕
達人は一部分にとらわれず全体を見通すので判断を誤らない。
鳥賦」〕
達人は一部分にとらわれず全体を見通すので判断を誤らない。
たっ・する【達する】🔗⭐🔉
たっ・する [0][3] 【達する】 (動サ変)[文]サ変 たつ・す
□一□(自動詞)
(1)ある場所に行き至る。到達する。「山頂に―・する」「目的地に―・する」
(2)情報がある人に伝わり届く。伝わってある人の知るところとなる。「社長の耳に―・する」「上聞ニ―・ス/ヘボン」
(3)程度が限度に及ぶ。最高のところまで至る。また,深く通じる。「名人の域に―・する」「孔子は此礼と云ふ者に深く博く―・した人と見える/百一新論(周)」「管絃の道に―・し/平家 3」
(4)一定の数値にまで届く。「人口が百万に―・する」「募金が目標額に―・する」
□二□(他動詞)
(1)物事を成しとげる。達成する。「目的を―・する」
(2)ある事柄を人に届け知らせる。広く告げ知らせる。「東京に於て某氏とのみ記せる書状を―・するは実に困難の極/新聞雑誌 46」
たっ-せい【達成】🔗⭐🔉
たっ-せい [0] 【達成】 (名)スル
成し遂げること。「目標を―する」
たっせい-どうき【達成動機】🔗⭐🔉
たっせい-どうき [5] 【達成動機】
〔心〕 困難な物事を迅速かつ立派にやりとげるために努力しようとする動機。
たっ-そん【達尊】🔗⭐🔉
たっ-そん [0] 【達尊】
世間一般に尊ばれる物事。学徳・爵位・年齢など。
たっち-もん【達智門】🔗⭐🔉
たっち-もん 【達智門】
平安京大内裏の外郭十二門の一。北面し,偉鑒(イカン)門の東にある。だっちもん。たちいもん。
→大内裏
たっ-て【達て・強って】🔗⭐🔉
たっ-て [1][0] 【達て・強って】 (副)
〔「達て」「強って」は当て字〕
要求・希望などをどうしても実現しようとするさま。無理に。しいて。どうしてでも。「―お望みとあれば致し方ない」「別に―飲みたくもないけれど/二人女房(紅葉)」
たって-の【達ての】🔗⭐🔉
たって-の 【達ての】 (連語)
大変切実な。大変激しい。現代では多く連体詞的に用いる。「―の願い」「―の所望」
たつ-どう【達道】🔗⭐🔉
たつ-どう ―ダウ [0] 【達道】
〔「たっとう」とも〕
いかなる場合にも行われるべき人間の道。
たっ-とく【達徳】🔗⭐🔉
たっ-とく [0] 【達徳】
古今東西を通じて尊ばれる徳。
たっ-ぱい【達拝】🔗⭐🔉
たっ-ぱい [0] 【達拝】
能の拝礼の型。両手を高めに肘(ヒジ)をひろげて前方に出し,こぶしを顔の前で合わせるようにするもの。ワキが名乗りのあとで行う。
たっ-ぴつ【達筆】🔗⭐🔉
たっ-ぴつ [0] 【達筆】 (名・形動)[文]ナリ
(1)文字を上手に書く・こと(さま)。また,その文字。能筆。「―な字」
(2)勢いのある筆づかい。健筆。
たつ-ぶん【達文】🔗⭐🔉
たつ-ぶん [0] 【達文】
(1)上手な,優れた文章。
(2)意味のよくわかる文章。達意の文。
たつ-べん【達弁】🔗⭐🔉
たつ-べん [0] 【達弁】
達者な弁舌。能弁。「―を振るう」
だつ-ま【達摩】🔗⭐🔉
だつ-ま [1] 【達摩】
(1)数珠(ジユズ)に通してある玉の中で,とめにする大玉。おやだま。
(2)達磨(ダルマ)のこと。
たつ-り【達理】🔗⭐🔉
たつ-り [1] 【達理】
道理に通じること。物事の奥義を身につけること。
たて-いれ【立て入れ・達入れ】🔗⭐🔉
たて-いれ [0] 【立て入れ・達入れ】
(1)男としての義理や意気地を立て通すこと。意地の張り合い。たてひき。「そりや―ぢやない。とつとの横入ぢや/滑稽本・浮世床(初)」
(2)喧嘩。
だて-しゅう【伊達衆・達衆】🔗⭐🔉
だて-しゅう 【伊達衆・達衆】
〔「たてしゅ」「たてし」とも〕
(1)伊達(ダテ)を好む人々。
(2)男伊達(ダテ)。侠客。「そこをそのまま通さぬが白柄組の―の意地づく/歌舞伎・鞘当」
たて-ひき【立て引き・達引き】🔗⭐🔉
たて-ひき 【立て引き・達引き】 (名)スル
(1)意地を張り通すこと。義理を立てること。「私(ワチキ)がお前に―でこれまでにした親切を/人情本・梅児誉美(後)」
(2)意気地を見せて支払いを引き受けること。金品を用立てること。「二朱と三朱の―までして呼んで遣りやあいいかと思つて/洒落本・客衆肝照子」
(3)意地を張り合うこと。談判。喧嘩。「角の酒屋で何やら―しやがつたさうだ/洒落本・郭中奇譚」
たて-ひ・く【立て引く・達て引く】🔗⭐🔉
たて-ひ・く 【立て引く・達て引く】 (動カ四)
(1)義理立てをする。意地を張り合う。「兄弟分の友誼(ヨシミ)で此事はいはないと―・いて呉れるなら/真景累ヶ淵(円朝)」
(2)義理を立てて他人の金銭を立て替える。特に遊女が客の遊興費を負担する。「梅田屋の女がいつでも―・くよ/洒落本・角鶏卵」
だるま【達磨】🔗⭐🔉
だるま [0] 【達磨】
(1)〔梵 Bodhi-dharma 菩提達磨と訳す〕
中国禅宗の祖。南インドの王子として生まれ,般若多羅から教えを受け,中国に渡って禅宗を伝えた。少林寺に九年面壁したといわれる。五世紀末から六世紀末の人とされる。なお,「達摩」と表記して,歴史上の人物として扱うことを示し,宗門上の伝説と区別することがある。円覚大師。達磨大師。生没年未詳。
(2){(1)}の座禅姿を模して作った張り子の玩具。赤く塗り,全体を丸くかたどり,底を重くして倒してもすぐ起き上がるようにしてある。開運の縁起物とされ,最初片目だけを書き,願いのかなった時にもう一方の目を書き込んで祝う。起き上がり小法師。不倒翁。
(3)形が丸いものや,全体の色が赤いものをいう。「―ストーブ」「血―」「火―」
(4)〔仏〕
〔梵 Dharma〕
「法{□二□}」に同じ。
(5)〔すぐにころぶことから〕
売春婦のこと。
だるま-いち【達磨市】🔗⭐🔉
だるま-いち [3] 【達磨市】
神社や寺の縁日で開かれる縁起物の達磨を売る市。多く東日本で一月ないし年末に開かれる。
だるま-いと【達磨糸】🔗⭐🔉
だるま-いと [4] 【達磨糸】
足踏み式の製糸機械で作った生糸。自転車取糸。
だるま-いんこ【達磨鸚哥】🔗⭐🔉
だるま-いんこ [4] 【達磨鸚哥】
オウム目インコ科の鳥。中形のインコで,翼長170ミリメートル内外。羽色は緑色を主調とし,胸は淡桃色など色彩に富む。尾が長い。雄の頬には太い黒線があり,達磨のひげに似るのでこの名がある。熱帯アジアに分布し,日本へは古くから飼鳥として輸入されている。
だるま-うた【達磨歌】🔗⭐🔉
だるま-うた [3] 【達磨歌】
歌論で意味の難解な歌のこと。特に定家らの象徴的幽玄の歌風を六条家側から揶揄(ヤユ)していった呼称。
だるま-おとし【達磨落(と)し】🔗⭐🔉
だるま-おとし [4] 【達磨落(と)し】
(1)玩具の一。円筒形の木片を数個重ねた上に達磨人形を置き,それが落ちないようにして木槌(キヅチ)で木片を横からたたいてはずして遊ぶもの。
(2)台の上の達磨人形を,コルク玉の鉄砲やまりで落とす遊戯。
だるま-がえし【達磨返し】🔗⭐🔉
だるま-がえし ―ガヘシ [4] 【達磨返し】
江戸末期・明治時代の女性の髪形の一。髪をひねって頭上にあげ,髱(タボ)の中に押し込み簪(カンザシ)でとめたもの。伝法な年増が多く結った。
達磨返し
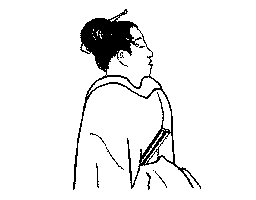 [図]
[図]
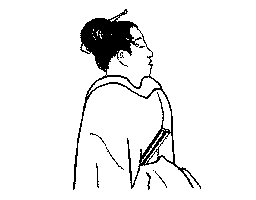 [図]
[図]
だるま-かずき【達磨被き】🔗⭐🔉
だるま-かずき ―カヅキ [4] 【達磨被き】
達磨が緋の衣をかぶっているように着物を上からすっぽりとかぶること。
だるま-き【達磨忌】🔗⭐🔉
だるま-き [3] 【達磨忌】
禅宗で,陰暦一〇月五日の達磨の忌日に行う法会(ホウエ)。少林忌。初祖忌。[季]冬。
だるま-ぎく【達磨菊】🔗⭐🔉
だるま-ぎく [3] 【達磨菊】
キク科の多年草。海岸の岩上に生え,また観賞用に栽培。茎は木質化しよく分枝する。葉は密に互生し,倒卵へら形で毛が多い。秋,枝先に頭花をつけ,舌状花は青紫色で美しい。
だるま-しゅう【達磨宗】🔗⭐🔉
だるま-しゅう [3] 【達磨宗】
(1)禅宗の異名。
(2)藤原定家などの和歌の新風を嘲っていう語。
→達磨歌
だるま-ストーブ【達磨―】🔗⭐🔉
だるま-ストーブ [5] 【達磨―】
丸形の簡単な構造の石炭ストーブ。
だるま-せん【達磨船】🔗⭐🔉
だるま-せん [0] 【達磨船】
積み荷を運ぶための幅の広い大きな伝馬船。だるまぶね。
だるま-そう【達磨草】🔗⭐🔉
だるま-そう ―サウ [0] 【達磨草】
ザゼンソウの別名。
だるま-だいし【達磨大師】🔗⭐🔉
だるま-だいし 【達磨大師】
達磨の尊称。
だるま-でら【達磨寺】🔗⭐🔉
だるま-でら 【達磨寺】
群馬県高崎市にある黄檗(オウバク)宗の寺。山号は少林山。正月六・七日に開かれる達磨市が有名。
だるま-はがし【達磨剥がし】🔗⭐🔉
だるま-はがし [4] 【達磨剥がし】
人の着ている羽織をぬがせて奪うこと。また,その盗人。
だるま-や【達磨屋】🔗⭐🔉
だるま-や [0] 【達磨屋】
売春婦を置いている宿。
たっかん【達観する】(和英)🔗⭐🔉
たっかん【達観する】
have an insight;→英和
viewwith a philosophic eye.
たっし【達し】(和英)🔗⭐🔉
たっし【達し】
an official notice.
たつじん【達人】(和英)🔗⭐🔉
たっぴつ【達筆】(和英)🔗⭐🔉
たっぴつ【達筆】
a good hand.〜でin a good hand.
だるま【達磨】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「達」で始まるの検索結果 1-61。