複数辞典一括検索+![]()
![]()
○背を縒るせをよる🔗⭐🔉
○背を縒るせをよる
労苦・苦痛に苦しむ。〈日葡辞書〉
⇒せ【背・脊】
せん【千・阡】
数の名。百の10倍。また、数の多いこと。「阡」は大字。
⇒千も万もいらぬ
せん【千】
姓氏の一つ。
⇒せん‐しょうあん【千少庵】
⇒せん‐そうえき【千宗易】
⇒せん‐そうさ【千宗左】
⇒せん‐そうしつ【千宗室】
⇒せん‐そうたん【千宗旦】
⇒せん‐どうあん【千道安】
⇒せん‐の‐りきゅう【千利休】
せん【仙・僊】
(→)仙人に同じ。
せん【先】
①さき。
㋐空間的に前の方。
㋑時間的に早いとき。以前。誹風柳多留20「―の亭主に御無用とうんのつき」。傾城禁短気「―橘の六郎右衛門が後家へ後連れに肝煎」。「―から知っている」
②過去になったもの。一つ前のもの。「―号の記事」
③他よりさきんじて事を行うこと。さきがけ。狂言、宗論「何がさて御坊が―ぢや」
④囲碁・将棋で、相手より先に打ち始める方。先手。
⇒先を越す
せん【疝】
(→)疝気せんきに同じ。
せん【宣】
①天子や神の言葉。みことのり。
②官衙・将軍などの命令。愚管抄5「諸国七道へ宮の―とて」。「太政官の―」
せん【専】
①第一のもの。必要欠くべからざること。宇治拾遺物語12「其の年の祭には、これを―にてぞありける」
②専門学校の略。
せん【泉】
①温泉の略。
②(銭の流通は泉のようであるからいう)貨幣。ぜに。
③和泉国いずみのくにの略。
せん【栓】
①物の穴に差し込んで、その物が動かないようにする物。
②管や容器などの口をふさぎ、中のものが漏れ出ないようにするもの。「―を抜く」
せん【戦】
たたかうこと。また、試合・競争。「リーグ―」「三―全勝」
せん【腺】
(宇田川榛斎(1769〜1834)が創った国字。「医範提綱」で初めて用いた)動物の上皮から分化し、それぞれに特有の物質を分泌する器官。導管を具えて体外あるいは消化管内に分泌物を出す外分泌腺と、導管が無く血液内に分泌物を出す内分泌腺とがある。
せん【詮】
①せんじつめること。結局。平家物語2「申しつくる所の―は、ただ重盛が首を召され候へ」
②くわしく調べること。源平盛衰記1「かやうの実の―に逢ひ奉らむ者は」
③なすべき方法。すべ。古今著聞集1「―尽きて眠りゐたりけるほどに」
④かい。しるし。ききめ。狂言、二人大名「参つた―もない事でござる」
せん【箋】
①目印やメモのための紙。ふだ。手紙。文書。「―を付ける」
②注釈を書きつけること。
③巻子本かんすぼんの軸や帙簀ちすの紐に結びつけ、または冊子に挿入し、検出の用に供する札。竹・木・象牙などで作り、書名や年号などを記し、その上部に孔をあけ、紐を通したもの。籤せん。
箋
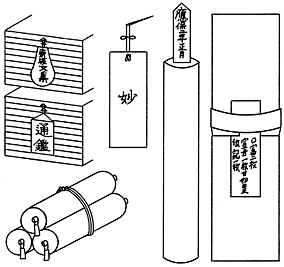 せん【銭】
①⇒ぜに。
②日本の貨幣の単位。
㋐円の100分の1。
㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。
③匁もんめの唐名。
せん【撰】
①詩文をつくること。
②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」
せん【線】
①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」
②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。
③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」
④物の輪郭。「身体の―」
⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」
⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」
⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」
⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」
⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」
せん【賤】
身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」
せん【選】
えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」
せん【暹】
暹羅シャムの略。
せん【磚・塼・甎】
中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。
せん【薦】
すすめること。推挙すること。
せん【氈】
毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」
せん【繊】
1の1000万分の1。
せん【餞】
はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」
せん【鏟・鑯】
両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。
鏟
せん【銭】
①⇒ぜに。
②日本の貨幣の単位。
㋐円の100分の1。
㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。
③匁もんめの唐名。
せん【撰】
①詩文をつくること。
②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」
せん【線】
①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」
②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。
③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」
④物の輪郭。「身体の―」
⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」
⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」
⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」
⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」
⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」
せん【賤】
身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」
せん【選】
えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」
せん【暹】
暹羅シャムの略。
せん【磚・塼・甎】
中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。
せん【薦】
すすめること。推挙すること。
せん【氈】
毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」
せん【繊】
1の1000万分の1。
せん【餞】
はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」
せん【鏟・鑯】
両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。
鏟
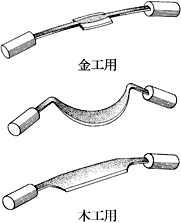 せん【饌】
神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。
せん【籤】
(→)箋せん3に同じ。
セン【Amartya Kumar Sen】
イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)
ぜん【全】
①欠けたところがないこと。
②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」
ぜん【前】
(呉音。漢音はセン)
①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」
②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」
㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」
ぜん【善】
正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪
⇒善に従うこと流るるが如し
⇒善に強い者は悪にも強い
⇒善の裏は悪
⇒善は急げ
⇒善を責むるは朋友の道なり
ぜん【然】
(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」
ぜん【禅】
①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」
②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。
③禅宗の略。
ぜん【漸】
徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。
⇒漸を追って
ぜん【膳】
①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」
②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」
③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」
④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」
せん‐あい【専愛】
多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。
せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥
囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん
せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ
硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。
閃亜鉛鉱
撮影:松原 聰
せん【饌】
神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。
せん【籤】
(→)箋せん3に同じ。
セン【Amartya Kumar Sen】
イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)
ぜん【全】
①欠けたところがないこと。
②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」
ぜん【前】
(呉音。漢音はセン)
①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」
②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」
㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」
ぜん【善】
正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪
⇒善に従うこと流るるが如し
⇒善に強い者は悪にも強い
⇒善の裏は悪
⇒善は急げ
⇒善を責むるは朋友の道なり
ぜん【然】
(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」
ぜん【禅】
①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」
②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。
③禅宗の略。
ぜん【漸】
徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。
⇒漸を追って
ぜん【膳】
①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」
②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」
③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」
④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」
せん‐あい【専愛】
多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。
せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥
囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん
せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ
硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。
閃亜鉛鉱
撮影:松原 聰
 ぜん‐あく【前悪】
以前に行なった悪事。前世の罪業。
ぜん‐あく【善悪】
(古くはゼンナク・ゼンマクとも)
[一]〔名〕
善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」
[二]〔副〕
よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」
⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】
⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】
⇒善悪の生を引く
⇒善悪の報は影の形に随うが如し
ぜん‐あく【前悪】
以前に行なった悪事。前世の罪業。
ぜん‐あく【善悪】
(古くはゼンナク・ゼンマクとも)
[一]〔名〕
善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」
[二]〔副〕
よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」
⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】
⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】
⇒善悪の生を引く
⇒善悪の報は影の形に随うが如し
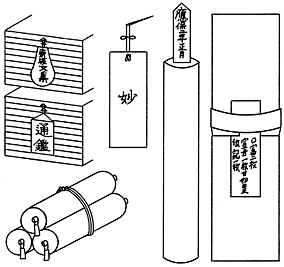 せん【銭】
①⇒ぜに。
②日本の貨幣の単位。
㋐円の100分の1。
㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。
③匁もんめの唐名。
せん【撰】
①詩文をつくること。
②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」
せん【線】
①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」
②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。
③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」
④物の輪郭。「身体の―」
⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」
⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」
⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」
⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」
⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」
せん【賤】
身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」
せん【選】
えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」
せん【暹】
暹羅シャムの略。
せん【磚・塼・甎】
中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。
せん【薦】
すすめること。推挙すること。
せん【氈】
毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」
せん【繊】
1の1000万分の1。
せん【餞】
はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」
せん【鏟・鑯】
両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。
鏟
せん【銭】
①⇒ぜに。
②日本の貨幣の単位。
㋐円の100分の1。
㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。
③匁もんめの唐名。
せん【撰】
①詩文をつくること。
②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」
せん【線】
①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」
②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。
③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」
④物の輪郭。「身体の―」
⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」
⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」
⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」
⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」
⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」
せん【賤】
身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」
せん【選】
えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」
せん【暹】
暹羅シャムの略。
せん【磚・塼・甎】
中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。
せん【薦】
すすめること。推挙すること。
せん【氈】
毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」
せん【繊】
1の1000万分の1。
せん【餞】
はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」
せん【鏟・鑯】
両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。
鏟
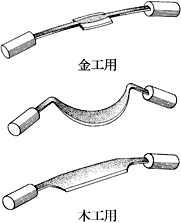 せん【饌】
神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。
せん【籤】
(→)箋せん3に同じ。
セン【Amartya Kumar Sen】
イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)
ぜん【全】
①欠けたところがないこと。
②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」
ぜん【前】
(呉音。漢音はセン)
①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」
②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」
㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」
ぜん【善】
正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪
⇒善に従うこと流るるが如し
⇒善に強い者は悪にも強い
⇒善の裏は悪
⇒善は急げ
⇒善を責むるは朋友の道なり
ぜん【然】
(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」
ぜん【禅】
①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」
②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。
③禅宗の略。
ぜん【漸】
徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。
⇒漸を追って
ぜん【膳】
①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」
②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」
③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」
④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」
せん‐あい【専愛】
多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。
せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥
囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん
せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ
硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。
閃亜鉛鉱
撮影:松原 聰
せん【饌】
神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。
せん【籤】
(→)箋せん3に同じ。
セン【Amartya Kumar Sen】
イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)
ぜん【全】
①欠けたところがないこと。
②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」
ぜん【前】
(呉音。漢音はセン)
①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」
②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」
㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」
ぜん【善】
正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪
⇒善に従うこと流るるが如し
⇒善に強い者は悪にも強い
⇒善の裏は悪
⇒善は急げ
⇒善を責むるは朋友の道なり
ぜん【然】
(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」
ぜん【禅】
①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」
②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。
③禅宗の略。
ぜん【漸】
徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。
⇒漸を追って
ぜん【膳】
①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」
②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」
③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」
④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」
せん‐あい【専愛】
多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。
せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥
囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん
せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ
硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。
閃亜鉛鉱
撮影:松原 聰
 ぜん‐あく【前悪】
以前に行なった悪事。前世の罪業。
ぜん‐あく【善悪】
(古くはゼンナク・ゼンマクとも)
[一]〔名〕
善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」
[二]〔副〕
よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」
⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】
⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】
⇒善悪の生を引く
⇒善悪の報は影の形に随うが如し
ぜん‐あく【前悪】
以前に行なった悪事。前世の罪業。
ぜん‐あく【善悪】
(古くはゼンナク・ゼンマクとも)
[一]〔名〕
善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」
[二]〔副〕
よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」
⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】
⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】
⇒善悪の生を引く
⇒善悪の報は影の形に随うが如し
広辞苑 ページ 11172 での【○背を縒る】単語。