複数辞典一括検索+![]()
![]()
○桑田変じて滄海となるそうでんへんじてそうかいとなる🔗⭐🔉
○桑田変じて滄海となるそうでんへんじてそうかいとなる
[劉廷芝、白頭を悲しむ翁に代われる詩]桑畑が変わって青い海になる。世の変遷のはげしいことのたとえ。「滄海変じて桑田となる」とも。
⇒そう‐でん【桑田】
そうでん‐りょう【相伝領】サウ‥リヤウ
代々つたえつぐ領地。
⇒そう‐でん【相伝】
そう‐と【壮図】サウ‥
壮大な企て。「―を抱く」
そう‐と【壮途】サウ‥
さかんなかどで。「勇躍―につく」
そう‐と【僧徒】
僧のともがら。僧侶。
そう‐と
〔副〕
そっと。狂言、吃り「紅を―うついて」
そう‐とう【双頭】サウ‥
頭が二つ並んでついていること。両頭。
⇒そうとう‐の‐わし【双頭の鷲】
そう‐とう【争闘】サウ‥
あらそいたたかうこと。闘争。「リング上の―」
そう‐とう【相当】サウタウ
①程度や地位などが、そのものにふさわしいこと、つりあうこと、あてはまること。「国賓―の待遇」「死に―する罪」「それ―のお礼」
②(副詞的にも用いる)普通を超えているさま。かなりな程度であるさま。「―な自信家」「―ひどい傷」
⇒そうとう‐いんがかんけい【相当因果関係】
⇒そうとう‐うち【相当打】
⇒そうとう‐かん【相当官】
⇒そうとう‐かんり【相当官吏】
⇒そうとう‐すう【相当数】
そう‐とう【相等】サウ‥
あいひとしいこと。同等。
⇒そうとう‐せい【相等性】
そう‐とう【草頭】サウ‥
①くさかんむり。
②草の上。
そう‐とう【掃討・掃蕩・剿討】サウタウ
敵などを、すっかり払い除くこと。討ちほろぼすこと。「―作戦」
そうとう【曹洞】サウ‥
曹洞宗の略。
⇒そうとう‐しゅう【曹洞宗】
そう‐とう【窓頭】サウ‥
まどのほとり。まどぎわ。
そう‐とう【想到】サウタウ
考えが及ぶこと。考えつくこと。
そう‐とう【掻頭】サウ‥
①頭をかくこと。
②かんざし。
そう‐とう【層塔】‥タフ
層をなした塔。幾層もある塔。三重・五重・十三重の塔の類。
そう‐とう【総統】
①統すべくくること。また、その官職。
②中華民国政府の最高官職。大統領に当たる。元首として国家を代表、行政院長を任命、総統府を主宰する。→大総統。
③(Führer ドイツ)ナチス‐ドイツの最高官職。大統領・首相・党首の全権をもち、ヒトラーがこの地位を占めて独裁権をふるった。→ドゥーチェ
そう‐とう【蒼頭】サウ‥
①(中国で青色の頭巾をかぶっていたからいう)士卒。
②しもべ。めしつかい。
そう‐どう【相同】サウ‥
①異種の生物の器官で、外観上の相違はあるが、発生的および体制的に同一であること。例えば鳥の翼と獣の前肢。ホモロジー。↔相似。
②塩基配列やアミノ酸の一致によって検出される、二つまたはそれ以上の遺伝子間に見られる類縁性。ホモロジー。
⇒そうどう‐きかん【相同器官】
⇒そうどう‐くみかえ【相同組換え】
⇒そうどう‐せんしょくたい【相同染色体】
そう‐どう【草堂】サウダウ
①くさぶきの家。草屋。また、自分の家の謙譲語。
②いおり。草庵。
そう‐どう【僧堂】‥ダウ
禅宗寺院の建物の一つで、坐禅修行の根本道場。もとは坐禅を中心に食事から睡眠までの一切がなされた。禅堂。雲堂。撰仏場。
そう‐どう【騒動】サウ‥
①多人数が乱れさわぐこと。平家物語7「廿二日の夜半ばかり、六波羅の辺おびたゝしう―す」。「上を下への大―」
②非常の事態。事変。「米―」
③もめごと。あらそい。「お家―」
⇒そうどう‐うち【騒動打】
ぞう‐とう【造塔】ザウタフ
供養のために、遺骨または経文を納めて塔を建造すること。
ぞう‐とう【贈答】‥タフ
物をおくったり、そのお返しをしたりすること。「―品」
⇒ぞうとう‐か【贈答歌】
そう‐どういん【総動員】‥ヰン
ある目的のために全員をかり出すこと。「―をかける」「社員―」
そうとう‐いんがかんけい【相当因果関係】サウタウ‥グワクワン‥
法律で因果関係が問題となる場合に、相当と認められる範囲に限定された因果関係。不法行為による損害賠償の範囲、犯罪行為の結果を問題とする刑事責任の範囲などに関して主張される。
⇒そう‐とう【相当】
そうとう‐うち【相当打】サウタウ‥
(→)後妻打うわなりうちに同じ。
⇒そう‐とう【相当】
そうどう‐うち【騒動打】サウ‥
(→)後妻打うわなりうちに同じ。
⇒そう‐どう【騒動】
ぞうとう‐か【贈答歌】‥タフ‥
二人がその意中を言いあい、やりとりする和歌。
⇒ぞう‐とう【贈答】
そうとう‐かん【相当官】サウタウクワン
その階級が、ある本官に相当しているもの。
⇒そう‐とう【相当】
そうとう‐かんり【相当官吏】サウタウクワン‥
旧制で、官吏と同等の待遇を受けた職員。官幣社・国幣社の神職、公立学校職員など。
⇒そう‐とう【相当】
そうどう‐きかん【相同器官】サウ‥クワン
異種の生物で相同である器官。
⇒そう‐どう【相同】
そうどう‐くみかえ【相同組換え】サウ‥カヘ
ゲノム中のある遺伝子座の配列を、それと相同的な対立遺伝子座のものと交換すること。
⇒そう‐どう【相同】
そうとう‐しゅう【曹洞宗】サウ‥
禅宗の一派。中国で洞山良价とうざんりょうかいと弟子の曹山本寂によって開かれ、日本では、道元が入宋して如浄からこれを伝え受けた。只管打坐しかんたざを説く。永平寺・総持寺を大本山とする。→臨済宗
⇒そうとう【曹洞】
そうとう‐すう【相当数】サウタウ‥
①それにふさわしい数。
②かなり多い数。
⇒そう‐とう【相当】
そうとう‐せい【相等性】サウ‥
(equality)二つの事象の間に分量上または性質上差異が認められないこと。→同一性
⇒そう‐とう【相等】
そうどう‐せん【双胴船】サウ‥
二つの船体を横に並べて、水面上の甲板で結んだ船。安定性と推進性能がよいため、ヨット・高速船などに用いられる。カタマラン。
そうどう‐せんしょくたい【相同染色体】サウ‥
減数分裂の際に対合する染色体。一般に有性生殖をする生物の体細胞(二倍体)は2個ずつの相同染色体を持ち、片方は雄性に、片方は雌性に由来する。
⇒そう‐どう【相同】
そうとう‐の‐わし【双頭の鷲】サウ‥
(double-headed eagle)神聖ローマ・オーストリア・ロシア3皇帝の紋章。
⇒そう‐とう【双頭】
そう‐どうめい【総同盟】
①日本労働総同盟の略称。1921年友愛会を改称。36年全労1と合流して全日本労働総同盟となり、40年解散。→友愛会。
②日本労働組合総同盟の略称。46年旧総同盟系を中心に結集した全国組織。50年左派は総評へ参加、右派は全労会議・同盟会議を経て、64年同盟へ解消。
そう‐どうめいひぎょう【総同盟罷業】‥ゲフ
ゼネラル‐ストライキの訳語。
そう‐とく【総督】
①統すべひきいること。
②軍隊を統べひきいる最高の官。軍司令官。
③中国で、明・清代の最高地方長官。1省を管轄する巡撫に対して、数省(例外的に1省)の政務・軍務を統轄。
④植民地の政務統轄に当たる官。旧日本の朝鮮総督・台湾総督など。
⇒そうとく‐ふ【総督府】
そう‐どく【瘡毒】サウ‥
梅毒。かさ。
そうど・くサウドク
〔自四〕
(「騒動」を活用させた語か)さわぎ立てる。ざわつく。源氏物語空蝉「きはぎはしう―・けば」
ぞう‐とく【蔵匿】ザウ‥
人に知られないように隠しておくこと。隠匿。→犯人蔵匿罪
そうとく‐ふ【総督府】
植民地の総督が政務を統轄する役所。
⇒そう‐とく【総督】
そう‐どしより【惣年寄】
江戸時代、大坂・岡山などで町奉行の支配を受けて御触れの通達、町年寄・町役人の監督など民政に当たった町人。→町年寄
そうとめ【早少女】サウトメ
⇒さおとめ。〈日葡辞書〉
そう‐ともサウ‥
全くその通りである。ごもっとも。
そう‐とん【草墩】サウ‥
(墩は太鼓形の腰掛)平安時代、宮中で用いた腰掛の一種。菰まこもなどを芯として円筒形につくり、上面と周囲を錦で包む。
草墩
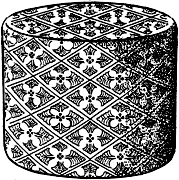 そう‐トン【総噸】
船舶の総トン数をいう時の単位語。
⇒そうトン‐すう【総噸数】
そうトン‐すう【総噸数】
①(一国の商船などの)トン数の総計。
②(gross tonnage)船舶の全容積をトンの単位で表したもの。グロス‐トン。
⇒そう‐トン【総噸】
そう‐な【草名】サウ‥
⇒そうみょう
そうなサウ‥
助動詞「そうだ」の連体形。→そうだ
ぞう‐ながもち【雑長持】ザフ‥
雑品ざっぴんを入れておく長持。
そう‐な・し【双無し】サウ‥
〔形ク〕
比類がない。ならぶものがない。徒然草「鳥には、雉―・きものなり」
そう‐な・し【左右無し】サウ‥
〔形ク〕
(「左右」は、とかくの意)
①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」
②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」
そう‐なみ【総並・惣並】
①全般にわたること。全部。史記抄「先づ―の列伝を立て」
②普通一般の傾向。天草本伊曾保物語「ともかくも―にまかさせられい」
そう‐なめ【総嘗め】
①それからそれへと全体に及ぶこと。「火の勢いは繁華街を―にした」
②次から次へと全部をうち負かすこと。「横綱・大関―の活躍」
そう‐なん【遭難】サウ‥
わざわいにあうこと。災難にであうこと。特に、登山・航海などの場合をいうことが多い。
⇒そうなん‐しんごう【遭難信号】
そうなん‐しんごう【遭難信号】サウ‥ガウ
遭難した船舶や航空機が、救助を求めるために発する信号。国際的に統一されている。無線電信のSOS信号、1分間隔の発砲または爆発信号、発炎信号、信号旗のNC信号など。
⇒そう‐なん【遭難】
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
ぞう‐に【雑煮】ザフ‥
餅を主に仕立てた汁もの。新年の祝賀などに食する。餅の形、取り合わせる具、汁の仕立て方など地方により特色がある。雑煮餅。〈[季]新年〉
⇒ぞうに‐ばし【雑煮箸】
⇒ぞうに‐もち【雑煮餅】
そう‐にかい【総二階】
1階部分と同じ大きさ・形で2階部分を作った建物。
ぞうに‐ばし【雑煮箸】ザフ‥
新年の雑煮を食べるのに用いる柳材などの白木箸。
⇒ぞう‐に【雑煮】
ぞうに‐もち【雑煮餅】ザフ‥
(→)雑煮に同じ。
⇒ぞう‐に【雑煮】
そう‐にゅう【挿入】サフニフ
さし入れること。さしこむこと。「図表を―する」
⇒そうにゅう‐か【挿入歌】
⇒そうにゅう‐く【挿入句】
そう‐にゅう【装入】サウニフ
中に取りつけ、またはつめこむこと。
そうにゅう‐か【挿入歌】サフニフ‥
映画・ドラマなどの劇中で流す歌。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そうにゅう‐く【挿入句】サフニフ‥
断り書きや説明あるいは同格として、文中に置かれた語句。はさみこみ。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そう‐にょう【爪繞】サウネウ
漢字の繞にょうの一つ。「爬」「
そう‐トン【総噸】
船舶の総トン数をいう時の単位語。
⇒そうトン‐すう【総噸数】
そうトン‐すう【総噸数】
①(一国の商船などの)トン数の総計。
②(gross tonnage)船舶の全容積をトンの単位で表したもの。グロス‐トン。
⇒そう‐トン【総噸】
そう‐な【草名】サウ‥
⇒そうみょう
そうなサウ‥
助動詞「そうだ」の連体形。→そうだ
ぞう‐ながもち【雑長持】ザフ‥
雑品ざっぴんを入れておく長持。
そう‐な・し【双無し】サウ‥
〔形ク〕
比類がない。ならぶものがない。徒然草「鳥には、雉―・きものなり」
そう‐な・し【左右無し】サウ‥
〔形ク〕
(「左右」は、とかくの意)
①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」
②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」
そう‐なみ【総並・惣並】
①全般にわたること。全部。史記抄「先づ―の列伝を立て」
②普通一般の傾向。天草本伊曾保物語「ともかくも―にまかさせられい」
そう‐なめ【総嘗め】
①それからそれへと全体に及ぶこと。「火の勢いは繁華街を―にした」
②次から次へと全部をうち負かすこと。「横綱・大関―の活躍」
そう‐なん【遭難】サウ‥
わざわいにあうこと。災難にであうこと。特に、登山・航海などの場合をいうことが多い。
⇒そうなん‐しんごう【遭難信号】
そうなん‐しんごう【遭難信号】サウ‥ガウ
遭難した船舶や航空機が、救助を求めるために発する信号。国際的に統一されている。無線電信のSOS信号、1分間隔の発砲または爆発信号、発炎信号、信号旗のNC信号など。
⇒そう‐なん【遭難】
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
ぞう‐に【雑煮】ザフ‥
餅を主に仕立てた汁もの。新年の祝賀などに食する。餅の形、取り合わせる具、汁の仕立て方など地方により特色がある。雑煮餅。〈[季]新年〉
⇒ぞうに‐ばし【雑煮箸】
⇒ぞうに‐もち【雑煮餅】
そう‐にかい【総二階】
1階部分と同じ大きさ・形で2階部分を作った建物。
ぞうに‐ばし【雑煮箸】ザフ‥
新年の雑煮を食べるのに用いる柳材などの白木箸。
⇒ぞう‐に【雑煮】
ぞうに‐もち【雑煮餅】ザフ‥
(→)雑煮に同じ。
⇒ぞう‐に【雑煮】
そう‐にゅう【挿入】サフニフ
さし入れること。さしこむこと。「図表を―する」
⇒そうにゅう‐か【挿入歌】
⇒そうにゅう‐く【挿入句】
そう‐にゅう【装入】サウニフ
中に取りつけ、またはつめこむこと。
そうにゅう‐か【挿入歌】サフニフ‥
映画・ドラマなどの劇中で流す歌。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そうにゅう‐く【挿入句】サフニフ‥
断り書きや説明あるいは同格として、文中に置かれた語句。はさみこみ。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そう‐にょう【爪繞】サウネウ
漢字の繞にょうの一つ。「爬」「 」などの繞の「爪」の称。
そう‐にょう【走繞】‥ネウ
漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐にん【奏任】
①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。
②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任。
⇒そうにん‐かん【奏任官】
そう‐にん【相人】サウ‥
人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」
そう‐にん【証人】
⇒しょうにん
ぞう‐にん【雑人】ザフ‥
身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」
⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】
⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】
ぞう‐にん【雑任】ザフ‥
古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。
そうにん‐かん【奏任官】‥クワン
旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」
⇒そう‐にん【奏任】
ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥
雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。
⇒ぞう‐にん【雑人】
ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ
鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。
⇒ぞう‐にん【雑人】
そうねつ‐せい【走熱性】
〔生〕媒体中の温度差を刺激とする生物の走性。多くの植物やヒトジラミがその例。温度走性。趨熱性。
そう‐ねん【壮年】サウ‥
血気盛んで働き盛りの年ごろ。また、その年ごろの人。壮齢。
⇒そうねん‐き【壮年期】
そう‐ねん【早年】サウ‥
年が若い時分。↔晩年
そう‐ねん【想念】サウ‥
かんがえ思うこと。思念。
そうねん‐き【壮年期】サウ‥
①人生における壮年の時期。
②〔地〕山地の地形変化の過程で、峰と谷の高度差、斜面の傾斜、山襞の密度が最大で最も険しくなった時期。
⇒そう‐ねん【壮年】
ぞう‐の‐うた【雑歌】ザフ‥
⇒ぞうか
ぞう‐の‐おり【象の檻】ザウ‥ヲリ
巨大な円形・籠形の軍事用アンテナの俗称。
そう‐の‐こと【箏の琴】サウ‥
箏そう。紫式部日記「和琴―しらべながら心に入れて」
そう‐の‐ふえ【笙の笛】サウ‥
笙しょう。源氏物語宿木「なのおほい殿の御七郎、童にて―吹く」
そう‐は【争覇】サウ‥
覇権を争うこと。優勝を競うこと。「―戦」
そう‐は【走破】
全行程を(困難をのりこえて)走りとおすこと。「マラソン‐コースを―する」
そう‐は【掻爬】サウ‥
〔医〕組織をかきとること。特に子宮腔内面をかきとり、内容を除去する手術は主として人工妊娠中絶に用いられる。
そう‐は【蒼波】サウ‥
あおい波。蒼浪。天草本平家物語「故郷を去つて―万里を遠しとし給はず」
そう‐ば【相馬】サウ‥
馬の形相を観て、その良否を鑑定すること。そうま。「―学」
そう‐ば【相場】サウ‥
①一般市場における物品の取引価格。時価。市価。〈日葡辞書〉。「―が安定する」
②為替かわせ相場。
③現物の取引をせず、市場の高下によって相互間に鞘取りをする売買取引。「―に手を出す」
④世間一般に定まっている考えや評価。また、大体の見当。「博打ばくちは負けるものと―がきまっている」
⇒そうば‐かいしょ【相場会所】
⇒そうば‐がき【相場書】
⇒そうば‐し【相場師】
⇒そうば‐そうじゅう【相場操縦】
⇒そうば‐ひょう【相場表】
⇒そうば‐わり【相場割】
そう‐ば【葬馬】サウ‥
葬送の時に(僧を乗せて)引く馬。太平記32「今まで秘蔵して乗られたる白瓦毛の馬白鞍置きて―に引かせ」
そう‐ば【痩馬】
やせた馬。やせうま。
ぞう‐は【増派】
さらに増員して派遣すること。「兵力―」
そう‐はい【送配】
おくりくばること。「電力―」
そう‐ばい【早梅】サウ‥
はや咲きの梅。〈[季]冬〉
そう‐ばい【層倍】
(「相倍」「双倍」とも書く)倍数を数える語。「幾―」「薬九―」
ぞう‐はい【増配】
株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配
そうば‐かいしょ【相場会所】サウ‥クワイ‥
江戸時代の取引所。
⇒そう‐ば【相場】
そうば‐がき【相場書】サウ‥
江戸時代、金・銀・米・綿・油などの相場を記した帳面。
⇒そう‐ば【相場】
そう‐はく【宗伯】
周代六卿の一人。春官の長。礼楽・祭祀をつかさどる。
そう‐はく【相博】サウ‥
(ソウバクとも)
①古代・中世、田地・所領などを交換すること。「―状」
②職務などを交代すること。
そう‐はく【蒼白】サウ‥
あおじろいこと。顔色などのあおざめて血色のわるいこと。「顔面―」
そう‐はく【蒼柏】サウ‥
あおあおと茂ったかしわ。
そう‐はく【糟粕】サウ‥
①酒のかす。
②(「糟魄」とも書く)転じて、滋味をとり去った残りかす。精神の抜けた外形。「古人の―」
⇒糟粕を嘗める
ぞう‐はく【増白】
繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。
」などの繞の「爪」の称。
そう‐にょう【走繞】‥ネウ
漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐にん【奏任】
①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。
②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任。
⇒そうにん‐かん【奏任官】
そう‐にん【相人】サウ‥
人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」
そう‐にん【証人】
⇒しょうにん
ぞう‐にん【雑人】ザフ‥
身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」
⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】
⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】
ぞう‐にん【雑任】ザフ‥
古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。
そうにん‐かん【奏任官】‥クワン
旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」
⇒そう‐にん【奏任】
ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥
雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。
⇒ぞう‐にん【雑人】
ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ
鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。
⇒ぞう‐にん【雑人】
そうねつ‐せい【走熱性】
〔生〕媒体中の温度差を刺激とする生物の走性。多くの植物やヒトジラミがその例。温度走性。趨熱性。
そう‐ねん【壮年】サウ‥
血気盛んで働き盛りの年ごろ。また、その年ごろの人。壮齢。
⇒そうねん‐き【壮年期】
そう‐ねん【早年】サウ‥
年が若い時分。↔晩年
そう‐ねん【想念】サウ‥
かんがえ思うこと。思念。
そうねん‐き【壮年期】サウ‥
①人生における壮年の時期。
②〔地〕山地の地形変化の過程で、峰と谷の高度差、斜面の傾斜、山襞の密度が最大で最も険しくなった時期。
⇒そう‐ねん【壮年】
ぞう‐の‐うた【雑歌】ザフ‥
⇒ぞうか
ぞう‐の‐おり【象の檻】ザウ‥ヲリ
巨大な円形・籠形の軍事用アンテナの俗称。
そう‐の‐こと【箏の琴】サウ‥
箏そう。紫式部日記「和琴―しらべながら心に入れて」
そう‐の‐ふえ【笙の笛】サウ‥
笙しょう。源氏物語宿木「なのおほい殿の御七郎、童にて―吹く」
そう‐は【争覇】サウ‥
覇権を争うこと。優勝を競うこと。「―戦」
そう‐は【走破】
全行程を(困難をのりこえて)走りとおすこと。「マラソン‐コースを―する」
そう‐は【掻爬】サウ‥
〔医〕組織をかきとること。特に子宮腔内面をかきとり、内容を除去する手術は主として人工妊娠中絶に用いられる。
そう‐は【蒼波】サウ‥
あおい波。蒼浪。天草本平家物語「故郷を去つて―万里を遠しとし給はず」
そう‐ば【相馬】サウ‥
馬の形相を観て、その良否を鑑定すること。そうま。「―学」
そう‐ば【相場】サウ‥
①一般市場における物品の取引価格。時価。市価。〈日葡辞書〉。「―が安定する」
②為替かわせ相場。
③現物の取引をせず、市場の高下によって相互間に鞘取りをする売買取引。「―に手を出す」
④世間一般に定まっている考えや評価。また、大体の見当。「博打ばくちは負けるものと―がきまっている」
⇒そうば‐かいしょ【相場会所】
⇒そうば‐がき【相場書】
⇒そうば‐し【相場師】
⇒そうば‐そうじゅう【相場操縦】
⇒そうば‐ひょう【相場表】
⇒そうば‐わり【相場割】
そう‐ば【葬馬】サウ‥
葬送の時に(僧を乗せて)引く馬。太平記32「今まで秘蔵して乗られたる白瓦毛の馬白鞍置きて―に引かせ」
そう‐ば【痩馬】
やせた馬。やせうま。
ぞう‐は【増派】
さらに増員して派遣すること。「兵力―」
そう‐はい【送配】
おくりくばること。「電力―」
そう‐ばい【早梅】サウ‥
はや咲きの梅。〈[季]冬〉
そう‐ばい【層倍】
(「相倍」「双倍」とも書く)倍数を数える語。「幾―」「薬九―」
ぞう‐はい【増配】
株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配
そうば‐かいしょ【相場会所】サウ‥クワイ‥
江戸時代の取引所。
⇒そう‐ば【相場】
そうば‐がき【相場書】サウ‥
江戸時代、金・銀・米・綿・油などの相場を記した帳面。
⇒そう‐ば【相場】
そう‐はく【宗伯】
周代六卿の一人。春官の長。礼楽・祭祀をつかさどる。
そう‐はく【相博】サウ‥
(ソウバクとも)
①古代・中世、田地・所領などを交換すること。「―状」
②職務などを交代すること。
そう‐はく【蒼白】サウ‥
あおじろいこと。顔色などのあおざめて血色のわるいこと。「顔面―」
そう‐はく【蒼柏】サウ‥
あおあおと茂ったかしわ。
そう‐はく【糟粕】サウ‥
①酒のかす。
②(「糟魄」とも書く)転じて、滋味をとり去った残りかす。精神の抜けた外形。「古人の―」
⇒糟粕を嘗める
ぞう‐はく【増白】
繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。
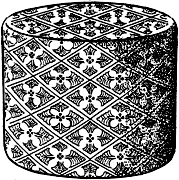 そう‐トン【総噸】
船舶の総トン数をいう時の単位語。
⇒そうトン‐すう【総噸数】
そうトン‐すう【総噸数】
①(一国の商船などの)トン数の総計。
②(gross tonnage)船舶の全容積をトンの単位で表したもの。グロス‐トン。
⇒そう‐トン【総噸】
そう‐な【草名】サウ‥
⇒そうみょう
そうなサウ‥
助動詞「そうだ」の連体形。→そうだ
ぞう‐ながもち【雑長持】ザフ‥
雑品ざっぴんを入れておく長持。
そう‐な・し【双無し】サウ‥
〔形ク〕
比類がない。ならぶものがない。徒然草「鳥には、雉―・きものなり」
そう‐な・し【左右無し】サウ‥
〔形ク〕
(「左右」は、とかくの意)
①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」
②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」
そう‐なみ【総並・惣並】
①全般にわたること。全部。史記抄「先づ―の列伝を立て」
②普通一般の傾向。天草本伊曾保物語「ともかくも―にまかさせられい」
そう‐なめ【総嘗め】
①それからそれへと全体に及ぶこと。「火の勢いは繁華街を―にした」
②次から次へと全部をうち負かすこと。「横綱・大関―の活躍」
そう‐なん【遭難】サウ‥
わざわいにあうこと。災難にであうこと。特に、登山・航海などの場合をいうことが多い。
⇒そうなん‐しんごう【遭難信号】
そうなん‐しんごう【遭難信号】サウ‥ガウ
遭難した船舶や航空機が、救助を求めるために発する信号。国際的に統一されている。無線電信のSOS信号、1分間隔の発砲または爆発信号、発炎信号、信号旗のNC信号など。
⇒そう‐なん【遭難】
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
ぞう‐に【雑煮】ザフ‥
餅を主に仕立てた汁もの。新年の祝賀などに食する。餅の形、取り合わせる具、汁の仕立て方など地方により特色がある。雑煮餅。〈[季]新年〉
⇒ぞうに‐ばし【雑煮箸】
⇒ぞうに‐もち【雑煮餅】
そう‐にかい【総二階】
1階部分と同じ大きさ・形で2階部分を作った建物。
ぞうに‐ばし【雑煮箸】ザフ‥
新年の雑煮を食べるのに用いる柳材などの白木箸。
⇒ぞう‐に【雑煮】
ぞうに‐もち【雑煮餅】ザフ‥
(→)雑煮に同じ。
⇒ぞう‐に【雑煮】
そう‐にゅう【挿入】サフニフ
さし入れること。さしこむこと。「図表を―する」
⇒そうにゅう‐か【挿入歌】
⇒そうにゅう‐く【挿入句】
そう‐にゅう【装入】サウニフ
中に取りつけ、またはつめこむこと。
そうにゅう‐か【挿入歌】サフニフ‥
映画・ドラマなどの劇中で流す歌。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そうにゅう‐く【挿入句】サフニフ‥
断り書きや説明あるいは同格として、文中に置かれた語句。はさみこみ。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そう‐にょう【爪繞】サウネウ
漢字の繞にょうの一つ。「爬」「
そう‐トン【総噸】
船舶の総トン数をいう時の単位語。
⇒そうトン‐すう【総噸数】
そうトン‐すう【総噸数】
①(一国の商船などの)トン数の総計。
②(gross tonnage)船舶の全容積をトンの単位で表したもの。グロス‐トン。
⇒そう‐トン【総噸】
そう‐な【草名】サウ‥
⇒そうみょう
そうなサウ‥
助動詞「そうだ」の連体形。→そうだ
ぞう‐ながもち【雑長持】ザフ‥
雑品ざっぴんを入れておく長持。
そう‐な・し【双無し】サウ‥
〔形ク〕
比類がない。ならぶものがない。徒然草「鳥には、雉―・きものなり」
そう‐な・し【左右無し】サウ‥
〔形ク〕
(「左右」は、とかくの意)
①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」
②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」
そう‐なみ【総並・惣並】
①全般にわたること。全部。史記抄「先づ―の列伝を立て」
②普通一般の傾向。天草本伊曾保物語「ともかくも―にまかさせられい」
そう‐なめ【総嘗め】
①それからそれへと全体に及ぶこと。「火の勢いは繁華街を―にした」
②次から次へと全部をうち負かすこと。「横綱・大関―の活躍」
そう‐なん【遭難】サウ‥
わざわいにあうこと。災難にであうこと。特に、登山・航海などの場合をいうことが多い。
⇒そうなん‐しんごう【遭難信号】
そうなん‐しんごう【遭難信号】サウ‥ガウ
遭難した船舶や航空機が、救助を求めるために発する信号。国際的に統一されている。無線電信のSOS信号、1分間隔の発砲または爆発信号、発炎信号、信号旗のNC信号など。
⇒そう‐なん【遭難】
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
ぞう‐に【雑煮】ザフ‥
餅を主に仕立てた汁もの。新年の祝賀などに食する。餅の形、取り合わせる具、汁の仕立て方など地方により特色がある。雑煮餅。〈[季]新年〉
⇒ぞうに‐ばし【雑煮箸】
⇒ぞうに‐もち【雑煮餅】
そう‐にかい【総二階】
1階部分と同じ大きさ・形で2階部分を作った建物。
ぞうに‐ばし【雑煮箸】ザフ‥
新年の雑煮を食べるのに用いる柳材などの白木箸。
⇒ぞう‐に【雑煮】
ぞうに‐もち【雑煮餅】ザフ‥
(→)雑煮に同じ。
⇒ぞう‐に【雑煮】
そう‐にゅう【挿入】サフニフ
さし入れること。さしこむこと。「図表を―する」
⇒そうにゅう‐か【挿入歌】
⇒そうにゅう‐く【挿入句】
そう‐にゅう【装入】サウニフ
中に取りつけ、またはつめこむこと。
そうにゅう‐か【挿入歌】サフニフ‥
映画・ドラマなどの劇中で流す歌。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そうにゅう‐く【挿入句】サフニフ‥
断り書きや説明あるいは同格として、文中に置かれた語句。はさみこみ。
⇒そう‐にゅう【挿入】
そう‐にょう【爪繞】サウネウ
漢字の繞にょうの一つ。「爬」「 」などの繞の「爪」の称。
そう‐にょう【走繞】‥ネウ
漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐にん【奏任】
①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。
②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任。
⇒そうにん‐かん【奏任官】
そう‐にん【相人】サウ‥
人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」
そう‐にん【証人】
⇒しょうにん
ぞう‐にん【雑人】ザフ‥
身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」
⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】
⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】
ぞう‐にん【雑任】ザフ‥
古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。
そうにん‐かん【奏任官】‥クワン
旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」
⇒そう‐にん【奏任】
ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥
雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。
⇒ぞう‐にん【雑人】
ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ
鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。
⇒ぞう‐にん【雑人】
そうねつ‐せい【走熱性】
〔生〕媒体中の温度差を刺激とする生物の走性。多くの植物やヒトジラミがその例。温度走性。趨熱性。
そう‐ねん【壮年】サウ‥
血気盛んで働き盛りの年ごろ。また、その年ごろの人。壮齢。
⇒そうねん‐き【壮年期】
そう‐ねん【早年】サウ‥
年が若い時分。↔晩年
そう‐ねん【想念】サウ‥
かんがえ思うこと。思念。
そうねん‐き【壮年期】サウ‥
①人生における壮年の時期。
②〔地〕山地の地形変化の過程で、峰と谷の高度差、斜面の傾斜、山襞の密度が最大で最も険しくなった時期。
⇒そう‐ねん【壮年】
ぞう‐の‐うた【雑歌】ザフ‥
⇒ぞうか
ぞう‐の‐おり【象の檻】ザウ‥ヲリ
巨大な円形・籠形の軍事用アンテナの俗称。
そう‐の‐こと【箏の琴】サウ‥
箏そう。紫式部日記「和琴―しらべながら心に入れて」
そう‐の‐ふえ【笙の笛】サウ‥
笙しょう。源氏物語宿木「なのおほい殿の御七郎、童にて―吹く」
そう‐は【争覇】サウ‥
覇権を争うこと。優勝を競うこと。「―戦」
そう‐は【走破】
全行程を(困難をのりこえて)走りとおすこと。「マラソン‐コースを―する」
そう‐は【掻爬】サウ‥
〔医〕組織をかきとること。特に子宮腔内面をかきとり、内容を除去する手術は主として人工妊娠中絶に用いられる。
そう‐は【蒼波】サウ‥
あおい波。蒼浪。天草本平家物語「故郷を去つて―万里を遠しとし給はず」
そう‐ば【相馬】サウ‥
馬の形相を観て、その良否を鑑定すること。そうま。「―学」
そう‐ば【相場】サウ‥
①一般市場における物品の取引価格。時価。市価。〈日葡辞書〉。「―が安定する」
②為替かわせ相場。
③現物の取引をせず、市場の高下によって相互間に鞘取りをする売買取引。「―に手を出す」
④世間一般に定まっている考えや評価。また、大体の見当。「博打ばくちは負けるものと―がきまっている」
⇒そうば‐かいしょ【相場会所】
⇒そうば‐がき【相場書】
⇒そうば‐し【相場師】
⇒そうば‐そうじゅう【相場操縦】
⇒そうば‐ひょう【相場表】
⇒そうば‐わり【相場割】
そう‐ば【葬馬】サウ‥
葬送の時に(僧を乗せて)引く馬。太平記32「今まで秘蔵して乗られたる白瓦毛の馬白鞍置きて―に引かせ」
そう‐ば【痩馬】
やせた馬。やせうま。
ぞう‐は【増派】
さらに増員して派遣すること。「兵力―」
そう‐はい【送配】
おくりくばること。「電力―」
そう‐ばい【早梅】サウ‥
はや咲きの梅。〈[季]冬〉
そう‐ばい【層倍】
(「相倍」「双倍」とも書く)倍数を数える語。「幾―」「薬九―」
ぞう‐はい【増配】
株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配
そうば‐かいしょ【相場会所】サウ‥クワイ‥
江戸時代の取引所。
⇒そう‐ば【相場】
そうば‐がき【相場書】サウ‥
江戸時代、金・銀・米・綿・油などの相場を記した帳面。
⇒そう‐ば【相場】
そう‐はく【宗伯】
周代六卿の一人。春官の長。礼楽・祭祀をつかさどる。
そう‐はく【相博】サウ‥
(ソウバクとも)
①古代・中世、田地・所領などを交換すること。「―状」
②職務などを交代すること。
そう‐はく【蒼白】サウ‥
あおじろいこと。顔色などのあおざめて血色のわるいこと。「顔面―」
そう‐はく【蒼柏】サウ‥
あおあおと茂ったかしわ。
そう‐はく【糟粕】サウ‥
①酒のかす。
②(「糟魄」とも書く)転じて、滋味をとり去った残りかす。精神の抜けた外形。「古人の―」
⇒糟粕を嘗める
ぞう‐はく【増白】
繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。
」などの繞の「爪」の称。
そう‐にょう【走繞】‥ネウ
漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐にん【奏任】
①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。
②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任。
⇒そうにん‐かん【奏任官】
そう‐にん【相人】サウ‥
人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」
そう‐にん【証人】
⇒しょうにん
ぞう‐にん【雑人】ザフ‥
身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」
⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】
⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】
ぞう‐にん【雑任】ザフ‥
古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。
そうにん‐かん【奏任官】‥クワン
旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」
⇒そう‐にん【奏任】
ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥
雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。
⇒ぞう‐にん【雑人】
ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ
鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。
⇒ぞう‐にん【雑人】
そうねつ‐せい【走熱性】
〔生〕媒体中の温度差を刺激とする生物の走性。多くの植物やヒトジラミがその例。温度走性。趨熱性。
そう‐ねん【壮年】サウ‥
血気盛んで働き盛りの年ごろ。また、その年ごろの人。壮齢。
⇒そうねん‐き【壮年期】
そう‐ねん【早年】サウ‥
年が若い時分。↔晩年
そう‐ねん【想念】サウ‥
かんがえ思うこと。思念。
そうねん‐き【壮年期】サウ‥
①人生における壮年の時期。
②〔地〕山地の地形変化の過程で、峰と谷の高度差、斜面の傾斜、山襞の密度が最大で最も険しくなった時期。
⇒そう‐ねん【壮年】
ぞう‐の‐うた【雑歌】ザフ‥
⇒ぞうか
ぞう‐の‐おり【象の檻】ザウ‥ヲリ
巨大な円形・籠形の軍事用アンテナの俗称。
そう‐の‐こと【箏の琴】サウ‥
箏そう。紫式部日記「和琴―しらべながら心に入れて」
そう‐の‐ふえ【笙の笛】サウ‥
笙しょう。源氏物語宿木「なのおほい殿の御七郎、童にて―吹く」
そう‐は【争覇】サウ‥
覇権を争うこと。優勝を競うこと。「―戦」
そう‐は【走破】
全行程を(困難をのりこえて)走りとおすこと。「マラソン‐コースを―する」
そう‐は【掻爬】サウ‥
〔医〕組織をかきとること。特に子宮腔内面をかきとり、内容を除去する手術は主として人工妊娠中絶に用いられる。
そう‐は【蒼波】サウ‥
あおい波。蒼浪。天草本平家物語「故郷を去つて―万里を遠しとし給はず」
そう‐ば【相馬】サウ‥
馬の形相を観て、その良否を鑑定すること。そうま。「―学」
そう‐ば【相場】サウ‥
①一般市場における物品の取引価格。時価。市価。〈日葡辞書〉。「―が安定する」
②為替かわせ相場。
③現物の取引をせず、市場の高下によって相互間に鞘取りをする売買取引。「―に手を出す」
④世間一般に定まっている考えや評価。また、大体の見当。「博打ばくちは負けるものと―がきまっている」
⇒そうば‐かいしょ【相場会所】
⇒そうば‐がき【相場書】
⇒そうば‐し【相場師】
⇒そうば‐そうじゅう【相場操縦】
⇒そうば‐ひょう【相場表】
⇒そうば‐わり【相場割】
そう‐ば【葬馬】サウ‥
葬送の時に(僧を乗せて)引く馬。太平記32「今まで秘蔵して乗られたる白瓦毛の馬白鞍置きて―に引かせ」
そう‐ば【痩馬】
やせた馬。やせうま。
ぞう‐は【増派】
さらに増員して派遣すること。「兵力―」
そう‐はい【送配】
おくりくばること。「電力―」
そう‐ばい【早梅】サウ‥
はや咲きの梅。〈[季]冬〉
そう‐ばい【層倍】
(「相倍」「双倍」とも書く)倍数を数える語。「幾―」「薬九―」
ぞう‐はい【増配】
株式の配当を増加すること。また、配給量を増すこと。↔減配
そうば‐かいしょ【相場会所】サウ‥クワイ‥
江戸時代の取引所。
⇒そう‐ば【相場】
そうば‐がき【相場書】サウ‥
江戸時代、金・銀・米・綿・油などの相場を記した帳面。
⇒そう‐ば【相場】
そう‐はく【宗伯】
周代六卿の一人。春官の長。礼楽・祭祀をつかさどる。
そう‐はく【相博】サウ‥
(ソウバクとも)
①古代・中世、田地・所領などを交換すること。「―状」
②職務などを交代すること。
そう‐はく【蒼白】サウ‥
あおじろいこと。顔色などのあおざめて血色のわるいこと。「顔面―」
そう‐はく【蒼柏】サウ‥
あおあおと茂ったかしわ。
そう‐はく【糟粕】サウ‥
①酒のかす。
②(「糟魄」とも書く)転じて、滋味をとり去った残りかす。精神の抜けた外形。「古人の―」
⇒糟粕を嘗める
ぞう‐はく【増白】
繊維や紙がより白くみえるようにすること。染料などの青色着色剤による青味づけと蛍光増白剤による蛍光増白とがある。
広辞苑 ページ 11464 での【○桑田変じて滄海となる】単語。