複数辞典一括検索+![]()
![]()
○どうも言われぬどうもいわれぬ🔗⭐🔉
○どうも言われぬどうもいわれぬ
何とも言えないくらいである。程度が甚だしくて形容のしようがない。「どうも言えぬ」とも。好色一代男7「腰つき―能き所あつて」
⇒どう‐も
どう‐もう【童蒙】
幼少で道理にくらい者。子供。
どう‐もう【獰猛】ダウマウ
性質が荒くたけだけしいこと。性質が悪く、強いさま。「―な犬」「―な顔付き」
どう‐もう【艟艨】
いくさぶね。軍艦。艨艟。
どうもうしょういん【童蒙頌韻】‥ヰン
詩賦に関する字書。三善為康著。2巻。1109年(天仁2)成る。詩作のために韻を暗誦する手段として工夫されたもので、上平声・下平声の綱目に従い、平声の文字を列挙、4字句として片仮名で音訓を施した書。
とう‐もく【湯沐】タウ‥
湯に浴し髪を洗うこと。湯で身体をきよめること。ゆあみ。
とう‐もく【頭目】
かしら。首領。
どう‐もく【瞠目】ダウ‥
驚いたり感心したりして目をみはること。
とう‐もしち【鄧茂七】
明代、福建の民衆蜂起の指導者。1448年貧窮化した小作人や無頼を組織して挙兵、王を称したが敗れ、戦死。( 〜1449)
とう‐もつ【唐物】タウ‥
⇒とうぶつ。日葡辞書「タウモッワヤク(和薬)」
どう‐もと【胴元・筒元】
①ばくちなどの親。賭場を主催している者。采さいの筒を振る意から起こったという。どうおや。貸元。
②転じて、しめくくりをする人。もとじめ。
どうもと【堂本】ダウ‥
姓氏の一つ。
⇒どうもと‐いんしょう【堂本印象】
どうもと‐いんしょう【堂本印象】ダウ‥シヤウ
日本画家。本名、三之助。京都生れ。優れた技巧にさまざまな表現法を取り入れた明快な画風を確立。日本画による抽象画も試みた。文化勲章。(1891〜1975)
堂本印象
撮影:田沼武能
 ⇒どうもと【堂本】
とう‐もの【当物】タウ‥
(取引用語)定期取引で当月限ぎりで売買されたもの。
とう‐もめん【唐木綿】タウ‥
西洋から渡来した木綿。糸が細く、織幅が広い。
どう‐もり【堂守】ダウ‥
堂を守ること。また、堂の番人。
とう‐もろこし【玉蜀黍】タウ‥
(「唐もろこし」の意)イネ科の一年生作物。中南米の原産とされる。世界各地に栽培され、小麦・稲に次ぎ食用作物で3位。日本には16世紀に渡来。茎は1〜3メートルで、直立。葉は互生し幅5〜10センチメートル、長さ約1メートル。雄花穂は茎頂に、雌花穂は葉腋に付く。粒は澱粉に富み、食用、工業原料。茎葉は青刈り飼料・サイレージとし、飼料作物として最も重要。変種にデント・フリント・ポップ・スイート・ハニーバンタムなどがある。トウキビ。ナンバンキビ。トウマメ。コウライ。ツトキビ。マキビ。アメリカ名、コーン。英語名、インディアン‐コーン。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物
とうもろこし
⇒どうもと【堂本】
とう‐もの【当物】タウ‥
(取引用語)定期取引で当月限ぎりで売買されたもの。
とう‐もめん【唐木綿】タウ‥
西洋から渡来した木綿。糸が細く、織幅が広い。
どう‐もり【堂守】ダウ‥
堂を守ること。また、堂の番人。
とう‐もろこし【玉蜀黍】タウ‥
(「唐もろこし」の意)イネ科の一年生作物。中南米の原産とされる。世界各地に栽培され、小麦・稲に次ぎ食用作物で3位。日本には16世紀に渡来。茎は1〜3メートルで、直立。葉は互生し幅5〜10センチメートル、長さ約1メートル。雄花穂は茎頂に、雌花穂は葉腋に付く。粒は澱粉に富み、食用、工業原料。茎葉は青刈り飼料・サイレージとし、飼料作物として最も重要。変種にデント・フリント・ポップ・スイート・ハニーバンタムなどがある。トウキビ。ナンバンキビ。トウマメ。コウライ。ツトキビ。マキビ。アメリカ名、コーン。英語名、インディアン‐コーン。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物
とうもろこし
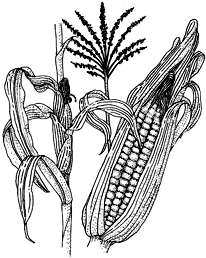 玉蜀黍
撮影:関戸 勇
玉蜀黍
撮影:関戸 勇
 玉蜀黍(実)
撮影:関戸 勇
玉蜀黍(実)
撮影:関戸 勇
 とう‐もん【東門】
①東方の門。東面の門。
②瓜の異名。〈文明本節用集〉
とう‐もん【藤門】
藤原惺窩せいかの門下。
⇒とうもん‐しか【藤門四家】
どう‐もん【同門】
①師を同じくすること。また、その人。あいでし。
②同じ門流。同じ宗派。日葡辞書「ドウモンドウシャウ(同姓)ノヒトナリ」
どう‐もん【洞門】
①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。
②向うまで貫通するほらあな。
どう‐もん【道門】ダウ‥
①道家の門流。道教。
②仏道に入る門。仏道。
とうもん‐しか【藤門四家】
藤門の四大家、林羅山・松永尺五・堀杏庵・那波活所の総称。藤門四天王とも。
⇒とう‐もん【藤門】
とう‐や【当夜】タウ‥
①その夜。その事の行われる夜。
②この夜。今夜。
とう‐や【当屋】タウ‥
(→)頭屋とうやに同じ。
とう‐や【陶冶】タウ‥
(陶器を造ることと、鋳物を鋳ることから)人間の持って生まれた性質を円満完全に発達させること。人材を薫陶養成すること。「人格の―」
とう‐や【塔屋】タフ‥
建物の屋上に突出した小屋。ビルの昇降機塔・装飾塔・換気塔の類。
とう‐や【頭屋】
部落の祭礼の神事宿。また、その家の主人。古くは世襲であったが、限られた家だけで交替しているところが多い。一般に、寄合の世話役にもいう。当屋。→宮座みやざ
どう‐や【同夜】
①おなじ夜。
②その日の夜。
とう‐やく【当役】タウ‥
①この役。その係。
②(→)頭役とうやくに同じ。
とう‐やく【当薬】タウ‥
センブリの開花期の全草を乾燥したもの。健胃剤。
⇒とうやく‐りんどう【当薬竜胆】
とう‐やく【投薬】
疾病に適した薬剤を与えること。投与。「患者に―する」
とう‐やく【唐薬】タウ‥
中国から渡来した薬。歌舞伎、東海道四谷怪談「先祖より伝はるソウキセイと申す―」
とう‐やく【湯薬】タウ‥
せんじぐすり。煎薬せんやく。
とう‐やく【膏薬】タウ‥
「こうやく」の忌みことば。紫式部日記「―くばれる、例のことどもなり」
とう‐やく【頭役】
祭礼や寄合の主役・世話役。また、それを務める人。当役。
とう‐やく【騰躍】
おどり上がること。飛び上がること。
どう‐やく【同役】
同じ役目。また、同じ役目を務める人。相役。同僚。
どうやく‐ハルマ【道訳法児馬】ダウ‥
(→)ハルマ(波留麻)2の別称。
とうやく‐りんどう【当薬竜胆】タウ‥ダウ
リンドウ科の多年草。高山帯に生える。葉は細く厚く、花は筒状、帯黄白色で緑斑がある。夏、開花。根は当薬(センブリ)のように苦く、薬用。
トウヤクリンドウ
提供:OPO
とう‐もん【東門】
①東方の門。東面の門。
②瓜の異名。〈文明本節用集〉
とう‐もん【藤門】
藤原惺窩せいかの門下。
⇒とうもん‐しか【藤門四家】
どう‐もん【同門】
①師を同じくすること。また、その人。あいでし。
②同じ門流。同じ宗派。日葡辞書「ドウモンドウシャウ(同姓)ノヒトナリ」
どう‐もん【洞門】
①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。
②向うまで貫通するほらあな。
どう‐もん【道門】ダウ‥
①道家の門流。道教。
②仏道に入る門。仏道。
とうもん‐しか【藤門四家】
藤門の四大家、林羅山・松永尺五・堀杏庵・那波活所の総称。藤門四天王とも。
⇒とう‐もん【藤門】
とう‐や【当夜】タウ‥
①その夜。その事の行われる夜。
②この夜。今夜。
とう‐や【当屋】タウ‥
(→)頭屋とうやに同じ。
とう‐や【陶冶】タウ‥
(陶器を造ることと、鋳物を鋳ることから)人間の持って生まれた性質を円満完全に発達させること。人材を薫陶養成すること。「人格の―」
とう‐や【塔屋】タフ‥
建物の屋上に突出した小屋。ビルの昇降機塔・装飾塔・換気塔の類。
とう‐や【頭屋】
部落の祭礼の神事宿。また、その家の主人。古くは世襲であったが、限られた家だけで交替しているところが多い。一般に、寄合の世話役にもいう。当屋。→宮座みやざ
どう‐や【同夜】
①おなじ夜。
②その日の夜。
とう‐やく【当役】タウ‥
①この役。その係。
②(→)頭役とうやくに同じ。
とう‐やく【当薬】タウ‥
センブリの開花期の全草を乾燥したもの。健胃剤。
⇒とうやく‐りんどう【当薬竜胆】
とう‐やく【投薬】
疾病に適した薬剤を与えること。投与。「患者に―する」
とう‐やく【唐薬】タウ‥
中国から渡来した薬。歌舞伎、東海道四谷怪談「先祖より伝はるソウキセイと申す―」
とう‐やく【湯薬】タウ‥
せんじぐすり。煎薬せんやく。
とう‐やく【膏薬】タウ‥
「こうやく」の忌みことば。紫式部日記「―くばれる、例のことどもなり」
とう‐やく【頭役】
祭礼や寄合の主役・世話役。また、それを務める人。当役。
とう‐やく【騰躍】
おどり上がること。飛び上がること。
どう‐やく【同役】
同じ役目。また、同じ役目を務める人。相役。同僚。
どうやく‐ハルマ【道訳法児馬】ダウ‥
(→)ハルマ(波留麻)2の別称。
とうやく‐りんどう【当薬竜胆】タウ‥ダウ
リンドウ科の多年草。高山帯に生える。葉は細く厚く、花は筒状、帯黄白色で緑斑がある。夏、開花。根は当薬(センブリ)のように苦く、薬用。
トウヤクリンドウ
提供:OPO
 ⇒とう‐やく【当薬】
とうや‐こ【洞爺湖】
北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。
洞爺湖
撮影:山梨勝弘
⇒とう‐やく【当薬】
とうや‐こ【洞爺湖】
北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。
洞爺湖
撮影:山梨勝弘
 ⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】
とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥
洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。
⇒とうや‐こ【洞爺湖】
とう‐やしゅう【東野州】‥シウ
東常縁とうのつねよりの別名。
⇒とう【東】
とうやま【頭山】
姓氏の一つ。
⇒とうやま‐みつる【頭山満】
とうやま‐みつる【頭山満】
右翼の巨頭。福岡藩士の子。萩の乱に連座して入獄。出獄後自由民権運動に従い、玄洋社を創設、井上馨・大隈重信の条約改正案に反対。国会開設後は国権の伸張、大陸進出を唱え、政界の黒幕。(1855〜1944)
⇒とうやま【頭山】
とうや‐まる【洞爺丸】
青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。
機上から撮影
提供:毎日新聞社
⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】
とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥
洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。
⇒とうや‐こ【洞爺湖】
とう‐やしゅう【東野州】‥シウ
東常縁とうのつねよりの別名。
⇒とう【東】
とうやま【頭山】
姓氏の一つ。
⇒とうやま‐みつる【頭山満】
とうやま‐みつる【頭山満】
右翼の巨頭。福岡藩士の子。萩の乱に連座して入獄。出獄後自由民権運動に従い、玄洋社を創設、井上馨・大隈重信の条約改正案に反対。国会開設後は国権の伸張、大陸進出を唱え、政界の黒幕。(1855〜1944)
⇒とうやま【頭山】
とうや‐まる【洞爺丸】
青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。
機上から撮影
提供:毎日新聞社
 船体引き上げ作業
提供:毎日新聞社
船体引き上げ作業
提供:毎日新聞社
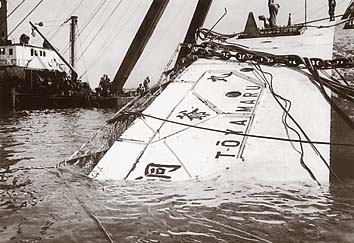 どう‐やら
〔副〕
①ようようのことで。なんとか。どうにか。「―暮しが成り立つ」
②何となく。どことなく。浮世風呂4「私共も―洗ひたう成ります」。「―一雨来そうだ」
⇒どうやら‐こうやら
どうやら‐こうやら‥カウ‥
ようやくのことで。かろうじて。どうにかこうにか。浮世風呂3「あれが気ままにして置いても、―覚えるから」
⇒どう‐やら
とう‐ゆ【灯油】
(kerosene)
①点灯用の油。ともしあぶら。
②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。
⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】
とう‐ゆ【桐油】
①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。
②桐油紙の略。
③桐油合羽の略。
⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】
⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】
⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】
とう‐ゆう【党友】タウイウ
①同じ党派のなかま。
②外部からその党派をたすける者。
どう‐ゆう【同友】‥イウ
志を同じくする友。
どう‐ゆう【同憂】‥イウ
憂いをともにすること。また、その人。「―の士」
どう‐ゆう【導誘】ダウイウ
みちびきいざなうこと。誘導。
とうゆうき【東遊記】‥イウ‥
紀行。橘南谿著。1784年(天明4)秋から2年間、京を出て江戸に至り、東海・東山・北陸を遍歴した間の佳話・異聞などを記録。前編5巻5冊は95年(寛政7)刊、後編5巻5冊は97年刊。→西遊記3
とう‐ゆう‐し【投融資】
投資と融資。
とうゆ‐うるし【桐油漆】
桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】
桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐がみ【桐油紙】
桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン
灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。
⇒とう‐ゆ【灯油】
とう‐ゆみ【唐弓】タウ‥
綿を打って柔らかくする道具。5尺余の木弓に鯨の弦を張ったもの。わたうちゆみ。日本永代蔵5「―といふ物はじめて作り出し」
とう‐よ【投与】
①投げ与えること。
②薬剤を与えること。
とうよ【東予】
愛媛県中部の旧市名。→西条1
とう‐よ【党与】タウ‥
なかま。くみ。徒党。折たく柴の記上「我が父もその―なり」
とう‐よう【灯用】
灯火に用いること。「―アルコール」
とう‐よう【当用】タウ‥
①さしあたっての用事。当面の需要。日葡辞書「タウヨウニタツ」
②さしあたって使用すること。
⇒とうよう‐かい【当用買い】
⇒とうよう‐かんじ【当用漢字】
⇒とうよう‐にっき【当用日記】
とう‐よう【東洋】‥ヤウ
①トルコ以東のアジア諸国の総称。特に、アジアの東部及び南部、すなわち日本・中国・インド・ミャンマー(ビルマ)・タイ・インドシナ・インドネシアなどの称。↔西洋。
②中国で、日本を指す称呼。
⇒とうよう‐いがく【東洋医学】
⇒とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】
⇒とうよう‐おり【東洋織】
⇒とうよう‐おんがく【東洋音楽】
⇒とうよう‐が【東洋画】
⇒とうよう‐がく【東洋学】
⇒とうよう‐く【東洋区】
⇒とうよう‐し【東洋紙】
⇒とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】
⇒とうよう‐だいがく【東洋大学】
⇒とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】
⇒とうよう‐だんつう【東洋緞通】
⇒とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】
とう‐よう【桃夭】タウエウ
[詩経周南、桃夭](「夭」は、若く美しいさま)嫁ぐ女性を桃の美しさにたとえていう語。よめいりどき。嫁期。
とう‐よう【盗用】タウ‥
ぬすんで使用すること。「デザイン―」
とう‐よう【陶窯】タウエウ
陶磁器を焼くかま。
とう‐よう【登用・登庸】
官職などに、人材を引きあげ用いること。「新人を―する」「―試験」
とう‐よう【蕩揺】タウエウ
ゆれ動くこと。ゆり動かすこと。
とう‐よう【糖葉】タウエフ
光合成で同化された炭水化物が、主としてブドウ糖や庶糖などの糖として堆積される葉。イネ科など単子葉植物の葉に多い。↔澱粉葉
どう‐よう【同様】‥ヤウ
同じさまであること。「ただ―の値段」「母―に親しんだ人」
どう‐よう【動揺】‥エウ
①動きゆらぐこと。ぐらつくこと。
②転じて、気持などが不安定になること。不安。「心の―を隠す」
③騒擾そうじょう。さわぎ。「政界の―」
どう‐よう【童幼】‥エウ
年少の者。おさないこども。
どう‐よう【童謡】‥エウ
①子供が作って口ずさむ歌、または詩。
②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。
㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。
⇒どうよう‐おどり【童謡踊】
とうよう‐いがく【東洋医学】‥ヤウ‥
東洋、特に中国の伝統的医学。→中国医学。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】‥ヤウ‥ヂヨ‥ヰン‥
私立大学の一つ。カナダ‐メソジスト教会の宣教師が1884年(明治17)に創設した東洋英和女学校を前身とし、1946年東洋英和女学院と改称。89年現大学。横浜市緑区。
⇒とう‐よう【東洋】
どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ
童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。
⇒どう‐よう【童謡】
とうよう‐おり【東洋織】‥ヤウ‥
①綿織物の一種。経緯たてよこともに木綿の太糸を用いた敷物用織物。
②絹綿交織まぜおり物。緯には綿糸を使い、経には二重の練絹糸を用いて紋様を織り出した布。袋物や鼻緒地とする。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐おんがく【東洋音楽】‥ヤウ‥
東洋、すなわち日本・中国・東南アジア・インド・西アジアなどのアジア諸民族間に行われる音楽の総称。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐が【東洋画】‥ヤウグワ
東洋、特に中国を中心に発達した絵画の総称。日本画も広い意味ではこれに含まれる。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐かい【当用買い】タウ‥カヒ
さしあたり使う分だけを買うこと。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐がく【東洋学】‥ヤウ‥
東洋について研究する学問。宣教師が現地の事情を本国に報告したことから、ヨーロッパに始まる。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐かんじ【当用漢字】タウ‥
現代国語を書き表すために、日常使用する漢字の範囲を定めたもので、国語審議会が決定・答申し、政府が訓令・告示をもって公布した1850字の漢字。1946年(昭和21)11月発表。その後、48年2月に当用漢字音訓表・当用漢字別表(いわゆる教育漢字)が、49年4月には当用漢字字体表が発表された。現在は常用漢字(1981年10月告示)がこれにかわる。→常用漢字。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐く【東洋区】‥ヤウ‥
動物地理学上の一区域。ボルネオ・フィリピン以西の東南アジア。ヒマラヤ山脈以南のインドからインドシナ、長江以南のユーラシア大陸を含む。ヒヨケザル類・テナガザル・メガネザル・ツパイなどの霊長類、マメジカ・コノハドリの類を産する。→動物地理区(図)。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐し【東洋紙】‥ヤウ‥
三椏みつまた繊維を原料とし、溜漉ためずき法による厚手の強靱な和紙。福岡県のほか高知・岐阜・福井などに産し、主に包み紙に使用。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】‥ヤウ‥イウタウ
大井憲太郎らが中心となって1892年(明治25)組織した政党。民権の拡張とともに強硬外交を唱える。翌年解散。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐だいがく【東洋大学】‥ヤウ‥
私立大学の一つ。前身は1887年(明治20)井上円了が創設した哲学館。1906年東洋大学と改称。49年新制大学。本部は東京都文京区。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】‥ヤウ‥グワイ‥
朝鮮における植民地的農業経営のために1908年に設立された日本の国策会社。土地買収・地主的農業経営を行い、のち中国東北部・南洋などにも進出。45年解体。東拓。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐だんつう【東洋緞通】‥ヤウ‥
トルコ・ペルシア・インド・中国および日本で製出する緞通の総称。主として手工業により、色の調和、模様の高尚優美を特徴とする。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐にっき【当用日記】タウ‥
さしあたっての用事を記す日記。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】‥ヤウ‥
東洋学関係の図書館・研究機関。1917年(大正6)に岩崎久弥がG.E.モリソンから購入した蔵書を中心としてモリソン文庫を設立。24年東洋文庫と改称。和漢洋の東洋学文献を収集し、また、和書の貴重書を含む岩崎文庫などを加える。第二次大戦後は国立国会図書館支部。東京都文京区。
⇒とう‐よう【東洋】
とう‐よく【湯浴】タウ‥
①ゆあみ。入浴。
②化学実験・製薬などで、湯煎ゆせんを行うこと。また、その用器。普通、広い円孔のある蓋をもつ半球形の薄い銅製の鍋。ウォーター‐バス。
どう‐よく【胴欲】
(ドンヨク(貪欲)の転)
①非常に欲が深いこと。ひどくむさぼること。可笑記「不行儀、―深く」
②むごいこと。非道なこと。狂言、清水「そのやうな―な事するものか」
どう‐よろい【胴鎧】‥ヨロヒ
胴の部分にまとう鎧。
ドヴラートフ【Sergei D. Dovlatov】
ロシア(ソ連)の小説家。父はユダヤ人、母はアルメニア人。レニングラードに育ち、1978年アメリカ合衆国に亡命。ユーモアとアイロニーに満ちた語り口を身上とする。「わが家の人々」「かばん」など。(1941〜1990)
とうらい
拳けんの用語で、十のこと。浄瑠璃、冥途飛脚「拳の手品の手もたゆく、ろませ、さい、―、さんな」
とう‐らい【当来】タウ‥
①当然に来るべきこと。あたりまえ。
②まさに来るべき世。未来。来世。今昔物語集4「聖人は必ず―に成仏し給はむとす」
⇒とうらい‐どうし【当来導師】
⇒とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】
とう‐らい【到来】タウ‥
①こちらへやって来ること。機運などの向いてくること。徒然草「我等が生死しょうじの―ただ今にもやあらん」。「時節―」
②他から贈物の届くこと。また、その物。
⇒とうらい‐ちょう【到来帳】
⇒とうらい‐もの【到来物】
とうらい‐さんな【唐来参和】タウ‥ワ
(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名)江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良よものあからの門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき」など。(1744〜1810)
→文献資料[莫切自根金生木]
とうらい‐ちょう【到来帳】タウ‥チヤウ
(→)野帳のちょう2に同じ。
⇒とう‐らい【到来】
とうらい‐どうし【当来導師】タウ‥ダウ‥
来るべき世に出現する導師、すなわち56億7000万年を経た後、この世界に出現し、成道して衆生を化導するという弥勒みろく菩薩。
⇒とう‐らい【当来】
とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】タウ‥
来るべき世で、弥勒菩薩に会って仏道を成ずること。太平記3「今生の逆罪を翻して―とや成らん」
⇒とう‐らい【当来】
とうらい‐もの【到来物】タウ‥
他から贈って来たもの。もらいもの。いただきもの。
⇒とう‐らい【到来】
とう‐らく【当落】タウ‥
当選と落選。「―が決まる」
とう‐らく【頭絡】
牛・馬・羊などの移動・運動・調教・使役の時に用いる綱・皮などの繋縛用具。
とう‐らく【騰落】
物価の高くなることと安くなること。騰貴と下落。
どう‐らく【道楽】ダウ‥
(道を解して自ら楽しむ意から)
①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」
②ものずき。好事こうず。
③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」
⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】
⇒どうらく‐もの【道楽者】
どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥
身持ちのよくない息子。放蕩息子。
⇒どう‐らく【道楽】
どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥
①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。
②なまけもの。
⇒どう‐らく【道楽】
とうら‐ご【俵子】
(西日本で)海鼠なまこ。特に正月には初俵という。たわらご。
とう‐らん【冬卵】
ワムシ・ミジンコなどや扁形動物のある種で、秋の終りに産む大形の卵。耐久卵。ふゆらん。↔夏卵
とう‐らん【闘乱】
争乱。戦乱。源平盛衰記9「たとひ合戦―の中なりとも」
どう‐らん【胴乱】
①革または羅紗ラシャ布などで作った方形の袋。薬・印・煙草・銭などを入れて腰に下げる。もとは銃丸を入れる袋だったという。銃卵。筒卵。佩嚢はいのう。
胴乱
どう‐やら
〔副〕
①ようようのことで。なんとか。どうにか。「―暮しが成り立つ」
②何となく。どことなく。浮世風呂4「私共も―洗ひたう成ります」。「―一雨来そうだ」
⇒どうやら‐こうやら
どうやら‐こうやら‥カウ‥
ようやくのことで。かろうじて。どうにかこうにか。浮世風呂3「あれが気ままにして置いても、―覚えるから」
⇒どう‐やら
とう‐ゆ【灯油】
(kerosene)
①点灯用の油。ともしあぶら。
②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。
⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】
とう‐ゆ【桐油】
①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。
②桐油紙の略。
③桐油合羽の略。
⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】
⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】
⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】
とう‐ゆう【党友】タウイウ
①同じ党派のなかま。
②外部からその党派をたすける者。
どう‐ゆう【同友】‥イウ
志を同じくする友。
どう‐ゆう【同憂】‥イウ
憂いをともにすること。また、その人。「―の士」
どう‐ゆう【導誘】ダウイウ
みちびきいざなうこと。誘導。
とうゆうき【東遊記】‥イウ‥
紀行。橘南谿著。1784年(天明4)秋から2年間、京を出て江戸に至り、東海・東山・北陸を遍歴した間の佳話・異聞などを記録。前編5巻5冊は95年(寛政7)刊、後編5巻5冊は97年刊。→西遊記3
とう‐ゆう‐し【投融資】
投資と融資。
とうゆ‐うるし【桐油漆】
桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】
桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐がみ【桐油紙】
桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン
灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。
⇒とう‐ゆ【灯油】
とう‐ゆみ【唐弓】タウ‥
綿を打って柔らかくする道具。5尺余の木弓に鯨の弦を張ったもの。わたうちゆみ。日本永代蔵5「―といふ物はじめて作り出し」
とう‐よ【投与】
①投げ与えること。
②薬剤を与えること。
とうよ【東予】
愛媛県中部の旧市名。→西条1
とう‐よ【党与】タウ‥
なかま。くみ。徒党。折たく柴の記上「我が父もその―なり」
とう‐よう【灯用】
灯火に用いること。「―アルコール」
とう‐よう【当用】タウ‥
①さしあたっての用事。当面の需要。日葡辞書「タウヨウニタツ」
②さしあたって使用すること。
⇒とうよう‐かい【当用買い】
⇒とうよう‐かんじ【当用漢字】
⇒とうよう‐にっき【当用日記】
とう‐よう【東洋】‥ヤウ
①トルコ以東のアジア諸国の総称。特に、アジアの東部及び南部、すなわち日本・中国・インド・ミャンマー(ビルマ)・タイ・インドシナ・インドネシアなどの称。↔西洋。
②中国で、日本を指す称呼。
⇒とうよう‐いがく【東洋医学】
⇒とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】
⇒とうよう‐おり【東洋織】
⇒とうよう‐おんがく【東洋音楽】
⇒とうよう‐が【東洋画】
⇒とうよう‐がく【東洋学】
⇒とうよう‐く【東洋区】
⇒とうよう‐し【東洋紙】
⇒とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】
⇒とうよう‐だいがく【東洋大学】
⇒とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】
⇒とうよう‐だんつう【東洋緞通】
⇒とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】
とう‐よう【桃夭】タウエウ
[詩経周南、桃夭](「夭」は、若く美しいさま)嫁ぐ女性を桃の美しさにたとえていう語。よめいりどき。嫁期。
とう‐よう【盗用】タウ‥
ぬすんで使用すること。「デザイン―」
とう‐よう【陶窯】タウエウ
陶磁器を焼くかま。
とう‐よう【登用・登庸】
官職などに、人材を引きあげ用いること。「新人を―する」「―試験」
とう‐よう【蕩揺】タウエウ
ゆれ動くこと。ゆり動かすこと。
とう‐よう【糖葉】タウエフ
光合成で同化された炭水化物が、主としてブドウ糖や庶糖などの糖として堆積される葉。イネ科など単子葉植物の葉に多い。↔澱粉葉
どう‐よう【同様】‥ヤウ
同じさまであること。「ただ―の値段」「母―に親しんだ人」
どう‐よう【動揺】‥エウ
①動きゆらぐこと。ぐらつくこと。
②転じて、気持などが不安定になること。不安。「心の―を隠す」
③騒擾そうじょう。さわぎ。「政界の―」
どう‐よう【童幼】‥エウ
年少の者。おさないこども。
どう‐よう【童謡】‥エウ
①子供が作って口ずさむ歌、または詩。
②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。
㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。
⇒どうよう‐おどり【童謡踊】
とうよう‐いがく【東洋医学】‥ヤウ‥
東洋、特に中国の伝統的医学。→中国医学。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】‥ヤウ‥ヂヨ‥ヰン‥
私立大学の一つ。カナダ‐メソジスト教会の宣教師が1884年(明治17)に創設した東洋英和女学校を前身とし、1946年東洋英和女学院と改称。89年現大学。横浜市緑区。
⇒とう‐よう【東洋】
どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ
童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。
⇒どう‐よう【童謡】
とうよう‐おり【東洋織】‥ヤウ‥
①綿織物の一種。経緯たてよこともに木綿の太糸を用いた敷物用織物。
②絹綿交織まぜおり物。緯には綿糸を使い、経には二重の練絹糸を用いて紋様を織り出した布。袋物や鼻緒地とする。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐おんがく【東洋音楽】‥ヤウ‥
東洋、すなわち日本・中国・東南アジア・インド・西アジアなどのアジア諸民族間に行われる音楽の総称。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐が【東洋画】‥ヤウグワ
東洋、特に中国を中心に発達した絵画の総称。日本画も広い意味ではこれに含まれる。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐かい【当用買い】タウ‥カヒ
さしあたり使う分だけを買うこと。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐がく【東洋学】‥ヤウ‥
東洋について研究する学問。宣教師が現地の事情を本国に報告したことから、ヨーロッパに始まる。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐かんじ【当用漢字】タウ‥
現代国語を書き表すために、日常使用する漢字の範囲を定めたもので、国語審議会が決定・答申し、政府が訓令・告示をもって公布した1850字の漢字。1946年(昭和21)11月発表。その後、48年2月に当用漢字音訓表・当用漢字別表(いわゆる教育漢字)が、49年4月には当用漢字字体表が発表された。現在は常用漢字(1981年10月告示)がこれにかわる。→常用漢字。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐く【東洋区】‥ヤウ‥
動物地理学上の一区域。ボルネオ・フィリピン以西の東南アジア。ヒマラヤ山脈以南のインドからインドシナ、長江以南のユーラシア大陸を含む。ヒヨケザル類・テナガザル・メガネザル・ツパイなどの霊長類、マメジカ・コノハドリの類を産する。→動物地理区(図)。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐し【東洋紙】‥ヤウ‥
三椏みつまた繊維を原料とし、溜漉ためずき法による厚手の強靱な和紙。福岡県のほか高知・岐阜・福井などに産し、主に包み紙に使用。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】‥ヤウ‥イウタウ
大井憲太郎らが中心となって1892年(明治25)組織した政党。民権の拡張とともに強硬外交を唱える。翌年解散。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐だいがく【東洋大学】‥ヤウ‥
私立大学の一つ。前身は1887年(明治20)井上円了が創設した哲学館。1906年東洋大学と改称。49年新制大学。本部は東京都文京区。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】‥ヤウ‥グワイ‥
朝鮮における植民地的農業経営のために1908年に設立された日本の国策会社。土地買収・地主的農業経営を行い、のち中国東北部・南洋などにも進出。45年解体。東拓。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐だんつう【東洋緞通】‥ヤウ‥
トルコ・ペルシア・インド・中国および日本で製出する緞通の総称。主として手工業により、色の調和、模様の高尚優美を特徴とする。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐にっき【当用日記】タウ‥
さしあたっての用事を記す日記。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】‥ヤウ‥
東洋学関係の図書館・研究機関。1917年(大正6)に岩崎久弥がG.E.モリソンから購入した蔵書を中心としてモリソン文庫を設立。24年東洋文庫と改称。和漢洋の東洋学文献を収集し、また、和書の貴重書を含む岩崎文庫などを加える。第二次大戦後は国立国会図書館支部。東京都文京区。
⇒とう‐よう【東洋】
とう‐よく【湯浴】タウ‥
①ゆあみ。入浴。
②化学実験・製薬などで、湯煎ゆせんを行うこと。また、その用器。普通、広い円孔のある蓋をもつ半球形の薄い銅製の鍋。ウォーター‐バス。
どう‐よく【胴欲】
(ドンヨク(貪欲)の転)
①非常に欲が深いこと。ひどくむさぼること。可笑記「不行儀、―深く」
②むごいこと。非道なこと。狂言、清水「そのやうな―な事するものか」
どう‐よろい【胴鎧】‥ヨロヒ
胴の部分にまとう鎧。
ドヴラートフ【Sergei D. Dovlatov】
ロシア(ソ連)の小説家。父はユダヤ人、母はアルメニア人。レニングラードに育ち、1978年アメリカ合衆国に亡命。ユーモアとアイロニーに満ちた語り口を身上とする。「わが家の人々」「かばん」など。(1941〜1990)
とうらい
拳けんの用語で、十のこと。浄瑠璃、冥途飛脚「拳の手品の手もたゆく、ろませ、さい、―、さんな」
とう‐らい【当来】タウ‥
①当然に来るべきこと。あたりまえ。
②まさに来るべき世。未来。来世。今昔物語集4「聖人は必ず―に成仏し給はむとす」
⇒とうらい‐どうし【当来導師】
⇒とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】
とう‐らい【到来】タウ‥
①こちらへやって来ること。機運などの向いてくること。徒然草「我等が生死しょうじの―ただ今にもやあらん」。「時節―」
②他から贈物の届くこと。また、その物。
⇒とうらい‐ちょう【到来帳】
⇒とうらい‐もの【到来物】
とうらい‐さんな【唐来参和】タウ‥ワ
(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名)江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良よものあからの門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき」など。(1744〜1810)
→文献資料[莫切自根金生木]
とうらい‐ちょう【到来帳】タウ‥チヤウ
(→)野帳のちょう2に同じ。
⇒とう‐らい【到来】
とうらい‐どうし【当来導師】タウ‥ダウ‥
来るべき世に出現する導師、すなわち56億7000万年を経た後、この世界に出現し、成道して衆生を化導するという弥勒みろく菩薩。
⇒とう‐らい【当来】
とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】タウ‥
来るべき世で、弥勒菩薩に会って仏道を成ずること。太平記3「今生の逆罪を翻して―とや成らん」
⇒とう‐らい【当来】
とうらい‐もの【到来物】タウ‥
他から贈って来たもの。もらいもの。いただきもの。
⇒とう‐らい【到来】
とう‐らく【当落】タウ‥
当選と落選。「―が決まる」
とう‐らく【頭絡】
牛・馬・羊などの移動・運動・調教・使役の時に用いる綱・皮などの繋縛用具。
とう‐らく【騰落】
物価の高くなることと安くなること。騰貴と下落。
どう‐らく【道楽】ダウ‥
(道を解して自ら楽しむ意から)
①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」
②ものずき。好事こうず。
③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」
⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】
⇒どうらく‐もの【道楽者】
どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥
身持ちのよくない息子。放蕩息子。
⇒どう‐らく【道楽】
どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥
①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。
②なまけもの。
⇒どう‐らく【道楽】
とうら‐ご【俵子】
(西日本で)海鼠なまこ。特に正月には初俵という。たわらご。
とう‐らん【冬卵】
ワムシ・ミジンコなどや扁形動物のある種で、秋の終りに産む大形の卵。耐久卵。ふゆらん。↔夏卵
とう‐らん【闘乱】
争乱。戦乱。源平盛衰記9「たとひ合戦―の中なりとも」
どう‐らん【胴乱】
①革または羅紗ラシャ布などで作った方形の袋。薬・印・煙草・銭などを入れて腰に下げる。もとは銃丸を入れる袋だったという。銃卵。筒卵。佩嚢はいのう。
胴乱
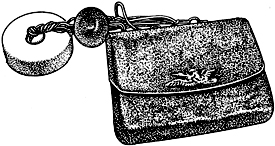 ②植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具。
③菓子の名。「ごまどうらん」の略。
どう‐らん【動乱】
世の中の騒ぎみだれること。騒乱。転じて、戦乱。太平記12「国々の―更にやむ時無し」。「―が起こる」
どう‐らん【銅藍】
硫化銅から成る鉱物。六方晶系の板状・鱗状結晶。濃藍色。銅の鉱石で、銅鉱床の酸化帯中などに見出される。コベライト。コベリン。
とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥
卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。
とう‐り【東籬】
東の方にあるまがき。
⇒とうり‐よきょう【東籬余興】
とう‐り【党利】タウ‥
自分の所属する政党・党派の利益。
⇒とうり‐とうりゃく【党利党略】
とう‐り【凍梨】
霜で凍った梨。また、しみの出た老人の膚はだにたとえていう。
とう‐り【桃李】タウ‥
①桃ももと李すもも。
②[劉禹錫、詩「満城桃李春官に属す」]試験官の採用した門下生。また、自分の推挙した人材。自分の取り立てた門人。
⇒桃李言わざれども下自ずから蹊を成す
⇒桃李の粧
⇒桃李門に満つ
とう‐り【統理】
統すべおさめること。
どう‐り【道理】ダウ‥
①物事のそうあるべきすじみち。ことわり。源氏物語帚木「世の―を思ひとりて」。「そんなことが許される―がない」
②人の行うべき正しい道。道義。「―にはずれた行為」
⇒どうり‐ぜめ【道理責め】
⇒どうり‐づめ【道理詰め】
⇒どうり‐で【道理で】
⇒どうり‐はずれ【道理外れ】
⇒道理を詰む
⇒道理を破る法はあれども法を破る道理なし
②植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具。
③菓子の名。「ごまどうらん」の略。
どう‐らん【動乱】
世の中の騒ぎみだれること。騒乱。転じて、戦乱。太平記12「国々の―更にやむ時無し」。「―が起こる」
どう‐らん【銅藍】
硫化銅から成る鉱物。六方晶系の板状・鱗状結晶。濃藍色。銅の鉱石で、銅鉱床の酸化帯中などに見出される。コベライト。コベリン。
とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥
卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。
とう‐り【東籬】
東の方にあるまがき。
⇒とうり‐よきょう【東籬余興】
とう‐り【党利】タウ‥
自分の所属する政党・党派の利益。
⇒とうり‐とうりゃく【党利党略】
とう‐り【凍梨】
霜で凍った梨。また、しみの出た老人の膚はだにたとえていう。
とう‐り【桃李】タウ‥
①桃ももと李すもも。
②[劉禹錫、詩「満城桃李春官に属す」]試験官の採用した門下生。また、自分の推挙した人材。自分の取り立てた門人。
⇒桃李言わざれども下自ずから蹊を成す
⇒桃李の粧
⇒桃李門に満つ
とう‐り【統理】
統すべおさめること。
どう‐り【道理】ダウ‥
①物事のそうあるべきすじみち。ことわり。源氏物語帚木「世の―を思ひとりて」。「そんなことが許される―がない」
②人の行うべき正しい道。道義。「―にはずれた行為」
⇒どうり‐ぜめ【道理責め】
⇒どうり‐づめ【道理詰め】
⇒どうり‐で【道理で】
⇒どうり‐はずれ【道理外れ】
⇒道理を詰む
⇒道理を破る法はあれども法を破る道理なし
 ⇒どうもと【堂本】
とう‐もの【当物】タウ‥
(取引用語)定期取引で当月限ぎりで売買されたもの。
とう‐もめん【唐木綿】タウ‥
西洋から渡来した木綿。糸が細く、織幅が広い。
どう‐もり【堂守】ダウ‥
堂を守ること。また、堂の番人。
とう‐もろこし【玉蜀黍】タウ‥
(「唐もろこし」の意)イネ科の一年生作物。中南米の原産とされる。世界各地に栽培され、小麦・稲に次ぎ食用作物で3位。日本には16世紀に渡来。茎は1〜3メートルで、直立。葉は互生し幅5〜10センチメートル、長さ約1メートル。雄花穂は茎頂に、雌花穂は葉腋に付く。粒は澱粉に富み、食用、工業原料。茎葉は青刈り飼料・サイレージとし、飼料作物として最も重要。変種にデント・フリント・ポップ・スイート・ハニーバンタムなどがある。トウキビ。ナンバンキビ。トウマメ。コウライ。ツトキビ。マキビ。アメリカ名、コーン。英語名、インディアン‐コーン。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物
とうもろこし
⇒どうもと【堂本】
とう‐もの【当物】タウ‥
(取引用語)定期取引で当月限ぎりで売買されたもの。
とう‐もめん【唐木綿】タウ‥
西洋から渡来した木綿。糸が細く、織幅が広い。
どう‐もり【堂守】ダウ‥
堂を守ること。また、堂の番人。
とう‐もろこし【玉蜀黍】タウ‥
(「唐もろこし」の意)イネ科の一年生作物。中南米の原産とされる。世界各地に栽培され、小麦・稲に次ぎ食用作物で3位。日本には16世紀に渡来。茎は1〜3メートルで、直立。葉は互生し幅5〜10センチメートル、長さ約1メートル。雄花穂は茎頂に、雌花穂は葉腋に付く。粒は澱粉に富み、食用、工業原料。茎葉は青刈り飼料・サイレージとし、飼料作物として最も重要。変種にデント・フリント・ポップ・スイート・ハニーバンタムなどがある。トウキビ。ナンバンキビ。トウマメ。コウライ。ツトキビ。マキビ。アメリカ名、コーン。英語名、インディアン‐コーン。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物
とうもろこし
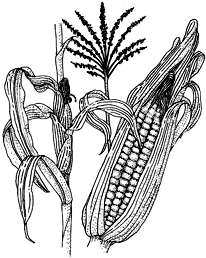 玉蜀黍
撮影:関戸 勇
玉蜀黍
撮影:関戸 勇
 玉蜀黍(実)
撮影:関戸 勇
玉蜀黍(実)
撮影:関戸 勇
 とう‐もん【東門】
①東方の門。東面の門。
②瓜の異名。〈文明本節用集〉
とう‐もん【藤門】
藤原惺窩せいかの門下。
⇒とうもん‐しか【藤門四家】
どう‐もん【同門】
①師を同じくすること。また、その人。あいでし。
②同じ門流。同じ宗派。日葡辞書「ドウモンドウシャウ(同姓)ノヒトナリ」
どう‐もん【洞門】
①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。
②向うまで貫通するほらあな。
どう‐もん【道門】ダウ‥
①道家の門流。道教。
②仏道に入る門。仏道。
とうもん‐しか【藤門四家】
藤門の四大家、林羅山・松永尺五・堀杏庵・那波活所の総称。藤門四天王とも。
⇒とう‐もん【藤門】
とう‐や【当夜】タウ‥
①その夜。その事の行われる夜。
②この夜。今夜。
とう‐や【当屋】タウ‥
(→)頭屋とうやに同じ。
とう‐や【陶冶】タウ‥
(陶器を造ることと、鋳物を鋳ることから)人間の持って生まれた性質を円満完全に発達させること。人材を薫陶養成すること。「人格の―」
とう‐や【塔屋】タフ‥
建物の屋上に突出した小屋。ビルの昇降機塔・装飾塔・換気塔の類。
とう‐や【頭屋】
部落の祭礼の神事宿。また、その家の主人。古くは世襲であったが、限られた家だけで交替しているところが多い。一般に、寄合の世話役にもいう。当屋。→宮座みやざ
どう‐や【同夜】
①おなじ夜。
②その日の夜。
とう‐やく【当役】タウ‥
①この役。その係。
②(→)頭役とうやくに同じ。
とう‐やく【当薬】タウ‥
センブリの開花期の全草を乾燥したもの。健胃剤。
⇒とうやく‐りんどう【当薬竜胆】
とう‐やく【投薬】
疾病に適した薬剤を与えること。投与。「患者に―する」
とう‐やく【唐薬】タウ‥
中国から渡来した薬。歌舞伎、東海道四谷怪談「先祖より伝はるソウキセイと申す―」
とう‐やく【湯薬】タウ‥
せんじぐすり。煎薬せんやく。
とう‐やく【膏薬】タウ‥
「こうやく」の忌みことば。紫式部日記「―くばれる、例のことどもなり」
とう‐やく【頭役】
祭礼や寄合の主役・世話役。また、それを務める人。当役。
とう‐やく【騰躍】
おどり上がること。飛び上がること。
どう‐やく【同役】
同じ役目。また、同じ役目を務める人。相役。同僚。
どうやく‐ハルマ【道訳法児馬】ダウ‥
(→)ハルマ(波留麻)2の別称。
とうやく‐りんどう【当薬竜胆】タウ‥ダウ
リンドウ科の多年草。高山帯に生える。葉は細く厚く、花は筒状、帯黄白色で緑斑がある。夏、開花。根は当薬(センブリ)のように苦く、薬用。
トウヤクリンドウ
提供:OPO
とう‐もん【東門】
①東方の門。東面の門。
②瓜の異名。〈文明本節用集〉
とう‐もん【藤門】
藤原惺窩せいかの門下。
⇒とうもん‐しか【藤門四家】
どう‐もん【同門】
①師を同じくすること。また、その人。あいでし。
②同じ門流。同じ宗派。日葡辞書「ドウモンドウシャウ(同姓)ノヒトナリ」
どう‐もん【洞門】
①ほらあなの入口。また、そこに設けた門戸。
②向うまで貫通するほらあな。
どう‐もん【道門】ダウ‥
①道家の門流。道教。
②仏道に入る門。仏道。
とうもん‐しか【藤門四家】
藤門の四大家、林羅山・松永尺五・堀杏庵・那波活所の総称。藤門四天王とも。
⇒とう‐もん【藤門】
とう‐や【当夜】タウ‥
①その夜。その事の行われる夜。
②この夜。今夜。
とう‐や【当屋】タウ‥
(→)頭屋とうやに同じ。
とう‐や【陶冶】タウ‥
(陶器を造ることと、鋳物を鋳ることから)人間の持って生まれた性質を円満完全に発達させること。人材を薫陶養成すること。「人格の―」
とう‐や【塔屋】タフ‥
建物の屋上に突出した小屋。ビルの昇降機塔・装飾塔・換気塔の類。
とう‐や【頭屋】
部落の祭礼の神事宿。また、その家の主人。古くは世襲であったが、限られた家だけで交替しているところが多い。一般に、寄合の世話役にもいう。当屋。→宮座みやざ
どう‐や【同夜】
①おなじ夜。
②その日の夜。
とう‐やく【当役】タウ‥
①この役。その係。
②(→)頭役とうやくに同じ。
とう‐やく【当薬】タウ‥
センブリの開花期の全草を乾燥したもの。健胃剤。
⇒とうやく‐りんどう【当薬竜胆】
とう‐やく【投薬】
疾病に適した薬剤を与えること。投与。「患者に―する」
とう‐やく【唐薬】タウ‥
中国から渡来した薬。歌舞伎、東海道四谷怪談「先祖より伝はるソウキセイと申す―」
とう‐やく【湯薬】タウ‥
せんじぐすり。煎薬せんやく。
とう‐やく【膏薬】タウ‥
「こうやく」の忌みことば。紫式部日記「―くばれる、例のことどもなり」
とう‐やく【頭役】
祭礼や寄合の主役・世話役。また、それを務める人。当役。
とう‐やく【騰躍】
おどり上がること。飛び上がること。
どう‐やく【同役】
同じ役目。また、同じ役目を務める人。相役。同僚。
どうやく‐ハルマ【道訳法児馬】ダウ‥
(→)ハルマ(波留麻)2の別称。
とうやく‐りんどう【当薬竜胆】タウ‥ダウ
リンドウ科の多年草。高山帯に生える。葉は細く厚く、花は筒状、帯黄白色で緑斑がある。夏、開花。根は当薬(センブリ)のように苦く、薬用。
トウヤクリンドウ
提供:OPO
 ⇒とう‐やく【当薬】
とうや‐こ【洞爺湖】
北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。
洞爺湖
撮影:山梨勝弘
⇒とう‐やく【当薬】
とうや‐こ【洞爺湖】
北海道南西部にあるカルデラ湖。湖面標高84メートル。最大深度180メートル。面積70.7平方キロメートル。南岸に有珠うす山・昭和新山の2火山がある。支笏しこつ湖とともに国立公園をなす。
洞爺湖
撮影:山梨勝弘
 ⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】
とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥
洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。
⇒とうや‐こ【洞爺湖】
とう‐やしゅう【東野州】‥シウ
東常縁とうのつねよりの別名。
⇒とう【東】
とうやま【頭山】
姓氏の一つ。
⇒とうやま‐みつる【頭山満】
とうやま‐みつる【頭山満】
右翼の巨頭。福岡藩士の子。萩の乱に連座して入獄。出獄後自由民権運動に従い、玄洋社を創設、井上馨・大隈重信の条約改正案に反対。国会開設後は国権の伸張、大陸進出を唱え、政界の黒幕。(1855〜1944)
⇒とうやま【頭山】
とうや‐まる【洞爺丸】
青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。
機上から撮影
提供:毎日新聞社
⇒とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】
とうやこ‐おんせん【洞爺湖温泉】‥ヲン‥
洞爺湖の南岸、有珠山の北麓にある温泉。泉質は塩化物泉。
⇒とうや‐こ【洞爺湖】
とう‐やしゅう【東野州】‥シウ
東常縁とうのつねよりの別名。
⇒とう【東】
とうやま【頭山】
姓氏の一つ。
⇒とうやま‐みつる【頭山満】
とうやま‐みつる【頭山満】
右翼の巨頭。福岡藩士の子。萩の乱に連座して入獄。出獄後自由民権運動に従い、玄洋社を創設、井上馨・大隈重信の条約改正案に反対。国会開設後は国権の伸張、大陸進出を唱え、政界の黒幕。(1855〜1944)
⇒とうやま【頭山】
とうや‐まる【洞爺丸】
青函連絡船の船名。1954年9月26日、台風15号のため函館港外で沈没。1155名が死亡、日本最大の海難事故となった。
機上から撮影
提供:毎日新聞社
 船体引き上げ作業
提供:毎日新聞社
船体引き上げ作業
提供:毎日新聞社
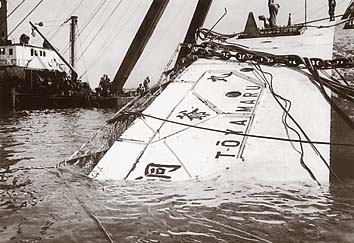 どう‐やら
〔副〕
①ようようのことで。なんとか。どうにか。「―暮しが成り立つ」
②何となく。どことなく。浮世風呂4「私共も―洗ひたう成ります」。「―一雨来そうだ」
⇒どうやら‐こうやら
どうやら‐こうやら‥カウ‥
ようやくのことで。かろうじて。どうにかこうにか。浮世風呂3「あれが気ままにして置いても、―覚えるから」
⇒どう‐やら
とう‐ゆ【灯油】
(kerosene)
①点灯用の油。ともしあぶら。
②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。
⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】
とう‐ゆ【桐油】
①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。
②桐油紙の略。
③桐油合羽の略。
⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】
⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】
⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】
とう‐ゆう【党友】タウイウ
①同じ党派のなかま。
②外部からその党派をたすける者。
どう‐ゆう【同友】‥イウ
志を同じくする友。
どう‐ゆう【同憂】‥イウ
憂いをともにすること。また、その人。「―の士」
どう‐ゆう【導誘】ダウイウ
みちびきいざなうこと。誘導。
とうゆうき【東遊記】‥イウ‥
紀行。橘南谿著。1784年(天明4)秋から2年間、京を出て江戸に至り、東海・東山・北陸を遍歴した間の佳話・異聞などを記録。前編5巻5冊は95年(寛政7)刊、後編5巻5冊は97年刊。→西遊記3
とう‐ゆう‐し【投融資】
投資と融資。
とうゆ‐うるし【桐油漆】
桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】
桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐がみ【桐油紙】
桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン
灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。
⇒とう‐ゆ【灯油】
とう‐ゆみ【唐弓】タウ‥
綿を打って柔らかくする道具。5尺余の木弓に鯨の弦を張ったもの。わたうちゆみ。日本永代蔵5「―といふ物はじめて作り出し」
とう‐よ【投与】
①投げ与えること。
②薬剤を与えること。
とうよ【東予】
愛媛県中部の旧市名。→西条1
とう‐よ【党与】タウ‥
なかま。くみ。徒党。折たく柴の記上「我が父もその―なり」
とう‐よう【灯用】
灯火に用いること。「―アルコール」
とう‐よう【当用】タウ‥
①さしあたっての用事。当面の需要。日葡辞書「タウヨウニタツ」
②さしあたって使用すること。
⇒とうよう‐かい【当用買い】
⇒とうよう‐かんじ【当用漢字】
⇒とうよう‐にっき【当用日記】
とう‐よう【東洋】‥ヤウ
①トルコ以東のアジア諸国の総称。特に、アジアの東部及び南部、すなわち日本・中国・インド・ミャンマー(ビルマ)・タイ・インドシナ・インドネシアなどの称。↔西洋。
②中国で、日本を指す称呼。
⇒とうよう‐いがく【東洋医学】
⇒とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】
⇒とうよう‐おり【東洋織】
⇒とうよう‐おんがく【東洋音楽】
⇒とうよう‐が【東洋画】
⇒とうよう‐がく【東洋学】
⇒とうよう‐く【東洋区】
⇒とうよう‐し【東洋紙】
⇒とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】
⇒とうよう‐だいがく【東洋大学】
⇒とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】
⇒とうよう‐だんつう【東洋緞通】
⇒とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】
とう‐よう【桃夭】タウエウ
[詩経周南、桃夭](「夭」は、若く美しいさま)嫁ぐ女性を桃の美しさにたとえていう語。よめいりどき。嫁期。
とう‐よう【盗用】タウ‥
ぬすんで使用すること。「デザイン―」
とう‐よう【陶窯】タウエウ
陶磁器を焼くかま。
とう‐よう【登用・登庸】
官職などに、人材を引きあげ用いること。「新人を―する」「―試験」
とう‐よう【蕩揺】タウエウ
ゆれ動くこと。ゆり動かすこと。
とう‐よう【糖葉】タウエフ
光合成で同化された炭水化物が、主としてブドウ糖や庶糖などの糖として堆積される葉。イネ科など単子葉植物の葉に多い。↔澱粉葉
どう‐よう【同様】‥ヤウ
同じさまであること。「ただ―の値段」「母―に親しんだ人」
どう‐よう【動揺】‥エウ
①動きゆらぐこと。ぐらつくこと。
②転じて、気持などが不安定になること。不安。「心の―を隠す」
③騒擾そうじょう。さわぎ。「政界の―」
どう‐よう【童幼】‥エウ
年少の者。おさないこども。
どう‐よう【童謡】‥エウ
①子供が作って口ずさむ歌、または詩。
②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。
㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。
⇒どうよう‐おどり【童謡踊】
とうよう‐いがく【東洋医学】‥ヤウ‥
東洋、特に中国の伝統的医学。→中国医学。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】‥ヤウ‥ヂヨ‥ヰン‥
私立大学の一つ。カナダ‐メソジスト教会の宣教師が1884年(明治17)に創設した東洋英和女学校を前身とし、1946年東洋英和女学院と改称。89年現大学。横浜市緑区。
⇒とう‐よう【東洋】
どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ
童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。
⇒どう‐よう【童謡】
とうよう‐おり【東洋織】‥ヤウ‥
①綿織物の一種。経緯たてよこともに木綿の太糸を用いた敷物用織物。
②絹綿交織まぜおり物。緯には綿糸を使い、経には二重の練絹糸を用いて紋様を織り出した布。袋物や鼻緒地とする。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐おんがく【東洋音楽】‥ヤウ‥
東洋、すなわち日本・中国・東南アジア・インド・西アジアなどのアジア諸民族間に行われる音楽の総称。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐が【東洋画】‥ヤウグワ
東洋、特に中国を中心に発達した絵画の総称。日本画も広い意味ではこれに含まれる。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐かい【当用買い】タウ‥カヒ
さしあたり使う分だけを買うこと。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐がく【東洋学】‥ヤウ‥
東洋について研究する学問。宣教師が現地の事情を本国に報告したことから、ヨーロッパに始まる。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐かんじ【当用漢字】タウ‥
現代国語を書き表すために、日常使用する漢字の範囲を定めたもので、国語審議会が決定・答申し、政府が訓令・告示をもって公布した1850字の漢字。1946年(昭和21)11月発表。その後、48年2月に当用漢字音訓表・当用漢字別表(いわゆる教育漢字)が、49年4月には当用漢字字体表が発表された。現在は常用漢字(1981年10月告示)がこれにかわる。→常用漢字。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐く【東洋区】‥ヤウ‥
動物地理学上の一区域。ボルネオ・フィリピン以西の東南アジア。ヒマラヤ山脈以南のインドからインドシナ、長江以南のユーラシア大陸を含む。ヒヨケザル類・テナガザル・メガネザル・ツパイなどの霊長類、マメジカ・コノハドリの類を産する。→動物地理区(図)。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐し【東洋紙】‥ヤウ‥
三椏みつまた繊維を原料とし、溜漉ためずき法による厚手の強靱な和紙。福岡県のほか高知・岐阜・福井などに産し、主に包み紙に使用。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】‥ヤウ‥イウタウ
大井憲太郎らが中心となって1892年(明治25)組織した政党。民権の拡張とともに強硬外交を唱える。翌年解散。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐だいがく【東洋大学】‥ヤウ‥
私立大学の一つ。前身は1887年(明治20)井上円了が創設した哲学館。1906年東洋大学と改称。49年新制大学。本部は東京都文京区。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】‥ヤウ‥グワイ‥
朝鮮における植民地的農業経営のために1908年に設立された日本の国策会社。土地買収・地主的農業経営を行い、のち中国東北部・南洋などにも進出。45年解体。東拓。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐だんつう【東洋緞通】‥ヤウ‥
トルコ・ペルシア・インド・中国および日本で製出する緞通の総称。主として手工業により、色の調和、模様の高尚優美を特徴とする。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐にっき【当用日記】タウ‥
さしあたっての用事を記す日記。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】‥ヤウ‥
東洋学関係の図書館・研究機関。1917年(大正6)に岩崎久弥がG.E.モリソンから購入した蔵書を中心としてモリソン文庫を設立。24年東洋文庫と改称。和漢洋の東洋学文献を収集し、また、和書の貴重書を含む岩崎文庫などを加える。第二次大戦後は国立国会図書館支部。東京都文京区。
⇒とう‐よう【東洋】
とう‐よく【湯浴】タウ‥
①ゆあみ。入浴。
②化学実験・製薬などで、湯煎ゆせんを行うこと。また、その用器。普通、広い円孔のある蓋をもつ半球形の薄い銅製の鍋。ウォーター‐バス。
どう‐よく【胴欲】
(ドンヨク(貪欲)の転)
①非常に欲が深いこと。ひどくむさぼること。可笑記「不行儀、―深く」
②むごいこと。非道なこと。狂言、清水「そのやうな―な事するものか」
どう‐よろい【胴鎧】‥ヨロヒ
胴の部分にまとう鎧。
ドヴラートフ【Sergei D. Dovlatov】
ロシア(ソ連)の小説家。父はユダヤ人、母はアルメニア人。レニングラードに育ち、1978年アメリカ合衆国に亡命。ユーモアとアイロニーに満ちた語り口を身上とする。「わが家の人々」「かばん」など。(1941〜1990)
とうらい
拳けんの用語で、十のこと。浄瑠璃、冥途飛脚「拳の手品の手もたゆく、ろませ、さい、―、さんな」
とう‐らい【当来】タウ‥
①当然に来るべきこと。あたりまえ。
②まさに来るべき世。未来。来世。今昔物語集4「聖人は必ず―に成仏し給はむとす」
⇒とうらい‐どうし【当来導師】
⇒とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】
とう‐らい【到来】タウ‥
①こちらへやって来ること。機運などの向いてくること。徒然草「我等が生死しょうじの―ただ今にもやあらん」。「時節―」
②他から贈物の届くこと。また、その物。
⇒とうらい‐ちょう【到来帳】
⇒とうらい‐もの【到来物】
とうらい‐さんな【唐来参和】タウ‥ワ
(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名)江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良よものあからの門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき」など。(1744〜1810)
→文献資料[莫切自根金生木]
とうらい‐ちょう【到来帳】タウ‥チヤウ
(→)野帳のちょう2に同じ。
⇒とう‐らい【到来】
とうらい‐どうし【当来導師】タウ‥ダウ‥
来るべき世に出現する導師、すなわち56億7000万年を経た後、この世界に出現し、成道して衆生を化導するという弥勒みろく菩薩。
⇒とう‐らい【当来】
とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】タウ‥
来るべき世で、弥勒菩薩に会って仏道を成ずること。太平記3「今生の逆罪を翻して―とや成らん」
⇒とう‐らい【当来】
とうらい‐もの【到来物】タウ‥
他から贈って来たもの。もらいもの。いただきもの。
⇒とう‐らい【到来】
とう‐らく【当落】タウ‥
当選と落選。「―が決まる」
とう‐らく【頭絡】
牛・馬・羊などの移動・運動・調教・使役の時に用いる綱・皮などの繋縛用具。
とう‐らく【騰落】
物価の高くなることと安くなること。騰貴と下落。
どう‐らく【道楽】ダウ‥
(道を解して自ら楽しむ意から)
①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」
②ものずき。好事こうず。
③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」
⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】
⇒どうらく‐もの【道楽者】
どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥
身持ちのよくない息子。放蕩息子。
⇒どう‐らく【道楽】
どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥
①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。
②なまけもの。
⇒どう‐らく【道楽】
とうら‐ご【俵子】
(西日本で)海鼠なまこ。特に正月には初俵という。たわらご。
とう‐らん【冬卵】
ワムシ・ミジンコなどや扁形動物のある種で、秋の終りに産む大形の卵。耐久卵。ふゆらん。↔夏卵
とう‐らん【闘乱】
争乱。戦乱。源平盛衰記9「たとひ合戦―の中なりとも」
どう‐らん【胴乱】
①革または羅紗ラシャ布などで作った方形の袋。薬・印・煙草・銭などを入れて腰に下げる。もとは銃丸を入れる袋だったという。銃卵。筒卵。佩嚢はいのう。
胴乱
どう‐やら
〔副〕
①ようようのことで。なんとか。どうにか。「―暮しが成り立つ」
②何となく。どことなく。浮世風呂4「私共も―洗ひたう成ります」。「―一雨来そうだ」
⇒どうやら‐こうやら
どうやら‐こうやら‥カウ‥
ようやくのことで。かろうじて。どうにかこうにか。浮世風呂3「あれが気ままにして置いても、―覚えるから」
⇒どう‐やら
とう‐ゆ【灯油】
(kerosene)
①点灯用の油。ともしあぶら。
②原油を蒸留しセ氏150〜280度で留出する留分りゅうぶん。古くは灯火用とし、暖房用燃料・ディーゼル発動機燃料・ジェット機関燃料・機械洗浄などに用いる。ケロシン。
⇒とうゆ‐きかん【灯油機関】
とう‐ゆ【桐油】
①アブラギリの種子を圧搾して得る乾性油。古くから灯火に用いられた。油紙用またペイント・ワニスの製造原料とするが、食用には不可。きりあぶら。
②桐油紙の略。
③桐油合羽の略。
⇒とうゆ‐うるし【桐油漆】
⇒とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】
⇒とうゆ‐がみ【桐油紙】
とう‐ゆう【党友】タウイウ
①同じ党派のなかま。
②外部からその党派をたすける者。
どう‐ゆう【同友】‥イウ
志を同じくする友。
どう‐ゆう【同憂】‥イウ
憂いをともにすること。また、その人。「―の士」
どう‐ゆう【導誘】ダウイウ
みちびきいざなうこと。誘導。
とうゆうき【東遊記】‥イウ‥
紀行。橘南谿著。1784年(天明4)秋から2年間、京を出て江戸に至り、東海・東山・北陸を遍歴した間の佳話・異聞などを記録。前編5巻5冊は95年(寛政7)刊、後編5巻5冊は97年刊。→西遊記3
とう‐ゆう‐し【投融資】
投資と融資。
とうゆ‐うるし【桐油漆】
桐油に滑石・密陀僧みつだそうなどを混ぜ、顔料を加えて製した塗料。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐ガッパ【桐油合羽】
桐油紙で製した合羽。多く人足や小者などが用いる。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐がみ【桐油紙】
桐油をひいた紙。もと美濃紙を用いたが、現時は多く洋紙に荏油えのあぶらをひいて製する。よく湿気・雨などを防ぐので桐油合羽・包み紙に用いる。合羽紙。
⇒とう‐ゆ【桐油】
とうゆ‐きかん【灯油機関】‥クワン
灯油を加熱気化し、これを点火爆発して動力を発生させる内燃機関。主に小馬力の漁船または農業機械に用いる。
⇒とう‐ゆ【灯油】
とう‐ゆみ【唐弓】タウ‥
綿を打って柔らかくする道具。5尺余の木弓に鯨の弦を張ったもの。わたうちゆみ。日本永代蔵5「―といふ物はじめて作り出し」
とう‐よ【投与】
①投げ与えること。
②薬剤を与えること。
とうよ【東予】
愛媛県中部の旧市名。→西条1
とう‐よ【党与】タウ‥
なかま。くみ。徒党。折たく柴の記上「我が父もその―なり」
とう‐よう【灯用】
灯火に用いること。「―アルコール」
とう‐よう【当用】タウ‥
①さしあたっての用事。当面の需要。日葡辞書「タウヨウニタツ」
②さしあたって使用すること。
⇒とうよう‐かい【当用買い】
⇒とうよう‐かんじ【当用漢字】
⇒とうよう‐にっき【当用日記】
とう‐よう【東洋】‥ヤウ
①トルコ以東のアジア諸国の総称。特に、アジアの東部及び南部、すなわち日本・中国・インド・ミャンマー(ビルマ)・タイ・インドシナ・インドネシアなどの称。↔西洋。
②中国で、日本を指す称呼。
⇒とうよう‐いがく【東洋医学】
⇒とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】
⇒とうよう‐おり【東洋織】
⇒とうよう‐おんがく【東洋音楽】
⇒とうよう‐が【東洋画】
⇒とうよう‐がく【東洋学】
⇒とうよう‐く【東洋区】
⇒とうよう‐し【東洋紙】
⇒とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】
⇒とうよう‐だいがく【東洋大学】
⇒とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】
⇒とうよう‐だんつう【東洋緞通】
⇒とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】
とう‐よう【桃夭】タウエウ
[詩経周南、桃夭](「夭」は、若く美しいさま)嫁ぐ女性を桃の美しさにたとえていう語。よめいりどき。嫁期。
とう‐よう【盗用】タウ‥
ぬすんで使用すること。「デザイン―」
とう‐よう【陶窯】タウエウ
陶磁器を焼くかま。
とう‐よう【登用・登庸】
官職などに、人材を引きあげ用いること。「新人を―する」「―試験」
とう‐よう【蕩揺】タウエウ
ゆれ動くこと。ゆり動かすこと。
とう‐よう【糖葉】タウエフ
光合成で同化された炭水化物が、主としてブドウ糖や庶糖などの糖として堆積される葉。イネ科など単子葉植物の葉に多い。↔澱粉葉
どう‐よう【同様】‥ヤウ
同じさまであること。「ただ―の値段」「母―に親しんだ人」
どう‐よう【動揺】‥エウ
①動きゆらぐこと。ぐらつくこと。
②転じて、気持などが不安定になること。不安。「心の―を隠す」
③騒擾そうじょう。さわぎ。「政界の―」
どう‐よう【童幼】‥エウ
年少の者。おさないこども。
どう‐よう【童謡】‥エウ
①子供が作って口ずさむ歌、または詩。
②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。
㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。
⇒どうよう‐おどり【童謡踊】
とうよう‐いがく【東洋医学】‥ヤウ‥
東洋、特に中国の伝統的医学。→中国医学。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐えいわ‐じょがくいん‐だいがく【東洋英和女学院大学】‥ヤウ‥ヂヨ‥ヰン‥
私立大学の一つ。カナダ‐メソジスト教会の宣教師が1884年(明治17)に創設した東洋英和女学校を前身とし、1946年東洋英和女学院と改称。89年現大学。横浜市緑区。
⇒とう‐よう【東洋】
どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ
童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。
⇒どう‐よう【童謡】
とうよう‐おり【東洋織】‥ヤウ‥
①綿織物の一種。経緯たてよこともに木綿の太糸を用いた敷物用織物。
②絹綿交織まぜおり物。緯には綿糸を使い、経には二重の練絹糸を用いて紋様を織り出した布。袋物や鼻緒地とする。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐おんがく【東洋音楽】‥ヤウ‥
東洋、すなわち日本・中国・東南アジア・インド・西アジアなどのアジア諸民族間に行われる音楽の総称。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐が【東洋画】‥ヤウグワ
東洋、特に中国を中心に発達した絵画の総称。日本画も広い意味ではこれに含まれる。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐かい【当用買い】タウ‥カヒ
さしあたり使う分だけを買うこと。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐がく【東洋学】‥ヤウ‥
東洋について研究する学問。宣教師が現地の事情を本国に報告したことから、ヨーロッパに始まる。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐かんじ【当用漢字】タウ‥
現代国語を書き表すために、日常使用する漢字の範囲を定めたもので、国語審議会が決定・答申し、政府が訓令・告示をもって公布した1850字の漢字。1946年(昭和21)11月発表。その後、48年2月に当用漢字音訓表・当用漢字別表(いわゆる教育漢字)が、49年4月には当用漢字字体表が発表された。現在は常用漢字(1981年10月告示)がこれにかわる。→常用漢字。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐く【東洋区】‥ヤウ‥
動物地理学上の一区域。ボルネオ・フィリピン以西の東南アジア。ヒマラヤ山脈以南のインドからインドシナ、長江以南のユーラシア大陸を含む。ヒヨケザル類・テナガザル・メガネザル・ツパイなどの霊長類、マメジカ・コノハドリの類を産する。→動物地理区(図)。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐し【東洋紙】‥ヤウ‥
三椏みつまた繊維を原料とし、溜漉ためずき法による厚手の強靱な和紙。福岡県のほか高知・岐阜・福井などに産し、主に包み紙に使用。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐じゆうとう【東洋自由党】‥ヤウ‥イウタウ
大井憲太郎らが中心となって1892年(明治25)組織した政党。民権の拡張とともに強硬外交を唱える。翌年解散。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐だいがく【東洋大学】‥ヤウ‥
私立大学の一つ。前身は1887年(明治20)井上円了が創設した哲学館。1906年東洋大学と改称。49年新制大学。本部は東京都文京区。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐たくしょく‐かぶしきがいしゃ【東洋拓殖株式会社】‥ヤウ‥グワイ‥
朝鮮における植民地的農業経営のために1908年に設立された日本の国策会社。土地買収・地主的農業経営を行い、のち中国東北部・南洋などにも進出。45年解体。東拓。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐だんつう【東洋緞通】‥ヤウ‥
トルコ・ペルシア・インド・中国および日本で製出する緞通の総称。主として手工業により、色の調和、模様の高尚優美を特徴とする。
⇒とう‐よう【東洋】
とうよう‐にっき【当用日記】タウ‥
さしあたっての用事を記す日記。
⇒とう‐よう【当用】
とうよう‐ぶんこ【東洋文庫】‥ヤウ‥
東洋学関係の図書館・研究機関。1917年(大正6)に岩崎久弥がG.E.モリソンから購入した蔵書を中心としてモリソン文庫を設立。24年東洋文庫と改称。和漢洋の東洋学文献を収集し、また、和書の貴重書を含む岩崎文庫などを加える。第二次大戦後は国立国会図書館支部。東京都文京区。
⇒とう‐よう【東洋】
とう‐よく【湯浴】タウ‥
①ゆあみ。入浴。
②化学実験・製薬などで、湯煎ゆせんを行うこと。また、その用器。普通、広い円孔のある蓋をもつ半球形の薄い銅製の鍋。ウォーター‐バス。
どう‐よく【胴欲】
(ドンヨク(貪欲)の転)
①非常に欲が深いこと。ひどくむさぼること。可笑記「不行儀、―深く」
②むごいこと。非道なこと。狂言、清水「そのやうな―な事するものか」
どう‐よろい【胴鎧】‥ヨロヒ
胴の部分にまとう鎧。
ドヴラートフ【Sergei D. Dovlatov】
ロシア(ソ連)の小説家。父はユダヤ人、母はアルメニア人。レニングラードに育ち、1978年アメリカ合衆国に亡命。ユーモアとアイロニーに満ちた語り口を身上とする。「わが家の人々」「かばん」など。(1941〜1990)
とうらい
拳けんの用語で、十のこと。浄瑠璃、冥途飛脚「拳の手品の手もたゆく、ろませ、さい、―、さんな」
とう‐らい【当来】タウ‥
①当然に来るべきこと。あたりまえ。
②まさに来るべき世。未来。来世。今昔物語集4「聖人は必ず―に成仏し給はむとす」
⇒とうらい‐どうし【当来導師】
⇒とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】
とう‐らい【到来】タウ‥
①こちらへやって来ること。機運などの向いてくること。徒然草「我等が生死しょうじの―ただ今にもやあらん」。「時節―」
②他から贈物の届くこと。また、その物。
⇒とうらい‐ちょう【到来帳】
⇒とうらい‐もの【到来物】
とうらい‐さんな【唐来参和】タウ‥ワ
(名は三和とも書く。拳けんで数を表す語をもじった名)江戸後期の狂歌師、洒落本・黄表紙作者。加藤氏。通称、和泉屋源蔵。武士の出で、後に町人となり、本所松井町の娼家和泉屋に入婿。狂歌は四方赤良よものあからの門。洒落本「和唐珍解」、黄表紙「莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき」など。(1744〜1810)
→文献資料[莫切自根金生木]
とうらい‐ちょう【到来帳】タウ‥チヤウ
(→)野帳のちょう2に同じ。
⇒とう‐らい【到来】
とうらい‐どうし【当来導師】タウ‥ダウ‥
来るべき世に出現する導師、すなわち56億7000万年を経た後、この世界に出現し、成道して衆生を化導するという弥勒みろく菩薩。
⇒とう‐らい【当来】
とうらい‐の‐ちぐ【当来の値遇】タウ‥
来るべき世で、弥勒菩薩に会って仏道を成ずること。太平記3「今生の逆罪を翻して―とや成らん」
⇒とう‐らい【当来】
とうらい‐もの【到来物】タウ‥
他から贈って来たもの。もらいもの。いただきもの。
⇒とう‐らい【到来】
とう‐らく【当落】タウ‥
当選と落選。「―が決まる」
とう‐らく【頭絡】
牛・馬・羊などの移動・運動・調教・使役の時に用いる綱・皮などの繋縛用具。
とう‐らく【騰落】
物価の高くなることと安くなること。騰貴と下落。
どう‐らく【道楽】ダウ‥
(道を解して自ら楽しむ意から)
①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」
②ものずき。好事こうず。
③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」
⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】
⇒どうらく‐もの【道楽者】
どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥
身持ちのよくない息子。放蕩息子。
⇒どう‐らく【道楽】
どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥
①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。
②なまけもの。
⇒どう‐らく【道楽】
とうら‐ご【俵子】
(西日本で)海鼠なまこ。特に正月には初俵という。たわらご。
とう‐らん【冬卵】
ワムシ・ミジンコなどや扁形動物のある種で、秋の終りに産む大形の卵。耐久卵。ふゆらん。↔夏卵
とう‐らん【闘乱】
争乱。戦乱。源平盛衰記9「たとひ合戦―の中なりとも」
どう‐らん【胴乱】
①革または羅紗ラシャ布などで作った方形の袋。薬・印・煙草・銭などを入れて腰に下げる。もとは銃丸を入れる袋だったという。銃卵。筒卵。佩嚢はいのう。
胴乱
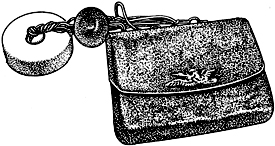 ②植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具。
③菓子の名。「ごまどうらん」の略。
どう‐らん【動乱】
世の中の騒ぎみだれること。騒乱。転じて、戦乱。太平記12「国々の―更にやむ時無し」。「―が起こる」
どう‐らん【銅藍】
硫化銅から成る鉱物。六方晶系の板状・鱗状結晶。濃藍色。銅の鉱石で、銅鉱床の酸化帯中などに見出される。コベライト。コベリン。
とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥
卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。
とう‐り【東籬】
東の方にあるまがき。
⇒とうり‐よきょう【東籬余興】
とう‐り【党利】タウ‥
自分の所属する政党・党派の利益。
⇒とうり‐とうりゃく【党利党略】
とう‐り【凍梨】
霜で凍った梨。また、しみの出た老人の膚はだにたとえていう。
とう‐り【桃李】タウ‥
①桃ももと李すもも。
②[劉禹錫、詩「満城桃李春官に属す」]試験官の採用した門下生。また、自分の推挙した人材。自分の取り立てた門人。
⇒桃李言わざれども下自ずから蹊を成す
⇒桃李の粧
⇒桃李門に満つ
とう‐り【統理】
統すべおさめること。
どう‐り【道理】ダウ‥
①物事のそうあるべきすじみち。ことわり。源氏物語帚木「世の―を思ひとりて」。「そんなことが許される―がない」
②人の行うべき正しい道。道義。「―にはずれた行為」
⇒どうり‐ぜめ【道理責め】
⇒どうり‐づめ【道理詰め】
⇒どうり‐で【道理で】
⇒どうり‐はずれ【道理外れ】
⇒道理を詰む
⇒道理を破る法はあれども法を破る道理なし
②植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具。
③菓子の名。「ごまどうらん」の略。
どう‐らん【動乱】
世の中の騒ぎみだれること。騒乱。転じて、戦乱。太平記12「国々の―更にやむ時無し」。「―が起こる」
どう‐らん【銅藍】
硫化銅から成る鉱物。六方晶系の板状・鱗状結晶。濃藍色。銅の鉱石で、銅鉱床の酸化帯中などに見出される。コベライト。コベリン。
とうらん‐けい【倒卵形】タウ‥
卵のやや尖った方を下にした形。植物の葉では、先端が円く下端がやや細くなったもの。
とう‐り【東籬】
東の方にあるまがき。
⇒とうり‐よきょう【東籬余興】
とう‐り【党利】タウ‥
自分の所属する政党・党派の利益。
⇒とうり‐とうりゃく【党利党略】
とう‐り【凍梨】
霜で凍った梨。また、しみの出た老人の膚はだにたとえていう。
とう‐り【桃李】タウ‥
①桃ももと李すもも。
②[劉禹錫、詩「満城桃李春官に属す」]試験官の採用した門下生。また、自分の推挙した人材。自分の取り立てた門人。
⇒桃李言わざれども下自ずから蹊を成す
⇒桃李の粧
⇒桃李門に満つ
とう‐り【統理】
統すべおさめること。
どう‐り【道理】ダウ‥
①物事のそうあるべきすじみち。ことわり。源氏物語帚木「世の―を思ひとりて」。「そんなことが許される―がない」
②人の行うべき正しい道。道義。「―にはずれた行為」
⇒どうり‐ぜめ【道理責め】
⇒どうり‐づめ【道理詰め】
⇒どうり‐で【道理で】
⇒どうり‐はずれ【道理外れ】
⇒道理を詰む
⇒道理を破る法はあれども法を破る道理なし
広辞苑 ページ 13969 での【○どうも言われぬ】単語。