複数辞典一括検索+![]()
![]()
とき【時】🔗⭐🔉
とき【時】
①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。
②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」
時
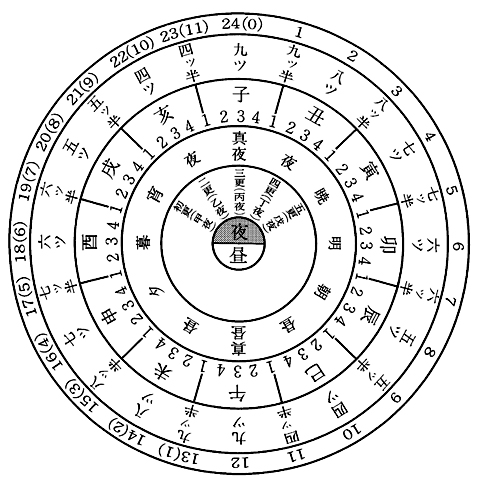 ③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
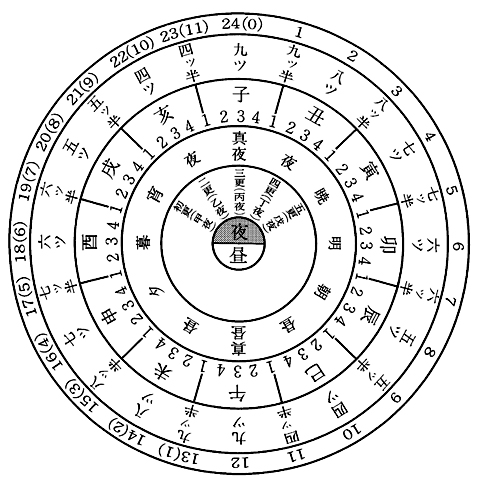 ③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
広辞苑 ページ 14032 での【時】単語。