複数辞典一括検索+![]()
![]()
じ【時】🔗⭐🔉
じ【時】
①ころ。おり。特定のとき。源氏物語夕霧「初夜の―果てむ程に」。「着水―のけが」
②1時間。また、時刻を示す語。「毎―30キロ」
じ‐い【時衣】🔗⭐🔉
じ‐い【時衣】
時節に着る衣服。時服。
○時雨の化じうのか🔗⭐🔉
○時雨の化じうのか
[孟子尽心上]仁君の教化を時雨が草木を潤すのにたとえていう語。
⇒じ‐う【時雨】
し‐うん【紫雲】
紫色の雲。めでたい雲。念仏行者の臨終のとき、仏がこの雲に乗って来迎らいごうするという。
じ‐うん【自運】
書道で、書く人の自由に筆を運ぶこと。また、そうして書いた書。↔臨書
じうん【似雲】
江戸中期の歌僧。初め如雲と称。安芸の人。武者小路実陰の門。西行に私淑し、諸国を行脚。著「磯の浪」、家集「年並草」など。(1673〜1753)
じ‐うん【時運】
時のまわりあわせ。時の運命。「―に恵まれる」
じうん【慈雲】
江戸中期の真言宗の僧。諱いみなは飲光おんこう。号は葛城山人・百不知童子。大坂の人。正法律を提唱し、悉曇しったん学を研究。また、雲伝神道を創唱。著「梵学津梁」「南海寄帰伝解纜鈔」「十善法語」など。(1718〜1804)
しうんえい【紫雲英】
〔植〕レンゲソウの漢名。
し‐うんてん【試運転】
乗物や機械などが完成した際、一般の使用前に運転状態を試験すること。「原子炉の―」
し‐うんどう【視運動】
地球上から見た諸天体の見かけの空間運動。天体の天球に対する運動から日周運動を除いたもの。
し‐え【四衛】‥ヱ
左右の衛士府えじふおよび左右の兵衛府ひょうえふの総称。
し‐え【紫衣】
(シイとも)紫色の僧衣。日本では1249年(建長1)以降、天皇が高僧に下賜した。紫袈裟。「―事件」
し‐え【緇衣】
(シイとも)
①黒色の衣。墨染めの衣。
②転じて、僧。
シェア【share】
①株式。
②共有すること。分かち合うこと。「ルーム‐―」
③マーケット‐シェアの略。
⇒シェア‐クロッパー【share cropper】
シェア‐クロッパー【share cropper】
分益小作農民。特に南北戦争後のアメリカ南部において、苛酷な小作条件と前借り制度によって隷属的な立場に置かれた小作人。第二次大戦期まで南部経済の中心を担う。
⇒シェア【share】
シェアリング【sharing】
分かち合うこと。共有すること。「ワーク‐―」
し‐えい【四裔】
(「裔」は衣のすその意)国の四方のはて。
し‐えい【市営】
地方自治団体である市の経営。「―バス」
し‐えい【私営】
個人の経営。
⇒しえい‐でん【私営田】
じ‐えい【自営】
独立して自ら事業を営むこと。
⇒じえい‐ぎょう【自営業】
じ‐えい【自衛】‥ヱイ
自力で自分を防衛すること。「―団」
⇒じえい‐かん【自衛官】
⇒じえい‐かん【自衛艦】
⇒じえい‐かんたい【自衛艦隊】
⇒じえい‐けん【自衛権】
⇒じえい‐たい【自衛隊】
じ‐えい【侍衛】‥ヱイ
貴人のそば近く仕えて護衛すること。
シエイエス【Emmanuel Joseph Sieyès】
フランスの政治家。初め聖職者。1789年「第三身分とは何か」を書き、ついで大革命の際、三部会・国民議会で活動。のち99年ナポレオンと提携、第2統領となる。アベ=シエイエス。(1748〜1836)
じえい‐かん【自衛官】‥ヱイクワン
防衛省の職員(隊員)のうち、陸上・海上・航空の各自衛隊などに勤務する者。制服を着用し、指定場所に居住する義務を負う。「女性―」「予備―」
⇒じ‐えい【自衛】
じえい‐かん【自衛艦】‥ヱイ‥
海上自衛隊の艦艇。護衛艦・潜水艦・掃海艦艇・哨戒艦艇などがある。
⇒じ‐えい【自衛】
じえい‐かんたい【自衛艦隊】‥ヱイ‥
海上自衛隊の主力実戦部隊。自衛艦隊司令部および護衛艦隊・航空集団・潜水艦隊・掃海隊群その他の直轄部隊から成る。
⇒じ‐えい【自衛】
じえい‐ぎょう【自営業】‥ゲフ
自ら事業を営んでいること。また、自ら経営する事業。
⇒じ‐えい【自営】
じえい‐けん【自衛権】‥ヱイ‥
国際法上、国家が自国または自国民に対する急迫不正の侵害を除去するため、やむを得ず行う防衛の権利。
⇒じ‐えい【自衛】
じえい‐たい【自衛隊】‥ヱイ‥
日本の安全を保つための、直接および間接の侵略に対する防衛組織。内閣総理大臣が最高指揮権を有し、防衛省が管理・運営する。陸上・海上・航空の各自衛隊から成る。1954年(昭和29)防衛庁設置法により、保安隊(警察予備隊の後身)・警備隊(海上警備隊の後身)を改組したもの。
インド洋へ向け出港する自衛艦(佐世保 2001年11月)
提供:毎日新聞社
 警察予備隊・保安隊・自衛隊
提供:NHK
⇒じ‐えい【自衛】
しえい‐でん【私営田】
奈良・平安時代、荒廃地・空閑地などを利用し、個人的に開発・経営した農場。土豪が直接経営するのが一般。↔公営田くえいでん
⇒し‐えい【私営】
シェイプ【shape】
⇒シェープ
ジェヴォンズ【William Stanley Jevons】
イギリスの経済学者。メンガー・ワルラスらと並んで限界効用理論を提唱。著「経済学の理論」「石炭問題」など。(1835〜1882)
ジェー【J・j】
①アルファベットの10番目の文字。
②〔理〕ジュール(仕事・エネルギーの単位)の記号(J)。
ジェー‐アール【JR】
(Japan Railway)国鉄が1987年に分割・民営化して新設した旅客鉄道会社6社と貨物鉄道1社の統一的略称。それぞれの会社はJR東海・JR西日本などと称する。→日本国有鉄道
ジェー‐エー【JA】
(Japan Agricultural cooperatives)農協の新しい呼称。1991年の全国農協大会で決まる。
ジェー‐オー‐シー【JOC】
(Japan Olympic Committee)日本オリンピック委員会の略称。
シェーカー【shaker】
カクテルを作るとき洋酒・氷などを入れて振り、混合したり素早く冷やしたりするための金属製の器具。攪拌器。
ジェー‐カーブ‐こうか【Jカーブ効果】‥カウクワ
〔経〕為替レートの変化により貿易収支を均衡させる効果がすぐには現れない現象。貿易収支の黒字による円の上昇(円高)がかえって貿易黒字を拡大させたのち、やがて黒字縮小に向かうのはその例。
シェーク【shake】
①小刻みに振ること。揺り動かすこと。
②カクテルやドレッシングを容器に入れて振りまぜること。
③材料を振りまぜて作った飲み物。特に、アイス‐クリームを材料とするものをいう。
⇒シェーク‐ハンド【shake-hands】
シェークスピア【William Shakespeare】
イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。ストラトフォード‐アポン‐エーヴォンの生れ。青年時代にロンドンに出て、初め俳優、のち座付作者として約37編の戯曲を創作。四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」をはじめ、史劇「リチャード三世」「ヘンリー四世」、悲劇「ロミオとジュリエット」「ジュリアス=シーザー」、喜劇「真夏の夜の夢」「ヴェニスの商人」、ロマンス劇「テンペスト」、そのほか詩集「ソネット集」などがある。沙翁。(1564〜1616)
シェーク‐ハンド【shake-hands】
(握手の意)シェークハンド‐グリップ(shake-hands grip)の略。卓球などで、握手するようなラケットの握り方。
⇒シェーク【shake】
シェーグレン‐しょうこうぐん【シェーグレン症候群】‥シヤウ‥
(スウェーデンの眼科医シェーグレン(H. S. C. Sjögren1899〜1987)に因む)涙腺や唾液腺の分泌が減少し、乾燥性結膜炎、角膜炎、唾液腺の腫脹、多発性関節炎などをひき起こす全身疾患。中年の女性に多く、自己免疫疾患と考えられる。
ジェー‐ターン
(和製語J turn)地方から都会へ出た人が、故郷に近い地方都市で就職・定住すること。→ユー‐ターン→アイ‐ターン
シェード【shade】
①光をさえぎる具。日除ひよけ。日覆ひおおい。
②電灯・電気スタンドの笠。
シェーバー【shaver】
剃刀かみそり。特に、電気剃刀。
シェーパー【shaper】
(→)形削かたけずり盤。
シェービング【shaving】
髭ひげなどをそること。「―‐クリーム」
シェープ【shape】
形。形状。シェイプ。
⇒シェープ‐アップ【shape up】
シェーファー【Anthony Shaffer】
イギリスの劇作家。P.L.シェーファーとは双子。作「スルース」など。兄弟合作の小説がある。(1926〜2001)
シェーファー【Peter Levin Shaffer】
イギリスの劇作家。伝統的写実に新技法を採り入れ、笑劇・歴史劇などさまざまな分野にわたる。作「アマデウス」など。シャファー。(1926〜)。
シェープ‐アップ【shape up】
美容や健康のために運動や減食をして体形をととのえること。
⇒シェープ【shape】
ジェー‐ペグ【JPEG】
(joint photographic experts group)画像データ記録のための圧縮方式の一つ。また、その方式によるファイル形式。→エムペグ。
▷もともとはカラー静止画像の圧縮規格を定めたISOと国際電気通信連合標準化セクター(ITU)の合同組織の呼称。
シェーマ【Schema ドイツ】
図式。形式。
ジェームズ【James】
(英語の男子名。ラテン語のヤコブス、ドイツ語のヤーコプ、フランス語のジャックに当たる)イギリス王。
①(1世)スチュアート王朝の祖。スコットランド王としては6世。1603年イングランド王位を継承して大ブリテン島を同君連合のもとに置いた。王権神授説を唱え、英国国教会強硬派を支持、議会と衝突。(1566〜1625)
②(2世)カトリックを復興、専断的政治を行なったため、1688年名誉革命によって王位を追われ、フランスに亡命。(1633〜1701)
ジェームズ【Cyril Lionel Robert James】
トリニダード‐トバゴ出身の小説家・歴史家・政治評論家。イギリス・アメリカで活動。代表作「黒いジャコバン」。(1901〜1989)
ジェームズ【Henry James】
イギリスの小説家。アメリカ生れ。W.ジェームズの弟。心理主義文学の先駆。作「ある婦人の肖像」「ねじの回転」など。(1843〜1916)
ジェームズ【William James】
アメリカの哲学者・心理学者。パースとともにプラグマティズムの提唱者。「純粋経験」に基づく根本的経験論を主張。また、思考を生存競争の道具とみなす機能的心理学を展開した。著「宗教経験の諸相」「心理学原理」「プラグマティズム」など。(1842〜1910)
ジェームズ‐ボンド【James Bond】
「フレミング(I. Fleming)」参照。
シェーラー【Max Scheler】
ドイツの哲学者。現象学的立場からカント倫理学の形式主義に反対し、実質的価値倫理学を展開、晩年には哲学的人間学の樹立を試みた。著「倫理学における形式主義と実質的価値倫理学」「宇宙における人間の位置」など。(1874〜1928)
ジェー‐リーグ
(和製語J league)1993年に発足した日本初のプロ‐サッカー‐リーグ。正式名は社団法人日本プロ‐サッカー‐リーグ。
シェーレ【Schere ドイツ】
〔経〕(鋏はさみの意)独占化した産業部門と非独占部門との価格差が鋏を開いたような形に漸次増大する現象。特に工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。鋏状価格差。
シェーレ【Carl Wilhelm Scheele】
スウェーデンの化学者。塩素・酸素・フッ化水素・乳酸・蓚酸しゅうさん・酒石酸の発見など多くの業績がある。(1742〜1786)
ジェーン‐エア【Jane Eyre】
C.ブロンテの長編小説。1847年刊。孤児ジェーンが地主ロチェスターの家庭教師として住み込み、狂気の妻バーサの死後、彼と結ばれるまでを描く。男性中心の社会に抵抗したヒロインが共感を呼んだ。
シェーンベルク【Arnold Schönberg】
オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。1933年アメリカへ移住。作「月に憑かれたピエロ」「ワルシャワの生き残り」など。(1874〜1951)
し‐えき【四駅】
江戸時代、江戸の四隅にあって、五街道の出発点であった宿駅。千住せんじゅ(日光・奥州街道)・板橋(中山道)・品川(東海道)・内藤新宿(甲州街道)。四宿。
し‐えき【私益】
一個人の利益。私利。↔公益
し‐えき【使役】
①人を使って仕事(特に雑役)をさせること。他人にある行為をさせること。「―に駆り出される」
②(文法用語)他人に動作を行わせたり事態を引き起こさせたりすること。また、その意味を表す形式。日本語では使役の助動詞を動詞の未然形に付けて表す。
し‐えき【資益】
助け利すること。利益。
じ‐えき【自益】
自分の利益。個人の利益。
⇒じえき‐けん【自益権】
⇒じえき‐しんたく【自益信託】
じ‐えき【時疫】
流行病。はやりやまい。浮世草子、好色敗毒散「―をわづらひてみまかりぬ」
じ‐えき【滋液】
滋味のある液。甘味のある液。
じえき‐けん【自益権】
社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。
⇒じ‐えき【自益】
じえき‐しんたく【自益信託】
信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。
⇒じ‐えき【自益】
しえき‐ほう【市易法】‥ハフ
中国、北宋の王安石の新法の一つ。小商人を豪商の搾取から守るため主な都市に市易務を設置し、小商人の滞貨を買い上げ、あるいはこれを抵当に低利で資金を融通した。
シエシエ【謝謝】
(中国語)ありがとう。
しえ‐じけん【紫衣事件】
1627年(寛永4)将軍徳川家光の時、皇室から大徳寺・妙心寺の僧に賜った紫衣を、幕府が法規を楯に奪い、幕命に従わない妙心寺の単伝・東源、大徳寺の沢庵・玉室らを罰した事件。
ジェズイット【Jesuit】
イエズス会に所属する修道士。
シエスタ【siesta スペイン】
スペインなどで、昼食後にとる昼寝。
ジェスチャー【gesture】
(ゼスチュアとも)
①身振り。手振り。手真似。「―を交えた会話」
②思わせぶりな態度。誠実さに欠ける形ばかりの態度。みせかけ。「―ばかりでやる気がない」
シェストフ【Lev Shestov】
ロシアの哲学者。フランスに亡命。真理は理性を超えるものとし、存在の非合理的根源を追求。不安の哲学として第一次大戦後に迎えられた。著「ドストエフスキーとニーチェ(悲劇の哲学)」「キルケゴールと実存哲学」など。(1866〜1938)
しえた・ぐ【虐ぐ・冤ぐ】シヘタグ
(古くはシヘタクと清音)〔他下二〕
①人をむごく扱う。虐待する。しいたげる。徒然草「すべて人を苦しめものを―・ぐることいやしき民の志をも奪ふべからず」
②道理をまげて無実の罪に落とす。続日本紀5「制断理に合ひ、獄訟冤しえたくることなく」
③征服する。平家物語12「毎度に味方おひ落されて、敵を―・ぐるに及ばず」
ジエチル‐エーテル【diethyl ether】
(→)エチル‐エーテルに同じ。
し‐エチル‐なまり【四エチル鉛】
(→)テトラエチル鉛に同じ。
し‐えつ【私謁】
天子などに私事で謁見すること。
ジェッダ【Jedda】
サウジ‐アラビア西部、ヘジャズ地方の紅海に臨む港湾都市。イスラムの聖地メッカの外港。ジッダ。人口82万4千(1992)。
ジェット【jet】
①孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。
②素粒子物理学で、狭い立体角内に集中して、多数のハドロン群の発生する現象。また、そのハドロン群。
③〔天〕原始星やクエーサーなどから高速で噴出するジェット1状のガス流。
④ジェット機の略。
⇒ジェット‐エンジン【jet engine】
⇒ジェット‐き【ジェット機】
⇒ジェット‐きりゅう【ジェット気流】
⇒ジェット‐コースター
⇒ジェット‐ストリーム【jet stream】
⇒ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】
⇒ジェット‐フォイル【jetfoil】
⇒ジェット‐ポンプ
⇒ジェット‐ルート【jet route】
ジェット‐エンジン【jet engine】
空気を圧縮し、燃料を吹き込んで燃焼させ、排気を高速で噴出させてその反作用として推進力を得る航空用発動機。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐き【ジェット機】
ジェット‐エンジンを推進装置とする航空機。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐きりゅう【ジェット気流】‥リウ
中緯度の対流圏上部に吹く強い西風。風速は冬には毎秒80メートル以上に達する。ジェット‐ストリーム。→偏西風帯。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐コースター
(和製語jet coaster)遊園地などの遊戯設備で、上下左右に曲がりくねったレール上を急スピードで走る滑走車。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ストリーム【jet stream】
(→)ジェット気流に同じ。
ジェットストリーム
撮影:NASA/STScI
警察予備隊・保安隊・自衛隊
提供:NHK
⇒じ‐えい【自衛】
しえい‐でん【私営田】
奈良・平安時代、荒廃地・空閑地などを利用し、個人的に開発・経営した農場。土豪が直接経営するのが一般。↔公営田くえいでん
⇒し‐えい【私営】
シェイプ【shape】
⇒シェープ
ジェヴォンズ【William Stanley Jevons】
イギリスの経済学者。メンガー・ワルラスらと並んで限界効用理論を提唱。著「経済学の理論」「石炭問題」など。(1835〜1882)
ジェー【J・j】
①アルファベットの10番目の文字。
②〔理〕ジュール(仕事・エネルギーの単位)の記号(J)。
ジェー‐アール【JR】
(Japan Railway)国鉄が1987年に分割・民営化して新設した旅客鉄道会社6社と貨物鉄道1社の統一的略称。それぞれの会社はJR東海・JR西日本などと称する。→日本国有鉄道
ジェー‐エー【JA】
(Japan Agricultural cooperatives)農協の新しい呼称。1991年の全国農協大会で決まる。
ジェー‐オー‐シー【JOC】
(Japan Olympic Committee)日本オリンピック委員会の略称。
シェーカー【shaker】
カクテルを作るとき洋酒・氷などを入れて振り、混合したり素早く冷やしたりするための金属製の器具。攪拌器。
ジェー‐カーブ‐こうか【Jカーブ効果】‥カウクワ
〔経〕為替レートの変化により貿易収支を均衡させる効果がすぐには現れない現象。貿易収支の黒字による円の上昇(円高)がかえって貿易黒字を拡大させたのち、やがて黒字縮小に向かうのはその例。
シェーク【shake】
①小刻みに振ること。揺り動かすこと。
②カクテルやドレッシングを容器に入れて振りまぜること。
③材料を振りまぜて作った飲み物。特に、アイス‐クリームを材料とするものをいう。
⇒シェーク‐ハンド【shake-hands】
シェークスピア【William Shakespeare】
イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。ストラトフォード‐アポン‐エーヴォンの生れ。青年時代にロンドンに出て、初め俳優、のち座付作者として約37編の戯曲を創作。四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」をはじめ、史劇「リチャード三世」「ヘンリー四世」、悲劇「ロミオとジュリエット」「ジュリアス=シーザー」、喜劇「真夏の夜の夢」「ヴェニスの商人」、ロマンス劇「テンペスト」、そのほか詩集「ソネット集」などがある。沙翁。(1564〜1616)
シェーク‐ハンド【shake-hands】
(握手の意)シェークハンド‐グリップ(shake-hands grip)の略。卓球などで、握手するようなラケットの握り方。
⇒シェーク【shake】
シェーグレン‐しょうこうぐん【シェーグレン症候群】‥シヤウ‥
(スウェーデンの眼科医シェーグレン(H. S. C. Sjögren1899〜1987)に因む)涙腺や唾液腺の分泌が減少し、乾燥性結膜炎、角膜炎、唾液腺の腫脹、多発性関節炎などをひき起こす全身疾患。中年の女性に多く、自己免疫疾患と考えられる。
ジェー‐ターン
(和製語J turn)地方から都会へ出た人が、故郷に近い地方都市で就職・定住すること。→ユー‐ターン→アイ‐ターン
シェード【shade】
①光をさえぎる具。日除ひよけ。日覆ひおおい。
②電灯・電気スタンドの笠。
シェーバー【shaver】
剃刀かみそり。特に、電気剃刀。
シェーパー【shaper】
(→)形削かたけずり盤。
シェービング【shaving】
髭ひげなどをそること。「―‐クリーム」
シェープ【shape】
形。形状。シェイプ。
⇒シェープ‐アップ【shape up】
シェーファー【Anthony Shaffer】
イギリスの劇作家。P.L.シェーファーとは双子。作「スルース」など。兄弟合作の小説がある。(1926〜2001)
シェーファー【Peter Levin Shaffer】
イギリスの劇作家。伝統的写実に新技法を採り入れ、笑劇・歴史劇などさまざまな分野にわたる。作「アマデウス」など。シャファー。(1926〜)。
シェープ‐アップ【shape up】
美容や健康のために運動や減食をして体形をととのえること。
⇒シェープ【shape】
ジェー‐ペグ【JPEG】
(joint photographic experts group)画像データ記録のための圧縮方式の一つ。また、その方式によるファイル形式。→エムペグ。
▷もともとはカラー静止画像の圧縮規格を定めたISOと国際電気通信連合標準化セクター(ITU)の合同組織の呼称。
シェーマ【Schema ドイツ】
図式。形式。
ジェームズ【James】
(英語の男子名。ラテン語のヤコブス、ドイツ語のヤーコプ、フランス語のジャックに当たる)イギリス王。
①(1世)スチュアート王朝の祖。スコットランド王としては6世。1603年イングランド王位を継承して大ブリテン島を同君連合のもとに置いた。王権神授説を唱え、英国国教会強硬派を支持、議会と衝突。(1566〜1625)
②(2世)カトリックを復興、専断的政治を行なったため、1688年名誉革命によって王位を追われ、フランスに亡命。(1633〜1701)
ジェームズ【Cyril Lionel Robert James】
トリニダード‐トバゴ出身の小説家・歴史家・政治評論家。イギリス・アメリカで活動。代表作「黒いジャコバン」。(1901〜1989)
ジェームズ【Henry James】
イギリスの小説家。アメリカ生れ。W.ジェームズの弟。心理主義文学の先駆。作「ある婦人の肖像」「ねじの回転」など。(1843〜1916)
ジェームズ【William James】
アメリカの哲学者・心理学者。パースとともにプラグマティズムの提唱者。「純粋経験」に基づく根本的経験論を主張。また、思考を生存競争の道具とみなす機能的心理学を展開した。著「宗教経験の諸相」「心理学原理」「プラグマティズム」など。(1842〜1910)
ジェームズ‐ボンド【James Bond】
「フレミング(I. Fleming)」参照。
シェーラー【Max Scheler】
ドイツの哲学者。現象学的立場からカント倫理学の形式主義に反対し、実質的価値倫理学を展開、晩年には哲学的人間学の樹立を試みた。著「倫理学における形式主義と実質的価値倫理学」「宇宙における人間の位置」など。(1874〜1928)
ジェー‐リーグ
(和製語J league)1993年に発足した日本初のプロ‐サッカー‐リーグ。正式名は社団法人日本プロ‐サッカー‐リーグ。
シェーレ【Schere ドイツ】
〔経〕(鋏はさみの意)独占化した産業部門と非独占部門との価格差が鋏を開いたような形に漸次増大する現象。特に工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。鋏状価格差。
シェーレ【Carl Wilhelm Scheele】
スウェーデンの化学者。塩素・酸素・フッ化水素・乳酸・蓚酸しゅうさん・酒石酸の発見など多くの業績がある。(1742〜1786)
ジェーン‐エア【Jane Eyre】
C.ブロンテの長編小説。1847年刊。孤児ジェーンが地主ロチェスターの家庭教師として住み込み、狂気の妻バーサの死後、彼と結ばれるまでを描く。男性中心の社会に抵抗したヒロインが共感を呼んだ。
シェーンベルク【Arnold Schönberg】
オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。1933年アメリカへ移住。作「月に憑かれたピエロ」「ワルシャワの生き残り」など。(1874〜1951)
し‐えき【四駅】
江戸時代、江戸の四隅にあって、五街道の出発点であった宿駅。千住せんじゅ(日光・奥州街道)・板橋(中山道)・品川(東海道)・内藤新宿(甲州街道)。四宿。
し‐えき【私益】
一個人の利益。私利。↔公益
し‐えき【使役】
①人を使って仕事(特に雑役)をさせること。他人にある行為をさせること。「―に駆り出される」
②(文法用語)他人に動作を行わせたり事態を引き起こさせたりすること。また、その意味を表す形式。日本語では使役の助動詞を動詞の未然形に付けて表す。
し‐えき【資益】
助け利すること。利益。
じ‐えき【自益】
自分の利益。個人の利益。
⇒じえき‐けん【自益権】
⇒じえき‐しんたく【自益信託】
じ‐えき【時疫】
流行病。はやりやまい。浮世草子、好色敗毒散「―をわづらひてみまかりぬ」
じ‐えき【滋液】
滋味のある液。甘味のある液。
じえき‐けん【自益権】
社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。
⇒じ‐えき【自益】
じえき‐しんたく【自益信託】
信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。
⇒じ‐えき【自益】
しえき‐ほう【市易法】‥ハフ
中国、北宋の王安石の新法の一つ。小商人を豪商の搾取から守るため主な都市に市易務を設置し、小商人の滞貨を買い上げ、あるいはこれを抵当に低利で資金を融通した。
シエシエ【謝謝】
(中国語)ありがとう。
しえ‐じけん【紫衣事件】
1627年(寛永4)将軍徳川家光の時、皇室から大徳寺・妙心寺の僧に賜った紫衣を、幕府が法規を楯に奪い、幕命に従わない妙心寺の単伝・東源、大徳寺の沢庵・玉室らを罰した事件。
ジェズイット【Jesuit】
イエズス会に所属する修道士。
シエスタ【siesta スペイン】
スペインなどで、昼食後にとる昼寝。
ジェスチャー【gesture】
(ゼスチュアとも)
①身振り。手振り。手真似。「―を交えた会話」
②思わせぶりな態度。誠実さに欠ける形ばかりの態度。みせかけ。「―ばかりでやる気がない」
シェストフ【Lev Shestov】
ロシアの哲学者。フランスに亡命。真理は理性を超えるものとし、存在の非合理的根源を追求。不安の哲学として第一次大戦後に迎えられた。著「ドストエフスキーとニーチェ(悲劇の哲学)」「キルケゴールと実存哲学」など。(1866〜1938)
しえた・ぐ【虐ぐ・冤ぐ】シヘタグ
(古くはシヘタクと清音)〔他下二〕
①人をむごく扱う。虐待する。しいたげる。徒然草「すべて人を苦しめものを―・ぐることいやしき民の志をも奪ふべからず」
②道理をまげて無実の罪に落とす。続日本紀5「制断理に合ひ、獄訟冤しえたくることなく」
③征服する。平家物語12「毎度に味方おひ落されて、敵を―・ぐるに及ばず」
ジエチル‐エーテル【diethyl ether】
(→)エチル‐エーテルに同じ。
し‐エチル‐なまり【四エチル鉛】
(→)テトラエチル鉛に同じ。
し‐えつ【私謁】
天子などに私事で謁見すること。
ジェッダ【Jedda】
サウジ‐アラビア西部、ヘジャズ地方の紅海に臨む港湾都市。イスラムの聖地メッカの外港。ジッダ。人口82万4千(1992)。
ジェット【jet】
①孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。
②素粒子物理学で、狭い立体角内に集中して、多数のハドロン群の発生する現象。また、そのハドロン群。
③〔天〕原始星やクエーサーなどから高速で噴出するジェット1状のガス流。
④ジェット機の略。
⇒ジェット‐エンジン【jet engine】
⇒ジェット‐き【ジェット機】
⇒ジェット‐きりゅう【ジェット気流】
⇒ジェット‐コースター
⇒ジェット‐ストリーム【jet stream】
⇒ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】
⇒ジェット‐フォイル【jetfoil】
⇒ジェット‐ポンプ
⇒ジェット‐ルート【jet route】
ジェット‐エンジン【jet engine】
空気を圧縮し、燃料を吹き込んで燃焼させ、排気を高速で噴出させてその反作用として推進力を得る航空用発動機。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐き【ジェット機】
ジェット‐エンジンを推進装置とする航空機。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐きりゅう【ジェット気流】‥リウ
中緯度の対流圏上部に吹く強い西風。風速は冬には毎秒80メートル以上に達する。ジェット‐ストリーム。→偏西風帯。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐コースター
(和製語jet coaster)遊園地などの遊戯設備で、上下左右に曲がりくねったレール上を急スピードで走る滑走車。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ストリーム【jet stream】
(→)ジェット気流に同じ。
ジェットストリーム
撮影:NASA/STScI
 ⇒ジェット【jet】
ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】‥レウ
ジェット‐エンジンに使用する燃料。ガソリンと灯油を混合して製する。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐フォイル【jetfoil】
吸いこんだ海水を後方に噴射して推進力を得る水中翼船。翼は水中に全没し、時速80キロメートル以上の高速で航走する。商標名。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ポンプ
(jet pump)細い円錐形の筒口から高圧の蒸気・圧縮空気などを噴出させ、その勢いで他の流体を誘い出す形式のポンプ。噴射ポンプ。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ルート【jet route】
高高度(2万4000フィート以上)を飛行するジェット旅客機のために設定された航空路。
⇒ジェット【jet】
ジェトロ【JETRO】
(Japan External Trade Organization)海外市場の調査、日本商品の宣伝などを行う独立行政法人。正式には日本貿易振興機構。1954年日本海外貿易振興会として設立、58年日本貿易振興会に改組。98年アジア経済研究所と統合、2003年独立行政法人となり、現名称。
シエナ【Siena】
イタリア中部、トスカーナ地方の都市。ゴシック期・ルネサンス期の建築・美術品に富む。
⇒シエナ‐は【シエナ派】
シエナ‐は【シエナ派】
(Scuola Senese イタリア)中世末期からルネサンス期にかけて、シエナを中心に活動した画派。優雅で装飾的な画風が特色。ドゥッチオやマルティーニらが代表的画家。
⇒シエナ【Siena】
ジェニーヴァ【Geneva】
ジュネーヴの英語名。
シェニール‐いと【シェニール糸】
(シェニール(chenille フランス)は毛虫の意)ビロード状にけば立てた組糸。外見が毛虫に似る。装飾用あるいはカーペット・肩掛・襟巻の製織用。チンコール糸。毛虫糸。
シェニエ【André de Chénier】
フランスの詩人。母はギリシア人。フランス革命に参加、断頭台で処刑。詩は死後発表。作「悲歌」「牧歌」など。(1762〜1794)
ジェネラル【general】
⇒ゼネラル
ジェネリック‐いやくひん【ジェネリック医薬品】
(generic drug)先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。
ジェネレーション【generation】
世代。また、同世代の人々。ゼネレーション。
⇒ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】
ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】
世代間に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。
⇒ジェネレーション【generation】
ジェノア【Genoa】
ジェノヴァの英語名。
ジェノヴァ【Genova】
イタリア北西部、同名の湾に臨む都市。地中海最古の港の一つ。コロンブスの生地。ミラノ・トリノとともに「工業の三角形地帯」の一角をなす。人口60万3千(2004)。英語名ジェノア。
ジェノサイド【genocide】
(「ジェノ」は人びと、「サイド」は殺害の意)集団殺戮さつりく。
⇒ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】
ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】‥デウ‥
正式には「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」。第二次大戦の経験から、国民・人種・民族ならびに宗教上の集団を迫害し殺害する行為を国際犯罪とし、各国協力のもとに防止・処罰しようというもので、1948年12月の国連総会で採択。
⇒ジェノサイド【genocide】
シェパード【shepherd】
(「羊飼い」の意)イヌの一品種。肩高約60センチメートルで、耳は立ち、全体にオオカミに似る。歴史は6000年前にさかのぼる。番犬・警察犬・軍用犬などとして有用。セパード。ジャーマン‐シェパード。アルサチアン。
シェフ【chef フランス】
(頭かしらの意)コック長。
ジェファソン【Thomas Jefferson】
アメリカ合衆国第3代大統領(1801〜1809)。1776年、独立宣言を起草。駐仏公使・初代国務長官・副大統領を歴任。大統領在任中にルイジアナを購入。晩年ヴァージニア大学総長。(1743〜1826)
シェフィールド【Sheffield】
イギリス、イングランド北部の都市。ヨークシャー地方南部に位置し、鉄鋼業のほか刃物製造が盛ん。人口53万(1996)。
シェフチェンコ【Taras G. Shevchenko】
ウクライナの国民詩人・画家。スラヴ民族の平等な団結を訴える政治結社に参加し、10年間の流刑を経験。詩によってウクライナの民族意識を鼓吹。詩集「吟遊詩人(コブザーリ)」など。(1814〜1861)
ジェフリー‐ビーン【Geoffrey Beene】
⇒ビーン
シェフレラ【Schefflera】
ウコギ科の観葉植物。常緑低木で光沢ある革質の掌状葉をつける。原産は南アジア。日本では鉢植とする。カポックと呼ぶことがあるが、パンヤ科のカポックとの誤認。フカノキ。
シェヘラザード【Shahrazād】
①「アラビアン‐ナイト」に、語り手として登場する女性。大臣の娘で、のち王妃。シャハラザード。
②リムスキー=コルサコフ作曲の交響組曲。1888年作曲。1に取材した標題音楽。シェエラザード。
リムスキー‐コルサコフ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】‥レウ
ジェット‐エンジンに使用する燃料。ガソリンと灯油を混合して製する。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐フォイル【jetfoil】
吸いこんだ海水を後方に噴射して推進力を得る水中翼船。翼は水中に全没し、時速80キロメートル以上の高速で航走する。商標名。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ポンプ
(jet pump)細い円錐形の筒口から高圧の蒸気・圧縮空気などを噴出させ、その勢いで他の流体を誘い出す形式のポンプ。噴射ポンプ。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ルート【jet route】
高高度(2万4000フィート以上)を飛行するジェット旅客機のために設定された航空路。
⇒ジェット【jet】
ジェトロ【JETRO】
(Japan External Trade Organization)海外市場の調査、日本商品の宣伝などを行う独立行政法人。正式には日本貿易振興機構。1954年日本海外貿易振興会として設立、58年日本貿易振興会に改組。98年アジア経済研究所と統合、2003年独立行政法人となり、現名称。
シエナ【Siena】
イタリア中部、トスカーナ地方の都市。ゴシック期・ルネサンス期の建築・美術品に富む。
⇒シエナ‐は【シエナ派】
シエナ‐は【シエナ派】
(Scuola Senese イタリア)中世末期からルネサンス期にかけて、シエナを中心に活動した画派。優雅で装飾的な画風が特色。ドゥッチオやマルティーニらが代表的画家。
⇒シエナ【Siena】
ジェニーヴァ【Geneva】
ジュネーヴの英語名。
シェニール‐いと【シェニール糸】
(シェニール(chenille フランス)は毛虫の意)ビロード状にけば立てた組糸。外見が毛虫に似る。装飾用あるいはカーペット・肩掛・襟巻の製織用。チンコール糸。毛虫糸。
シェニエ【André de Chénier】
フランスの詩人。母はギリシア人。フランス革命に参加、断頭台で処刑。詩は死後発表。作「悲歌」「牧歌」など。(1762〜1794)
ジェネラル【general】
⇒ゼネラル
ジェネリック‐いやくひん【ジェネリック医薬品】
(generic drug)先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。
ジェネレーション【generation】
世代。また、同世代の人々。ゼネレーション。
⇒ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】
ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】
世代間に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。
⇒ジェネレーション【generation】
ジェノア【Genoa】
ジェノヴァの英語名。
ジェノヴァ【Genova】
イタリア北西部、同名の湾に臨む都市。地中海最古の港の一つ。コロンブスの生地。ミラノ・トリノとともに「工業の三角形地帯」の一角をなす。人口60万3千(2004)。英語名ジェノア。
ジェノサイド【genocide】
(「ジェノ」は人びと、「サイド」は殺害の意)集団殺戮さつりく。
⇒ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】
ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】‥デウ‥
正式には「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」。第二次大戦の経験から、国民・人種・民族ならびに宗教上の集団を迫害し殺害する行為を国際犯罪とし、各国協力のもとに防止・処罰しようというもので、1948年12月の国連総会で採択。
⇒ジェノサイド【genocide】
シェパード【shepherd】
(「羊飼い」の意)イヌの一品種。肩高約60センチメートルで、耳は立ち、全体にオオカミに似る。歴史は6000年前にさかのぼる。番犬・警察犬・軍用犬などとして有用。セパード。ジャーマン‐シェパード。アルサチアン。
シェフ【chef フランス】
(頭かしらの意)コック長。
ジェファソン【Thomas Jefferson】
アメリカ合衆国第3代大統領(1801〜1809)。1776年、独立宣言を起草。駐仏公使・初代国務長官・副大統領を歴任。大統領在任中にルイジアナを購入。晩年ヴァージニア大学総長。(1743〜1826)
シェフィールド【Sheffield】
イギリス、イングランド北部の都市。ヨークシャー地方南部に位置し、鉄鋼業のほか刃物製造が盛ん。人口53万(1996)。
シェフチェンコ【Taras G. Shevchenko】
ウクライナの国民詩人・画家。スラヴ民族の平等な団結を訴える政治結社に参加し、10年間の流刑を経験。詩によってウクライナの民族意識を鼓吹。詩集「吟遊詩人(コブザーリ)」など。(1814〜1861)
ジェフリー‐ビーン【Geoffrey Beene】
⇒ビーン
シェフレラ【Schefflera】
ウコギ科の観葉植物。常緑低木で光沢ある革質の掌状葉をつける。原産は南アジア。日本では鉢植とする。カポックと呼ぶことがあるが、パンヤ科のカポックとの誤認。フカノキ。
シェヘラザード【Shahrazād】
①「アラビアン‐ナイト」に、語り手として登場する女性。大臣の娘で、のち王妃。シャハラザード。
②リムスキー=コルサコフ作曲の交響組曲。1888年作曲。1に取材した標題音楽。シェエラザード。
リムスキー‐コルサコフ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 →交響組曲「シェエラザード」王子と王女
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
しえやシヱヤ
〔感〕
嘆息・断念・決意などのときに発する語。ええままよ。ええい。万葉集4「かくしあらば―わが背子将来おくもいかにあらめ」
ジェラート【gelato イタリア】
イタリア風のアイス‐クリーム・シャーベット。
ジェラシー【jealousy】
ねたみ。嫉妬しっと。やきもち。
シェラック【shellac】
ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。
シエラ‐ネバダ【Sierra Nevada スペイン】
(「雪に被われた山脈」の意)
①スペイン南部の山脈。イベリア半島最高のムラセン山(3482メートル)がある。
②アメリカ、カリフォルニア州の山脈。延長650キロメートル、最高峰はホイットニー山(4418メートル)。西側にサン‐ホーキン構造谷が併走する。
シエラ‐マドレ【Sierra Madre】
メキシコの北西から南東に連なる山脈。長さ約2400キロメートル。東・西・南の三つの山脈からなり、その間にメキシコ高原が広がる。
シエラ‐レオネ【Sierra Leone】
アフリカの西岸にある共和国。1961年イギリスから独立、71年共和制。面積7万1000平方キロメートル。人口528万(2003)。首都フリータウン。→アフリカ(図)
ジェランド【gerund】
〔言〕(→)動名詞に同じ。
シェリー【sherry】
(原産地Jerez(Xerez)の転訛)スペイン南西部、アンダルシア地方原産のアルコール度を高めた白葡萄酒。また広く、これに類似する白葡萄酒。
シェリー【Mary Wollstonecraft Shelley】
イギリスの女性作家。ゴドウィン夫妻の子。P.B.シェリーの2番目の妻。人造人間の登場する小説「フランケンシュタイン」など。(1797〜1851)
シェリー【Percy Bysshe Shelley】
イギリスの詩人。キーツ・バイロンと共にロマン派の代表。革命的情熱や神秘主義、純粋な抒情性などをもつ。イタリア滞在中にボートが転覆して溺死。詩「西風の賦」「雲雀に寄す」や劇詩「チェンチ」「解放されたプロメテウス」など。(1792〜1822)
ジェリー【jelly】
⇒ゼリー
ジェリコー【Théodore Géricault】
フランスの画家。ロマン主義運動の先駆者。現実の人間の描写と明暗の鮮明な色彩で古典派に対抗。代表作「メデューズ号の筏」。(1791〜1824)
シェリダン【Richard Brinsley Sheridan】
イギリスの劇作家。アイルランドのダブリン生れ。18世紀の喜劇を代表。作「恋仇」「悪口学校」など。(1751〜1816)
シェリフ【sheriff】
保安官。
シェリング【Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling】
ドイツの哲学者。ドイツ観念論およびロマン派の代表者。自然をも自己形成の主体と捉え、自然と精神が絶対的に同一であるとする同一哲学を主張。この同一性は芸術的・知的直観によって把握されるとした。後には悪や神を含めた現実存在そのものの根拠を歴史的・神話論的展望のもとで問う積極哲学に向かった。著「自然哲学の理念」「超越論的観念論の体系」「人間的自由の本質」「啓示の哲学」など。(1775〜1854)
シェル【shell】
①貝・卵などの殻。
②軽快な競漕用のボート。
⇒シェル‐こうぞう【シェル構造】
⇒シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】
ジェル【gel】
ゼリー状のもの。特に、整髪料や薬品に言う。→ゲル
シェル‐こうぞう【シェル構造】‥ザウ
曲面の薄板を外殻(シェル)に用いた建築構造。支柱間隔を大きくした屋根などに用いる。
⇒シェル【shell】
ジェルジンスキー【Feliks E. Dzerzhinskii】
ソ連の政治家。ポーランド人で、ボリシェヴィキの一員。ロシア革命後、チェカの初代議長。(1877〜1926)
シェルター【shelter】
避難所。防空壕。「核―」
シェルパ【Sherpa】
ネパール東部を中心にインドの西ベンガル地域を含むヒマラヤ南面高地に住む少数民族。ジャガいも・大麦などの畑作農耕、山羊の移牧とチベット・ネパール間の仲介交易に従事。また、登山隊の案内人・荷役にやく人としても活躍。言語はチベット‐ビルマ語系に属し、宗教はチベット仏教。
シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】‥ハフ
(shell mold process)精密鋳造法の一つ。第二次大戦中ドイツで完成。熱硬化性樹脂を配合した合成砂を金型の上に撒まき、これを熱硬化させて作った鋳型を組み合わせて殻を作り、この中に溶融金属を鋳込むもの。鋳肌・精度ともに良好。量産が容易で安価。クローニング法。
⇒シェル【shell】
ジェロニモ【Geronimo】
アメリカ合衆国の軍事的支配に抵抗した最後の先住アメリカ人(アパッチ‐インディアン)指導者。(1829〜1909)
シェワルナゼ【Eduard A. Shevardnadze】
ソ連・グルジアの政治家。ゴルバチョフのもとで1985年からソ連共産党政治局員・ソ連外相。ソ連崩壊後グルジアに戻り、大統領、2003年失脚。(1928〜)
し‐えん【支援】‥ヱン
ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」
⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】
⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】
し‐えん【四遠】‥ヱン
四方の遠いはて。
し‐えん【四縁】
〔仏〕ものごとを生じさせる原因(縁)を四種に分類したもの。直接的原因である因縁、性質が結果と等しく、かつ時間的に直接連続して結果を生ずる原因である等無間縁とうむけんえん、認識を生じさせる認識対象である所縁縁しょえんねん、間接的原因である増上縁。
し‐えん【私怨】‥ヱン
個人的なうらみ。「―を抱く」
し‐えん【紙鳶】
凧たこ。いかのぼり。〈[季]新年〉
し‐えん【紫煙】
(紫色の煙の意から)タバコの煙。「―をくゆらす」
し‐えん【詩筵】
詩歌・俳句などの会合の席。文人会合の席。
し‐えん【試演】
演劇などを試験的に上演すること。
し‐えん【資縁】
仏道修行の助けとなる衣食住をいう。一言芳談「―省略のうへ、形のごとくの朝喰あさげし」
し‐えん【賜宴】
酒宴を賜ること。また、その酒宴。
じ‐えん【侍宴】
酒宴の席にはべること。
じえん【慈円】‥ヱン
平安末期〜鎌倉初期の僧。藤原忠通の子。前後4度、天台座主。四天王寺別当。勅諡号は慈鎮。和歌にすぐれ、即吟、修辞の練達、表出の流麗が特色。家集「拾玉集」のほか、独特の歴史観を示した史論「愚管抄」がある。(1155〜1225)
→著作:『愚管抄』
ジエン【diene】
1分子中に炭素原子間の二重結合を2個含む化合物の総称。共役二重結合をもつジエンは共役ジエンと呼ぶ。
⇒ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】
しえんか‐けいそ【四塩化珪素】‥クワ‥
分子式SiCl4 塩素の気流中で、ケイ素・炭化ケイ素、または炭素と無水ケイ酸との混合物を熱して得られる無色発煙性の刺激臭ある液体。単体のケイ素、シリコーンの原料。
しえんか‐たんそ【四塩化炭素】‥クワ‥
分子式CCl4 クロロホルム臭のある無色の液体。工業的には二硫化炭素に塩素を作用させて製造。脂肪・樹脂・タールなどをよく溶解するので溶剤として利用。引火性なく消火剤にも用いる。
シェンキェーヴィチ【Henryk Sienkiewicz】
ポーランドの小説家。17世紀ポーランドを描いた歴史小説で人気を博し、ポーランド人の愛国心を鼓舞した。代表作「クオ‐ヴァディス」。ノーベル賞。(1846〜1916)
ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】‥クワ‥
炭素原子間の二重結合を2個含む炭化水素の総称。ジオレフィンともいう。ブタジエン・イソプレンのように共役二重結合をもつものは重合しやすく、合成ゴムの原料。
⇒ジエン【diene】
しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥
航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。
⇒し‐えん【支援】
ジェンダー【gender】
①生物学的な性別を示すセックスに対して、社会的・文化的に形成される性別。作られた男らしさ・女らしさ。「―‐ギャップ」
②〔言〕(→)性4に同じ。
⇒ジェンダー‐バランス【gender balance】
⇒ジェンダー‐フリー
ジェンダー‐バランス【gender balance】
ある組織・集団内での男女の数の均衡。
⇒ジェンダー【gender】
ジェンダー‐フリー
(和製語gender free)社会的・文化的に形成された性差別の克服を目指す考え。
⇒ジェンダー【gender】
ジェンティーレ【Giovanni Gentile】
イタリアの哲学者・政治家。新ヘーゲル学派に属し、哲学を歴史の自己展開と見て、師クローチェに反して自由主義からファシズムへ転向後に暗殺。著「芸術哲学」「純粋行為としての精神の一般理論」「論理学体系」など。(1875〜1944)
ジ‐エンド【the end】
終幕。一巻の終り。
ジェントリー【gentry】
イギリス封建制のもとでは、騎士身分とほぼ同じ下級貴族。絶対主義時代には、ヨーマンと貴族の中間に位置する地主・名望家として地方行政の担い手となり、議会の下院でも指導的役割を演じた。郷紳と訳す。
ジェントルマン【gentleman】
紳士。殿方。ゼントルマン。↔レディー
ジェンナー【Edward Jenner】
イギリスの外科医。牛痘に感染した者が天然痘に対して免疫になることに気づいて、1796年に牛痘種痘法を発明。(1749〜1823)
しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥
障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。
⇒し‐えん【支援】
しお【入】シホ
物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」
しお【塩】シホ
①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。
②塩加減。しおけ。「―があまい」
⇒塩が浸む
しお【潮・汐】シホ
(「塩」と同語源)
①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」
②海水。海流。「―の流れ」
③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」
④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。
⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」
◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。
⇒潮を踏む
しお‐あい【潮合】シホアヒ
①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」
②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」
③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」
しお‐あし【潮足】シホ‥
潮汐の干満の速さ。「―が速い」
しお‐あし【潮蘆】シホ‥
海浜に生えている蘆。
しお‐あじ【塩味】シホアヂ
塩でつけた味。「―が強い」
しお‐あび【潮浴び】シホ‥
しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉
しお‐あみ【潮浴み】シホ‥
(→)「しおあび」に同じ。
しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥
塩漬にしたアユ。
しお‐あらし【潮嵐】シホ‥
吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」
しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥
⇒しおなわ
しお‐あん【塩餡】シホ‥
塩で味をつけた餡。
しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥
食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。
しおい【塩井】シホヰ
姓氏の一つ。
⇒しおい‐うこう【塩井雨江】
しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ
詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)
⇒しおい【塩井】
ジオイド【geoid】
地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面とほぼ一致する曲面。回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す。地球形。
しお‐いり【潮入】シホ‥
池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。
⇒しおいり‐いけ【潮入池】
しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥
海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」
⇒しお‐いり【潮入】
しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥
拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」
し‐おう【四王】‥ワウ
①四天王の略。
②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。
⇒しおう‐てん【四王天】
し‐おう【死王】‥ワウ
①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。
②死んだ王。
し‐おう【嗣王】‥ワウ
世を嗣ついだ王。
し‐おう【雌黄】‥ワウ
①石黄せきおうの古名。
②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。
③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。
じ‐おう【地黄】ヂワウ
ゴマノハグサ科の多年草。中国原産の薬用植物。地下茎は肥厚、根生葉は楕円形、表面にしわが多い。初夏、茎頂に紫紅色で筒状の美花を数個開く。茎・花冠に腺毛が密生する。根茎は著名な漢方生薬で、補血・強壮、また血糖降下作用がある。根茎の表面は赤黄色で、乾燥すれば黒色。特異な匂いがあり、味は初めわずかに甘く、後やや苦い。サオヒメ。アカヤジオウ。
じおう
→交響組曲「シェエラザード」王子と王女
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
しえやシヱヤ
〔感〕
嘆息・断念・決意などのときに発する語。ええままよ。ええい。万葉集4「かくしあらば―わが背子将来おくもいかにあらめ」
ジェラート【gelato イタリア】
イタリア風のアイス‐クリーム・シャーベット。
ジェラシー【jealousy】
ねたみ。嫉妬しっと。やきもち。
シェラック【shellac】
ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。
シエラ‐ネバダ【Sierra Nevada スペイン】
(「雪に被われた山脈」の意)
①スペイン南部の山脈。イベリア半島最高のムラセン山(3482メートル)がある。
②アメリカ、カリフォルニア州の山脈。延長650キロメートル、最高峰はホイットニー山(4418メートル)。西側にサン‐ホーキン構造谷が併走する。
シエラ‐マドレ【Sierra Madre】
メキシコの北西から南東に連なる山脈。長さ約2400キロメートル。東・西・南の三つの山脈からなり、その間にメキシコ高原が広がる。
シエラ‐レオネ【Sierra Leone】
アフリカの西岸にある共和国。1961年イギリスから独立、71年共和制。面積7万1000平方キロメートル。人口528万(2003)。首都フリータウン。→アフリカ(図)
ジェランド【gerund】
〔言〕(→)動名詞に同じ。
シェリー【sherry】
(原産地Jerez(Xerez)の転訛)スペイン南西部、アンダルシア地方原産のアルコール度を高めた白葡萄酒。また広く、これに類似する白葡萄酒。
シェリー【Mary Wollstonecraft Shelley】
イギリスの女性作家。ゴドウィン夫妻の子。P.B.シェリーの2番目の妻。人造人間の登場する小説「フランケンシュタイン」など。(1797〜1851)
シェリー【Percy Bysshe Shelley】
イギリスの詩人。キーツ・バイロンと共にロマン派の代表。革命的情熱や神秘主義、純粋な抒情性などをもつ。イタリア滞在中にボートが転覆して溺死。詩「西風の賦」「雲雀に寄す」や劇詩「チェンチ」「解放されたプロメテウス」など。(1792〜1822)
ジェリー【jelly】
⇒ゼリー
ジェリコー【Théodore Géricault】
フランスの画家。ロマン主義運動の先駆者。現実の人間の描写と明暗の鮮明な色彩で古典派に対抗。代表作「メデューズ号の筏」。(1791〜1824)
シェリダン【Richard Brinsley Sheridan】
イギリスの劇作家。アイルランドのダブリン生れ。18世紀の喜劇を代表。作「恋仇」「悪口学校」など。(1751〜1816)
シェリフ【sheriff】
保安官。
シェリング【Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling】
ドイツの哲学者。ドイツ観念論およびロマン派の代表者。自然をも自己形成の主体と捉え、自然と精神が絶対的に同一であるとする同一哲学を主張。この同一性は芸術的・知的直観によって把握されるとした。後には悪や神を含めた現実存在そのものの根拠を歴史的・神話論的展望のもとで問う積極哲学に向かった。著「自然哲学の理念」「超越論的観念論の体系」「人間的自由の本質」「啓示の哲学」など。(1775〜1854)
シェル【shell】
①貝・卵などの殻。
②軽快な競漕用のボート。
⇒シェル‐こうぞう【シェル構造】
⇒シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】
ジェル【gel】
ゼリー状のもの。特に、整髪料や薬品に言う。→ゲル
シェル‐こうぞう【シェル構造】‥ザウ
曲面の薄板を外殻(シェル)に用いた建築構造。支柱間隔を大きくした屋根などに用いる。
⇒シェル【shell】
ジェルジンスキー【Feliks E. Dzerzhinskii】
ソ連の政治家。ポーランド人で、ボリシェヴィキの一員。ロシア革命後、チェカの初代議長。(1877〜1926)
シェルター【shelter】
避難所。防空壕。「核―」
シェルパ【Sherpa】
ネパール東部を中心にインドの西ベンガル地域を含むヒマラヤ南面高地に住む少数民族。ジャガいも・大麦などの畑作農耕、山羊の移牧とチベット・ネパール間の仲介交易に従事。また、登山隊の案内人・荷役にやく人としても活躍。言語はチベット‐ビルマ語系に属し、宗教はチベット仏教。
シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】‥ハフ
(shell mold process)精密鋳造法の一つ。第二次大戦中ドイツで完成。熱硬化性樹脂を配合した合成砂を金型の上に撒まき、これを熱硬化させて作った鋳型を組み合わせて殻を作り、この中に溶融金属を鋳込むもの。鋳肌・精度ともに良好。量産が容易で安価。クローニング法。
⇒シェル【shell】
ジェロニモ【Geronimo】
アメリカ合衆国の軍事的支配に抵抗した最後の先住アメリカ人(アパッチ‐インディアン)指導者。(1829〜1909)
シェワルナゼ【Eduard A. Shevardnadze】
ソ連・グルジアの政治家。ゴルバチョフのもとで1985年からソ連共産党政治局員・ソ連外相。ソ連崩壊後グルジアに戻り、大統領、2003年失脚。(1928〜)
し‐えん【支援】‥ヱン
ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」
⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】
⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】
し‐えん【四遠】‥ヱン
四方の遠いはて。
し‐えん【四縁】
〔仏〕ものごとを生じさせる原因(縁)を四種に分類したもの。直接的原因である因縁、性質が結果と等しく、かつ時間的に直接連続して結果を生ずる原因である等無間縁とうむけんえん、認識を生じさせる認識対象である所縁縁しょえんねん、間接的原因である増上縁。
し‐えん【私怨】‥ヱン
個人的なうらみ。「―を抱く」
し‐えん【紙鳶】
凧たこ。いかのぼり。〈[季]新年〉
し‐えん【紫煙】
(紫色の煙の意から)タバコの煙。「―をくゆらす」
し‐えん【詩筵】
詩歌・俳句などの会合の席。文人会合の席。
し‐えん【試演】
演劇などを試験的に上演すること。
し‐えん【資縁】
仏道修行の助けとなる衣食住をいう。一言芳談「―省略のうへ、形のごとくの朝喰あさげし」
し‐えん【賜宴】
酒宴を賜ること。また、その酒宴。
じ‐えん【侍宴】
酒宴の席にはべること。
じえん【慈円】‥ヱン
平安末期〜鎌倉初期の僧。藤原忠通の子。前後4度、天台座主。四天王寺別当。勅諡号は慈鎮。和歌にすぐれ、即吟、修辞の練達、表出の流麗が特色。家集「拾玉集」のほか、独特の歴史観を示した史論「愚管抄」がある。(1155〜1225)
→著作:『愚管抄』
ジエン【diene】
1分子中に炭素原子間の二重結合を2個含む化合物の総称。共役二重結合をもつジエンは共役ジエンと呼ぶ。
⇒ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】
しえんか‐けいそ【四塩化珪素】‥クワ‥
分子式SiCl4 塩素の気流中で、ケイ素・炭化ケイ素、または炭素と無水ケイ酸との混合物を熱して得られる無色発煙性の刺激臭ある液体。単体のケイ素、シリコーンの原料。
しえんか‐たんそ【四塩化炭素】‥クワ‥
分子式CCl4 クロロホルム臭のある無色の液体。工業的には二硫化炭素に塩素を作用させて製造。脂肪・樹脂・タールなどをよく溶解するので溶剤として利用。引火性なく消火剤にも用いる。
シェンキェーヴィチ【Henryk Sienkiewicz】
ポーランドの小説家。17世紀ポーランドを描いた歴史小説で人気を博し、ポーランド人の愛国心を鼓舞した。代表作「クオ‐ヴァディス」。ノーベル賞。(1846〜1916)
ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】‥クワ‥
炭素原子間の二重結合を2個含む炭化水素の総称。ジオレフィンともいう。ブタジエン・イソプレンのように共役二重結合をもつものは重合しやすく、合成ゴムの原料。
⇒ジエン【diene】
しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥
航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。
⇒し‐えん【支援】
ジェンダー【gender】
①生物学的な性別を示すセックスに対して、社会的・文化的に形成される性別。作られた男らしさ・女らしさ。「―‐ギャップ」
②〔言〕(→)性4に同じ。
⇒ジェンダー‐バランス【gender balance】
⇒ジェンダー‐フリー
ジェンダー‐バランス【gender balance】
ある組織・集団内での男女の数の均衡。
⇒ジェンダー【gender】
ジェンダー‐フリー
(和製語gender free)社会的・文化的に形成された性差別の克服を目指す考え。
⇒ジェンダー【gender】
ジェンティーレ【Giovanni Gentile】
イタリアの哲学者・政治家。新ヘーゲル学派に属し、哲学を歴史の自己展開と見て、師クローチェに反して自由主義からファシズムへ転向後に暗殺。著「芸術哲学」「純粋行為としての精神の一般理論」「論理学体系」など。(1875〜1944)
ジ‐エンド【the end】
終幕。一巻の終り。
ジェントリー【gentry】
イギリス封建制のもとでは、騎士身分とほぼ同じ下級貴族。絶対主義時代には、ヨーマンと貴族の中間に位置する地主・名望家として地方行政の担い手となり、議会の下院でも指導的役割を演じた。郷紳と訳す。
ジェントルマン【gentleman】
紳士。殿方。ゼントルマン。↔レディー
ジェンナー【Edward Jenner】
イギリスの外科医。牛痘に感染した者が天然痘に対して免疫になることに気づいて、1796年に牛痘種痘法を発明。(1749〜1823)
しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥
障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。
⇒し‐えん【支援】
しお【入】シホ
物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」
しお【塩】シホ
①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。
②塩加減。しおけ。「―があまい」
⇒塩が浸む
しお【潮・汐】シホ
(「塩」と同語源)
①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」
②海水。海流。「―の流れ」
③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」
④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。
⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」
◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。
⇒潮を踏む
しお‐あい【潮合】シホアヒ
①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」
②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」
③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」
しお‐あし【潮足】シホ‥
潮汐の干満の速さ。「―が速い」
しお‐あし【潮蘆】シホ‥
海浜に生えている蘆。
しお‐あじ【塩味】シホアヂ
塩でつけた味。「―が強い」
しお‐あび【潮浴び】シホ‥
しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉
しお‐あみ【潮浴み】シホ‥
(→)「しおあび」に同じ。
しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥
塩漬にしたアユ。
しお‐あらし【潮嵐】シホ‥
吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」
しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥
⇒しおなわ
しお‐あん【塩餡】シホ‥
塩で味をつけた餡。
しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥
食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。
しおい【塩井】シホヰ
姓氏の一つ。
⇒しおい‐うこう【塩井雨江】
しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ
詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)
⇒しおい【塩井】
ジオイド【geoid】
地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面とほぼ一致する曲面。回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す。地球形。
しお‐いり【潮入】シホ‥
池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。
⇒しおいり‐いけ【潮入池】
しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥
海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」
⇒しお‐いり【潮入】
しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥
拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」
し‐おう【四王】‥ワウ
①四天王の略。
②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。
⇒しおう‐てん【四王天】
し‐おう【死王】‥ワウ
①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。
②死んだ王。
し‐おう【嗣王】‥ワウ
世を嗣ついだ王。
し‐おう【雌黄】‥ワウ
①石黄せきおうの古名。
②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。
③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。
じ‐おう【地黄】ヂワウ
ゴマノハグサ科の多年草。中国原産の薬用植物。地下茎は肥厚、根生葉は楕円形、表面にしわが多い。初夏、茎頂に紫紅色で筒状の美花を数個開く。茎・花冠に腺毛が密生する。根茎は著名な漢方生薬で、補血・強壮、また血糖降下作用がある。根茎の表面は赤黄色で、乾燥すれば黒色。特異な匂いがあり、味は初めわずかに甘く、後やや苦い。サオヒメ。アカヤジオウ。
じおう
 ⇒じおう‐がゆ【地黄粥】
⇒じおう‐がん【地黄丸】
⇒じおう‐せん【地黄煎】
しお‐うお【塩魚】シホウヲ
塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。
じおう‐がゆ【地黄粥】ヂワウ‥
地黄の根茎をきざみ入れた粥。正月にこれを食すれば邪気を除くという。
⇒じ‐おう【地黄】
じおう‐がん【地黄丸】ヂワウグワン
地黄を主剤として作った漢方の強壮・補血剤。好色一代女1「いまだ御年も若ふして―の御せんさく」
⇒じ‐おう【地黄】
じおう‐せん【地黄煎】ヂワウ‥
①穀芽の粉に地黄の汁をねり合わせたもの。気血を増すという。くだり。凝煎。
②地黄の汁を加えてねった飴。京都伏見稲荷門前の名産。上方かみがたより下ったので江戸では「くだりあめ」という。
⇒じ‐おう【地黄】
しお‐うち【塩打】シホ‥
大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」
しおう‐てん【四王天】‥ワウ‥
〔仏〕欲界六天の第1。須弥山しゅみせんの中腹にある。→四天王してんのう
⇒し‐おう【四王】
しお‐うに【塩雲丹】シホ‥
ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。
しお‐うみ【潮海】シホ‥
塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」
し‐お・える【為終える】‥ヲヘル
〔他下一〕
することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」
しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥
潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。
ジオーク【William Francis Giauque】
アメリカの物理化学者。酸素の同位体を発見。断熱消磁法により絶対零度に近い温度を得ることに成功、極低温における物質の諸特性の研究に貢献。ノーベル化学賞。(1895〜1982)
しお‐おけ【潮桶】シホヲケ
海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」
しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥
野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」
し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル
〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)
なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」
しおお‐にシホホ‥
〔副〕
涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」
しお‐がい【塩貝】シホガヒ
塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」
しお‐がい【潮貝】シホガヒ
海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」
しお‐がい【潮間】シホガヒ
(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」
しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥
漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。
しお‐がかり【潮繋り】シホ‥
潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」
しお‐かげん【塩加減】シホ‥
ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。
⇒じおう‐がゆ【地黄粥】
⇒じおう‐がん【地黄丸】
⇒じおう‐せん【地黄煎】
しお‐うお【塩魚】シホウヲ
塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。
じおう‐がゆ【地黄粥】ヂワウ‥
地黄の根茎をきざみ入れた粥。正月にこれを食すれば邪気を除くという。
⇒じ‐おう【地黄】
じおう‐がん【地黄丸】ヂワウグワン
地黄を主剤として作った漢方の強壮・補血剤。好色一代女1「いまだ御年も若ふして―の御せんさく」
⇒じ‐おう【地黄】
じおう‐せん【地黄煎】ヂワウ‥
①穀芽の粉に地黄の汁をねり合わせたもの。気血を増すという。くだり。凝煎。
②地黄の汁を加えてねった飴。京都伏見稲荷門前の名産。上方かみがたより下ったので江戸では「くだりあめ」という。
⇒じ‐おう【地黄】
しお‐うち【塩打】シホ‥
大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」
しおう‐てん【四王天】‥ワウ‥
〔仏〕欲界六天の第1。須弥山しゅみせんの中腹にある。→四天王してんのう
⇒し‐おう【四王】
しお‐うに【塩雲丹】シホ‥
ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。
しお‐うみ【潮海】シホ‥
塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」
し‐お・える【為終える】‥ヲヘル
〔他下一〕
することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」
しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥
潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。
ジオーク【William Francis Giauque】
アメリカの物理化学者。酸素の同位体を発見。断熱消磁法により絶対零度に近い温度を得ることに成功、極低温における物質の諸特性の研究に貢献。ノーベル化学賞。(1895〜1982)
しお‐おけ【潮桶】シホヲケ
海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」
しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥
野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」
し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル
〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)
なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」
しおお‐にシホホ‥
〔副〕
涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」
しお‐がい【塩貝】シホガヒ
塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」
しお‐がい【潮貝】シホガヒ
海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」
しお‐がい【潮間】シホガヒ
(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」
しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥
漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。
しお‐がかり【潮繋り】シホ‥
潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」
しお‐かげん【塩加減】シホ‥
ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。
 警察予備隊・保安隊・自衛隊
提供:NHK
⇒じ‐えい【自衛】
しえい‐でん【私営田】
奈良・平安時代、荒廃地・空閑地などを利用し、個人的に開発・経営した農場。土豪が直接経営するのが一般。↔公営田くえいでん
⇒し‐えい【私営】
シェイプ【shape】
⇒シェープ
ジェヴォンズ【William Stanley Jevons】
イギリスの経済学者。メンガー・ワルラスらと並んで限界効用理論を提唱。著「経済学の理論」「石炭問題」など。(1835〜1882)
ジェー【J・j】
①アルファベットの10番目の文字。
②〔理〕ジュール(仕事・エネルギーの単位)の記号(J)。
ジェー‐アール【JR】
(Japan Railway)国鉄が1987年に分割・民営化して新設した旅客鉄道会社6社と貨物鉄道1社の統一的略称。それぞれの会社はJR東海・JR西日本などと称する。→日本国有鉄道
ジェー‐エー【JA】
(Japan Agricultural cooperatives)農協の新しい呼称。1991年の全国農協大会で決まる。
ジェー‐オー‐シー【JOC】
(Japan Olympic Committee)日本オリンピック委員会の略称。
シェーカー【shaker】
カクテルを作るとき洋酒・氷などを入れて振り、混合したり素早く冷やしたりするための金属製の器具。攪拌器。
ジェー‐カーブ‐こうか【Jカーブ効果】‥カウクワ
〔経〕為替レートの変化により貿易収支を均衡させる効果がすぐには現れない現象。貿易収支の黒字による円の上昇(円高)がかえって貿易黒字を拡大させたのち、やがて黒字縮小に向かうのはその例。
シェーク【shake】
①小刻みに振ること。揺り動かすこと。
②カクテルやドレッシングを容器に入れて振りまぜること。
③材料を振りまぜて作った飲み物。特に、アイス‐クリームを材料とするものをいう。
⇒シェーク‐ハンド【shake-hands】
シェークスピア【William Shakespeare】
イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。ストラトフォード‐アポン‐エーヴォンの生れ。青年時代にロンドンに出て、初め俳優、のち座付作者として約37編の戯曲を創作。四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」をはじめ、史劇「リチャード三世」「ヘンリー四世」、悲劇「ロミオとジュリエット」「ジュリアス=シーザー」、喜劇「真夏の夜の夢」「ヴェニスの商人」、ロマンス劇「テンペスト」、そのほか詩集「ソネット集」などがある。沙翁。(1564〜1616)
シェーク‐ハンド【shake-hands】
(握手の意)シェークハンド‐グリップ(shake-hands grip)の略。卓球などで、握手するようなラケットの握り方。
⇒シェーク【shake】
シェーグレン‐しょうこうぐん【シェーグレン症候群】‥シヤウ‥
(スウェーデンの眼科医シェーグレン(H. S. C. Sjögren1899〜1987)に因む)涙腺や唾液腺の分泌が減少し、乾燥性結膜炎、角膜炎、唾液腺の腫脹、多発性関節炎などをひき起こす全身疾患。中年の女性に多く、自己免疫疾患と考えられる。
ジェー‐ターン
(和製語J turn)地方から都会へ出た人が、故郷に近い地方都市で就職・定住すること。→ユー‐ターン→アイ‐ターン
シェード【shade】
①光をさえぎる具。日除ひよけ。日覆ひおおい。
②電灯・電気スタンドの笠。
シェーバー【shaver】
剃刀かみそり。特に、電気剃刀。
シェーパー【shaper】
(→)形削かたけずり盤。
シェービング【shaving】
髭ひげなどをそること。「―‐クリーム」
シェープ【shape】
形。形状。シェイプ。
⇒シェープ‐アップ【shape up】
シェーファー【Anthony Shaffer】
イギリスの劇作家。P.L.シェーファーとは双子。作「スルース」など。兄弟合作の小説がある。(1926〜2001)
シェーファー【Peter Levin Shaffer】
イギリスの劇作家。伝統的写実に新技法を採り入れ、笑劇・歴史劇などさまざまな分野にわたる。作「アマデウス」など。シャファー。(1926〜)。
シェープ‐アップ【shape up】
美容や健康のために運動や減食をして体形をととのえること。
⇒シェープ【shape】
ジェー‐ペグ【JPEG】
(joint photographic experts group)画像データ記録のための圧縮方式の一つ。また、その方式によるファイル形式。→エムペグ。
▷もともとはカラー静止画像の圧縮規格を定めたISOと国際電気通信連合標準化セクター(ITU)の合同組織の呼称。
シェーマ【Schema ドイツ】
図式。形式。
ジェームズ【James】
(英語の男子名。ラテン語のヤコブス、ドイツ語のヤーコプ、フランス語のジャックに当たる)イギリス王。
①(1世)スチュアート王朝の祖。スコットランド王としては6世。1603年イングランド王位を継承して大ブリテン島を同君連合のもとに置いた。王権神授説を唱え、英国国教会強硬派を支持、議会と衝突。(1566〜1625)
②(2世)カトリックを復興、専断的政治を行なったため、1688年名誉革命によって王位を追われ、フランスに亡命。(1633〜1701)
ジェームズ【Cyril Lionel Robert James】
トリニダード‐トバゴ出身の小説家・歴史家・政治評論家。イギリス・アメリカで活動。代表作「黒いジャコバン」。(1901〜1989)
ジェームズ【Henry James】
イギリスの小説家。アメリカ生れ。W.ジェームズの弟。心理主義文学の先駆。作「ある婦人の肖像」「ねじの回転」など。(1843〜1916)
ジェームズ【William James】
アメリカの哲学者・心理学者。パースとともにプラグマティズムの提唱者。「純粋経験」に基づく根本的経験論を主張。また、思考を生存競争の道具とみなす機能的心理学を展開した。著「宗教経験の諸相」「心理学原理」「プラグマティズム」など。(1842〜1910)
ジェームズ‐ボンド【James Bond】
「フレミング(I. Fleming)」参照。
シェーラー【Max Scheler】
ドイツの哲学者。現象学的立場からカント倫理学の形式主義に反対し、実質的価値倫理学を展開、晩年には哲学的人間学の樹立を試みた。著「倫理学における形式主義と実質的価値倫理学」「宇宙における人間の位置」など。(1874〜1928)
ジェー‐リーグ
(和製語J league)1993年に発足した日本初のプロ‐サッカー‐リーグ。正式名は社団法人日本プロ‐サッカー‐リーグ。
シェーレ【Schere ドイツ】
〔経〕(鋏はさみの意)独占化した産業部門と非独占部門との価格差が鋏を開いたような形に漸次増大する現象。特に工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。鋏状価格差。
シェーレ【Carl Wilhelm Scheele】
スウェーデンの化学者。塩素・酸素・フッ化水素・乳酸・蓚酸しゅうさん・酒石酸の発見など多くの業績がある。(1742〜1786)
ジェーン‐エア【Jane Eyre】
C.ブロンテの長編小説。1847年刊。孤児ジェーンが地主ロチェスターの家庭教師として住み込み、狂気の妻バーサの死後、彼と結ばれるまでを描く。男性中心の社会に抵抗したヒロインが共感を呼んだ。
シェーンベルク【Arnold Schönberg】
オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。1933年アメリカへ移住。作「月に憑かれたピエロ」「ワルシャワの生き残り」など。(1874〜1951)
し‐えき【四駅】
江戸時代、江戸の四隅にあって、五街道の出発点であった宿駅。千住せんじゅ(日光・奥州街道)・板橋(中山道)・品川(東海道)・内藤新宿(甲州街道)。四宿。
し‐えき【私益】
一個人の利益。私利。↔公益
し‐えき【使役】
①人を使って仕事(特に雑役)をさせること。他人にある行為をさせること。「―に駆り出される」
②(文法用語)他人に動作を行わせたり事態を引き起こさせたりすること。また、その意味を表す形式。日本語では使役の助動詞を動詞の未然形に付けて表す。
し‐えき【資益】
助け利すること。利益。
じ‐えき【自益】
自分の利益。個人の利益。
⇒じえき‐けん【自益権】
⇒じえき‐しんたく【自益信託】
じ‐えき【時疫】
流行病。はやりやまい。浮世草子、好色敗毒散「―をわづらひてみまかりぬ」
じ‐えき【滋液】
滋味のある液。甘味のある液。
じえき‐けん【自益権】
社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。
⇒じ‐えき【自益】
じえき‐しんたく【自益信託】
信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。
⇒じ‐えき【自益】
しえき‐ほう【市易法】‥ハフ
中国、北宋の王安石の新法の一つ。小商人を豪商の搾取から守るため主な都市に市易務を設置し、小商人の滞貨を買い上げ、あるいはこれを抵当に低利で資金を融通した。
シエシエ【謝謝】
(中国語)ありがとう。
しえ‐じけん【紫衣事件】
1627年(寛永4)将軍徳川家光の時、皇室から大徳寺・妙心寺の僧に賜った紫衣を、幕府が法規を楯に奪い、幕命に従わない妙心寺の単伝・東源、大徳寺の沢庵・玉室らを罰した事件。
ジェズイット【Jesuit】
イエズス会に所属する修道士。
シエスタ【siesta スペイン】
スペインなどで、昼食後にとる昼寝。
ジェスチャー【gesture】
(ゼスチュアとも)
①身振り。手振り。手真似。「―を交えた会話」
②思わせぶりな態度。誠実さに欠ける形ばかりの態度。みせかけ。「―ばかりでやる気がない」
シェストフ【Lev Shestov】
ロシアの哲学者。フランスに亡命。真理は理性を超えるものとし、存在の非合理的根源を追求。不安の哲学として第一次大戦後に迎えられた。著「ドストエフスキーとニーチェ(悲劇の哲学)」「キルケゴールと実存哲学」など。(1866〜1938)
しえた・ぐ【虐ぐ・冤ぐ】シヘタグ
(古くはシヘタクと清音)〔他下二〕
①人をむごく扱う。虐待する。しいたげる。徒然草「すべて人を苦しめものを―・ぐることいやしき民の志をも奪ふべからず」
②道理をまげて無実の罪に落とす。続日本紀5「制断理に合ひ、獄訟冤しえたくることなく」
③征服する。平家物語12「毎度に味方おひ落されて、敵を―・ぐるに及ばず」
ジエチル‐エーテル【diethyl ether】
(→)エチル‐エーテルに同じ。
し‐エチル‐なまり【四エチル鉛】
(→)テトラエチル鉛に同じ。
し‐えつ【私謁】
天子などに私事で謁見すること。
ジェッダ【Jedda】
サウジ‐アラビア西部、ヘジャズ地方の紅海に臨む港湾都市。イスラムの聖地メッカの外港。ジッダ。人口82万4千(1992)。
ジェット【jet】
①孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。
②素粒子物理学で、狭い立体角内に集中して、多数のハドロン群の発生する現象。また、そのハドロン群。
③〔天〕原始星やクエーサーなどから高速で噴出するジェット1状のガス流。
④ジェット機の略。
⇒ジェット‐エンジン【jet engine】
⇒ジェット‐き【ジェット機】
⇒ジェット‐きりゅう【ジェット気流】
⇒ジェット‐コースター
⇒ジェット‐ストリーム【jet stream】
⇒ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】
⇒ジェット‐フォイル【jetfoil】
⇒ジェット‐ポンプ
⇒ジェット‐ルート【jet route】
ジェット‐エンジン【jet engine】
空気を圧縮し、燃料を吹き込んで燃焼させ、排気を高速で噴出させてその反作用として推進力を得る航空用発動機。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐き【ジェット機】
ジェット‐エンジンを推進装置とする航空機。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐きりゅう【ジェット気流】‥リウ
中緯度の対流圏上部に吹く強い西風。風速は冬には毎秒80メートル以上に達する。ジェット‐ストリーム。→偏西風帯。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐コースター
(和製語jet coaster)遊園地などの遊戯設備で、上下左右に曲がりくねったレール上を急スピードで走る滑走車。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ストリーム【jet stream】
(→)ジェット気流に同じ。
ジェットストリーム
撮影:NASA/STScI
警察予備隊・保安隊・自衛隊
提供:NHK
⇒じ‐えい【自衛】
しえい‐でん【私営田】
奈良・平安時代、荒廃地・空閑地などを利用し、個人的に開発・経営した農場。土豪が直接経営するのが一般。↔公営田くえいでん
⇒し‐えい【私営】
シェイプ【shape】
⇒シェープ
ジェヴォンズ【William Stanley Jevons】
イギリスの経済学者。メンガー・ワルラスらと並んで限界効用理論を提唱。著「経済学の理論」「石炭問題」など。(1835〜1882)
ジェー【J・j】
①アルファベットの10番目の文字。
②〔理〕ジュール(仕事・エネルギーの単位)の記号(J)。
ジェー‐アール【JR】
(Japan Railway)国鉄が1987年に分割・民営化して新設した旅客鉄道会社6社と貨物鉄道1社の統一的略称。それぞれの会社はJR東海・JR西日本などと称する。→日本国有鉄道
ジェー‐エー【JA】
(Japan Agricultural cooperatives)農協の新しい呼称。1991年の全国農協大会で決まる。
ジェー‐オー‐シー【JOC】
(Japan Olympic Committee)日本オリンピック委員会の略称。
シェーカー【shaker】
カクテルを作るとき洋酒・氷などを入れて振り、混合したり素早く冷やしたりするための金属製の器具。攪拌器。
ジェー‐カーブ‐こうか【Jカーブ効果】‥カウクワ
〔経〕為替レートの変化により貿易収支を均衡させる効果がすぐには現れない現象。貿易収支の黒字による円の上昇(円高)がかえって貿易黒字を拡大させたのち、やがて黒字縮小に向かうのはその例。
シェーク【shake】
①小刻みに振ること。揺り動かすこと。
②カクテルやドレッシングを容器に入れて振りまぜること。
③材料を振りまぜて作った飲み物。特に、アイス‐クリームを材料とするものをいう。
⇒シェーク‐ハンド【shake-hands】
シェークスピア【William Shakespeare】
イギリスの劇作家・詩人。エリザベス朝ルネサンス文学の代表者。ストラトフォード‐アポン‐エーヴォンの生れ。青年時代にロンドンに出て、初め俳優、のち座付作者として約37編の戯曲を創作。四大悲劇「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」をはじめ、史劇「リチャード三世」「ヘンリー四世」、悲劇「ロミオとジュリエット」「ジュリアス=シーザー」、喜劇「真夏の夜の夢」「ヴェニスの商人」、ロマンス劇「テンペスト」、そのほか詩集「ソネット集」などがある。沙翁。(1564〜1616)
シェーク‐ハンド【shake-hands】
(握手の意)シェークハンド‐グリップ(shake-hands grip)の略。卓球などで、握手するようなラケットの握り方。
⇒シェーク【shake】
シェーグレン‐しょうこうぐん【シェーグレン症候群】‥シヤウ‥
(スウェーデンの眼科医シェーグレン(H. S. C. Sjögren1899〜1987)に因む)涙腺や唾液腺の分泌が減少し、乾燥性結膜炎、角膜炎、唾液腺の腫脹、多発性関節炎などをひき起こす全身疾患。中年の女性に多く、自己免疫疾患と考えられる。
ジェー‐ターン
(和製語J turn)地方から都会へ出た人が、故郷に近い地方都市で就職・定住すること。→ユー‐ターン→アイ‐ターン
シェード【shade】
①光をさえぎる具。日除ひよけ。日覆ひおおい。
②電灯・電気スタンドの笠。
シェーバー【shaver】
剃刀かみそり。特に、電気剃刀。
シェーパー【shaper】
(→)形削かたけずり盤。
シェービング【shaving】
髭ひげなどをそること。「―‐クリーム」
シェープ【shape】
形。形状。シェイプ。
⇒シェープ‐アップ【shape up】
シェーファー【Anthony Shaffer】
イギリスの劇作家。P.L.シェーファーとは双子。作「スルース」など。兄弟合作の小説がある。(1926〜2001)
シェーファー【Peter Levin Shaffer】
イギリスの劇作家。伝統的写実に新技法を採り入れ、笑劇・歴史劇などさまざまな分野にわたる。作「アマデウス」など。シャファー。(1926〜)。
シェープ‐アップ【shape up】
美容や健康のために運動や減食をして体形をととのえること。
⇒シェープ【shape】
ジェー‐ペグ【JPEG】
(joint photographic experts group)画像データ記録のための圧縮方式の一つ。また、その方式によるファイル形式。→エムペグ。
▷もともとはカラー静止画像の圧縮規格を定めたISOと国際電気通信連合標準化セクター(ITU)の合同組織の呼称。
シェーマ【Schema ドイツ】
図式。形式。
ジェームズ【James】
(英語の男子名。ラテン語のヤコブス、ドイツ語のヤーコプ、フランス語のジャックに当たる)イギリス王。
①(1世)スチュアート王朝の祖。スコットランド王としては6世。1603年イングランド王位を継承して大ブリテン島を同君連合のもとに置いた。王権神授説を唱え、英国国教会強硬派を支持、議会と衝突。(1566〜1625)
②(2世)カトリックを復興、専断的政治を行なったため、1688年名誉革命によって王位を追われ、フランスに亡命。(1633〜1701)
ジェームズ【Cyril Lionel Robert James】
トリニダード‐トバゴ出身の小説家・歴史家・政治評論家。イギリス・アメリカで活動。代表作「黒いジャコバン」。(1901〜1989)
ジェームズ【Henry James】
イギリスの小説家。アメリカ生れ。W.ジェームズの弟。心理主義文学の先駆。作「ある婦人の肖像」「ねじの回転」など。(1843〜1916)
ジェームズ【William James】
アメリカの哲学者・心理学者。パースとともにプラグマティズムの提唱者。「純粋経験」に基づく根本的経験論を主張。また、思考を生存競争の道具とみなす機能的心理学を展開した。著「宗教経験の諸相」「心理学原理」「プラグマティズム」など。(1842〜1910)
ジェームズ‐ボンド【James Bond】
「フレミング(I. Fleming)」参照。
シェーラー【Max Scheler】
ドイツの哲学者。現象学的立場からカント倫理学の形式主義に反対し、実質的価値倫理学を展開、晩年には哲学的人間学の樹立を試みた。著「倫理学における形式主義と実質的価値倫理学」「宇宙における人間の位置」など。(1874〜1928)
ジェー‐リーグ
(和製語J league)1993年に発足した日本初のプロ‐サッカー‐リーグ。正式名は社団法人日本プロ‐サッカー‐リーグ。
シェーレ【Schere ドイツ】
〔経〕(鋏はさみの意)独占化した産業部門と非独占部門との価格差が鋏を開いたような形に漸次増大する現象。特に工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。鋏状価格差。
シェーレ【Carl Wilhelm Scheele】
スウェーデンの化学者。塩素・酸素・フッ化水素・乳酸・蓚酸しゅうさん・酒石酸の発見など多くの業績がある。(1742〜1786)
ジェーン‐エア【Jane Eyre】
C.ブロンテの長編小説。1847年刊。孤児ジェーンが地主ロチェスターの家庭教師として住み込み、狂気の妻バーサの死後、彼と結ばれるまでを描く。男性中心の社会に抵抗したヒロインが共感を呼んだ。
シェーンベルク【Arnold Schönberg】
オーストリアの作曲家。調性を否定した無調音楽、ついで十二音音楽の作曲技法を創始。1933年アメリカへ移住。作「月に憑かれたピエロ」「ワルシャワの生き残り」など。(1874〜1951)
し‐えき【四駅】
江戸時代、江戸の四隅にあって、五街道の出発点であった宿駅。千住せんじゅ(日光・奥州街道)・板橋(中山道)・品川(東海道)・内藤新宿(甲州街道)。四宿。
し‐えき【私益】
一個人の利益。私利。↔公益
し‐えき【使役】
①人を使って仕事(特に雑役)をさせること。他人にある行為をさせること。「―に駆り出される」
②(文法用語)他人に動作を行わせたり事態を引き起こさせたりすること。また、その意味を表す形式。日本語では使役の助動詞を動詞の未然形に付けて表す。
し‐えき【資益】
助け利すること。利益。
じ‐えき【自益】
自分の利益。個人の利益。
⇒じえき‐けん【自益権】
⇒じえき‐しんたく【自益信託】
じ‐えき【時疫】
流行病。はやりやまい。浮世草子、好色敗毒散「―をわづらひてみまかりぬ」
じ‐えき【滋液】
滋味のある液。甘味のある液。
じえき‐けん【自益権】
社員権の一つ。社員(株式会社では株主を指す)個人の利益のために社員に与えられている権利。剰余金配当請求権の類。↔共益権。
⇒じ‐えき【自益】
じえき‐しんたく【自益信託】
信託財産から生ずる利益が委託者に帰する信託。
⇒じ‐えき【自益】
しえき‐ほう【市易法】‥ハフ
中国、北宋の王安石の新法の一つ。小商人を豪商の搾取から守るため主な都市に市易務を設置し、小商人の滞貨を買い上げ、あるいはこれを抵当に低利で資金を融通した。
シエシエ【謝謝】
(中国語)ありがとう。
しえ‐じけん【紫衣事件】
1627年(寛永4)将軍徳川家光の時、皇室から大徳寺・妙心寺の僧に賜った紫衣を、幕府が法規を楯に奪い、幕命に従わない妙心寺の単伝・東源、大徳寺の沢庵・玉室らを罰した事件。
ジェズイット【Jesuit】
イエズス会に所属する修道士。
シエスタ【siesta スペイン】
スペインなどで、昼食後にとる昼寝。
ジェスチャー【gesture】
(ゼスチュアとも)
①身振り。手振り。手真似。「―を交えた会話」
②思わせぶりな態度。誠実さに欠ける形ばかりの態度。みせかけ。「―ばかりでやる気がない」
シェストフ【Lev Shestov】
ロシアの哲学者。フランスに亡命。真理は理性を超えるものとし、存在の非合理的根源を追求。不安の哲学として第一次大戦後に迎えられた。著「ドストエフスキーとニーチェ(悲劇の哲学)」「キルケゴールと実存哲学」など。(1866〜1938)
しえた・ぐ【虐ぐ・冤ぐ】シヘタグ
(古くはシヘタクと清音)〔他下二〕
①人をむごく扱う。虐待する。しいたげる。徒然草「すべて人を苦しめものを―・ぐることいやしき民の志をも奪ふべからず」
②道理をまげて無実の罪に落とす。続日本紀5「制断理に合ひ、獄訟冤しえたくることなく」
③征服する。平家物語12「毎度に味方おひ落されて、敵を―・ぐるに及ばず」
ジエチル‐エーテル【diethyl ether】
(→)エチル‐エーテルに同じ。
し‐エチル‐なまり【四エチル鉛】
(→)テトラエチル鉛に同じ。
し‐えつ【私謁】
天子などに私事で謁見すること。
ジェッダ【Jedda】
サウジ‐アラビア西部、ヘジャズ地方の紅海に臨む港湾都市。イスラムの聖地メッカの外港。ジッダ。人口82万4千(1992)。
ジェット【jet】
①孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物。噴流。
②素粒子物理学で、狭い立体角内に集中して、多数のハドロン群の発生する現象。また、そのハドロン群。
③〔天〕原始星やクエーサーなどから高速で噴出するジェット1状のガス流。
④ジェット機の略。
⇒ジェット‐エンジン【jet engine】
⇒ジェット‐き【ジェット機】
⇒ジェット‐きりゅう【ジェット気流】
⇒ジェット‐コースター
⇒ジェット‐ストリーム【jet stream】
⇒ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】
⇒ジェット‐フォイル【jetfoil】
⇒ジェット‐ポンプ
⇒ジェット‐ルート【jet route】
ジェット‐エンジン【jet engine】
空気を圧縮し、燃料を吹き込んで燃焼させ、排気を高速で噴出させてその反作用として推進力を得る航空用発動機。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐き【ジェット機】
ジェット‐エンジンを推進装置とする航空機。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐きりゅう【ジェット気流】‥リウ
中緯度の対流圏上部に吹く強い西風。風速は冬には毎秒80メートル以上に達する。ジェット‐ストリーム。→偏西風帯。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐コースター
(和製語jet coaster)遊園地などの遊戯設備で、上下左右に曲がりくねったレール上を急スピードで走る滑走車。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ストリーム【jet stream】
(→)ジェット気流に同じ。
ジェットストリーム
撮影:NASA/STScI
 ⇒ジェット【jet】
ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】‥レウ
ジェット‐エンジンに使用する燃料。ガソリンと灯油を混合して製する。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐フォイル【jetfoil】
吸いこんだ海水を後方に噴射して推進力を得る水中翼船。翼は水中に全没し、時速80キロメートル以上の高速で航走する。商標名。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ポンプ
(jet pump)細い円錐形の筒口から高圧の蒸気・圧縮空気などを噴出させ、その勢いで他の流体を誘い出す形式のポンプ。噴射ポンプ。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ルート【jet route】
高高度(2万4000フィート以上)を飛行するジェット旅客機のために設定された航空路。
⇒ジェット【jet】
ジェトロ【JETRO】
(Japan External Trade Organization)海外市場の調査、日本商品の宣伝などを行う独立行政法人。正式には日本貿易振興機構。1954年日本海外貿易振興会として設立、58年日本貿易振興会に改組。98年アジア経済研究所と統合、2003年独立行政法人となり、現名称。
シエナ【Siena】
イタリア中部、トスカーナ地方の都市。ゴシック期・ルネサンス期の建築・美術品に富む。
⇒シエナ‐は【シエナ派】
シエナ‐は【シエナ派】
(Scuola Senese イタリア)中世末期からルネサンス期にかけて、シエナを中心に活動した画派。優雅で装飾的な画風が特色。ドゥッチオやマルティーニらが代表的画家。
⇒シエナ【Siena】
ジェニーヴァ【Geneva】
ジュネーヴの英語名。
シェニール‐いと【シェニール糸】
(シェニール(chenille フランス)は毛虫の意)ビロード状にけば立てた組糸。外見が毛虫に似る。装飾用あるいはカーペット・肩掛・襟巻の製織用。チンコール糸。毛虫糸。
シェニエ【André de Chénier】
フランスの詩人。母はギリシア人。フランス革命に参加、断頭台で処刑。詩は死後発表。作「悲歌」「牧歌」など。(1762〜1794)
ジェネラル【general】
⇒ゼネラル
ジェネリック‐いやくひん【ジェネリック医薬品】
(generic drug)先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。
ジェネレーション【generation】
世代。また、同世代の人々。ゼネレーション。
⇒ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】
ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】
世代間に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。
⇒ジェネレーション【generation】
ジェノア【Genoa】
ジェノヴァの英語名。
ジェノヴァ【Genova】
イタリア北西部、同名の湾に臨む都市。地中海最古の港の一つ。コロンブスの生地。ミラノ・トリノとともに「工業の三角形地帯」の一角をなす。人口60万3千(2004)。英語名ジェノア。
ジェノサイド【genocide】
(「ジェノ」は人びと、「サイド」は殺害の意)集団殺戮さつりく。
⇒ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】
ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】‥デウ‥
正式には「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」。第二次大戦の経験から、国民・人種・民族ならびに宗教上の集団を迫害し殺害する行為を国際犯罪とし、各国協力のもとに防止・処罰しようというもので、1948年12月の国連総会で採択。
⇒ジェノサイド【genocide】
シェパード【shepherd】
(「羊飼い」の意)イヌの一品種。肩高約60センチメートルで、耳は立ち、全体にオオカミに似る。歴史は6000年前にさかのぼる。番犬・警察犬・軍用犬などとして有用。セパード。ジャーマン‐シェパード。アルサチアン。
シェフ【chef フランス】
(頭かしらの意)コック長。
ジェファソン【Thomas Jefferson】
アメリカ合衆国第3代大統領(1801〜1809)。1776年、独立宣言を起草。駐仏公使・初代国務長官・副大統領を歴任。大統領在任中にルイジアナを購入。晩年ヴァージニア大学総長。(1743〜1826)
シェフィールド【Sheffield】
イギリス、イングランド北部の都市。ヨークシャー地方南部に位置し、鉄鋼業のほか刃物製造が盛ん。人口53万(1996)。
シェフチェンコ【Taras G. Shevchenko】
ウクライナの国民詩人・画家。スラヴ民族の平等な団結を訴える政治結社に参加し、10年間の流刑を経験。詩によってウクライナの民族意識を鼓吹。詩集「吟遊詩人(コブザーリ)」など。(1814〜1861)
ジェフリー‐ビーン【Geoffrey Beene】
⇒ビーン
シェフレラ【Schefflera】
ウコギ科の観葉植物。常緑低木で光沢ある革質の掌状葉をつける。原産は南アジア。日本では鉢植とする。カポックと呼ぶことがあるが、パンヤ科のカポックとの誤認。フカノキ。
シェヘラザード【Shahrazād】
①「アラビアン‐ナイト」に、語り手として登場する女性。大臣の娘で、のち王妃。シャハラザード。
②リムスキー=コルサコフ作曲の交響組曲。1888年作曲。1に取材した標題音楽。シェエラザード。
リムスキー‐コルサコフ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ねんりょう【ジェット燃料】‥レウ
ジェット‐エンジンに使用する燃料。ガソリンと灯油を混合して製する。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐フォイル【jetfoil】
吸いこんだ海水を後方に噴射して推進力を得る水中翼船。翼は水中に全没し、時速80キロメートル以上の高速で航走する。商標名。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ポンプ
(jet pump)細い円錐形の筒口から高圧の蒸気・圧縮空気などを噴出させ、その勢いで他の流体を誘い出す形式のポンプ。噴射ポンプ。
⇒ジェット【jet】
ジェット‐ルート【jet route】
高高度(2万4000フィート以上)を飛行するジェット旅客機のために設定された航空路。
⇒ジェット【jet】
ジェトロ【JETRO】
(Japan External Trade Organization)海外市場の調査、日本商品の宣伝などを行う独立行政法人。正式には日本貿易振興機構。1954年日本海外貿易振興会として設立、58年日本貿易振興会に改組。98年アジア経済研究所と統合、2003年独立行政法人となり、現名称。
シエナ【Siena】
イタリア中部、トスカーナ地方の都市。ゴシック期・ルネサンス期の建築・美術品に富む。
⇒シエナ‐は【シエナ派】
シエナ‐は【シエナ派】
(Scuola Senese イタリア)中世末期からルネサンス期にかけて、シエナを中心に活動した画派。優雅で装飾的な画風が特色。ドゥッチオやマルティーニらが代表的画家。
⇒シエナ【Siena】
ジェニーヴァ【Geneva】
ジュネーヴの英語名。
シェニール‐いと【シェニール糸】
(シェニール(chenille フランス)は毛虫の意)ビロード状にけば立てた組糸。外見が毛虫に似る。装飾用あるいはカーペット・肩掛・襟巻の製織用。チンコール糸。毛虫糸。
シェニエ【André de Chénier】
フランスの詩人。母はギリシア人。フランス革命に参加、断頭台で処刑。詩は死後発表。作「悲歌」「牧歌」など。(1762〜1794)
ジェネラル【general】
⇒ゼネラル
ジェネリック‐いやくひん【ジェネリック医薬品】
(generic drug)先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。
ジェネレーション【generation】
世代。また、同世代の人々。ゼネレーション。
⇒ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】
ジェネレーション‐ギャップ【generation gap】
世代間に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。
⇒ジェネレーション【generation】
ジェノア【Genoa】
ジェノヴァの英語名。
ジェノヴァ【Genova】
イタリア北西部、同名の湾に臨む都市。地中海最古の港の一つ。コロンブスの生地。ミラノ・トリノとともに「工業の三角形地帯」の一角をなす。人口60万3千(2004)。英語名ジェノア。
ジェノサイド【genocide】
(「ジェノ」は人びと、「サイド」は殺害の意)集団殺戮さつりく。
⇒ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】
ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】‥デウ‥
正式には「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」。第二次大戦の経験から、国民・人種・民族ならびに宗教上の集団を迫害し殺害する行為を国際犯罪とし、各国協力のもとに防止・処罰しようというもので、1948年12月の国連総会で採択。
⇒ジェノサイド【genocide】
シェパード【shepherd】
(「羊飼い」の意)イヌの一品種。肩高約60センチメートルで、耳は立ち、全体にオオカミに似る。歴史は6000年前にさかのぼる。番犬・警察犬・軍用犬などとして有用。セパード。ジャーマン‐シェパード。アルサチアン。
シェフ【chef フランス】
(頭かしらの意)コック長。
ジェファソン【Thomas Jefferson】
アメリカ合衆国第3代大統領(1801〜1809)。1776年、独立宣言を起草。駐仏公使・初代国務長官・副大統領を歴任。大統領在任中にルイジアナを購入。晩年ヴァージニア大学総長。(1743〜1826)
シェフィールド【Sheffield】
イギリス、イングランド北部の都市。ヨークシャー地方南部に位置し、鉄鋼業のほか刃物製造が盛ん。人口53万(1996)。
シェフチェンコ【Taras G. Shevchenko】
ウクライナの国民詩人・画家。スラヴ民族の平等な団結を訴える政治結社に参加し、10年間の流刑を経験。詩によってウクライナの民族意識を鼓吹。詩集「吟遊詩人(コブザーリ)」など。(1814〜1861)
ジェフリー‐ビーン【Geoffrey Beene】
⇒ビーン
シェフレラ【Schefflera】
ウコギ科の観葉植物。常緑低木で光沢ある革質の掌状葉をつける。原産は南アジア。日本では鉢植とする。カポックと呼ぶことがあるが、パンヤ科のカポックとの誤認。フカノキ。
シェヘラザード【Shahrazād】
①「アラビアン‐ナイト」に、語り手として登場する女性。大臣の娘で、のち王妃。シャハラザード。
②リムスキー=コルサコフ作曲の交響組曲。1888年作曲。1に取材した標題音楽。シェエラザード。
リムスキー‐コルサコフ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 →交響組曲「シェエラザード」王子と王女
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
しえやシヱヤ
〔感〕
嘆息・断念・決意などのときに発する語。ええままよ。ええい。万葉集4「かくしあらば―わが背子将来おくもいかにあらめ」
ジェラート【gelato イタリア】
イタリア風のアイス‐クリーム・シャーベット。
ジェラシー【jealousy】
ねたみ。嫉妬しっと。やきもち。
シェラック【shellac】
ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。
シエラ‐ネバダ【Sierra Nevada スペイン】
(「雪に被われた山脈」の意)
①スペイン南部の山脈。イベリア半島最高のムラセン山(3482メートル)がある。
②アメリカ、カリフォルニア州の山脈。延長650キロメートル、最高峰はホイットニー山(4418メートル)。西側にサン‐ホーキン構造谷が併走する。
シエラ‐マドレ【Sierra Madre】
メキシコの北西から南東に連なる山脈。長さ約2400キロメートル。東・西・南の三つの山脈からなり、その間にメキシコ高原が広がる。
シエラ‐レオネ【Sierra Leone】
アフリカの西岸にある共和国。1961年イギリスから独立、71年共和制。面積7万1000平方キロメートル。人口528万(2003)。首都フリータウン。→アフリカ(図)
ジェランド【gerund】
〔言〕(→)動名詞に同じ。
シェリー【sherry】
(原産地Jerez(Xerez)の転訛)スペイン南西部、アンダルシア地方原産のアルコール度を高めた白葡萄酒。また広く、これに類似する白葡萄酒。
シェリー【Mary Wollstonecraft Shelley】
イギリスの女性作家。ゴドウィン夫妻の子。P.B.シェリーの2番目の妻。人造人間の登場する小説「フランケンシュタイン」など。(1797〜1851)
シェリー【Percy Bysshe Shelley】
イギリスの詩人。キーツ・バイロンと共にロマン派の代表。革命的情熱や神秘主義、純粋な抒情性などをもつ。イタリア滞在中にボートが転覆して溺死。詩「西風の賦」「雲雀に寄す」や劇詩「チェンチ」「解放されたプロメテウス」など。(1792〜1822)
ジェリー【jelly】
⇒ゼリー
ジェリコー【Théodore Géricault】
フランスの画家。ロマン主義運動の先駆者。現実の人間の描写と明暗の鮮明な色彩で古典派に対抗。代表作「メデューズ号の筏」。(1791〜1824)
シェリダン【Richard Brinsley Sheridan】
イギリスの劇作家。アイルランドのダブリン生れ。18世紀の喜劇を代表。作「恋仇」「悪口学校」など。(1751〜1816)
シェリフ【sheriff】
保安官。
シェリング【Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling】
ドイツの哲学者。ドイツ観念論およびロマン派の代表者。自然をも自己形成の主体と捉え、自然と精神が絶対的に同一であるとする同一哲学を主張。この同一性は芸術的・知的直観によって把握されるとした。後には悪や神を含めた現実存在そのものの根拠を歴史的・神話論的展望のもとで問う積極哲学に向かった。著「自然哲学の理念」「超越論的観念論の体系」「人間的自由の本質」「啓示の哲学」など。(1775〜1854)
シェル【shell】
①貝・卵などの殻。
②軽快な競漕用のボート。
⇒シェル‐こうぞう【シェル構造】
⇒シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】
ジェル【gel】
ゼリー状のもの。特に、整髪料や薬品に言う。→ゲル
シェル‐こうぞう【シェル構造】‥ザウ
曲面の薄板を外殻(シェル)に用いた建築構造。支柱間隔を大きくした屋根などに用いる。
⇒シェル【shell】
ジェルジンスキー【Feliks E. Dzerzhinskii】
ソ連の政治家。ポーランド人で、ボリシェヴィキの一員。ロシア革命後、チェカの初代議長。(1877〜1926)
シェルター【shelter】
避難所。防空壕。「核―」
シェルパ【Sherpa】
ネパール東部を中心にインドの西ベンガル地域を含むヒマラヤ南面高地に住む少数民族。ジャガいも・大麦などの畑作農耕、山羊の移牧とチベット・ネパール間の仲介交易に従事。また、登山隊の案内人・荷役にやく人としても活躍。言語はチベット‐ビルマ語系に属し、宗教はチベット仏教。
シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】‥ハフ
(shell mold process)精密鋳造法の一つ。第二次大戦中ドイツで完成。熱硬化性樹脂を配合した合成砂を金型の上に撒まき、これを熱硬化させて作った鋳型を組み合わせて殻を作り、この中に溶融金属を鋳込むもの。鋳肌・精度ともに良好。量産が容易で安価。クローニング法。
⇒シェル【shell】
ジェロニモ【Geronimo】
アメリカ合衆国の軍事的支配に抵抗した最後の先住アメリカ人(アパッチ‐インディアン)指導者。(1829〜1909)
シェワルナゼ【Eduard A. Shevardnadze】
ソ連・グルジアの政治家。ゴルバチョフのもとで1985年からソ連共産党政治局員・ソ連外相。ソ連崩壊後グルジアに戻り、大統領、2003年失脚。(1928〜)
し‐えん【支援】‥ヱン
ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」
⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】
⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】
し‐えん【四遠】‥ヱン
四方の遠いはて。
し‐えん【四縁】
〔仏〕ものごとを生じさせる原因(縁)を四種に分類したもの。直接的原因である因縁、性質が結果と等しく、かつ時間的に直接連続して結果を生ずる原因である等無間縁とうむけんえん、認識を生じさせる認識対象である所縁縁しょえんねん、間接的原因である増上縁。
し‐えん【私怨】‥ヱン
個人的なうらみ。「―を抱く」
し‐えん【紙鳶】
凧たこ。いかのぼり。〈[季]新年〉
し‐えん【紫煙】
(紫色の煙の意から)タバコの煙。「―をくゆらす」
し‐えん【詩筵】
詩歌・俳句などの会合の席。文人会合の席。
し‐えん【試演】
演劇などを試験的に上演すること。
し‐えん【資縁】
仏道修行の助けとなる衣食住をいう。一言芳談「―省略のうへ、形のごとくの朝喰あさげし」
し‐えん【賜宴】
酒宴を賜ること。また、その酒宴。
じ‐えん【侍宴】
酒宴の席にはべること。
じえん【慈円】‥ヱン
平安末期〜鎌倉初期の僧。藤原忠通の子。前後4度、天台座主。四天王寺別当。勅諡号は慈鎮。和歌にすぐれ、即吟、修辞の練達、表出の流麗が特色。家集「拾玉集」のほか、独特の歴史観を示した史論「愚管抄」がある。(1155〜1225)
→著作:『愚管抄』
ジエン【diene】
1分子中に炭素原子間の二重結合を2個含む化合物の総称。共役二重結合をもつジエンは共役ジエンと呼ぶ。
⇒ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】
しえんか‐けいそ【四塩化珪素】‥クワ‥
分子式SiCl4 塩素の気流中で、ケイ素・炭化ケイ素、または炭素と無水ケイ酸との混合物を熱して得られる無色発煙性の刺激臭ある液体。単体のケイ素、シリコーンの原料。
しえんか‐たんそ【四塩化炭素】‥クワ‥
分子式CCl4 クロロホルム臭のある無色の液体。工業的には二硫化炭素に塩素を作用させて製造。脂肪・樹脂・タールなどをよく溶解するので溶剤として利用。引火性なく消火剤にも用いる。
シェンキェーヴィチ【Henryk Sienkiewicz】
ポーランドの小説家。17世紀ポーランドを描いた歴史小説で人気を博し、ポーランド人の愛国心を鼓舞した。代表作「クオ‐ヴァディス」。ノーベル賞。(1846〜1916)
ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】‥クワ‥
炭素原子間の二重結合を2個含む炭化水素の総称。ジオレフィンともいう。ブタジエン・イソプレンのように共役二重結合をもつものは重合しやすく、合成ゴムの原料。
⇒ジエン【diene】
しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥
航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。
⇒し‐えん【支援】
ジェンダー【gender】
①生物学的な性別を示すセックスに対して、社会的・文化的に形成される性別。作られた男らしさ・女らしさ。「―‐ギャップ」
②〔言〕(→)性4に同じ。
⇒ジェンダー‐バランス【gender balance】
⇒ジェンダー‐フリー
ジェンダー‐バランス【gender balance】
ある組織・集団内での男女の数の均衡。
⇒ジェンダー【gender】
ジェンダー‐フリー
(和製語gender free)社会的・文化的に形成された性差別の克服を目指す考え。
⇒ジェンダー【gender】
ジェンティーレ【Giovanni Gentile】
イタリアの哲学者・政治家。新ヘーゲル学派に属し、哲学を歴史の自己展開と見て、師クローチェに反して自由主義からファシズムへ転向後に暗殺。著「芸術哲学」「純粋行為としての精神の一般理論」「論理学体系」など。(1875〜1944)
ジ‐エンド【the end】
終幕。一巻の終り。
ジェントリー【gentry】
イギリス封建制のもとでは、騎士身分とほぼ同じ下級貴族。絶対主義時代には、ヨーマンと貴族の中間に位置する地主・名望家として地方行政の担い手となり、議会の下院でも指導的役割を演じた。郷紳と訳す。
ジェントルマン【gentleman】
紳士。殿方。ゼントルマン。↔レディー
ジェンナー【Edward Jenner】
イギリスの外科医。牛痘に感染した者が天然痘に対して免疫になることに気づいて、1796年に牛痘種痘法を発明。(1749〜1823)
しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥
障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。
⇒し‐えん【支援】
しお【入】シホ
物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」
しお【塩】シホ
①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。
②塩加減。しおけ。「―があまい」
⇒塩が浸む
しお【潮・汐】シホ
(「塩」と同語源)
①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」
②海水。海流。「―の流れ」
③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」
④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。
⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」
◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。
⇒潮を踏む
しお‐あい【潮合】シホアヒ
①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」
②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」
③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」
しお‐あし【潮足】シホ‥
潮汐の干満の速さ。「―が速い」
しお‐あし【潮蘆】シホ‥
海浜に生えている蘆。
しお‐あじ【塩味】シホアヂ
塩でつけた味。「―が強い」
しお‐あび【潮浴び】シホ‥
しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉
しお‐あみ【潮浴み】シホ‥
(→)「しおあび」に同じ。
しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥
塩漬にしたアユ。
しお‐あらし【潮嵐】シホ‥
吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」
しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥
⇒しおなわ
しお‐あん【塩餡】シホ‥
塩で味をつけた餡。
しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥
食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。
しおい【塩井】シホヰ
姓氏の一つ。
⇒しおい‐うこう【塩井雨江】
しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ
詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)
⇒しおい【塩井】
ジオイド【geoid】
地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面とほぼ一致する曲面。回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す。地球形。
しお‐いり【潮入】シホ‥
池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。
⇒しおいり‐いけ【潮入池】
しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥
海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」
⇒しお‐いり【潮入】
しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥
拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」
し‐おう【四王】‥ワウ
①四天王の略。
②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。
⇒しおう‐てん【四王天】
し‐おう【死王】‥ワウ
①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。
②死んだ王。
し‐おう【嗣王】‥ワウ
世を嗣ついだ王。
し‐おう【雌黄】‥ワウ
①石黄せきおうの古名。
②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。
③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。
じ‐おう【地黄】ヂワウ
ゴマノハグサ科の多年草。中国原産の薬用植物。地下茎は肥厚、根生葉は楕円形、表面にしわが多い。初夏、茎頂に紫紅色で筒状の美花を数個開く。茎・花冠に腺毛が密生する。根茎は著名な漢方生薬で、補血・強壮、また血糖降下作用がある。根茎の表面は赤黄色で、乾燥すれば黒色。特異な匂いがあり、味は初めわずかに甘く、後やや苦い。サオヒメ。アカヤジオウ。
じおう
→交響組曲「シェエラザード」王子と王女
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
しえやシヱヤ
〔感〕
嘆息・断念・決意などのときに発する語。ええままよ。ええい。万葉集4「かくしあらば―わが背子将来おくもいかにあらめ」
ジェラート【gelato イタリア】
イタリア風のアイス‐クリーム・シャーベット。
ジェラシー【jealousy】
ねたみ。嫉妬しっと。やきもち。
シェラック【shellac】
ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。
シエラ‐ネバダ【Sierra Nevada スペイン】
(「雪に被われた山脈」の意)
①スペイン南部の山脈。イベリア半島最高のムラセン山(3482メートル)がある。
②アメリカ、カリフォルニア州の山脈。延長650キロメートル、最高峰はホイットニー山(4418メートル)。西側にサン‐ホーキン構造谷が併走する。
シエラ‐マドレ【Sierra Madre】
メキシコの北西から南東に連なる山脈。長さ約2400キロメートル。東・西・南の三つの山脈からなり、その間にメキシコ高原が広がる。
シエラ‐レオネ【Sierra Leone】
アフリカの西岸にある共和国。1961年イギリスから独立、71年共和制。面積7万1000平方キロメートル。人口528万(2003)。首都フリータウン。→アフリカ(図)
ジェランド【gerund】
〔言〕(→)動名詞に同じ。
シェリー【sherry】
(原産地Jerez(Xerez)の転訛)スペイン南西部、アンダルシア地方原産のアルコール度を高めた白葡萄酒。また広く、これに類似する白葡萄酒。
シェリー【Mary Wollstonecraft Shelley】
イギリスの女性作家。ゴドウィン夫妻の子。P.B.シェリーの2番目の妻。人造人間の登場する小説「フランケンシュタイン」など。(1797〜1851)
シェリー【Percy Bysshe Shelley】
イギリスの詩人。キーツ・バイロンと共にロマン派の代表。革命的情熱や神秘主義、純粋な抒情性などをもつ。イタリア滞在中にボートが転覆して溺死。詩「西風の賦」「雲雀に寄す」や劇詩「チェンチ」「解放されたプロメテウス」など。(1792〜1822)
ジェリー【jelly】
⇒ゼリー
ジェリコー【Théodore Géricault】
フランスの画家。ロマン主義運動の先駆者。現実の人間の描写と明暗の鮮明な色彩で古典派に対抗。代表作「メデューズ号の筏」。(1791〜1824)
シェリダン【Richard Brinsley Sheridan】
イギリスの劇作家。アイルランドのダブリン生れ。18世紀の喜劇を代表。作「恋仇」「悪口学校」など。(1751〜1816)
シェリフ【sheriff】
保安官。
シェリング【Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling】
ドイツの哲学者。ドイツ観念論およびロマン派の代表者。自然をも自己形成の主体と捉え、自然と精神が絶対的に同一であるとする同一哲学を主張。この同一性は芸術的・知的直観によって把握されるとした。後には悪や神を含めた現実存在そのものの根拠を歴史的・神話論的展望のもとで問う積極哲学に向かった。著「自然哲学の理念」「超越論的観念論の体系」「人間的自由の本質」「啓示の哲学」など。(1775〜1854)
シェル【shell】
①貝・卵などの殻。
②軽快な競漕用のボート。
⇒シェル‐こうぞう【シェル構造】
⇒シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】
ジェル【gel】
ゼリー状のもの。特に、整髪料や薬品に言う。→ゲル
シェル‐こうぞう【シェル構造】‥ザウ
曲面の薄板を外殻(シェル)に用いた建築構造。支柱間隔を大きくした屋根などに用いる。
⇒シェル【shell】
ジェルジンスキー【Feliks E. Dzerzhinskii】
ソ連の政治家。ポーランド人で、ボリシェヴィキの一員。ロシア革命後、チェカの初代議長。(1877〜1926)
シェルター【shelter】
避難所。防空壕。「核―」
シェルパ【Sherpa】
ネパール東部を中心にインドの西ベンガル地域を含むヒマラヤ南面高地に住む少数民族。ジャガいも・大麦などの畑作農耕、山羊の移牧とチベット・ネパール間の仲介交易に従事。また、登山隊の案内人・荷役にやく人としても活躍。言語はチベット‐ビルマ語系に属し、宗教はチベット仏教。
シェル‐モールド‐ほう【シェルモールド法】‥ハフ
(shell mold process)精密鋳造法の一つ。第二次大戦中ドイツで完成。熱硬化性樹脂を配合した合成砂を金型の上に撒まき、これを熱硬化させて作った鋳型を組み合わせて殻を作り、この中に溶融金属を鋳込むもの。鋳肌・精度ともに良好。量産が容易で安価。クローニング法。
⇒シェル【shell】
ジェロニモ【Geronimo】
アメリカ合衆国の軍事的支配に抵抗した最後の先住アメリカ人(アパッチ‐インディアン)指導者。(1829〜1909)
シェワルナゼ【Eduard A. Shevardnadze】
ソ連・グルジアの政治家。ゴルバチョフのもとで1985年からソ連共産党政治局員・ソ連外相。ソ連崩壊後グルジアに戻り、大統領、2003年失脚。(1928〜)
し‐えん【支援】‥ヱン
ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」
⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】
⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】
し‐えん【四遠】‥ヱン
四方の遠いはて。
し‐えん【四縁】
〔仏〕ものごとを生じさせる原因(縁)を四種に分類したもの。直接的原因である因縁、性質が結果と等しく、かつ時間的に直接連続して結果を生ずる原因である等無間縁とうむけんえん、認識を生じさせる認識対象である所縁縁しょえんねん、間接的原因である増上縁。
し‐えん【私怨】‥ヱン
個人的なうらみ。「―を抱く」
し‐えん【紙鳶】
凧たこ。いかのぼり。〈[季]新年〉
し‐えん【紫煙】
(紫色の煙の意から)タバコの煙。「―をくゆらす」
し‐えん【詩筵】
詩歌・俳句などの会合の席。文人会合の席。
し‐えん【試演】
演劇などを試験的に上演すること。
し‐えん【資縁】
仏道修行の助けとなる衣食住をいう。一言芳談「―省略のうへ、形のごとくの朝喰あさげし」
し‐えん【賜宴】
酒宴を賜ること。また、その酒宴。
じ‐えん【侍宴】
酒宴の席にはべること。
じえん【慈円】‥ヱン
平安末期〜鎌倉初期の僧。藤原忠通の子。前後4度、天台座主。四天王寺別当。勅諡号は慈鎮。和歌にすぐれ、即吟、修辞の練達、表出の流麗が特色。家集「拾玉集」のほか、独特の歴史観を示した史論「愚管抄」がある。(1155〜1225)
→著作:『愚管抄』
ジエン【diene】
1分子中に炭素原子間の二重結合を2個含む化合物の総称。共役二重結合をもつジエンは共役ジエンと呼ぶ。
⇒ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】
しえんか‐けいそ【四塩化珪素】‥クワ‥
分子式SiCl4 塩素の気流中で、ケイ素・炭化ケイ素、または炭素と無水ケイ酸との混合物を熱して得られる無色発煙性の刺激臭ある液体。単体のケイ素、シリコーンの原料。
しえんか‐たんそ【四塩化炭素】‥クワ‥
分子式CCl4 クロロホルム臭のある無色の液体。工業的には二硫化炭素に塩素を作用させて製造。脂肪・樹脂・タールなどをよく溶解するので溶剤として利用。引火性なく消火剤にも用いる。
シェンキェーヴィチ【Henryk Sienkiewicz】
ポーランドの小説家。17世紀ポーランドを描いた歴史小説で人気を博し、ポーランド人の愛国心を鼓舞した。代表作「クオ‐ヴァディス」。ノーベル賞。(1846〜1916)
ジエンけい‐たんかすいそ【ジエン系炭化水素】‥クワ‥
炭素原子間の二重結合を2個含む炭化水素の総称。ジオレフィンともいう。ブタジエン・イソプレンのように共役二重結合をもつものは重合しやすく、合成ゴムの原料。
⇒ジエン【diene】
しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥
航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。
⇒し‐えん【支援】
ジェンダー【gender】
①生物学的な性別を示すセックスに対して、社会的・文化的に形成される性別。作られた男らしさ・女らしさ。「―‐ギャップ」
②〔言〕(→)性4に同じ。
⇒ジェンダー‐バランス【gender balance】
⇒ジェンダー‐フリー
ジェンダー‐バランス【gender balance】
ある組織・集団内での男女の数の均衡。
⇒ジェンダー【gender】
ジェンダー‐フリー
(和製語gender free)社会的・文化的に形成された性差別の克服を目指す考え。
⇒ジェンダー【gender】
ジェンティーレ【Giovanni Gentile】
イタリアの哲学者・政治家。新ヘーゲル学派に属し、哲学を歴史の自己展開と見て、師クローチェに反して自由主義からファシズムへ転向後に暗殺。著「芸術哲学」「純粋行為としての精神の一般理論」「論理学体系」など。(1875〜1944)
ジ‐エンド【the end】
終幕。一巻の終り。
ジェントリー【gentry】
イギリス封建制のもとでは、騎士身分とほぼ同じ下級貴族。絶対主義時代には、ヨーマンと貴族の中間に位置する地主・名望家として地方行政の担い手となり、議会の下院でも指導的役割を演じた。郷紳と訳す。
ジェントルマン【gentleman】
紳士。殿方。ゼントルマン。↔レディー
ジェンナー【Edward Jenner】
イギリスの外科医。牛痘に感染した者が天然痘に対して免疫になることに気づいて、1796年に牛痘種痘法を発明。(1749〜1823)
しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥
障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。
⇒し‐えん【支援】
しお【入】シホ
物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」
しお【塩】シホ
①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。
②塩加減。しおけ。「―があまい」
⇒塩が浸む
しお【潮・汐】シホ
(「塩」と同語源)
①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」
②海水。海流。「―の流れ」
③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」
④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。
⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」
◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。
⇒潮を踏む
しお‐あい【潮合】シホアヒ
①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」
②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」
③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」
しお‐あし【潮足】シホ‥
潮汐の干満の速さ。「―が速い」
しお‐あし【潮蘆】シホ‥
海浜に生えている蘆。
しお‐あじ【塩味】シホアヂ
塩でつけた味。「―が強い」
しお‐あび【潮浴び】シホ‥
しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉
しお‐あみ【潮浴み】シホ‥
(→)「しおあび」に同じ。
しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥
塩漬にしたアユ。
しお‐あらし【潮嵐】シホ‥
吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」
しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥
⇒しおなわ
しお‐あん【塩餡】シホ‥
塩で味をつけた餡。
しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥
食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。
しおい【塩井】シホヰ
姓氏の一つ。
⇒しおい‐うこう【塩井雨江】
しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ
詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)
⇒しおい【塩井】
ジオイド【geoid】
地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面とほぼ一致する曲面。回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す。地球形。
しお‐いり【潮入】シホ‥
池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。
⇒しおいり‐いけ【潮入池】
しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥
海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」
⇒しお‐いり【潮入】
しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥
拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」
し‐おう【四王】‥ワウ
①四天王の略。
②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。
⇒しおう‐てん【四王天】
し‐おう【死王】‥ワウ
①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。
②死んだ王。
し‐おう【嗣王】‥ワウ
世を嗣ついだ王。
し‐おう【雌黄】‥ワウ
①石黄せきおうの古名。
②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。
③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。
じ‐おう【地黄】ヂワウ
ゴマノハグサ科の多年草。中国原産の薬用植物。地下茎は肥厚、根生葉は楕円形、表面にしわが多い。初夏、茎頂に紫紅色で筒状の美花を数個開く。茎・花冠に腺毛が密生する。根茎は著名な漢方生薬で、補血・強壮、また血糖降下作用がある。根茎の表面は赤黄色で、乾燥すれば黒色。特異な匂いがあり、味は初めわずかに甘く、後やや苦い。サオヒメ。アカヤジオウ。
じおう
 ⇒じおう‐がゆ【地黄粥】
⇒じおう‐がん【地黄丸】
⇒じおう‐せん【地黄煎】
しお‐うお【塩魚】シホウヲ
塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。
じおう‐がゆ【地黄粥】ヂワウ‥
地黄の根茎をきざみ入れた粥。正月にこれを食すれば邪気を除くという。
⇒じ‐おう【地黄】
じおう‐がん【地黄丸】ヂワウグワン
地黄を主剤として作った漢方の強壮・補血剤。好色一代女1「いまだ御年も若ふして―の御せんさく」
⇒じ‐おう【地黄】
じおう‐せん【地黄煎】ヂワウ‥
①穀芽の粉に地黄の汁をねり合わせたもの。気血を増すという。くだり。凝煎。
②地黄の汁を加えてねった飴。京都伏見稲荷門前の名産。上方かみがたより下ったので江戸では「くだりあめ」という。
⇒じ‐おう【地黄】
しお‐うち【塩打】シホ‥
大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」
しおう‐てん【四王天】‥ワウ‥
〔仏〕欲界六天の第1。須弥山しゅみせんの中腹にある。→四天王してんのう
⇒し‐おう【四王】
しお‐うに【塩雲丹】シホ‥
ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。
しお‐うみ【潮海】シホ‥
塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」
し‐お・える【為終える】‥ヲヘル
〔他下一〕
することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」
しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥
潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。
ジオーク【William Francis Giauque】
アメリカの物理化学者。酸素の同位体を発見。断熱消磁法により絶対零度に近い温度を得ることに成功、極低温における物質の諸特性の研究に貢献。ノーベル化学賞。(1895〜1982)
しお‐おけ【潮桶】シホヲケ
海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」
しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥
野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」
し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル
〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)
なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」
しおお‐にシホホ‥
〔副〕
涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」
しお‐がい【塩貝】シホガヒ
塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」
しお‐がい【潮貝】シホガヒ
海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」
しお‐がい【潮間】シホガヒ
(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」
しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥
漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。
しお‐がかり【潮繋り】シホ‥
潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」
しお‐かげん【塩加減】シホ‥
ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。
⇒じおう‐がゆ【地黄粥】
⇒じおう‐がん【地黄丸】
⇒じおう‐せん【地黄煎】
しお‐うお【塩魚】シホウヲ
塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。
じおう‐がゆ【地黄粥】ヂワウ‥
地黄の根茎をきざみ入れた粥。正月にこれを食すれば邪気を除くという。
⇒じ‐おう【地黄】
じおう‐がん【地黄丸】ヂワウグワン
地黄を主剤として作った漢方の強壮・補血剤。好色一代女1「いまだ御年も若ふして―の御せんさく」
⇒じ‐おう【地黄】
じおう‐せん【地黄煎】ヂワウ‥
①穀芽の粉に地黄の汁をねり合わせたもの。気血を増すという。くだり。凝煎。
②地黄の汁を加えてねった飴。京都伏見稲荷門前の名産。上方かみがたより下ったので江戸では「くだりあめ」という。
⇒じ‐おう【地黄】
しお‐うち【塩打】シホ‥
大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」
しおう‐てん【四王天】‥ワウ‥
〔仏〕欲界六天の第1。須弥山しゅみせんの中腹にある。→四天王してんのう
⇒し‐おう【四王】
しお‐うに【塩雲丹】シホ‥
ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。
しお‐うみ【潮海】シホ‥
塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」
し‐お・える【為終える】‥ヲヘル
〔他下一〕
することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」
しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥
潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。
ジオーク【William Francis Giauque】
アメリカの物理化学者。酸素の同位体を発見。断熱消磁法により絶対零度に近い温度を得ることに成功、極低温における物質の諸特性の研究に貢献。ノーベル化学賞。(1895〜1982)
しお‐おけ【潮桶】シホヲケ
海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」
しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥
野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」
し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル
〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)
なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」
しおお‐にシホホ‥
〔副〕
涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」
しお‐がい【塩貝】シホガヒ
塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」
しお‐がい【潮貝】シホガヒ
海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」
しお‐がい【潮間】シホガヒ
(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」
しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥
漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。
しお‐がかり【潮繋り】シホ‥
潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」
しお‐かげん【塩加減】シホ‥
ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。
しぐれ【時雨】🔗⭐🔉
しぐれ【時雨】
(「過ぐる」から出た語で、通り雨の意)
①秋の末から冬の初め頃に、降ったりやんだりする雨。〈[季]冬〉。万葉集8「時待ちてふりし―の雨止みぬ」
②比喩的に、涙を流すこと。「袖の―」
③一しきり続くもののたとえ。「蝉―」
④小督局こごうのつぼねの用いた琴の名。
⑤本阿弥光悦作の名物茶碗の名。
⑥時雨羹しぐれかんの略。
⑦時雨饅頭しぐれまんじゅうの略。
⇒しぐれ‐かん【時雨羹】
⇒しぐれ‐き【時雨忌】
⇒しぐれ‐ごこち【時雨心地】
⇒しぐれ‐づき【時雨月】
⇒しぐれ‐に【時雨煮】
⇒しぐれ‐の‐あき【時雨の秋】
⇒しぐれ‐の‐いろ【時雨の色】
⇒しぐれ‐はまぐり【時雨蛤】
⇒しぐれ‐まんじゅう【時雨饅頭】
しぐれ‐の‐あき【時雨の秋】🔗⭐🔉
しぐれ‐の‐あき【時雨の秋】
時雨の降る秋。万葉集13「九月ながづきの―は」
⇒しぐれ【時雨】
しぐれ‐の‐いろ【時雨の色】🔗⭐🔉
しぐれ‐の‐いろ【時雨の色】
時雨のために色づいた草木の葉色。
⇒しぐれ【時雨】
しぐ・れる【時雨れる】🔗⭐🔉
しぐ・れる【時雨れる】
〔自下一〕[文]しぐ・る(下二)
①しぐれになる。しぐれが降る。源氏物語宿木「うち―・るるにも」
②涙を催す。泣いて涙がこぼれる。源氏物語若菜上「まみのあたりうち―・れて」
じ‐じ【時時】🔗⭐🔉
じ‐じ【時時】
ときどき。おりおり。しばしば。狂言、察化「かやうのことは―あることでござる」
じじ‐こっこく【時時刻刻】‥コク‥🔗⭐🔉
じじ‐こっこく【時時刻刻】‥コク‥
時刻を追って。一刻一刻。次第次第に。「情勢は―変化する」
しだ【時】🔗⭐🔉
しだ【時】
(接尾語「しな」の古語)…の際。…する時。万葉集14「あが面おもの忘れむ―は国はふり嶺ねに立つ雲を見つつ偲はせ」
とき【時】🔗⭐🔉
とき【時】
①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。
②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」
時
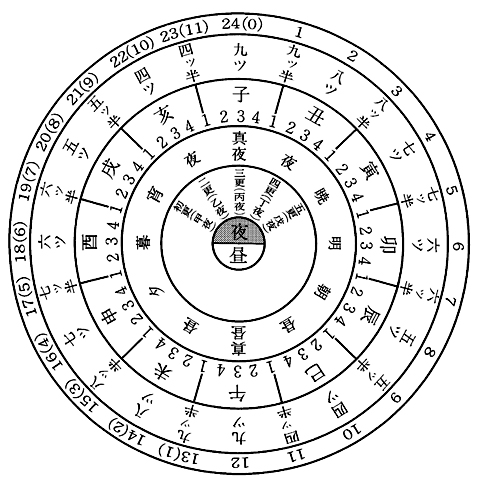 ③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
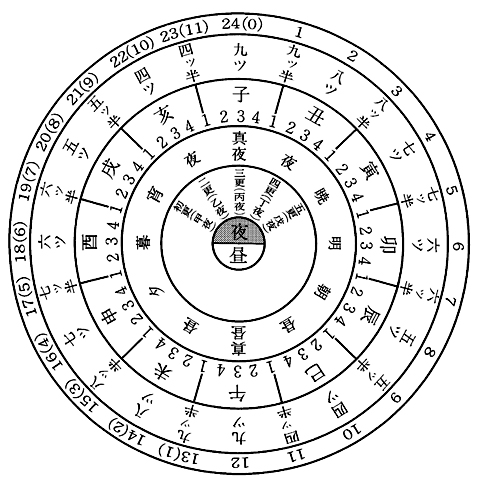 ③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
とき【鬨・時・鯨波】🔗⭐🔉
○時移り事去るときうつりことさる🔗⭐🔉
○時移り事去るときうつりことさる
[陳鴻、長恨歌伝「時移事去、楽尽悲来」]歳月が経過し諸事が変遷する。時世が移り変わる。古今和歌集序「たとひ時移り事去り、楽しび悲しび行きかふとも」
⇒とき【時】
とき‐うま【疾馬・駿馬】
走ることの速い馬。しゅんめ。〈倭名類聚鈔11〉
ときえだ【時枝】
姓氏の一つ。
⇒ときえだ‐もとき【時枝誠記】
ときえだ‐もとき【時枝誠記】
国語学者。東京生れ。京城大・東大・早大教授。新たな言語理論として「言語過程説」を提唱。著「国語学史」「国語学原論」「日本文法」など。(1900〜1967)
時枝誠記
提供:毎日新聞社
 ⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
と‐ぎかい【都議会】‥クワイ
東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。
⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】
とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン
都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。
⇒と‐ぎかい【都議会】
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白
⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
と‐ぎかい【都議会】‥クワイ
東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。
⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】
とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン
都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。
⇒と‐ぎかい【都議会】
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とぎ‐かわ【研革】‥カハ
刃物を研ぐのに用いる革。
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とぎ‐し【研師】
刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とぎ‐しゅう【伽衆】
⇒おとぎしゅう(御伽衆)
どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ
離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」
とき‐しらず【時知らず】
①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。
②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。
③時鮭ときざけの異称。
ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】
(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」
ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ
時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」
とぎ‐じる【磨ぎ汁】
(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。
ときしる‐あめ【時知る雨】
時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」
ときしる‐ぐ【時知る具】
時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」
トキシン【Toxin ドイツ】
(→)毒素。
とき‐すす・める【説き勧める】
〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)
説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」
ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥
鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」
とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】
〔他五〕
①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」
②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」
とき‐せち【時節】
(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」
とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)
土岐善麿
撮影:田沼武能
しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とぎ‐かわ【研革】‥カハ
刃物を研ぐのに用いる革。
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とぎ‐し【研師】
刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とぎ‐しゅう【伽衆】
⇒おとぎしゅう(御伽衆)
どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ
離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」
とき‐しらず【時知らず】
①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。
②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。
③時鮭ときざけの異称。
ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】
(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」
ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ
時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」
とぎ‐じる【磨ぎ汁】
(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。
ときしる‐あめ【時知る雨】
時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」
ときしる‐ぐ【時知る具】
時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」
トキシン【Toxin ドイツ】
(→)毒素。
とき‐すす・める【説き勧める】
〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)
説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」
ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥
鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」
とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】
〔他五〕
①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」
②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」
とき‐せち【時節】
(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」
とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)
土岐善麿
撮影:田沼武能
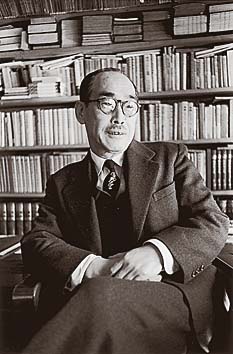 ⇒とき【土岐】
トキソイド【toxoid】
毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。
とき‐そう【鴇草】‥サウ
ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。
ときそば【時蕎麦】
落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。
トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ
(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。
とき‐だいこ【時太鼓】
時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」
とぎ‐だし【研ぎ出し】
①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。
②研出蒔絵まきえの略。
⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】
とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ
蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。
⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】
とぎ‐だ・す【研ぎ出す】
〔他五〕
研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」
とぎ‐たて【研ぎ立て】
研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」
とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】
〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)
刃物などを、念入りに研いで鋭くする。
とき‐たま【時偶】
時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」
とき‐たまご【溶き卵】
生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。
ど‐ぎつ・い
〔形〕
(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐づかさ【時司】
陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
どき‐つ・く
〔自五〕
不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つくばこ【土岐筑波子】
江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。
⇒とき【土岐】
とき‐づけ【時付け】
時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」
とき‐つげ‐どり【時告鳥】
鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」
とき‐つ・ける【説き付ける】
〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)
さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。
とき‐つづみ【時鼓】
時刻を知らせるために打つ鼓。
どきっ‐と
〔副〕
突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
どき‐どき
運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」
どぎ‐どぎ
①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」
②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
とき‐と‐する‐と【時とすると】
場合によっては。ともすると。たまに。
⇒とき【土岐】
トキソイド【toxoid】
毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。
とき‐そう【鴇草】‥サウ
ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。
ときそば【時蕎麦】
落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。
トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ
(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。
とき‐だいこ【時太鼓】
時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」
とぎ‐だし【研ぎ出し】
①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。
②研出蒔絵まきえの略。
⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】
とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ
蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。
⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】
とぎ‐だ・す【研ぎ出す】
〔他五〕
研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」
とぎ‐たて【研ぎ立て】
研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」
とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】
〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)
刃物などを、念入りに研いで鋭くする。
とき‐たま【時偶】
時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」
とき‐たまご【溶き卵】
生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。
ど‐ぎつ・い
〔形〕
(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐づかさ【時司】
陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
どき‐つ・く
〔自五〕
不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つくばこ【土岐筑波子】
江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。
⇒とき【土岐】
とき‐づけ【時付け】
時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」
とき‐つげ‐どり【時告鳥】
鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」
とき‐つ・ける【説き付ける】
〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)
さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。
とき‐つづみ【時鼓】
時刻を知らせるために打つ鼓。
どきっ‐と
〔副〕
突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
どき‐どき
運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」
どぎ‐どぎ
①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」
②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
とき‐と‐する‐と【時とすると】
場合によっては。ともすると。たまに。
 ⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
と‐ぎかい【都議会】‥クワイ
東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。
⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】
とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン
都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。
⇒と‐ぎかい【都議会】
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白
⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
と‐ぎかい【都議会】‥クワイ
東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。
⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】
とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン
都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。
⇒と‐ぎかい【都議会】
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とぎ‐かわ【研革】‥カハ
刃物を研ぐのに用いる革。
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とぎ‐し【研師】
刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とぎ‐しゅう【伽衆】
⇒おとぎしゅう(御伽衆)
どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ
離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」
とき‐しらず【時知らず】
①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。
②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。
③時鮭ときざけの異称。
ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】
(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」
ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ
時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」
とぎ‐じる【磨ぎ汁】
(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。
ときしる‐あめ【時知る雨】
時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」
ときしる‐ぐ【時知る具】
時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」
トキシン【Toxin ドイツ】
(→)毒素。
とき‐すす・める【説き勧める】
〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)
説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」
ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥
鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」
とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】
〔他五〕
①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」
②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」
とき‐せち【時節】
(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」
とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)
土岐善麿
撮影:田沼武能
しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とぎ‐かわ【研革】‥カハ
刃物を研ぐのに用いる革。
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とぎ‐し【研師】
刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とぎ‐しゅう【伽衆】
⇒おとぎしゅう(御伽衆)
どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ
離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」
とき‐しらず【時知らず】
①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。
②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。
③時鮭ときざけの異称。
ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】
(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」
ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ
時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」
とぎ‐じる【磨ぎ汁】
(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。
ときしる‐あめ【時知る雨】
時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」
ときしる‐ぐ【時知る具】
時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」
トキシン【Toxin ドイツ】
(→)毒素。
とき‐すす・める【説き勧める】
〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)
説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」
ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥
鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」
とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】
〔他五〕
①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」
②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」
とき‐せち【時節】
(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」
とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)
土岐善麿
撮影:田沼武能
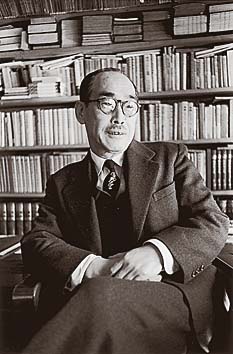 ⇒とき【土岐】
トキソイド【toxoid】
毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。
とき‐そう【鴇草】‥サウ
ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。
ときそば【時蕎麦】
落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。
トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ
(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。
とき‐だいこ【時太鼓】
時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」
とぎ‐だし【研ぎ出し】
①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。
②研出蒔絵まきえの略。
⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】
とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ
蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。
⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】
とぎ‐だ・す【研ぎ出す】
〔他五〕
研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」
とぎ‐たて【研ぎ立て】
研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」
とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】
〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)
刃物などを、念入りに研いで鋭くする。
とき‐たま【時偶】
時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」
とき‐たまご【溶き卵】
生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。
ど‐ぎつ・い
〔形〕
(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐づかさ【時司】
陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
どき‐つ・く
〔自五〕
不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つくばこ【土岐筑波子】
江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。
⇒とき【土岐】
とき‐づけ【時付け】
時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」
とき‐つげ‐どり【時告鳥】
鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」
とき‐つ・ける【説き付ける】
〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)
さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。
とき‐つづみ【時鼓】
時刻を知らせるために打つ鼓。
どきっ‐と
〔副〕
突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
どき‐どき
運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」
どぎ‐どぎ
①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」
②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
とき‐と‐する‐と【時とすると】
場合によっては。ともすると。たまに。
⇒とき【土岐】
トキソイド【toxoid】
毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。
とき‐そう【鴇草】‥サウ
ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。
ときそば【時蕎麦】
落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。
トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ
(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。
とき‐だいこ【時太鼓】
時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」
とぎ‐だし【研ぎ出し】
①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。
②研出蒔絵まきえの略。
⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】
とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ
蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。
⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】
とぎ‐だ・す【研ぎ出す】
〔他五〕
研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」
とぎ‐たて【研ぎ立て】
研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」
とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】
〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)
刃物などを、念入りに研いで鋭くする。
とき‐たま【時偶】
時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」
とき‐たまご【溶き卵】
生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。
ど‐ぎつ・い
〔形〕
(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐づかさ【時司】
陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
どき‐つ・く
〔自五〕
不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つくばこ【土岐筑波子】
江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。
⇒とき【土岐】
とき‐づけ【時付け】
時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」
とき‐つげ‐どり【時告鳥】
鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」
とき‐つ・ける【説き付ける】
〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)
さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。
とき‐つづみ【時鼓】
時刻を知らせるために打つ鼓。
どきっ‐と
〔副〕
突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
どき‐どき
運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」
どぎ‐どぎ
①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」
②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
とき‐と‐する‐と【時とすると】
場合によっては。ともすると。たまに。
とき・じ【時じ】🔗⭐🔉
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とき‐しまれ【時しまれ】🔗⭐🔉
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】🔗⭐🔉
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】🔗⭐🔉
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とき‐つ‐うみ【時つ海】🔗⭐🔉
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐つ‐かぜ【時つ風】🔗⭐🔉
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
とき‐つ‐くに【時つ国】🔗⭐🔉
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】🔗⭐🔉
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】🔗⭐🔉
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
とき‐と‐して【時として】🔗⭐🔉
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
○時となくときとなく🔗⭐🔉
○時となくときとなく
いつと時を定めないで。いつも。万葉集12「忘れ草わが紐に着く―思ひ渡れば生けりとも無し」
⇒とき【時】
○時と場合ときとばあい🔗⭐🔉
○時と場合ときとばあい
その時その時の事態。その時期と場所柄。「―に応じて適宜の処置をとる」
⇒とき【時】
とき‐どり【時取り】
①あらかじめ時刻を定めること。日葡辞書「トキドリヲスル」
②時間を計ること。浮世草子、好色盛衰記「ざつとあそびて―をして又立帰る浪の上」
とき‐な・う【時なふ】‥フ
〔自四〕
時節によくかなう。時機に相応する。医心方天養点「心志を和順にして飲食を節トキナヘヨ」
とき‐なか【時半・時中】
一時いっときのなかば。はんとき。今の1時間。大鏡師輔「さて―ばかりありてぞ」
とき‐なし【時無し】
①いつと定まった時がないこと。いつもあること。また、そのもの。時知らず。万葉集12「朝霜の消けぬべくのみや―に思ひ渡らむ息の緒にして」
②時無し大根の略。
⇒ときなし‐だいこん【時無し大根】
とき‐な・し【時無し】
〔形ク〕
①いつときまった時がない。時を定めない。いつものことである。万葉集4「間なく―・し我が恋ふらくは」
②失意の境遇にある。不遇である。今鏡「身の―・かりしを」
ときなし‐だいこん【時無し大根】
(四時、収穫することができるからいう)ダイコンの一品種。早春から晩秋まで栽培できる。
⇒とき‐なし【時無し】
とき‐なら‐ず【時ならず】
その時ではない。時節はずれである。思いがけない。万葉集2「悔くやしみか思ひ恋ふらむ―過ぎにし子らが朝露のごと夕霧のごと」
とき‐なら‐ぬ【時ならぬ】
その時節ではない。思いもよらない。「―雪」「―訪問」→時ならず
とき‐な・る【時成る】
〔自四〕
時刻が来る。時節が到来する。転じて、栄える。宇津保物語国譲中「亥の時に御はらへ―・りぬと申す」。宇津保物語嵯峨院「いと―・る人々多くさぶらふなれば」
とき‐な・う【時なふ】‥フ🔗⭐🔉
とき‐な・う【時なふ】‥フ
〔自四〕
時節によくかなう。時機に相応する。医心方天養点「心志を和順にして飲食を節トキナヘヨ」
とき‐なら‐ず【時ならず】🔗⭐🔉
とき‐なら‐ず【時ならず】
その時ではない。時節はずれである。思いがけない。万葉集2「悔くやしみか思ひ恋ふらむ―過ぎにし子らが朝露のごと夕霧のごと」
とき‐なら‐ぬ【時ならぬ】🔗⭐🔉
とき‐なら‐ぬ【時ならぬ】
その時節ではない。思いもよらない。「―雪」「―訪問」→時ならず
○時なるかなときなるかな🔗⭐🔉
○時なるかなときなるかな
今が最も好い時機だの意。
⇒とき【時】
とき‐なわ【解縄】‥ナハ
祓はらえの時に縄二筋を左右の手で持って、口にくわえて解くもの。定頼集「―のとくも急がじ禊にはゆふ懸けたるぞ神はうくらむ」
とき‐に【時に】
[一]〔副〕
①その時に。時あたかも。平家物語5「うきぬしづみぬ五六町こそながれたれ。―うつくしげなる童子一人来つて」。「―十一月三日文化の日」
②時々。おりおり。また、たまに。何かのはずみに。ともすると。「―大失策をやらかす」
[二]〔接続〕
(話を転ずる時にいう語)さて。ところで。それはそうと。「―あの件はどうなりました」
⇒ときに‐は【時には】
とき‐に【時に】🔗⭐🔉
とき‐に【時に】
[一]〔副〕
①その時に。時あたかも。平家物語5「うきぬしづみぬ五六町こそながれたれ。―うつくしげなる童子一人来つて」。「―十一月三日文化の日」
②時々。おりおり。また、たまに。何かのはずみに。ともすると。「―大失策をやらかす」
[二]〔接続〕
(話を転ずる時にいう語)さて。ところで。それはそうと。「―あの件はどうなりました」
⇒ときに‐は【時には】
○時に遇うときにあう
好時機にめぐりあう。世に用いられて栄える。源氏物語賢木「世に栄え時に遇ひし時は」
⇒とき【時】
○時に遇えば鼠も虎となるときにあえばねずみもとらとなる
時運に際会すれば、つまらないものも勢いを得る。
⇒とき【時】
○時に当たるときにあたる
その時にさしあたる。時に臨む。
⇒とき【時】
○時に従うときにしたがう
世の風習に従う。時勢に従う。源氏物語少女「―世の人の下には鼻まじろきをしつつ追従し」
⇒とき【時】
○時につくときにつく
時の権勢に従う。時世に順応する。源氏物語竹河「よろづのこと時につけたるをこそ世の人も許すめれ」
⇒とき【時】
○時に取りてときにとりて
①場合によって。徒然草「人、木石にあらねば、―物に感ずる事なきにあらず」
②その場に当たって。その当座。古今著聞集6「鴨のむなそりといふ秘曲をつかふまつりける、―いみじくなん侍りける」
⇒とき【時】
○時に遇うときにあう🔗⭐🔉
○時に遇うときにあう
好時機にめぐりあう。世に用いられて栄える。源氏物語賢木「世に栄え時に遇ひし時は」
⇒とき【時】
○時に遇えば鼠も虎となるときにあえばねずみもとらとなる🔗⭐🔉
○時に遇えば鼠も虎となるときにあえばねずみもとらとなる
時運に際会すれば、つまらないものも勢いを得る。
⇒とき【時】
○時に当たるときにあたる🔗⭐🔉
○時に当たるときにあたる
その時にさしあたる。時に臨む。
⇒とき【時】
○時に従うときにしたがう🔗⭐🔉
○時に従うときにしたがう
世の風習に従う。時勢に従う。源氏物語少女「―世の人の下には鼻まじろきをしつつ追従し」
⇒とき【時】
○時につくときにつく🔗⭐🔉
○時につくときにつく
時の権勢に従う。時世に順応する。源氏物語竹河「よろづのこと時につけたるをこそ世の人も許すめれ」
⇒とき【時】
○時に取りてときにとりて🔗⭐🔉
ときに‐は【時には】🔗⭐🔉
○時に因るときによる🔗⭐🔉
○時に因るときによる
その時の事態・状況に応ずる。
⇒とき【時】
○時に寄るときによる🔗⭐🔉
○時に寄るときによる
時の権勢になびき頼る。源氏物語藤裏葉「―心おごりして」
⇒とき【時】
とき‐の‐あめ【時の雨】
(「時雨じう」の訓読)しぐれ。夫木和歌抄16「かみなづきいかなる―なればかき曇るより物かなしかる」
とき‐の‐うじがみ【時の氏神】‥ウヂ‥
ちょうどよい時機に出て来て仲裁などをしてくれる、ありがたい人。
とき‐の‐うん【時の運】
その時の運命。天命。じうん。
とき‐の‐え【時の疫】
はやりやまい。えやみ。〈伊呂波字類抄〉
とき‐の‐かい【時の貝】‥カヒ
時刻を知らせるために吹き鳴らすほらがい。
とき‐の‐かね【時の鐘】
時刻を知らせる鐘。ときがね。
⇒ときのかね‐やく【時の鐘役】
ときのかね‐やく【時の鐘役】
江戸で、各戸から鐘役銭を取って時の鐘をつき鳴らした役。
⇒とき‐の‐かね【時の鐘】
とき‐の‐きざみ【時の刻み】
①漏刻ろうこくにきざんである矢のきざみ。また、漏刻。天智紀「漏尅ときのきざみを新しき台うてなに置く」
②時計の目盛り。
とき‐の‐きねんび【時の記念日】
6月10日。1920年(大正9)に始まる。671年4月25日(太陽暦6月10日)漏刻を新設し時を知らせたのに基づく。
とき‐の‐きら【時の綺羅】
時に会って栄えること。よい時節にめぐりあって隆盛をきわめること。平家物語1「世の覚え、―、めでたかりき」
とき‐の‐くい【時の杙】‥クヒ
時の簡ふだに差した杙。枕草子290「時丑三つ、子四つなど、はるかなる声にいひて、―さす音など」
とき‐の‐け【時の気】
はやりやまい。えやみ。疫病。〈倭名類聚鈔3〉
とき‐の‐こえ【鬨の声】‥コヱ
鬨をつくる声。大勢の人が一度にあげる声。鯨波。太平記3「―三度揚げて矢合せの流鏑かぶらを射懸けたれども」
とき‐の‐さかり【時の盛り】
時めいて栄えていること。宇津保物語嵯峨院「ただ今の―にておはしませば」
とき‐の‐しあわせ【時の仕合せ】‥アハセ
その時々のめぐり合せ。運不運。竹斎「誠に―にや、瘧おこりはそのまま落ちにけり」
とき‐の‐そう【時の奏】
宮中で時刻を奏すること。律令制では陰陽おんよう寮に時守ときもりを置き、漏刻ろうこくすなわち水時計を見守らせてその時々の鐘鼓を打たせ、宮中では亥いの刻の初めから寅とらの刻の終りまで宿直の官人が一刻いっときごとに時の簡ふだに杙くいを差し替えて時刻を告げた。
とき‐の‐あめ【時の雨】🔗⭐🔉
とき‐の‐あめ【時の雨】
(「時雨じう」の訓読)しぐれ。夫木和歌抄16「かみなづきいかなる―なればかき曇るより物かなしかる」
とき‐の‐うじがみ【時の氏神】‥ウヂ‥🔗⭐🔉
とき‐の‐うじがみ【時の氏神】‥ウヂ‥
ちょうどよい時機に出て来て仲裁などをしてくれる、ありがたい人。
とき‐の‐うん【時の運】🔗⭐🔉
とき‐の‐うん【時の運】
その時の運命。天命。じうん。
とき‐の‐え【時の疫】🔗⭐🔉
とき‐の‐え【時の疫】
はやりやまい。えやみ。〈伊呂波字類抄〉
とき‐の‐かい【時の貝】‥カヒ🔗⭐🔉
とき‐の‐かい【時の貝】‥カヒ
時刻を知らせるために吹き鳴らすほらがい。
とき‐の‐かね【時の鐘】🔗⭐🔉
とき‐の‐かね【時の鐘】
時刻を知らせる鐘。ときがね。
⇒ときのかね‐やく【時の鐘役】
ときのかね‐やく【時の鐘役】🔗⭐🔉
ときのかね‐やく【時の鐘役】
江戸で、各戸から鐘役銭を取って時の鐘をつき鳴らした役。
⇒とき‐の‐かね【時の鐘】
とき‐の‐きざみ【時の刻み】🔗⭐🔉
とき‐の‐きざみ【時の刻み】
①漏刻ろうこくにきざんである矢のきざみ。また、漏刻。天智紀「漏尅ときのきざみを新しき台うてなに置く」
②時計の目盛り。
とき‐の‐きねんび【時の記念日】🔗⭐🔉
とき‐の‐きねんび【時の記念日】
6月10日。1920年(大正9)に始まる。671年4月25日(太陽暦6月10日)漏刻を新設し時を知らせたのに基づく。
とき‐の‐きら【時の綺羅】🔗⭐🔉
とき‐の‐きら【時の綺羅】
時に会って栄えること。よい時節にめぐりあって隆盛をきわめること。平家物語1「世の覚え、―、めでたかりき」
とき‐の‐くい【時の杙】‥クヒ🔗⭐🔉
とき‐の‐くい【時の杙】‥クヒ
時の簡ふだに差した杙。枕草子290「時丑三つ、子四つなど、はるかなる声にいひて、―さす音など」
とき‐の‐け【時の気】🔗⭐🔉
とき‐の‐け【時の気】
はやりやまい。えやみ。疫病。〈倭名類聚鈔3〉
とき‐の‐さかり【時の盛り】🔗⭐🔉
とき‐の‐さかり【時の盛り】
時めいて栄えていること。宇津保物語嵯峨院「ただ今の―にておはしませば」
とき‐の‐しあわせ【時の仕合せ】‥アハセ🔗⭐🔉
とき‐の‐しあわせ【時の仕合せ】‥アハセ
その時々のめぐり合せ。運不運。竹斎「誠に―にや、瘧おこりはそのまま落ちにけり」
とき‐の‐そう【時の奏】🔗⭐🔉
とき‐の‐そう【時の奏】
宮中で時刻を奏すること。律令制では陰陽おんよう寮に時守ときもりを置き、漏刻ろうこくすなわち水時計を見守らせてその時々の鐘鼓を打たせ、宮中では亥いの刻の初めから寅とらの刻の終りまで宿直の官人が一刻いっときごとに時の簡ふだに杙くいを差し替えて時刻を告げた。
○時の代官、日の奉行ときのだいかんひのぶぎょう
その時の権勢ある者には服従するのがよいとのたとえ。
⇒とき【時】
○時の代官、日の奉行ときのだいかんひのぶぎょう🔗⭐🔉
○時の代官、日の奉行ときのだいかんひのぶぎょう
その時の権勢ある者には服従するのがよいとのたとえ。
⇒とき【時】
とき‐の‐たいこ【時の太鼓】
時刻を知らせる太鼓。ときだいこ。東海道中膝栗毛8「―もはや九つの数打ち過る頃」
とき‐の‐ちょうし【時の調子】‥テウ‥
四季などの時節に、また、その時その場にふさわしい音楽の調子。花鏡「―といつぱ、四季に分ち、又夜昼十二時におのおの双・黄・一越・平・盤の、その時々にあたれり」
とき‐の‐ところ【時の所】
時めく人の家。権門。落窪物語3「只今の―なれば恥をすてて参りつかうまつる」
とき‐の‐とり【時の鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐の‐ね【時の音】
その時節にふさわしい楽器の音調。呂りょ調が春にかなう類。
とき‐の‐はな【時の花】
その時節に咲く花。その時節にふさわしい花。万葉集20「―いやめづらしも」
⇒時の花をかざす
とき‐の‐たいこ【時の太鼓】🔗⭐🔉
とき‐の‐たいこ【時の太鼓】
時刻を知らせる太鼓。ときだいこ。東海道中膝栗毛8「―もはや九つの数打ち過る頃」
とき‐の‐ちょうし【時の調子】‥テウ‥🔗⭐🔉
とき‐の‐ちょうし【時の調子】‥テウ‥
四季などの時節に、また、その時その場にふさわしい音楽の調子。花鏡「―といつぱ、四季に分ち、又夜昼十二時におのおの双・黄・一越・平・盤の、その時々にあたれり」
とき‐の‐ところ【時の所】🔗⭐🔉
とき‐の‐ところ【時の所】
時めく人の家。権門。落窪物語3「只今の―なれば恥をすてて参りつかうまつる」
とき‐の‐とり【時の鳥】🔗⭐🔉
とき‐の‐とり【時の鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐の‐ね【時の音】🔗⭐🔉
とき‐の‐ね【時の音】
その時節にふさわしい楽器の音調。呂りょ調が春にかなう類。
とき‐の‐はな【時の花】🔗⭐🔉
とき‐の‐はな【時の花】
その時節に咲く花。その時節にふさわしい花。万葉集20「―いやめづらしも」
⇒時の花をかざす
○時の花をかざすときのはなをかざす
時勢に乗ってはなやかに栄える。栄華物語初花「なほなほしき人の譬にいふ―心ばへにや」
⇒とき‐の‐はな【時の花】
○時の花をかざすときのはなをかざす🔗⭐🔉
○時の花をかざすときのはなをかざす
時勢に乗ってはなやかに栄える。栄華物語初花「なほなほしき人の譬にいふ―心ばへにや」
⇒とき‐の‐はな【時の花】
とき‐の‐ひと【時の人】
①その時代の人。時人じじん。伊勢物語「これは貞数親王さだかずのみこ、―、中将の子となむいひける」
②時を得て栄えている人。枕草子121「我をばおぼさず、なにがしこそ、ただいまの―」
③今、世間で話題になっている人。
とき‐の‐ふだ【時の簡】
平安時代、清涼殿の殿上の間の小庭に立てた時刻を掲示する札。札に差した杙くいを時刻ごとに内豎ないじゅが差し換えた。讃岐典侍日記「―に杙さす音す」
とき‐の‐ほど【時の程】
少しの間。暫時。ときのま。平家物語12「―もおぼつかなう候ふに、帰りまゐらん」
とき‐の‐ま【時の間】
(→)「時の程」に同じ。後撰和歌集恋「―のうつつを忍ぶ心こそはかなき夢にまさらざりけれ」。「―に仕上げる」
とき‐の‐もの【時の物】
その時節の物。宇治拾遺物語5「沈地の机に―どもいろいろ」
とき‐の‐ひと【時の人】🔗⭐🔉
とき‐の‐ひと【時の人】
①その時代の人。時人じじん。伊勢物語「これは貞数親王さだかずのみこ、―、中将の子となむいひける」
②時を得て栄えている人。枕草子121「我をばおぼさず、なにがしこそ、ただいまの―」
③今、世間で話題になっている人。
とき‐の‐ふだ【時の簡】🔗⭐🔉
とき‐の‐ふだ【時の簡】
平安時代、清涼殿の殿上の間の小庭に立てた時刻を掲示する札。札に差した杙くいを時刻ごとに内豎ないじゅが差し換えた。讃岐典侍日記「―に杙さす音す」
とき‐の‐ほど【時の程】🔗⭐🔉
とき‐の‐ほど【時の程】
少しの間。暫時。ときのま。平家物語12「―もおぼつかなう候ふに、帰りまゐらん」
とき‐の‐ま【時の間】🔗⭐🔉
とき‐の‐ま【時の間】
(→)「時の程」に同じ。後撰和歌集恋「―のうつつを忍ぶ心こそはかなき夢にまさらざりけれ」。「―に仕上げる」
とき‐の‐もの【時の物】🔗⭐🔉
○時の用には鼻をも削ぐときのようにははなをもそぐ🔗⭐🔉
○時の用には鼻をも削ぐときのようにははなをもそぐ
急場の必要のためには手段を選ばないことのたとえ。
⇒とき【時】
○時は得難くして失い易しときはえがたくしてうしないやすし🔗⭐🔉
○時は得難くして失い易しときはえがたくしてうしないやすし
[淮南子原道訓]好機会は得難く、得ても、のがしやすい。
⇒とき【時】
○時は金なりときはかねなり🔗⭐🔉
○時は金なりときはかねなり
(Time is money.)時間は貴重・有効なものだから、むだに費やしてはいけない。
⇒とき【時】
とき‐はかり【時計】
⇒とけい。〈日葡辞書〉
とき‐はな・す【解き放す】
〔他五〕
①解いてはなればなれにする。「からまった糸を―・す」
②束縛を解いて自由にする。〈日葡辞書〉。「緊張から―・す」
とき‐はな・つ【解き放つ】
〔他五〕
(→)「ときはなす」に同じ。
とき‐び【斎日】
斎の施しのある日。狂言、布施無経ふせないきょう「今日は―ぢや程に旦那廻りを致さうと存ずる」
とき‐ひじ【斎非時】
僧侶の食事で、斎(午前の食事)と非時(午後の食事)。狂言、雪打合「われ等体の貧僧は―に参るに雪がふれば難儀に存ずるよ」
とき‐めか・し【時めかし】🔗⭐🔉
とき‐めか・し【時めかし】
〔形シク〕
時に合って栄えているようすだ。能因本枕草子すさまじきもの「さわがしう―・しき所に」
とき‐めか・す【時めかす】🔗⭐🔉
とき‐めか・す【時めかす】
〔他四〕
とりたてて寵愛する。宇津保物語忠乞「みかどは―・し給ふ事限りなし」
とき‐め・く【時めく】🔗⭐🔉
とき‐め・く【時めく】
〔自五〕
よい時機にあって栄える。時を得て当時の世にもてはやされる。源氏物語桐壺「いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて―・き給ふありけり」。「今を―・く人気スター」
○時も時ときもとき🔗⭐🔉
○時も時ときもとき
ちょうどその時。折も折。時しも。
⇒とき【時】
とき‐もの【解き物】
着物の縫糸をほどくこと。また、縫糸をほどくべき着物。ほどきもの。
とぎ‐もの【研ぎ物】
刃物や鏡をとぎみがくこと。また、とぎみがくべき刃物や鏡。「―師」
とき‐もり【時守】
陰陽おんよう寮に属し、宮中で漏刻ろうこくを守り、時刻を報ずることをつかさどった職。守辰丁しゅしんちょう。万葉集11「―のうち鳴なす鼓よみみれば」
⇒ときもり‐の‐はかせ【時守の博士】
ときもり‐の‐はかせ【時守の博士】
(→)漏刻博士に同じ。
⇒とき‐もり【時守】
○時わかずときわかず🔗⭐🔉
○時わかずときわかず
時を定めない。季節を区別しない。万葉集6「湯の原に鳴く蘆鶴はわがごとく妹に恋ふれや―鳴く」
⇒とき【時】
ときわ‐ぎ【常磐木】トキハ‥
一年中、緑葉を保つ木。松・杉の類。常緑樹。冬木。「常磐木落葉」は〈[季]夏〉。
⇒ときわ【常磐】
ときわ‐ぎょりゅう【常磐檉柳】トキハ‥リウ
〔植〕モクマオウの別称。
⇒ときわ【常磐】
ときわ‐ぐさ【常磐草】トキハ‥
①松の異称。
②カンアオイの異称。
⇒ときわ【常磐】
とき‐わけ【解分け】
袷あわせの衣服の縫糸をといて別々にすること。散木奇歌集「わが―の麻衣」
⇒ときわけ‐ごろも【解分け衣】
ときわけ‐ごろも【解分け衣】
袷あわせをといて単ひとえとした衣服。
⇒とき‐わけ【解分け】
とき‐わ・ける【解き分ける】
〔他下一〕[文]ときわ・く(下二)
ときはなって別々にする。袷あわせをほどいて単ひとえにする。
とき‐わ・ける【説き分ける】
〔他下一〕[文]ときわ・く(下二)
物の道理がわかるように説明する。
ときわ‐こうえん【常磐公園】トキハ‥ヱン
偕楽園の別称。
ときわ‐さんざし【常磐山樝子】トキハ‥
バラ科の常緑低木。南ヨーロッパ・小アジア原産。枝端はとげとなり生垣とする。葉は楕円形ないし倒披針形。花は小形、白色。果実は球形、赤色。近縁種にタチバナモドキがある。→ピラカンサ。
トキワサンザシ(花)
撮影:関戸 勇
 トキワサンザシ(実)
撮影:関戸 勇
トキワサンザシ(実)
撮影:関戸 勇
 ⇒ときわ【常磐】
ときわ‐じんじゃ【常磐神社】トキハ‥
茨城県水戸市の偕楽園内にある元別格官幣社。祭神は徳川光圀・徳川斉昭。
ときわず【常磐津】トキハヅ
①常磐津節ときわずぶしの略。
②常磐津節の芸姓。
⇒ときわず‐ぶし【常磐津節】
⇒ときわず‐もじたゆう【常磐津文字太夫】
⇒ときわず‐りんちゅう【常磐津林中】
ときわず‐ぶし【常磐津節】トキハヅ‥
浄瑠璃の一流派。広義の豊後節の一つ。1747年(延享4)宮古路豊後掾の高弟、初世常磐津文字太夫が創始。風紀上の理由で禁止された豊後節から脱して、義太夫節に近い格調ある芸風を目指した。歌舞伎の舞踊劇の音楽としても多く用いられる。代表作に「関の扉と」「戻駕もどりかご」「将門まさかど」「乗合船」など。
⇒ときわず【常磐津】
ときわず‐もじたゆう【常磐津文字太夫】トキハヅ‥タイフ
常磐津節の家元。初世は京都の人。宮古路豊後掾の高弟で前名は宮古路文字太夫。師とともに江戸に下って活躍したが、1736年(元文1)の豊後節禁止ののち常磐津に改姓し、常磐津節を創始。(1709?〜1781)
⇒ときわず【常磐津】
ときわず‐りんちゅう【常磐津林中】トキハヅ‥
(初世)常磐津節の太夫。本名、山蔭忠助。江戸生れ。近代屈指の名人。明快なせりふと自在な音楽性がレコードにも記録されて残る。(1842〜1906)
⇒ときわず【常磐津】
ときわ‐はぜ【常磐黄櫨】トキハ‥
ゴマノハグサ科の一年草。日本各地の路傍や庭に普通の雑草。サギゴケによく似るが茎が直立し、ロゼットにならない。葉は対生し、茎頂に淡紫色の唇形花をまばらに横向きに開く。
⇒ときわ【常磐】
ときわ‐みつなが【常盤光長】トキハ‥
平安末期の宮廷絵師。後白河法皇に用いられ、1173年(承安3)最勝光院障子絵を藤原隆信と合作したと記録される。また「年中行事絵巻」60巻の主要な画家と伝えられ「伴大納言絵巻」の作者とも考えられる。生没年未詳。
⇒ときわ【常盤】
⇒ときわ【常磐】
ときわ‐じんじゃ【常磐神社】トキハ‥
茨城県水戸市の偕楽園内にある元別格官幣社。祭神は徳川光圀・徳川斉昭。
ときわず【常磐津】トキハヅ
①常磐津節ときわずぶしの略。
②常磐津節の芸姓。
⇒ときわず‐ぶし【常磐津節】
⇒ときわず‐もじたゆう【常磐津文字太夫】
⇒ときわず‐りんちゅう【常磐津林中】
ときわず‐ぶし【常磐津節】トキハヅ‥
浄瑠璃の一流派。広義の豊後節の一つ。1747年(延享4)宮古路豊後掾の高弟、初世常磐津文字太夫が創始。風紀上の理由で禁止された豊後節から脱して、義太夫節に近い格調ある芸風を目指した。歌舞伎の舞踊劇の音楽としても多く用いられる。代表作に「関の扉と」「戻駕もどりかご」「将門まさかど」「乗合船」など。
⇒ときわず【常磐津】
ときわず‐もじたゆう【常磐津文字太夫】トキハヅ‥タイフ
常磐津節の家元。初世は京都の人。宮古路豊後掾の高弟で前名は宮古路文字太夫。師とともに江戸に下って活躍したが、1736年(元文1)の豊後節禁止ののち常磐津に改姓し、常磐津節を創始。(1709?〜1781)
⇒ときわず【常磐津】
ときわず‐りんちゅう【常磐津林中】トキハヅ‥
(初世)常磐津節の太夫。本名、山蔭忠助。江戸生れ。近代屈指の名人。明快なせりふと自在な音楽性がレコードにも記録されて残る。(1842〜1906)
⇒ときわず【常磐津】
ときわ‐はぜ【常磐黄櫨】トキハ‥
ゴマノハグサ科の一年草。日本各地の路傍や庭に普通の雑草。サギゴケによく似るが茎が直立し、ロゼットにならない。葉は対生し、茎頂に淡紫色の唇形花をまばらに横向きに開く。
⇒ときわ【常磐】
ときわ‐みつなが【常盤光長】トキハ‥
平安末期の宮廷絵師。後白河法皇に用いられ、1173年(承安3)最勝光院障子絵を藤原隆信と合作したと記録される。また「年中行事絵巻」60巻の主要な画家と伝えられ「伴大納言絵巻」の作者とも考えられる。生没年未詳。
⇒ときわ【常盤】
 トキワサンザシ(実)
撮影:関戸 勇
トキワサンザシ(実)
撮影:関戸 勇
 ⇒ときわ【常磐】
ときわ‐じんじゃ【常磐神社】トキハ‥
茨城県水戸市の偕楽園内にある元別格官幣社。祭神は徳川光圀・徳川斉昭。
ときわず【常磐津】トキハヅ
①常磐津節ときわずぶしの略。
②常磐津節の芸姓。
⇒ときわず‐ぶし【常磐津節】
⇒ときわず‐もじたゆう【常磐津文字太夫】
⇒ときわず‐りんちゅう【常磐津林中】
ときわず‐ぶし【常磐津節】トキハヅ‥
浄瑠璃の一流派。広義の豊後節の一つ。1747年(延享4)宮古路豊後掾の高弟、初世常磐津文字太夫が創始。風紀上の理由で禁止された豊後節から脱して、義太夫節に近い格調ある芸風を目指した。歌舞伎の舞踊劇の音楽としても多く用いられる。代表作に「関の扉と」「戻駕もどりかご」「将門まさかど」「乗合船」など。
⇒ときわず【常磐津】
ときわず‐もじたゆう【常磐津文字太夫】トキハヅ‥タイフ
常磐津節の家元。初世は京都の人。宮古路豊後掾の高弟で前名は宮古路文字太夫。師とともに江戸に下って活躍したが、1736年(元文1)の豊後節禁止ののち常磐津に改姓し、常磐津節を創始。(1709?〜1781)
⇒ときわず【常磐津】
ときわず‐りんちゅう【常磐津林中】トキハヅ‥
(初世)常磐津節の太夫。本名、山蔭忠助。江戸生れ。近代屈指の名人。明快なせりふと自在な音楽性がレコードにも記録されて残る。(1842〜1906)
⇒ときわず【常磐津】
ときわ‐はぜ【常磐黄櫨】トキハ‥
ゴマノハグサ科の一年草。日本各地の路傍や庭に普通の雑草。サギゴケによく似るが茎が直立し、ロゼットにならない。葉は対生し、茎頂に淡紫色の唇形花をまばらに横向きに開く。
⇒ときわ【常磐】
ときわ‐みつなが【常盤光長】トキハ‥
平安末期の宮廷絵師。後白河法皇に用いられ、1173年(承安3)最勝光院障子絵を藤原隆信と合作したと記録される。また「年中行事絵巻」60巻の主要な画家と伝えられ「伴大納言絵巻」の作者とも考えられる。生没年未詳。
⇒ときわ【常盤】
⇒ときわ【常磐】
ときわ‐じんじゃ【常磐神社】トキハ‥
茨城県水戸市の偕楽園内にある元別格官幣社。祭神は徳川光圀・徳川斉昭。
ときわず【常磐津】トキハヅ
①常磐津節ときわずぶしの略。
②常磐津節の芸姓。
⇒ときわず‐ぶし【常磐津節】
⇒ときわず‐もじたゆう【常磐津文字太夫】
⇒ときわず‐りんちゅう【常磐津林中】
ときわず‐ぶし【常磐津節】トキハヅ‥
浄瑠璃の一流派。広義の豊後節の一つ。1747年(延享4)宮古路豊後掾の高弟、初世常磐津文字太夫が創始。風紀上の理由で禁止された豊後節から脱して、義太夫節に近い格調ある芸風を目指した。歌舞伎の舞踊劇の音楽としても多く用いられる。代表作に「関の扉と」「戻駕もどりかご」「将門まさかど」「乗合船」など。
⇒ときわず【常磐津】
ときわず‐もじたゆう【常磐津文字太夫】トキハヅ‥タイフ
常磐津節の家元。初世は京都の人。宮古路豊後掾の高弟で前名は宮古路文字太夫。師とともに江戸に下って活躍したが、1736年(元文1)の豊後節禁止ののち常磐津に改姓し、常磐津節を創始。(1709?〜1781)
⇒ときわず【常磐津】
ときわず‐りんちゅう【常磐津林中】トキハヅ‥
(初世)常磐津節の太夫。本名、山蔭忠助。江戸生れ。近代屈指の名人。明快なせりふと自在な音楽性がレコードにも記録されて残る。(1842〜1906)
⇒ときわず【常磐津】
ときわ‐はぜ【常磐黄櫨】トキハ‥
ゴマノハグサ科の一年草。日本各地の路傍や庭に普通の雑草。サギゴケによく似るが茎が直立し、ロゼットにならない。葉は対生し、茎頂に淡紫色の唇形花をまばらに横向きに開く。
⇒ときわ【常磐】
ときわ‐みつなが【常盤光長】トキハ‥
平安末期の宮廷絵師。後白河法皇に用いられ、1173年(承安3)最勝光院障子絵を藤原隆信と合作したと記録される。また「年中行事絵巻」60巻の主要な画家と伝えられ「伴大納言絵巻」の作者とも考えられる。生没年未詳。
⇒ときわ【常盤】
○時を争うときをあらそう🔗⭐🔉
○時を争うときをあらそう
少しでも早く物事をしようとする。一刻を争う。「この手術は―」
⇒とき【時】
○時を失うときをうしなう🔗⭐🔉
○時を失うときをうしなう
①好機会をにがす。
②時勢にあわず、勢力が衰える。おちぶれる。古今和歌集序「きのふは栄えおごりて時を失ひ、世にわび」
⇒とき【時】
○時を移さずときをうつさず🔗⭐🔉
○時を移さずときをうつさず
手間どらずに。すぐさま。「決断したら―実行せよ」
⇒とき【時】
○時を得るときをえる🔗⭐🔉
○時を得るときをえる
好時機にめぐりあって栄える。
⇒とき【時】
○時を稼ぐときをかせぐ🔗⭐🔉
○時を稼ぐときをかせぐ
当面の難局を切り抜けるため、他の事で引き延ばして、時間を作り出す。時間を稼ぐ。
⇒とき【時】
○時をかわさずときをかわさず🔗⭐🔉
○時をかわさずときをかわさず
すぐに。即刻に。時を移さず。枕草子95「とみの御物なり。誰も誰もあまたして時かはさず縫ひてまゐらせよ」
⇒とき【時】
○時を奏すときをそうす🔗⭐🔉
○時を撞くときをつく🔗⭐🔉
○時を撞くときをつく
時の鐘を撞き鳴らす。
⇒とき【時】
○時をつくるときをつくる🔗⭐🔉
○時をつくるときをつくる
鶏が鳴いて夜明けの時を知らせる。
⇒とき【時】
○時を見るときをみる🔗⭐🔉
○時を見るときをみる
適当な時機が来るのを待つ。好機をえらぶ。「時を見て反撃に出る」
⇒とき【時】
と‐きん【と金】
将棋で、歩ふが成ったもの。金将と同じ働きをする。成ると駒を裏返して「と」と書いてある方を出すのでいう。
と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】
①修験者しゅげんじゃのかぶる小さいずきん。山中遍歴の際、瘴気しょうきに触れるのを防ぐためという。黒色の布でつくり、十二因縁にかたどって12の襞ひだを設け、紐で頤おとがいに結びとめる。
頭巾
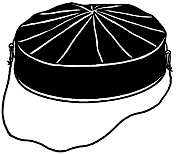 ②野ざらしになる柱の上部を方錐形にした部分。これを包む金物を頭巾金物という。
③丸太の両端を、搬出の際の損傷を防ぐために、1の形にとがらすこと。また、その部分。
⇒ときん‐いばら【頭巾薔薇】
と‐きん【鍍金】
①金を銅製品の表面に焼き付けめっきをすること。金を水銀に溶解させて作ったアマルガムを銅の表面に塗り、加熱により水銀を蒸発させる。焼き付けたものを金銅こんどうという。また、銀を焼き付けることを鍍銀という。
②⇒めっき
と‐ぎん【都銀】
都市銀行の略。
どきん
急な物事に驚きおそれて動悸どうきのうつさま。どきり。「怪しい人影に―とする」
ときん‐いばら【頭巾薔薇】
バラ科キイチゴ属の落葉低木。中国原産で観賞用。高さ1.5メートルに達し、若枝・葉柄にとげがある。葉は羽状複葉。夏にバラに似た大形白色の重弁花をつける。ボタンイバラ。
⇒と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】
ときん‐そう【吐金草】‥サウ
キク科の一年草。高さ約10センチメートル。多くは地に臥して群生。葉は基部狭く、3〜5の鋸歯がある。夏、淡緑色で褐紫色を帯びた球状の頭花を開く。花後、4稜ある黄色の果実を結び、花をつぶすとこれが出てくるのが、名の由来という。
とき‐ん‐ば【時んば】
(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」
とく【特】
ことにぬきんでること。他と別であること。とりわけ。「―に言うことはない」
とく【得】
①えること。手に入れること。徒然草「芸能・所作のみにあらず。大方のふるまひ・心づかひも、愚かにしてつつしめるは―の本なり」
②身につけること。さとること。
③もうけること。利益。また、有利なこと。落窪物語1「時の受領ずりようは世に―有る物といへば、只今そのほどなめれば、つかうまつらむ」。「―をする」「―な性分」→とく(徳)3
⇒得を取ろうより名を取れ
とく【徳】
①道をさとった立派な行為。善い行いをする性格。身についた品性。徒然草「人に本意なく思はせて我が心を慰まん事、―に背そむけり」。「―が高い」
②人を感化する人格の力。めぐみ。神仏の加護。枕草子161「宰相の中将の―を見ること。その方に向ひて拝むべし」。源氏物語澪標「心のうちに神の御―をあはれにめでたしと思ふ」。
③(「得」と通用)利益。もうけ。富。「有―人うとくじん」
⇒徳孤ならず必ず隣あり
⇒徳とする
⇒徳をもって怨みに報いる
と・く【着く】
〔自四〕
(ツクの転)到着する。つく。古事記中「伊知遅いちじ島、美島に―・き」
と・く【解く】
[一]〔他五〕
結ばれたり、こり固まったり、閉ざされたり、不明であったりしたものを、ゆるめほぐした状態にする意。
➊結びつけられているものを分けはなす。
①結び目をほどく。天智紀「臣の子の八重の紐―・く一重だにいまだ―・かねば御子の紐―・く」。平家物語11「判官剰あまつさへ封をも―・かず」。「帯を―・く」
②束ねてあるものをばらばらにする。万葉集16「か黒し髪を…挙げても巻き見―・き乱り童児わらわになし見」
③縫ってあるものをほどく。万葉集12「橡つるばみの衣―・き洗ひ」
④纏まとっていたものを脱ぐ。装っていたものをとりはずす。蜻蛉日記中「御車のしやうぞく―・きて」。今昔物語集1「身の瓔珞ようらくを脱ときて」。「旅装を―・く」
⑤(「梳く」とも書く)乱れもつれたものを分けはなして整える。髪をくしけずる。梳すく。源氏物語手習「髪は尼君のみ梳けずり給ふを…ただ少し―・きくだして」
⑥むすぼれた気持をさっぱりさせる。はらす。「愁いを―・く」「誤解を―・く」「緊張を―・く」
⑦束縛などをとりのぞく。「統制を―・く」
⑧警備などのために固めていた態勢をくずす。「警戒を―・く」「城の囲みを―・く」
⑨魚や鳥獣などを刃物で切りひらく。また、解剖する。蘭学事始「獣畜を―・きて、視あはせしことも度々の事なりき」
➋不明のものを明らかにする。
①答を出す。徒然草「なぞなぞを作りて―・かれける所へ」。「方程式を―・く」「事件を―・く鍵」
②説明する。解釈する。源氏物語賢木「六十巻といふふみよみ給ひ、覚束なき所々―・かせなどしておはしますを」
➌職をやめさせる。免ずる。「任を―・く」
[二]〔自下二〕
⇒とける(下一)
と・く【溶く・融く・熔く・鎔く】
(「解く」と同源)
[一]〔他五〕
液体に他の物質をまぜて均一な液体をつくる。「アルコールを水に―・く」「卵を―・く」
[二]〔自下二〕
⇒とける(下一)
◇「熔」「鎔」は、金属を液状にする場合に使う。
と・く【説く】
(「解く」と同源)〔他五〕
相手を納得させるために、物事の道理・筋道をわかりやすく述べる意。
①道理をいいさとす。源氏物語蛍「仏のいとうるはしき心にて、―・きおき給へる御法も」。「じゅんじゅんと―・く」
②解説する。説明する。源氏物語橋姫「年頃学び知り給へる事どもの深き心を―・き聞かせ奉り」。「語義を―・く」
とく【疾く】
(形容詞「疾し」の連用形)
①はやく。すみやかに。急に。「―行け」
②すでに。もう。とっく。「―御存知」
と・ぐ【研ぐ・磨ぐ】
〔他五〕
①玉・金属などをみがいて光沢を出す。「鏡を―・ぐ」
②刃物などを砥石ですって鋭くする。万葉集20「剣大刀いよよ―・ぐべし」。「包丁を―・ぐ」
③水中でこすって洗う。「米を―・ぐ」
④心などを練磨して立派にする。万葉集4「―・ぎし心を」
と・ぐ【遂ぐ】
〔他下二〕
⇒とげる(下一)
どく【毒】
①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」
②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」
③わざわい。
④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」
⇒毒にも薬にもならない
⇒毒を食わば皿まで
⇒毒を以て毒を制す
どく【独】
独逸ドイツの略。
ど・く【退く】
[一]〔自五〕
しりぞく。のく。ひく。浮世風呂2「湯水を遣つかふのだものを、かかるが悪くは、遠くへ―・いてるがいい」。「そこを―・け」
[二]〔他下二〕
⇒どける(下一)
どく‐あく【毒悪】
非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」
どく‐あたり【毒中り】
飲食物の毒または毒薬にあたって健康を害すること。中毒。
とく‐い【特異】
他のものと非常に異なっていること。「―な風習」「―な能力」
⇒とくい‐せい【特異性】
⇒とくい‐たいしつ【特異体質】
⇒とくい‐てん【特異点】
⇒とくい‐び【特異日】
とく‐い【得意】
①志をえて満足していること。望みどおりになって満足すること。「―の絶頂」↔失意。
②誇りたかぶること。また、誇らしげなさま。「―になって自慢する」
③最も熟練していること。最もすぐれていること。えて。「―の種目」「―の芸」
④親しい友。親友。源氏物語明石「入道はかの国の―にて、年頃あひ語らひ侍りつれど」
⑤ひいきにしてくれること。また、その人。枕草子87「御―ななり。さらによも語らひとらじ」
⑥(→)得意先に同じ。好色一代男2「元来もとより商ひの―殊更にあしらひ」。「御―様」
⇒とくい‐がお【得意顔】
⇒とくい‐げ【得意気】
⇒とくい‐さき【得意先】
⇒とくい‐ば【得意場】
⇒とくい‐まわり【得意回り】
⇒とくい‐まんめん【得意満面】
と‐ぐい【利杙】‥グヒ
先のとがったくい。源平盛衰記8「竹の―に貫かれて失せにけり」
とくい‐がお【得意顔】‥ガホ
誇らしげな顔つき。自慢そうな様子。
⇒とく‐い【得意】
とく‐いく【徳育】
道徳面の教育。森有礼、兵式体操に関する上奏案「夫レ教育ノ要タル、智育―体育ノ三者ヲシテ斉ひとシク発達セシムルニ在リ」→知育→体育
とくい‐げ【得意気】
得意そうであること。得意らしい様子。「―に技を披露する」
⇒とく‐い【得意】
とくい‐さき【得意先】
日常よく取引している相手方。商家などで常に買ってくれる客。取引先。「―を回る」
⇒とく‐い【得意】
とくい‐せい【特異性】
①事物にそなわっている特殊な性質。特殊性。
②〔化〕2種の基質間の高い選択的な反応性。免疫反応における抗原と抗体の反応など。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐たいしつ【特異体質】
一般的にある種の食物や化学物質、薬物などに対して過敏に反応する体質をいう。食物ではエビ・カニ・サバ・卵白など、薬物ではピリン・ヨードなどに対するものがしばしば見られ、多くアレルギーが基礎にある。イディオジンクラジー。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐てん【特異点】
〔数〕
①曲線上あるいは曲面上で、接線あるいは接平面が存在しなかったり、二つ以上存在したりするような点。
②複素関数が連続な導関数をもたないような点。
⇒とく‐い【特異】
どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】
イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。
とくい‐ば【得意場】
(→)得意先に同じ。
⇒とく‐い【得意】
とくい‐び【特異日】
例年、ある天気が高い確率で現れる特定の日。例えば、11月3日は晴れることが多く、9月17日と26日は強い台風の襲来が多いなど。シンギュラリティー。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐まわり【得意回り】‥マハリ
得意先を訪ねてまわること。
⇒とく‐い【得意】
とくい‐まんめん【得意満面】
得意な心持が顔全体に現れること。いかにも満足そうな様子。「―な語り口」
⇒とく‐い【得意】
どく‐いみ【毒忌】
主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。
とくいん‐がい【特飲街】
特殊飲食店の立ち並ぶまち。
ド‐クインシー【Thomas De Quincey】
イギリスの批評家・作家。自分の体験に基づく「阿片常用者の告白」や評論「芸術として見た殺人」がある。(1785〜1859)
ど‐くう【土公】
(→)土公神どくじんのこと。
ど‐ぐう【土偶】
①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。
②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木
②野ざらしになる柱の上部を方錐形にした部分。これを包む金物を頭巾金物という。
③丸太の両端を、搬出の際の損傷を防ぐために、1の形にとがらすこと。また、その部分。
⇒ときん‐いばら【頭巾薔薇】
と‐きん【鍍金】
①金を銅製品の表面に焼き付けめっきをすること。金を水銀に溶解させて作ったアマルガムを銅の表面に塗り、加熱により水銀を蒸発させる。焼き付けたものを金銅こんどうという。また、銀を焼き付けることを鍍銀という。
②⇒めっき
と‐ぎん【都銀】
都市銀行の略。
どきん
急な物事に驚きおそれて動悸どうきのうつさま。どきり。「怪しい人影に―とする」
ときん‐いばら【頭巾薔薇】
バラ科キイチゴ属の落葉低木。中国原産で観賞用。高さ1.5メートルに達し、若枝・葉柄にとげがある。葉は羽状複葉。夏にバラに似た大形白色の重弁花をつける。ボタンイバラ。
⇒と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】
ときん‐そう【吐金草】‥サウ
キク科の一年草。高さ約10センチメートル。多くは地に臥して群生。葉は基部狭く、3〜5の鋸歯がある。夏、淡緑色で褐紫色を帯びた球状の頭花を開く。花後、4稜ある黄色の果実を結び、花をつぶすとこれが出てくるのが、名の由来という。
とき‐ん‐ば【時んば】
(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」
とく【特】
ことにぬきんでること。他と別であること。とりわけ。「―に言うことはない」
とく【得】
①えること。手に入れること。徒然草「芸能・所作のみにあらず。大方のふるまひ・心づかひも、愚かにしてつつしめるは―の本なり」
②身につけること。さとること。
③もうけること。利益。また、有利なこと。落窪物語1「時の受領ずりようは世に―有る物といへば、只今そのほどなめれば、つかうまつらむ」。「―をする」「―な性分」→とく(徳)3
⇒得を取ろうより名を取れ
とく【徳】
①道をさとった立派な行為。善い行いをする性格。身についた品性。徒然草「人に本意なく思はせて我が心を慰まん事、―に背そむけり」。「―が高い」
②人を感化する人格の力。めぐみ。神仏の加護。枕草子161「宰相の中将の―を見ること。その方に向ひて拝むべし」。源氏物語澪標「心のうちに神の御―をあはれにめでたしと思ふ」。
③(「得」と通用)利益。もうけ。富。「有―人うとくじん」
⇒徳孤ならず必ず隣あり
⇒徳とする
⇒徳をもって怨みに報いる
と・く【着く】
〔自四〕
(ツクの転)到着する。つく。古事記中「伊知遅いちじ島、美島に―・き」
と・く【解く】
[一]〔他五〕
結ばれたり、こり固まったり、閉ざされたり、不明であったりしたものを、ゆるめほぐした状態にする意。
➊結びつけられているものを分けはなす。
①結び目をほどく。天智紀「臣の子の八重の紐―・く一重だにいまだ―・かねば御子の紐―・く」。平家物語11「判官剰あまつさへ封をも―・かず」。「帯を―・く」
②束ねてあるものをばらばらにする。万葉集16「か黒し髪を…挙げても巻き見―・き乱り童児わらわになし見」
③縫ってあるものをほどく。万葉集12「橡つるばみの衣―・き洗ひ」
④纏まとっていたものを脱ぐ。装っていたものをとりはずす。蜻蛉日記中「御車のしやうぞく―・きて」。今昔物語集1「身の瓔珞ようらくを脱ときて」。「旅装を―・く」
⑤(「梳く」とも書く)乱れもつれたものを分けはなして整える。髪をくしけずる。梳すく。源氏物語手習「髪は尼君のみ梳けずり給ふを…ただ少し―・きくだして」
⑥むすぼれた気持をさっぱりさせる。はらす。「愁いを―・く」「誤解を―・く」「緊張を―・く」
⑦束縛などをとりのぞく。「統制を―・く」
⑧警備などのために固めていた態勢をくずす。「警戒を―・く」「城の囲みを―・く」
⑨魚や鳥獣などを刃物で切りひらく。また、解剖する。蘭学事始「獣畜を―・きて、視あはせしことも度々の事なりき」
➋不明のものを明らかにする。
①答を出す。徒然草「なぞなぞを作りて―・かれける所へ」。「方程式を―・く」「事件を―・く鍵」
②説明する。解釈する。源氏物語賢木「六十巻といふふみよみ給ひ、覚束なき所々―・かせなどしておはしますを」
➌職をやめさせる。免ずる。「任を―・く」
[二]〔自下二〕
⇒とける(下一)
と・く【溶く・融く・熔く・鎔く】
(「解く」と同源)
[一]〔他五〕
液体に他の物質をまぜて均一な液体をつくる。「アルコールを水に―・く」「卵を―・く」
[二]〔自下二〕
⇒とける(下一)
◇「熔」「鎔」は、金属を液状にする場合に使う。
と・く【説く】
(「解く」と同源)〔他五〕
相手を納得させるために、物事の道理・筋道をわかりやすく述べる意。
①道理をいいさとす。源氏物語蛍「仏のいとうるはしき心にて、―・きおき給へる御法も」。「じゅんじゅんと―・く」
②解説する。説明する。源氏物語橋姫「年頃学び知り給へる事どもの深き心を―・き聞かせ奉り」。「語義を―・く」
とく【疾く】
(形容詞「疾し」の連用形)
①はやく。すみやかに。急に。「―行け」
②すでに。もう。とっく。「―御存知」
と・ぐ【研ぐ・磨ぐ】
〔他五〕
①玉・金属などをみがいて光沢を出す。「鏡を―・ぐ」
②刃物などを砥石ですって鋭くする。万葉集20「剣大刀いよよ―・ぐべし」。「包丁を―・ぐ」
③水中でこすって洗う。「米を―・ぐ」
④心などを練磨して立派にする。万葉集4「―・ぎし心を」
と・ぐ【遂ぐ】
〔他下二〕
⇒とげる(下一)
どく【毒】
①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」
②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」
③わざわい。
④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」
⇒毒にも薬にもならない
⇒毒を食わば皿まで
⇒毒を以て毒を制す
どく【独】
独逸ドイツの略。
ど・く【退く】
[一]〔自五〕
しりぞく。のく。ひく。浮世風呂2「湯水を遣つかふのだものを、かかるが悪くは、遠くへ―・いてるがいい」。「そこを―・け」
[二]〔他下二〕
⇒どける(下一)
どく‐あく【毒悪】
非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」
どく‐あたり【毒中り】
飲食物の毒または毒薬にあたって健康を害すること。中毒。
とく‐い【特異】
他のものと非常に異なっていること。「―な風習」「―な能力」
⇒とくい‐せい【特異性】
⇒とくい‐たいしつ【特異体質】
⇒とくい‐てん【特異点】
⇒とくい‐び【特異日】
とく‐い【得意】
①志をえて満足していること。望みどおりになって満足すること。「―の絶頂」↔失意。
②誇りたかぶること。また、誇らしげなさま。「―になって自慢する」
③最も熟練していること。最もすぐれていること。えて。「―の種目」「―の芸」
④親しい友。親友。源氏物語明石「入道はかの国の―にて、年頃あひ語らひ侍りつれど」
⑤ひいきにしてくれること。また、その人。枕草子87「御―ななり。さらによも語らひとらじ」
⑥(→)得意先に同じ。好色一代男2「元来もとより商ひの―殊更にあしらひ」。「御―様」
⇒とくい‐がお【得意顔】
⇒とくい‐げ【得意気】
⇒とくい‐さき【得意先】
⇒とくい‐ば【得意場】
⇒とくい‐まわり【得意回り】
⇒とくい‐まんめん【得意満面】
と‐ぐい【利杙】‥グヒ
先のとがったくい。源平盛衰記8「竹の―に貫かれて失せにけり」
とくい‐がお【得意顔】‥ガホ
誇らしげな顔つき。自慢そうな様子。
⇒とく‐い【得意】
とく‐いく【徳育】
道徳面の教育。森有礼、兵式体操に関する上奏案「夫レ教育ノ要タル、智育―体育ノ三者ヲシテ斉ひとシク発達セシムルニ在リ」→知育→体育
とくい‐げ【得意気】
得意そうであること。得意らしい様子。「―に技を披露する」
⇒とく‐い【得意】
とくい‐さき【得意先】
日常よく取引している相手方。商家などで常に買ってくれる客。取引先。「―を回る」
⇒とく‐い【得意】
とくい‐せい【特異性】
①事物にそなわっている特殊な性質。特殊性。
②〔化〕2種の基質間の高い選択的な反応性。免疫反応における抗原と抗体の反応など。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐たいしつ【特異体質】
一般的にある種の食物や化学物質、薬物などに対して過敏に反応する体質をいう。食物ではエビ・カニ・サバ・卵白など、薬物ではピリン・ヨードなどに対するものがしばしば見られ、多くアレルギーが基礎にある。イディオジンクラジー。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐てん【特異点】
〔数〕
①曲線上あるいは曲面上で、接線あるいは接平面が存在しなかったり、二つ以上存在したりするような点。
②複素関数が連続な導関数をもたないような点。
⇒とく‐い【特異】
どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】
イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。
とくい‐ば【得意場】
(→)得意先に同じ。
⇒とく‐い【得意】
とくい‐び【特異日】
例年、ある天気が高い確率で現れる特定の日。例えば、11月3日は晴れることが多く、9月17日と26日は強い台風の襲来が多いなど。シンギュラリティー。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐まわり【得意回り】‥マハリ
得意先を訪ねてまわること。
⇒とく‐い【得意】
とくい‐まんめん【得意満面】
得意な心持が顔全体に現れること。いかにも満足そうな様子。「―な語り口」
⇒とく‐い【得意】
どく‐いみ【毒忌】
主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。
とくいん‐がい【特飲街】
特殊飲食店の立ち並ぶまち。
ド‐クインシー【Thomas De Quincey】
イギリスの批評家・作家。自分の体験に基づく「阿片常用者の告白」や評論「芸術として見た殺人」がある。(1785〜1859)
ど‐くう【土公】
(→)土公神どくじんのこと。
ど‐ぐう【土偶】
①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。
②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木 みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。
土偶
みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。
土偶
 トクヴィル【Alexis de Tocqueville】
フランスの政治家。1830年代に米国を旅行。その見聞をもとにした「アメリカの民主政治」は、米国政治研究の古典。(1805〜1859)
どく‐うつぎ【毒空木】
ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。
どくうつぎ
トクヴィル【Alexis de Tocqueville】
フランスの政治家。1830年代に米国を旅行。その見聞をもとにした「アメリカの民主政治」は、米国政治研究の古典。(1805〜1859)
どく‐うつぎ【毒空木】
ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。
どくうつぎ
 どく‐え【毒荏】
〔植〕アブラギリの異称。
どく‐えい【独泳】
①ひとりで泳ぐこと。
②他を引き離して泳ぐこと。
どく‐えき【毒液】
毒をふくんだ液体。
どく‐えん【毒焔】
①有毒ガスを発散するほのお。
②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。
どく‐えん【独演】
演芸・講演などを一人だけで通して行うこと。また、その演芸・講演。「落語―会」
とく‐おう【徳王】‥ワウ
内モンゴルの政治家。本名デムチュクドンロプ。王公の家庭に生まれ、自治権獲得運動に従事。1939年日本の援助下に蒙古聯合自治政府を樹立、主席に就任。日本の敗戦後、外モンゴルで捕らえられ、中国送還。63年釈放後、内モンゴル自治区文史館勤務。(1902〜1966)
とくおう【徳応】
私年号の一つ。→私年号(表)
どく‐おう【独往】‥ワウ
他を省みず自主的に進むこと。
どくおう‐がっぽう【独墺合邦】‥アウ‥パウ
1938年3月、ナチス政権がオーストリアをドイツに併合したこと。
とくおか【徳岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒とくおか‐しんせん【徳岡神泉】
とくおか‐しんせん【徳岡神泉】‥ヲカ‥
日本画家。本名、時次郎。京都生れ。竹内栖鳳せいほうに学ぶ。奥深い象徴的な画風を確立。文化勲章。(1896〜1972)
⇒とくおか【徳岡】
とく‐おん【特恩】
特別の恩恵。
どく‐が【毒牙】
①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。
②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」
どく‐が【毒蛾】
①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。
②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。
どく‐が【独臥】‥グワ
ひとりで寝ること。ひとりね。〈運歩色葉集〉
どく‐がい【毒害】
①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。
②甚だしくそこなうこと。残害。
どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ
①毒を飲ませること。
②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」
とく‐がく【督学】
学事を監督すること。また、その人。
⇒とくがく‐かん【督学官】
とく‐がく【篤学】
学問に熱心にはげむこと。また、広く学問に通ずること。「―の士」
どく‐がく【独学】
師に就かずに独力で学問すること。「―で資格を取る」「フランス語を―する」
とくがく‐かん【督学官】‥クワン
旧制の教育行政官。1913年(大正2)視学官を改称して置かれた。文部大臣の指揮を受けて学事の視察監督をつかさどった。
⇒とく‐がく【督学】
どく‐ガス【毒ガス】
毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。
⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】
どくガス‐だん【毒ガス弾】
(→)ガス弾に同じ。
⇒どく‐ガス【毒ガス】
どくが‐ろん【独我論】
〔哲〕(solipsism)実在するのはわが自我とその所産のみであって、他我や外界などすべてはわが自我の観念または意識内容にすぎないとする主観的認識論。バークリー・フィヒテ・シュティルナーらの立場。唯我論。独在論。
とくがわ【徳川】‥ガハ
姓氏の一つ。江戸幕府の将軍家。元来は、三河国加茂郡松平村の土豪で、松平を称した。上野国の新田氏(徳川・得川氏を称)の後裔として清和源氏の嫡流ちゃくりゅうを汲むというのは、家康が将軍になるために偽作・付会したといわれる。宗家のほか御三家と三卿の嫡流だけ徳川を称し、他はすべて松平氏を称。→江戸幕府(表)。
徳川(略系図)
どく‐え【毒荏】
〔植〕アブラギリの異称。
どく‐えい【独泳】
①ひとりで泳ぐこと。
②他を引き離して泳ぐこと。
どく‐えき【毒液】
毒をふくんだ液体。
どく‐えん【毒焔】
①有毒ガスを発散するほのお。
②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。
どく‐えん【独演】
演芸・講演などを一人だけで通して行うこと。また、その演芸・講演。「落語―会」
とく‐おう【徳王】‥ワウ
内モンゴルの政治家。本名デムチュクドンロプ。王公の家庭に生まれ、自治権獲得運動に従事。1939年日本の援助下に蒙古聯合自治政府を樹立、主席に就任。日本の敗戦後、外モンゴルで捕らえられ、中国送還。63年釈放後、内モンゴル自治区文史館勤務。(1902〜1966)
とくおう【徳応】
私年号の一つ。→私年号(表)
どく‐おう【独往】‥ワウ
他を省みず自主的に進むこと。
どくおう‐がっぽう【独墺合邦】‥アウ‥パウ
1938年3月、ナチス政権がオーストリアをドイツに併合したこと。
とくおか【徳岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒とくおか‐しんせん【徳岡神泉】
とくおか‐しんせん【徳岡神泉】‥ヲカ‥
日本画家。本名、時次郎。京都生れ。竹内栖鳳せいほうに学ぶ。奥深い象徴的な画風を確立。文化勲章。(1896〜1972)
⇒とくおか【徳岡】
とく‐おん【特恩】
特別の恩恵。
どく‐が【毒牙】
①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。
②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」
どく‐が【毒蛾】
①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。
②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。
どく‐が【独臥】‥グワ
ひとりで寝ること。ひとりね。〈運歩色葉集〉
どく‐がい【毒害】
①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。
②甚だしくそこなうこと。残害。
どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ
①毒を飲ませること。
②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」
とく‐がく【督学】
学事を監督すること。また、その人。
⇒とくがく‐かん【督学官】
とく‐がく【篤学】
学問に熱心にはげむこと。また、広く学問に通ずること。「―の士」
どく‐がく【独学】
師に就かずに独力で学問すること。「―で資格を取る」「フランス語を―する」
とくがく‐かん【督学官】‥クワン
旧制の教育行政官。1913年(大正2)視学官を改称して置かれた。文部大臣の指揮を受けて学事の視察監督をつかさどった。
⇒とく‐がく【督学】
どく‐ガス【毒ガス】
毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。
⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】
どくガス‐だん【毒ガス弾】
(→)ガス弾に同じ。
⇒どく‐ガス【毒ガス】
どくが‐ろん【独我論】
〔哲〕(solipsism)実在するのはわが自我とその所産のみであって、他我や外界などすべてはわが自我の観念または意識内容にすぎないとする主観的認識論。バークリー・フィヒテ・シュティルナーらの立場。唯我論。独在論。
とくがわ【徳川】‥ガハ
姓氏の一つ。江戸幕府の将軍家。元来は、三河国加茂郡松平村の土豪で、松平を称した。上野国の新田氏(徳川・得川氏を称)の後裔として清和源氏の嫡流ちゃくりゅうを汲むというのは、家康が将軍になるために偽作・付会したといわれる。宗家のほか御三家と三卿の嫡流だけ徳川を称し、他はすべて松平氏を称。→江戸幕府(表)。
徳川(略系図)
 ⇒とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】
⇒とくがわ‐いえさだ【徳川家定】
⇒とくがわ‐いえしげ【徳川家重】
⇒とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】
⇒とくがわ‐いえつな【徳川家綱】
⇒とくがわ‐いえなり【徳川家斉】
⇒とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】
⇒とくがわ‐いえはる【徳川家治】
⇒とくがわ‐いえみつ【徳川家光】
⇒とくがわ‐いえもち【徳川家茂】
⇒とくがわ‐いえやす【徳川家康】
⇒とくがわ‐いえよし【徳川家慶】
⇒とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】
⇒とくがわ‐じだい【徳川時代】
⇒とくがわ‐じっき【徳川実紀】
⇒とくがわ‐ただなが【徳川忠長】
⇒とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】
⇒とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】
⇒とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】
⇒とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】
⇒とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】
⇒とくがわ‐みつくに【徳川光圀】
⇒とくがわ‐むせい【徳川夢声】
⇒とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】
⇒とくがわ‐むねはる【徳川宗春】
⇒とくがわ‐よしなお【徳川義直】
⇒とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】
⇒とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】
⇒とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】
⇒とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】
とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】‥ガハ‥
最後の水戸藩主。徳川斉昭の18男。三卿の清水家を相続し、1867年(慶応3)パリの万国博覧会に将軍慶喜の名代として参加。帰国後、生家を相続。(1853〜1910)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえさだ【徳川家定】‥ガハイヘ‥
徳川第13代将軍(在職1853〜1858)。家慶いえよしの4男。病弱で政務は阿部正弘らに任せる。継嗣なく、没後にいわゆる将軍継嗣問題が起きた。諡号、温恭院。(1824〜1858)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえしげ【徳川家重】‥ガハイヘ‥
徳川第9代将軍(在職1745〜1760)。吉宗の長子。言語不明瞭で、側用人大岡忠光だけがそれを理解できたという。諡号しごう、惇信院。(1711〜1761)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】‥ガハイヘ‥
徳川第7代将軍(在職1713〜1716)。家宣の3男。諡号しごう、有章院。(1709〜1716)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえつな【徳川家綱】‥ガハイヘ‥
徳川第4代将軍(在職1651〜1680)。家光の長子。保科正之・酒井忠勝・松平信綱らに補佐され、幕府の諸制度を整備。諡号しごう、厳有院。(1641〜1680)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえなり【徳川家斉】‥ガハイヘ‥
徳川第11代将軍(在職1787〜1837)。三卿の一橋治済はるさだの子。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行なったが、定信失脚後は文化・文政時代を現出。諡号しごう、文恭院。(1773〜1841)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】‥ガハイヘ‥
徳川第6代将軍(在職1709〜1712)。甲府藩主徳川綱重の長子。初名、綱豊。綱吉の養子。新井白石・間部詮房まなべあきふさを登用して政治の刷新を志すが、在職3年で没する。諡号しごう、文昭院。(1662〜1712)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえはる【徳川家治】‥ガハイヘ‥
徳川第10代将軍(在職1760〜1786)。家重の長子。田沼意次おきつぐを老中に登用し、田沼時代を現出。諡号しごう、浚明院。(1737〜1786)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえみつ【徳川家光】‥ガハイヘ‥
徳川第3代将軍(在職1623〜1651)。秀忠の次男。幼名竹千代。乳母、春日局。幕府の統治機構や参勤交代の制などを定め、キリシタン禁制を強化し、鎖国令をしき、諸侯を威圧して徳川氏隆盛の基礎を確立。諡号しごう、大猷院。(1604〜1651)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえもち【徳川家茂】‥ガハイヘ‥
徳川第14代将軍(在職1858〜1866)。紀州藩主斉順なりよりの長子。初名、慶福よしとみ。紀州藩主。のち将軍の位を継ぎ、公武合体のため和宮かずのみやと結婚。大坂城で第2次長州征討の軍を統督中に病没。諡号、昭徳院。(1846〜1866)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえやす【徳川家康】‥ガハイヘ‥
徳川初代将軍(在職1603〜1605)。松平広忠の長子。幼名、竹千代。初名、元康。今川義元に属したのち織田信長と結び、ついで豊臣秀吉と和し、1590年(天正18)関八州に封じられて江戸城に入り、秀吉の没後伏見城にあって執政。1600年(慶長5)関ヶ原の戦で石田三成らを破り、03年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれた。07年駿府に隠居後も大事は自ら決し、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府260年余の基礎を確立。諡号しごう、東照大権現。法号、安国院。(1542〜1616)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえよし【徳川家慶】‥ガハイヘ‥
徳川第12代将軍(在職1837〜1853)。家斉の次男。老中水野忠邦に命じて、いわゆる天保の改革を断行。諡号しごう、慎徳院。(1793〜1853)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】‥ガハ‥カウ
江戸幕府の法制史料集。司法省編。前集62巻、後集40巻。1878〜95年(明治11〜28)刊。前集は諸史料から収集した法令を分類、編纂。後集は1767年(明和4)の「科条類典」を主として採録。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐じだい【徳川時代】‥ガハ‥
(→)江戸時代に同じ。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐じっき【徳川実紀】‥ガハ‥
家康から10代家治に至る間の和文の編年体実録。江戸幕府が大学頭林述斎を総裁として成島司直もとなおらに編纂させたもの。1809年(文化6)起稿、43年(天保14)完成。全516巻。なお、本書に次いで家斉から慶喜までの実録を編纂した「続徳川実紀」があるが、未完成。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ただなが【徳川忠長】‥ガハ‥
江戸初期の大名。秀忠の3男。幼名国松。駿府55万石に封ぜられ、1626年(寛永3)権大納言に任。兄家光にうとまれ、また乱行が過ぎ高崎藩に預けられ、自刃じじん。駿河大納言。(1606〜1633)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】‥ガハ‥
甲府徳川家の祖。家光の次男。6代将軍家宣の父。1661年(寛文1)甲府25万石に封。(1644〜1678)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】‥ガハ‥
徳川第5代将軍(在職1680〜1709)。家光の4男。母は桂昌院。幼名、徳松。上州館林藩主から宗家を継ぐ。越後の高田騒動を親裁し、堀田正俊を大老に任じ、譜代大名・旗本・代官の綱紀を粛正、天和の治と称される善政を実現した。治世の後半には側用人牧野成貞・柳沢吉保を重用、服忌ぶっき令や生類しょうるい憐みの令を出し、社会の文明化を推進したが、人民を苦しめ、犬公方いぬくぼうとあだ名された。諡号しごう、常憲院。(1646〜1709)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】‥ガハ‥
幕末の水戸藩主。治紀はるとしの子。字は子信、号は景山・潜竜閣。藩校弘道館を開設して文武を奨励、鋭意藩政を改革、幕政を補佐したが、将軍継嗣問題で一橋派に属し、井伊大老に忌まれて永蟄居。諡号しごう、烈公。(1800〜1860)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】‥ガハ‥
(→)江戸幕府に同じ。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】‥ガハ‥
徳川第2代将軍(在職1605〜1623)。家康の3男。家康が定めた諸法度に基づき、一門・譜代を含む39大名を改易するなど、大名・朝廷・寺社の統制を強化、幕府創業に尽力。諡号しごう、台徳院。(1579〜1632)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐みつくに【徳川光圀】‥ガハ‥
江戸前期の水戸藩主。頼房の3男。字は子竜、号は梅里。彰考館を置いて「大日本史」の編纂に着手し、湊川に楠木正成の墓碑を建立。明の遺臣朱舜水を招く。権中納言となり水戸黄門と呼ばれた。晩年、西山荘に隠棲し、西山隠士と称す。義公。(1628〜1700)
→資料:『大日本史賛藪』
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むせい【徳川夢声】‥ガハ‥
映画説明者・漫談家。本名、福原駿雄としお。島根県生れ。朗読・対談・司会・著述などにも活躍。(1894〜1971)
徳川夢声(1)
撮影:田村 茂
⇒とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】
⇒とくがわ‐いえさだ【徳川家定】
⇒とくがわ‐いえしげ【徳川家重】
⇒とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】
⇒とくがわ‐いえつな【徳川家綱】
⇒とくがわ‐いえなり【徳川家斉】
⇒とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】
⇒とくがわ‐いえはる【徳川家治】
⇒とくがわ‐いえみつ【徳川家光】
⇒とくがわ‐いえもち【徳川家茂】
⇒とくがわ‐いえやす【徳川家康】
⇒とくがわ‐いえよし【徳川家慶】
⇒とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】
⇒とくがわ‐じだい【徳川時代】
⇒とくがわ‐じっき【徳川実紀】
⇒とくがわ‐ただなが【徳川忠長】
⇒とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】
⇒とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】
⇒とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】
⇒とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】
⇒とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】
⇒とくがわ‐みつくに【徳川光圀】
⇒とくがわ‐むせい【徳川夢声】
⇒とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】
⇒とくがわ‐むねはる【徳川宗春】
⇒とくがわ‐よしなお【徳川義直】
⇒とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】
⇒とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】
⇒とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】
⇒とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】
とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】‥ガハ‥
最後の水戸藩主。徳川斉昭の18男。三卿の清水家を相続し、1867年(慶応3)パリの万国博覧会に将軍慶喜の名代として参加。帰国後、生家を相続。(1853〜1910)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえさだ【徳川家定】‥ガハイヘ‥
徳川第13代将軍(在職1853〜1858)。家慶いえよしの4男。病弱で政務は阿部正弘らに任せる。継嗣なく、没後にいわゆる将軍継嗣問題が起きた。諡号、温恭院。(1824〜1858)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえしげ【徳川家重】‥ガハイヘ‥
徳川第9代将軍(在職1745〜1760)。吉宗の長子。言語不明瞭で、側用人大岡忠光だけがそれを理解できたという。諡号しごう、惇信院。(1711〜1761)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】‥ガハイヘ‥
徳川第7代将軍(在職1713〜1716)。家宣の3男。諡号しごう、有章院。(1709〜1716)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえつな【徳川家綱】‥ガハイヘ‥
徳川第4代将軍(在職1651〜1680)。家光の長子。保科正之・酒井忠勝・松平信綱らに補佐され、幕府の諸制度を整備。諡号しごう、厳有院。(1641〜1680)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえなり【徳川家斉】‥ガハイヘ‥
徳川第11代将軍(在職1787〜1837)。三卿の一橋治済はるさだの子。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行なったが、定信失脚後は文化・文政時代を現出。諡号しごう、文恭院。(1773〜1841)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】‥ガハイヘ‥
徳川第6代将軍(在職1709〜1712)。甲府藩主徳川綱重の長子。初名、綱豊。綱吉の養子。新井白石・間部詮房まなべあきふさを登用して政治の刷新を志すが、在職3年で没する。諡号しごう、文昭院。(1662〜1712)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえはる【徳川家治】‥ガハイヘ‥
徳川第10代将軍(在職1760〜1786)。家重の長子。田沼意次おきつぐを老中に登用し、田沼時代を現出。諡号しごう、浚明院。(1737〜1786)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえみつ【徳川家光】‥ガハイヘ‥
徳川第3代将軍(在職1623〜1651)。秀忠の次男。幼名竹千代。乳母、春日局。幕府の統治機構や参勤交代の制などを定め、キリシタン禁制を強化し、鎖国令をしき、諸侯を威圧して徳川氏隆盛の基礎を確立。諡号しごう、大猷院。(1604〜1651)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえもち【徳川家茂】‥ガハイヘ‥
徳川第14代将軍(在職1858〜1866)。紀州藩主斉順なりよりの長子。初名、慶福よしとみ。紀州藩主。のち将軍の位を継ぎ、公武合体のため和宮かずのみやと結婚。大坂城で第2次長州征討の軍を統督中に病没。諡号、昭徳院。(1846〜1866)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえやす【徳川家康】‥ガハイヘ‥
徳川初代将軍(在職1603〜1605)。松平広忠の長子。幼名、竹千代。初名、元康。今川義元に属したのち織田信長と結び、ついで豊臣秀吉と和し、1590年(天正18)関八州に封じられて江戸城に入り、秀吉の没後伏見城にあって執政。1600年(慶長5)関ヶ原の戦で石田三成らを破り、03年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれた。07年駿府に隠居後も大事は自ら決し、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府260年余の基礎を確立。諡号しごう、東照大権現。法号、安国院。(1542〜1616)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえよし【徳川家慶】‥ガハイヘ‥
徳川第12代将軍(在職1837〜1853)。家斉の次男。老中水野忠邦に命じて、いわゆる天保の改革を断行。諡号しごう、慎徳院。(1793〜1853)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】‥ガハ‥カウ
江戸幕府の法制史料集。司法省編。前集62巻、後集40巻。1878〜95年(明治11〜28)刊。前集は諸史料から収集した法令を分類、編纂。後集は1767年(明和4)の「科条類典」を主として採録。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐じだい【徳川時代】‥ガハ‥
(→)江戸時代に同じ。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐じっき【徳川実紀】‥ガハ‥
家康から10代家治に至る間の和文の編年体実録。江戸幕府が大学頭林述斎を総裁として成島司直もとなおらに編纂させたもの。1809年(文化6)起稿、43年(天保14)完成。全516巻。なお、本書に次いで家斉から慶喜までの実録を編纂した「続徳川実紀」があるが、未完成。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ただなが【徳川忠長】‥ガハ‥
江戸初期の大名。秀忠の3男。幼名国松。駿府55万石に封ぜられ、1626年(寛永3)権大納言に任。兄家光にうとまれ、また乱行が過ぎ高崎藩に預けられ、自刃じじん。駿河大納言。(1606〜1633)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】‥ガハ‥
甲府徳川家の祖。家光の次男。6代将軍家宣の父。1661年(寛文1)甲府25万石に封。(1644〜1678)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】‥ガハ‥
徳川第5代将軍(在職1680〜1709)。家光の4男。母は桂昌院。幼名、徳松。上州館林藩主から宗家を継ぐ。越後の高田騒動を親裁し、堀田正俊を大老に任じ、譜代大名・旗本・代官の綱紀を粛正、天和の治と称される善政を実現した。治世の後半には側用人牧野成貞・柳沢吉保を重用、服忌ぶっき令や生類しょうるい憐みの令を出し、社会の文明化を推進したが、人民を苦しめ、犬公方いぬくぼうとあだ名された。諡号しごう、常憲院。(1646〜1709)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】‥ガハ‥
幕末の水戸藩主。治紀はるとしの子。字は子信、号は景山・潜竜閣。藩校弘道館を開設して文武を奨励、鋭意藩政を改革、幕政を補佐したが、将軍継嗣問題で一橋派に属し、井伊大老に忌まれて永蟄居。諡号しごう、烈公。(1800〜1860)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】‥ガハ‥
(→)江戸幕府に同じ。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】‥ガハ‥
徳川第2代将軍(在職1605〜1623)。家康の3男。家康が定めた諸法度に基づき、一門・譜代を含む39大名を改易するなど、大名・朝廷・寺社の統制を強化、幕府創業に尽力。諡号しごう、台徳院。(1579〜1632)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐みつくに【徳川光圀】‥ガハ‥
江戸前期の水戸藩主。頼房の3男。字は子竜、号は梅里。彰考館を置いて「大日本史」の編纂に着手し、湊川に楠木正成の墓碑を建立。明の遺臣朱舜水を招く。権中納言となり水戸黄門と呼ばれた。晩年、西山荘に隠棲し、西山隠士と称す。義公。(1628〜1700)
→資料:『大日本史賛藪』
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むせい【徳川夢声】‥ガハ‥
映画説明者・漫談家。本名、福原駿雄としお。島根県生れ。朗読・対談・司会・著述などにも活躍。(1894〜1971)
徳川夢声(1)
撮影:田村 茂
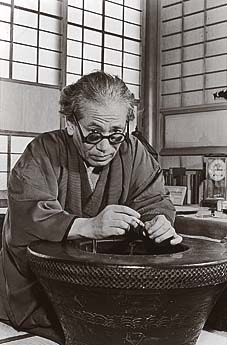 徳川夢声(2)
撮影:石井幸之助
徳川夢声(2)
撮影:石井幸之助
 ⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】‥ガハ‥
⇒たやすむねたけ(田安宗武)。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むねはる【徳川宗春】‥ガハ‥
尾張藩第7代藩主。「温知政要」を著して8代将軍吉宗の緊縮をむねとした政治を批判し、商業の重視、放任政策を説いたため、幕府から隠居させられ、著書は絶版。(1696〜1764)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしなお【徳川義直】‥ガハ‥ナホ
尾張徳川家の祖。家康の9男。名古屋城を築き、藩政の確立に尽力。儒学・軍学・神道を好む。諡号しごう、敬公。(1600〜1650)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】‥ガハ‥
徳川第15代将軍(在職1866〜1867)。徳川斉昭の7男。初め一橋家を嗣ぎ、後見職として将軍家茂を補佐、1866年(慶応2)将軍職を継いだが幕末の内憂外患に直面して、翌年遂に大政を奉還。68年鳥羽伏見の戦で敗れ、江戸城を明け渡して水戸に退き、駿府に隠棲。のち公爵。(1837〜1913)
徳川慶喜
提供:毎日新聞社
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】‥ガハ‥
⇒たやすむねたけ(田安宗武)。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むねはる【徳川宗春】‥ガハ‥
尾張藩第7代藩主。「温知政要」を著して8代将軍吉宗の緊縮をむねとした政治を批判し、商業の重視、放任政策を説いたため、幕府から隠居させられ、著書は絶版。(1696〜1764)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしなお【徳川義直】‥ガハ‥ナホ
尾張徳川家の祖。家康の9男。名古屋城を築き、藩政の確立に尽力。儒学・軍学・神道を好む。諡号しごう、敬公。(1600〜1650)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】‥ガハ‥
徳川第15代将軍(在職1866〜1867)。徳川斉昭の7男。初め一橋家を嗣ぎ、後見職として将軍家茂を補佐、1866年(慶応2)将軍職を継いだが幕末の内憂外患に直面して、翌年遂に大政を奉還。68年鳥羽伏見の戦で敗れ、江戸城を明け渡して水戸に退き、駿府に隠棲。のち公爵。(1837〜1913)
徳川慶喜
提供:毎日新聞社
 →資料:大政奉還上表文
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】‥ガハ‥
徳川第8代将軍(在職1716〜1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行なった。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684〜1751)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】‥ガハ‥
紀伊徳川家の祖。家康の10男。性剛毅で、大坂夏の陣に功を立てる。また、詩歌をよくした。諡号しごう、南竜公。(1602〜1671)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】‥ガハ‥
水戸徳川家の祖。家康の11男。領内検地を行い、藩政の基礎を築く。儒学・神道を修めた。諡号、威公。(1603〜1661)
⇒とくがわ【徳川】
どく‐がん【独眼】
かため。隻眼。
⇒どくがん‐りゅう【独眼竜】
どくがん‐りゅう【独眼竜】
[旧五代史唐書、武皇紀上]
①片目の英雄。
②伊達だて政宗の異名。
⇒どく‐がん【独眼】
と‐くき【鳥茎】
①鳥の羽の茎。
②「鳥茎の矢」の略。
⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】
とく‐ぎ【特技】
特にすぐれた技量。特別の技能。「―を披露する」「―を生かす」
とく‐ぎ【徳義】
道徳上の義理。道徳上の義務。「―心」
どく‐きのこ【毒茸】
有毒のきのこ。テングタケ・ツキヨタケ・ワライタケなど。その毒成分には神経系を侵すもの、消化器官を侵すものなどがある。どくたけ。有毒菌。
とくき‐の‐や【鳥茎の矢】
鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」
⇒と‐くき【鳥茎】
とく‐ぎゅう【犢牛】‥ギウ
こうし。
どく‐ぎょ【毒魚】
毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」
とく‐ぎょう【得業】‥ゲフ
定められた課程を学びおえること。→とくごう。
⇒とくぎょう‐せい【得業生】
とく‐ぎょう【徳業】‥ゲフ
徳行と事業。また、道徳的行為。
とくぎょう‐せい【得業生】‥ゲフ‥
①⇒とくごうしょう。
②卒業生。
⇒とく‐ぎょう【得業】
どく‐ぎん【独吟】
①一人で詩歌を吟ずること。
②一人で謡曲または歌謡をうたうこと。↔連吟。
③連歌・俳諧などの1巻を一人で作ること。また、その作品。片吟。→両吟→三吟
とく‐ぐう【特遇】
特別の待遇。殊遇。
どく‐ぐち【毒口】
毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。
どく‐ぐも【毒蜘蛛】
人間を死に至らしめるほど毒性の強いクモ。クロゴケグモ・シドニージョウゴグモ・ドクイトグモなど。3万5000種のクモのうちわずか40種ほどで、日本にも数種が生息。
とく‐ぐん【督軍】
中国で辛亥革命後、従来の総督・巡撫に代わって、省長と共に各省に置かれた地方軍政長官。多く省長を兼ねて文武の権を握り、ほとんど独立の軍閥を形成。後に督弁と改称、1928年廃止。
どく‐け【毒気】
⇒どっき
⇒どっけ
どく‐けし【毒消し】
①中毒を消すこと。解毒げどく。
②解毒剤。どっけし。
⇒どくけし‐うり【毒消し売り】
どくけし‐うり【毒消し売り】
夏、食中毒・暑気中あたりなどの薬を越後地方から売りに来た行商人。未婚女性が多く、紺絣こんがすりの筒袖に紺の手甲てっこう、地下足袋ばき、黒木綿の風呂敷の荷を背負った。どっけしうり。〈[季]夏〉。島崎藤村、千曲川のスケッチ「此節このせつ私は学校へ行く途中で、毎日のやうにその―の群に逢ふ」
⇒どく‐けし【毒消し】
とくげん【徳元】
⇒さいとうとくげん(斎藤徳元)
どく‐げん【毒言】
他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。
どく‐げん【独言】
ひとりごと。独語。
とく‐こ【独鈷】
⇒とっこ
どく‐ご【独語】
①ひとりごと。「ぶつぶつ―する」
②独逸ドイツ語の略。「―文典」
どくご【独語】
随筆。太宰春台著。1巻。和歌・茶道・俳諧・三絃・浄瑠璃・猿楽・俳優その他歌舞風俗等について、その流行・変遷などを記す。
どく‐ご【読後】
書物などを読んだあと。「―感」
とく‐ごう【得業】‥ゴフ
僧侶の学階。南都では興福寺の維摩会ゆいまえ・法華会、薬師寺の最勝会の竪義りゅうぎを勤めた者。山門では横川よかわの四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた者。また、浄土宗・浄土真宗の学階の一つ。
⇒とくごう‐しょう【得業生】
とくごう‐しょう【得業生】‥ゴフシヤウ
古代、大学の各専門課程の学生がくしょうから選ばれた少数の成績優秀者に与えられた身分。修学ののち試験に及第すると大学教官などに任じられた。730年(天平2)創設。文章得業生(定員2人)など。とくぎょうせい。
⇒とく‐ごう【得業】
とくごう‐とうげ【徳本峠】‥タウゲ
長野県西部、飛騨山脈東麓にある峠。安曇野から上高地に入る登山路に沿う。標高2135メートル。
→資料:大政奉還上表文
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】‥ガハ‥
徳川第8代将軍(在職1716〜1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行なった。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684〜1751)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】‥ガハ‥
紀伊徳川家の祖。家康の10男。性剛毅で、大坂夏の陣に功を立てる。また、詩歌をよくした。諡号しごう、南竜公。(1602〜1671)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】‥ガハ‥
水戸徳川家の祖。家康の11男。領内検地を行い、藩政の基礎を築く。儒学・神道を修めた。諡号、威公。(1603〜1661)
⇒とくがわ【徳川】
どく‐がん【独眼】
かため。隻眼。
⇒どくがん‐りゅう【独眼竜】
どくがん‐りゅう【独眼竜】
[旧五代史唐書、武皇紀上]
①片目の英雄。
②伊達だて政宗の異名。
⇒どく‐がん【独眼】
と‐くき【鳥茎】
①鳥の羽の茎。
②「鳥茎の矢」の略。
⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】
とく‐ぎ【特技】
特にすぐれた技量。特別の技能。「―を披露する」「―を生かす」
とく‐ぎ【徳義】
道徳上の義理。道徳上の義務。「―心」
どく‐きのこ【毒茸】
有毒のきのこ。テングタケ・ツキヨタケ・ワライタケなど。その毒成分には神経系を侵すもの、消化器官を侵すものなどがある。どくたけ。有毒菌。
とくき‐の‐や【鳥茎の矢】
鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」
⇒と‐くき【鳥茎】
とく‐ぎゅう【犢牛】‥ギウ
こうし。
どく‐ぎょ【毒魚】
毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」
とく‐ぎょう【得業】‥ゲフ
定められた課程を学びおえること。→とくごう。
⇒とくぎょう‐せい【得業生】
とく‐ぎょう【徳業】‥ゲフ
徳行と事業。また、道徳的行為。
とくぎょう‐せい【得業生】‥ゲフ‥
①⇒とくごうしょう。
②卒業生。
⇒とく‐ぎょう【得業】
どく‐ぎん【独吟】
①一人で詩歌を吟ずること。
②一人で謡曲または歌謡をうたうこと。↔連吟。
③連歌・俳諧などの1巻を一人で作ること。また、その作品。片吟。→両吟→三吟
とく‐ぐう【特遇】
特別の待遇。殊遇。
どく‐ぐち【毒口】
毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。
どく‐ぐも【毒蜘蛛】
人間を死に至らしめるほど毒性の強いクモ。クロゴケグモ・シドニージョウゴグモ・ドクイトグモなど。3万5000種のクモのうちわずか40種ほどで、日本にも数種が生息。
とく‐ぐん【督軍】
中国で辛亥革命後、従来の総督・巡撫に代わって、省長と共に各省に置かれた地方軍政長官。多く省長を兼ねて文武の権を握り、ほとんど独立の軍閥を形成。後に督弁と改称、1928年廃止。
どく‐け【毒気】
⇒どっき
⇒どっけ
どく‐けし【毒消し】
①中毒を消すこと。解毒げどく。
②解毒剤。どっけし。
⇒どくけし‐うり【毒消し売り】
どくけし‐うり【毒消し売り】
夏、食中毒・暑気中あたりなどの薬を越後地方から売りに来た行商人。未婚女性が多く、紺絣こんがすりの筒袖に紺の手甲てっこう、地下足袋ばき、黒木綿の風呂敷の荷を背負った。どっけしうり。〈[季]夏〉。島崎藤村、千曲川のスケッチ「此節このせつ私は学校へ行く途中で、毎日のやうにその―の群に逢ふ」
⇒どく‐けし【毒消し】
とくげん【徳元】
⇒さいとうとくげん(斎藤徳元)
どく‐げん【毒言】
他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。
どく‐げん【独言】
ひとりごと。独語。
とく‐こ【独鈷】
⇒とっこ
どく‐ご【独語】
①ひとりごと。「ぶつぶつ―する」
②独逸ドイツ語の略。「―文典」
どくご【独語】
随筆。太宰春台著。1巻。和歌・茶道・俳諧・三絃・浄瑠璃・猿楽・俳優その他歌舞風俗等について、その流行・変遷などを記す。
どく‐ご【読後】
書物などを読んだあと。「―感」
とく‐ごう【得業】‥ゴフ
僧侶の学階。南都では興福寺の維摩会ゆいまえ・法華会、薬師寺の最勝会の竪義りゅうぎを勤めた者。山門では横川よかわの四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた者。また、浄土宗・浄土真宗の学階の一つ。
⇒とくごう‐しょう【得業生】
とくごう‐しょう【得業生】‥ゴフシヤウ
古代、大学の各専門課程の学生がくしょうから選ばれた少数の成績優秀者に与えられた身分。修学ののち試験に及第すると大学教官などに任じられた。730年(天平2)創設。文章得業生(定員2人)など。とくぎょうせい。
⇒とく‐ごう【得業】
とくごう‐とうげ【徳本峠】‥タウゲ
長野県西部、飛騨山脈東麓にある峠。安曇野から上高地に入る登山路に沿う。標高2135メートル。
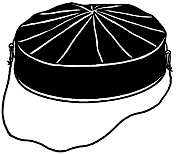 ②野ざらしになる柱の上部を方錐形にした部分。これを包む金物を頭巾金物という。
③丸太の両端を、搬出の際の損傷を防ぐために、1の形にとがらすこと。また、その部分。
⇒ときん‐いばら【頭巾薔薇】
と‐きん【鍍金】
①金を銅製品の表面に焼き付けめっきをすること。金を水銀に溶解させて作ったアマルガムを銅の表面に塗り、加熱により水銀を蒸発させる。焼き付けたものを金銅こんどうという。また、銀を焼き付けることを鍍銀という。
②⇒めっき
と‐ぎん【都銀】
都市銀行の略。
どきん
急な物事に驚きおそれて動悸どうきのうつさま。どきり。「怪しい人影に―とする」
ときん‐いばら【頭巾薔薇】
バラ科キイチゴ属の落葉低木。中国原産で観賞用。高さ1.5メートルに達し、若枝・葉柄にとげがある。葉は羽状複葉。夏にバラに似た大形白色の重弁花をつける。ボタンイバラ。
⇒と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】
ときん‐そう【吐金草】‥サウ
キク科の一年草。高さ約10センチメートル。多くは地に臥して群生。葉は基部狭く、3〜5の鋸歯がある。夏、淡緑色で褐紫色を帯びた球状の頭花を開く。花後、4稜ある黄色の果実を結び、花をつぶすとこれが出てくるのが、名の由来という。
とき‐ん‐ば【時んば】
(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」
とく【特】
ことにぬきんでること。他と別であること。とりわけ。「―に言うことはない」
とく【得】
①えること。手に入れること。徒然草「芸能・所作のみにあらず。大方のふるまひ・心づかひも、愚かにしてつつしめるは―の本なり」
②身につけること。さとること。
③もうけること。利益。また、有利なこと。落窪物語1「時の受領ずりようは世に―有る物といへば、只今そのほどなめれば、つかうまつらむ」。「―をする」「―な性分」→とく(徳)3
⇒得を取ろうより名を取れ
とく【徳】
①道をさとった立派な行為。善い行いをする性格。身についた品性。徒然草「人に本意なく思はせて我が心を慰まん事、―に背そむけり」。「―が高い」
②人を感化する人格の力。めぐみ。神仏の加護。枕草子161「宰相の中将の―を見ること。その方に向ひて拝むべし」。源氏物語澪標「心のうちに神の御―をあはれにめでたしと思ふ」。
③(「得」と通用)利益。もうけ。富。「有―人うとくじん」
⇒徳孤ならず必ず隣あり
⇒徳とする
⇒徳をもって怨みに報いる
と・く【着く】
〔自四〕
(ツクの転)到着する。つく。古事記中「伊知遅いちじ島、美島に―・き」
と・く【解く】
[一]〔他五〕
結ばれたり、こり固まったり、閉ざされたり、不明であったりしたものを、ゆるめほぐした状態にする意。
➊結びつけられているものを分けはなす。
①結び目をほどく。天智紀「臣の子の八重の紐―・く一重だにいまだ―・かねば御子の紐―・く」。平家物語11「判官剰あまつさへ封をも―・かず」。「帯を―・く」
②束ねてあるものをばらばらにする。万葉集16「か黒し髪を…挙げても巻き見―・き乱り童児わらわになし見」
③縫ってあるものをほどく。万葉集12「橡つるばみの衣―・き洗ひ」
④纏まとっていたものを脱ぐ。装っていたものをとりはずす。蜻蛉日記中「御車のしやうぞく―・きて」。今昔物語集1「身の瓔珞ようらくを脱ときて」。「旅装を―・く」
⑤(「梳く」とも書く)乱れもつれたものを分けはなして整える。髪をくしけずる。梳すく。源氏物語手習「髪は尼君のみ梳けずり給ふを…ただ少し―・きくだして」
⑥むすぼれた気持をさっぱりさせる。はらす。「愁いを―・く」「誤解を―・く」「緊張を―・く」
⑦束縛などをとりのぞく。「統制を―・く」
⑧警備などのために固めていた態勢をくずす。「警戒を―・く」「城の囲みを―・く」
⑨魚や鳥獣などを刃物で切りひらく。また、解剖する。蘭学事始「獣畜を―・きて、視あはせしことも度々の事なりき」
➋不明のものを明らかにする。
①答を出す。徒然草「なぞなぞを作りて―・かれける所へ」。「方程式を―・く」「事件を―・く鍵」
②説明する。解釈する。源氏物語賢木「六十巻といふふみよみ給ひ、覚束なき所々―・かせなどしておはしますを」
➌職をやめさせる。免ずる。「任を―・く」
[二]〔自下二〕
⇒とける(下一)
と・く【溶く・融く・熔く・鎔く】
(「解く」と同源)
[一]〔他五〕
液体に他の物質をまぜて均一な液体をつくる。「アルコールを水に―・く」「卵を―・く」
[二]〔自下二〕
⇒とける(下一)
◇「熔」「鎔」は、金属を液状にする場合に使う。
と・く【説く】
(「解く」と同源)〔他五〕
相手を納得させるために、物事の道理・筋道をわかりやすく述べる意。
①道理をいいさとす。源氏物語蛍「仏のいとうるはしき心にて、―・きおき給へる御法も」。「じゅんじゅんと―・く」
②解説する。説明する。源氏物語橋姫「年頃学び知り給へる事どもの深き心を―・き聞かせ奉り」。「語義を―・く」
とく【疾く】
(形容詞「疾し」の連用形)
①はやく。すみやかに。急に。「―行け」
②すでに。もう。とっく。「―御存知」
と・ぐ【研ぐ・磨ぐ】
〔他五〕
①玉・金属などをみがいて光沢を出す。「鏡を―・ぐ」
②刃物などを砥石ですって鋭くする。万葉集20「剣大刀いよよ―・ぐべし」。「包丁を―・ぐ」
③水中でこすって洗う。「米を―・ぐ」
④心などを練磨して立派にする。万葉集4「―・ぎし心を」
と・ぐ【遂ぐ】
〔他下二〕
⇒とげる(下一)
どく【毒】
①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」
②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」
③わざわい。
④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」
⇒毒にも薬にもならない
⇒毒を食わば皿まで
⇒毒を以て毒を制す
どく【独】
独逸ドイツの略。
ど・く【退く】
[一]〔自五〕
しりぞく。のく。ひく。浮世風呂2「湯水を遣つかふのだものを、かかるが悪くは、遠くへ―・いてるがいい」。「そこを―・け」
[二]〔他下二〕
⇒どける(下一)
どく‐あく【毒悪】
非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」
どく‐あたり【毒中り】
飲食物の毒または毒薬にあたって健康を害すること。中毒。
とく‐い【特異】
他のものと非常に異なっていること。「―な風習」「―な能力」
⇒とくい‐せい【特異性】
⇒とくい‐たいしつ【特異体質】
⇒とくい‐てん【特異点】
⇒とくい‐び【特異日】
とく‐い【得意】
①志をえて満足していること。望みどおりになって満足すること。「―の絶頂」↔失意。
②誇りたかぶること。また、誇らしげなさま。「―になって自慢する」
③最も熟練していること。最もすぐれていること。えて。「―の種目」「―の芸」
④親しい友。親友。源氏物語明石「入道はかの国の―にて、年頃あひ語らひ侍りつれど」
⑤ひいきにしてくれること。また、その人。枕草子87「御―ななり。さらによも語らひとらじ」
⑥(→)得意先に同じ。好色一代男2「元来もとより商ひの―殊更にあしらひ」。「御―様」
⇒とくい‐がお【得意顔】
⇒とくい‐げ【得意気】
⇒とくい‐さき【得意先】
⇒とくい‐ば【得意場】
⇒とくい‐まわり【得意回り】
⇒とくい‐まんめん【得意満面】
と‐ぐい【利杙】‥グヒ
先のとがったくい。源平盛衰記8「竹の―に貫かれて失せにけり」
とくい‐がお【得意顔】‥ガホ
誇らしげな顔つき。自慢そうな様子。
⇒とく‐い【得意】
とく‐いく【徳育】
道徳面の教育。森有礼、兵式体操に関する上奏案「夫レ教育ノ要タル、智育―体育ノ三者ヲシテ斉ひとシク発達セシムルニ在リ」→知育→体育
とくい‐げ【得意気】
得意そうであること。得意らしい様子。「―に技を披露する」
⇒とく‐い【得意】
とくい‐さき【得意先】
日常よく取引している相手方。商家などで常に買ってくれる客。取引先。「―を回る」
⇒とく‐い【得意】
とくい‐せい【特異性】
①事物にそなわっている特殊な性質。特殊性。
②〔化〕2種の基質間の高い選択的な反応性。免疫反応における抗原と抗体の反応など。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐たいしつ【特異体質】
一般的にある種の食物や化学物質、薬物などに対して過敏に反応する体質をいう。食物ではエビ・カニ・サバ・卵白など、薬物ではピリン・ヨードなどに対するものがしばしば見られ、多くアレルギーが基礎にある。イディオジンクラジー。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐てん【特異点】
〔数〕
①曲線上あるいは曲面上で、接線あるいは接平面が存在しなかったり、二つ以上存在したりするような点。
②複素関数が連続な導関数をもたないような点。
⇒とく‐い【特異】
どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】
イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。
とくい‐ば【得意場】
(→)得意先に同じ。
⇒とく‐い【得意】
とくい‐び【特異日】
例年、ある天気が高い確率で現れる特定の日。例えば、11月3日は晴れることが多く、9月17日と26日は強い台風の襲来が多いなど。シンギュラリティー。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐まわり【得意回り】‥マハリ
得意先を訪ねてまわること。
⇒とく‐い【得意】
とくい‐まんめん【得意満面】
得意な心持が顔全体に現れること。いかにも満足そうな様子。「―な語り口」
⇒とく‐い【得意】
どく‐いみ【毒忌】
主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。
とくいん‐がい【特飲街】
特殊飲食店の立ち並ぶまち。
ド‐クインシー【Thomas De Quincey】
イギリスの批評家・作家。自分の体験に基づく「阿片常用者の告白」や評論「芸術として見た殺人」がある。(1785〜1859)
ど‐くう【土公】
(→)土公神どくじんのこと。
ど‐ぐう【土偶】
①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。
②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木
②野ざらしになる柱の上部を方錐形にした部分。これを包む金物を頭巾金物という。
③丸太の両端を、搬出の際の損傷を防ぐために、1の形にとがらすこと。また、その部分。
⇒ときん‐いばら【頭巾薔薇】
と‐きん【鍍金】
①金を銅製品の表面に焼き付けめっきをすること。金を水銀に溶解させて作ったアマルガムを銅の表面に塗り、加熱により水銀を蒸発させる。焼き付けたものを金銅こんどうという。また、銀を焼き付けることを鍍銀という。
②⇒めっき
と‐ぎん【都銀】
都市銀行の略。
どきん
急な物事に驚きおそれて動悸どうきのうつさま。どきり。「怪しい人影に―とする」
ときん‐いばら【頭巾薔薇】
バラ科キイチゴ属の落葉低木。中国原産で観賞用。高さ1.5メートルに達し、若枝・葉柄にとげがある。葉は羽状複葉。夏にバラに似た大形白色の重弁花をつける。ボタンイバラ。
⇒と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】
ときん‐そう【吐金草】‥サウ
キク科の一年草。高さ約10センチメートル。多くは地に臥して群生。葉は基部狭く、3〜5の鋸歯がある。夏、淡緑色で褐紫色を帯びた球状の頭花を開く。花後、4稜ある黄色の果実を結び、花をつぶすとこれが出てくるのが、名の由来という。
とき‐ん‐ば【時んば】
(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」
とく【特】
ことにぬきんでること。他と別であること。とりわけ。「―に言うことはない」
とく【得】
①えること。手に入れること。徒然草「芸能・所作のみにあらず。大方のふるまひ・心づかひも、愚かにしてつつしめるは―の本なり」
②身につけること。さとること。
③もうけること。利益。また、有利なこと。落窪物語1「時の受領ずりようは世に―有る物といへば、只今そのほどなめれば、つかうまつらむ」。「―をする」「―な性分」→とく(徳)3
⇒得を取ろうより名を取れ
とく【徳】
①道をさとった立派な行為。善い行いをする性格。身についた品性。徒然草「人に本意なく思はせて我が心を慰まん事、―に背そむけり」。「―が高い」
②人を感化する人格の力。めぐみ。神仏の加護。枕草子161「宰相の中将の―を見ること。その方に向ひて拝むべし」。源氏物語澪標「心のうちに神の御―をあはれにめでたしと思ふ」。
③(「得」と通用)利益。もうけ。富。「有―人うとくじん」
⇒徳孤ならず必ず隣あり
⇒徳とする
⇒徳をもって怨みに報いる
と・く【着く】
〔自四〕
(ツクの転)到着する。つく。古事記中「伊知遅いちじ島、美島に―・き」
と・く【解く】
[一]〔他五〕
結ばれたり、こり固まったり、閉ざされたり、不明であったりしたものを、ゆるめほぐした状態にする意。
➊結びつけられているものを分けはなす。
①結び目をほどく。天智紀「臣の子の八重の紐―・く一重だにいまだ―・かねば御子の紐―・く」。平家物語11「判官剰あまつさへ封をも―・かず」。「帯を―・く」
②束ねてあるものをばらばらにする。万葉集16「か黒し髪を…挙げても巻き見―・き乱り童児わらわになし見」
③縫ってあるものをほどく。万葉集12「橡つるばみの衣―・き洗ひ」
④纏まとっていたものを脱ぐ。装っていたものをとりはずす。蜻蛉日記中「御車のしやうぞく―・きて」。今昔物語集1「身の瓔珞ようらくを脱ときて」。「旅装を―・く」
⑤(「梳く」とも書く)乱れもつれたものを分けはなして整える。髪をくしけずる。梳すく。源氏物語手習「髪は尼君のみ梳けずり給ふを…ただ少し―・きくだして」
⑥むすぼれた気持をさっぱりさせる。はらす。「愁いを―・く」「誤解を―・く」「緊張を―・く」
⑦束縛などをとりのぞく。「統制を―・く」
⑧警備などのために固めていた態勢をくずす。「警戒を―・く」「城の囲みを―・く」
⑨魚や鳥獣などを刃物で切りひらく。また、解剖する。蘭学事始「獣畜を―・きて、視あはせしことも度々の事なりき」
➋不明のものを明らかにする。
①答を出す。徒然草「なぞなぞを作りて―・かれける所へ」。「方程式を―・く」「事件を―・く鍵」
②説明する。解釈する。源氏物語賢木「六十巻といふふみよみ給ひ、覚束なき所々―・かせなどしておはしますを」
➌職をやめさせる。免ずる。「任を―・く」
[二]〔自下二〕
⇒とける(下一)
と・く【溶く・融く・熔く・鎔く】
(「解く」と同源)
[一]〔他五〕
液体に他の物質をまぜて均一な液体をつくる。「アルコールを水に―・く」「卵を―・く」
[二]〔自下二〕
⇒とける(下一)
◇「熔」「鎔」は、金属を液状にする場合に使う。
と・く【説く】
(「解く」と同源)〔他五〕
相手を納得させるために、物事の道理・筋道をわかりやすく述べる意。
①道理をいいさとす。源氏物語蛍「仏のいとうるはしき心にて、―・きおき給へる御法も」。「じゅんじゅんと―・く」
②解説する。説明する。源氏物語橋姫「年頃学び知り給へる事どもの深き心を―・き聞かせ奉り」。「語義を―・く」
とく【疾く】
(形容詞「疾し」の連用形)
①はやく。すみやかに。急に。「―行け」
②すでに。もう。とっく。「―御存知」
と・ぐ【研ぐ・磨ぐ】
〔他五〕
①玉・金属などをみがいて光沢を出す。「鏡を―・ぐ」
②刃物などを砥石ですって鋭くする。万葉集20「剣大刀いよよ―・ぐべし」。「包丁を―・ぐ」
③水中でこすって洗う。「米を―・ぐ」
④心などを練磨して立派にする。万葉集4「―・ぎし心を」
と・ぐ【遂ぐ】
〔他下二〕
⇒とげる(下一)
どく【毒】
①生命または健康を害するもの。特に、そのような薬物。今昔物語集1「我が手の指の端に―を塗りて仏の御足を礼らいし奉る様にて―を付けむとするに」
②人の心をきずつけるもの。悪いもの。「―のある言い方」
③わざわい。
④毒口どくぐちの略。悪口。誹風柳多留2「梶原が塀には―を書きちらし」。「―を言う」
⇒毒にも薬にもならない
⇒毒を食わば皿まで
⇒毒を以て毒を制す
どく【独】
独逸ドイツの略。
ど・く【退く】
[一]〔自五〕
しりぞく。のく。ひく。浮世風呂2「湯水を遣つかふのだものを、かかるが悪くは、遠くへ―・いてるがいい」。「そこを―・け」
[二]〔他下二〕
⇒どける(下一)
どく‐あく【毒悪】
非常にわるいこと。甚だしく害をなすこと。害毒。夏目漱石、吾輩は猫である「余り長たらしくつて―なのはよくない」
どく‐あたり【毒中り】
飲食物の毒または毒薬にあたって健康を害すること。中毒。
とく‐い【特異】
他のものと非常に異なっていること。「―な風習」「―な能力」
⇒とくい‐せい【特異性】
⇒とくい‐たいしつ【特異体質】
⇒とくい‐てん【特異点】
⇒とくい‐び【特異日】
とく‐い【得意】
①志をえて満足していること。望みどおりになって満足すること。「―の絶頂」↔失意。
②誇りたかぶること。また、誇らしげなさま。「―になって自慢する」
③最も熟練していること。最もすぐれていること。えて。「―の種目」「―の芸」
④親しい友。親友。源氏物語明石「入道はかの国の―にて、年頃あひ語らひ侍りつれど」
⑤ひいきにしてくれること。また、その人。枕草子87「御―ななり。さらによも語らひとらじ」
⑥(→)得意先に同じ。好色一代男2「元来もとより商ひの―殊更にあしらひ」。「御―様」
⇒とくい‐がお【得意顔】
⇒とくい‐げ【得意気】
⇒とくい‐さき【得意先】
⇒とくい‐ば【得意場】
⇒とくい‐まわり【得意回り】
⇒とくい‐まんめん【得意満面】
と‐ぐい【利杙】‥グヒ
先のとがったくい。源平盛衰記8「竹の―に貫かれて失せにけり」
とくい‐がお【得意顔】‥ガホ
誇らしげな顔つき。自慢そうな様子。
⇒とく‐い【得意】
とく‐いく【徳育】
道徳面の教育。森有礼、兵式体操に関する上奏案「夫レ教育ノ要タル、智育―体育ノ三者ヲシテ斉ひとシク発達セシムルニ在リ」→知育→体育
とくい‐げ【得意気】
得意そうであること。得意らしい様子。「―に技を披露する」
⇒とく‐い【得意】
とくい‐さき【得意先】
日常よく取引している相手方。商家などで常に買ってくれる客。取引先。「―を回る」
⇒とく‐い【得意】
とくい‐せい【特異性】
①事物にそなわっている特殊な性質。特殊性。
②〔化〕2種の基質間の高い選択的な反応性。免疫反応における抗原と抗体の反応など。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐たいしつ【特異体質】
一般的にある種の食物や化学物質、薬物などに対して過敏に反応する体質をいう。食物ではエビ・カニ・サバ・卵白など、薬物ではピリン・ヨードなどに対するものがしばしば見られ、多くアレルギーが基礎にある。イディオジンクラジー。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐てん【特異点】
〔数〕
①曲線上あるいは曲面上で、接線あるいは接平面が存在しなかったり、二つ以上存在したりするような点。
②複素関数が連続な導関数をもたないような点。
⇒とく‐い【特異】
どく‐いとぐも【毒糸蜘蛛】
イトグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、体は茶色で歩脚は細長い。南北アメリカに生息。暗所に不規則に糸を引いた網を張り、しばしば人家でもみつかる。特定外来生物。
とくい‐ば【得意場】
(→)得意先に同じ。
⇒とく‐い【得意】
とくい‐び【特異日】
例年、ある天気が高い確率で現れる特定の日。例えば、11月3日は晴れることが多く、9月17日と26日は強い台風の襲来が多いなど。シンギュラリティー。
⇒とく‐い【特異】
とくい‐まわり【得意回り】‥マハリ
得意先を訪ねてまわること。
⇒とく‐い【得意】
とくい‐まんめん【得意満面】
得意な心持が顔全体に現れること。いかにも満足そうな様子。「―な語り口」
⇒とく‐い【得意】
どく‐いみ【毒忌】
主として服薬の時、その薬のさわりとなるものを飲食しないこと。禁忌。
とくいん‐がい【特飲街】
特殊飲食店の立ち並ぶまち。
ド‐クインシー【Thomas De Quincey】
イギリスの批評家・作家。自分の体験に基づく「阿片常用者の告白」や評論「芸術として見た殺人」がある。(1785〜1859)
ど‐くう【土公】
(→)土公神どくじんのこと。
ど‐ぐう【土偶】
①人物や動物をかたどった土製品。つちにんぎょう。
②縄文時代を通じてある、人の形につくった土製品。呪術用または護符的なものか。大部分は女性をかたどっている。形によってハート形・木 みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。
土偶
みみずく・遮光器土偶などの名で呼ばれる。東日本に多い。
土偶
 トクヴィル【Alexis de Tocqueville】
フランスの政治家。1830年代に米国を旅行。その見聞をもとにした「アメリカの民主政治」は、米国政治研究の古典。(1805〜1859)
どく‐うつぎ【毒空木】
ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。
どくうつぎ
トクヴィル【Alexis de Tocqueville】
フランスの政治家。1830年代に米国を旅行。その見聞をもとにした「アメリカの民主政治」は、米国政治研究の古典。(1805〜1859)
どく‐うつぎ【毒空木】
ドクウツギ科の落葉低木。北海道・本州の山地・川原などに自生。高さ1〜2メートル。葉は無柄、3条の縦脈がある。春、黄緑色の細花をつける。雌雄同株。果実は豆粒大で赤、後に紫黒色。根に根瘤こんりゅうをもつ。枝葉・果実に劇毒を含む。
どくうつぎ
 どく‐え【毒荏】
〔植〕アブラギリの異称。
どく‐えい【独泳】
①ひとりで泳ぐこと。
②他を引き離して泳ぐこと。
どく‐えき【毒液】
毒をふくんだ液体。
どく‐えん【毒焔】
①有毒ガスを発散するほのお。
②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。
どく‐えん【独演】
演芸・講演などを一人だけで通して行うこと。また、その演芸・講演。「落語―会」
とく‐おう【徳王】‥ワウ
内モンゴルの政治家。本名デムチュクドンロプ。王公の家庭に生まれ、自治権獲得運動に従事。1939年日本の援助下に蒙古聯合自治政府を樹立、主席に就任。日本の敗戦後、外モンゴルで捕らえられ、中国送還。63年釈放後、内モンゴル自治区文史館勤務。(1902〜1966)
とくおう【徳応】
私年号の一つ。→私年号(表)
どく‐おう【独往】‥ワウ
他を省みず自主的に進むこと。
どくおう‐がっぽう【独墺合邦】‥アウ‥パウ
1938年3月、ナチス政権がオーストリアをドイツに併合したこと。
とくおか【徳岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒とくおか‐しんせん【徳岡神泉】
とくおか‐しんせん【徳岡神泉】‥ヲカ‥
日本画家。本名、時次郎。京都生れ。竹内栖鳳せいほうに学ぶ。奥深い象徴的な画風を確立。文化勲章。(1896〜1972)
⇒とくおか【徳岡】
とく‐おん【特恩】
特別の恩恵。
どく‐が【毒牙】
①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。
②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」
どく‐が【毒蛾】
①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。
②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。
どく‐が【独臥】‥グワ
ひとりで寝ること。ひとりね。〈運歩色葉集〉
どく‐がい【毒害】
①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。
②甚だしくそこなうこと。残害。
どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ
①毒を飲ませること。
②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」
とく‐がく【督学】
学事を監督すること。また、その人。
⇒とくがく‐かん【督学官】
とく‐がく【篤学】
学問に熱心にはげむこと。また、広く学問に通ずること。「―の士」
どく‐がく【独学】
師に就かずに独力で学問すること。「―で資格を取る」「フランス語を―する」
とくがく‐かん【督学官】‥クワン
旧制の教育行政官。1913年(大正2)視学官を改称して置かれた。文部大臣の指揮を受けて学事の視察監督をつかさどった。
⇒とく‐がく【督学】
どく‐ガス【毒ガス】
毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。
⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】
どくガス‐だん【毒ガス弾】
(→)ガス弾に同じ。
⇒どく‐ガス【毒ガス】
どくが‐ろん【独我論】
〔哲〕(solipsism)実在するのはわが自我とその所産のみであって、他我や外界などすべてはわが自我の観念または意識内容にすぎないとする主観的認識論。バークリー・フィヒテ・シュティルナーらの立場。唯我論。独在論。
とくがわ【徳川】‥ガハ
姓氏の一つ。江戸幕府の将軍家。元来は、三河国加茂郡松平村の土豪で、松平を称した。上野国の新田氏(徳川・得川氏を称)の後裔として清和源氏の嫡流ちゃくりゅうを汲むというのは、家康が将軍になるために偽作・付会したといわれる。宗家のほか御三家と三卿の嫡流だけ徳川を称し、他はすべて松平氏を称。→江戸幕府(表)。
徳川(略系図)
どく‐え【毒荏】
〔植〕アブラギリの異称。
どく‐えい【独泳】
①ひとりで泳ぐこと。
②他を引き離して泳ぐこと。
どく‐えき【毒液】
毒をふくんだ液体。
どく‐えん【毒焔】
①有毒ガスを発散するほのお。
②賊徒・奸人などの勢いのさかんなことのたとえ。
どく‐えん【独演】
演芸・講演などを一人だけで通して行うこと。また、その演芸・講演。「落語―会」
とく‐おう【徳王】‥ワウ
内モンゴルの政治家。本名デムチュクドンロプ。王公の家庭に生まれ、自治権獲得運動に従事。1939年日本の援助下に蒙古聯合自治政府を樹立、主席に就任。日本の敗戦後、外モンゴルで捕らえられ、中国送還。63年釈放後、内モンゴル自治区文史館勤務。(1902〜1966)
とくおう【徳応】
私年号の一つ。→私年号(表)
どく‐おう【独往】‥ワウ
他を省みず自主的に進むこと。
どくおう‐がっぽう【独墺合邦】‥アウ‥パウ
1938年3月、ナチス政権がオーストリアをドイツに併合したこと。
とくおか【徳岡】‥ヲカ
姓氏の一つ。
⇒とくおか‐しんせん【徳岡神泉】
とくおか‐しんせん【徳岡神泉】‥ヲカ‥
日本画家。本名、時次郎。京都生れ。竹内栖鳳せいほうに学ぶ。奥深い象徴的な画風を確立。文化勲章。(1896〜1972)
⇒とくおか【徳岡】
とく‐おん【特恩】
特別の恩恵。
どく‐が【毒牙】
①毒液を注入する牙。特に、毒蛇の牙。上顎骨に一対またはそれ以上あり、他の歯に比べ大形。基部には毒腺が開口、分泌された毒液は牙にある溝(溝牙)または管(管牙)を通って出る。前者にはコブラ・ウミヘビなど、後者にはマムシ・ハブ・ガラガラヘビ・クサリヘビなどがある。
②転じて、悪辣あくらつなたくらみ・手段などのたとえ。毒手。「―にかかる」
どく‐が【毒蛾】
①チョウ目ドクガ科のガの総称。一部の種は毒毛をもち、皮膚炎の原因となる。その一種のドクガは、中形で黄色、前翅に紫褐色の横帯がある。幼虫は、サクラやクヌギの葉を食う毛虫で、まばらな毛のほかに、叢毛を持ち、黒褐色で赤い線がある。成虫も幼虫も、その毛に触れれば、激しいかゆみを生ずる。夏、灯光に集まる。ナミドクガ。
②俗に、翅はねに毒々しく気味の悪い斑紋のある蛾。
どく‐が【独臥】‥グワ
ひとりで寝ること。ひとりね。〈運歩色葉集〉
どく‐がい【毒害】
①毒を飲ませて殺害すること。毒殺。
②甚だしくそこなうこと。残害。
どく‐がい【毒飼い】‥ガヒ
①毒を飲ませること。
②身をそこなわすこと。浄瑠璃、女殺油地獄「其の甘やかしが皆―」
とく‐がく【督学】
学事を監督すること。また、その人。
⇒とくがく‐かん【督学官】
とく‐がく【篤学】
学問に熱心にはげむこと。また、広く学問に通ずること。「―の士」
どく‐がく【独学】
師に就かずに独力で学問すること。「―で資格を取る」「フランス語を―する」
とくがく‐かん【督学官】‥クワン
旧制の教育行政官。1913年(大正2)視学官を改称して置かれた。文部大臣の指揮を受けて学事の視察監督をつかさどった。
⇒とく‐がく【督学】
どく‐ガス【毒ガス】
毒性を有する気体。一般には軍事目的で気化して使用する化合物を指し、第一次大戦でドイツ軍が初めて使用。ホスゲン・ジホスゲン(窒息性)、クロロジフェニルアルシン・アダムサイト(くしゃみ性)、塩化ピクリン・臭化ベンジル(催涙性)、ルイサイト・イペリット(糜爛びらん性)、青酸(中毒性)、各種の神経ガスなど多くの種類がある。
⇒どくガス‐だん【毒ガス弾】
どくガス‐だん【毒ガス弾】
(→)ガス弾に同じ。
⇒どく‐ガス【毒ガス】
どくが‐ろん【独我論】
〔哲〕(solipsism)実在するのはわが自我とその所産のみであって、他我や外界などすべてはわが自我の観念または意識内容にすぎないとする主観的認識論。バークリー・フィヒテ・シュティルナーらの立場。唯我論。独在論。
とくがわ【徳川】‥ガハ
姓氏の一つ。江戸幕府の将軍家。元来は、三河国加茂郡松平村の土豪で、松平を称した。上野国の新田氏(徳川・得川氏を称)の後裔として清和源氏の嫡流ちゃくりゅうを汲むというのは、家康が将軍になるために偽作・付会したといわれる。宗家のほか御三家と三卿の嫡流だけ徳川を称し、他はすべて松平氏を称。→江戸幕府(表)。
徳川(略系図)
 ⇒とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】
⇒とくがわ‐いえさだ【徳川家定】
⇒とくがわ‐いえしげ【徳川家重】
⇒とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】
⇒とくがわ‐いえつな【徳川家綱】
⇒とくがわ‐いえなり【徳川家斉】
⇒とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】
⇒とくがわ‐いえはる【徳川家治】
⇒とくがわ‐いえみつ【徳川家光】
⇒とくがわ‐いえもち【徳川家茂】
⇒とくがわ‐いえやす【徳川家康】
⇒とくがわ‐いえよし【徳川家慶】
⇒とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】
⇒とくがわ‐じだい【徳川時代】
⇒とくがわ‐じっき【徳川実紀】
⇒とくがわ‐ただなが【徳川忠長】
⇒とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】
⇒とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】
⇒とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】
⇒とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】
⇒とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】
⇒とくがわ‐みつくに【徳川光圀】
⇒とくがわ‐むせい【徳川夢声】
⇒とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】
⇒とくがわ‐むねはる【徳川宗春】
⇒とくがわ‐よしなお【徳川義直】
⇒とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】
⇒とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】
⇒とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】
⇒とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】
とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】‥ガハ‥
最後の水戸藩主。徳川斉昭の18男。三卿の清水家を相続し、1867年(慶応3)パリの万国博覧会に将軍慶喜の名代として参加。帰国後、生家を相続。(1853〜1910)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえさだ【徳川家定】‥ガハイヘ‥
徳川第13代将軍(在職1853〜1858)。家慶いえよしの4男。病弱で政務は阿部正弘らに任せる。継嗣なく、没後にいわゆる将軍継嗣問題が起きた。諡号、温恭院。(1824〜1858)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえしげ【徳川家重】‥ガハイヘ‥
徳川第9代将軍(在職1745〜1760)。吉宗の長子。言語不明瞭で、側用人大岡忠光だけがそれを理解できたという。諡号しごう、惇信院。(1711〜1761)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】‥ガハイヘ‥
徳川第7代将軍(在職1713〜1716)。家宣の3男。諡号しごう、有章院。(1709〜1716)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえつな【徳川家綱】‥ガハイヘ‥
徳川第4代将軍(在職1651〜1680)。家光の長子。保科正之・酒井忠勝・松平信綱らに補佐され、幕府の諸制度を整備。諡号しごう、厳有院。(1641〜1680)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえなり【徳川家斉】‥ガハイヘ‥
徳川第11代将軍(在職1787〜1837)。三卿の一橋治済はるさだの子。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行なったが、定信失脚後は文化・文政時代を現出。諡号しごう、文恭院。(1773〜1841)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】‥ガハイヘ‥
徳川第6代将軍(在職1709〜1712)。甲府藩主徳川綱重の長子。初名、綱豊。綱吉の養子。新井白石・間部詮房まなべあきふさを登用して政治の刷新を志すが、在職3年で没する。諡号しごう、文昭院。(1662〜1712)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえはる【徳川家治】‥ガハイヘ‥
徳川第10代将軍(在職1760〜1786)。家重の長子。田沼意次おきつぐを老中に登用し、田沼時代を現出。諡号しごう、浚明院。(1737〜1786)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえみつ【徳川家光】‥ガハイヘ‥
徳川第3代将軍(在職1623〜1651)。秀忠の次男。幼名竹千代。乳母、春日局。幕府の統治機構や参勤交代の制などを定め、キリシタン禁制を強化し、鎖国令をしき、諸侯を威圧して徳川氏隆盛の基礎を確立。諡号しごう、大猷院。(1604〜1651)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえもち【徳川家茂】‥ガハイヘ‥
徳川第14代将軍(在職1858〜1866)。紀州藩主斉順なりよりの長子。初名、慶福よしとみ。紀州藩主。のち将軍の位を継ぎ、公武合体のため和宮かずのみやと結婚。大坂城で第2次長州征討の軍を統督中に病没。諡号、昭徳院。(1846〜1866)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえやす【徳川家康】‥ガハイヘ‥
徳川初代将軍(在職1603〜1605)。松平広忠の長子。幼名、竹千代。初名、元康。今川義元に属したのち織田信長と結び、ついで豊臣秀吉と和し、1590年(天正18)関八州に封じられて江戸城に入り、秀吉の没後伏見城にあって執政。1600年(慶長5)関ヶ原の戦で石田三成らを破り、03年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれた。07年駿府に隠居後も大事は自ら決し、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府260年余の基礎を確立。諡号しごう、東照大権現。法号、安国院。(1542〜1616)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえよし【徳川家慶】‥ガハイヘ‥
徳川第12代将軍(在職1837〜1853)。家斉の次男。老中水野忠邦に命じて、いわゆる天保の改革を断行。諡号しごう、慎徳院。(1793〜1853)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】‥ガハ‥カウ
江戸幕府の法制史料集。司法省編。前集62巻、後集40巻。1878〜95年(明治11〜28)刊。前集は諸史料から収集した法令を分類、編纂。後集は1767年(明和4)の「科条類典」を主として採録。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐じだい【徳川時代】‥ガハ‥
(→)江戸時代に同じ。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐じっき【徳川実紀】‥ガハ‥
家康から10代家治に至る間の和文の編年体実録。江戸幕府が大学頭林述斎を総裁として成島司直もとなおらに編纂させたもの。1809年(文化6)起稿、43年(天保14)完成。全516巻。なお、本書に次いで家斉から慶喜までの実録を編纂した「続徳川実紀」があるが、未完成。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ただなが【徳川忠長】‥ガハ‥
江戸初期の大名。秀忠の3男。幼名国松。駿府55万石に封ぜられ、1626年(寛永3)権大納言に任。兄家光にうとまれ、また乱行が過ぎ高崎藩に預けられ、自刃じじん。駿河大納言。(1606〜1633)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】‥ガハ‥
甲府徳川家の祖。家光の次男。6代将軍家宣の父。1661年(寛文1)甲府25万石に封。(1644〜1678)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】‥ガハ‥
徳川第5代将軍(在職1680〜1709)。家光の4男。母は桂昌院。幼名、徳松。上州館林藩主から宗家を継ぐ。越後の高田騒動を親裁し、堀田正俊を大老に任じ、譜代大名・旗本・代官の綱紀を粛正、天和の治と称される善政を実現した。治世の後半には側用人牧野成貞・柳沢吉保を重用、服忌ぶっき令や生類しょうるい憐みの令を出し、社会の文明化を推進したが、人民を苦しめ、犬公方いぬくぼうとあだ名された。諡号しごう、常憲院。(1646〜1709)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】‥ガハ‥
幕末の水戸藩主。治紀はるとしの子。字は子信、号は景山・潜竜閣。藩校弘道館を開設して文武を奨励、鋭意藩政を改革、幕政を補佐したが、将軍継嗣問題で一橋派に属し、井伊大老に忌まれて永蟄居。諡号しごう、烈公。(1800〜1860)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】‥ガハ‥
(→)江戸幕府に同じ。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】‥ガハ‥
徳川第2代将軍(在職1605〜1623)。家康の3男。家康が定めた諸法度に基づき、一門・譜代を含む39大名を改易するなど、大名・朝廷・寺社の統制を強化、幕府創業に尽力。諡号しごう、台徳院。(1579〜1632)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐みつくに【徳川光圀】‥ガハ‥
江戸前期の水戸藩主。頼房の3男。字は子竜、号は梅里。彰考館を置いて「大日本史」の編纂に着手し、湊川に楠木正成の墓碑を建立。明の遺臣朱舜水を招く。権中納言となり水戸黄門と呼ばれた。晩年、西山荘に隠棲し、西山隠士と称す。義公。(1628〜1700)
→資料:『大日本史賛藪』
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むせい【徳川夢声】‥ガハ‥
映画説明者・漫談家。本名、福原駿雄としお。島根県生れ。朗読・対談・司会・著述などにも活躍。(1894〜1971)
徳川夢声(1)
撮影:田村 茂
⇒とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】
⇒とくがわ‐いえさだ【徳川家定】
⇒とくがわ‐いえしげ【徳川家重】
⇒とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】
⇒とくがわ‐いえつな【徳川家綱】
⇒とくがわ‐いえなり【徳川家斉】
⇒とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】
⇒とくがわ‐いえはる【徳川家治】
⇒とくがわ‐いえみつ【徳川家光】
⇒とくがわ‐いえもち【徳川家茂】
⇒とくがわ‐いえやす【徳川家康】
⇒とくがわ‐いえよし【徳川家慶】
⇒とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】
⇒とくがわ‐じだい【徳川時代】
⇒とくがわ‐じっき【徳川実紀】
⇒とくがわ‐ただなが【徳川忠長】
⇒とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】
⇒とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】
⇒とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】
⇒とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】
⇒とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】
⇒とくがわ‐みつくに【徳川光圀】
⇒とくがわ‐むせい【徳川夢声】
⇒とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】
⇒とくがわ‐むねはる【徳川宗春】
⇒とくがわ‐よしなお【徳川義直】
⇒とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】
⇒とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】
⇒とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】
⇒とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】
とくがわ‐あきたけ【徳川昭武】‥ガハ‥
最後の水戸藩主。徳川斉昭の18男。三卿の清水家を相続し、1867年(慶応3)パリの万国博覧会に将軍慶喜の名代として参加。帰国後、生家を相続。(1853〜1910)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえさだ【徳川家定】‥ガハイヘ‥
徳川第13代将軍(在職1853〜1858)。家慶いえよしの4男。病弱で政務は阿部正弘らに任せる。継嗣なく、没後にいわゆる将軍継嗣問題が起きた。諡号、温恭院。(1824〜1858)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえしげ【徳川家重】‥ガハイヘ‥
徳川第9代将軍(在職1745〜1760)。吉宗の長子。言語不明瞭で、側用人大岡忠光だけがそれを理解できたという。諡号しごう、惇信院。(1711〜1761)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえつぐ【徳川家継】‥ガハイヘ‥
徳川第7代将軍(在職1713〜1716)。家宣の3男。諡号しごう、有章院。(1709〜1716)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえつな【徳川家綱】‥ガハイヘ‥
徳川第4代将軍(在職1651〜1680)。家光の長子。保科正之・酒井忠勝・松平信綱らに補佐され、幕府の諸制度を整備。諡号しごう、厳有院。(1641〜1680)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえなり【徳川家斉】‥ガハイヘ‥
徳川第11代将軍(在職1787〜1837)。三卿の一橋治済はるさだの子。松平定信を老中に任じて寛政の改革を行なったが、定信失脚後は文化・文政時代を現出。諡号しごう、文恭院。(1773〜1841)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえのぶ【徳川家宣】‥ガハイヘ‥
徳川第6代将軍(在職1709〜1712)。甲府藩主徳川綱重の長子。初名、綱豊。綱吉の養子。新井白石・間部詮房まなべあきふさを登用して政治の刷新を志すが、在職3年で没する。諡号しごう、文昭院。(1662〜1712)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえはる【徳川家治】‥ガハイヘ‥
徳川第10代将軍(在職1760〜1786)。家重の長子。田沼意次おきつぐを老中に登用し、田沼時代を現出。諡号しごう、浚明院。(1737〜1786)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえみつ【徳川家光】‥ガハイヘ‥
徳川第3代将軍(在職1623〜1651)。秀忠の次男。幼名竹千代。乳母、春日局。幕府の統治機構や参勤交代の制などを定め、キリシタン禁制を強化し、鎖国令をしき、諸侯を威圧して徳川氏隆盛の基礎を確立。諡号しごう、大猷院。(1604〜1651)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえもち【徳川家茂】‥ガハイヘ‥
徳川第14代将軍(在職1858〜1866)。紀州藩主斉順なりよりの長子。初名、慶福よしとみ。紀州藩主。のち将軍の位を継ぎ、公武合体のため和宮かずのみやと結婚。大坂城で第2次長州征討の軍を統督中に病没。諡号、昭徳院。(1846〜1866)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえやす【徳川家康】‥ガハイヘ‥
徳川初代将軍(在職1603〜1605)。松平広忠の長子。幼名、竹千代。初名、元康。今川義元に属したのち織田信長と結び、ついで豊臣秀吉と和し、1590年(天正18)関八州に封じられて江戸城に入り、秀吉の没後伏見城にあって執政。1600年(慶長5)関ヶ原の戦で石田三成らを破り、03年征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開いた。将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれた。07年駿府に隠居後も大事は自ら決し、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、幕府260年余の基礎を確立。諡号しごう、東照大権現。法号、安国院。(1542〜1616)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐いえよし【徳川家慶】‥ガハイヘ‥
徳川第12代将軍(在職1837〜1853)。家斉の次男。老中水野忠邦に命じて、いわゆる天保の改革を断行。諡号しごう、慎徳院。(1793〜1853)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐きんれいこう【徳川禁令考】‥ガハ‥カウ
江戸幕府の法制史料集。司法省編。前集62巻、後集40巻。1878〜95年(明治11〜28)刊。前集は諸史料から収集した法令を分類、編纂。後集は1767年(明和4)の「科条類典」を主として採録。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐じだい【徳川時代】‥ガハ‥
(→)江戸時代に同じ。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐じっき【徳川実紀】‥ガハ‥
家康から10代家治に至る間の和文の編年体実録。江戸幕府が大学頭林述斎を総裁として成島司直もとなおらに編纂させたもの。1809年(文化6)起稿、43年(天保14)完成。全516巻。なお、本書に次いで家斉から慶喜までの実録を編纂した「続徳川実紀」があるが、未完成。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ただなが【徳川忠長】‥ガハ‥
江戸初期の大名。秀忠の3男。幼名国松。駿府55万石に封ぜられ、1626年(寛永3)権大納言に任。兄家光にうとまれ、また乱行が過ぎ高崎藩に預けられ、自刃じじん。駿河大納言。(1606〜1633)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐つなしげ【徳川綱重】‥ガハ‥
甲府徳川家の祖。家光の次男。6代将軍家宣の父。1661年(寛文1)甲府25万石に封。(1644〜1678)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐つなよし【徳川綱吉】‥ガハ‥
徳川第5代将軍(在職1680〜1709)。家光の4男。母は桂昌院。幼名、徳松。上州館林藩主から宗家を継ぐ。越後の高田騒動を親裁し、堀田正俊を大老に任じ、譜代大名・旗本・代官の綱紀を粛正、天和の治と称される善政を実現した。治世の後半には側用人牧野成貞・柳沢吉保を重用、服忌ぶっき令や生類しょうるい憐みの令を出し、社会の文明化を推進したが、人民を苦しめ、犬公方いぬくぼうとあだ名された。諡号しごう、常憲院。(1646〜1709)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐なりあき【徳川斉昭】‥ガハ‥
幕末の水戸藩主。治紀はるとしの子。字は子信、号は景山・潜竜閣。藩校弘道館を開設して文武を奨励、鋭意藩政を改革、幕政を補佐したが、将軍継嗣問題で一橋派に属し、井伊大老に忌まれて永蟄居。諡号しごう、烈公。(1800〜1860)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ばくふ【徳川幕府】‥ガハ‥
(→)江戸幕府に同じ。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐ひでただ【徳川秀忠】‥ガハ‥
徳川第2代将軍(在職1605〜1623)。家康の3男。家康が定めた諸法度に基づき、一門・譜代を含む39大名を改易するなど、大名・朝廷・寺社の統制を強化、幕府創業に尽力。諡号しごう、台徳院。(1579〜1632)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐みつくに【徳川光圀】‥ガハ‥
江戸前期の水戸藩主。頼房の3男。字は子竜、号は梅里。彰考館を置いて「大日本史」の編纂に着手し、湊川に楠木正成の墓碑を建立。明の遺臣朱舜水を招く。権中納言となり水戸黄門と呼ばれた。晩年、西山荘に隠棲し、西山隠士と称す。義公。(1628〜1700)
→資料:『大日本史賛藪』
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むせい【徳川夢声】‥ガハ‥
映画説明者・漫談家。本名、福原駿雄としお。島根県生れ。朗読・対談・司会・著述などにも活躍。(1894〜1971)
徳川夢声(1)
撮影:田村 茂
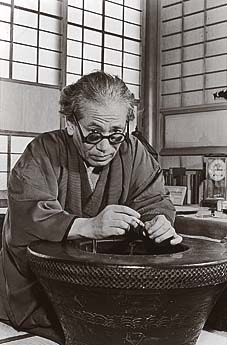 徳川夢声(2)
撮影:石井幸之助
徳川夢声(2)
撮影:石井幸之助
 ⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】‥ガハ‥
⇒たやすむねたけ(田安宗武)。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むねはる【徳川宗春】‥ガハ‥
尾張藩第7代藩主。「温知政要」を著して8代将軍吉宗の緊縮をむねとした政治を批判し、商業の重視、放任政策を説いたため、幕府から隠居させられ、著書は絶版。(1696〜1764)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしなお【徳川義直】‥ガハ‥ナホ
尾張徳川家の祖。家康の9男。名古屋城を築き、藩政の確立に尽力。儒学・軍学・神道を好む。諡号しごう、敬公。(1600〜1650)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】‥ガハ‥
徳川第15代将軍(在職1866〜1867)。徳川斉昭の7男。初め一橋家を嗣ぎ、後見職として将軍家茂を補佐、1866年(慶応2)将軍職を継いだが幕末の内憂外患に直面して、翌年遂に大政を奉還。68年鳥羽伏見の戦で敗れ、江戸城を明け渡して水戸に退き、駿府に隠棲。のち公爵。(1837〜1913)
徳川慶喜
提供:毎日新聞社
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むねたけ【徳川宗武】‥ガハ‥
⇒たやすむねたけ(田安宗武)。
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐むねはる【徳川宗春】‥ガハ‥
尾張藩第7代藩主。「温知政要」を著して8代将軍吉宗の緊縮をむねとした政治を批判し、商業の重視、放任政策を説いたため、幕府から隠居させられ、著書は絶版。(1696〜1764)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしなお【徳川義直】‥ガハ‥ナホ
尾張徳川家の祖。家康の9男。名古屋城を築き、藩政の確立に尽力。儒学・軍学・神道を好む。諡号しごう、敬公。(1600〜1650)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしのぶ【徳川慶喜】‥ガハ‥
徳川第15代将軍(在職1866〜1867)。徳川斉昭の7男。初め一橋家を嗣ぎ、後見職として将軍家茂を補佐、1866年(慶応2)将軍職を継いだが幕末の内憂外患に直面して、翌年遂に大政を奉還。68年鳥羽伏見の戦で敗れ、江戸城を明け渡して水戸に退き、駿府に隠棲。のち公爵。(1837〜1913)
徳川慶喜
提供:毎日新聞社
 →資料:大政奉還上表文
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】‥ガハ‥
徳川第8代将軍(在職1716〜1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行なった。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684〜1751)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】‥ガハ‥
紀伊徳川家の祖。家康の10男。性剛毅で、大坂夏の陣に功を立てる。また、詩歌をよくした。諡号しごう、南竜公。(1602〜1671)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】‥ガハ‥
水戸徳川家の祖。家康の11男。領内検地を行い、藩政の基礎を築く。儒学・神道を修めた。諡号、威公。(1603〜1661)
⇒とくがわ【徳川】
どく‐がん【独眼】
かため。隻眼。
⇒どくがん‐りゅう【独眼竜】
どくがん‐りゅう【独眼竜】
[旧五代史唐書、武皇紀上]
①片目の英雄。
②伊達だて政宗の異名。
⇒どく‐がん【独眼】
と‐くき【鳥茎】
①鳥の羽の茎。
②「鳥茎の矢」の略。
⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】
とく‐ぎ【特技】
特にすぐれた技量。特別の技能。「―を披露する」「―を生かす」
とく‐ぎ【徳義】
道徳上の義理。道徳上の義務。「―心」
どく‐きのこ【毒茸】
有毒のきのこ。テングタケ・ツキヨタケ・ワライタケなど。その毒成分には神経系を侵すもの、消化器官を侵すものなどがある。どくたけ。有毒菌。
とくき‐の‐や【鳥茎の矢】
鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」
⇒と‐くき【鳥茎】
とく‐ぎゅう【犢牛】‥ギウ
こうし。
どく‐ぎょ【毒魚】
毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」
とく‐ぎょう【得業】‥ゲフ
定められた課程を学びおえること。→とくごう。
⇒とくぎょう‐せい【得業生】
とく‐ぎょう【徳業】‥ゲフ
徳行と事業。また、道徳的行為。
とくぎょう‐せい【得業生】‥ゲフ‥
①⇒とくごうしょう。
②卒業生。
⇒とく‐ぎょう【得業】
どく‐ぎん【独吟】
①一人で詩歌を吟ずること。
②一人で謡曲または歌謡をうたうこと。↔連吟。
③連歌・俳諧などの1巻を一人で作ること。また、その作品。片吟。→両吟→三吟
とく‐ぐう【特遇】
特別の待遇。殊遇。
どく‐ぐち【毒口】
毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。
どく‐ぐも【毒蜘蛛】
人間を死に至らしめるほど毒性の強いクモ。クロゴケグモ・シドニージョウゴグモ・ドクイトグモなど。3万5000種のクモのうちわずか40種ほどで、日本にも数種が生息。
とく‐ぐん【督軍】
中国で辛亥革命後、従来の総督・巡撫に代わって、省長と共に各省に置かれた地方軍政長官。多く省長を兼ねて文武の権を握り、ほとんど独立の軍閥を形成。後に督弁と改称、1928年廃止。
どく‐け【毒気】
⇒どっき
⇒どっけ
どく‐けし【毒消し】
①中毒を消すこと。解毒げどく。
②解毒剤。どっけし。
⇒どくけし‐うり【毒消し売り】
どくけし‐うり【毒消し売り】
夏、食中毒・暑気中あたりなどの薬を越後地方から売りに来た行商人。未婚女性が多く、紺絣こんがすりの筒袖に紺の手甲てっこう、地下足袋ばき、黒木綿の風呂敷の荷を背負った。どっけしうり。〈[季]夏〉。島崎藤村、千曲川のスケッチ「此節このせつ私は学校へ行く途中で、毎日のやうにその―の群に逢ふ」
⇒どく‐けし【毒消し】
とくげん【徳元】
⇒さいとうとくげん(斎藤徳元)
どく‐げん【毒言】
他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。
どく‐げん【独言】
ひとりごと。独語。
とく‐こ【独鈷】
⇒とっこ
どく‐ご【独語】
①ひとりごと。「ぶつぶつ―する」
②独逸ドイツ語の略。「―文典」
どくご【独語】
随筆。太宰春台著。1巻。和歌・茶道・俳諧・三絃・浄瑠璃・猿楽・俳優その他歌舞風俗等について、その流行・変遷などを記す。
どく‐ご【読後】
書物などを読んだあと。「―感」
とく‐ごう【得業】‥ゴフ
僧侶の学階。南都では興福寺の維摩会ゆいまえ・法華会、薬師寺の最勝会の竪義りゅうぎを勤めた者。山門では横川よかわの四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた者。また、浄土宗・浄土真宗の学階の一つ。
⇒とくごう‐しょう【得業生】
とくごう‐しょう【得業生】‥ゴフシヤウ
古代、大学の各専門課程の学生がくしょうから選ばれた少数の成績優秀者に与えられた身分。修学ののち試験に及第すると大学教官などに任じられた。730年(天平2)創設。文章得業生(定員2人)など。とくぎょうせい。
⇒とく‐ごう【得業】
とくごう‐とうげ【徳本峠】‥タウゲ
長野県西部、飛騨山脈東麓にある峠。安曇野から上高地に入る登山路に沿う。標高2135メートル。
→資料:大政奉還上表文
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よしむね【徳川吉宗】‥ガハ‥
徳川第8代将軍(在職1716〜1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行なった。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684〜1751)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よりのぶ【徳川頼宣】‥ガハ‥
紀伊徳川家の祖。家康の10男。性剛毅で、大坂夏の陣に功を立てる。また、詩歌をよくした。諡号しごう、南竜公。(1602〜1671)
⇒とくがわ【徳川】
とくがわ‐よりふさ【徳川頼房】‥ガハ‥
水戸徳川家の祖。家康の11男。領内検地を行い、藩政の基礎を築く。儒学・神道を修めた。諡号、威公。(1603〜1661)
⇒とくがわ【徳川】
どく‐がん【独眼】
かため。隻眼。
⇒どくがん‐りゅう【独眼竜】
どくがん‐りゅう【独眼竜】
[旧五代史唐書、武皇紀上]
①片目の英雄。
②伊達だて政宗の異名。
⇒どく‐がん【独眼】
と‐くき【鳥茎】
①鳥の羽の茎。
②「鳥茎の矢」の略。
⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】
とく‐ぎ【特技】
特にすぐれた技量。特別の技能。「―を披露する」「―を生かす」
とく‐ぎ【徳義】
道徳上の義理。道徳上の義務。「―心」
どく‐きのこ【毒茸】
有毒のきのこ。テングタケ・ツキヨタケ・ワライタケなど。その毒成分には神経系を侵すもの、消化器官を侵すものなどがある。どくたけ。有毒菌。
とくき‐の‐や【鳥茎の矢】
鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」
⇒と‐くき【鳥茎】
とく‐ぎゅう【犢牛】‥ギウ
こうし。
どく‐ぎょ【毒魚】
毒をもつ魚の総称。フグのように内臓や筋肉などに毒をもつものと、アカエイ・アイゴ・オニオコゼなどのように毒棘をもつものとがある。日本霊異記下「―も呑まず」
とく‐ぎょう【得業】‥ゲフ
定められた課程を学びおえること。→とくごう。
⇒とくぎょう‐せい【得業生】
とく‐ぎょう【徳業】‥ゲフ
徳行と事業。また、道徳的行為。
とくぎょう‐せい【得業生】‥ゲフ‥
①⇒とくごうしょう。
②卒業生。
⇒とく‐ぎょう【得業】
どく‐ぎん【独吟】
①一人で詩歌を吟ずること。
②一人で謡曲または歌謡をうたうこと。↔連吟。
③連歌・俳諧などの1巻を一人で作ること。また、その作品。片吟。→両吟→三吟
とく‐ぐう【特遇】
特別の待遇。殊遇。
どく‐ぐち【毒口】
毒々しく言う言葉つき。あくたれぐち。毒舌。
どく‐ぐも【毒蜘蛛】
人間を死に至らしめるほど毒性の強いクモ。クロゴケグモ・シドニージョウゴグモ・ドクイトグモなど。3万5000種のクモのうちわずか40種ほどで、日本にも数種が生息。
とく‐ぐん【督軍】
中国で辛亥革命後、従来の総督・巡撫に代わって、省長と共に各省に置かれた地方軍政長官。多く省長を兼ねて文武の権を握り、ほとんど独立の軍閥を形成。後に督弁と改称、1928年廃止。
どく‐け【毒気】
⇒どっき
⇒どっけ
どく‐けし【毒消し】
①中毒を消すこと。解毒げどく。
②解毒剤。どっけし。
⇒どくけし‐うり【毒消し売り】
どくけし‐うり【毒消し売り】
夏、食中毒・暑気中あたりなどの薬を越後地方から売りに来た行商人。未婚女性が多く、紺絣こんがすりの筒袖に紺の手甲てっこう、地下足袋ばき、黒木綿の風呂敷の荷を背負った。どっけしうり。〈[季]夏〉。島崎藤村、千曲川のスケッチ「此節このせつ私は学校へ行く途中で、毎日のやうにその―の群に逢ふ」
⇒どく‐けし【毒消し】
とくげん【徳元】
⇒さいとうとくげん(斎藤徳元)
どく‐げん【毒言】
他人の名誉をそこなうことば。また、極めてあしざまに言うことば。毒舌。どくぐち。
どく‐げん【独言】
ひとりごと。独語。
とく‐こ【独鈷】
⇒とっこ
どく‐ご【独語】
①ひとりごと。「ぶつぶつ―する」
②独逸ドイツ語の略。「―文典」
どくご【独語】
随筆。太宰春台著。1巻。和歌・茶道・俳諧・三絃・浄瑠璃・猿楽・俳優その他歌舞風俗等について、その流行・変遷などを記す。
どく‐ご【読後】
書物などを読んだあと。「―感」
とく‐ごう【得業】‥ゴフ
僧侶の学階。南都では興福寺の維摩会ゆいまえ・法華会、薬師寺の最勝会の竪義りゅうぎを勤めた者。山門では横川よかわの四季講、定心房の三講の聴衆を勤めた者。また、浄土宗・浄土真宗の学階の一つ。
⇒とくごう‐しょう【得業生】
とくごう‐しょう【得業生】‥ゴフシヤウ
古代、大学の各専門課程の学生がくしょうから選ばれた少数の成績優秀者に与えられた身分。修学ののち試験に及第すると大学教官などに任じられた。730年(天平2)創設。文章得業生(定員2人)など。とくぎょうせい。
⇒とく‐ごう【得業】
とくごう‐とうげ【徳本峠】‥タウゲ
長野県西部、飛騨山脈東麓にある峠。安曇野から上高地に入る登山路に沿う。標高2135メートル。
とき‐ん‐ば【時んば】🔗⭐🔉
とき‐ん‐ば【時んば】
(「時には」の音便。漢文訓読で用いたのにはじまる)…する時には。…する場合は。…すれば。法華経遊意承保点「若し所受の法有る―即ち断相を堕す」。浄瑠璃、大職冠「君辱めらるる―、臣死す」
[漢]時🔗⭐🔉
時 字形
 筆順
筆順
 〔日(曰)部6画/10画/教育/2794・3B7E〕
〔音〕ジ(呉) シ(漢)
〔訓〕とき
[意味]
①とき。
㋐月日のうつりゆきのくぎり。ときのきざみ。「時代・時刻・四時しじ・しいじ・同時・片時へんじ・へんし」。特に、六十分きざみのとき。「時速・時針・十二時」
㋑そのとき。「時下・時事・時価」
㋒おり。しおどき。「時機・随時・不時着」
②ときどき。ときに。「時習」
[解字]
形声。「日」+音符「寺」(=手足を働かせて仕事をする。進行する)。日のうつりゆきの意。[
〔日(曰)部6画/10画/教育/2794・3B7E〕
〔音〕ジ(呉) シ(漢)
〔訓〕とき
[意味]
①とき。
㋐月日のうつりゆきのくぎり。ときのきざみ。「時代・時刻・四時しじ・しいじ・同時・片時へんじ・へんし」。特に、六十分きざみのとき。「時速・時針・十二時」
㋑そのとき。「時下・時事・時価」
㋒おり。しおどき。「時機・随時・不時着」
②ときどき。ときに。「時習」
[解字]
形声。「日」+音符「寺」(=手足を働かせて仕事をする。進行する)。日のうつりゆきの意。[ ][
][ ]は異体字。
[下ツキ
一時・往時・旧時・近時・現時・歳時記・暫時・四時・瞬時・少時・常時・四六時中・随時・寸時・盛時・昔時・戦時・即時・定時・適時・当時・同時・日時・二六時中・曩時・農時・非時・不時・平時・片時・毎時・幼時・臨時・六時
[難読]
時雨しぐれ・時化しけ・時計とけい・時鳥ほととぎす
]は異体字。
[下ツキ
一時・往時・旧時・近時・現時・歳時記・暫時・四時・瞬時・少時・常時・四六時中・随時・寸時・盛時・昔時・戦時・即時・定時・適時・当時・同時・日時・二六時中・曩時・農時・非時・不時・平時・片時・毎時・幼時・臨時・六時
[難読]
時雨しぐれ・時化しけ・時計とけい・時鳥ほととぎす
 筆順
筆順
 〔日(曰)部6画/10画/教育/2794・3B7E〕
〔音〕ジ(呉) シ(漢)
〔訓〕とき
[意味]
①とき。
㋐月日のうつりゆきのくぎり。ときのきざみ。「時代・時刻・四時しじ・しいじ・同時・片時へんじ・へんし」。特に、六十分きざみのとき。「時速・時針・十二時」
㋑そのとき。「時下・時事・時価」
㋒おり。しおどき。「時機・随時・不時着」
②ときどき。ときに。「時習」
[解字]
形声。「日」+音符「寺」(=手足を働かせて仕事をする。進行する)。日のうつりゆきの意。[
〔日(曰)部6画/10画/教育/2794・3B7E〕
〔音〕ジ(呉) シ(漢)
〔訓〕とき
[意味]
①とき。
㋐月日のうつりゆきのくぎり。ときのきざみ。「時代・時刻・四時しじ・しいじ・同時・片時へんじ・へんし」。特に、六十分きざみのとき。「時速・時針・十二時」
㋑そのとき。「時下・時事・時価」
㋒おり。しおどき。「時機・随時・不時着」
②ときどき。ときに。「時習」
[解字]
形声。「日」+音符「寺」(=手足を働かせて仕事をする。進行する)。日のうつりゆきの意。[ ][
][ ]は異体字。
[下ツキ
一時・往時・旧時・近時・現時・歳時記・暫時・四時・瞬時・少時・常時・四六時中・随時・寸時・盛時・昔時・戦時・即時・定時・適時・当時・同時・日時・二六時中・曩時・農時・非時・不時・平時・片時・毎時・幼時・臨時・六時
[難読]
時雨しぐれ・時化しけ・時計とけい・時鳥ほととぎす
]は異体字。
[下ツキ
一時・往時・旧時・近時・現時・歳時記・暫時・四時・瞬時・少時・常時・四六時中・随時・寸時・盛時・昔時・戦時・即時・定時・適時・当時・同時・日時・二六時中・曩時・農時・非時・不時・平時・片時・毎時・幼時・臨時・六時
[難読]
時雨しぐれ・時化しけ・時計とけい・時鳥ほととぎす
広辞苑に「時」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む