複数辞典一括検索+![]()
![]()
○木陰に臥す者は枝を手折らずこかげにふすものはえだをたおらず🔗⭐🔉
○木陰に臥す者は枝を手折らずこかげにふすものはえだをたおらず
[韓詩外伝2「其の樹を蔭とする者は其の枝を折らず」]恩をかけてくれた者に対しては、害を与えないのが人情であることのたとえ。
⇒こ‐かげ【木陰・木蔭】
コカ‐コーラ【Coca-Cola】
コーラ飲料の一つ。コーク。商標名。
こ‐かさがけ【小笠懸】
笠懸の一種。串くしに挟んだ方4寸の板を的とし、距離は遠笠懸とおかさがけよりも近く、小形の笠懸蟇目かさがけひきめの矢で射るもの。→笠懸
こかし
(動詞コカスの連用形から)
①人のために心を尽くしているように見せかけること。おためごかし。好色一代女1「いかなる粋も、いやとはいはぬ―なり」→ごかし。
②「山こかし」の略。
こかじ【小鍛冶】‥カヂ
①京都三条の刀工、宗近むねちかの異称。三条小鍛冶。
②能。小鍛冶宗近が稲荷明神の通力に助けられて宝剣小狐丸を作る。
③能を歌舞伎舞踊化したもの数種の通称。長唄に多く、また義太夫節景事けいごと物の一つ。
こがし【焦がし】
大麦・米などを炒いって粉としたもの。焦粉。香煎こうせん。日本永代蔵2「のどが乾けば、白湯さゆに―」。「麦―」
⇒こがし‐の【焦がし箆】
ごかし
〔接尾〕
(コカシの転)体言・動詞の連用形に付いて、そのようなふりをして相手をだまし、自分の利益をはかる意を表す。浄瑠璃、浦島年代記「勅諚―に非道を働くえせ者奴等」。「親切―」「おため―」「寝―」
ご‐かじ【五鍛冶】‥カヂ
近世、宮中御用を務めた京都在住の五派の刀工。丹波守吉道・近江守源久道・近江守粟田口忠綱・伊賀守来金道・信濃守源信吉の派。京五鍛冶。
こがし‐の【焦がし箆】
節ふしの所を少し焦がした矢柄。
⇒こがし【焦がし】
コカ‐しゅ【コカ酒】
赤葡萄酒にコカの葉を浸して作った薬用酒。
ごかじょう‐の‐せいもん【五カ条の誓文】‥デウ‥
慶応4年(1868)3月14日、明治天皇が宣布した明治新政の五カ条の基本政策。「一、広く会議を興し、万機公論に決すべし。一、上下しょうか心を一にして、盛に経綸けいりんを行ふべし。一、官武一途庶民に至る迄、各其志を遂げ、人心をして倦うまざらしめん事を要す。一、旧来の陋習ろうしゅうを破り、天地の公道に基くべし。一、智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし」。五箇条御誓文。→由利公正→福岡孝弟
→文献資料[五箇条の誓文]
ごかしょ‐しょうにん【五箇所商人】‥シヤウ‥
江戸時代、長崎に輸入される白糸(中国産生糸)の専売を許されていた、京都・堺・長崎・江戸・大坂の5カ所の糸割符いとわっぷ仲間の商人。→糸割符
ごかしょ‐わん【五ヶ所湾】
三重県東部、志摩半島南岸の湾。紀伊山地の東端が沈水してでき、山地が直接海に臨む。湾内では真珠・ハマチなどの養殖が盛ん。
こ‐がしら【小頭】
一群中でその一部の長。↔大頭おおがしら
ごかしわばら‐てんのう【後柏原天皇】‥カシハ‥ワウ
戦国時代の天皇。後土御門天皇の第1皇子。名は勝仁かつひと。1500年(明応9)践祚したが、財政逼迫のため21年(永正18)に即位。(在位1500〜1526)(1464〜1526)→天皇(表)
こか・す【転かす・倒かす】
〔他五〕
①たおす。ころばす。浄瑠璃、堀川波鼓「行灯を踏み―・し」
②他の場所にうつす。かくす。浄瑠璃、神霊矢口渡「玉はどつちへ―・しおつた」
③だます。ごまかして自分のものにする。くすねる。浄瑠璃、心中万年草「二十八貫目拾うた。恵比寿・大黒が乗り移つた作右衛門を、―・さうや。おいてくれ」
④動詞の連用形に付いて、その意を強調する。さんざんに…する。すっかり…する。「叱り―・す」「売り―・す」
こが・す【焦がす】
〔他五〕
①火で焼いて黒くする。「パンを―・す」
②薫物たきものの煙でくすべる。源氏物語夕顔「白き扇のいたう―・したるを」
③心を苦しめる。思い悩ます。後撰和歌集恋「いとかく胸は―・さざらまし」。「身を―・す」
こ‐かぜ【小風】
微風。そよ吹く風。赤染衛門集「森の―も吹きまさるなり」
こが‐せいり【古賀精里】
江戸後期の儒学者。寛政の三博士の一人。名は樸すなお。通称、弥助。佐賀藩士の子。はじめ陽明学、のち朱子学を奉じ、藩校弘道館の創設に尽力。幕府に登用され、昌平黌しょうへいこうの教官。著「四書集釈」「大学章句纂釈」など。(1750〜1817)
⇒こが【古賀】
こ‐かた【子方】
①封建的な主従関係で、親方おやかたの指揮・監督をうける者。子分。↔親方。
②能などで子供のする役。また、その役をつとめる役者。子役。
③子にあたる者。子ども分。武道伝来記「―のもの詮議してうたせとの仰せ出されなり」
こ‐がた【小形・小型】
形の小さいこと。小さい型。
⇒こがた‐あかいえか【小型赤家蚊】
⇒こがた‐じどうしゃ【小型自動車】
こがた‐あかいえか【小型赤家蚊】‥イヘ‥
カ科の昆虫。体長約4.5ミリメートルで、体は暗赤褐色。人家近くの溝や水田から発生する。日本脳炎を媒介する。
⇒こ‐がた【小形・小型】
ご‐がたき【碁敵】
常日頃、囲碁を楽しむ相手。
こがた‐じどうしゃ【小型自動車】
道路運送車両法における自動車の種別の一つ。ふつう総排気量が2.00リットル以下で、長さ・幅・高さがそれぞれ4.70メートル、1.70メートル、2.00メートル以下のもの。
⇒こ‐がた【小形・小型】
こか‐だて【古歌立て】
必要もないのに、古歌を引用すること。古歌の知識をひけらかすこと。狂言、舟ふな「おのれがぶんで―を言ひをる」
こ‐がたな【小刀】
①小さい刀。ナイフ。
②刀の鞘さやにさし添える小柄こづか。
⇒こがたな‐ざいく【小刀細工】
⇒こがたな‐びつ【小刀櫃】
こがたな‐ざいく【小刀細工】
①小刀でこまかな細工をすること。
②大局を見ず、いたずらに小策を弄すること。
⇒こ‐がたな【小刀】
こがたな‐びつ【小刀櫃】
刀の鞘さやの名所などころ。鞘の差し裏にあり、小柄の刀を挿し込む溝。小柄櫃。
⇒こ‐がたな【小刀】
こ‐かたびら【小帷子】
①小形の帷子。
②鎧よろいの下に着る、長さが膝までの半袖の帷子。
ごか‐ちほう【五河地方】‥ハウ
パンジャブのこと。
こ‐かつ【枯渇・涸渇】
①かわいて水分がなくなること。
②つき果てて、なくなること。「資金が―する」「才能の―」
ご‐がつ【五月】‥グワツ
一年の5番目の月。さつき。
⇒ごがつ‐あき【五月秋】
⇒ごがつ‐おんな【五月女】
⇒ごがつ‐かくめい【五月革命】
⇒ごがつ‐かぶと【五月冑】
⇒ごがつ‐かや【五月蚊帳】
⇒ごがつ‐ささげ【五月豇豆】
⇒ごがつ‐にんぎょう【五月人形】
⇒ごがつ‐のぼり【五月幟】
⇒ごがつ‐びょう【五月病】
ごがつ‐あき【五月秋】‥グワツ‥
陰暦5月の田植で忙しい季節。
⇒ご‐がつ【五月】
ごがつ‐おんな【五月女】‥グワツヲンナ
陰暦5月の田植の時に必要とする女手。諺に「五月女に秋男」といい、それぞれ田植と稲刈に欠くことのできない人手ひとでをいう。
⇒ご‐がつ【五月】
ごがつ‐かくめい【五月革命】‥グワツ‥
(Événements de Mai フランス)1968年5月、フランスでパリを中心として展開された、学生・労働者・市民による反政府行動。
⇒ご‐がつ【五月】
ごがつ‐かぶと【五月冑】‥グワツ‥
江戸時代、旧暦5月5日に甲冑を飾った儀式。
⇒ご‐がつ【五月】
ごがつ‐かや【五月蚊帳】‥グワツ‥
東北・関東地方で、5月に蚊帳をつり始めるのを忌んでいう語。
⇒ご‐がつ【五月】
ごがつ‐ささげ【五月豇豆】‥グワツ‥
(→)隠元豆いんげんまめに同じ。
⇒ご‐がつ【五月】
こ‐かつじぼん【古活字本】‥クワツ‥
文禄(1592〜1596)年間から慶安(1648〜1652)年間に刊行された活字本の総称。銅活字本はきわめて少なく、ほとんど木活字本。慶長勅版本・伏見版・駿河版(銅活字)・嵯峨本など。江戸後期から明治初年に刊行された木活字本に対していう。古活字版。→木活字版
ごがつ‐にんぎょう【五月人形】‥グワツ‥ギヤウ
5月の節句に男の子の祝いに飾る武者人形。〈[季]夏〉
⇒ご‐がつ【五月】
ごがつ‐のぼり【五月幟】‥グワツ‥
5月の節句に男の子の祝いに立てるのぼり。さつきのぼり。
⇒ご‐がつ【五月】
ごがつ‐びょう【五月病】‥グワツビヤウ
4月に新しく入った学生や社員などに、5月頃しばしば現れる神経症的な状態。
⇒ご‐がつ【五月】
こが‐とうあん【古賀侗庵】
江戸後期の儒学者。名は煜。精里の3子。昌平黌の教官。渡辺崋山・大槻玄沢ら蘭学者と交流し、海防問題にも通じる。著「海防臆測」など。(1788〜1847)
⇒こが【古賀】
こ‐がね【小金】
わずかな金銭。少しばかりのまとまった金。「―をためる」
⇒こがね‐かし【小金貸し】
こ‐がね【黄金・金】
(「こ」は「き(黄)」と同源。奈良時代は「くがね」)
①おうごん。きん。
②金の貨幣。金貨。宇津保物語初秋「千両の―をおくる」
③「こがねいろ」の略。宇津保物語蔵開下「―のあめ牛かけて」
Munsell color system: 2.5Y7.5/11
⇒こがね‐いろ【黄金色】
⇒こがね‐かん【黄金羹】
⇒こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】
⇒こがね‐ざね【黄金札】
⇒こがね‐しだ【黄金羊歯】
⇒こがね‐づくり【黄金作り】
⇒こがね‐の‐うてな【黄金の台】
⇒こがね‐の‐きし【黄金の岸】
⇒こがね‐の‐くるま【黄金の車】
⇒こがね‐の‐ことば【黄金の言葉】
⇒こがね‐の‐たち【黄金の太刀】
⇒こがね‐の‐つる【黄金の蔓】
⇒こがね‐の‐でい【黄金の泥】
⇒こがね‐の‐どう【黄金の堂】
⇒こがね‐の‐との【黄金の殿】
⇒こがね‐の‐なみ【黄金の波】
⇒こがね‐の‐はな【黄金の花】
⇒こがね‐の‐ひかり【黄金の光】
⇒こがね‐の‐みて【黄金の御手】
⇒こがね‐の‐もじ【黄金の文字】
⇒こがね‐の‐やま【黄金の山】
⇒こがね‐むし【黄金虫・金亀子】
⇒こがね‐めぬき【黄金目貫】
⇒黄金と侍は朽ちても朽ちぬ
⇒黄金の釜を掘りだしたよう
⇒黄金花咲く
こがねい【小金井】‥ヰ
東京都西郊、武蔵野台地にある市。昭和初期より近郊住宅地、第二次大戦後は学園都市として発達。人口11万4千。
こがねい【小金井】‥ヰ
姓氏の一つ。
⇒こがねい‐きみこ【小金井喜美子】
⇒こがねい‐こじろう【小金井小次郎】
⇒こがねい‐よしきよ【小金井良精】
こがねい‐きみこ【小金井喜美子】‥ヰ‥
翻訳家・小説家。本名、きみ。津和野生れ。森鴎外の妹。小金井良精よしきよの妻。「於母影おもかげ」「しからみ草紙」に翻訳を発表。(1871〜1956)
⇒こがねい【小金井】
こがねい‐こじろう【小金井小次郎】‥ヰ‥ラウ
幕末・明治の侠客。武蔵小金井の名主の次男。新門辰五郎の弟分。(1818〜1881)
⇒こがねい【小金井】
こがねい‐よしきよ【小金井良精】‥ヰ‥
人類学者。越後長岡生れ。東大教授。解剖学・組織学を研究し、アイヌの研究、朝鮮人・日本人の骨の研究で知られる。妻喜美子は森鴎外の妹。(1858〜1944)
小金井良精
提供:毎日新聞社
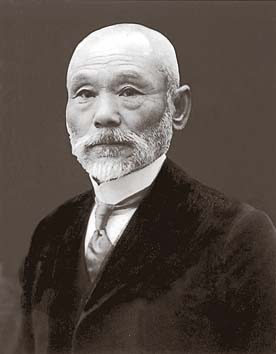 ⇒こがねい【小金井】
こがね‐いろ【黄金色】
黄金のように黄色に光る色。きんいろ。こんじき。「―の稲穂」
Munsell color system: 2.5Y7.5/11
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐かし【小金貸し】
わずかな金銭を貸す高利貸。
⇒こ‐がね【小金】
こがね‐かん【黄金羹】
鬱金粉うこんこをまぜて黄色にした羊羹。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】
コガネグモ科のクモ。雌は20〜25ミリメートル、雄は5ミリメートル。雌の腹部の背面は黒褐色の地に3条の黄帯を走らす。草間に隠れ帯のついた円網を張り、昆虫を捕食。8月頃産卵する。本州以南に分布。鹿児島県加治木町では、雌を訓練してクモ合戦をさせる。地方によりジョロウグモと呼ぶが、別種。サンバソウグモ。ヨロブリグモ。
こがねぐも
⇒こがねい【小金井】
こがね‐いろ【黄金色】
黄金のように黄色に光る色。きんいろ。こんじき。「―の稲穂」
Munsell color system: 2.5Y7.5/11
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐かし【小金貸し】
わずかな金銭を貸す高利貸。
⇒こ‐がね【小金】
こがね‐かん【黄金羹】
鬱金粉うこんこをまぜて黄色にした羊羹。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】
コガネグモ科のクモ。雌は20〜25ミリメートル、雄は5ミリメートル。雌の腹部の背面は黒褐色の地に3条の黄帯を走らす。草間に隠れ帯のついた円網を張り、昆虫を捕食。8月頃産卵する。本州以南に分布。鹿児島県加治木町では、雌を訓練してクモ合戦をさせる。地方によりジョロウグモと呼ぶが、別種。サンバソウグモ。ヨロブリグモ。
こがねぐも
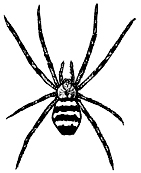 コガネグモ
提供:ネイチャー・プロダクション
コガネグモ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐ざね【黄金札】
金箔置きの鎧よろいの札。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐しだ【黄金羊歯】
リョウメンシダの別称。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐づくり【黄金作り】
黄金またはその鍍金めっきで装飾すること。また、その装飾した物。源氏物語宿木「檳榔毛の―六つ」
⇒こ‐がね【黄金・金】
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐ざね【黄金札】
金箔置きの鎧よろいの札。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐しだ【黄金羊歯】
リョウメンシダの別称。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐づくり【黄金作り】
黄金またはその鍍金めっきで装飾すること。また、その装飾した物。源氏物語宿木「檳榔毛の―六つ」
⇒こ‐がね【黄金・金】
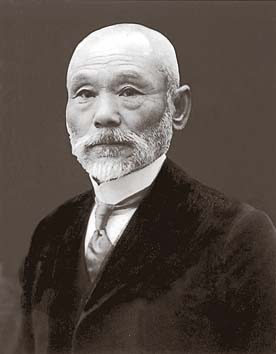 ⇒こがねい【小金井】
こがね‐いろ【黄金色】
黄金のように黄色に光る色。きんいろ。こんじき。「―の稲穂」
Munsell color system: 2.5Y7.5/11
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐かし【小金貸し】
わずかな金銭を貸す高利貸。
⇒こ‐がね【小金】
こがね‐かん【黄金羹】
鬱金粉うこんこをまぜて黄色にした羊羹。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】
コガネグモ科のクモ。雌は20〜25ミリメートル、雄は5ミリメートル。雌の腹部の背面は黒褐色の地に3条の黄帯を走らす。草間に隠れ帯のついた円網を張り、昆虫を捕食。8月頃産卵する。本州以南に分布。鹿児島県加治木町では、雌を訓練してクモ合戦をさせる。地方によりジョロウグモと呼ぶが、別種。サンバソウグモ。ヨロブリグモ。
こがねぐも
⇒こがねい【小金井】
こがね‐いろ【黄金色】
黄金のように黄色に光る色。きんいろ。こんじき。「―の稲穂」
Munsell color system: 2.5Y7.5/11
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐かし【小金貸し】
わずかな金銭を貸す高利貸。
⇒こ‐がね【小金】
こがね‐かん【黄金羹】
鬱金粉うこんこをまぜて黄色にした羊羹。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】
コガネグモ科のクモ。雌は20〜25ミリメートル、雄は5ミリメートル。雌の腹部の背面は黒褐色の地に3条の黄帯を走らす。草間に隠れ帯のついた円網を張り、昆虫を捕食。8月頃産卵する。本州以南に分布。鹿児島県加治木町では、雌を訓練してクモ合戦をさせる。地方によりジョロウグモと呼ぶが、別種。サンバソウグモ。ヨロブリグモ。
こがねぐも
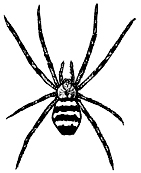 コガネグモ
提供:ネイチャー・プロダクション
コガネグモ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐ざね【黄金札】
金箔置きの鎧よろいの札。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐しだ【黄金羊歯】
リョウメンシダの別称。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐づくり【黄金作り】
黄金またはその鍍金めっきで装飾すること。また、その装飾した物。源氏物語宿木「檳榔毛の―六つ」
⇒こ‐がね【黄金・金】
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐ざね【黄金札】
金箔置きの鎧よろいの札。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐しだ【黄金羊歯】
リョウメンシダの別称。
⇒こ‐がね【黄金・金】
こがね‐づくり【黄金作り】
黄金またはその鍍金めっきで装飾すること。また、その装飾した物。源氏物語宿木「檳榔毛の―六つ」
⇒こ‐がね【黄金・金】
広辞苑 ページ 6896 での【○木陰に臥す者は枝を手折らず】単語。