複数辞典一括検索+![]()
![]()
つばめ【燕】🔗⭐🔉
つばめ【燕】
①スズメ目ツバメ科の鳥。背面は光沢ある青黒色で、顔・のどは栗色、上胸に黒帯があり、下面は白色。尾は長く、二つに割れている。日本には春飛来し、人家に営巣して、秋、南方に去る。なお、ツバメ科の鳥は、全長15〜20センチメートル前後。翼が良く発達し、速く飛びながら昆虫を捕食。世界に約90種、日本にはコシアカツバメ・イワツバメなど5種が分布。ツバクラ。ツバクロ。ツバクラメ。玄鳥。〈[季]春〉。万葉集19「―来る時になりぬと」
つばめ
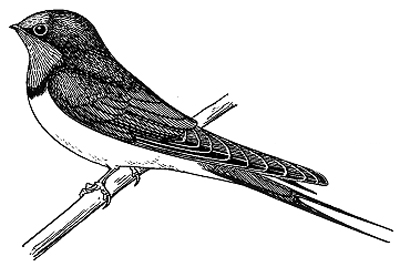 ツバメ
提供:OPO
ツバメ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
②燕算用の略。世間胸算用1「毎月の胸算用せぬによつて、―の合はぬ事ぞかし」
③年上の女にかわいがられている若い男。「若い―」
(地名別項)
⇒つばめ‐あわせ【燕合せ】
⇒つばめ‐うお【燕魚】
⇒つばめ‐お【燕尾】
⇒つばめ‐おもと【燕万年青】
⇒つばめ‐がえし【燕返し】
⇒つばめ‐ぐち【燕口】
⇒つばめ‐このしろ【燕鰶】
⇒つばめさり‐づき【燕去り月】
⇒つばめ‐さんよう【燕算用】
⇒つばめ‐ずいせん【燕水仙】
⇒つばめ‐ちどり【燕千鳥】
⇒つばめ‐の‐す【燕の巣】
⇒つばめ‐もり【燕銛】
⇒燕帰る
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
②燕算用の略。世間胸算用1「毎月の胸算用せぬによつて、―の合はぬ事ぞかし」
③年上の女にかわいがられている若い男。「若い―」
(地名別項)
⇒つばめ‐あわせ【燕合せ】
⇒つばめ‐うお【燕魚】
⇒つばめ‐お【燕尾】
⇒つばめ‐おもと【燕万年青】
⇒つばめ‐がえし【燕返し】
⇒つばめ‐ぐち【燕口】
⇒つばめ‐このしろ【燕鰶】
⇒つばめさり‐づき【燕去り月】
⇒つばめ‐さんよう【燕算用】
⇒つばめ‐ずいせん【燕水仙】
⇒つばめ‐ちどり【燕千鳥】
⇒つばめ‐の‐す【燕の巣】
⇒つばめ‐もり【燕銛】
⇒燕帰る
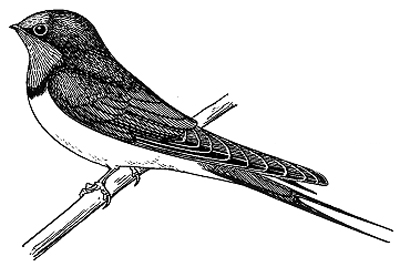 ツバメ
提供:OPO
ツバメ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
②燕算用の略。世間胸算用1「毎月の胸算用せぬによつて、―の合はぬ事ぞかし」
③年上の女にかわいがられている若い男。「若い―」
(地名別項)
⇒つばめ‐あわせ【燕合せ】
⇒つばめ‐うお【燕魚】
⇒つばめ‐お【燕尾】
⇒つばめ‐おもと【燕万年青】
⇒つばめ‐がえし【燕返し】
⇒つばめ‐ぐち【燕口】
⇒つばめ‐このしろ【燕鰶】
⇒つばめさり‐づき【燕去り月】
⇒つばめ‐さんよう【燕算用】
⇒つばめ‐ずいせん【燕水仙】
⇒つばめ‐ちどり【燕千鳥】
⇒つばめ‐の‐す【燕の巣】
⇒つばめ‐もり【燕銛】
⇒燕帰る
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
②燕算用の略。世間胸算用1「毎月の胸算用せぬによつて、―の合はぬ事ぞかし」
③年上の女にかわいがられている若い男。「若い―」
(地名別項)
⇒つばめ‐あわせ【燕合せ】
⇒つばめ‐うお【燕魚】
⇒つばめ‐お【燕尾】
⇒つばめ‐おもと【燕万年青】
⇒つばめ‐がえし【燕返し】
⇒つばめ‐ぐち【燕口】
⇒つばめ‐このしろ【燕鰶】
⇒つばめさり‐づき【燕去り月】
⇒つばめ‐さんよう【燕算用】
⇒つばめ‐ずいせん【燕水仙】
⇒つばめ‐ちどり【燕千鳥】
⇒つばめ‐の‐す【燕の巣】
⇒つばめ‐もり【燕銛】
⇒燕帰る
つばめ【燕】(地名)🔗⭐🔉
つばめ【燕】
新潟県中部の市。信濃川三角州の頂部に位置し、金属洋食器の生産が盛ん。人口8万3千。
つばめ‐あわせ【燕合せ】‥アハセ🔗⭐🔉
つばめ‐あわせ【燕合せ】‥アハセ
合計すること。燕算用。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐うお【燕魚】‥ウヲ🔗⭐🔉
つばめ‐うお【燕魚】‥ウヲ
①マンジュウダイ科の海産の硬骨魚。熱帯産。体は側扁して体高は著しく高く、背びれ・臀びれは巨大。全長約50センチメートル。ヒコウキウオ。
ツバメウオ
提供:東京動物園協会
 ②トビウオの異称。
⇒つばめ【燕】
②トビウオの異称。
⇒つばめ【燕】
 ②トビウオの異称。
⇒つばめ【燕】
②トビウオの異称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐お【燕尾】‥ヲ🔗⭐🔉
つばめ‐お【燕尾】‥ヲ
燕尾形の魚の尾。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐おもと【燕万年青】🔗⭐🔉
つばめ‐おもと【燕万年青】
ユリ科の多年草。亜高山の林下に自生。高さ30センチメートル余、葉は光沢ある緑色。オモトに似て地下茎の先端に叢生、長卵形で大きい。6月頃、花茎を出し、径1センチメートルほどの白色の6弁花を数個総状につける。花後藍色の美しい球形液果を結ぶ。ササニンドウ。
⇒つばめ【燕】
○燕帰るつばめかえる🔗⭐🔉
○燕帰るつばめかえる
春、南から渡ってきたツバメが、秋、南へ向けて飛び去って行く。帰燕きえん。〈[季]秋〉。↔燕来る
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ぐち【燕口】
①椀・折敷おしきなどで、ツバメの口のように外を黒く、内を赤く塗ったもの。
②鏃やじりの一種で、ツバメの口の形に似たもの。〈日葡辞書〉
⇒つばめ【燕】
つばめ‐このしろ【燕鰶】
ツバメコノシロ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。コノシロにやや似て、下あごが小さい。胸びれの下方に5本の軟条が感覚器として分かれている。南日本に産。アゴナシ。広義にはツバメコノシロ科魚類の総称。
ツバメコノシロ
提供:東京動物園協会
 ⇒つばめ【燕】
つばめさり‐づき【燕去り月】
陰暦8月の異称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐さんよう【燕算用】
合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ずいせん【燕水仙】
〔植〕スプレケリアの別称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ちどり【燕千鳥】
チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。
ツバメチドリ
撮影:小宮輝之
⇒つばめ【燕】
つばめさり‐づき【燕去り月】
陰暦8月の異称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐さんよう【燕算用】
合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ずいせん【燕水仙】
〔植〕スプレケリアの別称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ちどり【燕千鳥】
チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。
ツバメチドリ
撮影:小宮輝之
 ⇒つばめ【燕】
つばめ‐の‐す【燕の巣】
(→)燕窩えんかに同じ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐もり【燕銛】
漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。
⇒つばめ【燕】
つば‐もと【鍔元】
(→)「つばぎわ」に同じ。
つばら【委曲】
くわしいさま。つまびらか。万葉集1「―にも見つつ行かむを」
⇒つばら‐つばら‐に【委曲に】
つばら‐か【委曲か】
くわしいさま。こまごま。つまびらか。万葉集9「国のまほらを―に示し賜へば」
つばら‐つばら‐に【委曲に】
〔副〕
大変くわしいさま。まんべんなく。万葉集18「―我家わぎえしおもほゆ」
⇒つばら【委曲】
ツバル【Tuvalu】
南太平洋、ギルバート諸島南東方の国。旧称、エリス諸島。1978年英国から独立。面積26平方キロメートル。住民はポリネシア系。人口1万1千(2004)。首都フナフティ。トゥヴァル。→オセアニア(図)
⇒つばめ【燕】
つばめ‐の‐す【燕の巣】
(→)燕窩えんかに同じ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐もり【燕銛】
漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。
⇒つばめ【燕】
つば‐もと【鍔元】
(→)「つばぎわ」に同じ。
つばら【委曲】
くわしいさま。つまびらか。万葉集1「―にも見つつ行かむを」
⇒つばら‐つばら‐に【委曲に】
つばら‐か【委曲か】
くわしいさま。こまごま。つまびらか。万葉集9「国のまほらを―に示し賜へば」
つばら‐つばら‐に【委曲に】
〔副〕
大変くわしいさま。まんべんなく。万葉集18「―我家わぎえしおもほゆ」
⇒つばら【委曲】
ツバル【Tuvalu】
南太平洋、ギルバート諸島南東方の国。旧称、エリス諸島。1978年英国から独立。面積26平方キロメートル。住民はポリネシア系。人口1万1千(2004)。首都フナフティ。トゥヴァル。→オセアニア(図)
 ⇒つばめ【燕】
つばめさり‐づき【燕去り月】
陰暦8月の異称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐さんよう【燕算用】
合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ずいせん【燕水仙】
〔植〕スプレケリアの別称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ちどり【燕千鳥】
チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。
ツバメチドリ
撮影:小宮輝之
⇒つばめ【燕】
つばめさり‐づき【燕去り月】
陰暦8月の異称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐さんよう【燕算用】
合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ずいせん【燕水仙】
〔植〕スプレケリアの別称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ちどり【燕千鳥】
チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。
ツバメチドリ
撮影:小宮輝之
 ⇒つばめ【燕】
つばめ‐の‐す【燕の巣】
(→)燕窩えんかに同じ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐もり【燕銛】
漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。
⇒つばめ【燕】
つば‐もと【鍔元】
(→)「つばぎわ」に同じ。
つばら【委曲】
くわしいさま。つまびらか。万葉集1「―にも見つつ行かむを」
⇒つばら‐つばら‐に【委曲に】
つばら‐か【委曲か】
くわしいさま。こまごま。つまびらか。万葉集9「国のまほらを―に示し賜へば」
つばら‐つばら‐に【委曲に】
〔副〕
大変くわしいさま。まんべんなく。万葉集18「―我家わぎえしおもほゆ」
⇒つばら【委曲】
ツバル【Tuvalu】
南太平洋、ギルバート諸島南東方の国。旧称、エリス諸島。1978年英国から独立。面積26平方キロメートル。住民はポリネシア系。人口1万1千(2004)。首都フナフティ。トゥヴァル。→オセアニア(図)
⇒つばめ【燕】
つばめ‐の‐す【燕の巣】
(→)燕窩えんかに同じ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐もり【燕銛】
漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。
⇒つばめ【燕】
つば‐もと【鍔元】
(→)「つばぎわ」に同じ。
つばら【委曲】
くわしいさま。つまびらか。万葉集1「―にも見つつ行かむを」
⇒つばら‐つばら‐に【委曲に】
つばら‐か【委曲か】
くわしいさま。こまごま。つまびらか。万葉集9「国のまほらを―に示し賜へば」
つばら‐つばら‐に【委曲に】
〔副〕
大変くわしいさま。まんべんなく。万葉集18「―我家わぎえしおもほゆ」
⇒つばら【委曲】
ツバル【Tuvalu】
南太平洋、ギルバート諸島南東方の国。旧称、エリス諸島。1978年英国から独立。面積26平方キロメートル。住民はポリネシア系。人口1万1千(2004)。首都フナフティ。トゥヴァル。→オセアニア(図)
つばめ‐ぐち【燕口】🔗⭐🔉
つばめ‐ぐち【燕口】
①椀・折敷おしきなどで、ツバメの口のように外を黒く、内を赤く塗ったもの。
②鏃やじりの一種で、ツバメの口の形に似たもの。〈日葡辞書〉
⇒つばめ【燕】
つばめ‐このしろ【燕鰶】🔗⭐🔉
つばめ‐このしろ【燕鰶】
ツバメコノシロ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。コノシロにやや似て、下あごが小さい。胸びれの下方に5本の軟条が感覚器として分かれている。南日本に産。アゴナシ。広義にはツバメコノシロ科魚類の総称。
ツバメコノシロ
提供:東京動物園協会
 ⇒つばめ【燕】
⇒つばめ【燕】
 ⇒つばめ【燕】
⇒つばめ【燕】
つばめさり‐づき【燕去り月】🔗⭐🔉
つばめさり‐づき【燕去り月】
陰暦8月の異称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐さんよう【燕算用】🔗⭐🔉
つばめ‐さんよう【燕算用】
合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ずいせん【燕水仙】🔗⭐🔉
つばめ‐ずいせん【燕水仙】
〔植〕スプレケリアの別称。
⇒つばめ【燕】
つばめ‐ちどり【燕千鳥】🔗⭐🔉
つばめ‐ちどり【燕千鳥】
チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。
ツバメチドリ
撮影:小宮輝之
 ⇒つばめ【燕】
⇒つばめ【燕】
 ⇒つばめ【燕】
⇒つばめ【燕】
つばめ‐の‐す【燕の巣】🔗⭐🔉
つばめ‐もり【燕銛】🔗⭐🔉
つばめ‐もり【燕銛】
漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。
⇒つばめ【燕】
広辞苑に「ツバメ」で始まるの検索結果 1-16。