複数辞典一括検索+![]()
![]()
おおまつりごと‐びと【参議】オホ‥🔗⭐🔉
おおまつりごと‐びと【参議】オホ‥
⇒さんぎ。〈倭名類聚鈔5〉
⇒おお‐まつりごと【太政】
サムゲ‐タン【参鶏湯】🔗⭐🔉
サムゲ‐タン【参鶏湯】
(朝鮮語samgyet‘ang)鶏の腹に糯米もちごめ・栗・なつめ・朝鮮人参などを詰めて煮込んだ料理。
さん【三・参】🔗⭐🔉
さん【三・参】
①数の名。みつ。みっつ。「参」は「三」の大字。
②「三の糸」の略。「―下り」
③三(参)河国みかわのくにの略。「駿遠―」
さん‐いん【参院】‥ヰン🔗⭐🔉
さん‐いん【参院】‥ヰン
参議院の略称。
さん‐えつ【参謁】🔗⭐🔉
さん‐えつ【参謁】
参上して謁見すること。
さん‐か【参加】🔗⭐🔉
さん‐か【参加】
①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」
②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。
⇒さんか‐しょう【参加賞】
さん‐が【参賀】🔗⭐🔉
さん‐が【参賀】
参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉
さん‐かい【参会】‥クワイ🔗⭐🔉
さん‐かい【参会】‥クワイ
①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」
②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」
③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」
さん‐かく【参画】‥クワク🔗⭐🔉
さん‐かく【参画】‥クワク
計画に加わること。「大学の設立に―する」
さん‐がく【参学】🔗⭐🔉
さん‐がく【参学】
学問、特に仏学にたずさわること。太平記26「日夜の―、朝夕の法談」
さんか‐しょう【参加賞】‥シヤウ🔗⭐🔉
さんか‐しょう【参加賞】‥シヤウ
参加したことを記念する賞。また、その賞品。
⇒さん‐か【参加】
さん‐かん【参看】🔗⭐🔉
さん‐かん【参看】
照らし合わせ見ること。参照。
さん‐かん【参館】‥クワン🔗⭐🔉
さん‐かん【参館】‥クワン
他家を訪問することの謙譲語。参堂。
さん‐かん【参観】‥クワン🔗⭐🔉
さん‐かん【参観】‥クワン
その場に行って見ること。「授業―」
さん‐ぎ【参議】🔗⭐🔉
さん‐ぎ【参議】
(朝議に参与する意)
①(「三木」とも書く)奈良時代に設けられた令外りょうげの官。太政官に置かれ、大中納言に次ぐ重職で、四位以上の者から任ぜられ、公卿くぎょうの一員。8人が普通。おおいまつりごとびと。宰相。
②1869年(明治2)太政官に設け、大政に参与した官職。71年以降は太政大臣・左右大臣の次で、正三位相当。85年廃止。
③1937年(昭和12)日中戦争下、重要国務を諮問するために近衛内閣が設置した官職。内閣参議。43年廃止。
⇒さんぎ‐いん【参議院】
⇒さんぎいん‐ぎいん【参議院議員】
さんぎいん‐ぎいん【参議院議員】‥ヰン‥ヰン🔗⭐🔉
さんぎいん‐ぎいん【参議院議員】‥ヰン‥ヰン
参議院を組織する議員。比例代表(96人)・選挙区(146人)から公選され、任期6年、3年ごとに半数を改選。被選挙権は30歳以上。
⇒さん‐ぎ【参議】
さん‐きゅう【参究】‥キウ🔗⭐🔉
さん‐きゅう【参究】‥キウ
〔仏〕参禅して仏法の真髄を探求すること。
さん‐きん【参勤・参覲】🔗⭐🔉
さん‐きん【参勤・参覲】
①出仕して、主君のもとに勤めること。出仕したとき主君に目見まみえるのが通例なので、「参覲」の字も当てる。
②参勤交代の略。
⇒さんきん‐こうたい【参勤交代・参覲交代】
さんきん‐こうたい【参勤交代・参覲交代】‥カウ‥🔗⭐🔉
さんきん‐こうたい【参勤交代・参覲交代】‥カウ‥
江戸幕府が諸大名および交代寄合の旗本に課した義務の一つ。原則として隔年交代に石高に応じた人数を率いて出府し、江戸屋敷に居住して将軍の統帥下に入る制度。初め期限は定まっていなかったが、1635年(寛永12)外様とざま大名の、42年譜代ふだい大名の交代期限を定めた。
⇒さん‐きん【参勤・参覲】
さん‐ぐう【参宮】🔗⭐🔉
さん‐ぐう【参宮】
神社に参詣すること。特に伊勢神宮に参拝すること。
⇒さんぐう‐かいどう【参宮街道】
さんぐう‐かいどう【参宮街道】‥ダウ🔗⭐🔉
さんぐう‐かいどう【参宮街道】‥ダウ
(→)伊勢街道に同じ。
⇒さん‐ぐう【参宮】
さん‐けい【参詣】🔗⭐🔉
さん‐けい【参詣】
神仏におまいりに行くこと。「氏神様に―する」「―人」
さん‐ご【参伍】🔗⭐🔉
さん‐ご【参伍】
いりまじること。
さん‐こう【参向】‥カウ🔗⭐🔉
さん‐こう【参向】‥カウ
出向くこと。参上すること。
さん‐こう【参考】‥カウ🔗⭐🔉
さん‐こう【参考】‥カウ
てらしあわせて考えること。自分の考えややり方を決める手がかりとすること。また、その材料。去来抄「面影の事、支考も書き置かれたり。―せらるべし」。「従来の事例を―にする」「―資料」
⇒さんこう‐しょ【参考書】
⇒さんこう‐にん【参考人】
さん‐こう【参候】🔗⭐🔉
さん‐こう【参候】
①貴人のもとへ出向いて御機嫌をうかがうこと。平家物語1「ひそかに―の条」
②宮内省御歌所の職員。
さん‐こう【参校・参較】‥カウ🔗⭐🔉
さん‐こう【参校・参較】‥カウ
ひきあわせ考えること。
さんこう‐しょ【参考書】‥カウ‥🔗⭐🔉
さんこう‐しょ【参考書】‥カウ‥
調査・研究・学習などの参考にする書。
⇒さん‐こう【参考】
さんこうたいへいき【参考太平記】‥カウ‥🔗⭐🔉
さんこうたいへいき【参考太平記】‥カウ‥
太平記の流布本に、今出川本などの当時知られた有力な諸本を対校し、諸書を参照して記事の適否を考訂した書。41巻。徳川光圀の命により、今井弘済・内藤貞顕編。1689年(元禄2)完成、91年刊。なお、同じ編者による編書に参考源平盛衰記・参考平治物語・参考保元物語がある。
さんこう‐にん【参考人】‥カウ‥🔗⭐🔉
さんこう‐にん【参考人】‥カウ‥
〔法〕
①犯罪捜査のため捜査機関により取り調べられる者のうち、被疑者以外の者。被害者・目撃者など。また、嫌疑がはっきりしない被疑者を重要参考人ということがある。
②国会の委員会において、意見を求められた学識経験者など。
⇒さん‐こう【参考】
さん‐ざ【参座】🔗⭐🔉
さん‐ざ【参座】
集会の席に参列すること。
さん‐し【参仕】🔗⭐🔉
さん‐し【参仕】
参上して仕えること。
さん‐じ【参事】🔗⭐🔉
さん‐じ【参事】
①ある事務に参与すること。また、その職名。
②国会職員の一種。各議院の事務局・法制局、国立国会図書館その他に置かれる。
③旧制で、鉄道省高等官の一つ。1942年廃止。
⇒さんじ‐かい【参事会】
⇒さんじ‐かん【参事官】
さんじ‐かん【参事官】‥クワン🔗⭐🔉
さんじ‐かん【参事官】‥クワン
各省庁の部局の所掌事務に参加、重要事項の総括整理・企画に参画する官職、またはその職員。森鴎外、普請中「渡辺―は歌舞伎座の前で電車を降りた」
⇒さん‐じ【参事】
さん‐しゃ【参社】🔗⭐🔉
さん‐しゃ【参社】
神社に参詣すること。みやまいり。太平記17「日吉の大宮権現に―し給ひて」
さん‐しゃく【参酌】🔗⭐🔉
さん‐しゃく【参酌】
てらしあわせて善をとり悪をすてること。比べて参考にすること。斟酌しんしゃく。「事情を―する」
さん‐しゅう【参集】‥シフ🔗⭐🔉
さん‐しゅう【参集】‥シフ
寄り集まること。「定刻に御―願います」
さん‐しょう【参照】‥セウ🔗⭐🔉
さん‐しょう【参照】‥セウ
照らし合わせて見ること。引き比べて参考にすること。「別表―のこと」→シー‐エフ
さん‐じょう【参上】‥ジヤウ🔗⭐🔉
さん‐じょう【参上】‥ジヤウ
目上の人の所に行くこと。うかがうこと。「近く―します」
さん・じる【参じる】🔗⭐🔉
さん・じる【参じる】
〔自上一〕
(→)「参ずる」に同じ。
さん‐しん【参進】🔗⭐🔉
さん‐しん【参進】
神前や貴人の前に進み出ること。
さん‐じん【参陣】‥ヂン🔗⭐🔉
さん‐じん【参陣】‥ヂン
軍陣に参上すること。陣営に参加すること。〈日葡辞書〉
さん・する【参する】🔗⭐🔉
さん・する【参する】
〔自サ変〕[文]参す(サ変)
まじわる。加わる。たずさわる。参与する。
さん・ずる【参ずる】🔗⭐🔉
さん・ずる【参ずる】
〔自サ変〕[文]参ず(サ変)
①参上する。まいる。枕草子161「―・ぜむとするを今日明日の御物忌にてなん」。「持って―・じます」
②参禅する。
さん‐せい【参政】🔗⭐🔉
さん‐せい【参政】
①政治に参与すること。
②執政の次に位し、政治に参与する職。江戸幕府の若年寄など。
③1868年(明治1)藩政をつかさどらせるために各藩に置いた職名。
⇒さんせい‐けん【参政権】
さんせい‐けん【参政権】🔗⭐🔉
さんせい‐けん【参政権】
国民が国政に直接または間接に参与する権利。選挙権・被選挙権、国民投票、国民審査で投票する権利など。中江兆民、国会論「―は人民の所有物にして宰相百僚の所有物に非ざるなり」
⇒さん‐せい【参政】
さん‐せん【参戦】🔗⭐🔉
さん‐せん【参戦】
戦争に参加すること。「同盟国が―する」
さん‐ぜん【参禅】🔗⭐🔉
さん‐ぜん【参禅】
禅道に入って学ぶこと。坐禅して禅を修めること。問禅。
さん‐だい【参内】🔗⭐🔉
さん‐だい【参内】
内裏だいりに参上すること。
⇒さんだい‐がさ【参内傘】
⇒さんだい‐でん【参内殿】
さんだい‐がさ【参内傘】🔗⭐🔉
さんだい‐がさ【参内傘】
公卿・大名(10万石以上)などが参内または儀式に出るとき、従者にさしかけさせた長柄の傘。
参内傘
 ⇒さん‐だい【参内】
⇒さん‐だい【参内】
 ⇒さん‐だい【参内】
⇒さん‐だい【参内】
さんだい‐でん【参内殿】🔗⭐🔉
さんだい‐でん【参内殿】
京都御所内に設けられた殿舎。常御殿つねごてんの西、御車寄の内にあって、皇族・大臣などが参賀の際ここから参入した。
⇒さん‐だい【参内】
さん‐ち【参知】🔗⭐🔉
さん‐ち【参知】
あずかり知ること。たずさわること。
⇒さんち‐せいじ【参知政事】
さんち‐せいじ【参知政事】🔗⭐🔉
さんち‐せいじ【参知政事】
唐代から元代まで置かれた官名。唐では宰相に参知政事の名義を給した。宋では副宰相として、参政と簡称。
⇒さん‐ち【参知】
さん‐ちゃく【参着】🔗⭐🔉
さん‐ちゃく【参着】
①まいりつくこと。到着すること。
②参着払ばらいの略。
⇒さんちゃく‐ばらい【参着払】
さんちゃく‐ばらい【参着払】‥バラヒ🔗⭐🔉
さんちゃく‐ばらい【参着払】‥バラヒ
(特に外国為替について用いる語)(→)一覧払いちらんばらいに同じ。
⇒さん‐ちゃく【参着】
さん‐ちょう【参朝】‥テウ🔗⭐🔉
さん‐ちょう【参朝】‥テウ
朝廷に出仕すること。参内。
さん‐でん【参殿】🔗⭐🔉
さん‐でん【参殿】
①御殿に参上すること。
②人の家を訪問することの謙譲語。
さんてんだいごだいさんき【参天台五台山記】🔗⭐🔉
さんてんだいごだいさんき【参天台五台山記】
僧成尋じょうじんの入宋旅行日記。1072年(延久4)宋の商船に便乗して入宋、天台山に登り開封に赴き、翌年帰国する弟子と別れるところで日記を終わる。当時の宋の実状を詳細に書き留める。
さん‐どう【参堂】‥ダウ🔗⭐🔉
さん‐どう【参堂】‥ダウ
①寺に参詣すること。
②人の家を訪問することの謙譲語。参館。
さん‐どう【参道】‥ダウ🔗⭐🔉
さん‐どう【参道】‥ダウ
社寺に参詣するためにつくられた道。「表―」
さん‐にゅう【参入】‥ニフ🔗⭐🔉
さん‐にゅう【参入】‥ニフ
①高貴の所にまいること。入って行くこと。参上。
②加わること。参加すること。「他の業界に―する」
⇒さんにゅう‐おんじょう【参入音声】
しん‐し【参差】🔗⭐🔉
しん‐し【参差】
①長短ふぞろいであるさま。「枝葉―として茂る」
②入りまじっているさま。
③くいちがっているさま。ちぐはぐ。
しん‐しょう【参商】‥シヤウ🔗⭐🔉
しん‐しょう【参商】‥シヤウ
①参星と商星。
②(参星は西方に、商星は東方にあって、相隔たっているからいう)遠く相離れて会うことのないたとえ。太平記12「君が夫婦をして―たらしむ」
まい【参】マヰ🔗⭐🔉
まい【参】マヰ
自動詞(上一段か上二段か不明)の連用形。その音便形「まう」の形もある。意味は(→)「参る」(自五)に同じ。仁徳紀「うち渡す弥木栄やがはえなす来入り―来れ」。万葉集18「都へに―しわが夫せを」。万葉集6「―昇る八十氏人やそうじびとの手向けする」
まい‐いた・る【参到る】マヰ‥🔗⭐🔉
まい‐いた・る【参到る】マヰ‥
〔自四〕
参りいたる。参りつく。→まいたる
まい・す【参す】マヰス🔗⭐🔉
まい・す【参す】マヰス
〔他下二〕
(マイラスの約。のち、サ変にも活用した)進上する。たてまつる。まいらす。田植草紙「君に―・せう京絵書いたる扇を」
まい・ず【参出】マヰヅ🔗⭐🔉
まい・ず【参出】マヰヅ
〔自下二〕
(マイイヅの約)参上する。まいる。万葉集6「山たづの迎へ―・でむ君が来まさば」
まいた・る【参到る】マヰ‥🔗⭐🔉
まいた・る【参到る】マヰ‥
〔自四〕
(マイイタルの約)参りいたる。参りつく。仏足石歌「幸さきはひの厚き輩ともがら―・りて正目まさめに見けむ足跡あとのともしさ」
まいっ‐た【参った】マヰ‥🔗⭐🔉
まいっ‐た【参った】マヰ‥
①柔道・剣道で、負けた時の合図の声。
②(「負けた」の意の掛声から)相撲を指す。狂言、文相撲「間に―を致しまする」
まいで・く【参出来】マヰ‥🔗⭐🔉
まいで・く【参出来】マヰ‥
〔自カ変〕
まいりくる。まいる。もうでく。参上する。古事記中「何しかも汝いましの兄いろせは、朝夕の大御食おおみけに―・こざる」
まい‐のぼ・る【参上る】マヰ‥🔗⭐🔉
まい‐のぼ・る【参上る】マヰ‥
〔自四〕
まいる。参上する。万葉集6「―・る八十氏人やそうじびとの」
まいら・す【参らす】マヰラス🔗⭐🔉
まいら・す【参らす】マヰラス
〔他下二〕
①さし上げる。進上する。たてまつる。源氏物語夕顔「御くだものなど―・す」
②他の動詞の連用形に添えて、謙譲の意を表す。…して差し上げる。お…申し上げる。源氏物語橋姫「さだかに伝へ―・せん」
まいらせ‐そろ【参らせ候】マヰラセ‥🔗⭐🔉
まいらせ‐そろ【参らせ候】マヰラセ‥
①(近世、女性の手紙文に丁寧語として用いられた慣用句)ます。ございます。
参らせ候
 ②成行きまかせで物事をいいかげんにすること。そろべく候。
③恋文。誹風柳多留20「つれづれの外に―も書き」
②成行きまかせで物事をいいかげんにすること。そろべく候。
③恋文。誹風柳多留20「つれづれの外に―も書き」
 ②成行きまかせで物事をいいかげんにすること。そろべく候。
③恋文。誹風柳多留20「つれづれの外に―も書き」
②成行きまかせで物事をいいかげんにすること。そろべく候。
③恋文。誹風柳多留20「つれづれの外に―も書き」
まいり【参り】マヰリ🔗⭐🔉
まいり【参り】マヰリ
①行くこと、来ることの謙譲語。参上。蜻蛉日記中「年月の勘事こうじなりとも、今日の―には許されなん」
②高貴の人のところ、特に宮中に行くこと、また、仕えること。参上。参内。源氏物語少女「東の院には―の夜の人々の装束せさせ給ふ」
③社寺に参詣すること。また、その人。「宮―」「お百度―」
⇒まいり‐おんじょう【参入音声・参音声】
⇒まいり‐げこう【参り下向】
⇒まいり‐ざかな【参り肴】
⇒まいり‐ばか【詣り墓・参り墓】
⇒まいり‐もの【参り物】
まいり‐おんじょう【参入音声・参音声】マヰリ‥ジヤウ🔗⭐🔉
まいり‐おんじょう【参入音声・参音声】マヰリ‥ジヤウ
雅楽で、諸員の登場する時に奏する音楽。また、舞人の登場する時に奏する音楽。今は後者の意に使用。久米舞などにある。↔退出まかで音声。
⇒まいり【参り】
まいり・く【参り来】マヰリ‥🔗⭐🔉
まいり・く【参り来】マヰリ‥
〔自カ変〕
参上する。もうでく。落窪物語1「いつしか―・こんとて」
まいり‐げこう【参り下向】マヰリ‥カウ🔗⭐🔉
まいり‐げこう【参り下向】マヰリ‥カウ
①参上と下向。
②神仏に参詣して帰ること。また、その人。狂言、富士松「峰から谷、谷から峰まで―の人々はおびただしいことでござる」
⇒まいり【参り】
まいり‐ざかな【参り肴】マヰリ‥🔗⭐🔉
まいり‐ざかな【参り肴】マヰリ‥
式三献しきさんこんの肴に対して、普通の食膳の肴。
⇒まいり【参り】
まいり‐つ・く【参り着く】マヰリ‥🔗⭐🔉
まいり‐つ・く【参り着く】マヰリ‥
〔自五〕
到着する。参着する。
まいり‐ばか【詣り墓・参り墓】マヰリ‥🔗⭐🔉
まいり‐ばか【詣り墓・参り墓】マヰリ‥
両墓制で、死者を埋葬した墓とは別に、少し離れたところに供養のために石塔を建てる墓。墓参はこちらにする。引墓ひきはか。↔埋墓うめばか。
⇒まいり【参り】
まいり‐もの【参り物】マヰリ‥🔗⭐🔉
まいり‐もの【参り物】マヰリ‥
食物の尊敬語。召し上がり物。源氏物語玉鬘「―なるべし折敷おしき手づから取りて」
⇒まいり【参り】
まい・る【参る】マヰル🔗⭐🔉
まい・る【参る】マヰル
[一]〔自五〕
(マヰ(参)イ(入)ルの約)
➊高貴の所へ行く。
①宮廷または身分の高い人の所に行く。参上する。万葉集2「一日には千たび―・りしひむかしの大き御門を入りかてぬかも」。伊勢物語「内へ―・り給ふに」。「宮中に―・る」
②入内する。また、宮仕えなどに上がる。宇津保物語俊蔭「御娘の春宮に―・り給ふべき御料」。枕草子184「宮にはじめて―・りたるころ、もののはづかしきことの数知らず」
③神社・仏閣などにもうでる。参詣さんけいする。更級日記「清水にねむごろに―・りつかうまつらましかば」。「善光寺に―・る」
④物などが貴人の所などに到来するのにいう。源氏物語若菜上「古き世の一の物と名ある限りは、みなつどひ―・る御賀になむあめる」
⑤行く。行く先を敬っていう。転じて、聞き手へのへりくだりの気持をこめて、「行く」「来る」の意。また、一般的に、重々しい口調でいう時にも使う。おあん物語「おれが兄様は、折々山へ鉄鉋うちに―・られた」。「只今お宅の方へ―・ります」「御一緒に―・ります」「電車が―・ります」「地下鉄で―・ります」
➋相手に屈する。
①降参する。負ける。狂言、文相撲「取手、打こかして、―・つたのと云うて引込む」
②閉口する。「彼の毒舌には―・る」
③弱る。へたばる。また、「死ぬ」を、ややいやしめていう語。「さすがの彼も大分―・って来た」「とうとう―・ったか」
④心が奪われる。愛に溺れる。「彼女にすっかり―・っている」
➌「まゐらす(下二)」の形で、動詞の連用形に接続して謙譲の意を添える。→参らす2。
[二]〔他五〕
①身分の尊い人の手もとに差し上げる。(何かの仕事を)してさし上げる。伊勢物語「親王みこに馬の頭かみ大御酒―・る」。源氏物語胡蝶「人々御硯など―・りて御かへり疾くと聞ゆれば」
②「食う」「飲む」などの動作を表す尊敬語。召し上がる。また一般に、下位者の奉仕する行為をお受けになる。なさる。源氏物語帚木「火あかくかかげなどして御果物ばかり―・れり」。源氏物語葵「御湯―・れなどさへ扱ひ聞え給ふを」。源氏物語若紫「今宵は、なほしづかに加持など―・りて出でさせ給へ」
③「する」を重々しい口調でいうのに使う。狂言、文相撲「相撲…一番―・らう」
④女の手紙の脇付に用いる語。浄瑠璃、心中天の網島「行灯あんどんにて上書見れば、小春様―・る、紙屋内さんより」
みかわ【三河・参河】‥カハ🔗⭐🔉
みかわ【三河・参河】‥カハ
旧国名。今の愛知県の東部。三州さんしゅう。参州。
⇒みかわ‐しゅう【三河衆】
⇒みかわのくに‐いっこういっき【三河国一向一揆】
⇒みかわ‐まんざい【三河万歳】
⇒みかわ‐ものがたり【三河物語】
⇒みかわ‐もめん【三河木綿】
⇒みかわ‐わん【三河湾】
もう‐したが・う【参従ふ】マウシタガフ🔗⭐🔉
もう‐したが・う【参従ふ】マウシタガフ
〔自四〕
(マヰシタガフの音便)投降する。服従する。崇神紀「帰伏もうしたがひなむ」
もう‐のぼ・る【参上る】マウ‥🔗⭐🔉
もう‐のぼ・る【参上る】マウ‥
〔自四〕
(マヰノボルの音便)参上する。まいる。竹取物語「―・るといふ事を聞きて」
[漢]参🔗⭐🔉
参 字形
 筆順
筆順
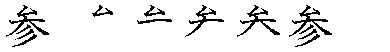 〔厶部6画/8画/教育/2718・3B32〕
[參] 字形
〔厶部6画/8画/教育/2718・3B32〕
[參] 字形
 〔厶部9画/11画/5052・5254〕
〔音〕サン・シン(呉)(漢)
〔訓〕まいる・みつ
[意味]
[一]サン
①まじわる。仲間にはいる。かかわりあう。「参加・参与・参画・参戦」
②まじえる。あれこれくらべ合わせる。「参考・参照」
③まいる。高貴の所へ行く。「明朝参じます」「参上・参詣さんけい・代参・日参・見参げんざん・持参・古参・新参しんざん」
④みっつ。みつ。「金参万円・参河みかわ国」▶「三」に代用する字。
[二]シン星座の名。オリオン座の中の三つの星。からすきぼし。「参宿・参商」
[解字]
形声。上半部は、髪飾りをつけた女性の姿を描いた象形文字。下に、光り輝く意味を示す音符「彡さん」を加えて、光がきらきらと入りまじる意味を表す。[
〔厶部9画/11画/5052・5254〕
〔音〕サン・シン(呉)(漢)
〔訓〕まいる・みつ
[意味]
[一]サン
①まじわる。仲間にはいる。かかわりあう。「参加・参与・参画・参戦」
②まじえる。あれこれくらべ合わせる。「参考・参照」
③まいる。高貴の所へ行く。「明朝参じます」「参上・参詣さんけい・代参・日参・見参げんざん・持参・古参・新参しんざん」
④みっつ。みつ。「金参万円・参河みかわ国」▶「三」に代用する字。
[二]シン星座の名。オリオン座の中の三つの星。からすきぼし。「参宿・参商」
[解字]
形声。上半部は、髪飾りをつけた女性の姿を描いた象形文字。下に、光り輝く意味を示す音符「彡さん」を加えて、光がきらきらと入りまじる意味を表す。[ ]は異体字。
[下ツキ
帰参・見参・降参・古参・直参・持参・新参・推参・代参・遅参・朝参・独参湯・日参・人参・不参・仏参・墓参・海参いりこ・光参きんこ
]は異体字。
[下ツキ
帰参・見参・降参・古参・直参・持参・新参・推参・代参・遅参・朝参・独参湯・日参・人参・不参・仏参・墓参・海参いりこ・光参きんこ
 筆順
筆順
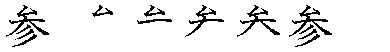 〔厶部6画/8画/教育/2718・3B32〕
[參] 字形
〔厶部6画/8画/教育/2718・3B32〕
[參] 字形
 〔厶部9画/11画/5052・5254〕
〔音〕サン・シン(呉)(漢)
〔訓〕まいる・みつ
[意味]
[一]サン
①まじわる。仲間にはいる。かかわりあう。「参加・参与・参画・参戦」
②まじえる。あれこれくらべ合わせる。「参考・参照」
③まいる。高貴の所へ行く。「明朝参じます」「参上・参詣さんけい・代参・日参・見参げんざん・持参・古参・新参しんざん」
④みっつ。みつ。「金参万円・参河みかわ国」▶「三」に代用する字。
[二]シン星座の名。オリオン座の中の三つの星。からすきぼし。「参宿・参商」
[解字]
形声。上半部は、髪飾りをつけた女性の姿を描いた象形文字。下に、光り輝く意味を示す音符「彡さん」を加えて、光がきらきらと入りまじる意味を表す。[
〔厶部9画/11画/5052・5254〕
〔音〕サン・シン(呉)(漢)
〔訓〕まいる・みつ
[意味]
[一]サン
①まじわる。仲間にはいる。かかわりあう。「参加・参与・参画・参戦」
②まじえる。あれこれくらべ合わせる。「参考・参照」
③まいる。高貴の所へ行く。「明朝参じます」「参上・参詣さんけい・代参・日参・見参げんざん・持参・古参・新参しんざん」
④みっつ。みつ。「金参万円・参河みかわ国」▶「三」に代用する字。
[二]シン星座の名。オリオン座の中の三つの星。からすきぼし。「参宿・参商」
[解字]
形声。上半部は、髪飾りをつけた女性の姿を描いた象形文字。下に、光り輝く意味を示す音符「彡さん」を加えて、光がきらきらと入りまじる意味を表す。[ ]は異体字。
[下ツキ
帰参・見参・降参・古参・直参・持参・新参・推参・代参・遅参・朝参・独参湯・日参・人参・不参・仏参・墓参・海参いりこ・光参きんこ
]は異体字。
[下ツキ
帰参・見参・降参・古参・直参・持参・新参・推参・代参・遅参・朝参・独参湯・日参・人参・不参・仏参・墓参・海参いりこ・光参きんこ
広辞苑に「参」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む