複数辞典一括検索+![]()
![]()
こめ【米】🔗⭐🔉
こめ【米】
稲の果実。籾殻もみがらを取り去ったままのものを玄米、精白したものを白米または精米という。五穀の一つとされ、小麦とともに世界で最も重要な食糧穀物。粳うるちは炊いて飯とし、糯もちごめは蒸して餅とする。また、菓子・酒・味噌・醤油などの原料。皇極紀「岩の上に小猿―焼く」
こめ‐いち【米市】🔗⭐🔉
こめ‐いち【米市】
江戸時代、米相場の立った市場。
こめ‐かいしょ【米会所】‥クワイ‥🔗⭐🔉
こめ‐かいしょ【米会所】‥クワイ‥
①江戸時代、米商組合の集合所。時に米相場・手形引替所を兼ねた。
②米穀取引所の1876年(明治9)以前の称。
こめ‐がし【米河岸】🔗⭐🔉
こめ‐がし【米河岸】
陸揚げした米穀の貯蔵庫が建ち並んだ河岸。日本永代蔵4「―の売買うりかい」
こめ‐かみ【米噛み】🔗⭐🔉
こめ‐かみ【米噛み】
(布施の米を噛む意という)比丘尼びくにのつれあるく弟子。風俗文選「比丘尼の師たるものをお寮といひて、其の弟子を―とはいふなり」
こめ‐かわせ【米為替】‥カハセ🔗⭐🔉
こめ‐かわせ【米為替】‥カハセ
中世、為替の方法で米を売買・譲渡すること。替米かえまい・かわしまい。→為替2㋐
こめ‐きって【米切手】🔗⭐🔉
こめ‐きって【米切手】
江戸時代、諸藩の蔵屋敷が蔵米の買主に発行した切手。特に、大坂の蔵屋敷が発行した切手。正米しょうまい切手。払米切手。米札。
こめ‐くい【米食い】‥クヒ🔗⭐🔉
こめ‐くい【米食い】‥クヒ
米を食うこと。
⇒こめくい‐ねずみ【米喰い鼠】
⇒こめくい‐むし【米食い虫】
こめくい‐ねずみ【米喰い鼠】‥クヒ‥🔗⭐🔉
こめくい‐ねずみ【米喰い鼠】‥クヒ‥
金沢の郷土玩具。桐材で作った鼠を竹発条たけばねで台に付け、竹発条を押すと米を食べる動作をする。
⇒こめ‐くい【米食い】
こめくい‐むし【米食い虫】‥クヒ‥🔗⭐🔉
こめくい‐むし【米食い虫】‥クヒ‥
①(→)コクゾウムシの別称。
②役に立たない人をののしっていう語。ごくつぶし。
⇒こめ‐くい【米食い】
こめ‐くぼう【米公方】‥バウ🔗⭐🔉
こめ‐くぼう【米公方】‥バウ
(→)米将軍に同じ。
こめ‐ぐら【米蔵】🔗⭐🔉
こめ‐ぐら【米蔵】
米穀を入れておく倉庫。よねぐら。
こめ‐こうじ【米麹】‥カウジ🔗⭐🔉
こめ‐こうじ【米麹】‥カウジ
米で作った麹。清酒・味噌などの製造に用いる。
こめ‐ざこ【米雑魚】🔗⭐🔉
こめ‐ざこ【米雑魚】
メダカの異称。
こめ‐さし【米刺】🔗⭐🔉
こめ‐さし【米刺】
俵の中に挿し入れて米を抜き出し、その品質を検査するのに用いる、斜めにそいで先を尖らせた竹の筒。日本永代蔵1「―の先を争ひ」
こめ‐じち【米質】🔗⭐🔉
こめ‐じち【米質】
米を抵当として金を貸すこと。浮世草子、世間手代気質「商売はなくて―を取り」
こめ‐しょうぐん【米将軍】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
こめ‐しょうぐん【米将軍】‥シヤウ‥
徳川吉宗の俗称。
こめ‐じるし【米印】🔗⭐🔉
こめ‐じるし【米印】
「米」の字に似た記号。「※」
こめ‐そうどう【米騒動】‥サウ‥🔗⭐🔉
こめ‐そうどう【米騒動】‥サウ‥
1918年(大正7)7〜9月、米価の暴騰のため生活難に苦しんでいた大衆が米の廉売を要求して米屋・富豪・警察などを襲撃した事件。富山県魚津に起こって全国に波及し、労働者・農民を主力とする未曾有の大民衆暴動に発展、軍隊が鎮圧に出動した。この事件で寺内内閣が倒れた。
米騒動は全国に.岡山精米会社は焼き討ちに.1918年8月13日
提供:毎日新聞社
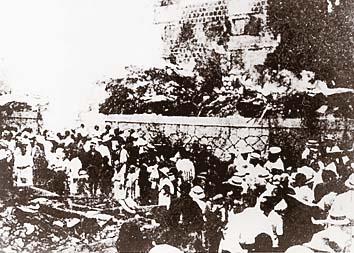
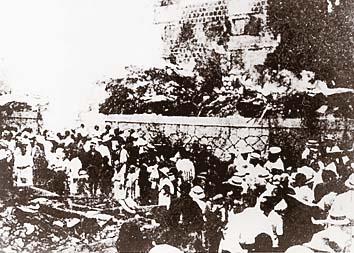
こめ‐そうば【米相場】‥サウ‥🔗⭐🔉
こめ‐そうば【米相場】‥サウ‥
①米穀の値段の高低。また、米穀の売買取引。山路愛山、現代金権史「日本の現代史は―の高下にて判断すべきこと多し」
②(→)空米相場くうまいそうばに同じ。
こめ‐だい【米代】🔗⭐🔉
こめ‐だい【米代】
米を買う代金。
こめ‐どころ【米所】🔗⭐🔉
こめ‐どころ【米所】
米を多く産する地。また、良米を産する地。
こめ‐ぬか【米糠】🔗⭐🔉
こめ‐ぬか【米糠】
玄米を精白する際に出るぬか。脂肪・蛋白質に富む。食用油をとったり、漬け物に用いたりするほか、家畜の飼料や肥料にも用いる。狭義のぬか。
こめ‐の‐いとこ【米の従兄弟】🔗⭐🔉
こめ‐の‐いとこ【米の従兄弟】
(埼玉地方で)父方の従兄弟。↔麦の従兄弟
こめ‐の‐こ【米の粉】🔗⭐🔉
こめ‐の‐こ【米の粉】
米をひいて粉状にしたもの。食料・糊料とする。→糝粉しんこ
こめ‐の‐じ【米の字】🔗⭐🔉
こめ‐の‐じ【米の字】
(「米」の字を三つに分解すると「八十八」となるので)88歳の称。米寿べいじゅ。「―の祝」
こめ‐の‐むし【米の虫】🔗⭐🔉
こめ‐の‐むし【米の虫】
(→)コクゾウムシの別称。
こめ‐の‐めし【米の飯】🔗⭐🔉
こめ‐の‐めし【米の飯】
①米を炊いた飯。
②何回でも飽きのこないもののたとえ。「熊野ゆや松風は―」
こめ‐ぶくろ【米袋】🔗⭐🔉
こめ‐ぶくろ【米袋】
①米を入れる袋。
②(→)大津袋に同じ。
こめ‐ぶね【米船】🔗⭐🔉
こめ‐ぶね【米船】
①米を積んだ船。
②兵糧ひょうろうを積みのせた船。
こめ‐や【米屋】🔗⭐🔉
こめ‐や【米屋】
米を売る店。また、その人。
⇒こめや‐かむり【米屋冠】
⇒こめや‐まち【米屋町】
こめや‐かむり【米屋冠】🔗⭐🔉
こめや‐かむり【米屋冠】
米屋・搗屋つきやなどが、糠のかかるのを防ぐためにする手拭のかぶり方。こめやかぶり。
⇒こめ‐や【米屋】
こめや‐まち【米屋町】🔗⭐🔉
こめや‐まち【米屋町】
①米相場によって生活する者の集まり住む町。
②(もと米穀取引所があったからいう)東京都中央区蠣殻かきがら町の異称。
⇒こめ‐や【米屋】
こめん‐じゃこ【米雑魚】🔗⭐🔉
こめん‐じゃこ【米雑魚】
〔動〕コメザコの訛。物類称呼「丁斑魚、めだか…大和にて―」
ビーチュウ【米酒】🔗⭐🔉
ビーチュウ【米酒】
(福建南部・台湾での発音)台湾産の蒸留酒。蒸した米に、麹こうじに相当する白粬ペイカを加え、発酵させて蒸留した酒。酒精含有20〜25パーセント。
べい【米】🔗⭐🔉
べい【米】
(呉音はマイ)
①こめ。狂言、かくすい「早田の―を十俵、御年貢にささぐる」
②亜米利加アメリカの略。
③米突メートルの略。
④(字形から)八十八のこと。「―寿」
べいあん【米庵】🔗⭐🔉
べいあん【米庵】
⇒いちかわべいあん(市河米庵)
べいえい‐せんそう【米英戦争】‥サウ🔗⭐🔉
べいえい‐せんそう【米英戦争】‥サウ
イギリスの対仏海上封鎖による通商妨害を原因として、1812〜14年に米英両国間で行われた戦争。英米戦争。1812年戦争。
べい‐えん【米塩】🔗⭐🔉
べい‐えん【米塩】
[史記酷吏伝、減宣]こめとしお。生きていくために、まず必要な物質。「―に窮する」
⇒べいえん‐の‐し【米塩の資】
べいえん‐の‐し【米塩の資】🔗⭐🔉
べいえん‐の‐し【米塩の資】
生計費。生活費。
⇒べい‐えん【米塩】
べい‐か【米価】🔗⭐🔉
べい‐か【米価】
米の値段。
⇒べいか‐しんぎかい【米価審議会】
⇒べいか‐ちょうせつ【米価調節】
べい‐か【米菓】‥クワ🔗⭐🔉
べい‐か【米菓】‥クワ
米を原料として焼くか揚げるかした塩味の菓子の総称。せんべい・あられなど。
べい‐か【米貨】‥クワ🔗⭐🔉
べい‐か【米貨】‥クワ
アメリカの貨幣。
べいか‐しんぎかい【米価審議会】‥クワイ🔗⭐🔉
べいか‐しんぎかい【米価審議会】‥クワイ
米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議し、必要事項を農林水産大臣に建議する諮問機関。1949年設立。略して米審。
⇒べい‐か【米価】
べいか‐ちょうせつ【米価調節】‥テウ‥🔗⭐🔉
べいか‐ちょうせつ【米価調節】‥テウ‥
政府が米穀の買上げ・払下げなどをなすことによって、米価の極端な騰落を調節すること。
⇒べい‐か【米価】
べい‐ぐん【米軍】🔗⭐🔉
べい‐ぐん【米軍】
アメリカ軍。
べい‐けん【米券】🔗⭐🔉
べい‐けん【米券】
①米穀証券の略。
②(→)米札べいさつ2に同じ。
べい‐ご【米語】🔗⭐🔉
べい‐ご【米語】
(もとの英語とは違いのある)アメリカ英語。
べい‐こく【米国】🔗⭐🔉
べい‐こく【米国】
亜米利加アメリカ合衆国の略称。
べい‐こく【米穀】🔗⭐🔉
べい‐こく【米穀】
こめ。その他の穀物を含めてもいう。
⇒べいこく‐しょうけん【米穀証券】
⇒べいこく‐つうちょう【米穀通帳】
⇒べいこく‐とうせい‐ほう【米穀統制法】
⇒べいこく‐とりひきじょ【米穀取引所】
⇒べいこく‐ねんど【米穀年度】
⇒べいこく‐はいきゅうとうせい‐ほう【米穀配給統制法】
⇒べいこく‐ほう【米穀法】
べいこく‐しょうけん【米穀証券】🔗⭐🔉
べいこく‐しょうけん【米穀証券】
米穀統制法実施当時、政府が米を買い上げるのに必要な資金を調達するため発行した短期債。米券。
⇒べい‐こく【米穀】
べいこく‐つうちょう【米穀通帳】‥チヤウ🔗⭐🔉
べいこく‐つうちょう【米穀通帳】‥チヤウ
米穀割当配給のために各世帯に交付された台帳。1941年(昭和16)六大都市で交付、翌年全国に及ぶ。82年食糧管理法の改正により廃止。
⇒べい‐こく【米穀】
べいこく‐とうせい‐ほう【米穀統制法】‥ハフ🔗⭐🔉
べいこく‐とうせい‐ほう【米穀統制法】‥ハフ
米の価格を調節するため、政府が米価基準を設定して米の売買を行うほか、輸出入制限などをすることを定めた法律。1933年制定。42年食糧管理法に解消。→米穀法。
⇒べい‐こく【米穀】
べいこく‐とりひきじょ【米穀取引所】🔗⭐🔉
べいこく‐とりひきじょ【米穀取引所】
米を売買物件とする商品取引所。大阪堂島をはじめ全国十数カ所にあった。1939年制定の米穀配給統制法により一般の商品取引所と区別して取り扱われ、42年食糧管理法制定により廃止。
⇒べい‐こく【米穀】
べいこく‐ねんど【米穀年度】🔗⭐🔉
べいこく‐ねんど【米穀年度】
前年11月から当年10月まで。終わる月の属する年をとる。
⇒べい‐こく【米穀】
べいこく‐はいきゅうとうせい‐ほう【米穀配給統制法】‥キフ‥ハフ🔗⭐🔉
べいこく‐はいきゅうとうせい‐ほう【米穀配給統制法】‥キフ‥ハフ
米穀需給の円滑と価格の適正とを図るために、その配給機構の整備を目的とした法律。1939年制定。42年食糧管理法制定により廃止。
⇒べい‐こく【米穀】
べいこく‐ほう【米穀法】‥ハフ🔗⭐🔉
べいこく‐ほう【米穀法】‥ハフ
米の需給調節を目的とした法律。米騒動後、1921年(大正10)制定。33年米穀統制法として強化された。
⇒べい‐こく【米穀】
べい‐さく【米作】🔗⭐🔉
べい‐さく【米作】
稲を栽培・収穫すること。こめづくり。また、稲のみのりぐあい。「―地帯」
べい‐さつ【米札】🔗⭐🔉
べい‐さつ【米札】
①米切手こめきって。
②江戸時代における藩札の一種。米穀を兌換だかん準備として発行したもの。「米五升定価五百文」などと記す。米券。
べい‐さん【米産】🔗⭐🔉
べい‐さん【米産】
米の生産。
べいさんじん【米山人】🔗⭐🔉
べいさんじん【米山人】
⇒おかだべいさんじん(岡田米山人)
べいしき‐しゅうきゅう【米式蹴球】‥シウキウ🔗⭐🔉
べいしき‐しゅうきゅう【米式蹴球】‥シウキウ
アメリカン‐フットボールの訳語。
べい‐じゅ【米寿】🔗⭐🔉
べい‐じゅ【米寿】
(「米」の字を分解すれば「八十八」になることから)八十八歳のこと。また、八十八歳の賀の祝い。米よねの祝い。「―を祝う」
べい‐しゅう【米収】‥シウ🔗⭐🔉
べい‐しゅう【米収】‥シウ
米の収穫。
べい‐しゅう【米州】‥シウ🔗⭐🔉
べい‐しゅう【米州】‥シウ
南北亜米利加アメリカ州の略。
⇒べいしゅう‐きこう【米州機構】
べいしゅう‐きこう【米州機構】‥シウ‥🔗⭐🔉
べいしゅう‐きこう【米州機構】‥シウ‥
(Organization of American States)米州における国際的協力機関で、第9回汎米会議(1948年)において組織されたもの。米州相互防衛条約の実施も担当。OAS
⇒べい‐しゅう【米州】
べい‐しょう【米商】‥シヤウ🔗⭐🔉
べい‐しょう【米商】‥シヤウ
米穀のあきない。米穀商。こめや。
べい‐しょく【米食】🔗⭐🔉
べい‐しょく【米食】
米を食うこと。米を主食とすること。
べい‐じん【米人】🔗⭐🔉
べい‐じん【米人】
米国人。アメリカ人。
べいせい‐せんそう【米西戦争】‥サウ🔗⭐🔉
べいせい‐せんそう【米西戦争】‥サウ
1898年アメリカとスペインとの間に行われた戦争。キューバの反乱とアメリカ軍艦メイン号の爆沈事件とを契機として勃発。この結果、キューバが独立、プエルト‐リコ・グアム島・フィリピン諸島をアメリカが獲得した。
べい‐せん【米銭】🔗⭐🔉
べい‐せん【米銭】
こめとぜに。また、米代。
べい‐そ【米租】🔗⭐🔉
べい‐そ【米租】
年貢の米。納米。
べい‐なす【米茄子】🔗⭐🔉
べい‐なす【米茄子】
(「米」は米国の意。アメリカに伝わった品種の改良種であることから)茄子の一品種。大きな卵形の球体で、ヘタが緑色。
べい‐の‐が【米の賀】🔗⭐🔉
べい‐の‐が【米の賀】
米寿の祝い。米よねの祝い。
まいばら【米原】🔗⭐🔉
まいばら【米原】
(マイハラとも)滋賀県北東部の市。琵琶湖東岸に臨み、中世には湖港朝妻・筑摩が栄え、今は市域の南西部は鉄道・国道・高速道路の分岐点として交通の要衝。人口4万1千。
めめ【米】🔗⭐🔉
めめ【米】
こめ。狂言、比丘貞「此祝儀に、―五十石まいすぞ」
よな【米】🔗⭐🔉
よな【米】
「よね」の古形。「―ぐら」
よなご【米子】🔗⭐🔉
よなご【米子】
鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。
よね【米】🔗⭐🔉
よね【米】
(ヨナの転)
①こめ。土佐日記「銭なければ―をとりかけて」
②(「米」の字の形から)八十八歳の称。米寿べいじゅ。「―の祝い」
よねいち【米市】🔗⭐🔉
よねいち【米市】
狂言。もらった女小袖を米俵にかけて背負い、「米市御寮人のお里帰り」だとしゃれるのを、若者たちが本気にして杯を強要する。
よねかわ‐りゅう【米川流】‥カハリウ🔗⭐🔉
よねかわ‐りゅう【米川流】‥カハリウ
香道の流派。寛文(1661〜1673)の頃、京都の米川三右衛門常伯にはじまる。大名家を中心に盛行し、幕末には大量の伝書を残したが、明治以後衰亡。
よね‐ず【米酢】🔗⭐🔉
よね‐ず【米酢】
こめを主原料とした醸造酢。日本特有の食酢で、鮨や日本料理に広く用いる。こめず。
よね‐の‐いわい【米の祝】‥イハヒ🔗⭐🔉
よね‐の‐いわい【米の祝】‥イハヒ
八十八歳の賀の祝い。べいじゅのいわい。→よね(米)2
よね‐の‐まもり【米の守り】🔗⭐🔉
よね‐の‐まもり【米の守り】
米寿の祝いの時に、「米」という字を書いて人に贈る丸い餅。浮世風呂2「中の隠居が八十八の―を出しますネ」
よね‐やま【米山】🔗⭐🔉
よね‐やま【米山】
新潟県中部、柏崎市と上越市柿崎区との境にある山。標高993メートル。民謡「三階節」に歌われる。
⇒よねやま‐じんく【米山甚句】
よねやま‐じんく【米山甚句】🔗⭐🔉
よねやま‐じんく【米山甚句】
米山地方の民謡。明治中期から広く流行し、御座敷唄の代表曲の一つ。
⇒よね‐やま【米山】
[漢]米🔗⭐🔉
米 字形
 筆順
筆順
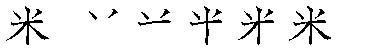 〔米部0画/6画/教育/4238・4A46〕
〔音〕ベイ(漢) マイ(呉) メ(慣)
〔訓〕こめ・よね・メートル
[意味]
①稲の実。こめ。よね。「米作・米穀・米塩・五斗米・玄米げんまい・精米せいまい・加州米かしゅうまい」
②アメリカ。「米国・米英・欧米・渡米」▶Americanの音訳「米利堅メリケン」の略。中国では「美メイ」をあてる。「美国」
③長さの単位。メートル。「平米へいべい・立米りゅうべい」▶mètreフランスの音訳「米突」「米的耳」の略。
[解字]
解字
〔米部0画/6画/教育/4238・4A46〕
〔音〕ベイ(漢) マイ(呉) メ(慣)
〔訓〕こめ・よね・メートル
[意味]
①稲の実。こめ。よね。「米作・米穀・米塩・五斗米・玄米げんまい・精米せいまい・加州米かしゅうまい」
②アメリカ。「米国・米英・欧米・渡米」▶Americanの音訳「米利堅メリケン」の略。中国では「美メイ」をあてる。「美国」
③長さの単位。メートル。「平米へいべい・立米りゅうべい」▶mètreフランスの音訳「米突」「米的耳」の略。
[解字]
解字 象形。黍きびの穂に小さな実がついているさまにかたどり、こめの意を表す。
[下ツキ
欧米・回米・外米・供米・玄米・古古米・五斗米・古米・散米・産米・地米・新米・神米・精米・節米・施米・洗米・饌米・白米・飯米・平米・立米・糧米・禄米
象形。黍きびの穂に小さな実がついているさまにかたどり、こめの意を表す。
[下ツキ
欧米・回米・外米・供米・玄米・古古米・五斗米・古米・散米・産米・地米・新米・神米・精米・節米・施米・洗米・饌米・白米・飯米・平米・立米・糧米・禄米
 筆順
筆順
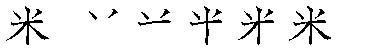 〔米部0画/6画/教育/4238・4A46〕
〔音〕ベイ(漢) マイ(呉) メ(慣)
〔訓〕こめ・よね・メートル
[意味]
①稲の実。こめ。よね。「米作・米穀・米塩・五斗米・玄米げんまい・精米せいまい・加州米かしゅうまい」
②アメリカ。「米国・米英・欧米・渡米」▶Americanの音訳「米利堅メリケン」の略。中国では「美メイ」をあてる。「美国」
③長さの単位。メートル。「平米へいべい・立米りゅうべい」▶mètreフランスの音訳「米突」「米的耳」の略。
[解字]
解字
〔米部0画/6画/教育/4238・4A46〕
〔音〕ベイ(漢) マイ(呉) メ(慣)
〔訓〕こめ・よね・メートル
[意味]
①稲の実。こめ。よね。「米作・米穀・米塩・五斗米・玄米げんまい・精米せいまい・加州米かしゅうまい」
②アメリカ。「米国・米英・欧米・渡米」▶Americanの音訳「米利堅メリケン」の略。中国では「美メイ」をあてる。「美国」
③長さの単位。メートル。「平米へいべい・立米りゅうべい」▶mètreフランスの音訳「米突」「米的耳」の略。
[解字]
解字 象形。黍きびの穂に小さな実がついているさまにかたどり、こめの意を表す。
[下ツキ
欧米・回米・外米・供米・玄米・古古米・五斗米・古米・散米・産米・地米・新米・神米・精米・節米・施米・洗米・饌米・白米・飯米・平米・立米・糧米・禄米
象形。黍きびの穂に小さな実がついているさまにかたどり、こめの意を表す。
[下ツキ
欧米・回米・外米・供米・玄米・古古米・五斗米・古米・散米・産米・地米・新米・神米・精米・節米・施米・洗米・饌米・白米・飯米・平米・立米・糧米・禄米
広辞苑に「米」で始まるの検索結果 1-92。もっと読み込む