複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (25)
くら【座】🔗⭐🔉
くら【座】
①物をのせる所。物をのせる台。「御手―」「矢―」
②すわる場所。座席。「天の磐―」「高御―」
③苗床なえどこの異称。
くら【蔵・倉・庫】🔗⭐🔉
くら【蔵・倉・庫】
①穀物・商品・家財などを火災・水湿・盗難などから守り、保管・貯蔵するための建物。倉庫。土蔵。万葉集16「新墾田あらきだの鹿猪田ししだの稲を―に蔵つみて」
②鎌倉・室町時代に、質屋のこと。
③(「蔵」と書く)歌舞伎などで、興行の不成立をいう隠語。おくら。
◇「倉」は、ものをしまっておく建物の意で広く使い、「蔵」は、大事なものを保管しておく建物で、日本式の土蔵にいうことが多い。
⇒蔵が建つ
くら【競】🔗⭐🔉
くら【競】
〔接尾〕
(「くらべ」の略)ある語の下に添えて「きそうこと」の意に用いる語。「かけ―」「おし―」
クラーク【kulak ロシア】🔗⭐🔉
クラーク【kulak ロシア】
ロシアにおける富農。階級としての富農は、十月革命後農業集団化の過程で漸次消滅。
クラーク【Kenneth M. Clark】🔗⭐🔉
クラーク【Kenneth M. Clark】
イギリスの美術史家。ナショナル‐ギャラリー館長・オックスフォード大学教授を歴任。著「風景画論」など。(1903〜1983)
クラーク【William Smith Clark】🔗⭐🔉
クラーク【William Smith Clark】
アメリカの教育家。北海道開拓使に招聘されて1876年(明治9)来日。新設の札幌農学校教頭に就任し、そのキリスト教信仰に基づく訓育は内村鑑三・新渡戸稲造らの学生に深い感化を及ぼした。「少年よ大志をいだけ」の語は有名。(1826〜1886)
クラーク像
撮影:新海良夫


くら‐あじ【鞍味】‥アヂ🔗⭐🔉
くら‐あじ【鞍味】‥アヂ
鞍の乗りごこち。くらごころ。
くら‐あずかり【蔵預り】‥アヅカリ🔗⭐🔉
くら‐あずかり【蔵預り】‥アヅカリ
倉庫に入れて預かること。また、その番人。蔵番。
⇒くらあずかり‐きって【蔵預り切手】
くらあずかり‐きって【蔵預り切手】‥アヅカリ‥🔗⭐🔉
くらあずかり‐きって【蔵預り切手】‥アヅカリ‥
江戸時代、各藩の蔵屋敷から蔵預りした貨物、特に米・砂糖などに対して振り出した倉荷証券。→出だし切手
⇒くら‐あずかり【蔵預り】
クラーレ【curare】🔗⭐🔉
クラーレ【curare】
(もと南米の土語)南米の先住民が毒矢に用いる植物性猛毒物質。多くはフジウツギ科の一種の樹皮から採り、ツヅラフジ科の一種を使うこともある。有効成分のツボクラリンは、脊椎動物の神経と筋との接合部を遮断し骨格筋を麻痺させる。筋弛緩剤および麻酔補助に用いる。ウーラリ(wourali)。
くらい【食らい】クラヒ🔗⭐🔉
くらい【食らい】クラヒ
食うこと。「大飯おおめし―」
⇒くらい‐だおれ【食らい倒れ】
⇒くらい‐ぬけ【食らい抜け】
くら‐い【位】クラヰ🔗⭐🔉
くら‐い【位】クラヰ
(「座くら居」の意)
[一]〔名〕
①そこにすわるための、設けの席。座所。持統紀「凡そ朝堂みかどの―の上にして」
②序列の上での位置。
㋐皇位。源氏物語明石「我は―にありし時あやまつことなかりしかど」
㋑官職の地位。源氏物語明石「親、大臣の―を保ち給へりき」
㋒親王・王・諸臣などの朝廷における着座の高下の標示。→位階1。
㋓物の等級または優劣。
㋔人や芸術作品などの品位・品格。
③十進法で数を表すために並べられた数字の、位置の名称。桁けた。「千の―」
④程度。「その―できれば安心だ」
[二]〔助詞〕
(副助詞。グライとも)体言、活用語の連体形、格助詞などに付いて、大体の程度・分量の基準・範囲を表す。ほど。ばかり。だけ。浄瑠璃、今宮の心中「なまなか茶漬―なら、いつそ戻つて寝てくれふ」。いろは文庫「人目の多い廓のうちを連れ出して来た―だものを」。「彼に―言えばいいのに」
⇒くらい‐ぎぬ【位衣】
⇒くらい‐だおれ【位倒れ】
⇒くらい‐だか【位高】
⇒くらい‐づけ【位付け】
⇒くらい‐づめ【位詰】
⇒くらい‐どり【位取り】
⇒くらい‐ぬけ【位抜け】
⇒くらい‐ぬすびと【位盗人】
⇒くらい‐の‐いろ【位の色】
⇒くらい‐の‐やま【位の山】
⇒くらい‐まけ【位負け】
⇒くらい‐やま【位山】
⇒くらい‐ゆずり【位譲り】
⇒くらい‐ろん【位論】
⇒位が付く
⇒位人臣を極める
くら・い【暗い・昏い・冥い】🔗⭐🔉
くら・い【暗い・昏い・冥い】
〔形〕[文]くら・し(ク)
①光がささない、または、さし方が不十分な状態である。古事記上「高天の原皆―・く葦原の中つ国悉に―・し」。「―・い夜道」「手もとが―・い」
②くもってはっきりしない。ぼんやりしている。色がくすんでいる。源氏物語総角「霧に隔てられて木の下も―・くなまめきたり」。「―・い緑色」「背景を―・い色にする」
③物を弁別する智力がない。暗愚である。徒然草「―・き人の、人をはかりて、其智をしれりと思はん、さらにあたるべからず」。浄瑠璃、国性爺合戦「―・き帝をいさめかね」
④物事に通じていない。「世界の動きに―・い」
⑤世の中が開けていない。神武紀「是の時に運よ鴻荒あらきに属あひ、時―・きに鍾あたれり」
⑥不満足である。不足である。浄瑠璃、国性爺合戦「我が韃靼は大国にて七珍万宝―・からずと申せ共」
⑦陰気である。晴々しない。不明朗である。「気分が―・くなる」「―・い性格」「―・い過去」
⇒暗い影がさす
⇒暗い所
クライアント【client】🔗⭐🔉
クライアント【client】
①弁護士・建築家・カウンセラーなど専門職への依頼人や相談者。
②顧客。得意先。取引先。
③ネットワーク上で他のコンピューターからサービスを受けるコンピューター。↔サーバー。
⇒クライアント‐サーバー‐システム【client server system】
クライアント‐サーバー‐システム【client server system】🔗⭐🔉
クライアント‐サーバー‐システム【client server system】
クライアントとサーバーによって構成されるコンピューター‐システム。クライアントでも一部の処理を分担して行うため、ホスト‐コンピューター‐システムに比べて入力に対する応答が速い。
⇒クライアント【client】
クライヴ【Robert Clive】🔗⭐🔉
クライヴ【Robert Clive】
イギリスの政治家・軍人。東インド会社書記として渡印。1757年ベンガル大守およびフランスの連合軍をプラッシーに破り、イギリスのインド支配の基礎を定めた。(1725〜1774)
○暗い影がさすくらいかげがさす
好調に進んで来たことに、悪くなりそうな前触れが現れる。「人生に暗い影がさし始める」
⇒くら・い【暗い・昏い・冥い】
○位が付くくらいがつく
品格・威厳がそなわる。
⇒くら‐い【位】
○暗い影がさすくらいかげがさす🔗⭐🔉
○暗い影がさすくらいかげがさす
好調に進んで来たことに、悪くなりそうな前触れが現れる。「人生に暗い影がさし始める」
⇒くら・い【暗い・昏い・冥い】
○位が付くくらいがつく🔗⭐🔉
○位が付くくらいがつく
品格・威厳がそなわる。
⇒くら‐い【位】
くらい‐ぎぬ【位衣】クラヰ‥
(→)位袍いほうに同じ。元輔集「―たのみそめてし色なれば」
⇒くら‐い【位】
くらい‐こ・む【食らい込む】クラヒ‥
〔自五〕
①深入りする。はまりこむ。誹風柳多留6「なまくらな鍛冶屋木辻へ―・み」
②捕らえられて牢に入れられる。留置される。
③(他動詞的に)やっかいなことをしょいこむ。「友人の借金を―・む」
くらいし【倉石】
姓氏の一つ。
⇒くらいし‐たけしろう【倉石武四郎】
クライシス【crisis】
①危機。夏目漱石、それから「―に証券を与へた様な気がした」
②経済上の危機。恐慌。
くらいし‐たけしろう【倉石武四郎】‥ラウ
中国語学・文学者。新潟県生れ。東大卒。京大・東大教授。現代中国語の研究・教育に尽力。著「岩波中国語辞典」「中国語五十年」など。(1897〜1975)
倉石武四郎
提供:毎日新聞社
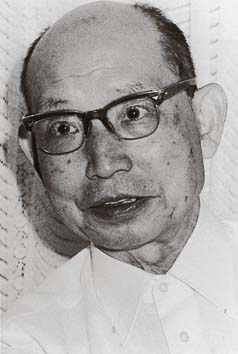 ⇒くらいし【倉石】
クライシュ【Quraysh アラビア】
イスラム勃興前後にメッカに居住していたアラブの部族名。活発な海外交易活動で有名。ムハンマドも、またウマイヤ朝・アッバース朝もクライシュの出身。
くら‐いしょう【蔵衣裳】‥シヤウ
江戸時代、歌舞伎の興行主が芝居の蔵から出して、下級の俳優に貸した衣裳。
⇒くらいし【倉石】
クライシュ【Quraysh アラビア】
イスラム勃興前後にメッカに居住していたアラブの部族名。活発な海外交易活動で有名。ムハンマドも、またウマイヤ朝・アッバース朝もクライシュの出身。
くら‐いしょう【蔵衣裳】‥シヤウ
江戸時代、歌舞伎の興行主が芝居の蔵から出して、下級の俳優に貸した衣裳。
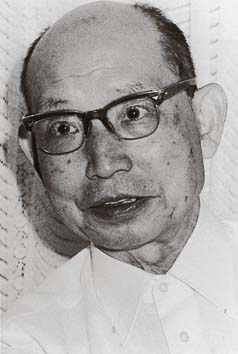 ⇒くらいし【倉石】
クライシュ【Quraysh アラビア】
イスラム勃興前後にメッカに居住していたアラブの部族名。活発な海外交易活動で有名。ムハンマドも、またウマイヤ朝・アッバース朝もクライシュの出身。
くら‐いしょう【蔵衣裳】‥シヤウ
江戸時代、歌舞伎の興行主が芝居の蔵から出して、下級の俳優に貸した衣裳。
⇒くらいし【倉石】
クライシュ【Quraysh アラビア】
イスラム勃興前後にメッカに居住していたアラブの部族名。活発な海外交易活動で有名。ムハンマドも、またウマイヤ朝・アッバース朝もクライシュの出身。
くら‐いしょう【蔵衣裳】‥シヤウ
江戸時代、歌舞伎の興行主が芝居の蔵から出して、下級の俳優に貸した衣裳。
くらい‐こ・む【食らい込む】クラヒ‥🔗⭐🔉
くらい‐こ・む【食らい込む】クラヒ‥
〔自五〕
①深入りする。はまりこむ。誹風柳多留6「なまくらな鍛冶屋木辻へ―・み」
②捕らえられて牢に入れられる。留置される。
③(他動詞的に)やっかいなことをしょいこむ。「友人の借金を―・む」
くらいし【倉石】🔗⭐🔉
くらいし【倉石】
姓氏の一つ。
⇒くらいし‐たけしろう【倉石武四郎】
クライシス【crisis】🔗⭐🔉
クライシス【crisis】
①危機。夏目漱石、それから「―に証券を与へた様な気がした」
②経済上の危機。恐慌。
くらいし‐たけしろう【倉石武四郎】‥ラウ🔗⭐🔉
くらいし‐たけしろう【倉石武四郎】‥ラウ
中国語学・文学者。新潟県生れ。東大卒。京大・東大教授。現代中国語の研究・教育に尽力。著「岩波中国語辞典」「中国語五十年」など。(1897〜1975)
倉石武四郎
提供:毎日新聞社
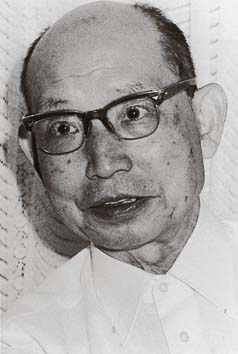 ⇒くらいし【倉石】
⇒くらいし【倉石】
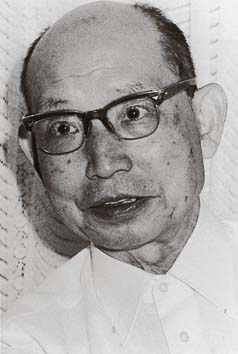 ⇒くらいし【倉石】
⇒くらいし【倉石】
クライシュ【Quraysh アラビア】🔗⭐🔉
クライシュ【Quraysh アラビア】
イスラム勃興前後にメッカに居住していたアラブの部族名。活発な海外交易活動で有名。ムハンマドも、またウマイヤ朝・アッバース朝もクライシュの出身。
大辞林の検索結果 (35)
くら【座】🔗⭐🔉
くら 【座】
高く設けられた場所。「天の石座(イワクラ)」「高御座(タカミクラ)」「御手座(ミテグラ)」など,複合語中にのみ用いられる。
くら【蔵・倉・庫】🔗⭐🔉
くら [2] 【蔵・倉・庫】
(1)家財や商品などを火災や盗難などから守り,保管しておく建物。倉庫。
(2)「お蔵(クラ){(2)}」に同じ。
くら【競】🔗⭐🔉
くら 【競】 (接尾)
〔「くらべ」の略〕
動詞の連用形またはそれに促音の付いた形に付いて,競争することの意を添える。「押し―」「にらめっ―」「かけっ―」
クラーク clerk
clerk 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クラーク [2]  clerk
clerk (1)書記。事務員。
(2)店員。
(1)書記。事務員。
(2)店員。
 clerk
clerk (1)書記。事務員。
(2)店員。
(1)書記。事務員。
(2)店員。
クラーク (ロシア) kulak
(ロシア) kulak 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クラーク [2]  (ロシア) kulak
(ロシア) kulak ロシアの,資産・資本を有する上層農民。社会主義革命後の農業集団化の過程で,階級としては消滅した。富農。
ロシアの,資産・資本を有する上層農民。社会主義革命後の農業集団化の過程で,階級としては消滅した。富農。
 (ロシア) kulak
(ロシア) kulak ロシアの,資産・資本を有する上層農民。社会主義革命後の農業集団化の過程で,階級としては消滅した。富農。
ロシアの,資産・資本を有する上層農民。社会主義革命後の農業集団化の過程で,階級としては消滅した。富農。
クラーク Clark
Clark 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クラーク  Clark
Clark (1)〔Colin Grant C.〕
(1905- ) イギリスの経済学者。産業を第一次から第三次に分類し,産業が高度化するにつれて国民所得の増大がみられることを発見。著「経済進歩の諸条件」など。
→ペティー=クラークの法則
(2)〔Kenneth Mackenzie C.〕
(1903-1983) イギリスの美術史家・評論家。ルネサンス美術の研究から出発し,自由な発想・文明史的視点から多数の美術評論を著す。著「レオナルド=ダ=ビンチ」「風景画論」「ザ-ヌード」など。
(3)〔William Smith C.〕
(1826-1886) アメリカの教育者。1876年(明治9)来日,札幌農学校の教頭となるが一年足らずで帰国。そのキリスト教精神と科学教育は内村鑑三・新渡戸稲造らの人材を育てた。離日に際し学生に言い残した言葉「青年よ大志を抱け(Boys, be ambitious)」は有名。
(1)〔Colin Grant C.〕
(1905- ) イギリスの経済学者。産業を第一次から第三次に分類し,産業が高度化するにつれて国民所得の増大がみられることを発見。著「経済進歩の諸条件」など。
→ペティー=クラークの法則
(2)〔Kenneth Mackenzie C.〕
(1903-1983) イギリスの美術史家・評論家。ルネサンス美術の研究から出発し,自由な発想・文明史的視点から多数の美術評論を著す。著「レオナルド=ダ=ビンチ」「風景画論」「ザ-ヌード」など。
(3)〔William Smith C.〕
(1826-1886) アメリカの教育者。1876年(明治9)来日,札幌農学校の教頭となるが一年足らずで帰国。そのキリスト教精神と科学教育は内村鑑三・新渡戸稲造らの人材を育てた。離日に際し学生に言い残した言葉「青年よ大志を抱け(Boys, be ambitious)」は有名。
 Clark
Clark (1)〔Colin Grant C.〕
(1905- ) イギリスの経済学者。産業を第一次から第三次に分類し,産業が高度化するにつれて国民所得の増大がみられることを発見。著「経済進歩の諸条件」など。
→ペティー=クラークの法則
(2)〔Kenneth Mackenzie C.〕
(1903-1983) イギリスの美術史家・評論家。ルネサンス美術の研究から出発し,自由な発想・文明史的視点から多数の美術評論を著す。著「レオナルド=ダ=ビンチ」「風景画論」「ザ-ヌード」など。
(3)〔William Smith C.〕
(1826-1886) アメリカの教育者。1876年(明治9)来日,札幌農学校の教頭となるが一年足らずで帰国。そのキリスト教精神と科学教育は内村鑑三・新渡戸稲造らの人材を育てた。離日に際し学生に言い残した言葉「青年よ大志を抱け(Boys, be ambitious)」は有名。
(1)〔Colin Grant C.〕
(1905- ) イギリスの経済学者。産業を第一次から第三次に分類し,産業が高度化するにつれて国民所得の増大がみられることを発見。著「経済進歩の諸条件」など。
→ペティー=クラークの法則
(2)〔Kenneth Mackenzie C.〕
(1903-1983) イギリスの美術史家・評論家。ルネサンス美術の研究から出発し,自由な発想・文明史的視点から多数の美術評論を著す。著「レオナルド=ダ=ビンチ」「風景画論」「ザ-ヌード」など。
(3)〔William Smith C.〕
(1826-1886) アメリカの教育者。1876年(明治9)来日,札幌農学校の教頭となるが一年足らずで帰国。そのキリスト教精神と科学教育は内村鑑三・新渡戸稲造らの人材を育てた。離日に際し学生に言い残した言葉「青年よ大志を抱け(Boys, be ambitious)」は有名。
クラーク Arthur Charles Clarke
Arthur Charles Clarke 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クラーク  Arthur Charles Clarke
Arthur Charles Clarke (1917- ) イギリスの SF 作家。作品は確かな科学知識に裏付けられた近未来物と,思弁的な作風の超未来物とがあり,ともに人類に対する温かい信頼感を基調とする。著「幼年期の終わり」「都市と星」「2001年宇宙の旅」など。
(1917- ) イギリスの SF 作家。作品は確かな科学知識に裏付けられた近未来物と,思弁的な作風の超未来物とがあり,ともに人類に対する温かい信頼感を基調とする。著「幼年期の終わり」「都市と星」「2001年宇宙の旅」など。
 Arthur Charles Clarke
Arthur Charles Clarke (1917- ) イギリスの SF 作家。作品は確かな科学知識に裏付けられた近未来物と,思弁的な作風の超未来物とがあり,ともに人類に対する温かい信頼感を基調とする。著「幼年期の終わり」「都市と星」「2001年宇宙の旅」など。
(1917- ) イギリスの SF 作家。作品は確かな科学知識に裏付けられた近未来物と,思弁的な作風の超未来物とがあり,ともに人類に対する温かい信頼感を基調とする。著「幼年期の終わり」「都市と星」「2001年宇宙の旅」など。
クラーゲス Ludwig Klages
Ludwig Klages 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クラーゲス  Ludwig Klages
Ludwig Klages (1872-1956) ドイツの哲学者・心理学者。表現についての人間的探究を背景に性格構造論を展開し,性格の精細な体系的分類を行うとともに,独自の筆跡学を樹立した。著「表現学の基礎」など。
(1872-1956) ドイツの哲学者・心理学者。表現についての人間的探究を背景に性格構造論を展開し,性格の精細な体系的分類を行うとともに,独自の筆跡学を樹立した。著「表現学の基礎」など。
 Ludwig Klages
Ludwig Klages (1872-1956) ドイツの哲学者・心理学者。表現についての人間的探究を背景に性格構造論を展開し,性格の精細な体系的分類を行うとともに,独自の筆跡学を樹立した。著「表現学の基礎」など。
(1872-1956) ドイツの哲学者・心理学者。表現についての人間的探究を背景に性格構造論を展開し,性格の精細な体系的分類を行うとともに,独自の筆跡学を樹立した。著「表現学の基礎」など。
くら-あずかり【蔵預かり】🔗⭐🔉
くら-あずかり ―アヅカリ [3] 【蔵預かり】
倉庫に入れてあずかること。また,その番人。
くらあずかり-きって【蔵預かり切手】🔗⭐🔉
くらあずかり-きって ―アヅカリ― [7] 【蔵預かり切手】
江戸時代,各藩が米や砂糖など蔵預かりしていたものに対して振り出した倉荷証券。
クラーテル (ギリシヤ) krat
(ギリシヤ) krat r
r 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クラーテル [2]  (ギリシヤ) krat
(ギリシヤ) krat r
r 〔クラテルとも〕
古代ギリシャの壺の一種。釣り鐘を逆さにした形で二つの取っ手がある。葡萄(ブドウ)酒を水で割るのに用いた。
〔クラテルとも〕
古代ギリシャの壺の一種。釣り鐘を逆さにした形で二つの取っ手がある。葡萄(ブドウ)酒を水で割るのに用いた。
 (ギリシヤ) krat
(ギリシヤ) krat r
r 〔クラテルとも〕
古代ギリシャの壺の一種。釣り鐘を逆さにした形で二つの取っ手がある。葡萄(ブドウ)酒を水で割るのに用いた。
〔クラテルとも〕
古代ギリシャの壺の一種。釣り鐘を逆さにした形で二つの取っ手がある。葡萄(ブドウ)酒を水で割るのに用いた。
クラーレ curare
curare 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クラーレ [2]  curare
curare 南アメリカの先住民が毒矢に用いた,ツヅラフジ科・フジウツギ科などの植物樹皮に含まれるアルカロイドの総称。猛毒物質。主成分のツボクラリンは運動神経末端の神経-筋接合部に作用し,骨格筋の弛緩・麻痺を起こす。薬理学研究や麻酔薬に利用。
南アメリカの先住民が毒矢に用いた,ツヅラフジ科・フジウツギ科などの植物樹皮に含まれるアルカロイドの総称。猛毒物質。主成分のツボクラリンは運動神経末端の神経-筋接合部に作用し,骨格筋の弛緩・麻痺を起こす。薬理学研究や麻酔薬に利用。
 curare
curare 南アメリカの先住民が毒矢に用いた,ツヅラフジ科・フジウツギ科などの植物樹皮に含まれるアルカロイドの総称。猛毒物質。主成分のツボクラリンは運動神経末端の神経-筋接合部に作用し,骨格筋の弛緩・麻痺を起こす。薬理学研究や麻酔薬に利用。
南アメリカの先住民が毒矢に用いた,ツヅラフジ科・フジウツギ科などの植物樹皮に含まれるアルカロイドの総称。猛毒物質。主成分のツボクラリンは運動神経末端の神経-筋接合部に作用し,骨格筋の弛緩・麻痺を起こす。薬理学研究や麻酔薬に利用。
くらい【位】🔗⭐🔉
くらい クラ [0] 【位】
〔「くらい(座居)」の意〕
(1)天皇の地位。また,その地位にあること。皇位。「―を譲る」「―に即(ツ)く」
(2)朝廷・国家から与えられる,身分・等級・称号など。「―を極める」
→位階
(3)ある集団内での地位・身分の上下関係。「棋聖の―」
(4)〔数〕 数をアラビア記数法で表示した一つの桁について,記数法の約束によりその桁に表示された数に乗ずべき数が
[0] 【位】
〔「くらい(座居)」の意〕
(1)天皇の地位。また,その地位にあること。皇位。「―を譲る」「―に即(ツ)く」
(2)朝廷・国家から与えられる,身分・等級・称号など。「―を極める」
→位階
(3)ある集団内での地位・身分の上下関係。「棋聖の―」
(4)〔数〕 数をアラビア記数法で表示した一つの桁について,記数法の約束によりその桁に表示された数に乗ずべき数が  であるとき,その桁を
であるとき,その桁を  の(または
の(または  に対応する命数の)位という。たとえば十進法の整数で下から五桁目は万の位。
(5)作品の品位・風格。「付句の―とはいかなる事にや/去来抄」
(6)芸道上の力量の程度。到達し得た境地。「この―を得たらん上手こそ天下にも許され/風姿花伝」
に対応する命数の)位という。たとえば十進法の整数で下から五桁目は万の位。
(5)作品の品位・風格。「付句の―とはいかなる事にや/去来抄」
(6)芸道上の力量の程度。到達し得た境地。「この―を得たらん上手こそ天下にも許され/風姿花伝」
 [0] 【位】
〔「くらい(座居)」の意〕
(1)天皇の地位。また,その地位にあること。皇位。「―を譲る」「―に即(ツ)く」
(2)朝廷・国家から与えられる,身分・等級・称号など。「―を極める」
→位階
(3)ある集団内での地位・身分の上下関係。「棋聖の―」
(4)〔数〕 数をアラビア記数法で表示した一つの桁について,記数法の約束によりその桁に表示された数に乗ずべき数が
[0] 【位】
〔「くらい(座居)」の意〕
(1)天皇の地位。また,その地位にあること。皇位。「―を譲る」「―に即(ツ)く」
(2)朝廷・国家から与えられる,身分・等級・称号など。「―を極める」
→位階
(3)ある集団内での地位・身分の上下関係。「棋聖の―」
(4)〔数〕 数をアラビア記数法で表示した一つの桁について,記数法の約束によりその桁に表示された数に乗ずべき数が  であるとき,その桁を
であるとき,その桁を  の(または
の(または  に対応する命数の)位という。たとえば十進法の整数で下から五桁目は万の位。
(5)作品の品位・風格。「付句の―とはいかなる事にや/去来抄」
(6)芸道上の力量の程度。到達し得た境地。「この―を得たらん上手こそ天下にも許され/風姿花伝」
に対応する命数の)位という。たとえば十進法の整数で下から五桁目は万の位。
(5)作品の品位・風格。「付句の―とはいかなる事にや/去来抄」
(6)芸道上の力量の程度。到達し得た境地。「この―を得たらん上手こそ天下にも許され/風姿花伝」
くらい-ぎぬ【位衣】🔗⭐🔉
くらい-ぎぬ クラ ― 【位衣】
⇒位袍(イホウ)
― 【位衣】
⇒位袍(イホウ)
 ― 【位衣】
⇒位袍(イホウ)
― 【位衣】
⇒位袍(イホウ)
くらい【食らい】🔗⭐🔉
くらい クラヒ [0] 【食らい】
食うこと。多く複合語として用いる。「大飯―」「ただ飯―」
くら・い【暗い】🔗⭐🔉
くら・い [0] 【暗い】 (形)[文]ク くら・し
〔動詞「暮る」と同源〕
(1)光の量が少なく,物がよく見えない状態である。明るさが足りない。「日が暮れて―・くなる」「―・い夜道」
(2)色がくすんでいる。黒ずんでいる。「―・い紫色」
(3)(性格や気分が)陰気で晴れやかでない。明朗でない。「―・い性格」「気持ちが―・くなる」
(4)犯罪・不幸・悲惨の存在を感じさせる。「―・い過去」「―・い世相」
(5)希望がもてない状態だ。「見通しは―・い」
(6)事情をよく知らない。精通していない。「法律に―・い」「この辺の地理に―・い」
(7)愚かだ。暗愚だ。「―・き人の,人をはかりてその智を知れりと思はん/徒然 193」
(8)不十分である。不足している。「我が韃靼(ダツタン)は大国にて七珍万宝―・からずと申せども/浄瑠璃・国性爺合戦」
⇔あかるい
[派生] ――さ(名)――み(名)
くらい🔗⭐🔉
くらい クラ (副助)
〔名詞「くらい(位)」からの転。中世以後生じたもの。「ぐらい」の形でも用いる〕
体言および活用する語の連体形に付く。
(1)おおよその分量・程度を表す。ほど。ばかり。「一キロ―行くと駅につく」「茶さじ一杯―の塩をいれる」「プロ選手―の実力はある」
(2)ある事柄を示し,その程度が軽いもの,弱いものとして表す。「酒―飲んだっていいよ」「ご飯―たけるよ」
(3)ある事柄を示し,動作・状態の程度を表す。「あんなことを言う―だから,何をするかわからない」「辺り一面真っ暗になる―のどしゃぶり」
(4)比較の基準を表す。「…くらい…はない」の形をとることが多い。「こども―かわいいものはない」「君―勉強ができるといいのだが」
(5)ある事柄を示し,それがひどく悪いもの,嫌うべきものとして表す。「くらいなら」の形をとることが多い。「降参する―なら死んだ方がましだ」
(副助)
〔名詞「くらい(位)」からの転。中世以後生じたもの。「ぐらい」の形でも用いる〕
体言および活用する語の連体形に付く。
(1)おおよその分量・程度を表す。ほど。ばかり。「一キロ―行くと駅につく」「茶さじ一杯―の塩をいれる」「プロ選手―の実力はある」
(2)ある事柄を示し,その程度が軽いもの,弱いものとして表す。「酒―飲んだっていいよ」「ご飯―たけるよ」
(3)ある事柄を示し,動作・状態の程度を表す。「あんなことを言う―だから,何をするかわからない」「辺り一面真っ暗になる―のどしゃぶり」
(4)比較の基準を表す。「…くらい…はない」の形をとることが多い。「こども―かわいいものはない」「君―勉強ができるといいのだが」
(5)ある事柄を示し,それがひどく悪いもの,嫌うべきものとして表す。「くらいなら」の形をとることが多い。「降参する―なら死んだ方がましだ」
 (副助)
〔名詞「くらい(位)」からの転。中世以後生じたもの。「ぐらい」の形でも用いる〕
体言および活用する語の連体形に付く。
(1)おおよその分量・程度を表す。ほど。ばかり。「一キロ―行くと駅につく」「茶さじ一杯―の塩をいれる」「プロ選手―の実力はある」
(2)ある事柄を示し,その程度が軽いもの,弱いものとして表す。「酒―飲んだっていいよ」「ご飯―たけるよ」
(3)ある事柄を示し,動作・状態の程度を表す。「あんなことを言う―だから,何をするかわからない」「辺り一面真っ暗になる―のどしゃぶり」
(4)比較の基準を表す。「…くらい…はない」の形をとることが多い。「こども―かわいいものはない」「君―勉強ができるといいのだが」
(5)ある事柄を示し,それがひどく悪いもの,嫌うべきものとして表す。「くらいなら」の形をとることが多い。「降参する―なら死んだ方がましだ」
(副助)
〔名詞「くらい(位)」からの転。中世以後生じたもの。「ぐらい」の形でも用いる〕
体言および活用する語の連体形に付く。
(1)おおよその分量・程度を表す。ほど。ばかり。「一キロ―行くと駅につく」「茶さじ一杯―の塩をいれる」「プロ選手―の実力はある」
(2)ある事柄を示し,その程度が軽いもの,弱いものとして表す。「酒―飲んだっていいよ」「ご飯―たけるよ」
(3)ある事柄を示し,動作・状態の程度を表す。「あんなことを言う―だから,何をするかわからない」「辺り一面真っ暗になる―のどしゃぶり」
(4)比較の基準を表す。「…くらい…はない」の形をとることが多い。「こども―かわいいものはない」「君―勉強ができるといいのだが」
(5)ある事柄を示し,それがひどく悪いもの,嫌うべきものとして表す。「くらいなら」の形をとることが多い。「降参する―なら死んだ方がましだ」
クライアント client
client 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クライアント [2]  client
client 〔依頼人・顧客の意〕
(1)広告代理店に依頼した広告主。
(2)ケース-ワークで,問題を抱えて訪れた人。来談者。広義には,社会福祉の要援助者全般をいう。
(3)コンピューター-ネットワーク上でサービスを受ける側にあるシステム。サーバー(サービスを提供するシステム)に対していう。
〔依頼人・顧客の意〕
(1)広告代理店に依頼した広告主。
(2)ケース-ワークで,問題を抱えて訪れた人。来談者。広義には,社会福祉の要援助者全般をいう。
(3)コンピューター-ネットワーク上でサービスを受ける側にあるシステム。サーバー(サービスを提供するシステム)に対していう。
 client
client 〔依頼人・顧客の意〕
(1)広告代理店に依頼した広告主。
(2)ケース-ワークで,問題を抱えて訪れた人。来談者。広義には,社会福祉の要援助者全般をいう。
(3)コンピューター-ネットワーク上でサービスを受ける側にあるシステム。サーバー(サービスを提供するシステム)に対していう。
〔依頼人・顧客の意〕
(1)広告代理店に依頼した広告主。
(2)ケース-ワークで,問題を抱えて訪れた人。来談者。広義には,社会福祉の要援助者全般をいう。
(3)コンピューター-ネットワーク上でサービスを受ける側にあるシステム。サーバー(サービスを提供するシステム)に対していう。
クライアント-サーバー-システム client server system
client server system 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クライアント-サーバー-システム [11]  client server system
client server system コンピューターでファイル管理・通信・印刷などのサービスを提供するコンピューター-システム(サーバー)とサービスを受け取る多数のパソコン・ワークステーションなどのシステム(クライアント)から構成され,分散処理を行うシステム。
コンピューターでファイル管理・通信・印刷などのサービスを提供するコンピューター-システム(サーバー)とサービスを受け取る多数のパソコン・ワークステーションなどのシステム(クライアント)から構成され,分散処理を行うシステム。
 client server system
client server system コンピューターでファイル管理・通信・印刷などのサービスを提供するコンピューター-システム(サーバー)とサービスを受け取る多数のパソコン・ワークステーションなどのシステム(クライアント)から構成され,分散処理を行うシステム。
コンピューターでファイル管理・通信・印刷などのサービスを提供するコンピューター-システム(サーバー)とサービスを受け取る多数のパソコン・ワークステーションなどのシステム(クライアント)から構成され,分散処理を行うシステム。
クライエント client
client 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クライエント-ちゅうしんりょうほう【―中心療法】🔗⭐🔉
クライエント-ちゅうしんりょうほう ―レウハフ [11] 【―中心療法】
ロジャーズが創始した心理療法。治療を受ける者自身の成長する力を尊重する立場をとる。来談者中心療法。
くらい-こ・む【食らい込む】🔗⭐🔉
くらい-こ・む クラヒ― [4] 【食らい込む】 (動マ五[四])
(1)捕らえられて,留置場や刑務所に入れられる。「詐欺で一年―・んだ」
(2)やっかいな事をむりやり引き受けさせられる。しょいこむ。「人の借金まで―・む」
くらいし【倉石】🔗⭐🔉
くらいし 【倉石】
姓氏の一。
くらいし-たけしろう【倉石武四郎】🔗⭐🔉
くらいし-たけしろう ―タケシラウ 【倉石武四郎】
(1897-1975) 中国語学者。新潟県生まれ。京大・東大教授。現代中国語の研究に業績を残す。著「中国語五十年」
クライシス crisis
crisis 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クライシス [2]  crisis
crisis (1)危機。
(2)経済上の危機。恐慌。
(1)危機。
(2)経済上の危機。恐慌。
 crisis
crisis (1)危機。
(2)経済上の危機。恐慌。
(1)危機。
(2)経済上の危機。恐慌。
クライシュ Quraysh
Quraysh 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クライシュ  Quraysh
Quraysh イスラム教勃興期,メッカに住んでいたアラブの部族。隊商による商業活動を活発に行なっていた。ムハンマドの出身部族。
イスラム教勃興期,メッカに住んでいたアラブの部族。隊商による商業活動を活発に行なっていた。ムハンマドの出身部族。
 Quraysh
Quraysh イスラム教勃興期,メッカに住んでいたアラブの部族。隊商による商業活動を活発に行なっていた。ムハンマドの出身部族。
イスラム教勃興期,メッカに住んでいたアラブの部族。隊商による商業活動を活発に行なっていた。ムハンマドの出身部族。
くら-いしょう【蔵衣装・蔵衣裳】🔗⭐🔉
くら-いしょう ―イシヤウ [3] 【蔵衣装・蔵衣裳】
(1)江戸時代,歌舞伎で興行主が下級俳優に貸与した衣装。
(2)他人の衣装を借りて着ること。また,その衣装。
クライスト Heinrich von Kleist
Heinrich von Kleist 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クライスト  Heinrich von Kleist
Heinrich von Kleist (1777-1811) ドイツの劇作家・小説家。異常な性格や恋愛心理を写実的に描き,近代写実主義の先駆をなした。戯曲「こわれ甕(ガメ)」「公子ホンブルク」,小説「ミヒャエル=コールハース」など。
(1777-1811) ドイツの劇作家・小説家。異常な性格や恋愛心理を写実的に描き,近代写実主義の先駆をなした。戯曲「こわれ甕(ガメ)」「公子ホンブルク」,小説「ミヒャエル=コールハース」など。
 Heinrich von Kleist
Heinrich von Kleist (1777-1811) ドイツの劇作家・小説家。異常な性格や恋愛心理を写実的に描き,近代写実主義の先駆をなした。戯曲「こわれ甕(ガメ)」「公子ホンブルク」,小説「ミヒャエル=コールハース」など。
(1777-1811) ドイツの劇作家・小説家。異常な性格や恋愛心理を写実的に描き,近代写実主義の先駆をなした。戯曲「こわれ甕(ガメ)」「公子ホンブルク」,小説「ミヒャエル=コールハース」など。
クライストチャーチ Christchurch
Christchurch 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クライストチャーチ  Christchurch
Christchurch ニュージーランド,南島(サウスアイランド)の北東部の都市。羊毛・羊肉などの集散が盛ん。外港はリトルトン。
クライストチャーチ(大聖堂前)
ニュージーランド,南島(サウスアイランド)の北東部の都市。羊毛・羊肉などの集散が盛ん。外港はリトルトン。
クライストチャーチ(大聖堂前)
 [カラー図版]
クライストチャーチ(キャプテンスコット像)
[カラー図版]
クライストチャーチ(キャプテンスコット像)
 [カラー図版]
[カラー図版]
 Christchurch
Christchurch ニュージーランド,南島(サウスアイランド)の北東部の都市。羊毛・羊肉などの集散が盛ん。外港はリトルトン。
クライストチャーチ(大聖堂前)
ニュージーランド,南島(サウスアイランド)の北東部の都市。羊毛・羊肉などの集散が盛ん。外港はリトルトン。
クライストチャーチ(大聖堂前)
 [カラー図版]
クライストチャーチ(キャプテンスコット像)
[カラー図版]
クライストチャーチ(キャプテンスコット像)
 [カラー図版]
[カラー図版]
くらい【位】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「クラ」で始まるの検索結果。もっと読み込む