複数辞典一括検索+![]()
![]()
児 こ🔗⭐🔉
【児】
 7画 儿部 [四年]
区点=2789 16進=3B79 シフトJIS=8E99
【兒】旧字人名に使える旧字
7画 儿部 [四年]
区点=2789 16進=3B79 シフトJIS=8E99
【兒】旧字人名に使える旧字
 8画 儿部
区点=4927 16進=513B シフトJIS=995A
《常用音訓》ジ/ニ
《音読み》
8画 儿部
区点=4927 16進=513B シフトJIS=995A
《常用音訓》ジ/ニ
《音読み》  ジ
ジ /ニ
/ニ 〈
〈 r〉/
r〉/ ゲイ
ゲイ /ゲ
/ゲ 〈n
〈n 〉
《訓読み》 こ
《名付け》 こ・ちご・のり・はじめ・る
《意味》
〉
《訓読み》 こ
《名付け》 こ・ちご・のり・はじめ・る
《意味》

 {名}こ。幼い子ども。〈類義語〉→孩ガイ・→子。「児童」「小児」
{名}こ。幼い子ども。〈類義語〉→孩ガイ・→子。「児童」「小児」
 {名}親が自分の子を呼ぶときのことば。
{名}親が自分の子を呼ぶときのことば。
 {名}子が親に対して自分のことをいうときのことば。「児已薄禄相=児スデニ禄相薄シ」〔古楽府〕「送児還故郷=児ヲ送リテ故郷ニ還ラシメヨ」〔古楽府〕
{名}子が親に対して自分のことをいうときのことば。「児已薄禄相=児スデニ禄相薄シ」〔古楽府〕「送児還故郷=児ヲ送リテ故郷ニ還ラシメヨ」〔古楽府〕
 {名}少年や小姓コショウ。「発沛中児得百二十人=沛中ノ児ヲ発シテ百二十人ヲ得タリ」〔→史記〕
{名}少年や小姓コショウ。「発沛中児得百二十人=沛中ノ児ヲ発シテ百二十人ヲ得タリ」〔→史記〕
 {名}若者。「健児」「愁殺楼蘭征戍児=愁殺ス楼蘭征戍ノ児」〔→岑参〕
{名}若者。「健児」「愁殺楼蘭征戍児=愁殺ス楼蘭征戍ノ児」〔→岑参〕
 {助}〔俗〕小さな物、かわいい物につける接尾辞。「鴬児インル(うぐいす)」「花児ホアル」
{助}〔俗〕小さな物、かわいい物につける接尾辞。「鴬児インル(うぐいす)」「花児ホアル」
 {名}姓の一つ。〈同義語〉→倪ゲイ。
《解字》
{名}姓の一つ。〈同義語〉→倪ゲイ。
《解字》
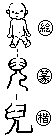 象形。上部に頭蓋ズガイの上部がまだあわさらない幼児の頭を描き、下に人体の形を添えたもの。兒ゲイは、小さく細かいの意を含み、睨ゲイ(目を細めてにらむ)
象形。上部に頭蓋ズガイの上部がまだあわさらない幼児の頭を描き、下に人体の形を添えたもの。兒ゲイは、小さく細かいの意を含み、睨ゲイ(目を細めてにらむ) 倪ゲイ(小さい子ども)
倪ゲイ(小さい子ども) 霓ゲイ(細いにじ)などに音符として含まれる。▽「説文解字」に「孺子ジュシ(おさなご)なり」とある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
霓ゲイ(細いにじ)などに音符として含まれる。▽「説文解字」に「孺子ジュシ(おさなご)なり」とある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 儿部 [四年]
区点=2789 16進=3B79 シフトJIS=8E99
【兒】旧字人名に使える旧字
7画 儿部 [四年]
区点=2789 16進=3B79 シフトJIS=8E99
【兒】旧字人名に使える旧字
 8画 儿部
区点=4927 16進=513B シフトJIS=995A
《常用音訓》ジ/ニ
《音読み》
8画 儿部
区点=4927 16進=513B シフトJIS=995A
《常用音訓》ジ/ニ
《音読み》  ジ
ジ /ニ
/ニ 〈
〈 r〉/
r〉/ ゲイ
ゲイ /ゲ
/ゲ 〈n
〈n 〉
《訓読み》 こ
《名付け》 こ・ちご・のり・はじめ・る
《意味》
〉
《訓読み》 こ
《名付け》 こ・ちご・のり・はじめ・る
《意味》

 {名}こ。幼い子ども。〈類義語〉→孩ガイ・→子。「児童」「小児」
{名}こ。幼い子ども。〈類義語〉→孩ガイ・→子。「児童」「小児」
 {名}親が自分の子を呼ぶときのことば。
{名}親が自分の子を呼ぶときのことば。
 {名}子が親に対して自分のことをいうときのことば。「児已薄禄相=児スデニ禄相薄シ」〔古楽府〕「送児還故郷=児ヲ送リテ故郷ニ還ラシメヨ」〔古楽府〕
{名}子が親に対して自分のことをいうときのことば。「児已薄禄相=児スデニ禄相薄シ」〔古楽府〕「送児還故郷=児ヲ送リテ故郷ニ還ラシメヨ」〔古楽府〕
 {名}少年や小姓コショウ。「発沛中児得百二十人=沛中ノ児ヲ発シテ百二十人ヲ得タリ」〔→史記〕
{名}少年や小姓コショウ。「発沛中児得百二十人=沛中ノ児ヲ発シテ百二十人ヲ得タリ」〔→史記〕
 {名}若者。「健児」「愁殺楼蘭征戍児=愁殺ス楼蘭征戍ノ児」〔→岑参〕
{名}若者。「健児」「愁殺楼蘭征戍児=愁殺ス楼蘭征戍ノ児」〔→岑参〕
 {助}〔俗〕小さな物、かわいい物につける接尾辞。「鴬児インル(うぐいす)」「花児ホアル」
{助}〔俗〕小さな物、かわいい物につける接尾辞。「鴬児インル(うぐいす)」「花児ホアル」
 {名}姓の一つ。〈同義語〉→倪ゲイ。
《解字》
{名}姓の一つ。〈同義語〉→倪ゲイ。
《解字》
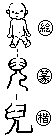 象形。上部に頭蓋ズガイの上部がまだあわさらない幼児の頭を描き、下に人体の形を添えたもの。兒ゲイは、小さく細かいの意を含み、睨ゲイ(目を細めてにらむ)
象形。上部に頭蓋ズガイの上部がまだあわさらない幼児の頭を描き、下に人体の形を添えたもの。兒ゲイは、小さく細かいの意を含み、睨ゲイ(目を細めてにらむ) 倪ゲイ(小さい子ども)
倪ゲイ(小さい子ども) 霓ゲイ(細いにじ)などに音符として含まれる。▽「説文解字」に「孺子ジュシ(おさなご)なり」とある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
霓ゲイ(細いにじ)などに音符として含まれる。▽「説文解字」に「孺子ジュシ(おさなご)なり」とある。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
子 こ🔗⭐🔉
【子】
 3画 子部 [一年]
区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71
《常用音訓》シ/ス/こ
《音読み》 シ
3画 子部 [一年]
区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71
《常用音訓》シ/ス/こ
《音読み》 シ
 /ス
/ス 〈z
〈z ・zi〉
《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね
《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす
《意味》
・zi〉
《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね
《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす
《意味》
 {名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕
{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕
 {名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」
{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」
 {名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕
{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕
 {名}…をする者。ひと。「読書子」
{名}…をする者。ひと。「読書子」
 {名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」
{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」
 {名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部
{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部
 {名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」
{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」
 {動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕
{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕
 {動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕
{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕
 {名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」
{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」
 {名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。
{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。
 {名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。
{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。
 {助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」
{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」
 {動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。
{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。
 {動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。
《解字》
{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。
《解字》
 象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。
《単語家族》
絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる)
象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。
《単語家族》
絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる) 字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 3画 子部 [一年]
区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71
《常用音訓》シ/ス/こ
《音読み》 シ
3画 子部 [一年]
区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71
《常用音訓》シ/ス/こ
《音読み》 シ
 /ス
/ス 〈z
〈z ・zi〉
《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね
《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす
《意味》
・zi〉
《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね
《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす
《意味》
 {名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕
{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕
 {名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」
{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」
 {名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕
{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕
 {名}…をする者。ひと。「読書子」
{名}…をする者。ひと。「読書子」
 {名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」
{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」
 {名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部
{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部
 {名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」
{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」
 {動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕
{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕
 {動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕
{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕
 {名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」
{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」
 {名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。
{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。
 {名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。
{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。
 {助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」
{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」
 {動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。
{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。
 {動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。
《解字》
{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。
《解字》
 象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。
《単語家族》
絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる)
象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。
《単語家族》
絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる) 字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
小 こ🔗⭐🔉
【小】
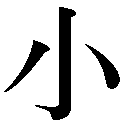 3画 小部 [一年]
区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC
《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい
《音読み》 ショウ(セウ)
3画 小部 [一年]
区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC
《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ
《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ
《意味》
o〉
《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ
《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ
《意味》
 ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕
ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕
 ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕
ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕
 {名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」
{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」
 {形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」
{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」
 {副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕
{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕
 {名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕
〔国〕
{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕
〔国〕 お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」
お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」 こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」
《解字》
こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」
《解字》
 象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。
《単語家族》
消(火をちいさくする)
象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。
《単語家族》
消(火をちいさくする) 宵(日光がちいさくなる夕方)
宵(日光がちいさくなる夕方) 肖(肉づきをちいさく削る)
肖(肉づきをちいさく削る) 削サク(ちいさくけずる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
削サク(ちいさくけずる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
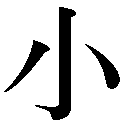 3画 小部 [一年]
区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC
《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい
《音読み》 ショウ(セウ)
3画 小部 [一年]
区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC
《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ
《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ
《意味》
o〉
《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ
《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ
《意味》
 ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕
ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕
 ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕
ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕
 {名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」
{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」
 {形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」
{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」
 {副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕
{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕
 {名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕
〔国〕
{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕
〔国〕 お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」
お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」 こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」
《解字》
こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」
《解字》
 象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。
《単語家族》
消(火をちいさくする)
象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。
《単語家族》
消(火をちいさくする) 宵(日光がちいさくなる夕方)
宵(日光がちいさくなる夕方) 肖(肉づきをちいさく削る)
肖(肉づきをちいさく削る) 削サク(ちいさくけずる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
削サク(ちいさくけずる)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
木 こ🔗⭐🔉
【木】
 4画 木部 [一年]
区点=4458 16進=4C5A シフトJIS=96D8
《常用音訓》ボク/モク/き/こ
《音読み》 ボク
4画 木部 [一年]
区点=4458 16進=4C5A シフトJIS=96D8
《常用音訓》ボク/モク/き/こ
《音読み》 ボク /モク
/モク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 こ/き/もく
《名付け》 き・こ・しげ
《意味》
〉
《訓読み》 こ/き/もく
《名付け》 き・こ・しげ
《意味》
 {名}き。葉や花をかぶったたちき。また広く、たちき。〈類義語〉→樹。「樹木」
{名}き。葉や花をかぶったたちき。また広く、たちき。〈類義語〉→樹。「樹木」
 {名}き。物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。「材木」「三木サンボク(手かせ・足かせ・首かせの三つ)」「就木=木ニ就ク」「朽木不可雕也=朽チタル木ハ雕ルベカラザルナリ」〔→論語〕
{名}き。物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。「材木」「三木サンボク(手かせ・足かせ・首かせの三つ)」「就木=木ニ就ク」「朽木不可雕也=朽チタル木ハ雕ルベカラザルナリ」〔→論語〕
 {名}五行の一つ。方角では東、色では青、時節では春、十干では甲と乙、五音では角に当てる。
{名}五行の一つ。方角では東、色では青、時節では春、十干では甲と乙、五音では角に当てる。
 {名}八音(八種の楽器)の一つ。木製のもの。
{名}八音(八種の楽器)の一つ。木製のもの。
 {名}星の名。木星。歳星。
{名}星の名。木星。歳星。
 {名・形}生き生きした感覚がない。また、そのもの。「木石」
{名・形}生き生きした感覚がない。また、そのもの。「木石」
 {形}かざりけがない。質朴シツボク。〈同義語〉→朴・→樸。「木訥ボクトツ」
〔国〕もく。七曜の一つ。「木曜日」の略。
《解字》
{形}かざりけがない。質朴シツボク。〈同義語〉→朴・→樸。「木訥ボクトツ」
〔国〕もく。七曜の一つ。「木曜日」の略。
《解字》
 象形。立ち木の形を描いたもの。上に葉や花をかぶった木。
《単語家族》
沐モク(頭から水をかぶる)と同系。
《類義》
樹は、じっとたっている木。材は、切りたおして物をつくるのに使う木。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
象形。立ち木の形を描いたもの。上に葉や花をかぶった木。
《単語家族》
沐モク(頭から水をかぶる)と同系。
《類義》
樹は、じっとたっている木。材は、切りたおして物をつくるのに使う木。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 4画 木部 [一年]
区点=4458 16進=4C5A シフトJIS=96D8
《常用音訓》ボク/モク/き/こ
《音読み》 ボク
4画 木部 [一年]
区点=4458 16進=4C5A シフトJIS=96D8
《常用音訓》ボク/モク/き/こ
《音読み》 ボク /モク
/モク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 こ/き/もく
《名付け》 き・こ・しげ
《意味》
〉
《訓読み》 こ/き/もく
《名付け》 き・こ・しげ
《意味》
 {名}き。葉や花をかぶったたちき。また広く、たちき。〈類義語〉→樹。「樹木」
{名}き。葉や花をかぶったたちき。また広く、たちき。〈類義語〉→樹。「樹木」
 {名}き。物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。「材木」「三木サンボク(手かせ・足かせ・首かせの三つ)」「就木=木ニ就ク」「朽木不可雕也=朽チタル木ハ雕ルベカラザルナリ」〔→論語〕
{名}き。物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。「材木」「三木サンボク(手かせ・足かせ・首かせの三つ)」「就木=木ニ就ク」「朽木不可雕也=朽チタル木ハ雕ルベカラザルナリ」〔→論語〕
 {名}五行の一つ。方角では東、色では青、時節では春、十干では甲と乙、五音では角に当てる。
{名}五行の一つ。方角では東、色では青、時節では春、十干では甲と乙、五音では角に当てる。
 {名}八音(八種の楽器)の一つ。木製のもの。
{名}八音(八種の楽器)の一つ。木製のもの。
 {名}星の名。木星。歳星。
{名}星の名。木星。歳星。
 {名・形}生き生きした感覚がない。また、そのもの。「木石」
{名・形}生き生きした感覚がない。また、そのもの。「木石」
 {形}かざりけがない。質朴シツボク。〈同義語〉→朴・→樸。「木訥ボクトツ」
〔国〕もく。七曜の一つ。「木曜日」の略。
《解字》
{形}かざりけがない。質朴シツボク。〈同義語〉→朴・→樸。「木訥ボクトツ」
〔国〕もく。七曜の一つ。「木曜日」の略。
《解字》
 象形。立ち木の形を描いたもの。上に葉や花をかぶった木。
《単語家族》
沐モク(頭から水をかぶる)と同系。
《類義》
樹は、じっとたっている木。材は、切りたおして物をつくるのに使う木。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
象形。立ち木の形を描いたもの。上に葉や花をかぶった木。
《単語家族》
沐モク(頭から水をかぶる)と同系。
《類義》
樹は、じっとたっている木。材は、切りたおして物をつくるのに使う木。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
粉 こ🔗⭐🔉
【粉】
 10画 米部 [四年]
区点=4220 16進=4A34 シフトJIS=95B2
《常用音訓》フン/こ/こな
《音読み》 フン
10画 米部 [四年]
区点=4220 16進=4A34 シフトJIS=95B2
《常用音訓》フン/こ/こな
《音読み》 フン
 〈f
〈f n〉
《訓読み》 こな/こ/こなにする(こなにす)
《意味》
n〉
《訓読み》 こな/こ/こなにする(こなにす)
《意味》
 {名}こな。こ。穀物をくだいたこな。「米粉」
{名}こな。こ。穀物をくだいたこな。「米粉」
 {動}こなにする(コナニス)。小さくくだいてこなにする。また、くだいてこなごなにする。「粉骨砕身」
{動}こなにする(コナニス)。小さくくだいてこなにする。また、くだいてこなごなにする。「粉骨砕身」
 {名}こなのおしろい。また、こなのおしろいのように白い色。▽古くは米のこなを用い、のち、鉛粉が多く用いられた。「粉黛フンタイ」「脂粉」
《解字》
会意兼形声。「米+音符分フン」。
《単語家族》
分(わける)
{名}こなのおしろい。また、こなのおしろいのように白い色。▽古くは米のこなを用い、のち、鉛粉が多く用いられた。「粉黛フンタイ」「脂粉」
《解字》
会意兼形声。「米+音符分フン」。
《単語家族》
分(わける) 貧(財産が分散した状態)
貧(財産が分散した状態) 頒(広くちらばる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
頒(広くちらばる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 米部 [四年]
区点=4220 16進=4A34 シフトJIS=95B2
《常用音訓》フン/こ/こな
《音読み》 フン
10画 米部 [四年]
区点=4220 16進=4A34 シフトJIS=95B2
《常用音訓》フン/こ/こな
《音読み》 フン
 〈f
〈f n〉
《訓読み》 こな/こ/こなにする(こなにす)
《意味》
n〉
《訓読み》 こな/こ/こなにする(こなにす)
《意味》
 {名}こな。こ。穀物をくだいたこな。「米粉」
{名}こな。こ。穀物をくだいたこな。「米粉」
 {動}こなにする(コナニス)。小さくくだいてこなにする。また、くだいてこなごなにする。「粉骨砕身」
{動}こなにする(コナニス)。小さくくだいてこなにする。また、くだいてこなごなにする。「粉骨砕身」
 {名}こなのおしろい。また、こなのおしろいのように白い色。▽古くは米のこなを用い、のち、鉛粉が多く用いられた。「粉黛フンタイ」「脂粉」
《解字》
会意兼形声。「米+音符分フン」。
《単語家族》
分(わける)
{名}こなのおしろい。また、こなのおしろいのように白い色。▽古くは米のこなを用い、のち、鉛粉が多く用いられた。「粉黛フンタイ」「脂粉」
《解字》
会意兼形声。「米+音符分フン」。
《単語家族》
分(わける) 貧(財産が分散した状態)
貧(財産が分散した状態) 頒(広くちらばる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
頒(広くちらばる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
黄 こ🔗⭐🔉
【黄】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 11画 黄部 [二年]
区点=1811 16進=322B シフトJIS=89A9
《常用音訓》オウ/コウ/き/こ
《音読み》 コウ(ク
11画 黄部 [二年]
区点=1811 16進=322B シフトJIS=89A9
《常用音訓》オウ/コウ/き/こ
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 こ/き/きばむ
《名付け》 かつみ・き
《意味》
ng〉
《訓読み》 こ/き/きばむ
《名付け》 かつみ・き
《意味》
 {名・形}き。きいろ。きいろい。五色(青・黄・赤・白・黒)の一つ。▽五方では、中央、五行では土の色に当たる。地上の支配者、皇帝の色。高貴な色とされる。「緑衣黄裏=緑ノ衣ニ黄ナル裏」〔→詩経〕
{名・形}き。きいろ。きいろい。五色(青・黄・赤・白・黒)の一つ。▽五方では、中央、五行では土の色に当たる。地上の支配者、皇帝の色。高貴な色とされる。「緑衣黄裏=緑ノ衣ニ黄ナル裏」〔→詩経〕
 {動}きばむ。きいろになる。「草木黄落=草木ハ黄バミ落ツ」〔→礼記〕
{動}きばむ。きいろになる。「草木黄落=草木ハ黄バミ落ツ」〔→礼記〕
 {名}唐代の戸籍で三歳以下の子どもをいった。▽口ばしがきいろい、ひなの意から。「黄口」
{名}唐代の戸籍で三歳以下の子どもをいった。▽口ばしがきいろい、ひなの意から。「黄口」
 {名}きいろになった麦。「青黄(青い稲と黄ばんだ麦)」
《解字》
{名}きいろになった麦。「青黄(青い稲と黄ばんだ麦)」
《解字》
 象形。火矢の形を描いたもの。上は「廿+火」(=光)の略体、下は、中央にふくらみのある矢の形で、油をしみこませ、火をつけて飛ばす火矢。火矢のきいろい光をあらわす。
《単語家族》
光(ひろがるひかり)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
象形。火矢の形を描いたもの。上は「廿+火」(=光)の略体、下は、中央にふくらみのある矢の形で、油をしみこませ、火をつけて飛ばす火矢。火矢のきいろい光をあらわす。
《単語家族》
光(ひろがるひかり)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
 11画 黄部 [二年]
区点=1811 16進=322B シフトJIS=89A9
《常用音訓》オウ/コウ/き/こ
《音読み》 コウ(ク
11画 黄部 [二年]
区点=1811 16進=322B シフトJIS=89A9
《常用音訓》オウ/コウ/き/こ
《音読み》 コウ(ク ウ)
ウ) /オウ(ワウ)
/オウ(ワウ) 〈hu
〈hu ng〉
《訓読み》 こ/き/きばむ
《名付け》 かつみ・き
《意味》
ng〉
《訓読み》 こ/き/きばむ
《名付け》 かつみ・き
《意味》
 {名・形}き。きいろ。きいろい。五色(青・黄・赤・白・黒)の一つ。▽五方では、中央、五行では土の色に当たる。地上の支配者、皇帝の色。高貴な色とされる。「緑衣黄裏=緑ノ衣ニ黄ナル裏」〔→詩経〕
{名・形}き。きいろ。きいろい。五色(青・黄・赤・白・黒)の一つ。▽五方では、中央、五行では土の色に当たる。地上の支配者、皇帝の色。高貴な色とされる。「緑衣黄裏=緑ノ衣ニ黄ナル裏」〔→詩経〕
 {動}きばむ。きいろになる。「草木黄落=草木ハ黄バミ落ツ」〔→礼記〕
{動}きばむ。きいろになる。「草木黄落=草木ハ黄バミ落ツ」〔→礼記〕
 {名}唐代の戸籍で三歳以下の子どもをいった。▽口ばしがきいろい、ひなの意から。「黄口」
{名}唐代の戸籍で三歳以下の子どもをいった。▽口ばしがきいろい、ひなの意から。「黄口」
 {名}きいろになった麦。「青黄(青い稲と黄ばんだ麦)」
《解字》
{名}きいろになった麦。「青黄(青い稲と黄ばんだ麦)」
《解字》
 象形。火矢の形を描いたもの。上は「廿+火」(=光)の略体、下は、中央にふくらみのある矢の形で、油をしみこませ、火をつけて飛ばす火矢。火矢のきいろい光をあらわす。
《単語家族》
光(ひろがるひかり)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
象形。火矢の形を描いたもの。上は「廿+火」(=光)の略体、下は、中央にふくらみのある矢の形で、油をしみこませ、火をつけて飛ばす火矢。火矢のきいろい光をあらわす。
《単語家族》
光(ひろがるひかり)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
漢字源に「こ」で完全一致するの検索結果 1-6。