複数辞典一括検索+![]()
![]()
目 ま🔗⭐🔉
【目】
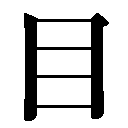 5画 目部 [一年]
区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA
《常用音訓》ボク/モク/ま/め
《音読み》 モク
5画 目部 [一年]
区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA
《常用音訓》ボク/モク/ま/め
《音読み》 モク /ボク
/ボク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)
《名付け》 ま・み・め・より
《意味》
〉
《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)
《名付け》 ま・み・め・より
《意味》
 {名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕
{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕
 {名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」
{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」
 モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕
モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕
 {名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕
{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕
 {名}め。網や、格子のめ。
{名}め。網や、格子のめ。
 {単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」
{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」
 {名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」
{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」
 {名}人の主となる者。かしら。「頭目」
〔国〕
{名}人の主となる者。かしら。「頭目」
〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。
さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」
め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」
め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」
碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」
《解字》
め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」
《解字》
 象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。
《単語家族》
モクとは木(葉をかぶった立ちき)
象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。
《単語家族》
モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)
沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。
《類義》
眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。
《類義》
眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
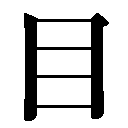 5画 目部 [一年]
区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA
《常用音訓》ボク/モク/ま/め
《音読み》 モク
5画 目部 [一年]
区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA
《常用音訓》ボク/モク/ま/め
《音読み》 モク /ボク
/ボク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)
《名付け》 ま・み・め・より
《意味》
〉
《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)
《名付け》 ま・み・め・より
《意味》
 {名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕
{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕
 {名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」
{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」
 モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕
モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕
 {名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕
{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕
 {名}め。網や、格子のめ。
{名}め。網や、格子のめ。
 {単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」
{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」
 {名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」
{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」
 {名}人の主となる者。かしら。「頭目」
〔国〕
{名}人の主となる者。かしら。「頭目」
〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。
さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」
め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」
め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」
碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」
《解字》
め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」
《解字》
 象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。
《単語家族》
モクとは木(葉をかぶった立ちき)
象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。
《単語家族》
モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)
沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。
《類義》
眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。
《類義》
眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
真 ま🔗⭐🔉
【真】
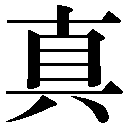 10画 目部 [三年]
区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E
【眞】旧字人名に使える旧字
10画 目部 [三年]
区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E
【眞】旧字人名に使える旧字
 10画 目部
区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1
《常用音訓》シン/ま
《音読み》 シン
10画 目部
区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1
《常用音訓》シン/ま
《音読み》 シン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 まこと/まことに/ま
《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み
《意味》
n〉
《訓読み》 まこと/まことに/ま
《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み
《意味》
 シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕
シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕
 {名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」
{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」
 {名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」
{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」
 {名}楷書カイショのこと。「真書」
{名}楷書カイショのこと。「真書」
 シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」
〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。
《解字》
シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」
〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。
《解字》
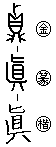 会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。
《類義》
→信
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。
《類義》
→信
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
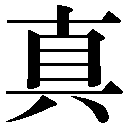 10画 目部 [三年]
区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E
【眞】旧字人名に使える旧字
10画 目部 [三年]
区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E
【眞】旧字人名に使える旧字
 10画 目部
区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1
《常用音訓》シン/ま
《音読み》 シン
10画 目部
区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1
《常用音訓》シン/ま
《音読み》 シン
 〈zh
〈zh n〉
《訓読み》 まこと/まことに/ま
《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み
《意味》
n〉
《訓読み》 まこと/まことに/ま
《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み
《意味》
 シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕
シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕
 {名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」
{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」
 {名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」
{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」
 {名}楷書カイショのこと。「真書」
{名}楷書カイショのこと。「真書」
 シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」
〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。
《解字》
シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」
〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。
《解字》
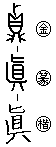 会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。
《類義》
→信
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。
《類義》
→信
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
間 ま🔗⭐🔉
【間】
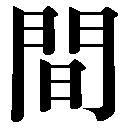 12画 門部 [二年]
区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4
《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま
《音読み》 カン
12画 門部 [二年]
区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4
《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま
《音読み》 カン /ケン
/ケン 〈ji
〈ji n・ji
n・ji n〉
《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)
《名付け》 ちか・はし・ま
《意味》
n〉
《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)
《名付け》 ちか・はし・ま
《意味》
 {名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」
{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」
 {名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」
{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」
 {名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕
{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕
 {名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕
{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕
 {副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。
{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。
 {単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕
{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕
 {名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。
{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。
 {名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕
{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕
 {名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕
{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕
 {名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。
{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。
 {動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」
{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」
 {形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」
{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」
 {動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」
{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」
 カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕
カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕
 カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕
(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」
(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕
〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。
《解字》
会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。
《単語家族》
簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)
カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕
(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」
(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕
〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。
《解字》
会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。
《単語家族》
簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)
柬(よりわける) 界(区切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
界(区切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
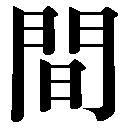 12画 門部 [二年]
区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4
《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま
《音読み》 カン
12画 門部 [二年]
区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4
《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま
《音読み》 カン /ケン
/ケン 〈ji
〈ji n・ji
n・ji n〉
《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)
《名付け》 ちか・はし・ま
《意味》
n〉
《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)
《名付け》 ちか・はし・ま
《意味》
 {名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」
{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」
 {名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」
{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」
 {名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕
{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕
 {名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕
{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕
 {副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。
{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。
 {単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕
{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕
 {名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。
{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。
 {名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕
{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕
 {名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕
{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕
 {名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。
{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。
 {動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」
{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」
 {形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」
{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」
 {動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」
{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」
 カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕
カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕
 カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕
(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」
(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕
〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。
《解字》
会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。
《単語家族》
簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)
カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕
(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」
(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕
〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。
《解字》
会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。
《単語家族》
簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)
柬(よりわける) 界(区切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
界(区切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
馬 ま🔗⭐🔉
【馬】
 10画 馬部 [二年]
区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E
《常用音訓》バ/うま/ま
《音読み》 バ
10画 馬部 [二年]
区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E
《常用音訓》バ/うま/ま
《音読み》 バ /メ
/メ /マ
/マ 〈m
〈m 〉
《訓読み》 ま/うま
《名付け》 うま・たけし・ま・むま
《意味》
{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」
《解字》
〉
《訓読み》 ま/うま
《名付け》 うま・たけし・ま・むま
《意味》
{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」
《解字》
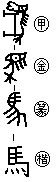 象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。
《単語家族》
武(危険をおかし、何かを求めて進む)
象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。
《単語家族》
武(危険をおかし、何かを求めて進む) 驀バク(あたりかまわず進む)
驀バク(あたりかまわず進む) 罵バ(相手かまわずののしる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
罵バ(相手かまわずののしる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 10画 馬部 [二年]
区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E
《常用音訓》バ/うま/ま
《音読み》 バ
10画 馬部 [二年]
区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E
《常用音訓》バ/うま/ま
《音読み》 バ /メ
/メ /マ
/マ 〈m
〈m 〉
《訓読み》 ま/うま
《名付け》 うま・たけし・ま・むま
《意味》
{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」
《解字》
〉
《訓読み》 ま/うま
《名付け》 うま・たけし・ま・むま
《意味》
{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」
《解字》
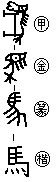 象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。
《単語家族》
武(危険をおかし、何かを求めて進む)
象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。
《単語家族》
武(危険をおかし、何かを求めて進む) 驀バク(あたりかまわず進む)
驀バク(あたりかまわず進む) 罵バ(相手かまわずののしる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
罵バ(相手かまわずののしる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
墹 ま🔗⭐🔉
【墹】
 15画 土部 〔国〕
区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF
《訓読み》 ま/まま
《意味》
ま。まま。地名に使われる。
15画 土部 〔国〕
区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF
《訓読み》 ま/まま
《意味》
ま。まま。地名に使われる。
 15画 土部 〔国〕
区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF
《訓読み》 ま/まま
《意味》
ま。まま。地名に使われる。
15画 土部 〔国〕
区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF
《訓読み》 ま/まま
《意味》
ま。まま。地名に使われる。
漢字源に「ま」で完全一致するの検索結果 1-5。