複数辞典一括検索+![]()
![]()
亜流 アリュウ🔗⭐🔉
【亜流】
アリュウ  その流派に属する人。
その流派に属する人。 すぐれた人に追随し、そのまねをするが、劣っていること。また、そのような人。エピゴーネン。
すぐれた人に追随し、そのまねをするが、劣っていること。また、そのような人。エピゴーネン。
 その流派に属する人。
その流派に属する人。 すぐれた人に追随し、そのまねをするが、劣っていること。また、そのような人。エピゴーネン。
すぐれた人に追随し、そのまねをするが、劣っていること。また、そのような人。エピゴーネン。
在 ありて🔗⭐🔉
【在】
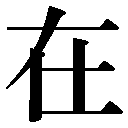 6画 土部 [五年]
区点=2663 16進=3A5F シフトJIS=8DDD
《常用音訓》ザイ/あ…る
《音読み》 ザイ
6画 土部 [五年]
区点=2663 16進=3A5F シフトJIS=8DDD
《常用音訓》ザイ/あ…る
《音読み》 ザイ /サイ
/サイ 〈z
〈z i〉
《訓読み》 ある(あり)/います/ありては/ありて/ざい
《名付け》 あき・あきら・あり・すみ・とお・とみ・まき・みつる
《意味》
i〉
《訓読み》 ある(あり)/います/ありては/ありて/ざい
《名付け》 あき・あきら・あり・すみ・とお・とみ・まき・みつる
《意味》
 {動}ある(アリ)じっとそこにとまっている。「在中」「心不在焉、視而不見=心ココニ在ラズンバ、視レドモ見エズ」〔→大学〕
{動}ある(アリ)じっとそこにとまっている。「在中」「心不在焉、視而不見=心ココニ在ラズンバ、視レドモ見エズ」〔→大学〕
 {動}ある(アリ)。います。生きている。この世にいる。「在世」「父在観其志=父在セバソノ志ヲ観ル」〔→論語〕
{動}ある(アリ)。います。生きている。この世にいる。「在世」「父在観其志=父在セバソノ志ヲ観ル」〔→論語〕
 {名}物のある場所。いる場所。▽去声に読む。「行在」
{名}物のある場所。いる場所。▽去声に読む。「行在」
 {動}ありては。…においては。〈類義語〉→於。「在他人則誅之=他人ニ在リテハスナハチコレヲ誅ス」〔→孟子〕
{動}ありては。…においては。〈類義語〉→於。「在他人則誅之=他人ニ在リテハスナハチコレヲ誅ス」〔→孟子〕
 {前}ありて。場所を示す前置詞。〈類義語〉→於。「豆在釜中泣=豆ハ釜中ニ在リテ泣ク」〔→曹植〕
{前}ありて。場所を示す前置詞。〈類義語〉→於。「豆在釜中泣=豆ハ釜中ニ在リテ泣ク」〔→曹植〕
 「在視ザイシ」「在察ザイサツ」とは、じっと目をとめてよく見ること。
〔国〕ざい。いなか。「千葉の在」「在所」
《解字》
「在視ザイシ」「在察ザイサツ」とは、じっと目をとめてよく見ること。
〔国〕ざい。いなか。「千葉の在」「在所」
《解字》
 会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをとめるせきを描いた象形文字で、その全形は形を変えて災(成長進行を止める支障)などに含まれる。才は、そのせきの形だけをとって描いた象形文字で、切り止める意を含む。在は「土+音符才」で、土でふさいで水流を切り止め進行を止めること。転じて、じっと止まる意となる。
《単語家族》
材(切った材木)
会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをとめるせきを描いた象形文字で、その全形は形を変えて災(成長進行を止める支障)などに含まれる。才は、そのせきの形だけをとって描いた象形文字で、切り止める意を含む。在は「土+音符才」で、土でふさいで水流を切り止め進行を止めること。転じて、じっと止まる意となる。
《単語家族》
材(切った材木) 裁(衣料を切る)
裁(衣料を切る) 災と同系。
《異字同訓》
ある。 →有
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
災と同系。
《異字同訓》
ある。 →有
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
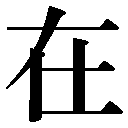 6画 土部 [五年]
区点=2663 16進=3A5F シフトJIS=8DDD
《常用音訓》ザイ/あ…る
《音読み》 ザイ
6画 土部 [五年]
区点=2663 16進=3A5F シフトJIS=8DDD
《常用音訓》ザイ/あ…る
《音読み》 ザイ /サイ
/サイ 〈z
〈z i〉
《訓読み》 ある(あり)/います/ありては/ありて/ざい
《名付け》 あき・あきら・あり・すみ・とお・とみ・まき・みつる
《意味》
i〉
《訓読み》 ある(あり)/います/ありては/ありて/ざい
《名付け》 あき・あきら・あり・すみ・とお・とみ・まき・みつる
《意味》
 {動}ある(アリ)じっとそこにとまっている。「在中」「心不在焉、視而不見=心ココニ在ラズンバ、視レドモ見エズ」〔→大学〕
{動}ある(アリ)じっとそこにとまっている。「在中」「心不在焉、視而不見=心ココニ在ラズンバ、視レドモ見エズ」〔→大学〕
 {動}ある(アリ)。います。生きている。この世にいる。「在世」「父在観其志=父在セバソノ志ヲ観ル」〔→論語〕
{動}ある(アリ)。います。生きている。この世にいる。「在世」「父在観其志=父在セバソノ志ヲ観ル」〔→論語〕
 {名}物のある場所。いる場所。▽去声に読む。「行在」
{名}物のある場所。いる場所。▽去声に読む。「行在」
 {動}ありては。…においては。〈類義語〉→於。「在他人則誅之=他人ニ在リテハスナハチコレヲ誅ス」〔→孟子〕
{動}ありては。…においては。〈類義語〉→於。「在他人則誅之=他人ニ在リテハスナハチコレヲ誅ス」〔→孟子〕
 {前}ありて。場所を示す前置詞。〈類義語〉→於。「豆在釜中泣=豆ハ釜中ニ在リテ泣ク」〔→曹植〕
{前}ありて。場所を示す前置詞。〈類義語〉→於。「豆在釜中泣=豆ハ釜中ニ在リテ泣ク」〔→曹植〕
 「在視ザイシ」「在察ザイサツ」とは、じっと目をとめてよく見ること。
〔国〕ざい。いなか。「千葉の在」「在所」
《解字》
「在視ザイシ」「在察ザイサツ」とは、じっと目をとめてよく見ること。
〔国〕ざい。いなか。「千葉の在」「在所」
《解字》
 会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをとめるせきを描いた象形文字で、その全形は形を変えて災(成長進行を止める支障)などに含まれる。才は、そのせきの形だけをとって描いた象形文字で、切り止める意を含む。在は「土+音符才」で、土でふさいで水流を切り止め進行を止めること。転じて、じっと止まる意となる。
《単語家族》
材(切った材木)
会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをとめるせきを描いた象形文字で、その全形は形を変えて災(成長進行を止める支障)などに含まれる。才は、そのせきの形だけをとって描いた象形文字で、切り止める意を含む。在は「土+音符才」で、土でふさいで水流を切り止め進行を止めること。転じて、じっと止まる意となる。
《単語家族》
材(切った材木) 裁(衣料を切る)
裁(衣料を切る) 災と同系。
《異字同訓》
ある。 →有
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
災と同系。
《異字同訓》
ある。 →有
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
垤 ありづか🔗⭐🔉
有 あり🔗⭐🔉
【有】
 6画 月部 [三年]
区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C
《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る
《音読み》 ユウ(イウ)
6画 月部 [三年]
区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C
《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る
《音読み》 ユウ(イウ) /ウ
/ウ 〈y
〈y u・y
u・y u〉
《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと
《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り
《意味》
u〉
《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと
《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り
《意味》
 {動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕
{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕
 {動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕
{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕
 ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕
ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕
 {名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕
{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕
 {動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕
{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕
 {助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」
{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」
 {名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」
{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」
 {助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕
〔国〕ある(アリ)。…である。
《解字》
{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕
〔国〕ある(アリ)。…である。
《解字》
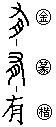 会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。
《単語家族》
佑ユウ(かかえこむ)
会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。
《単語家族》
佑ユウ(かかえこむ) 囿ユウ(わくを構えた区画)
囿ユウ(わくを構えた区画) 域(わくを構えた領分)と同系。
《類義》
在は、ある場所に動かず存在すること。
《異字同訓》
ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
域(わくを構えた領分)と同系。
《類義》
在は、ある場所に動かず存在すること。
《異字同訓》
ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 6画 月部 [三年]
区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C
《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る
《音読み》 ユウ(イウ)
6画 月部 [三年]
区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C
《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る
《音読み》 ユウ(イウ) /ウ
/ウ 〈y
〈y u・y
u・y u〉
《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと
《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り
《意味》
u〉
《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと
《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り
《意味》
 {動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕
{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕
 {動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕
{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕
 ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕
ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕
 {名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕
{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕
 {動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕
{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕
 {助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」
{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」
 {名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」
{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」
 {助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕
〔国〕ある(アリ)。…である。
《解字》
{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕
〔国〕ある(アリ)。…である。
《解字》
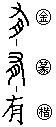 会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。
《単語家族》
佑ユウ(かかえこむ)
会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。
《単語家族》
佑ユウ(かかえこむ) 囿ユウ(わくを構えた区画)
囿ユウ(わくを構えた区画) 域(わくを構えた領分)と同系。
《類義》
在は、ある場所に動かず存在すること。
《異字同訓》
ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
域(わくを構えた領分)と同系。
《類義》
在は、ある場所に動かず存在すること。
《異字同訓》
ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
有明 アリアケ🔗⭐🔉
【有明】
アリアケ〔国〕 陰暦十六日以後で、空に月が残ったまま、夜が明けること。また、陰暦十六日ごろの夜明け。
陰暦十六日以後で、空に月が残ったまま、夜が明けること。また、陰暦十六日ごろの夜明け。 「有明行灯アンドン」の略。朝まで、まくらもとにともしておくあんどん。
「有明行灯アンドン」の略。朝まで、まくらもとにともしておくあんどん。
 陰暦十六日以後で、空に月が残ったまま、夜が明けること。また、陰暦十六日ごろの夜明け。
陰暦十六日以後で、空に月が残ったまま、夜が明けること。また、陰暦十六日ごろの夜明け。 「有明行灯アンドン」の略。朝まで、まくらもとにともしておくあんどん。
「有明行灯アンドン」の略。朝まで、まくらもとにともしておくあんどん。
蛾 あり🔗⭐🔉
【蛾】
 13画 虫部
区点=1875 16進=326B シフトJIS=89E9
《音読み》
13画 虫部
区点=1875 16進=326B シフトJIS=89E9
《音読み》  ガ
ガ
 〈
〈 〉/
〉/ ギ
ギ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 あり
《意味》
〉
《訓読み》 あり
《意味》

 {名}かいこの成虫。かいこが。
{名}かいこの成虫。かいこが。
 {名}虫の名。蝶チョウに似ている。夜間に飛び、また羽をひらいてとまる。毛虫の成虫。が。
{名}虫の名。蝶チョウに似ている。夜間に飛び、また羽をひらいてとまる。毛虫の成虫。が。
 「蛾眉ガビ」とは、蛾ガの触角のように、細長く曲がって、くっきりと目だつ眉マユ。細長く曲がってよく目だつ、美人の眉のこと。▽一説に、「蛾」は娥(美しい)。また、三日月の状態を形容することもある。〈類義語〉蛾黛ガタイ。
「蛾眉ガビ」とは、蛾ガの触角のように、細長く曲がって、くっきりと目だつ眉マユ。細長く曲がってよく目だつ、美人の眉のこと。▽一説に、「蛾」は娥(美しい)。また、三日月の状態を形容することもある。〈類義語〉蛾黛ガタイ。
 {名}あり。〈同義語〉→蟻。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符我(かどめがたつ、くっきりと目だつ)」。くっきりと目だつ形や色をした虫のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}あり。〈同義語〉→蟻。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符我(かどめがたつ、くっきりと目だつ)」。くっきりと目だつ形や色をした虫のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画 虫部
区点=1875 16進=326B シフトJIS=89E9
《音読み》
13画 虫部
区点=1875 16進=326B シフトJIS=89E9
《音読み》  ガ
ガ
 〈
〈 〉/
〉/ ギ
ギ
 〈y
〈y 〉
《訓読み》 あり
《意味》
〉
《訓読み》 あり
《意味》

 {名}かいこの成虫。かいこが。
{名}かいこの成虫。かいこが。
 {名}虫の名。蝶チョウに似ている。夜間に飛び、また羽をひらいてとまる。毛虫の成虫。が。
{名}虫の名。蝶チョウに似ている。夜間に飛び、また羽をひらいてとまる。毛虫の成虫。が。
 「蛾眉ガビ」とは、蛾ガの触角のように、細長く曲がって、くっきりと目だつ眉マユ。細長く曲がってよく目だつ、美人の眉のこと。▽一説に、「蛾」は娥(美しい)。また、三日月の状態を形容することもある。〈類義語〉蛾黛ガタイ。
「蛾眉ガビ」とは、蛾ガの触角のように、細長く曲がって、くっきりと目だつ眉マユ。細長く曲がってよく目だつ、美人の眉のこと。▽一説に、「蛾」は娥(美しい)。また、三日月の状態を形容することもある。〈類義語〉蛾黛ガタイ。
 {名}あり。〈同義語〉→蟻。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符我(かどめがたつ、くっきりと目だつ)」。くっきりと目だつ形や色をした虫のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}あり。〈同義語〉→蟻。
《解字》
会意兼形声。「虫+音符我(かどめがたつ、くっきりと目だつ)」。くっきりと目だつ形や色をした虫のこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源に「あり」で始まるの検索結果 1-7。
 9画 土部
区点=5225 16進=5439 シフトJIS=9AB7
《音読み》 テツ
9画 土部
区点=5225 16進=5439 シフトJIS=9AB7
《音読み》 テツ 19画 虫部
区点=2134 16進=3542 シフトJIS=8B61
《音読み》 ギ
19画 虫部
区点=2134 16進=3542 シフトJIS=8B61
《音読み》 ギ