複数辞典一括検索+![]()
![]()
兜 かぶと🔗⭐🔉
【兜】
 11画 儿部
区点=1985 16進=3375 シフトJIS=8A95
《音読み》 トウ
11画 儿部
区点=1985 16進=3375 シフトJIS=8A95
《音読み》 トウ /ト/ツ
/ト/ツ 〈d
〈d u〉
《訓読み》 かぶと
《意味》
u〉
《訓読み》 かぶと
《意味》
 {名}かぶと。頭を包んで囲むかぶり物。
{名}かぶと。頭を包んで囲むかぶり物。
 {動}とり囲んで包む。
《解字》
会意。白(人の頭)+儿(足の部分)にその頭を左右から包む形を加えたもの。頭を包むことに着目したことば。
《類義》
甲冑カッチュウの甲コウは、かぶせるかたいかぶとのこと。冑は、首だけ抜け出る胴巻きのこと。
《熟語》
→熟語
{動}とり囲んで包む。
《解字》
会意。白(人の頭)+儿(足の部分)にその頭を左右から包む形を加えたもの。頭を包むことに着目したことば。
《類義》
甲冑カッチュウの甲コウは、かぶせるかたいかぶとのこと。冑は、首だけ抜け出る胴巻きのこと。
《熟語》
→熟語
 11画 儿部
区点=1985 16進=3375 シフトJIS=8A95
《音読み》 トウ
11画 儿部
区点=1985 16進=3375 シフトJIS=8A95
《音読み》 トウ /ト/ツ
/ト/ツ 〈d
〈d u〉
《訓読み》 かぶと
《意味》
u〉
《訓読み》 かぶと
《意味》
 {名}かぶと。頭を包んで囲むかぶり物。
{名}かぶと。頭を包んで囲むかぶり物。
 {動}とり囲んで包む。
《解字》
会意。白(人の頭)+儿(足の部分)にその頭を左右から包む形を加えたもの。頭を包むことに着目したことば。
《類義》
甲冑カッチュウの甲コウは、かぶせるかたいかぶとのこと。冑は、首だけ抜け出る胴巻きのこと。
《熟語》
→熟語
{動}とり囲んで包む。
《解字》
会意。白(人の頭)+儿(足の部分)にその頭を左右から包む形を加えたもの。頭を包むことに着目したことば。
《類義》
甲冑カッチュウの甲コウは、かぶせるかたいかぶとのこと。冑は、首だけ抜け出る胴巻きのこと。
《熟語》
→熟語
冑 かぶと🔗⭐🔉
【冑】
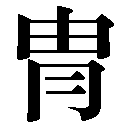 9画 冂部
区点=4941 16進=5149 シフトJIS=9968
《音読み》 チュウ(チウ)
9画 冂部
区点=4941 16進=5149 シフトJIS=9968
《音読み》 チュウ(チウ) /ジュウ(ヂウ)
/ジュウ(ヂウ) 〈zh
〈zh u〉
《訓読み》 かぶと
《意味》
u〉
《訓読み》 かぶと
《意味》
 {名}かぶと。頭を包み隠すもの。▽「甲冑カッチュウ」の甲はかぶと、冑は胴巻き、よろいのこと。後に、かぶとを冑という。
《解字》
{名}かぶと。頭を包み隠すもの。▽「甲冑カッチュウ」の甲はかぶと、冑は胴巻き、よろいのこと。後に、かぶとを冑という。
《解字》
 会意兼形声。冑の原字は、上部の頭にかぶとを載せた姿と、下部の冒(かぶる)の字からなる。冑は「かぶる、かくすしるし+音符由」。頭だけ上部に抜け出る胴巻きのこと。▽胄胤チュウインの胄は「肉+音符由」の字で、下部は月(にくづき)。親の身から抜け出た子のこと。のちには字体が混同した。
《単語家族》
抽チュウ(抜き出る)
会意兼形声。冑の原字は、上部の頭にかぶとを載せた姿と、下部の冒(かぶる)の字からなる。冑は「かぶる、かくすしるし+音符由」。頭だけ上部に抜け出る胴巻きのこと。▽胄胤チュウインの胄は「肉+音符由」の字で、下部は月(にくづき)。親の身から抜け出た子のこと。のちには字体が混同した。
《単語家族》
抽チュウ(抜き出る) 軸(車輪を抜け出るじく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
軸(車輪を抜け出るじく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
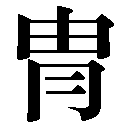 9画 冂部
区点=4941 16進=5149 シフトJIS=9968
《音読み》 チュウ(チウ)
9画 冂部
区点=4941 16進=5149 シフトJIS=9968
《音読み》 チュウ(チウ) /ジュウ(ヂウ)
/ジュウ(ヂウ) 〈zh
〈zh u〉
《訓読み》 かぶと
《意味》
u〉
《訓読み》 かぶと
《意味》
 {名}かぶと。頭を包み隠すもの。▽「甲冑カッチュウ」の甲はかぶと、冑は胴巻き、よろいのこと。後に、かぶとを冑という。
《解字》
{名}かぶと。頭を包み隠すもの。▽「甲冑カッチュウ」の甲はかぶと、冑は胴巻き、よろいのこと。後に、かぶとを冑という。
《解字》
 会意兼形声。冑の原字は、上部の頭にかぶとを載せた姿と、下部の冒(かぶる)の字からなる。冑は「かぶる、かくすしるし+音符由」。頭だけ上部に抜け出る胴巻きのこと。▽胄胤チュウインの胄は「肉+音符由」の字で、下部は月(にくづき)。親の身から抜け出た子のこと。のちには字体が混同した。
《単語家族》
抽チュウ(抜き出る)
会意兼形声。冑の原字は、上部の頭にかぶとを載せた姿と、下部の冒(かぶる)の字からなる。冑は「かぶる、かくすしるし+音符由」。頭だけ上部に抜け出る胴巻きのこと。▽胄胤チュウインの胄は「肉+音符由」の字で、下部は月(にくづき)。親の身から抜け出た子のこと。のちには字体が混同した。
《単語家族》
抽チュウ(抜き出る) 軸(車輪を抜け出るじく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
軸(車輪を抜け出るじく)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
甲 かぶと🔗⭐🔉
【甲】
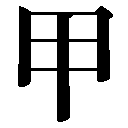 5画 田部 [常用漢字]
区点=2535 16進=3943 シフトJIS=8D62
《常用音訓》カン/コウ
《音読み》 コウ(カフ)
5画 田部 [常用漢字]
区点=2535 16進=3943 シフトJIS=8D62
《常用音訓》カン/コウ
《音読み》 コウ(カフ) /カン
/カン /キョウ(ケフ)
/キョウ(ケフ) 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 きのえ/かぶと/よろい(よろひ)/こう(かふ)
《名付け》 か・かつ・き・きのえ・まさる
《意味》
〉
《訓読み》 きのえ/かぶと/よろい(よろひ)/こう(かふ)
《名付け》 か・かつ・き・きのえ・まさる
《意味》

 {名}きのえ。十干ジッカンの一番め。▽五行では乙とともに木に当てる。日本の兄弟エトの「きのえ」は「木の兄エ」の意。順位の第一位を示す。
{名}きのえ。十干ジッカンの一番め。▽五行では乙とともに木に当てる。日本の兄弟エトの「きのえ」は「木の兄エ」の意。順位の第一位を示す。
 {名}科挙(官吏登用試験)で、成績による序列のこと。▽一甲・二甲・三甲と序列をきめ、一甲は状元・榜眼ボウガン・探花の三人。「鼎甲テイコウ(科挙で、三人の最優秀合格者)」「甲榜コウボウ(進士の試験の発表)」
{名}科挙(官吏登用試験)で、成績による序列のこと。▽一甲・二甲・三甲と序列をきめ、一甲は状元・榜眼ボウガン・探花の三人。「鼎甲テイコウ(科挙で、三人の最優秀合格者)」「甲榜コウボウ(進士の試験の発表)」
 {名}かぶと。よろい(ヨロヒ)。武具の一つ。からだにつけるかたい防具。「甲冑カッチュウ」「兵甲(武器やよろい)」「棄甲曳兵而走=甲ヲ棄テ兵ヲ曳キテ走ル」〔→孟子〕
{名}かぶと。よろい(ヨロヒ)。武具の一つ。からだにつけるかたい防具。「甲冑カッチュウ」「兵甲(武器やよろい)」「棄甲曳兵而走=甲ヲ棄テ兵ヲ曳キテ走ル」〔→孟子〕
 {名}かめ・えび・かに・昆虫などのかぶるかたいから。こうら。また、つめ。「亀甲キッコウ(かめのこうら)」「甲殻類」「指甲(つめ)」
{名}かめ・えび・かに・昆虫などのかぶるかたいから。こうら。また、つめ。「亀甲キッコウ(かめのこうら)」「甲殻類」「指甲(つめ)」
 「某甲ボウコウ」とは、その人の名がわからないときや、その人の名をはっきりと示さないときに用いることば。ある人。
「某甲ボウコウ」とは、その人の名がわからないときや、その人の名をはっきりと示さないときに用いることば。ある人。
 {名}地方自衛の制度で、十戸を一組とする組のこと。▽いくつかの甲をあわせて保(または団)という。宋ソウの王安石がはじめた。「保甲制」「甲長(甲の長)」
〔国〕
{名}地方自衛の制度で、十戸を一組とする組のこと。▽いくつかの甲をあわせて保(または団)という。宋ソウの王安石がはじめた。「保甲制」「甲長(甲の長)」
〔国〕 こう(カフ)。手や足で、表面の側。「手の甲」「甲が高い」
こう(カフ)。手や足で、表面の側。「手の甲」「甲が高い」 「甲高カンダカい」とは、声や音が強く高いこと。
《解字》
「甲高カンダカい」とは、声や音が強く高いこと。
《解字》
 象形。もと、うろこを描いた象形文字。のち、たねをとり巻いたかたいからを描いた象形文字。かぶせる意を含む。▽促音語尾のpがtに転じたばあいはカッと読む。
《単語家族》
盍コウ(かぶせる)
象形。もと、うろこを描いた象形文字。のち、たねをとり巻いたかたいからを描いた象形文字。かぶせる意を含む。▽促音語尾のpがtに転じたばあいはカッと読む。
《単語家族》
盍コウ(かぶせる) 盒ゴウ(ふたをする)
盒ゴウ(ふたをする) 合(ふたをする)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
合(ふたをする)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
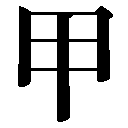 5画 田部 [常用漢字]
区点=2535 16進=3943 シフトJIS=8D62
《常用音訓》カン/コウ
《音読み》 コウ(カフ)
5画 田部 [常用漢字]
区点=2535 16進=3943 シフトJIS=8D62
《常用音訓》カン/コウ
《音読み》 コウ(カフ) /カン
/カン /キョウ(ケフ)
/キョウ(ケフ) 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 きのえ/かぶと/よろい(よろひ)/こう(かふ)
《名付け》 か・かつ・き・きのえ・まさる
《意味》
〉
《訓読み》 きのえ/かぶと/よろい(よろひ)/こう(かふ)
《名付け》 か・かつ・き・きのえ・まさる
《意味》

 {名}きのえ。十干ジッカンの一番め。▽五行では乙とともに木に当てる。日本の兄弟エトの「きのえ」は「木の兄エ」の意。順位の第一位を示す。
{名}きのえ。十干ジッカンの一番め。▽五行では乙とともに木に当てる。日本の兄弟エトの「きのえ」は「木の兄エ」の意。順位の第一位を示す。
 {名}科挙(官吏登用試験)で、成績による序列のこと。▽一甲・二甲・三甲と序列をきめ、一甲は状元・榜眼ボウガン・探花の三人。「鼎甲テイコウ(科挙で、三人の最優秀合格者)」「甲榜コウボウ(進士の試験の発表)」
{名}科挙(官吏登用試験)で、成績による序列のこと。▽一甲・二甲・三甲と序列をきめ、一甲は状元・榜眼ボウガン・探花の三人。「鼎甲テイコウ(科挙で、三人の最優秀合格者)」「甲榜コウボウ(進士の試験の発表)」
 {名}かぶと。よろい(ヨロヒ)。武具の一つ。からだにつけるかたい防具。「甲冑カッチュウ」「兵甲(武器やよろい)」「棄甲曳兵而走=甲ヲ棄テ兵ヲ曳キテ走ル」〔→孟子〕
{名}かぶと。よろい(ヨロヒ)。武具の一つ。からだにつけるかたい防具。「甲冑カッチュウ」「兵甲(武器やよろい)」「棄甲曳兵而走=甲ヲ棄テ兵ヲ曳キテ走ル」〔→孟子〕
 {名}かめ・えび・かに・昆虫などのかぶるかたいから。こうら。また、つめ。「亀甲キッコウ(かめのこうら)」「甲殻類」「指甲(つめ)」
{名}かめ・えび・かに・昆虫などのかぶるかたいから。こうら。また、つめ。「亀甲キッコウ(かめのこうら)」「甲殻類」「指甲(つめ)」
 「某甲ボウコウ」とは、その人の名がわからないときや、その人の名をはっきりと示さないときに用いることば。ある人。
「某甲ボウコウ」とは、その人の名がわからないときや、その人の名をはっきりと示さないときに用いることば。ある人。
 {名}地方自衛の制度で、十戸を一組とする組のこと。▽いくつかの甲をあわせて保(または団)という。宋ソウの王安石がはじめた。「保甲制」「甲長(甲の長)」
〔国〕
{名}地方自衛の制度で、十戸を一組とする組のこと。▽いくつかの甲をあわせて保(または団)という。宋ソウの王安石がはじめた。「保甲制」「甲長(甲の長)」
〔国〕 こう(カフ)。手や足で、表面の側。「手の甲」「甲が高い」
こう(カフ)。手や足で、表面の側。「手の甲」「甲が高い」 「甲高カンダカい」とは、声や音が強く高いこと。
《解字》
「甲高カンダカい」とは、声や音が強く高いこと。
《解字》
 象形。もと、うろこを描いた象形文字。のち、たねをとり巻いたかたいからを描いた象形文字。かぶせる意を含む。▽促音語尾のpがtに転じたばあいはカッと読む。
《単語家族》
盍コウ(かぶせる)
象形。もと、うろこを描いた象形文字。のち、たねをとり巻いたかたいからを描いた象形文字。かぶせる意を含む。▽促音語尾のpがtに転じたばあいはカッと読む。
《単語家族》
盍コウ(かぶせる) 盒ゴウ(ふたをする)
盒ゴウ(ふたをする) 合(ふたをする)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
合(ふたをする)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「かぶと」で始まるの検索結果 1-3。