複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (32)
おき【置き】🔗⭐🔉
おき【置き】
①すておくこと。
②(数量を表す語につけて)それだけずつの間を隔てること。「1日―」
③浄瑠璃や歌舞伎舞踊の冒頭で、人物の登場や物語の展開に先立って歌われる(語られる)前置き部分。浄瑠璃では「置浄瑠璃」、長唄では「置唄」という。
⇒置きにする
おき‐あわせ【置き合せ】‥アハセ🔗⭐🔉
おき‐あわせ【置き合せ】‥アハセ
とりあわせ。配合。東海道名所記「―には馬の角、牛の玉」
おき‐か・える【置き換える】‥カヘル🔗⭐🔉
おき‐か・える【置き換える】‥カヘル
〔他下一〕[文]おきか・ふ(下二)
①あれとこれとを取りかえて置く。「xをyに―・える」
②物を他の場所へ移して置く。「鏡台を―・える」
③もとの質物を新しい質物にかえる。
おき‐がお【置き顔】‥ガホ🔗⭐🔉
おき‐がお【置き顔】‥ガホ
(草葉におく露の消えやすいことにたとえていう語)しばらく世に生きながらえているありさま。謡曲、清経「とても消ゆべき露の身をなほ―に」
おき‐がさ【置き傘】🔗⭐🔉
おき‐がさ【置き傘】
不意の降雨に備えて、勤め先などに日常置いておく傘。
おき‐ぐすり【置き薬】🔗⭐🔉
おき‐ぐすり【置き薬】
家庭に常備しておく薬。特に、あらかじめ所定の薬を家庭に置き、巡回する販売員が使った分だけ代金と引き換えに補充するしくみの家庭薬。富山の薬売りによるものが有名。
おき‐くち【置き口】🔗⭐🔉
おき‐くち【置き口】
(オキグチとも)箱のふたや衣服の袖口などを縁どりして金銀などで飾ること。また、その縁。宇津保物語吹上上「―の衣箱一つに」
おき‐こ・む【置き籠む】🔗⭐🔉
おき‐こ・む【置き籠む】
〔他下二〕
一面に置きわたす。六百番歌合「露―・むるよはの初霜」
おき‐ざり【置き去り】🔗⭐🔉
おき‐ざり【置き去り】
①人や物を捨ておいて行ってしまうこと。おいてきぼり。おきずて。浄瑠璃、国性爺合戦「この小睦を―に」。「話から―にされる」
②妻を家に残して夫が出て行き、事実上離婚になること。日本永代蔵5「年寄女房が気にいらぬとて―にしてゆかれました」
おき‐しお【置き潮】‥シホ🔗⭐🔉
おき‐しお【置き潮】‥シホ
やめるのによい機会。狂言、三人片輪「好い―もござつたれども」
おき‐すえ【置き据え】‥スヱ🔗⭐🔉
おき‐すえ【置き据え】‥スヱ
そのままにしておくこと。すえおき。
おき‐す・える【置き据える】‥スヱル🔗⭐🔉
おき‐す・える【置き据える】‥スヱル
〔他下一〕[文]おきす・う(下二)
据えておく。
おき‐ずみ【置き炭】🔗⭐🔉
おき‐ずみ【置き炭】
小正月の夜、炉の中でヌルデやクルミの木などを焼き、その焦げ具合で月々の天候を占うこと。炭占すみうら。
おき‐ずみ【置き墨】🔗⭐🔉
おき‐ずみ【置き墨】
額ひたいの形を美しく見せるために髪の生えぎわに墨を塗り、あるいは墨で眉を描くこと。また、その墨。際墨きわずみ。好色一代女1「眉そりて―濃く」
おき‐ぜに【置き銭】🔗⭐🔉
おき‐ぜに【置き銭】
出立の際、宿屋に茶代として置く銭。日本永代蔵2「三人に三百の―、悦ぶ事限りなく」
おき‐せん【置き銭】🔗⭐🔉
おき‐せん【置き銭】
①ばくちにはる銭。
②情人の異称。また、男女の私通をいう。
③(→)「おきぜに」に同じ。
おき‐そ・う【置き添ふ】‥ソフ🔗⭐🔉
おき‐そ・う【置き添ふ】‥ソフ
[一]〔自四〕
置いてある上に更に置き加わる。源氏物語御法「ぬれにし袖に露ぞ―・ふ」
[二]〔他下二〕
⇒おきそえる(下一)
おき‐そ・える【置き添える】‥ソヘル🔗⭐🔉
おき‐そ・える【置き添える】‥ソヘル
〔他下一〕[文]おきそ・ふ(下二)
置いてある上に更に置き加える。おきそわせる。源氏物語桐壺「いとどしく虫の音しげき浅茅生あさぢふに露―・ふる雲の上人」
おき‐つち【置き土】🔗⭐🔉
おき‐つち【置き土】
①ものの上に置き添えた土。好色一代女2「天井も―して壁一尺余り厚く付けて」
②(→)客土きゃくどに同じ。
おき‐でっぽう【置き鉄砲】‥パウ🔗⭐🔉
おき‐でっぽう【置き鉄砲】‥パウ
(神奈川県北部などで)(→)「夜狙よねらい」に同じ。
おき‐どころ【置き所】🔗⭐🔉
おき‐どころ【置き所】
置くべき所。置き場所。安心していられる所。源氏物語初音「若き人々の心地ども―なく見ゆ」。「身の―がない」
○置きにするおきにする🔗⭐🔉
○置きにするおきにする
やめにする。浮世風呂2「なんの洒落臭しゃらっくせへ、―がいい」
⇒おき【置き】
おき‐に‐めす【御気に召す】
「気に入る」の尊敬語。
おき‐ば【置き場】🔗⭐🔉
おき‐ば【置き場】
①物を置く場所。「材木―」「身の―がない思い」
②(俗に)質屋。
おき‐ばし【置き箸】🔗⭐🔉
おき‐ばし【置き箸】
①食事中に箸を食器の上に置くこと。不作法とされる。
②自宅以外に備えておく自分の箸。
おき‐ピン【置きピン】🔗⭐🔉
おき‐ピン【置きピン】
被写体の動きを予測してある地点にあらかじめピントを設定しておく撮影法。
おき‐ぶるし【置き旧し】🔗⭐🔉
おき‐ぶるし【置き旧し】
おきふるすこと。おきふるしたもの。鷹筑波「年明けて今朝見る霜や―」
おき‐ふる・す【置き旧す】🔗⭐🔉
おき‐ふる・す【置き旧す】
〔他四〕
捨ておいたまま時を過ごす。物を使わずにふるくする。万葉集11「難波菅笠なにわすがかさ―・し」
おき‐まどわ・す【置き惑はす】‥マドハス🔗⭐🔉
おき‐まどわ・す【置き惑はす】‥マドハス
〔他四〕
①他と見わけにくいように置く。古今和歌集秋「初霜の―・せる白菊の花」
②置き忘れる。源氏物語夕顔「かぎを―・し侍りて」
おき‐まよ・う【置き迷ふ】‥マヨフ🔗⭐🔉
おき‐まよ・う【置き迷ふ】‥マヨフ
〔自四〕
①置場所にまよう。まちがって置く。新古今和歌集秋「色かはる露をば袖に―・ひ」
②置いたのかと見まちがう。新古今和歌集秋「宵のまに―・ふ色は山のはの月」
おき‐みち【置き路】🔗⭐🔉
おき‐みち【置き路】
土を盛って一段高くした路。
おきゃあがれ【置きゃあがれ】🔗⭐🔉
おきゃあがれ【置きゃあがれ】
(江戸語)やめてくれ。よせやい。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「―、コレヤイ、これを見ろ」
おき‐わす・れる【置き忘れる】🔗⭐🔉
おき‐わす・れる【置き忘れる】
〔他下一〕[文]おきわす・る(下二)
物を置いた場所を忘れる。また、置いたまま持ってくるのを忘れる。「眼鏡を―・れて捜しまわる」「タクシーに書類を―・れる」
大辞林の検索結果 (62)
おき【置(き)】🔗⭐🔉
おき 【置(き)】
■一■ [0] (名)
(1)「置き浄瑠璃」の略。
(2)「置き唄」の略。
■二■ (接尾)
時間・距離・数量などを表す語に付いて,それだけの間隔をおくことを表す。「三時間―」「二メートル―」「一人―」
おき-あみ【置(き)網】🔗⭐🔉
おき-あみ [0] 【置(き)網】
⇒待(マ)ち網(アミ)
おき-あわせ【置き合(わ)せ】🔗⭐🔉
おき-あわせ ―アハセ [0] 【置き合(わ)せ】
茶道などで,調和を考えて道具を配置すること。また,その道具。「―がいい」
おき-いけ【置(き)生け】🔗⭐🔉
おき-いけ [0] 【置(き)生け】
下に据えた花器にいけた生け花の総称。
おき-いし【置(き)石】🔗⭐🔉
おき-いし [0] 【置(き)石】
(1)風趣をそえるため,庭などに据える石。
(2)囲碁で,両者の力量に差があるときに,弱い方の人があらかじめ星の上に二子(ニシ)以上置く黒石。
おき-うた【置き唄】🔗⭐🔉
おき-うた [0] 【置き唄】
歌舞伎の下座唄や歌舞伎舞踊の伴奏の長唄で,場面展開や人物の登場の前にうたわれる序奏的部分。おき。
おき-うた【置(き)歌】🔗⭐🔉
おき-うた [0] 【置(き)歌】
「空札(カラフダ)」に同じ。
おき-え【置き餌】🔗⭐🔉
おき-え ― [0][2] 【置き餌】
ネズミ・ゴキブリなどを駆除するために仕掛ける餌(エサ)。
[0][2] 【置き餌】
ネズミ・ゴキブリなどを駆除するために仕掛ける餌(エサ)。
 [0][2] 【置き餌】
ネズミ・ゴキブリなどを駆除するために仕掛ける餌(エサ)。
[0][2] 【置き餌】
ネズミ・ゴキブリなどを駆除するために仕掛ける餌(エサ)。
おき-かえ【置(き)換え・置(き)替え】🔗⭐🔉
おき-かえ ―カヘ [0] 【置(き)換え・置(き)替え】
(1)おきかえること。
(2)精神分析の用語。ある特定の対象に向けられていた感情や態度がほかの対象に向けられたり,また,別の形で行動に表されたりすること。防衛機制の一つ。転位。
(3)〔「おきがえ」とも〕
掛け売りの方法の一。保証金を取って掛け売りをし,売掛金が保証金よりも大きくなれば,保証金を追加徴収する。「―の約束も年々かさみて/浮世草子・永代蔵 5」
おき-か・える【置(き)換える・置(き)替える】🔗⭐🔉
おき-か・える ―カヘル [4][3] 【置(き)換える・置(き)替える】 (動ア下一)[文]ハ下二 おきか・ふ
(1)物を現在ある場所から他の場所に移し置く。「机を明るい場所に―・える」
(2)現在ある物をどけて,あとに別の物を置く。「テレビと茶だんすを―・える」「 を
を  に―・える」
に―・える」
 を
を  に―・える」
に―・える」
おき-がさ【置(き)傘】🔗⭐🔉
おき-がさ [0][3] 【置(き)傘】
不意の雨に備えて,学校・勤め先などに置いておく傘。
おき-がた【置(き)形・置(き)型】🔗⭐🔉
おき-がた [0] 【置(き)形・置(き)型】
布などに型紙を置いて染め出した模様。
おき-ぐすり【置(き)薬】🔗⭐🔉
おき-ぐすり [3] 【置(き)薬】
行商人が常備薬として家庭に預ける薬。一定期間ののち,使った分の代金と引きかえに,薬を補充する。富山の薬売りのものが著名。配置薬。
おき-ぐち【置き口】🔗⭐🔉
おき-ぐち 【置き口】
〔「おきくち」とも〕
箱のふたの縁(フチ)や婦人の衣服の袖口・裾などに金や銀で縁飾りをすること。「袖口に―をし/紫式部日記」
おき-くら【置き座】🔗⭐🔉
おき-くら 【置き座】
物を置く台。台。「千座(チクラ)の―に置き足(タラ)はして/祝詞(六月晦大祓)」
おき-ご【置(き)碁】🔗⭐🔉
おき-ご [0] 【置(き)碁】
囲碁で,両者の力量に差のあるとき,弱い方の人があらかじめ星の上に二子(ニシ)以上の石を置いて打つこと。
おき-ごたつ【置き炬燵】🔗⭐🔉
おき-ごたつ [3] 【置き炬燵】
やぐらの内に炉を入れた,移動できるこたつ。[季]冬。
→掘り炬燵
おき-ざ【置(き)座】🔗⭐🔉
おき-ざ [0] 【置(き)座】
涼み台。おきえん。腰掛け台。
おき-ざり【置(き)去り】🔗⭐🔉
おき-ざり [0] 【置(き)去り】
そこに残したまま行ってしまうこと。おきずて。「―を食う」「連れに―にされる」
おき-じ【置(き)字】🔗⭐🔉
おき-じ [0] 【置(き)字】
(1)漢文を訓読する際,習慣として読まない助字。「焉(エン)」「乎(コ)」など。
(2)手紙の文章で,「抑(ソモソモ)」「将又(ハタマタ)」「又」など副詞や接続詞に用いる文字。
おき-じゃく【置(き)尺】🔗⭐🔉
おき-じゃく [0] 【置(き)尺】
布などの寸法を測るのに,布を下に置いて測ること。
⇔持ち尺
おき-じょうるり【置(き)浄瑠璃】🔗⭐🔉
おき-じょうるり ―ジヤウルリ [3] 【置(き)浄瑠璃】
常磐津(トキワズ)・清元など歌舞伎の舞踊劇の浄瑠璃で,曲の冒頭,踊り手が登場する前に演奏される部分。おき。
おき-すえ【置き据え】🔗⭐🔉
おき-すえ ―ス 【置き据え】
物事をある状態のままにして手をつけないこと。すえおき。「一両の工面も出来ぬといふからそんならそれは―で/歌舞伎・日月星享和政談」
【置き据え】
物事をある状態のままにして手をつけないこと。すえおき。「一両の工面も出来ぬといふからそんならそれは―で/歌舞伎・日月星享和政談」
 【置き据え】
物事をある状態のままにして手をつけないこと。すえおき。「一両の工面も出来ぬといふからそんならそれは―で/歌舞伎・日月星享和政談」
【置き据え】
物事をある状態のままにして手をつけないこと。すえおき。「一両の工面も出来ぬといふからそんならそれは―で/歌舞伎・日月星享和政談」
おき-ずきん【置(き)頭巾】🔗⭐🔉
おき-ずきん ―ヅキン [3][4] 【置(き)頭巾】
置き手拭(テヌグ)いのように,たたんだ布を頭にのせて頭巾としたもの。
おき-ずて【置(き)捨て】🔗⭐🔉
おき-ずて [0] 【置(き)捨て】
(1)ものを置いたままにしておくこと。
(2)「置き去り」に同じ。「途中で―にされた」
おき-ずみ【置き墨】🔗⭐🔉
おき-ずみ 【置き墨】
顔だちを整えるために,髪の生えぎわや眉などを墨で化粧すること。また,その墨。「眉剃りて―濃く/浮世草子・一代女 1」
おき-せん【置き銭】🔗⭐🔉
おき-せん 【置き銭】
(1)宿立ちなどの時,茶代として置く金銭。おきぜに。
(2)〔遊里からでた近世大坂の俗語〕
情人。愛人。また,そのような関係。「―といふ事…江戸で云ふ馴染や色事のことだとさ/洒落本・船頭深話」
おき-だて【置き楯】🔗⭐🔉
おき-だて [0] 【置き楯】
据えておく楯。
⇔持ち楯
おき-ちぎ【置(き)千木】🔗⭐🔉
おき-ちぎ [3] 【置(き)千木】
神社建築の千木で,棟の上に置く形式のもの。破風(ハフ)や垂木(タルキ)が突き出した本来の千木に対していう。
→千木
おき-つぎ【置き注ぎ】🔗⭐🔉
おき-つぎ [0] 【置き注ぎ】
置いたままの杯に酒をつぐこと。
おき-つけ【置(き)付け】🔗⭐🔉
おき-つけ [0] 【置(き)付け】
他に移さず常にその場に置いたままにしてあること。置きすえ。「―のテーブル」
おき-つち【置(き)土】🔗⭐🔉
おき-つち [0] 【置(き)土】
客土の一種。耕土が浅い田畑,あるいはくぼんだ畑などに土を置き加えるもの。
おき-つつ【置(き)筒】🔗⭐🔉
おき-つつ [0] 【置(き)筒】
つったり掛けたりせず,据え置いたまま用いる筒形の花器。
おき-つづみ【置(き)鼓】🔗⭐🔉
おき-つづみ [3] 【置(き)鼓】
(1)能楽の囃子(ハヤシ)の一。笛と小鼓で演奏される。「翁(オキナ)」のあとの脇能で,ワキが登場する際などに用いる。笛と小鼓を同時に演奏せず,笛を吹いている間は,小鼓の手をおくところからこの名がある。
(2)歌舞伎の下座音楽の一。{(1)}から転じたもの。
おきっ-ぱなし【置きっ放し】🔗⭐🔉
おきっ-ぱなし [0] 【置きっ放し】
置いたまま,ほうってあること。放置。「自転車を外に―にする」
おき-てがみ【置(き)手紙】🔗⭐🔉
おき-てがみ [3] 【置(き)手紙】 (名)スル
相手に会えないときなどに,用件を書き残しておくこと。また,その手紙。「―して外出する」
おき-てぬぐい【置(き)手拭い】🔗⭐🔉
おき-てぬぐい ―テヌグヒ [3] 【置(き)手拭い】
(1)手拭いをたたんで頭または肩に載せておくこと。また,その手拭い。
(2)兜(カブト)の鉢の一種。戦国時代に流行した形で,鉢の後ろに鍔(ツバ)が突き出ていて,手拭いを置いたようにみえる。
置き手拭い(1)
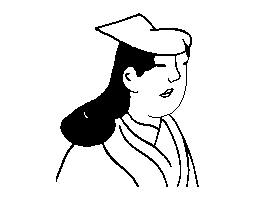 [図]
[図]
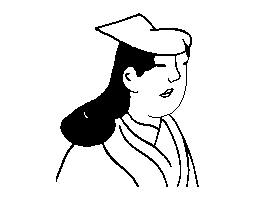 [図]
[図]
おき-ど【置き戸】🔗⭐🔉
おき-ど 【置き戸】
〔「ど」は所の意〕
罪やけがれをはらいつぐなわせるために科する品物を置く台。また,その品物。「速須佐男命(ハヤスサノオノミコト)に千座(チクラ)の―を負(オオ)せ/古事記(上訓)」
おき-どうろう【置(き)灯籠】🔗⭐🔉
おき-どうろう [3] 【置(き)灯籠】
足元の照明とする据え置き式の小型の灯籠。石造品が多く,庭の景色ともなる。
おき-どけい【置(き)時計】🔗⭐🔉
おき-どけい [3] 【置(き)時計】
棚や机の上などに置いて使う型の時計。
おき-どこ【置(き)床】🔗⭐🔉
おき-どこ [0] 【置(き)床】
床の間の代用とする移動できる台。付け床。
おき-どころ【置(き)所】🔗⭐🔉
おき-どころ [0] 【置(き)所】
(1)物を置く場所。置き場。「―に困る」
(2)心や身体を落ち着ける所。「身の―がない」
おき-ば【置(き)場】🔗⭐🔉
おき-ば [0] 【置(き)場】
(1)物を置くための場所。「自転車―」
(2)心や身体を落ち着かせる所。置き所。「身の―がない」
おき-ばな【置(き)花】🔗⭐🔉
おき-ばり【置(き)針】🔗⭐🔉
おき-ばり [0] 【置(き)針】
川魚の釣り方の一。夕方に,餌(エサ)をつけた釣り針を川に入れておき,翌朝あげて魚をとる法。ウナギやナマズなどに用いる。
おき-びき【置(き)引き】🔗⭐🔉
おき-びき [0] 【置(き)引き】 (名)スル
置いてある他人の荷物などを,盗み去ること。また,その者。「―にあう」
おき-びしゃく【置き柄杓】🔗⭐🔉
おき-びしゃく [3] 【置き柄杓】
茶道で,柄杓の扱い方の一。風炉(フロ)で釜に柄杓を置く際,親指を上,人差し指を下にして柄の節より少し下がった所を持って置く置き方。
おき-ぶたい【置(き)舞台】🔗⭐🔉
おき-ぶたい [3] 【置(き)舞台】
(1)舞台の上に置き,その上で舞楽を演じる一丈八尺(約5.4メートル)四方の台。
(2)「所作(シヨサ)舞台」に同じ。
おき-ぶみ【置(き)文】🔗⭐🔉
おき-ぶみ [0] 【置(き)文】
(1)書き置き。遺書。
(2)置き手紙。
(3)古文書の一。現在および将来にわたって守るべき規式を定めた文書。鎌倉・室町時代に多く用いられた。
おき-まどわ・す【置き惑はす】🔗⭐🔉
おき-まどわ・す ―マドハス 【置き惑はす】 (動サ四)
(1)露や霜が置いて他と見分けにくいようにする。「心あてに折らばや折らむ初霜の―・せる白菊の花/古今(秋下)」
(2)置き忘れて見失う。「かぎを―・し侍りて/源氏(夕顔)」
おき-まよ・う【置き迷う】🔗⭐🔉
おき-まよ・う ―マヨフ 【置き迷う】 (動ワ五[ハ四])
(1)置き場所を迷う。
(2)(露や霜が)置いたのかと見まがう。「宵の間に―・ふ色は山の端の月/新古今(秋下)」
おき-みずや【置(き)水屋】🔗⭐🔉
おき-みずや ―ミヅヤ [3] 【置(き)水屋】
茶の湯で用いる移動可能な水屋。普通の水屋が設けられない席で用いる。
おき-みやげ【置(き)土産】🔗⭐🔉
おき-みやげ [3] 【置(き)土産】
(1)立ち去るときにあとに残しておく贈り物。
(2)亡くなった人や前任者が残した業績や負債。「前政権の―」
おきゃあがれ【置きゃあがれ】🔗⭐🔉
おきゃあがれ 【置きゃあがれ】 (連語)
〔動詞「置く」に助動詞「やがる」の命令形が付いたもの〕
やめてくれ。ばか言うな。よせやい。「いまいましい―/浄瑠璃・神霊矢口渡」
おき-わすれ【置(き)忘れ】🔗⭐🔉
おき-わすれ [0] 【置(き)忘れ】
置き忘れること。「傘の―」
おき-わす・れる【置(き)忘れる】🔗⭐🔉
おき-わす・れる [5][0] 【置(き)忘れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 おきわす・る
物を置いたまま持ち帰るのを忘れる。また,置いた場所を忘れる。「ノートを教室に―・れた」
おき-わた【置(き)綿】🔗⭐🔉
おき-わた 【置(き)綿】
綿帽子の一種。真綿を広げて作ったかぶりもの。初めは老女の防寒用だったが,延宝(1673-1681)頃から若い女性にもひろがり,染め綿も用いられた。
おきざり【置き去りにする】(和英)🔗⭐🔉
おきざり【置き去りにする】
leavebehind;desert.→英和
おきちがえる【置き違える】(和英)🔗⭐🔉
おきちがえる【置き違える】
misplace;→英和
putin a wrong place.
おきどころ【置き所】(和英)🔗⭐🔉
おきどころ【置き所】
⇒置場(おきば).
おきわすれる【置き忘れる】(和英)🔗⭐🔉
おきわすれる【置き忘れる】
leavebehind;forget[leave].→英和
広辞苑+大辞林に「−置き」で始まるの検索結果。