複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (99)
いきさつ【経緯】🔗⭐🔉
いきさつ【経緯】
こみいった関係。事件の経過。「結婚までの―」「いろいろ―がある」
きょう【経】キヤウ🔗⭐🔉
きょう【経】キヤウ
(呉音。唐音はキン。梵語sūtra 修多羅の漢訳)
①仏の説いた教えを記したもの。契経。律・論を合わせて三蔵という。
②一切経・大蔵経という場合には律・論などを含めた仏典の総称。
③(仏教以外の)宗教の聖典。経典。「四書五―」
→けい(経)
きょう‐え【経会】キヤウヱ🔗⭐🔉
きょう‐え【経会】キヤウヱ
経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」
きょう‐え【経衣】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょう‐え【経衣】キヤウ‥
(→)「きょうかたびら」に同じ。
きょう‐おう【経王】キヤウワウ🔗⭐🔉
きょう‐おう【経王】キヤウワウ
経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。
きょう‐がわら【経瓦】キヤウガハラ🔗⭐🔉
きょう‐がわら【経瓦】キヤウガハラ
(→)瓦経かわらぎょうに同じ。
きょう‐かん【経巻】キヤウクワン🔗⭐🔉
きょう‐かん【経巻】キヤウクワン
経文を記した巻物。
きょう‐き【経軌】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょう‐き【経軌】キヤウ‥
〔仏〕密教の経典と儀軌ぎき。
きょう‐ぎょう【経教】キヤウゲウ🔗⭐🔉
きょう‐ぎょう【経教】キヤウゲウ
〔仏〕経典に示された教え。今昔物語集5「―にもよろづの物の譬には亀鶴を以て譬へたり」
きょう‐くよう【経供養】キヤウ‥ヤウ🔗⭐🔉
きょう‐くよう【経供養】キヤウ‥ヤウ
経文を書写した際に行う仏事。
きょう‐づくえ【経机】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょう‐づくえ【経机】キヤウ‥
仏前で読経の時、経文をのせておく机。多くは4脚で黒または朱の漆塗り、端を金具で飾る。
経机
撮影:関戸 勇


きょう‐の‐まき【経の巻】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょう‐の‐まき【経の巻】キヤウ‥
屋根の棟にある獅子口ししぐちの上にのせた、経巻に似た円筒形の瓦。
きょう‐ばい【経唄】キヤウ‥🔗⭐🔉
きょう‐ばい【経唄】キヤウ‥
経文を節をつけてよむこと。今昔物語集7「―の声を聞く毎に」
きん‐ひん【経行】🔗⭐🔉
きん‐ひん【経行】
(宋の俗音)〔仏〕
①歩く動作を一つずつ覚知する禅行の一つ。
②坐禅中に眠気を防ぐため、または運動のため、一定のところをめぐったり往復したりすること。きょうぎょう。
けい‐い【経緯】‥ヰ🔗⭐🔉
けい‐い【経緯】‥ヰ
①たて糸とよこ糸。たてとよこ。
②南北と東西。経線と緯線。経度と緯度。
③秩序を立てて治めととのえること。
④いきさつ。入りくんだ事情。物事がこれまで展開してきたすじ道。「事件の―を説明する」
⇒けいい‐ぎ【経緯儀】
けい‐えい【経営】🔗⭐🔉
けい‐えい【経営】
①力を尽くして物事を営むこと。工夫を凝らして建物などを造ること。太平記11「偏に後生菩提の―を」。平家物語7「多日の―をむなしうして片時の灰燼となりはてぬ」
②あれこれと世話や準備をすること。忙しく奔走すること。今昔物語集26「房主ぼうずの僧、思ひ懸けずと云ひて―す」。滑稽本、医者談義「医学修行に諸国―して」
③継続的・計画的に事業を遂行すること。特に、会社・商業など経済的活動を運営すること。また、そのための組織。「会社を―する」「―が行き詰まる」「多角―」
→けいめい。
⇒けいえい‐がく【経営学】
⇒けいえい‐かんり【経営管理】
⇒けいえい‐きょうぎかい【経営協議会】
⇒けいえい‐けいざいがく【経営経済学】
⇒けいえい‐けん【経営権】
⇒けいえい‐こうがく【経営工学】
⇒けいえい‐さんか【経営参加】
⇒けいえい‐しゃ【経営者】
⇒けいえい‐せんりゃく【経営戦略】
⇒けいえい‐ビジョン【経営ビジョン】
⇒けいえい‐ぶんせき【経営分析】
⇒けいえい‐りねん【経営理念】
⇒けいえい‐りんり【経営倫理】
けいえい‐がく【経営学】🔗⭐🔉
けいえい‐がく【経営学】
企業経営の経済的・技術的・人間的諸側面を研究する学問。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐かんり【経営管理】‥クワン‥🔗⭐🔉
けいえい‐かんり【経営管理】‥クワン‥
企業の目的を達成するために、経営者・管理者が総括する全般的な管理。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐きょうぎかい【経営協議会】‥ケフ‥クワイ🔗⭐🔉
けいえい‐きょうぎかい【経営協議会】‥ケフ‥クワイ
①(→)工場委員会に同じ。
②日本では、団体交渉事項以外の経営諸問題に関する使用者と労働組合の意思疎通機関で、経営参加の一形態。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐けいざいがく【経営経済学】🔗⭐🔉
けいえい‐けいざいがく【経営経済学】
個別経済、特に企業の価値増殖過程を研究する学問。経営学の一分野。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐けん【経営権】🔗⭐🔉
けいえい‐けん【経営権】
企業者が自らその企業組織を専断的に管理経営する権利。所有権の作用のうちに内包する一機能とみなして、労働者の経営参加要求に対して、使用者により主張されるもの。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐こうがく【経営工学】🔗⭐🔉
けいえい‐こうがく【経営工学】
企業などの経営体の運営に関わる業務を工学的見地から研究する学問の領域。市場予測・生産計画・意志決定などの問題を主に数理的手法を用いて研究する。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐さんか【経営参加】🔗⭐🔉
けいえい‐さんか【経営参加】
労働者または労働組合が経営の意思決定に参加すること。団体交渉・労使協議制・労働者重役制・利潤分配制度などの方式がある。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐しゃ【経営者】🔗⭐🔉
けいえい‐しゃ【経営者】
企業を経営する人。雇用関係からは使用者に同じ。所有と経営との分離していない企業にあっては、資本家・企業家などと同義。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐せんりゃく【経営戦略】🔗⭐🔉
けいえい‐せんりゃく【経営戦略】
外部に対して、企業が効果的に適応するための基本的な方針・方策。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐ビジョン【経営ビジョン】🔗⭐🔉
けいえい‐ビジョン【経営ビジョン】
企業のあるべき将来像に対する構想ないし願望。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐ぶんせき【経営分析】🔗⭐🔉
けいえい‐ぶんせき【経営分析】
貸借対照表・損益計算書などの財務諸表を材料として会社の収益力・資産内容など経営状態を判断すること。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐りねん【経営理念】🔗⭐🔉
けいえい‐りねん【経営理念】
企業経営における基本的な価値観・精神・信念あるいは行動基準を表明したもの。
⇒けい‐えい【経営】
けいえい‐りんり【経営倫理】🔗⭐🔉
けいえい‐りんり【経営倫理】
(→)企業倫理に同じ。
⇒けい‐えい【経営】
けい‐か【経過】‥クワ🔗⭐🔉
けい‐か【経過】‥クワ
①(時間が)過ぎゆくこと。「10秒―した」
②物事のうつりゆく状態。なりゆき。「術後の―は良好」「試合の途中―」
③太陽面を内惑星・彗星などの天体が通り過ぎる現象。また、惑星面をその衛星が通過すること。
⇒けいか‐ほう【経過法】
⇒けいか‐りし【経過利子】
けい‐かい【経回】‥クワイ🔗⭐🔉
けい‐かい【経回】‥クワイ
(ケイガイとも)
①へめぐり歩くこと。平家物語11「京都の―難治の間身を在々所々にかくし」
②生存して歳月を過ごすこと。源平盛衰記41「頼朝世に―せば、御方に奉公仕りて」
けい‐かい【境界・経界】🔗⭐🔉
けい‐かい【境界・経界】
地所の境。くぎり。しきり。きょうかい。
けい‐がく【経学】🔗⭐🔉
けい‐がく【経学】
四書・五経などの経書けいしょを研究する学問。
けいか‐ほう【経過法】‥クワハフ🔗⭐🔉
けいか‐ほう【経過法】‥クワハフ
法令の制定・改廃があった場合、旧法から新法への移行に必要な経過的措置を定めた法。時際法。経過規定。
⇒けい‐か【経過】
けいか‐りし【経過利子】‥クワ‥🔗⭐🔉
けいか‐りし【経過利子】‥クワ‥
債券を売買する場合、その受渡しの際に、前回の利払日以後受渡し当日までに経過した日数に応じて日割計算し、買方から売方へ支払う利子。
⇒けい‐か【経過】
けい‐かん【経巻】‥クワン🔗⭐🔉
けい‐かん【経巻】‥クワン
聖人のあらわした書物。経書。経典。経籍。
けい‐き【経紀】🔗⭐🔉
けい‐き【経紀】
①のり。みち。綱紀。また、のりを定め法を立てること。
②経営すること。
③(経理・経営の意)中国で、仲買人。商人。
けい‐ぎ【経義】🔗⭐🔉
けい‐ぎ【経義】
①経書の意味。経書の説く道。
②経書の解釈。また、経書の解釈をした書物。
③官吏登用試験に経書の中の文を題として作らせる文。
けいぎこう【経義考】‥カウ🔗⭐🔉
けいぎこう【経義考】‥カウ
経書の注釈書を網羅した目録・解題の書。清の朱彝尊しゅいそん撰。300巻。清の翁方綱はその補正「経義考補正」12巻を著す。
けい‐くん【経訓】🔗⭐🔉
けい‐くん【経訓】
経書けいしょの訓解。経書の解釈。
けい‐げい【経芸】🔗⭐🔉
けい‐げい【経芸】
①(六経を六芸とも称するから)六経りくけいのこと。
②経書に関する学問。経学。経術。
けい‐けつ【経穴】🔗⭐🔉
けい‐けつ【経穴】
灸を点じ鍼はりを打つべき身体の箇所。全身に数百カ所あり、経絡けいらくの要所に当たり、病気の診断と治療の対象点とされる。つぼ。
けい‐けん【経験】🔗⭐🔉
けい‐けん【経験】
(experience)
①人間が外界との相互作用の過程を意識化し自分のものとすること。人間のあらゆる個人的・社会的実践を含むが、人間が外界を変革するとともに自己自身を変化させる活動が基本的なもの。馬場辰猪、思想ノ説「之ヲ―スルヤ必ズ自ラ進デ其ノ事物ニ当ラザル可ラズ」
㋐外的あるいは内的な現実との直接的接触。
㋑認識として未だ組織化されていない、事実の直接的把握。
㋒何事かに直接ぶつかる場合、それが何らかの意味で自己を豊かにするという意味を含むこと。「得がたい―」
㋓何事かに直接にぶつかり、そこから技能・知識を得ること。「―を積む」
②〔哲〕感覚・知覚から始まって、道徳的行為や知的活動までを含む体験の自覚されたもの。
⇒けいけん‐かがく【経験科学】
⇒けいけん‐がくしゅう【経験学習】
⇒けいけん‐カリキュラム【経験カリキュラム】
⇒けいけん‐しゃ【経験者】
⇒けいけん‐しゅぎ【経験主義】
⇒けいけん‐そく【経験則】
⇒けいけん‐ち【経験値】
⇒けいけん‐てき【経験的】
⇒けいけんてき‐がいねん【経験的概念】
⇒けいけんてき‐ほうそく【経験的法則】
⇒けいけん‐ひはんろん【経験批判論】
⇒けいけん‐ろん【経験論】
けいけん‐かがく【経験科学】‥クワ‥🔗⭐🔉
けいけん‐かがく【経験科学】‥クワ‥
対象をありのままに観察・記述・分析し、対象の法則性・説明原理を導出しようとする学問。実証的諸科学を指す。
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐がくしゅう【経験学習】‥シフ🔗⭐🔉
けいけん‐がくしゅう【経験学習】‥シフ
児童・生徒の生活経験を重視し、これを基礎として行う学習。生活学習。↔系統学習。
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐カリキュラム【経験カリキュラム】🔗⭐🔉
けいけん‐カリキュラム【経験カリキュラム】
生活経験を重んじ、その発展を中心として編成する教育課程。
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐しゃ【経験者】🔗⭐🔉
けいけん‐しゃ【経験者】
それをすでに経験した人。「―は語る」「学識―」
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐しゅぎ【経験主義】🔗⭐🔉
けいけん‐しゅぎ【経験主義】
①(→)経験論に同じ。
②物事を、経験に基づいて判断しようとする態度。
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐そく【経験則】🔗⭐🔉
けいけん‐そく【経験則】
(→)経験的法則に同じ。
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐ち【経験値】🔗⭐🔉
けいけん‐ち【経験値】
これまでの経験から推測して得られる値。
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐てき【経験的】🔗⭐🔉
けいけん‐てき【経験的】
経験に基づくさま。「―事実」
⇒けい‐けん【経験】
けいけんてき‐がいねん【経験的概念】🔗⭐🔉
けいけんてき‐がいねん【経験的概念】
(empirical concept)純粋概念に対して、経験の抽象によって得られる概念。「花」「人」「動物」の類。
⇒けい‐けん【経験】
けいけんてき‐ほうそく【経験的法則】‥ハフ‥🔗⭐🔉
けいけんてき‐ほうそく【経験的法則】‥ハフ‥
経験的事実に基づいて得られた法則。
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐ひはんろん【経験批判論】🔗⭐🔉
けいけん‐ひはんろん【経験批判論】
(Empiriokritizismus ドイツ)ドイツの哲学者アヴェナリウス(R. Avenarius1843〜1896)の認識説。経験から個人的要素や形而上学的仮定を排除した純粋経験によって世界を説明しようとするもの。この純粋経験には主・客の対立はないから、唯物論・観念論の対立をこえたものと主張したが、純粋経験とは感覚的所与であり、それから独立的な対象を認めない点において、一種の主観的観念論である。これと類似するマッハの説もこの名で呼ぶことがある。
⇒けい‐けん【経験】
けいけん‐ろん【経験論】🔗⭐🔉
けいけん‐ろん【経験論】
(empiricism)認識の源泉をもっぱら経験に求める哲学説。代表的なものは17〜18世紀のイギリス経験論(F.ベーコン・ロック・バークリー・ヒューム)であり、一切の観念は感覚的経験から生ずるとして、生得観念を否定した。経験主義。↔理性論
⇒けい‐けん【経験】
けい‐こう【経口】🔗⭐🔉
けい‐こう【経口】
口を通して体内に入ること。薬剤などを口から与えること。「―ワクチン」
⇒けいこう‐かんせん【経口感染】
⇒けいこう‐どくせい【経口毒性】
⇒けいこう‐ひにんやく【経口避妊薬】
⇒けいこう‐めんえき【経口免疫】
けい‐こう【経行】‥カウ🔗⭐🔉
けい‐こう【経行】‥カウ
①へめぐり行くこと。経過すること。
②月経。経水。
けいこう‐かんせん【経口感染】🔗⭐🔉
けいこう‐かんせん【経口感染】
飲食物などを介し、口から病原体が体内に侵入すること。
⇒けい‐こう【経口】
けいこう‐どくせい【経口毒性】🔗⭐🔉
けいこう‐どくせい【経口毒性】
農薬などの化学物質の経口投与によって生体に発現する毒性。
⇒けい‐こう【経口】
○鶏口となるも牛後となるなかれけいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ
[戦国策韓策]小さい集団であってもその中で長となる方が、大きな集団の中でしりに付き従う者となるより良い、という意。
⇒けい‐こう【鶏口】
けいこう‐ひにんやく【経口避妊薬】🔗⭐🔉
けいこう‐ひにんやく【経口避妊薬】
服用によって避妊をはかる錠剤。卵胞ホルモン・黄体ホルモンを含み、排卵を抑制する効がある。俗称、ピル。
⇒けい‐こう【経口】
けいこう‐めんえき【経口免疫】🔗⭐🔉
けいこう‐めんえき【経口免疫】
内服ワクチンの服用によって、免疫を得ること。小児麻痺(ポリオ)などの予防に応用。
⇒けい‐こう【経口】
けい‐こく【経国】🔗⭐🔉
けい‐こく【経国】
国家を経営すること。国を治めること。「―済民」
けいこくしゅう【経国集】‥シフ🔗⭐🔉
けいこくしゅう【経国集】‥シフ
平安時代の勅撰漢詩文集。20巻。良岑よしみね安世らが827年(天長4)撰進。文武天皇から淳和天皇まで、707(慶雲4)〜827年の作を収め、日本で最初の詩文総集。6巻だけ現存。
けいこくびだん【経国美談】🔗⭐🔉
けいこくびだん【経国美談】
政治小説。矢野竜渓作。前編1883年(明治16)、後編84年刊。自由民権論を鼓吹するために書いたもの。テーベのエパミノンダスやペロピダスが国威を輝かした史実を潤色。
→文献資料[経国美談]
けい‐ざい【経済】🔗⭐🔉
けい‐ざい【経済】
①[文中子礼楽]国を治め人民を救うこと。経国済民。政治。
②(economy)人間の共同生活の基礎をなす財・サービスの生産・分配・消費の行為・過程、ならびにそれを通じて形成される人と人との社会関係の総体。転じて、金銭のやりくり。→理財。
③費用・手間のかからないこと。倹約。「時間の―をはかる」
⇒けいざい‐あんてい‐きゅうげんそく【経済安定九原則】
⇒けいざい‐あんてい‐ほんぶ【経済安定本部】
⇒けいざい‐か【経済家】
⇒けいざい‐かい【経済界】
⇒けいざいがいてき‐きょうせい【経済外的強制】
⇒けいざい‐がく【経済学】
⇒けいざい‐かんねん【経済観念】
⇒けいざい‐きかく‐ちょう【経済企画庁】
⇒けいざい‐きょうりょく【経済協力】
⇒けいざい‐きょうりょく‐かいはつ‐きこう【経済協力開発機構】
⇒けいざい‐けいさつ【経済警察】
⇒けいざい‐げんそく【経済原則】
⇒けいざい‐こうい【経済行為】
⇒けいざい‐こうか【経済効果】
⇒けいざい‐ざい【経済財】
⇒けいざい‐ざいせい‐はくしょ【経済財政白書】
⇒けいざい‐さんぎょう‐しょう【経済産業省】
⇒けいざい‐さんぎょう‐だいじん【経済産業大臣】
⇒けいざい‐し【経済史】
⇒けいざい‐しゃかい‐りじかい【経済社会理事会】
⇒けいざい‐しゅぎ【経済主義】
⇒けいざい‐じん【経済人】
⇒けいざい‐しんぎ‐ちょう【経済審議庁】
⇒けいざい‐じんるいがく【経済人類学】
⇒けいざい‐すいいき【経済水域】
⇒けいざい‐せい【経済性】
⇒けいざい‐せいさく【経済政策】
⇒けいざい‐せいちょう【経済成長】
⇒けいざい‐せいちょうりつ【経済成長率】
⇒けいざい‐たんい【経済単位】
⇒けいざい‐だんたい‐れんごうかい【経済団体連合会】
⇒けいざい‐ちりがく【経済地理学】
⇒けいざい‐てき【経済的】
⇒けいざい‐とうけい【経済統計】
⇒けいざい‐とうせい【経済統制】
⇒けいざい‐とうそう【経済闘争】
⇒けいざい‐どうゆうかい【経済同友会】
⇒けいざい‐とっく【経済特区】
⇒けいざい‐はくしょ【経済白書】
⇒けいざい‐ふうさ【経済封鎖】
⇒けいざい‐ブロック【経済ブロック】
⇒けいざい‐ほう【経済法】
⇒けいざい‐めん【経済面】
⇒けいざい‐よそく【経済予測】
けいざい‐あんてい‐きゅうげんそく【経済安定九原則】‥キウ‥🔗⭐🔉
けいざい‐あんてい‐きゅうげんそく【経済安定九原則】‥キウ‥
1948年にアメリカ政府がGHQを通じて日本政府に実施を命じた、9項目からなる経済・財政方針。冷戦下において日本の経済復興を早めるために経費削減・財政均衡を要求。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐あんてい‐ほんぶ【経済安定本部】🔗⭐🔉
けいざい‐あんてい‐ほんぶ【経済安定本部】
第二次大戦直後に経済安定の基本政策や緊急施策の企画立案、物価の統制などを担当した内閣総理大臣直轄の行政機関。1946年創設、52年経済審議庁に改組、55年経済企画庁と改称。略称、安本あんぽん。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐か【経済家】🔗⭐🔉
けいざい‐か【経済家】
①経済の道に明るい人。
②上手に費用を節約する人。また、何でも節約する人。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐かい【経済界】🔗⭐🔉
けいざい‐かい【経済界】
①社会の中で、経済的交渉が活発に行われる範囲。
②実業家の社会。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざいがいてき‐きょうせい【経済外的強制】‥グワイ‥キヤウ‥🔗⭐🔉
けいざいがいてき‐きょうせい【経済外的強制】‥グワイ‥キヤウ‥
(ausserökonomischer Zwang ドイツ)封建的土地所有者が農民から封建地代を徴収するために直接的な強制力を行使すること。領主裁判権と武力を背景とする身分的支配および土地への緊縛などを通じて行われた。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐がく【経済学】🔗⭐🔉
けいざい‐がく【経済学】
(economics; political economy)経済現象を研究する学問。旧称、理財学。斎藤緑雨、唯我「抑そもそも―とは富を造ると説始ときはじめられて」
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐かんねん【経済観念】‥クワン‥🔗⭐🔉
けいざい‐かんねん【経済観念】‥クワン‥
経済に関する考え。金銭を効率的に使い、うまくやりくりしようとする考え。「―のない人」
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐きかく‐ちょう【経済企画庁】‥クワクチヤウ🔗⭐🔉
けいざい‐きかく‐ちょう【経済企画庁】‥クワクチヤウ
長期経済計画の策定、経済に関する基本的な政策の総合調整、内外の経済動向および国民所得などに関する調査・分析などを任務とした旧総理府の外局。1955年に経済審議庁を改組し設置されたが、2001年に廃止。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐きょうりょく【経済協力】‥ケフ‥🔗⭐🔉
けいざい‐きょうりょく【経済協力】‥ケフ‥
政府資金による政府開発援助(ODA)その他の援助のほか、民間資金による直接投資・貸付・延払い輸出信用等の形態での他国に対する資金の流れ。民間非営利団体による資金・技術の供与も含まれる。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐きょうりょく‐かいはつ‐きこう【経済協力開発機構】‥ケフ‥🔗⭐🔉
けいざい‐きょうりょく‐かいはつ‐きこう【経済協力開発機構】‥ケフ‥
⇒オー‐イー‐シー‐ディー(OECD)。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐けいさつ【経済警察】🔗⭐🔉
けいざい‐けいさつ【経済警察】
①経済統制法違反を取り締まるため、戦時中に設けた特別の警察組織。
②経済生活に監督・取締りをする警察作用。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐げんそく【経済原則】🔗⭐🔉
けいざい‐げんそく【経済原則】
最小の費用によって最大の効果をあげるという原則。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐こうい【経済行為】‥カウヰ🔗⭐🔉
けいざい‐こうい【経済行為】‥カウヰ
生産や交換によって財貨を調達し、消費する行為。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐こうか【経済効果】‥カウクワ🔗⭐🔉
けいざい‐こうか【経済効果】‥カウクワ
ある出来事や催しが経済に及ぼす効果。特に、それによって新規に見込まれる需要。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐ざい【経済財】🔗⭐🔉
けいざい‐ざい【経済財】
財のうち、それを手に入れるために対価を必要とするもの。↔自由財。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐ざいせい‐はくしょ【経済財政白書】🔗⭐🔉
けいざい‐ざいせい‐はくしょ【経済財政白書】
国民経済を総合的に分析し、経済・財政の動向と政策の方向を示唆する年次報告書。1947年より経済企画庁(当時は経済安定本部)が「経済白書」として発表。2001年現名称となり、以降内閣府が発表。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐さんぎょう‐しょう【経済産業省】‥ゲフシヤウ🔗⭐🔉
けいざい‐さんぎょう‐しょう【経済産業省】‥ゲフシヤウ
経済および産業の発展、エネルギーの確保等を任務とする中央行政機関。経済産業大臣を長とする。2001年設置。通商産業省が前身。経産省。
⇒けい‐ざい【経済】
けいざい‐ブロック【経済ブロック】🔗⭐🔉
けいざい‐ブロック【経済ブロック】
いくつかの国が共通の経済的な目的を達成するためにつくり上げた排他的性格の経済圏。ポンド‐ブロックの類。
⇒けい‐ざい【経済】
けい‐めい【経営】🔗⭐🔉
けい‐めい【経営】
(ケイエイの転か)
①あれこれとしつらえること。かけまわって世話をすること。源氏物語夕顔「大殿も―し給ひて…様々の事をせさせ給ふ験にや」
②もてなし。ごちそう。増鏡「今日は院の御―にて」
た・つ【経つ】🔗⭐🔉
た・つ【経つ】
〔自五〕
⇒たつ(立)[一]➑2
たて【縦・竪・経】🔗⭐🔉
たて【縦・竪・経】
①上から下への方向、また長さ。「―書き」
②前から後ろの方向、また長さ。「―に並ぶ」↔横。
③細長い物の長い方向、また長さ。「材木を―に切る」
④南北の方向、また距離。
⑤「たて糸」の略。万葉集8「―もなく緯ぬきも定めず」↔緯ぬき。
⑥年齢・身分の上下の関係。「―社会」
⇒縦の物を横にもしない
たて‐いと【経・縦糸】🔗⭐🔉
たて‐いと【経・縦糸】
織物の、織機に向かって縦方向に通っている糸。緯よこいとの上または下となり、多くはこれと直角に組み合う。たて。↔緯
たて‐にしき【経錦】🔗⭐🔉
たて‐ぬき【経緯】🔗⭐🔉
たて‐ぬき【経緯】
機はたの経糸たていとと緯糸ぬきいと。たてよこ。万葉集7「苔むしろ誰か織りけむ―無しに」
たて‐まき【経巻】🔗⭐🔉
たて‐まき【経巻】
織物製造における準備工程。整経せいけいした経たて糸を織機の榺ちきりに巻きつけること。
たて‐よこ【経緯】🔗⭐🔉
たて‐よこ【経緯】
経たて糸と緯よこ糸。たてぬき。
⇒たてよこ‐ちりめん【経緯縮緬】
たてよこ‐ちりめん【経緯縮緬】🔗⭐🔉
たてよこ‐ちりめん【経緯縮緬】
経糸・緯糸ともに強撚糸を用いた縮緬。ジョーゼット。
⇒たて‐よこ【経緯】
へ‐めぐ・る【経回る・歴回る】🔗⭐🔉
へ‐めぐ・る【経回る・歴回る】
〔自五〕
方々をめぐりあるく。旅行して国々をめぐる。遍歴する。
へる【経る・歴る】🔗⭐🔉
へる【経る・歴る】
〔自下一〕[文]ふ(下二)
次々に順をふんで行く意。
①時が経つ。経過する。雄略紀「栄枝を五百ふる析かきて」。万葉集17「矢形尾の鷹を手にすゑ三島野に狩らぬ日まねく月そへにける」
②時をすごす。月日を送る。大鏡実頼「この、日の荒れて日ごろここにへ給ふはおのれがし侍ることなり」。天草本平家物語「日数をふれば、能登の国に着かせられた」
③その過程を通る。地位や段階を経験する。源平盛衰記1「太政大臣にあがる。左右をへずして此の位に至ること…先蹤なし」。「秘書をへて議員になる」「数多の困難をへる」
④そこを通って他へ行く。通過する。平家物語8「狩衣の頸かみに針を刺し、賤の緒環おだまきといふ物をつけてへて行く方をつないで行けば」。源平盛衰記32「伏見をへて京へ入る」。「多くの人の手をへる」
⑤順次、手続をふむ。通す。平家物語(延慶本)「奏聞をへられけるに」。日葡辞書「アンナイヲヘル」
わな・く【縊く・経く】🔗⭐🔉
わな・く【縊く・経く】
〔自他四〕
(ワナ(羂)の動詞化)くびをくくる。くびる。皇極紀(岩崎本)平安中期点「一時もろともに自ら経ワナキて倶に死ぬ」
[漢]経🔗⭐🔉
経 字形
 筆順
筆順
 〔糸部5画/11画/教育/2348・3750〕
[經] 字形
〔糸部5画/11画/教育/2348・3750〕
[經] 字形
 〔糸部7画/13画/6920・6534〕
〔音〕ケイ(漢) キョウ〈キャウ〉(呉) キン(唐)
〔訓〕へる・たつ (名)つね
[意味]
①織物のたていと。(対)緯。「経緯」
②たて。南北の方向。(対)緯。「経度・経線・東経」
③すじ。すじみち。「経絡・神経・経界」
④(すじが通って)変わらない。一定。つね。「経常・経費」
⑤儒教・仏教などの不変の道理(を説いた書物)。「門前の小僧、習わぬ経きょうを読む」「経書・経典けいてん・きょうてん・四書五経ごきょう・読経どきょう・看経かんきん」
⑥すじみちをつける。治める。管理する。「経営・経理・経国・経世・経綸けいりん」
⑦ヘる。そこを通り過ぎる。時間がたつ。「経過・経由・経路・経験」
⑧首をくくる。「自経」
[解字]
形声。右半部「
〔糸部7画/13画/6920・6534〕
〔音〕ケイ(漢) キョウ〈キャウ〉(呉) キン(唐)
〔訓〕へる・たつ (名)つね
[意味]
①織物のたていと。(対)緯。「経緯」
②たて。南北の方向。(対)緯。「経度・経線・東経」
③すじ。すじみち。「経絡・神経・経界」
④(すじが通って)変わらない。一定。つね。「経常・経費」
⑤儒教・仏教などの不変の道理(を説いた書物)。「門前の小僧、習わぬ経きょうを読む」「経書・経典けいてん・きょうてん・四書五経ごきょう・読経どきょう・看経かんきん」
⑥すじみちをつける。治める。管理する。「経営・経理・経国・経世・経綸けいりん」
⑦ヘる。そこを通り過ぎる。時間がたつ。「経過・経由・経路・経験」
⑧首をくくる。「自経」
[解字]
形声。右半部「 」は音符で、織機の台の上に糸を縦にまっすぐに張ったわくを置いた形を描いたもの。「糸」を加えて、織物のたて糸の意。
[下ツキ
看経かんきん・月経・五経・持経・自経・写経・初経・神経・誦経・西経・説経・石経・大蔵経・東経・読経・念経・納経・六経
」は音符で、織機の台の上に糸を縦にまっすぐに張ったわくを置いた形を描いたもの。「糸」を加えて、織物のたて糸の意。
[下ツキ
看経かんきん・月経・五経・持経・自経・写経・初経・神経・誦経・西経・説経・石経・大蔵経・東経・読経・念経・納経・六経
 筆順
筆順
 〔糸部5画/11画/教育/2348・3750〕
[經] 字形
〔糸部5画/11画/教育/2348・3750〕
[經] 字形
 〔糸部7画/13画/6920・6534〕
〔音〕ケイ(漢) キョウ〈キャウ〉(呉) キン(唐)
〔訓〕へる・たつ (名)つね
[意味]
①織物のたていと。(対)緯。「経緯」
②たて。南北の方向。(対)緯。「経度・経線・東経」
③すじ。すじみち。「経絡・神経・経界」
④(すじが通って)変わらない。一定。つね。「経常・経費」
⑤儒教・仏教などの不変の道理(を説いた書物)。「門前の小僧、習わぬ経きょうを読む」「経書・経典けいてん・きょうてん・四書五経ごきょう・読経どきょう・看経かんきん」
⑥すじみちをつける。治める。管理する。「経営・経理・経国・経世・経綸けいりん」
⑦ヘる。そこを通り過ぎる。時間がたつ。「経過・経由・経路・経験」
⑧首をくくる。「自経」
[解字]
形声。右半部「
〔糸部7画/13画/6920・6534〕
〔音〕ケイ(漢) キョウ〈キャウ〉(呉) キン(唐)
〔訓〕へる・たつ (名)つね
[意味]
①織物のたていと。(対)緯。「経緯」
②たて。南北の方向。(対)緯。「経度・経線・東経」
③すじ。すじみち。「経絡・神経・経界」
④(すじが通って)変わらない。一定。つね。「経常・経費」
⑤儒教・仏教などの不変の道理(を説いた書物)。「門前の小僧、習わぬ経きょうを読む」「経書・経典けいてん・きょうてん・四書五経ごきょう・読経どきょう・看経かんきん」
⑥すじみちをつける。治める。管理する。「経営・経理・経国・経世・経綸けいりん」
⑦ヘる。そこを通り過ぎる。時間がたつ。「経過・経由・経路・経験」
⑧首をくくる。「自経」
[解字]
形声。右半部「 」は音符で、織機の台の上に糸を縦にまっすぐに張ったわくを置いた形を描いたもの。「糸」を加えて、織物のたて糸の意。
[下ツキ
看経かんきん・月経・五経・持経・自経・写経・初経・神経・誦経・西経・説経・石経・大蔵経・東経・読経・念経・納経・六経
」は音符で、織機の台の上に糸を縦にまっすぐに張ったわくを置いた形を描いたもの。「糸」を加えて、織物のたて糸の意。
[下ツキ
看経かんきん・月経・五経・持経・自経・写経・初経・神経・誦経・西経・説経・石経・大蔵経・東経・読経・念経・納経・六経
大辞林の検索結果 (99)
いき-さつ【経緯】🔗⭐🔉
いき-さつ [0] 【経緯】
物事の経過。また,込み入った事情。「事件の―を説明する」
きょう【経】🔗⭐🔉
きょう キヤウ [0] 【経】
□一□〔仏〕
〔梵 s tra〕
(1)仏の教えを記した文章。仏の説いた言葉をそのまま伝えるという形式をとる。三蔵の一。契経(カイキヨウ)。
(2)十二分経の一。経のうち,散文で記された部分のこと。契経。
(3)仏教に関する文献の総称。{(1)}に論と律を加えたもの。
□二□仏教以外の宗教の聖典。
tra〕
(1)仏の教えを記した文章。仏の説いた言葉をそのまま伝えるという形式をとる。三蔵の一。契経(カイキヨウ)。
(2)十二分経の一。経のうち,散文で記された部分のこと。契経。
(3)仏教に関する文献の総称。{(1)}に論と律を加えたもの。
□二□仏教以外の宗教の聖典。
 tra〕
(1)仏の教えを記した文章。仏の説いた言葉をそのまま伝えるという形式をとる。三蔵の一。契経(カイキヨウ)。
(2)十二分経の一。経のうち,散文で記された部分のこと。契経。
(3)仏教に関する文献の総称。{(1)}に論と律を加えたもの。
□二□仏教以外の宗教の聖典。
tra〕
(1)仏の教えを記した文章。仏の説いた言葉をそのまま伝えるという形式をとる。三蔵の一。契経(カイキヨウ)。
(2)十二分経の一。経のうち,散文で記された部分のこと。契経。
(3)仏教に関する文献の総称。{(1)}に論と律を加えたもの。
□二□仏教以外の宗教の聖典。
きょう-え【経衣】🔗⭐🔉
きょう-え キヤウ― [1] 【経衣】
「経帷子(キヨウカタビラ)」に同じ。
きょう-おう【経王】🔗⭐🔉
きょう-おう キヤウワウ [3] 【経王】
経典中最高のもの。多く法華経・大般若経・最勝王経をいう。
きょう-が-しま【経が島】🔗⭐🔉
きょう-が-しま キヤウ― 【経が島】
〔平清盛が一切経を記した石を埋めて工事をしたことから〕
神戸市兵庫区にある,兵庫港築造の際防波堤として造った島。経の島。
きょう-がわら【経瓦】🔗⭐🔉
きょう-がわら キヤウガハラ [3] 【経瓦】
経文を刻みつけて経塚に埋納する瓦。平安中期・末期のものが多い。瓦経。
きょう-かん【経巻】🔗⭐🔉
きょう-かん キヤウクワン [0] 【経巻】
経文を書いた巻物。また,経典。
きょう-ぎょう【経行】🔗⭐🔉
きょう-ぎょう キヤウギヤウ [0] 【経行】
〔仏〕 食後や修行の合間,疲れや眠けをとるために一定の場所をゆっくり歩くこと。禅宗では「きんひん」と読む。
きょう-ぎょう【経教】🔗⭐🔉
きょう-ぎょう キヤウゲウ 【経教】
仏教の経典に示された教え。「仏の御名を唱へ,―の文を習ひ/盛衰記 48」
きょう-くよう【経供養】🔗⭐🔉
きょう-くよう キヤウクヤウ [3] 【経供養】
(1)経を書写して仏前に供え,仏事を行うこと。「法花経千部いそぎて―し給ふ/源氏(御法)」
(2)陰暦三月二日,大阪四天王寺の太子夢殿において行われた法会。
きょう-づくえ【経机】🔗⭐🔉
きょう-づくえ キヤウ― [3] 【経机】
読経(ドキヨウ)の際,経の本・経の巻き物を載せる机。経卓。経案。
経机
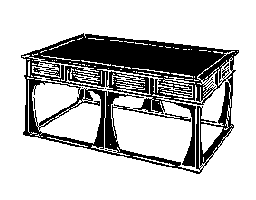 [図]
[図]
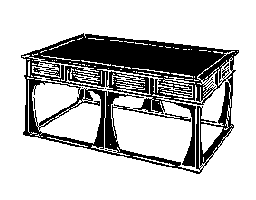 [図]
[図]
きょう-の-まき【経の巻】🔗⭐🔉
きょう-の-まき キヤウ― 【経の巻】
棟飾りの獅子口(シシグチ)の上に三つあるいは五つ並べて置かれる,巻物に似た形の瓦。
きん-ひん【経行】🔗⭐🔉
きん-ひん 【経行】
〔唐音〕
禅宗で,座禅中の疲れや,眠気をとるために一定の場所を歩くこと。きょうぎょう。「古往の聖人,おほく樹下露地に―す/正法眼蔵」
けい【経】🔗⭐🔉
けい [1] 【経】
(1)織物の経(タテ)糸。また,縦。
(2)正しい筋道。正しい道理。
(3)経書(ケイシヨ)。経典(ケイテン)。
けい-い【経緯】🔗⭐🔉
けい-い ― [1] 【経緯】 (名)スル
(1)織物の経(タテ)糸と緯(ヨコ)糸。たてとよこ。
(2)南北の方向と東西の方向。また,地球の経度と緯度。
(3)物事の入り組んだ事情。いきさつ。「事件の―を聞く」
(4)秩序を立てて治めること。治め整える根本となる道理。経営。「之を―するに官撰の議員を以てすべし/明六雑誌 29」
[1] 【経緯】 (名)スル
(1)織物の経(タテ)糸と緯(ヨコ)糸。たてとよこ。
(2)南北の方向と東西の方向。また,地球の経度と緯度。
(3)物事の入り組んだ事情。いきさつ。「事件の―を聞く」
(4)秩序を立てて治めること。治め整える根本となる道理。経営。「之を―するに官撰の議員を以てすべし/明六雑誌 29」
 [1] 【経緯】 (名)スル
(1)織物の経(タテ)糸と緯(ヨコ)糸。たてとよこ。
(2)南北の方向と東西の方向。また,地球の経度と緯度。
(3)物事の入り組んだ事情。いきさつ。「事件の―を聞く」
(4)秩序を立てて治めること。治め整える根本となる道理。経営。「之を―するに官撰の議員を以てすべし/明六雑誌 29」
[1] 【経緯】 (名)スル
(1)織物の経(タテ)糸と緯(ヨコ)糸。たてとよこ。
(2)南北の方向と東西の方向。また,地球の経度と緯度。
(3)物事の入り組んだ事情。いきさつ。「事件の―を聞く」
(4)秩序を立てて治めること。治め整える根本となる道理。経営。「之を―するに官撰の議員を以てすべし/明六雑誌 29」
けいい-ぎ【経緯儀】🔗⭐🔉
けいい-ぎ ― ― [3] 【経緯儀】
望遠鏡を垂直および水平の二つの回転軸で支えた形式の角度測定装置。水準器を備え,かつ各回転軸に目盛りを刻んだもので,天体の位置測定や地上の測量に使用される。セオドライト。
― [3] 【経緯儀】
望遠鏡を垂直および水平の二つの回転軸で支えた形式の角度測定装置。水準器を備え,かつ各回転軸に目盛りを刻んだもので,天体の位置測定や地上の測量に使用される。セオドライト。
 ― [3] 【経緯儀】
望遠鏡を垂直および水平の二つの回転軸で支えた形式の角度測定装置。水準器を備え,かつ各回転軸に目盛りを刻んだもので,天体の位置測定や地上の測量に使用される。セオドライト。
― [3] 【経緯儀】
望遠鏡を垂直および水平の二つの回転軸で支えた形式の角度測定装置。水準器を備え,かつ各回転軸に目盛りを刻んだもので,天体の位置測定や地上の測量に使用される。セオドライト。
けいい-だい【経緯台】🔗⭐🔉
けいい-だい ― ― [3] 【経緯台】
望遠鏡を水平方向と上下方向に回転させる二軸を備えた,望遠鏡を載せる架台。
→赤道儀
― [3] 【経緯台】
望遠鏡を水平方向と上下方向に回転させる二軸を備えた,望遠鏡を載せる架台。
→赤道儀
 ― [3] 【経緯台】
望遠鏡を水平方向と上下方向に回転させる二軸を備えた,望遠鏡を載せる架台。
→赤道儀
― [3] 【経緯台】
望遠鏡を水平方向と上下方向に回転させる二軸を備えた,望遠鏡を載せる架台。
→赤道儀
けい-えい【経営】🔗⭐🔉
けい-えい [0] 【経営】 (名)スル
(1)方針を定め,組織を整えて,目的を達成するよう持続的に事を行うこと。特に,会社事業を営むこと。「会社を―する」「―不振」「植民地の―」「学級―」
(2)土地を測り,土台を据えて建築すること。「多日の―をむなしうして,片時の灰燼となりはてぬ/平家 7」
(3)行事の準備・人の接待などのために奔走すること。事をなしとげるために考え,実行すること。「傅(メノト)達―して養ひ君もてなすとて/とはずがたり 2」
(4)あわてること。急ぐこと。けいめい。「弓場殿の方に人々走り,―して案内を問ふ/御堂関白記」
けいえい-がく【経営学】🔗⭐🔉
けいえい-がく [3] 【経営学】
企業活動の原理や構造,またその合理的な管理方法などを研究する学問。財務管理・生産管理・販売管理・労務管理などが含まれる。
けいえい-かんり【経営管理】🔗⭐🔉
けいえい-かんり ―クワン― [5] 【経営管理】
企業における生産・販売・労務・財務などの管理を,総括的に効率よく調整するなどの全般的な管理。企業だけでなく組織集団全般についてもいう。
けいえい-きょうぎかい【経営協議会】🔗⭐🔉
けいえい-きょうぎかい ―ケフギクワイ [7] 【経営協議会】
使用者と労働者の代表が,経営全般について協議するための機関。普通,労働協約に基づいて設置される。
けいえい-けん【経営権】🔗⭐🔉
けいえい-けん [3] 【経営権】
企業の経営者が企業組織を管理し運営する権利。実定法上の概念ではない。
けいえい-こうがく【経営工学】🔗⭐🔉
けいえい-こうがく [5] 【経営工学】
⇒インダストリアル-エンジニアリング
けいえい-さいこうせきにんしゃ【経営最高責任者】🔗⭐🔉
けいえい-さいこうせきにんしゃ ―サイカウ― [11] 【経営最高責任者】
〔chief executive officer〕
アメリカの企業組織において,通常の職位呼称とは別に,実質的な最高実力者を示す肩書き。CEO 。
けいえい-さんか【経営参加】🔗⭐🔉
けいえい-さんか [5][0] 【経営参加】
労働者または労働組合が何らかの形で経営に参加すること。
けいえい-しゃ【経営者】🔗⭐🔉
けいえい-しゃ [3] 【経営者】
企業の最高管理職能の担当者。出資者である企業家・所有経営者と雇われた専門経営者とに大別される。
けいえい-しゃ-かくめい【経営者革命】🔗⭐🔉
けいえい-しゃ-かくめい [6] 【経営者革命】
1941年にアメリカのバーナム(James Burnham (1905- ))が発表した近代的資本主義国家論。資本主義社会の次には,経営者が支配階級として君臨する経営者社会が到来すると主張した。
けいえい-しゃ-しはい【経営者支配】🔗⭐🔉
けいえい-しゃ-しはい [6] 【経営者支配】
企業の所有と経営とが完全に分離した結果,専門経営者が支配権を掌握した状況。
けいえい-じょうほう【経営情報】🔗⭐🔉
けいえい-じょうほう ―ジヤウ― [5] 【経営情報】
企業経営に必要な情報。政治経済・金融・技術・他社など企業を取り巻く情報や,その企業の生産・在庫・労務の状況など,企業が意思決定や管理を行うのに必要な情報群。
けいえい-ぶんせき【経営分析】🔗⭐🔉
けいえい-ぶんせき [5] 【経営分析】
貸借対照表・損益計算書などの財務諸表や企業内外の諸情報を資料として,企業の経営効率・経営成績・財政状態などを分析・判断すること。
けい-か【経過】🔗⭐🔉
けい-か ―クワ [0] 【経過】 (名)スル
(1)時間が過ぎて行くこと。「歳月が―する」
(2)ある段階・過程を通って次の段階・過程に移ること。また,その変化するありさま。「手術後の―は良好」「十和田湖に遊びて,四通りの路を―したり/十和田湖(桂月)」
けいか-おん【経過音】🔗⭐🔉
けいか-おん ―クワ― [3] 【経過音】
〔音〕 非和声音の一。二つの和声音の間にあって両者を順次進行で継ぐ役目をもつ。
けいか-きてい【経過規定】🔗⭐🔉
けいか-きてい ―クワ― [4] 【経過規定】
法令の制定改廃によってそれまでの法律状態から新しい法律状態に変化するとき,その過程を円滑に進めるために必要な措置を定めた規定。例えば,新法の適用開始時や旧法の効力の存続期間に関する規定など。経過法。
けいか-ほう【経過法】🔗⭐🔉
けいか-ほう ―クワハフ [0] 【経過法】
⇒経過規定(ケイカキテイ)
けいか-りし【経過利子】🔗⭐🔉
けいか-りし ―クワ― [4] 【経過利子】
利付き債券の売買で,前回利子支払い日以後,売買受け渡し日までの経過日数に応じて日割り計算して,買い手が売り手に支払う利子。
けい-かい【経回】🔗⭐🔉
けい-かい ―クワイ 【経回】 (名)スル
(1)めぐり歩くこと。「京・大坂等の所を―して帰り参りしのち/折たく柴の記」
(2)生きて月日を経ること。「頼朝世に―せば,御方に奉公仕りて/盛衰記 41」
けい-かい【境界・経界】🔗⭐🔉
けい-かい [0] 【境界・経界】
さかい。しきり。きょうかい。
けい-かく【経画】🔗⭐🔉
けい-かく ―クワク [0] 【経画】 (名)スル
(1)たてに線を引くこと。また,その線。
(2)組み立てておしはかること。
(3)「計画(ケイカク)」に同じ。「新聞を出さうとの―もあつた/思出の記(蘆花)」
けい-がく【経学】🔗⭐🔉
けい-がく [0][1] 【経学】
四書・五経など経書を研究する学問。
けい-かん【経巻】🔗⭐🔉
けい-かん ―クワン [0] 【経巻】
経書。経典。きょうかん。
けい-き【経紀】🔗⭐🔉
けい-き [1][0] 【経紀】 (名)スル
(1)国などを治める大本の法則。綱紀。
(2)経営。運営。
けい-けつ【経穴】🔗⭐🔉
けい-けつ [0] 【経穴】
そこに鍼(ハリ)や灸(キユウ)をすると効果がある身体の部分。つぼ。特に経絡に属するつぼをいう。
けい-けん【経験】🔗⭐🔉
けい-けん [0] 【経験】 (名)スル
(1)直接触れたり,見たり,実際にやってみたりすること。また,そのようにして得た知識や技術。「はじめての―」「この痛さは―しなければわからない」「―を積む」「―が浅い」
(2)実験。「蒸気の力を―する器具を製せしが/西国立志編(正直)」
(3)〔哲〕
〔experience〕
理念・思考や想像・記憶によってではなく,感覚や知覚によって直接に与えられ体験されるものごと。
けいけん-かがく【経験科学】🔗⭐🔉
けいけん-かがく ―クワ― [5] 【経験科学】
純粋に理論を探究する科学に対し,経験的事実を対象として実証的に諸法則を探究する科学。実証科学。
けいけん-がくしゅう【経験学習】🔗⭐🔉
けいけん-がくしゅう ―シフ [5] 【経験学習】
生活経験そのものを素材として展開される学習。経験上の問題解決を通して学習を進める。
→系統学習
けいけん-しゃ【経験者】🔗⭐🔉
けいけん-しゃ [3] 【経験者】
あるものごとを深く経験した人。「―は語る」
けいけん-しゅぎ【経験主義】🔗⭐🔉
けいけん-しゅぎ [5] 【経験主義】
(1)「経験論」に同じ。
(2)理論的認識によらずもっぱら自己の具体的な経験のみを重んずる態度。
⇔合理主義
けいけん-そく【経験則】🔗⭐🔉
けいけん-そく [3] 【経験則】
法則としての因果的必然性がまだ明らかになっておらず,経験上そう言えるというだけの規則。
けいけん-てき【経験的】🔗⭐🔉
けいけん-てき [0] 【経験的】 (形動)
経験によって得られるさま。また,経験によって得た知識や感覚を重視するさま。「昔の船乗りは嵐の前兆を―に知っていた」
けいけん-てき-がいねん【経験的概念】🔗⭐🔉
けいけん-てき-がいねん [7] 【経験的概念】
経験に由来して形成される概念。例えば,人・犬・動物など。
けいけん-ひはんろん【経験批判論】🔗⭐🔉
けいけん-ひはんろん [6] 【経験批判論】
アベナリウスらによって,一九世紀後半に唱えられた実証主義的哲学。経験内容から形而上学的仮定や個人的要素を除去して主客未分の純粋経験をもとめ,それに基づいて世界像を構成しようとする立場。唯物論と観念論の対立を超えると主張するが,レーニンはこれを一種の主観的観念論であるとして批判する。
けいけん-めいだい【経験命題】🔗⭐🔉
けいけん-めいだい [5] 【経験命題】
経験によって真偽を確かめることのできる命題。
けいけん-ろん【経験論】🔗⭐🔉
けいけん-ろん [3] 【経験論】
〔empiricism〕
知識の源泉は理性ではなく,もっぱら感覚的経験にあるとする哲学上の立場。生得観念を否定した一七,八世紀イギリス経験論( F =ベーコン・ロック・バークリー・ヒューム)が代表的。経験主義。経験哲学。
けい-こう【経口】🔗⭐🔉
けい-こう [0] 【経口】
口から身体に入ること。
けいこう-かんせん【経口感染】🔗⭐🔉
けいこう-かんせん [5] 【経口感染】
病原体が口を通って消化管から侵入するような感染のしかた。
けいこう-はんすう-ちしりょう【経口半数致死量】🔗⭐🔉
けいこう-はんすう-ちしりょう ―チシリヤウ [10] 【経口半数致死量】
化学物質・薬などの毒性の指標の一。口腔を通じて投与したとき,投与された実験動物の半数が死亡する薬剤の量。
→LD



けいこう-ひにんやく【経口避妊薬】🔗⭐🔉
けいこう-ひにんやく [6] 【経口避妊薬】
婦人用の内服避妊薬。ホルモン剤で,主として排卵を抑制して避妊の目的を達する。ピル。
けいこう-めんえき【経口免疫】🔗⭐🔉
けいこう-めんえき [5] 【経口免疫】
抗原が経口的に体内に入って抗体がつくられ,免疫が得られること。ポリオの生ワクチンなどで利用される。
けいこう-やく【経口薬】🔗⭐🔉
けいこう-やく [3] 【経口薬】
口から飲む薬。内服薬。内用薬。飲み薬。
けい-こく【経国】🔗⭐🔉
けい-こく [0] 【経国】
国家を経営すること。国を治めること。「―の事業」
けいこく-さいみん【経国済民】🔗⭐🔉
けいこく-さいみん [0] 【経国済民】
国を治め民の生活を安定させること。経世済民。
けいこく-たいてん【経国大典】🔗⭐🔉
けいこく-たいてん 【経国大典】
李氏朝鮮の基本法令集。世祖の命によって編纂事業が始められ,1485年完成。全六巻。吏・戸・礼・兵・刑・工の六典からなる。
けいこくしゅう【経国集】🔗⭐🔉
けいこくしゅう ―シフ 【経国集】
勅撰漢詩文集。二〇巻。現存六巻。淳和天皇の命を受け,良岑(ヨシミネ)安世が滋野貞主・菅原清公らと撰。827年成立。嵯峨天皇・石上宅嗣(イソノカミノヤカツグ)・淡海三船(オウミノミフネ)・空海らの詩文を収める。六朝(リクチヨウ)詩・唐詩の影響を受け,平安時代詩文の隆盛を示す。
けいこくびだん【経国美談】🔗⭐🔉
けいこくびだん 【経国美談】
小説。矢野竜渓作。1883(明治16)〜84年刊。古代ギリシャ勃興期のテーベを描き,日本の民権と国権の伸長を図った政治小説。
けい-ざい【経済】🔗⭐🔉
けい-ざい [1] 【経済】 (名)スル
〔「経世済民」から〕
(1)〔economy〕
物資の生産・流通・交換・分配とその消費・蓄積の全過程,およびその中で営まれる社会的諸関係の総体。
(2)世を治め,民の生活を安定させること。「男児の事業を為して天下を―するは/花柳春話(純一郎)」
(3)金銭の出入りに関すること。やりくり。「我が家の―は火の車だ」
(4)費用や手間が少なくてすむこと。節約。「電話ですむなら時間が―だ」
けいざい-あんぜんほしょう【経済安全保障】🔗⭐🔉
けいざい-あんぜんほしょう ―ホシヤウ [9] 【経済安全保障】
他国で政治的・経済的な混乱が生じても国内の経済活動が不安定にならないよう,事前に制度的側面においても物的側面においても対応できるように準備しておくこと。後者は食料や石油の備蓄などをいう。
けいざい-あんていきゅうげんそく【経済安定九原則】🔗⭐🔉
けいざい-あんていきゅうげんそく ―キウゲンソク 【経済安定九原則】
1948年(昭和23)12月,占領軍が日本の経済安定・インフレ収束のために指令した経済政策。経費節減,均衡予算,賃金・物価の統制,為替の管理強化など九項目からなる。
けいざい-あんてい-ほんぶ【経済安定本部】🔗⭐🔉
けいざい-あんてい-ほんぶ 【経済安定本部】
1946年(昭和21)戦後経済復興のため設置された,経済施策の企画立案・事務調整を行う行政機関。52年経済審議庁,55年経済企画庁に改組。安本(アンポン)。
けいざい-か【経済家】🔗⭐🔉
けいざい-か [0] 【経済家】
(1)経済の事に明るい人。
(2)お金を上手に使って,少しの費用ですませる人。節約家。また,けちな人。
けいざい-かい【経済界】🔗⭐🔉
けいざい-かい [3] 【経済界】
(1)社会の中で経済的活動の行われる範囲。
(2)実業家や金融業者の社会。財界。「―の実力者」
けいざい-がいてき-きょうせい【経済外的強制】🔗⭐🔉
けいざい-がいてき-きょうせい ―グワイテキキヤウセイ [9] 【経済外的強制】
農民に対する封建領主の収奪が経済法則や経済システムを通じてなされるのではなく,強制力によってなされること。社会的・身分的拘束,農民の土地への緊縛などの形態を通じて行われた。
けいざい-かいはつ【経済開発】🔗⭐🔉
けいざい-かいはつ [5] 【経済開発】
国や地域で,工業を中心とした各種産業の発展と所得増大を図ること。
けいざい-かいはつく【経済開発区】🔗⭐🔉
けいざい-かいはつく [8] 【経済開発区】
経済特別区についで,1984年中国で設立された対外経済開放区。大連・秦皇島・天津・煙台・青島・連雲港・南通・上海・寧波(ニンポー)・温州・福州・広州・湛江・北海など一四の沿岸都市と海南島が指定され,外資の国内への開放を認めている。
けいざい-がく【経済学】🔗⭐🔉
けいざい-がく [3] 【経済学】
〔economics; political economy〕
人間社会の経済現象,特に,財貨・サービスの生産・交換・消費の法則を研究する学問。法則を抽出する理論経済学,理論の応用である政策学,経済現象を史的に捉える経済史学に大別される。
けいざい-ブロック【経済―】🔗⭐🔉
けいざい-ブロック [6] 【経済―】
複数の国が共通の目的を達成するためにつくる排他的な政治的経済的連合。
けい-めい【経営】🔗⭐🔉
けい-めい 【経営】
〔「けいえい」の転〕
(1)「けいえい(経営){(3)}」に同じ。「いまこの―すぐして参らむよ,とて帰る/蜻蛉(下)」
(2)接待。もてなし。「けふは院の御―にて…檜破子やうの物,色々にいときよらに調じて/増鏡(草枕)」
た・つ【経つ】🔗⭐🔉
た・つ [1] 【経つ】 (動タ五[四])
〔「立つ」と同源〕
時・時間が経過する。「時が―・つ」「時間が―・つ」「もう少し―・ってから…」
たて【縦・竪・経】🔗⭐🔉
たて [1] 【縦・竪・経】
(1)(水平に対して)上下の方向。垂直の方向。また,その長さ。「―に線を引く」「―長」
(2)(左右に対して)前後への方向。また,その長さ。「―に並ぶ」
(3)(比喩的に)同僚との関係ではなく,上司と部下との関係。「―の人間関係」
(4)南北の方向。また,その距離。
(5)「経(タテ)糸」に同じ。「―もなく緯(ヌキ)も定めず娘子(オトメ)らが織るもみち葉に霜な降りそね/万葉 1512」
⇔横
たて-いと【経糸・経】🔗⭐🔉
たて-いと [0] 【経糸・経】
織物の縦の方向に通っている糸。
⇔緯(ヨコ)糸
たて-にしき【経錦】🔗⭐🔉
たて-にしき [3] 【経錦】
たて糸に数種の色糸を用いた錦。中国では漢代から見られる技法。ほぼ三色で,織り方も複雑なため,緯(ヌキ)錦の発達によって衰えた。けいきん。
たて-ぬき【経緯】🔗⭐🔉
たて-ぬき [0][2] 【経緯】
(1)織機のたて糸とよこ糸。
(2)たてと横。
(3)くわしい事情・経緯。
たて-まき【経巻(き)】🔗⭐🔉
たて-まき [0] 【経巻(き)】
経(タテ)糸を整えて織機の (チキリ)に巻きつけること。織物製造の準備工程として行う。
(チキリ)に巻きつけること。織物製造の準備工程として行う。
 (チキリ)に巻きつけること。織物製造の準備工程として行う。
(チキリ)に巻きつけること。織物製造の準備工程として行う。
たて-よこ【縦横・経緯】🔗⭐🔉
たて-よこ [1] 【縦横・経緯】
(1)たてとよこ。じゅうおう。「―十文字」
(2)たて糸とよこ糸。たてぬき。
たてよこ-がすり【経緯絣】🔗⭐🔉
たてよこ-がすり [5] 【経緯絣】
経(タテ)糸・緯(ヨコ)糸ともにくくり糸を用いた絣。高度の技術を要する。十字絣・井げた絣など。
たてよこ-ちりめん【経緯縮緬】🔗⭐🔉
たてよこ-ちりめん [5] 【経緯縮緬】
経緯ともに強撚糸を用いた縮緬。ジョーゼット。
へ-めぐ・る【経回る】🔗⭐🔉
へ-めぐ・る [3][0] 【経回る】 (動ラ五[四])
あちこちをめぐり歩く。遍歴する。「諸所を―・る」「かの君と共に国々を―・りて/即興詩人(鴎外)」
へる【経る】🔗⭐🔉
へる [1] 【経る】 (動ハ下一)[文]ハ下二 ふ
〔「綜(フ)」と同源〕
(1)ある場所を順次通って行く。経由する。「京都を〈へ〉て大阪へ行く」「何人もの手を〈へ〉て今の持ち主のものとなった」
(2)時がたつ。年月がすぎる。「多くの年月を〈へる〉」「なんでもかたちは猿のかうらを〈へ〉たのだぜ/西洋道中膝栗毛(魯文)」
(3)ある過程・段階などを通る。経過する。「審査を〈へ〉て採用される」「紆余(ウヨ)曲折を〈へ〉て結ばれた」
(4)歳月を過ごす。「なほ世に〈ふ〉まじき心地しければ/大和 150」
いきさつ【経緯】(和英)🔗⭐🔉
いきさつ【経緯】
circumstances (事情);particulars[details](詳細);trouble(s) (もめごと).→英和
きょう【経】(和英)🔗⭐🔉
きょう【経】
a sutra.→英和
けいい【経緯】(和英)🔗⭐🔉
けいい【経緯】
(1) warp and woof (縦糸と横糸).
(2)[いきさつ]details;circumstances.
けいえい【経営】(和英)🔗⭐🔉
けいえい【経営】
management;→英和
administration;→英和
operation (運営).→英和
〜する manage;→英和
run;→英和
keep;→英和
operate.→英和
‖経営学(部) (the faculty[department]of) business administration.経営合理化 streamlining of management.経営コンサルタント a management consultant.経営工学 management engineering.経営者 a manager.経営者(側)と労働者(側) (the) management and (the) labor.経営難に陥る fall into financial difficulties.
けいか【経過】(和英)🔗⭐🔉
けいけん【経験】(和英)🔗⭐🔉
けいこう【経口感染】(和英)🔗⭐🔉
けいこう【経口感染】
oral infection.経口避妊薬 an oral contraceptive;the pill.→英和
けいざい【経済】(和英)🔗⭐🔉
けいざい【経済】
economy;→英和
finance (財政).→英和
〜の economic.→英和
〜的な(に) economical(ly).→英和
‖経済援助 financial support.経済界 the economic world;financial circles.経済開発 economic development.経済学(部) (the faculty[department]of) economics.経済観念 a sense of economy.経済企画庁 the Economic Planning Agency.経済記事(欄) financial news (columns).経済状態 economic conditions;the state of one's finances (個人の).経済成長率 the rate of economic growth.経済大国 a great economic power.経済封鎖 an economic blockade.経済問題(危機,白書) an economic problem (crisis,white paper).
たつ【経つ】(和英)🔗⭐🔉
へて【経て】(和英)🔗⭐🔉
へる【経る】(和英)🔗⭐🔉
へる【経る】
(1)[時間が]pass;→英和
go by.(2)[出会う]go through.
⇒経て.
広辞苑+大辞林に「経」で始まるの検索結果。もっと読み込む