複数辞典一括検索+![]()
![]()
経🔗⭐🔉
【経】
 11画 糸部 [五年]
区点=2348 16進=3750 シフトJIS=8C6F
【經】旧字旧字
11画 糸部 [五年]
区点=2348 16進=3750 シフトJIS=8C6F
【經】旧字旧字
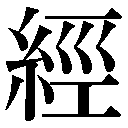 13画 糸部
区点=6920 16進=6534 シフトJIS=E353
《常用音訓》キョウ/ケイ/へ…る
《音読み》 ケイ
13画 糸部
区点=6920 16進=6534 シフトJIS=E353
《常用音訓》キョウ/ケイ/へ…る
《音読み》 ケイ /キョウ(キャウ)
/キョウ(キャウ) /キン
/キン 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 たていと/たて/つね/へる(ふ)/おさめる(をさむ)/くびれる(くびる)/すでに
《名付け》 おさむ・つね・のぶ・のり・ふ・ふる
《意味》
ng〉
《訓読み》 たていと/たて/つね/へる(ふ)/おさめる(をさむ)/くびれる(くびる)/すでに
《名付け》 おさむ・つね・のぶ・のり・ふ・ふる
《意味》
 {名}たていと。たて。まっすぐにとおった織物のたていと。おおすじ。転じて、地球の両極をたてにとおした仮定の線。〈対語〉→緯。「経度」
{名}たていと。たて。まっすぐにとおった織物のたていと。おおすじ。転じて、地球の両極をたてにとおした仮定の線。〈対語〉→緯。「経度」
 {名}つね。時代をたてに貫いて伝わる不変の道理。物事のすじ道。〈類義語〉→常。「経常」「天経地義(不変の道理)」「君子反経而已矣=君子ハ経ニ反ランノミ」〔→孟子〕
{名}つね。時代をたてに貫いて伝わる不変の道理。物事のすじ道。〈類義語〉→常。「経常」「天経地義(不変の道理)」「君子反経而已矣=君子ハ経ニ反ランノミ」〔→孟子〕
 {名}儒教で、不変のすじ道を説いたとされる書。「経書」「五経」
{名}儒教で、不変のすじ道を説いたとされる書。「経書」「五経」
 {名}仏教や宗教の道理を説いた書。「華厳経ケゴンキョウ」「聖経セイケイ・セイキョウ(バイブル)」
{名}仏教や宗教の道理を説いた書。「華厳経ケゴンキョウ」「聖経セイケイ・セイキョウ(バイブル)」
 {動}へる(フ)。まっすぐとおりぬける。場所や時間をとおりすぎる。「経過」「経年=年ヲ経」「経夕而活=夕ヲ経テ活キタリ」
{動}へる(フ)。まっすぐとおりぬける。場所や時間をとおりすぎる。「経過」「経年=年ヲ経」「経夕而活=夕ヲ経テ活キタリ」
 ケイス{動}おさめる(ヲサム)。すじ道やたての線を引く。また、転じて、物事の大すじをたてて処理する。管理する。「経営」「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕
ケイス{動}おさめる(ヲサム)。すじ道やたての線を引く。また、転じて、物事の大すじをたてて処理する。管理する。「経営」「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕
 {動}くびれる(クビル)。経(ひも)で首をくくる。「自経於溝涜=溝涜ニ自経ス」〔→論語〕
{動}くびれる(クビル)。経(ひも)で首をくくる。「自経於溝涜=溝涜ニ自経ス」〔→論語〕
 {名}月経。▽月ごとに経常的におこることから。「経血」
{名}月経。▽月ごとに経常的におこることから。「経血」
 {副}すでに。かつて経験したの意から、「すでに」の意となる。「曾経カツテスデニ」「已経スデニ」
《解字》
{副}すでに。かつて経験したの意から、「すでに」の意となる。「曾経カツテスデニ」「已経スデニ」
《解字》
 会意兼形声。經の右側の字(音ケイ)は、上のわくから下の台へたていとをまっすぐに張り通したさまを描いた象形文字。經はそれを音符とし、糸へんをそえて、たていとの意を明示した字。
《単語家族》
徑ケイ(=径。まっすぐな近道)
会意兼形声。經の右側の字(音ケイ)は、上のわくから下の台へたていとをまっすぐに張り通したさまを描いた象形文字。經はそれを音符とし、糸へんをそえて、たていとの意を明示した字。
《単語家族》
徑ケイ(=径。まっすぐな近道) 莖ケイ(=茎。まっすぐなくき)
莖ケイ(=茎。まっすぐなくき) 頸ケイ(まっすぐな首)
頸ケイ(まっすぐな首) 脛ケイ(まっすぐなすね)などと同系。
《類義》
→常・→維
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
脛ケイ(まっすぐなすね)などと同系。
《類義》
→常・→維
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
 11画 糸部 [五年]
区点=2348 16進=3750 シフトJIS=8C6F
【經】旧字旧字
11画 糸部 [五年]
区点=2348 16進=3750 シフトJIS=8C6F
【經】旧字旧字
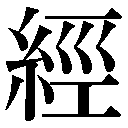 13画 糸部
区点=6920 16進=6534 シフトJIS=E353
《常用音訓》キョウ/ケイ/へ…る
《音読み》 ケイ
13画 糸部
区点=6920 16進=6534 シフトJIS=E353
《常用音訓》キョウ/ケイ/へ…る
《音読み》 ケイ /キョウ(キャウ)
/キョウ(キャウ) /キン
/キン 〈j
〈j ng〉
《訓読み》 たていと/たて/つね/へる(ふ)/おさめる(をさむ)/くびれる(くびる)/すでに
《名付け》 おさむ・つね・のぶ・のり・ふ・ふる
《意味》
ng〉
《訓読み》 たていと/たて/つね/へる(ふ)/おさめる(をさむ)/くびれる(くびる)/すでに
《名付け》 おさむ・つね・のぶ・のり・ふ・ふる
《意味》
 {名}たていと。たて。まっすぐにとおった織物のたていと。おおすじ。転じて、地球の両極をたてにとおした仮定の線。〈対語〉→緯。「経度」
{名}たていと。たて。まっすぐにとおった織物のたていと。おおすじ。転じて、地球の両極をたてにとおした仮定の線。〈対語〉→緯。「経度」
 {名}つね。時代をたてに貫いて伝わる不変の道理。物事のすじ道。〈類義語〉→常。「経常」「天経地義(不変の道理)」「君子反経而已矣=君子ハ経ニ反ランノミ」〔→孟子〕
{名}つね。時代をたてに貫いて伝わる不変の道理。物事のすじ道。〈類義語〉→常。「経常」「天経地義(不変の道理)」「君子反経而已矣=君子ハ経ニ反ランノミ」〔→孟子〕
 {名}儒教で、不変のすじ道を説いたとされる書。「経書」「五経」
{名}儒教で、不変のすじ道を説いたとされる書。「経書」「五経」
 {名}仏教や宗教の道理を説いた書。「華厳経ケゴンキョウ」「聖経セイケイ・セイキョウ(バイブル)」
{名}仏教や宗教の道理を説いた書。「華厳経ケゴンキョウ」「聖経セイケイ・セイキョウ(バイブル)」
 {動}へる(フ)。まっすぐとおりぬける。場所や時間をとおりすぎる。「経過」「経年=年ヲ経」「経夕而活=夕ヲ経テ活キタリ」
{動}へる(フ)。まっすぐとおりぬける。場所や時間をとおりすぎる。「経過」「経年=年ヲ経」「経夕而活=夕ヲ経テ活キタリ」
 ケイス{動}おさめる(ヲサム)。すじ道やたての線を引く。また、転じて、物事の大すじをたてて処理する。管理する。「経営」「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕
ケイス{動}おさめる(ヲサム)。すじ道やたての線を引く。また、転じて、物事の大すじをたてて処理する。管理する。「経営」「経之営之=コレヲ経シコレヲ営ス」〔→詩経〕
 {動}くびれる(クビル)。経(ひも)で首をくくる。「自経於溝涜=溝涜ニ自経ス」〔→論語〕
{動}くびれる(クビル)。経(ひも)で首をくくる。「自経於溝涜=溝涜ニ自経ス」〔→論語〕
 {名}月経。▽月ごとに経常的におこることから。「経血」
{名}月経。▽月ごとに経常的におこることから。「経血」
 {副}すでに。かつて経験したの意から、「すでに」の意となる。「曾経カツテスデニ」「已経スデニ」
《解字》
{副}すでに。かつて経験したの意から、「すでに」の意となる。「曾経カツテスデニ」「已経スデニ」
《解字》
 会意兼形声。經の右側の字(音ケイ)は、上のわくから下の台へたていとをまっすぐに張り通したさまを描いた象形文字。經はそれを音符とし、糸へんをそえて、たていとの意を明示した字。
《単語家族》
徑ケイ(=径。まっすぐな近道)
会意兼形声。經の右側の字(音ケイ)は、上のわくから下の台へたていとをまっすぐに張り通したさまを描いた象形文字。經はそれを音符とし、糸へんをそえて、たていとの意を明示した字。
《単語家族》
徑ケイ(=径。まっすぐな近道) 莖ケイ(=茎。まっすぐなくき)
莖ケイ(=茎。まっすぐなくき) 頸ケイ(まっすぐな首)
頸ケイ(まっすぐな首) 脛ケイ(まっすぐなすね)などと同系。
《類義》
→常・→維
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
脛ケイ(まっすぐなすね)などと同系。
《類義》
→常・→維
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要書物
経木 キョウギ🔗⭐🔉
【経木】
キョウギ〔国〕すぎ・ひのきなどの材木を紙のように広く薄く削ったもの。物を包んだり、帽子などをつくったりする。▽昔、経文を写すのに用いたことから。
経手 ケイシュ🔗⭐🔉
【経手】
ケイシュ  手がける。手をとおす。
手がける。手をとおす。 仲買いする。
仲買いする。
 手がける。手をとおす。
手がける。手をとおす。 仲買いする。
仲買いする。
経水 ケイスイ🔗⭐🔉
【経水】
ケイスイ  流れゆく水。山から流れ出て海に流れ入る水。また、川の本流。
流れゆく水。山から流れ出て海に流れ入る水。また、川の本流。 月経。
月経。
 流れゆく水。山から流れ出て海に流れ入る水。また、川の本流。
流れゆく水。山から流れ出て海に流れ入る水。また、川の本流。 月経。
月経。
経文 キョウモン🔗⭐🔉
【経文】
 ケイブン 経書の文章。
ケイブン 経書の文章。 キョウモン〔仏〕仏教の教理を説く文章。また、経典。
キョウモン〔仏〕仏教の教理を説く文章。また、経典。
 ケイブン 経書の文章。
ケイブン 経書の文章。 キョウモン〔仏〕仏教の教理を説く文章。また、経典。
キョウモン〔仏〕仏教の教理を説く文章。また、経典。
経文緯武 ケイブンイブ🔗⭐🔉
【経文緯武】
ケイブンイブ →「緯武経文イブケイブン」
経史子集 ケイシシシュウ🔗⭐🔉
【経史子集】
ケイシシシュウ 中国の書物の分類法で、経書・歴史書・諸子類・詩文集。
経世済民 ケイセイサイミン🔗⭐🔉
【経世済民】
ケイセイサイミン 世の中をおさめて、人民の生活を調整する。
経由 ケイユウ🔗⭐🔉
【経由】
ケイユ・ケイユウ ある所を通り過ぎて来る。
経行 キョウギョウ🔗⭐🔉
【経行】
 ケイコウ
ケイコウ  いつもきまった規律のある行い。
いつもきまった規律のある行い。 月経。
月経。 通過する。
通過する。 キョウギョウ・キンヒン 仏教で、座禅のとき、眠けをさますとき、食後や疲れたとき、静かにへやの中を歩くこと。〔王巾〕
キョウギョウ・キンヒン 仏教で、座禅のとき、眠けをさますとき、食後や疲れたとき、静かにへやの中を歩くこと。〔王巾〕
 ケイコウ
ケイコウ  いつもきまった規律のある行い。
いつもきまった規律のある行い。 月経。
月経。 通過する。
通過する。 キョウギョウ・キンヒン 仏教で、座禅のとき、眠けをさますとき、食後や疲れたとき、静かにへやの中を歩くこと。〔王巾〕
キョウギョウ・キンヒン 仏教で、座禅のとき、眠けをさますとき、食後や疲れたとき、静かにへやの中を歩くこと。〔王巾〕
経死 ケイシ🔗⭐🔉
【経死】
ケイシ 首をくくって死ぬ。〈類義語〉縊死イシ。
経伝 ケイデン🔗⭐🔉
【経伝】
ケイデン 経書とその注釈。▽「経」は、聖人が書きあらわしたもの、また、聖人のことばを記したもの。「伝」は、経の文章に注解を加えたもの。
経年 ケイネン🔗⭐🔉
経国 ケイコク🔗⭐🔉
【経国】
ケイコク 国をおさめる。「文章経国之大業=文章ハ経国ノ大業」〔魏文帝〕
経書 ケイショ🔗⭐🔉
【経典】
 ケイテン 四書・五経など儒教の教理を説いた書。『経書ケイショ・経籍ケイセキ』
ケイテン 四書・五経など儒教の教理を説いた書。『経書ケイショ・経籍ケイセキ』 キョウテン〔仏〕仏が説いたことを記した書。お経。▽「典」は、規則。
キョウテン〔仏〕仏が説いたことを記した書。お経。▽「典」は、規則。
 ケイテン 四書・五経など儒教の教理を説いた書。『経書ケイショ・経籍ケイセキ』
ケイテン 四書・五経など儒教の教理を説いた書。『経書ケイショ・経籍ケイセキ』 キョウテン〔仏〕仏が説いたことを記した書。お経。▽「典」は、規則。
キョウテン〔仏〕仏が説いたことを記した書。お経。▽「典」は、規則。
経巻 キョウカン🔗⭐🔉
【経巻】
 ケイカン 聖人があらわした書物。四書・五経など。
ケイカン 聖人があらわした書物。四書・五経など。 キョウカン 仏教の書物。
キョウカン 仏教の書物。
 ケイカン 聖人があらわした書物。四書・五経など。
ケイカン 聖人があらわした書物。四書・五経など。 キョウカン 仏教の書物。
キョウカン 仏教の書物。
経紀 ケイキ🔗⭐🔉
経度 ケイド🔗⭐🔉
【経度】
ケイド 地球上の位置を示すための座標。イギリスのグリニッジ天文台を通って南極・北極とを結ぶ線を零度として、この経線を含む平面と任意の経線を含む平面とが地球の中心に対してなす角度。東経百八十度、西経百八十度まである。〈対語〉緯度。
経解 ケイカイ🔗⭐🔉
【経訓】
ケイクン 経書を解釈する。また、経書の解釈。『経解ケイカイ』
経師 キョウジ🔗⭐🔉
【経師】
 ケイシ
ケイシ  経書を教える先生。
経書を教える先生。 人格を養成する教育をしないで、ただ経書を教授するだけの教師。▽人師(道を教え、人格の養成をはかる教師)に対する。
人格を養成する教育をしないで、ただ経書を教授するだけの教師。▽人師(道を教え、人格の養成をはかる教師)に対する。 キョウジ〔国〕
キョウジ〔国〕 経文を書き写した人。後には、経文の表装を職業とした人。
経文を書き写した人。後には、経文の表装を職業とした人。 書画・びょうぶ・ふすまなどの表装をする職人。表具師。
書画・びょうぶ・ふすまなどの表装をする職人。表具師。
 ケイシ
ケイシ  経書を教える先生。
経書を教える先生。 人格を養成する教育をしないで、ただ経書を教授するだけの教師。▽人師(道を教え、人格の養成をはかる教師)に対する。
人格を養成する教育をしないで、ただ経書を教授するだけの教師。▽人師(道を教え、人格の養成をはかる教師)に対する。 キョウジ〔国〕
キョウジ〔国〕 経文を書き写した人。後には、経文の表装を職業とした人。
経文を書き写した人。後には、経文の表装を職業とした人。 書画・びょうぶ・ふすまなどの表装をする職人。表具師。
書画・びょうぶ・ふすまなどの表装をする職人。表具師。
経済 ケイザイ🔗⭐🔉
【経済】
ケイザイ  「経世済民」の略。国をおさめ、人民の生活を調整する。「問以経済策、茫如墜煙霧=問フニ経済ノ策ヲモッテスレバ、茫トシテ煙霧ニ墜ツルガゴトシ」〔→李白〕
「経世済民」の略。国をおさめ、人民の生活を調整する。「問以経済策、茫如墜煙霧=問フニ経済ノ策ヲモッテスレバ、茫トシテ煙霧ニ墜ツルガゴトシ」〔→李白〕 人間が共同生活するのに必要な物を生産、分配、消費する行為・過程についてのいっさいの社会的関係。転じて、金銭のやりくり。
人間が共同生活するのに必要な物を生産、分配、消費する行為・過程についてのいっさいの社会的関係。転じて、金銭のやりくり。 〔国〕むだな費用をかけないこと。つましくすること。
〔国〕むだな費用をかけないこと。つましくすること。
 「経世済民」の略。国をおさめ、人民の生活を調整する。「問以経済策、茫如墜煙霧=問フニ経済ノ策ヲモッテスレバ、茫トシテ煙霧ニ墜ツルガゴトシ」〔→李白〕
「経世済民」の略。国をおさめ、人民の生活を調整する。「問以経済策、茫如墜煙霧=問フニ経済ノ策ヲモッテスレバ、茫トシテ煙霧ニ墜ツルガゴトシ」〔→李白〕 人間が共同生活するのに必要な物を生産、分配、消費する行為・過程についてのいっさいの社会的関係。転じて、金銭のやりくり。
人間が共同生活するのに必要な物を生産、分配、消費する行為・過程についてのいっさいの社会的関係。転じて、金銭のやりくり。 〔国〕むだな費用をかけないこと。つましくすること。
〔国〕むだな費用をかけないこと。つましくすること。
経術 ケイジュツ🔗⭐🔉
【経術】
ケイジュツ  経書を研究する学問。経学。
経書を研究する学問。経学。 儒教の経典にもとづいて得た政治上の方法。
儒教の経典にもとづいて得た政治上の方法。
 経書を研究する学問。経学。
経書を研究する学問。経学。 儒教の経典にもとづいて得た政治上の方法。
儒教の経典にもとづいて得た政治上の方法。
経商 ケイショウ🔗⭐🔉
【経商】
ケイショウ 行商人。
経渉 ケイショウ🔗⭐🔉
【経渉】
ケイショウ 通り過ぎる。通過する。
経常 ケイジョウ🔗⭐🔉
【経常】
ケイジョウ  一定してかわらない。
一定してかわらない。 〔俗〕いつも。
〔俗〕いつも。
 一定してかわらない。
一定してかわらない。 〔俗〕いつも。
〔俗〕いつも。
経理 ケイリ🔗⭐🔉
経営 ケイエイ🔗⭐🔉
経筵 ケイエン🔗⭐🔉
【経筵】
ケイエン 天子が経書を学ぶ席。
経路 ケイロ🔗⭐🔉
【経路】
ケイロ  通過するみち。
通過するみち。 物事が経過してきたすじみち。
物事が経過してきたすじみち。
 通過するみち。
通過するみち。 物事が経過してきたすじみち。
物事が経過してきたすじみち。
経説 ケイセツ🔗⭐🔉
【経説】
ケイセツ  経書に説かれていることば。
経書に説かれていることば。 経書の意義などを解説した書物。
経書の意義などを解説した書物。
 経書に説かれていることば。
経書に説かれていることば。 経書の意義などを解説した書物。
経書の意義などを解説した書物。
経歴 ケイレキ🔗⭐🔉
経緯 ケイイ🔗⭐🔉
経験 ケイケン🔗⭐🔉
【経験】
ケイケン  実際に自分でやってみる。
実際に自分でやってみる。 実際にしたり見たりして得た知識や技術。
実際にしたり見たりして得た知識や技術。
 実際に自分でやってみる。
実際に自分でやってみる。 実際にしたり見たりして得た知識や技術。
実際にしたり見たりして得た知識や技術。
経国集 ケイコクシュウ🔗⭐🔉
【経国集】
ケイコクシュウ〔日〕〈書物〉勅撰の漢詩文集。淳和ジュンナ天皇の命令で、良岑安世ヨシミネノヤスヨが滋野貞主シゲノサダヌシらと編集した。827年成立。二〇巻のうち、現存は六巻。奈良時代から平安時代への漢詩文全盛時代の代表作を収録し、作者は嵯峨サガ天皇・淳和天皇・石上宅嗣イソノカミノヤカツグ・淡海三船オウミノミフネ・空海など一七八人。『文選モンゼン』の形式にならって詩と文にわけ、さらに詩・賦・序・対策文に分類している。形式的には七言詩が多く、唐風の影響を知ることができる。書名は、魏ギの文帝の『典論』の「蓋ケダシ文章ハ経国之大業、不朽之盛事ナリ」にもとづく。
経典釈文 ケイテンシャクモン🔗⭐🔉
【経典釈文】
ケイテンシャクモン〈書物〉三〇巻。唐の陸徳明の著。583年ごろ成立。おもな古典の本文を校定し、その用語について発音と意味とを解説する「音義」をつけた書。第一巻は「序録」で、古典を伝えた漢代以来の師承の系統・派別を記し、第二巻以下には、『易経』『書経(古文尚書)』『詩経(毛詩)』『周礼シュライ』『儀礼ギライ』『礼記ライキ』『春秋左氏伝』『春秋公羊クヨウ伝』『春秋穀梁コクリョウ伝』『孝経』『論語』『爾雅ジガ』『老子』『荘子ソウジ』など一四の古典に関する音義を含む。当時『孟子モウシ』はなお経典としては扱われなかったために、その中に含まれず、また老荘が尊ばれた時代なのでとくに『老子』『荘子』が取りあげられている。その音注は、「易=盈隻反」のような反切か、または「偏=音篇」のような同音字で示される。なお、二巻本・一〇巻本があるが、内容に齟齬ソゴが多く、相互に参照する必要がある。
経伝釈詞 ケイデンシャクシ🔗⭐🔉
【経伝釈詞】
ケイデンシャクシ〈書物〉一〇巻。清シンの王引之オウインシ(1766〜1834)の著。ここで詞というのは虚詞(指示詞・接続詞・助詞・副詞など)のことで、本書は古典の中の虚詞約一六〇種について解説したもの。今日では再検討を必要とするが、古典解読には必読の書である。『経伝釈詞補・再補』(清の孫経世)とあわせて利用するとよい。
漢字源に「経」で始まるの検索結果 1-48。
 仲買人。▽「景気がよい」の「景気」は「経紀」の当て字。
仲買人。▽「景気がよい」の「景気」は「経紀」の当て字。
 ギヨウ時代の音楽の名。〔
ギヨウ時代の音楽の名。〔 〔国〕会計事務をとること。また、その係。
〔国〕会計事務をとること。また、その係。