複数辞典一括検索+![]()
![]()
まさ🔗⭐🔉
まさ [1]
(1)花崗(カコウ)岩などの風化・分解してできた砂。瀬戸内海沿岸地方や,愛知県・岐阜県下に発達。
(2)富士・愛鷹(アシタカ)山麓の固結した火山灰土の俗称。
(3)左官用の砂混じりの粘土。床の間の壁などに用いる。まさつち。とこつち。
まさ【正】🔗⭐🔉
まさ 【正】 (名・形動ナリ)
正しい・こと(さま)。「自性(ヒトトナリ)―なることを心に存す/霊異記(上訓注)」
まさ【柾】🔗⭐🔉
まさ [1] 【柾】
〔「まさ(正)」と同源〕
(1)「柾目(マサメ)」の略。「桐の―の下駄」
(2)「柾目紙」の略。
まさあ🔗⭐🔉
まさあ (連語)
〔丁寧の助動詞「ます」に終助詞「わ」の付いた「ますわ」の転。短呼して「まさ」とも〕
「ます」を強調して,威勢よく言う言い方。「病気はきっと治り―」
ま-さい【真 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
ま-さい ―サヒ 【真 】
〔「ま」は接頭語〕
鋭利な剣。「太刀ならば,呉(クレ)の―/日本書紀(推古)」
】
〔「ま」は接頭語〕
鋭利な剣。「太刀ならば,呉(クレ)の―/日本書紀(推古)」
 】
〔「ま」は接頭語〕
鋭利な剣。「太刀ならば,呉(クレ)の―/日本書紀(推古)」
】
〔「ま」は接頭語〕
鋭利な剣。「太刀ならば,呉(クレ)の―/日本書紀(推古)」
ま-さい【磨砕・摩砕】🔗⭐🔉
ま-さい [0] 【磨砕・摩砕】 (名)スル
こすり,くだくこと。石うすでこなごなにすること。
マサイ Masai
Masai 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
マサイ  Masai
Masai 東アフリカ,ビクトリア湖東部のサバンナに住む牧畜民。ウシ・ヤギ・ヒツジを飼養。
東アフリカ,ビクトリア湖東部のサバンナに住む牧畜民。ウシ・ヤギ・ヒツジを飼養。
 Masai
Masai 東アフリカ,ビクトリア湖東部のサバンナに住む牧畜民。ウシ・ヤギ・ヒツジを飼養。
東アフリカ,ビクトリア湖東部のサバンナに住む牧畜民。ウシ・ヤギ・ヒツジを飼養。
まさ う【坐さふ】🔗⭐🔉
う【坐さふ】🔗⭐🔉
まさ う ―フ 【坐さふ】 (連語)
〔尊敬語の動詞「坐す」に継続の助動詞「ふ」が付いた語〕
いらっしゃる。おいでになる。「脇息(キヨウソク)をおさへて―
う ―フ 【坐さふ】 (連語)
〔尊敬語の動詞「坐す」に継続の助動詞「ふ」が付いた語〕
いらっしゃる。おいでになる。「脇息(キヨウソク)をおさへて― へ万世に/後撰(慶賀)」
へ万世に/後撰(慶賀)」
 う ―フ 【坐さふ】 (連語)
〔尊敬語の動詞「坐す」に継続の助動詞「ふ」が付いた語〕
いらっしゃる。おいでになる。「脇息(キヨウソク)をおさへて―
う ―フ 【坐さふ】 (連語)
〔尊敬語の動詞「坐す」に継続の助動詞「ふ」が付いた語〕
いらっしゃる。おいでになる。「脇息(キヨウソク)をおさへて― へ万世に/後撰(慶賀)」
へ万世に/後撰(慶賀)」
ま-さお【真青】🔗⭐🔉
ま-さお ―サヲ 【真青】 (形動ナリ)
非常に青いさま。まっさお。「―に光る物有り/今昔 27」
まさおか【正岡】🔗⭐🔉
まさおか マサヲカ 【正岡】
姓氏の一。
まさおか-しき【正岡子規】🔗⭐🔉
まさおか-しき マサヲカ― 【正岡子規】
(1867-1902) 俳人・歌人。松山市生まれ。本名,常規。別号,獺祭(ダツサイ)書屋主人・竹の里人など。新聞「日本」・俳誌「ホトトギス」によって写生による新しい俳句を指導,「歌よみに与ふる書」を著して万葉調を重んじ,根岸短歌会を興す。また写生文による文章革新を試みるなど,近代文学史上に大きな足跡を残した。著「竹の里歌」「俳諧大要」「仰臥漫録」など。
まさか🔗⭐🔉
まさか [1]
■一■ (名)
(1)予期しない事態が目の前に迫っていること。「―の場合に備える」
(2)さしあたっての今。現在。当座。「奥をなかねそ―し良かば/万葉 3410」
■二■ (副)
(1)(打ち消しや反語の表現を伴う)どう考えても,そこに述べられている事態が起こりそうもないさま。いくらなんでも。よもや。まさかに。「―雨は降らないだろう」「―やめろともいえないし,困った」「『おまえがやったのか』『―』」
(2)そこに述べられている事態が実際に起こるさま。現実に。本当に。まさかに。「―合戦ニナルト,臆病神ガツク/ヘボン(三版)」「とは思つてゐるやうなものの,―影口が耳に入ると厭なものさ/浮雲(四迷)」
〔「真逆」とも書く〕
まさか-に🔗⭐🔉
まさか-に [1] (副)
「まさか{■二■}」に同じ。
(1)いくらなんでも。よもや。「―餓えるやうなことも御座いますまい/蒲団(花袋)」
(2)現実に。本当に。たしかに。「父は王者の子孫なり,と―聞て常に忘れず/慨世士伝(逍遥)」
〔「真逆に」とも書く〕
まさか-の-とき【まさかの時】🔗⭐🔉
まさか-の-とき [6] 【まさかの時】
予期しない事態が起こって切羽つまったとき。万一の場合。「―役に立つ」
ま-さかき【真榊・真賢木】🔗⭐🔉
ま-さかき 【真榊・真賢木】
〔「ま」は接頭語〕
榊(サカキ)の美称。「五百箇(イオツ)の―をねこじにこじて/日本書紀(神代上訓)」
ま-さかさま【真逆様】🔗⭐🔉
ま-さかさま 【真逆様】 (名・形動ナリ)
「まっさかさま(真逆様)」に同じ。「―のくせごと/著聞 16」
まさかど【将門】🔗⭐🔉
まさかど 【将門】
(1)平(タイラノ)将門のこと。
(2)歌舞伎舞踊「忍夜恋曲者(シノビヨルコイハクセモノ)」の通称。
まさかど-き【将門記】🔗⭐🔉
まさかど-き 【将門記】
⇒しょうもんき(将門記)
まさかり【鉞】🔗⭐🔉
まさかり [0][2] 【鉞】
(1)木を切ったり,削ったりするための刃幅の広い斧(オノ)。武具としても用いた。刃広(ハビロ)。
(2)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。菊と組み合わせるものもある。
鉞(1)
 [図]
[図]
 [図]
[図]
まさ-き【正木・柾】🔗⭐🔉
まさ-き [0] 【正木・柾】
ニシキギ科の常緑低木。海岸地方に生え,庭木や生け垣とする。高さ約4メートル。枝は緑色。葉は卵形で,質厚く光沢がある。夏,開花。果実は球形で,熟すと裂けて,黄赤色の種子を現す。
〔「柾の実」は [季]秋〕
まさき-の-かずら【柾の葛】🔗⭐🔉
まさき-の-かずら ―カヅラ 【柾の葛】
テイカカズラの古名。また,ツルマサキとも。「外山なる―色づきにけり/神楽歌」
まさき【正木】🔗⭐🔉
まさき 【正木】
姓氏の一。
まさき-ひろし【正木ひろし】🔗⭐🔉
まさき-ひろし 【正木ひろし】
(1896-1975) 弁護士。東京生まれ。東大卒。第二次大戦中から,個人誌「近きより」を刊行し,厳しく時局を批判。一貫して人道主義の立場にたち,戦後は三鷹事件・八海事件・白鳥事件の弁護を担当。
まさき-りゅう【正木流】🔗⭐🔉
まさき-りゅう ―リウ 【正木流】
薙刀(ナギナタ)の流派の一。正木太郎太夫利充(俊充とも)のはじめたもの。
まさき【松前】🔗⭐🔉
まさき 【松前】
愛媛県中西部,伊予郡の町。松山市の南に接し,伊予灘に面する。
ま-さきく【真幸く】🔗⭐🔉
ま-さきく 【真幸く】 (副)
〔「ま」は接頭語〕
無事で。つつがなく。「―あらばまたかへりみむ/万葉 141」
まさきよ【正清】🔗⭐🔉
まさきよ 【正清】
(1665-1730) 江戸中期の刀工。薩摩の人。江戸で将軍吉宗のために刀を鍛え,それにより主水正(モンドノシヨウ)を受領,一葉葵を刻むことを許された。
ま-さぐ・る【弄る】🔗⭐🔉
ま-さぐ・る [3][0] 【弄る】 (動ラ五[四])
(1)手をしきりに動かしてさぐる。「赤子が母親の懐を―・る」「ポケットを―・る」
(2)手で触れる。もてあそぶ。「琴を臥しながら―・りて/落窪 1」
ま-さご【真砂】🔗⭐🔉
ま-さご [0] 【真砂】
〔「真」は美称〕
砂や小さい石。いさご。まなご。「浜の―」
まさご-じ【真砂路】🔗⭐🔉
まさご-じ ―ヂ [3] 【真砂路】
小石や砂の道。砂浜の道。「―の次第に低くなりて/うたかたの記(鴎外)」
まさ-ざま【勝様】🔗⭐🔉
まさ-ざま 【勝様】 (形動ナリ)
よりまさっているさま。「このひめきみに殿教へきこえ給へりければ,―に今少し今めかしさ添ひて弾かせ給ふ/栄花(見はてぬ夢)」
まさ-ざま【増様】🔗⭐🔉
まさ-ざま 【増様】 (形動ナリ)
数量・程度が増していくさま。「督の殿の御方の女房は,この御方よりも―に急ぐ/栄花(初花)」
まさ・し【正し】🔗⭐🔉
まさ・し 【正し】 (形シク)
(1)事実と合っている。正しい。正確である。「かく恋ひむものとは我も思ひにき心のうちぞ―・しかりける/古今(恋四)」
(2)本物である。正真正銘の。「―・しい太上法皇の王子をうちたてまつる/平家 4」
(3)現実のことである。確実である。「鹿谷に寄り合ひたりし事は,―・しう見聞かれしかば/平家 3」
→まさしく
まさしく【正しく】🔗⭐🔉
まさしく [2] 【正しく】 (副)
〔形容詞「正し」の連用形から〕
確かに。まちがいなく。まさに。「これは―背信行為だ」
まさしげ-りゅう【正成流】🔗⭐🔉
まさしげ-りゅう ―リウ 【正成流】
兵法の流派の一。楠木正成の兵法を伝えたものという。
マサダ Masada
Masada 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
マサダ  Masada
Masada イスラエル,死海南西にある岩山。また,その崖(ガケ)の上にある遺跡。紀元後73年,ローマ軍の攻撃を受けてユダヤ反乱軍の全員九六〇名が自害。
イスラエル,死海南西にある岩山。また,その崖(ガケ)の上にある遺跡。紀元後73年,ローマ軍の攻撃を受けてユダヤ反乱軍の全員九六〇名が自害。
 Masada
Masada イスラエル,死海南西にある岩山。また,その崖(ガケ)の上にある遺跡。紀元後73年,ローマ軍の攻撃を受けてユダヤ反乱軍の全員九六〇名が自害。
イスラエル,死海南西にある岩山。また,その崖(ガケ)の上にある遺跡。紀元後73年,ローマ軍の攻撃を受けてユダヤ反乱軍の全員九六〇名が自害。
マサチューセッツ Massachusetts
Massachusetts 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
マサチューセッツ  Massachusetts
Massachusetts アメリカ合衆国北東部,大西洋岸にある州。ピューリタンが開拓。独立一三州の一。州都ボストン。
アメリカ合衆国北東部,大西洋岸にある州。ピューリタンが開拓。独立一三州の一。州都ボストン。
 Massachusetts
Massachusetts アメリカ合衆国北東部,大西洋岸にある州。ピューリタンが開拓。独立一三州の一。州都ボストン。
アメリカ合衆国北東部,大西洋岸にある州。ピューリタンが開拓。独立一三州の一。州都ボストン。
マサチューセッツ-こうかだいがく【―工科大学】🔗⭐🔉
マサチューセッツ-こうかだいがく ―コウクワ― 【―工科大学】
〔Massachusetts Institute of Technology〕
アメリカの私立大学の一。1861年創設。所在地はマサチューセッツ州ケンブリッジ。MIT 。
ま-さつ【摩擦】🔗⭐🔉
ま-さつ [0] 【摩擦】 (名)スル
〔friction〕
(1)こすること。すれ合うこと。「体を―する」
(2)利害・意見・性質の違いなどから生まれるもめごと。軋轢(アツレキ)。「―を生ずる」
(3)二物体が接触して相対運動をしようとするとき,または運動しているとき,その接触面で運動を阻止しようとする力が接線方向にはたらくこと,またはその力(摩擦力)。相対速度の有無により静止摩擦と運動摩擦,相対運動の種類により滑り摩擦と転がり摩擦がある。このほか,液体内部にはたらく内部摩擦(粘性)がある。
〔近世中国語からの借用〕
まさつ-おん【摩擦音】🔗⭐🔉
まさつ-おん [3] 【摩擦音】
調音方法による子音の分類の一。調音器官を接近させて呼気の通路に著しいせばめをつくり,そこを呼気が通過するときに生ずる噪音(ソウオン)。「すずめ」の[s][z]や,「しじみ」の[ ][
][ ]など。
]など。
 ][
][ ]など。
]など。
まさつ-かく【摩擦角】🔗⭐🔉
まさつ-かく [3] 【摩擦角】
物体をのせた斜面の傾きを次第に大きくしていって,物体が滑り始める角度。この角度の正接は静止摩擦係数に等しい。
まさつ-ぐい【摩擦杭】🔗⭐🔉
まさつ-ぐい ―グヒ [3] 【摩擦杭】
地盤との摩擦力によって支持される杭。
→支持杭
まさつ-クラッチ【摩擦―】🔗⭐🔉
まさつ-クラッチ [5] 【摩擦―】
摩擦により力を伝えたり切ったりする構造のクラッチ。円板クラッチ・円錐クラッチなどがある。
まさつ-ぐるま【摩擦車】🔗⭐🔉
まさつ-ぐるま [4] 【摩擦車】
摩擦によって回転を伝導する車。車または円板・円錐の表面にゴム・木など摩擦の多いものを貼りつけ,二つの車を圧着して伝導を行う。
まさつ-けいすう【摩擦係数】🔗⭐🔉
まさつ-けいすう [4][6] 【摩擦係数】
二つの物体の接触面に平行にはたらく摩擦力と,その面に直角にはたらく垂直抗力(圧力)との比。摩擦の種類,接する物質の違い・表面の状態などによって大きさが異なる。一般に,静止摩擦・滑り摩擦・転がり摩擦の順に小さくなる。
まさつ-そんしつ【摩擦損失】🔗⭐🔉
まさつ-そんしつ [4] 【摩擦損失】
運動エネルギーまたは仕事が,摩擦によって熱に転化すること。また,その転化量。
まさつ-つぎて【摩擦接(ぎ)手】🔗⭐🔉
まさつ-つぎて [4] 【摩擦接(ぎ)手】
二つの軸をそれぞれの端面を接触させ,摩擦力によって連動させる接ぎ手。
まさつ-ていこう【摩擦抵抗】🔗⭐🔉
まさつ-ていこう ―カウ [4] 【摩擦抵抗】
流体の中を進行する物体に生ずる抵抗力のうち,物体表面にはたらく摩擦力の,流れの方向への成分の総和。流体が粘性をもつために生じる。粘性抵抗。
まさつ-てき-しつぎょう【摩擦的失業】🔗⭐🔉
まさつ-てき-しつぎょう ―シツゲフ [0] 【摩擦的失業】
需要の変化により,ある産業が業績不振となって生じた失業者を,他産業がすぐ吸収できない場合に,一時的に発生する失業。
まさつ-でんき【摩擦電気】🔗⭐🔉
まさつ-でんき [4] 【摩擦電気】
異種の物体を互いに摩擦するときに生ずる正負の電気。
まさつ-ブレーキ【摩擦―】🔗⭐🔉
まさつ-ブレーキ [5] 【摩擦―】
回転体にブレーキ-シューなどを押しつけ,摩擦によって回転に制動をかけるブレーキ。
マサッチオ Masaccio
Masaccio 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
マサッチオ  Masaccio
Masaccio (1401-1428頃) イタリアの画家。絵画におけるルネサンス様式の創始者として盛期ルネサンスに大きな影響を及ぼした。代表作「楽園追放」
(1401-1428頃) イタリアの画家。絵画におけるルネサンス様式の創始者として盛期ルネサンスに大きな影響を及ぼした。代表作「楽園追放」
 Masaccio
Masaccio (1401-1428頃) イタリアの画家。絵画におけるルネサンス様式の創始者として盛期ルネサンスに大きな影響を及ぼした。代表作「楽園追放」
(1401-1428頃) イタリアの画家。絵画におけるルネサンス様式の創始者として盛期ルネサンスに大きな影響を及ぼした。代表作「楽園追放」
まさつね【正恒】🔗⭐🔉
まさつね 【正恒】
平安中期の備前の刀工。古備前中でも初期に属す。高尚な作風で,佐々木高綱の縄切正恒の作者。同名の刀工は古青江(コアオエ)にもいる。生没年未詳。
まさつね【政常】🔗⭐🔉
まさつね 【政常】
(1536-1619) 安土桃山・江戸初期の尾張の刀工。美濃の人。本名,納土太郎助。相模守(サガミノカミ)。関の兼常の門人で初銘兼常。直刃を得意とし,短刀の名手。
まさで-に【正でに】🔗⭐🔉
まさで-に 【正でに】 (副)
〔「で」は「手」で,様子・状態を表す〕
ありのままに。真実に。たしかに。「武蔵野に占部(ウラヘ)かた焼き―も告らぬ君が名占に出にけり/万葉 3374」
まさとし【正俊】🔗⭐🔉
まさとし 【正俊】
江戸初期,山城の刀工。美濃国関の兼道の四男。越中守。三品(ミシナ)派の基礎を築く。兄金道・吉道も良工であるが,正俊は覇気ある作刀で最も名高い。
まさな-ごと【正無事】🔗⭐🔉
まさな-ごと 【正無事】
冗談ごと。いたずら。「―せさせ給ひしを忘れ給はで/徒然 176」
まさ-な・し【正無し】🔗⭐🔉
まさ-な・し 【正無し】 (形ク)
普通の状態からかけ離れている。尋常でない。多く好ましくない場合にいい,不体裁・不都合・不似合いなどの意味にいう。
(1)みっともない。見苦しい。「こわ高になのたまひそ,屋の上にをる人どもの聞くに,いと―・し/竹取」「―・うも敵にうしろをば見する物かな/平家 8」
(2)よろしくない。いけない。「まめまめしき物は,―・かりなむ/更級」
(3)尋常でない。はなはだしい。「いとかう―・きまでいにしへの墨書の上手ども,あとを暗うなしつべかめるは/源氏(絵合)」
まさ-に【正に】🔗⭐🔉
まさ-に [1] 【正に】 (副)
(1)ある事柄が成り立つことが動かしがたいさま。疑いもなく。確実に。「金十万円―受領致しました」「―名案だ」「―一石二鳥だ」
(2)一つの事物をそれ以外にはないものとして特に取りたてるさま。ちょうど。ぴったり。「彼こそが―適任だ」「あの姿は―彼だ」「悲劇から今―一年が経過した」
(3)(多く「将に」と書く)もう少しのところで物事が起こるさま。ちょうど今。「―沈もうとする夕日」「彼は今―運命の分かれ目にさしかかろうとしている」「―出発する直前だった」
(4)(多く「当に」と書く。「まさに…べし」の形で)ある事柄が成立することが強く望まれているさま。当然。「彼こそが―罪を受けるべきだ」「男は―かくあるべきだ」
(5)(反語表現に用いられて)ある事柄が成立するはずのないことを強調する。どうして…しようか。「なに人か迎へきこえむ。―許さむや/竹取」
〔(3)(4)は漢文訓読に用いられた語法〕
ま-さば【真鯖】🔗⭐🔉
ま-さば [0] 【真鯖】
スズキ目の海魚。全長45センチメートルほど。体は紡錘形でやや側扁する。体色は背面が青緑色で波状紋があり,腹面は銀白色。食用とし,秋は特に美味。温帯域沿岸の回遊魚。ヒラサバ。ホンサバ。
→サバ
まさひで【正秀】🔗⭐🔉
まさひで 【正秀】
(1750-1825) 江戸中期の刀工・考証家。出羽の人。本名,川部儀八郎。水心子と号す。刀剣の沈滞期に復古刀論を唱え,江戸で各種の製作法を試みた。事実上の新新刀の祖。著「刀剣実用論」など。
まさ-ぶき【柾葺き】🔗⭐🔉
まさ-ぶき [0] 【柾葺き】
台形の 板(コケライタ)の厚みのある方を下に,羽重ねにして屋根を葺くこと。
板(コケライタ)の厚みのある方を下に,羽重ねにして屋根を葺くこと。
 板(コケライタ)の厚みのある方を下に,羽重ねにして屋根を葺くこと。
板(コケライタ)の厚みのある方を下に,羽重ねにして屋根を葺くこと。
まさ-ぼん【麻沙本】🔗⭐🔉
まさ-ぼん [0] 【麻沙本】
中国,福建省建陽県麻沙鎮の書店で作られた本。南宋から明代にかけて盛んに出版されたが,誤刻が多く,粗悪な刊本の称ともされた。福建本。 本(ビンポン)。
本(ビンポン)。
 本(ビンポン)。
本(ビンポン)。
まさむね【正宗】🔗⭐🔉
まさむね 【正宗】
(1)鎌倉末期の鎌倉の刀工。岡崎五郎入道と称し,また新藤五国光の弟子行光の子と伝える。近世以降刀工の代名詞のごとくその名は高いが,確実な在銘の作品はごく少なく,伝説的な部分が多い。名物,庖丁正宗・日向正宗などの作者と伝える。生没年未詳。
(2)正宗{(1)}が鍛えた刀。日本における代表的な名刀とされ,名刀の意にも用いる。
(3)灘(ナダ)の清酒の銘。天保年間(1830-1844)灘の山邑氏が名づけたのに始まるという。
まさむね【正宗】🔗⭐🔉
まさむね 【正宗】
姓氏の一。
まさむね-はくちょう【正宗白鳥】🔗⭐🔉
まさむね-はくちょう ―ハクテウ 【正宗白鳥】
(1879-1962) 小説家・劇作家・評論家。岡山県生まれ。本名,忠夫。早大卒。「塵埃」で文壇に登場,「何処へ」「微光」「泥人形」を書き自然主義文学の代表的作家となる。戯曲・評論にもすぐれ,「作家論」は他の追随を許さない人物批評。小説「牛部屋の臭い」「入江のほとり」,戯曲「人生の幸福」
まさ-め【正眼・正目】🔗⭐🔉
まさ-め [0] 【正眼・正目】
正面から見ること。まとも。「よく目をあけて―に私の顔を御覧/谷間の姫百合(謙澄)」
まさ-め【柾目・正目】🔗⭐🔉
まさ-め [0] 【柾目・正目】
木材を,その中心に向かう方向(半径方向)で縦断したときの面。多くは,年輪が平行な木目として現れる。まさ。
⇔板目
柾目
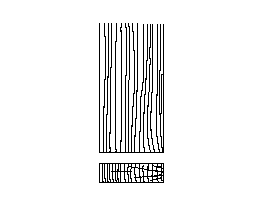 [図]
[図]
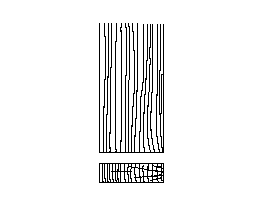 [図]
[図]
まさめ-がみ【柾目紙・正目紙】🔗⭐🔉
まさめ-がみ [3] 【柾目紙・正目紙】
(1)漉(ス)き目が柾目のように正しく厚く白い和紙。多く,錦絵(ニシキエ)を刷るのに用いた。
(2)桐・杉などの柾目の木材を鉋(カンナ)で薄く紙のように削ったもの。箱の上張りなどに用いる。まさ。
ま-さやか【真明か】🔗⭐🔉
ま-さやか 【真明か】 (形動ナリ)
〔「ま」は接頭語〕
はっきりしているさま。さやか。「御坂たばらば―に見む/万葉 4424」
まさり【勝り・優り】🔗⭐🔉
まさり [3] 【勝り・優り】
まさること。すぐれていること。現代語では多く他の語と複合して用いる。「男―」「親―」
まさり-おとり【優り劣り】🔗⭐🔉
まさり-おとり [0][4] 【優り劣り】
すぐれることと劣ること。「―がない」
まさり-がお【優り顔・勝り顔】🔗⭐🔉
まさり-がお ―ガホ 【優り顔・勝り顔】
得意げな顔つき。「あな,―や/宇津保(国譲上)」
まさり-ぐさ【優り草・勝り草】🔗⭐🔉
まさり-ぐさ 【優り草・勝り草】
菊の異名。「盃に向かへば色もなほ―/謡曲・松虫」
まさり-ざま【優り様・勝り様】🔗⭐🔉
まさり-ざま 【優り様・勝り様】 (形動ナリ)
よりすぐれているさま。「艶にまばゆきさまは,―にぞ見ゆる/源氏(明石)」
マサリク Tom
Tom
 Masaryk
Masaryk 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
マサリク  Tom
Tom
 Masaryk
Masaryk (1850-1937) チェコスロバキアの政治家・哲学者。プラハ大学教授。独立運動を指導,1918年共和国初代大統領となる。小協商結成・国内民主化・少数民族保護などに尽くした。
(1850-1937) チェコスロバキアの政治家・哲学者。プラハ大学教授。独立運動を指導,1918年共和国初代大統領となる。小協商結成・国内民主化・少数民族保護などに尽くした。
 Tom
Tom
 Masaryk
Masaryk (1850-1937) チェコスロバキアの政治家・哲学者。プラハ大学教授。独立運動を指導,1918年共和国初代大統領となる。小協商結成・国内民主化・少数民族保護などに尽くした。
(1850-1937) チェコスロバキアの政治家・哲学者。プラハ大学教授。独立運動を指導,1918年共和国初代大統領となる。小協商結成・国内民主化・少数民族保護などに尽くした。
ま-さる【真猿】🔗⭐🔉
ま-さる 【真猿】
猿。和歌で「増さる」にかけて用いられる。「こずゑにてわびしらになく声聞けばものの哀れの―なりけり/為忠百首(丹後守)」
まさ・る【勝る・優る】🔗⭐🔉
まさ・る [2][0] 【勝る・優る】 (動ラ五[四])
〔「増さる」と同源〕
(1)他のものと比べて力量や価値などが上である。すぐれている。
⇔劣る
「健康は富に―・る」「この車は経済性で―・る」
(2)相対的に程度が上である。他をしのぐ。「聞きしに―・る美しさだ」「静かと云ふよりは淋しさが―・つて居て/ふらんす物語(荷風)」
(3)官位などが上である。「先だちてより言ひける男は官―・りて/平中 1」
まさ・る【増さる】🔗⭐🔉
まさ・る [2][0] 【増さる】 (動ラ五[四])
数量や程度が大きくなる。ふえる。「雨で川の水かさが―・る」「数知らず苦しきことのみ―・れば/源氏(桐壺)」
まさか(和英)🔗⭐🔉
まさか
まさか! Nonsense!/That's impossible./Well,I never!/You don't say! 〜の時に in (an) emergency.
まさかり【鉞】(和英)🔗⭐🔉
まさかり【鉞】
a broadax(e).
まさき【柾】(和英)🔗⭐🔉
まさき【柾】
《植》a spindle tree.
まさしく【正しく】(和英)🔗⭐🔉
まさしく【正しく】
surely;certainly;→英和
no doubt;really.
まさつ【摩擦】(和英)🔗⭐🔉
まさに【正に】(和英)🔗⭐🔉
まさに(和英)🔗⭐🔉
まさに
〜…しようとしている be going[about]to do;be on the point of doing.
まさめ【柾目】(和英)🔗⭐🔉
まさめ【柾目】
the straight grain.〜の straight-grained.
まさゆめ【正夢だった】(和英)🔗⭐🔉
まさゆめ【正夢だった】
The dream came true.
まさる【勝る】(和英)🔗⭐🔉
まさる【勝る】
be better;be superior;surpass.→英和
〜とも劣らぬ not at all inferior.
大辞林に「マサ」で始まるの検索結果 1-92。もっと読み込む