複数辞典一括検索+![]()
![]()
じっ-かい【十戒・十誡】🔗⭐🔉
じっ-かい [0] 【十戒・十誡】
(1)〔仏〕(ア)二〇歳未満の出家者である沙弥・沙弥尼が守るべき一〇の戒め。不殺生・不偸盗(フチユウトウ)・不淫 (フインイツ)(性行為の禁止)・不妄語・不飲酒(フオンジユ)・不塗飾香鬘(フトシヨクコウマン)・不歌舞観聴(芸能観賞の禁止)・不坐高大広床・不非時食(フヒジジキ)・不蓄金銀宝戒のこと。沙弥の十戒。(イ)十善戒のこと。《十戒》
(2)〔Decalogue, Ten Commandments〕
旧約聖書の出エジプト記二〇章,申命記五章などで,モーセを介してシナイ山で神からイスラエルの民に与えられたとされる一〇か条の戒め。ヤハウェ以外のものを神としないこと,ヤハウェ神の名をみだりに挙げないこと,父母を敬うこと,安息日を聖別することのほか,殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲,偶像を作ることなどを禁じている。《十誡》
(フインイツ)(性行為の禁止)・不妄語・不飲酒(フオンジユ)・不塗飾香鬘(フトシヨクコウマン)・不歌舞観聴(芸能観賞の禁止)・不坐高大広床・不非時食(フヒジジキ)・不蓄金銀宝戒のこと。沙弥の十戒。(イ)十善戒のこと。《十戒》
(2)〔Decalogue, Ten Commandments〕
旧約聖書の出エジプト記二〇章,申命記五章などで,モーセを介してシナイ山で神からイスラエルの民に与えられたとされる一〇か条の戒め。ヤハウェ以外のものを神としないこと,ヤハウェ神の名をみだりに挙げないこと,父母を敬うこと,安息日を聖別することのほか,殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲,偶像を作ることなどを禁じている。《十誡》
 (フインイツ)(性行為の禁止)・不妄語・不飲酒(フオンジユ)・不塗飾香鬘(フトシヨクコウマン)・不歌舞観聴(芸能観賞の禁止)・不坐高大広床・不非時食(フヒジジキ)・不蓄金銀宝戒のこと。沙弥の十戒。(イ)十善戒のこと。《十戒》
(2)〔Decalogue, Ten Commandments〕
旧約聖書の出エジプト記二〇章,申命記五章などで,モーセを介してシナイ山で神からイスラエルの民に与えられたとされる一〇か条の戒め。ヤハウェ以外のものを神としないこと,ヤハウェ神の名をみだりに挙げないこと,父母を敬うこと,安息日を聖別することのほか,殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲,偶像を作ることなどを禁じている。《十誡》
(フインイツ)(性行為の禁止)・不妄語・不飲酒(フオンジユ)・不塗飾香鬘(フトシヨクコウマン)・不歌舞観聴(芸能観賞の禁止)・不坐高大広床・不非時食(フヒジジキ)・不蓄金銀宝戒のこと。沙弥の十戒。(イ)十善戒のこと。《十戒》
(2)〔Decalogue, Ten Commandments〕
旧約聖書の出エジプト記二〇章,申命記五章などで,モーセを介してシナイ山で神からイスラエルの民に与えられたとされる一〇か条の戒め。ヤハウェ以外のものを神としないこと,ヤハウェ神の名をみだりに挙げないこと,父母を敬うこと,安息日を聖別することのほか,殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲,偶像を作ることなどを禁じている。《十誡》
じっ-かい【十界】🔗⭐🔉
じっ-かい [0] 【十界】
〔仏〕 全世界を構成している一〇の世界。仏界・菩薩界・縁覚(エンガク)界・声聞(シヨウモン)界・天上界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界。初めの四つは聖者の世界で四聖といい,あとの六つは迷いをもつ凡夫の世界で六凡という。十の界。
じっかい-ごぐ【十界互具】🔗⭐🔉
じっかい-ごぐ [5] 【十界互具】
〔仏〕 天台宗の教理で,地獄界など,十界の一つがそれぞれ互いに他の九界をそなえているということ。
じっかい-だいまんだら【十界大曼荼羅】🔗⭐🔉
じっかい-だいまんだら [7] 【十界大曼荼羅】
日蓮宗の曼荼羅。題目を中心に,十界の諸菩薩などの名を記す。輪円具足の大曼荼羅。
じっ-かん【十干】🔗⭐🔉
じっ-かん [0][3] 【十干】
甲・乙・丙・丁(テイ)・戊(ボ)・己(キ)・庚(コウ)・辛・壬(ジン)・癸(キ)の総称。五行の木・火・土・金・水と結びつけて,それぞれ兄(エ)(陽),弟(ト)(陰)を当て,甲(キノエ)・乙(キノト)・丙(ヒノエ)・丁(ヒノト)・戊(ツチノエ)・己(ツチノト)・庚(カノエ)・辛(カノト)・壬(ミズノエ)・癸(ミズノト)とも読む。十二支と組み合わせて年・日の表示などに用いる。十母。
→十干[表]
じっかん-じゅうにし【十干十二支】🔗⭐🔉
じっかん-じゅうにし ―ジフニ― [7] 【十干十二支】
十干と十二支。また,それを組み合わせたもの。日にこの記号をつけて表す干支記日法は中国の殷(イン)代から始められ,中国と日本で共通に今日まで継続している。また,年に干支をつけて表す干支記年法は紀元前三世紀頃から行われ,やはり中国・日本と共通に今日まで継続している。干支(エト)((カンシ))。
→干支(エト)
じっきゃく-もく【十脚目】🔗⭐🔉
じっきゃく-もく [4] 【十脚目】
節足動物甲殻綱の一目。エビ・カニ・ヤドカリ類など。
じっきんしょう【十訓抄】🔗⭐🔉
じっきんしょう ―セウ 【十訓抄】
⇒じっくんしょう(十訓抄)
じっくんしょう【十訓抄】🔗⭐🔉
じっくんしょう ―セウ 【十訓抄】
説話集。三巻。菅原為長編,六波羅二臈左衛門入道編などの説があるが未詳。1252年成立。一〇項に分けて,中国説話を含む二百八十余の教訓的な説話を収録したもの。先行説話集から伝承した話が多い。じっきんしょう。
じっ-けつ【十傑】🔗⭐🔉
じっ-けつ [0] 【十傑】
ある分野で抜きんでている一〇人。ベストテン。「打撃―」
じっ-こう【十講】🔗⭐🔉
じっ-こう ―カウ [0] 【十講】
(1)「法華(ホツケ)十講」の略。
(2)一〇の講義。また,それを集めたもの。「英文学―」
じっこく-とうげ【十国峠・十石峠】🔗⭐🔉
じっこく-とうげ ―タウゲ 【十国峠・十石峠】
静岡県熱海市と函南(カンナミ)町の境にある峠。海抜774メートル。十国を一望できることからつけられた名で,眺望がよい。日金(ヒカネ)山。
じっ-さいし【十才子】🔗⭐🔉
じっ-さいし [3] 【十才子】
中国,明代の一〇人の詩仙。洪武〜永楽年間(1368-1424)では,林鴻(リンコウ)・鄭定(テイジヨウ)・王褒(オウホウ)・唐泰・高 (コウヘイ)・王恭・陳亮・永福王
(コウヘイ)・王恭・陳亮・永福王 (シヨウ)・周元・黄元。弘治・正徳年間(1488-1521)では,李夢陽(リボウヨウ)・何景明(カケイメイ)・徐禎卿(ジヨテイケイ)・辺貢・朱応登・顧
(シヨウ)・周元・黄元。弘治・正徳年間(1488-1521)では,李夢陽(リボウヨウ)・何景明(カケイメイ)・徐禎卿(ジヨテイケイ)・辺貢・朱応登・顧 (コリン)・陳沂(チンキ)・鄭善夫・康海・王九思をいう。
(コリン)・陳沂(チンキ)・鄭善夫・康海・王九思をいう。
 (コウヘイ)・王恭・陳亮・永福王
(コウヘイ)・王恭・陳亮・永福王 (シヨウ)・周元・黄元。弘治・正徳年間(1488-1521)では,李夢陽(リボウヨウ)・何景明(カケイメイ)・徐禎卿(ジヨテイケイ)・辺貢・朱応登・顧
(シヨウ)・周元・黄元。弘治・正徳年間(1488-1521)では,李夢陽(リボウヨウ)・何景明(カケイメイ)・徐禎卿(ジヨテイケイ)・辺貢・朱応登・顧 (コリン)・陳沂(チンキ)・鄭善夫・康海・王九思をいう。
(コリン)・陳沂(チンキ)・鄭善夫・康海・王九思をいう。
じっ-さいにち【十斎日】🔗⭐🔉
じっ-さいにち [3] 【十斎日】
〔仏〕 毎月,一・八・一四・一五・一八・二三・二四・二八・二九・三〇の各日をいう。この日に八斎戒を守り,それぞれの日に割り当てられた仏・菩薩(ボサツ)を念ずると罪消・増福の利益(リヤク)があるという。その仏・菩薩は,順に定光仏(ジヨウコウブツ)・薬師仏・普賢(フゲン)菩薩・阿弥陀(アミダ)仏・観世音菩薩・勢至菩薩・地蔵菩薩・毘盧舎那(ビルシヤナ)仏・薬王菩薩・釈迦牟尼(シヤカムニ)仏で,総じて十斎日仏と呼ぶ。
じっ-さく【十作】🔗⭐🔉
じっ-さく [0] 【十作】
鎌倉・室町時代にかけて現れたとされる能面作りの名人一〇人。多少の出入りがあるが,普通,日光・弥勒(ミロク)・夜叉(ヤシヤ)・文蔵・竜(辰)右衛門・赤鶴(シヤクヅル)・石王兵衛(イシオウヒヨウエ)・越智(エチ)・小牛・徳若をいう。
じゅう【十・拾】🔗⭐🔉
じゅう ジフ [1] 【十・拾】
数の名。九より一つ多い数。五の倍数。両手の指の数。と。とお。
じゅう=に八九(ハツク)🔗⭐🔉
――に八九(ハツク)
⇒十中八九(ジツチユウハツク)
じゅう=の一二(イチニ)🔗⭐🔉
――の一二(イチニ)
可能性などがわずかなこと。
じゅう-あく【十悪】🔗⭐🔉
じゅう-あく ジフ― [0][1] 【十悪】
(1)中国古代,特に重く罰せられた一〇の大罪。謀反(ムヘン)・謀大逆・謀叛(ムホン)・悪逆・不道・大不敬・不孝・不睦・不義・内乱の総称。
(2)〔仏〕 人間の基本的な一〇の罪悪。殺生・偸盗(チユウトウ)・邪婬(ジヤイン)・妄語・綺語(キゴ)・両舌・悪口・貪欲・瞋恚(シンイ)・邪見の総称。
⇔十善
じゅういち-がつ【十一月】🔗⭐🔉
じゅういち-がつ ジフイチグワツ [6] 【十一月】
一年の第一一番目の月。霜月。[季]冬。《あたゝかき―もすみにけり/中村草田男》
〔副詞的用法の場合,アクセントは [0]〕
じゅういちがつ-かくめい【十一月革命】🔗⭐🔉
じゅういちがつ-かくめい ジフイチグワツ― 【十一月革命】
(1)1917年11月(ロシア暦一〇月),レーニンらの指導するボルシェビキの武装蜂起(ホウキ)によって始まったロシア革命の一環をなす社会主義革命。ケレンスキー臨時政府が倒れ,ソビエト政府が成立。十月革命。
(2)「ドイツ革命」に同じ。
じゅういちがつ-じけん【十一月事件】🔗⭐🔉
じゅういちがつ-じけん ジフイチグワツ― 【十一月事件】
1934年(昭和9)村中孝次・磯部浅一ら陸軍皇道派青年将校が,クーデターを企図した容疑で,士官学校生徒とともに逮捕された事件。証拠不十分で不起訴になった。士官学校事件。
じゅういちめん-かんぜおん【十一面観世音】🔗⭐🔉
じゅういちめん-かんぜおん ジフイチメンクワンゼオン 【十一面観世音】
頭上に一一の面をもつ観音。衆生(シユジヨウ)を仏の悟りに到達させるとされる。一一の小面は,正面の三面が慈悲相,左方三面が瞋怒(シンド)相,右方三面が白牙上出相,後方の一面が大笑相,頂上の一面が仏相をそれぞれ現す。本面を加えて一一面とする像をはじめとして,面数も異なる物が多い。十一面観音。
十一面観世音
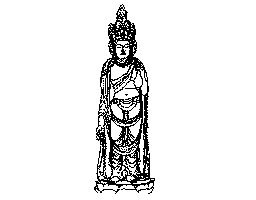 [図]
[図]
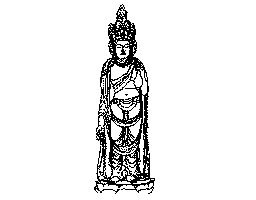 [図]
[図]
じゅういちめんかんぜおん-ほう【十一面観世音法】🔗⭐🔉
じゅういちめんかんぜおん-ほう ジフイチメンクワンゼオンホフ [10] 【十一面観世音法】
〔仏〕 密教で,十一面観世音を本尊として,無病息災を祈る修法。
じゅういちや【十一谷】🔗⭐🔉
じゅういちや ジフイチヤ 【十一谷】
姓氏の一。
じゅういちや-ぎさぶろう【十一谷義三郎】🔗⭐🔉
じゅういちや-ぎさぶろう ジフイチヤギサブラウ 【十一谷義三郎】
(1897-1937) 小説家。神戸生まれ。東大卒。「文芸時代」に参加。知的な文体で知られる。代表作「唐人お吉」
じゅう-おう【十王】🔗⭐🔉
じゅう-おう ジフワウ [3] 【十王】
〔仏〕 冥土にいて死者を裁く一〇人の王。秦広王・初江王・宋帝王・五官王・閻魔王・変成王・泰山王・平等王・都市王・五道転輪王の総称。死者は初七日から七七日までの各七日,百箇日,一周忌,三回忌にそれぞれの庁をめぐって来世の形態を定められる。中国,唐代末に道教の影響で成立し,平安中期以降日本にも移入された。
じゅうおう-の-ちょう【十王の庁】🔗⭐🔉
じゅうおう-の-ちょう ジフワウ―チヤウ 【十王の庁】
〔仏〕 十王のいる冥府の役所。冥土(メイド)。
じゅう-がつ【十月】🔗⭐🔉
じゅう-がつ ジフグワツ [4] 【十月】
一年の第一〇番目の月。神無(カンナ)月。[季]秋。
〔副詞的用法の場合,アクセントは [0]〕
じゅうがつ=の木(コ)の葉髪🔗⭐🔉
――の木(コ)の葉髪
陰暦一〇月頃になると,木の葉が落ちるように頭髪が抜け落ちること。
じゅうがつ-かくめい【十月革命】🔗⭐🔉
じゅうがつ-かくめい ジフグワツ― [5] 【十月革命】
〔ロシア暦で一〇月に起こったのでいう〕
⇒十一月革命(ジユウイチガツカクメイ)(1)
じゅうがつ-ざくら【十月桜】🔗⭐🔉
じゅうがつ-ざくら ジフグワツ― [5] 【十月桜】
シキザクラの別名。
じゅうがつ-じけん【十月事件】🔗⭐🔉
じゅうがつ-じけん ジフグワツ― 【十月事件】
1931年(昭和6)10月,旧陸軍の橋本欣五郎ら桜会幹部が中心となり,満州事変に呼応して,荒木貞夫中将を首班とする軍事政権樹立を企てたクーデター計画。未然に発覚したが,軍部の政治進出の契機となった。
じゅうがつ-じんみんほうき【十月人民蜂起】🔗⭐🔉
じゅうがつ-じんみんほうき ジフグワツ― 【十月人民蜂起】
1946年9月から一〇月にかけて,米軍政下の南朝鮮で起きた大規模なストライキ闘争。米の増配,賃上げなどを要求して労働組合がゼネストに突入し,米軍と衝突した。
じゅう-ぎ【十義】🔗⭐🔉
じゅう-ぎ ジフ― [1] 【十義】
〔礼記(礼運)〕
人がふみ行うべき十か条の徳義。父は慈,子は孝,兄は良,弟は弟,夫は義,婦は聴,長は恵,幼は順,君は仁,臣は忠であること。
じゅうぎゅう-ず【十牛図】🔗⭐🔉
じゅうぎゅう-ず ジフギウヅ [3] 【十牛図】
中国宋代の禅宗の書。仏道入門から真の悟りに至るまでの過程を,牧者と牛に託して一〇の絵と短文で示したもの。廓庵のものが広く行われ,尋牛・見跡・見牛・得牛・牧牛・騎牛帰家・忘牛存人・人牛倶忘・返本還源・入 (ニツテン)垂手の順。画題とされる。
(ニツテン)垂手の順。画題とされる。
 (ニツテン)垂手の順。画題とされる。
(ニツテン)垂手の順。画題とされる。
じゅうく-どよう【十九土用】🔗⭐🔉
じゅうく-どよう ジフク― [4] 【十九土用】
一九日間ある土用。普通,土用は一八日を一期とするが,没日(モツニチ)がある場合は一九日とし,夏季にあるときは特に暑いといわれる。
じゅうく-もん【十九文】🔗⭐🔉
じゅうく-もん ジフク― 【十九文】
〔十九文屋で売るような物の意〕
安物。がらくた。価値のないもの。「どれをとつても―/胆大小心録」
じゅうくもん-や【十九文屋】🔗⭐🔉
じゅうくもん-や ジフク― [0] 【十九文屋】
江戸時代,一九文均一で安物の雑貨を売った露店。十九文店。
じゅうげん-えんぎ【十玄縁起】🔗⭐🔉
じゅうげん-えんぎ ジフゲン― [5] 【十玄縁起】
〔仏〕「十玄縁起無礙(ムゲ)門」の略。華厳宗の根本的な教義の一。一〇の観点からすべての存在,すべての現象が果てしなく自在に一体となって,融通していることを説いた教説。十玄門。
じゅう-ごう【十号】🔗⭐🔉
じゅう-ごう ジフガウ [0] 【十号】
〔仏〕 仏の一〇の称号。如来・応来(オウグ)・正遍知・明行足・善逝(ゼンゼイ)・世間解・無上士・調御丈夫(ジヨウゴジヨウブ)・天人師・世尊。
じゅうご-ごそう【十語五草】🔗⭐🔉
じゅうご-ごそう ジフゴゴサウ [1] 【十語五草】
一〇種の物語と五種の草子。「秋斎間語」に竹取物語・宇津保物語・世継物語・いや世継物語・続世継物語・増鏡・栄花物語・狭衣物語・水鏡・伊勢物語,徒然草・枕草子・四季・御餝(オカザリ)の記・御湯殿の記が挙げられる。
じゅうご-しゅう【十五宗】🔗⭐🔉
じゅうご-しゅう ジフゴ― [1] 【十五宗】
十宗に,大念仏宗・真宗・時宗・日蓮宗・雑宗(修験道のこと)を加えたもの。
→十宗
じゅうご-だいじ【十五大寺】🔗⭐🔉
じゅうご-だいじ ジフゴ― [4] 【十五大寺】
奈良を中心とする一五の大寺の総称。「延喜式」では,東大寺・興福寺・元興寺・大安寺・薬師寺・西大寺・法隆寺・新薬師寺・招提寺・本元興寺・東寺・西寺・四天王寺・崇福寺・弘福寺を挙げる。
じゅうごにち-がゆ【十五日粥】🔗⭐🔉
じゅうごにち-がゆ ジフゴニチ― [5][0] 【十五日粥】
正月一五日の朝に食べる小豆(アズキ)粥。疫病・邪気をはらうという。また,粥占(カユウラ)を行う所もある。[季]新年。
じゅうごねん-せんそう【十五年戦争】🔗⭐🔉
じゅうごねん-せんそう ジフゴネンセンサウ 【十五年戦争】
満州事変(1931年)に始まり,日中戦争・太平洋戦争を経て1945年の敗戦に至る日本の15年間の対外戦争の総称。
じゅうご-や【十五夜】🔗⭐🔉
じゅうご-や ジフゴ― [0] 【十五夜】
(1)陰暦一五日の夜。満月の夜。
(2)陰暦八月一五日の夜。この夜,団子や芒(ススキ)の穂,果物などを供えて月をまつる。里芋などを供え,芋名月ともいう。かつては,これらの供え物を子供たちが持ち去るのを喜ぶ風習があった。仲秋。[季]秋。
→十三夜
じゅうさ-にち【十三日】🔗⭐🔉
じゅうさ-にち ジフサ― 【十三日】
〔「じゅうさんにち」とも〕
江戸時代,煤(スス)払いを行なった一二月一三日のこと。「毎年煤払ひ極月―に定めて/浮世草子・胸算用 1」
じゅうさん-かいき【十三回忌】🔗⭐🔉
じゅうさん-かいき ジフサンクワイキ [5] 【十三回忌】
死後満12年,死んだ日から数えて一三回目の回忌。十三年忌。
じゅうさん-かいだん【十三階段】🔗⭐🔉
じゅうさん-かいだん ジフサン― [5] 【十三階段】
〔台上まで階段が一三段あることから〕
絞首台の異名。
じゅうさん-がつ【十三月】🔗⭐🔉
じゅうさん-がつ ジフサングワツ [3] 【十三月】
〔一二月の翌月の意〕
一月。正月。
じゅうさんがつ=なる顔付き🔗⭐🔉
――なる顔付き
〔一年が一三か月もあるような気でいるということから,また一説に正月のような気分でいるところから〕
のんきな顔付き。おめでたい顔付き。「工商の家に―かまへ/浮世草子・永代蔵 5」
じゅうさん-がね【十三鐘】🔗⭐🔉
じゅうさん-がね ジフサン― 【十三鐘】
(1)奈良の興福寺で,衆徒の勤行(ゴンギヨウ)のため,明け七つと暮六つの時刻につきならした鐘。
(2)地歌の一。鹿を殺して石子詰めの刑を受けた一三歳の子の伝説に取材したもの。
じゅうさん-ぎょう【十三経】🔗⭐🔉
じゅうさん-ぎょう ジフサンギヤウ [3] 【十三経】
中国,儒家の一三の基本的経典。周易(易経)・尚書(書経)・毛詩(詩経)・周礼(シユライ)・儀礼(ギライ)・礼記(ライキ)・春秋左氏伝・春秋公羊(クヨウ)伝・春秋穀梁(コクリヨウ)伝・論語・孝経・爾雅(ジガ)・孟子をいい,宋代に定められた。じゅうさんけい。
じゅうさん-しゅう【十三宗】🔗⭐🔉
じゅうさん-しゅう ジフサン― [3] 【十三宗】
(1)中国仏教の一三宗派。涅槃(ネハン)・地論・摂論・成実(ジヨウジツ)・毘曇(ビドン)・律・三論・浄土・禅・天台・華厳・法相(ホツソウ)・真言。
(2)日本仏教の一三宗派。華厳・法相・律・天台・真言・臨済・曹洞(ソウトウ)・黄檗(オウバク)・浄土・真・融通念仏・時・日蓮。一三門派。
じゅうさんぞく-みつぶせ【十三束三伏せ】🔗⭐🔉
じゅうさんぞく-みつぶせ ジフサンゾク― 【十三束三伏せ】
手で握った幅の一三倍に指三本の幅を加えた長さ。また,その矢。「三人張りに―取つて矧(ハ)げ/義経記 5」
→十二束三伏せ
じゅうさん-づか【十三塚】🔗⭐🔉
じゅうさん-づか ジフサン― [3] 【十三塚】
一三個内外の塚が並んでいる遺跡。供養塚と思われるが,石棺・副葬品はなく,古墳とは区別される。丘陵・村境・峠などに多い。
じゅうさん-ななつ【十三七つ】🔗⭐🔉
じゅうさん-ななつ ジフサン― [1]-[2] 【十三七つ】
〔「お月さまいくつ,十三七つ」の童謡から出た言葉。十三夜の七つどきの月の意で〕
まだ若いこと。
じゅうさん-ぶつ【十三仏】🔗⭐🔉
じゅうさん-ぶつ ジフサン― [3] 【十三仏】
初七日から三十三回忌までの一三回の追善供養仏事に配当した仏・菩薩の総称。室町時代に成立した信仰。
→十三仏[表]
じゅうさん-まいり【十三参り・十三詣り】🔗⭐🔉
じゅうさん-まいり ジフサンマ リ [5] 【十三参り・十三詣り】
四月一三日に,一三歳になった少年・少女が福徳・知恵などを授かることを願って,虚空蔵(コクウゾウ)に参ること。京都嵐山の法輪寺などが著名。知恵詣(モウ)で。知恵もらい。[季]春。
リ [5] 【十三参り・十三詣り】
四月一三日に,一三歳になった少年・少女が福徳・知恵などを授かることを願って,虚空蔵(コクウゾウ)に参ること。京都嵐山の法輪寺などが著名。知恵詣(モウ)で。知恵もらい。[季]春。
 リ [5] 【十三参り・十三詣り】
四月一三日に,一三歳になった少年・少女が福徳・知恵などを授かることを願って,虚空蔵(コクウゾウ)に参ること。京都嵐山の法輪寺などが著名。知恵詣(モウ)で。知恵もらい。[季]春。
リ [5] 【十三参り・十三詣り】
四月一三日に,一三歳になった少年・少女が福徳・知恵などを授かることを願って,虚空蔵(コクウゾウ)に参ること。京都嵐山の法輪寺などが著名。知恵詣(モウ)で。知恵もらい。[季]春。
じゅうさん-めいか【十三名家】🔗⭐🔉
じゅうさん-めいか ジフサン― [5] 【十三名家】
公家の家格で,弁官・蔵人頭を兼ね,大納言まで昇り得る一三の家柄。すなわち,日野・広橋・烏丸・柳原・竹屋・裏松・甘露寺・葉室・勧修寺・万里小路・清閑寺・中御門・坊城。
じゅうさん-もんぜき【十三門跡】🔗⭐🔉
じゅうさん-もんぜき ジフサン― [5] 【十三門跡】
主な一三の門跡寺院の称。天台宗の輪王寺・妙法院・聖護院・昭高院・青蓮(シヨウレン)院・梶井宮(三千院)・曼殊(マンジユ)院・毘沙門堂・円満院,真言宗の仁和寺・大覚寺・勧修(カンジユ)寺,浄土宗の知恩院。
じゅうさん-もんぱ【十三門派】🔗⭐🔉
じゅうさん-もんぱ ジフサン― [5] 【十三門派】
(1)「十三宗{(2)}」に同じ。
(2)日本禅宗の一三宗派。臨済宗の建仁寺・永源寺・建長寺・東福寺・円覚寺・南禅寺・大徳寺・妙心寺・天竜寺・相国寺・仏通寺・万福寺の各派と曹洞宗の永平寺派の称。
じゅうさん-や【十三夜】🔗⭐🔉
じゅうさん-や ジフサン― [3] 【十三夜】
(1)陰暦一三日の夜。
(2)陰暦九月一三日の夜。月をまつり,枝豆や栗を供えることが多いことから八月十五夜の月を芋名月というのに対して,豆名月・栗名月とも,また「後(ノチ)の月」ともよばれる。十五夜・十三夜の一方の月見を欠かすことを片月見といって忌む風がある。日本固有の習俗で,かつては秋の収穫祭の一つだったと考えられている。[季]秋。《みちのくの如く寒しや―/山口青邨》
じゅうさんや【十三夜】🔗⭐🔉
じゅうさんや ジフサンヤ 【十三夜】
小説。樋口一葉作。1895年(明治28)発表。酷薄な夫にもただ耐えるほかはない女主人公を通し,封建的な社会に生きる女性の悲惨を描く。
じゅうさん-り【十三里】🔗⭐🔉
じゅうさん-り ジフサン― [3] 【十三里】
〔栗(九里)より(四里)うまいという洒落〕
サツマイモの称。また,焼き芋の称。
じゅうし-じ【十四事】🔗⭐🔉
じゅうし-じ ジフシ― [3] 【十四事】
江戸時代に重んじた一四種の武芸の総称。すなわち,射・騎・棒・刀・抜刀(イアイ)・撃剣・薙刀(ナギナタ)・鎌・槍・鳥銃・石火箭(イシビヤ)・火箭(ヒヤ)・捕縛(トリテ)・拳(ヤワラ)。
じゅう-しまつ【十姉妹】🔗⭐🔉
じゅう-しまつ ジフ― [3] 【十姉妹】
スズメ目カエデチョウ科の飼い鳥。全長12センチメートルほど。羽色は純白から黒に近いものまで,変異が多い。東南アジア産のダンドク(コシジロキンパラ)が原種といわれる。江戸時代に中国から輸入され,日本で改良された。じゅうしまい。
じゅう-の-しま【十の島】🔗⭐🔉
じゅう-の-しま ジフ― 【十の島】
〔平仮名の「あほ」の二字を分解して「十のしま」と読んだもの〕
ばか。あほう。
じゅうよっか-としこし【十四日年越し】🔗⭐🔉
じゅうよっか-としこし ジフヨツカ― [6] 【十四日年越し】
正月一五日を小正月といい,その前日の一四日を年越しとして祝うこと。
そ【十】🔗⭐🔉
そ 【十】
じゅう。とお。「みそか(三十日)」「やそしま(八十島)」などの形で用いられる。
そごう-びたい【十河額】🔗⭐🔉
そごう-びたい ソガウビタヒ [4] 【十河額】
江戸前期に流行した,男子の額の剃(ソ)り方。生え際を剃り上げて,額を広く作る。
と【十】🔗⭐🔉
と [1] 【十】
数のとお。じゅう。多く名詞の上に付いて,接頭語的に用いる。「―文(モン)」「―月」
と-いち【十一】🔗⭐🔉
と-いち [0] 【十一】
(1)一〇日で一割も取る高利の金融。「―金融」
(2)花札で,一〇点札一枚とかす札ばかりの手役。
とお【十】🔗⭐🔉
とお トヲ [1] 【十】
(1)じゅう。一〇個。物の数を数える時に使う。
(2)一〇歳。
とお=が十(トオ)🔗⭐🔉
――が十(トオ)
初めから終わりまで。すっかり。みんな。「―ながら,ほれられるつもりにて/黄表紙・艶気樺焼」
とお=で神童(シンドウ)十五で才子(サイシ)二十(ハタチ)過ぎれば只(タダ)の人🔗⭐🔉
――で神童(シンドウ)十五で才子(サイシ)二十(ハタチ)過ぎれば只(タダ)の人
幼時に神童と評判の高かった人も,成長するにつれて普通の人と同じになることが多いのをいう。
とお-ごう-さん【十五三】🔗⭐🔉
とお-ごう-さん トヲ― [3][1]-[1]-[0] 【十五三】
課税所得の捕捉率が,給与所得は十割であるのに対して,自営業は五割,農業は三割程度であるという意味の俗称。サラリーマンの重税感を表した語。
→くろよん(九六四)
とお-の-いましめ【十の戒め】🔗⭐🔉
とお-の-いましめ トヲ― [1] 【十の戒め】
仏教の十戒(ジツカイ)のこと。
とさのすなやま【十三の砂山】🔗⭐🔉
とさのすなやま 【十三の砂山】
青森県津軽地方の民謡で,市浦村十三(ジユウサン)の盆踊り唄。山形県酒田市の「酒田節」が千石船の船乗りの伝馬船漕ぎの唄となって十三港に伝えられ,のちに盆踊り唄として唄われた。
とすじえもん【十筋右衛門】🔗⭐🔉
とすじえもん トスヂ モン 【十筋右衛門】
頭髪の少ないことを人名めかしていう語。六筋右衛門。三筋右衛門。「かもじいくつか落ちて,地髪は―/浮世草子・一代女 3」
モン 【十筋右衛門】
頭髪の少ないことを人名めかしていう語。六筋右衛門。三筋右衛門。「かもじいくつか落ちて,地髪は―/浮世草子・一代女 3」
 モン 【十筋右衛門】
頭髪の少ないことを人名めかしていう語。六筋右衛門。三筋右衛門。「かもじいくつか落ちて,地髪は―/浮世草子・一代女 3」
モン 【十筋右衛門】
頭髪の少ないことを人名めかしていう語。六筋右衛門。三筋右衛門。「かもじいくつか落ちて,地髪は―/浮世草子・一代女 3」
と-つか【十握・十拳・十束】🔗⭐🔉
と-つか 【十握・十拳・十束】
〔「つか」は,親指を除いた握りこぶしの幅〕
一つかみの約十倍の長さ。
とつか-の-つるぎ【十握剣】🔗⭐🔉
とつか-の-つるぎ 【十握剣】
刀身が十つかみほどの長さの剣。「伊邪那岐の命,佩かせる―を抜きて/古事記(上訓)」
とつき-とおか【十月十日】🔗⭐🔉
とつき-とおか ―トヲカ [1] 【十月十日】
一〇か月と一〇日。胎児が母の胎内にいる期間。
じっかい【十戒】(和英)🔗⭐🔉
じっかい【十戒】
[聖書の]the Ten Commandments.
じっかく【十角(形)】(和英)🔗⭐🔉
じっかく【十角(形)】
a decagon.→英和
〜の decagonal.
じゅう【十】(和英)🔗⭐🔉
じゅういちがつ【十一月】(和英)🔗⭐🔉
じゅういちがつ【十一月】
November.→英和
じゅうおく【十億】(和英)🔗⭐🔉
じゅうおく【十億】
a billion.→英和
じゅうがつ【十月】(和英)🔗⭐🔉
じゅうがつ【十月】
October.→英和
じゅうく【十九】(和英)🔗⭐🔉
じゅうく【十九】
nineteen.→英和
第〜(の) the nineteenth.
じゅうご【十五】(和英)🔗⭐🔉
じゅうごや【十五夜】(和英)🔗⭐🔉
じゅうごや【十五夜】
the night of a full moon.十五夜の月 a full moon;the harvest moon (中秋の).
じゅうさん【十三】(和英)🔗⭐🔉
じゅうさん【十三】
thirteen.→英和
第〜(の) the thirteenth.‖十三日の金曜日 Black Friday;Friday the 13th.
じゅうし【十四】(和英)🔗⭐🔉
じゅうし【十四】
fourteen.→英和
第〜(の) the fourteenth.
大辞林に「十」で始まるの検索結果 1-98。もっと読み込む