複数辞典一括検索+![]()
![]()
おお-ともい-の-つかさ【弁官】🔗⭐🔉
おお-ともい-の-つかさ オホトモヒ― 【弁官】
⇒べんかん(弁官)
ばん-ず【弁事】🔗⭐🔉
ばん-ず [1] 【弁事】
禅宗で,雑務に使う者の総称。べんじ。
べ-ざい【弁才・弁財】🔗⭐🔉
べ-ざい [0] 【弁才・弁財】
「弁才船(ベザイセン)」の略。
べざい-せん【弁才船・弁財船】🔗⭐🔉
べざい-せん [0] 【弁才船・弁財船】
和船の一。江戸時代,海運の隆盛に対応して全国的に活躍し,俗に千石船と呼ばれた典型的和船。船首形状や垣立(カキタツ)に特徴があり,一本マストに横帆一枚ながら帆走性能・経済性にすぐれた。菱垣(ヒガキ)廻船・樽(タル)廻船・北前船などもすべてこの形式を用いた。べざいぶね。べんざいせん。
べざい-てん【弁才天】🔗⭐🔉
べざい-てん 【弁才天】
⇒べんざいてん(弁才天)
べん【弁(瓣)】🔗⭐🔉
べん [1] 【弁(瓣)】
(1)花びら。花弁。「五―の椿」
(2)「弁膜」に同じ。
(3)管などを流れる気体や液体の出入りや流れの方向を調節する装置。バルブ。
べん【弁(辯)】🔗⭐🔉
べん [1] 【弁(辯)】
(1)話すこと。説明すること。また,話しぶり。「立候補の―」「気障(キザ)な―を揮(フル)ひながら/社会百面相(魯庵)」
(2)地方名のあとに付けて,その地方独特の言葉遣いであることを表す。「津軽―」
べん=が立・つ🔗⭐🔉
――が立・つ
しゃべることがうまい。雄弁である。
べん=を弄(ロウ)・する🔗⭐🔉
――を弄(ロウ)・する
しゃべりまくる。勝手な理屈をこねる。
べんあ【弁阿】🔗⭐🔉
べんあ 【弁阿】
⇒弁長(ベンチヨウ)
べんえん【弁円】🔗⭐🔉
べんえん ベン ン 【弁円】
(1202-1280) 鎌倉時代の臨済宗の僧。諱(イミナ)は円爾(エンニ)。諡号(シゴウ)は聖一国師。駿河の人。1235年宋に渡り,帰国後は九州に禅法を広め,藤原道家の招きで上洛して東福寺開山となる。鎌倉の寿福寺,京都の建仁寺に歴住。東福寺派の祖。
ン 【弁円】
(1202-1280) 鎌倉時代の臨済宗の僧。諱(イミナ)は円爾(エンニ)。諡号(シゴウ)は聖一国師。駿河の人。1235年宋に渡り,帰国後は九州に禅法を広め,藤原道家の招きで上洛して東福寺開山となる。鎌倉の寿福寺,京都の建仁寺に歴住。東福寺派の祖。
 ン 【弁円】
(1202-1280) 鎌倉時代の臨済宗の僧。諱(イミナ)は円爾(エンニ)。諡号(シゴウ)は聖一国師。駿河の人。1235年宋に渡り,帰国後は九州に禅法を広め,藤原道家の招きで上洛して東福寺開山となる。鎌倉の寿福寺,京都の建仁寺に歴住。東福寺派の祖。
ン 【弁円】
(1202-1280) 鎌倉時代の臨済宗の僧。諱(イミナ)は円爾(エンニ)。諡号(シゴウ)は聖一国師。駿河の人。1235年宋に渡り,帰国後は九州に禅法を広め,藤原道家の招きで上洛して東福寺開山となる。鎌倉の寿福寺,京都の建仁寺に歴住。東福寺派の祖。
べん-かい【弁解】🔗⭐🔉
べん-かい [0] 【弁解】 (名)スル
言いわけをすること。言いわけ。「いまさら―してもはじまらない」「―の余地はない」
べん-かん【弁官】🔗⭐🔉
べん-かん ―クワン [0] 【弁官】
律令制において,太政官を構成する機構の一。太政官とその管轄下の諸官司・諸国とを結んでその行政指揮運営の実際をつかさどった。左弁官・右弁官に分かれ,それぞれ大中少の弁(おおともい)があった。おおともいのつかさ。
べんかん=の下文(クダシブミ)🔗⭐🔉
――の下文(クダシブミ)
⇒官宣旨(カンセンジ)
べんけい【弁慶】🔗⭐🔉
べんけい 【弁慶】
(1)(?-1189) 平安末・鎌倉初期の僧。「吾妻鏡」「義経記」などの伝えるところによれば,熊野の別当の子で比叡山西塔で修行し武蔵坊と称して武勇を好んだ。のち,源義経に仕えた。義経の奥州落ちに従い,安宅関,衣川の合戦などでの武勇は能・歌舞伎などに多く脚色された。
(2)〔弁慶が強かったところから〕
強いもの,強がる者のたとえ。「内―」
(3)〔弁慶が七つ道具を背負った姿,あるいは体中に矢を受けた姿になぞらえていう〕
竹筒に穴をあけ,その穴に勝手道具や団扇などを差すようにしたもの。また,花かんざしなどを差しておく藁(ワラ)を束ねたものにもいう。
(4)たいこもち。幇間(ホウカン)。「判官(キヤク)へいろ
 と讒(コミズ)をいうて,ほかへ導く―衆も有よし/洒落本・秘事真告」
(5)「弁慶縞」の略。
と讒(コミズ)をいうて,ほかへ導く―衆も有よし/洒落本・秘事真告」
(5)「弁慶縞」の略。

 と讒(コミズ)をいうて,ほかへ導く―衆も有よし/洒落本・秘事真告」
(5)「弁慶縞」の略。
と讒(コミズ)をいうて,ほかへ導く―衆も有よし/洒落本・秘事真告」
(5)「弁慶縞」の略。
べんけい=の立ち往生(オウジヨウ)🔗⭐🔉
――の立ち往生(オウジヨウ)
〔衣川の合戦で,弁慶が満身に矢を受け,薙刀(ナギナタ)を杖にして立ったまま死んだという故事から〕
進退きわまることのたとえ。
べんけい=の泣き所🔗⭐🔉
――の泣き所
〔弁慶ほどの豪の者でも蹴(ケ)られると痛がって泣く急所の意〕
むこうずねのこと。転じて,ただ一つの弱点。
べんけい-がに【弁慶蟹】🔗⭐🔉
べんけい-がに [3] 【弁慶蟹】
カニの一種。甲はほぼ四角形で幅約3センチメートル。鋏脚と甲の前半分は赤みがかるが残りは青黒色。河口付近の湿地などにすむ。本州中部以南に分布。
べんけい-じま【弁慶縞】🔗⭐🔉
べんけい-じま [0] 【弁慶縞】
縞柄の一。茶と紺など二色の色糸をたて・よこ双方に用いて同じ幅の碁盤模様に織ったもの。弁慶格子。弁慶。
→格子縞
べんけい-じょうし【弁慶上使】🔗⭐🔉
べんけい-じょうし ―ジヤウ― 【弁慶上使】
人形浄瑠璃「御所桜堀川夜討」三段目の切の通称。弁慶が義経の正妻京(卿)の君の首受け取りの上使となり,わが娘信夫(シノブ)を身代わりとする節。
べんけい-そう【弁慶草】🔗⭐🔉
べんけい-そう ―サウ [0] 【弁慶草】
ベンケイソウ科の多年草。山野に自生し,栽培もされる。全体に多肉質で白緑色。茎は高さ約50センチメートルで,楕円形の葉を対生。夏,茎頂に淡紅色の小花多数が散房状につく。古名イキクサ。[季]秋。《雨つよし―も土に伏し/杉田久女》
弁慶草
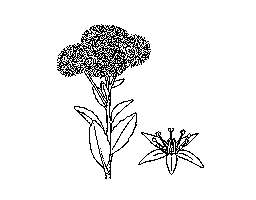 [図]
[図]
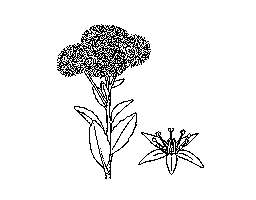 [図]
[図]
べんけい-そう-か【弁慶草科】🔗⭐🔉
べんけい-そう-か ―サウクワ [0] 【弁慶草科】
双子葉植物離弁花類の一科。世界に三五属一三〇〇種あり,ほとんど多年草。乾燥地帯や岩上に生育し,葉は多肉質でしばしば無性生殖を行う。コモチマンネングサ・イワレンゲ・ミセバヤ・カランコエなど。
べん-ご【弁護】🔗⭐🔉
べん-ご [1] 【弁護】 (名)スル
その人のために申し開きをして,その立場を護ること。その人の利益となることを主張して助けること。「無実を信じて―(を)する」
べんご-し【弁護士】🔗⭐🔉
べんご-し [3] 【弁護士】
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって,訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為,その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。弁護士法に定める一定の資格を有し,日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されなければならない。
べんご-し-かい【弁護士会】🔗⭐🔉
べんご-し-かい ―クワイ [4] 【弁護士会】
弁護士の指導・連絡・監督に関する事務を行う法人。地方裁判所の管轄区域ごとに設立される。全国の弁護士会は日本弁護士連合会を組織する。
べんご-し-ほう【弁護士法】🔗⭐🔉
べんご-し-ほう ―ハフ 【弁護士法】
弁護士の職務・資格・登録や弁護士会に関する事項を規定する弁護士制度の基本法。1949年(昭和24)制定。
べんご-にん【弁護人】🔗⭐🔉
べんご-にん [0] 【弁護人】
刑事訴訟において,被疑者・被告人の利益を保護する補助者で,その弁護を担当する者。原則として弁護士の中から選任される。
べん-こう【弁口】🔗⭐🔉
べん-こう [0] 【弁口】
口のきき方。言い方。しゃべり方。また,口のきき方がうまいこと。
べん-こう【弁巧】🔗⭐🔉
べん-こう ―カウ [0] 【弁巧】
言い回しの巧みなこと。口先のうまいこと。「―に載せられて/鉄仮面(涙香)」
べんこう-ざい【弁甲材】🔗⭐🔉
べんこう-ざい ベンカフ― [3] 【弁甲材】
木造船用材。杉丸太を太鼓落としに削(ハツ)ったもの。宮崎県の飫肥(オビ)杉が有名。
べん-さい【弁才】🔗⭐🔉
べん-さい [0] 【弁才】
〔「べんざい」とも〕
弁舌の才能。うまく話す能力。
べん-さい【弁済】🔗⭐🔉
べん-さい [0] 【弁済】 (名)スル
(1)借りていた金品を返すこと。
(2)〔法〕 債務者が債務の内容である給付を実現し債務を消滅させること。「債務を―する」「―能力」
→履行(2)
べん-ざい【弁才・弁財】🔗⭐🔉
べん-ざい [0] 【弁才・弁財】
「べざいせん(弁財船)」に同じ。
べんざい-せん【弁財船】🔗⭐🔉
べんざい-せん [0] 【弁財船】
「べざいせん(弁財船)」に同じ。
べんざい-し【弁済使】🔗⭐🔉
べんざい-し [3] 【弁済使】
九〜一〇世紀,中央に送る調庸の管理および中央への貢上折衝のために受領(ズリヨウ)が私的に置いた機関。貢調庸の有名無実化の原因として禁止されたが効を奏さなかった。
べんざい-てん【弁才天・弁財天】🔗⭐🔉
べんざい-てん 【弁才天・弁財天】
〔仏〕
〔梵 Sarasvat 〕
元来,インドの河神で,音楽・智恵・財物の神として吉祥天とともに広く信仰された女神。仏教にも取り入れられたが,吉祥天と同一視されるようになった。八本の手で各種の武具を持つ像もあるが,鎌倉時代には二手で琵琶を持つ女神像が一般化した。日本では七福神の一人として民衆の信仰を集めてきた。弁天。べざいてん。
弁才天
〕
元来,インドの河神で,音楽・智恵・財物の神として吉祥天とともに広く信仰された女神。仏教にも取り入れられたが,吉祥天と同一視されるようになった。八本の手で各種の武具を持つ像もあるが,鎌倉時代には二手で琵琶を持つ女神像が一般化した。日本では七福神の一人として民衆の信仰を集めてきた。弁天。べざいてん。
弁才天
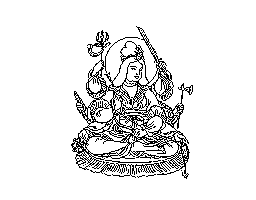 [図]
[図]
 〕
元来,インドの河神で,音楽・智恵・財物の神として吉祥天とともに広く信仰された女神。仏教にも取り入れられたが,吉祥天と同一視されるようになった。八本の手で各種の武具を持つ像もあるが,鎌倉時代には二手で琵琶を持つ女神像が一般化した。日本では七福神の一人として民衆の信仰を集めてきた。弁天。べざいてん。
弁才天
〕
元来,インドの河神で,音楽・智恵・財物の神として吉祥天とともに広く信仰された女神。仏教にも取り入れられたが,吉祥天と同一視されるようになった。八本の手で各種の武具を持つ像もあるが,鎌倉時代には二手で琵琶を持つ女神像が一般化した。日本では七福神の一人として民衆の信仰を集めてきた。弁天。べざいてん。
弁才天
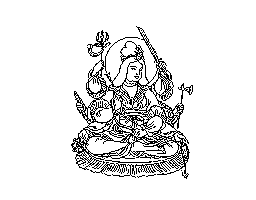 [図]
[図]
べん-し【弁士】🔗⭐🔉
べん-し [1] 【弁士】
(1)弁舌の巧みな人。話のうまい人。
(2)講演・演説などをする人。「選挙運動の応援―」
(3)無声映画を上映しながら,その内容を語りで表現するのを業とした人。活弁。
べん-じ【弁事】🔗⭐🔉
べん-じ [1] 【弁事】
事務を取り扱うこと。また,その人。
べん-しき【弁識】🔗⭐🔉
べん-しき [0] 【弁識】 (名)スル
わきまえ知ること。識別。「吾人智力の―する能はざる所/明六雑誌 25」
べんじ-た・てる【弁じ立てる】🔗⭐🔉
べんじ-た・てる [5] 【弁じ立てる】 (動タ下一)
さかんに述べる。「無差別幕(ノベツマク)なしに―・てる/社会百面相(魯庵)」
べんじ-つ・ける【弁じ付ける】🔗⭐🔉
べんじ-つ・ける [5] 【弁じ付ける】 (動カ下一)
一方的に続けざまに言い立てる。まくしたてる。「お嶺が攻鼓(セメヅツミ)を打つやうに―・けるを/社会百面相(魯庵)」
べん-しゃ【弁者】🔗⭐🔉
べん-しゃ [1] 【弁者】
〔「べんじゃ」とも〕
弁舌の巧みな者。
べん-しょう【弁証】🔗⭐🔉
べん-しょう [0] 【弁証】 (名)スル
ある事柄を論じて証明すること。また,弁別して証明すること。論証。
べんしょう-がく【弁証学】🔗⭐🔉
べんしょう-がく [3] 【弁証学】
〔(ラテン) dialectica〕
古代末期から中世にかけて研究・教育された自由学芸の一。正しく推論し,議論するための学問。伝統的論理学はこの学科に該当する。弁証術。
べんしょう-ほう【弁証法】🔗⭐🔉
べんしょう-ほう ―ハフ [0] 【弁証法】
〔(ギリシヤ) dialektik ; (ドイツ) Dialektik〕
(1)古代ギリシャで,対話などを通して事物の真の認識とイデアに到達する,ソクラテス・プラトンにみられる仮説演繹的方法(問答法)をいう。アリストテレスでは,確からしいが真理とはいえない命題を前提とする推理をさし,真なる学問的論証と区別される。
(2)カントでは,経験による裏付けのない不確実な推理を意味し,それを純粋理性の誤用に基づく仮象の論理学ととらえる。
(3)矛盾を含む否定性に積極的意味を見いだすヘーゲルでは,有限なものが自己自身のうちに自己との対立・矛盾を生み出し,それを止揚することで高次なものへ発展する思考および存在を貫く運動の論理をさす。それは思考と存在との根源的な同一性であるイデーの自己展開ととらえられる。ヘーゲル弁証法。
(4)マルクス・エンゲルスでは,イデーを展開の主体とするヘーゲル弁証法の観念論を批判し,自然・社会および思惟の一般的運動法則についての科学とした。
; (ドイツ) Dialektik〕
(1)古代ギリシャで,対話などを通して事物の真の認識とイデアに到達する,ソクラテス・プラトンにみられる仮説演繹的方法(問答法)をいう。アリストテレスでは,確からしいが真理とはいえない命題を前提とする推理をさし,真なる学問的論証と区別される。
(2)カントでは,経験による裏付けのない不確実な推理を意味し,それを純粋理性の誤用に基づく仮象の論理学ととらえる。
(3)矛盾を含む否定性に積極的意味を見いだすヘーゲルでは,有限なものが自己自身のうちに自己との対立・矛盾を生み出し,それを止揚することで高次なものへ発展する思考および存在を貫く運動の論理をさす。それは思考と存在との根源的な同一性であるイデーの自己展開ととらえられる。ヘーゲル弁証法。
(4)マルクス・エンゲルスでは,イデーを展開の主体とするヘーゲル弁証法の観念論を批判し,自然・社会および思惟の一般的運動法則についての科学とした。
 ; (ドイツ) Dialektik〕
(1)古代ギリシャで,対話などを通して事物の真の認識とイデアに到達する,ソクラテス・プラトンにみられる仮説演繹的方法(問答法)をいう。アリストテレスでは,確からしいが真理とはいえない命題を前提とする推理をさし,真なる学問的論証と区別される。
(2)カントでは,経験による裏付けのない不確実な推理を意味し,それを純粋理性の誤用に基づく仮象の論理学ととらえる。
(3)矛盾を含む否定性に積極的意味を見いだすヘーゲルでは,有限なものが自己自身のうちに自己との対立・矛盾を生み出し,それを止揚することで高次なものへ発展する思考および存在を貫く運動の論理をさす。それは思考と存在との根源的な同一性であるイデーの自己展開ととらえられる。ヘーゲル弁証法。
(4)マルクス・エンゲルスでは,イデーを展開の主体とするヘーゲル弁証法の観念論を批判し,自然・社会および思惟の一般的運動法則についての科学とした。
; (ドイツ) Dialektik〕
(1)古代ギリシャで,対話などを通して事物の真の認識とイデアに到達する,ソクラテス・プラトンにみられる仮説演繹的方法(問答法)をいう。アリストテレスでは,確からしいが真理とはいえない命題を前提とする推理をさし,真なる学問的論証と区別される。
(2)カントでは,経験による裏付けのない不確実な推理を意味し,それを純粋理性の誤用に基づく仮象の論理学ととらえる。
(3)矛盾を含む否定性に積極的意味を見いだすヘーゲルでは,有限なものが自己自身のうちに自己との対立・矛盾を生み出し,それを止揚することで高次なものへ発展する思考および存在を貫く運動の論理をさす。それは思考と存在との根源的な同一性であるイデーの自己展開ととらえられる。ヘーゲル弁証法。
(4)マルクス・エンゲルスでは,イデーを展開の主体とするヘーゲル弁証法の観念論を批判し,自然・社会および思惟の一般的運動法則についての科学とした。
べんしょう-ほう-しんがく【弁証法神学】🔗⭐🔉
べんしょう-ほう-しんがく ―ハフ― [7] 【弁証法神学】
〔(ドイツ) dialektische Theologie〕
第一次大戦後,ドイツのカール=バルトらが起こした神学運動。神と人間との間の根本的断絶を強調し,この断絶は聴聞者における神の言葉への信仰によってのみ弁証法的に克服されると説く。従来の自由主義神学を批判し,宗教改革的伝統(特にカルビニズム)への回帰を主張。危機神学。
べんしょう-ほうてき-ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】🔗⭐🔉
べんしょう-ほうてき-ゆいぶつろん ―ハフテキ― [12] 【弁証法的唯物論】
〔(ドイツ) dialektischer Materialismus〕
マルクスとエンゲルスにより創出され,レーニンらによって発展させられた唯物論。形而上学的・機械的見方に対し弁証法的であり,観念論に対し唯物論的である。世界は全体として統一をもちながら相互に連関し発展する物質であり,思考や意識もその物質の模写の過程であるとする。弁証法的唯物論が歴史の発展についての見方に適用されて唯物史観となる。
べんしょう-ほうてき-ろんりがく【弁証法的論理学】🔗⭐🔉
べんしょう-ほうてき-ろんりがく ―ハフテキ― [11] 【弁証法的論理学】
〔dialectical logic〕
アリストテレス以来の形式論理学に対して,ヘーゲル・マルクスの弁証法を論理学として扱ったもの。事物や思考の運動,発展の一般的な法則を対象とする。
べん-しょう【弁償】🔗⭐🔉
べん-しょう ―シヤウ [0] 【弁償】 (名)スル
他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。「なくした本を―する」
べん・じる【弁(辯・辨)じる】🔗⭐🔉
べん・じる [3][0] 【弁(辯・辨)じる】 (動ザ上一)
〔サ変動詞「弁ずる」の上一段化〕
「弁ずる」に同じ。「一席―・じる」「黒白(コクビヤク)を―・じる」
べんしん-ろん【弁神論】🔗⭐🔉
べんしん-ろん [3] 【弁神論】
⇒神義論(シンギロン)
べん・ずる【弁(辨)ずる】🔗⭐🔉
べん・ずる [3][0] 【弁(辨)ずる】 (動サ変)[文]サ変 べん・ず
(1)区別する。弁別する。「黒白(コクビヤク)を―・ずる」「物事のよしあしを―・ずる能力」「東西を―・ぜず」「永遠の利害を―・ずるの明(メイ)あるが故に/福翁百話(諭吉)」
(2)ものごとをうまく処理する。すませる。「多々(タタ)益々(マスマス)―・ず」
べん・ずる【弁(辯)ずる】🔗⭐🔉
べん・ずる [3][0] 【弁(辯)ずる】 (動サ変)[文]サ変 べん・ず
(1)意見を述べる。言う。「滔々(トウトウ)と―・ずる」「これについて一席―・じておきたい」
(2)言いわけをする。弁明する。「友人のために―・ずる」
べん-ぜつ【弁舌】🔗⭐🔉
べん-ぜつ [0] 【弁舌】
ものを言うこと。また,ものの言い方。「―さわやか」「―を振るう」
べん-ぜつ【弁説】🔗⭐🔉
べん-ぜつ [0] 【弁説】
物事の是非を分けて説き明かすこと。
べん-そ【弁疏】🔗⭐🔉
べん-そ [1] 【弁疏】 (名)スル
言い開きをすること。いいわけ。弁解。「汗を拭(ヌグ)ひつつ―せり/火の柱(尚江)」
べん-そく【弁足】🔗⭐🔉
べん-そく [0] 【弁足】
鳥の足指(趾)の両側に弁状に膜が発達しているもの。カイツブリ科,ヒレアシ科,クイナ科オオバン属,シギ科ヒレアシシギ属などに見られる。
べん-たつ【弁達】🔗⭐🔉
べん-たつ [0] 【弁達】 (名)スル
述べ伝えること。弁告。「神の言を―する者なりと称して/民約論(徳)」
べん-ち【弁知】🔗⭐🔉
べん-ち [1] 【弁知】 (名)スル
道理をわきまえ,分別のあること。「道義をしも―したれば/小説神髄(逍遥)」
べんちょう【弁長】🔗⭐🔉
べんちょう ベンチヤウ 【弁長】
(1162-1238) 鎌倉初期の浄土宗の僧。字(アザナ)は弁阿,号は聖光房。筑前の生まれ。浄土宗第二祖。鎮西派の祖。はじめ比叡山で天台教学を学び,のち法然の弟子となる。九州で念仏を広めた。鎮西上人。著「浄土宗要集」「徹選択念仏集」など。
べん-てん【弁天】🔗⭐🔉
べん-てん [0] 【弁天】
(1)「弁才天」の略。「―さま」
(2)転じて,美人。
べんてん-むすめ【弁天娘】🔗⭐🔉
べんてん-むすめ [5] 【弁天娘】
弁天のように美しい娘。
べんてん-こぞう【弁天小僧】🔗⭐🔉
べんてん-こぞう 【弁天小僧】
河竹黙阿弥作の歌舞伎「青砥稿花紅彩画(アオトゾウシハナノニシキエ)」中の人物。名は菊之助。白浪五人男の一人。浜松屋での女装でのゆすり,極楽寺山門での立ち腹が見せ場。
べんてん-じま【弁天島】🔗⭐🔉
べんてん-じま 【弁天島】
静岡県,浜名湖南端にある島。大小七つの小島から成り,観光・遊覧地。東海道新幹線・東海道本線・国道一号が通る。
べん-とう【弁当】🔗⭐🔉
べん-とう ―タウ [3] 【弁当】
(1)容器に入れて携え,外出先で食べる食べ物。
(2)外出先や会議の席などで,取り寄せて食べる食事。「参会者に―を出す」
べんとう=を使・う🔗⭐🔉
――を使・う
弁当を食べる。
べんとう-だい【弁当代】🔗⭐🔉
べんとう-だい ―タウ― [0] 【弁当代】
外出先で食事をするためのお金。また,その程度の少額のお金。小遣い銭。
べんとう-ばこ【弁当箱】🔗⭐🔉
べんとう-ばこ ―タウ― [3] 【弁当箱】
弁当を入れる容器。
べん-なん【弁難】🔗⭐🔉
べん-なん [0] 【弁難】 (名)スル
言いたてて非難すること。論難。
べん-の-ないし【弁内侍】🔗⭐🔉
べん-の-ないし 【弁内侍】
鎌倉中期の歌人。藤原信実(ノブザネ)の女(ムスメ)。後深草天皇に出仕。晩年,出家した。「続後撰和歌集」以下の勅撰集に四五首入集。日記「弁内侍日記」がある。生没年未詳。
べんのないし-にっき【弁内侍日記】🔗⭐🔉
べんのないし-にっき 【弁内侍日記】
日記。二巻。弁内侍作。後深草天皇に仕えた作者が,1246年から52年に至る宮中生活を,自作歌を交えつつ記したもの。後深草院弁内侍集。弁内侍寛元記。
べん-ばく【弁駁】🔗⭐🔉
べん-ばく [0] 【弁駁】 (名)スル
〔「べんぱく」とも〕
他人の説に反論して言い破ること。論駁。「反対派の論説を―する」
べん-ぱつ【弁髪・辮髪】🔗⭐🔉
べん-ぱつ [0] 【弁髪・辮髪】
〔「辮」は編む意〕
北アジア諸民族の男子の風習で,頭髪の一部を編んで垂らし,他をそり落とす髪形。民族や時代により形は異なる。満州族は北京に入城して漢民族に弁髪を強制し,清朝崩壊まで続いた。
弁髪
 [図]
[図]
 [図]
[図]
わきまえ【弁え】🔗⭐🔉
わきまえ ワキマヘ [0][3] 【弁え】
〔「わきまえる」の連用形から〕
(1)区別。弁別。識別。「前後の―もなく」「そのぐらいの―はある」
(2)つぐない。弁済。弁償。「おのれが金千両を負ひ給へり。その―してこそ出で給はめ/宇治拾遺 1」
わきま・える【弁える】🔗⭐🔉
わきま・える ワキマヘル [4][3] 【弁える】 (動ア下一)[文]ハ下二 わきま・ふ
(1)物事の区別や善悪の区別をする。「ことの善悪を―・えなければならない」
(2)人としての道理を承知している。「礼儀を―・える」「場所柄を―・える」
(3)つぐなう。弁償する。「彼の母の借れる所の稲を員(カズ)の如く―・へて/今昔 20」
(4)調達する。「十八軒の飛脚宿から―・へ/浄瑠璃・冥途の飛脚(上)」
べん【弁】(和英)🔗⭐🔉
べんかい【弁解】(和英)🔗⭐🔉
べんけい【弁慶の泣き所】(和英)🔗⭐🔉
べんけい【弁慶の泣き所】
an Achilles' heel.弁慶縞 checks;<米>checkers.
べんけいそう【弁慶草】(和英)🔗⭐🔉
べんけいそう【弁慶草】
《植》an orpin(e).
べんご【弁護】(和英)🔗⭐🔉
べんさい【弁済】(和英)🔗⭐🔉
べんざいてん【弁財天】(和英)🔗⭐🔉
べんざいてん【弁財天】
⇒弁天.
べんし【弁士】(和英)🔗⭐🔉
べんしょう【弁償】(和英)🔗⭐🔉
べんしょう【弁償】
reparation;→英和
compensation.〜する pay[make up]for.⇒賠償.
べんしょうほう【弁証法】(和英)🔗⭐🔉
べんしょうほう【弁証法】
dialectics.弁証法的唯物論 dialectical materialism.
べんぜつ【弁舌】(和英)🔗⭐🔉
べんてん【弁天】(和英)🔗⭐🔉
べんてん【弁天】
Benten;the goddess of fortune.
べんとう【弁当】(和英)🔗⭐🔉
べんとう【弁当】
alunch.→英和
べんぱつ【弁髪】(和英)🔗⭐🔉
べんぱつ【弁髪】
a pigtail.→英和
大辞林に「弁」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む