複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぼろ【梵論・暮露】🔗⭐🔉
ぼろ [1] 【梵論・暮露】
有髪の乞食坊主の一種。中世末期にはその中から尺八を吹く薦僧(コモソウ)(虚無僧(コムソウ)の前身)が現れたので,薦僧・虚無僧の異名としても用いられた。ぼろぼろ。梵論子(ボロンジ)。梵字(ボンジ)。「もしこの御中にいろをし房と申す―やおはします/徒然 115」
ぼろ-ぼろ【梵論梵論】🔗⭐🔉
ぼろ-ぼろ 【梵論梵論】
「ぼろ(梵論)」に同じ。「―多く集まりて,九品の念仏を申しけるに/徒然 115」
ぼろん-じ【梵論子】🔗⭐🔉
ぼろん-じ [2] 【梵論子】
「ぼろ(梵論)」に同じ。
ぼん-おう【梵王】🔗⭐🔉
ぼん-おう ―ワウ 【梵王】
⇒梵天(ボンテン)(1)
ぼん-おん【梵音】🔗⭐🔉
ぼん-おん [0] 【梵音】
〔仏〕
〔「ぼんのん」とも〕
(1)梵天王の発する清浄な音声。
(2)声明(シヨウミヨウ)の一種。清浄な音声で仏法僧の徳をたたえる偈頌(ゲジユ)で,四箇(シカ)の法要で散華の次に唱える。
(3)読経の声。
(4)梵語の発音・音声。
ぼんが-いちにょ【梵我一如】🔗⭐🔉
ぼんが-いちにょ [1]-[2] 【梵我一如】
〔仏〕 宇宙の根本原理であるブラフマン(梵)と個人の本体であるアートマン(我)とが同一不二であること。インドの正統バラモン教思想の根本原理。
ぼん-がく【梵学】🔗⭐🔉
ぼん-がく [0] 【梵学】
(1)仏教に関する学問。
(2)梵語の学問。
ぼん-ぎょう【梵行】🔗⭐🔉
ぼん-ぎょう ―ギヤウ [0] 【梵行】
仏道の修行。特に性欲を断つ行法。
ぼん-ぐう【梵宮】🔗⭐🔉
ぼん-ぐう [3] 【梵宮】
(1)梵天の宮殿。
(2)寺。寺院。
ぼん-さい【梵妻】🔗⭐🔉
ぼん-さい [0] 【梵妻】
僧の妻。大黒(ダイコク)。
ぼん-し【梵志】🔗⭐🔉
ぼん-し [0] 【梵志】
〔「ぼんじ」とも。梵(ブラフマン)を志す者の意〕
(1)バラモンの別名。
(2)転じて,バラモン階級出身の僧。
ぼん-じ【梵字】🔗⭐🔉
ぼん-じ [0] 【梵字】
(1)梵語(サンスクリット)の表記に用いられた文字の総称。悉曇(シツタン)文字・デーバナーガリー文字など。
(2)「ぼろ(梵論)」に同じ。「ぼろんじ・―・漢字など云ける者/徒然 115」
ぼんしゅん【梵舜】🔗⭐🔉
ぼんしゅん 【梵舜】
(1553-1632) 江戸初期の神道家。号,神竜院。豊国神社創建に参画し,神宮寺別当となる。徳川家康の信任を得,神道の普及に貢献。
ぼん-しょう【梵鐘】🔗⭐🔉
ぼん-しょう [0] 【梵鐘】
寺院の鐘楼の釣り鐘。青銅製が多く,撞木(シユモク)で打ち鳴らす。洪鐘・蒲牢(ホロウ)・鯨鐘・巨鯨・華鯨・長鯨など多くの異名がある。
梵鐘
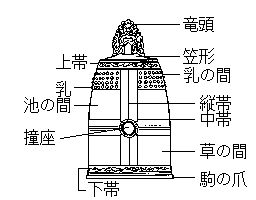 [図]
[図]
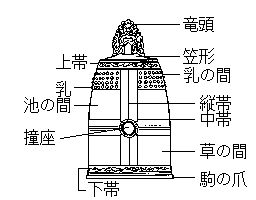 [図]
[図]
ぼん-ぜい【梵砌】🔗⭐🔉
ぼん-ぜい [0] 【梵砌】
寺院。寺院の境内。
ぼん-せつ【梵刹】🔗⭐🔉
ぼん-せつ [0] 【梵刹】
〔梵 brahma-k etra〕〔清浄な国土を意味する梵語の音写〕
寺。寺院。ぼんさつ。
etra〕〔清浄な国土を意味する梵語の音写〕
寺。寺院。ぼんさつ。
 etra〕〔清浄な国土を意味する梵語の音写〕
寺。寺院。ぼんさつ。
etra〕〔清浄な国土を意味する梵語の音写〕
寺。寺院。ぼんさつ。
ぼん-そう【梵僧】🔗⭐🔉
ぼん-そう [0] 【梵僧】
〔仏〕
(1)戒律を守って清浄な行を修する僧。
(2)僧。
(3)インドの僧。
ぼん-てん【梵天】🔗⭐🔉
ぼん-てん 【梵天】
〔「ぼんでん」とも〕
(1)〔梵 Brahma〕
色界の初禅天の王。本来はバラモン教で根本原理を人格化した最高神であったが,仏教に取り入れられて正法護持の神とされる。大梵天。梵王(ボンオウ)。梵天王(ボンテンオウ)。婆羅門(バラモン)天。
→ブラフマン
(2){(1)}の住む天。色界の初禅天。
(3)〔「ほて{(3)}」の転か〕
御幣(ゴヘイ)。幣帛(ヘイハク)。頭屋(トウヤ)の標識にしたり,神幸や山伏の峰入り行列の先頭に立てたりする。梵天祭として二月一六,一七日に秋田県横手市で行われるものなどが有名。[季]春。
(4)漁具につける浮標。延縄(ハエナワ)や流し網などにつけるガラス球の類。
梵天(1)
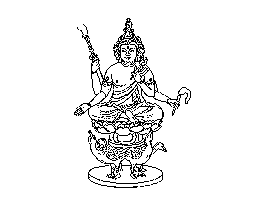 [図]
[図]
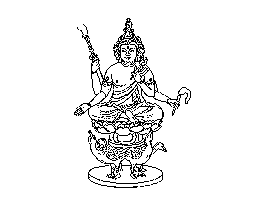 [図]
[図]
ぼんてん-うり【梵天瓜】🔗⭐🔉
ぼんてん-うり [5] 【梵天瓜】
マクワウリの異名。
ぼんてん-おう【梵天王】🔗⭐🔉
ぼんてん-おう ―ワウ 【梵天王】
〔「ぼんてんのう」とも〕
「梵天(ボンテン){(1)}」に同じ。
ぼんてん-か【梵天花】🔗⭐🔉
ぼんてん-か ―クワ [3] 【梵天花】
アオイ科の草本状の低木。暖地に生える。茎は高さ約1メートル。葉は掌状に五深裂する。秋,上方の葉腋(ヨウエキ)に紅色の小五弁花を開く。
ぼんてん-こく【梵天国】🔗⭐🔉
ぼんてん-こく 【梵天国】
〔「ぼんでんこく」とも〕
(1)御伽草子。室町期の成立。梵天王の姫と結婚した主人公中納言が,帝の難題を退け,また羅刹国に連れ去られた妻を助け出す物語。のちに古浄瑠璃・説経節などとしても広く行われた。
(2)〔江戸初期の浄瑠璃興行で,一日の興行の終わりに必ず(1)を語る習慣があったことから〕
物事の終わり。「たとひこの身は―になるとも/松の葉」
(3)〔(2)から転じて〕
主人などから追放されること。「やきもちのやの字もあると,忽ち―さ/滑稽本・浮世床 2」
ぼんとうあん【梵灯庵】🔗⭐🔉
ぼんとうあん 【梵灯庵】
(1349-?) 室町初期の連歌師。姓は朝山。もと足利義満の臣。和歌を冷泉為秀に,連歌を二条良基に学ぶ。救済(キユウセイ)・周阿・良基没後の連歌衰退期における数少ない名手。著「長短抄」「梵灯庵主返答書」など。
ぼん-ぶん【梵文】🔗⭐🔉
ぼん-ぶん [0] 【梵文】
梵語で書かれた文章や経文。
ぼんもう【梵網】🔗⭐🔉
ぼんもう ボンマウ 【梵網】
〔仏〕「梵網経」の略。
ぼんもう-え【梵網会】🔗⭐🔉
ぼんもう-え ボンマウ [3] 【梵網会】
梵網経を講讃する法会(ホウエ)。
[3] 【梵網会】
梵網経を講讃する法会(ホウエ)。
 [3] 【梵網会】
梵網経を講讃する法会(ホウエ)。
[3] 【梵網会】
梵網経を講讃する法会(ホウエ)。
ぼんもう-きょう【梵網経】🔗⭐🔉
ぼんもう-きょう ボンマウキヤウ 【梵網経】
二巻。鳩摩羅什(クマラジユウ)訳と伝えるが,五世紀後半に中国で成立したとする学説が有力。仏性の自覚に基づく大乗独自の戒律を説く。梵網経盧舎那仏説菩薩心地戒品第十。梵網菩薩戒経。菩薩戒本。
→円頓戒(エンドンカイ)
ぼんもう-ぼさつかい【梵網菩薩戒】🔗⭐🔉
ぼんもう-ぼさつかい ボンマウ― [7] 【梵網菩薩戒】
梵網経に説かれ,大乗仏教の戒律の中心をなす十重禁戒と四十八軽戒。梵網戒。
ぼん-らん【梵卵】🔗⭐🔉
ぼん-らん [0] 【梵卵】
古代インドの宇宙説の一。そこから世界が生まれたとされる卵。
ぼんご【梵語】(和英)🔗⭐🔉
ぼんご【梵語】
Sanskrit.→英和
大辞林に「梵」で始まるの検索結果 1-36。