複数辞典一括検索+![]()
![]()
いかずち【△雷】いかづち🔗⭐🔉
いかずち【△雷】いかづち
《「厳(いか)つ霊(ち)」の意。「つ」は助詞》かみなり。なるかみ。《季 夏》「―に松籟(しようらい)どっと乱れ落つ/茅舎」
いかずち‐の‐おか【雷丘】いかづち‐をか🔗⭐🔉
いかずち‐の‐おか【雷丘】いかづち‐をか
奈良県高市郡明日香(あすか)村にある丘。雄略紀に、少子部連
 (ちいさこべのむらじすがる)がこの地で雷を捕らえたという記事がある。
(ちいさこべのむらじすがる)がこの地で雷を捕らえたという記事がある。

 (ちいさこべのむらじすがる)がこの地で雷を捕らえたという記事がある。
(ちいさこべのむらじすがる)がこの地で雷を捕らえたという記事がある。
かみ‐なり【雷】🔗⭐🔉
かみ‐なり【雷】
《「神鳴り」の意》 電気を帯びた雲と雲との間、あるいは雲と地表との間に起こる放電現象。電光が見え、雷鳴が聞こえる。一般に強い風と雨を伴う。いかずち。なるかみ。「―が鳴る」「―に打たれる」《季 夏》「―に小屋は焼かれて瓜の花/蕪村」
電気を帯びた雲と雲との間、あるいは雲と地表との間に起こる放電現象。電光が見え、雷鳴が聞こえる。一般に強い風と雨を伴う。いかずち。なるかみ。「―が鳴る」「―に打たれる」《季 夏》「―に小屋は焼かれて瓜の花/蕪村」 雲の上にいて、雷を起こすという神。鬼の姿をしていて、虎の皮の褌(ふんどし)を締め、太鼓を背負って、これを打ち鳴らし、また、人間のへそを好むとされる。雷神。はたた神。かみなりさま。
雲の上にいて、雷を起こすという神。鬼の姿をしていて、虎の皮の褌(ふんどし)を締め、太鼓を背負って、これを打ち鳴らし、また、人間のへそを好むとされる。雷神。はたた神。かみなりさま。 頭ごなしにどなりつけること。腹を立ててがみがみと叱責(しつせき)すること。「―を落とす」
[類語](
頭ごなしにどなりつけること。腹を立ててがみがみと叱責(しつせき)すること。「―を落とす」
[類語]( )雷(いかずち)・鳴る神・雷(らい)・雷鳴・雷電・天雷・急雷・疾雷(しつらい)・迅雷(じんらい)・霹靂(へきれき)・雷公・遠雷・春雷・界雷・熱雷・落雷・稲妻(いなずま)・稲光(いなびかり)・電光・紫電(しでん)
)雷(いかずち)・鳴る神・雷(らい)・雷鳴・雷電・天雷・急雷・疾雷(しつらい)・迅雷(じんらい)・霹靂(へきれき)・雷公・遠雷・春雷・界雷・熱雷・落雷・稲妻(いなずま)・稲光(いなびかり)・電光・紫電(しでん)
 電気を帯びた雲と雲との間、あるいは雲と地表との間に起こる放電現象。電光が見え、雷鳴が聞こえる。一般に強い風と雨を伴う。いかずち。なるかみ。「―が鳴る」「―に打たれる」《季 夏》「―に小屋は焼かれて瓜の花/蕪村」
電気を帯びた雲と雲との間、あるいは雲と地表との間に起こる放電現象。電光が見え、雷鳴が聞こえる。一般に強い風と雨を伴う。いかずち。なるかみ。「―が鳴る」「―に打たれる」《季 夏》「―に小屋は焼かれて瓜の花/蕪村」 雲の上にいて、雷を起こすという神。鬼の姿をしていて、虎の皮の褌(ふんどし)を締め、太鼓を背負って、これを打ち鳴らし、また、人間のへそを好むとされる。雷神。はたた神。かみなりさま。
雲の上にいて、雷を起こすという神。鬼の姿をしていて、虎の皮の褌(ふんどし)を締め、太鼓を背負って、これを打ち鳴らし、また、人間のへそを好むとされる。雷神。はたた神。かみなりさま。 頭ごなしにどなりつけること。腹を立ててがみがみと叱責(しつせき)すること。「―を落とす」
[類語](
頭ごなしにどなりつけること。腹を立ててがみがみと叱責(しつせき)すること。「―を落とす」
[類語]( )雷(いかずち)・鳴る神・雷(らい)・雷鳴・雷電・天雷・急雷・疾雷(しつらい)・迅雷(じんらい)・霹靂(へきれき)・雷公・遠雷・春雷・界雷・熱雷・落雷・稲妻(いなずま)・稲光(いなびかり)・電光・紫電(しでん)
)雷(いかずち)・鳴る神・雷(らい)・雷鳴・雷電・天雷・急雷・疾雷(しつらい)・迅雷(じんらい)・霹靂(へきれき)・雷公・遠雷・春雷・界雷・熱雷・落雷・稲妻(いなずま)・稲光(いなびかり)・電光・紫電(しでん)
雷が落・ちる🔗⭐🔉
雷が落・ちる
目上の人に大声でどなられてしかられる。「父の―・ちる」
かみなり‐いか【雷烏=賊】🔗⭐🔉
かみなり‐いか【雷烏=賊】
コウイカ科のイカ。外套(がいとう)長約四〇センチで、背面に楕円形の眼状紋が並ぶ。房総半島以南に産し、刺身や鮨種(すしだね)にする。紋甲烏賊(もんごういか)。
かみなり‐うお【雷魚】‐うを🔗⭐🔉
かみなり‐うお【雷魚】‐うを
ハタハタのこと。秋田地方で、漁期の冬によく雷が鳴るところからいう。《季 冬》
かみなり‐おこし【雷 =
= 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
かみなり‐おこし【雷 =
= 】
江戸浅草の雷門前で売りはじめたおこし。大阪のあわおこしに対する東京名物菓子。
】
江戸浅草の雷門前で売りはじめたおこし。大阪のあわおこしに対する東京名物菓子。
 =
= 】
江戸浅草の雷門前で売りはじめたおこし。大阪のあわおこしに対する東京名物菓子。
】
江戸浅草の雷門前で売りはじめたおこし。大阪のあわおこしに対する東京名物菓子。
かみなり‐おやじ【雷親△父】‐おやぢ🔗⭐🔉
かみなり‐おやじ【雷親△父】‐おやぢ
何かというと大声でどなりつける、口やかましいおやじ。
かみなり‐ぐも【雷雲】🔗⭐🔉
かみなり‐ぐも【雷雲】
 らいうん(雷雲)
らいうん(雷雲)
 らいうん(雷雲)
らいうん(雷雲)
かみなり‐ごえ【雷声】‐ごゑ🔗⭐🔉
かみなり‐ごえ【雷声】‐ごゑ
辺りに響き渡る大きな声。「御殿もゆるぐ―」〈浄・振袖始〉
かみなり‐ぞく【雷族】🔗⭐🔉
かみなり‐ぞく【雷族】
騒がしい音を立てて猛烈な速度でオートバイを走らせる若者の称。昭和三四年(一九五九)ごろからの語。
かみなり‐の‐じん【△雷鳴の陣】‐ヂン🔗⭐🔉
かみなり‐の‐じん【△雷鳴の陣】‐ヂン
平安時代、雷鳴のときに宮中に臨時に設けられた警固の陣。近衛の大将・次将が清涼殿の孫庇(まごびさし)に伺候(しこう)し、弦打(つるう)ちして天皇を守護し、将監(しようげん)以下も諸所を警固した。かんなりのじん。
かみなり‐の‐つぼ【雷鳴の壺】🔗⭐🔉
かみなり‐の‐つぼ【雷鳴の壺】
平安京内裏の襲芳舎(しほうしや)の異称。雷鳴のときに天皇が臨御(りんぎよ)したのでいう。かんなりのつぼ。
かみなり‐ぼし【雷干し】🔗⭐🔉
かみなり‐ぼし【雷干し】
シロウリを小口から螺旋(らせん)状に長く続けて切り、塩押しにして干したもの。適宜に切り三杯酢で食べる。輪の形のつながるさまが雷神の太鼓に似るところからの名という。干し瓜。《季 夏》
かみなり‐もん【雷門】🔗⭐🔉
かみなり‐もん【雷門】
東京都台東区の地名。浅草寺(せんそうじ)の風神・雷神を安置した雷門の南側にある。
かみなり‐よけ【雷△除け】🔗⭐🔉
かみなり‐よけ【雷△除け】
 落雷をよけること。また、その害を防ぐための避雷針などの装置。
落雷をよけること。また、その害を防ぐための避雷針などの装置。 落雷を避けるために神社や寺院で出す守り札。
落雷を避けるために神社や寺院で出す守り札。
 落雷をよけること。また、その害を防ぐための避雷針などの装置。
落雷をよけること。また、その害を防ぐための避雷針などの装置。 落雷を避けるために神社や寺院で出す守り札。
落雷を避けるために神社や寺院で出す守り札。
かん‐なり【△雷鳴】🔗⭐🔉
かん‐なり【△雷鳴】
 「かみなり」の音変化。
「かみなり」の音変化。 「雷鳴(かんなり)の壺(つぼ)」の略。
「雷鳴(かんなり)の壺(つぼ)」の略。
 「かみなり」の音変化。
「かみなり」の音変化。 「雷鳴(かんなり)の壺(つぼ)」の略。
「雷鳴(かんなり)の壺(つぼ)」の略。
かんなり‐の‐じん【△雷鳴の陣】‐ヂン🔗⭐🔉
かんなり‐の‐じん【△雷鳴の陣】‐ヂン
「かみなりのじん」に同じ。「―の舎人(とねり)」〈枕・二五八〉
かんなり‐の‐つぼ【雷鳴の壺】🔗⭐🔉
かんなり‐の‐つぼ【雷鳴の壺】
「かみなりのつぼ」に同じ。「―に人々集まりて」〈古今・秋上・詞書〉
はたはた【× ・×鰰・雷=魚・燭=魚】🔗⭐🔉
・×鰰・雷=魚・燭=魚】🔗⭐🔉
はたはた【× ・×鰰・雷=魚・燭=魚】
・×鰰・雷=魚・燭=魚】

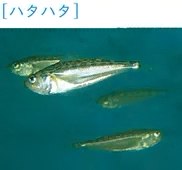 スズキ目ハタハタ科の海水魚。全長約二〇センチ。体はやや細長く側扁(そくへん)し、口が大きく、うろこはない。北太平洋と日本海の深海に分布し、一一月下旬から一二月にかけて産卵のため沿岸の藻場に押し寄せる。秋田・山形沿岸でこの時期に漁獲。淡泊な味で、ぶりことよぶ卵塊とともに食用。おきあじ。かみなりうお。《季 冬》◆「
スズキ目ハタハタ科の海水魚。全長約二〇センチ。体はやや細長く側扁(そくへん)し、口が大きく、うろこはない。北太平洋と日本海の深海に分布し、一一月下旬から一二月にかけて産卵のため沿岸の藻場に押し寄せる。秋田・山形沿岸でこの時期に漁獲。淡泊な味で、ぶりことよぶ卵塊とともに食用。おきあじ。かみなりうお。《季 冬》◆「 」「鰰」は国字。
」「鰰」は国字。
 ・×鰰・雷=魚・燭=魚】
・×鰰・雷=魚・燭=魚】

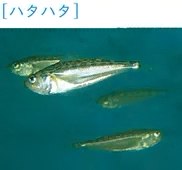 スズキ目ハタハタ科の海水魚。全長約二〇センチ。体はやや細長く側扁(そくへん)し、口が大きく、うろこはない。北太平洋と日本海の深海に分布し、一一月下旬から一二月にかけて産卵のため沿岸の藻場に押し寄せる。秋田・山形沿岸でこの時期に漁獲。淡泊な味で、ぶりことよぶ卵塊とともに食用。おきあじ。かみなりうお。《季 冬》◆「
スズキ目ハタハタ科の海水魚。全長約二〇センチ。体はやや細長く側扁(そくへん)し、口が大きく、うろこはない。北太平洋と日本海の深海に分布し、一一月下旬から一二月にかけて産卵のため沿岸の藻場に押し寄せる。秋田・山形沿岸でこの時期に漁獲。淡泊な味で、ぶりことよぶ卵塊とともに食用。おきあじ。かみなりうお。《季 冬》◆「 」「鰰」は国字。
」「鰰」は国字。
らい【雷】🔗⭐🔉
らい【雷】
かみなり。いかずち。《季 夏》
らい‐う【雷雨】🔗⭐🔉
らい‐う【雷雨】
かみなりを伴う激しい雨。《季 夏》
らい‐うん【雷雲】🔗⭐🔉
らい‐うん【雷雲】
かみなりや雷雨をもたらす雲。多くは積雲や積乱雲。かみなりぐも。《季 夏》
らい‐か【雷火】‐クワ🔗⭐🔉
らい‐か【雷火】‐クワ
いなびかり。いなずま。また、落雷によって起こる火災。《季 夏》
らい‐かん【雷管】‐クワン🔗⭐🔉
らい‐かん【雷管】‐クワン
火薬の起爆に用いる、金属製の容器に雷汞(らいこう)などを詰めたもの。
らい‐がん【雷丸】‐グワン🔗⭐🔉
らい‐がん【雷丸】‐グワン
竹に寄生するサルノコシカケ科のキノコの一種の菌体。直径一、二センチの塊状。回虫・条虫などの駆虫薬にされる。
らい‐ぎょ【雷魚】🔗⭐🔉
らい‐ぎょ【雷魚】
タイワンドジョウとカムルチーの通称。ともに肉食性で、他の魚などを食害する。
らい‐けい【雷鶏】🔗⭐🔉
らい‐けい【雷鶏】
ライチョウの別名。
らい‐げき【雷撃】🔗⭐🔉
らい‐げき【雷撃】
[名]スル 落雷すること。かみなりが落ちること。
落雷すること。かみなりが落ちること。 魚雷で敵艦を攻撃すること。また、その攻撃。
魚雷で敵艦を攻撃すること。また、その攻撃。
 落雷すること。かみなりが落ちること。
落雷すること。かみなりが落ちること。 魚雷で敵艦を攻撃すること。また、その攻撃。
魚雷で敵艦を攻撃すること。また、その攻撃。
らいげき‐き【雷撃機】🔗⭐🔉
らいげき‐き【雷撃機】
魚雷を発射する装備をもつ飛行機。
らい‐こ【雷鼓】🔗⭐🔉
らい‐こ【雷鼓】
雷神が持っているという太鼓。また、かみなりの鳴る音。
らい‐こう【雷公】🔗⭐🔉
らい‐こう【雷公】
かみなりの俗称。《季 夏》
らい‐こう【雷光】‐クワウ🔗⭐🔉
らい‐こう【雷光】‐クワウ
いなびかり。いなずま。
らい‐こう【雷×汞】🔗⭐🔉
らい‐こう【雷×汞】
水銀を濃硝酸に溶かし、アルコールで処理して得られる白色の針状結晶。加熱・衝撃・摩擦などで爆発しやすく、起爆薬として雷管に用いる。化学式Hg(ONC)2 雷酸水銀。
らいさん‐すいぎん【雷酸水銀】🔗⭐🔉
らいさん‐すいぎん【雷酸水銀】
雷酸HONCと水銀との塩。古くから知られ、爆発しやすく、雷酸水銀 は雷汞(らいこう)とよばれる。
は雷汞(らいこう)とよばれる。
 は雷汞(らいこう)とよばれる。
は雷汞(らいこう)とよばれる。
らい‐じゅう【雷獣】‐ジウ🔗⭐🔉
らい‐じゅう【雷獣】‐ジウ
落雷とともに地上へ降り、人畜を殺傷したり、樹木を引き裂いたりするといわれる、想像上の動物。
らいしゅう‐はんとう【雷州半島】ライシウハンタウ🔗⭐🔉
らいしゅう‐はんとう【雷州半島】ライシウハンタウ
中国広東(カントン)省南西部、南シナ海に突き出ている半島。瓊州(けいしゆう)海峡を隔てて海南島に対する。中心都市は湛江(たんこう)。レイチョウ半島。
らい‐じん【雷神】🔗⭐🔉
らい‐じん【雷神】
かみなりを起こすと信じられた神。ふつう虎の皮の褌(ふんどし)をした鬼が、輪形に連ねた太鼓を負い、手にばちを持った姿で描かれる。古くは水神の性格も持つものとされた。《季 夏》
らい‐せい【雷声】🔗⭐🔉
らい‐せい【雷声】
 かみなりの音。雷鳴。《季 夏》
かみなりの音。雷鳴。《季 夏》 かみなりのような大きい音や声。
かみなりのような大きい音や声。
 かみなりの音。雷鳴。《季 夏》
かみなりの音。雷鳴。《季 夏》 かみなりのような大きい音や声。
かみなりのような大きい音や声。
らい‐そん【雷×樽】🔗⭐🔉
らい‐そん【雷×樽】
古代中国の酒器の一。雷文を刻んだ酒樽(さかだる)。
らい‐ちょう【雷鳥】‐テウ🔗⭐🔉
らい‐ちょう【雷鳥】‐テウ
 キジ目キジ科ライチョウ亜科の鳥。全長三七センチくらい。尾は長くなく、丸い体つきで、あまり飛ばない。羽色は夏は褐色、冬は白色になり、雄では目の上に赤い裸出部がある。ユーラシア・アメリカの北部に分布。日本では中部地方の高山に生息し特別天然記念物。同亜科にはエゾライチョウなど一八種が含まれ、北半球に分布。《季 夏》「―や雨に倦む日をまれに啼く/辰之助」
キジ目キジ科ライチョウ亜科の鳥。全長三七センチくらい。尾は長くなく、丸い体つきで、あまり飛ばない。羽色は夏は褐色、冬は白色になり、雄では目の上に赤い裸出部がある。ユーラシア・アメリカの北部に分布。日本では中部地方の高山に生息し特別天然記念物。同亜科にはエゾライチョウなど一八種が含まれ、北半球に分布。《季 夏》「―や雨に倦む日をまれに啼く/辰之助」
 キジ目キジ科ライチョウ亜科の鳥。全長三七センチくらい。尾は長くなく、丸い体つきで、あまり飛ばない。羽色は夏は褐色、冬は白色になり、雄では目の上に赤い裸出部がある。ユーラシア・アメリカの北部に分布。日本では中部地方の高山に生息し特別天然記念物。同亜科にはエゾライチョウなど一八種が含まれ、北半球に分布。《季 夏》「―や雨に倦む日をまれに啼く/辰之助」
キジ目キジ科ライチョウ亜科の鳥。全長三七センチくらい。尾は長くなく、丸い体つきで、あまり飛ばない。羽色は夏は褐色、冬は白色になり、雄では目の上に赤い裸出部がある。ユーラシア・アメリカの北部に分布。日本では中部地方の高山に生息し特別天然記念物。同亜科にはエゾライチョウなど一八種が含まれ、北半球に分布。《季 夏》「―や雨に倦む日をまれに啼く/辰之助」
らい‐てい【雷×霆】🔗⭐🔉
らい‐てい【雷×霆】
《「霆」は激しい雷の意》かみなり。いかずち。《季 夏》
らい‐でん【雷電】🔗⭐🔉
らい‐でん【雷電】
 かみなりといなびかり。雷鳴と電光。
かみなりといなびかり。雷鳴と電光。 旧日本海軍の単発単座の迎撃戦闘機。局地防空用として開発された。
旧日本海軍の単発単座の迎撃戦闘機。局地防空用として開発された。
 かみなりといなびかり。雷鳴と電光。
かみなりといなびかり。雷鳴と電光。 旧日本海軍の単発単座の迎撃戦闘機。局地防空用として開発された。
旧日本海軍の単発単座の迎撃戦闘機。局地防空用として開発された。
らいでん‐ためえもん【雷電為右衛門】‐ためヱモン🔗⭐🔉
らいでん‐ためえもん【雷電為右衛門】‐ためヱモン
[一七六七〜一八二五]江戸後期の力士。信濃の人。大関在位一七年。三二場所中、二五四勝一〇敗、勝率九割六分以上の驚異的な成績を残した。
らい‐どう【雷同】スル🔗⭐🔉
らい‐どう【雷同】スル
《「礼記」曲礼上から。雷の音に応じて万物が響く意》自分自身の考えをもたず、むやみに他人の説や行動に同調すること。「付和―」「卑屈の気風に制せられ其気風に―して」〈福沢・学問のすゝめ〉
らい‐どう【雷動】🔗⭐🔉
らい‐どう【雷動】
かみなりの鳴り響くように、どよめき騒ぐこと。「夜々の蜂起、谷々の―やむ時無し」〈太平記・二四〉
ライヒー【雷魚】🔗⭐🔉
ライヒー【雷魚】
《中国語》タイワンドジョウの別名。
らい‐ふ【雷×斧】🔗⭐🔉
らい‐ふ【雷×斧】
落雷などのあとに発見された石器時代の石斧などの遺物を、天から降ってきた雷神などの持ち物と考えたもの。天狗(てんぐ)の鉞(まさかり)。雷斧石。
らい‐めい【雷名】🔗⭐🔉
らい‐めい【雷名】
世間に知れわたっている名声。また、相手の名声を敬っていう。「―をとどろかす」
らい‐めい【雷鳴】🔗⭐🔉
らい‐めい【雷鳴】
かみなりが鳴ること。また、その音。《季 夏》「―を尽くせし後の動かぬ日/草田男」
らい‐もん【雷文】🔗⭐🔉
らい‐もん【雷文】

 方形の渦巻き状の文様。連続して用いるのが特色。中国で古代から愛好された。
方形の渦巻き状の文様。連続して用いるのが特色。中国で古代から愛好された。

 方形の渦巻き状の文様。連続して用いるのが特色。中国で古代から愛好された。
方形の渦巻き状の文様。連続して用いるのが特色。中国で古代から愛好された。
らい‐よけ【雷△除け】🔗⭐🔉
らい‐よけ【雷△除け】
「かみなりよけ」に同じ。
らい‐りゅう【雷竜】🔗⭐🔉
らい‐りゅう【雷竜】
 ブロントサウルス
ブロントサウルス
 ブロントサウルス
ブロントサウルス
雷🔗⭐🔉
雷
[音]ライ
[訓]かみなり
いかずち
[部首]雨
[総画数]13
[コード]区点 4575
JIS 4D6B
S‐JIS 978B
[分類]常用漢字
[難読語]
→かもわけいかずち‐じんじゃ【賀茂別雷神社】
→かもわけいかずち‐の‐みこと【賀茂別雷命】
→かん‐なり【雷鳴】
→たけみかづち‐の‐かみ【武甕槌神・建御雷神】
→トゥルイ【Tului】
→はたはた【 ・鰰・雷魚・燭魚】
→らい‐こう【雷汞】
→ライヒー【雷魚】
→らい‐ふ【雷斧】
・鰰・雷魚・燭魚】
→らい‐こう【雷汞】
→ライヒー【雷魚】
→らい‐ふ【雷斧】
 ・鰰・雷魚・燭魚】
→らい‐こう【雷汞】
→ライヒー【雷魚】
→らい‐ふ【雷斧】
・鰰・雷魚・燭魚】
→らい‐こう【雷汞】
→ライヒー【雷魚】
→らい‐ふ【雷斧】
大辞泉に「雷」で始まるの検索結果 1-54。