複数辞典一括検索+![]()
![]()
さめ【鮫】🔗⭐🔉
さめ【鮫】
①(狭目さめの意か)軟骨魚綱板鰓類ばんさいるいで、エイ目以外のものの総称。体は紡錘形で、骨格は軟骨。口は頭部の下面に横に開き、尾びれは刀状。皮膚は硬質の歯状鱗で被われ、左右の体側に5〜7個ずつの鰓孔があり、歯は鋭い。多くは胎生。凶暴で、貪食、運動迅速なものが少なくない。温帯・熱帯の海に産。肉・ひれは食用に供し、また蒲鉾かまぼこの材料とする。皮は乾かして物を磨くのに用い(さめやすり)、また刀剣の装飾用とする。出雲風土記「北の海に捕るところの雑くさぐさの物は、志毗しび・鮐ふぐ・―…」→鱶ふか。
サカタザメ
提供:東京動物園協会
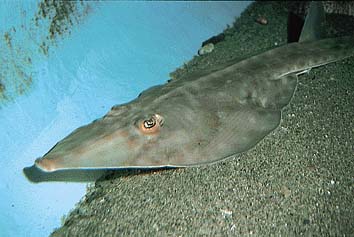 アカシュモクザメ
提供:東京動物園協会
アカシュモクザメ
提供:東京動物園協会
 ②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」
②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」
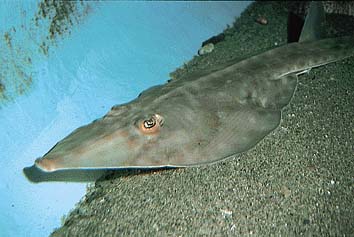 アカシュモクザメ
提供:東京動物園協会
アカシュモクザメ
提供:東京動物園協会
 ②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」
②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」
さめ【白眼】🔗⭐🔉
さめ【白眼】
牛・馬の両眼縁が白いもの。一説に、毛の白いもの。太平記31「白葦毛・白瓦毛・白―・つき毛なる馬に乗つて」
さめ‐が‐はし【鮫が橋】🔗⭐🔉
さめ‐が‐はし【鮫が橋】
江戸四谷辺の地名。また、そこにあった娼家の俗称。明治時代、貧民窟として聞こえた。
さめ‐がわ【鮫皮・沙皮】‥ガハ🔗⭐🔉
さめ‐がわ【鮫皮・沙皮】‥ガハ
サメの皮(実は東南アジア産のエイの一種、真鮫まさめなどの背中の皮)を乾かしたもの。近世、輸入されて刀剣の柄つかや鞘さやなどに用いた。さめ。柄皮。→かいらぎ(梅花皮)
さめ‐かんゆ【鮫肝油】🔗⭐🔉
さめ‐かんゆ【鮫肝油】
サメ類の肝臓から採った黄色の油脂。化粧品・潤滑油などに用いる。
さめ‐ぎわ【覚め際・醒め際】‥ギハ🔗⭐🔉
さめ‐ぎわ【覚め際・醒め際】‥ギハ
眠り・酔いなどからさめるまぎわ。さめぐち。
さめ・く🔗⭐🔉
さめ・く
〔自四〕
①さらさらと音がする。さっと音がする。類聚名義抄「颯、サメク」
②(ザメクとも)騒がしく音を立てる。ざわめく。枕草子28「鳥の集まりてとびちがひ、―・き鳴きたる」。四河入海「昔は酒を飲で―・きしが」
さめ‐ぐち【覚め口・醒め口】🔗⭐🔉
さめ‐ぐち【覚め口・醒め口】
(→)「さめぎわ」に同じ。
さめ‐こもん【鮫小紋】🔗⭐🔉
さめ‐こもん【鮫小紋】
刀の柄つかに使用する鮫皮のような小紋。細かく白い点で半円形を重ねた文様に染め上げたもので、多く上下かみしもに用いた。
さめ‐ざめ🔗⭐🔉
さめ‐ざめ
〔副〕
①涙を流して静かに泣き続けるさま。「―と泣く」
②しみじみと言うさま。また、こまごまと述べるさま。愚管抄3「―とおほせられけり」
さめ‐ざや【鮫鞘】🔗⭐🔉
さめ‐ざや【鮫鞘】
鮫皮で巻いた刀の鞘。竹斎「―に赤銅作りの大小を差し」
さめ‐すが【鮫氷】🔗⭐🔉
さめ‐すが【鮫氷】
鮫皮についた革質状の部分を乾かした食品。三杯酢にし、または煮て食う。宮城県の名産。
さめ‐はだ【鮫肌】🔗⭐🔉
さめ‐はだ【鮫肌】
鮫の皮のようにざらざらした人の肌。また、ざらざらしたもののたとえ。
⇒さめはだ‐やき【鮫肌焼】
さめはだ‐やき【鮫肌焼】🔗⭐🔉
さめはだ‐やき【鮫肌焼】
陶器の焼成法・装飾法の一種。釉うわぐすりの表面が鮫の肌のように粒状を呈したものをいう。薩摩焼・萩焼などにみられる。鮫焼。
⇒さめ‐はだ【鮫肌】
さめ‐びたき【鮫鶲】🔗⭐🔉
さめ‐びたき【鮫鶲】
スズメ目ヒタキ科の鳥。灰褐色の地味な小鳥で、亜高山帯の針葉樹林にすむ。夏鳥で、秋には東南アジアに渡る。
さめ‐やき【鮫焼】🔗⭐🔉
さめ‐やき【鮫焼】
(→)鮫肌焼さめはだやきに同じ。
さめ‐やすり【鮫鑢】🔗⭐🔉
さめ‐やすり【鮫鑢】
鮫皮を板にはりつけて作り、物を研磨するのに用いるもの。
さめ‐やらぬ【覚め遣らぬ・醒め遣らぬ】🔗⭐🔉
さめ‐やらぬ【覚め遣らぬ・醒め遣らぬ】
完全に覚めきっていない。覚めきらず名残の気配がある。「夢―様子」「興奮―時」
さ・める【冷める・覚める・醒める・褪める】🔗⭐🔉
さ・める【冷める・覚める・醒める・褪める】
〔自下一〕[文]さ・む(下二)
(「寒い」と同源)
➊物体の熱、物事に対する熱意が低下してもとの状態になる。
①《冷》熱くした物の温度が普段の温度まで下がる。ぬるくなる。冷たくなる。永久百首「夜と共に下に焚く火はなけれどもしまねの御湯は―・むるよもなし」。「スープの―・めない距離」
②《冷・覚・醒》心の高ぶりがなくなり、普段の心の状態に戻る。気持が静まる。源氏物語夕顔「ただあなむつかしと思ひける心地皆―・めて、泣き惑ふさまいといみじ」。日葡辞書「ココロガサメタ」。「あの人に対する熱も―・めた」「ほとぼりが―・める」「興味が―・める」「―・めた目で見る」
➋《覚・醒》眠り・酔い・迷いなどが消え去って、普段の判断ができるようになる。
①眠った状態から起きた状態に戻る。夢からうつつにかえる。正気に戻る。万葉集19「夜よぐたちに寝―・めて居れば河瀬とめ心もしのに鳴く千鳥かも」。日本霊異記中「地にたふれて臥し嘿然しずかなり。ものいはず、やや久にありて蘇さめ起ち」。源氏物語帚木「いたづらぶしとおぼさるるに御目―・めて」。「夢から―・める」
②酒の酔いがなくなる。大鏡道隆「この殿御酔のほどよりはとく―・むることをぞせさせ給ひし」。「酔いが―・める」
③迷いがなくなり、普段の判断ができるようになる。物思いが晴れる。源氏物語槿「今日は老いも忘れ、憂き世の嘆き皆―・めぬる心地なむ」。「迷いから―・める」
➌《褪》染色などがうすれて、濃かった色が薄い色になる。色が分からなくなる。くすむ。あせる。風雅和歌集夏「風わたる田の面もの早苗色―・めて入日のこれる岡の松原」。「着物の色が―・める」
広辞苑に「さめ」で始まるの検索結果 1-19。