複数辞典一括検索+![]()
![]()
とき【時】🔗⭐🔉
とき【時】
①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。
②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」
時
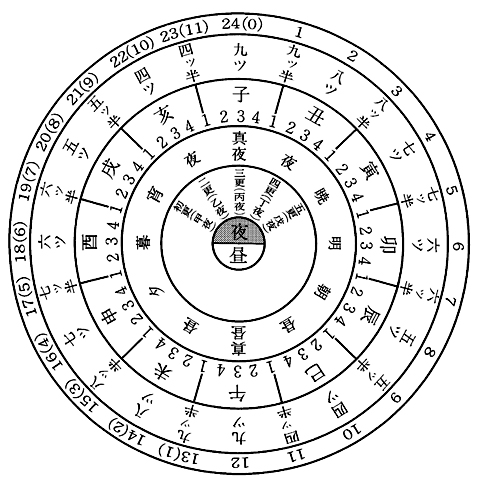 ③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
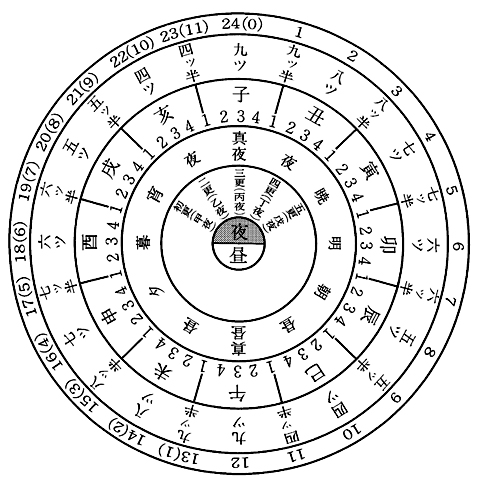 ③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
③時候。季節。「―の花」
④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」
⑤特定の時期。
㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」
㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」
㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」
㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」
⑥㋐時代。年代。世。「若い―」
㋑当時。当代。「―の将軍」
⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」
㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」
⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。
⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」
⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」
⇒時移り事去る
⇒時となく
⇒時と場合
⇒時なるかな
⇒時に遇う
⇒時に遇えば鼠も虎となる
⇒時に当たる
⇒時に従う
⇒時につく
⇒時に取りて
⇒時に因る
⇒時に寄る
⇒時の代官、日の奉行
⇒時の用には鼻をも削ぐ
⇒時は得難くして失い易し
⇒時は金なり
⇒時人を待たず
⇒時も時
⇒時わかず
⇒時を争う
⇒時を失う
⇒時を移さず
⇒時を得る
⇒時を稼ぐ
⇒時をかわさず
⇒時を奏す
⇒時を撞く
⇒時をつくる
⇒時を見る
とき【斎】🔗⭐🔉
とき【斎】
(食すべき時の意)
①仏家ぶっけで、午前中にとる食事。午後は食しないと戒律で定めている。斎食。時食。南海寄帰内法伝平安後期点「若し斎トキの了はてむを待たむに」↔非時ひじ。
②肉食しないこと。精進しょうじん料理。
③寺で出す食事。また、法要その他仏事の参会者に出す食事。
④法要。仏事。黄表紙、敵討義女英「けさは茂之介が命日にて、この家へ―に来りけるが」
⑤正月・5月・9月の16日。西日本で、精進をし仕事を休んだ。ときの日。→正五九しょうごく
とき【鴇・朱鷺】🔗⭐🔉
とき【鴇・朱鷺】
コウノトリ目トキ科の鳥。東アジア特産。全長約75センチメートル、嘴くちばしは長大で下方に曲がる。全体白色であるが、羽毛、殊に風切羽と尾羽の基部は淡紅色(とき色)。後頭に冠毛があり、顔は裸で赤色。脚も赤い。朝鮮・中国・日本に分布していたが、その数は激減し絶滅のおそれがある。日本では佐渡に残った5羽を1981年に捕獲し、飼育下で繁殖を試みたが成功せず、2003年に最後の1羽が死亡。1999年に中国から贈られたつがいの繁殖に成功。特別天然記念物・国際保護鳥に指定。桃花鳥。つき。とう。どう。
とき
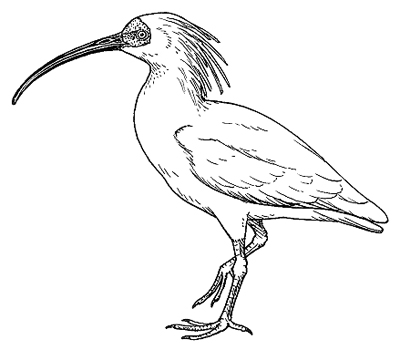 トキ
提供:佐渡トキ保護センター
トキ
提供:佐渡トキ保護センター
 トキ
提供:NHK
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
トキ
提供:NHK
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
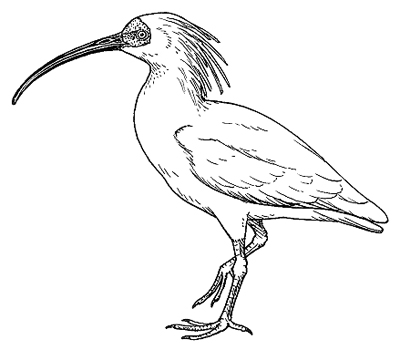 トキ
提供:佐渡トキ保護センター
トキ
提供:佐渡トキ保護センター
 トキ
提供:NHK
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
トキ
提供:NHK
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
とき【鬨・時・鯨波】🔗⭐🔉
とき【土岐】(地名)🔗⭐🔉
とき【土岐】
岐阜県南東部、土岐川に沿う市。美濃焼の発祥地で、陶磁器生産が盛ん。人口6万2千。
とき【土岐】(姓氏)🔗⭐🔉
とき【土岐】
姓氏の一つ。美濃源氏。土岐郡に土着し、中世、美濃の守護。戦国時代末、斎藤道三により没落。多治見・明智など庶流も多い。支流は近世、沼田藩主。
⇒とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
⇒とき‐つくばこ【土岐筑波子】
とき‐あか・す【解き明かす】🔗⭐🔉
とき‐あか・す【解き明かす】
〔他五〕
問題を解決してその意味を明らかにする。「難問を―・す」
とき‐あか・す【説き明かす】🔗⭐🔉
とき‐あか・す【説き明かす】
〔他五〕
物事の意味をよく分かるように説明する。「詩の主題を―・す」
とき‐あかり【時明り】🔗⭐🔉
とき‐あかり【時明り】
①明け方が近づき、東方がかすかに明るくなること。
②雨天の時、雲がうすくなって空がときどき明るくなること。
ときあけ‐もの【解き明け物】🔗⭐🔉
ときあけ‐もの【解き明け物】
綿入れの綿を抜いて袷あわせに縫いなおしたもの。綿貫わたぬき。引解ひきとき。西鶴織留2「世上に綿入着る時―に風をしのぎ」
とき‐あらい【解き洗い】‥アラヒ🔗⭐🔉
とき‐あらい【解き洗い】‥アラヒ
着物の縫糸をといて洗うこと。また、洗い張りをすること。
⇒ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】
⇒ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】
ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】‥アラヒ‥🔗⭐🔉
ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】‥アラヒ‥
解いて洗い張りする着物。ときあらいごろも。万葉集7「つるばみの―のあやしくも殊に着欲しきこの夕かも」
⇒とき‐あらい【解き洗い】
ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】‥アラヒ‥🔗⭐🔉
ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】‥アラヒ‥
(→)「ときあらいぎぬ」に同じ。万葉集15「吾妹子が―行きてはや着む」
⇒とき‐あらい【解き洗い】
とき‐い・ず【説き出づ】‥イヅ🔗⭐🔉
とき‐い・ず【説き出づ】‥イヅ
〔自下二〕
(→)「ときいだす」に同じ。枕草子33「いかで語り伝ふばかりと―・でたなり」
とき‐いだ・す【説き出す】🔗⭐🔉
とき‐いだ・す【説き出す】
〔自五〕
説きはじめる。語りだす。
とき‐いろ【鴇色】🔗⭐🔉
とき‐いろ【鴇色】
鴇の羽のような色、すなわち淡紅色。
Munsell color system: 7RP7.5/8
○時移り事去るときうつりことさる
[陳鴻、長恨歌伝「時移事去、楽尽悲来」]歳月が経過し諸事が変遷する。時世が移り変わる。古今和歌集序「たとひ時移り事去り、楽しび悲しび行きかふとも」
⇒とき【時】
○時移り事去るときうつりことさる🔗⭐🔉
○時移り事去るときうつりことさる
[陳鴻、長恨歌伝「時移事去、楽尽悲来」]歳月が経過し諸事が変遷する。時世が移り変わる。古今和歌集序「たとひ時移り事去り、楽しび悲しび行きかふとも」
⇒とき【時】
とき‐うま【疾馬・駿馬】
走ることの速い馬。しゅんめ。〈倭名類聚鈔11〉
ときえだ【時枝】
姓氏の一つ。
⇒ときえだ‐もとき【時枝誠記】
ときえだ‐もとき【時枝誠記】
国語学者。東京生れ。京城大・東大・早大教授。新たな言語理論として「言語過程説」を提唱。著「国語学史」「国語学原論」「日本文法」など。(1900〜1967)
時枝誠記
提供:毎日新聞社
 ⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
と‐ぎかい【都議会】‥クワイ
東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。
⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】
とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン
都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。
⇒と‐ぎかい【都議会】
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白
⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
と‐ぎかい【都議会】‥クワイ
東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。
⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】
とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン
都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。
⇒と‐ぎかい【都議会】
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とぎ‐かわ【研革】‥カハ
刃物を研ぐのに用いる革。
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とぎ‐し【研師】
刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とぎ‐しゅう【伽衆】
⇒おとぎしゅう(御伽衆)
どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ
離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」
とき‐しらず【時知らず】
①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。
②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。
③時鮭ときざけの異称。
ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】
(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」
ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ
時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」
とぎ‐じる【磨ぎ汁】
(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。
ときしる‐あめ【時知る雨】
時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」
ときしる‐ぐ【時知る具】
時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」
トキシン【Toxin ドイツ】
(→)毒素。
とき‐すす・める【説き勧める】
〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)
説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」
ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥
鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」
とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】
〔他五〕
①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」
②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」
とき‐せち【時節】
(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」
とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)
土岐善麿
撮影:田沼武能
しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とぎ‐かわ【研革】‥カハ
刃物を研ぐのに用いる革。
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とぎ‐し【研師】
刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とぎ‐しゅう【伽衆】
⇒おとぎしゅう(御伽衆)
どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ
離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」
とき‐しらず【時知らず】
①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。
②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。
③時鮭ときざけの異称。
ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】
(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」
ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ
時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」
とぎ‐じる【磨ぎ汁】
(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。
ときしる‐あめ【時知る雨】
時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」
ときしる‐ぐ【時知る具】
時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」
トキシン【Toxin ドイツ】
(→)毒素。
とき‐すす・める【説き勧める】
〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)
説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」
ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥
鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」
とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】
〔他五〕
①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」
②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」
とき‐せち【時節】
(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」
とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)
土岐善麿
撮影:田沼武能
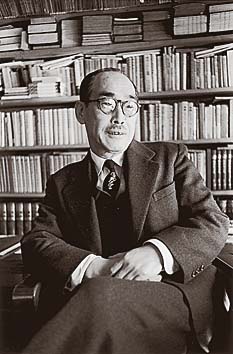 ⇒とき【土岐】
トキソイド【toxoid】
毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。
とき‐そう【鴇草】‥サウ
ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。
ときそば【時蕎麦】
落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。
トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ
(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。
とき‐だいこ【時太鼓】
時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」
とぎ‐だし【研ぎ出し】
①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。
②研出蒔絵まきえの略。
⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】
とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ
蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。
⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】
とぎ‐だ・す【研ぎ出す】
〔他五〕
研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」
とぎ‐たて【研ぎ立て】
研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」
とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】
〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)
刃物などを、念入りに研いで鋭くする。
とき‐たま【時偶】
時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」
とき‐たまご【溶き卵】
生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。
ど‐ぎつ・い
〔形〕
(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐づかさ【時司】
陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
どき‐つ・く
〔自五〕
不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つくばこ【土岐筑波子】
江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。
⇒とき【土岐】
とき‐づけ【時付け】
時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」
とき‐つげ‐どり【時告鳥】
鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」
とき‐つ・ける【説き付ける】
〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)
さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。
とき‐つづみ【時鼓】
時刻を知らせるために打つ鼓。
どきっ‐と
〔副〕
突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
どき‐どき
運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」
どぎ‐どぎ
①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」
②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
とき‐と‐する‐と【時とすると】
場合によっては。ともすると。たまに。
⇒とき【土岐】
トキソイド【toxoid】
毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。
とき‐そう【鴇草】‥サウ
ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。
ときそば【時蕎麦】
落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。
トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ
(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。
とき‐だいこ【時太鼓】
時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」
とぎ‐だし【研ぎ出し】
①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。
②研出蒔絵まきえの略。
⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】
とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ
蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。
⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】
とぎ‐だ・す【研ぎ出す】
〔他五〕
研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」
とぎ‐たて【研ぎ立て】
研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」
とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】
〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)
刃物などを、念入りに研いで鋭くする。
とき‐たま【時偶】
時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」
とき‐たまご【溶き卵】
生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。
ど‐ぎつ・い
〔形〕
(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐づかさ【時司】
陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
どき‐つ・く
〔自五〕
不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つくばこ【土岐筑波子】
江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。
⇒とき【土岐】
とき‐づけ【時付け】
時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」
とき‐つげ‐どり【時告鳥】
鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」
とき‐つ・ける【説き付ける】
〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)
さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。
とき‐つづみ【時鼓】
時刻を知らせるために打つ鼓。
どきっ‐と
〔副〕
突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
どき‐どき
運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」
どぎ‐どぎ
①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」
②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
とき‐と‐する‐と【時とすると】
場合によっては。ともすると。たまに。
 ⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
と‐ぎかい【都議会】‥クワイ
東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。
⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】
とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン
都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。
⇒と‐ぎかい【都議会】
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白
⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
と‐ぎかい【都議会】‥クワイ
東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。
⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】
とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン
都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。
⇒と‐ぎかい【都議会】
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とぎ‐かわ【研革】‥カハ
刃物を研ぐのに用いる革。
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とぎ‐し【研師】
刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とぎ‐しゅう【伽衆】
⇒おとぎしゅう(御伽衆)
どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ
離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」
とき‐しらず【時知らず】
①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。
②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。
③時鮭ときざけの異称。
ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】
(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」
ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ
時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」
とぎ‐じる【磨ぎ汁】
(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。
ときしる‐あめ【時知る雨】
時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」
ときしる‐ぐ【時知る具】
時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」
トキシン【Toxin ドイツ】
(→)毒素。
とき‐すす・める【説き勧める】
〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)
説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」
ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥
鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」
とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】
〔他五〕
①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」
②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」
とき‐せち【時節】
(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」
とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)
土岐善麿
撮影:田沼武能
しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とぎ‐かわ【研革】‥カハ
刃物を研ぐのに用いる革。
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
とぎ‐し【研師】
刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
ときしも‐あれ【時しもあれ】
他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」
⇒とき‐し‐も【時しも】
とぎ‐しゅう【伽衆】
⇒おとぎしゅう(御伽衆)
どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ
離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」
とき‐しらず【時知らず】
①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。
②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。
③時鮭ときざけの異称。
ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】
(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」
ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ
時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」
とぎ‐じる【磨ぎ汁】
(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。
ときしる‐あめ【時知る雨】
時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」
ときしる‐ぐ【時知る具】
時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」
トキシン【Toxin ドイツ】
(→)毒素。
とき‐すす・める【説き勧める】
〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)
説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」
ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥
鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」
とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】
〔他五〕
①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」
②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」
とき‐せち【時節】
(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」
とき‐ぜんまろ【土岐善麿】
歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)
土岐善麿
撮影:田沼武能
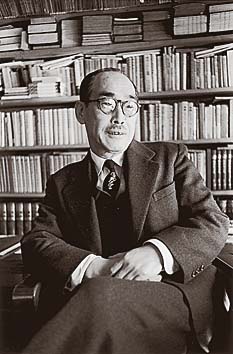 ⇒とき【土岐】
トキソイド【toxoid】
毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。
とき‐そう【鴇草】‥サウ
ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。
ときそば【時蕎麦】
落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。
トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ
(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。
とき‐だいこ【時太鼓】
時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」
とぎ‐だし【研ぎ出し】
①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。
②研出蒔絵まきえの略。
⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】
とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ
蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。
⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】
とぎ‐だ・す【研ぎ出す】
〔他五〕
研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」
とぎ‐たて【研ぎ立て】
研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」
とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】
〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)
刃物などを、念入りに研いで鋭くする。
とき‐たま【時偶】
時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」
とき‐たまご【溶き卵】
生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。
ど‐ぎつ・い
〔形〕
(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐づかさ【時司】
陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
どき‐つ・く
〔自五〕
不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つくばこ【土岐筑波子】
江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。
⇒とき【土岐】
とき‐づけ【時付け】
時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」
とき‐つげ‐どり【時告鳥】
鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」
とき‐つ・ける【説き付ける】
〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)
さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。
とき‐つづみ【時鼓】
時刻を知らせるために打つ鼓。
どきっ‐と
〔副〕
突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
どき‐どき
運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」
どぎ‐どぎ
①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」
②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
とき‐と‐する‐と【時とすると】
場合によっては。ともすると。たまに。
⇒とき【土岐】
トキソイド【toxoid】
毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。
とき‐そう【鴇草】‥サウ
ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。
ときそば【時蕎麦】
落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。
トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ
(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。
とき‐だいこ【時太鼓】
時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」
とぎ‐だし【研ぎ出し】
①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。
②研出蒔絵まきえの略。
⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】
とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ
蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。
⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】
とぎ‐だ・す【研ぎ出す】
〔他五〕
研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」
とぎ‐たて【研ぎ立て】
研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」
とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】
〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)
刃物などを、念入りに研いで鋭くする。
とき‐たま【時偶】
時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」
とき‐たまご【溶き卵】
生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。
ど‐ぎつ・い
〔形〕
(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」
とき‐つ‐うみ【時つ海】
時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」
とき‐づかさ【時司】
陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏
とき‐つ‐かぜ【時つ風】
[一]〔名〕
①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」
②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」
[二]〔枕〕
(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」
どき‐つ・く
〔自五〕
不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」
とき‐つ‐くに【時つ国】
四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」
とき‐つくばこ【土岐筑波子】
江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。
⇒とき【土岐】
とき‐づけ【時付け】
時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」
とき‐つげ‐どり【時告鳥】
鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」
とき‐つ・ける【説き付ける】
〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)
さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。
とき‐つづみ【時鼓】
時刻を知らせるために打つ鼓。
どきっ‐と
〔副〕
突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」
とき‐つ‐どり【時つ鳥】
(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。
とき‐どき【時時】
①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」
②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」
▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」
どき‐どき
運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」
どぎ‐どぎ
①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」
②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」
とき‐と‐して【時として】
①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」
②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」
とき‐と‐する‐と【時とすると】
場合によっては。ともすると。たまに。
とき‐うま【疾馬・駿馬】🔗⭐🔉
とき‐うま【疾馬・駿馬】
走ることの速い馬。しゅんめ。〈倭名類聚鈔11〉
ときえだ【時枝】🔗⭐🔉
ときえだ【時枝】
姓氏の一つ。
⇒ときえだ‐もとき【時枝誠記】
ときえだ‐もとき【時枝誠記】🔗⭐🔉
ときえだ‐もとき【時枝誠記】
国語学者。東京生れ。京城大・東大・早大教授。新たな言語理論として「言語過程説」を提唱。著「国語学史」「国語学原論」「日本文法」など。(1900〜1967)
時枝誠記
提供:毎日新聞社
 ⇒ときえだ【時枝】
⇒ときえだ【時枝】
 ⇒ときえだ【時枝】
⇒ときえだ【時枝】
とき‐おこ・す【説き起こす】🔗⭐🔉
とき‐おこ・す【説き起こす】
〔自五〕
説明を始める。「事の由来から―・す」
とき‐おと・す【説き落とす】🔗⭐🔉
とき‐おと・す【説き落とす】
〔他五〕
事情をよく説明して承知させる。説得する。
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】🔗⭐🔉
とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】
〔自五〕
説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。
とき‐おり【時折】‥ヲリ🔗⭐🔉
とき‐おり【時折】‥ヲリ
①時々。ときたま。「―便りがある」
②(近畿地方で)節日せちにちの総称。
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ🔗⭐🔉
とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ
〔他下二〕
①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」
②解いて形見に交換する。万葉集4「白 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」
とき‐がし【時貸し】🔗⭐🔉
とき‐がし【時貸し】
一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り
とき‐がしら【鬨頭】🔗⭐🔉
とき‐がしら【鬨頭】
鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨
とき‐かた【解き方】🔗⭐🔉
とき‐かた【解き方】
①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。
②糸・紐などをほどく方法。
とき‐がね【時鐘】🔗⭐🔉
とき‐がね【時鐘】
時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。
とき‐がみ【解き髪】🔗⭐🔉
とき‐がみ【解き髪】
結髪をといた髪。ほぐした髪。
とき‐がらし【溶き芥子】🔗⭐🔉
とき‐がらし【溶き芥子】
芥子の粉末を水で溶いたもの。
とき‐がり【時借り】🔗⭐🔉
とき‐がり【時借り】
一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス🔗⭐🔉
とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス
〔他四〕
帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」
とき‐きか・せる【説き聞かせる】🔗⭐🔉
とき‐きか・せる【説き聞かせる】
〔他下一〕[文]とききか・す(下二)
事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」
とき‐ぎぬ【解き衣】🔗⭐🔉
とき‐ぎぬ【解き衣】
縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。
⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】
ときぎぬ‐の【解き衣の】🔗⭐🔉
ときぎぬ‐の【解き衣の】
〔枕〕
「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」
⇒とき‐ぎぬ【解き衣】
とき‐ぎり【時切り】🔗⭐🔉
とき‐ぎり【時切り】
時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」
とき‐ぎれ【時切れ】🔗⭐🔉
とき‐ぎれ【時切れ】
人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」
とき‐ぐし【解き櫛】🔗⭐🔉
とき‐ぐし【解き櫛】
髪をとくための歯のあらい櫛。
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ🔗⭐🔉
とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ
江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。
とき‐ごろも【解き衣】🔗⭐🔉
とき‐ごろも【解き衣】
(→)「ときぎぬ」に同じ。
とき‐さ・く【解き放く】🔗⭐🔉
とき‐さ・く【解き放く】
〔他下二〕
解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」
とき‐ざけ【時鮭】🔗⭐🔉
とき‐ざけ【時鮭】
春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。
とき‐ざし【時指し】🔗⭐🔉
とき‐ざし【時指し】
時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」
とき‐さと・す【説き諭す】🔗⭐🔉
とき‐さと・す【説き諭す】
〔他五〕
道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。
とき・じ【時じ】🔗⭐🔉
とき・じ【時じ】
〔形シク〕
①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」
②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】🔗⭐🔉
ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】
(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」
とき‐しまれ【時しまれ】🔗⭐🔉
とき‐しまれ【時しまれ】
「時しもあれ」の約。
とき‐し‐も【時しも】🔗⭐🔉
とき‐し‐も【時しも】
(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」
⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】
広辞苑に「とき」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む