複数辞典一括検索+![]()
![]()
なさけ【情け】🔗⭐🔉
なさけ【情け】
①人間としての心。感情。三宝絵詞「木・草・山・川・鳥・獣・魚・虫など…―なきものに」
②他をあわれむ心。慈愛。人情。思いやり。「―容赦もなく」「―を尽くす」
③みやびごころ。風流心。伊勢物語「―ある人にて、瓶かめに花をさせり」
④ふぜい。興趣。宇津保物語吹上下「草木などは…人近にて朝夕なでつくろひたるなむ、すがたありさま―侍る」
⑤男女の情愛。恋情。恋ごころ。情事。宇治拾遺物語3「女も見知りて―は交しながら」
⑥義理。
⑦情じょうにすがること。お慈悲。おなさけ。好色五人女4「―に一腰かし給へ」
⇒なさけ‐がお【情け顔】
⇒なさけ‐ごかし【情けごかし】
⇒なさけ‐ごころ【情け心】
⇒なさけ‐ざかり【情け盛り】
⇒なさけ‐しらず【情け知らず】
⇒なさけ‐しり【情け知り】
⇒なさけ‐すがた【情け姿】
⇒なさけ‐づめ【情け詰め】
⇒なさけ‐な【情け無】
⇒なさけ‐の‐あに【情けの兄】
⇒なさけ‐の‐いと【情けの糸】
⇒なさけ‐の‐うみ【情けの海】
⇒なさけ‐の‐すえ【情けの末】
⇒なさけ‐の‐たね【情けの種】
⇒なさけ‐の‐つゆ【情けの露】
⇒なさけ‐の‐にしき【情けの錦】
⇒なさけ‐の‐ふみ【情けの文】
⇒なさけ‐の‐みち【情けの道】
⇒なさけ‐の‐やま【情けの山】
⇒なさけ‐びと【情け人】
⇒なさけ‐むよう【情け無用】
⇒なさけ‐もよう【情け模様】
⇒なさけ‐やど【情け宿】
⇒情け売る里
⇒情けが仇
⇒情けに刃向かう刃なし
⇒情けは人の為ならず
⇒情け容赦も無い
⇒情けを売る
⇒情けを掛ける
⇒情けを交わす
⇒情けを知る
○情け売る里なさけうるさと🔗⭐🔉
○情け売る里なさけうるさと
遊里。遊郭。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐おく・る【情け後る】
〔自下二〕
情味が乏しい。愛情が薄い。源氏物語末摘花「たとしへなう―・るるまめやかさなど」
なさけ‐おく・る【情け後る】🔗⭐🔉
なさけ‐おく・る【情け後る】
〔自下二〕
情味が乏しい。愛情が薄い。源氏物語末摘花「たとしへなう―・るるまめやかさなど」
○情けが仇なさけがあだ
なさけをこめてしたことがかえってためにならないこと。好意が逆効果を生むこと。
⇒なさけ【情け】
○情けが仇なさけがあだ🔗⭐🔉
○情けが仇なさけがあだ
なさけをこめてしたことがかえってためにならないこと。好意が逆効果を生むこと。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐がお【情け顔】‥ガホ
なさけのあるらしい顔つき。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐が・る【情けがる】
〔自四〕
なさけがあるらしくふるまう。あわれむ。源氏物語関屋「昔よりすき心ありてすこし―・りける」
なさけ‐ごかし【情けごかし】
表面はなさけ深そうにみせて、実は自分の利益を計ること。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐ごころ【情け心】
なさけのある心。なさけ。慈悲心。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐ざかり【情け盛り】
なさけごころのあるさかり。色気ざかり。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐しらず【情け知らず】
人情を解しないこと。思いやりのないこと。男女の情愛を知らないこと。また、その人。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐しり【情け知り】
人情を解すること。人情に通じていること。男女の情愛についてよくわきまえていること。また、その人。恋知り。わけ知り。粋すい。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐すがた【情け姿】
なさけをこめた姿。色気のある姿。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐だ・つ【情け立つ】
〔自四〕
①なさけがあるらしく見える。なさけがありそうにふるまう。源氏物語藤裏葉「―・ち給ふ若人はうらめしと思ふもありけり」
②風流がる。源氏物語帚木「よしばみ―・たざらむなむ目やすかるべき」
なさけ‐づく・る【情け作る】
〔自四〕
なさけがあるらしくふるまう。源氏物語関屋「―・れど、うはべこそあれ、つらき事多かり」
なさけ‐づめ【情け詰め】
人情ずくで攻めたてられること。なさけに迫られること。なさけぜめ。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐な【情け無】
(「情無し」の語幹)なさけのないこと。新撰六帖3「人のしわざの―の世や」
⇒なさけ【情け】
なさけ‐な・い【情け無い】
〔形〕[文]なさけな・し(ク)
①なさけ心がない。おもいやりがない。無情である。伊勢物語「―・くいらへてやみぬ」
②つれない。無愛想である。源氏物語帚木「殊更に―・くつれなきさまを見せて」。「―・い素振り」
③不風流である。無骨である。源氏物語玉鬘「歌ふ声の―・きもあはれに聞ゆ」
④あさましい。あきれるほどである。栄華物語耀く藤壺「此の頃の人はうたて―・きまで着重ねても、なほこそは風なども起るめれ」
⑤嘆かわしい。みじめである。「―・い男」「―・い羽目になる」
なさけ‐なさけ・し【情け情けし】
〔形シク〕
いかにもなさけが深いようである。源氏物語帚木「―・しく宣ひつくすべかめれど」
なさけ‐がお【情け顔】‥ガホ🔗⭐🔉
なさけ‐がお【情け顔】‥ガホ
なさけのあるらしい顔つき。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐が・る【情けがる】🔗⭐🔉
なさけ‐が・る【情けがる】
〔自四〕
なさけがあるらしくふるまう。あわれむ。源氏物語関屋「昔よりすき心ありてすこし―・りける」
なさけ‐ごかし【情けごかし】🔗⭐🔉
なさけ‐ごかし【情けごかし】
表面はなさけ深そうにみせて、実は自分の利益を計ること。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐ごころ【情け心】🔗⭐🔉
なさけ‐ごころ【情け心】
なさけのある心。なさけ。慈悲心。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐ざかり【情け盛り】🔗⭐🔉
なさけ‐ざかり【情け盛り】
なさけごころのあるさかり。色気ざかり。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐しらず【情け知らず】🔗⭐🔉
なさけ‐しらず【情け知らず】
人情を解しないこと。思いやりのないこと。男女の情愛を知らないこと。また、その人。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐しり【情け知り】🔗⭐🔉
なさけ‐しり【情け知り】
人情を解すること。人情に通じていること。男女の情愛についてよくわきまえていること。また、その人。恋知り。わけ知り。粋すい。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐すがた【情け姿】🔗⭐🔉
なさけ‐すがた【情け姿】
なさけをこめた姿。色気のある姿。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐だ・つ【情け立つ】🔗⭐🔉
なさけ‐だ・つ【情け立つ】
〔自四〕
①なさけがあるらしく見える。なさけがありそうにふるまう。源氏物語藤裏葉「―・ち給ふ若人はうらめしと思ふもありけり」
②風流がる。源氏物語帚木「よしばみ―・たざらむなむ目やすかるべき」
なさけ‐づく・る【情け作る】🔗⭐🔉
なさけ‐づく・る【情け作る】
〔自四〕
なさけがあるらしくふるまう。源氏物語関屋「―・れど、うはべこそあれ、つらき事多かり」
なさけ‐づめ【情け詰め】🔗⭐🔉
なさけ‐づめ【情け詰め】
人情ずくで攻めたてられること。なさけに迫られること。なさけぜめ。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐な【情け無】🔗⭐🔉
なさけ‐な【情け無】
(「情無し」の語幹)なさけのないこと。新撰六帖3「人のしわざの―の世や」
⇒なさけ【情け】
なさけ‐な・い【情け無い】🔗⭐🔉
なさけ‐な・い【情け無い】
〔形〕[文]なさけな・し(ク)
①なさけ心がない。おもいやりがない。無情である。伊勢物語「―・くいらへてやみぬ」
②つれない。無愛想である。源氏物語帚木「殊更に―・くつれなきさまを見せて」。「―・い素振り」
③不風流である。無骨である。源氏物語玉鬘「歌ふ声の―・きもあはれに聞ゆ」
④あさましい。あきれるほどである。栄華物語耀く藤壺「此の頃の人はうたて―・きまで着重ねても、なほこそは風なども起るめれ」
⑤嘆かわしい。みじめである。「―・い男」「―・い羽目になる」
なさけ‐なさけ・し【情け情けし】🔗⭐🔉
なさけ‐なさけ・し【情け情けし】
〔形シク〕
いかにもなさけが深いようである。源氏物語帚木「―・しく宣ひつくすべかめれど」
○情けに刃向かう刃なしなさけにはむかうやいばなし
なさけをかけられれば、誰も反抗のしようがない。
⇒なさけ【情け】
○情けに刃向かう刃なしなさけにはむかうやいばなし🔗⭐🔉
○情けに刃向かう刃なしなさけにはむかうやいばなし
なさけをかけられれば、誰も反抗のしようがない。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐あに【情けの兄】
義理の兄。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐いと【情けの糸】
なさけにひかされることを糸にたとえていう語。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐うみ【情けの海】
愛欲の迷いの深さを海にたとえていう語。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐すえ【情けの末】‥スヱ
情愛の及ぶ末。謡曲、花筐「かくばかり―を白露の」
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐たね【情けの種】
①人情の根源。
②腹にやどした情人の子。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐つゆ【情けの露】
情愛のうるおいを露にたとえていう語。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐にしき【情けの錦】
美しい情愛を錦にたとえていう語。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐ふみ【情けの文】
恋ぶみ。艶書。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐みち【情けの道】
人情のみち。恋のみち。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐やま【情けの山】
多情なことを山にたとえていう語。好色五人女3「都に―を動かし」
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐あに【情けの兄】🔗⭐🔉
なさけ‐の‐あに【情けの兄】
義理の兄。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐いと【情けの糸】🔗⭐🔉
なさけ‐の‐いと【情けの糸】
なさけにひかされることを糸にたとえていう語。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐うみ【情けの海】🔗⭐🔉
なさけ‐の‐うみ【情けの海】
愛欲の迷いの深さを海にたとえていう語。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐すえ【情けの末】‥スヱ🔗⭐🔉
なさけ‐の‐すえ【情けの末】‥スヱ
情愛の及ぶ末。謡曲、花筐「かくばかり―を白露の」
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐たね【情けの種】🔗⭐🔉
なさけ‐の‐たね【情けの種】
①人情の根源。
②腹にやどした情人の子。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐つゆ【情けの露】🔗⭐🔉
なさけ‐の‐つゆ【情けの露】
情愛のうるおいを露にたとえていう語。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐にしき【情けの錦】🔗⭐🔉
なさけ‐の‐にしき【情けの錦】
美しい情愛を錦にたとえていう語。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐ふみ【情けの文】🔗⭐🔉
なさけ‐の‐ふみ【情けの文】
恋ぶみ。艶書。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐の‐みち【情けの道】🔗⭐🔉
なさけ‐の‐みち【情けの道】
人情のみち。恋のみち。
⇒なさけ【情け】
○情けは人の為ならずなさけはひとのためならず🔗⭐🔉
○情けは人の為ならずなさけはひとのためならず
情けを人にかけておけば、めぐりめぐって自分によい報いが来る。人に親切にしておけば、必ずよい報いがある。
▷人に情けをかけるのは自立の妨げになりその人のためにならない、の意に解するのは誤り。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐ば・む【情けばむ】
〔自四〕
なさけありげにふるまう。源氏物語夕霧「内々の御心遣ひはこののたまふさまにかなひてもしばしは―・まむ」
なさけ‐びと【情け人】
①なさけ深い人。
②色を売る人。
⇒なさけ【情け】
なさけ・ぶ【情けぶ】
〔自上二〕
なさけあるようにふるまう。風流めく。源氏物語玉鬘「いと―・び、きらぎらしく物し給ひしを」
なさけ‐ぶか・い【情け深い】
〔形〕[文]なさけぶか・し(ク)
あわれみぶかい。思いやりがある。深い情じょうがある。また、風流心がある。「―・い主人」
なさけ‐むよう【情け無用】
情けをかけても無駄なこと。情けをかける必要はないこと。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐もよう【情け模様】‥ヤウ
なさけありげな模様。粋な模様。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐やど【情け宿】
①親切で人をとめること。また、その宿。
②恋のとりもちをする宿。あいびき宿。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐ば・む【情けばむ】🔗⭐🔉
なさけ‐ば・む【情けばむ】
〔自四〕
なさけありげにふるまう。源氏物語夕霧「内々の御心遣ひはこののたまふさまにかなひてもしばしは―・まむ」
なさけ‐びと【情け人】🔗⭐🔉
なさけ‐びと【情け人】
①なさけ深い人。
②色を売る人。
⇒なさけ【情け】
なさけ・ぶ【情けぶ】🔗⭐🔉
なさけ・ぶ【情けぶ】
〔自上二〕
なさけあるようにふるまう。風流めく。源氏物語玉鬘「いと―・び、きらぎらしく物し給ひしを」
なさけ‐ぶか・い【情け深い】🔗⭐🔉
なさけ‐ぶか・い【情け深い】
〔形〕[文]なさけぶか・し(ク)
あわれみぶかい。思いやりがある。深い情じょうがある。また、風流心がある。「―・い主人」
なさけ‐むよう【情け無用】🔗⭐🔉
なさけ‐むよう【情け無用】
情けをかけても無駄なこと。情けをかける必要はないこと。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐もよう【情け模様】‥ヤウ🔗⭐🔉
なさけ‐もよう【情け模様】‥ヤウ
なさけありげな模様。粋な模様。
⇒なさけ【情け】
なさけ‐やど【情け宿】🔗⭐🔉
○情け容赦も無いなさけようしゃもない🔗⭐🔉
○情け容赦も無いなさけようしゃもない
同情して許すことなどしない。きわめてきびしい。「―仕打ち」
⇒なさけ【情け】
なさけ‐らし・い【情けらしい】
〔形〕[文]なさけら・し(シク)
なさけがあるらしい。やさしい。狂言、花子「ことば尋常に匂ひなどして―・しう言うてくるるによつて」
○情けを売るなさけをうる🔗⭐🔉
○情けを売るなさけをうる
①色を売る。淫をひさぐ。
②自分の利益を考えて、人に親切をしておく。
⇒なさけ【情け】
○情けを掛けるなさけをかける🔗⭐🔉
○情けを掛けるなさけをかける
なさけをほどこす。あわれみをかける。思いやりをこめた言動をする。
⇒なさけ【情け】
○情けを交わすなさけをかわす🔗⭐🔉
○情けを交わすなさけをかわす
情愛を交わす。親しみあう。
⇒なさけ【情け】
○情けを知るなさけをしる🔗⭐🔉
○情けを知るなさけをしる
①人情の何たるかを知る。
②男女間の情愛に通じている。
⇒なさけ【情け】
ナサコム【NASAKOM】
インドネシアの大統領スカルノが提唱した国民綱領。民族主義(nasionalisme)、宗教(agama)、共産主義(kommunisme)の統一を目指したもの。1965年の九‐三十事件により消滅。
な‐ざし【名指し】
名をあげて指定すること。指名。「―で非難する」
⇒なざし‐にん【名指人】
なざし‐にん【名指人】
①指名された人。
②指定した手形の受取人。
⇒な‐ざし【名指し】
な‐ざ・す【名指す】
〔他五〕
だれそれと名を指し示す。指名する。
なさぬ‐なか【生さぬ仲】
肉親でない親子の仲。継父または継母と継子との間柄。また、養父母と養子との間柄。
なさ・る【為さる】
[一]〔他五〕
①「する」「なす」の尊敬語。「卒業―・る時」
②動詞の連用形に付いて、尊敬の意を表す。「行き―・る」「お読み―・った」
[二]〔他下二〕
⇒なされる(下一)
ナザルバエフ【Nursultan A. Nazarbaev】
カザフスタンの政治家。ソ連のペレストロイカ期にカザフ共産党第一書記。1991年カザフスタン共和国独立とともに大統領。強権的に政治を運営、大統領任期を延長。(1940〜)
ナザレ【Nazareth】
イスラエル北部の都市。地中海岸ハイファの東南東約30キロメートル、ヨルダン渓谷の西側の山地にある。イエスが育った地。ナゼラト。
⇒ナザレ‐びと【ナザレ人】
ナザレ‐びと【ナザレ人】
①ナザレの人。特にイエスを指す。
②(ユダヤ人、後にイスラム教徒の側から)キリスト教徒の蔑称。
⇒ナザレ【Nazareth】
なさ・れる【為される】
〔他下一〕[文]なさ・る(下二)
(→)「なさる」(五段)に同じ。狂言、萩大名「あれへお出で―・れたならばお褒め―・れませ」
なし【生し】
生むこと。生んだこと。万葉集9「父母が―のまにまに」
なし【為し・作し】
なすこと。しわざ。…のせい。源氏物語紅梅「心の―にやありけむ」
なし【梨・梨子】
バラ科の落葉高木。日本の中部以南および中国大陸に自生する原種から、それぞれ独立に果樹として改良。葉は卵形。4月頃、葉と共にサクラに似てやや大きな白花をつける。果実は大形で球形、外皮に小さい斑点があり、食用。大別して「長十郎」に代表される赤梨と「二十世紀」に代表される青梨とがある。ありのみ。「梨の花」は〈[季]春〉、「梨の実」は〈[季]秋〉。万葉集10「妻―の木を手折りかざさむ」
⇒梨の礫
なし【無し】
ないこと。むなしいこと。無駄。無む。狂言、船渡聟「其方の骨折は―にはせまい程に」。「人で―」「言いっこ―」
な・し【無し・亡し】
〔形ク〕
⇒ない
な・し
〔接尾〕
⇒ない
なじ【何】
〔副〕
なぜ。なにゆえ。沙石集(一本)「さらば―に思し食したちたる」
ナジ【Nagy Imre】
ハンガリーの政治家。1953〜55年首相。56年ハンガリー事件の際に首相に復帰し、部分的な民主化を推進。ソ連の武力介入で逮捕・処刑された。89年名誉回復。(1896〜1958)
なし‐あ・ぐ【成し上ぐ】
〔他下二〕
①官位などをのぼす。昇進させる。源氏物語東屋「けふあすといふばかりに―・げてむ」
②なしとげる。しあげる。成就する。
なし‐い・ず【成し出づ】‥イヅ
〔他下二〕
引き立てて昇進させる。源氏物語関屋「とりわきて―・で給ひければ」
なし‐い・ず【為し出づ】‥イヅ
〔他下二〕
しでかす。なす。宇津保物語俊蔭「その折の事のみ―・でつ」
なし‐うち【梨子打】
(ナシウチはナヤ(萎)シウチの約で、柔らかに造ったの意)「なしうちえぼし」の略。
⇒なしうち‐えぼし【梨子打烏帽子】
なしうち‐えぼし【梨子打烏帽子】
揉もみ烏帽子の一種。黒の紗や綾地に薄く漆を塗って柔らかく作り、兜の下に着用。軍陣で武将が用いた。
梨子打烏帽子
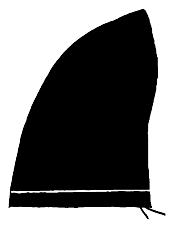 ⇒なし‐うち【梨子打】
なし‐うり【梨瓜】
マクワウリの一品種。中国から渡来。果実は卵形で黄白色、果肉は緑白色。ニューメロン。〈[季]夏〉
なし‐え【梨絵】‥ヱ
梨子地なしじの蒔絵まきえ。枕草子184「沈の御火桶の―したるに」
なじ‐か
〔副〕
(ナニシニカの約)どうしてか。なぜか。風雅和歌集恋「―と思ふ情もぞ見る」
⇒なじか‐は
なじか‐は
〔副〕
①どうしてか。いかでか。普通、下に反語を伴う。保元物語(金刀比羅本)「―ふたたびとり返し候ふべき」
②なにゆえ。なぜ。どうして。徒然草「―捨てしなどいはむは」
⇒なじ‐か
なし‐かん【梨子羹】
梨の実をすりおろした汁に、寒天・砂糖などを加えて流し固めたもの。
なし‐くずし【済し崩し】‥クヅシ
①借金を少しずつ返却すること。元禄大平記「―の借銭」
②物事を少しずつすましてゆくこと。「―に既成事実ができ上がる」
なし‐くず・す【済し崩す】‥クヅス
〔自五〕
なしくずしにする。
ナシ‐ゴレン【nasi goreng マレー】
(ナシは米飯、ゴレンは油で炒める意)インドネシア・マレーシアの焼飯。ケチャップ‐マニス(甘口醤油)などで調味し、サンバル(ペースト状の辛口の薬味)を添えて食べる。
なし‐じ【梨子地】‥ヂ
①蒔絵まきえの地蒔の一種。漆地に金や銀の梨子地粉を蒔き、上に梨子地漆を塗り、粉が露出しない程度に研ぎ出したもの。金銀粉が漆を通してまだらに見え、梨の実の肌に似る。梨地。曾我物語1「外は―にまきて」
②梨子地織の略で、織物地質の一つ。格子に似た織り方で、布面に梨の実の表皮に似た外観を与えたもの。
⇒なしじ‐うるし【梨子地漆】
⇒なしじ‐ぬり【梨子地塗】
⇒なしじ‐ふん【梨子地粉】
なしじ‐うるし【梨子地漆】‥ヂ‥
主として梨子地塗に用いる透明な漆。梨子地粉の発色をよくするため、雌黄しおう2か梔子くちなしから採った染料を生漆に加えて製する。
⇒なし‐じ【梨子地】
なしじ‐ぬり【梨子地塗】‥ヂ‥
梨子地に塗ること。また、その塗物。
⇒なし‐じ【梨子地】
なしじ‐ふん【梨子地粉】‥ヂ‥
梨子地に用いる金や銀の粉。平目粉ひらめふんをさらに細かくしたもの。
⇒なし‐じ【梨子地】
なし‐しゅ【梨酒】
梨の果汁をしぼり、発酵させて造った酒。または、梨の果肉を砂糖とともに焼酎に漬けた果実酒。
なし‐た・つ【成し立つ】
〔他下二〕
世に立つようにする。立派に育て上げる。源氏物語玉鬘「御子どもみな物めかし―・て給ふを聞けば」
なし‐つぼ【梨壺】
昭陽舎の異称。庭前に梨を植えたからいう。
⇒なしつぼ‐の‐ごにん【梨壺の五人】
なしつぼ‐の‐ごにん【梨壺の五人】
951年(天暦5)梨壺に置かれた和歌所の寄人よりうど。すなわち、後撰集の撰集と万葉集の付訓に当たった大中臣能宣・清原元輔・源順したごう・紀時文・坂上望城もちきの5人の称。
⇒なし‐つぼ【梨壺】
な‐して
〔副〕
(東北地方・新潟県・西日本で)どうして。なぜ。
なし‐と・げる【為し遂げる・成し遂げる】
〔他下一〕[文]なしと・ぐ(下二)
物事をしとげる。完成する。「偉業を―・げる」
なしのき‐じんじゃ【梨木神社】
京都市上京区にある元別格官幣社。祭神は三条実万さねつむ・三条実美さねとみ。1885年(明治18)創建。
梨木神社
撮影:的場 啓
⇒なし‐うち【梨子打】
なし‐うり【梨瓜】
マクワウリの一品種。中国から渡来。果実は卵形で黄白色、果肉は緑白色。ニューメロン。〈[季]夏〉
なし‐え【梨絵】‥ヱ
梨子地なしじの蒔絵まきえ。枕草子184「沈の御火桶の―したるに」
なじ‐か
〔副〕
(ナニシニカの約)どうしてか。なぜか。風雅和歌集恋「―と思ふ情もぞ見る」
⇒なじか‐は
なじか‐は
〔副〕
①どうしてか。いかでか。普通、下に反語を伴う。保元物語(金刀比羅本)「―ふたたびとり返し候ふべき」
②なにゆえ。なぜ。どうして。徒然草「―捨てしなどいはむは」
⇒なじ‐か
なし‐かん【梨子羹】
梨の実をすりおろした汁に、寒天・砂糖などを加えて流し固めたもの。
なし‐くずし【済し崩し】‥クヅシ
①借金を少しずつ返却すること。元禄大平記「―の借銭」
②物事を少しずつすましてゆくこと。「―に既成事実ができ上がる」
なし‐くず・す【済し崩す】‥クヅス
〔自五〕
なしくずしにする。
ナシ‐ゴレン【nasi goreng マレー】
(ナシは米飯、ゴレンは油で炒める意)インドネシア・マレーシアの焼飯。ケチャップ‐マニス(甘口醤油)などで調味し、サンバル(ペースト状の辛口の薬味)を添えて食べる。
なし‐じ【梨子地】‥ヂ
①蒔絵まきえの地蒔の一種。漆地に金や銀の梨子地粉を蒔き、上に梨子地漆を塗り、粉が露出しない程度に研ぎ出したもの。金銀粉が漆を通してまだらに見え、梨の実の肌に似る。梨地。曾我物語1「外は―にまきて」
②梨子地織の略で、織物地質の一つ。格子に似た織り方で、布面に梨の実の表皮に似た外観を与えたもの。
⇒なしじ‐うるし【梨子地漆】
⇒なしじ‐ぬり【梨子地塗】
⇒なしじ‐ふん【梨子地粉】
なしじ‐うるし【梨子地漆】‥ヂ‥
主として梨子地塗に用いる透明な漆。梨子地粉の発色をよくするため、雌黄しおう2か梔子くちなしから採った染料を生漆に加えて製する。
⇒なし‐じ【梨子地】
なしじ‐ぬり【梨子地塗】‥ヂ‥
梨子地に塗ること。また、その塗物。
⇒なし‐じ【梨子地】
なしじ‐ふん【梨子地粉】‥ヂ‥
梨子地に用いる金や銀の粉。平目粉ひらめふんをさらに細かくしたもの。
⇒なし‐じ【梨子地】
なし‐しゅ【梨酒】
梨の果汁をしぼり、発酵させて造った酒。または、梨の果肉を砂糖とともに焼酎に漬けた果実酒。
なし‐た・つ【成し立つ】
〔他下二〕
世に立つようにする。立派に育て上げる。源氏物語玉鬘「御子どもみな物めかし―・て給ふを聞けば」
なし‐つぼ【梨壺】
昭陽舎の異称。庭前に梨を植えたからいう。
⇒なしつぼ‐の‐ごにん【梨壺の五人】
なしつぼ‐の‐ごにん【梨壺の五人】
951年(天暦5)梨壺に置かれた和歌所の寄人よりうど。すなわち、後撰集の撰集と万葉集の付訓に当たった大中臣能宣・清原元輔・源順したごう・紀時文・坂上望城もちきの5人の称。
⇒なし‐つぼ【梨壺】
な‐して
〔副〕
(東北地方・新潟県・西日本で)どうして。なぜ。
なし‐と・げる【為し遂げる・成し遂げる】
〔他下一〕[文]なしと・ぐ(下二)
物事をしとげる。完成する。「偉業を―・げる」
なしのき‐じんじゃ【梨木神社】
京都市上京区にある元別格官幣社。祭神は三条実万さねつむ・三条実美さねとみ。1885年(明治18)創建。
梨木神社
撮影:的場 啓

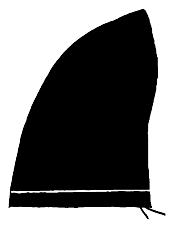 ⇒なし‐うち【梨子打】
なし‐うり【梨瓜】
マクワウリの一品種。中国から渡来。果実は卵形で黄白色、果肉は緑白色。ニューメロン。〈[季]夏〉
なし‐え【梨絵】‥ヱ
梨子地なしじの蒔絵まきえ。枕草子184「沈の御火桶の―したるに」
なじ‐か
〔副〕
(ナニシニカの約)どうしてか。なぜか。風雅和歌集恋「―と思ふ情もぞ見る」
⇒なじか‐は
なじか‐は
〔副〕
①どうしてか。いかでか。普通、下に反語を伴う。保元物語(金刀比羅本)「―ふたたびとり返し候ふべき」
②なにゆえ。なぜ。どうして。徒然草「―捨てしなどいはむは」
⇒なじ‐か
なし‐かん【梨子羹】
梨の実をすりおろした汁に、寒天・砂糖などを加えて流し固めたもの。
なし‐くずし【済し崩し】‥クヅシ
①借金を少しずつ返却すること。元禄大平記「―の借銭」
②物事を少しずつすましてゆくこと。「―に既成事実ができ上がる」
なし‐くず・す【済し崩す】‥クヅス
〔自五〕
なしくずしにする。
ナシ‐ゴレン【nasi goreng マレー】
(ナシは米飯、ゴレンは油で炒める意)インドネシア・マレーシアの焼飯。ケチャップ‐マニス(甘口醤油)などで調味し、サンバル(ペースト状の辛口の薬味)を添えて食べる。
なし‐じ【梨子地】‥ヂ
①蒔絵まきえの地蒔の一種。漆地に金や銀の梨子地粉を蒔き、上に梨子地漆を塗り、粉が露出しない程度に研ぎ出したもの。金銀粉が漆を通してまだらに見え、梨の実の肌に似る。梨地。曾我物語1「外は―にまきて」
②梨子地織の略で、織物地質の一つ。格子に似た織り方で、布面に梨の実の表皮に似た外観を与えたもの。
⇒なしじ‐うるし【梨子地漆】
⇒なしじ‐ぬり【梨子地塗】
⇒なしじ‐ふん【梨子地粉】
なしじ‐うるし【梨子地漆】‥ヂ‥
主として梨子地塗に用いる透明な漆。梨子地粉の発色をよくするため、雌黄しおう2か梔子くちなしから採った染料を生漆に加えて製する。
⇒なし‐じ【梨子地】
なしじ‐ぬり【梨子地塗】‥ヂ‥
梨子地に塗ること。また、その塗物。
⇒なし‐じ【梨子地】
なしじ‐ふん【梨子地粉】‥ヂ‥
梨子地に用いる金や銀の粉。平目粉ひらめふんをさらに細かくしたもの。
⇒なし‐じ【梨子地】
なし‐しゅ【梨酒】
梨の果汁をしぼり、発酵させて造った酒。または、梨の果肉を砂糖とともに焼酎に漬けた果実酒。
なし‐た・つ【成し立つ】
〔他下二〕
世に立つようにする。立派に育て上げる。源氏物語玉鬘「御子どもみな物めかし―・て給ふを聞けば」
なし‐つぼ【梨壺】
昭陽舎の異称。庭前に梨を植えたからいう。
⇒なしつぼ‐の‐ごにん【梨壺の五人】
なしつぼ‐の‐ごにん【梨壺の五人】
951年(天暦5)梨壺に置かれた和歌所の寄人よりうど。すなわち、後撰集の撰集と万葉集の付訓に当たった大中臣能宣・清原元輔・源順したごう・紀時文・坂上望城もちきの5人の称。
⇒なし‐つぼ【梨壺】
な‐して
〔副〕
(東北地方・新潟県・西日本で)どうして。なぜ。
なし‐と・げる【為し遂げる・成し遂げる】
〔他下一〕[文]なしと・ぐ(下二)
物事をしとげる。完成する。「偉業を―・げる」
なしのき‐じんじゃ【梨木神社】
京都市上京区にある元別格官幣社。祭神は三条実万さねつむ・三条実美さねとみ。1885年(明治18)創建。
梨木神社
撮影:的場 啓
⇒なし‐うち【梨子打】
なし‐うり【梨瓜】
マクワウリの一品種。中国から渡来。果実は卵形で黄白色、果肉は緑白色。ニューメロン。〈[季]夏〉
なし‐え【梨絵】‥ヱ
梨子地なしじの蒔絵まきえ。枕草子184「沈の御火桶の―したるに」
なじ‐か
〔副〕
(ナニシニカの約)どうしてか。なぜか。風雅和歌集恋「―と思ふ情もぞ見る」
⇒なじか‐は
なじか‐は
〔副〕
①どうしてか。いかでか。普通、下に反語を伴う。保元物語(金刀比羅本)「―ふたたびとり返し候ふべき」
②なにゆえ。なぜ。どうして。徒然草「―捨てしなどいはむは」
⇒なじ‐か
なし‐かん【梨子羹】
梨の実をすりおろした汁に、寒天・砂糖などを加えて流し固めたもの。
なし‐くずし【済し崩し】‥クヅシ
①借金を少しずつ返却すること。元禄大平記「―の借銭」
②物事を少しずつすましてゆくこと。「―に既成事実ができ上がる」
なし‐くず・す【済し崩す】‥クヅス
〔自五〕
なしくずしにする。
ナシ‐ゴレン【nasi goreng マレー】
(ナシは米飯、ゴレンは油で炒める意)インドネシア・マレーシアの焼飯。ケチャップ‐マニス(甘口醤油)などで調味し、サンバル(ペースト状の辛口の薬味)を添えて食べる。
なし‐じ【梨子地】‥ヂ
①蒔絵まきえの地蒔の一種。漆地に金や銀の梨子地粉を蒔き、上に梨子地漆を塗り、粉が露出しない程度に研ぎ出したもの。金銀粉が漆を通してまだらに見え、梨の実の肌に似る。梨地。曾我物語1「外は―にまきて」
②梨子地織の略で、織物地質の一つ。格子に似た織り方で、布面に梨の実の表皮に似た外観を与えたもの。
⇒なしじ‐うるし【梨子地漆】
⇒なしじ‐ぬり【梨子地塗】
⇒なしじ‐ふん【梨子地粉】
なしじ‐うるし【梨子地漆】‥ヂ‥
主として梨子地塗に用いる透明な漆。梨子地粉の発色をよくするため、雌黄しおう2か梔子くちなしから採った染料を生漆に加えて製する。
⇒なし‐じ【梨子地】
なしじ‐ぬり【梨子地塗】‥ヂ‥
梨子地に塗ること。また、その塗物。
⇒なし‐じ【梨子地】
なしじ‐ふん【梨子地粉】‥ヂ‥
梨子地に用いる金や銀の粉。平目粉ひらめふんをさらに細かくしたもの。
⇒なし‐じ【梨子地】
なし‐しゅ【梨酒】
梨の果汁をしぼり、発酵させて造った酒。または、梨の果肉を砂糖とともに焼酎に漬けた果実酒。
なし‐た・つ【成し立つ】
〔他下二〕
世に立つようにする。立派に育て上げる。源氏物語玉鬘「御子どもみな物めかし―・て給ふを聞けば」
なし‐つぼ【梨壺】
昭陽舎の異称。庭前に梨を植えたからいう。
⇒なしつぼ‐の‐ごにん【梨壺の五人】
なしつぼ‐の‐ごにん【梨壺の五人】
951年(天暦5)梨壺に置かれた和歌所の寄人よりうど。すなわち、後撰集の撰集と万葉集の付訓に当たった大中臣能宣・清原元輔・源順したごう・紀時文・坂上望城もちきの5人の称。
⇒なし‐つぼ【梨壺】
な‐して
〔副〕
(東北地方・新潟県・西日本で)どうして。なぜ。
なし‐と・げる【為し遂げる・成し遂げる】
〔他下一〕[文]なしと・ぐ(下二)
物事をしとげる。完成する。「偉業を―・げる」
なしのき‐じんじゃ【梨木神社】
京都市上京区にある元別格官幣社。祭神は三条実万さねつむ・三条実美さねとみ。1885年(明治18)創建。
梨木神社
撮影:的場 啓

広辞苑に「情け」で始まるの検索結果 1-43。