複数辞典一括検索+![]()
![]()
あが・る【上がる・揚がる・挙がる・騰る】🔗⭐🔉
あが・る【上がる・揚がる・挙がる・騰る】
〔自五〕
位置や段階や次元が高い方へ移る。
➊そのもの全体または部分の位置が高い方に向かう。また、上方に位置する。
①上方に向かう。万葉集20「朝なさな―・る雲雀」。竹取物語「土より五尺ばかり―・りたる程に立ちつらねたり」。「屋根に―・る」
②水上・水中または船などから陸上へ移る。平家物語灌頂「魚うおの陸くがに―・れるが如く」。「おかに―・る」
③風呂から出る。夜の寝覚1「ただ今御湯より―・らせ給ひて」
④地中から地上に生え出る。狂言、竹の子「当年はおびただしう筍が―・つてござるによつて」
⑤(地面から)座敷などにはいる。昨日は今日の物語「―・らうとしても、縁が高さに―・りかねて」。「―・って話しこむ」
⑥田舎から上方かみがたへ行く。
⑦上かみの方へさかのぼる。源氏物語若菜下「時ならぬ霜・雪を降らせ、雲いかづちを騒がしたるためし、―・りたる世にはありけり」
⑧京都で、北(内裏のある方角)へ行く。大阪で、大阪城の方へ近寄る。浮世草子、好色産毛「宿に帰るまでもなく、―・る町の門の戸陰に立ち寄りて」。浮世草子、好色万金丹「阿波座を上かみへ―・り新町を西へさがる」
⑨馬がはね上がって駆け出そうとする。枕草子3「馬の―・りさわぐなどもいとおそろしう見ゆれば」
⑩乗り移っていた神霊が離れて天へ帰る。平家物語1「山王―・らせ給ひけり」
⑪(血が頭に上る意から)気持がたかぶる。のぼせて落着きを失う。源氏物語賢木「御気―・りて、なほ悩ましうせさせ給ふ」。「―・っていたので何も覚えていない」
⑫《揚》(油を切って金網の上にあげられる意から)揚げ物が出来上がる。「てんぷらが―・った」
➋そのものの価値・資格・程度・勢力・品質などが高まる。
①価が高くなる。騰貴する。続日本紀32「天下の穀の価、騰あがり貴たかし」。「物価が―・る」「料金が―・る」
②地位が高くなる。源氏物語薄雲「大納言になりて、右大将かけ給へるを、いま一きは―・りなむに、何事もゆづりてむ」
③技能などが高度になる。上達する。狂言、薩摩守「最前ので乗り覚えたと見えて、乗りぶりが―・つた」。「腕が―・る」
④度が増す。また、勢いさかんになる。「気温が―・る」「血圧が―・る」「意気が―・る」「ピッチが―・る」「速度が―・る」
⑤仕上がり、出来映え、風采などが立派になる。玉塵抄15「人を染めて、色の―・つて行く事は、五色の絵の具…の色より過ぎたぞ」。「男ぶりが―・る」
⑥入学する。進級する。「学校に―・る」
➌そのものが極点にまで達する。完了する。
①仕上がる。出来上がる。日葡辞書「フシンガアガル」。浮世風呂2「まだ―・らぬか―・らぬかと、草稿を急ぐこと長湯の迎ひにさも似たり」。「仕事が―・る」「一題―・る」
②雨などがやむ。また、雨季が終わる。日葡辞書「ツユ、または、ナガシガアガル」。猿蓑「春雨の―・るや軒になく雀」
③双六すごろくなどで駒が最終の場所にはいる。また、トランプ・麻雀などで勝負がつく。鹿の巻筆「読よみのかるたは一枚のこり、―・られる事」
④経費がそれだけですむ。片がつく。滑稽本、続膝栗毛「下直げじきに―・ります」。「月千円で―・る」
⑤貴人の食事が終わる。日葡辞書「ゴゼンガアガル」
⑥お手上げになる。だめになる。浮世風呂2「五日も三日もなまけだすと細工は―・つたりさ」。「商売が―・ったりになる」
⑦(脈・乳など、続いていたものが)終わる。絶える。止まる。浄瑠璃、大経師昔暦「脈の―・つた死病も」。「バッテリーが―・る」
⑧魚などが死ぬ。また、草木が枯れる。色道大鏡「―・るといふ詞は魚の死してはたらかざるかたちをいふ」。「瓜の蔓が―・る」
➍そのものが高く人目につくようになる。
①高く揚げられる。「旗が―・る」
②名前が出る。名高くなる。有名になる。大鏡頼忠「かばかりの詩をつくりたらましかば、名の―・らむこともまさりなまし」。「候補者に―・る」
③声が発せられる。「大喚声が―・る」
④(事実・証拠などが)明るみに出る。歌舞伎、韓人漢文手管始「じたばたせまひ。たくみの手目は―・つてある」。「証拠が―・る」
⑤(効果・実績などが)はっきりあらわれる。よい結果が得られる。「学習効果が―・る」
➎そのものが高位のものに渡される。また、ことが高位のものに向かってなされる。
①神仏に供えられる。「灯明が―・る」
②貴人に献上される。日葡辞書「ウエサマエシンモッ(進物)ガアガッタ」
③(献上される意から、その物を貴人がとり入れる意に広がり、「飲食する」の尊敬語)めしあがる。狂言、饅頭食「上つ方のお菓子に―・りまらする饅頭は」。「お八つを―・る」
④年貢などが領主などの手に収められる。転じて、家賃・地代・収益などが、所有者・経営者などに収められる。「田畑から地代が―・る」
⑤領地・役目などを取り上げられる。日葡辞書「チギャウ、ヤク(役)アガッタ」
⑥犯人が召しとられる。検挙される。「犯人が―・る」
⑦屋敷などへ奉公に行く。浮世風呂2「この子が―・りましたお屋敷さまは」。「奉公に―・る」
⑧(「行く」「たずねる」の謙譲語)参上する。参る。浮世風呂2「藤間さんがお屋敷へお―・んなさいますから」。「早速店の者をお宅へ―・らせます」
➏(動詞の連用形に付いて)
①㋐その動作が済んだ意を示す。「刷り―・る」
㋑極点にまで達する意を示す。すっかり…する。「晴れ―・る」「震え―・る」
②その動作が激しくなる意を示す。落窪物語2「やがてただいひにいひ―・りて、車の床縛りをなん切りて侍りける」
③(本来は、なまいきに出過ぎて…するの意で、いやしめ、ののしる気持を添えるようになった。命令形で使うことが多い)…やがる。…くさる。浄瑠璃、女殺油地獄「ヤイかしましい。あたり隣もあるぞかし。よつぽどにほたへ―・れ」
◇広く一般には「上」。高くあがる意に「揚」、はっきり示される意で「挙」、値段があがる意には「騰」も使う。「花火が揚がる」「証拠が挙がる」「物価が騰る」
あ・ぐ【上ぐ・挙ぐ・揚ぐ】🔗⭐🔉
あ・ぐ【上ぐ・挙ぐ・揚ぐ】
〔他下二〕
⇒あげる(下一)
あげ‐あし【揚げ足・挙足】🔗⭐🔉
あげ‐あし【揚げ足・挙足】
①足をあげること。また、その足。
②一方の足を折り曲げ他方の足の上に乗せること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「御前近くも無遠慮に縁先に―して」
⇒揚げ足を取る
○揚げ足を取るあげあしをとる
(相手が蹴ろうとしてあげた足を取って逆に相手を倒す意から)相手の言いそこないや言葉じりにつけこんでなじったり、皮肉を言ったりする。
⇒あげ‐あし【揚げ足・挙足】
あげ‐うた【挙歌・上歌】🔗⭐🔉
あげ‐うた【挙歌・上歌】
①古代歌謡で、声を上げ高調子に歌われる歌。神代紀下「凡て此の贈答二首ふたうたを号なづけて―と曰ふ」
②能の構成部分の一つ。高い音域で始まる拍子に乗る謡。↔下歌さげうた
あげ‐く【挙句・揚句】🔗⭐🔉
あげ‐く【挙句・揚句】
①連歌・連句の最後の七・七の句。↔発句ほっく。
②転じて、おわり。結局。副詞的にも用いる。「さんざん振り回された―が、この結果だ」「考えに考えた―、転職した」
⇒あげく‐の‐はて【挙句の果て】
あげく‐の‐はて【挙句の果て】🔗⭐🔉
あげく‐の‐はて【挙句の果て】
挙句2を強めた言い方。最後の最後。とどのつまり。結局。
⇒あげ‐く【挙句・揚句】
あげ‐て【挙げて】🔗⭐🔉
あげ‐て【挙げて】
残らず。すべて。こぞって。「国を―賛成する」「―私に責任がある」
あげ‐また【挙股】🔗⭐🔉
あげ‐また【挙股】
(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」
あ・げる【上げる・挙げる・揚げる】🔗⭐🔉
あ・げる【上げる・挙げる・揚げる】
〔他下一〕[文]あ・ぐ(下二)
力や手を加えて、物の位置や状態や次元を高くする。
➊そのもの全体または部分の位置を高くする。
①上へやる。高い所に移動させる。丹後風土記逸文「大和べに風吹き―・げて」。竹取物語「燕はいかなる時にか子産むと知りて人をば―・ぐべき」。「棚に―・げる」
②上向きにする。「目を―・げる」
③空高く浮かぶようにする。「凧を―・げる」「花火を―・げる」
④高い位置に据え付ける。「棟を―・げる」
⑤陸上へ移す。平家物語11「―・げ置いたる船」。「おかに―・げる」
⑥下げていた髪を結い上げる。万葉集16「橘の寺の長屋に吾がゐねし童女放髪うないはなりは髪―・げつらむか」
⑦下に敷いてあるものを取りのける。「畳を―・げる」「布団を―・げる」
⑧吸い上げる。「切花が水を―・げる」
⑨(胃から口の方へ)もどす。吐く。「船に酔って―・げる」
⑩家の中に入らせる。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「はじめてのお方を同道申した。…一つ―・げます座敷があるか」
⑪《揚》芸者・遊女を(座敷へ)呼び寄せる。また、呼んで遊ぶ。西鶴織留1「丸屋の七左衛門方に太夫の吉野を―・げ置き」。「芸者を―・げて大騒ぎする」
⑫(人を)都へのぼらせる。上京させる。源氏物語玉鬘「とかく構へて、京へ―・げ奉りてむ」
⑬勢いよく馬を跳ねあがらせる。古今著聞集10「おとど力及ばで、あがり馬をひかれにけり。なか道くちをはづさせて―・げけり」
⑭(気を)たかぶらせる。栄華物語若枝「あないみじ。気け―・げさせ給ふな」
⑮(水位を高める意から自動詞的に使われて)潮がさす。「潮が―・げてくる」
⑯《揚》(金網にのせて油をきる意)熱した油の中へ入れて、調理する。「てんぷらを―・げる」
➋価値・資格・程度・勢いなどを高める。
①(「騰げる」とも書く)価を高くする。金額をふやす。「料金を―・げる」
②地位を高める。昇進させる。続日本紀10「冠位一階―・げ賜ふ事」
③(子女などを)寺子屋・学校などに入れる。浮世物語「寺に―・げて手ならひをさすれども」。「娘を大学に―・げる」
④技能などを高度にする。上達させる。日葡辞書「ガクモンナドノイロヲアグル」。「腕を―・げる」
⑤度を増す。また、勢いをさかんにする。勢いをつける。「ピッチを―・げる」「温度を―・げる」
⑥声量を大にする。高く発する。日葡辞書「コエヲアグル」
⑦顔だち・風采また評価などをよくする。「男ぶりを―・げる」「男を―・げる」
➌極点にまで至らせる。事を終わらせる。
①なしとげる。仕上げる。「この仕事は今夜中に―・げなければならない」
②育てあげる。今昔物語集9「その子を遂に―・げずして棄てつ」
③(赤子を)とりあげる。もうける。「二男一女を―・げる」
④経費をそれだけですませる。浮世床初「一分。ヱ。それで―・げるつもりかヱ」。「費用を安く―・げる」
⑤遊興や投資に金を全部使う。入れあげる。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「新地狂ひに身代―・げ、方々の借銭」
⑥《挙》全部出しつくす。「全力を―・げる」「国を―・げて祝う」
⑦撤去する。かたづける。玉塵抄14「食ひ果てて、食ひ残しの分けのあるを、婦が膳を―・げて」
➍高く人目につくようにする。広く知られるようにする。
①高く掲げ示す。平家物語2「天下に兵乱起つて、烽火を―・げたりければ」。「看板を―・げる」
②(実例・証拠などを)明確に表面にあらわす。また、(効果・実績などが)はっきりあらわれるようにする。「証拠を―・げる」「成果を―・げる」
③(名声などを)世に広める。平家物語6「日本一州に名を―・げ」
④取り立てて示す。平家物語1「大織冠・淡海公の御事は―・げて申すに及ばず」
⑤ほめたたえる。また、その地位や仕事に適した人として推挙する。雨月物語3「この玉河てふ川は国々にありて、いづれをよめる歌もその流れの清きを―・げしなるを思へば」。「委員には某君を―・げる」
⑥大勢の人を集め動かして事を起こす。十訓抄「義兵を―・げて、かの国へ向ひ給ひし時」
⑦(行事や儀式などを)とり行う。「式を―・げる」
➎高位または有力なものの所に到達するようにする。
①神仏に供える。奉納する。栄華物語鶴林「関白殿、日ごとに法華経一部、阿弥陀経あまた…を―・げさせ給ひて」。「お賽銭さいせんを―・げる」
②身分の高い者にさし出す。献上する。景行紀「すなはち朝庭みかどに進上あげたまふ」
③返上する。辞任する。玉塵抄2「周公の摂政を―・げて、山東の東国へひつこまれたぞ」
④(本来は「与える」「やる」の相手を敬った言い方)物を渡す場合の丁寧表現。「君に―・げよう」
⑤屋敷などに奉公にやる。浮世風呂2「六ツの秋、御奉公に―・げました」
⑥参上させる。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「ずいぶん申し触らしまして、横着な借手を―・げませう」
⑦(官が領地・役目などを)召し上げる。没収する。諏訪の本地「彼が知行の所領を―・げて、我等半分づつ知行せん」
⑧物をむりに取り上げる。まきあげる。浮世風呂前「トレ手拭を見せや。…あれが所から―・げて来やアがつて」
⑨賊などを召しとる。検挙する。「犯人を―・げる」
➏①(動詞の連用形に付いて)その動作を完了させる意を示す。古今和歌集六帖2「わが門の早稲田わさだもいまだ刈り―・げぬに」。「一刻も早くし―・げてほしい」「勤め―・げる」
②(「申す」「頼む」「願う」などの動詞の連用形に付いて)その動作の対象をあがめ敬う意を添える。狂言、三人夫「汝らが名を申し―・げい」。「お名前は存じ―・げております」
③(動詞連用形に助詞「て(で)」の付いた形に添えて)その動作を他にしてやる意の丁寧表現。梅暦「どこぞへ私わちきがあづけられて、お金をこしらへて―・げるよ」。「教えて―・げる」「本を読んで―・げる」
◇広く一般には「上」。はっきり示す意で「挙」、高くあげる・陸上に移すなどの意では「揚」も使う。
⇒上げたり下げたり
きょ【挙】🔗⭐🔉
きょ【挙】
事をおこすこと。くわだてること。行動。ふるまい。「反撃の―に出る」
きょ‐か【挙火】‥クワ🔗⭐🔉
きょ‐か【挙火】‥クワ
①(炊事の火を燃やす意から)生計をたてること。
②昔、朝鮮で国王への直訴の一法。首都漢城の南山で烽火のろしを挙げるもの。
きょ‐か【挙家】🔗⭐🔉
きょ‐か【挙家】
家内残らず。全家。「―離村」
きょ‐ぐう【挙隅】🔗⭐🔉
きょ‐ぐう【挙隅】
[論語述而「子曰わく、憤せざれば啓せず、悱ひせざれば発せず、一隅を挙げて三隅を以て反せざれば、則ち復ふたたびせざる也」]孔子の教育法。一部を挙げて全体を分からせること。挙一反三。
⇒きょぐう‐ほう【挙隅法】
きょぐう‐ほう【挙隅法】‥ハフ🔗⭐🔉
きょぐう‐ほう【挙隅法】‥ハフ
修辞法の一つ。一部を示して全体を知らしめる技法。挙隅。
⇒きょ‐ぐう【挙隅】
きょ‐こう【挙行】‥カウ🔗⭐🔉
きょ‐こう【挙行】‥カウ
儀式や行事などを行うこと。「式典を―する」
⇒きょこうち‐ほう【挙行地法】
きょこうち‐ほう【挙行地法】‥カウ‥ハフ🔗⭐🔉
きょこうち‐ほう【挙行地法】‥カウ‥ハフ
行為地法の一種。婚姻挙行地の法律。国際私法上、婚姻の形式的成立要件の準拠法として認められる。
⇒きょ‐こう【挙行】
きょ‐こく【挙国】🔗⭐🔉
きょ‐こく【挙国】
(「国を挙あげて」の意)一国全体。国民全体。
⇒きょこく‐いっち【挙国一致】
きょこく‐いっち【挙国一致】🔗⭐🔉
きょこく‐いっち【挙国一致】
国民全体が一致して同じ態度をとること。「―内閣」
⇒きょ‐こく【挙国】
きょ‐ざ【挙座】🔗⭐🔉
きょ‐ざ【挙座】
その場にいる者みな。満座。
きょ‐し【挙子】🔗⭐🔉
きょ‐し【挙子】
科挙に応ずる人。
きょ‐し【挙止】🔗⭐🔉
きょ‐し【挙止】
立ち居ふるまい。挙動。「―進退」
きょ‐しき【挙式】🔗⭐🔉
きょ‐しき【挙式】
式、特に結婚式をあげること。「神前で―する」
きょ‐しゅ【挙手】🔗⭐🔉
きょ‐しゅ【挙手】
手をあげること。「採決は―でする」
⇒きょしゅ‐ちゅうもく‐の‐れい【挙手注目の礼】
きょしゅ‐ちゅうもく‐の‐れい【挙手注目の礼】🔗⭐🔉
きょしゅ‐ちゅうもく‐の‐れい【挙手注目の礼】
右手を額の横に挙げ、眼を相手の眼に注いでする敬礼。挙手の礼。
⇒きょ‐しゅ【挙手】
きょ‐しょう【挙証】🔗⭐🔉
きょ‐しょう【挙証】
証拠をあげ示すこと。立証。
⇒きょしょう‐せきにん【挙証責任】
きょ‐しょう【挙踵】🔗⭐🔉
きょ‐しょう【挙踵】
①足をつまだてること。
②足をつまだて伸び上がって人を待ち望むこと。
きょ‐じょう【挙状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
きょ‐じょう【挙状】‥ジヤウ
(コジョウとも)
①推薦の書状。吹挙すいきょ状。
②鎌倉・室町時代、訴訟しようとする身分の低い者に、所属の長の与えた添書。
きょ‐じょう【挙場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
きょ‐じょう【挙場】‥ヂヤウ
①中国で、科挙の試験場。
②その場所にいるものすべて。満場。挙座。
きょしょう‐せきにん【挙証責任】🔗⭐🔉
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
〔法〕訴訟上、ある事実の存否が確定されない場合、そのことによって一方の当事者が受ける不利益な負担をいう。民事訴訟では事項により原告と被告とに分配され、刑事訴訟では原則として検察官が負う。証明責任。立証責任。
⇒きょ‐しょう【挙証】
きょ・す【挙す】🔗⭐🔉
きょ・す【挙す】
〔他サ変〕
人を推挙して、上の地位にあげる。平家物語3「御弟子覚成僧都、法印に―・せらる」
きょ‐せい【挙世】🔗⭐🔉
きょ‐せい【挙世】
世間の人残らず。世の中じゅう。
きょ‐ぞく【挙族】🔗⭐🔉
きょ‐ぞく【挙族】
一族のこらず。一門全体。
○挙措を失うきょそをうしなう🔗⭐🔉
○挙措を失うきょそをうしなう
どうしていいかわからず、とり乱す。
⇒きょ‐そ【挙措】
きょ‐そん【居村】
自分の居住している村。いむら。
きょ‐そん【踞蹲】
しゃがむこと。蹲踞。
ぎょ‐そん【漁村】
おもに漁業を生業としている村。海辺の村。
きょ‐た【許多】
数の多いこと。多数。あまた。
きょ‐たい【巨体】
きわめて大きなからだ。「―をもてあます」
きょ‐だい【巨大】
きわめて大きいこと。「―な組織」「―化」
⇒きょだい‐かがく【巨大科学】
⇒きょだい‐じしん【巨大地震】
⇒きょだい‐ぶんし【巨大分子】
ぎょ‐たい【魚袋】
束帯着用の時の装飾具。節会せちえ・大嘗会御禊だいじょうえごけいなどの儀に際し、右腰に下げた。初めは袋形、後世は長方形の箱状の木を白鮫の皮で包み、金製または銀製の魚の形を表に六つ裏に一つ付け、紫または紺の組糸をつける。金魚袋(公卿の料)・銀魚袋(殿上人の料)の2種がある。唐代の魚符に模したもの。大鏡師輔「つけさせ給ふべき―のそこなはれたりければ」
魚袋
 ぎょ‐たい【御体】
⇒ごたい
ぎょ‐だい【御題】
①天子親筆の題字。
②天子選定の詩歌・文章の題。勅題。
きょだい‐かがく【巨大科学】‥クワ‥
多数の研究者と巨額の資金を組織的に投入して開発を進める科学技術の対象。宇宙開発・原子力開発・核融合実験など。ビッグ‐サイエンス。
⇒きょ‐だい【巨大】
きょだい‐じしん【巨大地震】‥ヂ‥
沈み込みに伴い海洋プレート上面と大陸プレート下面との間のずれにより起こるマグニチュード8程度以上の地震。南海道地震が一例。
⇒きょ‐だい【巨大】
きょたい‐とし【巨帯都市】
(→)メガロポリスに同じ。
きょだい‐ぶんし【巨大分子】
(→)高分子に同じ。
⇒きょ‐だい【巨大】
きよたき【清滝】
京都市右京区嵯峨、愛宕山東麓を南下して保津川に注ぐ清滝川沿いの地。紅葉の名所。
清滝
撮影:的場 啓
ぎょ‐たい【御体】
⇒ごたい
ぎょ‐だい【御題】
①天子親筆の題字。
②天子選定の詩歌・文章の題。勅題。
きょだい‐かがく【巨大科学】‥クワ‥
多数の研究者と巨額の資金を組織的に投入して開発を進める科学技術の対象。宇宙開発・原子力開発・核融合実験など。ビッグ‐サイエンス。
⇒きょ‐だい【巨大】
きょだい‐じしん【巨大地震】‥ヂ‥
沈み込みに伴い海洋プレート上面と大陸プレート下面との間のずれにより起こるマグニチュード8程度以上の地震。南海道地震が一例。
⇒きょ‐だい【巨大】
きょたい‐とし【巨帯都市】
(→)メガロポリスに同じ。
きょだい‐ぶんし【巨大分子】
(→)高分子に同じ。
⇒きょ‐だい【巨大】
きよたき【清滝】
京都市右京区嵯峨、愛宕山東麓を南下して保津川に注ぐ清滝川沿いの地。紅葉の名所。
清滝
撮影:的場 啓
 きょ‐たく【居宅】
いつも住んでいる家。
きょ‐たく【虚託】
いつわりかこつけること。かこつけ。
きょ‐だく【許諾】
要求を聞き入れ、許すこと。承諾。
ぎょ‐たく【魚拓】
魚の拓本。魚の表面に和紙を置き、魚の形を摺り写したもの。
ぎょ‐たく【魚柝】
(→)木魚もくぎょに同じ。
きょ‐たつ【挙達】
①推挙を得て栄達すること。
②とりあげて進達すること。
きょ‐だつ【虚脱】
①心臓が衰弱して体力がなくなり、瀕死の状態となること。
②気力がぬけて、ぼんやりと何も手につかない状態。「―感」
きょ‐たん【袪痰・去痰】
気管または気管支にたまっている喀痰を除去すること。
⇒きょたん‐やく【袪痰薬】
きょ‐たん【虚誕】
事実無根のことをおおげさに言うこと。うそ。でたらめ。
きょ‐だん【巨弾】
大きな砲弾や爆弾。痛烈できわめて効果的な非難や手段のたとえ。
きょ‐だん【虚談】
事実でない話。つくりばなし。虚説。
ぎょ‐たん【魚探】
魚群探知機の略。
きょたん‐やく【袪痰薬】
袪痰に用いる薬剤。桔梗根・セネガ根・吐根・アンモニアウイキョウ精など。
⇒きょ‐たん【袪痰・去痰】
きょ‐ちゅう【居中】
両方の中間に立つこと。また、中間にあって偏しないこと。
⇒きょちゅう‐ちょうてい【居中調停】
ぎょ‐ちゅう【魚虫】
魚と虫。虫魚。古今著聞集20「禽獣―」
ぎょ‐ちゅう【御注・御註】
天子が自ら書籍に注釈を加えること。また、その注釈。「―孝経」
きょちゅう‐ちょうてい【居中調停】‥テウ‥
(mediation)第三国が国際紛争当事国の間に立って、平和に解決するようにとりもつこと。仲介。
⇒きょ‐ちゅう【居中】
きょ‐ちょう【挙朝】‥テウ
朝廷の人残らず。朝廷全体。
きょ‐ちょう【秬鬯】‥チヤウ
黒黍きび(秬)と香草(鬯)とを合わせて造った酒。
ぎょ‐ちょう【魚鳥】‥テウ
魚と鳥。
⇒ぎょちょう‐どめ【魚鳥留め】
ぎょ‐ちょう【漁釣】‥テウ
魚を釣ること。魚つり。
ぎょちょう‐どめ【魚鳥留め】‥テウ‥
①魚鳥を捕ることや食べることを禁止すること。
②精進のため、喪中や忌日に魚鳥類を家の中にいれないこと。誹風柳多留147「精進の看板を出す―」
⇒ぎょ‐ちょう【魚鳥】
ギヨチン【guillotine フランス】
⇒ギロチン
きょっ‐かい【曲解】キヨク‥
相手の言動・心中を、素直でなくわざと曲げて解釈すること。「人の言うことを―する」
ぎょっ‐かい【玉階】ギヨク‥
宮殿の階段。御階。みはし。
きょっ‐かく【極核】キヨク‥
⇒きょくかく
きょっ‐かん【極官】キヨククワン
⇒ごっかん
きょっ‐かん【極冠】キヨククワン
火星の両極地方に当たる部分に認められる白い箇所。一部は氷だが、大半は二酸化炭素の氷(ドライアイス)でできていると考えられる。
きょっ‐かん【極諫】キヨク‥
ことばを尽くしていさめること。強くいさめること。
ぎょっ‐かん【玉冠】ギヨククワン
玉で飾った冠。→礼冠らいかん
ぎょっ‐かん【玉簡・玉翰】ギヨク‥
相手に敬意を表してその手紙をいう語。
きょっ‐き【旭暉】キヨク‥
あさひの光。旭光。
きょっ‐き【旭旗】キヨク‥
日の丸の旗。旭日旗。日章旗。
ぎょっ‐き【玉机・玉几】ギヨク‥
①玉で飾った机。机の美称。
②他人の机の尊敬語。玉案。
ぎょっ‐き【玉肌】ギヨク‥
玉のような美しいはだ。たまのはだ。玉膚。
ぎょっ‐き【玉器】ギヨク‥
玉で作った器物。
きょっ‐きゅう【曲球】キヨクキウ
野球で、カーブのこと。
きょっ‐けい【極刑】キヨク‥
この上なく重い刑罰。死刑。「―に処する」
ぎょっ‐けい【玉笄】ギヨク‥
玉で作ったかんざし。
ぎょっ‐けい【玉磬】ギヨク‥
玉で作った磬。
きょっけい‐どうぶつ【曲形動物】キヨク‥
(→)内肛動物の旧名。
ぎょっ‐けつ【玉玦】ギヨク‥
環の一部分が欠けたかたちの佩玉はいぎょく。
ぎょっ‐けつ【玉闕】ギヨク‥
玉で飾った美しい宮殿。玉殿。
きょっ‐けん【極圏】キヨク‥
地球の南北両極からそれぞれ23度27分の所にある緯線(南極圏・北極圏)。また、この両極圏から高緯度の地域。
ぎょっ‐こ【玉壺】ギヨク‥
玉で作ったつぼ。美しいつぼ。
きょっ‐こう【旭光】キヨククワウ
朝日の光。
きょっ‐こう【曲行】キヨクカウ
①曲がり曲がって行くこと。
②不正な行い。
きょっ‐こう【曲肱】キヨク‥
(「肱」は、ひじ)ひじを曲げること。特に、ひじを曲げて枕がわりにすること。ひじ枕をすること。
⇒きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】
きょっ‐こう【極光】キヨククワウ
(→)オーロラに同じ。
ぎょっ‐こう【玉稿】ギヨクカウ
他人の草稿の尊敬語。御原稿。
きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】キヨク‥
[論語述而「疏食そしを飯くらい水を飲み、肱を曲げて之を枕とす、楽しみまた其の中に在り」]貧しい生活の中にも楽しみがあるということ。簡素な生活の楽しさ。
⇒きょっ‐こう【曲肱】
ぎょっ‐こつ【玉骨】ギヨク‥
①玉のような骨。高潔な風姿をいう。また、梅の幹枝にたとえ、梅樹の異称。
②貴人または美人の死骸・骨。太平記21「―はたとひ南山の苔に埋もるとも」
ぎょっ‐と
〔副〕
不意に予期しない物事に出合って驚きや恐怖を感じ緊張するさま。「一瞬―なる」「―して立ちどまる」
きよつね【清経】
能。世阿弥作の修羅物。妻を都に残して合戦におもむいた平清経が豊前国柳浦で入水したことを脚色。
きょ‐てい【居邸】
すまいするやしき。居宅。
ぎょ‐てい【魚梯】
河川に滝・ダムなどがある場合、魚類を遡上させるために河の一部に設けられた緩傾斜の水路、または幾段にもなった水路のこと。魚道の一種。
ぎょ‐てい【漁艇】
①漁猟に使用する小舟。
②大型漁船に積んで、漁場で下ろして使う小舟。
きょ‐てん【拠点】
活動のよりどころになる所。「戦略上の―」「生産―」
きょ‐でん【虚伝】
根もないうわさ・言いつたえ。
ぎょ‐でん【魚田】
(魚の田楽の意)魚を串に刺し味噌をぬって焼いた料理。
ぎょ‐と【魚肚】
チョウザメ・イシモチなどの鰾うきぶくろを乾燥した食品。中国料理で用いる。
きょと・い
〔形〕
(キョウトイの転)
①はなはだしい。東海道中膝栗毛3「お江戸は―・いはんじやうなとこぢやわいの」
②恐ろしい。ひどい。無事志有意「滅相な―・いこといはんす」
きょ‐とう【去冬】
去年の冬。
きょ‐とう【巨盗】‥タウ
おおどろぼう。巨賊。大盗。
きょ‐とう【巨頭】
①大きなあたま。
②ある方面や団体でのおもだった人。大立者。「―会談」
きょ‐とう【巨濤】‥タウ
大きな波。大浪。
きょ‐とう【挙党】‥タウ
一つの政党全体。「―一致」
きょ‐どう【挙動】
①立ち居ふるまい。人の動作や行為。しわざ。様子。挙止。
②体操で、単一な個々の動作。
⇒きょどう‐はん【挙動犯】
⇒きょどう‐ふしん【挙動不審】
ぎょ‐とう【魚灯】
魚灯油の略。傾城買四十八手「行灯あんどうは―をとぼす故、紙へ付けて吸ひつける」
⇒ぎょとう‐ゆ【魚灯油】
ぎょ‐とう【魚頭】
魚の頭。狂言、鱸庖丁「一の刀にて―を継ぎ」
ぎょ‐とう【漁灯】
漁業に用いる灯火。いさり火。
ぎょ‐どう【魚道】‥ダウ
①魚群の回遊経路。魚種・深浅・潮流などによってほぼ一定。
②河川にダムや堰を築造する時、魚類の通路として設ける水路。魚梯ぎょていが主なもの。
③(→)「ぎょうどう(凝当)」に同じ。〈文明本節用集〉
きょどう‐はん【挙動犯】
犯罪の構成要件上、一定の身体的動静のみで足り、外部的結果の発生を必要としない犯罪。偽証罪・公然猥褻わいせつ罪の類。↔結果犯。
⇒きょ‐どう【挙動】
きょどう‐ふしん【挙動不審】
外での行動や様子があやしいこと。
⇒きょ‐どう【挙動】
ぎょとう‐ゆ【魚灯油】
イワシ・ニシンなどの脂肪から採った、臭気の強い下等の灯油。
⇒ぎょ‐とう【魚灯】
きょと‐きょと
不安や恐れなどのため落着きなく視線を走らせるさま。きょろきょろ。「―見回す」
きよ‐どころ【清所】
御厨子所みずしどころの異称。貴人の台所にもいう。おきよどころ。
きょとん
事の意外さに事態がとっさに理解できず、驚きと当惑でただ目を見開いているさま。「急にどなられて―とする」
ぎょ‐にく【魚肉】
①食用としての魚の肉。
②魚と獣肉。
⇒ぎょにく‐ソーセージ【魚肉ソーセージ】
⇒魚肉となる
ぎょにく‐ソーセージ【魚肉ソーセージ】
魚肉を使って畜肉ソーセージに似せて作る練り製品。フィッシュ‐ソーセージ。
⇒ぎょ‐にく【魚肉】
きょ‐たく【居宅】
いつも住んでいる家。
きょ‐たく【虚託】
いつわりかこつけること。かこつけ。
きょ‐だく【許諾】
要求を聞き入れ、許すこと。承諾。
ぎょ‐たく【魚拓】
魚の拓本。魚の表面に和紙を置き、魚の形を摺り写したもの。
ぎょ‐たく【魚柝】
(→)木魚もくぎょに同じ。
きょ‐たつ【挙達】
①推挙を得て栄達すること。
②とりあげて進達すること。
きょ‐だつ【虚脱】
①心臓が衰弱して体力がなくなり、瀕死の状態となること。
②気力がぬけて、ぼんやりと何も手につかない状態。「―感」
きょ‐たん【袪痰・去痰】
気管または気管支にたまっている喀痰を除去すること。
⇒きょたん‐やく【袪痰薬】
きょ‐たん【虚誕】
事実無根のことをおおげさに言うこと。うそ。でたらめ。
きょ‐だん【巨弾】
大きな砲弾や爆弾。痛烈できわめて効果的な非難や手段のたとえ。
きょ‐だん【虚談】
事実でない話。つくりばなし。虚説。
ぎょ‐たん【魚探】
魚群探知機の略。
きょたん‐やく【袪痰薬】
袪痰に用いる薬剤。桔梗根・セネガ根・吐根・アンモニアウイキョウ精など。
⇒きょ‐たん【袪痰・去痰】
きょ‐ちゅう【居中】
両方の中間に立つこと。また、中間にあって偏しないこと。
⇒きょちゅう‐ちょうてい【居中調停】
ぎょ‐ちゅう【魚虫】
魚と虫。虫魚。古今著聞集20「禽獣―」
ぎょ‐ちゅう【御注・御註】
天子が自ら書籍に注釈を加えること。また、その注釈。「―孝経」
きょちゅう‐ちょうてい【居中調停】‥テウ‥
(mediation)第三国が国際紛争当事国の間に立って、平和に解決するようにとりもつこと。仲介。
⇒きょ‐ちゅう【居中】
きょ‐ちょう【挙朝】‥テウ
朝廷の人残らず。朝廷全体。
きょ‐ちょう【秬鬯】‥チヤウ
黒黍きび(秬)と香草(鬯)とを合わせて造った酒。
ぎょ‐ちょう【魚鳥】‥テウ
魚と鳥。
⇒ぎょちょう‐どめ【魚鳥留め】
ぎょ‐ちょう【漁釣】‥テウ
魚を釣ること。魚つり。
ぎょちょう‐どめ【魚鳥留め】‥テウ‥
①魚鳥を捕ることや食べることを禁止すること。
②精進のため、喪中や忌日に魚鳥類を家の中にいれないこと。誹風柳多留147「精進の看板を出す―」
⇒ぎょ‐ちょう【魚鳥】
ギヨチン【guillotine フランス】
⇒ギロチン
きょっ‐かい【曲解】キヨク‥
相手の言動・心中を、素直でなくわざと曲げて解釈すること。「人の言うことを―する」
ぎょっ‐かい【玉階】ギヨク‥
宮殿の階段。御階。みはし。
きょっ‐かく【極核】キヨク‥
⇒きょくかく
きょっ‐かん【極官】キヨククワン
⇒ごっかん
きょっ‐かん【極冠】キヨククワン
火星の両極地方に当たる部分に認められる白い箇所。一部は氷だが、大半は二酸化炭素の氷(ドライアイス)でできていると考えられる。
きょっ‐かん【極諫】キヨク‥
ことばを尽くしていさめること。強くいさめること。
ぎょっ‐かん【玉冠】ギヨククワン
玉で飾った冠。→礼冠らいかん
ぎょっ‐かん【玉簡・玉翰】ギヨク‥
相手に敬意を表してその手紙をいう語。
きょっ‐き【旭暉】キヨク‥
あさひの光。旭光。
きょっ‐き【旭旗】キヨク‥
日の丸の旗。旭日旗。日章旗。
ぎょっ‐き【玉机・玉几】ギヨク‥
①玉で飾った机。机の美称。
②他人の机の尊敬語。玉案。
ぎょっ‐き【玉肌】ギヨク‥
玉のような美しいはだ。たまのはだ。玉膚。
ぎょっ‐き【玉器】ギヨク‥
玉で作った器物。
きょっ‐きゅう【曲球】キヨクキウ
野球で、カーブのこと。
きょっ‐けい【極刑】キヨク‥
この上なく重い刑罰。死刑。「―に処する」
ぎょっ‐けい【玉笄】ギヨク‥
玉で作ったかんざし。
ぎょっ‐けい【玉磬】ギヨク‥
玉で作った磬。
きょっけい‐どうぶつ【曲形動物】キヨク‥
(→)内肛動物の旧名。
ぎょっ‐けつ【玉玦】ギヨク‥
環の一部分が欠けたかたちの佩玉はいぎょく。
ぎょっ‐けつ【玉闕】ギヨク‥
玉で飾った美しい宮殿。玉殿。
きょっ‐けん【極圏】キヨク‥
地球の南北両極からそれぞれ23度27分の所にある緯線(南極圏・北極圏)。また、この両極圏から高緯度の地域。
ぎょっ‐こ【玉壺】ギヨク‥
玉で作ったつぼ。美しいつぼ。
きょっ‐こう【旭光】キヨククワウ
朝日の光。
きょっ‐こう【曲行】キヨクカウ
①曲がり曲がって行くこと。
②不正な行い。
きょっ‐こう【曲肱】キヨク‥
(「肱」は、ひじ)ひじを曲げること。特に、ひじを曲げて枕がわりにすること。ひじ枕をすること。
⇒きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】
きょっ‐こう【極光】キヨククワウ
(→)オーロラに同じ。
ぎょっ‐こう【玉稿】ギヨクカウ
他人の草稿の尊敬語。御原稿。
きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】キヨク‥
[論語述而「疏食そしを飯くらい水を飲み、肱を曲げて之を枕とす、楽しみまた其の中に在り」]貧しい生活の中にも楽しみがあるということ。簡素な生活の楽しさ。
⇒きょっ‐こう【曲肱】
ぎょっ‐こつ【玉骨】ギヨク‥
①玉のような骨。高潔な風姿をいう。また、梅の幹枝にたとえ、梅樹の異称。
②貴人または美人の死骸・骨。太平記21「―はたとひ南山の苔に埋もるとも」
ぎょっ‐と
〔副〕
不意に予期しない物事に出合って驚きや恐怖を感じ緊張するさま。「一瞬―なる」「―して立ちどまる」
きよつね【清経】
能。世阿弥作の修羅物。妻を都に残して合戦におもむいた平清経が豊前国柳浦で入水したことを脚色。
きょ‐てい【居邸】
すまいするやしき。居宅。
ぎょ‐てい【魚梯】
河川に滝・ダムなどがある場合、魚類を遡上させるために河の一部に設けられた緩傾斜の水路、または幾段にもなった水路のこと。魚道の一種。
ぎょ‐てい【漁艇】
①漁猟に使用する小舟。
②大型漁船に積んで、漁場で下ろして使う小舟。
きょ‐てん【拠点】
活動のよりどころになる所。「戦略上の―」「生産―」
きょ‐でん【虚伝】
根もないうわさ・言いつたえ。
ぎょ‐でん【魚田】
(魚の田楽の意)魚を串に刺し味噌をぬって焼いた料理。
ぎょ‐と【魚肚】
チョウザメ・イシモチなどの鰾うきぶくろを乾燥した食品。中国料理で用いる。
きょと・い
〔形〕
(キョウトイの転)
①はなはだしい。東海道中膝栗毛3「お江戸は―・いはんじやうなとこぢやわいの」
②恐ろしい。ひどい。無事志有意「滅相な―・いこといはんす」
きょ‐とう【去冬】
去年の冬。
きょ‐とう【巨盗】‥タウ
おおどろぼう。巨賊。大盗。
きょ‐とう【巨頭】
①大きなあたま。
②ある方面や団体でのおもだった人。大立者。「―会談」
きょ‐とう【巨濤】‥タウ
大きな波。大浪。
きょ‐とう【挙党】‥タウ
一つの政党全体。「―一致」
きょ‐どう【挙動】
①立ち居ふるまい。人の動作や行為。しわざ。様子。挙止。
②体操で、単一な個々の動作。
⇒きょどう‐はん【挙動犯】
⇒きょどう‐ふしん【挙動不審】
ぎょ‐とう【魚灯】
魚灯油の略。傾城買四十八手「行灯あんどうは―をとぼす故、紙へ付けて吸ひつける」
⇒ぎょとう‐ゆ【魚灯油】
ぎょ‐とう【魚頭】
魚の頭。狂言、鱸庖丁「一の刀にて―を継ぎ」
ぎょ‐とう【漁灯】
漁業に用いる灯火。いさり火。
ぎょ‐どう【魚道】‥ダウ
①魚群の回遊経路。魚種・深浅・潮流などによってほぼ一定。
②河川にダムや堰を築造する時、魚類の通路として設ける水路。魚梯ぎょていが主なもの。
③(→)「ぎょうどう(凝当)」に同じ。〈文明本節用集〉
きょどう‐はん【挙動犯】
犯罪の構成要件上、一定の身体的動静のみで足り、外部的結果の発生を必要としない犯罪。偽証罪・公然猥褻わいせつ罪の類。↔結果犯。
⇒きょ‐どう【挙動】
きょどう‐ふしん【挙動不審】
外での行動や様子があやしいこと。
⇒きょ‐どう【挙動】
ぎょとう‐ゆ【魚灯油】
イワシ・ニシンなどの脂肪から採った、臭気の強い下等の灯油。
⇒ぎょ‐とう【魚灯】
きょと‐きょと
不安や恐れなどのため落着きなく視線を走らせるさま。きょろきょろ。「―見回す」
きよ‐どころ【清所】
御厨子所みずしどころの異称。貴人の台所にもいう。おきよどころ。
きょとん
事の意外さに事態がとっさに理解できず、驚きと当惑でただ目を見開いているさま。「急にどなられて―とする」
ぎょ‐にく【魚肉】
①食用としての魚の肉。
②魚と獣肉。
⇒ぎょにく‐ソーセージ【魚肉ソーセージ】
⇒魚肉となる
ぎょにく‐ソーセージ【魚肉ソーセージ】
魚肉を使って畜肉ソーセージに似せて作る練り製品。フィッシュ‐ソーセージ。
⇒ぎょ‐にく【魚肉】
 ぎょ‐たい【御体】
⇒ごたい
ぎょ‐だい【御題】
①天子親筆の題字。
②天子選定の詩歌・文章の題。勅題。
きょだい‐かがく【巨大科学】‥クワ‥
多数の研究者と巨額の資金を組織的に投入して開発を進める科学技術の対象。宇宙開発・原子力開発・核融合実験など。ビッグ‐サイエンス。
⇒きょ‐だい【巨大】
きょだい‐じしん【巨大地震】‥ヂ‥
沈み込みに伴い海洋プレート上面と大陸プレート下面との間のずれにより起こるマグニチュード8程度以上の地震。南海道地震が一例。
⇒きょ‐だい【巨大】
きょたい‐とし【巨帯都市】
(→)メガロポリスに同じ。
きょだい‐ぶんし【巨大分子】
(→)高分子に同じ。
⇒きょ‐だい【巨大】
きよたき【清滝】
京都市右京区嵯峨、愛宕山東麓を南下して保津川に注ぐ清滝川沿いの地。紅葉の名所。
清滝
撮影:的場 啓
ぎょ‐たい【御体】
⇒ごたい
ぎょ‐だい【御題】
①天子親筆の題字。
②天子選定の詩歌・文章の題。勅題。
きょだい‐かがく【巨大科学】‥クワ‥
多数の研究者と巨額の資金を組織的に投入して開発を進める科学技術の対象。宇宙開発・原子力開発・核融合実験など。ビッグ‐サイエンス。
⇒きょ‐だい【巨大】
きょだい‐じしん【巨大地震】‥ヂ‥
沈み込みに伴い海洋プレート上面と大陸プレート下面との間のずれにより起こるマグニチュード8程度以上の地震。南海道地震が一例。
⇒きょ‐だい【巨大】
きょたい‐とし【巨帯都市】
(→)メガロポリスに同じ。
きょだい‐ぶんし【巨大分子】
(→)高分子に同じ。
⇒きょ‐だい【巨大】
きよたき【清滝】
京都市右京区嵯峨、愛宕山東麓を南下して保津川に注ぐ清滝川沿いの地。紅葉の名所。
清滝
撮影:的場 啓
 きょ‐たく【居宅】
いつも住んでいる家。
きょ‐たく【虚託】
いつわりかこつけること。かこつけ。
きょ‐だく【許諾】
要求を聞き入れ、許すこと。承諾。
ぎょ‐たく【魚拓】
魚の拓本。魚の表面に和紙を置き、魚の形を摺り写したもの。
ぎょ‐たく【魚柝】
(→)木魚もくぎょに同じ。
きょ‐たつ【挙達】
①推挙を得て栄達すること。
②とりあげて進達すること。
きょ‐だつ【虚脱】
①心臓が衰弱して体力がなくなり、瀕死の状態となること。
②気力がぬけて、ぼんやりと何も手につかない状態。「―感」
きょ‐たん【袪痰・去痰】
気管または気管支にたまっている喀痰を除去すること。
⇒きょたん‐やく【袪痰薬】
きょ‐たん【虚誕】
事実無根のことをおおげさに言うこと。うそ。でたらめ。
きょ‐だん【巨弾】
大きな砲弾や爆弾。痛烈できわめて効果的な非難や手段のたとえ。
きょ‐だん【虚談】
事実でない話。つくりばなし。虚説。
ぎょ‐たん【魚探】
魚群探知機の略。
きょたん‐やく【袪痰薬】
袪痰に用いる薬剤。桔梗根・セネガ根・吐根・アンモニアウイキョウ精など。
⇒きょ‐たん【袪痰・去痰】
きょ‐ちゅう【居中】
両方の中間に立つこと。また、中間にあって偏しないこと。
⇒きょちゅう‐ちょうてい【居中調停】
ぎょ‐ちゅう【魚虫】
魚と虫。虫魚。古今著聞集20「禽獣―」
ぎょ‐ちゅう【御注・御註】
天子が自ら書籍に注釈を加えること。また、その注釈。「―孝経」
きょちゅう‐ちょうてい【居中調停】‥テウ‥
(mediation)第三国が国際紛争当事国の間に立って、平和に解決するようにとりもつこと。仲介。
⇒きょ‐ちゅう【居中】
きょ‐ちょう【挙朝】‥テウ
朝廷の人残らず。朝廷全体。
きょ‐ちょう【秬鬯】‥チヤウ
黒黍きび(秬)と香草(鬯)とを合わせて造った酒。
ぎょ‐ちょう【魚鳥】‥テウ
魚と鳥。
⇒ぎょちょう‐どめ【魚鳥留め】
ぎょ‐ちょう【漁釣】‥テウ
魚を釣ること。魚つり。
ぎょちょう‐どめ【魚鳥留め】‥テウ‥
①魚鳥を捕ることや食べることを禁止すること。
②精進のため、喪中や忌日に魚鳥類を家の中にいれないこと。誹風柳多留147「精進の看板を出す―」
⇒ぎょ‐ちょう【魚鳥】
ギヨチン【guillotine フランス】
⇒ギロチン
きょっ‐かい【曲解】キヨク‥
相手の言動・心中を、素直でなくわざと曲げて解釈すること。「人の言うことを―する」
ぎょっ‐かい【玉階】ギヨク‥
宮殿の階段。御階。みはし。
きょっ‐かく【極核】キヨク‥
⇒きょくかく
きょっ‐かん【極官】キヨククワン
⇒ごっかん
きょっ‐かん【極冠】キヨククワン
火星の両極地方に当たる部分に認められる白い箇所。一部は氷だが、大半は二酸化炭素の氷(ドライアイス)でできていると考えられる。
きょっ‐かん【極諫】キヨク‥
ことばを尽くしていさめること。強くいさめること。
ぎょっ‐かん【玉冠】ギヨククワン
玉で飾った冠。→礼冠らいかん
ぎょっ‐かん【玉簡・玉翰】ギヨク‥
相手に敬意を表してその手紙をいう語。
きょっ‐き【旭暉】キヨク‥
あさひの光。旭光。
きょっ‐き【旭旗】キヨク‥
日の丸の旗。旭日旗。日章旗。
ぎょっ‐き【玉机・玉几】ギヨク‥
①玉で飾った机。机の美称。
②他人の机の尊敬語。玉案。
ぎょっ‐き【玉肌】ギヨク‥
玉のような美しいはだ。たまのはだ。玉膚。
ぎょっ‐き【玉器】ギヨク‥
玉で作った器物。
きょっ‐きゅう【曲球】キヨクキウ
野球で、カーブのこと。
きょっ‐けい【極刑】キヨク‥
この上なく重い刑罰。死刑。「―に処する」
ぎょっ‐けい【玉笄】ギヨク‥
玉で作ったかんざし。
ぎょっ‐けい【玉磬】ギヨク‥
玉で作った磬。
きょっけい‐どうぶつ【曲形動物】キヨク‥
(→)内肛動物の旧名。
ぎょっ‐けつ【玉玦】ギヨク‥
環の一部分が欠けたかたちの佩玉はいぎょく。
ぎょっ‐けつ【玉闕】ギヨク‥
玉で飾った美しい宮殿。玉殿。
きょっ‐けん【極圏】キヨク‥
地球の南北両極からそれぞれ23度27分の所にある緯線(南極圏・北極圏)。また、この両極圏から高緯度の地域。
ぎょっ‐こ【玉壺】ギヨク‥
玉で作ったつぼ。美しいつぼ。
きょっ‐こう【旭光】キヨククワウ
朝日の光。
きょっ‐こう【曲行】キヨクカウ
①曲がり曲がって行くこと。
②不正な行い。
きょっ‐こう【曲肱】キヨク‥
(「肱」は、ひじ)ひじを曲げること。特に、ひじを曲げて枕がわりにすること。ひじ枕をすること。
⇒きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】
きょっ‐こう【極光】キヨククワウ
(→)オーロラに同じ。
ぎょっ‐こう【玉稿】ギヨクカウ
他人の草稿の尊敬語。御原稿。
きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】キヨク‥
[論語述而「疏食そしを飯くらい水を飲み、肱を曲げて之を枕とす、楽しみまた其の中に在り」]貧しい生活の中にも楽しみがあるということ。簡素な生活の楽しさ。
⇒きょっ‐こう【曲肱】
ぎょっ‐こつ【玉骨】ギヨク‥
①玉のような骨。高潔な風姿をいう。また、梅の幹枝にたとえ、梅樹の異称。
②貴人または美人の死骸・骨。太平記21「―はたとひ南山の苔に埋もるとも」
ぎょっ‐と
〔副〕
不意に予期しない物事に出合って驚きや恐怖を感じ緊張するさま。「一瞬―なる」「―して立ちどまる」
きよつね【清経】
能。世阿弥作の修羅物。妻を都に残して合戦におもむいた平清経が豊前国柳浦で入水したことを脚色。
きょ‐てい【居邸】
すまいするやしき。居宅。
ぎょ‐てい【魚梯】
河川に滝・ダムなどがある場合、魚類を遡上させるために河の一部に設けられた緩傾斜の水路、または幾段にもなった水路のこと。魚道の一種。
ぎょ‐てい【漁艇】
①漁猟に使用する小舟。
②大型漁船に積んで、漁場で下ろして使う小舟。
きょ‐てん【拠点】
活動のよりどころになる所。「戦略上の―」「生産―」
きょ‐でん【虚伝】
根もないうわさ・言いつたえ。
ぎょ‐でん【魚田】
(魚の田楽の意)魚を串に刺し味噌をぬって焼いた料理。
ぎょ‐と【魚肚】
チョウザメ・イシモチなどの鰾うきぶくろを乾燥した食品。中国料理で用いる。
きょと・い
〔形〕
(キョウトイの転)
①はなはだしい。東海道中膝栗毛3「お江戸は―・いはんじやうなとこぢやわいの」
②恐ろしい。ひどい。無事志有意「滅相な―・いこといはんす」
きょ‐とう【去冬】
去年の冬。
きょ‐とう【巨盗】‥タウ
おおどろぼう。巨賊。大盗。
きょ‐とう【巨頭】
①大きなあたま。
②ある方面や団体でのおもだった人。大立者。「―会談」
きょ‐とう【巨濤】‥タウ
大きな波。大浪。
きょ‐とう【挙党】‥タウ
一つの政党全体。「―一致」
きょ‐どう【挙動】
①立ち居ふるまい。人の動作や行為。しわざ。様子。挙止。
②体操で、単一な個々の動作。
⇒きょどう‐はん【挙動犯】
⇒きょどう‐ふしん【挙動不審】
ぎょ‐とう【魚灯】
魚灯油の略。傾城買四十八手「行灯あんどうは―をとぼす故、紙へ付けて吸ひつける」
⇒ぎょとう‐ゆ【魚灯油】
ぎょ‐とう【魚頭】
魚の頭。狂言、鱸庖丁「一の刀にて―を継ぎ」
ぎょ‐とう【漁灯】
漁業に用いる灯火。いさり火。
ぎょ‐どう【魚道】‥ダウ
①魚群の回遊経路。魚種・深浅・潮流などによってほぼ一定。
②河川にダムや堰を築造する時、魚類の通路として設ける水路。魚梯ぎょていが主なもの。
③(→)「ぎょうどう(凝当)」に同じ。〈文明本節用集〉
きょどう‐はん【挙動犯】
犯罪の構成要件上、一定の身体的動静のみで足り、外部的結果の発生を必要としない犯罪。偽証罪・公然猥褻わいせつ罪の類。↔結果犯。
⇒きょ‐どう【挙動】
きょどう‐ふしん【挙動不審】
外での行動や様子があやしいこと。
⇒きょ‐どう【挙動】
ぎょとう‐ゆ【魚灯油】
イワシ・ニシンなどの脂肪から採った、臭気の強い下等の灯油。
⇒ぎょ‐とう【魚灯】
きょと‐きょと
不安や恐れなどのため落着きなく視線を走らせるさま。きょろきょろ。「―見回す」
きよ‐どころ【清所】
御厨子所みずしどころの異称。貴人の台所にもいう。おきよどころ。
きょとん
事の意外さに事態がとっさに理解できず、驚きと当惑でただ目を見開いているさま。「急にどなられて―とする」
ぎょ‐にく【魚肉】
①食用としての魚の肉。
②魚と獣肉。
⇒ぎょにく‐ソーセージ【魚肉ソーセージ】
⇒魚肉となる
ぎょにく‐ソーセージ【魚肉ソーセージ】
魚肉を使って畜肉ソーセージに似せて作る練り製品。フィッシュ‐ソーセージ。
⇒ぎょ‐にく【魚肉】
きょ‐たく【居宅】
いつも住んでいる家。
きょ‐たく【虚託】
いつわりかこつけること。かこつけ。
きょ‐だく【許諾】
要求を聞き入れ、許すこと。承諾。
ぎょ‐たく【魚拓】
魚の拓本。魚の表面に和紙を置き、魚の形を摺り写したもの。
ぎょ‐たく【魚柝】
(→)木魚もくぎょに同じ。
きょ‐たつ【挙達】
①推挙を得て栄達すること。
②とりあげて進達すること。
きょ‐だつ【虚脱】
①心臓が衰弱して体力がなくなり、瀕死の状態となること。
②気力がぬけて、ぼんやりと何も手につかない状態。「―感」
きょ‐たん【袪痰・去痰】
気管または気管支にたまっている喀痰を除去すること。
⇒きょたん‐やく【袪痰薬】
きょ‐たん【虚誕】
事実無根のことをおおげさに言うこと。うそ。でたらめ。
きょ‐だん【巨弾】
大きな砲弾や爆弾。痛烈できわめて効果的な非難や手段のたとえ。
きょ‐だん【虚談】
事実でない話。つくりばなし。虚説。
ぎょ‐たん【魚探】
魚群探知機の略。
きょたん‐やく【袪痰薬】
袪痰に用いる薬剤。桔梗根・セネガ根・吐根・アンモニアウイキョウ精など。
⇒きょ‐たん【袪痰・去痰】
きょ‐ちゅう【居中】
両方の中間に立つこと。また、中間にあって偏しないこと。
⇒きょちゅう‐ちょうてい【居中調停】
ぎょ‐ちゅう【魚虫】
魚と虫。虫魚。古今著聞集20「禽獣―」
ぎょ‐ちゅう【御注・御註】
天子が自ら書籍に注釈を加えること。また、その注釈。「―孝経」
きょちゅう‐ちょうてい【居中調停】‥テウ‥
(mediation)第三国が国際紛争当事国の間に立って、平和に解決するようにとりもつこと。仲介。
⇒きょ‐ちゅう【居中】
きょ‐ちょう【挙朝】‥テウ
朝廷の人残らず。朝廷全体。
きょ‐ちょう【秬鬯】‥チヤウ
黒黍きび(秬)と香草(鬯)とを合わせて造った酒。
ぎょ‐ちょう【魚鳥】‥テウ
魚と鳥。
⇒ぎょちょう‐どめ【魚鳥留め】
ぎょ‐ちょう【漁釣】‥テウ
魚を釣ること。魚つり。
ぎょちょう‐どめ【魚鳥留め】‥テウ‥
①魚鳥を捕ることや食べることを禁止すること。
②精進のため、喪中や忌日に魚鳥類を家の中にいれないこと。誹風柳多留147「精進の看板を出す―」
⇒ぎょ‐ちょう【魚鳥】
ギヨチン【guillotine フランス】
⇒ギロチン
きょっ‐かい【曲解】キヨク‥
相手の言動・心中を、素直でなくわざと曲げて解釈すること。「人の言うことを―する」
ぎょっ‐かい【玉階】ギヨク‥
宮殿の階段。御階。みはし。
きょっ‐かく【極核】キヨク‥
⇒きょくかく
きょっ‐かん【極官】キヨククワン
⇒ごっかん
きょっ‐かん【極冠】キヨククワン
火星の両極地方に当たる部分に認められる白い箇所。一部は氷だが、大半は二酸化炭素の氷(ドライアイス)でできていると考えられる。
きょっ‐かん【極諫】キヨク‥
ことばを尽くしていさめること。強くいさめること。
ぎょっ‐かん【玉冠】ギヨククワン
玉で飾った冠。→礼冠らいかん
ぎょっ‐かん【玉簡・玉翰】ギヨク‥
相手に敬意を表してその手紙をいう語。
きょっ‐き【旭暉】キヨク‥
あさひの光。旭光。
きょっ‐き【旭旗】キヨク‥
日の丸の旗。旭日旗。日章旗。
ぎょっ‐き【玉机・玉几】ギヨク‥
①玉で飾った机。机の美称。
②他人の机の尊敬語。玉案。
ぎょっ‐き【玉肌】ギヨク‥
玉のような美しいはだ。たまのはだ。玉膚。
ぎょっ‐き【玉器】ギヨク‥
玉で作った器物。
きょっ‐きゅう【曲球】キヨクキウ
野球で、カーブのこと。
きょっ‐けい【極刑】キヨク‥
この上なく重い刑罰。死刑。「―に処する」
ぎょっ‐けい【玉笄】ギヨク‥
玉で作ったかんざし。
ぎょっ‐けい【玉磬】ギヨク‥
玉で作った磬。
きょっけい‐どうぶつ【曲形動物】キヨク‥
(→)内肛動物の旧名。
ぎょっ‐けつ【玉玦】ギヨク‥
環の一部分が欠けたかたちの佩玉はいぎょく。
ぎょっ‐けつ【玉闕】ギヨク‥
玉で飾った美しい宮殿。玉殿。
きょっ‐けん【極圏】キヨク‥
地球の南北両極からそれぞれ23度27分の所にある緯線(南極圏・北極圏)。また、この両極圏から高緯度の地域。
ぎょっ‐こ【玉壺】ギヨク‥
玉で作ったつぼ。美しいつぼ。
きょっ‐こう【旭光】キヨククワウ
朝日の光。
きょっ‐こう【曲行】キヨクカウ
①曲がり曲がって行くこと。
②不正な行い。
きょっ‐こう【曲肱】キヨク‥
(「肱」は、ひじ)ひじを曲げること。特に、ひじを曲げて枕がわりにすること。ひじ枕をすること。
⇒きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】
きょっ‐こう【極光】キヨククワウ
(→)オーロラに同じ。
ぎょっ‐こう【玉稿】ギヨクカウ
他人の草稿の尊敬語。御原稿。
きょっこう‐の‐たのしみ【曲肱の楽しみ】キヨク‥
[論語述而「疏食そしを飯くらい水を飲み、肱を曲げて之を枕とす、楽しみまた其の中に在り」]貧しい生活の中にも楽しみがあるということ。簡素な生活の楽しさ。
⇒きょっ‐こう【曲肱】
ぎょっ‐こつ【玉骨】ギヨク‥
①玉のような骨。高潔な風姿をいう。また、梅の幹枝にたとえ、梅樹の異称。
②貴人または美人の死骸・骨。太平記21「―はたとひ南山の苔に埋もるとも」
ぎょっ‐と
〔副〕
不意に予期しない物事に出合って驚きや恐怖を感じ緊張するさま。「一瞬―なる」「―して立ちどまる」
きよつね【清経】
能。世阿弥作の修羅物。妻を都に残して合戦におもむいた平清経が豊前国柳浦で入水したことを脚色。
きょ‐てい【居邸】
すまいするやしき。居宅。
ぎょ‐てい【魚梯】
河川に滝・ダムなどがある場合、魚類を遡上させるために河の一部に設けられた緩傾斜の水路、または幾段にもなった水路のこと。魚道の一種。
ぎょ‐てい【漁艇】
①漁猟に使用する小舟。
②大型漁船に積んで、漁場で下ろして使う小舟。
きょ‐てん【拠点】
活動のよりどころになる所。「戦略上の―」「生産―」
きょ‐でん【虚伝】
根もないうわさ・言いつたえ。
ぎょ‐でん【魚田】
(魚の田楽の意)魚を串に刺し味噌をぬって焼いた料理。
ぎょ‐と【魚肚】
チョウザメ・イシモチなどの鰾うきぶくろを乾燥した食品。中国料理で用いる。
きょと・い
〔形〕
(キョウトイの転)
①はなはだしい。東海道中膝栗毛3「お江戸は―・いはんじやうなとこぢやわいの」
②恐ろしい。ひどい。無事志有意「滅相な―・いこといはんす」
きょ‐とう【去冬】
去年の冬。
きょ‐とう【巨盗】‥タウ
おおどろぼう。巨賊。大盗。
きょ‐とう【巨頭】
①大きなあたま。
②ある方面や団体でのおもだった人。大立者。「―会談」
きょ‐とう【巨濤】‥タウ
大きな波。大浪。
きょ‐とう【挙党】‥タウ
一つの政党全体。「―一致」
きょ‐どう【挙動】
①立ち居ふるまい。人の動作や行為。しわざ。様子。挙止。
②体操で、単一な個々の動作。
⇒きょどう‐はん【挙動犯】
⇒きょどう‐ふしん【挙動不審】
ぎょ‐とう【魚灯】
魚灯油の略。傾城買四十八手「行灯あんどうは―をとぼす故、紙へ付けて吸ひつける」
⇒ぎょとう‐ゆ【魚灯油】
ぎょ‐とう【魚頭】
魚の頭。狂言、鱸庖丁「一の刀にて―を継ぎ」
ぎょ‐とう【漁灯】
漁業に用いる灯火。いさり火。
ぎょ‐どう【魚道】‥ダウ
①魚群の回遊経路。魚種・深浅・潮流などによってほぼ一定。
②河川にダムや堰を築造する時、魚類の通路として設ける水路。魚梯ぎょていが主なもの。
③(→)「ぎょうどう(凝当)」に同じ。〈文明本節用集〉
きょどう‐はん【挙動犯】
犯罪の構成要件上、一定の身体的動静のみで足り、外部的結果の発生を必要としない犯罪。偽証罪・公然猥褻わいせつ罪の類。↔結果犯。
⇒きょ‐どう【挙動】
きょどう‐ふしん【挙動不審】
外での行動や様子があやしいこと。
⇒きょ‐どう【挙動】
ぎょとう‐ゆ【魚灯油】
イワシ・ニシンなどの脂肪から採った、臭気の強い下等の灯油。
⇒ぎょ‐とう【魚灯】
きょと‐きょと
不安や恐れなどのため落着きなく視線を走らせるさま。きょろきょろ。「―見回す」
きよ‐どころ【清所】
御厨子所みずしどころの異称。貴人の台所にもいう。おきよどころ。
きょとん
事の意外さに事態がとっさに理解できず、驚きと当惑でただ目を見開いているさま。「急にどなられて―とする」
ぎょ‐にく【魚肉】
①食用としての魚の肉。
②魚と獣肉。
⇒ぎょにく‐ソーセージ【魚肉ソーセージ】
⇒魚肉となる
ぎょにく‐ソーセージ【魚肉ソーセージ】
魚肉を使って畜肉ソーセージに似せて作る練り製品。フィッシュ‐ソーセージ。
⇒ぎょ‐にく【魚肉】
きょ‐たつ【挙達】🔗⭐🔉
きょ‐たつ【挙達】
①推挙を得て栄達すること。
②とりあげて進達すること。
きょ‐ちょう【挙朝】‥テウ🔗⭐🔉
きょ‐ちょう【挙朝】‥テウ
朝廷の人残らず。朝廷全体。
きょ‐とう【挙党】‥タウ🔗⭐🔉
きょ‐とう【挙党】‥タウ
一つの政党全体。「―一致」
きょ‐どう【挙動】🔗⭐🔉
きょ‐どう【挙動】
①立ち居ふるまい。人の動作や行為。しわざ。様子。挙止。
②体操で、単一な個々の動作。
⇒きょどう‐はん【挙動犯】
⇒きょどう‐ふしん【挙動不審】
きょどう‐はん【挙動犯】🔗⭐🔉
きょどう‐はん【挙動犯】
犯罪の構成要件上、一定の身体的動静のみで足り、外部的結果の発生を必要としない犯罪。偽証罪・公然猥褻わいせつ罪の類。↔結果犯。
⇒きょ‐どう【挙動】
きょどう‐ふしん【挙動不審】🔗⭐🔉
きょどう‐ふしん【挙動不審】
外での行動や様子があやしいこと。
⇒きょ‐どう【挙動】
きょ‐はく【挙白】🔗⭐🔉
きょ‐はく【挙白】
杯を手に取って酒を飲むこと。また、酒をすすめること。
きょはく【挙白】(人名)🔗⭐🔉
きょはく【挙白】
木下長嘯子ちょうしょうしの別号。
⇒きょはく‐しゅう【挙白集】
⇒きょはく‐どう【挙白堂】
きょはく‐しゅう【挙白集】‥シフ🔗⭐🔉
きょはく‐しゅう【挙白集】‥シフ
歌文集。10巻8冊。木下長嘯子作。1649年(慶安2)刊。歌風は清新・奇抜。
⇒きょはく【挙白】
きょはく‐どう【挙白堂】‥ダウ🔗⭐🔉
きょはく‐どう【挙白堂】‥ダウ
木下長嘯子が京都東山に設けた隠宅。また、長嘯子の別号。
⇒きょはく【挙白】
きょ‐へい【挙兵】🔗⭐🔉
きょ‐へい【挙兵】
兵を集めて戦いを起こすこと。はたあげ。
きょ‐よう【挙用】🔗⭐🔉
きょ‐よう【挙用】
下位にある者を引きあげて用いること。人を取り立てて用いること。登用。「部長に―する」
きょ‐れい【挙例】🔗⭐🔉
きょ‐れい【挙例】
実例を挙げること。
⇒きょれい‐ほう【挙例法】
きょれい‐ほう【挙例法】‥ハフ🔗⭐🔉
きょれい‐ほう【挙例法】‥ハフ
修辞法の一つ。立論を証するために例を挙げる技法。
⇒きょ‐れい【挙例】
こ‐じん【挙人】🔗⭐🔉
こ‐じん【挙人】
律令制の大学から官人に登用されるよう推挙された学生。きょじん。
こ・す【挙す】🔗⭐🔉
こ・す【挙す】
〔他サ変〕
①持ちあげる。日本霊異記上「礠石じしゃくの鉄山を―・して鉄を嘘すふ」
②推挙する。沙石集(一本)「老体の身ものうく侍り。―・し申さん」
こ‐ぜい【挙税】🔗⭐🔉
こ‐ぜい【挙税】
奈良・平安時代、稲穀・銭貨を貸し出して利息を取ったこと。出挙稲すいことう。出挙銭。
こぞっ‐て【挙って】🔗⭐🔉
こぞっ‐て【挙って】
〔副〕
(コゾリテの音便)一人残らず。ことごとく皆。あげて。「―参加する」
こぞ・る【挙る】🔗⭐🔉
こぞ・る【挙る】
[一]〔自五〕
①(その場にいる者、それに関係する者が)一致した行動をする。いっせいにする。伊勢物語「舟―・りて泣きにけり」。島崎藤村、夜明け前「一家―・つて逃げなければならない騒ぎ」
②ことごとく集まる。残らずそろう。皇極紀「国―・る民おおみたから」
[二]〔他五〕
ことごとくそろえる。残らず集める。「国を―・って歓迎する」
ころも【挙母】🔗⭐🔉
ころも【挙母】
愛知県豊田市の旧称。
○衣打つころもうつ
布・衣服をやわらかくし、また、つやを出すために、砧きぬたで打つ。その音は秋の景物として古来詩歌に多く詠まれた。〈[季]秋〉
⇒ころも【衣】
しりあげ‐むし【挙尾虫】🔗⭐🔉
しりあげ‐むし【挙尾虫】
①シリアゲムシ目シリアゲムシ科の昆虫の総称。ややウスバカゲロウに類似し、体長約2センチメートル。雄の尾端にはさみがあり、常に尾端を上に曲げる。林の中にすみ、地上の虫の死体を食う。また、その一種。全体は光沢のある黒色。成虫は4〜7月に出現する。
シリアゲムシ
撮影:海野和男
 ②ハサミムシの俗称。
②ハサミムシの俗称。
 ②ハサミムシの俗称。
②ハサミムシの俗称。
[漢]挙🔗⭐🔉
挙 字形
 筆順
筆順
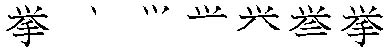 〔手(扌)部6画/10画/教育/2183・3573〕
[擧] 字形
〔手(扌)部6画/10画/教育/2183・3573〕
[擧] 字形
 〔手(扌)部13画/17画/5809・5A29〕
〔音〕キョ(漢) コ(呉)
〔訓〕あげる・あがる・こぞる
[意味]
①高く持ちあげる。上にあげる。「挙手」
②目立つように事をおこす。くわだて。「反撃の挙に出る」「挙行・挙兵・挙式・快挙」
③体を動かす。ふるまい。「挙動・挙措・一挙一動」
④人をとりたてる。登用する。「挙用・推挙・科挙・選挙」
⑤召し上げる。「検挙・出挙すいこ」
⑥とりあげて示す。ならべたてる。「挙例・挙証・枚挙・列挙」
⑦こぞる。すべて。のこらず。あげて。「挙国・挙党一致」
[解字]
形声。「手」+音符「與」(=ともに持ち上げる)。手で高く持ちあげる意。[舉]は異体字。
[下ツキ
一挙・快挙・科挙・義挙・愚挙・軽挙・検挙・貢挙・再挙・推挙・出挙・盛挙・選挙・壮挙・大挙・美挙・暴挙・妄挙・枚挙・列挙
〔手(扌)部13画/17画/5809・5A29〕
〔音〕キョ(漢) コ(呉)
〔訓〕あげる・あがる・こぞる
[意味]
①高く持ちあげる。上にあげる。「挙手」
②目立つように事をおこす。くわだて。「反撃の挙に出る」「挙行・挙兵・挙式・快挙」
③体を動かす。ふるまい。「挙動・挙措・一挙一動」
④人をとりたてる。登用する。「挙用・推挙・科挙・選挙」
⑤召し上げる。「検挙・出挙すいこ」
⑥とりあげて示す。ならべたてる。「挙例・挙証・枚挙・列挙」
⑦こぞる。すべて。のこらず。あげて。「挙国・挙党一致」
[解字]
形声。「手」+音符「與」(=ともに持ち上げる)。手で高く持ちあげる意。[舉]は異体字。
[下ツキ
一挙・快挙・科挙・義挙・愚挙・軽挙・検挙・貢挙・再挙・推挙・出挙・盛挙・選挙・壮挙・大挙・美挙・暴挙・妄挙・枚挙・列挙
 筆順
筆順
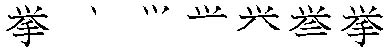 〔手(扌)部6画/10画/教育/2183・3573〕
[擧] 字形
〔手(扌)部6画/10画/教育/2183・3573〕
[擧] 字形
 〔手(扌)部13画/17画/5809・5A29〕
〔音〕キョ(漢) コ(呉)
〔訓〕あげる・あがる・こぞる
[意味]
①高く持ちあげる。上にあげる。「挙手」
②目立つように事をおこす。くわだて。「反撃の挙に出る」「挙行・挙兵・挙式・快挙」
③体を動かす。ふるまい。「挙動・挙措・一挙一動」
④人をとりたてる。登用する。「挙用・推挙・科挙・選挙」
⑤召し上げる。「検挙・出挙すいこ」
⑥とりあげて示す。ならべたてる。「挙例・挙証・枚挙・列挙」
⑦こぞる。すべて。のこらず。あげて。「挙国・挙党一致」
[解字]
形声。「手」+音符「與」(=ともに持ち上げる)。手で高く持ちあげる意。[舉]は異体字。
[下ツキ
一挙・快挙・科挙・義挙・愚挙・軽挙・検挙・貢挙・再挙・推挙・出挙・盛挙・選挙・壮挙・大挙・美挙・暴挙・妄挙・枚挙・列挙
〔手(扌)部13画/17画/5809・5A29〕
〔音〕キョ(漢) コ(呉)
〔訓〕あげる・あがる・こぞる
[意味]
①高く持ちあげる。上にあげる。「挙手」
②目立つように事をおこす。くわだて。「反撃の挙に出る」「挙行・挙兵・挙式・快挙」
③体を動かす。ふるまい。「挙動・挙措・一挙一動」
④人をとりたてる。登用する。「挙用・推挙・科挙・選挙」
⑤召し上げる。「検挙・出挙すいこ」
⑥とりあげて示す。ならべたてる。「挙例・挙証・枚挙・列挙」
⑦こぞる。すべて。のこらず。あげて。「挙国・挙党一致」
[解字]
形声。「手」+音符「與」(=ともに持ち上げる)。手で高く持ちあげる意。[舉]は異体字。
[下ツキ
一挙・快挙・科挙・義挙・愚挙・軽挙・検挙・貢挙・再挙・推挙・出挙・盛挙・選挙・壮挙・大挙・美挙・暴挙・妄挙・枚挙・列挙
広辞苑に「挙」で始まるの検索結果 1-60。
 部7画〕
部7画〕