複数辞典一括検索+![]()
![]()
ちん‐もく【沈黙】🔗⭐🔉
ちん‐もく【沈黙】
①だまって、口をきかないこと。「―を守る」「―を破る」
②活動せずに静かにしていること。「5年間の―の後、作品を発表する」
⇒ちんもく‐こうえき【沈黙交易】
⇒沈黙は金、雄弁は銀
ちんもく‐こうえき【沈黙交易】‥カウ‥🔗⭐🔉
ちんもく‐こうえき【沈黙交易】‥カウ‥
異民族の間で行われた交易形態の一つ。双方が無言で、また顔を合わせることもなく、互いに置かれた品物を交換する方法。
⇒ちん‐もく【沈黙】
○沈黙は金、雄弁は銀ちんもくはきんゆうべんはぎん
(西洋の諺から)沈黙の方が雄弁よりも価値がある。黙っているのが最上の分別。
⇒ちん‐もく【沈黙】
○沈黙は金、雄弁は銀ちんもくはきんゆうべんはぎん🔗⭐🔉
○沈黙は金、雄弁は銀ちんもくはきんゆうべんはぎん
(西洋の諺から)沈黙の方が雄弁よりも価値がある。黙っているのが最上の分別。
⇒ちん‐もく【沈黙】
ちん‐もち【賃餅】
賃銭を取って餅をつくこと。また、その餅。
ちん‐もん【珍問】
変わった質問。見当はずれの質問。
ちん‐やく【沈約】
⇒しんやく
ちん‐ゆう【沈勇】
沈着で勇気のあること。
ちん‐ゆう【珍優】‥イウ
おもしろおかしい演技を得意とする俳優。
ちん‐よう【陳容】
南宋末期の文人画家。字は公儲こうちょ。号は所翁。長楽(福建)の人。水墨の竜を得意とし、宝祐(1253〜1258)年間に名を馳せる。作「九竜図」。
ちん‐よう【椿葉】‥エフ
(「荘子」にみえる、椿という霊木の葉の意から)長い年月のたとえ。保元物語「縦ひ―の陰再び改まると雖いうとも」→大椿だいちゅん
ちん‐よぎ【陳与義】
南宋の詩人。字は去非、号は簡斎・無住。河南洛陽の人。南宋政権下で官を歴任、参知政事に至る。黄庭堅・陳師道と並び江西詩派三宗の一人。散文・詞・書にも秀でる。著「簡斎集」。(1090〜1138)
ちん‐りっぷ【陳立夫】
(Chen Lifu)中国の政治家。浙江財閥四大家族の一つ。浙江呉興の人。アメリカに留学。国民党中央組織部門の実権者で、兄果夫とともにCC系の領袖。著「唯生論」「成敗之鑑」。(1900〜2001)
ちん‐りょう【賃料】‥レウ
賃貸借契約において賃借人が支払う使用の対価。特に不動産の地代・家賃など。
ちん‐りん【沈淪】
(「淪」もしずむ意)
①深くしずむこと。
②おちぶれはてること。零落。「―流浪」
ちん‐れつ【陳列】
見せるために物品をならべておくこと。「絵画を―する」「―棚」
⇒ちんれつ‐まど【陳列窓】
ちんれつ‐まど【陳列窓】
人目をひくように商品を陳列しておく店先のガラス窓。ショー‐ウィンドー。
⇒ちん‐れつ【陳列】
ちん‐ろうどう【賃労働】‥ラウ‥
(wage-labour イギリス・Lohnarbeit ドイツ)生産手段(土地・工場・機械・原料など)をもたない労働者が、労働力を生産手段の所有者たる資本家(企業主)に売り、賃金をうけとる労働の形態。資本主義社会において一般的となった。↔奴隷労働
ちん‐わく【沈枠】
堤防または海岸の修築に用いる枠。太い丸太を四隅に柱木として立て、これに貫木を挿み、側面と底部に小材を並べ、中に円石をうめて水中に沈める。四つ枠。
ちん‐わけい【陳和卿】
⇒ちんなけい
ちん‐わた【賃綿】
賃銭を取って綿を繰ること。
ちん‐わん【枕腕】
執筆法の一つ。左手を平らに机上に伏せ、筆を執る右手をその上にのせて文字を書くこと。多く細字を書くときに用いる。→懸腕→提腕
つ
①舌端を上前歯のもとに密着して破裂摩擦させる無声子音〔ts〕と、母音〔u〕との結合した音節。〔tsu〕
②平仮名「つ」は「州」の略体の草体とも、「川」「津」「鬥」の草体とも。片仮名「ツ」は「州」の略体。
つ【津】
①船舶の碇泊する所。ふなつき。港。万葉集19「君が船漕ぎ帰りきて―にはつるまで」
②わたしば。渡船場。
③人の集まる所。狂言、蚊相撲「いやこれは早、人々の通る―でござる」
つ【津】
三重県の市。県庁所在地。古く伊勢海に臨む安濃津あのつの港で、もと藤堂氏32万石の城下町。津綟子つもじ・阿漕焼あこぎやきを産する。人口28万9千。
つ【唾】
つば。つばき。〈色葉字類抄〉
⇒唾を引く
つ
〔助動〕
(活用は下二段型。活用語の連用形に付く。[活用]て/て/つ/つる/つれ/てよく)動詞「棄うつ」の約という。動作・作用が話し手など当事者の意図に基づき、作為的・意志的に成り立ったことを表し、無作為的・自然推移的意味で使われる「ぬ」と区別がある。室町時代からは用法が限られ、口語では衰える。→たり。
①動作・状態が完了する意。…してしまう。…した。後に推量の意味が続いた時は、強意と解釈されることもある。古事記中「新治にいばり筑波を過ぎて幾夜か寝つる」。万葉集8「沫雪に降らえて咲ける梅の花君がりやらばよそへてむかも」。保元物語「あはれ、取りもかふる物ならば、忠実が命にかへてまし」
②した人を責める思いを込めて、動作・事態の完了をいう。伊勢物語「みそかに通ふ女ありけり。それがもとよりこよひ夢になん見え給ひつるといへりければ」。源氏物語若紫「雀の子を犬君が逃がしつる」
③自分に責任があるという思いを込めて、動作・事態の完了をいう。万葉集5「手に持てる吾あが児飛ばしつ世の中の道」。古今和歌集恋「飛鳥川淵は瀬になる世なりとも思ひそめてむ人は忘れじ」
④(終止形だけの用法)対照的な動作を並列的に述べる。口語では並立助詞とする。中華若木詩抄「舞せつ歌せつする」。天草本平家物語「泣いつ笑うつせられた」
つ
〔助詞〕
➊(格助詞)体言と体言を「の」の関係で結ぶ働きをする語。多く場所を示す名詞の後に付き、「の」よりも用法が狭い。上代の文献に見え、平安時代には「昼―方」「奥―方」と、複合語の中で見られるだけとなる。「天―神」「目ま―毛」「はじめ―方かた」
➋(接続助詞)(文語完了の助動詞「つ」から)動詞の連用形に付く。動作の並行・継起することを表す。前が撥音のときは「づ」となる。
①(「…つ…つ」の形で)…たり…たり。太平記6「追つ―返し―同士軍をぞしたりける」。浄瑠璃、心中天の網島「抜け―隠れ―なされても」。「組んづほぐれつ」
②(二つの動作・作用が同時に行われる時に、従属的な方の動作・作用に付ける)…ながら。方丈記「苦しむ時は休め―、まめなれば使ふ」
③…たりなどして。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「作病起して振つて見―、色々飽かるる工面して」
つ【箇・個】
〔接尾〕
数詞の下に添えて数を表す語。ち。古事記上「五百いお―真榊まさかき」。「ひと―」
づ
「つ」の濁音。鎌倉時代まで舌尖有声破裂音〔du〕であったが、後に舌尖有声破裂摩擦音〔dzu〕となり、室町末期には「ず」〔zu〕と混同し始め、現在一般には「づ」「ず」の区別はない。
ツァー【czar; tsar】
⇒ツァーリ
ツアー【tour】
①回遊。周遊旅行。小旅行。「―を組む」「スキー‐―」
②旅行会社などが企画する団体旅行。
③歌手・劇団などの巡業。「コンサート‐―」
⇒ツアー‐ガイド【tour guide】
⇒ツアー‐コンダクター【tour conductor】
ツアー‐ガイド【tour guide】
旅行案内人。添乗員。
⇒ツアー【tour】
ツアー‐コンダクター【tour conductor】
団体旅行を案内・誘導する人。添乗員。
⇒ツアー【tour】
ツァーリ【tsar' ロシア】
帝政時代のロシア君主の称号。ラテン語の皇帝の意になったカエサル(Caesar)から出た語。ツァー。ツァール。ザール。ザー。→ツァーリズム
ツァーリズム【tsarizm ロシア・czarism; tsarism イギリス】
(ツァーリに基づく語)1917年二月革命以前のロシアの専制君主政体。ロシア特有の絶対王政。
ツァール【tsar' ロシア】
⇒ツァーリ
ツァイダム【柴達木・Tsaidam】
中国青海省北西部にある盆地。南東部には沼沢・塩湖が多い。鉱物資源が豊富。
ツァイチェン【再見】
(中国語)さようなら。御機嫌よう。
ツァイト【Die Zeit】
(「時」の意)ドイツの週刊新聞。1946年創刊。論調はリベラル。
ツァイトガイスト【Zeitgeist ドイツ】
時代精神。
ツァッケ【Zacke ドイツ】
(尖端の意)主としてフォーク・ピッケルなどの、尖とがった先の部分。
つ‐あて【唾当て】
(「つ」は、つばの意)幼児のよだれかけ。
ツァラ【Tristan Tzara】
フランスの詩人。ルーマニア生れ。ダダイスムの創始者の一人。詩集「近似的人間」など。(1896〜1963)
ツァラトゥストラ【Zarathustra】
ゾロアスター教の開祖ゾロアスターのドイツ語名。
つい【終】ツヒ
①おわり。はて。源氏物語帚木「―のたのみ所には思ひおくべかりける」。「―のすみか」
②特に、人生のおわり。死。最期さいご。源氏物語椎本「―の別れをのがれぬわざなめれど」
③(副詞的に)(→)「ついぞ」に同じ。
つい【対】
(呉音)
①二つそろって一組をなすもの。つがい。そろい。また、そのようなものを数える語。「―になる」
②(→)対句ついくに同じ。
→たい(対)
つい
〔副〕
①はからず。思わず。「―過あやまって」
②時間や距離がわずかなさま。ちょっと。「―先程」「―近くまで」
③動作のすばやいさま。狂言、月見座頭「歌の一首や二首は―詠む事でおりやる」
つい
〔接頭〕
(ツキ(突)の音便)動詞に添えて語勢を強め、また、「ちょっと」「そのまま」「突然」などの意を表す。落窪物語1「―かがまりて」。源氏物語若紫「―ゐたり」
ツイーター【tweeter】
高音域再生用スピーカー。→スコーカー→ウーファー
ツイード【tweed】
(→)スコッチ1に同じ。
つい・いる【つい居る】‥ヰル
〔自上一〕
(ツイは接頭語)
①ひざまずく。かしこまる。源氏物語夕顔「御随身―・ゐて」
②ちょっといる。そのままにいる。源氏物語野分「端の方に―・ゐ給ひて」
つい‐いん【追院】‥ヰン
江戸時代、僧に科した刑の一種。犯罪の宣告を受けた僧を、居住の寺院に帰ることを許さず直ちに追放すること。いったん寺院に帰ることを許す退院より重い。
つい‐う【堆烏】
(→)堆黒ついこくに同じ。
ついえ【費え・弊え・潰え】ツヒエ
(動詞ツイユの連用形から)
①くずれやぶれること。悪くなること。
②つかれ苦しむこと。弱ること。太平記37「あはれ―に乗る(弱点につけこむ)処やと思ひければ」
③かかり。費用。入費。今昔物語集7「軽物を分ちて交易するに、その―多かり」。「思わぬ―」
④無用の入費。損害。むだづかい。方丈記「七珍万宝さながら灰燼となりにき。その―いくそばくぞ」。「国家の―」
◇3・4は、ふつう「費え」と書く。
つい・える【費える・弊える・潰える】ツヒエル
〔自下一〕[文]つひ・ゆ(下二)
①へる。乏しくなる。皇極紀「損おとり―・ゆること極めて甚だし」。「貯えが―・える」
②やつれ、おとろえる。疲れる。源氏物語蓬生「年ごろいたう―・えたれど」
③くずれる。また、潰走する。〈色葉字類抄〉。「優勝の夢が―・える」
④いたずらに経過する。「無駄に一日が―・える」
◇1・4には、ふつう「費」を使う。
つい‐えん【追遠】‥ヱン
[論語学而「終りを慎み遠きを追えば、民の徳厚きに帰す」]先祖の徳を追慕して心をこめて供養すること。
つい‐おう【堆黄】‥ワウ
堆朱ついしゅの一種。黄色の漆を主体とするもの。
つい‐おく【追憶】
過ぎ去ったことを思い出すこと。追懐。「―にひたる」
ツィオルコフスキー【Konstantin Tsiolkovskii】
ロシアのロケット理論学者。独学で宇宙飛行の理論を研究。主著「ロケットの運動原理」。(1857〜1935)
つい‐か【追加】
①後から増し加えること。また、その加えられたもの。
②連歌・俳諧で、千句・万句などのあとに当季の句を発句とした表一順をつけ加えること。また、そのもの。
⇒ついか‐はいとう【追加配当】
⇒ついか‐よさん【追加予算】
つい‐か【墜下】
下におちること。墜落。落下。
つい‐かい【追悔】‥クワイ
事の終わった後からくやむこと。後悔。
つい‐かい【追懐】‥クワイ
昔の事や人などをあとから思い出してしのぶこと。追憶。追想。「―の情」「故人を―する」
つい‐がき【築垣・築牆】
(ツキカキの音便。ツイカキとも)(→)築地ついじに同じ。
つい‐がさね【衝重】
(ツキガサネの音便)神供じんぐや食器をのせるのに用いる膳具。折敷おしきの下に台をつけたもの。普通、白木を用いる。三方に穴をあけたのを三方さんぼう、四方に穴をあけたのを四方、穴をあけないのを供饗くぎょうという。
衝重
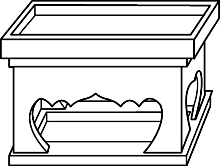 ついか‐はいとう【追加配当】‥タウ
破産手続で、最後の配当の通知を発した後に、新たに配当にあてるべき財産があった時に行う配当。
⇒つい‐か【追加】
ついか‐よさん【追加予算】
「補正予算」参照。
⇒つい‐か【追加】
つい‐かん【追刊】
後から続けて刊行すること。続刊。
つい‐かん【追完】‥クワン
〔法〕追認とほぼ同義に用いられる語。
つい‐がん【追願】‥グワン
ある願いをしている上に、さらに他の願いをあとから出すこと。おいねがい。
ついかん‐ばん【椎間板】
脊柱せきちゅうに連なる椎骨と椎骨との間にある円板状の組織。中心部の髄核と周辺の線維輪から成り、髄核は水分に富むゼリー状、線維輪は線維軟骨。椎間円板。
⇒ついかんばん‐ヘルニア【椎間板ヘルニア】
ついかんばん‐ヘルニア【椎間板ヘルニア】
椎間板の線維輪に変性・損傷があって、髄核が後方に脱出し、脊髄や神経根を圧迫して神経症状を起こす病態。特に下位腰椎に最も多く、この場合、坐骨神経痛の症状を呈する。
⇒ついかん‐ばん【椎間板】
つい‐き【追記】
あとから付け足して、本文のあとに書き加えること。また、その文句。
つい‐き【鎚起】
鍛金たんきんの一技法。金属板を鎚つちで立体的に打ちのばす金工技法。
つい‐きそ【追起訴】
ある事件が第一審裁判所で審理中、検察官がその事件と併合審理を求めるため、同一被告人の別事件をその裁判所に公訴提起すること。
つい‐きゅう【追及】‥キフ
①後から追いかけていっておいつくこと。
②責任などを、どこまでも追い責めること。「余罪を―する」
⇒ついきゅう‐けん【追及権】
つい‐きゅう【追求】‥キウ
(ツイクとも)どこまでも後を追いかけ求めること。「幸福を―する」「利潤の―」
つい‐きゅう【追究】‥キウ
学問などを、尋ねきわめること。追窮。「真理を―する」
つい‐きゅう【追咎】‥キウ
事のすんだ後になってとがめること。
つい‐きゅう【追給】‥キフ
①給与などの不足分や増加分をあとから支給すること。また、その給与。
②不足分をあとから払うこと。追い払い。
つい‐きゅう【追窮】
不確かなことを、どこまでもおしきわめること。追究。
つい‐きゅう【椎弓】
椎骨の椎体の背側から出る橋状の突起。椎孔を囲み、後ろ側・左右・上下に3種7個の突起を出す。棘きょく突起1、横おう突起2、上下の関節突起4。
ついきゅう‐けん【追及権】‥キフ‥
〔法〕物権の特性の一つ。その目的物の所有者または占有者が何人に変わっても、これに追随して行使しうる権能。
⇒つい‐きゅう【追及】
つい‐きょう【追孝】‥ケウ
⇒ついこう
つい‐きん【堆錦】
琉球漆器特有の装飾法。漆と多量の顔料とを混ぜたものを乾燥させて薄くのばし、模様に切り取り成形して、漆器面にはりつける。
つい‐きん【鎚金】
鍛金の一技法。金属を型に当て、または裏面から鏨たがねで打ち出し、表面に文様などを凸起させる。うちだし。
つい‐く【対句】
修辞法の一つ。語の並べ方を同じくし、意味は対ついになる二つ以上の句を連ねて表現すること。また、それらの句。「魚は水に飽かず。魚にあらざれば、その心を知らず。鳥は林をねがふ。鳥にあらざれば、その心を知らず」の類。儷句れいく。
つい‐く【追求】
⇒ついきゅう。〈伊呂波字類抄〉
つい‐く【追駆】
あとから追いかけること。
つい‐くぐ・る【つい潜る】
〔自四〕
(ツイは接頭語)ちょっとくぐる。平家物語4「揚る矢をば―・り」
ツィクルス【Zyklus ドイツ】
(円環・連続・連鎖の意)
①連続演奏会。ある作曲家やあるジャンルの作品を、一定の意図のもとに一連の音楽会で連続して演奏するもの。「ベートーヴェン‐―」
②複数の曲が一定の意図・主題のもとにまとめられて一つの作品となったもの。連作歌曲。シューベルトの「冬の旅」など。
つい‐けい【追啓】
(→)追伸ついしんに同じ。
つい‐げき【追撃】
逃げて行く敵を後から追いかけて撃つこと。おいうち。尾撃。「―をかわす」
つい‐ご【対語】
①漢語の熟語で、事物が相対するように構成されたもの。大小(対比)・桃李(類似)・花鳥(接近)の類。
②(→)対義語に同じ。
つい‐こう【追考】‥カウ
あとから以前の物事について考えること。また、その考え。
つい‐こう【追行】‥カウ
①あとから追いかけること。
②つづいてあとから事を行うこと。
つい‐こう【追孝】‥カウ
(ツイキョウとも)死んだ親などに供養をして孝道を尽くすこと。菩提をとむらうこと。太平記20「一日経を書き供養して、―の作善さぜんをぞ致しける」
つい‐こう【堆紅】
堆朱ついしゅの一種。
つい‐ごう【対合】‥ガフ
〔生〕
⇒たいごう
つい‐ごう【追号】‥ガウ
人が死んだ後に生前の功績をたたえて贈る称号。おくりな。保元物語「―ありて崇徳院とぞ申しける」
つい‐こく【堆黒】
堆朱ついしゅの一種。黒色の漆を主体とするもの。堆烏ついう。
つい‐こつ【椎骨】
脊柱せきちゅうを構成する個々の骨。円柱状の椎体、その背側に延びて椎孔を囲む椎弓およびこれから出ている突起から成り、軟骨(椎間板)で連結されて脊柱を作る。頸椎・胸椎・腰椎・仙椎・尾椎に分かれ、椎孔は上下に連なって長い脊柱管をなし、中に脊髄を入れる。人の場合は32〜34個。
つい‐さ・す【つい挿す】
〔他四〕
(ツイは接頭語)ちょっとさしこむ。枕草子138「上かみに―・しておきたるを」
つい‐し【追思】
あとから過去を思うこと。追想。
つい‐し【追試】
①人の実験したことを、あとからその通りに試みて確かめること。
②追試験の略。
つい‐し【追諡】
死後におくりなを追贈すること。
つい‐し【墜死】
高い所から墜落して死ぬこと。
つい‐し【鎚子】
節会せちえなどに用いた唐菓子の一種。米の粉または小麦粉をこねてサトイモの形に製し、油で揚げたもの。
つい‐じ【築地】‥ヂ
(ツキヒヂ(築泥)の音便ツイヒヂの約)
①土塀の上に屋根を葺ふいたもの。古くは、土を盛り上げて固めただけのものであった。ついがき。ついじべい。えんじ籬まがき。枕草子27「―のくづれ」
築地
ついか‐はいとう【追加配当】‥タウ
破産手続で、最後の配当の通知を発した後に、新たに配当にあてるべき財産があった時に行う配当。
⇒つい‐か【追加】
ついか‐よさん【追加予算】
「補正予算」参照。
⇒つい‐か【追加】
つい‐かん【追刊】
後から続けて刊行すること。続刊。
つい‐かん【追完】‥クワン
〔法〕追認とほぼ同義に用いられる語。
つい‐がん【追願】‥グワン
ある願いをしている上に、さらに他の願いをあとから出すこと。おいねがい。
ついかん‐ばん【椎間板】
脊柱せきちゅうに連なる椎骨と椎骨との間にある円板状の組織。中心部の髄核と周辺の線維輪から成り、髄核は水分に富むゼリー状、線維輪は線維軟骨。椎間円板。
⇒ついかんばん‐ヘルニア【椎間板ヘルニア】
ついかんばん‐ヘルニア【椎間板ヘルニア】
椎間板の線維輪に変性・損傷があって、髄核が後方に脱出し、脊髄や神経根を圧迫して神経症状を起こす病態。特に下位腰椎に最も多く、この場合、坐骨神経痛の症状を呈する。
⇒ついかん‐ばん【椎間板】
つい‐き【追記】
あとから付け足して、本文のあとに書き加えること。また、その文句。
つい‐き【鎚起】
鍛金たんきんの一技法。金属板を鎚つちで立体的に打ちのばす金工技法。
つい‐きそ【追起訴】
ある事件が第一審裁判所で審理中、検察官がその事件と併合審理を求めるため、同一被告人の別事件をその裁判所に公訴提起すること。
つい‐きゅう【追及】‥キフ
①後から追いかけていっておいつくこと。
②責任などを、どこまでも追い責めること。「余罪を―する」
⇒ついきゅう‐けん【追及権】
つい‐きゅう【追求】‥キウ
(ツイクとも)どこまでも後を追いかけ求めること。「幸福を―する」「利潤の―」
つい‐きゅう【追究】‥キウ
学問などを、尋ねきわめること。追窮。「真理を―する」
つい‐きゅう【追咎】‥キウ
事のすんだ後になってとがめること。
つい‐きゅう【追給】‥キフ
①給与などの不足分や増加分をあとから支給すること。また、その給与。
②不足分をあとから払うこと。追い払い。
つい‐きゅう【追窮】
不確かなことを、どこまでもおしきわめること。追究。
つい‐きゅう【椎弓】
椎骨の椎体の背側から出る橋状の突起。椎孔を囲み、後ろ側・左右・上下に3種7個の突起を出す。棘きょく突起1、横おう突起2、上下の関節突起4。
ついきゅう‐けん【追及権】‥キフ‥
〔法〕物権の特性の一つ。その目的物の所有者または占有者が何人に変わっても、これに追随して行使しうる権能。
⇒つい‐きゅう【追及】
つい‐きょう【追孝】‥ケウ
⇒ついこう
つい‐きん【堆錦】
琉球漆器特有の装飾法。漆と多量の顔料とを混ぜたものを乾燥させて薄くのばし、模様に切り取り成形して、漆器面にはりつける。
つい‐きん【鎚金】
鍛金の一技法。金属を型に当て、または裏面から鏨たがねで打ち出し、表面に文様などを凸起させる。うちだし。
つい‐く【対句】
修辞法の一つ。語の並べ方を同じくし、意味は対ついになる二つ以上の句を連ねて表現すること。また、それらの句。「魚は水に飽かず。魚にあらざれば、その心を知らず。鳥は林をねがふ。鳥にあらざれば、その心を知らず」の類。儷句れいく。
つい‐く【追求】
⇒ついきゅう。〈伊呂波字類抄〉
つい‐く【追駆】
あとから追いかけること。
つい‐くぐ・る【つい潜る】
〔自四〕
(ツイは接頭語)ちょっとくぐる。平家物語4「揚る矢をば―・り」
ツィクルス【Zyklus ドイツ】
(円環・連続・連鎖の意)
①連続演奏会。ある作曲家やあるジャンルの作品を、一定の意図のもとに一連の音楽会で連続して演奏するもの。「ベートーヴェン‐―」
②複数の曲が一定の意図・主題のもとにまとめられて一つの作品となったもの。連作歌曲。シューベルトの「冬の旅」など。
つい‐けい【追啓】
(→)追伸ついしんに同じ。
つい‐げき【追撃】
逃げて行く敵を後から追いかけて撃つこと。おいうち。尾撃。「―をかわす」
つい‐ご【対語】
①漢語の熟語で、事物が相対するように構成されたもの。大小(対比)・桃李(類似)・花鳥(接近)の類。
②(→)対義語に同じ。
つい‐こう【追考】‥カウ
あとから以前の物事について考えること。また、その考え。
つい‐こう【追行】‥カウ
①あとから追いかけること。
②つづいてあとから事を行うこと。
つい‐こう【追孝】‥カウ
(ツイキョウとも)死んだ親などに供養をして孝道を尽くすこと。菩提をとむらうこと。太平記20「一日経を書き供養して、―の作善さぜんをぞ致しける」
つい‐こう【堆紅】
堆朱ついしゅの一種。
つい‐ごう【対合】‥ガフ
〔生〕
⇒たいごう
つい‐ごう【追号】‥ガウ
人が死んだ後に生前の功績をたたえて贈る称号。おくりな。保元物語「―ありて崇徳院とぞ申しける」
つい‐こく【堆黒】
堆朱ついしゅの一種。黒色の漆を主体とするもの。堆烏ついう。
つい‐こつ【椎骨】
脊柱せきちゅうを構成する個々の骨。円柱状の椎体、その背側に延びて椎孔を囲む椎弓およびこれから出ている突起から成り、軟骨(椎間板)で連結されて脊柱を作る。頸椎・胸椎・腰椎・仙椎・尾椎に分かれ、椎孔は上下に連なって長い脊柱管をなし、中に脊髄を入れる。人の場合は32〜34個。
つい‐さ・す【つい挿す】
〔他四〕
(ツイは接頭語)ちょっとさしこむ。枕草子138「上かみに―・しておきたるを」
つい‐し【追思】
あとから過去を思うこと。追想。
つい‐し【追試】
①人の実験したことを、あとからその通りに試みて確かめること。
②追試験の略。
つい‐し【追諡】
死後におくりなを追贈すること。
つい‐し【墜死】
高い所から墜落して死ぬこと。
つい‐し【鎚子】
節会せちえなどに用いた唐菓子の一種。米の粉または小麦粉をこねてサトイモの形に製し、油で揚げたもの。
つい‐じ【築地】‥ヂ
(ツキヒヂ(築泥)の音便ツイヒヂの約)
①土塀の上に屋根を葺ふいたもの。古くは、土を盛り上げて固めただけのものであった。ついがき。ついじべい。えんじ籬まがき。枕草子27「―のくづれ」
築地
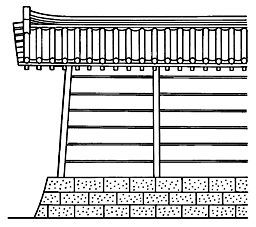 ②(その邸に築地をめぐらしてあったからいう)公家衆くげしゅう。公卿くぎょう。
⇒ついじ‐じょろう【築地女郎】
⇒ついじ‐べい【築地塀】
つい‐しか【終しか】ツヒ‥
〔副〕
ついに。いまだに。たえて。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―お目にはかからねど」
つい‐じく【対軸】‥ヂク
(→)対幅ついふくに同じ。
つい‐しけん【追試験】
病気・事故等のため正規の試験を受けられなかった者や前の試験の不合格者に対して、後で行う試験。追試。
ついじ‐じょろう【築地女郎】‥ヂヂヨラウ
(公家衆に奉公する女の意)貴人の家に奉公する女。
⇒つい‐じ【築地】
つい‐しつ【堆漆】
堆朱ついしゅ・堆黒ついこくなどの総称。
ついじ‐べい【築地塀】‥ヂ‥
(→)築地ついじ1に同じ。
⇒つい‐じ【築地】
つい‐しゅ【追修】
〔仏〕死者の冥福を祈って仏事を修めること。追善。
つい‐しゅ【堆朱】
彫漆の一種。朱漆を幾層にも塗り重ね、その表面に山水・花鳥・人物などを彫り出したもの。宋代以後盛んに行われ、室町時代に日本に渡来。君台観左右帳記「各堆紅・―のほり物なり」→堆黄ついおう→堆黒ついこく。
⇒ついしゅ‐ぞめ【堆朱染】
つい‐じゅう【追従】
人のあとにつき従うこと。「人の意見に―する」→ついしょう(追従)
つい‐じゅく【追熟】
収穫期の脱落などを防ぐため早目に果実を収穫し、あとで完熟させること。後熟。
ついしゅ‐ぞめ【堆朱染】
地を紅染めにし、その上に黒で堆朱文様を染め出したもの。宝暦(1751〜1764)前後に盛行。
⇒つい‐しゅ【堆朱】
つい‐しゅつ【追出】
追い出すこと。平家物語1「外法げほう行ひける聖を―せむとしければ」
つい‐じょ【追叙】
人の死後、叙位・叙勲をすること。
つい‐しょう【追従】
人のあとにつき従うこと。転じて、こびへつらうこと。おべっかをつかうこと。「お―を言う」
⇒ついしょう‐ぐち【追従口】
⇒ついしょう‐わらい【追従笑い】
つい‐しょう【追頌】
人の死後、その功績・善行などをほめあらわすこと。
つい‐しょう【追賞】‥シヤウ
あとから功績を賞すること。
つい‐しょう【追蹤】
①あとをつけて行くこと。追跡。
②過ぎ去った事を思い出すこと。
つい‐じょう【追躡】‥デフ
(「躡」は踏む意)あとから追いかけること。追跡。
⇒ついじょう‐けん【追躡権】
ついしょう‐ぐち【追従口】
こびへつらって言うことば。お世辞。おべっか。
⇒つい‐しょう【追従】
ついじょう‐けん【追躡権】‥デフ‥
(→)追跡権に同じ。
⇒つい‐じょう【追躡】
ついしょう‐わらい【追従笑い】‥ワラヒ
こびへつらって、おかしくもないのに笑うこと。また、そのような笑い。
⇒つい‐しょう【追従】
つい‐しろ【土代】
(ツチシロの転)地上に敷く敷物。皇太神宮儀式帳「―白細布帳一条」
つい‐しん【追申】
①前のにつづいて申請すること。
②⇒ついしん(追伸)
つい‐しん【追伸・追申】
(後から加えて申す意)手紙などで、追記の文。また、そのはじめに書く語。追而書おってがき。なおなお書き。追啓。追白。追陳。二伸。
つい‐じん【追尋】
目的を達しようとして追い求めること。追求。
つい・す【対す】
〔自サ変〕
一対になる。また、対とするに似つかわしい。
つい・ず【序づ・叙づ】ツイヅ
〔他下二〕
次第を立てる。順序を定める。順序よく置く。三蔵法師伝延久点「余を迫せめて以て之を次ツイテしむ」
つい‐ずい【追随】
①あとにつきしたがって行くこと。追従。「―者」
②追いつくこと。「他の―を許さない」
③死者などをあとからしたうこと。追慕。
つい‐す・う【つい据う】
〔他下二〕
(ツイは接頭語)すえおく。さしおく。能因本枕草子たくみの物くふこそ「かはらけは―・ゑつつ」
つい‐すく・う【つい掬ふ】‥スクフ
〔他四〕
(ツイは接頭語)無造作にすくい上げる。狂言、地蔵舞「錫杖を取り直いて、かいすくうてほつたり、―・うてひつたり」
ツイスト【twist】
(「ひねる」「ねじる」の意)
①ビリヤードなどで、球にひねりを与えること。
②脚や腰をねじってする活発な踊り。1960年代初頭にアメリカから流行。
⇒ツイスト‐ドリル【twist drill】
ツイスト‐ドリル【twist drill】
(→)ドリル1に同じ。
⇒ツイスト【twist】
つい‐す・ゆ【つい据ゆ】
〔他下二〕
(ツイスウの転)ちょっと置く。宇治拾遺物語1「雨だれに―・ゆと思ひしに」
つい‐せき【追惜】
死後その人をいたみおしむこと。
つい‐せき【追跡】
①逃げる者のあとを追いかけること。跡をつけること。追蹤ついしょう。追躡ついじょう。
②比喩的に、物事のその後の経過を追うこと。
⇒ついせき‐けん【追跡権】
⇒ついせき‐ちょうさ【追跡調査】
⇒ついせき‐もうそう【追跡妄想】
ついせき‐けん【追跡権】
〔法〕外国船舶が沿岸領海で沿岸国の裁判管轄権に属する犯罪を犯したとき、領海内から軍艦や巡視艇などの公船がこれを追跡し、公海において拿捕だほし得る権利。継続追跡権。
⇒つい‐せき【追跡】
ついせき‐ちょうさ【追跡調査】‥テウ‥
事物の経過を追って継続的に調査すること。
⇒つい‐せき【追跡】
ついせき‐もうそう【追跡妄想】‥マウサウ
いつも自分が追いかけられ、また監視されているように思う妄想。
⇒つい‐せき【追跡】
つい‐ぜん【追善】
死者の冥福を祈るため遺族などが読経・斎会などの善事を行うこと。また、死者の年忌などに仏事を営むこと。追福。追薦。
⇒ついぜん‐がっせん【追善合戦】
⇒ついぜん‐くよう【追善供養】
⇒ついぜん‐こうぎょう【追善興行】
ついぜん‐がっせん【追善合戦】
(→)弔合戦とむらいがっせんに同じ。
⇒つい‐ぜん【追善】
ついぜん‐くよう【追善供養】‥ヤウ
追善のためにする供養。
⇒つい‐ぜん【追善】
ついぜん‐こうぎょう【追善興行】‥ギヤウ
亡くなった役者・芸人などをしのび、その冥福を祈って催す興行。
⇒つい‐ぜん【追善】
つい‐そ【追訴】
はじめの訴えに追加して訴えること。また、その訴え。
つい‐ぞ【終ぞ】ツヒ‥
〔副〕
(下に否定の語を伴う)いまだかつて。いちども。「―見かけない」
つい‐そう【追走】
追いかけて走ること。
つい‐そう【追送】
①すぐあとから送ること。
②あとを見送ること。
つい‐そう【追従】
(ソウはショウの直音化)
⇒ついしょう。源氏物語空蝉「とのゐ人などもことに見いれ―せず」
つい‐そう【追崇】
(→)追尊ついそんに同じ。
つい‐そう【追想】‥サウ
過去の事や去った人のことを思い出してしのぶこと。「若き日を―する」
つい‐ぞう【追増】
あとから加え足すこと。追加。
つい‐ぞう【追贈】
死後に官位・勲章などを贈ること。
つい‐そん【追尊】
死後に尊号を贈ること。
⇒ついそん‐てんのう【追尊天皇】
ついそん‐てんのう【追尊天皇】‥ワウ
帝位につかない親王に、その没後に天皇号を追贈したもの。歴代に加えない。崇道すどう天皇(光仁天皇の皇子早良さわら親王)の類。
⇒つい‐そん【追尊】
つい‐たい【椎体】
椎骨の中央にある円筒状の部分。
つい‐たいけん【追体験】
(Nacherleben ドイツ)他人の体験をあとからなぞり、自分の体験のようにとらえること。
つい‐たけ【対丈】
(ツキタケ(衝丈)の音便か)身の丈と同じに布地を裁って着物を仕立てること。仮名文章娘節用「ひとへものに―の襦袢」
つい‐たち【朔日・朔・一日】
(ツキタチ(月立)の音便。こもっていた月が出はじめる意)
①西方の空に、日の入ったあと、月がほのかに見えはじめる日を初めとして、それから10日ばかりの間の称。(陰暦の)月の初め。上旬。初旬。伊勢物語「時はやよひの―、雨そほふるに」
②月の第一日。いちじつ。古くは「ついたちの日」ということが多い。蜻蛉日記下「閏二月の―の日、雨のどかなり」
③特に、正月一日。元日。紫式部日記「ことしの―、御まかなひ、宰相の君」
⇒ついたち‐がん【朔日丸】
⇒ついたち‐そう【朔日草】
⇒ついたち‐ぶり【朔日降り】
⇒ついたち‐みち【朔日路】
ついたち‐がん【朔日丸】‥グワン
女が毎月朔日に飲めば孕はらまないといわれた丸薬。江戸四つ目屋発売。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐そう【朔日草】‥サウ
福寿草の異称。新年を祝う花として元旦に用いる。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐そうじ【衝立障子】‥サウ‥
(ツイタチショウジとも)(→)「ついたてそうじ」に同じ。古今著聞集11「清涼殿の弘廂に―を立てて」
ついたち‐ぶり【朔日降り】
月の第1日に雨の降ること。俗に、その月は雨が多いという。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐みち【朔日路】
盆路ぼんみちのこと。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
つい‐た・つ【つい立つ】
〔自四〕
(ツイは接頭語)さっと立つ。突然立つ。ちょっと立つ。平家物語4「ちつとも騒がず―・つて」
つい‐だつ【追奪】
①追いかけて奪うこと。
②死後に生前の官位などを取り上げること。
③〔法〕いったん他人の権利に属したものを、自己の権利を主張して取りもどすこと。
⇒ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
〔法〕主に売買の目的物に権利の瑕疵かしがあった場合に買主が追及しうる売主の責任、すなわち損害賠償や代金減額の請求または契約の解除。
⇒つい‐だつ【追奪】
つい‐たて【衝立】
衝立障子ついたてそうじの略。
⇒ついたて‐しょうじ【衝立障子】
⇒ついたて‐そうじ【衝立障子】
ついたて‐しょうじ【衝立障子】‥シヤウ‥
⇒ついたてそうじ。
⇒つい‐たて【衝立】
ついたて‐そうじ【衝立障子】‥サウ‥
(ツイタテショウジとも)屏障具へいしょうぐの一つ。1枚の襖ふすま障子または板障子に、移動しやすいように台をつけたもの。平安時代から宮中や寝殿に用いられ、後世では玄関・座敷などに立てて隔てとする。清涼殿の昆明池こんめいちの障子、年中行事の障子など。
⇒つい‐たて【衝立】
つい‐だんな【吊手綱】
(タンナはタヅナの訛)越中褌えっちゅうふんどし。ついだん。つりだんな。
つい‐ちく【追逐】
①あとを追いかけること。
②追いはらうこと。
③追いつ追われつすること。
④互いに相伴うこと。
つい‐ちょう【追弔】‥テウ
死後にその生前をしのびとむらうこと。
⇒ついちょう‐え【追弔会】
つい‐ちょう【追徴】
①税金などの公課を追加して取り立てること。あとから不足額を取り立てること。
②刑法上、没収すべき物を没収できないときに、その物の価額の納付を強制すること。
⇒ついちょう‐きん【追徴金】
ついちょう‐え【追弔会】‥テウヱ
追弔のために催す法会。
⇒つい‐ちょう【追弔】
ついちょう‐きん【追徴金】
追徴として取り立てる金銭。
⇒つい‐ちょう【追徴】
つい‐ちん【追陳】
追記の語。追伸。
つい‐つい
〔副〕
(副詞「つい」を重ねた語)そうするつもりではないのに。思いに反して。「―食べてしまう」
つい‐て【就いて】
(ツキテの音便)
①…に関して。「あなたに―何も知らない」
②…ごとに。「一回に―千円の罰金」
→つく(就)[一]➒。
⇒ついて‐は【就いては】
ついで【序で】
(ツイヅの連用形から)
①順序。次第。順番。宇津保物語藤原君「物は―を越さずいでたちつべきものなり」
②よいおり。機会。あることを併せてするよい機会。源氏物語桐壺「かくても、おのづから、若宮など生ひ出でたまはば、さるべき―もありなむ」。「お―の節」
⇒ついで‐な・し【序で無し】
⇒ついで‐に【序でに】
つい‐で【次いで・尋いで】
(ツギテの音便)
[一]〔副〕
つづいて。ほどなく。まもなく。「はじめに上下動が、―横揺れが来た」
[二]〔接続〕
次に。それから。三蔵法師伝永久点「尋ツイテ詔を下して翻訳せしむることを賜ふことを蒙れり」。「―第二部がはじまった」
ついで‐な・し【序で無し】
〔形ク〕
きっかけがない。突然だ。徒然草「人に物を取らせたるも、―・くてこれを奉らんと言ひたる」
⇒ついで【序で】
ついで‐に【序でに】
そのおりに。その場合に。その機会に乗じて。「近くに来た―寄った」「―言えば」
⇒ついで【序で】
ついて‐は【就いては】
〔接続〕
したがって。よって。それゆえに。
⇒つい‐て【就いて】
ついて‐まわ・る【付いて回る】‥マハル
〔自五〕
離れずにいっしょに動く。つきまとう。「悪評がどこまでも―・る」
つい‐てる
(ツイテイルの約)運が向いている。つきがある。→つく(付く)[一]➎7
つい‐と
〔副〕
①いきなり。つと。ずいと。「―立ち上がる」
②はやく通りすぎるさま。つっと。
つい‐どツヒ‥
〔副〕
(「ついぞ」の転)いまだかつて。めったに。浮世草子、好色産毛「―見ぬきたない女」
つい‐とう【追討】‥タウ
賊徒などを追いかけて征伐すること。討手うってを差し向けて討ち取ること。「―使」
つい‐とう【追悼】‥タウ
死者をしのんで、いたみ悲しむこと。「事故犠牲者を―する」「―会」
つい‐どう【隧道】‥ダウ
スイドウの誤読。
つい‐とおり【つい通り】‥トホリ
なみ。普通。体源抄「―の説は用なり」
つい‐とつ【追突】
(乗物などが)後ろから衝突すること。「―事故」
つ‐いな【都維那】‥ヰ‥
〔仏〕(→)維那いなに同じ。
つい‐な【追儺】
宮中の年中行事の一つ。大晦日の夜、悪鬼を払い疫病を除く儀式。舎人とねりの鬼に扮装した者を、内裏の四門をめぐって追いまわす。大舎人長が鬼を払う方相氏ほうそうしの役をつとめ、黄金四つ目の仮面をかぶり、黒衣朱裳を着し、手に矛・楯を執った。これを大儺たいなといい、紺の布衣に緋の抹額まっこうを着けて大儺に従って駆けまわる童子を小儺しょうなとよぶ。殿上人は桃の弓、葦の矢で鬼を射る。古く中国に始まり、日本には8世紀初め頃、文武天皇の時に伝わったといわれ、社寺・民間にも行われた。近世、民間では、節分の行事となる。「おにやらい」「なやらい」とも。〈[季]冬〉
追儺
②(その邸に築地をめぐらしてあったからいう)公家衆くげしゅう。公卿くぎょう。
⇒ついじ‐じょろう【築地女郎】
⇒ついじ‐べい【築地塀】
つい‐しか【終しか】ツヒ‥
〔副〕
ついに。いまだに。たえて。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―お目にはかからねど」
つい‐じく【対軸】‥ヂク
(→)対幅ついふくに同じ。
つい‐しけん【追試験】
病気・事故等のため正規の試験を受けられなかった者や前の試験の不合格者に対して、後で行う試験。追試。
ついじ‐じょろう【築地女郎】‥ヂヂヨラウ
(公家衆に奉公する女の意)貴人の家に奉公する女。
⇒つい‐じ【築地】
つい‐しつ【堆漆】
堆朱ついしゅ・堆黒ついこくなどの総称。
ついじ‐べい【築地塀】‥ヂ‥
(→)築地ついじ1に同じ。
⇒つい‐じ【築地】
つい‐しゅ【追修】
〔仏〕死者の冥福を祈って仏事を修めること。追善。
つい‐しゅ【堆朱】
彫漆の一種。朱漆を幾層にも塗り重ね、その表面に山水・花鳥・人物などを彫り出したもの。宋代以後盛んに行われ、室町時代に日本に渡来。君台観左右帳記「各堆紅・―のほり物なり」→堆黄ついおう→堆黒ついこく。
⇒ついしゅ‐ぞめ【堆朱染】
つい‐じゅう【追従】
人のあとにつき従うこと。「人の意見に―する」→ついしょう(追従)
つい‐じゅく【追熟】
収穫期の脱落などを防ぐため早目に果実を収穫し、あとで完熟させること。後熟。
ついしゅ‐ぞめ【堆朱染】
地を紅染めにし、その上に黒で堆朱文様を染め出したもの。宝暦(1751〜1764)前後に盛行。
⇒つい‐しゅ【堆朱】
つい‐しゅつ【追出】
追い出すこと。平家物語1「外法げほう行ひける聖を―せむとしければ」
つい‐じょ【追叙】
人の死後、叙位・叙勲をすること。
つい‐しょう【追従】
人のあとにつき従うこと。転じて、こびへつらうこと。おべっかをつかうこと。「お―を言う」
⇒ついしょう‐ぐち【追従口】
⇒ついしょう‐わらい【追従笑い】
つい‐しょう【追頌】
人の死後、その功績・善行などをほめあらわすこと。
つい‐しょう【追賞】‥シヤウ
あとから功績を賞すること。
つい‐しょう【追蹤】
①あとをつけて行くこと。追跡。
②過ぎ去った事を思い出すこと。
つい‐じょう【追躡】‥デフ
(「躡」は踏む意)あとから追いかけること。追跡。
⇒ついじょう‐けん【追躡権】
ついしょう‐ぐち【追従口】
こびへつらって言うことば。お世辞。おべっか。
⇒つい‐しょう【追従】
ついじょう‐けん【追躡権】‥デフ‥
(→)追跡権に同じ。
⇒つい‐じょう【追躡】
ついしょう‐わらい【追従笑い】‥ワラヒ
こびへつらって、おかしくもないのに笑うこと。また、そのような笑い。
⇒つい‐しょう【追従】
つい‐しろ【土代】
(ツチシロの転)地上に敷く敷物。皇太神宮儀式帳「―白細布帳一条」
つい‐しん【追申】
①前のにつづいて申請すること。
②⇒ついしん(追伸)
つい‐しん【追伸・追申】
(後から加えて申す意)手紙などで、追記の文。また、そのはじめに書く語。追而書おってがき。なおなお書き。追啓。追白。追陳。二伸。
つい‐じん【追尋】
目的を達しようとして追い求めること。追求。
つい・す【対す】
〔自サ変〕
一対になる。また、対とするに似つかわしい。
つい・ず【序づ・叙づ】ツイヅ
〔他下二〕
次第を立てる。順序を定める。順序よく置く。三蔵法師伝延久点「余を迫せめて以て之を次ツイテしむ」
つい‐ずい【追随】
①あとにつきしたがって行くこと。追従。「―者」
②追いつくこと。「他の―を許さない」
③死者などをあとからしたうこと。追慕。
つい‐す・う【つい据う】
〔他下二〕
(ツイは接頭語)すえおく。さしおく。能因本枕草子たくみの物くふこそ「かはらけは―・ゑつつ」
つい‐すく・う【つい掬ふ】‥スクフ
〔他四〕
(ツイは接頭語)無造作にすくい上げる。狂言、地蔵舞「錫杖を取り直いて、かいすくうてほつたり、―・うてひつたり」
ツイスト【twist】
(「ひねる」「ねじる」の意)
①ビリヤードなどで、球にひねりを与えること。
②脚や腰をねじってする活発な踊り。1960年代初頭にアメリカから流行。
⇒ツイスト‐ドリル【twist drill】
ツイスト‐ドリル【twist drill】
(→)ドリル1に同じ。
⇒ツイスト【twist】
つい‐す・ゆ【つい据ゆ】
〔他下二〕
(ツイスウの転)ちょっと置く。宇治拾遺物語1「雨だれに―・ゆと思ひしに」
つい‐せき【追惜】
死後その人をいたみおしむこと。
つい‐せき【追跡】
①逃げる者のあとを追いかけること。跡をつけること。追蹤ついしょう。追躡ついじょう。
②比喩的に、物事のその後の経過を追うこと。
⇒ついせき‐けん【追跡権】
⇒ついせき‐ちょうさ【追跡調査】
⇒ついせき‐もうそう【追跡妄想】
ついせき‐けん【追跡権】
〔法〕外国船舶が沿岸領海で沿岸国の裁判管轄権に属する犯罪を犯したとき、領海内から軍艦や巡視艇などの公船がこれを追跡し、公海において拿捕だほし得る権利。継続追跡権。
⇒つい‐せき【追跡】
ついせき‐ちょうさ【追跡調査】‥テウ‥
事物の経過を追って継続的に調査すること。
⇒つい‐せき【追跡】
ついせき‐もうそう【追跡妄想】‥マウサウ
いつも自分が追いかけられ、また監視されているように思う妄想。
⇒つい‐せき【追跡】
つい‐ぜん【追善】
死者の冥福を祈るため遺族などが読経・斎会などの善事を行うこと。また、死者の年忌などに仏事を営むこと。追福。追薦。
⇒ついぜん‐がっせん【追善合戦】
⇒ついぜん‐くよう【追善供養】
⇒ついぜん‐こうぎょう【追善興行】
ついぜん‐がっせん【追善合戦】
(→)弔合戦とむらいがっせんに同じ。
⇒つい‐ぜん【追善】
ついぜん‐くよう【追善供養】‥ヤウ
追善のためにする供養。
⇒つい‐ぜん【追善】
ついぜん‐こうぎょう【追善興行】‥ギヤウ
亡くなった役者・芸人などをしのび、その冥福を祈って催す興行。
⇒つい‐ぜん【追善】
つい‐そ【追訴】
はじめの訴えに追加して訴えること。また、その訴え。
つい‐ぞ【終ぞ】ツヒ‥
〔副〕
(下に否定の語を伴う)いまだかつて。いちども。「―見かけない」
つい‐そう【追走】
追いかけて走ること。
つい‐そう【追送】
①すぐあとから送ること。
②あとを見送ること。
つい‐そう【追従】
(ソウはショウの直音化)
⇒ついしょう。源氏物語空蝉「とのゐ人などもことに見いれ―せず」
つい‐そう【追崇】
(→)追尊ついそんに同じ。
つい‐そう【追想】‥サウ
過去の事や去った人のことを思い出してしのぶこと。「若き日を―する」
つい‐ぞう【追増】
あとから加え足すこと。追加。
つい‐ぞう【追贈】
死後に官位・勲章などを贈ること。
つい‐そん【追尊】
死後に尊号を贈ること。
⇒ついそん‐てんのう【追尊天皇】
ついそん‐てんのう【追尊天皇】‥ワウ
帝位につかない親王に、その没後に天皇号を追贈したもの。歴代に加えない。崇道すどう天皇(光仁天皇の皇子早良さわら親王)の類。
⇒つい‐そん【追尊】
つい‐たい【椎体】
椎骨の中央にある円筒状の部分。
つい‐たいけん【追体験】
(Nacherleben ドイツ)他人の体験をあとからなぞり、自分の体験のようにとらえること。
つい‐たけ【対丈】
(ツキタケ(衝丈)の音便か)身の丈と同じに布地を裁って着物を仕立てること。仮名文章娘節用「ひとへものに―の襦袢」
つい‐たち【朔日・朔・一日】
(ツキタチ(月立)の音便。こもっていた月が出はじめる意)
①西方の空に、日の入ったあと、月がほのかに見えはじめる日を初めとして、それから10日ばかりの間の称。(陰暦の)月の初め。上旬。初旬。伊勢物語「時はやよひの―、雨そほふるに」
②月の第一日。いちじつ。古くは「ついたちの日」ということが多い。蜻蛉日記下「閏二月の―の日、雨のどかなり」
③特に、正月一日。元日。紫式部日記「ことしの―、御まかなひ、宰相の君」
⇒ついたち‐がん【朔日丸】
⇒ついたち‐そう【朔日草】
⇒ついたち‐ぶり【朔日降り】
⇒ついたち‐みち【朔日路】
ついたち‐がん【朔日丸】‥グワン
女が毎月朔日に飲めば孕はらまないといわれた丸薬。江戸四つ目屋発売。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐そう【朔日草】‥サウ
福寿草の異称。新年を祝う花として元旦に用いる。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐そうじ【衝立障子】‥サウ‥
(ツイタチショウジとも)(→)「ついたてそうじ」に同じ。古今著聞集11「清涼殿の弘廂に―を立てて」
ついたち‐ぶり【朔日降り】
月の第1日に雨の降ること。俗に、その月は雨が多いという。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐みち【朔日路】
盆路ぼんみちのこと。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
つい‐た・つ【つい立つ】
〔自四〕
(ツイは接頭語)さっと立つ。突然立つ。ちょっと立つ。平家物語4「ちつとも騒がず―・つて」
つい‐だつ【追奪】
①追いかけて奪うこと。
②死後に生前の官位などを取り上げること。
③〔法〕いったん他人の権利に属したものを、自己の権利を主張して取りもどすこと。
⇒ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
〔法〕主に売買の目的物に権利の瑕疵かしがあった場合に買主が追及しうる売主の責任、すなわち損害賠償や代金減額の請求または契約の解除。
⇒つい‐だつ【追奪】
つい‐たて【衝立】
衝立障子ついたてそうじの略。
⇒ついたて‐しょうじ【衝立障子】
⇒ついたて‐そうじ【衝立障子】
ついたて‐しょうじ【衝立障子】‥シヤウ‥
⇒ついたてそうじ。
⇒つい‐たて【衝立】
ついたて‐そうじ【衝立障子】‥サウ‥
(ツイタテショウジとも)屏障具へいしょうぐの一つ。1枚の襖ふすま障子または板障子に、移動しやすいように台をつけたもの。平安時代から宮中や寝殿に用いられ、後世では玄関・座敷などに立てて隔てとする。清涼殿の昆明池こんめいちの障子、年中行事の障子など。
⇒つい‐たて【衝立】
つい‐だんな【吊手綱】
(タンナはタヅナの訛)越中褌えっちゅうふんどし。ついだん。つりだんな。
つい‐ちく【追逐】
①あとを追いかけること。
②追いはらうこと。
③追いつ追われつすること。
④互いに相伴うこと。
つい‐ちょう【追弔】‥テウ
死後にその生前をしのびとむらうこと。
⇒ついちょう‐え【追弔会】
つい‐ちょう【追徴】
①税金などの公課を追加して取り立てること。あとから不足額を取り立てること。
②刑法上、没収すべき物を没収できないときに、その物の価額の納付を強制すること。
⇒ついちょう‐きん【追徴金】
ついちょう‐え【追弔会】‥テウヱ
追弔のために催す法会。
⇒つい‐ちょう【追弔】
ついちょう‐きん【追徴金】
追徴として取り立てる金銭。
⇒つい‐ちょう【追徴】
つい‐ちん【追陳】
追記の語。追伸。
つい‐つい
〔副〕
(副詞「つい」を重ねた語)そうするつもりではないのに。思いに反して。「―食べてしまう」
つい‐て【就いて】
(ツキテの音便)
①…に関して。「あなたに―何も知らない」
②…ごとに。「一回に―千円の罰金」
→つく(就)[一]➒。
⇒ついて‐は【就いては】
ついで【序で】
(ツイヅの連用形から)
①順序。次第。順番。宇津保物語藤原君「物は―を越さずいでたちつべきものなり」
②よいおり。機会。あることを併せてするよい機会。源氏物語桐壺「かくても、おのづから、若宮など生ひ出でたまはば、さるべき―もありなむ」。「お―の節」
⇒ついで‐な・し【序で無し】
⇒ついで‐に【序でに】
つい‐で【次いで・尋いで】
(ツギテの音便)
[一]〔副〕
つづいて。ほどなく。まもなく。「はじめに上下動が、―横揺れが来た」
[二]〔接続〕
次に。それから。三蔵法師伝永久点「尋ツイテ詔を下して翻訳せしむることを賜ふことを蒙れり」。「―第二部がはじまった」
ついで‐な・し【序で無し】
〔形ク〕
きっかけがない。突然だ。徒然草「人に物を取らせたるも、―・くてこれを奉らんと言ひたる」
⇒ついで【序で】
ついで‐に【序でに】
そのおりに。その場合に。その機会に乗じて。「近くに来た―寄った」「―言えば」
⇒ついで【序で】
ついて‐は【就いては】
〔接続〕
したがって。よって。それゆえに。
⇒つい‐て【就いて】
ついて‐まわ・る【付いて回る】‥マハル
〔自五〕
離れずにいっしょに動く。つきまとう。「悪評がどこまでも―・る」
つい‐てる
(ツイテイルの約)運が向いている。つきがある。→つく(付く)[一]➎7
つい‐と
〔副〕
①いきなり。つと。ずいと。「―立ち上がる」
②はやく通りすぎるさま。つっと。
つい‐どツヒ‥
〔副〕
(「ついぞ」の転)いまだかつて。めったに。浮世草子、好色産毛「―見ぬきたない女」
つい‐とう【追討】‥タウ
賊徒などを追いかけて征伐すること。討手うってを差し向けて討ち取ること。「―使」
つい‐とう【追悼】‥タウ
死者をしのんで、いたみ悲しむこと。「事故犠牲者を―する」「―会」
つい‐どう【隧道】‥ダウ
スイドウの誤読。
つい‐とおり【つい通り】‥トホリ
なみ。普通。体源抄「―の説は用なり」
つい‐とつ【追突】
(乗物などが)後ろから衝突すること。「―事故」
つ‐いな【都維那】‥ヰ‥
〔仏〕(→)維那いなに同じ。
つい‐な【追儺】
宮中の年中行事の一つ。大晦日の夜、悪鬼を払い疫病を除く儀式。舎人とねりの鬼に扮装した者を、内裏の四門をめぐって追いまわす。大舎人長が鬼を払う方相氏ほうそうしの役をつとめ、黄金四つ目の仮面をかぶり、黒衣朱裳を着し、手に矛・楯を執った。これを大儺たいなといい、紺の布衣に緋の抹額まっこうを着けて大儺に従って駆けまわる童子を小儺しょうなとよぶ。殿上人は桃の弓、葦の矢で鬼を射る。古く中国に始まり、日本には8世紀初め頃、文武天皇の時に伝わったといわれ、社寺・民間にも行われた。近世、民間では、節分の行事となる。「おにやらい」「なやらい」とも。〈[季]冬〉
追儺
 つい‐に【終に・遂に】ツヒニ
〔副〕
(一説に、ツヒユ(衰える・潰れる意)と同源かという)
①おわりに。しまいに。とうとう。結局。万葉集3「生ける者―も死ぬるものにあれば」。「―日の目を見た」
②(下に否定を伴って)いまもって。いまだに。ついぞ。好色一代女2「島原の門口に―見ぬ図なることあり」
つい‐にん【追認】
①過去にさかのぼって事実を認めること。
②〔法〕いったん為された不完全な法律行為を後から確定的に有効にする一方的意思表示。
つい‐ねん【追年】
年を追って進むこと。逐年。
つい‐ねん【追念】
①過去の事を思い出すこと。追思。
②残念に思うこと。くやしく思うこと。太平記34「旧主先帝の御―をも休めまゐらせらるべき」
つい‐のう【追納】‥ナフ
不足額をあとから追加して納めること。
つい‐の‐こと【終の事】ツヒ‥
結局はそうなること。落ち着くこと。結末。源氏物語夕霧「なだらかならむのみこそ、人は―には侍るめれ」
つい‐の‐すみか【終の住処・終の栖】ツヒ‥
終生住んでいるべきところ。また、最後にすむ所。死後に落ち着く所。「これがまあ―か雪五尺」(一茶)
つい‐の‐みち【終の道】ツヒ‥
人が最後にゆく道。死出の道。
つい‐の・る【つい乗る】
〔自四〕
(ツイは接頭語)すぐ乗る。急ぎ乗る。狂言、宝の槌「此馬に馬道具そへて―・るやうにして打ちいだすほどに」
つい‐の‐わかれ【終の別れ】ツヒ‥
最後の別れ。死にわかれ。源氏物語椎本「世のこととして―をのがれぬわざなめれど」
つい‐は【終は】ツヒ‥
〔副〕
ついには。しまいには。
つい‐はく【追白】
(「白」は申す意)(→)追伸ついしんに同じ。
つい‐ばつ【追罰】
①あとから更に罰すること。
②追討。太平記2「事停滞して武家―の宣旨を下されなば」
つい‐ば・む【啄む】
〔他五〕
(ツキハムの音便。古くはツイハム)(鳥が)くちばしで物をつついて食う。今昔物語集9「鳥、…面・眼を―・みうがちて」。「餌を―・む」
つい‐はり【突い張り】
(ツキハリの音便)(→)「つっぱり」に同じ。狂言、腰祈「うしろから―をめされい」
つい‐ひ【追肥】
おいごえ。補肥ほひ。「―を施す」
つい‐ひ【追賁】
(「賁」は飾る意)死後に供養してその功徳を飾ること。追善。太平記20「更に称名読経の―をもなすべからず」
つい‐び【追尾】
①あとをつけて行くこと。追跡。「ミサイルが敵機を―する」
②電報指定事項の一つ。受信人が指定の住所に不在の場合、その居所を追って手渡す手続。
つい‐ひじ【築泥】‥ヒヂ
⇒ついじ(築地)。伊勢物語「童べの踏みあけたる―のくづれより通ひけり」
つい‐びな【対雛】
男女一対のひな。めおとびな。
つい‐ひらが・る【つい平がる】
〔自四〕
(ツイは接頭語)平たくなる。はいつくばる。ひれふす。宇治拾遺物語12「虎、人の香をかぎて、―・りて猫の鼠をうかがふやうにてあるを」
つい‐ぶ【追捕】
(ツイフ・ツイホ・ツイフクとも)
①悪者を追いかけて捕らえること。
②没収すること。奪い取ること。
⇒ついぶ‐し【追捕使】
つい‐ふく【対幅】
一対になっている書画の幅。双幅。対軸。
つい‐ふく【追捕】
⇒ついぶ。天草本平家物語「やがて―の官人が参つて資財雑具をも奪ひ取り」
⇒ついふく‐し【追捕使】
つい‐ふく【追福】
(→)追善ついぜんに同じ。
つい‐ふく【追腹】
主君の死を悲しみ臣下がそのあとを追って切腹すること。おいばら。
ついふく‐きょく【追復曲】
〔音〕カノンの訳語。
ついふく‐し【追捕使】
⇒ついぶし
⇒つい‐ふく【追捕】
ついぶ‐し【追捕使】
(ツイフシとも)平安時代、凶徒を逮捕するために補任された令外りょうげの官。国ごとに国司が国内の武勇の者を選んで任じた。ほかに、反乱鎮圧のため、中央から臨時に派遣された場合もある。押領使おうりょうしとほぼ同じ。
⇒つい‐ぶ【追捕】
つい‐ほ【追捕】
⇒ついぶ
つい‐ほ【追補】
出版・著作物などで、追加・訂正する事柄を、あとから補うこと。補遺。
つい‐ぼ【追慕】
死んだ人や遠く去って二度とあえない人を思い出して、恋しく思うこと。「―の念がつのる」
つい‐ほう【追放】‥ハウ
①おいはなつこと。おい払うこと。放逐。今昔物語集29「言ふ甲斐なし。速に―せられよ」。「汚職―」
②犯罪者を一定地域外に放逐する刑。江戸時代には所払ところばらい・江戸払・江戸追放・軽追放・中追放・重追放などがあった。庶民は軽・中・重追放のいずれも江戸十里四方・犯罪地・住国からの追放とし、付加刑の闕所けっしょの範囲だけが異なっていた。構かまえ。
③〔法〕一国において、その在留が危険であると認める自国人もしくは外国人、あるいは正規の手続によらない入国者に対して、国外退去を命ずること。
④一定の理由をもって、公職・教職などからしりぞけること。パージ。
つい‐まち【対待】
物干し竿を渡す2本の柱。
つい‐まつ【続松】
(ツギマツの音便)
①松明たいまつ。
②(歌の上の句に1の炭で下の句を書き継いだ伊勢物語の故事から)歌ガルタや歌貝の、和歌の上下の句を合わせる遊び。偐にせ紫田舎源氏「―、十種香、貝おほひ、様々遊びを仕尽して」
⇒ついまつ‐とり【続松取】
ついまつ‐とり【続松取】
歌ガルタあるいは歌貝を取ってする勝負ごと。
⇒つい‐まつ【続松】
つい‐に【終に・遂に】ツヒニ
〔副〕
(一説に、ツヒユ(衰える・潰れる意)と同源かという)
①おわりに。しまいに。とうとう。結局。万葉集3「生ける者―も死ぬるものにあれば」。「―日の目を見た」
②(下に否定を伴って)いまもって。いまだに。ついぞ。好色一代女2「島原の門口に―見ぬ図なることあり」
つい‐にん【追認】
①過去にさかのぼって事実を認めること。
②〔法〕いったん為された不完全な法律行為を後から確定的に有効にする一方的意思表示。
つい‐ねん【追年】
年を追って進むこと。逐年。
つい‐ねん【追念】
①過去の事を思い出すこと。追思。
②残念に思うこと。くやしく思うこと。太平記34「旧主先帝の御―をも休めまゐらせらるべき」
つい‐のう【追納】‥ナフ
不足額をあとから追加して納めること。
つい‐の‐こと【終の事】ツヒ‥
結局はそうなること。落ち着くこと。結末。源氏物語夕霧「なだらかならむのみこそ、人は―には侍るめれ」
つい‐の‐すみか【終の住処・終の栖】ツヒ‥
終生住んでいるべきところ。また、最後にすむ所。死後に落ち着く所。「これがまあ―か雪五尺」(一茶)
つい‐の‐みち【終の道】ツヒ‥
人が最後にゆく道。死出の道。
つい‐の・る【つい乗る】
〔自四〕
(ツイは接頭語)すぐ乗る。急ぎ乗る。狂言、宝の槌「此馬に馬道具そへて―・るやうにして打ちいだすほどに」
つい‐の‐わかれ【終の別れ】ツヒ‥
最後の別れ。死にわかれ。源氏物語椎本「世のこととして―をのがれぬわざなめれど」
つい‐は【終は】ツヒ‥
〔副〕
ついには。しまいには。
つい‐はく【追白】
(「白」は申す意)(→)追伸ついしんに同じ。
つい‐ばつ【追罰】
①あとから更に罰すること。
②追討。太平記2「事停滞して武家―の宣旨を下されなば」
つい‐ば・む【啄む】
〔他五〕
(ツキハムの音便。古くはツイハム)(鳥が)くちばしで物をつついて食う。今昔物語集9「鳥、…面・眼を―・みうがちて」。「餌を―・む」
つい‐はり【突い張り】
(ツキハリの音便)(→)「つっぱり」に同じ。狂言、腰祈「うしろから―をめされい」
つい‐ひ【追肥】
おいごえ。補肥ほひ。「―を施す」
つい‐ひ【追賁】
(「賁」は飾る意)死後に供養してその功徳を飾ること。追善。太平記20「更に称名読経の―をもなすべからず」
つい‐び【追尾】
①あとをつけて行くこと。追跡。「ミサイルが敵機を―する」
②電報指定事項の一つ。受信人が指定の住所に不在の場合、その居所を追って手渡す手続。
つい‐ひじ【築泥】‥ヒヂ
⇒ついじ(築地)。伊勢物語「童べの踏みあけたる―のくづれより通ひけり」
つい‐びな【対雛】
男女一対のひな。めおとびな。
つい‐ひらが・る【つい平がる】
〔自四〕
(ツイは接頭語)平たくなる。はいつくばる。ひれふす。宇治拾遺物語12「虎、人の香をかぎて、―・りて猫の鼠をうかがふやうにてあるを」
つい‐ぶ【追捕】
(ツイフ・ツイホ・ツイフクとも)
①悪者を追いかけて捕らえること。
②没収すること。奪い取ること。
⇒ついぶ‐し【追捕使】
つい‐ふく【対幅】
一対になっている書画の幅。双幅。対軸。
つい‐ふく【追捕】
⇒ついぶ。天草本平家物語「やがて―の官人が参つて資財雑具をも奪ひ取り」
⇒ついふく‐し【追捕使】
つい‐ふく【追福】
(→)追善ついぜんに同じ。
つい‐ふく【追腹】
主君の死を悲しみ臣下がそのあとを追って切腹すること。おいばら。
ついふく‐きょく【追復曲】
〔音〕カノンの訳語。
ついふく‐し【追捕使】
⇒ついぶし
⇒つい‐ふく【追捕】
ついぶ‐し【追捕使】
(ツイフシとも)平安時代、凶徒を逮捕するために補任された令外りょうげの官。国ごとに国司が国内の武勇の者を選んで任じた。ほかに、反乱鎮圧のため、中央から臨時に派遣された場合もある。押領使おうりょうしとほぼ同じ。
⇒つい‐ぶ【追捕】
つい‐ほ【追捕】
⇒ついぶ
つい‐ほ【追補】
出版・著作物などで、追加・訂正する事柄を、あとから補うこと。補遺。
つい‐ぼ【追慕】
死んだ人や遠く去って二度とあえない人を思い出して、恋しく思うこと。「―の念がつのる」
つい‐ほう【追放】‥ハウ
①おいはなつこと。おい払うこと。放逐。今昔物語集29「言ふ甲斐なし。速に―せられよ」。「汚職―」
②犯罪者を一定地域外に放逐する刑。江戸時代には所払ところばらい・江戸払・江戸追放・軽追放・中追放・重追放などがあった。庶民は軽・中・重追放のいずれも江戸十里四方・犯罪地・住国からの追放とし、付加刑の闕所けっしょの範囲だけが異なっていた。構かまえ。
③〔法〕一国において、その在留が危険であると認める自国人もしくは外国人、あるいは正規の手続によらない入国者に対して、国外退去を命ずること。
④一定の理由をもって、公職・教職などからしりぞけること。パージ。
つい‐まち【対待】
物干し竿を渡す2本の柱。
つい‐まつ【続松】
(ツギマツの音便)
①松明たいまつ。
②(歌の上の句に1の炭で下の句を書き継いだ伊勢物語の故事から)歌ガルタや歌貝の、和歌の上下の句を合わせる遊び。偐にせ紫田舎源氏「―、十種香、貝おほひ、様々遊びを仕尽して」
⇒ついまつ‐とり【続松取】
ついまつ‐とり【続松取】
歌ガルタあるいは歌貝を取ってする勝負ごと。
⇒つい‐まつ【続松】
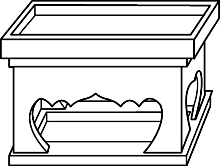 ついか‐はいとう【追加配当】‥タウ
破産手続で、最後の配当の通知を発した後に、新たに配当にあてるべき財産があった時に行う配当。
⇒つい‐か【追加】
ついか‐よさん【追加予算】
「補正予算」参照。
⇒つい‐か【追加】
つい‐かん【追刊】
後から続けて刊行すること。続刊。
つい‐かん【追完】‥クワン
〔法〕追認とほぼ同義に用いられる語。
つい‐がん【追願】‥グワン
ある願いをしている上に、さらに他の願いをあとから出すこと。おいねがい。
ついかん‐ばん【椎間板】
脊柱せきちゅうに連なる椎骨と椎骨との間にある円板状の組織。中心部の髄核と周辺の線維輪から成り、髄核は水分に富むゼリー状、線維輪は線維軟骨。椎間円板。
⇒ついかんばん‐ヘルニア【椎間板ヘルニア】
ついかんばん‐ヘルニア【椎間板ヘルニア】
椎間板の線維輪に変性・損傷があって、髄核が後方に脱出し、脊髄や神経根を圧迫して神経症状を起こす病態。特に下位腰椎に最も多く、この場合、坐骨神経痛の症状を呈する。
⇒ついかん‐ばん【椎間板】
つい‐き【追記】
あとから付け足して、本文のあとに書き加えること。また、その文句。
つい‐き【鎚起】
鍛金たんきんの一技法。金属板を鎚つちで立体的に打ちのばす金工技法。
つい‐きそ【追起訴】
ある事件が第一審裁判所で審理中、検察官がその事件と併合審理を求めるため、同一被告人の別事件をその裁判所に公訴提起すること。
つい‐きゅう【追及】‥キフ
①後から追いかけていっておいつくこと。
②責任などを、どこまでも追い責めること。「余罪を―する」
⇒ついきゅう‐けん【追及権】
つい‐きゅう【追求】‥キウ
(ツイクとも)どこまでも後を追いかけ求めること。「幸福を―する」「利潤の―」
つい‐きゅう【追究】‥キウ
学問などを、尋ねきわめること。追窮。「真理を―する」
つい‐きゅう【追咎】‥キウ
事のすんだ後になってとがめること。
つい‐きゅう【追給】‥キフ
①給与などの不足分や増加分をあとから支給すること。また、その給与。
②不足分をあとから払うこと。追い払い。
つい‐きゅう【追窮】
不確かなことを、どこまでもおしきわめること。追究。
つい‐きゅう【椎弓】
椎骨の椎体の背側から出る橋状の突起。椎孔を囲み、後ろ側・左右・上下に3種7個の突起を出す。棘きょく突起1、横おう突起2、上下の関節突起4。
ついきゅう‐けん【追及権】‥キフ‥
〔法〕物権の特性の一つ。その目的物の所有者または占有者が何人に変わっても、これに追随して行使しうる権能。
⇒つい‐きゅう【追及】
つい‐きょう【追孝】‥ケウ
⇒ついこう
つい‐きん【堆錦】
琉球漆器特有の装飾法。漆と多量の顔料とを混ぜたものを乾燥させて薄くのばし、模様に切り取り成形して、漆器面にはりつける。
つい‐きん【鎚金】
鍛金の一技法。金属を型に当て、または裏面から鏨たがねで打ち出し、表面に文様などを凸起させる。うちだし。
つい‐く【対句】
修辞法の一つ。語の並べ方を同じくし、意味は対ついになる二つ以上の句を連ねて表現すること。また、それらの句。「魚は水に飽かず。魚にあらざれば、その心を知らず。鳥は林をねがふ。鳥にあらざれば、その心を知らず」の類。儷句れいく。
つい‐く【追求】
⇒ついきゅう。〈伊呂波字類抄〉
つい‐く【追駆】
あとから追いかけること。
つい‐くぐ・る【つい潜る】
〔自四〕
(ツイは接頭語)ちょっとくぐる。平家物語4「揚る矢をば―・り」
ツィクルス【Zyklus ドイツ】
(円環・連続・連鎖の意)
①連続演奏会。ある作曲家やあるジャンルの作品を、一定の意図のもとに一連の音楽会で連続して演奏するもの。「ベートーヴェン‐―」
②複数の曲が一定の意図・主題のもとにまとめられて一つの作品となったもの。連作歌曲。シューベルトの「冬の旅」など。
つい‐けい【追啓】
(→)追伸ついしんに同じ。
つい‐げき【追撃】
逃げて行く敵を後から追いかけて撃つこと。おいうち。尾撃。「―をかわす」
つい‐ご【対語】
①漢語の熟語で、事物が相対するように構成されたもの。大小(対比)・桃李(類似)・花鳥(接近)の類。
②(→)対義語に同じ。
つい‐こう【追考】‥カウ
あとから以前の物事について考えること。また、その考え。
つい‐こう【追行】‥カウ
①あとから追いかけること。
②つづいてあとから事を行うこと。
つい‐こう【追孝】‥カウ
(ツイキョウとも)死んだ親などに供養をして孝道を尽くすこと。菩提をとむらうこと。太平記20「一日経を書き供養して、―の作善さぜんをぞ致しける」
つい‐こう【堆紅】
堆朱ついしゅの一種。
つい‐ごう【対合】‥ガフ
〔生〕
⇒たいごう
つい‐ごう【追号】‥ガウ
人が死んだ後に生前の功績をたたえて贈る称号。おくりな。保元物語「―ありて崇徳院とぞ申しける」
つい‐こく【堆黒】
堆朱ついしゅの一種。黒色の漆を主体とするもの。堆烏ついう。
つい‐こつ【椎骨】
脊柱せきちゅうを構成する個々の骨。円柱状の椎体、その背側に延びて椎孔を囲む椎弓およびこれから出ている突起から成り、軟骨(椎間板)で連結されて脊柱を作る。頸椎・胸椎・腰椎・仙椎・尾椎に分かれ、椎孔は上下に連なって長い脊柱管をなし、中に脊髄を入れる。人の場合は32〜34個。
つい‐さ・す【つい挿す】
〔他四〕
(ツイは接頭語)ちょっとさしこむ。枕草子138「上かみに―・しておきたるを」
つい‐し【追思】
あとから過去を思うこと。追想。
つい‐し【追試】
①人の実験したことを、あとからその通りに試みて確かめること。
②追試験の略。
つい‐し【追諡】
死後におくりなを追贈すること。
つい‐し【墜死】
高い所から墜落して死ぬこと。
つい‐し【鎚子】
節会せちえなどに用いた唐菓子の一種。米の粉または小麦粉をこねてサトイモの形に製し、油で揚げたもの。
つい‐じ【築地】‥ヂ
(ツキヒヂ(築泥)の音便ツイヒヂの約)
①土塀の上に屋根を葺ふいたもの。古くは、土を盛り上げて固めただけのものであった。ついがき。ついじべい。えんじ籬まがき。枕草子27「―のくづれ」
築地
ついか‐はいとう【追加配当】‥タウ
破産手続で、最後の配当の通知を発した後に、新たに配当にあてるべき財産があった時に行う配当。
⇒つい‐か【追加】
ついか‐よさん【追加予算】
「補正予算」参照。
⇒つい‐か【追加】
つい‐かん【追刊】
後から続けて刊行すること。続刊。
つい‐かん【追完】‥クワン
〔法〕追認とほぼ同義に用いられる語。
つい‐がん【追願】‥グワン
ある願いをしている上に、さらに他の願いをあとから出すこと。おいねがい。
ついかん‐ばん【椎間板】
脊柱せきちゅうに連なる椎骨と椎骨との間にある円板状の組織。中心部の髄核と周辺の線維輪から成り、髄核は水分に富むゼリー状、線維輪は線維軟骨。椎間円板。
⇒ついかんばん‐ヘルニア【椎間板ヘルニア】
ついかんばん‐ヘルニア【椎間板ヘルニア】
椎間板の線維輪に変性・損傷があって、髄核が後方に脱出し、脊髄や神経根を圧迫して神経症状を起こす病態。特に下位腰椎に最も多く、この場合、坐骨神経痛の症状を呈する。
⇒ついかん‐ばん【椎間板】
つい‐き【追記】
あとから付け足して、本文のあとに書き加えること。また、その文句。
つい‐き【鎚起】
鍛金たんきんの一技法。金属板を鎚つちで立体的に打ちのばす金工技法。
つい‐きそ【追起訴】
ある事件が第一審裁判所で審理中、検察官がその事件と併合審理を求めるため、同一被告人の別事件をその裁判所に公訴提起すること。
つい‐きゅう【追及】‥キフ
①後から追いかけていっておいつくこと。
②責任などを、どこまでも追い責めること。「余罪を―する」
⇒ついきゅう‐けん【追及権】
つい‐きゅう【追求】‥キウ
(ツイクとも)どこまでも後を追いかけ求めること。「幸福を―する」「利潤の―」
つい‐きゅう【追究】‥キウ
学問などを、尋ねきわめること。追窮。「真理を―する」
つい‐きゅう【追咎】‥キウ
事のすんだ後になってとがめること。
つい‐きゅう【追給】‥キフ
①給与などの不足分や増加分をあとから支給すること。また、その給与。
②不足分をあとから払うこと。追い払い。
つい‐きゅう【追窮】
不確かなことを、どこまでもおしきわめること。追究。
つい‐きゅう【椎弓】
椎骨の椎体の背側から出る橋状の突起。椎孔を囲み、後ろ側・左右・上下に3種7個の突起を出す。棘きょく突起1、横おう突起2、上下の関節突起4。
ついきゅう‐けん【追及権】‥キフ‥
〔法〕物権の特性の一つ。その目的物の所有者または占有者が何人に変わっても、これに追随して行使しうる権能。
⇒つい‐きゅう【追及】
つい‐きょう【追孝】‥ケウ
⇒ついこう
つい‐きん【堆錦】
琉球漆器特有の装飾法。漆と多量の顔料とを混ぜたものを乾燥させて薄くのばし、模様に切り取り成形して、漆器面にはりつける。
つい‐きん【鎚金】
鍛金の一技法。金属を型に当て、または裏面から鏨たがねで打ち出し、表面に文様などを凸起させる。うちだし。
つい‐く【対句】
修辞法の一つ。語の並べ方を同じくし、意味は対ついになる二つ以上の句を連ねて表現すること。また、それらの句。「魚は水に飽かず。魚にあらざれば、その心を知らず。鳥は林をねがふ。鳥にあらざれば、その心を知らず」の類。儷句れいく。
つい‐く【追求】
⇒ついきゅう。〈伊呂波字類抄〉
つい‐く【追駆】
あとから追いかけること。
つい‐くぐ・る【つい潜る】
〔自四〕
(ツイは接頭語)ちょっとくぐる。平家物語4「揚る矢をば―・り」
ツィクルス【Zyklus ドイツ】
(円環・連続・連鎖の意)
①連続演奏会。ある作曲家やあるジャンルの作品を、一定の意図のもとに一連の音楽会で連続して演奏するもの。「ベートーヴェン‐―」
②複数の曲が一定の意図・主題のもとにまとめられて一つの作品となったもの。連作歌曲。シューベルトの「冬の旅」など。
つい‐けい【追啓】
(→)追伸ついしんに同じ。
つい‐げき【追撃】
逃げて行く敵を後から追いかけて撃つこと。おいうち。尾撃。「―をかわす」
つい‐ご【対語】
①漢語の熟語で、事物が相対するように構成されたもの。大小(対比)・桃李(類似)・花鳥(接近)の類。
②(→)対義語に同じ。
つい‐こう【追考】‥カウ
あとから以前の物事について考えること。また、その考え。
つい‐こう【追行】‥カウ
①あとから追いかけること。
②つづいてあとから事を行うこと。
つい‐こう【追孝】‥カウ
(ツイキョウとも)死んだ親などに供養をして孝道を尽くすこと。菩提をとむらうこと。太平記20「一日経を書き供養して、―の作善さぜんをぞ致しける」
つい‐こう【堆紅】
堆朱ついしゅの一種。
つい‐ごう【対合】‥ガフ
〔生〕
⇒たいごう
つい‐ごう【追号】‥ガウ
人が死んだ後に生前の功績をたたえて贈る称号。おくりな。保元物語「―ありて崇徳院とぞ申しける」
つい‐こく【堆黒】
堆朱ついしゅの一種。黒色の漆を主体とするもの。堆烏ついう。
つい‐こつ【椎骨】
脊柱せきちゅうを構成する個々の骨。円柱状の椎体、その背側に延びて椎孔を囲む椎弓およびこれから出ている突起から成り、軟骨(椎間板)で連結されて脊柱を作る。頸椎・胸椎・腰椎・仙椎・尾椎に分かれ、椎孔は上下に連なって長い脊柱管をなし、中に脊髄を入れる。人の場合は32〜34個。
つい‐さ・す【つい挿す】
〔他四〕
(ツイは接頭語)ちょっとさしこむ。枕草子138「上かみに―・しておきたるを」
つい‐し【追思】
あとから過去を思うこと。追想。
つい‐し【追試】
①人の実験したことを、あとからその通りに試みて確かめること。
②追試験の略。
つい‐し【追諡】
死後におくりなを追贈すること。
つい‐し【墜死】
高い所から墜落して死ぬこと。
つい‐し【鎚子】
節会せちえなどに用いた唐菓子の一種。米の粉または小麦粉をこねてサトイモの形に製し、油で揚げたもの。
つい‐じ【築地】‥ヂ
(ツキヒヂ(築泥)の音便ツイヒヂの約)
①土塀の上に屋根を葺ふいたもの。古くは、土を盛り上げて固めただけのものであった。ついがき。ついじべい。えんじ籬まがき。枕草子27「―のくづれ」
築地
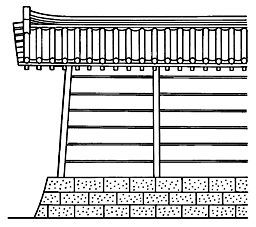 ②(その邸に築地をめぐらしてあったからいう)公家衆くげしゅう。公卿くぎょう。
⇒ついじ‐じょろう【築地女郎】
⇒ついじ‐べい【築地塀】
つい‐しか【終しか】ツヒ‥
〔副〕
ついに。いまだに。たえて。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―お目にはかからねど」
つい‐じく【対軸】‥ヂク
(→)対幅ついふくに同じ。
つい‐しけん【追試験】
病気・事故等のため正規の試験を受けられなかった者や前の試験の不合格者に対して、後で行う試験。追試。
ついじ‐じょろう【築地女郎】‥ヂヂヨラウ
(公家衆に奉公する女の意)貴人の家に奉公する女。
⇒つい‐じ【築地】
つい‐しつ【堆漆】
堆朱ついしゅ・堆黒ついこくなどの総称。
ついじ‐べい【築地塀】‥ヂ‥
(→)築地ついじ1に同じ。
⇒つい‐じ【築地】
つい‐しゅ【追修】
〔仏〕死者の冥福を祈って仏事を修めること。追善。
つい‐しゅ【堆朱】
彫漆の一種。朱漆を幾層にも塗り重ね、その表面に山水・花鳥・人物などを彫り出したもの。宋代以後盛んに行われ、室町時代に日本に渡来。君台観左右帳記「各堆紅・―のほり物なり」→堆黄ついおう→堆黒ついこく。
⇒ついしゅ‐ぞめ【堆朱染】
つい‐じゅう【追従】
人のあとにつき従うこと。「人の意見に―する」→ついしょう(追従)
つい‐じゅく【追熟】
収穫期の脱落などを防ぐため早目に果実を収穫し、あとで完熟させること。後熟。
ついしゅ‐ぞめ【堆朱染】
地を紅染めにし、その上に黒で堆朱文様を染め出したもの。宝暦(1751〜1764)前後に盛行。
⇒つい‐しゅ【堆朱】
つい‐しゅつ【追出】
追い出すこと。平家物語1「外法げほう行ひける聖を―せむとしければ」
つい‐じょ【追叙】
人の死後、叙位・叙勲をすること。
つい‐しょう【追従】
人のあとにつき従うこと。転じて、こびへつらうこと。おべっかをつかうこと。「お―を言う」
⇒ついしょう‐ぐち【追従口】
⇒ついしょう‐わらい【追従笑い】
つい‐しょう【追頌】
人の死後、その功績・善行などをほめあらわすこと。
つい‐しょう【追賞】‥シヤウ
あとから功績を賞すること。
つい‐しょう【追蹤】
①あとをつけて行くこと。追跡。
②過ぎ去った事を思い出すこと。
つい‐じょう【追躡】‥デフ
(「躡」は踏む意)あとから追いかけること。追跡。
⇒ついじょう‐けん【追躡権】
ついしょう‐ぐち【追従口】
こびへつらって言うことば。お世辞。おべっか。
⇒つい‐しょう【追従】
ついじょう‐けん【追躡権】‥デフ‥
(→)追跡権に同じ。
⇒つい‐じょう【追躡】
ついしょう‐わらい【追従笑い】‥ワラヒ
こびへつらって、おかしくもないのに笑うこと。また、そのような笑い。
⇒つい‐しょう【追従】
つい‐しろ【土代】
(ツチシロの転)地上に敷く敷物。皇太神宮儀式帳「―白細布帳一条」
つい‐しん【追申】
①前のにつづいて申請すること。
②⇒ついしん(追伸)
つい‐しん【追伸・追申】
(後から加えて申す意)手紙などで、追記の文。また、そのはじめに書く語。追而書おってがき。なおなお書き。追啓。追白。追陳。二伸。
つい‐じん【追尋】
目的を達しようとして追い求めること。追求。
つい・す【対す】
〔自サ変〕
一対になる。また、対とするに似つかわしい。
つい・ず【序づ・叙づ】ツイヅ
〔他下二〕
次第を立てる。順序を定める。順序よく置く。三蔵法師伝延久点「余を迫せめて以て之を次ツイテしむ」
つい‐ずい【追随】
①あとにつきしたがって行くこと。追従。「―者」
②追いつくこと。「他の―を許さない」
③死者などをあとからしたうこと。追慕。
つい‐す・う【つい据う】
〔他下二〕
(ツイは接頭語)すえおく。さしおく。能因本枕草子たくみの物くふこそ「かはらけは―・ゑつつ」
つい‐すく・う【つい掬ふ】‥スクフ
〔他四〕
(ツイは接頭語)無造作にすくい上げる。狂言、地蔵舞「錫杖を取り直いて、かいすくうてほつたり、―・うてひつたり」
ツイスト【twist】
(「ひねる」「ねじる」の意)
①ビリヤードなどで、球にひねりを与えること。
②脚や腰をねじってする活発な踊り。1960年代初頭にアメリカから流行。
⇒ツイスト‐ドリル【twist drill】
ツイスト‐ドリル【twist drill】
(→)ドリル1に同じ。
⇒ツイスト【twist】
つい‐す・ゆ【つい据ゆ】
〔他下二〕
(ツイスウの転)ちょっと置く。宇治拾遺物語1「雨だれに―・ゆと思ひしに」
つい‐せき【追惜】
死後その人をいたみおしむこと。
つい‐せき【追跡】
①逃げる者のあとを追いかけること。跡をつけること。追蹤ついしょう。追躡ついじょう。
②比喩的に、物事のその後の経過を追うこと。
⇒ついせき‐けん【追跡権】
⇒ついせき‐ちょうさ【追跡調査】
⇒ついせき‐もうそう【追跡妄想】
ついせき‐けん【追跡権】
〔法〕外国船舶が沿岸領海で沿岸国の裁判管轄権に属する犯罪を犯したとき、領海内から軍艦や巡視艇などの公船がこれを追跡し、公海において拿捕だほし得る権利。継続追跡権。
⇒つい‐せき【追跡】
ついせき‐ちょうさ【追跡調査】‥テウ‥
事物の経過を追って継続的に調査すること。
⇒つい‐せき【追跡】
ついせき‐もうそう【追跡妄想】‥マウサウ
いつも自分が追いかけられ、また監視されているように思う妄想。
⇒つい‐せき【追跡】
つい‐ぜん【追善】
死者の冥福を祈るため遺族などが読経・斎会などの善事を行うこと。また、死者の年忌などに仏事を営むこと。追福。追薦。
⇒ついぜん‐がっせん【追善合戦】
⇒ついぜん‐くよう【追善供養】
⇒ついぜん‐こうぎょう【追善興行】
ついぜん‐がっせん【追善合戦】
(→)弔合戦とむらいがっせんに同じ。
⇒つい‐ぜん【追善】
ついぜん‐くよう【追善供養】‥ヤウ
追善のためにする供養。
⇒つい‐ぜん【追善】
ついぜん‐こうぎょう【追善興行】‥ギヤウ
亡くなった役者・芸人などをしのび、その冥福を祈って催す興行。
⇒つい‐ぜん【追善】
つい‐そ【追訴】
はじめの訴えに追加して訴えること。また、その訴え。
つい‐ぞ【終ぞ】ツヒ‥
〔副〕
(下に否定の語を伴う)いまだかつて。いちども。「―見かけない」
つい‐そう【追走】
追いかけて走ること。
つい‐そう【追送】
①すぐあとから送ること。
②あとを見送ること。
つい‐そう【追従】
(ソウはショウの直音化)
⇒ついしょう。源氏物語空蝉「とのゐ人などもことに見いれ―せず」
つい‐そう【追崇】
(→)追尊ついそんに同じ。
つい‐そう【追想】‥サウ
過去の事や去った人のことを思い出してしのぶこと。「若き日を―する」
つい‐ぞう【追増】
あとから加え足すこと。追加。
つい‐ぞう【追贈】
死後に官位・勲章などを贈ること。
つい‐そん【追尊】
死後に尊号を贈ること。
⇒ついそん‐てんのう【追尊天皇】
ついそん‐てんのう【追尊天皇】‥ワウ
帝位につかない親王に、その没後に天皇号を追贈したもの。歴代に加えない。崇道すどう天皇(光仁天皇の皇子早良さわら親王)の類。
⇒つい‐そん【追尊】
つい‐たい【椎体】
椎骨の中央にある円筒状の部分。
つい‐たいけん【追体験】
(Nacherleben ドイツ)他人の体験をあとからなぞり、自分の体験のようにとらえること。
つい‐たけ【対丈】
(ツキタケ(衝丈)の音便か)身の丈と同じに布地を裁って着物を仕立てること。仮名文章娘節用「ひとへものに―の襦袢」
つい‐たち【朔日・朔・一日】
(ツキタチ(月立)の音便。こもっていた月が出はじめる意)
①西方の空に、日の入ったあと、月がほのかに見えはじめる日を初めとして、それから10日ばかりの間の称。(陰暦の)月の初め。上旬。初旬。伊勢物語「時はやよひの―、雨そほふるに」
②月の第一日。いちじつ。古くは「ついたちの日」ということが多い。蜻蛉日記下「閏二月の―の日、雨のどかなり」
③特に、正月一日。元日。紫式部日記「ことしの―、御まかなひ、宰相の君」
⇒ついたち‐がん【朔日丸】
⇒ついたち‐そう【朔日草】
⇒ついたち‐ぶり【朔日降り】
⇒ついたち‐みち【朔日路】
ついたち‐がん【朔日丸】‥グワン
女が毎月朔日に飲めば孕はらまないといわれた丸薬。江戸四つ目屋発売。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐そう【朔日草】‥サウ
福寿草の異称。新年を祝う花として元旦に用いる。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐そうじ【衝立障子】‥サウ‥
(ツイタチショウジとも)(→)「ついたてそうじ」に同じ。古今著聞集11「清涼殿の弘廂に―を立てて」
ついたち‐ぶり【朔日降り】
月の第1日に雨の降ること。俗に、その月は雨が多いという。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐みち【朔日路】
盆路ぼんみちのこと。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
つい‐た・つ【つい立つ】
〔自四〕
(ツイは接頭語)さっと立つ。突然立つ。ちょっと立つ。平家物語4「ちつとも騒がず―・つて」
つい‐だつ【追奪】
①追いかけて奪うこと。
②死後に生前の官位などを取り上げること。
③〔法〕いったん他人の権利に属したものを、自己の権利を主張して取りもどすこと。
⇒ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
〔法〕主に売買の目的物に権利の瑕疵かしがあった場合に買主が追及しうる売主の責任、すなわち損害賠償や代金減額の請求または契約の解除。
⇒つい‐だつ【追奪】
つい‐たて【衝立】
衝立障子ついたてそうじの略。
⇒ついたて‐しょうじ【衝立障子】
⇒ついたて‐そうじ【衝立障子】
ついたて‐しょうじ【衝立障子】‥シヤウ‥
⇒ついたてそうじ。
⇒つい‐たて【衝立】
ついたて‐そうじ【衝立障子】‥サウ‥
(ツイタテショウジとも)屏障具へいしょうぐの一つ。1枚の襖ふすま障子または板障子に、移動しやすいように台をつけたもの。平安時代から宮中や寝殿に用いられ、後世では玄関・座敷などに立てて隔てとする。清涼殿の昆明池こんめいちの障子、年中行事の障子など。
⇒つい‐たて【衝立】
つい‐だんな【吊手綱】
(タンナはタヅナの訛)越中褌えっちゅうふんどし。ついだん。つりだんな。
つい‐ちく【追逐】
①あとを追いかけること。
②追いはらうこと。
③追いつ追われつすること。
④互いに相伴うこと。
つい‐ちょう【追弔】‥テウ
死後にその生前をしのびとむらうこと。
⇒ついちょう‐え【追弔会】
つい‐ちょう【追徴】
①税金などの公課を追加して取り立てること。あとから不足額を取り立てること。
②刑法上、没収すべき物を没収できないときに、その物の価額の納付を強制すること。
⇒ついちょう‐きん【追徴金】
ついちょう‐え【追弔会】‥テウヱ
追弔のために催す法会。
⇒つい‐ちょう【追弔】
ついちょう‐きん【追徴金】
追徴として取り立てる金銭。
⇒つい‐ちょう【追徴】
つい‐ちん【追陳】
追記の語。追伸。
つい‐つい
〔副〕
(副詞「つい」を重ねた語)そうするつもりではないのに。思いに反して。「―食べてしまう」
つい‐て【就いて】
(ツキテの音便)
①…に関して。「あなたに―何も知らない」
②…ごとに。「一回に―千円の罰金」
→つく(就)[一]➒。
⇒ついて‐は【就いては】
ついで【序で】
(ツイヅの連用形から)
①順序。次第。順番。宇津保物語藤原君「物は―を越さずいでたちつべきものなり」
②よいおり。機会。あることを併せてするよい機会。源氏物語桐壺「かくても、おのづから、若宮など生ひ出でたまはば、さるべき―もありなむ」。「お―の節」
⇒ついで‐な・し【序で無し】
⇒ついで‐に【序でに】
つい‐で【次いで・尋いで】
(ツギテの音便)
[一]〔副〕
つづいて。ほどなく。まもなく。「はじめに上下動が、―横揺れが来た」
[二]〔接続〕
次に。それから。三蔵法師伝永久点「尋ツイテ詔を下して翻訳せしむることを賜ふことを蒙れり」。「―第二部がはじまった」
ついで‐な・し【序で無し】
〔形ク〕
きっかけがない。突然だ。徒然草「人に物を取らせたるも、―・くてこれを奉らんと言ひたる」
⇒ついで【序で】
ついで‐に【序でに】
そのおりに。その場合に。その機会に乗じて。「近くに来た―寄った」「―言えば」
⇒ついで【序で】
ついて‐は【就いては】
〔接続〕
したがって。よって。それゆえに。
⇒つい‐て【就いて】
ついて‐まわ・る【付いて回る】‥マハル
〔自五〕
離れずにいっしょに動く。つきまとう。「悪評がどこまでも―・る」
つい‐てる
(ツイテイルの約)運が向いている。つきがある。→つく(付く)[一]➎7
つい‐と
〔副〕
①いきなり。つと。ずいと。「―立ち上がる」
②はやく通りすぎるさま。つっと。
つい‐どツヒ‥
〔副〕
(「ついぞ」の転)いまだかつて。めったに。浮世草子、好色産毛「―見ぬきたない女」
つい‐とう【追討】‥タウ
賊徒などを追いかけて征伐すること。討手うってを差し向けて討ち取ること。「―使」
つい‐とう【追悼】‥タウ
死者をしのんで、いたみ悲しむこと。「事故犠牲者を―する」「―会」
つい‐どう【隧道】‥ダウ
スイドウの誤読。
つい‐とおり【つい通り】‥トホリ
なみ。普通。体源抄「―の説は用なり」
つい‐とつ【追突】
(乗物などが)後ろから衝突すること。「―事故」
つ‐いな【都維那】‥ヰ‥
〔仏〕(→)維那いなに同じ。
つい‐な【追儺】
宮中の年中行事の一つ。大晦日の夜、悪鬼を払い疫病を除く儀式。舎人とねりの鬼に扮装した者を、内裏の四門をめぐって追いまわす。大舎人長が鬼を払う方相氏ほうそうしの役をつとめ、黄金四つ目の仮面をかぶり、黒衣朱裳を着し、手に矛・楯を執った。これを大儺たいなといい、紺の布衣に緋の抹額まっこうを着けて大儺に従って駆けまわる童子を小儺しょうなとよぶ。殿上人は桃の弓、葦の矢で鬼を射る。古く中国に始まり、日本には8世紀初め頃、文武天皇の時に伝わったといわれ、社寺・民間にも行われた。近世、民間では、節分の行事となる。「おにやらい」「なやらい」とも。〈[季]冬〉
追儺
②(その邸に築地をめぐらしてあったからいう)公家衆くげしゅう。公卿くぎょう。
⇒ついじ‐じょろう【築地女郎】
⇒ついじ‐べい【築地塀】
つい‐しか【終しか】ツヒ‥
〔副〕
ついに。いまだに。たえて。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―お目にはかからねど」
つい‐じく【対軸】‥ヂク
(→)対幅ついふくに同じ。
つい‐しけん【追試験】
病気・事故等のため正規の試験を受けられなかった者や前の試験の不合格者に対して、後で行う試験。追試。
ついじ‐じょろう【築地女郎】‥ヂヂヨラウ
(公家衆に奉公する女の意)貴人の家に奉公する女。
⇒つい‐じ【築地】
つい‐しつ【堆漆】
堆朱ついしゅ・堆黒ついこくなどの総称。
ついじ‐べい【築地塀】‥ヂ‥
(→)築地ついじ1に同じ。
⇒つい‐じ【築地】
つい‐しゅ【追修】
〔仏〕死者の冥福を祈って仏事を修めること。追善。
つい‐しゅ【堆朱】
彫漆の一種。朱漆を幾層にも塗り重ね、その表面に山水・花鳥・人物などを彫り出したもの。宋代以後盛んに行われ、室町時代に日本に渡来。君台観左右帳記「各堆紅・―のほり物なり」→堆黄ついおう→堆黒ついこく。
⇒ついしゅ‐ぞめ【堆朱染】
つい‐じゅう【追従】
人のあとにつき従うこと。「人の意見に―する」→ついしょう(追従)
つい‐じゅく【追熟】
収穫期の脱落などを防ぐため早目に果実を収穫し、あとで完熟させること。後熟。
ついしゅ‐ぞめ【堆朱染】
地を紅染めにし、その上に黒で堆朱文様を染め出したもの。宝暦(1751〜1764)前後に盛行。
⇒つい‐しゅ【堆朱】
つい‐しゅつ【追出】
追い出すこと。平家物語1「外法げほう行ひける聖を―せむとしければ」
つい‐じょ【追叙】
人の死後、叙位・叙勲をすること。
つい‐しょう【追従】
人のあとにつき従うこと。転じて、こびへつらうこと。おべっかをつかうこと。「お―を言う」
⇒ついしょう‐ぐち【追従口】
⇒ついしょう‐わらい【追従笑い】
つい‐しょう【追頌】
人の死後、その功績・善行などをほめあらわすこと。
つい‐しょう【追賞】‥シヤウ
あとから功績を賞すること。
つい‐しょう【追蹤】
①あとをつけて行くこと。追跡。
②過ぎ去った事を思い出すこと。
つい‐じょう【追躡】‥デフ
(「躡」は踏む意)あとから追いかけること。追跡。
⇒ついじょう‐けん【追躡権】
ついしょう‐ぐち【追従口】
こびへつらって言うことば。お世辞。おべっか。
⇒つい‐しょう【追従】
ついじょう‐けん【追躡権】‥デフ‥
(→)追跡権に同じ。
⇒つい‐じょう【追躡】
ついしょう‐わらい【追従笑い】‥ワラヒ
こびへつらって、おかしくもないのに笑うこと。また、そのような笑い。
⇒つい‐しょう【追従】
つい‐しろ【土代】
(ツチシロの転)地上に敷く敷物。皇太神宮儀式帳「―白細布帳一条」
つい‐しん【追申】
①前のにつづいて申請すること。
②⇒ついしん(追伸)
つい‐しん【追伸・追申】
(後から加えて申す意)手紙などで、追記の文。また、そのはじめに書く語。追而書おってがき。なおなお書き。追啓。追白。追陳。二伸。
つい‐じん【追尋】
目的を達しようとして追い求めること。追求。
つい・す【対す】
〔自サ変〕
一対になる。また、対とするに似つかわしい。
つい・ず【序づ・叙づ】ツイヅ
〔他下二〕
次第を立てる。順序を定める。順序よく置く。三蔵法師伝延久点「余を迫せめて以て之を次ツイテしむ」
つい‐ずい【追随】
①あとにつきしたがって行くこと。追従。「―者」
②追いつくこと。「他の―を許さない」
③死者などをあとからしたうこと。追慕。
つい‐す・う【つい据う】
〔他下二〕
(ツイは接頭語)すえおく。さしおく。能因本枕草子たくみの物くふこそ「かはらけは―・ゑつつ」
つい‐すく・う【つい掬ふ】‥スクフ
〔他四〕
(ツイは接頭語)無造作にすくい上げる。狂言、地蔵舞「錫杖を取り直いて、かいすくうてほつたり、―・うてひつたり」
ツイスト【twist】
(「ひねる」「ねじる」の意)
①ビリヤードなどで、球にひねりを与えること。
②脚や腰をねじってする活発な踊り。1960年代初頭にアメリカから流行。
⇒ツイスト‐ドリル【twist drill】
ツイスト‐ドリル【twist drill】
(→)ドリル1に同じ。
⇒ツイスト【twist】
つい‐す・ゆ【つい据ゆ】
〔他下二〕
(ツイスウの転)ちょっと置く。宇治拾遺物語1「雨だれに―・ゆと思ひしに」
つい‐せき【追惜】
死後その人をいたみおしむこと。
つい‐せき【追跡】
①逃げる者のあとを追いかけること。跡をつけること。追蹤ついしょう。追躡ついじょう。
②比喩的に、物事のその後の経過を追うこと。
⇒ついせき‐けん【追跡権】
⇒ついせき‐ちょうさ【追跡調査】
⇒ついせき‐もうそう【追跡妄想】
ついせき‐けん【追跡権】
〔法〕外国船舶が沿岸領海で沿岸国の裁判管轄権に属する犯罪を犯したとき、領海内から軍艦や巡視艇などの公船がこれを追跡し、公海において拿捕だほし得る権利。継続追跡権。
⇒つい‐せき【追跡】
ついせき‐ちょうさ【追跡調査】‥テウ‥
事物の経過を追って継続的に調査すること。
⇒つい‐せき【追跡】
ついせき‐もうそう【追跡妄想】‥マウサウ
いつも自分が追いかけられ、また監視されているように思う妄想。
⇒つい‐せき【追跡】
つい‐ぜん【追善】
死者の冥福を祈るため遺族などが読経・斎会などの善事を行うこと。また、死者の年忌などに仏事を営むこと。追福。追薦。
⇒ついぜん‐がっせん【追善合戦】
⇒ついぜん‐くよう【追善供養】
⇒ついぜん‐こうぎょう【追善興行】
ついぜん‐がっせん【追善合戦】
(→)弔合戦とむらいがっせんに同じ。
⇒つい‐ぜん【追善】
ついぜん‐くよう【追善供養】‥ヤウ
追善のためにする供養。
⇒つい‐ぜん【追善】
ついぜん‐こうぎょう【追善興行】‥ギヤウ
亡くなった役者・芸人などをしのび、その冥福を祈って催す興行。
⇒つい‐ぜん【追善】
つい‐そ【追訴】
はじめの訴えに追加して訴えること。また、その訴え。
つい‐ぞ【終ぞ】ツヒ‥
〔副〕
(下に否定の語を伴う)いまだかつて。いちども。「―見かけない」
つい‐そう【追走】
追いかけて走ること。
つい‐そう【追送】
①すぐあとから送ること。
②あとを見送ること。
つい‐そう【追従】
(ソウはショウの直音化)
⇒ついしょう。源氏物語空蝉「とのゐ人などもことに見いれ―せず」
つい‐そう【追崇】
(→)追尊ついそんに同じ。
つい‐そう【追想】‥サウ
過去の事や去った人のことを思い出してしのぶこと。「若き日を―する」
つい‐ぞう【追増】
あとから加え足すこと。追加。
つい‐ぞう【追贈】
死後に官位・勲章などを贈ること。
つい‐そん【追尊】
死後に尊号を贈ること。
⇒ついそん‐てんのう【追尊天皇】
ついそん‐てんのう【追尊天皇】‥ワウ
帝位につかない親王に、その没後に天皇号を追贈したもの。歴代に加えない。崇道すどう天皇(光仁天皇の皇子早良さわら親王)の類。
⇒つい‐そん【追尊】
つい‐たい【椎体】
椎骨の中央にある円筒状の部分。
つい‐たいけん【追体験】
(Nacherleben ドイツ)他人の体験をあとからなぞり、自分の体験のようにとらえること。
つい‐たけ【対丈】
(ツキタケ(衝丈)の音便か)身の丈と同じに布地を裁って着物を仕立てること。仮名文章娘節用「ひとへものに―の襦袢」
つい‐たち【朔日・朔・一日】
(ツキタチ(月立)の音便。こもっていた月が出はじめる意)
①西方の空に、日の入ったあと、月がほのかに見えはじめる日を初めとして、それから10日ばかりの間の称。(陰暦の)月の初め。上旬。初旬。伊勢物語「時はやよひの―、雨そほふるに」
②月の第一日。いちじつ。古くは「ついたちの日」ということが多い。蜻蛉日記下「閏二月の―の日、雨のどかなり」
③特に、正月一日。元日。紫式部日記「ことしの―、御まかなひ、宰相の君」
⇒ついたち‐がん【朔日丸】
⇒ついたち‐そう【朔日草】
⇒ついたち‐ぶり【朔日降り】
⇒ついたち‐みち【朔日路】
ついたち‐がん【朔日丸】‥グワン
女が毎月朔日に飲めば孕はらまないといわれた丸薬。江戸四つ目屋発売。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐そう【朔日草】‥サウ
福寿草の異称。新年を祝う花として元旦に用いる。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐そうじ【衝立障子】‥サウ‥
(ツイタチショウジとも)(→)「ついたてそうじ」に同じ。古今著聞集11「清涼殿の弘廂に―を立てて」
ついたち‐ぶり【朔日降り】
月の第1日に雨の降ること。俗に、その月は雨が多いという。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
ついたち‐みち【朔日路】
盆路ぼんみちのこと。
⇒つい‐たち【朔日・朔・一日】
つい‐た・つ【つい立つ】
〔自四〕
(ツイは接頭語)さっと立つ。突然立つ。ちょっと立つ。平家物語4「ちつとも騒がず―・つて」
つい‐だつ【追奪】
①追いかけて奪うこと。
②死後に生前の官位などを取り上げること。
③〔法〕いったん他人の権利に属したものを、自己の権利を主張して取りもどすこと。
⇒ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
ついだつ‐たんぽ【追奪担保】
〔法〕主に売買の目的物に権利の瑕疵かしがあった場合に買主が追及しうる売主の責任、すなわち損害賠償や代金減額の請求または契約の解除。
⇒つい‐だつ【追奪】
つい‐たて【衝立】
衝立障子ついたてそうじの略。
⇒ついたて‐しょうじ【衝立障子】
⇒ついたて‐そうじ【衝立障子】
ついたて‐しょうじ【衝立障子】‥シヤウ‥
⇒ついたてそうじ。
⇒つい‐たて【衝立】
ついたて‐そうじ【衝立障子】‥サウ‥
(ツイタテショウジとも)屏障具へいしょうぐの一つ。1枚の襖ふすま障子または板障子に、移動しやすいように台をつけたもの。平安時代から宮中や寝殿に用いられ、後世では玄関・座敷などに立てて隔てとする。清涼殿の昆明池こんめいちの障子、年中行事の障子など。
⇒つい‐たて【衝立】
つい‐だんな【吊手綱】
(タンナはタヅナの訛)越中褌えっちゅうふんどし。ついだん。つりだんな。
つい‐ちく【追逐】
①あとを追いかけること。
②追いはらうこと。
③追いつ追われつすること。
④互いに相伴うこと。
つい‐ちょう【追弔】‥テウ
死後にその生前をしのびとむらうこと。
⇒ついちょう‐え【追弔会】
つい‐ちょう【追徴】
①税金などの公課を追加して取り立てること。あとから不足額を取り立てること。
②刑法上、没収すべき物を没収できないときに、その物の価額の納付を強制すること。
⇒ついちょう‐きん【追徴金】
ついちょう‐え【追弔会】‥テウヱ
追弔のために催す法会。
⇒つい‐ちょう【追弔】
ついちょう‐きん【追徴金】
追徴として取り立てる金銭。
⇒つい‐ちょう【追徴】
つい‐ちん【追陳】
追記の語。追伸。
つい‐つい
〔副〕
(副詞「つい」を重ねた語)そうするつもりではないのに。思いに反して。「―食べてしまう」
つい‐て【就いて】
(ツキテの音便)
①…に関して。「あなたに―何も知らない」
②…ごとに。「一回に―千円の罰金」
→つく(就)[一]➒。
⇒ついて‐は【就いては】
ついで【序で】
(ツイヅの連用形から)
①順序。次第。順番。宇津保物語藤原君「物は―を越さずいでたちつべきものなり」
②よいおり。機会。あることを併せてするよい機会。源氏物語桐壺「かくても、おのづから、若宮など生ひ出でたまはば、さるべき―もありなむ」。「お―の節」
⇒ついで‐な・し【序で無し】
⇒ついで‐に【序でに】
つい‐で【次いで・尋いで】
(ツギテの音便)
[一]〔副〕
つづいて。ほどなく。まもなく。「はじめに上下動が、―横揺れが来た」
[二]〔接続〕
次に。それから。三蔵法師伝永久点「尋ツイテ詔を下して翻訳せしむることを賜ふことを蒙れり」。「―第二部がはじまった」
ついで‐な・し【序で無し】
〔形ク〕
きっかけがない。突然だ。徒然草「人に物を取らせたるも、―・くてこれを奉らんと言ひたる」
⇒ついで【序で】
ついで‐に【序でに】
そのおりに。その場合に。その機会に乗じて。「近くに来た―寄った」「―言えば」
⇒ついで【序で】
ついて‐は【就いては】
〔接続〕
したがって。よって。それゆえに。
⇒つい‐て【就いて】
ついて‐まわ・る【付いて回る】‥マハル
〔自五〕
離れずにいっしょに動く。つきまとう。「悪評がどこまでも―・る」
つい‐てる
(ツイテイルの約)運が向いている。つきがある。→つく(付く)[一]➎7
つい‐と
〔副〕
①いきなり。つと。ずいと。「―立ち上がる」
②はやく通りすぎるさま。つっと。
つい‐どツヒ‥
〔副〕
(「ついぞ」の転)いまだかつて。めったに。浮世草子、好色産毛「―見ぬきたない女」
つい‐とう【追討】‥タウ
賊徒などを追いかけて征伐すること。討手うってを差し向けて討ち取ること。「―使」
つい‐とう【追悼】‥タウ
死者をしのんで、いたみ悲しむこと。「事故犠牲者を―する」「―会」
つい‐どう【隧道】‥ダウ
スイドウの誤読。
つい‐とおり【つい通り】‥トホリ
なみ。普通。体源抄「―の説は用なり」
つい‐とつ【追突】
(乗物などが)後ろから衝突すること。「―事故」
つ‐いな【都維那】‥ヰ‥
〔仏〕(→)維那いなに同じ。
つい‐な【追儺】
宮中の年中行事の一つ。大晦日の夜、悪鬼を払い疫病を除く儀式。舎人とねりの鬼に扮装した者を、内裏の四門をめぐって追いまわす。大舎人長が鬼を払う方相氏ほうそうしの役をつとめ、黄金四つ目の仮面をかぶり、黒衣朱裳を着し、手に矛・楯を執った。これを大儺たいなといい、紺の布衣に緋の抹額まっこうを着けて大儺に従って駆けまわる童子を小儺しょうなとよぶ。殿上人は桃の弓、葦の矢で鬼を射る。古く中国に始まり、日本には8世紀初め頃、文武天皇の時に伝わったといわれ、社寺・民間にも行われた。近世、民間では、節分の行事となる。「おにやらい」「なやらい」とも。〈[季]冬〉
追儺
 つい‐に【終に・遂に】ツヒニ
〔副〕
(一説に、ツヒユ(衰える・潰れる意)と同源かという)
①おわりに。しまいに。とうとう。結局。万葉集3「生ける者―も死ぬるものにあれば」。「―日の目を見た」
②(下に否定を伴って)いまもって。いまだに。ついぞ。好色一代女2「島原の門口に―見ぬ図なることあり」
つい‐にん【追認】
①過去にさかのぼって事実を認めること。
②〔法〕いったん為された不完全な法律行為を後から確定的に有効にする一方的意思表示。
つい‐ねん【追年】
年を追って進むこと。逐年。
つい‐ねん【追念】
①過去の事を思い出すこと。追思。
②残念に思うこと。くやしく思うこと。太平記34「旧主先帝の御―をも休めまゐらせらるべき」
つい‐のう【追納】‥ナフ
不足額をあとから追加して納めること。
つい‐の‐こと【終の事】ツヒ‥
結局はそうなること。落ち着くこと。結末。源氏物語夕霧「なだらかならむのみこそ、人は―には侍るめれ」
つい‐の‐すみか【終の住処・終の栖】ツヒ‥
終生住んでいるべきところ。また、最後にすむ所。死後に落ち着く所。「これがまあ―か雪五尺」(一茶)
つい‐の‐みち【終の道】ツヒ‥
人が最後にゆく道。死出の道。
つい‐の・る【つい乗る】
〔自四〕
(ツイは接頭語)すぐ乗る。急ぎ乗る。狂言、宝の槌「此馬に馬道具そへて―・るやうにして打ちいだすほどに」
つい‐の‐わかれ【終の別れ】ツヒ‥
最後の別れ。死にわかれ。源氏物語椎本「世のこととして―をのがれぬわざなめれど」
つい‐は【終は】ツヒ‥
〔副〕
ついには。しまいには。
つい‐はく【追白】
(「白」は申す意)(→)追伸ついしんに同じ。
つい‐ばつ【追罰】
①あとから更に罰すること。
②追討。太平記2「事停滞して武家―の宣旨を下されなば」
つい‐ば・む【啄む】
〔他五〕
(ツキハムの音便。古くはツイハム)(鳥が)くちばしで物をつついて食う。今昔物語集9「鳥、…面・眼を―・みうがちて」。「餌を―・む」
つい‐はり【突い張り】
(ツキハリの音便)(→)「つっぱり」に同じ。狂言、腰祈「うしろから―をめされい」
つい‐ひ【追肥】
おいごえ。補肥ほひ。「―を施す」
つい‐ひ【追賁】
(「賁」は飾る意)死後に供養してその功徳を飾ること。追善。太平記20「更に称名読経の―をもなすべからず」
つい‐び【追尾】
①あとをつけて行くこと。追跡。「ミサイルが敵機を―する」
②電報指定事項の一つ。受信人が指定の住所に不在の場合、その居所を追って手渡す手続。
つい‐ひじ【築泥】‥ヒヂ
⇒ついじ(築地)。伊勢物語「童べの踏みあけたる―のくづれより通ひけり」
つい‐びな【対雛】
男女一対のひな。めおとびな。
つい‐ひらが・る【つい平がる】
〔自四〕
(ツイは接頭語)平たくなる。はいつくばる。ひれふす。宇治拾遺物語12「虎、人の香をかぎて、―・りて猫の鼠をうかがふやうにてあるを」
つい‐ぶ【追捕】
(ツイフ・ツイホ・ツイフクとも)
①悪者を追いかけて捕らえること。
②没収すること。奪い取ること。
⇒ついぶ‐し【追捕使】
つい‐ふく【対幅】
一対になっている書画の幅。双幅。対軸。
つい‐ふく【追捕】
⇒ついぶ。天草本平家物語「やがて―の官人が参つて資財雑具をも奪ひ取り」
⇒ついふく‐し【追捕使】
つい‐ふく【追福】
(→)追善ついぜんに同じ。
つい‐ふく【追腹】
主君の死を悲しみ臣下がそのあとを追って切腹すること。おいばら。
ついふく‐きょく【追復曲】
〔音〕カノンの訳語。
ついふく‐し【追捕使】
⇒ついぶし
⇒つい‐ふく【追捕】
ついぶ‐し【追捕使】
(ツイフシとも)平安時代、凶徒を逮捕するために補任された令外りょうげの官。国ごとに国司が国内の武勇の者を選んで任じた。ほかに、反乱鎮圧のため、中央から臨時に派遣された場合もある。押領使おうりょうしとほぼ同じ。
⇒つい‐ぶ【追捕】
つい‐ほ【追捕】
⇒ついぶ
つい‐ほ【追補】
出版・著作物などで、追加・訂正する事柄を、あとから補うこと。補遺。
つい‐ぼ【追慕】
死んだ人や遠く去って二度とあえない人を思い出して、恋しく思うこと。「―の念がつのる」
つい‐ほう【追放】‥ハウ
①おいはなつこと。おい払うこと。放逐。今昔物語集29「言ふ甲斐なし。速に―せられよ」。「汚職―」
②犯罪者を一定地域外に放逐する刑。江戸時代には所払ところばらい・江戸払・江戸追放・軽追放・中追放・重追放などがあった。庶民は軽・中・重追放のいずれも江戸十里四方・犯罪地・住国からの追放とし、付加刑の闕所けっしょの範囲だけが異なっていた。構かまえ。
③〔法〕一国において、その在留が危険であると認める自国人もしくは外国人、あるいは正規の手続によらない入国者に対して、国外退去を命ずること。
④一定の理由をもって、公職・教職などからしりぞけること。パージ。
つい‐まち【対待】
物干し竿を渡す2本の柱。
つい‐まつ【続松】
(ツギマツの音便)
①松明たいまつ。
②(歌の上の句に1の炭で下の句を書き継いだ伊勢物語の故事から)歌ガルタや歌貝の、和歌の上下の句を合わせる遊び。偐にせ紫田舎源氏「―、十種香、貝おほひ、様々遊びを仕尽して」
⇒ついまつ‐とり【続松取】
ついまつ‐とり【続松取】
歌ガルタあるいは歌貝を取ってする勝負ごと。
⇒つい‐まつ【続松】
つい‐に【終に・遂に】ツヒニ
〔副〕
(一説に、ツヒユ(衰える・潰れる意)と同源かという)
①おわりに。しまいに。とうとう。結局。万葉集3「生ける者―も死ぬるものにあれば」。「―日の目を見た」
②(下に否定を伴って)いまもって。いまだに。ついぞ。好色一代女2「島原の門口に―見ぬ図なることあり」
つい‐にん【追認】
①過去にさかのぼって事実を認めること。
②〔法〕いったん為された不完全な法律行為を後から確定的に有効にする一方的意思表示。
つい‐ねん【追年】
年を追って進むこと。逐年。
つい‐ねん【追念】
①過去の事を思い出すこと。追思。
②残念に思うこと。くやしく思うこと。太平記34「旧主先帝の御―をも休めまゐらせらるべき」
つい‐のう【追納】‥ナフ
不足額をあとから追加して納めること。
つい‐の‐こと【終の事】ツヒ‥
結局はそうなること。落ち着くこと。結末。源氏物語夕霧「なだらかならむのみこそ、人は―には侍るめれ」
つい‐の‐すみか【終の住処・終の栖】ツヒ‥
終生住んでいるべきところ。また、最後にすむ所。死後に落ち着く所。「これがまあ―か雪五尺」(一茶)
つい‐の‐みち【終の道】ツヒ‥
人が最後にゆく道。死出の道。
つい‐の・る【つい乗る】
〔自四〕
(ツイは接頭語)すぐ乗る。急ぎ乗る。狂言、宝の槌「此馬に馬道具そへて―・るやうにして打ちいだすほどに」
つい‐の‐わかれ【終の別れ】ツヒ‥
最後の別れ。死にわかれ。源氏物語椎本「世のこととして―をのがれぬわざなめれど」
つい‐は【終は】ツヒ‥
〔副〕
ついには。しまいには。
つい‐はく【追白】
(「白」は申す意)(→)追伸ついしんに同じ。
つい‐ばつ【追罰】
①あとから更に罰すること。
②追討。太平記2「事停滞して武家―の宣旨を下されなば」
つい‐ば・む【啄む】
〔他五〕
(ツキハムの音便。古くはツイハム)(鳥が)くちばしで物をつついて食う。今昔物語集9「鳥、…面・眼を―・みうがちて」。「餌を―・む」
つい‐はり【突い張り】
(ツキハリの音便)(→)「つっぱり」に同じ。狂言、腰祈「うしろから―をめされい」
つい‐ひ【追肥】
おいごえ。補肥ほひ。「―を施す」
つい‐ひ【追賁】
(「賁」は飾る意)死後に供養してその功徳を飾ること。追善。太平記20「更に称名読経の―をもなすべからず」
つい‐び【追尾】
①あとをつけて行くこと。追跡。「ミサイルが敵機を―する」
②電報指定事項の一つ。受信人が指定の住所に不在の場合、その居所を追って手渡す手続。
つい‐ひじ【築泥】‥ヒヂ
⇒ついじ(築地)。伊勢物語「童べの踏みあけたる―のくづれより通ひけり」
つい‐びな【対雛】
男女一対のひな。めおとびな。
つい‐ひらが・る【つい平がる】
〔自四〕
(ツイは接頭語)平たくなる。はいつくばる。ひれふす。宇治拾遺物語12「虎、人の香をかぎて、―・りて猫の鼠をうかがふやうにてあるを」
つい‐ぶ【追捕】
(ツイフ・ツイホ・ツイフクとも)
①悪者を追いかけて捕らえること。
②没収すること。奪い取ること。
⇒ついぶ‐し【追捕使】
つい‐ふく【対幅】
一対になっている書画の幅。双幅。対軸。
つい‐ふく【追捕】
⇒ついぶ。天草本平家物語「やがて―の官人が参つて資財雑具をも奪ひ取り」
⇒ついふく‐し【追捕使】
つい‐ふく【追福】
(→)追善ついぜんに同じ。
つい‐ふく【追腹】
主君の死を悲しみ臣下がそのあとを追って切腹すること。おいばら。
ついふく‐きょく【追復曲】
〔音〕カノンの訳語。
ついふく‐し【追捕使】
⇒ついぶし
⇒つい‐ふく【追捕】
ついぶ‐し【追捕使】
(ツイフシとも)平安時代、凶徒を逮捕するために補任された令外りょうげの官。国ごとに国司が国内の武勇の者を選んで任じた。ほかに、反乱鎮圧のため、中央から臨時に派遣された場合もある。押領使おうりょうしとほぼ同じ。
⇒つい‐ぶ【追捕】
つい‐ほ【追捕】
⇒ついぶ
つい‐ほ【追補】
出版・著作物などで、追加・訂正する事柄を、あとから補うこと。補遺。
つい‐ぼ【追慕】
死んだ人や遠く去って二度とあえない人を思い出して、恋しく思うこと。「―の念がつのる」
つい‐ほう【追放】‥ハウ
①おいはなつこと。おい払うこと。放逐。今昔物語集29「言ふ甲斐なし。速に―せられよ」。「汚職―」
②犯罪者を一定地域外に放逐する刑。江戸時代には所払ところばらい・江戸払・江戸追放・軽追放・中追放・重追放などがあった。庶民は軽・中・重追放のいずれも江戸十里四方・犯罪地・住国からの追放とし、付加刑の闕所けっしょの範囲だけが異なっていた。構かまえ。
③〔法〕一国において、その在留が危険であると認める自国人もしくは外国人、あるいは正規の手続によらない入国者に対して、国外退去を命ずること。
④一定の理由をもって、公職・教職などからしりぞけること。パージ。
つい‐まち【対待】
物干し竿を渡す2本の柱。
つい‐まつ【続松】
(ツギマツの音便)
①松明たいまつ。
②(歌の上の句に1の炭で下の句を書き継いだ伊勢物語の故事から)歌ガルタや歌貝の、和歌の上下の句を合わせる遊び。偐にせ紫田舎源氏「―、十種香、貝おほひ、様々遊びを仕尽して」
⇒ついまつ‐とり【続松取】
ついまつ‐とり【続松取】
歌ガルタあるいは歌貝を取ってする勝負ごと。
⇒つい‐まつ【続松】
広辞苑に「沈黙」で始まるの検索結果 1-3。