複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (47)
きぬ‐あや【絹綾】🔗⭐🔉
きぬ‐あや【絹綾】
綾織の薄い羅紗ラシャ。
きぬ‐いと【絹糸】🔗⭐🔉
きぬ‐いと【絹糸】
蚕の繭からとった糸。生糸・練糸などがある。
⇒きぬいと‐そう【絹糸草】
⇒きぬいと‐ぼうせき【絹糸紡績】
きぬいと‐そう【絹糸草】‥サウ🔗⭐🔉
きぬいと‐そう【絹糸草】‥サウ
(→)「ひえまき(稗蒔)」に同じ。〈[季]夏〉
⇒きぬ‐いと【絹糸】
きぬいと‐ぼうせき【絹糸紡績】‥バウ‥🔗⭐🔉
きぬいと‐ぼうせき【絹糸紡績】‥バウ‥
⇒けんしぼうせき
⇒きぬ‐いと【絹糸】
きぬ‐うんも【絹雲母】🔗⭐🔉
きぬ‐うんも【絹雲母】
微細な鱗片状白雲母の総称。陶土として利用。
きぬ‐え【絹絵】‥ヱ🔗⭐🔉
きぬ‐え【絹絵】‥ヱ
絹地にかいた絵。
きぬ‐おり【絹織】🔗⭐🔉
きぬ‐おり【絹織】
経緯たてよことも絹糸で織ること。また、その織物。羽二重はぶたえ・縮緬ちりめん・透綾すきや・海気かいき・塩瀬しおぜ・斜子ななこ・紬つむぎ・琥珀こはくなど種類が多い。
⇒きぬおり‐もの【絹織物】
きぬおり‐もの【絹織物】🔗⭐🔉
きぬおり‐もの【絹織物】
絹織の織物。
⇒きぬ‐おり【絹織】
きぬ‐がき【絹垣】🔗⭐🔉
きぬ‐がき【絹垣】
①神祭などの時、垣のようにひきめぐらした絹のとばり。綾垣。古事記中「その山の上に―を張り帷幕を立てて」
②神霊遷御の際に神体の上面・側面を覆う絹布。きんがい。
きぬ‐がさ【衣笠・絹傘・華蓋】🔗⭐🔉
きぬ‐がさ【衣笠・絹傘・華蓋】
①絹張りの長柄の傘。古代、天皇・親王・公卿などの外出時に、背後からさしかざすのに用いた。翳えい。万葉集3「わがおほきみは―にせり」
衣笠
 ②天蓋てんがい。〈倭名類聚鈔14〉
⇒きぬがさ‐そう【衣笠草】
⇒きぬがさ‐たけ【絹傘茸】
②天蓋てんがい。〈倭名類聚鈔14〉
⇒きぬがさ‐そう【衣笠草】
⇒きぬがさ‐たけ【絹傘茸】
 ②天蓋てんがい。〈倭名類聚鈔14〉
⇒きぬがさ‐そう【衣笠草】
⇒きぬがさ‐たけ【絹傘茸】
②天蓋てんがい。〈倭名類聚鈔14〉
⇒きぬがさ‐そう【衣笠草】
⇒きぬがさ‐たけ【絹傘茸】
きぬがさ‐たけ【絹傘茸】🔗⭐🔉
きぬがさ‐たけ【絹傘茸】
担子菌類のきのこ。夏に竹林中に奇異な子実体を生ずる。約10センチメートルの円柱状白色蝋質の茎の上端に鐘形の頭部を有し、表面に網状の突出がある。表面全体をおおう緑褐色の粘液は無数の胞子を含み、悪臭を放つ。また菌の傘の下部から白色の網状のマントを垂下。中国料理で珍重する。コムソウタケ。
⇒きぬ‐がさ【衣笠・絹傘・華蓋】
きぬ‐ぐら【絹座】🔗⭐🔉
きぬ‐ぐら【絹座】
絹を売買する所。宇津保物語藤原君「―にある徳まちといふ市女」
きぬ‐こくら【絹小倉】🔗⭐🔉
きぬ‐こくら【絹小倉】
小倉織に絹紡績糸または撚糸ねんしを用いた洋服地。
きぬ‐ごし【絹漉し】🔗⭐🔉
きぬ‐ごし【絹漉し】
①絹篩きぬぶるいまたは絹で細かに漉すこと。また、その漉した物。
②絹漉し豆腐の略。
⇒きぬごし‐どうふ【絹漉し豆腐】
きぬごし‐どうふ【絹漉し豆腐】🔗⭐🔉
きぬごし‐どうふ【絹漉し豆腐】
濃い豆乳と凝固剤を型箱の中に入れ、上澄みをとらずに全体をかたまらせた豆腐。絹で漉したかのように、きめこまかく滑らかなのでいう。きぬごし。ささのゆき。↔木綿豆腐
⇒きぬ‐ごし【絹漉し】
きぬ‐こまちいと【絹小町糸】🔗⭐🔉
きぬ‐こまちいと【絹小町糸】
紡績絹糸でつくった縫糸。絹小町。
きぬ‐ゴロ【絹呉絽】🔗⭐🔉
きぬ‐ゴロ【絹呉絽】
絹糸でゴロフクレンのように織った織物。
きぬ‐ざ【絹座】🔗⭐🔉
きぬ‐ざ【絹座】
鎌倉時代以後、絹の販売業者の組合。七座の一つ。
きぬ‐サラサ【絹更紗】🔗⭐🔉
きぬ‐サラサ【絹更紗】
絹地に更紗模様を染めたもの。
きぬ‐じ【絹地】‥ヂ🔗⭐🔉
きぬ‐じ【絹地】‥ヂ
①絹織の生地。
②日本画をかくのに用いる絹。絵絹。
きぬ‐じょうふ【絹上布】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
きぬ‐じょうふ【絹上布】‥ジヤウ‥
(→)透綾すきやに同じ。
きぬ‐ずきん【絹頭巾】‥ヅ‥🔗⭐🔉
きぬ‐ずきん【絹頭巾】‥ヅ‥
頭巾の一種。つばはなく、絹布で円柱のやや平たいような形に造り、頭の全部にはめるようにしたもの。
きぬ‐セル【絹セル】🔗⭐🔉
きぬ‐セル【絹セル】
①絹をまぜて織ったセル地。
②絹糸を加工撚糸ねんしとしてセル風に織り出したもの。春秋の衣服に用いる。
きぬ‐ちぢみ【絹縮】🔗⭐🔉
きぬ‐ちぢみ【絹縮】
経たてに生糸、緯よこに左撚よりの強撚糸きょうねんしを用いた絹織物の一種。精練・しぼ出し処理によって片しぼになる。夏の単衣ひとえ・帯揚げ・腰紐などに用いる。きぬち。
きぬ‐てん【絹天】🔗⭐🔉
きぬ‐てん【絹天】
(「天」はビロードの意の「天鵞絨」の略)絹ビロードの一種。一般の別珍より高級なもの。足袋たび・鼻緒・夜具襟えりなどに用いる。
きぬ‐の‐みち【絹の道】🔗⭐🔉
きぬ‐の‐みち【絹の道】
シルクロードの訳語。
きぬ‐ばり【絹針】🔗⭐🔉
きぬ‐ばり【絹針】
絹布を縫うのに用いる細い針。
きぬ‐ばり【絹張り】🔗⭐🔉
きぬ‐ばり【絹張り】
①絹布を張ること。また、張った物。「―の屏風」
②木や竹製の棒で、絹布を洗い張りするときに両端に付け、ひっぱって皺しわをのばす道具。また、それを使って絹布を伸子しんし張りすること。浄瑠璃、堀川波鼓「松の木に―結び」
③絹布をのり張りする板。
きぬ‐ひょうぐ【絹表具・絹裱具】‥ヘウ‥🔗⭐🔉
きぬ‐ひょうぐ【絹表具・絹裱具】‥ヘウ‥
絹布を用いた表具。巻物・掛軸・書画帖・襖ふすま・屏風びょうぶなど。↔紙表具
きぬ‐ふたこ【絹双子】🔗⭐🔉
きぬ‐ふたこ【絹双子】
双子糸に絹糸を少し混ぜて織った双子縞ふたこじま。
きぬまき‐せん【絹巻線】🔗⭐🔉
きぬまき‐せん【絹巻線】
絹糸を絶縁体として被覆した銅線。
きぬ‐モスリン【絹モスリン】🔗⭐🔉
きぬ‐モスリン【絹モスリン】
経緯たてよこともに1本の生糸に強撚を施した糸を用い、きわめて地を薄く平織りにした絹織物。肩掛・カーテンに用いる。シフォン。
きぬ‐もの【絹物】🔗⭐🔉
きぬ‐もの【絹物】
①絹織物。
②絹製の衣服。
きぬ‐や【絹屋】🔗⭐🔉
きぬ‐や【絹屋】
①絹の幕を屋根と四方とに張りめぐらした仮小屋。栄華物語あさ緑「前に―造りて黄牛あめうし飼はせ給ふ」
②絹布を織り、または売る人。また、その家。
○絹を裂くようきぬをさくよう🔗⭐🔉
○絹を裂くようきぬをさくよう
(絹布を裂くとき、高く鋭い音が出ることから)女性の悲鳴など、かん高く鋭い叫び声の形容。
⇒きぬ【絹】
きね【杵】
穀物などを臼に入れてつくのに用いる木製の具。中細。打杵。〈倭名類聚鈔16〉
杵
 横杵
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
横杵
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 竪杵
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
竪杵
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒杵であたり杓子であたる
きね【巫覡】
神に仕える人。巫女かんなぎ。社人。ふげき。拾遺和歌集神楽歌「ときはなる蔭にさかゆる神の―かな」
き‐ね【木根】
(ネは接尾語)木。祝詞、大殿祭「磐根・―」
き‐ねい【帰寧】
[詩経周南、葛覃]
①嫁した女が生家に帰って父母の安否を問うこと。さとがえり。
②男子の帰省。
③諸侯が京師で天子にまみえ、帰って後、人民を安んじ治めること。
きね‐うた【杵歌】
杵で物をつく時にうたう歌。きうた。狂言、勝栗「歌とは田歌か―の事でござりまするか」
キネオラマ【kineorama】
(キネマとパノラマの合成語)パノラマに色光線を用いて景色を変化させて見せる装置。明治末期〜大正初めの興行物の一つ。北原白秋、東京景物詩「日は暮れて河岸かしのかなたは―のごとく灯あかり点き」
ギネス‐ブック【Guinness Book】
(ギネスはアイルランドのビール会社名)多種多様な世界一の記録集。1956年以後毎年発行。
き‐ねずみ【木鼠】
①(→)リスの異称。
②(→)ゴジュウカラの異称。
きね‐たち【木根立】
樹木を切った跡の切り株。
きね‐づか【杵束】
〔建〕上下両端が太く、形が手杵に似た真束しんづか。
きね‐づか【杵柄】
杵のえ。「昔とった―」
⇒杵であたり杓子であたる
きね【巫覡】
神に仕える人。巫女かんなぎ。社人。ふげき。拾遺和歌集神楽歌「ときはなる蔭にさかゆる神の―かな」
き‐ね【木根】
(ネは接尾語)木。祝詞、大殿祭「磐根・―」
き‐ねい【帰寧】
[詩経周南、葛覃]
①嫁した女が生家に帰って父母の安否を問うこと。さとがえり。
②男子の帰省。
③諸侯が京師で天子にまみえ、帰って後、人民を安んじ治めること。
きね‐うた【杵歌】
杵で物をつく時にうたう歌。きうた。狂言、勝栗「歌とは田歌か―の事でござりまするか」
キネオラマ【kineorama】
(キネマとパノラマの合成語)パノラマに色光線を用いて景色を変化させて見せる装置。明治末期〜大正初めの興行物の一つ。北原白秋、東京景物詩「日は暮れて河岸かしのかなたは―のごとく灯あかり点き」
ギネス‐ブック【Guinness Book】
(ギネスはアイルランドのビール会社名)多種多様な世界一の記録集。1956年以後毎年発行。
き‐ねずみ【木鼠】
①(→)リスの異称。
②(→)ゴジュウカラの異称。
きね‐たち【木根立】
樹木を切った跡の切り株。
きね‐づか【杵束】
〔建〕上下両端が太く、形が手杵に似た真束しんづか。
きね‐づか【杵柄】
杵のえ。「昔とった―」
 横杵
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
横杵
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 竪杵
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
竪杵
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ⇒杵であたり杓子であたる
きね【巫覡】
神に仕える人。巫女かんなぎ。社人。ふげき。拾遺和歌集神楽歌「ときはなる蔭にさかゆる神の―かな」
き‐ね【木根】
(ネは接尾語)木。祝詞、大殿祭「磐根・―」
き‐ねい【帰寧】
[詩経周南、葛覃]
①嫁した女が生家に帰って父母の安否を問うこと。さとがえり。
②男子の帰省。
③諸侯が京師で天子にまみえ、帰って後、人民を安んじ治めること。
きね‐うた【杵歌】
杵で物をつく時にうたう歌。きうた。狂言、勝栗「歌とは田歌か―の事でござりまするか」
キネオラマ【kineorama】
(キネマとパノラマの合成語)パノラマに色光線を用いて景色を変化させて見せる装置。明治末期〜大正初めの興行物の一つ。北原白秋、東京景物詩「日は暮れて河岸かしのかなたは―のごとく灯あかり点き」
ギネス‐ブック【Guinness Book】
(ギネスはアイルランドのビール会社名)多種多様な世界一の記録集。1956年以後毎年発行。
き‐ねずみ【木鼠】
①(→)リスの異称。
②(→)ゴジュウカラの異称。
きね‐たち【木根立】
樹木を切った跡の切り株。
きね‐づか【杵束】
〔建〕上下両端が太く、形が手杵に似た真束しんづか。
きね‐づか【杵柄】
杵のえ。「昔とった―」
⇒杵であたり杓子であたる
きね【巫覡】
神に仕える人。巫女かんなぎ。社人。ふげき。拾遺和歌集神楽歌「ときはなる蔭にさかゆる神の―かな」
き‐ね【木根】
(ネは接尾語)木。祝詞、大殿祭「磐根・―」
き‐ねい【帰寧】
[詩経周南、葛覃]
①嫁した女が生家に帰って父母の安否を問うこと。さとがえり。
②男子の帰省。
③諸侯が京師で天子にまみえ、帰って後、人民を安んじ治めること。
きね‐うた【杵歌】
杵で物をつく時にうたう歌。きうた。狂言、勝栗「歌とは田歌か―の事でござりまするか」
キネオラマ【kineorama】
(キネマとパノラマの合成語)パノラマに色光線を用いて景色を変化させて見せる装置。明治末期〜大正初めの興行物の一つ。北原白秋、東京景物詩「日は暮れて河岸かしのかなたは―のごとく灯あかり点き」
ギネス‐ブック【Guinness Book】
(ギネスはアイルランドのビール会社名)多種多様な世界一の記録集。1956年以後毎年発行。
き‐ねずみ【木鼠】
①(→)リスの異称。
②(→)ゴジュウカラの異称。
きね‐たち【木根立】
樹木を切った跡の切り株。
きね‐づか【杵束】
〔建〕上下両端が太く、形が手杵に似た真束しんづか。
きね‐づか【杵柄】
杵のえ。「昔とった―」
きん‐がい【絹垣】🔗⭐🔉
きん‐がい【絹垣】
キヌガキの音便。「錦蓋」とも書く。
けん‐し【絹糸】🔗⭐🔉
けんし‐こうたく【絹糸光沢】‥クワウ‥🔗⭐🔉
けんし‐こうたく【絹糸光沢】‥クワウ‥
絹糸がもつような光沢。珪線石など繊維状結晶の鉱物に見られる。
⇒けん‐し【絹糸】
けんし‐せん【絹糸腺】🔗⭐🔉
けんし‐せん【絹糸腺】
チョウ目・トビケラ目の昆虫の幼虫に発達している一対の外分泌腺。ここから分泌される粘稠ねんちゅう液は、空気にふれると1本に合体されて絹糸となり、繭などをつくる。
⇒けん‐し【絹糸】
けんし‐ぼうせき【絹糸紡績】‥バウ‥🔗⭐🔉
けんし‐ぼうせき【絹糸紡績】‥バウ‥
屑生糸くずきいと・屑繭くずまゆなど屑物の絹繊維を短繊維にして紡績すること。絹紡。
⇒けん‐し【絹糸】
けん‐ちゅう【繭紬・絹紬】‥チウ🔗⭐🔉
けん‐ちゅう【繭紬・絹紬】‥チウ
経緯たてよこに柞蚕糸さくさんしを用いて織った織物。淡褐色を帯びて節がある。中国山東省で多く産出。
けん‐ぷ【絹布】🔗⭐🔉
けん‐ぷ【絹布】
絹糸で織った布。絹織物。
けん‐ぼう【絹紡】‥バウ🔗⭐🔉
けん‐ぼう【絹紡】‥バウ
①絹糸紡績けんしぼうせきの略。
②紡績した絹糸のこと。
⇒けんぼう‐ちりめん【絹紡縮緬】
けんぼう‐ちりめん【絹紡縮緬】‥バウ‥🔗⭐🔉
けんぼう‐ちりめん【絹紡縮緬】‥バウ‥
絹紡2で製した縮緬。
⇒けん‐ぼう【絹紡】
[漢]絹🔗⭐🔉
絹 字形
 筆順
筆順
 〔糸部7画/13画/教育/2408・3828〕
〔音〕ケン(呉)(漢)
〔訓〕きぬ
[意味]
きぬ。蚕の繭まゆからとった糸。生糸で織った布。「絹糸・絹帛けんぱく・絹本・素絹・人絹」
[解字]
形声。右半部は音符で、「
〔糸部7画/13画/教育/2408・3828〕
〔音〕ケン(呉)(漢)
〔訓〕きぬ
[意味]
きぬ。蚕の繭まゆからとった糸。生糸で織った布。「絹糸・絹帛けんぱく・絹本・素絹・人絹」
[解字]
形声。右半部は音符で、「 」(=まるく巻いた虫)の原字。「糸」を加えて、まるく巻いた蚕から取った糸の意。[
」(=まるく巻いた虫)の原字。「糸」を加えて、まるく巻いた蚕から取った糸の意。[ ]は異体字。
[下ツキ
純絹・正絹・人絹・生絹・素絹・本絹
]は異体字。
[下ツキ
純絹・正絹・人絹・生絹・素絹・本絹
 筆順
筆順
 〔糸部7画/13画/教育/2408・3828〕
〔音〕ケン(呉)(漢)
〔訓〕きぬ
[意味]
きぬ。蚕の繭まゆからとった糸。生糸で織った布。「絹糸・絹帛けんぱく・絹本・素絹・人絹」
[解字]
形声。右半部は音符で、「
〔糸部7画/13画/教育/2408・3828〕
〔音〕ケン(呉)(漢)
〔訓〕きぬ
[意味]
きぬ。蚕の繭まゆからとった糸。生糸で織った布。「絹糸・絹帛けんぱく・絹本・素絹・人絹」
[解字]
形声。右半部は音符で、「 」(=まるく巻いた虫)の原字。「糸」を加えて、まるく巻いた蚕から取った糸の意。[
」(=まるく巻いた虫)の原字。「糸」を加えて、まるく巻いた蚕から取った糸の意。[ ]は異体字。
[下ツキ
純絹・正絹・人絹・生絹・素絹・本絹
]は異体字。
[下ツキ
純絹・正絹・人絹・生絹・素絹・本絹
大辞林の検索結果 (47)
きぬ【絹】🔗⭐🔉
きぬ [1] 【絹】
(1)蚕の繭からとった繊維。
(2)絹糸で織った織物。絹織物。
きぬ=を裂(サ)くよう🔗⭐🔉
――を裂(サ)くよう
〔絹の布を裂くときに高く鋭い音が出ることから〕
かん高い鋭い声の形容。多く,女性の声についていう。「―な叫び声が聞こえた」
きぬ-あや【絹綾】🔗⭐🔉
きぬ-あや [2][0] 【絹綾】
薄い綾織りの絹織物。
きぬ-あんどん【絹行灯】🔗⭐🔉
きぬ-あんどん [3] 【絹行灯】
木や竹のわくに絹の布を張った行灯。
きぬ-いと【絹糸】🔗⭐🔉
きぬ-いと [0] 【絹糸】
蚕の繭からとった糸。生糸を含めず,精練した糸のみをいうことが多い。けんし。
きぬいと-そう【絹糸草】🔗⭐🔉
きぬいと-そう ―サウ [0] 【絹糸草】
チモシー(オオアワガエリ)の種を水盤の脱脂綿にまいて萌(モ)え出た糸のような芽のこと。その鮮緑色の涼味を観賞する。[季]夏。
→稗蒔(ヒエマ)き
きぬ-うちわ【絹団扇】🔗⭐🔉
きぬ-うちわ ―ウチハ [4][3] 【絹団扇】
絹の布を張ったうちわ。[季]夏。
きぬ-うんも【絹雲母】🔗⭐🔉
きぬ-うんも [3] 【絹雲母】
白雲母の一種。微細な鱗片状の鉱物。単斜晶系。絹糸状光沢がある。絹雲母結晶片岩の構成鉱物。また,熱水変質によって生成した粘土として産する。良質のものは陶土として利用。
きぬ-え【絹絵】🔗⭐🔉
きぬ-え ― [2] 【絹絵】
絹の布地に描いた絵。
[2] 【絹絵】
絹の布地に描いた絵。
 [2] 【絹絵】
絹の布地に描いた絵。
[2] 【絹絵】
絹の布地に描いた絵。
きぬ-おり【絹織(り)】🔗⭐🔉
きぬ-おり [0] 【絹織(り)】
絹糸で織ること。また,その織った布。
きぬおり-もの【絹織物】🔗⭐🔉
きぬおり-もの [3][4] 【絹織物】
絹糸で織った織物の総称。しなやかで光沢があり,染色性に富むため衣料として古くから用いられた。羽二重・縮緬(チリメン)・御召・紬(ツムギ)など。
きぬ-がき【絹垣】🔗⭐🔉
きぬ-がき [2] 【絹垣】
(1)神祭りなどの際,垣のようにめぐらす絹布のとばり。文垣(アヤガキ)。「亦其の山の上に―を張り帷幕を立てて/古事記(中訓)」
(2)神霊遷宮の際,御神体の上面,側面をおおう絹布。
きぬ-がさ【衣笠・絹傘・蓋】🔗⭐🔉
きぬ-がさ [3][2] 【衣笠・絹傘・蓋】
(1)絹を張った柄の長い傘。古く,貴人の外出の際,後ろからさしかけるのに用いた。「我が大君は―にせり/万葉 240」
(2)仏像にかざす天蓋(テンガイ)。[和名抄]
衣笠(1)
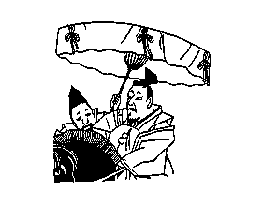 [図]
[図]
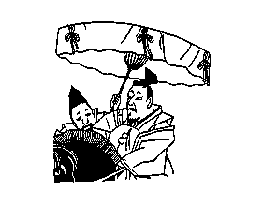 [図]
[図]
きぬがさ-たけ【絹傘茸】🔗⭐🔉
きぬがさ-たけ [4] 【絹傘茸】
担子菌類腹菌目のきのこ。夏から秋にかけ竹林などに生える。初め,径4センチメートルほどの球形の外皮につつまれ,数時間で茎の高さ15センチメートルあまりに生長する。頭に鐘形で悪臭を放つ傘をかぶり,その下部から純白の網状のレースを垂らす。中国料理で珍重する。コムソウタケ。
絹笠茸
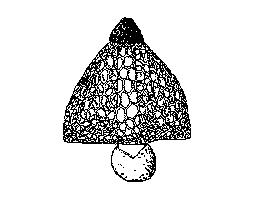 [図]
[図]
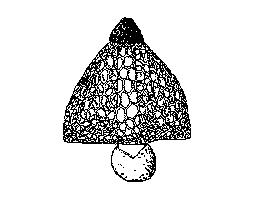 [図]
[図]
きぬ-かわ【絹皮】🔗⭐🔉
きぬ-かわ ―カハ [2][0] 【絹皮】
「姫皮(ヒメカワ)」に同じ。
きぬ-こくら【絹小倉】🔗⭐🔉
きぬ-こくら [3] 【絹小倉】
経(タテ)糸・緯(ヨコ)糸ともに絹紡糸を用いた小倉織り。夏服地とする。
きぬ-ごし【絹漉し】🔗⭐🔉
きぬ-ごし [0] 【絹漉し】
(1)絹のふるいや袋などでこすこと。また,こしたもの。
(2)「絹漉し豆腐」の略。
きぬごし-どうふ【絹漉し豆腐】🔗⭐🔉
きぬごし-どうふ [5] 【絹漉し豆腐】
濃厚な豆乳に適量の苦汁(ニガリ)を加え,そのまま器の中で静かに固めた豆腐。木綿豆腐のように布でこさないので,布目がなくきめが細かい。きぬごし。あわゆきどうふ。ささのゆき。
きぬ-こまち【絹小町】🔗⭐🔉
きぬ-こまち [3] 【絹小町】
紡績絹糸を縒(ヨ)り合わせた縫い糸。絹小町糸。
きぬ-ゴロ【絹―】🔗⭐🔉
きぬ-ゴロ [0][3] 【絹―】
毛織物のゴロフクレンに似せて織った絹織物。多くは,黒色で夏服に用いる。
きぬ-サラサ【絹―】🔗⭐🔉
きぬ-サラサ [3][4] 【絹―】
更紗(サラサ)模様を染め出した絹地。
きぬ-ざる【絹猿】🔗⭐🔉
きぬ-ざる [3] 【絹猿】
マーモセットの別名。
きぬ-じ【絹地】🔗⭐🔉
きぬ-じ ―ヂ [0] 【絹地】
(1)絹織物の布地。
(2)日本画を描くのに用いる絹布。絵絹。
きぬ-じょうふ【絹上布】🔗⭐🔉
きぬ-じょうふ ―ジヤウフ [3] 【絹上布】
上布のようにさらりとした手ざわりの薄地の絹織物。夏の着尺に用いる。透綾(スキヤ)。
きぬ-ずきん【絹頭巾】🔗⭐🔉
きぬ-ずきん ―ヅキン [3] 【絹頭巾】
絹布でやや平たい円筒形に作り,頭が全部はまるようにした,錣(シコロ)のない頭巾。
きぬ-セル【絹―】🔗⭐🔉
きぬ-セル [0] 【絹―】
(1)経(タテ)糸を絹,緯(ヨコ)糸を梳毛(ソモウ)糸で織ったセル風の交織(コウシヨク)織物。
(2)経(タテ)・緯(ヨコ)ともに絹糸を使い,糸の縒(ヨ)り方でセルの風合いをもたせた織物。
きぬ-ちぢみ【絹縮】🔗⭐🔉
きぬ-ちぢみ [3] 【絹縮】
絹糸で織ったちぢみ。たてしぼのあるのが特徴。
きぬ-てん【絹天】🔗⭐🔉
きぬ-てん [0] 【絹天】
〔「天」はビロードの当て字「天鵞絨」の略〕
絹のビロード。明治から大正にかけて,足袋(タビ)・鼻緒・夜具襟などに用いられた。
きぬ-の-みち【絹の道】🔗⭐🔉
きぬ-の-みち 【絹の道】
⇒シルク-ロード
きぬ-ばた【絹機】🔗⭐🔉
きぬ-ばた [2] 【絹機】
絹布を織る手織りの機械。
きぬ-ばり【絹針】🔗⭐🔉
きぬ-ばり [3][2] 【絹針】
絹布を縫うのに用いる細い針。
きぬ-ばり【絹張(り)】🔗⭐🔉
きぬ-ばり [0] 【絹張(り)】
(1)絹布を物の表面に張ること。また,張ったもの。「―の屏風」
(2)絹布を洗い張りする時,その両端につけて引っ張ってしわをのばすための木の棒。
(3)スズキ目の海魚。ハゼ類の一種。全長11センチメートルほど。地色が黄色,もしくは帯紫色で,体側に六,七本の黒褐色の横帯があり美しい。東北地方以南の沿岸に分布。
きぬ-ひょうぐ【絹表具】🔗⭐🔉
きぬ-ひょうぐ ―ヘウグ [3] 【絹表具】
絹布を使った表具。絹表装。
きぬまき-せん【絹巻(き)線】🔗⭐🔉
きぬまき-せん [0] 【絹巻(き)線】
絶縁体として絹糸を緊密に巻きつけた銅線。
きぬ-モスリン【絹―】🔗⭐🔉
きぬ-モスリン [3] 【絹―】
⇒シフォン
きぬ-やつし【絹やつし】🔗⭐🔉
きぬ-やつし [3] 【絹やつし】
歌舞伎で,絹物の衣装のこと。
けん-うん【巻雲・絹雲】🔗⭐🔉
けん-うん [0] 【巻雲・絹雲】
対流圏の上部に現れる氷晶よりなる雲。俗にすじ雲と呼ばれ,繊細な繊維状の雲。気温が摂氏約マイナス二〇度以下のところに現れる。
けんし-せん【絹糸腺】🔗⭐🔉
けんし-せん [0] 【絹糸腺】
昆虫の鱗翅(リンシ)目・毛翅目などの幼虫にみられる一対の外分泌腺。分泌物は空気に触れて絹糸となり繭や巣をつくる。カイコガでよく発達している。
けんし-ぼうせき【絹糸紡績】🔗⭐🔉
けんし-ぼうせき ―バウ― [4] 【絹糸紡績】
屑繭や製糸の際に出る絹糸屑などをほぐして糸にする紡績。絹紡。
けんせき-うん【巻積雲・絹積雲】🔗⭐🔉
けんせき-うん [3][4] 【巻積雲・絹積雲】
上層雲の一種。白雲の小さな塊が群集してまだら状または波状をなすもの。氷晶が集まったもので,通常6〜10キロメートルの高さに現れる。まだら雲。さば雲。うろこ雲。いわし雲。記号 Cc
けんそう-うん【巻層雲・絹層雲】🔗⭐🔉
けんそう-うん [3] 【巻層雲・絹層雲】
上層雲の一種。通常5〜13キロメートルの高さに現れる。薄い白いベール状で,空一面にひろがることが多い。氷晶からなる。記号 Cs
けん-ちゅう【絹紬・繭紬】🔗⭐🔉
けん-ちゅう ―チウ [1] 【絹紬・繭紬】
柞蚕糸(サクサンシ)を経緯(タテヨコ)に用いた薄地の平織物。
けん-ぷ【絹布】🔗⭐🔉
けん-ぷ [1] 【絹布】
絹糸で織った布。絹織物。
きぬ【絹】(和英)🔗⭐🔉
けんし【絹糸】(和英)🔗⭐🔉
けんし【絹糸】
silk thread.
けんぷ【絹布】(和英)🔗⭐🔉
けんぷ【絹布】
silk;→英和
silk cloth[stuff].
広辞苑+大辞林に「絹」で始まるの検索結果。もっと読み込む