複数辞典一括検索+![]()
![]()
攻 せめる🔗⭐🔉
【攻】
 7画 攴部 [常用漢字]
区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55
《常用音訓》コウ/せ…める
《音読み》 コウ
7画 攴部 [常用漢字]
区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55
《常用音訓》コウ/せ…める
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g ng〉
《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)
《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)
《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし
《意味》
 {動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕
{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕
 {動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕
{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕
 {動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」
《解字》
会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。
《単語家族》
空(突き抜けた)
{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」
《解字》
会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。
《単語家族》
空(突き抜けた) 孔(突き抜けたあな)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
孔(突き抜けたあな)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 7画 攴部 [常用漢字]
区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55
《常用音訓》コウ/せ…める
《音読み》 コウ
7画 攴部 [常用漢字]
区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55
《常用音訓》コウ/せ…める
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g ng〉
《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)
《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)
《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし
《意味》
 {動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕
{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕
 {動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕
{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕
 {動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」
《解字》
会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。
《単語家族》
空(突き抜けた)
{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」
《解字》
会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。
《単語家族》
空(突き抜けた) 孔(突き抜けたあな)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
孔(突き抜けたあな)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
訟 せめる🔗⭐🔉
【訟】
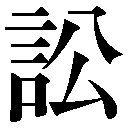 11画 言部 [常用漢字]
区点=3057 16進=3E59 シフトJIS=8FD7
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ
11画 言部 [常用漢字]
区点=3057 16進=3E59 シフトJIS=8FD7
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ /ズ/ジュ
/ズ/ジュ 〈s
〈s ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/うったえ(うつたへ)/せめる(せむ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/うったえ(うつたへ)/せめる(せむ)
《意味》
 {動・名}あらそう(アラソフ)。うったえる(ウツタフ)。うったえ(ウツタヘ)。公の場所で、あけすけにいい分をいいとおす。裁判でいいあらそう。いいあらそい。「訴訟」「訟獄者、不之
{動・名}あらそう(アラソフ)。うったえる(ウツタフ)。うったえ(ウツタヘ)。公の場所で、あけすけにいい分をいいとおす。裁判でいいあらそう。いいあらそい。「訴訟」「訟獄者、不之 之子、而之舜=獄ニ訟フル者、
之子、而之舜=獄ニ訟フル者、 ノ子ニ之カズシテ、舜ニ之ク」〔→孟子〕「必也使無訟乎=必ズヤ訟無カラシメンカ」〔→論語〕
ノ子ニ之カズシテ、舜ニ之ク」〔→孟子〕「必也使無訟乎=必ズヤ訟無カラシメンカ」〔→論語〕
 {動}せめる(セム)。あけすけに議論する。条理をいいあらそう。まちがいをとがめる。「訟論」「吾未見能見其過、而内自訟者也=吾イマダヨクソノ過チヲ見テ、内ニミヅカラ訟ムル者ヲ見ザルナリ」〔→論語〕
{動}せめる(セム)。あけすけに議論する。条理をいいあらそう。まちがいをとがめる。「訟論」「吾未見能見其過、而内自訟者也=吾イマダヨクソノ過チヲ見テ、内ニミヅカラ訟ムル者ヲ見ザルナリ」〔→論語〕
 {名}周易の六十四卦カの一つ。坎下乾上カンカケンショウの形で、裏では弱く表では強くいいあらそうさまをあらわす。
《解字》
会意兼形声。公は、松ショウ・頌ショウの場合と同じでショウの音をあらわし、あけすけに通るの意を含む。訟は「言+音符公」で、ことばであけすけにいうこと。
《単語家族》
頌ショウ(あけすけにとなえる)
{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下乾上カンカケンショウの形で、裏では弱く表では強くいいあらそうさまをあらわす。
《解字》
会意兼形声。公は、松ショウ・頌ショウの場合と同じでショウの音をあらわし、あけすけに通るの意を含む。訟は「言+音符公」で、ことばであけすけにいうこと。
《単語家族》
頌ショウ(あけすけにとなえる) 誦ショウ(あけすけにいいとおす)
誦ショウ(あけすけにいいとおす) 松(葉があけすけに離れ、すきまが通っているまつ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
松(葉があけすけに離れ、すきまが通っているまつ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
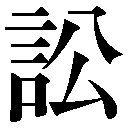 11画 言部 [常用漢字]
区点=3057 16進=3E59 シフトJIS=8FD7
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ
11画 言部 [常用漢字]
区点=3057 16進=3E59 シフトJIS=8FD7
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ /ズ/ジュ
/ズ/ジュ 〈s
〈s ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/うったえ(うつたへ)/せめる(せむ)
《意味》
ng〉
《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/うったえ(うつたへ)/せめる(せむ)
《意味》
 {動・名}あらそう(アラソフ)。うったえる(ウツタフ)。うったえ(ウツタヘ)。公の場所で、あけすけにいい分をいいとおす。裁判でいいあらそう。いいあらそい。「訴訟」「訟獄者、不之
{動・名}あらそう(アラソフ)。うったえる(ウツタフ)。うったえ(ウツタヘ)。公の場所で、あけすけにいい分をいいとおす。裁判でいいあらそう。いいあらそい。「訴訟」「訟獄者、不之 之子、而之舜=獄ニ訟フル者、
之子、而之舜=獄ニ訟フル者、 ノ子ニ之カズシテ、舜ニ之ク」〔→孟子〕「必也使無訟乎=必ズヤ訟無カラシメンカ」〔→論語〕
ノ子ニ之カズシテ、舜ニ之ク」〔→孟子〕「必也使無訟乎=必ズヤ訟無カラシメンカ」〔→論語〕
 {動}せめる(セム)。あけすけに議論する。条理をいいあらそう。まちがいをとがめる。「訟論」「吾未見能見其過、而内自訟者也=吾イマダヨクソノ過チヲ見テ、内ニミヅカラ訟ムル者ヲ見ザルナリ」〔→論語〕
{動}せめる(セム)。あけすけに議論する。条理をいいあらそう。まちがいをとがめる。「訟論」「吾未見能見其過、而内自訟者也=吾イマダヨクソノ過チヲ見テ、内ニミヅカラ訟ムル者ヲ見ザルナリ」〔→論語〕
 {名}周易の六十四卦カの一つ。坎下乾上カンカケンショウの形で、裏では弱く表では強くいいあらそうさまをあらわす。
《解字》
会意兼形声。公は、松ショウ・頌ショウの場合と同じでショウの音をあらわし、あけすけに通るの意を含む。訟は「言+音符公」で、ことばであけすけにいうこと。
《単語家族》
頌ショウ(あけすけにとなえる)
{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下乾上カンカケンショウの形で、裏では弱く表では強くいいあらそうさまをあらわす。
《解字》
会意兼形声。公は、松ショウ・頌ショウの場合と同じでショウの音をあらわし、あけすけに通るの意を含む。訟は「言+音符公」で、ことばであけすけにいうこと。
《単語家族》
頌ショウ(あけすけにとなえる) 誦ショウ(あけすけにいいとおす)
誦ショウ(あけすけにいいとおす) 松(葉があけすけに離れ、すきまが通っているまつ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
松(葉があけすけに離れ、すきまが通っているまつ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
訶 せめる🔗⭐🔉
【訶】
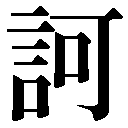 12画 言部
区点=7537 16進=6B45 シフトJIS=E664
《音読み》 カ
12画 言部
区点=7537 16進=6B45 シフトJIS=E664
《音読み》 カ
 〈h
〈h 〉
《訓読み》 しかる/せめる(せむ)
《意味》
〉
《訓読み》 しかる/せめる(せむ)
《意味》
 {動}しかる。大声でどなってしかる。のどをかすらせてどなりつける。〈同義語〉→呵。〈類義語〉→喝カツ。「詆訶テイカ」
{動}しかる。大声でどなってしかる。のどをかすらせてどなりつける。〈同義語〉→呵。〈類義語〉→喝カツ。「詆訶テイカ」
 {動}せめる(セム)。とがめる。「譴訶ケンカ」
{動}せめる(セム)。とがめる。「譴訶ケンカ」
 {形}はっと強い息を出すさま。「訶訶カカ」
《解字》
会意兼形声。可は、かぎ型に曲がる、まっすぐにいかず、かどでまさつをおこすという基本義を持つ。まがりなりにも承知すること。訶は「言+音符可」で、のどもとに強いまさつをおこしてどなること。喝カツ(どなる)は、その語尾が転じた語。
《類義》
→叱
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}はっと強い息を出すさま。「訶訶カカ」
《解字》
会意兼形声。可は、かぎ型に曲がる、まっすぐにいかず、かどでまさつをおこすという基本義を持つ。まがりなりにも承知すること。訶は「言+音符可」で、のどもとに強いまさつをおこしてどなること。喝カツ(どなる)は、その語尾が転じた語。
《類義》
→叱
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
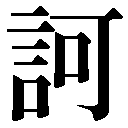 12画 言部
区点=7537 16進=6B45 シフトJIS=E664
《音読み》 カ
12画 言部
区点=7537 16進=6B45 シフトJIS=E664
《音読み》 カ
 〈h
〈h 〉
《訓読み》 しかる/せめる(せむ)
《意味》
〉
《訓読み》 しかる/せめる(せむ)
《意味》
 {動}しかる。大声でどなってしかる。のどをかすらせてどなりつける。〈同義語〉→呵。〈類義語〉→喝カツ。「詆訶テイカ」
{動}しかる。大声でどなってしかる。のどをかすらせてどなりつける。〈同義語〉→呵。〈類義語〉→喝カツ。「詆訶テイカ」
 {動}せめる(セム)。とがめる。「譴訶ケンカ」
{動}せめる(セム)。とがめる。「譴訶ケンカ」
 {形}はっと強い息を出すさま。「訶訶カカ」
《解字》
会意兼形声。可は、かぎ型に曲がる、まっすぐにいかず、かどでまさつをおこすという基本義を持つ。まがりなりにも承知すること。訶は「言+音符可」で、のどもとに強いまさつをおこしてどなること。喝カツ(どなる)は、その語尾が転じた語。
《類義》
→叱
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}はっと強い息を出すさま。「訶訶カカ」
《解字》
会意兼形声。可は、かぎ型に曲がる、まっすぐにいかず、かどでまさつをおこすという基本義を持つ。まがりなりにも承知すること。訶は「言+音符可」で、のどもとに強いまさつをおこしてどなること。喝カツ(どなる)は、その語尾が転じた語。
《類義》
→叱
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
詭 せめる🔗⭐🔉
【詭】
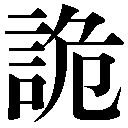 13画 言部
区点=7544 16進=6B4C シフトJIS=E66B
《音読み》 キ(ク
13画 言部
区点=7544 16進=6B4C シフトJIS=E66B
《音読み》 キ(ク )
)
 〈gu
〈gu 〉
《訓読み》 せめる(せむ)/いつわる(いつはる)/たがう(たがふ)
《意味》
〉
《訓読み》 せめる(せむ)/いつわる(いつはる)/たがう(たがふ)
《意味》
 {動}せめる(セム)。きつくせめ求める。「詭求キキュウ」
{動}せめる(セム)。きつくせめ求める。「詭求キキュウ」
 {動}いつわる(イツハル)。変な計略を用いて人をだます。悪だくみで人をあざむく。こじつける。「詭計キケイ」「詭辞而出=辞ヲ詭ツテ出ヅ」〔→穀梁〕
{動}いつわる(イツハル)。変な計略を用いて人をだます。悪だくみで人をあざむく。こじつける。「詭計キケイ」「詭辞而出=辞ヲ詭ツテ出ヅ」〔→穀梁〕
 {動・形}たがう(タガフ)。ふつうの姿や道理と異なる。「有所詭於天之理与=天之理ニ詭フ所有ルカ」〔→漢書〕
{動・形}たがう(タガフ)。ふつうの姿や道理と異なる。「有所詭於天之理与=天之理ニ詭フ所有ルカ」〔→漢書〕
 キナリ{形}ふつうのものとちがうさま。特異であるさま。「詭形キケイ」「殊形詭制シュケイキセイ」
《解字》
会意兼形声。「言+音符危(変にとがった、並はずれてきつい)」。こじつけや、変なたくらみのことばをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
キナリ{形}ふつうのものとちがうさま。特異であるさま。「詭形キケイ」「殊形詭制シュケイキセイ」
《解字》
会意兼形声。「言+音符危(変にとがった、並はずれてきつい)」。こじつけや、変なたくらみのことばをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
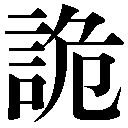 13画 言部
区点=7544 16進=6B4C シフトJIS=E66B
《音読み》 キ(ク
13画 言部
区点=7544 16進=6B4C シフトJIS=E66B
《音読み》 キ(ク )
)
 〈gu
〈gu 〉
《訓読み》 せめる(せむ)/いつわる(いつはる)/たがう(たがふ)
《意味》
〉
《訓読み》 せめる(せむ)/いつわる(いつはる)/たがう(たがふ)
《意味》
 {動}せめる(セム)。きつくせめ求める。「詭求キキュウ」
{動}せめる(セム)。きつくせめ求める。「詭求キキュウ」
 {動}いつわる(イツハル)。変な計略を用いて人をだます。悪だくみで人をあざむく。こじつける。「詭計キケイ」「詭辞而出=辞ヲ詭ツテ出ヅ」〔→穀梁〕
{動}いつわる(イツハル)。変な計略を用いて人をだます。悪だくみで人をあざむく。こじつける。「詭計キケイ」「詭辞而出=辞ヲ詭ツテ出ヅ」〔→穀梁〕
 {動・形}たがう(タガフ)。ふつうの姿や道理と異なる。「有所詭於天之理与=天之理ニ詭フ所有ルカ」〔→漢書〕
{動・形}たがう(タガフ)。ふつうの姿や道理と異なる。「有所詭於天之理与=天之理ニ詭フ所有ルカ」〔→漢書〕
 キナリ{形}ふつうのものとちがうさま。特異であるさま。「詭形キケイ」「殊形詭制シュケイキセイ」
《解字》
会意兼形声。「言+音符危(変にとがった、並はずれてきつい)」。こじつけや、変なたくらみのことばをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
キナリ{形}ふつうのものとちがうさま。特異であるさま。「詭形キケイ」「殊形詭制シュケイキセイ」
《解字》
会意兼形声。「言+音符危(変にとがった、並はずれてきつい)」。こじつけや、変なたくらみのことばをあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
誅 せめる🔗⭐🔉
【誅】
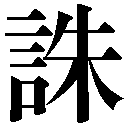 13画 言部
区点=7547 16進=6B4F シフトJIS=E66E
《音読み》 チュウ
13画 言部
区点=7547 16進=6B4F シフトJIS=E66E
《音読み》 チュウ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 ころす/ほろぼす/せめる(せむ)
《意味》
〉
《訓読み》 ころす/ほろぼす/せめる(せむ)
《意味》
 チュウス{動・名}ころす。罪をせめてころす。死刑。「罪不容誅=罪誅ヲ容サレズ」〔→漢書〕
チュウス{動・名}ころす。罪をせめてころす。死刑。「罪不容誅=罪誅ヲ容サレズ」〔→漢書〕
 チュウス{動・名}ほろぼす。罪のある者に関係している者をすべてころす。一族を皆ごろしにする。皆ごろしの刑罰。「誅伐チュウバツ」
チュウス{動・名}ほろぼす。罪のある者に関係している者をすべてころす。一族を皆ごろしにする。皆ごろしの刑罰。「誅伐チュウバツ」
 チュウス{動}せめる(セム)。責任や罪を数えたててせめる。とがめる。「筆誅ヒッチュウ」「於予与何誅=予ニオイテカナンゾ誅メン」〔→論語〕
チュウス{動}せめる(セム)。責任や罪を数えたててせめる。とがめる。「筆誅ヒッチュウ」「於予与何誅=予ニオイテカナンゾ誅メン」〔→論語〕
 チュウス{動}草木を切り払い除く。「誅茅=茅ヲ誅ス」
《解字》
会意兼形声。「言+音符朱(ばっさりと木の株を切る)」で、相手の罪を言明してばっさりと切りころすこと。
《単語家族》
殊(胴切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
チュウス{動}草木を切り払い除く。「誅茅=茅ヲ誅ス」
《解字》
会意兼形声。「言+音符朱(ばっさりと木の株を切る)」で、相手の罪を言明してばっさりと切りころすこと。
《単語家族》
殊(胴切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
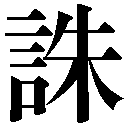 13画 言部
区点=7547 16進=6B4F シフトJIS=E66E
《音読み》 チュウ
13画 言部
区点=7547 16進=6B4F シフトJIS=E66E
《音読み》 チュウ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 ころす/ほろぼす/せめる(せむ)
《意味》
〉
《訓読み》 ころす/ほろぼす/せめる(せむ)
《意味》
 チュウス{動・名}ころす。罪をせめてころす。死刑。「罪不容誅=罪誅ヲ容サレズ」〔→漢書〕
チュウス{動・名}ころす。罪をせめてころす。死刑。「罪不容誅=罪誅ヲ容サレズ」〔→漢書〕
 チュウス{動・名}ほろぼす。罪のある者に関係している者をすべてころす。一族を皆ごろしにする。皆ごろしの刑罰。「誅伐チュウバツ」
チュウス{動・名}ほろぼす。罪のある者に関係している者をすべてころす。一族を皆ごろしにする。皆ごろしの刑罰。「誅伐チュウバツ」
 チュウス{動}せめる(セム)。責任や罪を数えたててせめる。とがめる。「筆誅ヒッチュウ」「於予与何誅=予ニオイテカナンゾ誅メン」〔→論語〕
チュウス{動}せめる(セム)。責任や罪を数えたててせめる。とがめる。「筆誅ヒッチュウ」「於予与何誅=予ニオイテカナンゾ誅メン」〔→論語〕
 チュウス{動}草木を切り払い除く。「誅茅=茅ヲ誅ス」
《解字》
会意兼形声。「言+音符朱(ばっさりと木の株を切る)」で、相手の罪を言明してばっさりと切りころすこと。
《単語家族》
殊(胴切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
チュウス{動}草木を切り払い除く。「誅茅=茅ヲ誅ス」
《解字》
会意兼形声。「言+音符朱(ばっさりと木の株を切る)」で、相手の罪を言明してばっさりと切りころすこと。
《単語家族》
殊(胴切り)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
誚 せめる🔗⭐🔉
謫 せめる🔗⭐🔉
【謫】
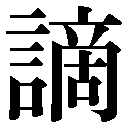 18画 言部
区点=7583 16進=6B73 シフトJIS=E693
《音読み》 タク
18画 言部
区点=7583 16進=6B73 シフトJIS=E693
《音読み》 タク /チャク
/チャク 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 せめる(せむ)/つみする(つみす)/つみ
《意味》
〉
《訓読み》 せめる(せむ)/つみする(つみす)/つみ
《意味》
 タクス{動}せめる(セム)。つみする(ツミス)。罪をせめる。また、罪をせめて罰する。「国子謫我=国子我ヲ謫セントス」〔→左伝〕
タクス{動}せめる(セム)。つみする(ツミス)。罪をせめる。また、罪をせめて罰する。「国子謫我=国子我ヲ謫セントス」〔→左伝〕
 タクス・タクセラル{動}官職をおとして地方の役人にしたり、辺境の防備につかせたりする。また、官職をおとされて地方に流される。「流謫ルタク」「謫守巴陵郡=謫セラレテ巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕
タクス・タクセラル{動}官職をおとして地方の役人にしたり、辺境の防備につかせたりする。また、官職をおとされて地方に流される。「流謫ルタク」「謫守巴陵郡=謫セラレテ巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕
 {名}つみ。とがめ。
《解字》
会意兼形声。「言+音符適テキ(まともにあたる)の略体」。まともに人に非難をぶちあてること。
《単語家族》
敵(まともにぶつかる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}つみ。とがめ。
《解字》
会意兼形声。「言+音符適テキ(まともにあたる)の略体」。まともに人に非難をぶちあてること。
《単語家族》
敵(まともにぶつかる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
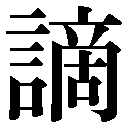 18画 言部
区点=7583 16進=6B73 シフトJIS=E693
《音読み》 タク
18画 言部
区点=7583 16進=6B73 シフトJIS=E693
《音読み》 タク /チャク
/チャク 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 せめる(せむ)/つみする(つみす)/つみ
《意味》
〉
《訓読み》 せめる(せむ)/つみする(つみす)/つみ
《意味》
 タクス{動}せめる(セム)。つみする(ツミス)。罪をせめる。また、罪をせめて罰する。「国子謫我=国子我ヲ謫セントス」〔→左伝〕
タクス{動}せめる(セム)。つみする(ツミス)。罪をせめる。また、罪をせめて罰する。「国子謫我=国子我ヲ謫セントス」〔→左伝〕
 タクス・タクセラル{動}官職をおとして地方の役人にしたり、辺境の防備につかせたりする。また、官職をおとされて地方に流される。「流謫ルタク」「謫守巴陵郡=謫セラレテ巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕
タクス・タクセラル{動}官職をおとして地方の役人にしたり、辺境の防備につかせたりする。また、官職をおとされて地方に流される。「流謫ルタク」「謫守巴陵郡=謫セラレテ巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕
 {名}つみ。とがめ。
《解字》
会意兼形声。「言+音符適テキ(まともにあたる)の略体」。まともに人に非難をぶちあてること。
《単語家族》
敵(まともにぶつかる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}つみ。とがめ。
《解字》
会意兼形声。「言+音符適テキ(まともにあたる)の略体」。まともに人に非難をぶちあてること。
《単語家族》
敵(まともにぶつかる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
譲 せめる🔗⭐🔉
【譲】
 20画 言部 [常用漢字]
区点=3089 16進=3E79 シフトJIS=8FF7
【讓】旧字人名に使える旧字
20画 言部 [常用漢字]
区点=3089 16進=3E79 シフトJIS=8FF7
【讓】旧字人名に使える旧字
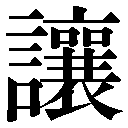 24画 言部
区点=7610 16進=6C2A シフトJIS=E6A8
《常用音訓》ジョウ/ゆず…る
《音読み》 ジョウ(ジャウ)
24画 言部
区点=7610 16進=6C2A シフトJIS=E6A8
《常用音訓》ジョウ/ゆず…る
《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ニョウ(ニャウ)
/ニョウ(ニャウ) 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 ゆずる(ゆづる)/せめる(せむ)
《名付け》 うや・せむ・のり・まさ・ゆずり・ゆずる・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 ゆずる(ゆづる)/せめる(せむ)
《名付け》 うや・せむ・のり・まさ・ゆずり・ゆずる・よし
《意味》
 {動}ゆずる(ユヅル)。場所をあけてわりこませる。「譲歩」「三以天下譲=三タビ天下ヲモッテ譲ル」〔→論語〕
{動}ゆずる(ユヅル)。場所をあけてわりこませる。「譲歩」「三以天下譲=三タビ天下ヲモッテ譲ル」〔→論語〕
 {動・形・名}自分をあとにして人を先にする。ひかえめな。ひかえめな態度や行い。「謙譲」「遜譲ソンジョウ」「揖譲而入=揖譲シテ入ル」〔→礼記〕「禁者、政之本也、譲者、徳之主也=禁ハ、政ノ本ナリ、譲ハ、徳ノ本ナリ」〔→晏子〕
{動・形・名}自分をあとにして人を先にする。ひかえめな。ひかえめな態度や行い。「謙譲」「遜譲ソンジョウ」「揖譲而入=揖譲シテ入ル」〔→礼記〕「禁者、政之本也、譲者、徳之主也=禁ハ、政ノ本ナリ、譲ハ、徳ノ本ナリ」〔→晏子〕
 {動}せめる(セム)。理屈で相手をせめたてる。なじる。「責譲」
{動}せめる(セム)。理屈で相手をせめたてる。なじる。「責譲」
 {助動}〔俗〕本人の希望どおりにさせてあげる。また、させてもらう。
《解字》
会意兼形声。襄ジョウは、中にわりこむの意を含む。讓は「言+音符襄」で、どうぞといって間にわりこませること。転じて、間にはさんで両わきからせめる意ともなる。
《単語家族》
釀ジョウ(=醸。こうじを中にわりこませて酒をかもす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{助動}〔俗〕本人の希望どおりにさせてあげる。また、させてもらう。
《解字》
会意兼形声。襄ジョウは、中にわりこむの意を含む。讓は「言+音符襄」で、どうぞといって間にわりこませること。転じて、間にはさんで両わきからせめる意ともなる。
《単語家族》
釀ジョウ(=醸。こうじを中にわりこませて酒をかもす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 20画 言部 [常用漢字]
区点=3089 16進=3E79 シフトJIS=8FF7
【讓】旧字人名に使える旧字
20画 言部 [常用漢字]
区点=3089 16進=3E79 シフトJIS=8FF7
【讓】旧字人名に使える旧字
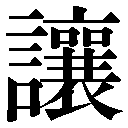 24画 言部
区点=7610 16進=6C2A シフトJIS=E6A8
《常用音訓》ジョウ/ゆず…る
《音読み》 ジョウ(ジャウ)
24画 言部
区点=7610 16進=6C2A シフトJIS=E6A8
《常用音訓》ジョウ/ゆず…る
《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ニョウ(ニャウ)
/ニョウ(ニャウ) 〈r
〈r ng〉
《訓読み》 ゆずる(ゆづる)/せめる(せむ)
《名付け》 うや・せむ・のり・まさ・ゆずり・ゆずる・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 ゆずる(ゆづる)/せめる(せむ)
《名付け》 うや・せむ・のり・まさ・ゆずり・ゆずる・よし
《意味》
 {動}ゆずる(ユヅル)。場所をあけてわりこませる。「譲歩」「三以天下譲=三タビ天下ヲモッテ譲ル」〔→論語〕
{動}ゆずる(ユヅル)。場所をあけてわりこませる。「譲歩」「三以天下譲=三タビ天下ヲモッテ譲ル」〔→論語〕
 {動・形・名}自分をあとにして人を先にする。ひかえめな。ひかえめな態度や行い。「謙譲」「遜譲ソンジョウ」「揖譲而入=揖譲シテ入ル」〔→礼記〕「禁者、政之本也、譲者、徳之主也=禁ハ、政ノ本ナリ、譲ハ、徳ノ本ナリ」〔→晏子〕
{動・形・名}自分をあとにして人を先にする。ひかえめな。ひかえめな態度や行い。「謙譲」「遜譲ソンジョウ」「揖譲而入=揖譲シテ入ル」〔→礼記〕「禁者、政之本也、譲者、徳之主也=禁ハ、政ノ本ナリ、譲ハ、徳ノ本ナリ」〔→晏子〕
 {動}せめる(セム)。理屈で相手をせめたてる。なじる。「責譲」
{動}せめる(セム)。理屈で相手をせめたてる。なじる。「責譲」
 {助動}〔俗〕本人の希望どおりにさせてあげる。また、させてもらう。
《解字》
会意兼形声。襄ジョウは、中にわりこむの意を含む。讓は「言+音符襄」で、どうぞといって間にわりこませること。転じて、間にはさんで両わきからせめる意ともなる。
《単語家族》
釀ジョウ(=醸。こうじを中にわりこませて酒をかもす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{助動}〔俗〕本人の希望どおりにさせてあげる。また、させてもらう。
《解字》
会意兼形声。襄ジョウは、中にわりこむの意を含む。讓は「言+音符襄」で、どうぞといって間にわりこませること。転じて、間にはさんで両わきからせめる意ともなる。
《単語家族》
釀ジョウ(=醸。こうじを中にわりこませて酒をかもす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
譴 せめる🔗⭐🔉
責 せめる🔗⭐🔉
【責】
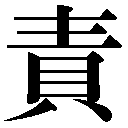 11画 貝部 [五年]
区点=3253 16進=4055 シフトJIS=90D3
《常用音訓》セキ/せ…める
《音読み》 セキ
11画 貝部 [五年]
区点=3253 16進=4055 シフトJIS=90D3
《常用音訓》セキ/せ…める
《音読み》 セキ /サク
/サク /シャク
/シャク 〈z
〈z 〉
《訓読み》 せめる(せむ)/せめ
《意味》
〉
《訓読み》 せめる(せむ)/せめ
《意味》
 {動}せめる(セム)。とげでさすようにとがめる。ちくちくと、とがめさいなむ。「叱責シッセキ(しかる)」「呵責カシャク(きびしく、しかりとがめる)」
{動}せめる(セム)。とげでさすようにとがめる。ちくちくと、とがめさいなむ。「叱責シッセキ(しかる)」「呵責カシャク(きびしく、しかりとがめる)」
 {動・名}せめる(セム)。せめ。せざるをえないようにせきたてる。しきりに要求する。また、せめとがめられるおいめ。「責務」「負責=責ヲ負フ」「責善朋友之道也=善ヲ責ムルハ朋友ノ道ナリ」〔→孟子〕
{動・名}せめる(セム)。せめ。せざるをえないようにせきたてる。しきりに要求する。また、せめとがめられるおいめ。「責務」「負責=責ヲ負フ」「責善朋友之道也=善ヲ責ムルハ朋友ノ道ナリ」〔→孟子〕
 {動・名}せめる(セム)。罪をとがめてせめる。刑罰。「杖責ジョウセキ(棒でうつ刑)」「笞責チセキ(むちでうつ刑)」
{動・名}せめる(セム)。罪をとがめてせめる。刑罰。「杖責ジョウセキ(棒でうつ刑)」「笞責チセキ(むちでうつ刑)」
 {名}返すようにせめられるおいめ。借金や借財。▽負債フサイの債に当てた用法。
《解字》
{名}返すようにせめられるおいめ。借金や借財。▽負債フサイの債に当てた用法。
《解字》
 会意兼形声。朿シ(束ソクではない)は、先のとがったとげや針を描いた象形文字で、刺シ(さす)の原字。責は「貝(財貨)+音符朿」で、貸借について、とげでさすように、せめさいなむこと。債の原字。
《単語家族》
策サク(とげのついたむち)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。朿シ(束ソクではない)は、先のとがったとげや針を描いた象形文字で、刺シ(さす)の原字。責は「貝(財貨)+音符朿」で、貸借について、とげでさすように、せめさいなむこと。債の原字。
《単語家族》
策サク(とげのついたむち)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
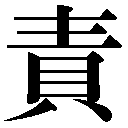 11画 貝部 [五年]
区点=3253 16進=4055 シフトJIS=90D3
《常用音訓》セキ/せ…める
《音読み》 セキ
11画 貝部 [五年]
区点=3253 16進=4055 シフトJIS=90D3
《常用音訓》セキ/せ…める
《音読み》 セキ /サク
/サク /シャク
/シャク 〈z
〈z 〉
《訓読み》 せめる(せむ)/せめ
《意味》
〉
《訓読み》 せめる(せむ)/せめ
《意味》
 {動}せめる(セム)。とげでさすようにとがめる。ちくちくと、とがめさいなむ。「叱責シッセキ(しかる)」「呵責カシャク(きびしく、しかりとがめる)」
{動}せめる(セム)。とげでさすようにとがめる。ちくちくと、とがめさいなむ。「叱責シッセキ(しかる)」「呵責カシャク(きびしく、しかりとがめる)」
 {動・名}せめる(セム)。せめ。せざるをえないようにせきたてる。しきりに要求する。また、せめとがめられるおいめ。「責務」「負責=責ヲ負フ」「責善朋友之道也=善ヲ責ムルハ朋友ノ道ナリ」〔→孟子〕
{動・名}せめる(セム)。せめ。せざるをえないようにせきたてる。しきりに要求する。また、せめとがめられるおいめ。「責務」「負責=責ヲ負フ」「責善朋友之道也=善ヲ責ムルハ朋友ノ道ナリ」〔→孟子〕
 {動・名}せめる(セム)。罪をとがめてせめる。刑罰。「杖責ジョウセキ(棒でうつ刑)」「笞責チセキ(むちでうつ刑)」
{動・名}せめる(セム)。罪をとがめてせめる。刑罰。「杖責ジョウセキ(棒でうつ刑)」「笞責チセキ(むちでうつ刑)」
 {名}返すようにせめられるおいめ。借金や借財。▽負債フサイの債に当てた用法。
《解字》
{名}返すようにせめられるおいめ。借金や借財。▽負債フサイの債に当てた用法。
《解字》
 会意兼形声。朿シ(束ソクではない)は、先のとがったとげや針を描いた象形文字で、刺シ(さす)の原字。責は「貝(財貨)+音符朿」で、貸借について、とげでさすように、せめさいなむこと。債の原字。
《単語家族》
策サク(とげのついたむち)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。朿シ(束ソクではない)は、先のとがったとげや針を描いた象形文字で、刺シ(さす)の原字。責は「貝(財貨)+音符朿」で、貸借について、とげでさすように、せめさいなむこと。債の原字。
《単語家族》
策サク(とげのついたむち)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「せめる」で完全一致するの検索結果 1-10。
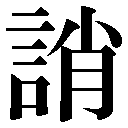 14画 言部
区点=7555 16進=6B57 シフトJIS=E676
《音読み》 ショウ(セウ)
14画 言部
区点=7555 16進=6B57 シフトJIS=E676
《音読み》 ショウ(セウ)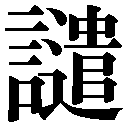 21画 言部
区点=7604 16進=6C24 シフトJIS=E6A2
《音読み》 ケン
21画 言部
区点=7604 16進=6C24 シフトJIS=E6A2
《音読み》 ケン n〉
《訓読み》 せめる(せむ)/せめ/つみ
《意味》
n〉
《訓読み》 せめる(せむ)/せめ/つみ
《意味》