複数辞典一括検索+![]()
![]()
捶 むち🔗⭐🔉
杖 むち🔗⭐🔉
【杖】
 7画 木部
区点=3083 16進=3E73 シフトJIS=8FF1
《音読み》 ジョウ(ヂャウ)
7画 木部
区点=3083 16進=3E73 シフトJIS=8FF1
《音読み》 ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)
/チョウ(チャウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)/よる/たよる/むち/むちうつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)/よる/たよる/むち/むちうつ
《意味》
 {名}つえ(ツ
{名}つえ(ツ )。歩行をたすけるため手にもつ長い棒。「負手曳杖=手ヲ負ヒ杖ヲ曳ク」〔→礼記〕
)。歩行をたすけるため手にもつ長い棒。「負手曳杖=手ヲ負ヒ杖ヲ曳ク」〔→礼記〕
 {動}つえつく(ツ
{動}つえつく(ツ ツク)。つえをつく。「八十杖於朝=八十ニシテ朝ニ杖ク」〔→礼記〕
ツク)。つえをつく。「八十杖於朝=八十ニシテ朝ニ杖ク」〔→礼記〕
 {動}よる。たよる。たよりにする。〈同義語〉→仗。「近臣已不足杖矣=近臣スデニ杖ルニ足ラズ」〔→漢書〕
{動}よる。たよる。たよりにする。〈同義語〉→仗。「近臣已不足杖矣=近臣スデニ杖ルニ足ラズ」〔→漢書〕
 {名}むち。人をたたく長い棒。「刑杖ケイジョウ」
{名}むち。人をたたく長い棒。「刑杖ケイジョウ」
 {動}むちうつ。こらしめるために棒でたたく。「杖笞ジョウチ」
{動}むちうつ。こらしめるために棒でたたく。「杖笞ジョウチ」
 {名}五刑の一つ。棒でたたいてこらしめる刑。
《解字》
会意兼形声。丈は「十+攴(て)」の会意文字で、手尺の幅(=尺)の十倍の長さをあらわす。杖は「木+音符丈」で、長い棒のこと。
《類義》
→棒
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}五刑の一つ。棒でたたいてこらしめる刑。
《解字》
会意兼形声。丈は「十+攴(て)」の会意文字で、手尺の幅(=尺)の十倍の長さをあらわす。杖は「木+音符丈」で、長い棒のこと。
《類義》
→棒
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 7画 木部
区点=3083 16進=3E73 シフトJIS=8FF1
《音読み》 ジョウ(ヂャウ)
7画 木部
区点=3083 16進=3E73 シフトJIS=8FF1
《音読み》 ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)
/チョウ(チャウ) 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)/よる/たよる/むち/むちうつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)/よる/たよる/むち/むちうつ
《意味》
 {名}つえ(ツ
{名}つえ(ツ )。歩行をたすけるため手にもつ長い棒。「負手曳杖=手ヲ負ヒ杖ヲ曳ク」〔→礼記〕
)。歩行をたすけるため手にもつ長い棒。「負手曳杖=手ヲ負ヒ杖ヲ曳ク」〔→礼記〕
 {動}つえつく(ツ
{動}つえつく(ツ ツク)。つえをつく。「八十杖於朝=八十ニシテ朝ニ杖ク」〔→礼記〕
ツク)。つえをつく。「八十杖於朝=八十ニシテ朝ニ杖ク」〔→礼記〕
 {動}よる。たよる。たよりにする。〈同義語〉→仗。「近臣已不足杖矣=近臣スデニ杖ルニ足ラズ」〔→漢書〕
{動}よる。たよる。たよりにする。〈同義語〉→仗。「近臣已不足杖矣=近臣スデニ杖ルニ足ラズ」〔→漢書〕
 {名}むち。人をたたく長い棒。「刑杖ケイジョウ」
{名}むち。人をたたく長い棒。「刑杖ケイジョウ」
 {動}むちうつ。こらしめるために棒でたたく。「杖笞ジョウチ」
{動}むちうつ。こらしめるために棒でたたく。「杖笞ジョウチ」
 {名}五刑の一つ。棒でたたいてこらしめる刑。
《解字》
会意兼形声。丈は「十+攴(て)」の会意文字で、手尺の幅(=尺)の十倍の長さをあらわす。杖は「木+音符丈」で、長い棒のこと。
《類義》
→棒
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}五刑の一つ。棒でたたいてこらしめる刑。
《解字》
会意兼形声。丈は「十+攴(て)」の会意文字で、手尺の幅(=尺)の十倍の長さをあらわす。杖は「木+音符丈」で、長い棒のこと。
《類義》
→棒
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
枚 むち🔗⭐🔉
【枚】
 8画 木部 [六年]
区点=4371 16進=4B67 シフトJIS=9687
《常用音訓》マイ
《音読み》 マイ/メ
8画 木部 [六年]
区点=4371 16進=4B67 シフトJIS=9687
《常用音訓》マイ
《音読み》 マイ/メ /バイ
/バイ 〈m
〈m i〉
《訓読み》 むち
《名付け》 かず・ひら・ふむ
《意味》
i〉
《訓読み》 むち
《名付け》 かず・ひら・ふむ
《意味》
 {名}つえにするぐらいの太さの幹。つえ。
{名}つえにするぐらいの太さの幹。つえ。
 {名}むち。馬を打つむち。「以枚数闔=枚ヲモッテ闔ヲ数フ」〔→左伝〕
{名}むち。馬を打つむち。「以枚数闔=枚ヲモッテ闔ヲ数フ」〔→左伝〕
 {名}声を立てないようにするため、口にくわえるもの。箸ハシのような形の木片で両端にひもがあり、くわえて首の後ろでむすぶ。夜討ちや行軍のときなどに使う。「銜枚=枚ヲ銜ム」
{名}声を立てないようにするため、口にくわえるもの。箸ハシのような形の木片で両端にひもがあり、くわえて首の後ろでむすぶ。夜討ちや行軍のときなどに使う。「銜枚=枚ヲ銜ム」
 {単位}物を数える単位。▽日本では平らで薄いものに限って使うが、本来そのような制限はなかった。
{単位}物を数える単位。▽日本では平らで薄いものに限って使うが、本来そのような制限はなかった。
 {副}一つ一つ。ひとりひとり。いちいち。「枚挙」
《解字》
会意。「木+攴(手に持つ)」。手に持つつえやむち。毎(一つ一つ)と同系で、同じような物をつぎつぎにかぞえる単位として用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{副}一つ一つ。ひとりひとり。いちいち。「枚挙」
《解字》
会意。「木+攴(手に持つ)」。手に持つつえやむち。毎(一つ一つ)と同系で、同じような物をつぎつぎにかぞえる単位として用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 8画 木部 [六年]
区点=4371 16進=4B67 シフトJIS=9687
《常用音訓》マイ
《音読み》 マイ/メ
8画 木部 [六年]
区点=4371 16進=4B67 シフトJIS=9687
《常用音訓》マイ
《音読み》 マイ/メ /バイ
/バイ 〈m
〈m i〉
《訓読み》 むち
《名付け》 かず・ひら・ふむ
《意味》
i〉
《訓読み》 むち
《名付け》 かず・ひら・ふむ
《意味》
 {名}つえにするぐらいの太さの幹。つえ。
{名}つえにするぐらいの太さの幹。つえ。
 {名}むち。馬を打つむち。「以枚数闔=枚ヲモッテ闔ヲ数フ」〔→左伝〕
{名}むち。馬を打つむち。「以枚数闔=枚ヲモッテ闔ヲ数フ」〔→左伝〕
 {名}声を立てないようにするため、口にくわえるもの。箸ハシのような形の木片で両端にひもがあり、くわえて首の後ろでむすぶ。夜討ちや行軍のときなどに使う。「銜枚=枚ヲ銜ム」
{名}声を立てないようにするため、口にくわえるもの。箸ハシのような形の木片で両端にひもがあり、くわえて首の後ろでむすぶ。夜討ちや行軍のときなどに使う。「銜枚=枚ヲ銜ム」
 {単位}物を数える単位。▽日本では平らで薄いものに限って使うが、本来そのような制限はなかった。
{単位}物を数える単位。▽日本では平らで薄いものに限って使うが、本来そのような制限はなかった。
 {副}一つ一つ。ひとりひとり。いちいち。「枚挙」
《解字》
会意。「木+攴(手に持つ)」。手に持つつえやむち。毎(一つ一つ)と同系で、同じような物をつぎつぎにかぞえる単位として用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{副}一つ一つ。ひとりひとり。いちいち。「枚挙」
《解字》
会意。「木+攴(手に持つ)」。手に持つつえやむち。毎(一つ一つ)と同系で、同じような物をつぎつぎにかぞえる単位として用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
無知 ムチ🔗⭐🔉
【無知{智}】
ムチ・チナシ  知識がないこと。知らないこと。
知識がないこと。知らないこと。 思慮がなくて愚かなこと。
思慮がなくて愚かなこと。
 知識がないこと。知らないこと。
知識がないこと。知らないこと。 思慮がなくて愚かなこと。
思慮がなくて愚かなこと。
無恥 ムチ🔗⭐🔉
【無恥】
ムチ・ハジナシ 恥ずべきことをしても恥ずかしいとは思わないこと。はじ知らず。「厚顔無恥」
無知 ムチ🔗⭐🔉
【無知】
ムチ〈人名〉春秋時代、斉セイの襄ジョウ公の従弟。襄公を殺して自ら斉君と称した。
笞 むち🔗⭐🔉
【笞】
 11画 竹部
区点=6790 16進=637A シフトJIS=E29A
《音読み》 チ
11画 竹部
区点=6790 16進=637A シフトJIS=E29A
《音読み》 チ
 〈ch
〈ch 〉
《訓読み》 むち/むちうつ
《意味》
〉
《訓読み》 むち/むちうつ
《意味》
 {名}むち。竹などでつくった細長い棒。▽人をきびしくためなおしたり、こらしめたりするために、たたいて苦痛を与えるのに用いる。「笞杖チジョウ」
{名}むち。竹などでつくった細長い棒。▽人をきびしくためなおしたり、こらしめたりするために、たたいて苦痛を与えるのに用いる。「笞杖チジョウ」
 {動}むちうつ。こらしめのために罪人などをむちでたたく。「鞭笞ベンチ」
{動}むちうつ。こらしめのために罪人などをむちでたたく。「鞭笞ベンチ」
 {名}昔の刑罰の一つ。罪の軽重によって一定の数だけ、むちでうってこらしめる刑。たたき。「笞刑チケイ」
《解字》
会意兼形声。「竹+音符台(ためる、人工を加える)」。
《単語家族》
治(河川に人工を加えてなおす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}昔の刑罰の一つ。罪の軽重によって一定の数だけ、むちでうってこらしめる刑。たたき。「笞刑チケイ」
《解字》
会意兼形声。「竹+音符台(ためる、人工を加える)」。
《単語家族》
治(河川に人工を加えてなおす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画 竹部
区点=6790 16進=637A シフトJIS=E29A
《音読み》 チ
11画 竹部
区点=6790 16進=637A シフトJIS=E29A
《音読み》 チ
 〈ch
〈ch 〉
《訓読み》 むち/むちうつ
《意味》
〉
《訓読み》 むち/むちうつ
《意味》
 {名}むち。竹などでつくった細長い棒。▽人をきびしくためなおしたり、こらしめたりするために、たたいて苦痛を与えるのに用いる。「笞杖チジョウ」
{名}むち。竹などでつくった細長い棒。▽人をきびしくためなおしたり、こらしめたりするために、たたいて苦痛を与えるのに用いる。「笞杖チジョウ」
 {動}むちうつ。こらしめのために罪人などをむちでたたく。「鞭笞ベンチ」
{動}むちうつ。こらしめのために罪人などをむちでたたく。「鞭笞ベンチ」
 {名}昔の刑罰の一つ。罪の軽重によって一定の数だけ、むちでうってこらしめる刑。たたき。「笞刑チケイ」
《解字》
会意兼形声。「竹+音符台(ためる、人工を加える)」。
《単語家族》
治(河川に人工を加えてなおす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}昔の刑罰の一つ。罪の軽重によって一定の数だけ、むちでうってこらしめる刑。たたき。「笞刑チケイ」
《解字》
会意兼形声。「竹+音符台(ためる、人工を加える)」。
《単語家族》
治(河川に人工を加えてなおす)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
策 むち🔗⭐🔉
【策】
 12画 竹部 [六年]
区点=2686 16進=3A76 シフトJIS=8DF4
《常用音訓》サク
《音読み》 サク
12画 竹部 [六年]
区点=2686 16進=3A76 シフトJIS=8DF4
《常用音訓》サク
《音読み》 サク /シャク
/シャク 〈c
〈c 〉
《訓読み》 ふだ/ふみ/はかりごと/むち/むちうつ/つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)
《名付け》 かず・つか・もり
《意味》
〉
《訓読み》 ふだ/ふみ/はかりごと/むち/むちうつ/つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)
《名付け》 かず・つか・もり
《意味》
 サクス{名・動}ふだ。むかし紙のなかったころ、文字を書きつけた竹のふだ。また、竹の札に書きしるす。〈同義語〉→冊サク。〈類義語〉→簡。「簡策(文書)」
サクス{名・動}ふだ。むかし紙のなかったころ、文字を書きつけた竹のふだ。また、竹の札に書きしるす。〈同義語〉→冊サク。〈類義語〉→簡。「簡策(文書)」
 {名}ふみ。竹札に書いたたいせつな文書。転じて、天子の命令や辞令書。「策命(天子の命令)」「対策(天子の下問に答える書)」
{名}ふみ。竹札に書いたたいせつな文書。転じて、天子の命令や辞令書。「策命(天子の命令)」「対策(天子の下問に答える書)」
 {名}はかりごと。書きしるした計画書。計画の案。また、計画や意見をのべる文体。「上策(最上の案)」「下策(まずいがやむをえない案)」「対策(事件を処置するための案。また、その文体)」
{名}はかりごと。書きしるした計画書。計画の案。また、計画や意見をのべる文体。「上策(最上の案)」「下策(まずいがやむをえない案)」「対策(事件を処置するための案。また、その文体)」
 サクス{動}計画する。
サクス{動}計画する。
 {名}占いに用いるめどぎ。〈同義語〉→筴。〈類義語〉→籤セン。「占策」「神策(おみくじ)」
{名}占いに用いるめどぎ。〈同義語〉→筴。〈類義語〉→籤セン。「占策」「神策(おみくじ)」
 {名}むち。先端がぎざぎざととがって、馬の腹を刺激するむち。〈類義語〉→鞭ベン。「策鞭サクベン」
{名}むち。先端がぎざぎざととがって、馬の腹を刺激するむち。〈類義語〉→鞭ベン。「策鞭サクベン」
 {動}むちうつ。馬をむちでうつ。また、むちでうつように刺激を与える。「策励(刺激してはげます)」「策其馬=ソノ馬ニ策ツ」〔→論語〕
{動}むちうつ。馬をむちでうつ。また、むちでうつように刺激を与える。「策励(刺激してはげます)」「策其馬=ソノ馬ニ策ツ」〔→論語〕
 {名・動}つえ(ツ
{名・動}つえ(ツ )。つえつく(ツ
)。つえつく(ツ ツク)。むちのような形をしたつえ。また、それをつく。「扶策フサク(つえをわきの下に入れてからだをささえる)」
ツク)。むちのような形をしたつえ。また、それをつく。「扶策フサク(つえをわきの下に入れてからだをささえる)」
 {名}永字八法の一つ。
《解字》
会意兼形声。朿シ・セキはとげの出た枝を描いた象形文字。刺(さす)の原字。策は「竹+音符朿シ(とげ)」で、ぎざぎざととがっていて刺激するむち。また竹札を重ねて端がぎざぎざとつかえる冊(短冊)のこと。
《単語家族》
積(端がぎざぎざとするように重ねる)
{名}永字八法の一つ。
《解字》
会意兼形声。朿シ・セキはとげの出た枝を描いた象形文字。刺(さす)の原字。策は「竹+音符朿シ(とげ)」で、ぎざぎざととがっていて刺激するむち。また竹札を重ねて端がぎざぎざとつかえる冊(短冊)のこと。
《単語家族》
積(端がぎざぎざとするように重ねる) 柵サク(木をぎざぎざに並べたさく)などと同系。
《類義》
→計
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
柵サク(木をぎざぎざに並べたさく)などと同系。
《類義》
→計
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 竹部 [六年]
区点=2686 16進=3A76 シフトJIS=8DF4
《常用音訓》サク
《音読み》 サク
12画 竹部 [六年]
区点=2686 16進=3A76 シフトJIS=8DF4
《常用音訓》サク
《音読み》 サク /シャク
/シャク 〈c
〈c 〉
《訓読み》 ふだ/ふみ/はかりごと/むち/むちうつ/つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)
《名付け》 かず・つか・もり
《意味》
〉
《訓読み》 ふだ/ふみ/はかりごと/むち/むちうつ/つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)
《名付け》 かず・つか・もり
《意味》
 サクス{名・動}ふだ。むかし紙のなかったころ、文字を書きつけた竹のふだ。また、竹の札に書きしるす。〈同義語〉→冊サク。〈類義語〉→簡。「簡策(文書)」
サクス{名・動}ふだ。むかし紙のなかったころ、文字を書きつけた竹のふだ。また、竹の札に書きしるす。〈同義語〉→冊サク。〈類義語〉→簡。「簡策(文書)」
 {名}ふみ。竹札に書いたたいせつな文書。転じて、天子の命令や辞令書。「策命(天子の命令)」「対策(天子の下問に答える書)」
{名}ふみ。竹札に書いたたいせつな文書。転じて、天子の命令や辞令書。「策命(天子の命令)」「対策(天子の下問に答える書)」
 {名}はかりごと。書きしるした計画書。計画の案。また、計画や意見をのべる文体。「上策(最上の案)」「下策(まずいがやむをえない案)」「対策(事件を処置するための案。また、その文体)」
{名}はかりごと。書きしるした計画書。計画の案。また、計画や意見をのべる文体。「上策(最上の案)」「下策(まずいがやむをえない案)」「対策(事件を処置するための案。また、その文体)」
 サクス{動}計画する。
サクス{動}計画する。
 {名}占いに用いるめどぎ。〈同義語〉→筴。〈類義語〉→籤セン。「占策」「神策(おみくじ)」
{名}占いに用いるめどぎ。〈同義語〉→筴。〈類義語〉→籤セン。「占策」「神策(おみくじ)」
 {名}むち。先端がぎざぎざととがって、馬の腹を刺激するむち。〈類義語〉→鞭ベン。「策鞭サクベン」
{名}むち。先端がぎざぎざととがって、馬の腹を刺激するむち。〈類義語〉→鞭ベン。「策鞭サクベン」
 {動}むちうつ。馬をむちでうつ。また、むちでうつように刺激を与える。「策励(刺激してはげます)」「策其馬=ソノ馬ニ策ツ」〔→論語〕
{動}むちうつ。馬をむちでうつ。また、むちでうつように刺激を与える。「策励(刺激してはげます)」「策其馬=ソノ馬ニ策ツ」〔→論語〕
 {名・動}つえ(ツ
{名・動}つえ(ツ )。つえつく(ツ
)。つえつく(ツ ツク)。むちのような形をしたつえ。また、それをつく。「扶策フサク(つえをわきの下に入れてからだをささえる)」
ツク)。むちのような形をしたつえ。また、それをつく。「扶策フサク(つえをわきの下に入れてからだをささえる)」
 {名}永字八法の一つ。
《解字》
会意兼形声。朿シ・セキはとげの出た枝を描いた象形文字。刺(さす)の原字。策は「竹+音符朿シ(とげ)」で、ぎざぎざととがっていて刺激するむち。また竹札を重ねて端がぎざぎざとつかえる冊(短冊)のこと。
《単語家族》
積(端がぎざぎざとするように重ねる)
{名}永字八法の一つ。
《解字》
会意兼形声。朿シ・セキはとげの出た枝を描いた象形文字。刺(さす)の原字。策は「竹+音符朿シ(とげ)」で、ぎざぎざととがっていて刺激するむち。また竹札を重ねて端がぎざぎざとつかえる冊(短冊)のこと。
《単語家族》
積(端がぎざぎざとするように重ねる) 柵サク(木をぎざぎざに並べたさく)などと同系。
《類義》
→計
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
柵サク(木をぎざぎざに並べたさく)などと同系。
《類義》
→計
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「むち」で完全一致するの検索結果 1-9。
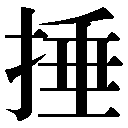 11画
11画  部
区点=5757 16進=5959 シフトJIS=9D78
《音読み》 スイ
部
区点=5757 16進=5959 シフトJIS=9D78
《音読み》 スイ ・chu
・chu 〉
《訓読み》 むちうつ/うつ/むち
《意味》
〉
《訓読み》 むちうつ/うつ/むち
《意味》
 18画 革部
区点=4260 16進=4A5C シフトJIS=95DA
《音読み》 ベン
18画 革部
区点=4260 16進=4A5C シフトJIS=95DA
《音読み》 ベン /ヘン
/ヘン n〉
《訓読み》 むち/むちうつ
《意味》
n〉
《訓読み》 むち/むちうつ
《意味》