複数辞典一括検索+![]()
![]()
吝 おしむ🔗⭐🔉
【吝】
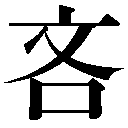 7画 口部
区点=5071 16進=5267 シフトJIS=99E5
《音読み》 リン
7画 口部
区点=5071 16進=5267 シフトJIS=99E5
《音読み》 リン
 〈l
〈l n〉
《訓読み》 おしむ(をしむ)/やぶさか(やぶさかなり)
《意味》
n〉
《訓読み》 おしむ(をしむ)/やぶさか(やぶさかなり)
《意味》
 リンナリ{動・形}おしむ(ヲシム)。やぶさか(ヤブサカナリ)。ものおしみする。金銭に対して思い切りが悪い。けちである。〈同義語〉→悋。「吝嗇リンショク」「使驕且吝=驕リテカツ吝ナラ使メバ」〔→論語〕
リンナリ{動・形}おしむ(ヲシム)。やぶさか(ヤブサカナリ)。ものおしみする。金銭に対して思い切りが悪い。けちである。〈同義語〉→悋。「吝嗇リンショク」「使驕且吝=驕リテカツ吝ナラ使メバ」〔→論語〕
 {形}度量が狭くさっぱりしないさま。「鄙吝ヒリン」
{形}度量が狭くさっぱりしないさま。「鄙吝ヒリン」
 {形}くよくよして思い切りが悪いさま。▽「不吝フリン」とは、くよくよせず思い切りよく承認すること。「やぶさかならず」と訓読することがある。「吝情リンジョウ」
〔国〕「吝気リンキ」とは、やきもち。〈同義語〉悋気。「女房の吝気」
《解字》
会意。「文+口」。文は修飾を意味する。口さきを飾っていいわけし、金品を手放さない意を示す。憐レン(思い切りわるく、心を悩ます)ときわめて近い。
《類義》
→惜
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}くよくよして思い切りが悪いさま。▽「不吝フリン」とは、くよくよせず思い切りよく承認すること。「やぶさかならず」と訓読することがある。「吝情リンジョウ」
〔国〕「吝気リンキ」とは、やきもち。〈同義語〉悋気。「女房の吝気」
《解字》
会意。「文+口」。文は修飾を意味する。口さきを飾っていいわけし、金品を手放さない意を示す。憐レン(思い切りわるく、心を悩ます)ときわめて近い。
《類義》
→惜
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
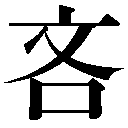 7画 口部
区点=5071 16進=5267 シフトJIS=99E5
《音読み》 リン
7画 口部
区点=5071 16進=5267 シフトJIS=99E5
《音読み》 リン
 〈l
〈l n〉
《訓読み》 おしむ(をしむ)/やぶさか(やぶさかなり)
《意味》
n〉
《訓読み》 おしむ(をしむ)/やぶさか(やぶさかなり)
《意味》
 リンナリ{動・形}おしむ(ヲシム)。やぶさか(ヤブサカナリ)。ものおしみする。金銭に対して思い切りが悪い。けちである。〈同義語〉→悋。「吝嗇リンショク」「使驕且吝=驕リテカツ吝ナラ使メバ」〔→論語〕
リンナリ{動・形}おしむ(ヲシム)。やぶさか(ヤブサカナリ)。ものおしみする。金銭に対して思い切りが悪い。けちである。〈同義語〉→悋。「吝嗇リンショク」「使驕且吝=驕リテカツ吝ナラ使メバ」〔→論語〕
 {形}度量が狭くさっぱりしないさま。「鄙吝ヒリン」
{形}度量が狭くさっぱりしないさま。「鄙吝ヒリン」
 {形}くよくよして思い切りが悪いさま。▽「不吝フリン」とは、くよくよせず思い切りよく承認すること。「やぶさかならず」と訓読することがある。「吝情リンジョウ」
〔国〕「吝気リンキ」とは、やきもち。〈同義語〉悋気。「女房の吝気」
《解字》
会意。「文+口」。文は修飾を意味する。口さきを飾っていいわけし、金品を手放さない意を示す。憐レン(思い切りわるく、心を悩ます)ときわめて近い。
《類義》
→惜
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{形}くよくよして思い切りが悪いさま。▽「不吝フリン」とは、くよくよせず思い切りよく承認すること。「やぶさかならず」と訓読することがある。「吝情リンジョウ」
〔国〕「吝気リンキ」とは、やきもち。〈同義語〉悋気。「女房の吝気」
《解字》
会意。「文+口」。文は修飾を意味する。口さきを飾っていいわけし、金品を手放さない意を示す。憐レン(思い切りわるく、心を悩ます)ときわめて近い。
《類義》
→惜
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
和尚 オショウ🔗⭐🔉
【和尚】
 オショウ・カショウ・ワジョウ〔仏〕高徳の僧に対する敬称。▽宗派によって読み方が異なり、禅宗・浄土宗ではオショウ、天台宗ではカショウ、法相宗・真言宗ではワジョウと読む。律宗では「和上」と書き、ワジョウと読む。
オショウ・カショウ・ワジョウ〔仏〕高徳の僧に対する敬称。▽宗派によって読み方が異なり、禅宗・浄土宗ではオショウ、天台宗ではカショウ、法相宗・真言宗ではワジョウと読む。律宗では「和上」と書き、ワジョウと読む。 オショウ〔国〕寺の住職。また広く、僧のこと。
オショウ〔国〕寺の住職。また広く、僧のこと。
 オショウ・カショウ・ワジョウ〔仏〕高徳の僧に対する敬称。▽宗派によって読み方が異なり、禅宗・浄土宗ではオショウ、天台宗ではカショウ、法相宗・真言宗ではワジョウと読む。律宗では「和上」と書き、ワジョウと読む。
オショウ・カショウ・ワジョウ〔仏〕高徳の僧に対する敬称。▽宗派によって読み方が異なり、禅宗・浄土宗ではオショウ、天台宗ではカショウ、法相宗・真言宗ではワジョウと読む。律宗では「和上」と書き、ワジョウと読む。 オショウ〔国〕寺の住職。また広く、僧のこと。
オショウ〔国〕寺の住職。また広く、僧のこと。
唖 おし🔗⭐🔉
【唖】
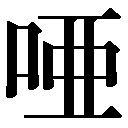 10画 口部
区点=1602 16進=3022 シフトJIS=88A0
《音読み》
10画 口部
区点=1602 16進=3022 シフトJIS=88A0
《音読み》  ア
ア /エ
/エ 〈y
〈y ・y
・y 〉/
〉/ アク
アク /ヤク
/ヤク 〈
〈 〉
《訓読み》 おし
《意味》
〉
《訓読み》 おし
《意味》

 {名・形}おし。声がのどにつかえて出ない。また、そのさま。また、口がきけない人。「聾唖ロウア」「唖然アゼン(あっと驚いてのどに息がつかえる)」「呑炭為唖=炭ヲ呑ミテ唖ト為ル」〔→史記〕
{名・形}おし。声がのどにつかえて出ない。また、そのさま。また、口がきけない人。「聾唖ロウア」「唖然アゼン(あっと驚いてのどに息がつかえる)」「呑炭為唖=炭ヲ呑ミテ唖ト為ル」〔→史記〕
 {形}からすが、ああと鳴く声。▽去声に読む。
{形}からすが、ああと鳴く声。▽去声に読む。
 {感}あっはと笑う声。また、ああと驚く声。
《解字》
会意兼形声。亞(=亜)は、地下に四角く掘った土台の姿を描いた象形文字で、下積みとなってつかえる意を含む。唖は「口+音符亞」で、のどがつかえる意。
《単語家族》
惡(=悪。胸がつかえて気持ちがわるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{感}あっはと笑う声。また、ああと驚く声。
《解字》
会意兼形声。亞(=亜)は、地下に四角く掘った土台の姿を描いた象形文字で、下積みとなってつかえる意を含む。唖は「口+音符亞」で、のどがつかえる意。
《単語家族》
惡(=悪。胸がつかえて気持ちがわるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
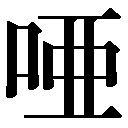 10画 口部
区点=1602 16進=3022 シフトJIS=88A0
《音読み》
10画 口部
区点=1602 16進=3022 シフトJIS=88A0
《音読み》  ア
ア /エ
/エ 〈y
〈y ・y
・y 〉/
〉/ アク
アク /ヤク
/ヤク 〈
〈 〉
《訓読み》 おし
《意味》
〉
《訓読み》 おし
《意味》

 {名・形}おし。声がのどにつかえて出ない。また、そのさま。また、口がきけない人。「聾唖ロウア」「唖然アゼン(あっと驚いてのどに息がつかえる)」「呑炭為唖=炭ヲ呑ミテ唖ト為ル」〔→史記〕
{名・形}おし。声がのどにつかえて出ない。また、そのさま。また、口がきけない人。「聾唖ロウア」「唖然アゼン(あっと驚いてのどに息がつかえる)」「呑炭為唖=炭ヲ呑ミテ唖ト為ル」〔→史記〕
 {形}からすが、ああと鳴く声。▽去声に読む。
{形}からすが、ああと鳴く声。▽去声に読む。
 {感}あっはと笑う声。また、ああと驚く声。
《解字》
会意兼形声。亞(=亜)は、地下に四角く掘った土台の姿を描いた象形文字で、下積みとなってつかえる意を含む。唖は「口+音符亞」で、のどがつかえる意。
《単語家族》
惡(=悪。胸がつかえて気持ちがわるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{感}あっはと笑う声。また、ああと驚く声。
《解字》
会意兼形声。亞(=亜)は、地下に四角く掘った土台の姿を描いた象形文字で、下積みとなってつかえる意を含む。唖は「口+音符亞」で、のどがつかえる意。
《単語家族》
惡(=悪。胸がつかえて気持ちがわるい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
垂教 オシエヲタル🔗⭐🔉
【垂訓】
スイクン  下位の者、また、後世に教訓を示す。
下位の者、また、後世に教訓を示す。 示した教え。『垂教スイキョウ・オシエヲタル』
示した教え。『垂教スイキョウ・オシエヲタル』
 下位の者、また、後世に教訓を示す。
下位の者、また、後世に教訓を示す。 示した教え。『垂教スイキョウ・オシエヲタル』
示した教え。『垂教スイキョウ・オシエヲタル』
悪念 オシン🔗⭐🔉
【悪心】
 アクシン 悪いことをしようとする心。『悪念アクネン』
アクシン 悪いことをしようとする心。『悪念アクネン』 オシン 気分が悪くなること。むかむかするいやな感じ。はきけ。
オシン 気分が悪くなること。むかむかするいやな感じ。はきけ。
 アクシン 悪いことをしようとする心。『悪念アクネン』
アクシン 悪いことをしようとする心。『悪念アクネン』 オシン 気分が悪くなること。むかむかするいやな感じ。はきけ。
オシン 気分が悪くなること。むかむかするいやな感じ。はきけ。
愛 おしむ🔗⭐🔉
【愛】
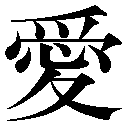 13画 心部 [四年]
区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4
《常用音訓》アイ
《音読み》 アイ
13画 心部 [四年]
区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4
《常用音訓》アイ
《音読み》 アイ /オ/アイ
/オ/アイ 〈
〈 i〉
《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)
《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より
《意味》
i〉
《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)
《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より
《意味》
 アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕
アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕
 アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
 アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕
アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕
 {名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
《解字》
{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
《解字》
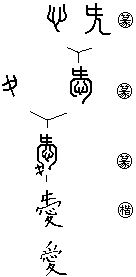 会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
《単語家族》
既キ(いっぱいである)
会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
《単語家族》
既キ(いっぱいである) 漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
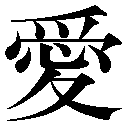 13画 心部 [四年]
区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4
《常用音訓》アイ
《音読み》 アイ
13画 心部 [四年]
区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4
《常用音訓》アイ
《音読み》 アイ /オ/アイ
/オ/アイ 〈
〈 i〉
《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)
《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より
《意味》
i〉
《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)
《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より
《意味》
 アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕
アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕
 アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕
 アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕
アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕
 {名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
《解字》
{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。
《解字》
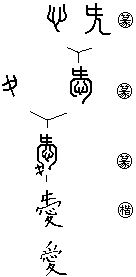 会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
《単語家族》
既キ(いっぱいである)
会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。
《単語家族》
既キ(いっぱいである) 漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
惜 おしい🔗⭐🔉
【惜】
 11画
11画  部 [常用漢字]
区点=3243 16進=404B シフトJIS=90C9
《常用音訓》セキ/お…しい/お…しむ
《音読み》 セキ
部 [常用漢字]
区点=3243 16進=404B シフトJIS=90C9
《常用音訓》セキ/お…しい/お…しむ
《音読み》 セキ /シャク
/シャク 〈x
〈x 〉
《訓読み》 おしい(をし)/おしむ(をしむ)/おしむらくは(をしむらくは)
《意味》
〉
《訓読み》 おしい(をし)/おしむ(をしむ)/おしむらくは(をしむらくは)
《意味》
 {形}おしい(ヲシ)。いつまでも心が残って、残念だ。もったいない。「惜乎=惜シイ乎」〔→論語〕
{形}おしい(ヲシ)。いつまでも心が残って、残念だ。もったいない。「惜乎=惜シイ乎」〔→論語〕
 {動}おしむ(ヲシム)。もったいないと思う。思い切れず、残念がる。また、大切にする。「愛惜アイセキ」「可惜=惜シムベシ」「洛陽女児惜顔色=洛陽ノ女児、顔色ヲ惜シム」〔→劉希夷〕
{動}おしむ(ヲシム)。もったいないと思う。思い切れず、残念がる。また、大切にする。「愛惜アイセキ」「可惜=惜シムベシ」「洛陽女児惜顔色=洛陽ノ女児、顔色ヲ惜シム」〔→劉希夷〕
 {副}おしむらくは(ヲシムラクハ)。文の初めにつけて、おしいことにはの意をあらわす。「惜未知兵法=惜シムラクハ、イマダ兵法ヲ知ラズ」〔→外史〕
《解字》
会意兼形声。昔セキは、日が重なることで、重なる意を含む。惜は「心+音符昔」で、一度きりでは忘れ去らず、心中に残り重なって思いがつのること。
《類義》
吝リンは、けちけちすること。嗇ショクは、自分の手に取りこんで出さないこと。愛は、胸の詰まる思いのすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{副}おしむらくは(ヲシムラクハ)。文の初めにつけて、おしいことにはの意をあらわす。「惜未知兵法=惜シムラクハ、イマダ兵法ヲ知ラズ」〔→外史〕
《解字》
会意兼形声。昔セキは、日が重なることで、重なる意を含む。惜は「心+音符昔」で、一度きりでは忘れ去らず、心中に残り重なって思いがつのること。
《類義》
吝リンは、けちけちすること。嗇ショクは、自分の手に取りこんで出さないこと。愛は、胸の詰まる思いのすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 11画
11画  部 [常用漢字]
区点=3243 16進=404B シフトJIS=90C9
《常用音訓》セキ/お…しい/お…しむ
《音読み》 セキ
部 [常用漢字]
区点=3243 16進=404B シフトJIS=90C9
《常用音訓》セキ/お…しい/お…しむ
《音読み》 セキ /シャク
/シャク 〈x
〈x 〉
《訓読み》 おしい(をし)/おしむ(をしむ)/おしむらくは(をしむらくは)
《意味》
〉
《訓読み》 おしい(をし)/おしむ(をしむ)/おしむらくは(をしむらくは)
《意味》
 {形}おしい(ヲシ)。いつまでも心が残って、残念だ。もったいない。「惜乎=惜シイ乎」〔→論語〕
{形}おしい(ヲシ)。いつまでも心が残って、残念だ。もったいない。「惜乎=惜シイ乎」〔→論語〕
 {動}おしむ(ヲシム)。もったいないと思う。思い切れず、残念がる。また、大切にする。「愛惜アイセキ」「可惜=惜シムベシ」「洛陽女児惜顔色=洛陽ノ女児、顔色ヲ惜シム」〔→劉希夷〕
{動}おしむ(ヲシム)。もったいないと思う。思い切れず、残念がる。また、大切にする。「愛惜アイセキ」「可惜=惜シムベシ」「洛陽女児惜顔色=洛陽ノ女児、顔色ヲ惜シム」〔→劉希夷〕
 {副}おしむらくは(ヲシムラクハ)。文の初めにつけて、おしいことにはの意をあらわす。「惜未知兵法=惜シムラクハ、イマダ兵法ヲ知ラズ」〔→外史〕
《解字》
会意兼形声。昔セキは、日が重なることで、重なる意を含む。惜は「心+音符昔」で、一度きりでは忘れ去らず、心中に残り重なって思いがつのること。
《類義》
吝リンは、けちけちすること。嗇ショクは、自分の手に取りこんで出さないこと。愛は、胸の詰まる思いのすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{副}おしむらくは(ヲシムラクハ)。文の初めにつけて、おしいことにはの意をあらわす。「惜未知兵法=惜シムラクハ、イマダ兵法ヲ知ラズ」〔→外史〕
《解字》
会意兼形声。昔セキは、日が重なることで、重なる意を含む。惜は「心+音符昔」で、一度きりでは忘れ去らず、心中に残り重なって思いがつのること。
《類義》
吝リンは、けちけちすること。嗇ショクは、自分の手に取りこんで出さないこと。愛は、胸の詰まる思いのすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
慳 おしむ🔗⭐🔉
折敷 オシキ🔗⭐🔉
【折敷】
オシキ〔国〕へぎ板を折り曲げて四方をかこんだ四角い盆。
押 おし🔗⭐🔉
【押】
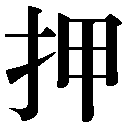 8画
8画  部 [常用漢字]
区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F
《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す
《音読み》
部 [常用漢字]
区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F
《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す
《音読み》  オウ(アフ)
オウ(アフ) /ヨウ(エフ)
/ヨウ(エフ) 〈y
〈y 〉/
〉/ コウ(カフ)
コウ(カフ) /キョウ(ケフ)
/キョウ(ケフ) 《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし
《名付け》 おし
《意味》
《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし
《名付け》 おし
《意味》

 {動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」
{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」
 {動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」
{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」
 {動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」
{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」
 「花押」とは、記号ふうの署名のこと。
「花押」とは、記号ふうの署名のこと。
 {動}かぶせる。
〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」
《解字》
会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲
《単語家族》
匣コウ(ふたつきのはこ)
{動}かぶせる。
〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」
《解字》
会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲
《単語家族》
匣コウ(ふたつきのはこ) 厭ヨウ(上からおさえられる)
厭ヨウ(上からおさえられる) 壓アツ(=圧。おさえる)と同系。
《類義》
→推
《異字同訓》
おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
壓アツ(=圧。おさえる)と同系。
《類義》
→推
《異字同訓》
おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
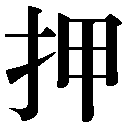 8画
8画  部 [常用漢字]
区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F
《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す
《音読み》
部 [常用漢字]
区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F
《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す
《音読み》  オウ(アフ)
オウ(アフ) /ヨウ(エフ)
/ヨウ(エフ) 〈y
〈y 〉/
〉/ コウ(カフ)
コウ(カフ) /キョウ(ケフ)
/キョウ(ケフ) 《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし
《名付け》 おし
《意味》
《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし
《名付け》 おし
《意味》

 {動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」
{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」
 {動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」
{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」
 {動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」
{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」
 「花押」とは、記号ふうの署名のこと。
「花押」とは、記号ふうの署名のこと。
 {動}かぶせる。
〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」
《解字》
会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲
《単語家族》
匣コウ(ふたつきのはこ)
{動}かぶせる。
〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」
《解字》
会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲
《単語家族》
匣コウ(ふたつきのはこ) 厭ヨウ(上からおさえられる)
厭ヨウ(上からおさえられる) 壓アツ(=圧。おさえる)と同系。
《類義》
→推
《異字同訓》
おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
壓アツ(=圧。おさえる)と同系。
《類義》
→推
《異字同訓》
おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
教 おしえ🔗⭐🔉
【教】
 11画 攴部 [二年]
区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3
《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる
《音読み》 キョウ(ケウ)
11画 攴部 [二年]
区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3
《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる
《音読み》 キョウ(ケウ) /コウ(カウ)
/コウ(カウ) 〈ji
〈ji o・ji
o・ji o〉
《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ
《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき
《意味》
o〉
《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ
《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき
《意味》
 {動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕
{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕
{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」
{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」
 {名}領主の命令。「教令」
{名}領主の命令。「教令」
 {名}宗教。「回教」
{名}宗教。「回教」
 {助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕
《解字》
{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕
《解字》
 会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。
《単語家族》
交(まじえる)
会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。
《単語家族》
交(まじえる) 較コウ・カク(まじえ比べる)
較コウ・カク(まじえ比べる) 效コウ(=効。交流して習う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
效コウ(=効。交流して習う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 11画 攴部 [二年]
区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3
《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる
《音読み》 キョウ(ケウ)
11画 攴部 [二年]
区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3
《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる
《音読み》 キョウ(ケウ) /コウ(カウ)
/コウ(カウ) 〈ji
〈ji o・ji
o・ji o〉
《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ
《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき
《意味》
o〉
《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ
《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき
《意味》
 {動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕
{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕
{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」
{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」
 {名}領主の命令。「教令」
{名}領主の命令。「教令」
 {名}宗教。「回教」
{名}宗教。「回教」
 {助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕
《解字》
{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕
《解字》
 会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。
《単語家族》
交(まじえる)
会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。
《単語家族》
交(まじえる) 較コウ・カク(まじえ比べる)
較コウ・カク(まじえ比べる) 效コウ(=効。交流して習う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
效コウ(=効。交流して習う)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
教学半 オシウルハマナブノナカバナリ🔗⭐🔉
【教学半】
オシウルハマナブノナカバナリ〈故事〉人を教えるということは、結局自分の勉学の半分をなすものである。人を教えることによって、自分の学問も進歩すること。〔→書経〕
敷教 オシエヲシク🔗⭐🔉
【敷教】
フキョウ・オシエヲシク  教化を広く及ぼす。
教化を広く及ぼす。 宗教を伝え広める。〈同義語〉布教。
宗教を伝え広める。〈同義語〉布教。
 教化を広く及ぼす。
教化を広く及ぼす。 宗教を伝え広める。〈同義語〉布教。
宗教を伝え広める。〈同義語〉布教。
於是 オシ🔗⭐🔉
【於是】
オシ・ココニオイテ そこで。この時にあたって。
汚職 オショク🔗⭐🔉
【汚職】
オショク〔国〕職務上の権力を利用して自分の利益をはかり悪いことをする。涜職トクショク。
立教 オシエヲタツ🔗⭐🔉
【立教】
リッキョウ・オシエヲタツ 教えの方針・原則をきめて示す。
訓 おしえ🔗⭐🔉
【訓】
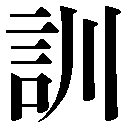 10画 言部 [四年]
区点=2317 16進=3731 シフトJIS=8C50
《常用音訓》クン
《音読み》 クン
10画 言部 [四年]
区点=2317 16進=3731 シフトJIS=8C50
《常用音訓》クン
《音読み》 クン
 /キン
/キン 〈x
〈x n〉
《訓読み》 おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/くん
《名付け》 くに・しる・とき・のり・みち
《意味》
n〉
《訓読み》 おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/くん
《名付け》 くに・しる・とき・のり・みち
《意味》
 {動}おしえる(ヲシフ)。しこりや難問をときほぐして説く。転じて、物事の筋を通しておしえる。「教訓」「訓戒」「訓諸司以徳=諸司ニ訓フルニ徳ヲモッテス」〔→左伝〕
{動}おしえる(ヲシフ)。しこりや難問をときほぐして説く。転じて、物事の筋を通しておしえる。「教訓」「訓戒」「訓諸司以徳=諸司ニ訓フルニ徳ヲモッテス」〔→左伝〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。すじを通した説明。また、年長者や上役の説明や指示。「家訓」「請訓(上司の指示を受ける)」
{名}おしえ(ヲシヘ)。すじを通した説明。また、年長者や上役の説明や指示。「家訓」「請訓(上司の指示を受ける)」
 クンズ{動・名}むずかしい字句の意味をやさしいことばでときほぐす説明。また、その説明のことば。よみ方。〈類義語〉→注・→釈。「訓釈」「古訓」
クンズ{動・名}むずかしい字句の意味をやさしいことばでときほぐす説明。また、その説明のことば。よみ方。〈類義語〉→注・→釈。「訓釈」「古訓」
 {名}たよるべき昔のおしえ。「経訓」「訓曰=訓ニ曰ク」
〔国〕くん。音オンに対して、漢字を日本語に訳して、その訳がその漢字の読みとして固定したもの。たとえば、「日月」においては「ニチ」「ゲツ」が音オン、「ひ」「つき」が訓である。「音訓」
《解字》
会意兼形声。川は、難所やしこりを貫通して流れるかわを描いた象形文字。貫カン(つらぬく)
{名}たよるべき昔のおしえ。「経訓」「訓曰=訓ニ曰ク」
〔国〕くん。音オンに対して、漢字を日本語に訳して、その訳がその漢字の読みとして固定したもの。たとえば、「日月」においては「ニチ」「ゲツ」が音オン、「ひ」「つき」が訓である。「音訓」
《解字》
会意兼形声。川は、難所やしこりを貫通して流れるかわを描いた象形文字。貫カン(つらぬく) 穿セン(うがつ)と同系のことば。訓は「言+音符川」で、ことばで難題をほぐして通すこと。キンは唐宋トウソウ音。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
穿セン(うがつ)と同系のことば。訓は「言+音符川」で、ことばで難題をほぐして通すこと。キンは唐宋トウソウ音。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
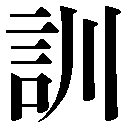 10画 言部 [四年]
区点=2317 16進=3731 シフトJIS=8C50
《常用音訓》クン
《音読み》 クン
10画 言部 [四年]
区点=2317 16進=3731 シフトJIS=8C50
《常用音訓》クン
《音読み》 クン
 /キン
/キン 〈x
〈x n〉
《訓読み》 おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/くん
《名付け》 くに・しる・とき・のり・みち
《意味》
n〉
《訓読み》 おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/くん
《名付け》 くに・しる・とき・のり・みち
《意味》
 {動}おしえる(ヲシフ)。しこりや難問をときほぐして説く。転じて、物事の筋を通しておしえる。「教訓」「訓戒」「訓諸司以徳=諸司ニ訓フルニ徳ヲモッテス」〔→左伝〕
{動}おしえる(ヲシフ)。しこりや難問をときほぐして説く。転じて、物事の筋を通しておしえる。「教訓」「訓戒」「訓諸司以徳=諸司ニ訓フルニ徳ヲモッテス」〔→左伝〕
 {名}おしえ(ヲシヘ)。すじを通した説明。また、年長者や上役の説明や指示。「家訓」「請訓(上司の指示を受ける)」
{名}おしえ(ヲシヘ)。すじを通した説明。また、年長者や上役の説明や指示。「家訓」「請訓(上司の指示を受ける)」
 クンズ{動・名}むずかしい字句の意味をやさしいことばでときほぐす説明。また、その説明のことば。よみ方。〈類義語〉→注・→釈。「訓釈」「古訓」
クンズ{動・名}むずかしい字句の意味をやさしいことばでときほぐす説明。また、その説明のことば。よみ方。〈類義語〉→注・→釈。「訓釈」「古訓」
 {名}たよるべき昔のおしえ。「経訓」「訓曰=訓ニ曰ク」
〔国〕くん。音オンに対して、漢字を日本語に訳して、その訳がその漢字の読みとして固定したもの。たとえば、「日月」においては「ニチ」「ゲツ」が音オン、「ひ」「つき」が訓である。「音訓」
《解字》
会意兼形声。川は、難所やしこりを貫通して流れるかわを描いた象形文字。貫カン(つらぬく)
{名}たよるべき昔のおしえ。「経訓」「訓曰=訓ニ曰ク」
〔国〕くん。音オンに対して、漢字を日本語に訳して、その訳がその漢字の読みとして固定したもの。たとえば、「日月」においては「ニチ」「ゲツ」が音オン、「ひ」「つき」が訓である。「音訓」
《解字》
会意兼形声。川は、難所やしこりを貫通して流れるかわを描いた象形文字。貫カン(つらぬく) 穿セン(うがつ)と同系のことば。訓は「言+音符川」で、ことばで難題をほぐして通すこと。キンは唐宋トウソウ音。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
穿セン(うがつ)と同系のことば。訓は「言+音符川」で、ことばで難題をほぐして通すこと。キンは唐宋トウソウ音。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
誨 おしえる🔗⭐🔉
魴 おしきうお🔗⭐🔉
【魴】
 15画 魚部
区点=8223 16進=7237 シフトJIS=E9B5
《音読み》 ホウ(ハウ)
15画 魚部
区点=8223 16進=7237 シフトJIS=E9B5
《音読み》 ホウ(ハウ) /ボウ(バウ)
/ボウ(バウ) 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 おしきうお(をしきうを)
《意味》
{名}おしきうお(ヲシキウヲ)。淡水魚の一種。頭がとがって小さく、からだは青白い。疲労すると尾が赤くなるという。
《解字》
形声。「魚+音符方」。
ng〉
《訓読み》 おしきうお(をしきうを)
《意味》
{名}おしきうお(ヲシキウヲ)。淡水魚の一種。頭がとがって小さく、からだは青白い。疲労すると尾が赤くなるという。
《解字》
形声。「魚+音符方」。
 15画 魚部
区点=8223 16進=7237 シフトJIS=E9B5
《音読み》 ホウ(ハウ)
15画 魚部
区点=8223 16進=7237 シフトJIS=E9B5
《音読み》 ホウ(ハウ) /ボウ(バウ)
/ボウ(バウ) 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 おしきうお(をしきうを)
《意味》
{名}おしきうお(ヲシキウヲ)。淡水魚の一種。頭がとがって小さく、からだは青白い。疲労すると尾が赤くなるという。
《解字》
形声。「魚+音符方」。
ng〉
《訓読み》 おしきうお(をしきうを)
《意味》
{名}おしきうお(ヲシキウヲ)。淡水魚の一種。頭がとがって小さく、からだは青白い。疲労すると尾が赤くなるという。
《解字》
形声。「魚+音符方」。
漢字源に「おし」で始まるの検索結果 1-23。
 15画
15画 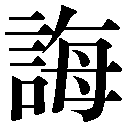 14画 言部
区点=7550 16進=6B52 シフトJIS=E671
《音読み》 カイ(ク
14画 言部
区点=7550 16進=6B52 シフトJIS=E671
《音読み》 カイ(ク イ)
イ) 16画 鳥部
区点=1785 16進=3175 シフトJIS=8995
《音読み》 エン(
16画 鳥部
区点=1785 16進=3175 シフトJIS=8995
《音読み》 エン( ン)
ン)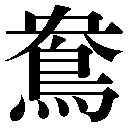 16画 鳥部
区点=8283 16進=7273 シフトJIS=E9F1
《音読み》 オウ(アウ)
16画 鳥部
区点=8283 16進=7273 シフトJIS=E9F1
《音読み》 オウ(アウ)