複数辞典一括検索+![]()
![]()
御 おん🔗⭐🔉
【御】
 12画 彳部 [常用漢字]
区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4
《常用音訓》ギョ/ゴ/おん
《音読み》 ギョ
12画 彳部 [常用漢字]
区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4
《常用音訓》ギョ/ゴ/おん
《音読み》 ギョ /ゴ
/ゴ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み
《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ
《意味》
〉
《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み
《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ
《意味》
 {動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕
{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕
 ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕
ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕
 {名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」
{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」
 ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」
ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」
 {名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」
{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」
 {形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」
{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」
 {動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。
〔国〕
{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。
〔国〕 お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」
お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」 自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」
自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」 相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」
《解字》
会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。
《類義》
治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」
《解字》
会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。
《類義》
治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 12画 彳部 [常用漢字]
区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4
《常用音訓》ギョ/ゴ/おん
《音読み》 ギョ
12画 彳部 [常用漢字]
区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4
《常用音訓》ギョ/ゴ/おん
《音読み》 ギョ /ゴ
/ゴ 〈y
〈y 〉
《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み
《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ
《意味》
〉
《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み
《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ
《意味》
 {動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕
{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕
 ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕
ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕
 {名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」
{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」
 ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」
ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」
 {名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」
{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」
 {形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」
{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」
 {動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。
〔国〕
{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。
〔国〕 お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」
お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」 自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」
自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」 相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」
《解字》
会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。
《類義》
治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」
《解字》
会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。
《類義》
治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
怨家 オンケ🔗⭐🔉
【怨家】
 エンカ うらみあう関係にある家。
エンカ うらみあう関係にある家。 オンケ〔仏〕自分をうらんでいる人。
オンケ〔仏〕自分をうらんでいる人。
 エンカ うらみあう関係にある家。
エンカ うらみあう関係にある家。 オンケ〔仏〕自分をうらんでいる人。
オンケ〔仏〕自分をうらんでいる人。
恩化 オンカ🔗⭐🔉
【恩化】
オンカ 情けで民を教え導く政治のこと。
恩旧 オンキュウ🔗⭐🔉
【恩旧】
オンキュウ 昔からの交際。古いよしみ。
恩仮 オンカ🔗⭐🔉
【恩仮】
オンカ  「恩暇」と同じ。
「恩暇」と同じ。 君主のおかげによる幸い。
君主のおかげによる幸い。 大目にみていただく。
大目にみていただく。
 「恩暇」と同じ。
「恩暇」と同じ。 君主のおかげによる幸い。
君主のおかげによる幸い。 大目にみていただく。
大目にみていただく。
恩威 オンイ🔗⭐🔉
【恩威】
オンイ 恩恵と威光。恵みと力。「恩威並行=恩威並ビ行ハル」
恩栄 オンエイ🔗⭐🔉
【恩栄】
オンエイ 主君の恩恵を受ける光栄。
恩恵 オンケイ🔗⭐🔉
【恩恵】
オンケイ 人のことを思いやる親切な心。恵み。情け。いつくしみ。『恩徳オントク』
恩給 オンキュウ🔗⭐🔉
【恩給】
オンキュウ  功績のほうびとして、禄などをたまわること。
功績のほうびとして、禄などをたまわること。 〔国〕公務員が一定期間勤めたあと、退職または死後に、国家から、本人または遺族に与えられる金銭。
〔国〕公務員が一定期間勤めたあと、退職または死後に、国家から、本人または遺族に与えられる金銭。
 功績のほうびとして、禄などをたまわること。
功績のほうびとして、禄などをたまわること。 〔国〕公務員が一定期間勤めたあと、退職または死後に、国家から、本人または遺族に与えられる金銭。
〔国〕公務員が一定期間勤めたあと、退職または死後に、国家から、本人または遺族に与えられる金銭。
恩遇 オングウ🔗⭐🔉
【恩遇】
オングウ 情け深いもてなし。手厚いもてなし。優遇。
恩仮 オンカ🔗⭐🔉
【恩暇】
オンカ 君主から賜る休暇。『恩仮オンカ』
恩義 オンギ🔗⭐🔉
【恩義{誼}】
オンギ  恩愛と義理。また、義理と人情。
恩愛と義理。また、義理と人情。 いつくしみ。いたわりあい。「吾已失恩義=吾スデニ恩義ヲ失ヘリ」〔古楽府〕
いつくしみ。いたわりあい。「吾已失恩義=吾スデニ恩義ヲ失ヘリ」〔古楽府〕
 恩愛と義理。また、義理と人情。
恩愛と義理。また、義理と人情。 いつくしみ。いたわりあい。「吾已失恩義=吾スデニ恩義ヲ失ヘリ」〔古楽府〕
いつくしみ。いたわりあい。「吾已失恩義=吾スデニ恩義ヲ失ヘリ」〔古楽府〕
恩賜 オンシ🔗⭐🔉
【恩賜】
オンシ  天子から物などを賜ること。また、その物。
天子から物などを賜ること。また、その物。 恵み深いたまもの。
恵み深いたまもの。
 天子から物などを賜ること。また、その物。
天子から物などを賜ること。また、その物。 恵み深いたまもの。
恵み深いたまもの。
恩眷 オンケン🔗⭐🔉
【恩顧】
オンコ 情けをかける。引き立てる。『恩眷オンケン』
恩仇 オンキュウ🔗⭐🔉
【恩讎】
オンシュウ 恩と、あだ。『恩仇オンキュウ』
温克 オンコク🔗⭐🔉
【温克】
ウンコク・オンコク おだやかな気持ちをもち、腹をたてない。▽「詩経」小雅・小宛の「飲酒温克=酒ヲ飲メドモ温克」について、鄭玄ジョウゲンは、温は温藉ウンシャ、克はおのれに勝つとし、朱熹シュキは、温を温恭オンキョウとした。
温故知新 オンコチシン🔗⭐🔉
【温故知新】
オンコチシン・フルキヲアタタメテアタラシキヲシル〈故事〉前に学んだことや古いことばをもう一度よみがえらせて、新しい真理をさとること。「温故而知新、可以為師矣=故キヲ温メテ新シキヲ知レバ、以テ師為ル可シ」〔→論語〕
温厚 オンコウ🔗⭐🔉
【温厚】
オンコウ  おだやかで、誠実なさま。
おだやかで、誠実なさま。 富んで豊かなこと。
富んで豊かなこと。
 おだやかで、誠実なさま。
おだやかで、誠実なさま。 富んで豊かなこと。
富んで豊かなこと。
温恭 オンキョウ🔗⭐🔉
【温恭】
オンキョウ おだやかで、つつしみぶかいさま。
温温 オンオン🔗⭐🔉
【温温】
オンオン  おだやかなさま。
おだやかなさま。 うるおいのあるさま。
うるおいのあるさま。 あたたかなさま。
あたたかなさま。
 おだやかなさま。
おだやかなさま。 うるおいのあるさま。
うるおいのあるさま。 あたたかなさま。
あたたかなさま。
温雅 オンガ🔗⭐🔉
【温雅】
オンガ おだやかで、奥ゆかしい。おとなしく、上品である。
温岐 オンキ🔗⭐🔉
【温岐】
オンキ・オンテイイン〈人名〉庭[イン]は別名。812〜70?晩唐の詩人。太原(山西省)の人。岐は本名。、字アザナは飛卿ヒケイ。詞に巧みであり、詞の文学的地位を不動のものとした。『温飛卿集』がある。
瘟疫 オンエキ🔗⭐🔉
【瘟疫】
オンエキ 熱がこもってひかない急性の伝染病。
穏健 オンケン🔗⭐🔉
【穏健】
オンケン  性格がおだやかで、しっかりしている。
性格がおだやかで、しっかりしている。 〔国〕思想がおだやかである。
〔国〕思想がおだやかである。
 性格がおだやかで、しっかりしている。
性格がおだやかで、しっかりしている。 〔国〕思想がおだやかである。
〔国〕思想がおだやかである。
穏穏 オンオン🔗⭐🔉
【穏穏】
オンオン やすらかなこと。かどだたないさま。
褞褐 オンカツ🔗⭐🔉
【褞褐】
オンカツ  もめんの綿入れ。ぬのこ。
もめんの綿入れ。ぬのこ。 粗布のぬのこを着た人。卑しい人のこと。
粗布のぬのこを着た人。卑しい人のこと。
 もめんの綿入れ。ぬのこ。
もめんの綿入れ。ぬのこ。 粗布のぬのこを着た人。卑しい人のこと。
粗布のぬのこを着た人。卑しい人のこと。
遠志 オンジ🔗⭐🔉
【遠志】
 エンシ 遠大な志。将来のことまで考えた大きな志のこと。
エンシ 遠大な志。将来のことまで考えた大きな志のこと。 オンジ 草の名。ひめはぎ。
オンジ 草の名。ひめはぎ。
 エンシ 遠大な志。将来のことまで考えた大きな志のこと。
エンシ 遠大な志。将来のことまで考えた大きな志のこと。 オンジ 草の名。ひめはぎ。
オンジ 草の名。ひめはぎ。
音 おん🔗⭐🔉
【音】
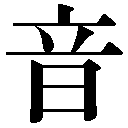 9画 音部 [一年]
区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9
《常用音訓》イン/オン/おと/ね
《音読み》 オン(オム)
9画 音部 [一年]
区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9
《常用音訓》イン/オン/おと/ね
《音読み》 オン(オム) /イン(イム)
/イン(イム) 〈y
〈y n〉
《訓読み》 おと/ね/おん
《名付け》 お・おと・と・なり・ね
《意味》
n〉
《訓読み》 おと/ね/おん
《名付け》 お・おと・と・なり・ね
《意味》
 {名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。
{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。
 {名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕
{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕
 {名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」
{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」
 「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。
〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。
《解字》
「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。
〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。
《解字》
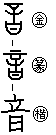 会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。
《単語家族》
暗アン(はっきりしない)
会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。
《単語家族》
暗アン(はっきりしない) 陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
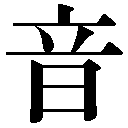 9画 音部 [一年]
区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9
《常用音訓》イン/オン/おと/ね
《音読み》 オン(オム)
9画 音部 [一年]
区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9
《常用音訓》イン/オン/おと/ね
《音読み》 オン(オム) /イン(イム)
/イン(イム) 〈y
〈y n〉
《訓読み》 おと/ね/おん
《名付け》 お・おと・と・なり・ね
《意味》
n〉
《訓読み》 おと/ね/おん
《名付け》 お・おと・と・なり・ね
《意味》
 {名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。
{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。
 {名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕
{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕
 {名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」
{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」
 「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。
〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。
《解字》
「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。
〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。
《解字》
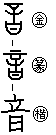 会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。
《単語家族》
暗アン(はっきりしない)
会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。
《単語家族》
暗アン(はっきりしない) 陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
音叉 オンサ🔗⭐🔉
【音叉】
オンサ 音の振動数の一定した基本的発音体。楽器の調律や音響実験などに用いる。鋼鉄製のU字形の棒の中央に柄をつけたもの。
音曲 オンキョク🔗⭐🔉
【音曲】
 オンキョク
オンキョク  音楽のふしまわし。
音楽のふしまわし。 音楽。
音楽。 オンギョク〔国〕琴・三味線などにあわせてうたう俗曲。
オンギョク〔国〕琴・三味線などにあわせてうたう俗曲。
 オンキョク
オンキョク  音楽のふしまわし。
音楽のふしまわし。 音楽。
音楽。 オンギョク〔国〕琴・三味線などにあわせてうたう俗曲。
オンギョク〔国〕琴・三味線などにあわせてうたう俗曲。
音字 オンジ🔗⭐🔉
【音字】
オンジ  反切の上下二字の中で、下の字の韻字に対して、上の字。▽頭子音をあらわす。
反切の上下二字の中で、下の字の韻字に対して、上の字。▽頭子音をあらわす。 「音標文字」と同じ。
「音標文字」と同じ。
 反切の上下二字の中で、下の字の韻字に対して、上の字。▽頭子音をあらわす。
反切の上下二字の中で、下の字の韻字に対して、上の字。▽頭子音をあらわす。 「音標文字」と同じ。
「音標文字」と同じ。
音耗 オンコウ🔗⭐🔉
【音信】
オンシン・インシン たより。手紙。「人事音書漫寂寥=人事音書漫ニ寂寥タリ」〔→杜甫〕『音息オンソク・音訊オンジン・音塵オンジン・音耗オンコウ・音問オンモン・音書オンショ』
音訓 オンクン🔗⭐🔉
【音訓】
オンクン  「音義
「音義 」と同じ。
」と同じ。 発音の上から文字の意味を解釈すること。〈類義語〉声訓。
発音の上から文字の意味を解釈すること。〈類義語〉声訓。 〔国〕漢字の字音と字訓。
〔国〕漢字の字音と字訓。
 「音義
「音義 」と同じ。
」と同じ。 発音の上から文字の意味を解釈すること。〈類義語〉声訓。
発音の上から文字の意味を解釈すること。〈類義語〉声訓。 〔国〕漢字の字音と字訓。
〔国〕漢字の字音と字訓。
音階 オンカイ🔗⭐🔉
【音階】
オンカイ 一定の音程によって、楽音を高さの順にならべたもの。楽曲をつくるもとになる。
音義 オンギ🔗⭐🔉
【音義】
オンギ  文字の発音と意味。また、それを説いた書。『音訓オンクン』
文字の発音と意味。また、それを説いた書。『音訓オンクン』 文字の発音に基づいて、語句の意味を説明すること。
文字の発音に基づいて、語句の意味を説明すること。
 文字の発音と意味。また、それを説いた書。『音訓オンクン』
文字の発音と意味。また、それを説いた書。『音訓オンクン』 文字の発音に基づいて、語句の意味を説明すること。
文字の発音に基づいて、語句の意味を説明すること。
音字 オンジ🔗⭐🔉
【音標文字】
オンピョウモジ 一字ごとには一定の意味をもたず、ことばの発音だけを示す文字。仮名、アルファベットの類。「表音文字」とも。『音字オンジ』
音韻 オンイン🔗⭐🔉
【音韻】
オンイン  音。また、ねいろ。
音。また、ねいろ。 漢字の音(頭子音。普通は声という)と韻(語頭子音をのぞいたのこりの音)。
漢字の音(頭子音。普通は声という)と韻(語頭子音をのぞいたのこりの音)。 現代の言語学で、ことばを形成する要素としての音声の単位。また、その体系。
現代の言語学で、ことばを形成する要素としての音声の単位。また、その体系。
 音。また、ねいろ。
音。また、ねいろ。 漢字の音(頭子音。普通は声という)と韻(語頭子音をのぞいたのこりの音)。
漢字の音(頭子音。普通は声という)と韻(語頭子音をのぞいたのこりの音)。 現代の言語学で、ことばを形成する要素としての音声の単位。また、その体系。
現代の言語学で、ことばを形成する要素としての音声の単位。また、その体系。
音響 オンキョウ🔗⭐🔉
【音響】
オンキョウ 音や声の響き。
漢字源に「おん」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む