複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (53)
くり【栗】🔗⭐🔉
くり【栗】
ブナ科の落葉高木。低山地の落葉樹林に広く分布。樹皮は暗褐色。葉は長さ8〜12センチメートルの長楕円形、刺状の鋸歯があり、互生。6月頃花穂を出し淡黄色の細花をつける。単性花で雌雄同株。果実は「いが」で包まれ、食用・菓子などにする。木材は耐久・耐湿性が強く、家屋の土台、鉄道の枕木、艪ろ・車・運動具などに用いる。〈[季]秋〉。「栗の花」は〈[季]夏〉。万葉集5「瓜はめば子ども思ほゆ―はめばまして偲しぬはゆ」
クリ(実)
撮影:関戸 勇
 クリ(花)
撮影:関戸 勇
クリ(花)
撮影:関戸 勇

 クリ(花)
撮影:関戸 勇
クリ(花)
撮影:関戸 勇

くり‐あん【栗餡】🔗⭐🔉
くり‐あん【栗餡】
白餡に栗の実を細かく刻んでまぜたもの。栗饅頭の餡にする。
くり‐いし【栗石】🔗⭐🔉
くり‐いし【栗石】
①栗の実くらいの小石。
②河原に散在する直径10〜15センチメートルぐらいの丸石。コンクリート骨材などに使用。ぐりいし。
くり‐いろ【栗色】🔗⭐🔉
くり‐いろ【栗色】
栗の実の皮のような色。焦茶色。
Munsell color system: 2YR3.5/4
⇒くりいろ‐ど【栗色土】
くりいろ‐ど【栗色土】🔗⭐🔉
くりいろ‐ど【栗色土】
乾燥地域の土壌。腐植質が少なく、表土の色は熟した栗の色に似ている。ユーラシア大陸ではチェルノーゼム帯の南側、中国北部・北アメリカではチェルノーゼム帯の西側に分布。
⇒くり‐いろ【栗色】
くり‐うめ【栗梅】🔗⭐🔉
くり‐うめ【栗梅】
染色の一つ。栗皮色の赤みの勝ったもの。栗梅色。毛吹草6「色こきは―ぞめの紅葉哉」
Munsell color system: 10R4/5.5
くり‐かすげ【栗糟毛】🔗⭐🔉
くり‐かすげ【栗糟毛】
馬の毛色の名。白い差毛さしげのある栗毛。
くり‐がた【栗形】🔗⭐🔉
くり‐がた【栗形】
刀の鞘表さやおもての鯉口こいぐち近くに付ける、孔を穿うがった栗の実み状のもの。角製または金属製。この孔に下緒さげおを通す。下緒通さげおどおし。→腰刀(図)
栗形


くり‐かのこ【栗鹿の子】🔗⭐🔉
くり‐かのこ【栗鹿の子】
求肥ぎゅうひ糖を小豆漉餡こしあんで包んで丸め、周りに栗の蜜漬をつけ、寒天液などで固めた菓子。
栗鹿の子
撮影:関戸 勇


くり‐カボチャ【栗南瓜】🔗⭐🔉
くり‐カボチャ【栗南瓜】
「カボチャ(南瓜)」参照。
くり‐かわ【栗皮】‥カハ🔗⭐🔉
くり‐かわ【栗皮】‥カハ
①栗の実の皮。
②黒みをおびた赤茶色の革。栗革。
③栗皮茶の略。
⇒くりかわ‐ちゃ【栗皮茶】
くりかわ‐ちゃ【栗皮茶】‥カハ‥🔗⭐🔉
くりかわ‐ちゃ【栗皮茶】‥カハ‥
黒みをおびた赤茶色。栗革茶。くりかわ。
⇒くり‐かわ【栗皮】
くり‐きんとん【栗金団】🔗⭐🔉
くり‐きんとん【栗金団】
クリの実を煮つぶして作ったきんとん。また、クリの実をまぜたきんとん。
くり‐げ【栗毛】🔗⭐🔉
くり‐げ【栗毛】
馬の毛色の名。たてがみと尾は赤褐色で、地色の赤黒色のもの。平家物語8「―なる馬の下尾白いに乗りかへて」
⇒くりげ‐ぶち【栗毛駁】
くりげ‐ぶち【栗毛駁】🔗⭐🔉
くりげ‐ぶち【栗毛駁】
馬の毛色の名。栗毛のぶちのあるもの。くりぶち。
⇒くり‐げ【栗毛】
くりこ‐の‐もち【栗粉の餅】🔗⭐🔉
くりこ‐の‐もち【栗粉の餅】
(→)「栗の子餅」に同じ。狂言、業平餅「―とくりごとを」
くりこま‐やま【栗駒山】🔗⭐🔉
くりこま‐やま【栗駒山】
宮城・岩手・秋田3県の県境にある二重式火山。標高1627メートル。山麓南側に栗駒五湯など温泉が多く、こけしの産地がある。須川岳。
栗駒山
提供:オフィス史朗


くりさき‐りゅう【栗崎流】‥リウ🔗⭐🔉
くりさき‐りゅう【栗崎流】‥リウ
天正(1573〜1592)の頃、肥後国宇土郡栗崎の人栗崎道喜(1568〜1651)が呂宋ルソン島に渡ってスペイン人に外科術を学び、帰国後長崎で始めた南蛮外科医術の流派。
くりしぎ‐ぞうむし【栗鴫象虫】‥ザウ‥🔗⭐🔉
くりしぎ‐ぞうむし【栗鴫象虫】‥ザウ‥
ゾウムシ科の甲虫。体は灰黄色の鱗毛を密生。体長約8ミリメートル。細長い口吻で栗の実に小孔を穿ち、卵を産み込む。幼虫は蛆うじ型で俗に「くりむし」といい、栗の実を食害する。シギムシ。
クリシギゾウムシ(幼虫)
撮影:海野和男


くりしま【栗島】🔗⭐🔉
くりしま【栗島】
姓氏の一つ。
⇒くりしま‐すみこ【栗島すみ子】
くりしま‐すみこ【栗島すみ子】🔗⭐🔉
くりしま‐すみこ【栗島すみ子】
映画女優・日本舞踊家。本姓、池田。東京生れ。映画「虞美人草」(1921年)などに出演、初期のスターとなる。(1902〜1987)
⇒くりしま【栗島】
くりた【栗田】🔗⭐🔉
くりた【栗田】
姓氏の一つ。
⇒くりた‐ひろし【栗田寛】
くり‐たけ【栗茸】🔗⭐🔉
くり‐たけ【栗茸】
担子菌類のきのこ。秋、広葉樹の枯切株・倒木に群生。傘は初め半球形で後開く。赤褐色で直径3〜7センチメートル。食用。同属のニグリクリタケは有毒。〈[季]秋〉
くりた‐ひろし【栗田寛】🔗⭐🔉
くりた‐ひろし【栗田寛】
歴史学者。号は栗里。水戸生れ。彰考館で「大日本史」編纂にあたる。維新後は東大教授。著「標注古風土記」「上古職官考」など。(1835〜1899)
⇒くりた【栗田】
くり‐たまばち【栗癭蜂】🔗⭐🔉
くり‐たまばち【栗癭蜂】
タマバチ科のハチ。体長は約3ミリメートル。雌だけで繁殖、雄は未知。発生は年1回、クリの芽に虫癭ちゅうえいが形成されると木は衰弱、枯死することもある。中国原産の侵入種で、法定森林害虫。
くり‐ねずみ【栗鼠】🔗⭐🔉
くり‐ねずみ【栗鼠】
①馬の毛色の名。栗毛の鼠色をおびたもの。
②栗鼠色の略。
⇒くりねずみ‐いろ【栗鼠色】
くりねずみ‐いろ【栗鼠色】🔗⭐🔉
くりねずみ‐いろ【栗鼠色】
栗色がかった鼠色。くりねずみ。
⇒くり‐ねずみ【栗鼠】
くりのこ‐もち【栗の子餅】🔗⭐🔉
くりのこ‐もち【栗の子餅】
栗の実の粉を入れたり、まぶしたりした餅。9月9日重陽ちょうようの節句に用いた。栗粉の餅。
くりのもと‐しゅう【栗本衆】🔗⭐🔉
くりのもと‐しゅう【栗本衆】
鎌倉初期、俳諧連歌を作る人々の称。無心衆。栗本の衆。栗本。↔柿本衆
くりはら【栗原】🔗⭐🔉
くりはら【栗原】
宮城県北西部の市。東部にラムサール条約湿地の伊豆沼・内沼がある。中心部の築館つきだては奥州街道の宿場町。人口8万。
くりは‐らん【栗葉蘭】🔗⭐🔉
くりは‐らん【栗葉蘭】
ウラボシ科の常緑シダ。暖地の岩や樹幹上をはう太い針金状の根茎から、クリの葉に似た長さ15センチメートル内外の葉を生ずる。
くりはらん


くり‐ひろい【栗拾い】‥ヒロヒ🔗⭐🔉
くり‐ひろい【栗拾い】‥ヒロヒ
栗の実を拾い集めること。
くり‐ぶち【栗駁】🔗⭐🔉
くり‐ぶち【栗駁】
馬の毛色の名。栗毛のぶちのあるもの。くりげぶち。
くり‐まんじゅう【栗饅頭】‥ヂユウ🔗⭐🔉
くり‐まんじゅう【栗饅頭】‥ヂユウ
栗餡を包んだ小判形の饅頭。皮の上に卵黄を塗って艶よく焼いたもの。くりまん。
栗饅頭
撮影:関戸 勇


くり‐めいげつ【栗名月】🔗⭐🔉
くり‐めいげつ【栗名月】
(月見に栗を供えるからいう)旧暦九月十三夜の月。のちの月。豆名月。〈[季]秋〉。→芋名月
くり‐めし【栗飯】🔗⭐🔉
くり‐めし【栗飯】
クリの実を入れて炊いた飯。〈[季]秋〉。正岡子規、仰臥漫録「午、―ノ粥四碗」
くりもと【栗本】🔗⭐🔉
くりもと【栗本】
姓氏の一つ。
⇒くりもと‐じょうん【栗本鋤雲】
⇒くりもと‐は【栗本派】
くりもと‐じょうん【栗本鋤雲】🔗⭐🔉
くりもと‐じょうん【栗本鋤雲】
新聞記者。名は鯤こん。号は匏庵ほうあん。江戸生れの幕臣。幕府奥詰医師となり、箱館奉行所組頭・外国奉行を歴任。親仏政策を推進し1867年(慶応3)渡仏。維新後、73年から郵便報知新聞の主筆。(1822〜1897)
⇒くりもと【栗本】
くりもと‐は【栗本派】🔗⭐🔉
くりもと‐は【栗本派】
蒔絵師の一派。幸阿弥6代長清(1506〜1603)の子、栗本幸阿弥を祖とする。
⇒くりもと【栗本】
くりやき【栗焼】🔗⭐🔉
くりやき【栗焼】
狂言。太郎冠者が栗を焼くよう命ぜられ、一つ食べ二つ食べして皆食べてしまい、作り話と謡で言いわけし、叱られる。
くりやま【栗山】🔗⭐🔉
くりやま【栗山】
姓氏の一つ。
⇒くりやま‐せんぽう【栗山潜鋒】
⇒くりやま‐たいぜん【栗山大膳】
くりやま‐おけ【栗山桶】‥ヲケ🔗⭐🔉
くりやま‐おけ【栗山桶】‥ヲケ
把手とってをつけた曲物まげもの。つるし下げて手水鉢、また、湯桶ゆとうとする。日光の名物。
くりやま‐せんぽう【栗山潜鋒】🔗⭐🔉
くりやま‐せんぽう【栗山潜鋒】
江戸中期の儒学者・史学者。名は愿すなお。山城淀の人。水戸藩儒。国史に通じ、1697年(元禄10)27歳で彰考館総裁。著「保建大記」は史論として名著。(1671〜1706)
⇒くりやま【栗山】
くりやま‐たいぜん【栗山大膳】🔗⭐🔉
くりやま‐たいぜん【栗山大膳】
江戸初期、筑前福岡藩黒田家の家老。名は利章。藩主忠之を謀反の企てありと幕府に訴えたが、敗訴して盛岡藩に預けられた。黒田騒動として演劇・講談などに脚色。(1591〜1652)
⇒くりやま【栗山】
くり‐ようかん【栗羊羹】‥ヤウ‥🔗⭐🔉
くり‐ようかん【栗羊羹】‥ヤウ‥
栗の実をすりつぶして、栗だけで作った羊羹。または、蜜漬けの栗の実を小豆の練羊羹に混ぜて作ったもの。
くるすの【栗栖野】🔗⭐🔉
くるすの【栗栖野】
①山城国宇治郡山科村(現、京都市山科区)の地名。
②京都市北区鷹峰の東、西賀茂の辺。みくるすの。(歌枕)
り‐す【栗鼠】🔗⭐🔉
り‐す【栗鼠】
(リスは漢字の音読み)ネズミ目リス科の哺乳類の総称。また特にニホンリスのことで、頭胴長20センチメートル、尾長15センチメートルほど。夏毛は赤褐色、冬毛は黄褐色で、腹は白い。森林に生息し、木の実や木の葉、昆虫などを食べる。小枝や葉を集め、枝の間に巣を作る。日本特産。北海道には類似種のキタリスがいる。また各地で、より大形のタイワンリスが野生化。キネズミ。〈日葡辞書〉
タイワンリス
提供:東京動物園協会
 ニホンリス
提供:東京動物園協会
ニホンリス
提供:東京動物園協会

 ニホンリス
提供:東京動物園協会
ニホンリス
提供:東京動物園協会

りす‐ざる【栗鼠猿】🔗⭐🔉
りす‐ざる【栗鼠猿】
オマキザル科リスザル属のサル3〜5種の総称。また、そのうちのコモンリスザルを指す。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。毛色は明るい褐色で、顔から胸にかけて白い。アマゾン流域からコロンビアの森林に分布し、集団で生活。ペット・実験動物としても飼育。
リスザル
提供:東京動物園協会


りっとう【栗東】🔗⭐🔉
りっとう【栗東】
滋賀県南部の市。道路交通の要地。史跡の狛坂こまさか磨崖仏が有名。人口6万。
りつりん‐こうえん【栗林公園】‥ヱン🔗⭐🔉
りつりん‐こうえん【栗林公園】‥ヱン
香川県高松市にある公園。高松藩主松平頼重(1622〜1695)の築造。のち5世頼恭よりたかの時に回遊式庭園が完成。
栗林公園
撮影:新海良夫


[漢]栗🔗⭐🔉
栗 字形
 〔木部6画/10画/人名/2310・372A〕
〔音〕リツ(漢)
〔訓〕くり
[意味]
①木の名。くり(の実)。「栗子・栗爆(=くりの実が火ではじける)」
②おそれおののく。ふるえる。きびしい。(同)慄。「栗栗・栗烈・戦栗」
▷[
〔木部6画/10画/人名/2310・372A〕
〔音〕リツ(漢)
〔訓〕くり
[意味]
①木の名。くり(の実)。「栗子・栗爆(=くりの実が火ではじける)」
②おそれおののく。ふるえる。きびしい。(同)慄。「栗栗・栗烈・戦栗」
▷[ ]は異体字。
]は異体字。
 〔木部6画/10画/人名/2310・372A〕
〔音〕リツ(漢)
〔訓〕くり
[意味]
①木の名。くり(の実)。「栗子・栗爆(=くりの実が火ではじける)」
②おそれおののく。ふるえる。きびしい。(同)慄。「栗栗・栗烈・戦栗」
▷[
〔木部6画/10画/人名/2310・372A〕
〔音〕リツ(漢)
〔訓〕くり
[意味]
①木の名。くり(の実)。「栗子・栗爆(=くりの実が火ではじける)」
②おそれおののく。ふるえる。きびしい。(同)慄。「栗栗・栗烈・戦栗」
▷[ ]は異体字。
]は異体字。
大辞林の検索結果 (57)
くり【栗】🔗⭐🔉
くり [2] 【栗】
ブナ科の落葉高木。山中に生え,また果樹として栽植。雌雄同株。葉は狭長楕円形。六月頃,数個の雌花と黄白色の雄花穂をつけ,秋,いがに包まれた果実は食用。材は重硬で,腐りにくく建築土台・枕木・家具用。[季]秋。《古寺や―を埋けたる縁の下/鬼貫》
〔「栗の花」は [季]夏。《日高きに宿もとめ得つ―の花/虚子》〕
くり-あん【栗餡】🔗⭐🔉
くり-あん [0] 【栗餡】
栗を刻み入れた白餡。また,栗で作った餡。
くり-いし【栗石】🔗⭐🔉
くり-いし [2] 【栗石】
(1)栗の実ぐらいの小石。
(2)直径15センチメートル前後の大きさの石。地盤固めや石垣の埋め石などに用いる。割り栗石。ぐり。
くり-いろ【栗色】🔗⭐🔉
くり-いろ [0] 【栗色】
栗の実の皮のような黒みがかった茶色。栗皮色。「―の髪」
くりいろ-ど【栗色土】🔗⭐🔉
くりいろ-ど [4] 【栗色土】
温帯のステップ地帯に生成する暗褐色の土壌。チェルノーゼム(黒土)地帯より降水量の少ない地帯に分布する。
くり-うめ【栗梅】🔗⭐🔉
くり-うめ [2] 【栗梅】
染め色の名。紫がかった栗色。[日葡]
くり-かた【栗形】🔗⭐🔉
くり-かた [0] 【栗形】
打ち刀や腰刀の鞘口(サヤグチ)近くにつけ,下げ緒(オ)を通すもの。木・角・金属で作った環で,多く栗の実を半截(ハンセツ)した形。「栗形」は当て字で,緒を通す穴を刳(ク)った物の意で「刳り形」が語源らしい。下げ緒通し。
くり-かのこ【栗鹿の子】🔗⭐🔉
くり-かのこ [3] 【栗鹿の子】
求肥(ギユウヒ)糖を小豆(アズキ)の漉餡(コシアン)で包み,周囲に栗の蜜漬けをつけた和菓子。
くり-カボチャ【栗―】🔗⭐🔉
くり-カボチャ [3] 【栗―】
セイヨウカボチャの一種。南アメリカ山地原産といわれ,冷涼地で栽培される。果実は大きく,倒卵形ないし球形で,果皮は平滑。味が栗のようだというのでこの名がある。
くり-かわ【栗皮】🔗⭐🔉
くり-かわ ―カハ [0] 【栗皮】
(1)栗の実の皮。
(2)栗皮茶色の革。赤黒い茶色の革。
(3)「栗皮茶」の略。
くりかわ-ちゃ【栗皮茶】🔗⭐🔉
くりかわ-ちゃ ―カハ― [4] 【栗皮茶】
赤黒い茶色。くりかわ。
くり-きんとん【栗金団】🔗⭐🔉
くり-きんとん [3] 【栗金団】
クリまたはサツマイモの餡(アン)に,ゆでたクリを加えて練ったきんとん。
くり-げ【栗毛】🔗⭐🔉
くり-げ [0] 【栗毛】
馬の毛色の名。全体に明るい黄褐色。たてがみや尾も同色のものが多いが,白いものは尾花(オバナ)栗毛と呼ぶ。
くりげ-ぶち【栗毛駁】🔗⭐🔉
くりげ-ぶち [4][0] 【栗毛駁】
馬の毛色の名。栗色でぶちのあるもの。
くり-けむし【栗毛虫】🔗⭐🔉
くり-けむし [3] 【栗毛虫】
樟蚕(クスサン)の幼虫。白色の長毛のある緑色の毛虫。シラガタロウ。
くりこま【栗駒】🔗⭐🔉
くりこま 【栗駒】
宮城県北西部,栗原郡の町。栗駒山南東斜面と山麓の町。旧城下町。栗駒国定公園に属し,駒 湯・新湯などの温泉がある。
湯・新湯などの温泉がある。
 湯・新湯などの温泉がある。
湯・新湯などの温泉がある。
くりこま-こくていこうえん【栗駒国定公園】🔗⭐🔉
くりこま-こくていこうえん ―コウ ン 【栗駒国定公園】
栗駒山を中心とする国定公園。火山・温泉・渓谷・原生林に恵まれる。
ン 【栗駒国定公園】
栗駒山を中心とする国定公園。火山・温泉・渓谷・原生林に恵まれる。
 ン 【栗駒国定公園】
栗駒山を中心とする国定公園。火山・温泉・渓谷・原生林に恵まれる。
ン 【栗駒国定公園】
栗駒山を中心とする国定公園。火山・温泉・渓谷・原生林に恵まれる。
くりこま-やま【栗駒山】🔗⭐🔉
くりこま-やま 【栗駒山】
岩手・宮城・秋田三県の県境にある成層火山。海抜1627メートル。高山植物の種類が豊富。岩手県側では須川岳,秋田県側では大日岳と呼ぶ。
くりさき-りゅう【栗崎流】🔗⭐🔉
くりさき-りゅう ―リウ 【栗崎流】
南蛮外科医術の流派。肥後国栗崎の人,栗崎道喜(1582-1651)がルソンに渡り外科術を学び,帰国して長崎で始めたもの。
くり-しぎぞうむし【栗鷸象虫】🔗⭐🔉
くり-しぎぞうむし ―シギザウムシ [5] 【栗鷸象虫】
ゾウムシ科の甲虫。体は長卵形で,体長6〜10ミリメートル。頭部は細長く伸長した吻(フン)となる。雌はクリのいがの上から吻で実まで穴をあけて産卵し,幼虫(クリムシ)は内部を食害。シギムシ。
くりしま【栗島】🔗⭐🔉
くりしま 【栗島】
姓氏の一。
くりしま-すみこ【栗島すみ子】🔗⭐🔉
くりしま-すみこ 【栗島すみ子】
(1902-1987) 映画女優。東京生まれ。本名,池田すみ子。ヘンリー小谷監督の「虞美人草」に主演して人気を集め,以後松竹蒲田撮影所の看板スターとして君臨。代表作「生さぬ仲」「不如帰」「船頭小唄」「水藻の花」「浪子」「受難華」など。
くりた【栗田】🔗⭐🔉
くりた 【栗田】
姓氏の一。
くりた-ひろし【栗田寛】🔗⭐🔉
くりた-ひろし 【栗田寛】
(1835-1899) 歴史学者。水戸の生まれ。彰考館に出仕。水戸家の「大日本史」編纂に参与。のち東大教授。主著「荘園考」「新撰姓氏録考証」など。
くり-たい【栗帯】🔗⭐🔉
くり-たい [0] 【栗帯】
山地帯の下部で,クリ・コナラ・エノキなどを主体とする夏緑樹林帯をいう。この上部にあるブナ帯に含められることもある。
くり-たけ【栗茸】🔗⭐🔉
くり-たけ [2] 【栗茸】
担子菌類ハラタケ目のきのこ。秋,クリ・ナラ・クヌギなどに群生。傘は径3〜8センチメートルで赤褐色ないし茶褐色。食用。アカンボウ。
栗茸
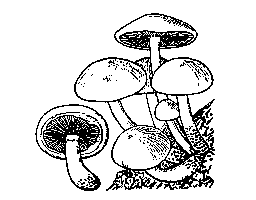 [図]
[図]
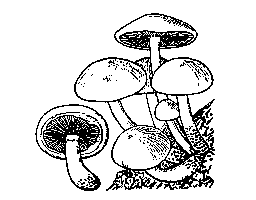 [図]
[図]
くり-ねずみ【栗鼠】🔗⭐🔉
くり-ねずみ [3] 【栗鼠】
(1)馬の毛色の名。鼠色のまじった栗毛。
(2)栗鼠色。
くりねずみ-いろ【栗鼠色】🔗⭐🔉
くりねずみ-いろ [0] 【栗鼠色】
栗色がかった鼠色。くりねずみ。
くり-の-もと【栗本】🔗⭐🔉
くり-の-もと 【栗本】
(1)鎌倉時代,狂歌を詠む一派の称。無心。
→柿本(カキノモト)
(2)卑俗・滑稽な連歌。俳諧連歌。無心連歌。
くりのもと-の-しゅう【栗本衆】🔗⭐🔉
くりのもと-の-しゅう 【栗本衆】
後鳥羽院の頃,滑稽で座興的な連歌,いわゆる「無心連歌」を詠んだ人々の称。無心衆。
→柿本衆(カキノモトシユウ)
くりはし【栗橋】🔗⭐🔉
くりはし 【栗橋】
埼玉県北東部,北葛飾郡の町。近世には日光街道の宿駅で利根川の河川交通の要地。
くりはら【栗原】🔗⭐🔉
くりはら 【栗原】
姓氏の一。
くりはら-いね【栗原イネ】🔗⭐🔉
くりはら-いね 【栗原イネ】
(1852-1922) 企業家。下野の人。上京し織物工場を設立。従業員の技術教育にも尽力。
くり-ひろい【栗拾い】🔗⭐🔉
くり-ひろい ―ヒロヒ [3] 【栗拾い】
栗の実を拾うこと。また,その人。[季]秋。
くり-まんじゅう【栗饅頭】🔗⭐🔉
くり-まんじゅう ―マンヂユウ [3] 【栗饅頭】
栗餡(クリアン)を,卵・砂糖などをまぜた小麦粉の皮で包み,栗色に焼き上げた饅頭。
くり-むし【栗虫】🔗⭐🔉
くり-むし [2] 【栗虫】
クリシギゾウムシの幼虫。クリの実を食害する害虫。
くり-めいげつ【栗名月】🔗⭐🔉
くり-めいげつ [3] 【栗名月】
陰暦九月一三夜の月の別名。栗を供えて月見をする風習がある。豆名月。後(ノチ)の月。[季]秋。
→芋名月
くり-めし【栗飯】🔗⭐🔉
くり-めし [0] 【栗飯】
栗の実を入れてたいた飯。[季]秋。
くりもと【栗本】🔗⭐🔉
くりもと 【栗本】
姓氏の一。
くりもと-じょうん【栗本鋤雲】🔗⭐🔉
くりもと-じょうん 【栗本鋤雲】
(1822-1897) 新聞記者。名は鯤(コン)。別号,匏菴(ホウアン)。旧幕臣。学問所頭取・外国奉行を歴任。1873年(明治6)郵便報知新聞の編集主任となった。著「匏菴遺稿」など。
くりもと-は【栗本派】🔗⭐🔉
くりもと-は 【栗本派】
蒔絵(マキエ)師の一流派。幸阿弥六代清長の子,栗本幸阿弥を祖とする。幸阿弥派。
→幸阿弥
くりやき【栗焼】🔗⭐🔉
くりやき 【栗焼】
狂言の一。主に命ぜられて栗を焼いていた太郎冠者は,一つ食べ二つ食べして皆食べてしまい,竈(カマ)の神に進上したと苦しい言い訳をする。
くりやま【栗山】🔗⭐🔉
くりやま 【栗山】
北海道中央部,夕張(ユウバリ)郡の町。夕張川中流域の町。
くりやま【栗山】🔗⭐🔉
くりやま 【栗山】
姓氏の一。
くりやま-こうあん【栗山孝庵】🔗⭐🔉
くりやま-こうあん ―カウアン 【栗山孝庵】
〔名は「幸庵」とも書く〕
(1728-1791) 江戸後期の医師。萩の人。山脇東洋に師事。日本で初めて女体の解剖を行なった。
くりやま-せんぽう【栗山潜鋒】🔗⭐🔉
くりやま-せんぽう 【栗山潜鋒】
(1671-1706) 江戸中期の儒者。名は愿(スナオ)。山城の人。徳川光圀に招かれ,「大日本史」の編纂に従事。彰考館総裁。著「保建大記」など。
くりやま-だいぜん【栗山大膳】🔗⭐🔉
くりやま-だいぜん 【栗山大膳】
(1591-1652) 江戸初期の福岡藩家老。「黒田騒動」の中心人物。藩主黒田忠之の行状を諫めるためあえて幕府に出訴,南部藩預かりの身となり,その地で没した。
くり-ようかん【栗羊羹】🔗⭐🔉
くり-ようかん ―ヤウカン [3] 【栗羊羹】
栗を加えた練り羊羹。また,小豆(アズキ)のこし餡(アン)に栗を加えた蒸し羊羹。
くるすの【栗栖野】🔗⭐🔉
くるすの 【栗栖野】
(1)山城国宇治郡山科村(現在京都市東山区稲荷山の東麓にあたる)の地名。
(2)京都市北区,鷹ヶ峰の奥の山間の古地名。古く皇室の狩猟場であった。御栗栖野(ミクルスノ)。
りす【栗鼠】🔗⭐🔉
りす [1] 【栗鼠】
〔字音「りっそ」の転〕
(1)齧歯(ゲツシ)目リス科の哺乳類のうち,ムササビ類を除くものの総称。
(2){(1)}の一種。頭胴長約20センチメートル。尾長は16センチメートルほどで,毛がふさふさとしている。毛色は夏冬および産地で異なり,冬毛の背面は北方産が暗褐色,南方産は黄褐色,腹面は白色。夏毛は体側が橙褐色を帯びる。平地から亜高山帯の針葉樹林にすみ,木登りがうまく,泳ぎも巧み。昼行性で,種子や木の実を食べる。本州・四国・九州に分布。キネズミ。
りす-ざる【栗鼠猿】🔗⭐🔉
りす-ざる [3] 【栗鼠猿】
オマキザル科の哺乳類。頭胴長約30センチメートル,尾長もほぼ同じ。体毛は短く,黄褐色。群れをつくり,樹上生活をする。雑食性。中南米の森林に分布。ペットや実験動物とされる。
りす-もどき【栗鼠擬】🔗⭐🔉
りす-もどき [3] 【栗鼠擬】
ツパイの別名。
りっとう【栗東】🔗⭐🔉
りっとう 【栗東】
滋賀県南部,栗太(クリタ)郡の町。名神高速道路の開通後,内陸工業地域として発展。中央競馬会のトレーニング-センターがある。
りつりん-こうえん【栗林公園】🔗⭐🔉
りつりん-こうえん ―コウ ン 【栗林公園】
香川県高松市にある公園。高松藩主松平頼重(1622-1695)が,生駒氏の旧庭を増改築したのに始まり,四代をかけて完成した池泉回遊式庭園。1875年(明治8)公開。
ン 【栗林公園】
香川県高松市にある公園。高松藩主松平頼重(1622-1695)が,生駒氏の旧庭を増改築したのに始まり,四代をかけて完成した池泉回遊式庭園。1875年(明治8)公開。
 ン 【栗林公園】
香川県高松市にある公園。高松藩主松平頼重(1622-1695)が,生駒氏の旧庭を増改築したのに始まり,四代をかけて完成した池泉回遊式庭園。1875年(明治8)公開。
ン 【栗林公園】
香川県高松市にある公園。高松藩主松平頼重(1622-1695)が,生駒氏の旧庭を増改築したのに始まり,四代をかけて完成した池泉回遊式庭園。1875年(明治8)公開。
くり【栗】(和英)🔗⭐🔉
くり【栗】
a chestnut (実);→英和
a chestnut tree (木).〜色の nut-brown.〜拾いに行く go chestnut gathering.
くりげ【栗毛の馬】(和英)🔗⭐🔉
くりげ【栗毛の馬】
a chestnut (horse).→英和
りす【栗鼠】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「栗」で始まるの検索結果。