複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (44)
かぶす【臭橙】🔗⭐🔉
かぶす【臭橙】
ダイダイの一変種。実は酸味強く苦い。香味料として用いる。
くさ・い【臭い】🔗⭐🔉
くさ・い【臭い】
〔形〕[文]くさ・し(ク)
①いやなにおいがする。源氏物語帚木「極熱ごくねちの草薬を服して、いと―・きによりてなむ」。「靴下が―・い」
②疑わしい。あやしい。浄瑠璃、心中二つ腹帯「大方これ―・い者、ぬくぬくと駆落ぢやの」。「あの女のそぶりが―・い」
③わざとらしくていやみだ。「―・い演技」
④(接尾語的に)
㋐…のにおいがする。「こげ―・い」
㋑…のように感じられる。…らしい。「仙人―・い」「バタ―・い」「いんちき―・い」
㋒いやになる程…だ。「てれ―・い」「面倒―・い」
⇒臭い飯を食う
⇒臭い物に蠅がたかる
⇒臭いものに蓋をする
⇒臭いもの身知らず
○臭い飯を食うくさいめしをくう🔗⭐🔉
○臭い飯を食うくさいめしをくう
刑務所で服役する。
⇒くさ・い【臭い】
○臭い物に蠅がたかるくさいものにはえがたかる🔗⭐🔉
○臭い物に蠅がたかるくさいものにはえがたかる
醜悪なものが類をもって集まるたとえ。
⇒くさ・い【臭い】
○臭いものに蓋をするくさいものにふたをする🔗⭐🔉
○臭いものに蓋をするくさいものにふたをする
悪事や醜聞などを、他人に知られないように一時的なてだてで隠す。
⇒くさ・い【臭い】
○臭いもの身知らずくさいものみしらず🔗⭐🔉
○臭いもの身知らずくさいものみしらず
自分の放つにおいは気にならないように、自分の欠点には気がつかない。
⇒くさ・い【臭い】
くさいり‐ずいしょう【草入り水晶】‥シヤウ
(草を含んだように見えるからいう)電気石などの針状結晶を含んだ水晶。
くさ‐いろ【草色】
青みがかった緑色。もえぎいろ。
Munsell color system: 5GY5/5
くさ‐うお【草魚】‥ウヲ
クサウオ科の海産の硬骨魚。全長45センチメートル余だが、体は柔軟でこんにゃく状。北日本に多産し、肥料とする。広義にはクサウオ科魚類の総称。
くさ‐うら【草占】
路傍の草を結びあわせてそれが解けるか解けないかを見て吉凶を判ずること。草が風になびくさまを見て占うことともいう。
くさえ‐の‐さか【孔舎衛坂】クサヱ‥
(一説に、「衛」は「衙」の誤りかという)(→)「くさかざか」に同じ。
くさか【久坂】
姓氏の一つ。
⇒くさか‐げんずい【久坂玄瑞】
くさ‐かい【草飼い】‥カヒ
馬に草を与えること。
⇒くさかい‐どころ【草飼い所】
くさかい‐どころ【草飼い所】‥カヒ‥
まぐさを得るための領地。曾我物語8「一所給はりて馬の―をもしたまへ」
⇒くさ‐かい【草飼い】
くさ‐か・う【草飼う】‥カフ
〔自五〕
馬・牛などに飼料の草を与える。
くさ‐かき【草掻き】
草を掻き除くこと。また、その人・道具。草削り。
くさ‐がき【草垣】
草が生い茂って垣のようになったもの。
くさ‐がく・る【草隠る】
〔自下二〕
草かげに隠れる。後拾遺和歌集恋「夏山の木のした水は―・れつつ」
くさ‐がくれ【草隠れ】
①草かげに隠れること。また、その所。
②草深い田舎の隠れ家。源氏物語蓬生「かかる―に過ぐし給ひける年月のあはれもおろかならず」
くさ‐かげ【草陰】
茂った草のかげ。
⇒くさかげ‐の【草陰の】
くさかげ‐の【草陰の】
〔枕〕
「あら」「あの」などの「あ」にかかる。万葉集12「―あらゐの崎の笠島を」
⇒くさ‐かげ【草陰】
くさ‐かげろう【草蜉蝣・草蜻蛉】‥カゲロフ
アミメカゲロウ目クサカゲロウ科の昆虫の総称。また、その一種。形は小さいトンボのようで弱々しく、緑色。翅は透明、多くの翅脈がある。体長約1センチメートル。成虫も幼虫もアブラムシを食う益虫。成虫は灯火に飛来する。卵には長柄があり、優曇華うどんげという。〈[季]夏〉
くさかげろう
 クサカゲロウ
撮影:海野和男
クサカゲロウ
撮影:海野和男
 くさか‐げんずい【久坂玄瑞】
幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)
⇒くさか【久坂】
くさ‐かご【草籠】
刈った草を入れる籠。くさかりかご。
くさか‐ざか【孔舎衙坂】
生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。
くさ‐かす・む【草霞む】
〔自四〕
草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)
くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ
蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」
くさ‐かたばみ【草酢漿】
紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。
くさかべ【日下部】
姓氏の一つ。
⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】
くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥
天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)
くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】
書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)
⇒くさかべ【日下部】
くさ‐がま【草鎌】
草刈り鎌。
くさ‐かまり【草屈】
くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。
くさ‐がめ【草亀・臭亀】
①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。
クサガメ
提供:東京動物園協会
くさか‐げんずい【久坂玄瑞】
幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)
⇒くさか【久坂】
くさ‐かご【草籠】
刈った草を入れる籠。くさかりかご。
くさか‐ざか【孔舎衙坂】
生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。
くさ‐かす・む【草霞む】
〔自四〕
草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)
くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ
蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」
くさ‐かたばみ【草酢漿】
紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。
くさかべ【日下部】
姓氏の一つ。
⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】
くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥
天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)
くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】
書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)
⇒くさかべ【日下部】
くさ‐がま【草鎌】
草刈り鎌。
くさ‐かまり【草屈】
くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。
くさ‐がめ【草亀・臭亀】
①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。
クサガメ
提供:東京動物園協会
 ②カメムシの別称。
くさかや‐ひめ【草茅姫】
草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」
くさか‐やま【草香山】
大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)
くさ‐かり【草刈】
草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」
⇒くさかり‐うた【草刈唄】
⇒くさかり‐うま【草刈馬】
⇒くさかり‐がま【草刈鎌】
⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】
⇒くさかり‐ば【草刈場】
⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】
⇒くさかり‐わらわ【草刈童】
くさかり‐うた【草刈唄】
草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐うま【草刈馬】
7月7日の朝、真菰まこもや藁わらで作った馬を草刈につれてゆく行事。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐がま【草刈鎌】
草を刈るのに用いる鎌。草鎌。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】‥ダヒ
カワビシャ科の海産の硬骨魚。ツボダイと俗称。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐ば【草刈場】
①飼料・肥料などにする草を刈り取るための共有の原野。秣場まぐさば。
②比喩的に、そこから利益を得ようと多くの人が目をつける場所・集団。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐ぶえ【草刈笛】
草刈童わらわなどが吹く笛。草笛。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐わらわ【草刈童】‥ワラハ
草を刈る子ども。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさ‐がれ【草枯れ】
秋から冬にかけて草が枯れること。また、その時節。〈[季]冬〉。源氏物語葵「―のまがきに残るなでしこを別れし秋の形見とぞ見る」
くさ‐かんむり【草冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「花」「草」などの冠の「艹」の称。字書では「艸」部でひく。草頭そうとう。そうこう。
くさ‐き【草木】
草と木。そうもく。
⇒くさき‐ぞめ【草木染】
⇒草木にも心を置く
⇒草木も靡く
⇒草木も眠る
⇒草木も揺がぬ
くさ‐ぎ【臭木】
クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」
クサギ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
②カメムシの別称。
くさかや‐ひめ【草茅姫】
草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」
くさか‐やま【草香山】
大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)
くさ‐かり【草刈】
草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」
⇒くさかり‐うた【草刈唄】
⇒くさかり‐うま【草刈馬】
⇒くさかり‐がま【草刈鎌】
⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】
⇒くさかり‐ば【草刈場】
⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】
⇒くさかり‐わらわ【草刈童】
くさかり‐うた【草刈唄】
草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐うま【草刈馬】
7月7日の朝、真菰まこもや藁わらで作った馬を草刈につれてゆく行事。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐がま【草刈鎌】
草を刈るのに用いる鎌。草鎌。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】‥ダヒ
カワビシャ科の海産の硬骨魚。ツボダイと俗称。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐ば【草刈場】
①飼料・肥料などにする草を刈り取るための共有の原野。秣場まぐさば。
②比喩的に、そこから利益を得ようと多くの人が目をつける場所・集団。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐ぶえ【草刈笛】
草刈童わらわなどが吹く笛。草笛。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐わらわ【草刈童】‥ワラハ
草を刈る子ども。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさ‐がれ【草枯れ】
秋から冬にかけて草が枯れること。また、その時節。〈[季]冬〉。源氏物語葵「―のまがきに残るなでしこを別れし秋の形見とぞ見る」
くさ‐かんむり【草冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「花」「草」などの冠の「艹」の称。字書では「艸」部でひく。草頭そうとう。そうこう。
くさ‐き【草木】
草と木。そうもく。
⇒くさき‐ぞめ【草木染】
⇒草木にも心を置く
⇒草木も靡く
⇒草木も眠る
⇒草木も揺がぬ
くさ‐ぎ【臭木】
クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」
クサギ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
くさき‐ぞめ【草木染】
天然の植物染料で染めること。また、それで染めたもの。合成染料によるものと区別するために、染色家の山崎斌あきら(1892〜1972)が昭和初期に命名。
草木染のはがき
撮影:関戸 勇
⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
くさき‐ぞめ【草木染】
天然の植物染料で染めること。また、それで染めたもの。合成染料によるものと区別するために、染色家の山崎斌あきら(1892〜1972)が昭和初期に命名。
草木染のはがき
撮影:関戸 勇
 草木染の和紙
撮影:関戸 勇
草木染の和紙
撮影:関戸 勇
 ⇒くさ‐き【草木】
⇒くさ‐き【草木】
 クサカゲロウ
撮影:海野和男
クサカゲロウ
撮影:海野和男
 くさか‐げんずい【久坂玄瑞】
幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)
⇒くさか【久坂】
くさ‐かご【草籠】
刈った草を入れる籠。くさかりかご。
くさか‐ざか【孔舎衙坂】
生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。
くさ‐かす・む【草霞む】
〔自四〕
草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)
くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ
蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」
くさ‐かたばみ【草酢漿】
紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。
くさかべ【日下部】
姓氏の一つ。
⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】
くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥
天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)
くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】
書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)
⇒くさかべ【日下部】
くさ‐がま【草鎌】
草刈り鎌。
くさ‐かまり【草屈】
くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。
くさ‐がめ【草亀・臭亀】
①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。
クサガメ
提供:東京動物園協会
くさか‐げんずい【久坂玄瑞】
幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)
⇒くさか【久坂】
くさ‐かご【草籠】
刈った草を入れる籠。くさかりかご。
くさか‐ざか【孔舎衙坂】
生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。
くさ‐かす・む【草霞む】
〔自四〕
草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)
くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ
蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」
くさ‐かたばみ【草酢漿】
紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。
くさかべ【日下部】
姓氏の一つ。
⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】
くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥
天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)
くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】
書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)
⇒くさかべ【日下部】
くさ‐がま【草鎌】
草刈り鎌。
くさ‐かまり【草屈】
くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。
くさ‐がめ【草亀・臭亀】
①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。
クサガメ
提供:東京動物園協会
 ②カメムシの別称。
くさかや‐ひめ【草茅姫】
草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」
くさか‐やま【草香山】
大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)
くさ‐かり【草刈】
草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」
⇒くさかり‐うた【草刈唄】
⇒くさかり‐うま【草刈馬】
⇒くさかり‐がま【草刈鎌】
⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】
⇒くさかり‐ば【草刈場】
⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】
⇒くさかり‐わらわ【草刈童】
くさかり‐うた【草刈唄】
草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐うま【草刈馬】
7月7日の朝、真菰まこもや藁わらで作った馬を草刈につれてゆく行事。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐がま【草刈鎌】
草を刈るのに用いる鎌。草鎌。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】‥ダヒ
カワビシャ科の海産の硬骨魚。ツボダイと俗称。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐ば【草刈場】
①飼料・肥料などにする草を刈り取るための共有の原野。秣場まぐさば。
②比喩的に、そこから利益を得ようと多くの人が目をつける場所・集団。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐ぶえ【草刈笛】
草刈童わらわなどが吹く笛。草笛。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐わらわ【草刈童】‥ワラハ
草を刈る子ども。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさ‐がれ【草枯れ】
秋から冬にかけて草が枯れること。また、その時節。〈[季]冬〉。源氏物語葵「―のまがきに残るなでしこを別れし秋の形見とぞ見る」
くさ‐かんむり【草冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「花」「草」などの冠の「艹」の称。字書では「艸」部でひく。草頭そうとう。そうこう。
くさ‐き【草木】
草と木。そうもく。
⇒くさき‐ぞめ【草木染】
⇒草木にも心を置く
⇒草木も靡く
⇒草木も眠る
⇒草木も揺がぬ
くさ‐ぎ【臭木】
クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」
クサギ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
②カメムシの別称。
くさかや‐ひめ【草茅姫】
草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」
くさか‐やま【草香山】
大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)
くさ‐かり【草刈】
草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」
⇒くさかり‐うた【草刈唄】
⇒くさかり‐うま【草刈馬】
⇒くさかり‐がま【草刈鎌】
⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】
⇒くさかり‐ば【草刈場】
⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】
⇒くさかり‐わらわ【草刈童】
くさかり‐うた【草刈唄】
草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐うま【草刈馬】
7月7日の朝、真菰まこもや藁わらで作った馬を草刈につれてゆく行事。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐がま【草刈鎌】
草を刈るのに用いる鎌。草鎌。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】‥ダヒ
カワビシャ科の海産の硬骨魚。ツボダイと俗称。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐ば【草刈場】
①飼料・肥料などにする草を刈り取るための共有の原野。秣場まぐさば。
②比喩的に、そこから利益を得ようと多くの人が目をつける場所・集団。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐ぶえ【草刈笛】
草刈童わらわなどが吹く笛。草笛。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさかり‐わらわ【草刈童】‥ワラハ
草を刈る子ども。
⇒くさ‐かり【草刈】
くさ‐がれ【草枯れ】
秋から冬にかけて草が枯れること。また、その時節。〈[季]冬〉。源氏物語葵「―のまがきに残るなでしこを別れし秋の形見とぞ見る」
くさ‐かんむり【草冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「花」「草」などの冠の「艹」の称。字書では「艸」部でひく。草頭そうとう。そうこう。
くさ‐き【草木】
草と木。そうもく。
⇒くさき‐ぞめ【草木染】
⇒草木にも心を置く
⇒草木も靡く
⇒草木も眠る
⇒草木も揺がぬ
くさ‐ぎ【臭木】
クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」
クサギ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
くさき‐ぞめ【草木染】
天然の植物染料で染めること。また、それで染めたもの。合成染料によるものと区別するために、染色家の山崎斌あきら(1892〜1972)が昭和初期に命名。
草木染のはがき
撮影:関戸 勇
⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
くさき‐ぞめ【草木染】
天然の植物染料で染めること。また、それで染めたもの。合成染料によるものと区別するために、染色家の山崎斌あきら(1892〜1972)が昭和初期に命名。
草木染のはがき
撮影:関戸 勇
 草木染の和紙
撮影:関戸 勇
草木染の和紙
撮影:関戸 勇
 ⇒くさ‐き【草木】
⇒くさ‐き【草木】
くさ‐がめ【草亀・臭亀】🔗⭐🔉
くさ‐がめ【草亀・臭亀】
①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。
クサガメ
提供:東京動物園協会
 ②カメムシの別称。
②カメムシの別称。
 ②カメムシの別称。
②カメムシの別称。
くさ‐ぎ【臭木】🔗⭐🔉
くさ‐ぎ【臭木】
クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」
クサギ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
 クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
くさ‐ぎり【臭桐】🔗⭐🔉
くさ‐ぎり【臭桐】
クサギの別称。
くさ‐ずみ【臭墨】🔗⭐🔉
くさ‐ずみ【臭墨】
悪臭のある下等な墨。
くさ‐み【臭み】🔗⭐🔉
くさ‐み【臭み】
①くさいこと。また、その程度。「―を抜く」
②人柄や行為などの、何となく感じられるいやな感じ。「―のある文章」
くさ‐もの【臭物】🔗⭐🔉
くさ‐もの【臭物】
①(女房詞)ネギの異称。
②にせ物らしいもの。
くそうず【臭水】クサウヅ🔗⭐🔉
くそうず【臭水】クサウヅ
(クサミズの音便)石油の古称。大和物語本草「是越後にある―なるべし。田沢の中にあり。土より出る油なり」
しゅう【臭】シウ🔗⭐🔉
しゅう【臭】シウ
①におい。特に、悪いにおい。くさみ。「官僚―」
②臭素の略。
しゅう‐え【臭穢】シウヱ🔗⭐🔉
しゅう‐え【臭穢】シウヱ
くさくきたないこと。
しゅう‐か【臭化】シウクワ🔗⭐🔉
しゅう‐か【臭化】シウクワ
〔化〕臭化物であることを示す語。
⇒しゅうか‐エチル【臭化エチル】
⇒しゅうか‐カリウム【臭化カリウム】
⇒しゅうか‐ぎん【臭化銀】
⇒しゅうか‐すいそ【臭化水素】
⇒しゅうか‐ぶつ【臭化物】
⇒しゅうか‐メチル【臭化メチル】
しゅう‐がい【臭害】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐がい【臭害】シウ‥
悪臭が引き起こす害。
しゅうか‐エチル【臭化エチル】シウクワ‥🔗⭐🔉
しゅうか‐エチル【臭化エチル】シウクワ‥
分子式C2H5Br 揮発性無色の液体。冷凍剤原料、局所麻酔剤などに用いる。
⇒しゅう‐か【臭化】
しゅうか‐カリウム【臭化カリウム】シウクワ‥🔗⭐🔉
しゅうか‐カリウム【臭化カリウム】シウクワ‥
化学式KBr 無色の立方晶系結晶。水によく溶ける。催眠鎮静剤・写真感光材料の製造、現像液に用いる。臭剥しゅうポツ。臭化カリ。
⇒しゅう‐か【臭化】
しゅうか‐ぎん【臭化銀】シウクワ‥🔗⭐🔉
しゅうか‐ぎん【臭化銀】シウクワ‥
化学式AgBr 淡黄色の粉末。水に溶けにくい。光が当たると漸次分解して銀を遊離し暗色となる。写真感光材料の主要構成要素。
⇒しゅう‐か【臭化】
しゅう‐かく【臭覚】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐かく【臭覚】シウ‥
(→)嗅覚きゅうかくに同じ。
しゅうか‐すいそ【臭化水素】シウクワ‥🔗⭐🔉
しゅうか‐すいそ【臭化水素】シウクワ‥
分子式HBr 無色の刺激臭ある気体。水によく溶け、水溶液は強酸。
⇒しゅう‐か【臭化】
しゅうか‐ぶつ【臭化物】シウクワ‥🔗⭐🔉
しゅうか‐ぶつ【臭化物】シウクワ‥
(bromide)臭素と他の元素または原子団との化合物。臭化水素・臭化カリウムの類。
⇒しゅう‐か【臭化】
しゅうか‐メチル【臭化メチル】シウクワ‥🔗⭐🔉
しゅうか‐メチル【臭化メチル】シウクワ‥
分子式CH3Br ブロモメタン。無色の有毒ガスで、有機合成原料・害虫駆除・土壌燻蒸に広く用いられたが、1992年のモントリオール議定書締約国会合においてオゾン層破壊物質に指定され、先進国での全廃を決定。
⇒しゅう‐か【臭化】
しゅうかん‐しょう【臭汗症】シウ‥シヤウ🔗⭐🔉
しゅうかん‐しょう【臭汗症】シウ‥シヤウ
腋窩えきか・陰部などから悪臭のある汗を分泌する病症。腋臭わきがの類。
しゅう‐き【臭気】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐き【臭気】シウ‥
くさいにおい。不快なにおい。悪臭。くさみ。「―が鼻をつく」
⇒しゅうき‐どめ【臭気止め】
⇒しゅうき‐ぬき【臭気抜き】
しゅう‐きつ【臭橘】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐きつ【臭橘】シウ‥
〔植〕カラタチの別称。
しゅうき‐どめ【臭気止め】シウ‥🔗⭐🔉
しゅうき‐どめ【臭気止め】シウ‥
悪臭を消し止める薬剤。防臭剤。
⇒しゅう‐き【臭気】
しゅうき‐ぬき【臭気抜き】シウ‥🔗⭐🔉
しゅうき‐ぬき【臭気抜き】シウ‥
いやなにおいを抜くための装置。
⇒しゅう‐き【臭気】
しゅう‐さいぼう【臭細胞】シウ‥バウ🔗⭐🔉
しゅう‐さいぼう【臭細胞】シウ‥バウ
(→)嗅きゅう細胞に同じ。
しゅう‐せん【臭腺】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐せん【臭腺】シウ‥
強い臭いを発する液体を分泌する外分泌腺。皮膚腺、特に皮脂腺が特殊化したもの。スカンクのものが有名。ジャコウジカの雄の香腺、鳥類の尾腺、カメムシ類の後胸腺など。臭液腺。悪臭腺。
しゅう‐そ【臭素】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐そ【臭素】シウ‥
(bromine)ハロゲン族元素の一種。元素記号Br 原子番号35。原子量79.90。赤褐色で常温では液体。揮発しやすく激しい刺激性の臭気をもつ。カリウム・マグネシウムなどの化合物として存在。有毒。酸化剤・殺菌剤として用い、写真用薬品・医薬の原料とする。ブロム。
⇒しゅうそ‐し【臭素紙】
⇒しゅうそ‐しん【臭素疹】
⇒しゅうそ‐すい【臭素水】
しゅうそ‐し【臭素紙】シウ‥🔗⭐🔉
しゅうそ‐し【臭素紙】シウ‥
(→)ブロマイド紙に同じ。
⇒しゅう‐そ【臭素】
しゅうそ‐しん【臭素疹】シウ‥🔗⭐🔉
しゅうそ‐しん【臭素疹】シウ‥
臭素または臭素塩類の服用によって皮膚面に生じる暗褐紅色の発疹。主として個人的素質に起因。
⇒しゅう‐そ【臭素】
しゅうそ‐すい【臭素水】シウ‥🔗⭐🔉
しゅうそ‐すい【臭素水】シウ‥
臭素の水溶液。黄色ないし褐色を呈し、試薬に使用。ブロム水。
⇒しゅう‐そ【臭素】
しゅう‐ふ【臭腐】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐ふ【臭腐】シウ‥
腐って臭くなること。
しゅう‐ポツ【臭剥】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐ポツ【臭剥】シウ‥
(ポツはカリウムの英語名ポタシウムから)(→)臭化カリウムの通称。しゅうボツ。
しゅう‐み【臭味】シウ‥🔗⭐🔉
しゅう‐み【臭味】シウ‥
①くさみ。臭気。
②身にしみついたよくない気風・気分。
におい【匂】ニホヒ🔗⭐🔉
におい【匂】ニホヒ
①赤などのあざやかな色が美しく映えること。万葉集10「黄葉もみちばの―は繁し」
②はなやかなこと。つやつやしいこと。万葉集18「少女らがゑまひの―」
③かおり。香気。狭衣物語3「かうばしき―」。「香水の―」
④(「臭」と書く)くさいかおり。臭気。「すえた―」
⑤ひかり。威光。源氏物語椎本「つかさ位世の中の―も」
⑥人柄などの、おもむき。気品。源氏物語幻「かどかどしう、らうらうじう、―多かりし心ざま、もてなし、言の葉」
⑦(「臭」とも書く)そのものが持つ雰囲気。それらしい感じ。「庶民的な―」「犯罪の―」
⑧同色の濃淡によるぼかし。
㋐染色法また襲かさねの色目などで、上が濃く、下が薄い配色。上を濃くするのを普通とし、下を濃くするのを裾濃すそごという。
㋑匂縅においおどしの略。
㋒女のかき眉の下の方の薄くぼかしたところ。
㋓日本刀の刃の、地肌との境目の部分に霧のようにほんのりと見える文様。最も大切な見所の一つ。
⑨芸能や和歌・俳諧などで、そのものに漂う気分・情趣・余情など。花鏡「一声の―より、舞へ移る境にて妙力あるべし」。去来抄「移り、―、響きはつけざまのあんばいなり」→匂付においづけ。
◇「臭」は、好ましくないものに使うことが多い。
⇒におい‐あぶら【匂油】
⇒におい‐あらせいとう【匂紫羅欄花】
⇒におい‐おどし【匂縅】
⇒におい‐が【匂香】
⇒におい‐かけ【匂懸】
⇒におい‐かたじろ【匂肩白】
⇒におい‐ぎれ【匂切】
⇒におい‐ぐさ【匂草】
⇒におい‐こ【匂粉】
⇒におい‐ざくら【匂桜】
⇒におい‐ずみ【匂墨】
⇒におい‐すみれ【匂菫】
⇒におい‐だま【匂玉】
⇒におい‐づけ【匂付】
⇒におい‐どり【匂鳥】
⇒におい‐の‐はな【匂の花】
⇒におい‐ぶくろ【匂袋】
⇒におい‐やぐるま【匂矢車】
におい【臭】ニホヒ🔗⭐🔉
におい【臭】ニホヒ
⇒におい(匂)4・7
にお・う【匂う・臭う】ニホフ🔗⭐🔉
にお・う【匂う・臭う】ニホフ
[一]〔自五〕
(ニは丹で赤色、ホは穂・秀の意で外に現れること、すなわち赤などの色にくっきり色づくのが原義。転じて、ものの香りがほのぼのと立つ意)
①木・草または赤土などの色に染まる。万葉集8「草枕旅ゆく人も行き触らば―・ひぬべくも咲ける萩かも」
②赤などのあざやかな色が美しく映える。万葉集11「紅の濃染の衣を下に着ば人の見らくに―・ひ出でむかも」。万葉集19「春の苑紅―・ふ桃の花した照る道に出で立つをとめ」
③よい香りが立つ。万葉集17「橘の―・へる香かもほととぎす鳴く夜の雨に移ろひぬらむ」
④悪いにおいがする。臭気がただよう。「腐った魚がひどく―・う」
⑤生き生きとした美しさなどが溢れる。万葉集14「筑紫なる―・ふ子故に陸奥のかとりをとめの結ひし紐とく」。源氏物語野分「見奉るわが顔にも移りくるやうに愛敬は―・ひたり」
⑥余光・恩恵などが(周囲に)及ぶ。源氏物語真木柱「人一人を思ひかしづき給はむ故は、ほとりまでも―・ふためしこそあれと心得ざりしを」
⑦(染色・襲かさねの色目などを)次第に薄くぼかしてある。讃岐典侍日記「五節の折着たりし黄なるより紅まで―・ひたりし紅葉どもに、えび染めの唐衣とかや着たりし」。類聚名義抄「暈、ニホフ」
⑧雰囲気として感じられる。かすかにその気配がある。「不正が―・う」
◇多く、よい感じの場合は「匂う」、悪い感じの場合は「臭う」と書く。
[二]〔他下二〕
美しく染めつける。万葉集16「すみのえの岸野の榛はりに―・ふれど」
[漢]臭🔗⭐🔉
臭 字形
 筆順
筆順
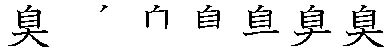 〔自部3画/9画/常用/2913・3D2D〕
[
〔自部3画/9画/常用/2913・3D2D〕
[ ] 字形
] 字形
 〔自部4画/10画〕
〔音〕シュウ〈シウ〉(漢)
〔訓〕くさい・におい
[意味]
におい。いやなにおい。くさい。「臭気・悪臭・体臭」。くさみ。いやな感じ。「俗臭・役人臭」
[解字]
会意。「自」(=はな)+「犬」。犬がはなでにおいをかぐ意。
[下ツキ
悪臭・異臭・汚臭・劇臭・激臭・口臭・俗臭・体臭・脱臭・同臭・銅臭・乳臭・腐臭・防臭・無臭・余臭・和臭
[難読]
臭橙かぼす
〔自部4画/10画〕
〔音〕シュウ〈シウ〉(漢)
〔訓〕くさい・におい
[意味]
におい。いやなにおい。くさい。「臭気・悪臭・体臭」。くさみ。いやな感じ。「俗臭・役人臭」
[解字]
会意。「自」(=はな)+「犬」。犬がはなでにおいをかぐ意。
[下ツキ
悪臭・異臭・汚臭・劇臭・激臭・口臭・俗臭・体臭・脱臭・同臭・銅臭・乳臭・腐臭・防臭・無臭・余臭・和臭
[難読]
臭橙かぼす
 筆順
筆順
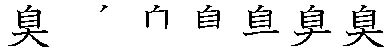 〔自部3画/9画/常用/2913・3D2D〕
[
〔自部3画/9画/常用/2913・3D2D〕
[ ] 字形
] 字形
 〔自部4画/10画〕
〔音〕シュウ〈シウ〉(漢)
〔訓〕くさい・におい
[意味]
におい。いやなにおい。くさい。「臭気・悪臭・体臭」。くさみ。いやな感じ。「俗臭・役人臭」
[解字]
会意。「自」(=はな)+「犬」。犬がはなでにおいをかぐ意。
[下ツキ
悪臭・異臭・汚臭・劇臭・激臭・口臭・俗臭・体臭・脱臭・同臭・銅臭・乳臭・腐臭・防臭・無臭・余臭・和臭
[難読]
臭橙かぼす
〔自部4画/10画〕
〔音〕シュウ〈シウ〉(漢)
〔訓〕くさい・におい
[意味]
におい。いやなにおい。くさい。「臭気・悪臭・体臭」。くさみ。いやな感じ。「俗臭・役人臭」
[解字]
会意。「自」(=はな)+「犬」。犬がはなでにおいをかぐ意。
[下ツキ
悪臭・異臭・汚臭・劇臭・激臭・口臭・俗臭・体臭・脱臭・同臭・銅臭・乳臭・腐臭・防臭・無臭・余臭・和臭
[難読]
臭橙かぼす
大辞林の検索結果 (45)
かぶす【臭橙】🔗⭐🔉
かぶす [0][1] 【臭橙】
ダイダイの一種。酸味が強い。食酢をとる。しゅうとう。
くさ・い【臭い】🔗⭐🔉
くさ・い 【臭い】
■一■ [2] (形)[文]ク くさ・し
〔動詞「腐(クサ)る」と同源〕
(1)いやなにおいがする。「―・いどぶ川」「取り捨つるわざも知らねば,―・き香世界にみち満ちて/方丈記」
(2)疑わしい様子である。あやしい。うさんくさい。「犯行現場から急ぎ足で立ち去った男が―・い」
■二■ (接尾)
〔形容詞型活用 ([文]ク くさ・し)〕
体言およびそれに準ずるものに付く。
(1)そのようなにおいがする意を表す。「汗―・い」「ガス―・い」「こげ―・い」
(2)いかにもそのように感じられる,そのような傾向を帯びている意を表す。「いんちき―・い説明」「素人―・い」「抹香(マツコウ)―・い」
(3)(形容動詞の語幹に付いて)その語の意味を強めるはたらきをする。「面倒―・い」「ばか―・い」
[派生] ――が・る(動ラ五[四])――さ(名)――み(名)
臭い飯(メシ)を食・う🔗⭐🔉
臭い飯(メシ)を食・う
囚人として,刑務所の飯を食う。刑務所に入る。
臭い物に蠅(ハエ)がたかる🔗⭐🔉
臭い物に蠅(ハエ)がたかる
悪臭のするものによく蠅がたかるように,悪い者どうしは類をもって集まるものだというたとえ。
臭い物に蓋(フタ)をする🔗⭐🔉
臭い物に蓋(フタ)をする
悪事や失敗や知られると都合の悪い事柄を一時のがれに隠そうとすることのたとえ。
臭い物身(ミ)知らず🔗⭐🔉
臭い物身(ミ)知らず
身体に悪臭があるのを自分では気づかないように,自分の欠点は自分ではわからないというたとえ。
くさ-がめ【草亀・臭亀】🔗⭐🔉
くさ-がめ [3][0] 【草亀・臭亀】
(1)カメの一種。甲長12〜25センチメートルで,背甲は暗褐色。四肢の付け根にある腺から臭液を出す。子はゼニガメと呼ばれる。本州以南と朝鮮・台湾・中国に分布。
(2)カメムシの異名。
くさ-ぎ【臭木】🔗⭐🔉
くさ-ぎ [0] 【臭木】
クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多い。高さ約3メートル。全体に臭気がある。葉は大きく広卵形。八月頃,枝頂に白花を多数つける。果実は球形で濃青色,果実の下に赤紫色の萼が星形に残る。果実を染料に,若葉を食用にする。クサギリ。
〔「臭木の花」「臭木の実」は [季]秋〕
臭木
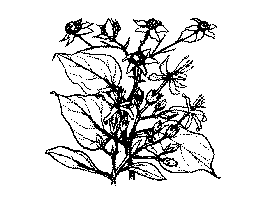 [図]
[図]
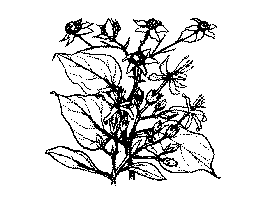 [図]
[図]
くさぎ-かめむし【臭木椿象】🔗⭐🔉
くさぎ-かめむし [5] 【臭木椿象】
カメムシの一種。体長約16ミリメートル。体は黒褐色の地に黄褐色の斑紋がある。サクラ・モモ・クサギなどについて果実から汁を吸う。不快な臭気を発する。九州以北の各地と東アジアに分布。
くさぎ-の-むし【臭木の虫】🔗⭐🔉
くさぎ-の-むし [0] 【臭木の虫】
クサギの幹につくカミキリムシなどの幼虫。子供の疳(カン)の薬とした。
くさ-ぎり【臭桐】🔗⭐🔉
くさ-ぎり [2] 【臭桐】
クサギの別名。
くさ-ずみ【臭墨】🔗⭐🔉
くさ-ずみ [2] 【臭墨】
悪いにおいのする粗悪な墨。
くさ-み【臭み】🔗⭐🔉
くさ-み [3] 【臭み】
(1)不快なにおい。また,におっている状態やその程度。「水道の水にいやな―がある」
(2)人に与える嫌な感じ。不快な印象。嫌み。「―のある芝居」
(3)葱(ネギ)。
くさ-もの【臭物】🔗⭐🔉
くさ-もの 【臭物】
〔近世女性語〕
葱(ネギ)・蒜(ヒル)・韮(ニラ)などをいう。
くそうず【臭水】🔗⭐🔉
くそうず クサウヅ 【臭水】
〔「くさみず」の転〕
石油の古名。
しゅう-か【臭化】🔗⭐🔉
しゅう-か シウクワ [0] 【臭化】
臭素と化合すること。また,化合していること。
しゅうか-エチル【臭化―】🔗⭐🔉
しゅうか-エチル シウクワ― [4] 【臭化―】
エチルアルコールに臭化水素酸と硫酸を加えてつくる揮発性の無色液体。化学式 C H
H Br 有機合成用試薬・局所麻酔剤などに用いる。ブロモエタン。
Br 有機合成用試薬・局所麻酔剤などに用いる。ブロモエタン。
 H
H Br 有機合成用試薬・局所麻酔剤などに用いる。ブロモエタン。
Br 有機合成用試薬・局所麻酔剤などに用いる。ブロモエタン。
しゅうか-カリウム【臭化―】🔗⭐🔉
しゅうか-カリウム シウクワ― [5] 【臭化―】
カリウムの臭化物で,白色の結晶。化学式 KBr 水に溶けやすい。写真の定着剤,鎮静剤,赤外線吸収スペクトル測定用プリズムなどに用いる。臭化カリ。
しゅうか-ぎん【臭化銀】🔗⭐🔉
しゅうか-ぎん シウクワ― [3] 【臭化銀】
黄色味をおびた白色の固体。化学式 AgBr 光にあたると徐々に分解し,銀を遊離して黒色になる。鋭い感光性を利用し,写真感光材料に用いる。
しゅうか-すいそ【臭化水素】🔗⭐🔉
しゅうか-すいそ シウクワ― [4] 【臭化水素】
臭素と水素を反応させてつくる刺激臭のある気体。化学式 HBr 塩化水素に似た性質をもち,水によく溶けて強酸である臭化水素酸を生じるが,塩化水素と異なり酸化されやすい。
しゅうか-ぶつ【臭化物】🔗⭐🔉
しゅうか-ぶつ シウクワ― [3] 【臭化物】
臭素と臭素より陽性な元素との化合物。臭化カリウム・臭化水素など。
しゅう-がい【臭害】🔗⭐🔉
しゅう-がい シウ― [0] 【臭害】
いやなにおいが引き起こす公害。
しゅう-かく【臭覚】🔗⭐🔉
しゅう-かく シウ― [0][1] 【臭覚】
「嗅覚(キユウカク)」に同じ。
しゅうかん-しょう【臭汗症】🔗⭐🔉
しゅうかん-しょう シウカンシヤウ [0] 【臭汗症】
強い臭いのある汗を分泌する病症。腋(ワキ)の下のものは,わきがと呼ばれる。
しゅう-き【臭気】🔗⭐🔉
しゅう-き シウ― [1] 【臭気】
くさいにおい。いやなにおい。悪臭。「―がただよう」
しゅうき-ぬき【臭気抜き】🔗⭐🔉
しゅうき-ぬき シウ― [0] 【臭気抜き】
臭気を抜くための器具・装置。
しゅう-きつ【臭橘】🔗⭐🔉
しゅう-きつ シウ― [0] 【臭橘】
カラタチの異名。
しゅう-さいぼう【臭細胞】🔗⭐🔉
しゅう-さいぼう シウサイバウ [3] 【臭細胞】
⇒嗅細胞(キユウサイボウ)
しゅう-せん【臭腺】🔗⭐🔉
しゅう-せん シウ― [0] 【臭腺】
動物の強い臭気のある液を分泌する腺。哺乳類ではイタチ・スカンクの肛門腺,ジャコウジカ・ジャコウネコの麝香(ジヤコウ)腺がよく知られる。前者は護身用,後者は異性の誘引に役立つ。昆虫のカメムシ類・ゴミムシ類にもある。臭液腺。悪臭腺。
しゅう-そ【臭素】🔗⭐🔉
しゅう-そ シウ― [1] 【臭素】
〔bromine〕
ハロゲンの一。元素記号 Br 原子番号三五。原子量七九・九〇。常温では赤褐色の悪臭のある液体。揮発しやすく蒸気は目の粘膜を刺激する。有毒。医薬・写真材料などに用いる。ブロム。
しゅうそ-し【臭素紙】🔗⭐🔉
しゅうそ-し シウ― [3] 【臭素紙】
⇒ブロマイド紙(シ)
しゅう-とつ【臭突】🔗⭐🔉
しゅう-とつ シウ― [0] 【臭突】
臭気を外に拡散させるための煙突状のもの。
しゅう-ふ【臭腐】🔗⭐🔉
しゅう-ふ シウ― [1] 【臭腐】
くさってにおうこと。
しゅう-ポツ【臭―】🔗⭐🔉
しゅう-ポツ シウ― [0] 【臭―】
臭化カリウム。しゅうボツ。
〔「臭剥」とも書く。「剥」はポタシウム(カリウムの英語名)の当て字「剥篤叟母」の略〕
しゅう-み【臭味】🔗⭐🔉
しゅう-み シウ― [1][3] 【臭味】
(1)くさいにおい。くさみ。臭気。
(2)身についたよくない気風・気質。「成上りものに近いある―を/明暗(漱石)」
だい-だい【橙・臭橙】🔗⭐🔉
だい-だい [3] 【橙・臭橙】
ミカン科の常緑小高木。日本への渡来は非常に古い。初夏,葉腋に白色の小花をつけ,球形の液果を結ぶ。果実は冬に黄熟するが,そのまま木に置くと翌春再び緑色を帯びるので「回青橙」の名もある。。冬を経ても実が落ちないため「代代(ダイダイ)」に通じさせ,正月の飾りに用いる。また,健胃薬や料理に用いる。[季]秋。
におい【匂い・臭い】🔗⭐🔉
におい ニホヒ [2] 【匂い・臭い】
〔動詞「匂う」の連用形から〕
(1)物から発散されて,鼻で感じる刺激。かおり・くさみなど。臭気。
〔「かおり」が快い刺激についていうのに対し,「におい」は快・不快両方についていう。不快な場合の漢字表記は多くは「臭い」〕
「花の―をかぐ」「香水の―」「玉ねぎの腐った―」「変な―がする」「薬品の―をかぐ」
(2)そのものがもつ雰囲気やおもむき。それらしい感じ。「パリの―のする雑誌」「生活の―の感じられない女優」「不正の―がする」「悪の―」
(3)日本刀の重要な見所の一。地肌と刃部との境い目にそって霧のように白くほんのりと見える部分。
→沸(ニエ)
(4)色,特に赤い色の映えのある美しさ。色が美しく照り映えること。「紅に染めてし衣雨降りて―はすとも/万葉 3877」
(5)つややかな美しさ。はなやかな美しさ。「この(=若宮)御―には並び給ふべくもあらざりければ/源氏(桐壺)」
(6)威光。栄華。「官位(ツカサクライ),世の中の―も何ともおぼえずなむ/源氏(椎本)」
(7)染め色,襲(カサネ)や縅(オドシ)の色目で,濃い色から次第に薄くなっているもの。「蘇枋(スオウ)の下すだれ,―いと清らにて/枕草子 60」
(8)「匂い縅(オドシ)」の略。「萌黄の―の鎧きて/平家 7」
(9)描(カ)き眉の,薄くぼかしてある部分。
(10)俳諧用語。発句または付句から感じとられる情趣。「今はうつり・響き・―・位を以て付くるを良しとす/去来抄」
→匂付け
にお・う【匂う・臭う】🔗⭐🔉
にお・う ニホフ [2] 【匂う・臭う】
■一■ (動ワ五[ハ四])
□一□
(1)あるにおいがあたりにただよう。それがあるにおいを発散する。
〔「かおる」が快いにおいについていうのに対し,「におう」は快・不快両方についていうが,不快な場合の漢字表記は多くは「臭う」〕
「梅の香が―・う」「肉を焼くにおいが―・ってくる」「くつ下が―・う」「橘の―・へる香かもほととぎす/万葉 3916」
(2)何となく,それらしい雰囲気が感じられる。多く好ましくない場合に用いる。「不正が―・ってくる」
□二□
(1)赤などの色があざやかに照り輝く。「春の園(ソノ)紅(クレナイ)―・ふ桃の花下照る道に出で立つ娘子(オトメ)/万葉 4139」
(2)美しさ・魅力などが,その内部からただよい出る。美しくつややかである。「―・うばかりの美少女」「愛嬌が―・う女性」「紫の―・へる妹(イモ)を/万葉 21」
(3)他のものの色に映り染まる。「手に取れば袖さへ―・ふをみなえし/万葉 2115」
(4)他のものの影響を受けて,はなやかに栄える。恩恵やおかげをこうむる。「人ひとりを思ひかしづき給はむ故(ユエ)は,ほとりまでも―・ふ例(タメシ)こそあれ/源氏(真木柱)」
(5)染色・襲(カサネ)・縅(オドシ)などで,色を次第にぼかしていく。「うへはうすくて,したざまにこく―・ひて/雅亮装束抄」
■二■ (動ハ下二)
美しく色づける。「住吉(スミノエ)の岸野の榛(ハリ)に―・ふれど/万葉 3801」
〔古くは,「に」は「丹」で赤色の意,「ほ」は「秀(ホ)に出ず」などの「秀」でぬきんでる意で用いられた。「におう」は,本来は色彩に関する美しさをいう語。「匂わす」に対する自動詞〕
くさい【臭い】(和英)🔗⭐🔉
くさみ【臭味】(和英)🔗⭐🔉
しゅうか【臭化物】(和英)🔗⭐🔉
しゅうか【臭化物】
《化》a bromide.→英和
しゅうき【臭気】(和英)🔗⭐🔉
しゅうそ【臭素】(和英)🔗⭐🔉
しゅうそ【臭素】
《化》bromine.→英和
臭素カリ potassium bromide.
しゅうみ【臭味】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「臭」で始まるの検索結果。