複数辞典一括検索+![]()
![]()
あ【足】🔗⭐🔉
あ 【足】
あし。「―の音せず行かむ駒もが/万葉 3387」
〔多く「足掻(アガ)き」「足結(アユイ)」など,複合した形で見られる〕
あし【足・脚】🔗⭐🔉
あし [2] 【足・脚】
(1)動物の胴に付属していて,歩行や体を支えるのに用いる部分。特に足首から先の部分をさすこともある。「―を組んで椅子に座る」「―に合わない靴」
〔哺乳動物には「肢」,昆虫には「脚」を多く用い,ヒトの場合は足首からつま先までを「足」,足首から骨盤までを「脚」と書き分けることもある〕
(2)形態が{(1)}のようなもの。(ア)物の下方にあってそれを支えている部分。「机の―」(イ)本体から分かれて出ている部分。「かんざしの―」「旗の―を見て/盛衰記 35」(ウ)漢字の構成部分の名称。「想」「然」などの漢字の下部にある「心」「 」など。脚(キヤク)。
〔多く「脚」と書く〕
(エ)船や櫓(ロ)の水中に入る部分。(オ)〔数〕 垂線が直線または平面と交わる点。「垂線の―」
(3)(ア)歩くこと。行ったり来たりすること。「―を止める」「―を伸ばす」(イ)歩行の速さ・能力。「君の―なら五分で行ける」「―が強い」(ウ)交通の手段。「―の便が悪い」(エ)物事の動きや推移を,動物の足の動きや歩みに見立てていう。「雨―」「日―」
(4)銭。おあし。《足》
〔中国,晋の魚褒の「銭神論」に「翼なくして飛び,足なくして走る」とあることからという〕
(5)(餅などの)ねばり。腰。
(6)「足金物」に同じ。一の足・二の足がある。
」など。脚(キヤク)。
〔多く「脚」と書く〕
(エ)船や櫓(ロ)の水中に入る部分。(オ)〔数〕 垂線が直線または平面と交わる点。「垂線の―」
(3)(ア)歩くこと。行ったり来たりすること。「―を止める」「―を伸ばす」(イ)歩行の速さ・能力。「君の―なら五分で行ける」「―が強い」(ウ)交通の手段。「―の便が悪い」(エ)物事の動きや推移を,動物の足の動きや歩みに見立てていう。「雨―」「日―」
(4)銭。おあし。《足》
〔中国,晋の魚褒の「銭神論」に「翼なくして飛び,足なくして走る」とあることからという〕
(5)(餅などの)ねばり。腰。
(6)「足金物」に同じ。一の足・二の足がある。
 」など。脚(キヤク)。
〔多く「脚」と書く〕
(エ)船や櫓(ロ)の水中に入る部分。(オ)〔数〕 垂線が直線または平面と交わる点。「垂線の―」
(3)(ア)歩くこと。行ったり来たりすること。「―を止める」「―を伸ばす」(イ)歩行の速さ・能力。「君の―なら五分で行ける」「―が強い」(ウ)交通の手段。「―の便が悪い」(エ)物事の動きや推移を,動物の足の動きや歩みに見立てていう。「雨―」「日―」
(4)銭。おあし。《足》
〔中国,晋の魚褒の「銭神論」に「翼なくして飛び,足なくして走る」とあることからという〕
(5)(餅などの)ねばり。腰。
(6)「足金物」に同じ。一の足・二の足がある。
」など。脚(キヤク)。
〔多く「脚」と書く〕
(エ)船や櫓(ロ)の水中に入る部分。(オ)〔数〕 垂線が直線または平面と交わる点。「垂線の―」
(3)(ア)歩くこと。行ったり来たりすること。「―を止める」「―を伸ばす」(イ)歩行の速さ・能力。「君の―なら五分で行ける」「―が強い」(ウ)交通の手段。「―の便が悪い」(エ)物事の動きや推移を,動物の足の動きや歩みに見立てていう。「雨―」「日―」
(4)銭。おあし。《足》
〔中国,晋の魚褒の「銭神論」に「翼なくして飛び,足なくして走る」とあることからという〕
(5)(餅などの)ねばり。腰。
(6)「足金物」に同じ。一の足・二の足がある。
あし=が奪わ れる🔗⭐🔉
れる🔗⭐🔉
――が奪わ れる
交通機関が麻痺(マヒ)状態になり,通勤・通学などができないようになる。
れる
交通機関が麻痺(マヒ)状態になり,通勤・通学などができないようになる。
 れる
交通機関が麻痺(マヒ)状態になり,通勤・通学などができないようになる。
れる
交通機関が麻痺(マヒ)状態になり,通勤・通学などができないようになる。
あし=が重・い🔗⭐🔉
――が重・い
(1)足がだるい。
(2)出かけたりする気がすすまない。
あし=が地に付か ない🔗⭐🔉
ない🔗⭐🔉
――が地に付か ない
(1)うれしくて,興奮して落ち着かないさまをいう。
(2)考えや行動がしっかりしていない。
ない
(1)うれしくて,興奮して落ち着かないさまをいう。
(2)考えや行動がしっかりしていない。
 ない
(1)うれしくて,興奮して落ち着かないさまをいう。
(2)考えや行動がしっかりしていない。
ない
(1)うれしくて,興奮して落ち着かないさまをいう。
(2)考えや行動がしっかりしていない。
あし=が付・く🔗⭐🔉
――が付・く
(1)犯人の身元や逃げた足どりがわかる。また,犯行が露見する。
(2)情夫ができる。ひもが付く。「げい子にや又しても―・く/滑稽本・膝栗毛 8」
あし=が 出る🔗⭐🔉
出る🔗⭐🔉
――が 出る
(1)予算を超えた支出になる。「出張すると,いつも―
出る
(1)予算を超えた支出になる。「出張すると,いつも― 出る」
(2)隠しごとが現れる。足が付く。
出る」
(2)隠しごとが現れる。足が付く。
 出る
(1)予算を超えた支出になる。「出張すると,いつも―
出る
(1)予算を超えた支出になる。「出張すると,いつも― 出る」
(2)隠しごとが現れる。足が付く。
出る」
(2)隠しごとが現れる。足が付く。
あし=が遠の・く🔗⭐🔉
――が遠の・く
訪ねることが間遠になる。
あし=が早・い🔗⭐🔉
――が早・い
(1)歩いたり走ったりするのが速い。
(2)食物が腐りやすい。「ゆで卵は―・い」
(3)売れ行きが早い。
あし=が棒にな・る🔗⭐🔉
――が棒にな・る
長い間歩いたり,立ち続けたりして,足の筋肉がこわばる。非常に足が疲れる。
あし=が乱・れる🔗⭐🔉
――が乱・れる
(1)足並みが乱れる。「反対運動の―・れる」
(2)事故などで交通機関が乱れる。
あし=が向・く🔗⭐🔉
――が向・く
知らず知らずその方へ行く。
あし=に任(マカ)・せる🔗⭐🔉
――に任(マカ)・せる
(1)これというあてもなく,気の向いた方へ歩いて行く。
(2)足の力の続くかぎり歩く。
あし=を洗・う🔗⭐🔉
――を洗・う
悪事やよくない仕事をやめて正業につく。堅気になる。また,単に現在の職業をやめる意でも使う。
あし=を重ねて立ち、目を側(ソバダ)てて視(ミ)る🔗⭐🔉
――を重ねて立ち、目を側(ソバダ)てて視(ミ)る
〔史記(汲黯伝)〕
左右の足をぴったりとつけ,うつむいて横目で見る。非常に恐れているさま,おずおずするさまにいう。
あし=をすく・う🔗⭐🔉
――をすく・う
相手のすきをついて,卑劣なやり方で失敗させる。「部下に―・われた」
あし=を空(ソラ)🔗⭐🔉
――を空(ソラ)
足が地につかないほどあわてふためくさま。「ことごとしくののしりて―にまどふが/徒然 19」
あし=を出・す🔗⭐🔉
――を出・す
(1)予算を超えて支出する。
(2)相場などで損をして,委託保証金・証拠金などを支払いにあてても払いきれなくなる。また,損をする。
あし=を使・う🔗⭐🔉
――を使・う
活発に動き回る。「―・って書いた記事」
あし=を取ら れる🔗⭐🔉
れる🔗⭐🔉
――を取ら れる
(1)足もとをすくわれる。
(2)酒に酔って歩けなくなる。
れる
(1)足もとをすくわれる。
(2)酒に酔って歩けなくなる。
 れる
(1)足もとをすくわれる。
(2)酒に酔って歩けなくなる。
れる
(1)足もとをすくわれる。
(2)酒に酔って歩けなくなる。
あし=を抜・く🔗⭐🔉
――を抜・く
関係を絶つ。仲間からはずれる。
あし=を伸ば・す🔗⭐🔉
――を伸ば・す
(1)楽な姿勢をとってくつろぐ。
(2)ある地点に着いたあと,さらにそこから遠くへ行く。
あし=を運・ぶ🔗⭐🔉
――を運・ぶ
出向いて行く。「陳情のため何度も―・ぶ」
あし=を引っ張・る🔗⭐🔉
――を引っ張・る
仲間の成功・勝利・前進などのじゃまをする。また,結果としてじゃまになる行動をする。
あし=を踏み入・れる🔗⭐🔉
――を踏み入・れる
入り込む。特に,それまで関係のなかった方面に,関係するようになる。足を入れる。
あし=を棒に する🔗⭐🔉
する🔗⭐🔉
――を棒に する
足が疲れて感覚がなくなるほど歩き回る。奔走する。足を擂(ス)り粉木にする。「―
する
足が疲れて感覚がなくなるほど歩き回る。奔走する。足を擂(ス)り粉木にする。「― して探す」
して探す」
 する
足が疲れて感覚がなくなるほど歩き回る。奔走する。足を擂(ス)り粉木にする。「―
する
足が疲れて感覚がなくなるほど歩き回る。奔走する。足を擂(ス)り粉木にする。「― して探す」
して探す」
あし=を向・ける🔗⭐🔉
――を向・ける
(1)ある方向へ向かう。
(2)(「足を向けて寝られない」の形で)人に対する恐れ多い気持ちや感謝の気持ちを表す。
あし-おと【足音】🔗⭐🔉
あし-おと [3][4] 【足音】
(1)歩く時の足の音。「―を忍ばせる」
(2)近づいてくる物事の気配。「春の―」
あし-がかり【足掛(か)り】🔗⭐🔉
あし-がかり [3] 【足掛(か)り】
(1)高い所へ登るときに,足を掛けるところ。足場。
(2)物事をする時の手掛かりとなるもの。糸口。「解決の―を得る」
あし-かけ【足掛(け)】🔗⭐🔉
あし-がた【足形】🔗⭐🔉
あし-がた [0] 【足形】
(1)踏んだあとに残る足の形。あしあと。
(2)(多く「足型」と書く)足袋や靴を作る時に使う,足の形の木型。
あし-かなもの【足金物】🔗⭐🔉
あし-かなもの [3] 【足金物】
太刀の鞘(サヤ)につける帯取りの革緒を通す金具。足金(アシガネ)。足。
あし-がる【足軽】🔗⭐🔉
あし-がる [0] 【足軽】
〔足軽く疾走する者の意〕
戦闘に駆使される歩卒・雑兵をさす。集団戦の普及とともに訓練・組織され,室町時代末には弓足軽・鉄砲足軽などに編成され,足軽大将に率いられた。江戸時代には武士の最下層に位置づけられた。
足軽
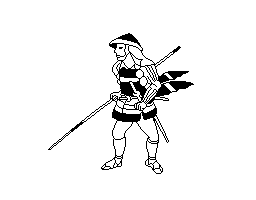 [図]
[図]
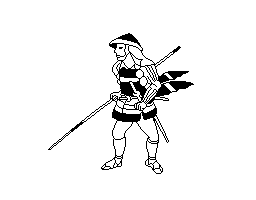 [図]
[図]
あしがる-だいしょう【足軽大将】🔗⭐🔉
あしがる-だいしょう ―シヤウ [5] 【足軽大将】
戦国時代より江戸時代にかけて,足軽の部隊を指揮する者。また,その職。
あし-かわ【足革】🔗⭐🔉
あし-かわ ―カハ 【足革】
「足緒(アシオ){(2)}」に同じ。
あしくぼ-ちゃ【足久保茶・蘆窪茶】🔗⭐🔉
あしくぼ-ちゃ [4] 【足久保茶・蘆窪茶】
静岡市足久保付近から産する茶。近世,幕府に献上された。あしくぼ。
あし-げい【足芸】🔗⭐🔉
あし-げい [0] 【足芸】
仰向けに寝て足だけで種々の技をおこなう曲芸。足先で樽(タル)・盥(タライ)などを回したりする。
あし-たま【足玉】🔗⭐🔉
あし-たま 【足玉】
足の飾りに付ける玉。「―も手玉もゆらに織る服(ハタ)を/万葉 2065」
あし-ちか・い【足近い】🔗⭐🔉
あし-ちか・い [4] 【足近い】 (形)
間をおかずしばしば訪れる。「―・く訪(ト)はるるを心憂く思ふ余に/金色夜叉(紅葉)」
あし-つ-お【足つ緒】🔗⭐🔉
あし-つ-お ―ヲ 【足つ緒】
(1)琴の各弦の端を組糸で結びかがった部分。「東の琴の―に/新撰六帖 5」
(2)太い綱。差し縄{(1)}などにする。「―の綱をひきまはして/雅亮装束抄」
あし-づかい【足遣い】🔗⭐🔉
あし-づかい ―ヅカヒ [3] 【足遣い】
三人遣いの操り人形の両足を操作する役の人。
あし-つぎ【足継ぎ】🔗⭐🔉
あし-つぎ [4][0] 【足継ぎ】
踏み台。ふみつぎ。「椅子とは―の下に箱を置いたゞけのこと/非凡なる凡人(独歩)」
あしひき-の【足引きの】🔗⭐🔉
あしひき-の 【足引きの】 (枕詞)
〔「あしびきの」とも〕
「山」「峰(オ)」などにかかる。語義・かかり方未詳。「―山のしづくに妹待つと/万葉 107」
あし-まめ【足まめ】🔗⭐🔉
あし-まめ [0] 【足まめ】 (名・形動)
面倒がらずに気軽に出歩くさま。また,そのような人。「―に通う」
あし-まわり【足回り】🔗⭐🔉
あし-まわり ―マハリ [3] 【足回り】
(1)足もと。また,足ごしらえ。
(2)自動車などで,車輪とそれを取り付ける部分の全体。「―の良い車」
あし-もと【足下・足元・足許】🔗⭐🔉
あし-もと [3] 【足下・足元・足許】
(1)立ったり歩いたりしている足が地についている所。また,そのあたり。「―が暗い」
(2)足の運び方。歩き方。足どり。「―がふらつく」
(3)身の回り。身辺。また,置かれている状況。「―を脅かす」「―を固める」
(4)(「足元」と書く)家屋の,土台から根太(ネダ)までの部分。
(5)(芝居小屋などで)はきもの。
あしもと=から鳥が立・つ🔗⭐🔉
――から鳥が立・つ
(1)思いがけない事が突然身近に起こるたとえ。
(2)あわただしく行動を起こすたとえ。
あしもと=に付け込・む🔗⭐🔉
――に付け込・む
相手の弱点につけ入る。
あしもと=に火がつ・く🔗⭐🔉
――に火がつ・く
身に危険がせまるたとえ。
あしもと=にも及ば ない🔗⭐🔉
ない🔗⭐🔉
――にも及ば ない
相手の器量や力量が格段にすぐれていて,とてもかなわない。
ない
相手の器量や力量が格段にすぐれていて,とてもかなわない。
 ない
相手の器量や力量が格段にすぐれていて,とてもかなわない。
ない
相手の器量や力量が格段にすぐれていて,とてもかなわない。
あしもと=の明るいうち🔗⭐🔉
――の明るいうち
(1)日の暮れないうち。
(2)自分の状況が悪くならないうち。「―にとっとと帰れ」
あしもと=へも寄りつけ ない🔗⭐🔉
ない🔗⭐🔉
――へも寄りつけ ない
相手が格段にすぐれていてとても及ばない。足元にも及ばない。
ない
相手が格段にすぐれていてとても及ばない。足元にも及ばない。
 ない
相手が格段にすぐれていてとても及ばない。足元にも及ばない。
ない
相手が格段にすぐれていてとても及ばない。足元にも及ばない。
あしもと=を 見る🔗⭐🔉
見る🔗⭐🔉
――を 見る
相手の弱点を見抜く。相手の弱みにつけこむ。足許に付け込む。
見る
相手の弱点を見抜く。相手の弱みにつけこむ。足許に付け込む。
 見る
相手の弱点を見抜く。相手の弱みにつけこむ。足許に付け込む。
見る
相手の弱点を見抜く。相手の弱みにつけこむ。足許に付け込む。
あし-やすめ【足休め】🔗⭐🔉
あし-やすめ [3] 【足休め】 (名)スル
疲れた足を休めること。
あしょろ【足寄】🔗⭐🔉
あしょろ 【足寄】
北海道東部,足寄郡の町。東部には雌阿寒岳・オンネトーなどがあり,阿寒国立公園となる。町では最大の面積。
あし-わざ【足技・足業】🔗⭐🔉
あし-わざ [0] 【足技・足業】
(1)「足芸(アシゲイ)」に同じ。
(2)柔道・相撲で,足を使って相手を倒すわざ。
あ-もと【足元・足下】🔗⭐🔉
あ-もと 【足元・足下】
人の家柄・経歴。身元。氏素性。「―アル者ヂヤ/日葡」
あ-ゆい【足結・脚結】🔗⭐🔉
あ-ゆい ―ユヒ 【足結・脚結】
(1)上代,男子が外出や正装のとき,袴の上から膝下あたりで結ぶ紐(ヒモ)。鈴や玉をつけることもあった。あしゆい。あよい。
⇔手結(タユイ)
「宮人の―の小鈴落ちにきと/古事記(下)」
(2)富士谷成章の用いた文法用語。現在の助詞・助動詞・接尾語などに相当する。
→挿頭抄(カザシシヨウ)
足結(1)
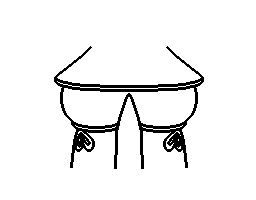 [図]
[図]
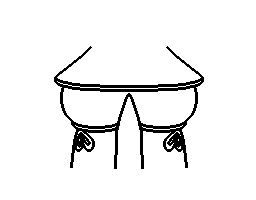 [図]
[図]
あ-ゆ・う【足結ふ】🔗⭐🔉
あ-ゆ・う ―ユフ 【足結ふ】 (動ハ四)
袴の膝下あたりを紐(ヒモ)でくくる。「あゆい」をつける。「―・ひ出でぬれぬこの川の瀬に/万葉 1110」
しゅ-きょう【足恭】🔗⭐🔉
しゅ-きょう [0] 【足恭】
〔「しゅ」は漢音〕
⇒すうきょう(足恭)
すう-きょう【足恭】🔗⭐🔉
すう-きょう [0] 【足恭】
〔論語(公冶長)〕
度が過ぎてうやうやしいこと。おもねり,へつらうこと。すきょう。しゅきょう。
そく【足】🔗⭐🔉
そく 【足】 (接尾)
助数詞。両足につける一対のものを数えるのに用いる。「靴一―」
そくおん-き【足温器】🔗⭐🔉
そくおん-き ソクヲン― [3] 【足温器】
足を温める電熱器具。両足先を入れるスリッパ状のものが多い。
そっ-か【足下】🔗⭐🔉
そっ-か ソク― [1] 【足下】
■一■ (名)
(1)立っている足の下。足もと。「―に踏まえる」
(2)(相手の足もと・おそばの意)手紙の脇付の一。
■二■ (代)
二人称。自分と同等の地位または下位の相手を敬って,あるいはあらたまって呼ぶ語。貴殿。「―の意見を聞きたい」
そっか-てん【足下点】🔗⭐🔉
そっか-てん ソク― [3] 【足下点】
⇒天底(テンテイ)
たし【足し】🔗⭐🔉
たし [0] 【足し】
不足を補うもの。補い。「生活費の―にする」「腹の―にならない」
たし-ざん【足し算】🔗⭐🔉
たし-ざん [2] 【足し算】
二つ以上の数を加えてその合計を出す計算。加え算。寄せ算。加法。加算。
⇔引き算
たし-な・い【足し無い】🔗⭐🔉
たし-な・い [3] 【足し無い】 (形)[文]ク たしな・し
(1)数・量が少ない。乏しい。「―・い船の中の淡水では洗つても
 /或る女(武郎)」
(2)物が乏しく苦しい。困窮している。「徳を布き恵心(ウツクシビ)を施して,困しく―・きを振(スク)ふ/日本書紀(仁徳訓)」
/或る女(武郎)」
(2)物が乏しく苦しい。困窮している。「徳を布き恵心(ウツクシビ)を施して,困しく―・きを振(スク)ふ/日本書紀(仁徳訓)」

 /或る女(武郎)」
(2)物が乏しく苦しい。困窮している。「徳を布き恵心(ウツクシビ)を施して,困しく―・きを振(スク)ふ/日本書紀(仁徳訓)」
/或る女(武郎)」
(2)物が乏しく苦しい。困窮している。「徳を布き恵心(ウツクシビ)を施して,困しく―・きを振(スク)ふ/日本書紀(仁徳訓)」
たし-まえ【足し前】🔗⭐🔉
たし-まえ ―マヘ [0] 【足し前】
不足を補う分。おぎない。
た・す【足す】🔗⭐🔉
た・す [0] 【足す】 (動サ五[四])
(1)すでにあるものの上にさらに加える。足りない分を補う。「少し砂糖を―・す」「一―・す二」
(2)必要なことをやる。用事を済ます。「用を―・す」
[可能] たせる
たら・う【足らふ】🔗⭐🔉
たら・う タラフ 【足らふ】 (動ハ四)
〔動詞「たる」に継続の助動詞「ふ」が付いたものから〕
(1)十分である。すべて備わっている。「―・はぬ事ありとも言ふべきにあらず/落窪 3」
(2)その資格がある。「さてまた,宮仕にも,いとよく―・ひたらむかし/源氏(藤袴)」
たらず【足らず】🔗⭐🔉
たらず 【足らず】 (接尾)
(1)数詞に付いて,その数値に満たないことを表す。「一〇人―しか集まらない」「五分―のスピーチ」
(2)名詞に付いて,十分でないことを表す。「舌―」「月―」
たらわ・す【足らはす】🔗⭐🔉
たらわ・す タラハス 【足らはす】 (動サ四)
満たす。十分にする。「韓国(カラクニ)に行き―・して帰り来む/万葉 4262」
た・りる【足りる】🔗⭐🔉
た・りる [0] 【足りる】 (動ラ上一)
〔四段動詞「足る」の上一段化。近世江戸語以降の語〕
(1)必要なだけの数量が十分ある。十分である。「昼食には千円あれば―・りる」「プリントが三人分―・りない」
(2)それで間にあう。「電話で用が―・りるのに,わざわざ出かけていく」
(3)(「…するにたりる」の形で)…するだけの価値・資格がある。「一読するに―・りる本」「全くとるに―・りない些細(ササイ)なこと」「あんなものは論ずるに―・りない」
足り ない🔗⭐🔉
ない🔗⭐🔉
足り ない
頭の働きがわるい。愚かである。「少し―
ない
頭の働きがわるい。愚かである。「少し― ない男」「頭の―
ない男」「頭の― ないやつ」
ないやつ」
 ない
頭の働きがわるい。愚かである。「少し―
ない
頭の働きがわるい。愚かである。「少し― ない男」「頭の―
ない男」「頭の― ないやつ」
ないやつ」
た・る【足る】🔗⭐🔉
た・る [0] 【足る】 (動ラ五[四])
(1)不足や欠けたところがない状態になる。たりる。「お金が―・らない」「努力が―・らない」「望月の―・れる面わに/万葉 1807」
(2)それにふさわしい資格や価値がある。たりる。「将となすに―・る人物」「論ずるに―・らぬこと」「とるに―・らぬこと」「頼むに―・らぬ」
(3)満足する。「―・ることを知れ」
(4)「たらぬ」の形で,頭の働きが悪いの意を表す。「すこし―・らぬ人を賭にして/浮世草子・一代男 8」
(5)一定の数量に達する。「御年まだ六十にも―・らせ給はねば/大鏡(師輔)」
〔現代語では,慣用的用法のほかは,上一段活用の「足りる」が一般に用いられる〕
たる-ひ【足る日】🔗⭐🔉
たる-ひ 【足る日】
物事の満ち足りるよい日。充実した日。「今日の生日(イクヒ)の―に/祝詞(出雲国造神賀詞)」
たれ-り【足れり】🔗⭐🔉
たれ-り 【足れり】 (連語)
〔四段動詞「足る」の巳然形に助動詞「り」の付いたもの〕
足りている。十分だ。「それで―とする」
たんぬ【足んぬ】🔗⭐🔉
たんぬ 【足んぬ】
〔動詞「たる(足)」の連用形に完了の助動詞「ぬ」の付いた「足りぬ」の転〕
満足すること。十分なこと。「一男両女があるほどに―した者ぞ/蒙求抄 4」
あし【足】(和英)🔗⭐🔉
あし【足】
[脚]a leg(脚);→英和
a foot(足);→英和
a paw(犬・猫などの).→英和
〜が達者である be a good walker.〜がつく be traced.〜が出る be short of money.〜が遠くなる fall away.〜が早い(遅い) be swift(slow) of foot.〜が痛い have a sore foot.〜の浅い(深い)船 a ship of light(deep) draft.〜の裏 the sole of a foot.〜の長い long-legged.〜を洗う wash one's hands of.〜を奪われる be deprived of the means of transport(ation).〜をさらわれる be carried off one's feet.〜を揃える keep pace.〜を止める stop.→英和
〜を早める quicken one's pace.〜を引っぱる drag a person down.〜を踏みはずす miss one's footing.
あしおと【足音】(和英)🔗⭐🔉
あしおと【足音】
(the sound of) footsteps;a footfall.→英和
〜をたてる(ない) walk noisily(quietly).
あしがかり【足掛り】(和英)🔗⭐🔉
あしがかり【足掛り】
a foothold[footing].→英和
あしつき【(ふらつく)足つき】(和英)🔗⭐🔉
あしつき【(ふらつく)足つき】
one's (unsteady) gait.
あしもと【足許に[の]】(和英)🔗⭐🔉
あしもと【足許に[の]】
at one's feet.〜が危い have an unsteady gait.〜に気をつける watch one's step.〜の明るいうちに before it gets dark;before it is too late.〜につけこむ take mean advantage of.〜にも及ばない cannot compare with a person.→英和
あしわざ【足技】(和英)🔗⭐🔉
あしわざ【足技】
footwork.→英和
すべらす【足を滑らす】(和英)🔗⭐🔉
すべらす【足を滑らす】
miss one's footing.口を〜 make a slip of the tongue.→英和
そくおんき【足温器】(和英)🔗⭐🔉
そくおんき【足温器】
a foot-warmer.
たしざん【足し算】(和英)🔗⭐🔉
たしざん【足し算】
addition.→英和
たす【足す】(和英)🔗⭐🔉
たりる【足りる】(和英)🔗⭐🔉
たりる【足りる】
⇒足(た)る.
たる【足る】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「−足」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む