複数辞典一括検索+![]()
![]()
ま‐ぎ【間木】🔗⭐🔉
ま‐ぎ【間木】
《「まき」とも》長押(なげし)の上などに設けた棚のようなもの。「数珠(ずず)も―に打ち上げなど、らうがはしきに」〈かげろふ・中〉
まき‐あし【巻(き)足】🔗⭐🔉
まき‐あし【巻(き)足】
 紀州流の水泳術で、立ち泳ぎの足の使い方。下肢を、膝を中心にして交互に外から内へ回して浮力をつけるやり方。
紀州流の水泳術で、立ち泳ぎの足の使い方。下肢を、膝を中心にして交互に外から内へ回して浮力をつけるやり方。 文楽人形の型で、左右の足を交互に外から回してゆったりと足を運ぶ歩き方。
文楽人形の型で、左右の足を交互に外から回してゆったりと足を運ぶ歩き方。
 紀州流の水泳術で、立ち泳ぎの足の使い方。下肢を、膝を中心にして交互に外から内へ回して浮力をつけるやり方。
紀州流の水泳術で、立ち泳ぎの足の使い方。下肢を、膝を中心にして交互に外から内へ回して浮力をつけるやり方。 文楽人形の型で、左右の足を交互に外から回してゆったりと足を運ぶ歩き方。
文楽人形の型で、左右の足を交互に外から回してゆったりと足を運ぶ歩き方。
まき‐あみ【巻(き)網・△旋網】🔗⭐🔉
まき‐あみ【巻(き)網・△旋網】

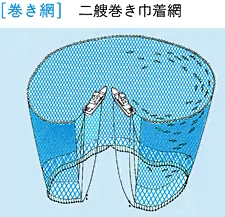 魚群を網で取り巻き、その囲みを狭め網裾を締めて捕る漁法。また、その網。巾着網など。操作する船の数により、二艘巻(にそうま)き・一艘巻きがある。
魚群を網で取り巻き、その囲みを狭め網裾を締めて捕る漁法。また、その網。巾着網など。操作する船の数により、二艘巻(にそうま)き・一艘巻きがある。

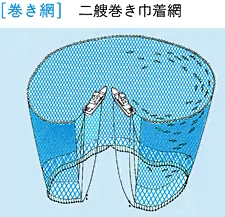 魚群を網で取り巻き、その囲みを狭め網裾を締めて捕る漁法。また、その網。巾着網など。操作する船の数により、二艘巻(にそうま)き・一艘巻きがある。
魚群を網で取り巻き、その囲みを狭め網裾を締めて捕る漁法。また、その網。巾着網など。操作する船の数により、二艘巻(にそうま)き・一艘巻きがある。
まき‐ありつね【槙有恒】🔗⭐🔉
まき‐ありつね【槙有恒】
[一八九四〜一九八九]登山家。宮城の生まれ。大正一〇年(一九二一)アイガー東山稜初登攀に成功、昭和三一年(一九五六)には隊長としてマナスル初登頂に成功した。著「山行」「マナスル登頂記」など。
まき‐いし【×蒔石】🔗⭐🔉
まき‐いし【×蒔石】
茶室の庭などに、まき散らしたように所々に置く石。
まき‐い・る【巻き入る・×捲き入る】🔗⭐🔉
まき‐い・る【巻き入る・×捲き入る】
[動ラ下二]巻いて中に入れる。巻き込む。「汝が船を海底に―・れんと思ふ」〈今昔・四・一三〉
まき‐えい【巻×纓】🔗⭐🔉
まき‐えい【巻×纓】
 けんえい(巻纓)
けんえい(巻纓)
 けんえい(巻纓)
けんえい(巻纓)
まきえ‐ふん【×蒔絵粉】まきヱ‐🔗⭐🔉
まきえ‐ふん【×蒔絵粉】まきヱ‐
蒔絵に用いる金・銀・銅・錫(すず)などの粉。平目粉・梨子地粉・平粉・丸粉・鑢(やすり)粉など。
まき‐おこ・す【巻(き)起(こ)す・×捲き起(こ)す】🔗⭐🔉
まき‐おこ・す【巻(き)起(こ)す・×捲き起(こ)す】
[動サ五(四)] 風などが巻くように吹き上げる。「砂ぼこりを―・す」
風などが巻くように吹き上げる。「砂ぼこりを―・す」 思いがけないことをひきおこす。「センセーションを―・す」
思いがけないことをひきおこす。「センセーションを―・す」
 風などが巻くように吹き上げる。「砂ぼこりを―・す」
風などが巻くように吹き上げる。「砂ぼこりを―・す」 思いがけないことをひきおこす。「センセーションを―・す」
思いがけないことをひきおこす。「センセーションを―・す」
まき‐おこ・る【巻(き)起(こ)る・×捲き起(こ)る】🔗⭐🔉
まき‐おこ・る【巻(き)起(こ)る・×捲き起(こ)る】
[動ラ五(四)] うずを巻くようにして立ちのぼる。「黒雲が―・る」
うずを巻くようにして立ちのぼる。「黒雲が―・る」 多くのものが一時に激しく盛んになる。わきおこる。「拍手が―・る」
多くのものが一時に激しく盛んになる。わきおこる。「拍手が―・る」
 うずを巻くようにして立ちのぼる。「黒雲が―・る」
うずを巻くようにして立ちのぼる。「黒雲が―・る」 多くのものが一時に激しく盛んになる。わきおこる。「拍手が―・る」
多くのものが一時に激しく盛んになる。わきおこる。「拍手が―・る」
まき‐おとし【巻(き)落(と)し】🔗⭐🔉
まき‐おとし【巻(き)落(と)し】
相撲のきまり手の一。まわしをとらず、差し手で相手のからだを抱きかかえ、巻きこむようにしてひねり倒す技。
まき‐かえ【巻(き)替え】‐かへ🔗⭐🔉
まき‐かえ【巻(き)替え】‐かへ
相撲で、相手の差し手の中に手を入れ、自分の有利な体勢にすること。
まき‐かえし【巻(き)返し・×捲き返し】‐かへし🔗⭐🔉
まき‐かえし【巻(き)返し・×捲き返し】‐かへし
 劣勢から、態勢を立て直して反撃すること。「―をはかる」「―に出る」
劣勢から、態勢を立て直して反撃すること。「―をはかる」「―に出る」 小枠などに巻いてある糸を、さらに他の小枠に巻きとってその張りの力を一定させること。
小枠などに巻いてある糸を、さらに他の小枠に巻きとってその張りの力を一定させること。 巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移すこと。また、折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。
巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移すこと。また、折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。
 劣勢から、態勢を立て直して反撃すること。「―をはかる」「―に出る」
劣勢から、態勢を立て直して反撃すること。「―をはかる」「―に出る」 小枠などに巻いてある糸を、さらに他の小枠に巻きとってその張りの力を一定させること。
小枠などに巻いてある糸を、さらに他の小枠に巻きとってその張りの力を一定させること。 巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移すこと。また、折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。
巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移すこと。また、折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。
まき‐かえ・す【巻(き)返す・×捲き返す】‐かへす🔗⭐🔉
まき‐かえ・す【巻(き)返す・×捲き返す】‐かへす
[動サ五(四)] 巻いて、もとの状態へ戻す。「巻き尺を―・す」
巻いて、もとの状態へ戻す。「巻き尺を―・す」 劣勢から、勢いを取り戻して反撃する。「土壇場で―・す」
劣勢から、勢いを取り戻して反撃する。「土壇場で―・す」
 巻いて、もとの状態へ戻す。「巻き尺を―・す」
巻いて、もとの状態へ戻す。「巻き尺を―・す」 劣勢から、勢いを取り戻して反撃する。「土壇場で―・す」
劣勢から、勢いを取り戻して反撃する。「土壇場で―・す」
まき‐こ・む【巻(き)込む・×捲き込む】🔗⭐🔉
まき‐こ・む【巻(き)込む・×捲き込む】
[動マ五(四)] 巻いて中へ入れる。「機械に―・まれる」
巻いて中へ入れる。「機械に―・まれる」 ある人間関係や事態に引き入れる。巻き添えにする。「無関係な他人を―・む」「内紛に―・まれる」
ある人間関係や事態に引き入れる。巻き添えにする。「無関係な他人を―・む」「内紛に―・まれる」
 巻いて中へ入れる。「機械に―・まれる」
巻いて中へ入れる。「機械に―・まれる」 ある人間関係や事態に引き入れる。巻き添えにする。「無関係な他人を―・む」「内紛に―・まれる」
ある人間関係や事態に引き入れる。巻き添えにする。「無関係な他人を―・む」「内紛に―・まれる」
まき‐さく【真木割く・真木△栄く】🔗⭐🔉
まき‐さく【真木割く・真木△栄く】
〔枕〕木をさいた割れ目を「ひ」というところから、「檜(ひ)」にかかる。「―檜の御門(みかど)」〈記・下・歌謡〉
マキシマム【maximum】🔗⭐🔉
マキシマム【maximum】
 最大。最大限。極限。「計測値はその―に達した」
最大。最大限。極限。「計測値はその―に達した」 ミニマム。
ミニマム。 数学で、極大。極大値。
数学で、極大。極大値。 ミニマム。
ミニマム。
 最大。最大限。極限。「計測値はその―に達した」
最大。最大限。極限。「計測値はその―に達した」 ミニマム。
ミニマム。 数学で、極大。極大値。
数学で、極大。極大値。 ミニマム。
ミニマム。
マキシム【maxim】🔗⭐🔉
マキシム【maxim】
格言。金言。箴言(しんげん)。
ま‐きた【真北】🔗⭐🔉
ま‐きた【真北】
正しく北にあたる方角。正北。
まき‐ちら・す【×撒き散らす】🔗⭐🔉
まき‐ちら・す【×撒き散らす】
[動サ五(四)]あたり一面に広がるようにまく。また、あちらこちらに広める。「悪臭を―・す」「うわさを―・す」
まき‐つ・く【巻(き)付く】🔗⭐🔉
まき‐つ・く【巻(き)付く】
 [動カ五(四)]他の物のまわりに絡んでつく。ぐるぐる巻いてつく。「ヘチマのつるが支柱に―・く」「綱がスクリューに―・く」
[動カ五(四)]他の物のまわりに絡んでつく。ぐるぐる巻いてつく。「ヘチマのつるが支柱に―・く」「綱がスクリューに―・く」 [動カ下二]「まきつける」の文語形。
[動カ下二]「まきつける」の文語形。
 [動カ五(四)]他の物のまわりに絡んでつく。ぐるぐる巻いてつく。「ヘチマのつるが支柱に―・く」「綱がスクリューに―・く」
[動カ五(四)]他の物のまわりに絡んでつく。ぐるぐる巻いてつく。「ヘチマのつるが支柱に―・く」「綱がスクリューに―・く」 [動カ下二]「まきつける」の文語形。
[動カ下二]「まきつける」の文語形。
まき‐つけ【×蒔き付け】🔗⭐🔉
まき‐つけ【×蒔き付け】
作物の種をまくこと。
まき‐と【巻斗】🔗⭐🔉
まき‐と【巻斗】
肘木(ひじき)の上に用いる小さい斗(ます)。上の肘木や桁(けた)などを一方向のみ支えるもの。
まき‐とり【巻(き)取り】🔗⭐🔉
まき‐とり【巻(き)取り】
 巻き取ること。
巻き取ること。 「巻き取り紙」の略。
「巻き取り紙」の略。
 巻き取ること。
巻き取ること。 「巻き取り紙」の略。
「巻き取り紙」の略。
まき‐と・る【巻(き)取る】🔗⭐🔉
まき‐と・る【巻(き)取る】
[動ラ五(四)]巻いて別のものに移し取る。「たこ糸を木片へ―・る」
まき‐なおし【×蒔き直し】‐なほし🔗⭐🔉
まき‐なおし【×蒔き直し】‐なほし
 種をもう一度まくこと。
種をもう一度まくこと。 物事を初めからやり直すこと。「新規―」
物事を初めからやり直すこと。「新規―」
 種をもう一度まくこと。
種をもう一度まくこと。 物事を初めからやり直すこと。「新規―」
物事を初めからやり直すこと。「新規―」
まき・ぬ【×纏き△寝・×枕き△寝】🔗⭐🔉
まき・ぬ【×纏き△寝・×枕き△寝】
[動ナ下二]互いに手を枕にして寝る。共寝する。「現(うつつ)には更にもえ言はず夢にだに妹がたもとを―・ぬとし見ば」〈万・七八四〉
まきの【牧野】🔗⭐🔉
まきの【牧野】
姓氏の一。
まきの‐えいいち【牧野英一】🔗⭐🔉
まきの‐えいいち【牧野英一】
[一八七八〜一九七〇]刑法学者。岐阜の生まれ。主観主義的な刑法理論を展開、応報刑主義を批判して教育刑主義を唱えた。文化勲章受章。著「日本刑法」「刑法研究」など。
まきのお【槙尾】まきのを🔗⭐🔉
まきのお【槙尾】まきのを
京都市右京区北部の地名。清滝川に沿う紅葉の名所で、高尾(高雄)・栂尾(とがのお)とともに三尾(さんび)とよばれる。西明寺がある。
まきの‐しんいち【牧野信一】🔗⭐🔉
まきの‐しんいち【牧野信一】
[一八九六〜一九三六]小説家。神奈川の生まれ。私小説「父を売る子」で登場。のち、幻想的作風に転じた。他に「ゼーロン」「鬼涙村(きなだむら)」など。
まきの‐とみたろう【牧野富太郎】‐とみタラウ🔗⭐🔉
まきの‐とみたろう【牧野富太郎】‐とみタラウ
[一八六二〜一九五七]植物分類学者。高知の生まれ。小学校中退、独学で植物学を研究。日本各地の植物を採集して歩き、多数の新種を発見・命名。すぐれた植物図を描き、植物採集会を指導するなど知識の普及にも尽力した。文化勲章受章。著「日本植物志図篇」「日本植物図鑑」など。
まき‐の‐はら【牧 原】🔗⭐🔉
原】🔗⭐🔉
まき‐の‐はら【牧 原】
静岡県中南部、大井川下流西岸の台地。明治初期の士族の入植以来、茶の産地。
原】
静岡県中南部、大井川下流西岸の台地。明治初期の士族の入植以来、茶の産地。
 原】
静岡県中南部、大井川下流西岸の台地。明治初期の士族の入植以来、茶の産地。
原】
静岡県中南部、大井川下流西岸の台地。明治初期の士族の入植以来、茶の産地。
まき‐ふう【巻(き)封】🔗⭐🔉
まき‐ふう【巻(き)封】
上包みを用いずに、書状の紙を巻いて紙の端を裏へ折り返し、のりで封じたもの。
まき‐ほん【巻(き)本】🔗⭐🔉
まき‐ほん【巻(き)本】
巻き物にした本。巻子本(かんすぼん)。
まきむく‐やま【巻向山・纏向山】🔗⭐🔉
まきむく‐やま【巻向山・纏向山】
奈良県桜井市にある山。標高五六五メートル。南東に長谷寺(はせでら)がある。
まき‐め【巻き目】🔗⭐🔉
まき‐め【巻き目】
紙などを巻いて、巻きおえた端。また、巻いた箇所。「いとほそく巻きて結びたる、―はこまごまとくぼみたるに」〈枕・二九四〉
まき‐も・つ【巻き持つ・×纏き持つ】🔗⭐🔉
まき‐も・つ【巻き持つ・×纏き持つ】
[動タ四]手に巻きつけて持つ。「我(あ)が恋ふる君玉ならば手に―・ちて」〈万・一五〇〉
まき‐もの【巻(き)物】🔗⭐🔉
まき‐もめん【巻(き)木綿】🔗⭐🔉
まき‐もめん【巻(き)木綿】
傷口などに巻きつける木綿。包帯にする木綿。
ま‐ぎょう【ま行・マ行】‐ギヤウ🔗⭐🔉
ま‐ぎょう【ま行・マ行】‐ギヤウ
五十音図の第七行。ま・み・む・め・も。
まぎら【紛ら】🔗⭐🔉
まぎら【紛ら】
まぎらわすこと。ごまかし。「えてあんな事で―を食はされるものぢゃ」〈伎・桑名屋徳蔵〉
まぎら‐かし【紛らかし】🔗⭐🔉
まぎら‐かし【紛らかし】
九州地方で、嫁入りの際に嫁につき添っていく未婚の女性をいう。花嫁と同じ礼装で宴席に並ぶ。嫁紛らかし。添い嫁。
まぎら‐か・す【紛らかす】🔗⭐🔉
まぎら‐か・す【紛らかす】
[動サ五(四)]「紛らす」に同じ。「寂しさを―・す」
まぎら・す【紛らす】🔗⭐🔉
まぎら・す【紛らす】
[動サ五(四)]関心を他に移すなどして、そのことがわからなくなるようにする。ごまかす。また、気持ちを他に向けてふさいだ気分などを晴らす。まぎらわす。「姿を人込みに―・す」「気を―・す」「退屈を―・す」
[可能]まぎらせる
まぎら・せる【紛らせる】🔗⭐🔉
まぎら・せる【紛らせる】
[動サ下一]「紛らす」に同じ。「恋の悩みをスポーツで―・せる」
まぎらわし【紛らはし】まぎらはし🔗⭐🔉
まぎらわし【紛らはし】まぎらはし
まぎれるようにすること。関心などを他に移すようにすること。「御心の―には、さしも驚かせ給ふばかり聞こえなれはべらば」〈源・橋姫〉
まぎらわし・い【紛らわしい】まぎらはしい🔗⭐🔉
まぎらわし・い【紛らわしい】まぎらはしい
[形] まぎらは・し[シク]《古くは「まきらはし」》
まぎらは・し[シク]《古くは「まきらはし」》 似ていて区別がつきにくい。「本物と―・いレプリカ」「―・い名前」
似ていて区別がつきにくい。「本物と―・いレプリカ」「―・い名前」 まぶしい。まばゆい。「上野(かみつけの)まぐはしまとに朝日さし―・しもなありつつ見れば」〈万・三四〇七〉
まぶしい。まばゆい。「上野(かみつけの)まぐはしまとに朝日さし―・しもなありつつ見れば」〈万・三四〇七〉 気持ちがまぎれるようである。「おのづからうちたゆみ、―・しくてなむ、過ぐし来るを」〈源・橋姫〉
気持ちがまぎれるようである。「おのづからうちたゆみ、―・しくてなむ、過ぐし来るを」〈源・橋姫〉 めまぐるしく多忙である。「わが身も―・しき事あれば、えこそ助け奉るまじけれ」〈仮・伊曾保・下〉
[派生]まぎらわしげ[形動]まぎらわしさ[名]
めまぐるしく多忙である。「わが身も―・しき事あれば、えこそ助け奉るまじけれ」〈仮・伊曾保・下〉
[派生]まぎらわしげ[形動]まぎらわしさ[名]
 まぎらは・し[シク]《古くは「まきらはし」》
まぎらは・し[シク]《古くは「まきらはし」》 似ていて区別がつきにくい。「本物と―・いレプリカ」「―・い名前」
似ていて区別がつきにくい。「本物と―・いレプリカ」「―・い名前」 まぶしい。まばゆい。「上野(かみつけの)まぐはしまとに朝日さし―・しもなありつつ見れば」〈万・三四〇七〉
まぶしい。まばゆい。「上野(かみつけの)まぐはしまとに朝日さし―・しもなありつつ見れば」〈万・三四〇七〉 気持ちがまぎれるようである。「おのづからうちたゆみ、―・しくてなむ、過ぐし来るを」〈源・橋姫〉
気持ちがまぎれるようである。「おのづからうちたゆみ、―・しくてなむ、過ぐし来るを」〈源・橋姫〉 めまぐるしく多忙である。「わが身も―・しき事あれば、えこそ助け奉るまじけれ」〈仮・伊曾保・下〉
[派生]まぎらわしげ[形動]まぎらわしさ[名]
めまぐるしく多忙である。「わが身も―・しき事あれば、えこそ助け奉るまじけれ」〈仮・伊曾保・下〉
[派生]まぎらわしげ[形動]まぎらわしさ[名]
まぎらわ・す【紛らわす】まぎらはす🔗⭐🔉
まぎらわ・す【紛らわす】まぎらはす
[動サ五(四)]「紛らす」に同じ。「水で空腹を―・す」
ま‐ぎり【間切り】🔗⭐🔉
ま‐ぎり【間切り】
 区切ること。区切り。
区切ること。区切り。 もと、琉球の行政区画。数村からなり、琉球処分以後も存続したが、明治四〇年(一九〇七)廃止。
もと、琉球の行政区画。数村からなり、琉球処分以後も存続したが、明治四〇年(一九〇七)廃止。
 区切ること。区切り。
区切ること。区切り。 もと、琉球の行政区画。数村からなり、琉球処分以後も存続したが、明治四〇年(一九〇七)廃止。
もと、琉球の行政区画。数村からなり、琉球処分以後も存続したが、明治四〇年(一九〇七)廃止。
まぎり‐ばしり【間切り走り】🔗⭐🔉
まぎり‐ばしり【間切り走り】
向かい風のときの帆船の走り方。斜め前方から風を受けるように、左右に交互に帆面を向けながらジグザグに前進する。
ま‐ぎ・る【間切る】🔗⭐🔉
ま‐ぎ・る【間切る】
[動ラ五(四)]波間を切って船を進める。また、間切り走りで帆船を進める。「帆ヲ―・ッテ走ル」〈和英語林集成〉
まぎ・る【紛る】🔗⭐🔉
まぎ・る【紛る】
[動ラ下二]「まぎれる」の文語形。
まぎれ【紛れ】🔗⭐🔉
まぎれ【紛れ】
 ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。「怒った―に外の芸者を買いはしまいか」〈荷風・腕くらべ〉
ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。「怒った―に外の芸者を買いはしまいか」〈荷風・腕くらべ〉 他に入りまじって区別がつかなくなること。「山かぜに桜ふきまき乱れなむ花の―に立ちとまるべく」〈古今・離別〉
他に入りまじって区別がつかなくなること。「山かぜに桜ふきまき乱れなむ花の―に立ちとまるべく」〈古今・離別〉 他の事に心を奪われること。「今年は―多くて過ぐし給ふ」〈源・若菜下〉
他の事に心を奪われること。「今年は―多くて過ぐし給ふ」〈源・若菜下〉 心情を表す形容詞の語幹、動詞の連用形に付いて、その心情に駆られて分別を失うさまを表す。「に」を伴って副詞的に用いることが多い。…のあまり。「苦し―にうそをつく」「腹立ち―」
心情を表す形容詞の語幹、動詞の連用形に付いて、その心情に駆られて分別を失うさまを表す。「に」を伴って副詞的に用いることが多い。…のあまり。「苦し―にうそをつく」「腹立ち―」
 ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。「怒った―に外の芸者を買いはしまいか」〈荷風・腕くらべ〉
ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。「怒った―に外の芸者を買いはしまいか」〈荷風・腕くらべ〉 他に入りまじって区別がつかなくなること。「山かぜに桜ふきまき乱れなむ花の―に立ちとまるべく」〈古今・離別〉
他に入りまじって区別がつかなくなること。「山かぜに桜ふきまき乱れなむ花の―に立ちとまるべく」〈古今・離別〉 他の事に心を奪われること。「今年は―多くて過ぐし給ふ」〈源・若菜下〉
他の事に心を奪われること。「今年は―多くて過ぐし給ふ」〈源・若菜下〉 心情を表す形容詞の語幹、動詞の連用形に付いて、その心情に駆られて分別を失うさまを表す。「に」を伴って副詞的に用いることが多い。…のあまり。「苦し―にうそをつく」「腹立ち―」
心情を表す形容詞の語幹、動詞の連用形に付いて、その心情に駆られて分別を失うさまを表す。「に」を伴って副詞的に用いることが多い。…のあまり。「苦し―にうそをつく」「腹立ち―」
まぎれ‐あり・く【紛れ△歩く】🔗⭐🔉
まぎれ‐あり・く【紛れ△歩く】
[動カ四] しのび歩く。「心もや慰むと立ち出でて―・き給ふ」〈源・少女〉
しのび歩く。「心もや慰むと立ち出でて―・き給ふ」〈源・少女〉 人々の間にまじって歩きまわる。「小姫君は…、こなたかなた―・かせ給ふ」〈栄花・初花〉
人々の間にまじって歩きまわる。「小姫君は…、こなたかなた―・かせ給ふ」〈栄花・初花〉
 しのび歩く。「心もや慰むと立ち出でて―・き給ふ」〈源・少女〉
しのび歩く。「心もや慰むと立ち出でて―・き給ふ」〈源・少女〉 人々の間にまじって歩きまわる。「小姫君は…、こなたかなた―・かせ給ふ」〈栄花・初花〉
人々の間にまじって歩きまわる。「小姫君は…、こなたかなた―・かせ給ふ」〈栄花・初花〉
まぎれ‐こ・む【紛れ込む】🔗⭐🔉
まぎれ‐こ・む【紛れ込む】
[動マ五(四)] まちがって入り込む。「よその郵便物が―・む」
まちがって入り込む。「よその郵便物が―・む」 いつのまにか他の物の中に入り込む。混雑をうまく利用して入り込む。「雑踏の中に―・んで姿を消す」
いつのまにか他の物の中に入り込む。混雑をうまく利用して入り込む。「雑踏の中に―・んで姿を消す」
 まちがって入り込む。「よその郵便物が―・む」
まちがって入り込む。「よその郵便物が―・む」 いつのまにか他の物の中に入り込む。混雑をうまく利用して入り込む。「雑踏の中に―・んで姿を消す」
いつのまにか他の物の中に入り込む。混雑をうまく利用して入り込む。「雑踏の中に―・んで姿を消す」
まぎれ‐どころ【紛れ所】🔗⭐🔉
まぎれ‐どころ【紛れ所】
見分けにくいところ。「あさましきまで―なき御顔つきを」〈源・紅葉賀〉
まぎ・れる【紛れる】🔗⭐🔉
まぎ・れる【紛れる】
[動ラ下一] まぎ・る[ラ下二]
まぎ・る[ラ下二] 入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。「人込みに―・れて見失う」「勝負の行方が―・れてくる」
入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。「人込みに―・れて見失う」「勝負の行方が―・れてくる」 似通っていて見分けがつかなくなる。「―・れやすい色」
似通っていて見分けがつかなくなる。「―・れやすい色」 他と見分けのつかない状況などをうまく利用する。混乱などに乗じる。「騒ぎに―・れて盗みを働く」「夜陰に―・れて逃げる」
他と見分けのつかない状況などをうまく利用する。混乱などに乗じる。「騒ぎに―・れて盗みを働く」「夜陰に―・れて逃げる」 他に心が奪われて、本来行うべきことがおろそかになる。「多忙に―・れて返事が遅れる」
他に心が奪われて、本来行うべきことがおろそかになる。「多忙に―・れて返事が遅れる」 他に心が移って、悲しみなどを忘れる。「気が―・れる」
他に心が移って、悲しみなどを忘れる。「気が―・れる」 他に差し障りがある。「舞も見たけれども、けふは―・るる事いできたり」〈平家・一〉
他に差し障りがある。「舞も見たけれども、けふは―・るる事いできたり」〈平家・一〉
 まぎ・る[ラ下二]
まぎ・る[ラ下二] 入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。「人込みに―・れて見失う」「勝負の行方が―・れてくる」
入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。「人込みに―・れて見失う」「勝負の行方が―・れてくる」 似通っていて見分けがつかなくなる。「―・れやすい色」
似通っていて見分けがつかなくなる。「―・れやすい色」 他と見分けのつかない状況などをうまく利用する。混乱などに乗じる。「騒ぎに―・れて盗みを働く」「夜陰に―・れて逃げる」
他と見分けのつかない状況などをうまく利用する。混乱などに乗じる。「騒ぎに―・れて盗みを働く」「夜陰に―・れて逃げる」 他に心が奪われて、本来行うべきことがおろそかになる。「多忙に―・れて返事が遅れる」
他に心が奪われて、本来行うべきことがおろそかになる。「多忙に―・れて返事が遅れる」 他に心が移って、悲しみなどを忘れる。「気が―・れる」
他に心が移って、悲しみなどを忘れる。「気が―・れる」 他に差し障りがある。「舞も見たけれども、けふは―・るる事いできたり」〈平家・一〉
他に差し障りがある。「舞も見たけれども、けふは―・るる事いできたり」〈平家・一〉
ま‐ぎわ【真際・間際】‐ぎは🔗⭐🔉
ま‐ぎわ【真際・間際】‐ぎは
 物事がまさに行われようとするとき。寸前。「出発―に電話がくる」
物事がまさに行われようとするとき。寸前。「出発―に電話がくる」 境界に接する直前の部分。「がけの―まで家が建つ」
境界に接する直前の部分。「がけの―まで家が建つ」
 物事がまさに行われようとするとき。寸前。「出発―に電話がくる」
物事がまさに行われようとするとき。寸前。「出発―に電話がくる」 境界に接する直前の部分。「がけの―まで家が建つ」
境界に接する直前の部分。「がけの―まで家が建つ」
まき‐わら【巻き×藁】🔗⭐🔉
まき‐わら【巻き×藁】
稲のわらを巻いて束ねたもの。弓術練習の的、また空手道で突きの稽古など、武術練習の道具に用いられる。
まき‐わり【△薪割(り)】🔗⭐🔉
まき‐わり【△薪割(り)】
薪を燃やしやすい大きさに割ること。また、それに用いる刃物。
紛🔗⭐🔉
紛
[音]フン
[訓]まぎ‐れる
まぎ‐らわす
まぎ‐らす
まぎ‐らわしい
[部首]糸
[総画数]10
[コード]区点 4222
JIS 4A36
S‐JIS 95B4
[分類]常用漢字
[難読語]
→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】
大辞泉に「まぎ」で始まるの検索結果 1-62。