複数辞典一括検索+![]()
![]()
そく【束】🔗⭐🔉
そく【束】
①つかねたものを数える語。稲10把・半紙10帖など、10個を一組としたものを1束という。たば。また、釣りで魚100尾、蟇目ひきめの矢20本にもいう。今昔物語集26「或いは二、三―刈りてとらす」
②矢の長さの単位。親指以外の指4本の幅。平家物語5「わづかに十三―こそ仕り候へ」
③(江戸時代の隠語)一、十、百などを示すのに用いた。浮世床初「夕ベも三百さんぞくばかりへいりやした」
そく‐がり【束刈】🔗⭐🔉
そく‐がり【束刈】
田地の面積を、刈り取った稲の束数によって計ること。
そく‐しゅ【束手】🔗⭐🔉
そく‐しゅ【束手】
手をつかねること。手出しをせずに傍観すること。
そく‐しゅう【束脩】‥シウ🔗⭐🔉
そく‐しゅう【束脩】‥シウ
[論語述而](「束ねた乾肉」の意。中国の古代、初めて入門する時、手軽な贈物として持参した)師のもとに入門する時に贈呈する礼物。転じて、入学の時に納める金銭。
そく‐せい【束生】🔗⭐🔉
そく‐せい【束生】
茎・枝・葉や花などが集まって、互いに近接して多数生じること。同一の節に生じる輪生とは異なる。叢生。簇生そうせい。
そく‐たい【束帯】🔗⭐🔉
そく‐たい【束帯】
[論語公冶長「赤や、束帯にして朝に立つ」]
①礼服を着、大帯をつけること。
②平安時代以降の朝服の名。天皇以下文武百官が朝廷の公事に着用する正服。衣冠・直衣を宿直とのい装束というのに対して、昼ひの装束という。冠・袍ほう(縫腋・闕腋けってき)・半臂はんぴ・忘緒わすれお・下襲したがさね・衵あこめ(または引倍木ひへぎ)・単ひとえ・表袴うえのはかま・大口・石帯せきたい・魚袋ぎょたい・襪しとうず・靴かのくつ(または浅沓・深沓・半靴ほうか)・笏しゃく・帖紙たとうがみ・桧扇ひおうぎなどを具備し、武官および勅許を得た文官は別に平緒によって太刀を佩く。物具もののぐ。
束帯
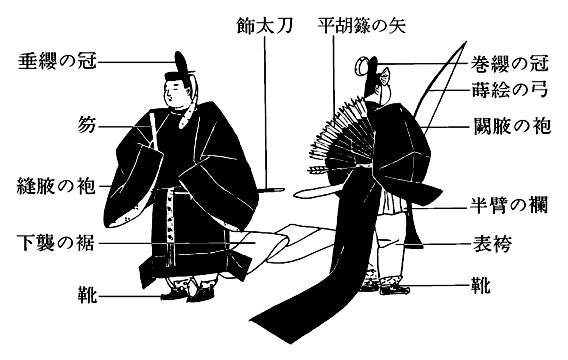
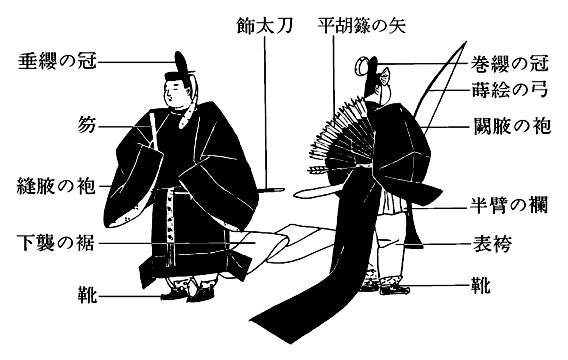
そく‐た・う【束帯ふ】‥タフ🔗⭐🔉
そく‐た・う【束帯ふ】‥タフ
〔自四〕
(「束帯」を活用させた語)束帯をつける。衣服を正す。また、堅苦しくする。天草本伊曾保物語「いかにも―・ひちぎつてまかりづれば」
そく‐はく【束帛】🔗⭐🔉
そく‐はく【束帛】
たばねた絹。昔、中国で礼物に用いた。
そく‐ばく【束縛】🔗⭐🔉
そく‐ばく【束縛】
①まとめて縛ること。つなぎ捕らえること。
②制限を加えて自由にさせないこと。「行動を―する」「時間に―される」
そく‐はつ【束髪】🔗⭐🔉
そく‐はつ【束髪】
①髪をたばねて結ぶこと。
②明治・大正の女性の代表的な西洋風の髪型。1885年(明治18)婦人束髪会が発足して広まり、軽便かつ衛生的なため流行。揚げ巻・下げ巻・英吉利イギリス巻・マガレイト、また、庇髪ひさしがみ・耳隠し・二百三高地・七三しちさん・オールバック・S巻など、種々の変型を生じた。尾崎紅葉、三人妻「同車あいのりは―の白襟紋服の女なり」
束髪


たば‐かぜ【束風】🔗⭐🔉
たば‐かぜ【束風】
(主として日本海岸で)乾いぬいすなわち北西方から吹く暴風。
たばね【束ね】🔗⭐🔉
たばね【束ね】
①たばねること。また、たばねたもの。
②とりしまること。まとめること。また、その役。狂言、泣尼「この浦の―を致す者でござる」
③男の髪の結い方の一つ。(→)嚊束かかあたばねに同じ。
⇒たばね‐がみ【束ね髪】
⇒たばね‐ぎ【束ね木】
⇒たばね‐ばしら【束ね柱】
⇒たばね‐わた【束ね綿】
たばね‐がみ【束ね髪】🔗⭐🔉
たばね‐がみ【束ね髪】
たばねた頭髪。そくはつ。
⇒たばね【束ね】
たばね‐ぎ【束ね木】🔗⭐🔉
たばね‐ぎ【束ね木】
一束ずつたばねた薪。好色一代男3「こなから酒に両隣を傾け、―の当座買ひ、やがて立消ゆる煙なるべし」
⇒たばね【束ね】
たばね‐ばしら【束ね柱】🔗⭐🔉
たばね‐ばしら【束ね柱】
太い柱の周りに細い柱を数本付けた柱。簇柱ぞくちゅう。
⇒たばね【束ね】
たば・ねる【束ねる】🔗⭐🔉
たば・ねる【束ねる】
〔他下一〕[文]たば・ぬ(下二)
①一つにつかねる。束にする。一つにまとめる。〈文明本節用集〉。「髪を―・ねる」
②すべくくる。統率する。「荒くれ男どもを―・ねる」
たばね‐わた【束ね綿】🔗⭐🔉
たばね‐わた【束ね綿】
上等の真綿をたばねくくったもの。多く進物に用いた。
⇒たばね【束ね】
たば‐わけ【束分け】🔗⭐🔉
たば‐わけ【束分け】
地主と小作とが、米麦収穫の際、刈り取った米麦をあらかじめ約定した割合で分け合った旧習。刈分け。稲分け。
たわし【束子】タハシ🔗⭐🔉
たわし【束子】タハシ
わら・棕梠しゅろの毛などをたばねて造り、器物をこすり洗う道具。「―でこする」
束子
撮影:薗部 澄(JCII蔵)


つか【束】🔗⭐🔉
つか【束】
①握ったときの4本の指の幅ほどの長さ。太平記25「其の尺僅かに十―なれば又十―の剣とも名付けたり」
②たばねた数の単位。孝徳紀「段きだごとに租たちからの稲二―二把たばり」
③短い垂直の材。束柱つかばしら。日葡辞書「ツカヲカ(支)ウ」
④紙をたばねたものの厚み。転じて、書物の厚み。
つか‐いし【束石】🔗⭐🔉
つか‐いし【束石】
床束ゆかづかなどの下に据える石。
つか‐いね【束稲】🔗⭐🔉
つか‐いね【束稲】
つかねた稲。稲のたば。
つか‐なみ【束並・藁藉】🔗⭐🔉
つか‐なみ【束並・藁藉】
山家などで、わらを編んで畳の広さほどにつくった敷物。わらぐみ。ねこがき。散木奇歌集「―の上によるよる旅寝して」
つかね‐お【束ね緒】‥ヲ🔗⭐🔉
つかね‐お【束ね緒】‥ヲ
しばるために用いる紐。結び紐。古今和歌集恋「何をかは恋の乱れの―にせむ」
つか・ねる【束ねる】🔗⭐🔉
つか・ねる【束ねる】
〔他下一〕[文]つか・ぬ(下二)
①集めて一つにしてくくる。たばねる。万葉集16「か黒し髪をま櫛もちここにかき垂り取り―・ね」。平家物語7「貴賤手を―・ね緇素しそ足をいただく」
②こまぬく。「手を―・ねる」
③すべつかさどる。統帥する。「三軍を―・ねる」
つか‐の‐あいだ【束の間】‥アヒダ🔗⭐🔉
つか‐の‐あいだ【束の間】‥アヒダ
(→)「つかのま」に同じ。万葉集2「―もわれ忘れめや」
つか‐の‐ま【束の間】🔗⭐🔉
つか‐の‐ま【束の間】
(一束ほどの短い間の意)ちょっとの間。しばらく。万葉集4「夏野行く牡鹿の角の―も」。「―の平安」
つか‐ばしら【束柱】🔗⭐🔉
つか‐ばしら【束柱】
短い柱。つか。平家物語3「小柴墻こぼち、大床の―わりなどして」
つか‐ふな【束鮒】🔗⭐🔉
つか‐ふな【束鮒】
一束ほどの大きさの鮒。万葉集4「妹がためわがすなどれる藻臥し―」
つか‐みほん【束見本】🔗⭐🔉
つか‐みほん【束見本】
実際と同じ用紙を用いて作った製本見本。印刷・製本作業に先立ち、装丁・体裁・外形・重さなどを確認するもの。
[漢]束🔗⭐🔉
束 字形
 筆順
筆順
 〔木部3画/7画/教育/3411・422B〕
〔音〕ソク(呉)
〔訓〕たば・たばねる・つか・つかねる
[意味]
①たばにしてくくる。つかねる。動きがとれないようにしめつける。「束縛・束帯・結束・収束・約束」
②たば(を数える語)。「一束・二束三文」▶稲十把ぱ、紙十帖じょうなど、十個のたばを一束とする。
③指を四本並べた幅。つか。矢の長さをはかる単位。「十二束二つ伏せ、よっぴいてひゃうど放つ」〔平家〕
[解字]
象形。たきぎのような木をなわでたばねた形。
[下ツキ
羈束・結束・検束・拘束・収束・集束・装束・二束三文・幣束・約束
[難読]
束子たわし
〔木部3画/7画/教育/3411・422B〕
〔音〕ソク(呉)
〔訓〕たば・たばねる・つか・つかねる
[意味]
①たばにしてくくる。つかねる。動きがとれないようにしめつける。「束縛・束帯・結束・収束・約束」
②たば(を数える語)。「一束・二束三文」▶稲十把ぱ、紙十帖じょうなど、十個のたばを一束とする。
③指を四本並べた幅。つか。矢の長さをはかる単位。「十二束二つ伏せ、よっぴいてひゃうど放つ」〔平家〕
[解字]
象形。たきぎのような木をなわでたばねた形。
[下ツキ
羈束・結束・検束・拘束・収束・集束・装束・二束三文・幣束・約束
[難読]
束子たわし
 筆順
筆順
 〔木部3画/7画/教育/3411・422B〕
〔音〕ソク(呉)
〔訓〕たば・たばねる・つか・つかねる
[意味]
①たばにしてくくる。つかねる。動きがとれないようにしめつける。「束縛・束帯・結束・収束・約束」
②たば(を数える語)。「一束・二束三文」▶稲十把ぱ、紙十帖じょうなど、十個のたばを一束とする。
③指を四本並べた幅。つか。矢の長さをはかる単位。「十二束二つ伏せ、よっぴいてひゃうど放つ」〔平家〕
[解字]
象形。たきぎのような木をなわでたばねた形。
[下ツキ
羈束・結束・検束・拘束・収束・集束・装束・二束三文・幣束・約束
[難読]
束子たわし
〔木部3画/7画/教育/3411・422B〕
〔音〕ソク(呉)
〔訓〕たば・たばねる・つか・つかねる
[意味]
①たばにしてくくる。つかねる。動きがとれないようにしめつける。「束縛・束帯・結束・収束・約束」
②たば(を数える語)。「一束・二束三文」▶稲十把ぱ、紙十帖じょうなど、十個のたばを一束とする。
③指を四本並べた幅。つか。矢の長さをはかる単位。「十二束二つ伏せ、よっぴいてひゃうど放つ」〔平家〕
[解字]
象形。たきぎのような木をなわでたばねた形。
[下ツキ
羈束・結束・検束・拘束・収束・集束・装束・二束三文・幣束・約束
[難読]
束子たわし
広辞苑に「−束」で始まるの検索結果 1-34。