複数辞典一括検索+![]()
![]()
あまし‐もの【余し物・余し者】🔗⭐🔉
あまし‐もの【余し物・余し者】
①もてあました品物。また、もてあまされた人。もてあましもの。
②残した物。残り物。
あま・す【余す】🔗⭐🔉
あま・す【余す】
〔他五〕
①余分・余力・余地を残す。残っている。古事記下「築くや玉垣つき―・し」。「ご飯を―・す」「夏休みも―・すところ3日」
②もらす。とり逃がす。平家物語6「―・すな、もらすなとて攻め給へば」
③(主として受身の形で用いる)処理できないものとする。また、もてあます。平家物語1「世に―・されたるいたづら者なんど」
④余勢で外にほうり出す。保元物語「馬は屏風を倒すごとく、がはと倒るれば、主は前へぞ―・されける」
⇒余すところなく
○余すところなくあますところなく🔗⭐🔉
○余すところなくあますところなく
残らず。ことごとく。
⇒あま・す【余す】
あま‐ずら【甘葛】‥ヅラ
①ツタの古名。
②今のアマチャヅルに当たるといわれる蔓草の一種。また、その蔓草からとった甘味料。甘葛煎あまずらせん。味煎。宇津保物語蔵開上「金のかめ二つに、一つには蜜、一つには―入れて」
あま‐ぜ【尼前】
尼御前の略。平家物語3「御車の尻には、―一人まゐられたり」
あま‐そうぞく【雨装束】‥サウ‥
外出の時に着る、雨にぬれない用意の衣服。
あま‐そぎ【天削】
高い峰。(八雲御抄に見える)
あま‐そぎ【尼削】
①肩から背のあたりで髪を切り揃えること。在俗のまま仏門に入った優婆夷うばいの髪型。そぎあま。さげあま。
②女性の髪を尼のように肩のあたりで切り揃えること。源氏物語薄雲「この春よりおほす御ぐし―の程にて」
あま‐そそぎ【雨注ぎ】
(古くは清音)あまだれ。雨のしずく。催馬楽、東屋「東屋のまやのあまりのその―」
アマゾネス
(Amazon(アマゾン)に、英語で女性形を示す接尾辞essを付けて、女性であることを強調した和製語)(→)アマゾンに同じ。
あま‐ぞら【雨空】
雨が降りそうな空。また、雨が降っている空。
アマゾン【Amazon(s)】
(もとギリシア語で「乳なし」の意。戦闘と狩りを好み、弓をひくのに邪魔な右の乳房を切除する慣わしだった)
①ギリシア神話に出てくる女戦士から成る部族。小アジア北東部に住み、ペンテシレイアなどの女王に率いられて戦った。
②転じて、女丈夫・女傑・勇婦の意。
⇒アマゾン‐がわ【アマゾン川】
⇒アマゾン‐せき【アマゾン石】
アマゾン‐がわ【アマゾン川】‥ガハ
南米の大河。アンデス山脈中の源流からブラジル北部アマゾン盆地を東に貫流して大西洋に注ぐ。密林が流域の大部分をおおい、長さ約6516キロメートル。川幅は河口で100キロメートル。流域705万平方キロメートル。水量・流域面積とも世界第一。
アマゾン川
提供:NHK
⇒アマゾン【Amazon(s)】
アマゾン‐せき【アマゾン石】
(amazonite)微斜長石(カリ長石の一種)のうち、美しい緑青色のもの。アマゾナイト。天河石。
⇒アマゾン【Amazon(s)】
アマゾン‐ドット‐コム【Amazon.com】
世界的規模のインターネット小売業者。1995年アメリカで書籍の販売から創業。
あま‐た【数多】
〔名・副〕
①(数量について)多く。たくさん。允恭紀「―は寝ずにただ一夜のみ」。「―の人」「引く手―」
②(程度について)非常に。甚だしく。万葉集7「沖つ波さわくを聞けば―悲しも」
⇒あまた‐え【数多重】
⇒あまた‐かえり【数多返り】
⇒あまた‐たび【数多度】
あま‐だ
(→)天棚あまだなに同じ。
あまだ【天田】
姓氏の一つ。
⇒あまだ‐ぐあん【天田愚庵】
あま‐だい【あま台】
(「あま」は女の意。三重県から北陸にかけていう)裁縫用の針箱。あまむろ。
あま‐だい【甘鯛】‥ダヒ
アマダイ科の海産の硬骨魚の総称。全長30〜50センチメートル。体はやや長く側扁、頭は短く、鮮赤色で横縞がある。冬に美味。南日本・朝鮮に多い。シロアマダイ・アカアマダイ・キアマダイなどがある。〈[季]冬〉
あかあまだい
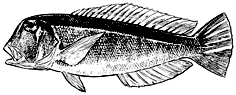 アマダイ
提供:東京動物園協会
アマダイ
提供:東京動物園協会
 あまた‐え【数多重】‥へ
幾重にも重なるさま。栄華物語耀く藤壺「御袖も一つならず―濡らさせ給ふ」
⇒あま‐た【数多】
あまた‐かえり【数多返り】‥カヘリ
何度も。たびたび。源氏物語総角「御文は明くる日ごとに―づつ奉らせ給ふ」
⇒あま‐た【数多】
あまだ‐ぐあん【天田愚庵】
歌人。本名、甘田五郎。剃髪して鉄眼。磐城生れ。正岡子規と交わり、その歌風に影響を与えた。「愚庵全集」がある。(1854〜1904)
⇒あまだ【天田】
あまた‐たび【数多度】
たびたび。しばしば。古今和歌集旅「草の枕に―ねぬ」
⇒あま‐た【数多】
あま‐だな【天棚】
①炉の上に天井からつるした棚。火棚。天皿あまざら。火天ひあま。火高。あまだ。
②天井。転じて、二階のことをもいう。あまだ。あまごこ。
あま‐だな【尼店・尼棚】
今の東京日本橋室町1丁目南西付近の俗称。江戸時代には塗物問屋が多くあった。尼崎店。
あま‐だむ【天飛む】
〔枕〕
(アマトブの転)「かり(雁)」「かる(軽)」にかかる。古事記下「―軽のをとめ」
あま‐たら・す【天足らす】
〔自四〕
(スは尊敬の助動詞)天界に満ち満ちておられる。万葉集2「大君の御寿みいのちはながく―・したり」
あま‐だり【雨垂り】
①あまだれ。
②あまだれの落ちるところ。宇治拾遺物語1「しばし―におはしませと」
⇒あまだり‐うけ【雨垂り受け】
あまだり‐うけ【雨垂り受け】
雨だれを受ける樋とい。
⇒あま‐だり【雨垂り】
あま‐たる・い【甘たるい】
〔形〕
(→)「あまったるい」に同じ。
あま‐だれ【雨垂れ】
軒先などから落ちる雨のしずく。
⇒あまだれ‐おち【雨垂れ落ち】
⇒あまだれ‐びょうし【雨垂れ拍子】
⇒雨垂れ石を穿つ
あまた‐え【数多重】‥へ
幾重にも重なるさま。栄華物語耀く藤壺「御袖も一つならず―濡らさせ給ふ」
⇒あま‐た【数多】
あまた‐かえり【数多返り】‥カヘリ
何度も。たびたび。源氏物語総角「御文は明くる日ごとに―づつ奉らせ給ふ」
⇒あま‐た【数多】
あまだ‐ぐあん【天田愚庵】
歌人。本名、甘田五郎。剃髪して鉄眼。磐城生れ。正岡子規と交わり、その歌風に影響を与えた。「愚庵全集」がある。(1854〜1904)
⇒あまだ【天田】
あまた‐たび【数多度】
たびたび。しばしば。古今和歌集旅「草の枕に―ねぬ」
⇒あま‐た【数多】
あま‐だな【天棚】
①炉の上に天井からつるした棚。火棚。天皿あまざら。火天ひあま。火高。あまだ。
②天井。転じて、二階のことをもいう。あまだ。あまごこ。
あま‐だな【尼店・尼棚】
今の東京日本橋室町1丁目南西付近の俗称。江戸時代には塗物問屋が多くあった。尼崎店。
あま‐だむ【天飛む】
〔枕〕
(アマトブの転)「かり(雁)」「かる(軽)」にかかる。古事記下「―軽のをとめ」
あま‐たら・す【天足らす】
〔自四〕
(スは尊敬の助動詞)天界に満ち満ちておられる。万葉集2「大君の御寿みいのちはながく―・したり」
あま‐だり【雨垂り】
①あまだれ。
②あまだれの落ちるところ。宇治拾遺物語1「しばし―におはしませと」
⇒あまだり‐うけ【雨垂り受け】
あまだり‐うけ【雨垂り受け】
雨だれを受ける樋とい。
⇒あま‐だり【雨垂り】
あま‐たる・い【甘たるい】
〔形〕
(→)「あまったるい」に同じ。
あま‐だれ【雨垂れ】
軒先などから落ちる雨のしずく。
⇒あまだれ‐おち【雨垂れ落ち】
⇒あまだれ‐びょうし【雨垂れ拍子】
⇒雨垂れ石を穿つ
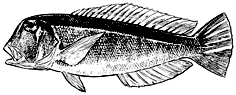 アマダイ
提供:東京動物園協会
アマダイ
提供:東京動物園協会
 あまた‐え【数多重】‥へ
幾重にも重なるさま。栄華物語耀く藤壺「御袖も一つならず―濡らさせ給ふ」
⇒あま‐た【数多】
あまた‐かえり【数多返り】‥カヘリ
何度も。たびたび。源氏物語総角「御文は明くる日ごとに―づつ奉らせ給ふ」
⇒あま‐た【数多】
あまだ‐ぐあん【天田愚庵】
歌人。本名、甘田五郎。剃髪して鉄眼。磐城生れ。正岡子規と交わり、その歌風に影響を与えた。「愚庵全集」がある。(1854〜1904)
⇒あまだ【天田】
あまた‐たび【数多度】
たびたび。しばしば。古今和歌集旅「草の枕に―ねぬ」
⇒あま‐た【数多】
あま‐だな【天棚】
①炉の上に天井からつるした棚。火棚。天皿あまざら。火天ひあま。火高。あまだ。
②天井。転じて、二階のことをもいう。あまだ。あまごこ。
あま‐だな【尼店・尼棚】
今の東京日本橋室町1丁目南西付近の俗称。江戸時代には塗物問屋が多くあった。尼崎店。
あま‐だむ【天飛む】
〔枕〕
(アマトブの転)「かり(雁)」「かる(軽)」にかかる。古事記下「―軽のをとめ」
あま‐たら・す【天足らす】
〔自四〕
(スは尊敬の助動詞)天界に満ち満ちておられる。万葉集2「大君の御寿みいのちはながく―・したり」
あま‐だり【雨垂り】
①あまだれ。
②あまだれの落ちるところ。宇治拾遺物語1「しばし―におはしませと」
⇒あまだり‐うけ【雨垂り受け】
あまだり‐うけ【雨垂り受け】
雨だれを受ける樋とい。
⇒あま‐だり【雨垂り】
あま‐たる・い【甘たるい】
〔形〕
(→)「あまったるい」に同じ。
あま‐だれ【雨垂れ】
軒先などから落ちる雨のしずく。
⇒あまだれ‐おち【雨垂れ落ち】
⇒あまだれ‐びょうし【雨垂れ拍子】
⇒雨垂れ石を穿つ
あまた‐え【数多重】‥へ
幾重にも重なるさま。栄華物語耀く藤壺「御袖も一つならず―濡らさせ給ふ」
⇒あま‐た【数多】
あまた‐かえり【数多返り】‥カヘリ
何度も。たびたび。源氏物語総角「御文は明くる日ごとに―づつ奉らせ給ふ」
⇒あま‐た【数多】
あまだ‐ぐあん【天田愚庵】
歌人。本名、甘田五郎。剃髪して鉄眼。磐城生れ。正岡子規と交わり、その歌風に影響を与えた。「愚庵全集」がある。(1854〜1904)
⇒あまだ【天田】
あまた‐たび【数多度】
たびたび。しばしば。古今和歌集旅「草の枕に―ねぬ」
⇒あま‐た【数多】
あま‐だな【天棚】
①炉の上に天井からつるした棚。火棚。天皿あまざら。火天ひあま。火高。あまだ。
②天井。転じて、二階のことをもいう。あまだ。あまごこ。
あま‐だな【尼店・尼棚】
今の東京日本橋室町1丁目南西付近の俗称。江戸時代には塗物問屋が多くあった。尼崎店。
あま‐だむ【天飛む】
〔枕〕
(アマトブの転)「かり(雁)」「かる(軽)」にかかる。古事記下「―軽のをとめ」
あま‐たら・す【天足らす】
〔自四〕
(スは尊敬の助動詞)天界に満ち満ちておられる。万葉集2「大君の御寿みいのちはながく―・したり」
あま‐だり【雨垂り】
①あまだれ。
②あまだれの落ちるところ。宇治拾遺物語1「しばし―におはしませと」
⇒あまだり‐うけ【雨垂り受け】
あまだり‐うけ【雨垂り受け】
雨だれを受ける樋とい。
⇒あま‐だり【雨垂り】
あま‐たる・い【甘たるい】
〔形〕
(→)「あまったるい」に同じ。
あま‐だれ【雨垂れ】
軒先などから落ちる雨のしずく。
⇒あまだれ‐おち【雨垂れ落ち】
⇒あまだれ‐びょうし【雨垂れ拍子】
⇒雨垂れ石を穿つ
あまり【余り】🔗⭐🔉
あまり【余り】
①事をした結果、出た残り。
㋐事物をあることに役立てた残り。余分。剰余。古事記下「枯野(船の名)を塩に焼き、其しが―琴につくり」。「生活費の―を貯金する」
㋑割り算で割り切れずに残った数。整数aを自然数bで割るとき、
a=bq+r(0≦r<b)
をみたす整数q、rがただ一組定まる。q、rをそれぞれ商、余りという。また、整式f(x)を整式g(x)で割るとき、
f(x)=g(x)q(x)+r(x)(r(x)の次数<g(x)の次数)
をみたす整式の組q(x),r(x)がただ一組定まる。q(x),r(x)をそれぞれ商、余りという。剰余。
②(副詞的にも使う)
㋐物事が普通(正当)と思われる程度を越えること。過度。法外。あんまり。「―ひどいのであきれた」「―たべると腹をこわす」
㋑主として「…の―に」の形で「度をこして…した結果」の意に、また「―の…」の形で「度をこした…のため」の意に用いる。土佐日記「京の近づくよろこびの―に或る童のよめる」。日葡辞書「アマリノコトニ」。「―の暑さに食欲をなくす」「心痛の―に寝込む」「急ぐ―、失敗した」
③(下に打消を伴って)それほど。そんなに。「―よくは知らない」
④数詞に付いて、さらに余分のあることを示す。仏足石歌「三十―二つの相」。源氏物語紅葉賀「朱雀院の行幸は十月十日―なり」。土佐日記「師走の二十日―一日ひとひの日」。日葡辞書「サンネンアマリ」。「50人―の参加者」
⇒あまり‐ごと【余り事】
⇒あまり‐ちゃ【余り茶】
⇒あまり‐に【余りに】
⇒あまり‐べ【余戸】
⇒あまり‐もの【余り物】
⇒あまり‐もの【余り者】
⇒余りと言えば
⇒余り物に福あり
あまり‐ある【余り有る】🔗⭐🔉
あまり‐ある【余り有る】
余分がある。しつくせないほどである。続後撰和歌集雑「ももしきや古き軒端の忍ぶにも猶―昔なりけり」。「彼の心中は察するに―」
あまり‐ごと【余り事】🔗⭐🔉
あまり‐ごと【余り事】
余分なこと。また、過分なこと。源氏物語真木柱「いかに面目あらましと―をぞ思ひてのたまふ」
⇒あまり【余り】
あまり‐ちゃ【余り茶】🔗⭐🔉
あまり‐ちゃ【余り茶】
茶筒などに余っている茶。また、茶碗などに飲み残した茶。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―には福が有る」
⇒あまり【余り】
あまり‐て【余りて】🔗⭐🔉
あまり‐て【余りて】
〔副〕
あまりにも。後撰和歌集恋「―などか人の恋しき」
○余りと言えばあまりといえば
(程度のひどいさまに使う)あまりにも。甚だしく。「―ひどいやり方」
⇒あまり【余り】
あまり‐に【余りに】🔗⭐🔉
あまり‐に【余りに】
〔副〕
過度に。法外に。「―ひどい仕打ち」
⇒あまり【余り】
あまり‐べ【余戸】🔗⭐🔉
あまり‐べ【余戸】
大化改新後の律令国家で50戸を「里」としたとき、それに満たなかった小集落。あまるべ。余目あまるめ。あまべ。地名の余戸よど・よごはこの転かという。
⇒あまり【余り】
あまり‐もの【余り物】🔗⭐🔉
あまり‐もの【余り物】
残ったもの。不用なもの。
⇒あまり【余り】
あまり‐もの【余り者】🔗⭐🔉
○余り物に福ありあまりものにふくあり🔗⭐🔉
○余り物に福ありあまりものにふくあり
人の残したものや最後に残ったものに、かえっていいことがある。残り物には福がある。
⇒あまり【余り】
あま‐りょう【雨竜・螭竜】
想像上の動物。竜の一種。トカゲに似て大きく、角なく尾は細く、青黄色をなすといわれる。
アマリリス【amaryllis】
①熱帯アメリカ産のヒガンバナ科ヒペアストラム属の数種をもとに交雑した園芸品種の総称。一種は嘉永(1848〜1854)年間に渡来、ジャガタラ水仙と呼ばれた。多くの品種がある。形状は2に似るが、花は弁質厚く、白・桃・鮭肉・赤色など。普通、温室で栽培。暖地の戸外では夏咲き。
アマリリス
提供:OPO
 ②ヒガンバナ科の多年草で、1属(その学名)1種。南アフリカ原産。長大な広線形の葉を叢生。40〜50センチメートルの太い花茎の頂部に散形花序をつける。6弁の大輪で緋色または紅色。ホンアマリリス。
あま・る【余る】
〔自五〕
①必要量や容量などを越える。多すぎて残る。余勢が残る。また、割り切れずに残る。古今和歌集序「在原業平は、其の心―・りて、詞足らず」。保元物語「冑の星を射けづりて―・る矢」。日葡辞書「アクギャクミニアマル」。「会費が―・る」「人手が―・る」「10を3で割って1が―・る」
②目安や区切りを越える。それ以上である。宇津保物語吹上上「髪丈に―・り色白くて」。竹取物語「翁、年七十に―・りぬ」。「身の丈六尺に―・る」
③可能性を越える。能力以上である。伊勢物語「田舎人の歌にては―・れりや、足らずや」。愚管抄6「手に―・りたる事かな」。「目に―・る行状」「言葉に―・る」
④分際を越える。分不相応である。源氏物語若菜上「おもだたしきことをも身に―・りて並びなく思ひ侍り」。「身に―・る光栄」
アマルガム【amalgam】
(ギリシア語の「やわらかい物質」に由来)水銀と他の金属との合金。鉄・白金・タングステン・ニッケル・マンガンなどの高融点金属との間にはできにくい。汞和金こうわきん。
⇒アマルガム‐ほう【アマルガム法】
アマルガム‐ほう【アマルガム法】‥ハフ
金・銀の精錬法の一つ。金銀鉱石を水銀に接触させてアマルガムをつくり、これを蒸留して金または銀を回収する。古くから用いられ、比較的粗粒の鉱石に適する。混汞こんこう法。→青化法
⇒アマルガム【amalgam】
アマルナ‐じだい【アマルナ時代】
(Amarna)古代エジプト第18王朝の一時期(前14世紀)。一神教の創始、新都の建設など革新策が行われたが間もなく旧に復した。芸術上の写実的な新傾向(アマルナ芸術)はのちにまで強い影響を及ぼした。
あまる‐べ【余部・余戸】
(→)「あまりべ」に同じ。安閑紀「安芸国の過戸あまるべ」
あまる‐め【余目】
(→)「あまりべ」に同じ。
あまんじゃく【天ん邪鬼】
アマノジャクの転訛。
あまん・じる【甘んじる】
〔自上一〕
「あまんずる」に同じ。
あまん・ずる【甘んずる】
〔自サ変〕[文]あまん・ず(サ変)
(アマミスのミが撥音化したもの)
①よい味だとする。満足に思う。奥の細道「坐してまのあたり奇景を―・ず」
②与えられたものをしかたないと思って受ける。「薄給に―・ずる」「―・じて犠牲となる」
アマンタジン【amantadine】
A型インフルエンザ‐ウイルスに有効な抗ウイルス剤。パーキンソン病の治療や精神活動改善にも使用。商品名、シンメトレル。
アマンド【amande フランス】
アーモンド。巴旦杏はたんきょう。
あみ【網】
①鳥獣や魚などをとるために、糸や針金を編んで造った道具。また一般に、糸や針金を編んで造ったもの。万葉集17「二上ふたがみの彼面おもて此面このもに―さして吾が待つ鷹を夢いめに告げつも」。「―ですくう」
②比喩的に、人や物を捕らえるために綿密にはりめぐらしたもの。「検問の―にひっかかる」「法の―をくぐる」
③(印刷で)網点・網版の略。
⇒網が上がる
⇒網が下りる
⇒網呑舟の魚を漏らす
⇒網無くて淵をのぞくな
⇒網を張る
あみ【醤蝦】
アミ目の甲殻類の総称。形はエビに似るが小形で、鋏はさみをもたない。体長1センチメートル内外。海産種が多く、沿岸から深海まで約1000種が知られている。釣りのまき餌にするほか、佃煮として食用。コマセアミ・イサザアミなど。新撰字鏡9「
②ヒガンバナ科の多年草で、1属(その学名)1種。南アフリカ原産。長大な広線形の葉を叢生。40〜50センチメートルの太い花茎の頂部に散形花序をつける。6弁の大輪で緋色または紅色。ホンアマリリス。
あま・る【余る】
〔自五〕
①必要量や容量などを越える。多すぎて残る。余勢が残る。また、割り切れずに残る。古今和歌集序「在原業平は、其の心―・りて、詞足らず」。保元物語「冑の星を射けづりて―・る矢」。日葡辞書「アクギャクミニアマル」。「会費が―・る」「人手が―・る」「10を3で割って1が―・る」
②目安や区切りを越える。それ以上である。宇津保物語吹上上「髪丈に―・り色白くて」。竹取物語「翁、年七十に―・りぬ」。「身の丈六尺に―・る」
③可能性を越える。能力以上である。伊勢物語「田舎人の歌にては―・れりや、足らずや」。愚管抄6「手に―・りたる事かな」。「目に―・る行状」「言葉に―・る」
④分際を越える。分不相応である。源氏物語若菜上「おもだたしきことをも身に―・りて並びなく思ひ侍り」。「身に―・る光栄」
アマルガム【amalgam】
(ギリシア語の「やわらかい物質」に由来)水銀と他の金属との合金。鉄・白金・タングステン・ニッケル・マンガンなどの高融点金属との間にはできにくい。汞和金こうわきん。
⇒アマルガム‐ほう【アマルガム法】
アマルガム‐ほう【アマルガム法】‥ハフ
金・銀の精錬法の一つ。金銀鉱石を水銀に接触させてアマルガムをつくり、これを蒸留して金または銀を回収する。古くから用いられ、比較的粗粒の鉱石に適する。混汞こんこう法。→青化法
⇒アマルガム【amalgam】
アマルナ‐じだい【アマルナ時代】
(Amarna)古代エジプト第18王朝の一時期(前14世紀)。一神教の創始、新都の建設など革新策が行われたが間もなく旧に復した。芸術上の写実的な新傾向(アマルナ芸術)はのちにまで強い影響を及ぼした。
あまる‐べ【余部・余戸】
(→)「あまりべ」に同じ。安閑紀「安芸国の過戸あまるべ」
あまる‐め【余目】
(→)「あまりべ」に同じ。
あまんじゃく【天ん邪鬼】
アマノジャクの転訛。
あまん・じる【甘んじる】
〔自上一〕
「あまんずる」に同じ。
あまん・ずる【甘んずる】
〔自サ変〕[文]あまん・ず(サ変)
(アマミスのミが撥音化したもの)
①よい味だとする。満足に思う。奥の細道「坐してまのあたり奇景を―・ず」
②与えられたものをしかたないと思って受ける。「薄給に―・ずる」「―・じて犠牲となる」
アマンタジン【amantadine】
A型インフルエンザ‐ウイルスに有効な抗ウイルス剤。パーキンソン病の治療や精神活動改善にも使用。商品名、シンメトレル。
アマンド【amande フランス】
アーモンド。巴旦杏はたんきょう。
あみ【網】
①鳥獣や魚などをとるために、糸や針金を編んで造った道具。また一般に、糸や針金を編んで造ったもの。万葉集17「二上ふたがみの彼面おもて此面このもに―さして吾が待つ鷹を夢いめに告げつも」。「―ですくう」
②比喩的に、人や物を捕らえるために綿密にはりめぐらしたもの。「検問の―にひっかかる」「法の―をくぐる」
③(印刷で)網点・網版の略。
⇒網が上がる
⇒網が下りる
⇒網呑舟の魚を漏らす
⇒網無くて淵をのぞくな
⇒網を張る
あみ【醤蝦】
アミ目の甲殻類の総称。形はエビに似るが小形で、鋏はさみをもたない。体長1センチメートル内外。海産種が多く、沿岸から深海まで約1000種が知られている。釣りのまき餌にするほか、佃煮として食用。コマセアミ・イサザアミなど。新撰字鏡9「 、阿弥」
あみ【阿弥】
「阿弥陀号あみだごう」参照。
アミ【ami(e) フランス】
友人。特に異性の友だち。愛人。
あみあげ‐ぐつ【編上靴】
足の甲や脛すねをおおう部分を紐でからげて履く半長靴。あみあげ。
アミアン【Amiens】
フランス北西部の都市。ソンム川に沿い、繊維工業が発達。13世紀建設のフランス最大の大聖堂は世界遺産。1802年英仏休戦条約締結の地。人口13万5千(1999)。
アミアン
提供:JTBフォト
、阿弥」
あみ【阿弥】
「阿弥陀号あみだごう」参照。
アミ【ami(e) フランス】
友人。特に異性の友だち。愛人。
あみあげ‐ぐつ【編上靴】
足の甲や脛すねをおおう部分を紐でからげて履く半長靴。あみあげ。
アミアン【Amiens】
フランス北西部の都市。ソンム川に沿い、繊維工業が発達。13世紀建設のフランス最大の大聖堂は世界遺産。1802年英仏休戦条約締結の地。人口13万5千(1999)。
アミアン
提供:JTBフォト
 あみ‐あんどん【網行灯】
金網をはった行灯。
アミーゴ【amigo スペイン】
(男性の)友だち。親友。
あみ‐いし【網石】
漁網のおもりにする石。沈子いわ。
あみ‐いた【編板・箯輿】
⇒あんだ。〈倭名類聚鈔13〉
あみ‐いと【編糸】
編物用の糸。毛糸・レース糸など。
アミーバ【amoeba】
⇒アメーバ
あみいり‐ガラス【網入硝子】
金網を封じ込んだ板ガラス。衝撃などに比較的よく堪える。
アミール【amīr アラビア】
司令官。総督。首長。また、イスラム王朝の君主または王子の称号。
アミーレ‐フスラウ【Amīr-i Khusraw】
北インド出身のペルシア語詩人。「インドの鸚鵡」の渾名を持つ。叙事詩「マジュヌーンとライラー」など。(1253〜1325)
あみ‐うち【網打ち】
①投網とあみを打って魚を捕ること。また、その人。
②(その形が投網を打つさまに似ているところから)相撲の手の一つ。相手の差し手を両手で抱えるようにして、差し手の側に捻ひねり倒すもの。
あみうち
⇒あみうち‐ば【網打場】
あみうち‐ば【網打場】
江戸深川の遊里の一つで、やや下等な所。
⇒あみ‐うち【網打ち】
あみ‐うど【網人】
(アミビトの転)漁師。平家物語3「―に魚をもらうてもち」
アミエル【Henri Frédéric Amiel】
フランス系スイスの哲学者・文学者。深い省察に満ちた、30年余にわたる「日記」で有名。(1821〜1881)
あみ‐おり【網織】
細かく切った漁網を緯糸よこいとに交ぜて織った織物。
あみ‐おろし【網卸し・網下し】
①新調の網を初めて使用すること。
②網漁始めの祝祭。恵比寿祝。大玉起し。
あみ‐あんどん【網行灯】
金網をはった行灯。
アミーゴ【amigo スペイン】
(男性の)友だち。親友。
あみ‐いし【網石】
漁網のおもりにする石。沈子いわ。
あみ‐いた【編板・箯輿】
⇒あんだ。〈倭名類聚鈔13〉
あみ‐いと【編糸】
編物用の糸。毛糸・レース糸など。
アミーバ【amoeba】
⇒アメーバ
あみいり‐ガラス【網入硝子】
金網を封じ込んだ板ガラス。衝撃などに比較的よく堪える。
アミール【amīr アラビア】
司令官。総督。首長。また、イスラム王朝の君主または王子の称号。
アミーレ‐フスラウ【Amīr-i Khusraw】
北インド出身のペルシア語詩人。「インドの鸚鵡」の渾名を持つ。叙事詩「マジュヌーンとライラー」など。(1253〜1325)
あみ‐うち【網打ち】
①投網とあみを打って魚を捕ること。また、その人。
②(その形が投網を打つさまに似ているところから)相撲の手の一つ。相手の差し手を両手で抱えるようにして、差し手の側に捻ひねり倒すもの。
あみうち
⇒あみうち‐ば【網打場】
あみうち‐ば【網打場】
江戸深川の遊里の一つで、やや下等な所。
⇒あみ‐うち【網打ち】
あみ‐うど【網人】
(アミビトの転)漁師。平家物語3「―に魚をもらうてもち」
アミエル【Henri Frédéric Amiel】
フランス系スイスの哲学者・文学者。深い省察に満ちた、30年余にわたる「日記」で有名。(1821〜1881)
あみ‐おり【網織】
細かく切った漁網を緯糸よこいとに交ぜて織った織物。
あみ‐おろし【網卸し・網下し】
①新調の網を初めて使用すること。
②網漁始めの祝祭。恵比寿祝。大玉起し。
 ②ヒガンバナ科の多年草で、1属(その学名)1種。南アフリカ原産。長大な広線形の葉を叢生。40〜50センチメートルの太い花茎の頂部に散形花序をつける。6弁の大輪で緋色または紅色。ホンアマリリス。
あま・る【余る】
〔自五〕
①必要量や容量などを越える。多すぎて残る。余勢が残る。また、割り切れずに残る。古今和歌集序「在原業平は、其の心―・りて、詞足らず」。保元物語「冑の星を射けづりて―・る矢」。日葡辞書「アクギャクミニアマル」。「会費が―・る」「人手が―・る」「10を3で割って1が―・る」
②目安や区切りを越える。それ以上である。宇津保物語吹上上「髪丈に―・り色白くて」。竹取物語「翁、年七十に―・りぬ」。「身の丈六尺に―・る」
③可能性を越える。能力以上である。伊勢物語「田舎人の歌にては―・れりや、足らずや」。愚管抄6「手に―・りたる事かな」。「目に―・る行状」「言葉に―・る」
④分際を越える。分不相応である。源氏物語若菜上「おもだたしきことをも身に―・りて並びなく思ひ侍り」。「身に―・る光栄」
アマルガム【amalgam】
(ギリシア語の「やわらかい物質」に由来)水銀と他の金属との合金。鉄・白金・タングステン・ニッケル・マンガンなどの高融点金属との間にはできにくい。汞和金こうわきん。
⇒アマルガム‐ほう【アマルガム法】
アマルガム‐ほう【アマルガム法】‥ハフ
金・銀の精錬法の一つ。金銀鉱石を水銀に接触させてアマルガムをつくり、これを蒸留して金または銀を回収する。古くから用いられ、比較的粗粒の鉱石に適する。混汞こんこう法。→青化法
⇒アマルガム【amalgam】
アマルナ‐じだい【アマルナ時代】
(Amarna)古代エジプト第18王朝の一時期(前14世紀)。一神教の創始、新都の建設など革新策が行われたが間もなく旧に復した。芸術上の写実的な新傾向(アマルナ芸術)はのちにまで強い影響を及ぼした。
あまる‐べ【余部・余戸】
(→)「あまりべ」に同じ。安閑紀「安芸国の過戸あまるべ」
あまる‐め【余目】
(→)「あまりべ」に同じ。
あまんじゃく【天ん邪鬼】
アマノジャクの転訛。
あまん・じる【甘んじる】
〔自上一〕
「あまんずる」に同じ。
あまん・ずる【甘んずる】
〔自サ変〕[文]あまん・ず(サ変)
(アマミスのミが撥音化したもの)
①よい味だとする。満足に思う。奥の細道「坐してまのあたり奇景を―・ず」
②与えられたものをしかたないと思って受ける。「薄給に―・ずる」「―・じて犠牲となる」
アマンタジン【amantadine】
A型インフルエンザ‐ウイルスに有効な抗ウイルス剤。パーキンソン病の治療や精神活動改善にも使用。商品名、シンメトレル。
アマンド【amande フランス】
アーモンド。巴旦杏はたんきょう。
あみ【網】
①鳥獣や魚などをとるために、糸や針金を編んで造った道具。また一般に、糸や針金を編んで造ったもの。万葉集17「二上ふたがみの彼面おもて此面このもに―さして吾が待つ鷹を夢いめに告げつも」。「―ですくう」
②比喩的に、人や物を捕らえるために綿密にはりめぐらしたもの。「検問の―にひっかかる」「法の―をくぐる」
③(印刷で)網点・網版の略。
⇒網が上がる
⇒網が下りる
⇒網呑舟の魚を漏らす
⇒網無くて淵をのぞくな
⇒網を張る
あみ【醤蝦】
アミ目の甲殻類の総称。形はエビに似るが小形で、鋏はさみをもたない。体長1センチメートル内外。海産種が多く、沿岸から深海まで約1000種が知られている。釣りのまき餌にするほか、佃煮として食用。コマセアミ・イサザアミなど。新撰字鏡9「
②ヒガンバナ科の多年草で、1属(その学名)1種。南アフリカ原産。長大な広線形の葉を叢生。40〜50センチメートルの太い花茎の頂部に散形花序をつける。6弁の大輪で緋色または紅色。ホンアマリリス。
あま・る【余る】
〔自五〕
①必要量や容量などを越える。多すぎて残る。余勢が残る。また、割り切れずに残る。古今和歌集序「在原業平は、其の心―・りて、詞足らず」。保元物語「冑の星を射けづりて―・る矢」。日葡辞書「アクギャクミニアマル」。「会費が―・る」「人手が―・る」「10を3で割って1が―・る」
②目安や区切りを越える。それ以上である。宇津保物語吹上上「髪丈に―・り色白くて」。竹取物語「翁、年七十に―・りぬ」。「身の丈六尺に―・る」
③可能性を越える。能力以上である。伊勢物語「田舎人の歌にては―・れりや、足らずや」。愚管抄6「手に―・りたる事かな」。「目に―・る行状」「言葉に―・る」
④分際を越える。分不相応である。源氏物語若菜上「おもだたしきことをも身に―・りて並びなく思ひ侍り」。「身に―・る光栄」
アマルガム【amalgam】
(ギリシア語の「やわらかい物質」に由来)水銀と他の金属との合金。鉄・白金・タングステン・ニッケル・マンガンなどの高融点金属との間にはできにくい。汞和金こうわきん。
⇒アマルガム‐ほう【アマルガム法】
アマルガム‐ほう【アマルガム法】‥ハフ
金・銀の精錬法の一つ。金銀鉱石を水銀に接触させてアマルガムをつくり、これを蒸留して金または銀を回収する。古くから用いられ、比較的粗粒の鉱石に適する。混汞こんこう法。→青化法
⇒アマルガム【amalgam】
アマルナ‐じだい【アマルナ時代】
(Amarna)古代エジプト第18王朝の一時期(前14世紀)。一神教の創始、新都の建設など革新策が行われたが間もなく旧に復した。芸術上の写実的な新傾向(アマルナ芸術)はのちにまで強い影響を及ぼした。
あまる‐べ【余部・余戸】
(→)「あまりべ」に同じ。安閑紀「安芸国の過戸あまるべ」
あまる‐め【余目】
(→)「あまりべ」に同じ。
あまんじゃく【天ん邪鬼】
アマノジャクの転訛。
あまん・じる【甘んじる】
〔自上一〕
「あまんずる」に同じ。
あまん・ずる【甘んずる】
〔自サ変〕[文]あまん・ず(サ変)
(アマミスのミが撥音化したもの)
①よい味だとする。満足に思う。奥の細道「坐してまのあたり奇景を―・ず」
②与えられたものをしかたないと思って受ける。「薄給に―・ずる」「―・じて犠牲となる」
アマンタジン【amantadine】
A型インフルエンザ‐ウイルスに有効な抗ウイルス剤。パーキンソン病の治療や精神活動改善にも使用。商品名、シンメトレル。
アマンド【amande フランス】
アーモンド。巴旦杏はたんきょう。
あみ【網】
①鳥獣や魚などをとるために、糸や針金を編んで造った道具。また一般に、糸や針金を編んで造ったもの。万葉集17「二上ふたがみの彼面おもて此面このもに―さして吾が待つ鷹を夢いめに告げつも」。「―ですくう」
②比喩的に、人や物を捕らえるために綿密にはりめぐらしたもの。「検問の―にひっかかる」「法の―をくぐる」
③(印刷で)網点・網版の略。
⇒網が上がる
⇒網が下りる
⇒網呑舟の魚を漏らす
⇒網無くて淵をのぞくな
⇒網を張る
あみ【醤蝦】
アミ目の甲殻類の総称。形はエビに似るが小形で、鋏はさみをもたない。体長1センチメートル内外。海産種が多く、沿岸から深海まで約1000種が知られている。釣りのまき餌にするほか、佃煮として食用。コマセアミ・イサザアミなど。新撰字鏡9「 、阿弥」
あみ【阿弥】
「阿弥陀号あみだごう」参照。
アミ【ami(e) フランス】
友人。特に異性の友だち。愛人。
あみあげ‐ぐつ【編上靴】
足の甲や脛すねをおおう部分を紐でからげて履く半長靴。あみあげ。
アミアン【Amiens】
フランス北西部の都市。ソンム川に沿い、繊維工業が発達。13世紀建設のフランス最大の大聖堂は世界遺産。1802年英仏休戦条約締結の地。人口13万5千(1999)。
アミアン
提供:JTBフォト
、阿弥」
あみ【阿弥】
「阿弥陀号あみだごう」参照。
アミ【ami(e) フランス】
友人。特に異性の友だち。愛人。
あみあげ‐ぐつ【編上靴】
足の甲や脛すねをおおう部分を紐でからげて履く半長靴。あみあげ。
アミアン【Amiens】
フランス北西部の都市。ソンム川に沿い、繊維工業が発達。13世紀建設のフランス最大の大聖堂は世界遺産。1802年英仏休戦条約締結の地。人口13万5千(1999)。
アミアン
提供:JTBフォト
 あみ‐あんどん【網行灯】
金網をはった行灯。
アミーゴ【amigo スペイン】
(男性の)友だち。親友。
あみ‐いし【網石】
漁網のおもりにする石。沈子いわ。
あみ‐いた【編板・箯輿】
⇒あんだ。〈倭名類聚鈔13〉
あみ‐いと【編糸】
編物用の糸。毛糸・レース糸など。
アミーバ【amoeba】
⇒アメーバ
あみいり‐ガラス【網入硝子】
金網を封じ込んだ板ガラス。衝撃などに比較的よく堪える。
アミール【amīr アラビア】
司令官。総督。首長。また、イスラム王朝の君主または王子の称号。
アミーレ‐フスラウ【Amīr-i Khusraw】
北インド出身のペルシア語詩人。「インドの鸚鵡」の渾名を持つ。叙事詩「マジュヌーンとライラー」など。(1253〜1325)
あみ‐うち【網打ち】
①投網とあみを打って魚を捕ること。また、その人。
②(その形が投網を打つさまに似ているところから)相撲の手の一つ。相手の差し手を両手で抱えるようにして、差し手の側に捻ひねり倒すもの。
あみうち
⇒あみうち‐ば【網打場】
あみうち‐ば【網打場】
江戸深川の遊里の一つで、やや下等な所。
⇒あみ‐うち【網打ち】
あみ‐うど【網人】
(アミビトの転)漁師。平家物語3「―に魚をもらうてもち」
アミエル【Henri Frédéric Amiel】
フランス系スイスの哲学者・文学者。深い省察に満ちた、30年余にわたる「日記」で有名。(1821〜1881)
あみ‐おり【網織】
細かく切った漁網を緯糸よこいとに交ぜて織った織物。
あみ‐おろし【網卸し・網下し】
①新調の網を初めて使用すること。
②網漁始めの祝祭。恵比寿祝。大玉起し。
あみ‐あんどん【網行灯】
金網をはった行灯。
アミーゴ【amigo スペイン】
(男性の)友だち。親友。
あみ‐いし【網石】
漁網のおもりにする石。沈子いわ。
あみ‐いた【編板・箯輿】
⇒あんだ。〈倭名類聚鈔13〉
あみ‐いと【編糸】
編物用の糸。毛糸・レース糸など。
アミーバ【amoeba】
⇒アメーバ
あみいり‐ガラス【網入硝子】
金網を封じ込んだ板ガラス。衝撃などに比較的よく堪える。
アミール【amīr アラビア】
司令官。総督。首長。また、イスラム王朝の君主または王子の称号。
アミーレ‐フスラウ【Amīr-i Khusraw】
北インド出身のペルシア語詩人。「インドの鸚鵡」の渾名を持つ。叙事詩「マジュヌーンとライラー」など。(1253〜1325)
あみ‐うち【網打ち】
①投網とあみを打って魚を捕ること。また、その人。
②(その形が投網を打つさまに似ているところから)相撲の手の一つ。相手の差し手を両手で抱えるようにして、差し手の側に捻ひねり倒すもの。
あみうち
⇒あみうち‐ば【網打場】
あみうち‐ば【網打場】
江戸深川の遊里の一つで、やや下等な所。
⇒あみ‐うち【網打ち】
あみ‐うど【網人】
(アミビトの転)漁師。平家物語3「―に魚をもらうてもち」
アミエル【Henri Frédéric Amiel】
フランス系スイスの哲学者・文学者。深い省察に満ちた、30年余にわたる「日記」で有名。(1821〜1881)
あみ‐おり【網織】
細かく切った漁網を緯糸よこいとに交ぜて織った織物。
あみ‐おろし【網卸し・網下し】
①新調の網を初めて使用すること。
②網漁始めの祝祭。恵比寿祝。大玉起し。
あま・る【余る】🔗⭐🔉
あま・る【余る】
〔自五〕
①必要量や容量などを越える。多すぎて残る。余勢が残る。また、割り切れずに残る。古今和歌集序「在原業平は、其の心―・りて、詞足らず」。保元物語「冑の星を射けづりて―・る矢」。日葡辞書「アクギャクミニアマル」。「会費が―・る」「人手が―・る」「10を3で割って1が―・る」
②目安や区切りを越える。それ以上である。宇津保物語吹上上「髪丈に―・り色白くて」。竹取物語「翁、年七十に―・りぬ」。「身の丈六尺に―・る」
③可能性を越える。能力以上である。伊勢物語「田舎人の歌にては―・れりや、足らずや」。愚管抄6「手に―・りたる事かな」。「目に―・る行状」「言葉に―・る」
④分際を越える。分不相応である。源氏物語若菜上「おもだたしきことをも身に―・りて並びなく思ひ侍り」。「身に―・る光栄」
あまる‐べ【余部・余戸】🔗⭐🔉
あまる‐べ【余部・余戸】
(→)「あまりべ」に同じ。安閑紀「安芸国の過戸あまるべ」
あんまり【余】🔗⭐🔉
あんまり【余】
〔名・副〕
(アマリの撥音化)度を過ぎるさま。度はずれて。浄瑠璃、曾根崎「ほんに又―な」。「―ひどいじゃないか」「―あわてると失敗するぞ」
まり【余】🔗⭐🔉
まり【余】
〔接尾〕
「あまり」の略。続日本後紀15「百ももち―十」
よ【余・餘】🔗⭐🔉
よ【余・餘】
➊(「余」と書く)われ。おのれ。予。「―の信念」
➋①それ以上であること。端数があることを示すときにいう語。「百人―の参加者」
②そのほか。それ以外。「―の儀ではない」
よ‐い【余威】‥ヰ🔗⭐🔉
よ‐い【余威】‥ヰ
ある事を成し遂げ、そのあとになお余った勢い。また、後々まで残っている先人の威光。
よ‐い【余意】🔗⭐🔉
よ‐い【余意】
言外の意味。
よいち【余市】🔗⭐🔉
よいち【余市】
北海道西部、後志しりべし支庁北部の町。積丹しゃこたん半島北東側基部にあり、石狩湾に臨む。果樹栽培・ウィスキー製造で知られる。
よ‐いん【余胤】🔗⭐🔉
よ‐いん【余胤】
あとにつづいた血筋。後胤こういん。
よ‐いん【余蔭】🔗⭐🔉
よ‐いん【余蔭】
あとに残された恩恵。先人のおかげ。余徳。
よ‐いん【余韻】‥ヰン🔗⭐🔉
よ‐いん【余韻】‥ヰン
①音の消えたあとまで残る響き。「余音」とも書く。
②転じて、事が終わったあとも残る風情や味わい。また、詩文などで言葉に表されていない趣。余情。「感動の―にひたる」
よ‐えい【余映】🔗⭐🔉
よ‐えい【余映】
あとに残っている輝き。余光。
よ‐えい【余栄】🔗⭐🔉
よ‐えい【余栄】
死後の光栄。死後に残る名誉。
よ‐えん【余炎】🔗⭐🔉
よ‐えん【余炎】
①他に及ぶほのお。また、消え残りのほのお。
②残りの暑さ。残暑。
よ‐えん【余煙】🔗⭐🔉
よ‐えん【余煙】
消え残るけむり。
よ‐か【余花】‥クワ🔗⭐🔉
よ‐か【余花】‥クワ
春におくれて咲く花。特に初夏に咲くおそ咲きの桜。〈[季]夏〉
よ‐かく【余角】🔗⭐🔉
よ‐かく【余角】
〔数〕二つの角の和が直角に等しい時、その一方の角を他の角の余角という。
よ‐かん【余寒】🔗⭐🔉
よ‐かん【余寒】
立春後の寒気。寒があけてもまだ残る寒さ。残寒。〈[季]春〉。「―がなお厳しい」
よ‐ぎ【余技】🔗⭐🔉
よ‐ぎ【余技】
専門以外の技芸。「―に絵を描く」「ほんの―にすぎない」
よ‐ぎ【余儀】🔗⭐🔉
よ‐ぎ【余儀】
他の事。他の方法。→余儀無い
○善き意志よきいし
〔哲〕(Guter Wille ドイツ)理性の命ずるところによって道徳法則に従う意志。カントは、行為の結果ではなくて、善き意志が道徳における絶対的な善であると考えた。善意志。
⇒よ・い【良い・善い・好い・佳い】
よぎ‐な・い【余儀無い】🔗⭐🔉
よぎ‐な・い【余儀無い】
〔形〕[文]よぎな・し(ク)
①他にとるべき方法が無い。やむを得ない。「―・い事だ」「撤退を―・くされる」
②へだて心がない。他事ない。浄瑠璃、心中二つ腹帯「互に―・く見えければ」
○よき分別は老人に問えよきふんべつはろうじんにとえ
名案は経験豊かな老人に教えてもらうのがよい。
⇒よ・い【良い・善い・好い・佳い】
よ‐きょう【余教】‥ケウ🔗⭐🔉
よ‐きょう【余教】‥ケウ
それ以外の教え。大鏡序「法華経一部をときたてまつらんとてこそ、まづ―をばとき給ひけれ」
よ‐きょう【余興】🔗⭐🔉
よ‐きょう【余興】
①感興のあまっていること。また、あまっている感興。方丈記「もし―あれば、しばしば松の響に秋風楽をたぐへ」
②行事・宴会などの席で、興を添えるために行う演芸など。アトラクション。「―に歌を歌う」
よ‐きょう【余響】‥キヤウ🔗⭐🔉
よ‐きょう【余響】‥キヤウ
もとの音がなくなってからもなお残るひびき。余韻。
よ‐ぎょう【余業】‥ゲフ🔗⭐🔉
よ‐ぎょう【余業】‥ゲフ
①残りの仕事。残した事業。
②本業以外の仕事。
よ‐くん【余薫】🔗⭐🔉
よ‐くん【余薫】
①残りのかおり。余香。
②先代の余徳。余慶。
よ‐けい【余計】🔗⭐🔉
よ‐けい【余計】
①物が余ること。あまり。余分。日本永代蔵4「金銀に―なく、京・堺の者によい事させて」
②そのほか。その上。浮世風呂2「朝晩の介抱から口食物、縫針の―に人仕事だ」
③必要の度を越えてかえって無用なこと。むだ。無益。「―なお世話」
④(副詞的に)いっそう。「それでは―困る」「他人より―に練習する」
⇒よけい‐もの【余計物】
⇒よけい‐もの【余計者】
よ‐けい【余慶】🔗⭐🔉
よ‐けい【余慶】
①[易経坤卦]先祖の善行のおかげで子孫が得る幸福。「積善の家には必ず―あり」↔余殃よおう。
②おかげ。余光。
よけい‐もの【余計物】🔗⭐🔉
よけい‐もの【余計物】
あって困る物。持て余す物。無用の長物。
⇒よ‐けい【余計】
よけい‐もの【余計者】🔗⭐🔉
よけい‐もの【余計者】
①はみ出た者。厄介者。
②19世紀のロシア文学に現れた没落貴族・インテリゲンチアの一典型。新旧の階級からはみ出し、方向を失って無為に暮らす人。ゴンチャローフの「オブローモフ」、ツルゲーネフの「ルージン」の主人公など。
⇒よ‐けい【余計】
よ‐げん【余弦】🔗⭐🔉
よ‐げん【余弦】
〔数〕(cosine)三角関数の一つ。コサイン。→三角関数。
⇒よげん‐ていり【余弦定理】
よげん‐ていり【余弦定理】🔗⭐🔉
よげん‐ていり【余弦定理】
三角形ABCにおいて、頂点A、B、Cの対辺の長さをa、b、cとするとき、
a2=b2+c2−2bccosA
などが成り立つという定理。余弦法則。
⇒よ‐げん【余弦】
よ‐こう【余光】‥クワウ🔗⭐🔉
よ‐こう【余光】‥クワウ
①日没のあとに残っているひかり。
②おかげ。余徳。
よ‐こう【余香】‥カウ🔗⭐🔉
よ‐こう【余香】‥カウ
後に残るかおり。のこりが。うつりが。
よ‐こく【余国】🔗⭐🔉
よ‐こく【余国】
余の国。他の国。他国。
よご‐こ【余呉湖】🔗⭐🔉
よご‐こ【余呉湖】
滋賀県北部、伊香郡余呉町にある陥没湖。湖面標高132メートル。最大深度13メートル。面積1.8平方キロメートル。余呉川によって琵琶湖に注ぐ。羽衣伝説がある。よごのうみ。
余呉湖
撮影:的場 啓


よ‐ざい【余材】🔗⭐🔉
よ‐ざい【余材】
余った材木、または材料。
よ‐ざい【余財】🔗⭐🔉
よ‐ざい【余財】
①余った財宝や資金。
②その財物以外の財物。
よ‐ざい【余罪】🔗⭐🔉
よ‐ざい【余罪】
①余れる罪。つぐないきれない罪。
②問われている罪以外の罪。主たる罪以外の罪。「―が発覚した」
よ‐さん【余算】🔗⭐🔉
よ‐さん【余算】
余命の数。余命。残生。方丈記「一期ごの月影かたぶきて、―山の端に近し」
よ‐し【余子】🔗⭐🔉
よ‐し【余子】
①長子以外の子。
②その人以外の人。
よ‐し【余資】🔗⭐🔉
よ‐し【余資】
余っている資金。使い残りの資金。余財。
よ‐じ【余事】🔗⭐🔉
よ‐じ【余事】
①余力でする仕事。余暇でする仕事。
②それ以外の事柄。他事。「―にかまける」
よ‐じしょう【余事象】‥シヤウ🔗⭐🔉
よ‐じしょう【余事象】‥シヤウ
〔数〕事象Aが起こらないという事象A′をAの余事象という。p(A),p(A′)をそれぞれの確率とすればp(A)+p(A′)=1
よ‐しゅう【余宗】🔗⭐🔉
よ‐しゅう【余宗】
別の宗旨。他の宗旨。
よ‐しゅう【余臭】‥シウ🔗⭐🔉
よ‐しゅう【余臭】‥シウ
残っているにおい。昔からのなごり。「前代の―をとどめる」
よ‐しゅう【余執】‥シフ🔗⭐🔉
よ‐しゅう【余執】‥シフ
〔仏〕心に残って離れない執念。前世から現世に、または現世から来世まで残る執着。無名抄「この歌の入りて侍るが、生死の―ともなるばかり嬉しく侍るなり」
よ‐しゅう【余習】‥シフ🔗⭐🔉
よ‐しゅう【余習】‥シフ
①残っているならわし。余臭。
②〔仏〕煩悩を断った後にも残る煩悩の潜在的影響力。声聞しょうもんと縁覚えんがくの二乗はこれを断つことができないとされる。
よ‐しゅうごう【余集合】‥シフガフ🔗⭐🔉
よ‐しゅうごう【余集合】‥シフガフ
〔数〕(→)補集合に同じ。
よ‐そ【余所・他所】🔗⭐🔉
よそ‐いき【余所行き】🔗⭐🔉
よそ‐いき【余所行き】
(→)「よそゆき」に同じ。
よそ‐がたり【余所語り】🔗⭐🔉
よそ‐がたり【余所語り】
よその物語。世間ばなし。
よそ‐がまし・い【余所がましい】🔗⭐🔉
よそ‐がまし・い【余所がましい】
〔形〕[文]よそがま・し(シク)
よそよそしい様子である。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「あ、―・い、何のお礼」
よそ‐げ【余所げ】🔗⭐🔉
よそ‐げ【余所げ】
よそよそしいさま。関係のない様子。新古今和歌集冬「もみぢ葉はおのが染めたる色ぞかし―における今朝の霜かな」
よそ‐ご【余所子】🔗⭐🔉
よそ‐ご【余所子】
よその子。他人の子。栄華物語布引滝「同じ程―のやうに生ませさせ給へり」
よそ‐ごころ【余所心】🔗⭐🔉
よそ‐ごころ【余所心】
よそよそしい心。
よそ‐ごと【余所事】🔗⭐🔉
よそ‐ごと【余所事】
自分に直接関係のないこと。「―とは思えない」
よそ‐づま【余所妻】🔗⭐🔉
よそ‐づま【余所妻】
①他人の妻。
②他所にかこっておく妻。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「―は知らぬが花よ折らば折れ」
よそ‐ながら【余所ながら】🔗⭐🔉
よそ‐ながら【余所ながら】
①自分に関係したことではないけれども。古今和歌集雑体「―わが身にいとのよるといへばただいつはりにすぐばかりなり」
②よそにいながら。遠く離れていながら。大和物語「―思ひしよりも夏の夜の見はてぬ夢ぞはかなかりける」。「―御多幸を祈る」
③それとなく。間接に。平家物語6「少将―も小督殿見奉る事もやと」
○余所に聞くよそにきく
他人の事のように聞き流す。
⇒よ‐そ【余所・他所】
○余所にするよそにする
いいかげんにして、かえりみない。なおざりにする。「仕事をよそにして遊び歩く」
⇒よ‐そ【余所・他所】
○余所に見るよそにみる
自分と関係のない事のように見る。無関心に見る。
⇒よ‐そ【余所・他所】
○余所に聞くよそにきく🔗⭐🔉
○余所に聞くよそにきく
他人の事のように聞き流す。
⇒よ‐そ【余所・他所】
○余所にするよそにする🔗⭐🔉
○余所にするよそにする
いいかげんにして、かえりみない。なおざりにする。「仕事をよそにして遊び歩く」
⇒よ‐そ【余所・他所】
○余所に見るよそにみる🔗⭐🔉
○余所に見るよそにみる
自分と関係のない事のように見る。無関心に見る。
⇒よ‐そ【余所・他所】
よそ‐びと【余所人】
よその人。他所にいる人。他人。宇津保物語俊蔭「―に聞き見むだにあるに」
よそ‐ほか【余所外】
(「よそ」を強めていう語)まったくほかの所。また、まったく関係のないこと。狂言、悪太郎「誠に―ではなし、伯父と甥との事ぢやによつて」
よそ‐み【余所見】
①よそを見ること。他を見ること。わきみ。よそめ。
②他人の見たところ。よそめ。はため。
③よそごととして見ること。見て見ぬふりをすること。好色一代女5「人の手にさはり腰を叩く程のことは―しておきしが」
よそ‐みみ【余所耳】
よそながら聞くこと。聞くともなく聞くこと。曾丹集「―に鹿のと声を聞きしより」
よそ‐め【余所目】
①よそながら見ること。見るともなしに見ること。万葉集12「―にも君が姿を見てばこそ」
②よそを見るような目つき。わきめ。よこみ。よそみ。為忠百首「あたりなる花の―に」
③他人の見る目。第三者が見たところ。はため。ひとめ。能因本枕草子故殿の御ために「さる人しも―よりほかに褒むるたぐひ多かれ」。日葡辞書「ヨソメヲハバカル」。「―には幸福そうだ」「―を気にする」
④わきから見て見まがうこと。千載和歌集夏「卯の花の―なりけり山里の垣根ばかりに降れる白雪」
よそ‐もの【余所者】
他の土地から来た者。他国者。「―はことばで分かる」「―扱いする」
よそもの‐どころ【装物所】
(ヨソヒモノドコロの約か)節会せちえなどの時、紫宸殿の内に、屏風でかこい倚子いしを立てて天皇が装束をつけた所。
よそ‐ゆき【余所行き】
①よそへ行くこと。他出。外出。
②外出の時に着る衣服。はれぎ。
③比喩的に、特に改まったことば遣いや態度。「―の顔」
よそ‐よそ
①ゆったりと落ちつきはらっているさま。悠々。栄華物語玉台「行者の智恵のけしき―にして」
②山が高くそびえているさま。巍巍ぎぎ。〈類聚名義抄〉
よそ‐よそ【余所余所】
①別れ別れ。別々なこと。また、その所。源氏物語若菜下「―にていとおぼつかなしとて」
②よそよそしいさま。親しくないさま。輔親集「相かたらふ人の―なるに」
③所在をほのめかしていう語。そこらあたり。浄瑠璃、心中重井筒「その銀かねで、―のお山がひとつ買うて見たい」
よそよそ‐し・い【余所余所しい】
〔形〕[文]よそよそ・し(シク)
他人同士のように親しみがなく、冷淡である。他人行儀である。うとうとしい。狭衣物語2「―・しからむもてなしに」。「―・い態度」
よ‐ぞら【夜空】
夜の空。
よそり‐づま【寄夫・寄妻】
関係があると噂を立てられた相手の異性。万葉集14「青嶺ねろにいさよふ雲の―はも」
よそ・る【寄る】
〔自四〕
①自然に寄せられる。引きつけられる。万葉集13「荒山も人し寄すれば―・るとぞいふ」
②打ち寄せられる。寄せる。万葉集20「白波の―・る浜辺に」
③ある異性と関係があると言われる。万葉集14「吾に―・り間はしなる児らしあやに愛かなしも」
よそ・る【装る】
〔他五〕
(「よそう」と「もる」との混交した語)飲食物を器に盛る。
よた【与太】
①知恵の足りない者。役に立たない者。おろかもの。滑稽本、旧観帖「―婆アさまには困るよう」
②でたらめ。ふざけた、くだらないことば。「―を飛ばす」
よだ【依田】
姓氏の一つ。
⇒よだ‐がっかい【依田学海】
よたい‐りつ【預貸率】
銀行の預金残高に対する貸出残高の比率。銀行の資産構成を示す一つの指標。
よ‐たか【夜鷹】
①ヨタカ目ヨタカ科の鳥。カケス大で、全身灰褐色。口は大きく、扁平。昼間は樹枝上か地上に眠り、夕刻から活動して飛びながら虫を捕食。東アジアと南アジアで繁殖し、冬南方に渡る。蚊吸鳥かすいどり。蚊母鳥。怪鴟。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔18〉
よたか(雄)
 ヨタカ
提供:OPO
ヨタカ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
②夜歩きをする者のたとえ。浄瑠璃、大職冠「大事の男を―にして」
③江戸で、夜間、路傍で客をひく下等の売春婦の称。つじぎみ。やほち。根無草「地にたたずむ―は客をとめんことをはかる」
④「夜鷹そば」の略。
⇒よたか‐そば【夜鷹蕎麦】
よたか‐そば【夜鷹蕎麦】
夜ふけまで街上を売り歩く蕎麦屋。また、その売っている蕎麦。夜鳴蕎麦。〈[季]冬〉
⇒よ‐たか【夜鷹】
よだ‐がっかい【依田学海】‥ガク‥
漢学者・演劇評論家・劇作家。名は朝宗、字は百川。佐倉藩士。江戸生れ。演劇改革に参与し、脚本「吉野拾遺名歌誉」など。日記「学海日録」は明治文壇史上、貴重な資料。(1833〜1909)
⇒よだ【依田】
よ‐だき【夜焚・夜抱】
夜、火を焚いてその光に集まる魚をとること。火振ひぶり。〈[季]夏〉
よだき・い
〔形〕
(大分・宮崎県で)億劫おっくうだ。面倒くさい。
よ‐たく【余沢】
先人が残しためぐみ。余徳。「―にあずかる」
よ‐たく【預託】
①あずけまかせること。寄託。
②政府や日本銀行の金を普通金融機関に預け入れること。
⇒よたく‐しょうほう【預託商法】
よたく‐しょうほう【預託商法】‥シヤウハフ
契約者が購入した商品を業者が預かり、その商品から生じた収益を契約者に還元する商法。預託牛飼育など。
⇒よ‐たく【預託】
よ‐だけ【裄丈】
衣服の裄ゆきのたけ。ゆだけ。山家集「―たつ袖にたたへて忍ぶかな袂の滝に落つる涙を」
⇒裄丈も無い
よ‐だけ【節竹】
(一説に「良い竹」「世竹」の意とも)ふしのある竹。節の多い竹。節を含めて切った竹。継体紀「泊瀬の川ゆ流れ来る竹のい組竹―」
よだけ・し
〔形ク〕
①ことごとしい。大層である。大げさである。源氏物語鈴虫「所せく―・き儀式を」
②ものうい。大儀である。面倒である。おっくうである。源氏物語行幸「よろづうひうひしう―・くなりにて侍り」
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
②夜歩きをする者のたとえ。浄瑠璃、大職冠「大事の男を―にして」
③江戸で、夜間、路傍で客をひく下等の売春婦の称。つじぎみ。やほち。根無草「地にたたずむ―は客をとめんことをはかる」
④「夜鷹そば」の略。
⇒よたか‐そば【夜鷹蕎麦】
よたか‐そば【夜鷹蕎麦】
夜ふけまで街上を売り歩く蕎麦屋。また、その売っている蕎麦。夜鳴蕎麦。〈[季]冬〉
⇒よ‐たか【夜鷹】
よだ‐がっかい【依田学海】‥ガク‥
漢学者・演劇評論家・劇作家。名は朝宗、字は百川。佐倉藩士。江戸生れ。演劇改革に参与し、脚本「吉野拾遺名歌誉」など。日記「学海日録」は明治文壇史上、貴重な資料。(1833〜1909)
⇒よだ【依田】
よ‐だき【夜焚・夜抱】
夜、火を焚いてその光に集まる魚をとること。火振ひぶり。〈[季]夏〉
よだき・い
〔形〕
(大分・宮崎県で)億劫おっくうだ。面倒くさい。
よ‐たく【余沢】
先人が残しためぐみ。余徳。「―にあずかる」
よ‐たく【預託】
①あずけまかせること。寄託。
②政府や日本銀行の金を普通金融機関に預け入れること。
⇒よたく‐しょうほう【預託商法】
よたく‐しょうほう【預託商法】‥シヤウハフ
契約者が購入した商品を業者が預かり、その商品から生じた収益を契約者に還元する商法。預託牛飼育など。
⇒よ‐たく【預託】
よ‐だけ【裄丈】
衣服の裄ゆきのたけ。ゆだけ。山家集「―たつ袖にたたへて忍ぶかな袂の滝に落つる涙を」
⇒裄丈も無い
よ‐だけ【節竹】
(一説に「良い竹」「世竹」の意とも)ふしのある竹。節の多い竹。節を含めて切った竹。継体紀「泊瀬の川ゆ流れ来る竹のい組竹―」
よだけ・し
〔形ク〕
①ことごとしい。大層である。大げさである。源氏物語鈴虫「所せく―・き儀式を」
②ものうい。大儀である。面倒である。おっくうである。源氏物語行幸「よろづうひうひしう―・くなりにて侍り」
 ヨタカ
提供:OPO
ヨタカ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
②夜歩きをする者のたとえ。浄瑠璃、大職冠「大事の男を―にして」
③江戸で、夜間、路傍で客をひく下等の売春婦の称。つじぎみ。やほち。根無草「地にたたずむ―は客をとめんことをはかる」
④「夜鷹そば」の略。
⇒よたか‐そば【夜鷹蕎麦】
よたか‐そば【夜鷹蕎麦】
夜ふけまで街上を売り歩く蕎麦屋。また、その売っている蕎麦。夜鳴蕎麦。〈[季]冬〉
⇒よ‐たか【夜鷹】
よだ‐がっかい【依田学海】‥ガク‥
漢学者・演劇評論家・劇作家。名は朝宗、字は百川。佐倉藩士。江戸生れ。演劇改革に参与し、脚本「吉野拾遺名歌誉」など。日記「学海日録」は明治文壇史上、貴重な資料。(1833〜1909)
⇒よだ【依田】
よ‐だき【夜焚・夜抱】
夜、火を焚いてその光に集まる魚をとること。火振ひぶり。〈[季]夏〉
よだき・い
〔形〕
(大分・宮崎県で)億劫おっくうだ。面倒くさい。
よ‐たく【余沢】
先人が残しためぐみ。余徳。「―にあずかる」
よ‐たく【預託】
①あずけまかせること。寄託。
②政府や日本銀行の金を普通金融機関に預け入れること。
⇒よたく‐しょうほう【預託商法】
よたく‐しょうほう【預託商法】‥シヤウハフ
契約者が購入した商品を業者が預かり、その商品から生じた収益を契約者に還元する商法。預託牛飼育など。
⇒よ‐たく【預託】
よ‐だけ【裄丈】
衣服の裄ゆきのたけ。ゆだけ。山家集「―たつ袖にたたへて忍ぶかな袂の滝に落つる涙を」
⇒裄丈も無い
よ‐だけ【節竹】
(一説に「良い竹」「世竹」の意とも)ふしのある竹。節の多い竹。節を含めて切った竹。継体紀「泊瀬の川ゆ流れ来る竹のい組竹―」
よだけ・し
〔形ク〕
①ことごとしい。大層である。大げさである。源氏物語鈴虫「所せく―・き儀式を」
②ものうい。大儀である。面倒である。おっくうである。源氏物語行幸「よろづうひうひしう―・くなりにて侍り」
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
②夜歩きをする者のたとえ。浄瑠璃、大職冠「大事の男を―にして」
③江戸で、夜間、路傍で客をひく下等の売春婦の称。つじぎみ。やほち。根無草「地にたたずむ―は客をとめんことをはかる」
④「夜鷹そば」の略。
⇒よたか‐そば【夜鷹蕎麦】
よたか‐そば【夜鷹蕎麦】
夜ふけまで街上を売り歩く蕎麦屋。また、その売っている蕎麦。夜鳴蕎麦。〈[季]冬〉
⇒よ‐たか【夜鷹】
よだ‐がっかい【依田学海】‥ガク‥
漢学者・演劇評論家・劇作家。名は朝宗、字は百川。佐倉藩士。江戸生れ。演劇改革に参与し、脚本「吉野拾遺名歌誉」など。日記「学海日録」は明治文壇史上、貴重な資料。(1833〜1909)
⇒よだ【依田】
よ‐だき【夜焚・夜抱】
夜、火を焚いてその光に集まる魚をとること。火振ひぶり。〈[季]夏〉
よだき・い
〔形〕
(大分・宮崎県で)億劫おっくうだ。面倒くさい。
よ‐たく【余沢】
先人が残しためぐみ。余徳。「―にあずかる」
よ‐たく【預託】
①あずけまかせること。寄託。
②政府や日本銀行の金を普通金融機関に預け入れること。
⇒よたく‐しょうほう【預託商法】
よたく‐しょうほう【預託商法】‥シヤウハフ
契約者が購入した商品を業者が預かり、その商品から生じた収益を契約者に還元する商法。預託牛飼育など。
⇒よ‐たく【預託】
よ‐だけ【裄丈】
衣服の裄ゆきのたけ。ゆだけ。山家集「―たつ袖にたたへて忍ぶかな袂の滝に落つる涙を」
⇒裄丈も無い
よ‐だけ【節竹】
(一説に「良い竹」「世竹」の意とも)ふしのある竹。節の多い竹。節を含めて切った竹。継体紀「泊瀬の川ゆ流れ来る竹のい組竹―」
よだけ・し
〔形ク〕
①ことごとしい。大層である。大げさである。源氏物語鈴虫「所せく―・き儀式を」
②ものうい。大儀である。面倒である。おっくうである。源氏物語行幸「よろづうひうひしう―・くなりにて侍り」
よそ‐びと【余所人】🔗⭐🔉
よそ‐びと【余所人】
よその人。他所にいる人。他人。宇津保物語俊蔭「―に聞き見むだにあるに」
よそ‐ほか【余所外】🔗⭐🔉
よそ‐ほか【余所外】
(「よそ」を強めていう語)まったくほかの所。また、まったく関係のないこと。狂言、悪太郎「誠に―ではなし、伯父と甥との事ぢやによつて」
よそ‐み【余所見】🔗⭐🔉
よそ‐み【余所見】
①よそを見ること。他を見ること。わきみ。よそめ。
②他人の見たところ。よそめ。はため。
③よそごととして見ること。見て見ぬふりをすること。好色一代女5「人の手にさはり腰を叩く程のことは―しておきしが」
よそ‐みみ【余所耳】🔗⭐🔉
よそ‐みみ【余所耳】
よそながら聞くこと。聞くともなく聞くこと。曾丹集「―に鹿のと声を聞きしより」
よそ‐もの【余所者】🔗⭐🔉
よそ‐もの【余所者】
他の土地から来た者。他国者。「―はことばで分かる」「―扱いする」
よそ‐ゆき【余所行き】🔗⭐🔉
よそ‐ゆき【余所行き】
①よそへ行くこと。他出。外出。
②外出の時に着る衣服。はれぎ。
③比喩的に、特に改まったことば遣いや態度。「―の顔」
よっ‐ぽど【余っ程】🔗⭐🔉
よっ‐ぽど【余っ程】
〔名・副〕
(ヨキ(善)ホドの転。「余」は江戸中期以後の当て字)
①程よいさま。適宜。日葡辞書「シロノフシン(普請)ヲヨッポドニシナイタ」
②かなり。相当。ほとんど。日葡辞書「コノコトヲヨッポドキ(聞)キハタ(果)イタ」。「―ましだ」
③(1を逆説的に)いい加減。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―にあがけよ(ふざけるのもいい加減にせよ)そこなぬく奴め」
④すんでのところで。ほとんどもう。「―言ってやろうと思った」
→よほど
よ‐づめ【余詰め】🔗⭐🔉
よ‐づめ【余詰め】
詰将棋で、作者の意図した正解以外の詰め方があり、不完全であること。
よ‐ない【余内・余荷】🔗⭐🔉
よ‐ない【余内・余荷】
江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。
よ‐の‐ぎ【余の儀】🔗⭐🔉
よ‐の‐ぎ【余の儀】
ほかのこと。「―にあらず」
よ‐まき【余蒔】🔗⭐🔉
よ‐まき【余蒔】
とれた種子を、その年のうちにまくこと。また、遅くまくこと。〈俚言集覧〉
[漢]余1🔗⭐🔉
余1 字形
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部5画/7画/4530・4D3E〕
〔音〕ヨ(呉)(漢)
[意味]
自称の代名詞。われ。自分。予。「余は如何いかにして基督キリスト信徒となりし乎か」「余輩」
[解字]
会意。「
)部5画/7画/4530・4D3E〕
〔音〕ヨ(呉)(漢)
[意味]
自称の代名詞。われ。自分。予。「余は如何いかにして基督キリスト信徒となりし乎か」「余輩」
[解字]
会意。「 」(=スコップの形)+「八」(=分散させる)。スコップで土を押し広げる意。転じて、ゆったりとのばす意。一人称に用いるのは仮借。
」(=スコップの形)+「八」(=分散させる)。スコップで土を押し広げる意。転じて、ゆったりとのばす意。一人称に用いるのは仮借。
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部5画/7画/4530・4D3E〕
〔音〕ヨ(呉)(漢)
[意味]
自称の代名詞。われ。自分。予。「余は如何いかにして基督キリスト信徒となりし乎か」「余輩」
[解字]
会意。「
)部5画/7画/4530・4D3E〕
〔音〕ヨ(呉)(漢)
[意味]
自称の代名詞。われ。自分。予。「余は如何いかにして基督キリスト信徒となりし乎か」「余輩」
[解字]
会意。「 」(=スコップの形)+「八」(=分散させる)。スコップで土を押し広げる意。転じて、ゆったりとのばす意。一人称に用いるのは仮借。
」(=スコップの形)+「八」(=分散させる)。スコップで土を押し広げる意。転じて、ゆったりとのばす意。一人称に用いるのは仮借。
[漢]余2🔗⭐🔉
余2 字形
 筆順
筆順
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部5画/7画/教育/4530・4D3E〕
[餘] 字形
)部5画/7画/教育/4530・4D3E〕
[餘] 字形
 〔食部7画/16画/8117・7131〕
〔音〕ヨ(呉)(漢)
〔訓〕あまる・あます
[意味]
①ありあまって残っている。あまり。あます。「一年の余もかかった」「余分・余白・残余・酔余・三年余」
②(その)ほか。別。「余の儀でもない」「余人・余罪・余所よそ・余談」
[解字]
形声。「食」+音符「余」(=ゆとりがある)。食物が十分にある意。
[下ツキ
窮余・刑余・月余・蘖余・残余・尺余・旬余・時余・爾余・自余・丈余・剰余・緒余・睡余・酔余・寸余・有余・零余
[難読]
余所よそ・余波なごり
〔食部7画/16画/8117・7131〕
〔音〕ヨ(呉)(漢)
〔訓〕あまる・あます
[意味]
①ありあまって残っている。あまり。あます。「一年の余もかかった」「余分・余白・残余・酔余・三年余」
②(その)ほか。別。「余の儀でもない」「余人・余罪・余所よそ・余談」
[解字]
形声。「食」+音符「余」(=ゆとりがある)。食物が十分にある意。
[下ツキ
窮余・刑余・月余・蘖余・残余・尺余・旬余・時余・爾余・自余・丈余・剰余・緒余・睡余・酔余・寸余・有余・零余
[難読]
余所よそ・余波なごり
 筆順
筆順
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部5画/7画/教育/4530・4D3E〕
[餘] 字形
)部5画/7画/教育/4530・4D3E〕
[餘] 字形
 〔食部7画/16画/8117・7131〕
〔音〕ヨ(呉)(漢)
〔訓〕あまる・あます
[意味]
①ありあまって残っている。あまり。あます。「一年の余もかかった」「余分・余白・残余・酔余・三年余」
②(その)ほか。別。「余の儀でもない」「余人・余罪・余所よそ・余談」
[解字]
形声。「食」+音符「余」(=ゆとりがある)。食物が十分にある意。
[下ツキ
窮余・刑余・月余・蘖余・残余・尺余・旬余・時余・爾余・自余・丈余・剰余・緒余・睡余・酔余・寸余・有余・零余
[難読]
余所よそ・余波なごり
〔食部7画/16画/8117・7131〕
〔音〕ヨ(呉)(漢)
〔訓〕あまる・あます
[意味]
①ありあまって残っている。あまり。あます。「一年の余もかかった」「余分・余白・残余・酔余・三年余」
②(その)ほか。別。「余の儀でもない」「余人・余罪・余所よそ・余談」
[解字]
形声。「食」+音符「余」(=ゆとりがある)。食物が十分にある意。
[下ツキ
窮余・刑余・月余・蘖余・残余・尺余・旬余・時余・爾余・自余・丈余・剰余・緒余・睡余・酔余・寸余・有余・零余
[難読]
余所よそ・余波なごり
広辞苑に「余」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む