複数辞典一括検索+![]()
![]()
し‐か【知客】🔗⭐🔉
し‐か【知客】
(唐音)禅寺で、客を接待する役僧。
しった‐か‐ぶり【知ったか振り】🔗⭐🔉
しった‐か‐ぶり【知ったか振り】
それほどよくは、または、まるで知らないのに、知っているようなふうを(得意になって)すること。「―してしゃべる」
しった‐ふり【知った振り】🔗⭐🔉
しった‐ふり【知った振り】
(→)「しったかぶり」に同じ。日葡辞書「シッタブリ、また、シッタフリ」
○知らざるを知らずとせよしらざるをしらずとせよ🔗⭐🔉
○知らざるを知らずとせよしらざるをしらずとせよ
[論語為政]知らないことを知ったように見せかけるな、知らないことを知らないと言明するのが、真に知るということである。
⇒し・る【知る】
しら‐じ【白地】‥ヂ
①瓦・陶器などの、まだ焼かない生土のままのもの。
②紙・布などの、まだ何も書いたり染めたりしていない、白い地のままのもの。
③(「白地娘」の略)まだ男子に接せぬ女。処女。きむすめ。
④(女房詞)すりばち。
⇒しらじ‐けいほう【白地刑法】
⇒しらじ‐こぎって【白地小切手】
⇒しらじしき‐うらがき【白地式裏書】
⇒しらじ‐てがた【白地手形】
⇒しらじ‐ひきうけ【白地引受】
⇒しらじ‐ふりだし【白地振出】
しらじ‐けいほう【白地刑法】‥ヂ‥ハフ
法律が一定の刑罰だけを規定し、これに対する犯罪の規定を他の法令に委任している刑罰法規。刑法の局外中立命令違反罪の類。空白刑罰法規。
⇒しら‐じ【白地】
しら‐しげどう【白重籐】
重籐の弓の一種。黒く塗った上に生地のままの細割りの籐で繁く巻いた弓。
しらじ‐こぎって【白地小切手】‥ヂ‥
要件の全部または一部を後日、取得者に補充させる意思で、わざと白地のまま発行された小切手。→白地手形。
⇒しら‐じ【白地】
しらじしき‐うらがき【白地式裏書】‥ヂ‥
被裏書人(譲受人)を表示せずにされる裏書。裏書人の署名以外に、裏書の日付・宛所・指図文句などを記載することがある。
⇒しら‐じ【白地】
しらじ‐てがた【白地手形】‥ヂ‥
手形行為をなす者が手形取得者に、後日手形要件の全部または一部を補充させる意思で、わざと手形要件を欠いた未完成手形に署名したもの。
⇒しら‐じ【白地】
しらじ‐ひきうけ【白地引受】‥ヂ‥
既存の白地手形に支払人が引受署名すること、またはみずから白地手形をつくって引受署名すること。このような手形を白地引受手形という。なお、保証人として署名する場合は白地保証といい、同じく有効。
⇒しら‐じ【白地】
しらじ‐ふりだし【白地振出】‥ヂ‥
振出人が自分の署名だけをして白地手形・白地小切手を振り出すこと。
⇒しら‐じ【白地】
しら‐しぼり【白搾り・白絞り】
菜種・胡麻・大豆・綿実の種子を加熱せずに搾り取った油。しろあぶら。しろしぼり。↔黒搾り
しらし‐め・す【知らしめす】
〔他四〕
(「知る」の尊敬語「しらす」よりさらに敬意の強い言い方)お治めなさる。しろしめす。万葉集18「葦原のみづほの国をあまくだり―・しけるすめろきの」
しらしめ‐ゆ【白絞油】
菜種油を精製した淡黄色の油。また、大豆・綿の実の精製油。
しら‐じら【白白】
(シラシラとも)
①いかにも白いさま。また、夜が次第に明けて白むさま。公任集「―としらけたる夜の月影に」。「夜が―と明ける」
②あからさまなこと。はっきり。閑吟集「面影ばかり遺して東の方へ下りし人の名は―と云ふまじ」
③興ざめであるさま。また、そらぞらしいさま。「―とした気持」
⇒しらじら‐あけ【白白明け】
しらじら‐あけ【白白明け】
夜のあけゆく頃。あけがた。
⇒しら‐じら【白白】
しらじら‐し・い【白白しい】
〔形〕[文]しらじら・し(シク)
(シラシラシとも)
①いかにも白く見える。白い。〈類聚名義抄〉
②興ざめである。あじきない。枕草子48「美々しうてをかしき君たちも、随身なきはいと―・し」。「―・いその場の空気」
③しらばくれている。裏の気持が見えすいている。そらぞらしい。「―・いおせじを言う」
しら‐す【白子】
①シロウオの別称。
②カタクチイワシ・ウナギ・アユなどの稚魚の称。
⇒しらす‐うなぎ【白子鰻】
⇒しらす‐ぼし【白子乾し】
しら‐す【白洲・白州・白沙】
①白い砂の洲。
②邸宅の玄関前または庭などの、白い砂の敷いてある所。玄関先。庭先。太平記10「―の上に物の具脱ぎ棄てて一面に並み居て」
③能舞台と観覧席との間で、礫こいしを敷いてあるところ。→能舞台(図)。
④(礫が敷いてあったからいう)訴訟を裁断し、または罪人を取り調べる場所。転じて、奉行所。法廷。おしらす。
しら‐す【白砂】
大隅・薩摩両半島、都城付近に広く分布する火山灰・軽石の層。現在の鹿児島湾を形成している昔の姶良あいら火山・阿多火山などの噴出物が堆積したもの。「―台地」
しら・す【知らす】
[一]〔他五〕
①(「しる」に尊敬の意を表す助動詞「す」の付いたもの)お治めになる。しろす。万葉集18「天の日嗣と―・しくる君の御代御代」
②(→)「知らせる」に同じ。
[二]〔他下二〕
⇒しらせる(下一)
しら‐ず【知らず】
①(「―、…か」の形で)見当がつかない意を表す。さあ、…のかしら。平家物語3「―、われ餓鬼道に尋ね来たるか」
②(「…は―」の形で)問題として取りあげない意を表す。…はさておいて。平家物語10「天竺・震旦は―、わが朝には」
⇒しらず‐がお【知らず顔】
⇒しらず‐さんてん【知らず三点】
⇒しらず‐しらず【知らず識らず・不知不識】
⇒しらず‐よみ【知らず詠み】
じら・す【焦らす】
〔他五〕
からかったり、理由もなく待たせたりして、人の気をいらだたせる。じれさせる。契情買虎之巻「―・しなさりやすな」。「―・してなかなか話さない」「対戦相手を―・す」
しらす‐うなぎ【白子鰻】
ウナギ属魚類の幼魚の呼称。孵化ふか後の大回遊を終え、河川に入る前の半透明のもの。養殖用の種苗。
⇒しら‐す【白子】
しらず‐がお【知らず顔】‥ガホ
(→)「しらんかお」に同じ。落窪物語1「さるべき受領あらば、―にてくれてやらんとしつるものを」
⇒しら‐ず【知らず】
しら‐すげ【白菅】
スゲの一種。日本をはじめアジア温帯に広く自生。高さ約30〜70センチメートル。葉は質柔らかく、長くてやや幅広く、淡緑色で白色がち。5〜6月頃、茎頂に花穂をつける。
⇒しらすげ‐の【白菅の】
しらすげ‐の【白菅の】
〔枕〕
「まの(真野)」「知る」にかかる。
⇒しら‐すげ【白菅】
しらず‐さんてん【知らず三点】
俳諧の点者が点付けをするのに、わからない句は中位の三点にすること。
⇒しら‐ず【知らず】
しらず‐しらず【知らず識らず・不知不識】
無意識のうちに。ついつい。思わずしらず。「―涙があふれてきた」
⇒しら‐ず【知らず】
しら‐すな【白砂】
白い砂。
しらす‐ぼし【白子乾し】
カタクチイワシなどの稚魚を煮干しにしたもの。〈[季]春〉
⇒しら‐す【白子】
しら‐ずみ【白炭】
⇒しろずみ
しら‐ずみ【白墨】
胡粉ごふんを練り固めた白色の絵具。しろずみ。
しらず‐よみ【知らず詠み】
知らぬふりをして歌を詠むこと。伊勢物語「男―によみける」
⇒しら‐ず【知らず】
しら‐すり【白磨】
白くみがくこと。太平記6「三十六差いたる―の銀筈しろがねはずの大中黒の矢に」
しらせ【知らせ・報せ】
①知らせること。また、その内容。報知。通知。「悪い―」
②事の起こるきざし。前兆。
③歌舞伎で、舞台転換や道具が変わる時、また浄瑠璃にかかる時など、合図に打つ拍子木。詳しくは「道具替りの知らせ」という。
⇒しらせ‐ぶみ【知らせ文】
しらせ【白瀬】
姓氏の一つ。
⇒しらせ‐のぶ【白瀬矗】
しらせ‐のぶ【白瀬矗】
陸軍軍人・探検家。出羽金浦このうら村(現、秋田県にかほ市)生れ。予備役編入後、1912年(明治45)開南丸で南極大陸に上陸、1月28日南緯80度5分に到達し、大和やまと雪原と命名した。(1861〜1946)
白瀬矗
提供:毎日新聞社
 ⇒しらせ【白瀬】
しらせ‐ぶみ【知らせ文】
先方へ知らせる書面。通知書。通知状。
⇒しらせ【知らせ・報せ】
しら・せる【知らせる・報せる】
〔他下一〕[文]しら・す(下二)
他人に通知して、その人が知るようにする。「時を―・せる」「合格を―・せる」
しら‐た【白太】
①材の白い杉。
②(→)辺材に同じ。〈日葡辞書〉↔赤身
しら‐だいしゅ【白大衆】
官位を持たない僧侶たち。平家物語1「―・神人・宮仕・専当みちみちて」
しら‐たえ【白妙・白
⇒しらせ【白瀬】
しらせ‐ぶみ【知らせ文】
先方へ知らせる書面。通知書。通知状。
⇒しらせ【知らせ・報せ】
しら・せる【知らせる・報せる】
〔他下一〕[文]しら・す(下二)
他人に通知して、その人が知るようにする。「時を―・せる」「合格を―・せる」
しら‐た【白太】
①材の白い杉。
②(→)辺材に同じ。〈日葡辞書〉↔赤身
しら‐だいしゅ【白大衆】
官位を持たない僧侶たち。平家物語1「―・神人・宮仕・専当みちみちて」
しら‐たえ【白妙・白 】‥タヘ
⇒しろたえ
しら‐たき【白滝】
①白布をかけたように流れ落ちる滝。
②糸ごんにゃくのさらに細く作ったもの。
しらたき‐いせき【白滝遺跡】‥ヰ‥
北海道網走支庁遠軽えんがる町白滝にある旧石器時代の遺跡。湧別ゆうべつ川とその支流沿いの段丘上を中心に数多く残る石器出土地点からなる。
しら‐たず【白田鶴】‥タヅ
ソデグロヅルの異称。兼盛集「―の天の原より飛びつるは」
しら‐たま【白玉・真珠】
①白色の美しい玉。はくぎょく。古事記上「赤玉は緒さへ光れど―の君が装ひし貴くありけり」
②真珠しんじゅの古名。あこやだま。武烈紀「あが欲る玉の鰒あわび―」
③白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子。汁粉に入れたり、冷やして白砂糖をかけたりして食べる。
④白玉椿の略。
⇒しらたま‐こ【白玉粉】
⇒しらたま‐つばき【白玉椿】
⇒しらたま‐の‐き【白玉の木】
⇒しらたま‐ひめ【白玉姫】
⇒しらたま‐ゆり【白玉百合】
しらたま‐こ【白玉粉】
糯米もちごめを洗い水に漬けたのち水切りし、水を加えながら磨砕し、水にさらし、乾燥させたもの。以前は寒中に作ったので、寒晒し粉ともいう。〈[季]夏〉
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐つばき【白玉椿】
白い花の咲くツバキ。催馬楽、高砂「高砂のをのへに立てる―」
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐の‐き【白玉の木】
ツツジ科の常緑小低木。本州と北海道の亜高山・高山帯に生ずる。長い地下茎があり、地上部は高さ10〜30センチメートルで斜上、しばしば群生する。葉は互生し卵形、質は硬い。夏に枝端に花穂を直立し、スズランに似た小白花を数個下向きに開く。果実は球形で白色。シロモノ。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐ひめ【白玉姫】
霞の異称。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐ゆり【白玉百合】
〔植〕カノコユリの一変種。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたみ【疝】
腹が急に痛み出す病。疝気せんき。〈倭名類聚鈔3〉
し‐らち【為埒】
処置して埒をあけること。あとかたづけ。しまつ。歌舞伎、阿国御前化粧鏡「どの道―は付けてやる」
しら‐ち【白血】
白帯下はくたいげの異称。〈伊呂波字類抄〉
しら‐ちゃ【白茶】
白みがかった茶色。うす茶色。浄瑠璃、心中宵庚申「―の死装束」
⇒しらちゃ・ける【白茶ける】
しらちゃ・ける【白茶ける】
〔自下一〕
色があせて白っぽくなる。
⇒しら‐ちゃ【白茶】
しら‐つか【白柄】
白い鮫皮さめがわをかけた刀の柄。だてな風俗。世間胸算用3「―の脇指」
⇒しらつか‐ぐみ【白柄組・白
】‥タヘ
⇒しろたえ
しら‐たき【白滝】
①白布をかけたように流れ落ちる滝。
②糸ごんにゃくのさらに細く作ったもの。
しらたき‐いせき【白滝遺跡】‥ヰ‥
北海道網走支庁遠軽えんがる町白滝にある旧石器時代の遺跡。湧別ゆうべつ川とその支流沿いの段丘上を中心に数多く残る石器出土地点からなる。
しら‐たず【白田鶴】‥タヅ
ソデグロヅルの異称。兼盛集「―の天の原より飛びつるは」
しら‐たま【白玉・真珠】
①白色の美しい玉。はくぎょく。古事記上「赤玉は緒さへ光れど―の君が装ひし貴くありけり」
②真珠しんじゅの古名。あこやだま。武烈紀「あが欲る玉の鰒あわび―」
③白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子。汁粉に入れたり、冷やして白砂糖をかけたりして食べる。
④白玉椿の略。
⇒しらたま‐こ【白玉粉】
⇒しらたま‐つばき【白玉椿】
⇒しらたま‐の‐き【白玉の木】
⇒しらたま‐ひめ【白玉姫】
⇒しらたま‐ゆり【白玉百合】
しらたま‐こ【白玉粉】
糯米もちごめを洗い水に漬けたのち水切りし、水を加えながら磨砕し、水にさらし、乾燥させたもの。以前は寒中に作ったので、寒晒し粉ともいう。〈[季]夏〉
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐つばき【白玉椿】
白い花の咲くツバキ。催馬楽、高砂「高砂のをのへに立てる―」
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐の‐き【白玉の木】
ツツジ科の常緑小低木。本州と北海道の亜高山・高山帯に生ずる。長い地下茎があり、地上部は高さ10〜30センチメートルで斜上、しばしば群生する。葉は互生し卵形、質は硬い。夏に枝端に花穂を直立し、スズランに似た小白花を数個下向きに開く。果実は球形で白色。シロモノ。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐ひめ【白玉姫】
霞の異称。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐ゆり【白玉百合】
〔植〕カノコユリの一変種。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたみ【疝】
腹が急に痛み出す病。疝気せんき。〈倭名類聚鈔3〉
し‐らち【為埒】
処置して埒をあけること。あとかたづけ。しまつ。歌舞伎、阿国御前化粧鏡「どの道―は付けてやる」
しら‐ち【白血】
白帯下はくたいげの異称。〈伊呂波字類抄〉
しら‐ちゃ【白茶】
白みがかった茶色。うす茶色。浄瑠璃、心中宵庚申「―の死装束」
⇒しらちゃ・ける【白茶ける】
しらちゃ・ける【白茶ける】
〔自下一〕
色があせて白っぽくなる。
⇒しら‐ちゃ【白茶】
しら‐つか【白柄】
白い鮫皮さめがわをかけた刀の柄。だてな風俗。世間胸算用3「―の脇指」
⇒しらつか‐ぐみ【白柄組・白 組】
しらつか‐ぐみ【白柄組・白
組】
しらつか‐ぐみ【白柄組・白 組】
江戸前期、旗本奴はたもとやっこの徒党の一団。刀の柄を白糸で巻き、白馬にまたがって、好んで異様の風をなし、幕府上層部に反発した。はじめ水野十郎左衛門を盟主とし、江戸市中を横行して町人に迷惑を及ぼすこと多く、1686年(貞享3)に至って幕府に処断された。
⇒しら‐つか【白柄】
しら‐つきげ【白月毛】
馬の毛色の名。白みがかった月毛。しろつきげ。
しら‐つち【白土】
①白色の土。はくど。〈倭名類聚鈔1〉
②陶土とうど。〈本草和名〉
③漆喰しっくい。
しらっ‐と
〔副〕
①しらけたさま。「―した雰囲気」
②そっけ無いさま。「会っても―して挨拶もしない」
しらっ‐ぱく・れる
〔自下一〕
(→)「しらばくれる」に同じ。
シラップ【syrup】
⇒シロップ
しら‐つゆ【白露】
白く光って見える露。露の美称。〈[季]秋〉。万葉集20「秋草に置く―の厭かずのみ」
⇒しらつゆ‐の【白露の】
しらつゆ‐の【白露の】
〔枕〕
「け(消)」「おく」「たま」にかかる。
⇒しら‐つゆ【白露】
しら‐つる【白鶴】
ソデグロツルの異称。
しら‐つるばみ【白橡】
白みがかったつるばみ色。鈍色にびいろの薄いもの。宇津保物語吹上上「青き―の唐衣」
しら‐と【白砥】
粗砥あらとと仕上砥との間に用いる白色の砥石。愛媛県宇和島の名産。
しらとほふ
〔枕〕
「にひ(新)」にかかる。
しら‐とり【白とり】
(関西以西で)醤油の表面に浮かぶ白いかび。関東以東では「さざみ」という。
しら‐とり【白鳥】
①白い羽毛の鳥。
②はくちょう。
⇒しらとり‐の【白鳥の】
⇒しらとり‐の‐は【白鳥の羽】
しらとり【白鳥】
姓氏の一つ。
⇒しらとり‐くらきち【白鳥庫吉】
しらとり‐くらきち【白鳥庫吉】
東洋史学者。上総茂原生れ。東大教授。近代的東洋史学を確立し、北方民族および西域諸国の研究を開拓。東洋文庫研究部を創設。著「西域史研究」など。(1865〜1942)
⇒しらとり【白鳥】
しらとり‐の【白鳥の】
〔枕〕
「さぎ(鷺)」「とば(鳥羽)」にかかる。
⇒しら‐とり【白鳥】
しらとり‐の‐は【白鳥の羽】
矢羽に用いる、白色の鷲の羽。
⇒しら‐とり【白鳥】
しらとり‐の‐みささぎ【白鳥陵】
日本武尊やまとたけるのみことの陵。死後、白鳥に化してとまった所に建てたというもの。伊勢国能褒野のぼののほか、大和やまと・河内にもあった。
しら‐なみ【白波・白浪】
①白く泡立つなみ。
②(「白波はくはの賊」の「白波」を訓読したもの)盗賊の異称。
⇒しらなみ‐の【白波の】
⇒しらなみ‐もの【白浪物】
しらなみごにんおとこ【白浪五人男】‥ヲトコ
歌舞伎脚本「青砥稿花紅彩画あおとぞうしはなのにしきえ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1862年(文久2)初演。3世歌川豊国(初世国貞)の見立錦絵に暗示を得て、日本駄右衛門・忠信利平・南郷力丸・赤星十三郎(重三)・弁天小僧の5人を扱った白浪物。
→文献資料[青砥稿花紅彩画(四幕目)]
しらなみごにんおんな【白浪五人女】‥ヲンナ
歌舞伎脚本「処女評判善悪鏡むすめひょうばんぜんあくかがみ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1865年(慶応1)初演。「白浪五人男」にならい、須走お熊・雲切お六・おさらばお伝・木鼠お吉・山猫おさんの5人の女賊を扱い、津山の孝女お浅の物語を織り込む。
しらなみ‐の【白波の】
〔枕〕
「よる」「かへる」などにかかる。
⇒しら‐なみ【白波・白浪】
しらなみ‐もの【白浪物】
盗賊を主人公とする歌舞伎狂言などの総称。講談の松林しょうりん伯円、歌舞伎の河竹黙阿弥が得意とした。「白浪五人男」「白浪五人女」「三人吉三」「鼠小僧」の類。
⇒しら‐なみ【白波・白浪】
しら‐なわ【白縄】‥ナハ
鵜川などで、魚の逃げるのを防ぐためにひきめぐらした縄。散木奇歌集「ますらをは鵜川の瀬々に鮎とると引く―のたえずもあるかな」
しら‐に【白煮】
調味料を用いずに或いは塩味だけで煮たもの。しらたき。本朝桜陰比事「汁は鱸の―鱠にきすご」
しら‐に【知らに】
(ニは打消の助動詞ズの連用形の古形)知らないで。万葉集5「言はむすべ為むすべ―」
しら‐にきて【白和幣】
穀かじの皮の繊維で織った白布の幣帛。古事記上「下枝に―青にきてを取り垂しでて」→にきて
しらぬい【不知火・白縫】‥ヌヒ
[一]〔名〕
(景行天皇が海路火の国(肥前・肥後)に熊襲くまそを征伐した時、暗夜に多くの火が海上に現れ、無事に船を岸につけたが、何人なんぴとの火とも知られなかったという)九州の八代やつしろ海に、旧暦7月末頃の夜に見える無数の火影。沖に浮かぶイカ釣船の漁火が水面付近にただよう冷気によって屈折し、さまざまな形に変化してみえる現象。〈[季]秋〉
[二]〔枕〕
「つくし(筑紫)」にかかる。上代特殊仮名遣のうえから、「ひ」を「火」と解することはできない。「領しらぬ霊ひ憑つく」意からとも、また「知らぬ日(多くの日数)を尽くして行く地」の意から筑紫にかかるともいう。
⇒しらぬい‐かい【不知火海】
⇒しらぬい‐の【白縫の】
しらぬい‐かい【不知火海】‥ヌヒ‥
八代やつしろ海の別称。
⇒しらぬい【不知火・白縫】
しらぬい‐がた【不知火型】‥ヌヒ‥
横綱の土俵入りの型の一つ。せり上がりのとき、両腕を左右に大きく開くのが特徴。攻めを表す。綱の後方の結び目は左右に二つの輪を作り中央の輪を立てる。11代横綱不知火光右衛門が創始。→雲竜型
しらぬい‐の【白縫の】‥ヌヒ‥
〔枕〕
「つくし(筑紫)」にかかる。
⇒しらぬい【不知火・白縫】
しらぬいものがたり【白縫譚】‥ヌヒ‥
合巻ごうかん中の最大長編。90編。柳下亭種員・2世種彦・柳水亭種清の合作。1849〜85年(嘉永2〜明治18)刊。豊後臼杵うすきの城主大友宗麟の女むすめ若菜姫が蜘蛛の妖術を行なって父の仇筑紫の太守菊地氏を討ち果たそうとする筋。
しらぬ‐がお【不知顔】‥ガホ
(→)「しらんかお」に同じ。栄華物語初花「いざ、いと―なるはわろし」
⇒しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】
しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】‥ガホ‥ヱ
知らぬ顔をして少しもとりあわないこと。そしらぬふりをすること。また、その人。浮世風呂2「何を云つても知らん顔の半兵衛さんだ」。「―をきめこむ」
⇒しらぬ‐がお【不知顔】
組】
江戸前期、旗本奴はたもとやっこの徒党の一団。刀の柄を白糸で巻き、白馬にまたがって、好んで異様の風をなし、幕府上層部に反発した。はじめ水野十郎左衛門を盟主とし、江戸市中を横行して町人に迷惑を及ぼすこと多く、1686年(貞享3)に至って幕府に処断された。
⇒しら‐つか【白柄】
しら‐つきげ【白月毛】
馬の毛色の名。白みがかった月毛。しろつきげ。
しら‐つち【白土】
①白色の土。はくど。〈倭名類聚鈔1〉
②陶土とうど。〈本草和名〉
③漆喰しっくい。
しらっ‐と
〔副〕
①しらけたさま。「―した雰囲気」
②そっけ無いさま。「会っても―して挨拶もしない」
しらっ‐ぱく・れる
〔自下一〕
(→)「しらばくれる」に同じ。
シラップ【syrup】
⇒シロップ
しら‐つゆ【白露】
白く光って見える露。露の美称。〈[季]秋〉。万葉集20「秋草に置く―の厭かずのみ」
⇒しらつゆ‐の【白露の】
しらつゆ‐の【白露の】
〔枕〕
「け(消)」「おく」「たま」にかかる。
⇒しら‐つゆ【白露】
しら‐つる【白鶴】
ソデグロツルの異称。
しら‐つるばみ【白橡】
白みがかったつるばみ色。鈍色にびいろの薄いもの。宇津保物語吹上上「青き―の唐衣」
しら‐と【白砥】
粗砥あらとと仕上砥との間に用いる白色の砥石。愛媛県宇和島の名産。
しらとほふ
〔枕〕
「にひ(新)」にかかる。
しら‐とり【白とり】
(関西以西で)醤油の表面に浮かぶ白いかび。関東以東では「さざみ」という。
しら‐とり【白鳥】
①白い羽毛の鳥。
②はくちょう。
⇒しらとり‐の【白鳥の】
⇒しらとり‐の‐は【白鳥の羽】
しらとり【白鳥】
姓氏の一つ。
⇒しらとり‐くらきち【白鳥庫吉】
しらとり‐くらきち【白鳥庫吉】
東洋史学者。上総茂原生れ。東大教授。近代的東洋史学を確立し、北方民族および西域諸国の研究を開拓。東洋文庫研究部を創設。著「西域史研究」など。(1865〜1942)
⇒しらとり【白鳥】
しらとり‐の【白鳥の】
〔枕〕
「さぎ(鷺)」「とば(鳥羽)」にかかる。
⇒しら‐とり【白鳥】
しらとり‐の‐は【白鳥の羽】
矢羽に用いる、白色の鷲の羽。
⇒しら‐とり【白鳥】
しらとり‐の‐みささぎ【白鳥陵】
日本武尊やまとたけるのみことの陵。死後、白鳥に化してとまった所に建てたというもの。伊勢国能褒野のぼののほか、大和やまと・河内にもあった。
しら‐なみ【白波・白浪】
①白く泡立つなみ。
②(「白波はくはの賊」の「白波」を訓読したもの)盗賊の異称。
⇒しらなみ‐の【白波の】
⇒しらなみ‐もの【白浪物】
しらなみごにんおとこ【白浪五人男】‥ヲトコ
歌舞伎脚本「青砥稿花紅彩画あおとぞうしはなのにしきえ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1862年(文久2)初演。3世歌川豊国(初世国貞)の見立錦絵に暗示を得て、日本駄右衛門・忠信利平・南郷力丸・赤星十三郎(重三)・弁天小僧の5人を扱った白浪物。
→文献資料[青砥稿花紅彩画(四幕目)]
しらなみごにんおんな【白浪五人女】‥ヲンナ
歌舞伎脚本「処女評判善悪鏡むすめひょうばんぜんあくかがみ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1865年(慶応1)初演。「白浪五人男」にならい、須走お熊・雲切お六・おさらばお伝・木鼠お吉・山猫おさんの5人の女賊を扱い、津山の孝女お浅の物語を織り込む。
しらなみ‐の【白波の】
〔枕〕
「よる」「かへる」などにかかる。
⇒しら‐なみ【白波・白浪】
しらなみ‐もの【白浪物】
盗賊を主人公とする歌舞伎狂言などの総称。講談の松林しょうりん伯円、歌舞伎の河竹黙阿弥が得意とした。「白浪五人男」「白浪五人女」「三人吉三」「鼠小僧」の類。
⇒しら‐なみ【白波・白浪】
しら‐なわ【白縄】‥ナハ
鵜川などで、魚の逃げるのを防ぐためにひきめぐらした縄。散木奇歌集「ますらをは鵜川の瀬々に鮎とると引く―のたえずもあるかな」
しら‐に【白煮】
調味料を用いずに或いは塩味だけで煮たもの。しらたき。本朝桜陰比事「汁は鱸の―鱠にきすご」
しら‐に【知らに】
(ニは打消の助動詞ズの連用形の古形)知らないで。万葉集5「言はむすべ為むすべ―」
しら‐にきて【白和幣】
穀かじの皮の繊維で織った白布の幣帛。古事記上「下枝に―青にきてを取り垂しでて」→にきて
しらぬい【不知火・白縫】‥ヌヒ
[一]〔名〕
(景行天皇が海路火の国(肥前・肥後)に熊襲くまそを征伐した時、暗夜に多くの火が海上に現れ、無事に船を岸につけたが、何人なんぴとの火とも知られなかったという)九州の八代やつしろ海に、旧暦7月末頃の夜に見える無数の火影。沖に浮かぶイカ釣船の漁火が水面付近にただよう冷気によって屈折し、さまざまな形に変化してみえる現象。〈[季]秋〉
[二]〔枕〕
「つくし(筑紫)」にかかる。上代特殊仮名遣のうえから、「ひ」を「火」と解することはできない。「領しらぬ霊ひ憑つく」意からとも、また「知らぬ日(多くの日数)を尽くして行く地」の意から筑紫にかかるともいう。
⇒しらぬい‐かい【不知火海】
⇒しらぬい‐の【白縫の】
しらぬい‐かい【不知火海】‥ヌヒ‥
八代やつしろ海の別称。
⇒しらぬい【不知火・白縫】
しらぬい‐がた【不知火型】‥ヌヒ‥
横綱の土俵入りの型の一つ。せり上がりのとき、両腕を左右に大きく開くのが特徴。攻めを表す。綱の後方の結び目は左右に二つの輪を作り中央の輪を立てる。11代横綱不知火光右衛門が創始。→雲竜型
しらぬい‐の【白縫の】‥ヌヒ‥
〔枕〕
「つくし(筑紫)」にかかる。
⇒しらぬい【不知火・白縫】
しらぬいものがたり【白縫譚】‥ヌヒ‥
合巻ごうかん中の最大長編。90編。柳下亭種員・2世種彦・柳水亭種清の合作。1849〜85年(嘉永2〜明治18)刊。豊後臼杵うすきの城主大友宗麟の女むすめ若菜姫が蜘蛛の妖術を行なって父の仇筑紫の太守菊地氏を討ち果たそうとする筋。
しらぬ‐がお【不知顔】‥ガホ
(→)「しらんかお」に同じ。栄華物語初花「いざ、いと―なるはわろし」
⇒しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】
しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】‥ガホ‥ヱ
知らぬ顔をして少しもとりあわないこと。そしらぬふりをすること。また、その人。浮世風呂2「何を云つても知らん顔の半兵衛さんだ」。「―をきめこむ」
⇒しらぬ‐がお【不知顔】
 ⇒しらせ【白瀬】
しらせ‐ぶみ【知らせ文】
先方へ知らせる書面。通知書。通知状。
⇒しらせ【知らせ・報せ】
しら・せる【知らせる・報せる】
〔他下一〕[文]しら・す(下二)
他人に通知して、その人が知るようにする。「時を―・せる」「合格を―・せる」
しら‐た【白太】
①材の白い杉。
②(→)辺材に同じ。〈日葡辞書〉↔赤身
しら‐だいしゅ【白大衆】
官位を持たない僧侶たち。平家物語1「―・神人・宮仕・専当みちみちて」
しら‐たえ【白妙・白
⇒しらせ【白瀬】
しらせ‐ぶみ【知らせ文】
先方へ知らせる書面。通知書。通知状。
⇒しらせ【知らせ・報せ】
しら・せる【知らせる・報せる】
〔他下一〕[文]しら・す(下二)
他人に通知して、その人が知るようにする。「時を―・せる」「合格を―・せる」
しら‐た【白太】
①材の白い杉。
②(→)辺材に同じ。〈日葡辞書〉↔赤身
しら‐だいしゅ【白大衆】
官位を持たない僧侶たち。平家物語1「―・神人・宮仕・専当みちみちて」
しら‐たえ【白妙・白 】‥タヘ
⇒しろたえ
しら‐たき【白滝】
①白布をかけたように流れ落ちる滝。
②糸ごんにゃくのさらに細く作ったもの。
しらたき‐いせき【白滝遺跡】‥ヰ‥
北海道網走支庁遠軽えんがる町白滝にある旧石器時代の遺跡。湧別ゆうべつ川とその支流沿いの段丘上を中心に数多く残る石器出土地点からなる。
しら‐たず【白田鶴】‥タヅ
ソデグロヅルの異称。兼盛集「―の天の原より飛びつるは」
しら‐たま【白玉・真珠】
①白色の美しい玉。はくぎょく。古事記上「赤玉は緒さへ光れど―の君が装ひし貴くありけり」
②真珠しんじゅの古名。あこやだま。武烈紀「あが欲る玉の鰒あわび―」
③白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子。汁粉に入れたり、冷やして白砂糖をかけたりして食べる。
④白玉椿の略。
⇒しらたま‐こ【白玉粉】
⇒しらたま‐つばき【白玉椿】
⇒しらたま‐の‐き【白玉の木】
⇒しらたま‐ひめ【白玉姫】
⇒しらたま‐ゆり【白玉百合】
しらたま‐こ【白玉粉】
糯米もちごめを洗い水に漬けたのち水切りし、水を加えながら磨砕し、水にさらし、乾燥させたもの。以前は寒中に作ったので、寒晒し粉ともいう。〈[季]夏〉
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐つばき【白玉椿】
白い花の咲くツバキ。催馬楽、高砂「高砂のをのへに立てる―」
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐の‐き【白玉の木】
ツツジ科の常緑小低木。本州と北海道の亜高山・高山帯に生ずる。長い地下茎があり、地上部は高さ10〜30センチメートルで斜上、しばしば群生する。葉は互生し卵形、質は硬い。夏に枝端に花穂を直立し、スズランに似た小白花を数個下向きに開く。果実は球形で白色。シロモノ。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐ひめ【白玉姫】
霞の異称。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐ゆり【白玉百合】
〔植〕カノコユリの一変種。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたみ【疝】
腹が急に痛み出す病。疝気せんき。〈倭名類聚鈔3〉
し‐らち【為埒】
処置して埒をあけること。あとかたづけ。しまつ。歌舞伎、阿国御前化粧鏡「どの道―は付けてやる」
しら‐ち【白血】
白帯下はくたいげの異称。〈伊呂波字類抄〉
しら‐ちゃ【白茶】
白みがかった茶色。うす茶色。浄瑠璃、心中宵庚申「―の死装束」
⇒しらちゃ・ける【白茶ける】
しらちゃ・ける【白茶ける】
〔自下一〕
色があせて白っぽくなる。
⇒しら‐ちゃ【白茶】
しら‐つか【白柄】
白い鮫皮さめがわをかけた刀の柄。だてな風俗。世間胸算用3「―の脇指」
⇒しらつか‐ぐみ【白柄組・白
】‥タヘ
⇒しろたえ
しら‐たき【白滝】
①白布をかけたように流れ落ちる滝。
②糸ごんにゃくのさらに細く作ったもの。
しらたき‐いせき【白滝遺跡】‥ヰ‥
北海道網走支庁遠軽えんがる町白滝にある旧石器時代の遺跡。湧別ゆうべつ川とその支流沿いの段丘上を中心に数多く残る石器出土地点からなる。
しら‐たず【白田鶴】‥タヅ
ソデグロヅルの異称。兼盛集「―の天の原より飛びつるは」
しら‐たま【白玉・真珠】
①白色の美しい玉。はくぎょく。古事記上「赤玉は緒さへ光れど―の君が装ひし貴くありけり」
②真珠しんじゅの古名。あこやだま。武烈紀「あが欲る玉の鰒あわび―」
③白玉粉を水でこね、小さく丸めてゆでた団子。汁粉に入れたり、冷やして白砂糖をかけたりして食べる。
④白玉椿の略。
⇒しらたま‐こ【白玉粉】
⇒しらたま‐つばき【白玉椿】
⇒しらたま‐の‐き【白玉の木】
⇒しらたま‐ひめ【白玉姫】
⇒しらたま‐ゆり【白玉百合】
しらたま‐こ【白玉粉】
糯米もちごめを洗い水に漬けたのち水切りし、水を加えながら磨砕し、水にさらし、乾燥させたもの。以前は寒中に作ったので、寒晒し粉ともいう。〈[季]夏〉
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐つばき【白玉椿】
白い花の咲くツバキ。催馬楽、高砂「高砂のをのへに立てる―」
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐の‐き【白玉の木】
ツツジ科の常緑小低木。本州と北海道の亜高山・高山帯に生ずる。長い地下茎があり、地上部は高さ10〜30センチメートルで斜上、しばしば群生する。葉は互生し卵形、質は硬い。夏に枝端に花穂を直立し、スズランに似た小白花を数個下向きに開く。果実は球形で白色。シロモノ。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐ひめ【白玉姫】
霞の異称。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたま‐ゆり【白玉百合】
〔植〕カノコユリの一変種。
⇒しら‐たま【白玉・真珠】
しらたみ【疝】
腹が急に痛み出す病。疝気せんき。〈倭名類聚鈔3〉
し‐らち【為埒】
処置して埒をあけること。あとかたづけ。しまつ。歌舞伎、阿国御前化粧鏡「どの道―は付けてやる」
しら‐ち【白血】
白帯下はくたいげの異称。〈伊呂波字類抄〉
しら‐ちゃ【白茶】
白みがかった茶色。うす茶色。浄瑠璃、心中宵庚申「―の死装束」
⇒しらちゃ・ける【白茶ける】
しらちゃ・ける【白茶ける】
〔自下一〕
色があせて白っぽくなる。
⇒しら‐ちゃ【白茶】
しら‐つか【白柄】
白い鮫皮さめがわをかけた刀の柄。だてな風俗。世間胸算用3「―の脇指」
⇒しらつか‐ぐみ【白柄組・白 組】
しらつか‐ぐみ【白柄組・白
組】
しらつか‐ぐみ【白柄組・白 組】
江戸前期、旗本奴はたもとやっこの徒党の一団。刀の柄を白糸で巻き、白馬にまたがって、好んで異様の風をなし、幕府上層部に反発した。はじめ水野十郎左衛門を盟主とし、江戸市中を横行して町人に迷惑を及ぼすこと多く、1686年(貞享3)に至って幕府に処断された。
⇒しら‐つか【白柄】
しら‐つきげ【白月毛】
馬の毛色の名。白みがかった月毛。しろつきげ。
しら‐つち【白土】
①白色の土。はくど。〈倭名類聚鈔1〉
②陶土とうど。〈本草和名〉
③漆喰しっくい。
しらっ‐と
〔副〕
①しらけたさま。「―した雰囲気」
②そっけ無いさま。「会っても―して挨拶もしない」
しらっ‐ぱく・れる
〔自下一〕
(→)「しらばくれる」に同じ。
シラップ【syrup】
⇒シロップ
しら‐つゆ【白露】
白く光って見える露。露の美称。〈[季]秋〉。万葉集20「秋草に置く―の厭かずのみ」
⇒しらつゆ‐の【白露の】
しらつゆ‐の【白露の】
〔枕〕
「け(消)」「おく」「たま」にかかる。
⇒しら‐つゆ【白露】
しら‐つる【白鶴】
ソデグロツルの異称。
しら‐つるばみ【白橡】
白みがかったつるばみ色。鈍色にびいろの薄いもの。宇津保物語吹上上「青き―の唐衣」
しら‐と【白砥】
粗砥あらとと仕上砥との間に用いる白色の砥石。愛媛県宇和島の名産。
しらとほふ
〔枕〕
「にひ(新)」にかかる。
しら‐とり【白とり】
(関西以西で)醤油の表面に浮かぶ白いかび。関東以東では「さざみ」という。
しら‐とり【白鳥】
①白い羽毛の鳥。
②はくちょう。
⇒しらとり‐の【白鳥の】
⇒しらとり‐の‐は【白鳥の羽】
しらとり【白鳥】
姓氏の一つ。
⇒しらとり‐くらきち【白鳥庫吉】
しらとり‐くらきち【白鳥庫吉】
東洋史学者。上総茂原生れ。東大教授。近代的東洋史学を確立し、北方民族および西域諸国の研究を開拓。東洋文庫研究部を創設。著「西域史研究」など。(1865〜1942)
⇒しらとり【白鳥】
しらとり‐の【白鳥の】
〔枕〕
「さぎ(鷺)」「とば(鳥羽)」にかかる。
⇒しら‐とり【白鳥】
しらとり‐の‐は【白鳥の羽】
矢羽に用いる、白色の鷲の羽。
⇒しら‐とり【白鳥】
しらとり‐の‐みささぎ【白鳥陵】
日本武尊やまとたけるのみことの陵。死後、白鳥に化してとまった所に建てたというもの。伊勢国能褒野のぼののほか、大和やまと・河内にもあった。
しら‐なみ【白波・白浪】
①白く泡立つなみ。
②(「白波はくはの賊」の「白波」を訓読したもの)盗賊の異称。
⇒しらなみ‐の【白波の】
⇒しらなみ‐もの【白浪物】
しらなみごにんおとこ【白浪五人男】‥ヲトコ
歌舞伎脚本「青砥稿花紅彩画あおとぞうしはなのにしきえ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1862年(文久2)初演。3世歌川豊国(初世国貞)の見立錦絵に暗示を得て、日本駄右衛門・忠信利平・南郷力丸・赤星十三郎(重三)・弁天小僧の5人を扱った白浪物。
→文献資料[青砥稿花紅彩画(四幕目)]
しらなみごにんおんな【白浪五人女】‥ヲンナ
歌舞伎脚本「処女評判善悪鏡むすめひょうばんぜんあくかがみ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1865年(慶応1)初演。「白浪五人男」にならい、須走お熊・雲切お六・おさらばお伝・木鼠お吉・山猫おさんの5人の女賊を扱い、津山の孝女お浅の物語を織り込む。
しらなみ‐の【白波の】
〔枕〕
「よる」「かへる」などにかかる。
⇒しら‐なみ【白波・白浪】
しらなみ‐もの【白浪物】
盗賊を主人公とする歌舞伎狂言などの総称。講談の松林しょうりん伯円、歌舞伎の河竹黙阿弥が得意とした。「白浪五人男」「白浪五人女」「三人吉三」「鼠小僧」の類。
⇒しら‐なみ【白波・白浪】
しら‐なわ【白縄】‥ナハ
鵜川などで、魚の逃げるのを防ぐためにひきめぐらした縄。散木奇歌集「ますらをは鵜川の瀬々に鮎とると引く―のたえずもあるかな」
しら‐に【白煮】
調味料を用いずに或いは塩味だけで煮たもの。しらたき。本朝桜陰比事「汁は鱸の―鱠にきすご」
しら‐に【知らに】
(ニは打消の助動詞ズの連用形の古形)知らないで。万葉集5「言はむすべ為むすべ―」
しら‐にきて【白和幣】
穀かじの皮の繊維で織った白布の幣帛。古事記上「下枝に―青にきてを取り垂しでて」→にきて
しらぬい【不知火・白縫】‥ヌヒ
[一]〔名〕
(景行天皇が海路火の国(肥前・肥後)に熊襲くまそを征伐した時、暗夜に多くの火が海上に現れ、無事に船を岸につけたが、何人なんぴとの火とも知られなかったという)九州の八代やつしろ海に、旧暦7月末頃の夜に見える無数の火影。沖に浮かぶイカ釣船の漁火が水面付近にただよう冷気によって屈折し、さまざまな形に変化してみえる現象。〈[季]秋〉
[二]〔枕〕
「つくし(筑紫)」にかかる。上代特殊仮名遣のうえから、「ひ」を「火」と解することはできない。「領しらぬ霊ひ憑つく」意からとも、また「知らぬ日(多くの日数)を尽くして行く地」の意から筑紫にかかるともいう。
⇒しらぬい‐かい【不知火海】
⇒しらぬい‐の【白縫の】
しらぬい‐かい【不知火海】‥ヌヒ‥
八代やつしろ海の別称。
⇒しらぬい【不知火・白縫】
しらぬい‐がた【不知火型】‥ヌヒ‥
横綱の土俵入りの型の一つ。せり上がりのとき、両腕を左右に大きく開くのが特徴。攻めを表す。綱の後方の結び目は左右に二つの輪を作り中央の輪を立てる。11代横綱不知火光右衛門が創始。→雲竜型
しらぬい‐の【白縫の】‥ヌヒ‥
〔枕〕
「つくし(筑紫)」にかかる。
⇒しらぬい【不知火・白縫】
しらぬいものがたり【白縫譚】‥ヌヒ‥
合巻ごうかん中の最大長編。90編。柳下亭種員・2世種彦・柳水亭種清の合作。1849〜85年(嘉永2〜明治18)刊。豊後臼杵うすきの城主大友宗麟の女むすめ若菜姫が蜘蛛の妖術を行なって父の仇筑紫の太守菊地氏を討ち果たそうとする筋。
しらぬ‐がお【不知顔】‥ガホ
(→)「しらんかお」に同じ。栄華物語初花「いざ、いと―なるはわろし」
⇒しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】
しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】‥ガホ‥ヱ
知らぬ顔をして少しもとりあわないこと。そしらぬふりをすること。また、その人。浮世風呂2「何を云つても知らん顔の半兵衛さんだ」。「―をきめこむ」
⇒しらぬ‐がお【不知顔】
組】
江戸前期、旗本奴はたもとやっこの徒党の一団。刀の柄を白糸で巻き、白馬にまたがって、好んで異様の風をなし、幕府上層部に反発した。はじめ水野十郎左衛門を盟主とし、江戸市中を横行して町人に迷惑を及ぼすこと多く、1686年(貞享3)に至って幕府に処断された。
⇒しら‐つか【白柄】
しら‐つきげ【白月毛】
馬の毛色の名。白みがかった月毛。しろつきげ。
しら‐つち【白土】
①白色の土。はくど。〈倭名類聚鈔1〉
②陶土とうど。〈本草和名〉
③漆喰しっくい。
しらっ‐と
〔副〕
①しらけたさま。「―した雰囲気」
②そっけ無いさま。「会っても―して挨拶もしない」
しらっ‐ぱく・れる
〔自下一〕
(→)「しらばくれる」に同じ。
シラップ【syrup】
⇒シロップ
しら‐つゆ【白露】
白く光って見える露。露の美称。〈[季]秋〉。万葉集20「秋草に置く―の厭かずのみ」
⇒しらつゆ‐の【白露の】
しらつゆ‐の【白露の】
〔枕〕
「け(消)」「おく」「たま」にかかる。
⇒しら‐つゆ【白露】
しら‐つる【白鶴】
ソデグロツルの異称。
しら‐つるばみ【白橡】
白みがかったつるばみ色。鈍色にびいろの薄いもの。宇津保物語吹上上「青き―の唐衣」
しら‐と【白砥】
粗砥あらとと仕上砥との間に用いる白色の砥石。愛媛県宇和島の名産。
しらとほふ
〔枕〕
「にひ(新)」にかかる。
しら‐とり【白とり】
(関西以西で)醤油の表面に浮かぶ白いかび。関東以東では「さざみ」という。
しら‐とり【白鳥】
①白い羽毛の鳥。
②はくちょう。
⇒しらとり‐の【白鳥の】
⇒しらとり‐の‐は【白鳥の羽】
しらとり【白鳥】
姓氏の一つ。
⇒しらとり‐くらきち【白鳥庫吉】
しらとり‐くらきち【白鳥庫吉】
東洋史学者。上総茂原生れ。東大教授。近代的東洋史学を確立し、北方民族および西域諸国の研究を開拓。東洋文庫研究部を創設。著「西域史研究」など。(1865〜1942)
⇒しらとり【白鳥】
しらとり‐の【白鳥の】
〔枕〕
「さぎ(鷺)」「とば(鳥羽)」にかかる。
⇒しら‐とり【白鳥】
しらとり‐の‐は【白鳥の羽】
矢羽に用いる、白色の鷲の羽。
⇒しら‐とり【白鳥】
しらとり‐の‐みささぎ【白鳥陵】
日本武尊やまとたけるのみことの陵。死後、白鳥に化してとまった所に建てたというもの。伊勢国能褒野のぼののほか、大和やまと・河内にもあった。
しら‐なみ【白波・白浪】
①白く泡立つなみ。
②(「白波はくはの賊」の「白波」を訓読したもの)盗賊の異称。
⇒しらなみ‐の【白波の】
⇒しらなみ‐もの【白浪物】
しらなみごにんおとこ【白浪五人男】‥ヲトコ
歌舞伎脚本「青砥稿花紅彩画あおとぞうしはなのにしきえ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1862年(文久2)初演。3世歌川豊国(初世国貞)の見立錦絵に暗示を得て、日本駄右衛門・忠信利平・南郷力丸・赤星十三郎(重三)・弁天小僧の5人を扱った白浪物。
→文献資料[青砥稿花紅彩画(四幕目)]
しらなみごにんおんな【白浪五人女】‥ヲンナ
歌舞伎脚本「処女評判善悪鏡むすめひょうばんぜんあくかがみ」の通称。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1865年(慶応1)初演。「白浪五人男」にならい、須走お熊・雲切お六・おさらばお伝・木鼠お吉・山猫おさんの5人の女賊を扱い、津山の孝女お浅の物語を織り込む。
しらなみ‐の【白波の】
〔枕〕
「よる」「かへる」などにかかる。
⇒しら‐なみ【白波・白浪】
しらなみ‐もの【白浪物】
盗賊を主人公とする歌舞伎狂言などの総称。講談の松林しょうりん伯円、歌舞伎の河竹黙阿弥が得意とした。「白浪五人男」「白浪五人女」「三人吉三」「鼠小僧」の類。
⇒しら‐なみ【白波・白浪】
しら‐なわ【白縄】‥ナハ
鵜川などで、魚の逃げるのを防ぐためにひきめぐらした縄。散木奇歌集「ますらをは鵜川の瀬々に鮎とると引く―のたえずもあるかな」
しら‐に【白煮】
調味料を用いずに或いは塩味だけで煮たもの。しらたき。本朝桜陰比事「汁は鱸の―鱠にきすご」
しら‐に【知らに】
(ニは打消の助動詞ズの連用形の古形)知らないで。万葉集5「言はむすべ為むすべ―」
しら‐にきて【白和幣】
穀かじの皮の繊維で織った白布の幣帛。古事記上「下枝に―青にきてを取り垂しでて」→にきて
しらぬい【不知火・白縫】‥ヌヒ
[一]〔名〕
(景行天皇が海路火の国(肥前・肥後)に熊襲くまそを征伐した時、暗夜に多くの火が海上に現れ、無事に船を岸につけたが、何人なんぴとの火とも知られなかったという)九州の八代やつしろ海に、旧暦7月末頃の夜に見える無数の火影。沖に浮かぶイカ釣船の漁火が水面付近にただよう冷気によって屈折し、さまざまな形に変化してみえる現象。〈[季]秋〉
[二]〔枕〕
「つくし(筑紫)」にかかる。上代特殊仮名遣のうえから、「ひ」を「火」と解することはできない。「領しらぬ霊ひ憑つく」意からとも、また「知らぬ日(多くの日数)を尽くして行く地」の意から筑紫にかかるともいう。
⇒しらぬい‐かい【不知火海】
⇒しらぬい‐の【白縫の】
しらぬい‐かい【不知火海】‥ヌヒ‥
八代やつしろ海の別称。
⇒しらぬい【不知火・白縫】
しらぬい‐がた【不知火型】‥ヌヒ‥
横綱の土俵入りの型の一つ。せり上がりのとき、両腕を左右に大きく開くのが特徴。攻めを表す。綱の後方の結び目は左右に二つの輪を作り中央の輪を立てる。11代横綱不知火光右衛門が創始。→雲竜型
しらぬい‐の【白縫の】‥ヌヒ‥
〔枕〕
「つくし(筑紫)」にかかる。
⇒しらぬい【不知火・白縫】
しらぬいものがたり【白縫譚】‥ヌヒ‥
合巻ごうかん中の最大長編。90編。柳下亭種員・2世種彦・柳水亭種清の合作。1849〜85年(嘉永2〜明治18)刊。豊後臼杵うすきの城主大友宗麟の女むすめ若菜姫が蜘蛛の妖術を行なって父の仇筑紫の太守菊地氏を討ち果たそうとする筋。
しらぬ‐がお【不知顔】‥ガホ
(→)「しらんかお」に同じ。栄華物語初花「いざ、いと―なるはわろし」
⇒しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】
しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】‥ガホ‥ヱ
知らぬ顔をして少しもとりあわないこと。そしらぬふりをすること。また、その人。浮世風呂2「何を云つても知らん顔の半兵衛さんだ」。「―をきめこむ」
⇒しらぬ‐がお【不知顔】
しらし‐め・す【知らしめす】🔗⭐🔉
しらし‐め・す【知らしめす】
〔他四〕
(「知る」の尊敬語「しらす」よりさらに敬意の強い言い方)お治めなさる。しろしめす。万葉集18「葦原のみづほの国をあまくだり―・しけるすめろきの」
しら・す【知らす】🔗⭐🔉
しら‐ず【知らず】🔗⭐🔉
しら‐ず【知らず】
①(「―、…か」の形で)見当がつかない意を表す。さあ、…のかしら。平家物語3「―、われ餓鬼道に尋ね来たるか」
②(「…は―」の形で)問題として取りあげない意を表す。…はさておいて。平家物語10「天竺・震旦は―、わが朝には」
⇒しらず‐がお【知らず顔】
⇒しらず‐さんてん【知らず三点】
⇒しらず‐しらず【知らず識らず・不知不識】
⇒しらず‐よみ【知らず詠み】
しらず‐がお【知らず顔】‥ガホ🔗⭐🔉
しらず‐がお【知らず顔】‥ガホ
(→)「しらんかお」に同じ。落窪物語1「さるべき受領あらば、―にてくれてやらんとしつるものを」
⇒しら‐ず【知らず】
しらず‐さんてん【知らず三点】🔗⭐🔉
しらず‐さんてん【知らず三点】
俳諧の点者が点付けをするのに、わからない句は中位の三点にすること。
⇒しら‐ず【知らず】
しらず‐しらず【知らず識らず・不知不識】🔗⭐🔉
しらず‐しらず【知らず識らず・不知不識】
無意識のうちに。ついつい。思わずしらず。「―涙があふれてきた」
⇒しら‐ず【知らず】
しらず‐よみ【知らず詠み】🔗⭐🔉
しらず‐よみ【知らず詠み】
知らぬふりをして歌を詠むこと。伊勢物語「男―によみける」
⇒しら‐ず【知らず】
しらせ【知らせ・報せ】🔗⭐🔉
しらせ【知らせ・報せ】
①知らせること。また、その内容。報知。通知。「悪い―」
②事の起こるきざし。前兆。
③歌舞伎で、舞台転換や道具が変わる時、また浄瑠璃にかかる時など、合図に打つ拍子木。詳しくは「道具替りの知らせ」という。
⇒しらせ‐ぶみ【知らせ文】
しらせ‐ぶみ【知らせ文】🔗⭐🔉
しらせ‐ぶみ【知らせ文】
先方へ知らせる書面。通知書。通知状。
⇒しらせ【知らせ・報せ】
しら・せる【知らせる・報せる】🔗⭐🔉
しら・せる【知らせる・報せる】
〔他下一〕[文]しら・す(下二)
他人に通知して、その人が知るようにする。「時を―・せる」「合格を―・せる」
しら‐に【知らに】🔗⭐🔉
しら‐に【知らに】
(ニは打消の助動詞ズの連用形の古形)知らないで。万葉集5「言はむすべ為むすべ―」
しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】‥ガホ‥ヱ🔗⭐🔉
しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】‥ガホ‥ヱ
知らぬ顔をして少しもとりあわないこと。そしらぬふりをすること。また、その人。浮世風呂2「何を云つても知らん顔の半兵衛さんだ」。「―をきめこむ」
⇒しらぬ‐がお【不知顔】
○知らぬが仏しらぬがほとけ
知ればこそ腹も立つが、知らなければ仏のように平穏な境地でいられる。転じて、当人だけが知らずに平気でいるさまをあわれみ、あざけっていう語。
⇒し・る【知る】
○知らぬは亭主ばかりなりしらぬはていしゅばかりなり
女房の浮気を皆知っているのに、知らないのは当の亭主ばかりだということ。一般に、当事者だけが知らないで平気でいるのを、あわれんだりからかったりしていう。
⇒し・る【知る】
○知らぬが仏しらぬがほとけ🔗⭐🔉
○知らぬが仏しらぬがほとけ
知ればこそ腹も立つが、知らなければ仏のように平穏な境地でいられる。転じて、当人だけが知らずに平気でいるさまをあわれみ、あざけっていう語。
⇒し・る【知る】
○知らぬ仏より馴染の鬼しらぬほとけよりなじみのおに🔗⭐🔉
○知らぬ仏より馴染の鬼しらぬほとけよりなじみのおに
どんな人間でも疎遠な者よりもなじみの者の方がよい。
⇒し・る【知る】
しらぬ‐よ【知らぬ世】
①自分のまだ生まれなかった昔の世。過去の世。
②自分のまだ知らない世界。源氏物語槿「―にまどひ侍りしを」
しら‐ぬり【白塗り】
銀でめっきをすること。万葉集19「―の小鈴もゆらに合はせ遣り」→しろぬり
しら‐ね【しら寝】
独り寝ること。いたずらぶし。ひとりね。夫木和歌抄36「あしやに寝ても―をぞする」
しら‐ね【白根】
①植物の茎および根の土中にあって白色をした部分。
②〔植〕
⇒しろね。
⇒しらね‐あおい【白根葵】
⇒しらね‐にんじん【白根人参】
しらね‐あおい【白根葵】‥アフヒ
キンポウゲ科の多年草。日本特産で、主に東北地方と日本海側の亜高山の樹下にしばしば群生。高さ約30〜60センチメートル。葉は掌状複葉で、通常3枚が互生する。夏、茎頂に青紫色の大形4弁の美花を単生、蒴果さくかを結ぶ。ハルフヨウ。
シラネアオイ
撮影:関戸 勇
 ⇒しら‐ね【白根】
しらね‐さん【白根山】
①群馬県北西部、吾妻郡にある火山。標高2171メートル。東側山腹に草津温泉がある。草津白根。
草津白根山
提供:オフィス史朗
⇒しら‐ね【白根】
しらね‐さん【白根山】
①群馬県北西部、吾妻郡にある火山。標高2171メートル。東側山腹に草津温泉がある。草津白根。
草津白根山
提供:オフィス史朗
 ②栃木・群馬県境、日光の北西にある二重式火山。標高2578メートル。前白根山・坐禅山は外輪山をなし、これら山頂群の間に五色沼・阿弥陀ガ池・血ノ池地獄などの湖沼がある。日光白根。
日光白根山
提供:オフィス史朗
②栃木・群馬県境、日光の北西にある二重式火山。標高2578メートル。前白根山・坐禅山は外輪山をなし、これら山頂群の間に五色沼・阿弥陀ガ池・血ノ池地獄などの湖沼がある。日光白根。
日光白根山
提供:オフィス史朗
 ③(「白峰山」とも書く)山梨・長野・静岡の県境付近にそびえる高山の総称。甲斐嶺かいがねともいう。南アルプスの主峰。北岳・間ノ岳あいのたけ・農鳥のうとり岳の3峰がつらなる。白根三山。
白峰三山
提供:オフィス史朗
③(「白峰山」とも書く)山梨・長野・静岡の県境付近にそびえる高山の総称。甲斐嶺かいがねともいう。南アルプスの主峰。北岳・間ノ岳あいのたけ・農鳥のうとり岳の3峰がつらなる。白根三山。
白峰三山
提供:オフィス史朗
 北岳
提供:オフィス史朗
北岳
提供:オフィス史朗
 北岳(2)
提供:オフィス史朗
北岳(2)
提供:オフィス史朗
 間ノ岳
提供:オフィス史朗
間ノ岳
提供:オフィス史朗
 農鳥岳
提供:オフィス史朗
農鳥岳
提供:オフィス史朗
 しらね‐にんじん【白根人参】
セリ科の多年草。高山草原に生ずる。日本を含む東アジアに分布。太い直根があり、根生葉は2回羽状複葉で羽片はさらに裂ける。茎葉の基部は茎を抱く。夏に茎頂に小型の散房花序を出し、白い細花を無数につける。
⇒しら‐ね【白根】
しら‐の【白箆】
もとの竹のままで、漆を塗ってない矢柄やがら。しろの。平家物語11「―に鶴のもとじろ」
シラノ‐ド‐ベルジュラック【Cyrano de Bergerac】
①フランスの文人・自由思想家。空想諷刺小説「月世界物語」「太陽世界物語」など。(1619〜1655)
②1をモデルとしたロスタンの戯曲。1897年初演。醜い鼻を持つ剣客シラノの、従妹ロクサーヌに対する悲恋を描く。日本で翻案された「白野弁十郎」は1926年(大正15)初演。
しら‐は【白刃】
鞘さやから抜き放った刃。刀身。ぬきみ。日葡辞書「シラハデマイリアワウ」
しら‐は【白羽】
斑ふのない真っ白な矢羽やばね。義経記8「黒羽、―、染羽、色々の矢ども風に吹かれて」
⇒白羽の矢が立つ
しら‐は【白歯】
①白い歯。おあん物語「―の首はお歯黒つけて給はれ」
②(まだ嫁入りしない女は歯を黒く染めなかったからいう)未婚の女。処女。浄瑠璃、新版歌祭文「たくみの底は―のお染」
しら‐はい【白灰】‥ハヒ
白い灰水。あく。永久百首「ははそ原露の―さしつれば」
しら‐はえ【白南風】
(九州地方などで)梅雨明けの頃に吹く南風。また、8月頃の昼間吹く南風。しろはえ。〈[季]夏〉
しらはがれ‐びょう【白葉枯病】‥ビヤウ
細菌によるイネの主要な病害。葉に黄色条斑を生じ後に白色に枯れ上がる。若い苗に感染すると萎凋いちょう症状をおこす。
しら‐はぎ【白萩】
①花の白い萩。〈[季]秋〉
②ヌマトラノオの異称。
しら‐ばく・れる
〔自下一〕
知っていながら知らないふりをする。白しらを切る。しらばっくれる。しらっぱくれる。「どこまでも―・れて通す」
しら‐ばけ【白化け】
①わざとありのままに言って、相手の心をとらえること。直化すぐばけ。西鶴織留5「精進腹では酒が呑めぬと―のかる口」
②あけすけに言うさま。あからさま。通言総籬つうげんそうまがき「―にごふてきをいふな」
③しらばくれること。歌舞伎、与話情浮名横櫛「その―か黒塀に格子造りのかこひもの」
しら‐はし【白箸】
白木のままの箸。
シラバス【syllabus】
〔教〕講義実施要綱。講義の目的・内容・使用テキスト・参考文献・評価方法などについて記した計画書。
しら‐はた【白旗】
白地の旗。源氏の旗とされ、また、戦争の際、戦意のないことの証明や降服の意を表すのに用いる。しろはた。「―を掲げる」
⇒しらはた‐いっき【白旗一揆】
しら‐はだ【白肌・白膚】
①色白の皮膚。
②しらはたけ。しろなまず。〈倭名類聚鈔3〉
しらはた‐いっき【白旗一揆】
中世、関東に結成された源氏の中小武士の集団。
⇒しら‐はた【白旗】
しら‐はたけ【白癩】
児童の顔面に白色の円形斑を生じる皮膚病。しらはた。
しら‐ばっく・れる
〔自下一〕
(→)「しらばくれる」に同じ。
しらね‐にんじん【白根人参】
セリ科の多年草。高山草原に生ずる。日本を含む東アジアに分布。太い直根があり、根生葉は2回羽状複葉で羽片はさらに裂ける。茎葉の基部は茎を抱く。夏に茎頂に小型の散房花序を出し、白い細花を無数につける。
⇒しら‐ね【白根】
しら‐の【白箆】
もとの竹のままで、漆を塗ってない矢柄やがら。しろの。平家物語11「―に鶴のもとじろ」
シラノ‐ド‐ベルジュラック【Cyrano de Bergerac】
①フランスの文人・自由思想家。空想諷刺小説「月世界物語」「太陽世界物語」など。(1619〜1655)
②1をモデルとしたロスタンの戯曲。1897年初演。醜い鼻を持つ剣客シラノの、従妹ロクサーヌに対する悲恋を描く。日本で翻案された「白野弁十郎」は1926年(大正15)初演。
しら‐は【白刃】
鞘さやから抜き放った刃。刀身。ぬきみ。日葡辞書「シラハデマイリアワウ」
しら‐は【白羽】
斑ふのない真っ白な矢羽やばね。義経記8「黒羽、―、染羽、色々の矢ども風に吹かれて」
⇒白羽の矢が立つ
しら‐は【白歯】
①白い歯。おあん物語「―の首はお歯黒つけて給はれ」
②(まだ嫁入りしない女は歯を黒く染めなかったからいう)未婚の女。処女。浄瑠璃、新版歌祭文「たくみの底は―のお染」
しら‐はい【白灰】‥ハヒ
白い灰水。あく。永久百首「ははそ原露の―さしつれば」
しら‐はえ【白南風】
(九州地方などで)梅雨明けの頃に吹く南風。また、8月頃の昼間吹く南風。しろはえ。〈[季]夏〉
しらはがれ‐びょう【白葉枯病】‥ビヤウ
細菌によるイネの主要な病害。葉に黄色条斑を生じ後に白色に枯れ上がる。若い苗に感染すると萎凋いちょう症状をおこす。
しら‐はぎ【白萩】
①花の白い萩。〈[季]秋〉
②ヌマトラノオの異称。
しら‐ばく・れる
〔自下一〕
知っていながら知らないふりをする。白しらを切る。しらばっくれる。しらっぱくれる。「どこまでも―・れて通す」
しら‐ばけ【白化け】
①わざとありのままに言って、相手の心をとらえること。直化すぐばけ。西鶴織留5「精進腹では酒が呑めぬと―のかる口」
②あけすけに言うさま。あからさま。通言総籬つうげんそうまがき「―にごふてきをいふな」
③しらばくれること。歌舞伎、与話情浮名横櫛「その―か黒塀に格子造りのかこひもの」
しら‐はし【白箸】
白木のままの箸。
シラバス【syllabus】
〔教〕講義実施要綱。講義の目的・内容・使用テキスト・参考文献・評価方法などについて記した計画書。
しら‐はた【白旗】
白地の旗。源氏の旗とされ、また、戦争の際、戦意のないことの証明や降服の意を表すのに用いる。しろはた。「―を掲げる」
⇒しらはた‐いっき【白旗一揆】
しら‐はだ【白肌・白膚】
①色白の皮膚。
②しらはたけ。しろなまず。〈倭名類聚鈔3〉
しらはた‐いっき【白旗一揆】
中世、関東に結成された源氏の中小武士の集団。
⇒しら‐はた【白旗】
しら‐はたけ【白癩】
児童の顔面に白色の円形斑を生じる皮膚病。しらはた。
しら‐ばっく・れる
〔自下一〕
(→)「しらばくれる」に同じ。
 ⇒しら‐ね【白根】
しらね‐さん【白根山】
①群馬県北西部、吾妻郡にある火山。標高2171メートル。東側山腹に草津温泉がある。草津白根。
草津白根山
提供:オフィス史朗
⇒しら‐ね【白根】
しらね‐さん【白根山】
①群馬県北西部、吾妻郡にある火山。標高2171メートル。東側山腹に草津温泉がある。草津白根。
草津白根山
提供:オフィス史朗
 ②栃木・群馬県境、日光の北西にある二重式火山。標高2578メートル。前白根山・坐禅山は外輪山をなし、これら山頂群の間に五色沼・阿弥陀ガ池・血ノ池地獄などの湖沼がある。日光白根。
日光白根山
提供:オフィス史朗
②栃木・群馬県境、日光の北西にある二重式火山。標高2578メートル。前白根山・坐禅山は外輪山をなし、これら山頂群の間に五色沼・阿弥陀ガ池・血ノ池地獄などの湖沼がある。日光白根。
日光白根山
提供:オフィス史朗
 ③(「白峰山」とも書く)山梨・長野・静岡の県境付近にそびえる高山の総称。甲斐嶺かいがねともいう。南アルプスの主峰。北岳・間ノ岳あいのたけ・農鳥のうとり岳の3峰がつらなる。白根三山。
白峰三山
提供:オフィス史朗
③(「白峰山」とも書く)山梨・長野・静岡の県境付近にそびえる高山の総称。甲斐嶺かいがねともいう。南アルプスの主峰。北岳・間ノ岳あいのたけ・農鳥のうとり岳の3峰がつらなる。白根三山。
白峰三山
提供:オフィス史朗
 北岳
提供:オフィス史朗
北岳
提供:オフィス史朗
 北岳(2)
提供:オフィス史朗
北岳(2)
提供:オフィス史朗
 間ノ岳
提供:オフィス史朗
間ノ岳
提供:オフィス史朗
 農鳥岳
提供:オフィス史朗
農鳥岳
提供:オフィス史朗
 しらね‐にんじん【白根人参】
セリ科の多年草。高山草原に生ずる。日本を含む東アジアに分布。太い直根があり、根生葉は2回羽状複葉で羽片はさらに裂ける。茎葉の基部は茎を抱く。夏に茎頂に小型の散房花序を出し、白い細花を無数につける。
⇒しら‐ね【白根】
しら‐の【白箆】
もとの竹のままで、漆を塗ってない矢柄やがら。しろの。平家物語11「―に鶴のもとじろ」
シラノ‐ド‐ベルジュラック【Cyrano de Bergerac】
①フランスの文人・自由思想家。空想諷刺小説「月世界物語」「太陽世界物語」など。(1619〜1655)
②1をモデルとしたロスタンの戯曲。1897年初演。醜い鼻を持つ剣客シラノの、従妹ロクサーヌに対する悲恋を描く。日本で翻案された「白野弁十郎」は1926年(大正15)初演。
しら‐は【白刃】
鞘さやから抜き放った刃。刀身。ぬきみ。日葡辞書「シラハデマイリアワウ」
しら‐は【白羽】
斑ふのない真っ白な矢羽やばね。義経記8「黒羽、―、染羽、色々の矢ども風に吹かれて」
⇒白羽の矢が立つ
しら‐は【白歯】
①白い歯。おあん物語「―の首はお歯黒つけて給はれ」
②(まだ嫁入りしない女は歯を黒く染めなかったからいう)未婚の女。処女。浄瑠璃、新版歌祭文「たくみの底は―のお染」
しら‐はい【白灰】‥ハヒ
白い灰水。あく。永久百首「ははそ原露の―さしつれば」
しら‐はえ【白南風】
(九州地方などで)梅雨明けの頃に吹く南風。また、8月頃の昼間吹く南風。しろはえ。〈[季]夏〉
しらはがれ‐びょう【白葉枯病】‥ビヤウ
細菌によるイネの主要な病害。葉に黄色条斑を生じ後に白色に枯れ上がる。若い苗に感染すると萎凋いちょう症状をおこす。
しら‐はぎ【白萩】
①花の白い萩。〈[季]秋〉
②ヌマトラノオの異称。
しら‐ばく・れる
〔自下一〕
知っていながら知らないふりをする。白しらを切る。しらばっくれる。しらっぱくれる。「どこまでも―・れて通す」
しら‐ばけ【白化け】
①わざとありのままに言って、相手の心をとらえること。直化すぐばけ。西鶴織留5「精進腹では酒が呑めぬと―のかる口」
②あけすけに言うさま。あからさま。通言総籬つうげんそうまがき「―にごふてきをいふな」
③しらばくれること。歌舞伎、与話情浮名横櫛「その―か黒塀に格子造りのかこひもの」
しら‐はし【白箸】
白木のままの箸。
シラバス【syllabus】
〔教〕講義実施要綱。講義の目的・内容・使用テキスト・参考文献・評価方法などについて記した計画書。
しら‐はた【白旗】
白地の旗。源氏の旗とされ、また、戦争の際、戦意のないことの証明や降服の意を表すのに用いる。しろはた。「―を掲げる」
⇒しらはた‐いっき【白旗一揆】
しら‐はだ【白肌・白膚】
①色白の皮膚。
②しらはたけ。しろなまず。〈倭名類聚鈔3〉
しらはた‐いっき【白旗一揆】
中世、関東に結成された源氏の中小武士の集団。
⇒しら‐はた【白旗】
しら‐はたけ【白癩】
児童の顔面に白色の円形斑を生じる皮膚病。しらはた。
しら‐ばっく・れる
〔自下一〕
(→)「しらばくれる」に同じ。
しらね‐にんじん【白根人参】
セリ科の多年草。高山草原に生ずる。日本を含む東アジアに分布。太い直根があり、根生葉は2回羽状複葉で羽片はさらに裂ける。茎葉の基部は茎を抱く。夏に茎頂に小型の散房花序を出し、白い細花を無数につける。
⇒しら‐ね【白根】
しら‐の【白箆】
もとの竹のままで、漆を塗ってない矢柄やがら。しろの。平家物語11「―に鶴のもとじろ」
シラノ‐ド‐ベルジュラック【Cyrano de Bergerac】
①フランスの文人・自由思想家。空想諷刺小説「月世界物語」「太陽世界物語」など。(1619〜1655)
②1をモデルとしたロスタンの戯曲。1897年初演。醜い鼻を持つ剣客シラノの、従妹ロクサーヌに対する悲恋を描く。日本で翻案された「白野弁十郎」は1926年(大正15)初演。
しら‐は【白刃】
鞘さやから抜き放った刃。刀身。ぬきみ。日葡辞書「シラハデマイリアワウ」
しら‐は【白羽】
斑ふのない真っ白な矢羽やばね。義経記8「黒羽、―、染羽、色々の矢ども風に吹かれて」
⇒白羽の矢が立つ
しら‐は【白歯】
①白い歯。おあん物語「―の首はお歯黒つけて給はれ」
②(まだ嫁入りしない女は歯を黒く染めなかったからいう)未婚の女。処女。浄瑠璃、新版歌祭文「たくみの底は―のお染」
しら‐はい【白灰】‥ハヒ
白い灰水。あく。永久百首「ははそ原露の―さしつれば」
しら‐はえ【白南風】
(九州地方などで)梅雨明けの頃に吹く南風。また、8月頃の昼間吹く南風。しろはえ。〈[季]夏〉
しらはがれ‐びょう【白葉枯病】‥ビヤウ
細菌によるイネの主要な病害。葉に黄色条斑を生じ後に白色に枯れ上がる。若い苗に感染すると萎凋いちょう症状をおこす。
しら‐はぎ【白萩】
①花の白い萩。〈[季]秋〉
②ヌマトラノオの異称。
しら‐ばく・れる
〔自下一〕
知っていながら知らないふりをする。白しらを切る。しらばっくれる。しらっぱくれる。「どこまでも―・れて通す」
しら‐ばけ【白化け】
①わざとありのままに言って、相手の心をとらえること。直化すぐばけ。西鶴織留5「精進腹では酒が呑めぬと―のかる口」
②あけすけに言うさま。あからさま。通言総籬つうげんそうまがき「―にごふてきをいふな」
③しらばくれること。歌舞伎、与話情浮名横櫛「その―か黒塀に格子造りのかこひもの」
しら‐はし【白箸】
白木のままの箸。
シラバス【syllabus】
〔教〕講義実施要綱。講義の目的・内容・使用テキスト・参考文献・評価方法などについて記した計画書。
しら‐はた【白旗】
白地の旗。源氏の旗とされ、また、戦争の際、戦意のないことの証明や降服の意を表すのに用いる。しろはた。「―を掲げる」
⇒しらはた‐いっき【白旗一揆】
しら‐はだ【白肌・白膚】
①色白の皮膚。
②しらはたけ。しろなまず。〈倭名類聚鈔3〉
しらはた‐いっき【白旗一揆】
中世、関東に結成された源氏の中小武士の集団。
⇒しら‐はた【白旗】
しら‐はたけ【白癩】
児童の顔面に白色の円形斑を生じる皮膚病。しらはた。
しら‐ばっく・れる
〔自下一〕
(→)「しらばくれる」に同じ。
しらぬ‐よ【知らぬ世】🔗⭐🔉
しらぬ‐よ【知らぬ世】
①自分のまだ生まれなかった昔の世。過去の世。
②自分のまだ知らない世界。源氏物語槿「―にまどひ侍りしを」
しらん‐かお【知らん顔】‥カホ🔗⭐🔉
しらん‐かお【知らん顔】‥カホ
知らぬふり。そしらぬ顔。「話しかけても―をしている」
しらん‐ぷり【知らん振り】🔗⭐🔉
しらん‐ぷり【知らん振り】
(シラヌフリの転)知っていながら知らないような様子をすること。
しり‐あ・う【知り合う】‥アフ🔗⭐🔉
しり‐あ・う【知り合う】‥アフ
〔自五〕
互いに知る。知合いとなる。「同好会で―・う」
しり‐がお【知り顔】‥ガホ🔗⭐🔉
しり‐がお【知り顔】‥ガホ
よく心得ているという顔つき。知っているふう。源氏物語薄雲「秋のあはれを―に」
○尻が重いしりがおもい
無精ぶしょうで、容易に腰をあげない。また、機敏に振る舞わない。
⇒しり【尻・臀・後】
○尻が軽いしりがかるい
①動作が機敏である。
②落着きがなく、言語動作が軽々しい。
③女の、浮気なさまにいう。
⇒しり【尻・臀・後】
しり‐げ【知り気】🔗⭐🔉
しり‐げ【知り気】
知っているけはい。古今著聞集16「我を笑ふとは―もなくて」
しり‐ぬ・く【知り抜く】🔗⭐🔉
しり‐ぬ・く【知り抜く】
〔他五〕
ある事について何から何までくわしく知る。知り尽くす。「政界の裏を―・く」
しり‐びと【知り人】🔗⭐🔉
しり‐びと【知り人】
知合いの人。ちじん。
し・る【知る】🔗⭐🔉
し・る【知る】
[一]〔他五〕
(「領しる」と同源)ある現象・状態を広く隅々まで自分のものとする意。
①物事の内容を理解する。わきまえる。悟る。万葉集20「みつぼなす仮れる身そとは―・れれどもなほし願ひつ千年の命を」。日葡辞書「ゼンゴヲシラヌ」。「子を持って―・る親の恩」「野球をよく―・っている」「―・らない者ほどよくしゃべる」
②見分ける。識別する。万葉集2「埴安の池の堤の隠沼こもりぬの行方を―・らに舎人は惑ふ」
③ある事柄の存在を認める。認識する。古事記下「天飛だむ軽の乙女甚いた泣かば人―・りぬべし」。醒睡笑「少々寒きことを―・らず」。「自分の無知を―・る」「雨のふっているのを―・らなかった」
④ある事柄のおこることをさとる。推知する。予見する。万葉集11「思ふ人来むと―・りせば八重葎やえむぐらおほへる庭に玉敷かましを」。「うまく行くと―・っていたらあわてなかったのに」
⑤経験する。源氏物語夕顔「いにしへもかくやは人のまどひけむわがまだ―・らぬしののめの道」。「私の―・らない世界の事だ」「酒の味を―・る」
⑥かかわりを持つ。関知する。源氏物語東屋「この君はただまかせ聞えさせて―・り侍らじ」。「私の―・った事ではない」
⑦(打消の形で)できない、不可能の意。万葉集5「言はむすべせむすべ知らに石木をも問ひさけ―・らず」
⑧(打消の形で)一切それをしないの意。「疲れを―・らない人」「妥協を―・らない」
[二]〔自下二〕
⇒しれる(下一)
⇒知らざるを知らずとせよ
⇒知らぬが仏
⇒知らぬは亭主ばかりなり
⇒知らぬ仏より馴染の鬼
⇒知る人ぞ知る
⇒知る者は言わず、言う者は知らず
⇒知る由もない
し・る【領る・知る】(他五)🔗⭐🔉
し・る【領る・知る】
〔他五〕
(ある範囲の隅々まで支配する意。原義は、物をすっかり自分のものにすることという)
①(国などを)治める。君臨する。統治する。古事記下「汝が御子や遂に―・らむと雁は卵こ産むらし」。万葉集6「あれまさむ御子のつぎつぎ天の下―・らしいませと」
②(土地などを)占める。領有する。万葉集7「葛城の高間の草野かやのはや―・りて標しめささましを今そ悔やしき」
③(ものなどを)専有して管理する。専有して扱う。今昔物語集10「親の行きけむ方を知らず。子の逃げけむ道を失へり。いはむや家の財・物の具―・ることなくして」
④(妻・愛人などとして)世話をする。枕草子28「わが―・る人にてある人の、早う見し女のことほめ言ひ出でなどするも」
しる‐けんり【知る権利】🔗⭐🔉
しる‐けんり【知る権利】
(right to know)国民が国の政治や行政に関する公的な情報を知る権利。民主主義国家における言論報道の自由や情報公開制度の正当化のための現代的な憲法原理。
しる‐たより【知る便り】🔗⭐🔉
しる‐たより【知る便り】
縁故のある人。知人。しるべ。源氏物語澪標「―ありて」
○知る人ぞ知るしるひとぞしる🔗⭐🔉
○知る人ぞ知るしるひとぞしる
多くの人に知られてはいないが、一部の人にはその真価は十分に理解されている。「この人は―笛の名手です」
⇒し・る【知る】
しる‐べ【導・標】
(「知方しるべ」の意)
①道案内。先導。古今和歌集春「花のかを風のたよりにたぐへてぞ鶯さそふ―にはやる」
②知るたより。みちびき。てびき。春雨物語「御―につきて、文よみ歌学ばん」
⇒しるべ‐がお【導顔】
しる‐べ【知辺】
知合いの人。ゆかりのある人。「―をたよって上京する」
しるべ‐がお【導顔】‥ガホ
案内するような様子。十六夜日記「―なるここちして」
⇒しる‐べ【導・標】
しるまし【怪】
(不吉な)前兆。崇神紀「其の歌の―を知りて」
シルミン【silumin】
ケイ素などを加えた鋳物用のアルミニウム合金。軽量で、延性・展性が大きく、かつ鋳造後の収縮率がきわめて少なく、海水に浸されにくい。航空機・自動車の複雑な形状の部品などに用いる。アルパックス。
しる‐もの【汁物】
①吸物。しるのもの。つゆもの。
②汁の多い料理。
○知る者は言わず、言う者は知らずしるものはいわずいうものはしらず🔗⭐🔉
○知る者は言わず、言う者は知らずしるものはいわずいうものはしらず
[老子第56章]深く知りぬいている人はみだりに発言しない、やたらに発言する者はよく知らない者である。
⇒し・る【知る】
○知る由もないしるよしもない🔗⭐🔉
○知る由もないしるよしもない
知るための手がかりも方法もない。「その後の彼の行方は―」
⇒し・る【知る】
シルル‐き【シルル紀】
(Silurian Period)地質年代で、古生代のうちオルドビス紀の後、デボン紀の前の時代。ゴトランド紀ともいわれた。約4億4000万年前から4億1000万年前までの時代。植物は海藻類、動物は珊瑚さんご虫・筆石類・三葉虫類などが生息。末期に最初の陸上植物であるシダ植物が出現。オルドビス紀とゴトランド紀とを併せてシルル紀と呼んだこともある。シルリア紀。→地質年代(表)
シルル‐けい【シルル系】
(Silurian System)シルル紀に形成された地層。シルリア系。
しるわかし‐もち【汁沸餅】
(→)「汁の餅」に同じ。
しる‐わん【汁椀】
汁物を盛る椀。〈日葡辞書〉
じれ
じれったいこと。やきもきすること。黄表紙、見徳一炊夢みるがとくいっすいのゆめ「言葉不通ゆゑ、清太郎ぐつと―が来て」
し‐れい【司令】
軍隊・艦船などを指揮・監督すること。また、その人。航空隊司令・消防司令など。
⇒しれい‐かん【司令官】
⇒しれい‐ちょうかん【司令長官】
⇒しれい‐とう【司令塔】
⇒しれい‐ぶ【司令部】
し‐れい【死霊】
死者の霊魂。しりょう。↔生霊せいれい。
⇒しれい‐しんこう【死霊信仰】
し‐れい【使令】
①命令して人を使うこと。
②召使い。太平記25「従官―」
し‐れい【指令】
指揮命令。上級機関が下級機関に対して行うさしず。「―を発する」
し‐れい【砥礪】
(「砥」は細石、「礪」は黒石の意)
①といし。
②とぎみがくこと。品性・学問などを修養すること。砥磨。
じ‐れい【事例】
①事件の前例。前例となる事実。「稀有けうな―」
②個々の場合における、それぞれの事実。
⇒じれい‐けんきゅう‐ほう【事例研究法】
じ‐れい【時令】
①一年中の、時節に応じてする行事。年中行事。
②時節。
じ‐れい【辞令】
①応対のことばづかい。いいまわし。あいさつ。「外交―」
②文章のあや。詞章。「―の妙を極める」
③官職任免に際し、その旨をしたためて本人に交付する文書。「―書」「―が出る」
しれい‐かん【司令官】‥クワン
方面軍・駐屯軍・艦隊などを統率・指揮する職。
⇒し‐れい【司令】
じれい‐けんきゅう‐ほう【事例研究法】‥キウハフ
一つまたは少数の事例について詳しく調査・研究し、それによって問題の所在・原因等を発見・究明しようとする方法。ケース‐スタディー。
⇒じ‐れい【事例】
しれい‐しんこう【死霊信仰】‥カウ
(manism; manes-worship)死者の霊が生者に禍福をもたらすとみなし、死者の霊を恐れたり祀ったりする信仰。→祖先崇拝
⇒し‐れい【死霊】
しれい‐ちょうかん【司令長官】‥チヤウクワン
天皇に直属して、艦隊・鎮守府・警備府の統率・指揮に当たった海軍の軍職。「連合艦隊―」
⇒し‐れい【司令】
しれい‐とう【司令塔】‥タフ
①軍艦で、艦長・司令・司令官などが指揮を行う装甲を施した塔。
②中心となって指示をする組織・人。「チームの―」
⇒し‐れい【司令】
しれい‐ぶ【司令部】
司令官が指揮を執る所。
⇒し‐れい【司令】
ジレー【gilet フランス】
チョッキ。ベスト。また、婦人用の装飾的な胸飾りがついた胴衣。
しれ‐がま・し【痴れがまし】
〔形シク〕
おろかなさまである。ばかげている。源氏物語夕霧「かうのみ―・しうて出で入らむもあやしければ」
じ‐れき【事歴】
物事の来歴。
じ‐れきせい【地瀝青】ヂ‥
(→)アスファルトのこと。
しれ‐ごと【痴れ言】
おろかなことば。たわごと。宇治拾遺物語13「―な言ひそ」
しれ‐ごと【痴れ事】
おろかな事。ばかばかしい事柄。古今著聞集17「おのづからも―つかうまつり候はば」
じれ‐こ・む【焦れ込む】
〔自五〕
いらだつ。あせる。滑稽本、続膝栗毛「きた八―・みてありたけ手をのばし」
シレジア【Silesia】
ヨーロッパ中部の地方。ポーランド南西部のオーデル川上流地方、およびこれに隣接するチェコ・ドイツ東部の一部。3度のシレジア戦争(1740〜42年、44〜45年、56〜63年(七年戦争))におけるプロイセンとオーストリアとの係争の地。豊富な地下資源を有し、ポーランドの大工業中心地。ポーランド語名シロンスク。ドイツ語名シュレジエン。チェコ語名スレスコ。
しれ‐じれ【痴れ痴れ】
いかにもおろかなさま。また、そらぞらしいさま。能因本枕草子円融院の御はての年「―とうち笑みて、ともかくも言はで」
しれ‐じれ・し【痴れ痴れし】
〔形シク〕
①いかにもおろかである。源氏物語行幸「思ひ寄らざりけることよと、―・しき心地す」
②そらぞらしい。しらじらしい。狂言、痩松「あの―・しい面はいの」
しれ‐た【知れた】
①わかりきったさま。あたりまえであること。また、高がしれたさま。歌舞伎、韓人漢文手管始「ハテ―、…生け置ては折角押領有ても大学様の邪魔」
②一般に知れわたっているさま。好色一代男4「人の娘に限らず―いたづら」
⇒しれた‐こと【知れた事】
しれた‐こと【知れた事】
①人々によく知られたこと。わかりきったこと。「―を言うな」
②それほどではないこと。「高いといっても―さ」
⇒しれ‐た【知れた】
し‐れつ【歯列】
①歯ならび。歯なみ。「―矯正」
②歯が並んでいるように並ぶこと。
し‐れつ【熾烈】
(「熾」は火勢が強い意)勢いがさかんではげしいさま。「―な戦い」「―をきわめる」
じれった・い【焦れったい】
〔形〕
思うようにならないで腹立たしい。いらだたしい。はがゆい。東海道中膝栗毛5「おいらもさつきにから―・くてならなんだ」。「―・い、早くしろ」「―・い話」
じれった‐むすび【じれった結び】
江戸後期の女の髪の結い方で、下流の女または洗髪した女などが、無造作に櫛巻風に結うもの。
ジレッタント【dilettante】
⇒ディレッタント
しれっ‐と
〔副〕
他からの働きかけにも動ぜず平然としているさま。何事もなかったかの如く振る舞うさま。「追及の質問に―答える」
しれとこ【知床】
北海道北東端の斜里・羅臼両町全域と、その周辺海域。2005年、世界自然遺産に登録。
知床
提供:NHK
 知床
提供:NHK
⇒しれとこ‐こくりつこうえん【知床国立公園】
⇒しれとこ‐はんとう【知床半島】
しれとこ‐こくりつこうえん【知床国立公園】‥ヱン
知床半島を中心とする国立公園。半島をおおう原生林・火山性湖沼群が特色。
知床連山
撮影:山梨勝弘
知床
提供:NHK
⇒しれとこ‐こくりつこうえん【知床国立公園】
⇒しれとこ‐はんとう【知床半島】
しれとこ‐こくりつこうえん【知床国立公園】‥ヱン
知床半島を中心とする国立公園。半島をおおう原生林・火山性湖沼群が特色。
知床連山
撮影:山梨勝弘
 ⇒しれとこ【知床】
しれとこ‐はんとう【知床半島】‥タウ
北海道北東端、オホーツク海に突出する細長い半島。中央に1000メートル以上の火山が並び、海岸線は断崖が多い。
⇒しれとこ【知床】
シレノス【Silēnos】
ギリシア神話で山野の精霊。好色な老人だが、深い叡知も持つ。
しれ‐ば・む【痴ればむ】
〔自四〕
おろかに見える。栄華物語月宴「美しき御心ならで、うたてひがひがしく―・みて」
しれ‐びと【痴れ人】
おろかな人。ばかもの。
しれ‐もの【痴れ者】
①おろかな者。源氏物語帚木「なにがしは―の物語をせん」
②狼藉ろうぜき者。乱暴者。弁慶物語「弁慶もとより―にて、行きあふ者を蹴倒し、踏み倒す事、たびたびなれば」
③その道にうちこんでいる者。その道でのしたたか者。奥の細道「風流の―」
しれ‐ものぐるい【痴れ物狂い】‥グルヒ
おろかで、常軌を逸していること。また、そのような人。宇治拾遺物語2「かくえもいはぬ―とは知りたりつれども」
し・れる【知れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
①おのずと知る、または知られた状態に至る。狂言、六地蔵「都の様子を見るに、知らぬ事は呼ばはつて通ると、―・れると見えた」。「お里が―・れる」「得体が―・れない」「高が―・れる」
②人に知られるようにする。知らせる。万葉集8「春の野にあさる鴙きぎしの妻恋ひに己があたりを人に―・れつつ」。拾遺和歌集恋「恋すてふわが名はまだきたちにけり人―・れずこそ思ひそめしか」
③(「…かも―・れない」の形で)その可能性もあることを示す。「来るかも―・れない」
④(不定詞に続けて「…か―・れない」の形で)言い表しがたいほどの甚だしさを示す。「どんなに嬉しかったか―・れない」
し・れる【痴れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
(一説、「しれ」は「領しる」の受身形で、「支配される」が原義)
①判断・識別の能力がはたらかなくなる。おろかになる。ぼける。竹取物語「心地ただ―・れに―・れてまもり合へり」。「酔い―・れる」
②(「たり」を伴って)ふざける。いたずらを好む。徒然草「―・れたる女房ども、若き男達の参らるる毎に、郭公ほととぎすや聞き給へると問ひてこころみられけるに」
じ・れる【焦れる】
〔自下一〕
心のままにならず、もどかしく思う。せいていらだつ。いらいらする。浄瑠璃、神霊矢口渡「―・れさせて討死さすか」。「相手の態度に―・れる」
しれ‐わた・る【知れ渡る】
〔自五〕
多くの人に知られる。「うわさが町中に―・る」
しれ‐わらい【痴れ笑い】‥ワラヒ
おろかなさまで笑うこと。ばかわらい。義経記8「―してあるは只事ならず」
し‐れん【思恋】
思い慕うこと。恋しく思うこと。
し‐れん【試練・試煉】
信仰・決心・実力の程度をこころみためすこと。また、そのための苦難。「―に耐える」「―を受ける」
じ‐れんが【地連歌】ヂ‥
連歌で、特別に趣向をこらすことなく、淡々と付け進めていく付け方。連理秘抄「常の―に、言葉の幽玄はあらはる也」
ジレンマ【dilemma】
⇒ディレンマ
しろ【代】
①かわりのもの。代用。播磨風土記「塩―の田」。万葉集8「たな霧らひ雪も降らぬか梅の花咲かぬが―にそへてだに見む」
②その物の代りとして償う金銭や物品。代価。代金。謡曲、烏帽子折「およそ烏帽子の―は定まりて候ふほどに」。「飲み―」
③材料。「壁―」
④何かのために取っておく部分。「糊―」「縫―」
⑤(「茸の代」の意)菌類が菌糸などを伸ばし、地中あるいは地表で占有した特定の場所のこと。ふつう、毎年そこにきのこが生ずる。
⑥田。田地。また、田の一区画・一区域。平家物語3「田―を育王山へ申し寄せて」。「―を掻く」
⑦古代・中世の田地の丈量単位。稲1束を収穫する面積を1代とする。律令制では50代を1段、500代を1町歩とした。束代そくしろ。
しろ【白】
①太陽の光線をあらゆる波長にわたって一様に反射することによって見える色。雪のような色。
Munsell color system: N9.5
②何も書いたり加工したりしてないこと。「―紙子」
③囲碁で、白石の略。また、白石を持つ方。後手ごて。↔黒。
④「しろがね(銀)」の略。梅暦「―の喜世留の重たきやつを」
⑤犯罪容疑が晴れること。また、その人。無罪。潔白。「判決は―と出た」↔黒
しろ【城】
敵を防ぐために築いた軍事的構造物。日本では、古くは柵さくや石垣または濠ほり・土塁をめぐらしたが、中世には、地形を利用して防御を施す山城やまじろが発達し、もっぱら戦闘用であった。戦国時代以降は、領内統治・城内居住・権勢表示などをも兼ねた、いわゆる城郭が完成。多く平野にのぞむ小丘の上または平地に築かれ、二重三重に濠をめぐらし、本丸・二の丸・三の丸などに郭くるわを区分、石塁上に多数の櫓やぐら類を建てて視察・射撃に利し、本丸には天守閣を設けて郭の中軸とし、表には大手門、裏には搦手からめての門を構え、住居用の殿舎をも備えた。き(城)。じょう。
しろ【子路】
①孔門十哲の一人。姓は仲、名は由。子路は字。魯の人。直情で勇を好んだ。季路。(前542〜前480)
②「論語」の編名。
し‐ろ【支路】
えだみち。わかれみち。
じ‐ろ【地炉】ヂ‥
地上または床に切った炉。いろり。
しろ‐あい【白藍】‥アヰ
藍(インジゴ)を還元して得る白色の粉末。アルカリ液に溶解し、藍染めに用いる。はくらん。
しろ‐あお【白青】‥アヲ
⇒しらあお
しろ‐あお【白襖】‥アヲ
表裏ともに白い狩衣かりぎぬ。
しろ‐あかげ【白赤毛】
⇒しらあかげ
しろ‐あがり【白上り】
(→)「しろあげ」に同じ。
しろ‐あげ【白上げ】
染物で、黒地または紺地などに白く模様を染め抜くこと。しろあがり。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―に紺染の大夜着」
しろ‐あしげ【白葦毛】
⇒しらあしげ
しろ‐あと【城跡・城址】
城のあったところ。じょうし。
しろ‐あぶら【白油】
白胡麻からとった油。しらしぼり。
しろ‐あめ【白飴】
固飴かたあめの一種。水飴を煮詰め、冷ましながらひきのばして飴の中に空気を入れ、気泡を作ることによって白色にしたもの。
しろ‐あり【白蟻】
シロアリ目の昆虫の総称。体の形はややアリに似るが常に暗い所にすみ、体の色も白い。アリに似た社会生活を営み、木材の内部に食い入って、家屋などに大害を加える。日本にはヤマトシロアリ・イエシロアリなど、熱帯には巨大な塚を作るツカシロアリなどがいる。
いえしろあり
⇒しれとこ【知床】
しれとこ‐はんとう【知床半島】‥タウ
北海道北東端、オホーツク海に突出する細長い半島。中央に1000メートル以上の火山が並び、海岸線は断崖が多い。
⇒しれとこ【知床】
シレノス【Silēnos】
ギリシア神話で山野の精霊。好色な老人だが、深い叡知も持つ。
しれ‐ば・む【痴ればむ】
〔自四〕
おろかに見える。栄華物語月宴「美しき御心ならで、うたてひがひがしく―・みて」
しれ‐びと【痴れ人】
おろかな人。ばかもの。
しれ‐もの【痴れ者】
①おろかな者。源氏物語帚木「なにがしは―の物語をせん」
②狼藉ろうぜき者。乱暴者。弁慶物語「弁慶もとより―にて、行きあふ者を蹴倒し、踏み倒す事、たびたびなれば」
③その道にうちこんでいる者。その道でのしたたか者。奥の細道「風流の―」
しれ‐ものぐるい【痴れ物狂い】‥グルヒ
おろかで、常軌を逸していること。また、そのような人。宇治拾遺物語2「かくえもいはぬ―とは知りたりつれども」
し・れる【知れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
①おのずと知る、または知られた状態に至る。狂言、六地蔵「都の様子を見るに、知らぬ事は呼ばはつて通ると、―・れると見えた」。「お里が―・れる」「得体が―・れない」「高が―・れる」
②人に知られるようにする。知らせる。万葉集8「春の野にあさる鴙きぎしの妻恋ひに己があたりを人に―・れつつ」。拾遺和歌集恋「恋すてふわが名はまだきたちにけり人―・れずこそ思ひそめしか」
③(「…かも―・れない」の形で)その可能性もあることを示す。「来るかも―・れない」
④(不定詞に続けて「…か―・れない」の形で)言い表しがたいほどの甚だしさを示す。「どんなに嬉しかったか―・れない」
し・れる【痴れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
(一説、「しれ」は「領しる」の受身形で、「支配される」が原義)
①判断・識別の能力がはたらかなくなる。おろかになる。ぼける。竹取物語「心地ただ―・れに―・れてまもり合へり」。「酔い―・れる」
②(「たり」を伴って)ふざける。いたずらを好む。徒然草「―・れたる女房ども、若き男達の参らるる毎に、郭公ほととぎすや聞き給へると問ひてこころみられけるに」
じ・れる【焦れる】
〔自下一〕
心のままにならず、もどかしく思う。せいていらだつ。いらいらする。浄瑠璃、神霊矢口渡「―・れさせて討死さすか」。「相手の態度に―・れる」
しれ‐わた・る【知れ渡る】
〔自五〕
多くの人に知られる。「うわさが町中に―・る」
しれ‐わらい【痴れ笑い】‥ワラヒ
おろかなさまで笑うこと。ばかわらい。義経記8「―してあるは只事ならず」
し‐れん【思恋】
思い慕うこと。恋しく思うこと。
し‐れん【試練・試煉】
信仰・決心・実力の程度をこころみためすこと。また、そのための苦難。「―に耐える」「―を受ける」
じ‐れんが【地連歌】ヂ‥
連歌で、特別に趣向をこらすことなく、淡々と付け進めていく付け方。連理秘抄「常の―に、言葉の幽玄はあらはる也」
ジレンマ【dilemma】
⇒ディレンマ
しろ【代】
①かわりのもの。代用。播磨風土記「塩―の田」。万葉集8「たな霧らひ雪も降らぬか梅の花咲かぬが―にそへてだに見む」
②その物の代りとして償う金銭や物品。代価。代金。謡曲、烏帽子折「およそ烏帽子の―は定まりて候ふほどに」。「飲み―」
③材料。「壁―」
④何かのために取っておく部分。「糊―」「縫―」
⑤(「茸の代」の意)菌類が菌糸などを伸ばし、地中あるいは地表で占有した特定の場所のこと。ふつう、毎年そこにきのこが生ずる。
⑥田。田地。また、田の一区画・一区域。平家物語3「田―を育王山へ申し寄せて」。「―を掻く」
⑦古代・中世の田地の丈量単位。稲1束を収穫する面積を1代とする。律令制では50代を1段、500代を1町歩とした。束代そくしろ。
しろ【白】
①太陽の光線をあらゆる波長にわたって一様に反射することによって見える色。雪のような色。
Munsell color system: N9.5
②何も書いたり加工したりしてないこと。「―紙子」
③囲碁で、白石の略。また、白石を持つ方。後手ごて。↔黒。
④「しろがね(銀)」の略。梅暦「―の喜世留の重たきやつを」
⑤犯罪容疑が晴れること。また、その人。無罪。潔白。「判決は―と出た」↔黒
しろ【城】
敵を防ぐために築いた軍事的構造物。日本では、古くは柵さくや石垣または濠ほり・土塁をめぐらしたが、中世には、地形を利用して防御を施す山城やまじろが発達し、もっぱら戦闘用であった。戦国時代以降は、領内統治・城内居住・権勢表示などをも兼ねた、いわゆる城郭が完成。多く平野にのぞむ小丘の上または平地に築かれ、二重三重に濠をめぐらし、本丸・二の丸・三の丸などに郭くるわを区分、石塁上に多数の櫓やぐら類を建てて視察・射撃に利し、本丸には天守閣を設けて郭の中軸とし、表には大手門、裏には搦手からめての門を構え、住居用の殿舎をも備えた。き(城)。じょう。
しろ【子路】
①孔門十哲の一人。姓は仲、名は由。子路は字。魯の人。直情で勇を好んだ。季路。(前542〜前480)
②「論語」の編名。
し‐ろ【支路】
えだみち。わかれみち。
じ‐ろ【地炉】ヂ‥
地上または床に切った炉。いろり。
しろ‐あい【白藍】‥アヰ
藍(インジゴ)を還元して得る白色の粉末。アルカリ液に溶解し、藍染めに用いる。はくらん。
しろ‐あお【白青】‥アヲ
⇒しらあお
しろ‐あお【白襖】‥アヲ
表裏ともに白い狩衣かりぎぬ。
しろ‐あかげ【白赤毛】
⇒しらあかげ
しろ‐あがり【白上り】
(→)「しろあげ」に同じ。
しろ‐あげ【白上げ】
染物で、黒地または紺地などに白く模様を染め抜くこと。しろあがり。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―に紺染の大夜着」
しろ‐あしげ【白葦毛】
⇒しらあしげ
しろ‐あと【城跡・城址】
城のあったところ。じょうし。
しろ‐あぶら【白油】
白胡麻からとった油。しらしぼり。
しろ‐あめ【白飴】
固飴かたあめの一種。水飴を煮詰め、冷ましながらひきのばして飴の中に空気を入れ、気泡を作ることによって白色にしたもの。
しろ‐あり【白蟻】
シロアリ目の昆虫の総称。体の形はややアリに似るが常に暗い所にすみ、体の色も白い。アリに似た社会生活を営み、木材の内部に食い入って、家屋などに大害を加える。日本にはヤマトシロアリ・イエシロアリなど、熱帯には巨大な塚を作るツカシロアリなどがいる。
いえしろあり
 シロアリ
撮影:海野和男
シロアリ
撮影:海野和男
 ⇒しろあり‐もどき【擬白蟻】
しろあり‐もどき【擬白蟻】
シロアリモドキ目シロアリモドキ科の昆虫の総称。細長い小昆虫で不完全変態。前肢の跗節から糸を出して樹皮上に天幕を張り、その中で小群の集団生活を営み、植物質を食う。日本にはコケシロアリモドキだけが知られ、九州に分布。体長5〜10ミリメートル。
⇒しろ‐あり【白蟻】
しろ‐あわ【白泡・白沫】
白いあわ。口から吹く白い泡。
しろ‐あん【白餡】
ゆでた白小豆や白隠元などをすりつぶしてこしたものに白砂糖・水飴を練りまぜて作った白い餡。
しろ・い【白い】
〔形〕[文]しろ・し(ク)
①白色である。白である。雪のような色をしている。古事記上「
⇒しろあり‐もどき【擬白蟻】
しろあり‐もどき【擬白蟻】
シロアリモドキ目シロアリモドキ科の昆虫の総称。細長い小昆虫で不完全変態。前肢の跗節から糸を出して樹皮上に天幕を張り、その中で小群の集団生活を営み、植物質を食う。日本にはコケシロアリモドキだけが知られ、九州に分布。体長5〜10ミリメートル。
⇒しろ‐あり【白蟻】
しろ‐あわ【白泡・白沫】
白いあわ。口から吹く白い泡。
しろ‐あん【白餡】
ゆでた白小豆や白隠元などをすりつぶしてこしたものに白砂糖・水飴を練りまぜて作った白い餡。
しろ・い【白い】
〔形〕[文]しろ・し(ク)
①白色である。白である。雪のような色をしている。古事記上「 綱たくずのの―・き腕ただむき」。天草本平家物語「黒かつた髪もみな―・うなり」。「―・い雲」
②どの色にも染めてない。また、何も書いてない。枕草子191「―・き単ひとえのいたうしぼみたるを」。「―・いページ」
③明るい。輝いている。平家物語5「月―・く嵐はげしかりし夜」
④経験にとぼしい。野暮である。浮世草子、好色盛衰記「諸分合点のゆかぬお客なれば、―・い事ども有るべし」
⑤潔白である。正しい。人情本、恋の花染「知県所だいかんしよへ引き摺り出し、―・いか黒いか分けやせう」
⇒白い大陸
⇒白い歯を見せない
⇒白い眼で見る
しろい【白井】‥ヰ
千葉県北西部の市。千葉ニュータウンの開発とともに住宅地化が進行。ナシ栽培が盛ん。人口5万3千。
しろいきょとう【白い巨塔】‥タフ
小説。山崎豊子作。1965年(昭和40)刊。関西の大学病院を舞台に人事抗争や医療問題を描いた社会小説。
しろいし【白石】
宮城県南西部、白石盆地の南部を占める市。もと仙台藩支藩片倉氏の城下町。蔵王観光の入口で、西部に鎌先・小原の温泉がある。人口3万9千。
綱たくずのの―・き腕ただむき」。天草本平家物語「黒かつた髪もみな―・うなり」。「―・い雲」
②どの色にも染めてない。また、何も書いてない。枕草子191「―・き単ひとえのいたうしぼみたるを」。「―・いページ」
③明るい。輝いている。平家物語5「月―・く嵐はげしかりし夜」
④経験にとぼしい。野暮である。浮世草子、好色盛衰記「諸分合点のゆかぬお客なれば、―・い事ども有るべし」
⑤潔白である。正しい。人情本、恋の花染「知県所だいかんしよへ引き摺り出し、―・いか黒いか分けやせう」
⇒白い大陸
⇒白い歯を見せない
⇒白い眼で見る
しろい【白井】‥ヰ
千葉県北西部の市。千葉ニュータウンの開発とともに住宅地化が進行。ナシ栽培が盛ん。人口5万3千。
しろいきょとう【白い巨塔】‥タフ
小説。山崎豊子作。1965年(昭和40)刊。関西の大学病院を舞台に人事抗争や医療問題を描いた社会小説。
しろいし【白石】
宮城県南西部、白石盆地の南部を占める市。もと仙台藩支藩片倉氏の城下町。蔵王観光の入口で、西部に鎌先・小原の温泉がある。人口3万9千。
 知床
提供:NHK
⇒しれとこ‐こくりつこうえん【知床国立公園】
⇒しれとこ‐はんとう【知床半島】
しれとこ‐こくりつこうえん【知床国立公園】‥ヱン
知床半島を中心とする国立公園。半島をおおう原生林・火山性湖沼群が特色。
知床連山
撮影:山梨勝弘
知床
提供:NHK
⇒しれとこ‐こくりつこうえん【知床国立公園】
⇒しれとこ‐はんとう【知床半島】
しれとこ‐こくりつこうえん【知床国立公園】‥ヱン
知床半島を中心とする国立公園。半島をおおう原生林・火山性湖沼群が特色。
知床連山
撮影:山梨勝弘
 ⇒しれとこ【知床】
しれとこ‐はんとう【知床半島】‥タウ
北海道北東端、オホーツク海に突出する細長い半島。中央に1000メートル以上の火山が並び、海岸線は断崖が多い。
⇒しれとこ【知床】
シレノス【Silēnos】
ギリシア神話で山野の精霊。好色な老人だが、深い叡知も持つ。
しれ‐ば・む【痴ればむ】
〔自四〕
おろかに見える。栄華物語月宴「美しき御心ならで、うたてひがひがしく―・みて」
しれ‐びと【痴れ人】
おろかな人。ばかもの。
しれ‐もの【痴れ者】
①おろかな者。源氏物語帚木「なにがしは―の物語をせん」
②狼藉ろうぜき者。乱暴者。弁慶物語「弁慶もとより―にて、行きあふ者を蹴倒し、踏み倒す事、たびたびなれば」
③その道にうちこんでいる者。その道でのしたたか者。奥の細道「風流の―」
しれ‐ものぐるい【痴れ物狂い】‥グルヒ
おろかで、常軌を逸していること。また、そのような人。宇治拾遺物語2「かくえもいはぬ―とは知りたりつれども」
し・れる【知れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
①おのずと知る、または知られた状態に至る。狂言、六地蔵「都の様子を見るに、知らぬ事は呼ばはつて通ると、―・れると見えた」。「お里が―・れる」「得体が―・れない」「高が―・れる」
②人に知られるようにする。知らせる。万葉集8「春の野にあさる鴙きぎしの妻恋ひに己があたりを人に―・れつつ」。拾遺和歌集恋「恋すてふわが名はまだきたちにけり人―・れずこそ思ひそめしか」
③(「…かも―・れない」の形で)その可能性もあることを示す。「来るかも―・れない」
④(不定詞に続けて「…か―・れない」の形で)言い表しがたいほどの甚だしさを示す。「どんなに嬉しかったか―・れない」
し・れる【痴れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
(一説、「しれ」は「領しる」の受身形で、「支配される」が原義)
①判断・識別の能力がはたらかなくなる。おろかになる。ぼける。竹取物語「心地ただ―・れに―・れてまもり合へり」。「酔い―・れる」
②(「たり」を伴って)ふざける。いたずらを好む。徒然草「―・れたる女房ども、若き男達の参らるる毎に、郭公ほととぎすや聞き給へると問ひてこころみられけるに」
じ・れる【焦れる】
〔自下一〕
心のままにならず、もどかしく思う。せいていらだつ。いらいらする。浄瑠璃、神霊矢口渡「―・れさせて討死さすか」。「相手の態度に―・れる」
しれ‐わた・る【知れ渡る】
〔自五〕
多くの人に知られる。「うわさが町中に―・る」
しれ‐わらい【痴れ笑い】‥ワラヒ
おろかなさまで笑うこと。ばかわらい。義経記8「―してあるは只事ならず」
し‐れん【思恋】
思い慕うこと。恋しく思うこと。
し‐れん【試練・試煉】
信仰・決心・実力の程度をこころみためすこと。また、そのための苦難。「―に耐える」「―を受ける」
じ‐れんが【地連歌】ヂ‥
連歌で、特別に趣向をこらすことなく、淡々と付け進めていく付け方。連理秘抄「常の―に、言葉の幽玄はあらはる也」
ジレンマ【dilemma】
⇒ディレンマ
しろ【代】
①かわりのもの。代用。播磨風土記「塩―の田」。万葉集8「たな霧らひ雪も降らぬか梅の花咲かぬが―にそへてだに見む」
②その物の代りとして償う金銭や物品。代価。代金。謡曲、烏帽子折「およそ烏帽子の―は定まりて候ふほどに」。「飲み―」
③材料。「壁―」
④何かのために取っておく部分。「糊―」「縫―」
⑤(「茸の代」の意)菌類が菌糸などを伸ばし、地中あるいは地表で占有した特定の場所のこと。ふつう、毎年そこにきのこが生ずる。
⑥田。田地。また、田の一区画・一区域。平家物語3「田―を育王山へ申し寄せて」。「―を掻く」
⑦古代・中世の田地の丈量単位。稲1束を収穫する面積を1代とする。律令制では50代を1段、500代を1町歩とした。束代そくしろ。
しろ【白】
①太陽の光線をあらゆる波長にわたって一様に反射することによって見える色。雪のような色。
Munsell color system: N9.5
②何も書いたり加工したりしてないこと。「―紙子」
③囲碁で、白石の略。また、白石を持つ方。後手ごて。↔黒。
④「しろがね(銀)」の略。梅暦「―の喜世留の重たきやつを」
⑤犯罪容疑が晴れること。また、その人。無罪。潔白。「判決は―と出た」↔黒
しろ【城】
敵を防ぐために築いた軍事的構造物。日本では、古くは柵さくや石垣または濠ほり・土塁をめぐらしたが、中世には、地形を利用して防御を施す山城やまじろが発達し、もっぱら戦闘用であった。戦国時代以降は、領内統治・城内居住・権勢表示などをも兼ねた、いわゆる城郭が完成。多く平野にのぞむ小丘の上または平地に築かれ、二重三重に濠をめぐらし、本丸・二の丸・三の丸などに郭くるわを区分、石塁上に多数の櫓やぐら類を建てて視察・射撃に利し、本丸には天守閣を設けて郭の中軸とし、表には大手門、裏には搦手からめての門を構え、住居用の殿舎をも備えた。き(城)。じょう。
しろ【子路】
①孔門十哲の一人。姓は仲、名は由。子路は字。魯の人。直情で勇を好んだ。季路。(前542〜前480)
②「論語」の編名。
し‐ろ【支路】
えだみち。わかれみち。
じ‐ろ【地炉】ヂ‥
地上または床に切った炉。いろり。
しろ‐あい【白藍】‥アヰ
藍(インジゴ)を還元して得る白色の粉末。アルカリ液に溶解し、藍染めに用いる。はくらん。
しろ‐あお【白青】‥アヲ
⇒しらあお
しろ‐あお【白襖】‥アヲ
表裏ともに白い狩衣かりぎぬ。
しろ‐あかげ【白赤毛】
⇒しらあかげ
しろ‐あがり【白上り】
(→)「しろあげ」に同じ。
しろ‐あげ【白上げ】
染物で、黒地または紺地などに白く模様を染め抜くこと。しろあがり。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―に紺染の大夜着」
しろ‐あしげ【白葦毛】
⇒しらあしげ
しろ‐あと【城跡・城址】
城のあったところ。じょうし。
しろ‐あぶら【白油】
白胡麻からとった油。しらしぼり。
しろ‐あめ【白飴】
固飴かたあめの一種。水飴を煮詰め、冷ましながらひきのばして飴の中に空気を入れ、気泡を作ることによって白色にしたもの。
しろ‐あり【白蟻】
シロアリ目の昆虫の総称。体の形はややアリに似るが常に暗い所にすみ、体の色も白い。アリに似た社会生活を営み、木材の内部に食い入って、家屋などに大害を加える。日本にはヤマトシロアリ・イエシロアリなど、熱帯には巨大な塚を作るツカシロアリなどがいる。
いえしろあり
⇒しれとこ【知床】
しれとこ‐はんとう【知床半島】‥タウ
北海道北東端、オホーツク海に突出する細長い半島。中央に1000メートル以上の火山が並び、海岸線は断崖が多い。
⇒しれとこ【知床】
シレノス【Silēnos】
ギリシア神話で山野の精霊。好色な老人だが、深い叡知も持つ。
しれ‐ば・む【痴ればむ】
〔自四〕
おろかに見える。栄華物語月宴「美しき御心ならで、うたてひがひがしく―・みて」
しれ‐びと【痴れ人】
おろかな人。ばかもの。
しれ‐もの【痴れ者】
①おろかな者。源氏物語帚木「なにがしは―の物語をせん」
②狼藉ろうぜき者。乱暴者。弁慶物語「弁慶もとより―にて、行きあふ者を蹴倒し、踏み倒す事、たびたびなれば」
③その道にうちこんでいる者。その道でのしたたか者。奥の細道「風流の―」
しれ‐ものぐるい【痴れ物狂い】‥グルヒ
おろかで、常軌を逸していること。また、そのような人。宇治拾遺物語2「かくえもいはぬ―とは知りたりつれども」
し・れる【知れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
①おのずと知る、または知られた状態に至る。狂言、六地蔵「都の様子を見るに、知らぬ事は呼ばはつて通ると、―・れると見えた」。「お里が―・れる」「得体が―・れない」「高が―・れる」
②人に知られるようにする。知らせる。万葉集8「春の野にあさる鴙きぎしの妻恋ひに己があたりを人に―・れつつ」。拾遺和歌集恋「恋すてふわが名はまだきたちにけり人―・れずこそ思ひそめしか」
③(「…かも―・れない」の形で)その可能性もあることを示す。「来るかも―・れない」
④(不定詞に続けて「…か―・れない」の形で)言い表しがたいほどの甚だしさを示す。「どんなに嬉しかったか―・れない」
し・れる【痴れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
(一説、「しれ」は「領しる」の受身形で、「支配される」が原義)
①判断・識別の能力がはたらかなくなる。おろかになる。ぼける。竹取物語「心地ただ―・れに―・れてまもり合へり」。「酔い―・れる」
②(「たり」を伴って)ふざける。いたずらを好む。徒然草「―・れたる女房ども、若き男達の参らるる毎に、郭公ほととぎすや聞き給へると問ひてこころみられけるに」
じ・れる【焦れる】
〔自下一〕
心のままにならず、もどかしく思う。せいていらだつ。いらいらする。浄瑠璃、神霊矢口渡「―・れさせて討死さすか」。「相手の態度に―・れる」
しれ‐わた・る【知れ渡る】
〔自五〕
多くの人に知られる。「うわさが町中に―・る」
しれ‐わらい【痴れ笑い】‥ワラヒ
おろかなさまで笑うこと。ばかわらい。義経記8「―してあるは只事ならず」
し‐れん【思恋】
思い慕うこと。恋しく思うこと。
し‐れん【試練・試煉】
信仰・決心・実力の程度をこころみためすこと。また、そのための苦難。「―に耐える」「―を受ける」
じ‐れんが【地連歌】ヂ‥
連歌で、特別に趣向をこらすことなく、淡々と付け進めていく付け方。連理秘抄「常の―に、言葉の幽玄はあらはる也」
ジレンマ【dilemma】
⇒ディレンマ
しろ【代】
①かわりのもの。代用。播磨風土記「塩―の田」。万葉集8「たな霧らひ雪も降らぬか梅の花咲かぬが―にそへてだに見む」
②その物の代りとして償う金銭や物品。代価。代金。謡曲、烏帽子折「およそ烏帽子の―は定まりて候ふほどに」。「飲み―」
③材料。「壁―」
④何かのために取っておく部分。「糊―」「縫―」
⑤(「茸の代」の意)菌類が菌糸などを伸ばし、地中あるいは地表で占有した特定の場所のこと。ふつう、毎年そこにきのこが生ずる。
⑥田。田地。また、田の一区画・一区域。平家物語3「田―を育王山へ申し寄せて」。「―を掻く」
⑦古代・中世の田地の丈量単位。稲1束を収穫する面積を1代とする。律令制では50代を1段、500代を1町歩とした。束代そくしろ。
しろ【白】
①太陽の光線をあらゆる波長にわたって一様に反射することによって見える色。雪のような色。
Munsell color system: N9.5
②何も書いたり加工したりしてないこと。「―紙子」
③囲碁で、白石の略。また、白石を持つ方。後手ごて。↔黒。
④「しろがね(銀)」の略。梅暦「―の喜世留の重たきやつを」
⑤犯罪容疑が晴れること。また、その人。無罪。潔白。「判決は―と出た」↔黒
しろ【城】
敵を防ぐために築いた軍事的構造物。日本では、古くは柵さくや石垣または濠ほり・土塁をめぐらしたが、中世には、地形を利用して防御を施す山城やまじろが発達し、もっぱら戦闘用であった。戦国時代以降は、領内統治・城内居住・権勢表示などをも兼ねた、いわゆる城郭が完成。多く平野にのぞむ小丘の上または平地に築かれ、二重三重に濠をめぐらし、本丸・二の丸・三の丸などに郭くるわを区分、石塁上に多数の櫓やぐら類を建てて視察・射撃に利し、本丸には天守閣を設けて郭の中軸とし、表には大手門、裏には搦手からめての門を構え、住居用の殿舎をも備えた。き(城)。じょう。
しろ【子路】
①孔門十哲の一人。姓は仲、名は由。子路は字。魯の人。直情で勇を好んだ。季路。(前542〜前480)
②「論語」の編名。
し‐ろ【支路】
えだみち。わかれみち。
じ‐ろ【地炉】ヂ‥
地上または床に切った炉。いろり。
しろ‐あい【白藍】‥アヰ
藍(インジゴ)を還元して得る白色の粉末。アルカリ液に溶解し、藍染めに用いる。はくらん。
しろ‐あお【白青】‥アヲ
⇒しらあお
しろ‐あお【白襖】‥アヲ
表裏ともに白い狩衣かりぎぬ。
しろ‐あかげ【白赤毛】
⇒しらあかげ
しろ‐あがり【白上り】
(→)「しろあげ」に同じ。
しろ‐あげ【白上げ】
染物で、黒地または紺地などに白く模様を染め抜くこと。しろあがり。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―に紺染の大夜着」
しろ‐あしげ【白葦毛】
⇒しらあしげ
しろ‐あと【城跡・城址】
城のあったところ。じょうし。
しろ‐あぶら【白油】
白胡麻からとった油。しらしぼり。
しろ‐あめ【白飴】
固飴かたあめの一種。水飴を煮詰め、冷ましながらひきのばして飴の中に空気を入れ、気泡を作ることによって白色にしたもの。
しろ‐あり【白蟻】
シロアリ目の昆虫の総称。体の形はややアリに似るが常に暗い所にすみ、体の色も白い。アリに似た社会生活を営み、木材の内部に食い入って、家屋などに大害を加える。日本にはヤマトシロアリ・イエシロアリなど、熱帯には巨大な塚を作るツカシロアリなどがいる。
いえしろあり
 シロアリ
撮影:海野和男
シロアリ
撮影:海野和男
 ⇒しろあり‐もどき【擬白蟻】
しろあり‐もどき【擬白蟻】
シロアリモドキ目シロアリモドキ科の昆虫の総称。細長い小昆虫で不完全変態。前肢の跗節から糸を出して樹皮上に天幕を張り、その中で小群の集団生活を営み、植物質を食う。日本にはコケシロアリモドキだけが知られ、九州に分布。体長5〜10ミリメートル。
⇒しろ‐あり【白蟻】
しろ‐あわ【白泡・白沫】
白いあわ。口から吹く白い泡。
しろ‐あん【白餡】
ゆでた白小豆や白隠元などをすりつぶしてこしたものに白砂糖・水飴を練りまぜて作った白い餡。
しろ・い【白い】
〔形〕[文]しろ・し(ク)
①白色である。白である。雪のような色をしている。古事記上「
⇒しろあり‐もどき【擬白蟻】
しろあり‐もどき【擬白蟻】
シロアリモドキ目シロアリモドキ科の昆虫の総称。細長い小昆虫で不完全変態。前肢の跗節から糸を出して樹皮上に天幕を張り、その中で小群の集団生活を営み、植物質を食う。日本にはコケシロアリモドキだけが知られ、九州に分布。体長5〜10ミリメートル。
⇒しろ‐あり【白蟻】
しろ‐あわ【白泡・白沫】
白いあわ。口から吹く白い泡。
しろ‐あん【白餡】
ゆでた白小豆や白隠元などをすりつぶしてこしたものに白砂糖・水飴を練りまぜて作った白い餡。
しろ・い【白い】
〔形〕[文]しろ・し(ク)
①白色である。白である。雪のような色をしている。古事記上「 綱たくずのの―・き腕ただむき」。天草本平家物語「黒かつた髪もみな―・うなり」。「―・い雲」
②どの色にも染めてない。また、何も書いてない。枕草子191「―・き単ひとえのいたうしぼみたるを」。「―・いページ」
③明るい。輝いている。平家物語5「月―・く嵐はげしかりし夜」
④経験にとぼしい。野暮である。浮世草子、好色盛衰記「諸分合点のゆかぬお客なれば、―・い事ども有るべし」
⑤潔白である。正しい。人情本、恋の花染「知県所だいかんしよへ引き摺り出し、―・いか黒いか分けやせう」
⇒白い大陸
⇒白い歯を見せない
⇒白い眼で見る
しろい【白井】‥ヰ
千葉県北西部の市。千葉ニュータウンの開発とともに住宅地化が進行。ナシ栽培が盛ん。人口5万3千。
しろいきょとう【白い巨塔】‥タフ
小説。山崎豊子作。1965年(昭和40)刊。関西の大学病院を舞台に人事抗争や医療問題を描いた社会小説。
しろいし【白石】
宮城県南西部、白石盆地の南部を占める市。もと仙台藩支藩片倉氏の城下町。蔵王観光の入口で、西部に鎌先・小原の温泉がある。人口3万9千。
綱たくずのの―・き腕ただむき」。天草本平家物語「黒かつた髪もみな―・うなり」。「―・い雲」
②どの色にも染めてない。また、何も書いてない。枕草子191「―・き単ひとえのいたうしぼみたるを」。「―・いページ」
③明るい。輝いている。平家物語5「月―・く嵐はげしかりし夜」
④経験にとぼしい。野暮である。浮世草子、好色盛衰記「諸分合点のゆかぬお客なれば、―・い事ども有るべし」
⑤潔白である。正しい。人情本、恋の花染「知県所だいかんしよへ引き摺り出し、―・いか黒いか分けやせう」
⇒白い大陸
⇒白い歯を見せない
⇒白い眼で見る
しろい【白井】‥ヰ
千葉県北西部の市。千葉ニュータウンの開発とともに住宅地化が進行。ナシ栽培が盛ん。人口5万3千。
しろいきょとう【白い巨塔】‥タフ
小説。山崎豊子作。1965年(昭和40)刊。関西の大学病院を舞台に人事抗争や医療問題を描いた社会小説。
しろいし【白石】
宮城県南西部、白石盆地の南部を占める市。もと仙台藩支藩片倉氏の城下町。蔵王観光の入口で、西部に鎌先・小原の温泉がある。人口3万9千。
しれ‐た【知れた】🔗⭐🔉
しれ‐た【知れた】
①わかりきったさま。あたりまえであること。また、高がしれたさま。歌舞伎、韓人漢文手管始「ハテ―、…生け置ては折角押領有ても大学様の邪魔」
②一般に知れわたっているさま。好色一代男4「人の娘に限らず―いたづら」
⇒しれた‐こと【知れた事】
しれた‐こと【知れた事】🔗⭐🔉
しれた‐こと【知れた事】
①人々によく知られたこと。わかりきったこと。「―を言うな」
②それほどではないこと。「高いといっても―さ」
⇒しれ‐た【知れた】
し・れる【知れる】🔗⭐🔉
し・れる【知れる】
〔自下一〕[文]し・る(下二)
①おのずと知る、または知られた状態に至る。狂言、六地蔵「都の様子を見るに、知らぬ事は呼ばはつて通ると、―・れると見えた」。「お里が―・れる」「得体が―・れない」「高が―・れる」
②人に知られるようにする。知らせる。万葉集8「春の野にあさる鴙きぎしの妻恋ひに己があたりを人に―・れつつ」。拾遺和歌集恋「恋すてふわが名はまだきたちにけり人―・れずこそ思ひそめしか」
③(「…かも―・れない」の形で)その可能性もあることを示す。「来るかも―・れない」
④(不定詞に続けて「…か―・れない」の形で)言い表しがたいほどの甚だしさを示す。「どんなに嬉しかったか―・れない」
しれ‐わた・る【知れ渡る】🔗⭐🔉
しれ‐わた・る【知れ渡る】
〔自五〕
多くの人に知られる。「うわさが町中に―・る」
しろし‐め・す【知ろしめす】🔗⭐🔉
しろし‐め・す【知ろしめす】
〔他五〕
(「知る」の尊敬語「しろす」よりさらに敬意の強い言い方。上代には「しらしめす」とも)
①お知りになる。ご存知である。源氏物語花宴「くはしう―・し調へさせ給へるけなり」。天草本平家物語「鎌倉殿までもさる者のあるとは―・されつらう」
②領せられる。お治めになる。古今和歌集序「すべらぎの天の下―・すこと」。平家物語11「ただ世の乱れをしづめて、国を―・さんを君とせん」
③お世話なさる。源氏物語夢浮橋「更に―・すべきこととは、いかでか空に悟り侍らむ」
ち【知】🔗⭐🔉
ち【知】
①しること。しらせること。
②よくしること。したしくすること。しりあい。「旧―の仲」
③(「智」の通用字)さとること。
ち【智・知】🔗⭐🔉
ち‐いく【知育・智育】🔗⭐🔉
ち‐いく【知育・智育】
徳育・体育などに対して、知的認識能力・思考能力を高めることを目的とする教育。
ち‐いん【知音】🔗⭐🔉
ち‐いん【知音】
①[列子湯問](鍾子期しょうしきが、琴の名手伯牙の琴の音色をよく聞き分けた故事から)よく心を知り合っている人。親友。→高山流水→断琴の交わり。
②知りあい。知人。
③恋人。情人。好色一代男3「しほらしき女は大方―ありて」
⇒ちいん‐にょうぼう【知音女房】
ちいん‐にょうぼう【知音女房】‥バウ🔗⭐🔉
ちいん‐にょうぼう【知音女房】‥バウ
なじんだ女房。恋女房。東海道中膝栗毛8「ソリヤわしが―ぢやわいな」
⇒ち‐いん【知音】
ち‐え【知恵・智慧】‥ヱ🔗⭐🔉
ち‐え【知恵・智慧】‥ヱ
①物事の理を悟り、適切に処理する能力。「―を働かせる」「―がつく」
②〔仏〕(梵語prajñā般若。ふつう「智慧」と書く)真理を明らかにし、悟りを開く働き。宗教的叡知。六波羅蜜の第6。また、「慈悲」と対にして用いる。
③〔哲〕(sophia ギリシア・wisdom イギリス)四つの枢要徳の一つ。古代ギリシア以来さまざまな意味を与えられているが、今日では一般に、人生の指針となるような、人格と深く結びついている哲学的知識をいう。
⇒知恵出でて大偽あり
⇒知恵が回る
⇒知恵の持ち腐れ
⇒知恵は小出しにせよ
⇒知恵を借りる
⇒知恵を絞る
⇒知恵を付ける
ちえ‐いず【知恵伊豆】‥ヱ‥ヅ🔗⭐🔉
ちえ‐いず【知恵伊豆】‥ヱ‥ヅ
松平伊豆守信綱のぶつなのあだ名。
○知恵出でて大偽ありちえいでてたいぎあり
[老子第18章]昔、人間が素朴であった時代には、人々は自然に従って平和であったが、後世、人々の知恵が進んで不自然な人為が行われたので、大なる偽りを生じ、世の中が乱れてしまった。
⇒ち‐え【知恵・智慧】
○知恵が回るちえがまわる🔗⭐🔉
○知恵が回るちえがまわる
とっさにその場に合った判断ができる。頭の回転が速い。「よく―子」
⇒ち‐え【知恵・智慧】
ちえ‐がゆ【知恵粥】‥ヱ‥
(→)大師粥だいしがゆに同じ。
ち‐えき【地役】
①他人の土地を自分の土地の便益に供すること。
②地役権の略。
⇒ちえき‐けん【地役権】
ちえき‐けん【地役権】
〔法〕他人の土地を自己の土地の便益(通行・通水・眺望など)に供しうる物権。用益物権の一種。
⇒ち‐えき【地役】
ちえ‐くらべ【知恵競べ】‥ヱ‥
知恵の優劣をきそうこと。
チェコ【Czech】
中部ヨーロッパに位置する共和国。面積7万9000平方キロメートル。人口1020万7千(2004)。ボヘミアとモラヴィア両地方から成る。1939年スロヴァキアと分離してドイツに合併、45年再びスロヴァキアと合併。93年独立。2004年EU加盟。首都プラハ。狭義にはボヘミアを指す。→ヨーロッパ(図)。
プラハ
撮影:田沼武能
 ⇒チェコ‐ご【チェコ語】
⇒チェコ‐じけん【チェコ事件】
⇒チェコ‐スロヴァキア【Czech and Slovakia】
ちえ‐こう【智慧光】‥ヱクワウ
〔仏〕阿弥陀如来の十二光の一つ。衆生しゅじょうの無明の闇を照らす光明。
チェコ‐ご【チェコ語】
(Czech)チェコ共和国の公用語。インド‐ヨーロッパ語族のスラヴ語派西スラヴ語群に属する。隣接するスロヴァキア語とは12世紀ごろから分かれた。
⇒チェコ【Czech】
チェコ‐じけん【チェコ事件】
1968年8月20日、ソ連軍を中心とする東欧5カ国軍がチェコ‐スロヴァキアに侵攻し、同国での民主化運動を鎮圧した事件。→プラハの春。
⇒チェコ【Czech】
チェコ‐スロヴァキア【Czech and Slovakia】
中部ヨーロッパに位置し、1918〜93年に存在した連邦共和国。スラヴ系のチェコ人・スロヴァキア人が1918年オーストリア‐ハンガリー帝国からチェコスロヴァキア共和国として独立。39年ナチス‐ドイツに占領されたが、第二次大戦末期に解放、48年社会主義国、68年の政変を経て、69年チェコとスロヴァキアとの連邦制。東欧民主化のなかで、89年共産党政権が崩壊。90年、国名から「社会主義」を削り、さらに「チェコ‐スロヴァキア」と変更。93年、チェコ共和国とスロヴァキア共和国とに分離、独立。
⇒チェコ【Czech】
ちえ‐さき‐ら【知恵先ら】‥ヱ‥
(ラは接尾語)知恵があって弁舌のさわやかなこと。
チェ‐ジェウ【崔済愚】
(Ch‘oe Je-u)朝鮮の東学の創始者。万人の平等を唱えるその思想は農民の間に広まったが、政府により処刑された。(1824〜1864)
チェ‐ジェソ【崔載瑞】
(Ch‘oe Jae-sŏ)朝鮮の文学評論家。号は石耕牛。創氏名、石田耕造。京城帝大大学院卒。著「文学と知性」「転換期の朝鮮文学」。(1908〜1964)
ちえ‐しゃ【知恵者】‥ヱ‥
知恵のすぐれた人。
チェシャー‐チーズ【Cheshire cheese】
イギリス、チェシャー州原産の硬質のナチュラル‐チーズ。赤・白・ブルーの3種類ある。チェスター‐チーズ。
チェジュ‐ド【済州島】
(Cheju-do)朝鮮半島の南西海上にある大火山島。面積1840平方キロメートル。古くは耽羅たんら国が成立していたが、高麗により併合。1948年、南朝鮮単独選挙に反対する武装蜂起(四‐三蜂起)の舞台となる。付近海域はアジ・サバの好漁場。観光地として有名。周辺の島嶼と共に済州道をなす。→朝鮮(図)
チェス【chess】
西洋将棋。白・黒16個ずつの駒すなわちキング(王)・クイーン(女王)各1、ビショップ(僧正)・ナイト(騎士)・ルーク(城)各2、ポーン(卒)8を、縦横8列の六四枡ますから成る市松いちまつ模様の盤上に並べ、相手の王を詰めた方が勝ち。将棋に似るが、取った駒は使えない。
チェスタートン【Gilbert Keith Chesterton】
イギリスの作家。カトリックの立場に立ち、知的で諷刺的な作風を示す。小説「木曜日の男」、推理小説「ブラウン神父の童心」、評論「ディケンズ論」など。(1874〜1936)
チェスターフィールド【chesterfield】
比翼仕立てでウェストを絞った男性用オーバー‐コート。1840年代、イギリスのチェスターフィールド伯が着用し始めたのでいう。→コート(図)
チェスト【chest】
①胸。
②大型でふたつきの収納箱。
⇒チェスト‐パス【chest pass】
ちぇすと
〔感〕
詩吟・演説などの高潮した際に、聴衆から発する声援の掛け声。主として明治期に使われた語。鹿児島地方で使い始めたという。
チェスト‐パス【chest pass】
バスケット‐ボールで、パスをする時、ボールを胸の辺りから押し出すように投げること。
⇒チェスト【chest】
チェ‐スンヒ【崔承喜】
(Ch‘oe Sŭng-hŭi)朝鮮の女性舞踊家。ソウル生れ。石井漠に師事。朝鮮・日本さらには中国・欧米で活躍。1946年北朝鮮に渡り、以後はその文化芸術を指導。(1911〜1969)
ち‐えだ【千枝】
多くの枝。ちえ。玉葉集賀「薄く濃く―に咲ける藤波の」
⇒ちえだ‐ぐさ【千枝草】
チェダー‐チーズ【Cheddar cheese】
硬質のナチュラル‐チーズの一種。イギリスのチェダー村原産。温和な酸味と甘い芳香がある。
ちえだ‐ぐさ【千枝草】
松の異称。
⇒ち‐えだ【千枝】
ちえ‐だて【知恵立て】‥ヱ‥
自分の知恵を見せびらかすこと。〈日葡辞書〉
ちぇちぇくり‐あ・う【ちぇちぇ繰り合ふ】‥アフ
〔自四〕
「ちちくりあう」に同じ。風来六部集「讃州志度の浦にて海士人あまびとと―・ひ」
チェチェン【Chechen】
(正式名称はチェチニャーChechnya)ロシア連邦の共和国の一つ。カフカス山脈北部のイスラム系山地民族の国。ソ連崩壊の過程でロシアからの独立を求め、これを鎮圧するために1994年出兵したロシア軍と戦争状態に入る。首都グロズヌイ。
チェッカー【checker; chequer】
①西洋碁。赤・黒12個ずつの丸い駒を、縦横8列の市松模様の盤上に相対して並べ、互いに相手の駒を斜め前へ飛び越えて取り合う。
②市松いちまつ模様。碁盤縞。チェック。
③検査する者。特に船荷の積込み・荷揚げの監督者。
⇒チェッカー‐フラッグ【checkered flag】
チェッカー‐フラッグ【checkered flag】
自動車競走などで、スタート・ゴール地点で合図のために振る白黒の市松模様の旗。チェッカー。
⇒チェッカー【checker; chequer】
ちえづき‐どき【知恵付き時】‥ヱ‥
急速に知能が発達する年齢。7〜8歳から12〜13歳ごろまで。世間胸算用5「―に身をもちかためたるこそ」
チェック【check】
①小切手。「トラベラーズ‐―」
②⇒チッキ。
③照合すること。確認すること。また、それが済んだしるし。「在庫を―する」
④阻止すること。抑制すること。「行き過ぎを―する」
⑤洋服などの市松いちまつ模様。格子縞こうしじま。「―のスカート」
⑥チェスで、王手。
⇒チェック‐アウト【check-out】
⇒チェック‐アンド‐バランス【checks and balances】
⇒チェック‐イン【check-in】
⇒チェック‐オフ【checkoff】
⇒チェック‐バルブ【check-valve】
⇒チェック‐プロテクター【check protector】
⇒チェック‐ポイント【checkpoint】
⇒チェック‐メート【checkmate】
⇒チェック‐ライター【checkwriter】
⇒チェック‐リスト【check list】
ちえ‐づ・く【知恵付く】‥ヱ‥
〔自五〕
幼児が成長するにつれて知恵が増してくる。幼児が日一日と知恵が付く。
チェック‐アウト【check-out】
ホテルを発つための手続をすること。↔チェック‐イン。
⇒チェック【check】
チェック‐アンド‐バランス【checks and balances】
権力を分散させることによって特定部門の行き過ぎを抑え、全体の均衡を図ること。また、その原理。抑制均衡。
⇒チェック【check】
チェック‐イン【check-in】
①ホテルで、宿泊するための手続をすること。↔チェック‐アウト。
②空港で、旅客機の搭乗手続をすること。
⇒チェック【check】
チェック‐オフ【checkoff】
使用者が労働組合に代わって組合員の賃金から組合費などを差し引いて支給すること。使用者による便宜供与の一つ。
⇒チェック【check】
チェック‐バルブ【check-valve】
〔機〕(→)「逆止め弁」に同じ。
⇒チェック【check】
チェック‐プロテクター【check protector】
手形(小切手を含む)の改変を防ぐため、手形金額を不滅インクで刷込みまたは打抜きにする器具。手形保全器。手形保護印字器。チェック‐ライター。
⇒チェック【check】
チェック‐ポイント【checkpoint】
①点検・調査の際に特に注意すべき箇所や点。
②検問所。
③マラソンやラリー3などで、コースの途中に設けた点検・記録のための地点。
⇒チェック【check】
チェック‐メート【checkmate】
チェスで、王手詰み。また、そのかけ声。
⇒チェック【check】
チェック‐ライター【checkwriter】
(→)チェック‐プロテクターに同じ。
⇒チェック【check】
チェック‐リスト【check list】
点検・調査事項を列挙した表。照合表。
⇒チェック【check】
チェッリーニ【Benvenuto Cellini】
イタリアの彫金師・彫刻家。波瀾の生涯を綴った「自伝」は有名。(1500〜1571)
ちえ‐なみ【千重波】‥ヘ‥
幾重にもかさなって寄せてくる波。万葉集6「朝なぎに―寄り」
⇒ちえなみ‐しき‐に【千重波頻に】
ちえなみ‐しき‐に【千重波頻に】‥ヘ‥
千重波の寄せるように頻繁なさま。万葉集3「ひと日には―思へども」
⇒ちえ‐なみ【千重波】
チェ‐ナムソン【崔南善】
(Ch‘oe Nam-sŏn)朝鮮の詩人・評論家・出版人。ソウル生れ。号は六堂。自由詩「海から少年へ」は朝鮮近代詩の嚆矢。三‐一独立宣言文を起草。(1890〜1957)
ちえ‐ねつ【知恵熱】‥ヱ‥
乳児が知恵づきはじめる頃、不意に出る熱。ちえぼとり。
ちえ‐の‐いた【知恵の板】‥ヱ‥
江戸中期以降流行した、種々の形の小さい板を集めてさまざまな形をつくる遊具。中国で考案され、19世紀以降ヨーロッパで流行したタングラムも同類。
ちえ‐の‐うみ【智慧の海】‥ヱ‥
智慧の深いことを海にたとえていう語。
ちえ‐の‐かがみ【智慧の鏡】‥ヱ‥
智慧の明らかなことを鏡にたとえていう語。毛吹草2「―も曇る」
ちえ‐の‐けん【智慧の剣】‥ヱ‥
智慧がよく煩悩ぼんのうを断ち、生死の絆きずなを断つことを鋭利な剣にたとえていう語。智慧の利剣。
ちえ‐の‐こま【知恵の駒】‥ヱ‥
正方形の浅い箱に、番号を記した正方形の駒15個を置き、駒1個だけの空地を利用して、駒を動かし、番号順に並べるゲーム。
ちえ‐の‐ひ【智慧の火】‥ヱ‥
智慧が煩悩ぼんのうを焼き尽くすことを火にたとえていう語。智火。慧火。
⇒チェコ‐ご【チェコ語】
⇒チェコ‐じけん【チェコ事件】
⇒チェコ‐スロヴァキア【Czech and Slovakia】
ちえ‐こう【智慧光】‥ヱクワウ
〔仏〕阿弥陀如来の十二光の一つ。衆生しゅじょうの無明の闇を照らす光明。
チェコ‐ご【チェコ語】
(Czech)チェコ共和国の公用語。インド‐ヨーロッパ語族のスラヴ語派西スラヴ語群に属する。隣接するスロヴァキア語とは12世紀ごろから分かれた。
⇒チェコ【Czech】
チェコ‐じけん【チェコ事件】
1968年8月20日、ソ連軍を中心とする東欧5カ国軍がチェコ‐スロヴァキアに侵攻し、同国での民主化運動を鎮圧した事件。→プラハの春。
⇒チェコ【Czech】
チェコ‐スロヴァキア【Czech and Slovakia】
中部ヨーロッパに位置し、1918〜93年に存在した連邦共和国。スラヴ系のチェコ人・スロヴァキア人が1918年オーストリア‐ハンガリー帝国からチェコスロヴァキア共和国として独立。39年ナチス‐ドイツに占領されたが、第二次大戦末期に解放、48年社会主義国、68年の政変を経て、69年チェコとスロヴァキアとの連邦制。東欧民主化のなかで、89年共産党政権が崩壊。90年、国名から「社会主義」を削り、さらに「チェコ‐スロヴァキア」と変更。93年、チェコ共和国とスロヴァキア共和国とに分離、独立。
⇒チェコ【Czech】
ちえ‐さき‐ら【知恵先ら】‥ヱ‥
(ラは接尾語)知恵があって弁舌のさわやかなこと。
チェ‐ジェウ【崔済愚】
(Ch‘oe Je-u)朝鮮の東学の創始者。万人の平等を唱えるその思想は農民の間に広まったが、政府により処刑された。(1824〜1864)
チェ‐ジェソ【崔載瑞】
(Ch‘oe Jae-sŏ)朝鮮の文学評論家。号は石耕牛。創氏名、石田耕造。京城帝大大学院卒。著「文学と知性」「転換期の朝鮮文学」。(1908〜1964)
ちえ‐しゃ【知恵者】‥ヱ‥
知恵のすぐれた人。
チェシャー‐チーズ【Cheshire cheese】
イギリス、チェシャー州原産の硬質のナチュラル‐チーズ。赤・白・ブルーの3種類ある。チェスター‐チーズ。
チェジュ‐ド【済州島】
(Cheju-do)朝鮮半島の南西海上にある大火山島。面積1840平方キロメートル。古くは耽羅たんら国が成立していたが、高麗により併合。1948年、南朝鮮単独選挙に反対する武装蜂起(四‐三蜂起)の舞台となる。付近海域はアジ・サバの好漁場。観光地として有名。周辺の島嶼と共に済州道をなす。→朝鮮(図)
チェス【chess】
西洋将棋。白・黒16個ずつの駒すなわちキング(王)・クイーン(女王)各1、ビショップ(僧正)・ナイト(騎士)・ルーク(城)各2、ポーン(卒)8を、縦横8列の六四枡ますから成る市松いちまつ模様の盤上に並べ、相手の王を詰めた方が勝ち。将棋に似るが、取った駒は使えない。
チェスタートン【Gilbert Keith Chesterton】
イギリスの作家。カトリックの立場に立ち、知的で諷刺的な作風を示す。小説「木曜日の男」、推理小説「ブラウン神父の童心」、評論「ディケンズ論」など。(1874〜1936)
チェスターフィールド【chesterfield】
比翼仕立てでウェストを絞った男性用オーバー‐コート。1840年代、イギリスのチェスターフィールド伯が着用し始めたのでいう。→コート(図)
チェスト【chest】
①胸。
②大型でふたつきの収納箱。
⇒チェスト‐パス【chest pass】
ちぇすと
〔感〕
詩吟・演説などの高潮した際に、聴衆から発する声援の掛け声。主として明治期に使われた語。鹿児島地方で使い始めたという。
チェスト‐パス【chest pass】
バスケット‐ボールで、パスをする時、ボールを胸の辺りから押し出すように投げること。
⇒チェスト【chest】
チェ‐スンヒ【崔承喜】
(Ch‘oe Sŭng-hŭi)朝鮮の女性舞踊家。ソウル生れ。石井漠に師事。朝鮮・日本さらには中国・欧米で活躍。1946年北朝鮮に渡り、以後はその文化芸術を指導。(1911〜1969)
ち‐えだ【千枝】
多くの枝。ちえ。玉葉集賀「薄く濃く―に咲ける藤波の」
⇒ちえだ‐ぐさ【千枝草】
チェダー‐チーズ【Cheddar cheese】
硬質のナチュラル‐チーズの一種。イギリスのチェダー村原産。温和な酸味と甘い芳香がある。
ちえだ‐ぐさ【千枝草】
松の異称。
⇒ち‐えだ【千枝】
ちえ‐だて【知恵立て】‥ヱ‥
自分の知恵を見せびらかすこと。〈日葡辞書〉
ちぇちぇくり‐あ・う【ちぇちぇ繰り合ふ】‥アフ
〔自四〕
「ちちくりあう」に同じ。風来六部集「讃州志度の浦にて海士人あまびとと―・ひ」
チェチェン【Chechen】
(正式名称はチェチニャーChechnya)ロシア連邦の共和国の一つ。カフカス山脈北部のイスラム系山地民族の国。ソ連崩壊の過程でロシアからの独立を求め、これを鎮圧するために1994年出兵したロシア軍と戦争状態に入る。首都グロズヌイ。
チェッカー【checker; chequer】
①西洋碁。赤・黒12個ずつの丸い駒を、縦横8列の市松模様の盤上に相対して並べ、互いに相手の駒を斜め前へ飛び越えて取り合う。
②市松いちまつ模様。碁盤縞。チェック。
③検査する者。特に船荷の積込み・荷揚げの監督者。
⇒チェッカー‐フラッグ【checkered flag】
チェッカー‐フラッグ【checkered flag】
自動車競走などで、スタート・ゴール地点で合図のために振る白黒の市松模様の旗。チェッカー。
⇒チェッカー【checker; chequer】
ちえづき‐どき【知恵付き時】‥ヱ‥
急速に知能が発達する年齢。7〜8歳から12〜13歳ごろまで。世間胸算用5「―に身をもちかためたるこそ」
チェック【check】
①小切手。「トラベラーズ‐―」
②⇒チッキ。
③照合すること。確認すること。また、それが済んだしるし。「在庫を―する」
④阻止すること。抑制すること。「行き過ぎを―する」
⑤洋服などの市松いちまつ模様。格子縞こうしじま。「―のスカート」
⑥チェスで、王手。
⇒チェック‐アウト【check-out】
⇒チェック‐アンド‐バランス【checks and balances】
⇒チェック‐イン【check-in】
⇒チェック‐オフ【checkoff】
⇒チェック‐バルブ【check-valve】
⇒チェック‐プロテクター【check protector】
⇒チェック‐ポイント【checkpoint】
⇒チェック‐メート【checkmate】
⇒チェック‐ライター【checkwriter】
⇒チェック‐リスト【check list】
ちえ‐づ・く【知恵付く】‥ヱ‥
〔自五〕
幼児が成長するにつれて知恵が増してくる。幼児が日一日と知恵が付く。
チェック‐アウト【check-out】
ホテルを発つための手続をすること。↔チェック‐イン。
⇒チェック【check】
チェック‐アンド‐バランス【checks and balances】
権力を分散させることによって特定部門の行き過ぎを抑え、全体の均衡を図ること。また、その原理。抑制均衡。
⇒チェック【check】
チェック‐イン【check-in】
①ホテルで、宿泊するための手続をすること。↔チェック‐アウト。
②空港で、旅客機の搭乗手続をすること。
⇒チェック【check】
チェック‐オフ【checkoff】
使用者が労働組合に代わって組合員の賃金から組合費などを差し引いて支給すること。使用者による便宜供与の一つ。
⇒チェック【check】
チェック‐バルブ【check-valve】
〔機〕(→)「逆止め弁」に同じ。
⇒チェック【check】
チェック‐プロテクター【check protector】
手形(小切手を含む)の改変を防ぐため、手形金額を不滅インクで刷込みまたは打抜きにする器具。手形保全器。手形保護印字器。チェック‐ライター。
⇒チェック【check】
チェック‐ポイント【checkpoint】
①点検・調査の際に特に注意すべき箇所や点。
②検問所。
③マラソンやラリー3などで、コースの途中に設けた点検・記録のための地点。
⇒チェック【check】
チェック‐メート【checkmate】
チェスで、王手詰み。また、そのかけ声。
⇒チェック【check】
チェック‐ライター【checkwriter】
(→)チェック‐プロテクターに同じ。
⇒チェック【check】
チェック‐リスト【check list】
点検・調査事項を列挙した表。照合表。
⇒チェック【check】
チェッリーニ【Benvenuto Cellini】
イタリアの彫金師・彫刻家。波瀾の生涯を綴った「自伝」は有名。(1500〜1571)
ちえ‐なみ【千重波】‥ヘ‥
幾重にもかさなって寄せてくる波。万葉集6「朝なぎに―寄り」
⇒ちえなみ‐しき‐に【千重波頻に】
ちえなみ‐しき‐に【千重波頻に】‥ヘ‥
千重波の寄せるように頻繁なさま。万葉集3「ひと日には―思へども」
⇒ちえ‐なみ【千重波】
チェ‐ナムソン【崔南善】
(Ch‘oe Nam-sŏn)朝鮮の詩人・評論家・出版人。ソウル生れ。号は六堂。自由詩「海から少年へ」は朝鮮近代詩の嚆矢。三‐一独立宣言文を起草。(1890〜1957)
ちえ‐ねつ【知恵熱】‥ヱ‥
乳児が知恵づきはじめる頃、不意に出る熱。ちえぼとり。
ちえ‐の‐いた【知恵の板】‥ヱ‥
江戸中期以降流行した、種々の形の小さい板を集めてさまざまな形をつくる遊具。中国で考案され、19世紀以降ヨーロッパで流行したタングラムも同類。
ちえ‐の‐うみ【智慧の海】‥ヱ‥
智慧の深いことを海にたとえていう語。
ちえ‐の‐かがみ【智慧の鏡】‥ヱ‥
智慧の明らかなことを鏡にたとえていう語。毛吹草2「―も曇る」
ちえ‐の‐けん【智慧の剣】‥ヱ‥
智慧がよく煩悩ぼんのうを断ち、生死の絆きずなを断つことを鋭利な剣にたとえていう語。智慧の利剣。
ちえ‐の‐こま【知恵の駒】‥ヱ‥
正方形の浅い箱に、番号を記した正方形の駒15個を置き、駒1個だけの空地を利用して、駒を動かし、番号順に並べるゲーム。
ちえ‐の‐ひ【智慧の火】‥ヱ‥
智慧が煩悩ぼんのうを焼き尽くすことを火にたとえていう語。智火。慧火。
 ⇒チェコ‐ご【チェコ語】
⇒チェコ‐じけん【チェコ事件】
⇒チェコ‐スロヴァキア【Czech and Slovakia】
ちえ‐こう【智慧光】‥ヱクワウ
〔仏〕阿弥陀如来の十二光の一つ。衆生しゅじょうの無明の闇を照らす光明。
チェコ‐ご【チェコ語】
(Czech)チェコ共和国の公用語。インド‐ヨーロッパ語族のスラヴ語派西スラヴ語群に属する。隣接するスロヴァキア語とは12世紀ごろから分かれた。
⇒チェコ【Czech】
チェコ‐じけん【チェコ事件】
1968年8月20日、ソ連軍を中心とする東欧5カ国軍がチェコ‐スロヴァキアに侵攻し、同国での民主化運動を鎮圧した事件。→プラハの春。
⇒チェコ【Czech】
チェコ‐スロヴァキア【Czech and Slovakia】
中部ヨーロッパに位置し、1918〜93年に存在した連邦共和国。スラヴ系のチェコ人・スロヴァキア人が1918年オーストリア‐ハンガリー帝国からチェコスロヴァキア共和国として独立。39年ナチス‐ドイツに占領されたが、第二次大戦末期に解放、48年社会主義国、68年の政変を経て、69年チェコとスロヴァキアとの連邦制。東欧民主化のなかで、89年共産党政権が崩壊。90年、国名から「社会主義」を削り、さらに「チェコ‐スロヴァキア」と変更。93年、チェコ共和国とスロヴァキア共和国とに分離、独立。
⇒チェコ【Czech】
ちえ‐さき‐ら【知恵先ら】‥ヱ‥
(ラは接尾語)知恵があって弁舌のさわやかなこと。
チェ‐ジェウ【崔済愚】
(Ch‘oe Je-u)朝鮮の東学の創始者。万人の平等を唱えるその思想は農民の間に広まったが、政府により処刑された。(1824〜1864)
チェ‐ジェソ【崔載瑞】
(Ch‘oe Jae-sŏ)朝鮮の文学評論家。号は石耕牛。創氏名、石田耕造。京城帝大大学院卒。著「文学と知性」「転換期の朝鮮文学」。(1908〜1964)
ちえ‐しゃ【知恵者】‥ヱ‥
知恵のすぐれた人。
チェシャー‐チーズ【Cheshire cheese】
イギリス、チェシャー州原産の硬質のナチュラル‐チーズ。赤・白・ブルーの3種類ある。チェスター‐チーズ。
チェジュ‐ド【済州島】
(Cheju-do)朝鮮半島の南西海上にある大火山島。面積1840平方キロメートル。古くは耽羅たんら国が成立していたが、高麗により併合。1948年、南朝鮮単独選挙に反対する武装蜂起(四‐三蜂起)の舞台となる。付近海域はアジ・サバの好漁場。観光地として有名。周辺の島嶼と共に済州道をなす。→朝鮮(図)
チェス【chess】
西洋将棋。白・黒16個ずつの駒すなわちキング(王)・クイーン(女王)各1、ビショップ(僧正)・ナイト(騎士)・ルーク(城)各2、ポーン(卒)8を、縦横8列の六四枡ますから成る市松いちまつ模様の盤上に並べ、相手の王を詰めた方が勝ち。将棋に似るが、取った駒は使えない。
チェスタートン【Gilbert Keith Chesterton】
イギリスの作家。カトリックの立場に立ち、知的で諷刺的な作風を示す。小説「木曜日の男」、推理小説「ブラウン神父の童心」、評論「ディケンズ論」など。(1874〜1936)
チェスターフィールド【chesterfield】
比翼仕立てでウェストを絞った男性用オーバー‐コート。1840年代、イギリスのチェスターフィールド伯が着用し始めたのでいう。→コート(図)
チェスト【chest】
①胸。
②大型でふたつきの収納箱。
⇒チェスト‐パス【chest pass】
ちぇすと
〔感〕
詩吟・演説などの高潮した際に、聴衆から発する声援の掛け声。主として明治期に使われた語。鹿児島地方で使い始めたという。
チェスト‐パス【chest pass】
バスケット‐ボールで、パスをする時、ボールを胸の辺りから押し出すように投げること。
⇒チェスト【chest】
チェ‐スンヒ【崔承喜】
(Ch‘oe Sŭng-hŭi)朝鮮の女性舞踊家。ソウル生れ。石井漠に師事。朝鮮・日本さらには中国・欧米で活躍。1946年北朝鮮に渡り、以後はその文化芸術を指導。(1911〜1969)
ち‐えだ【千枝】
多くの枝。ちえ。玉葉集賀「薄く濃く―に咲ける藤波の」
⇒ちえだ‐ぐさ【千枝草】
チェダー‐チーズ【Cheddar cheese】
硬質のナチュラル‐チーズの一種。イギリスのチェダー村原産。温和な酸味と甘い芳香がある。
ちえだ‐ぐさ【千枝草】
松の異称。
⇒ち‐えだ【千枝】
ちえ‐だて【知恵立て】‥ヱ‥
自分の知恵を見せびらかすこと。〈日葡辞書〉
ちぇちぇくり‐あ・う【ちぇちぇ繰り合ふ】‥アフ
〔自四〕
「ちちくりあう」に同じ。風来六部集「讃州志度の浦にて海士人あまびとと―・ひ」
チェチェン【Chechen】
(正式名称はチェチニャーChechnya)ロシア連邦の共和国の一つ。カフカス山脈北部のイスラム系山地民族の国。ソ連崩壊の過程でロシアからの独立を求め、これを鎮圧するために1994年出兵したロシア軍と戦争状態に入る。首都グロズヌイ。
チェッカー【checker; chequer】
①西洋碁。赤・黒12個ずつの丸い駒を、縦横8列の市松模様の盤上に相対して並べ、互いに相手の駒を斜め前へ飛び越えて取り合う。
②市松いちまつ模様。碁盤縞。チェック。
③検査する者。特に船荷の積込み・荷揚げの監督者。
⇒チェッカー‐フラッグ【checkered flag】
チェッカー‐フラッグ【checkered flag】
自動車競走などで、スタート・ゴール地点で合図のために振る白黒の市松模様の旗。チェッカー。
⇒チェッカー【checker; chequer】
ちえづき‐どき【知恵付き時】‥ヱ‥
急速に知能が発達する年齢。7〜8歳から12〜13歳ごろまで。世間胸算用5「―に身をもちかためたるこそ」
チェック【check】
①小切手。「トラベラーズ‐―」
②⇒チッキ。
③照合すること。確認すること。また、それが済んだしるし。「在庫を―する」
④阻止すること。抑制すること。「行き過ぎを―する」
⑤洋服などの市松いちまつ模様。格子縞こうしじま。「―のスカート」
⑥チェスで、王手。
⇒チェック‐アウト【check-out】
⇒チェック‐アンド‐バランス【checks and balances】
⇒チェック‐イン【check-in】
⇒チェック‐オフ【checkoff】
⇒チェック‐バルブ【check-valve】
⇒チェック‐プロテクター【check protector】
⇒チェック‐ポイント【checkpoint】
⇒チェック‐メート【checkmate】
⇒チェック‐ライター【checkwriter】
⇒チェック‐リスト【check list】
ちえ‐づ・く【知恵付く】‥ヱ‥
〔自五〕
幼児が成長するにつれて知恵が増してくる。幼児が日一日と知恵が付く。
チェック‐アウト【check-out】
ホテルを発つための手続をすること。↔チェック‐イン。
⇒チェック【check】
チェック‐アンド‐バランス【checks and balances】
権力を分散させることによって特定部門の行き過ぎを抑え、全体の均衡を図ること。また、その原理。抑制均衡。
⇒チェック【check】
チェック‐イン【check-in】
①ホテルで、宿泊するための手続をすること。↔チェック‐アウト。
②空港で、旅客機の搭乗手続をすること。
⇒チェック【check】
チェック‐オフ【checkoff】
使用者が労働組合に代わって組合員の賃金から組合費などを差し引いて支給すること。使用者による便宜供与の一つ。
⇒チェック【check】
チェック‐バルブ【check-valve】
〔機〕(→)「逆止め弁」に同じ。
⇒チェック【check】
チェック‐プロテクター【check protector】
手形(小切手を含む)の改変を防ぐため、手形金額を不滅インクで刷込みまたは打抜きにする器具。手形保全器。手形保護印字器。チェック‐ライター。
⇒チェック【check】
チェック‐ポイント【checkpoint】
①点検・調査の際に特に注意すべき箇所や点。
②検問所。
③マラソンやラリー3などで、コースの途中に設けた点検・記録のための地点。
⇒チェック【check】
チェック‐メート【checkmate】
チェスで、王手詰み。また、そのかけ声。
⇒チェック【check】
チェック‐ライター【checkwriter】
(→)チェック‐プロテクターに同じ。
⇒チェック【check】
チェック‐リスト【check list】
点検・調査事項を列挙した表。照合表。
⇒チェック【check】
チェッリーニ【Benvenuto Cellini】
イタリアの彫金師・彫刻家。波瀾の生涯を綴った「自伝」は有名。(1500〜1571)
ちえ‐なみ【千重波】‥ヘ‥
幾重にもかさなって寄せてくる波。万葉集6「朝なぎに―寄り」
⇒ちえなみ‐しき‐に【千重波頻に】
ちえなみ‐しき‐に【千重波頻に】‥ヘ‥
千重波の寄せるように頻繁なさま。万葉集3「ひと日には―思へども」
⇒ちえ‐なみ【千重波】
チェ‐ナムソン【崔南善】
(Ch‘oe Nam-sŏn)朝鮮の詩人・評論家・出版人。ソウル生れ。号は六堂。自由詩「海から少年へ」は朝鮮近代詩の嚆矢。三‐一独立宣言文を起草。(1890〜1957)
ちえ‐ねつ【知恵熱】‥ヱ‥
乳児が知恵づきはじめる頃、不意に出る熱。ちえぼとり。
ちえ‐の‐いた【知恵の板】‥ヱ‥
江戸中期以降流行した、種々の形の小さい板を集めてさまざまな形をつくる遊具。中国で考案され、19世紀以降ヨーロッパで流行したタングラムも同類。
ちえ‐の‐うみ【智慧の海】‥ヱ‥
智慧の深いことを海にたとえていう語。
ちえ‐の‐かがみ【智慧の鏡】‥ヱ‥
智慧の明らかなことを鏡にたとえていう語。毛吹草2「―も曇る」
ちえ‐の‐けん【智慧の剣】‥ヱ‥
智慧がよく煩悩ぼんのうを断ち、生死の絆きずなを断つことを鋭利な剣にたとえていう語。智慧の利剣。
ちえ‐の‐こま【知恵の駒】‥ヱ‥
正方形の浅い箱に、番号を記した正方形の駒15個を置き、駒1個だけの空地を利用して、駒を動かし、番号順に並べるゲーム。
ちえ‐の‐ひ【智慧の火】‥ヱ‥
智慧が煩悩ぼんのうを焼き尽くすことを火にたとえていう語。智火。慧火。
⇒チェコ‐ご【チェコ語】
⇒チェコ‐じけん【チェコ事件】
⇒チェコ‐スロヴァキア【Czech and Slovakia】
ちえ‐こう【智慧光】‥ヱクワウ
〔仏〕阿弥陀如来の十二光の一つ。衆生しゅじょうの無明の闇を照らす光明。
チェコ‐ご【チェコ語】
(Czech)チェコ共和国の公用語。インド‐ヨーロッパ語族のスラヴ語派西スラヴ語群に属する。隣接するスロヴァキア語とは12世紀ごろから分かれた。
⇒チェコ【Czech】
チェコ‐じけん【チェコ事件】
1968年8月20日、ソ連軍を中心とする東欧5カ国軍がチェコ‐スロヴァキアに侵攻し、同国での民主化運動を鎮圧した事件。→プラハの春。
⇒チェコ【Czech】
チェコ‐スロヴァキア【Czech and Slovakia】
中部ヨーロッパに位置し、1918〜93年に存在した連邦共和国。スラヴ系のチェコ人・スロヴァキア人が1918年オーストリア‐ハンガリー帝国からチェコスロヴァキア共和国として独立。39年ナチス‐ドイツに占領されたが、第二次大戦末期に解放、48年社会主義国、68年の政変を経て、69年チェコとスロヴァキアとの連邦制。東欧民主化のなかで、89年共産党政権が崩壊。90年、国名から「社会主義」を削り、さらに「チェコ‐スロヴァキア」と変更。93年、チェコ共和国とスロヴァキア共和国とに分離、独立。
⇒チェコ【Czech】
ちえ‐さき‐ら【知恵先ら】‥ヱ‥
(ラは接尾語)知恵があって弁舌のさわやかなこと。
チェ‐ジェウ【崔済愚】
(Ch‘oe Je-u)朝鮮の東学の創始者。万人の平等を唱えるその思想は農民の間に広まったが、政府により処刑された。(1824〜1864)
チェ‐ジェソ【崔載瑞】
(Ch‘oe Jae-sŏ)朝鮮の文学評論家。号は石耕牛。創氏名、石田耕造。京城帝大大学院卒。著「文学と知性」「転換期の朝鮮文学」。(1908〜1964)
ちえ‐しゃ【知恵者】‥ヱ‥
知恵のすぐれた人。
チェシャー‐チーズ【Cheshire cheese】
イギリス、チェシャー州原産の硬質のナチュラル‐チーズ。赤・白・ブルーの3種類ある。チェスター‐チーズ。
チェジュ‐ド【済州島】
(Cheju-do)朝鮮半島の南西海上にある大火山島。面積1840平方キロメートル。古くは耽羅たんら国が成立していたが、高麗により併合。1948年、南朝鮮単独選挙に反対する武装蜂起(四‐三蜂起)の舞台となる。付近海域はアジ・サバの好漁場。観光地として有名。周辺の島嶼と共に済州道をなす。→朝鮮(図)
チェス【chess】
西洋将棋。白・黒16個ずつの駒すなわちキング(王)・クイーン(女王)各1、ビショップ(僧正)・ナイト(騎士)・ルーク(城)各2、ポーン(卒)8を、縦横8列の六四枡ますから成る市松いちまつ模様の盤上に並べ、相手の王を詰めた方が勝ち。将棋に似るが、取った駒は使えない。
チェスタートン【Gilbert Keith Chesterton】
イギリスの作家。カトリックの立場に立ち、知的で諷刺的な作風を示す。小説「木曜日の男」、推理小説「ブラウン神父の童心」、評論「ディケンズ論」など。(1874〜1936)
チェスターフィールド【chesterfield】
比翼仕立てでウェストを絞った男性用オーバー‐コート。1840年代、イギリスのチェスターフィールド伯が着用し始めたのでいう。→コート(図)
チェスト【chest】
①胸。
②大型でふたつきの収納箱。
⇒チェスト‐パス【chest pass】
ちぇすと
〔感〕
詩吟・演説などの高潮した際に、聴衆から発する声援の掛け声。主として明治期に使われた語。鹿児島地方で使い始めたという。
チェスト‐パス【chest pass】
バスケット‐ボールで、パスをする時、ボールを胸の辺りから押し出すように投げること。
⇒チェスト【chest】
チェ‐スンヒ【崔承喜】
(Ch‘oe Sŭng-hŭi)朝鮮の女性舞踊家。ソウル生れ。石井漠に師事。朝鮮・日本さらには中国・欧米で活躍。1946年北朝鮮に渡り、以後はその文化芸術を指導。(1911〜1969)
ち‐えだ【千枝】
多くの枝。ちえ。玉葉集賀「薄く濃く―に咲ける藤波の」
⇒ちえだ‐ぐさ【千枝草】
チェダー‐チーズ【Cheddar cheese】
硬質のナチュラル‐チーズの一種。イギリスのチェダー村原産。温和な酸味と甘い芳香がある。
ちえだ‐ぐさ【千枝草】
松の異称。
⇒ち‐えだ【千枝】
ちえ‐だて【知恵立て】‥ヱ‥
自分の知恵を見せびらかすこと。〈日葡辞書〉
ちぇちぇくり‐あ・う【ちぇちぇ繰り合ふ】‥アフ
〔自四〕
「ちちくりあう」に同じ。風来六部集「讃州志度の浦にて海士人あまびとと―・ひ」
チェチェン【Chechen】
(正式名称はチェチニャーChechnya)ロシア連邦の共和国の一つ。カフカス山脈北部のイスラム系山地民族の国。ソ連崩壊の過程でロシアからの独立を求め、これを鎮圧するために1994年出兵したロシア軍と戦争状態に入る。首都グロズヌイ。
チェッカー【checker; chequer】
①西洋碁。赤・黒12個ずつの丸い駒を、縦横8列の市松模様の盤上に相対して並べ、互いに相手の駒を斜め前へ飛び越えて取り合う。
②市松いちまつ模様。碁盤縞。チェック。
③検査する者。特に船荷の積込み・荷揚げの監督者。
⇒チェッカー‐フラッグ【checkered flag】
チェッカー‐フラッグ【checkered flag】
自動車競走などで、スタート・ゴール地点で合図のために振る白黒の市松模様の旗。チェッカー。
⇒チェッカー【checker; chequer】
ちえづき‐どき【知恵付き時】‥ヱ‥
急速に知能が発達する年齢。7〜8歳から12〜13歳ごろまで。世間胸算用5「―に身をもちかためたるこそ」
チェック【check】
①小切手。「トラベラーズ‐―」
②⇒チッキ。
③照合すること。確認すること。また、それが済んだしるし。「在庫を―する」
④阻止すること。抑制すること。「行き過ぎを―する」
⑤洋服などの市松いちまつ模様。格子縞こうしじま。「―のスカート」
⑥チェスで、王手。
⇒チェック‐アウト【check-out】
⇒チェック‐アンド‐バランス【checks and balances】
⇒チェック‐イン【check-in】
⇒チェック‐オフ【checkoff】
⇒チェック‐バルブ【check-valve】
⇒チェック‐プロテクター【check protector】
⇒チェック‐ポイント【checkpoint】
⇒チェック‐メート【checkmate】
⇒チェック‐ライター【checkwriter】
⇒チェック‐リスト【check list】
ちえ‐づ・く【知恵付く】‥ヱ‥
〔自五〕
幼児が成長するにつれて知恵が増してくる。幼児が日一日と知恵が付く。
チェック‐アウト【check-out】
ホテルを発つための手続をすること。↔チェック‐イン。
⇒チェック【check】
チェック‐アンド‐バランス【checks and balances】
権力を分散させることによって特定部門の行き過ぎを抑え、全体の均衡を図ること。また、その原理。抑制均衡。
⇒チェック【check】
チェック‐イン【check-in】
①ホテルで、宿泊するための手続をすること。↔チェック‐アウト。
②空港で、旅客機の搭乗手続をすること。
⇒チェック【check】
チェック‐オフ【checkoff】
使用者が労働組合に代わって組合員の賃金から組合費などを差し引いて支給すること。使用者による便宜供与の一つ。
⇒チェック【check】
チェック‐バルブ【check-valve】
〔機〕(→)「逆止め弁」に同じ。
⇒チェック【check】
チェック‐プロテクター【check protector】
手形(小切手を含む)の改変を防ぐため、手形金額を不滅インクで刷込みまたは打抜きにする器具。手形保全器。手形保護印字器。チェック‐ライター。
⇒チェック【check】
チェック‐ポイント【checkpoint】
①点検・調査の際に特に注意すべき箇所や点。
②検問所。
③マラソンやラリー3などで、コースの途中に設けた点検・記録のための地点。
⇒チェック【check】
チェック‐メート【checkmate】
チェスで、王手詰み。また、そのかけ声。
⇒チェック【check】
チェック‐ライター【checkwriter】
(→)チェック‐プロテクターに同じ。
⇒チェック【check】
チェック‐リスト【check list】
点検・調査事項を列挙した表。照合表。
⇒チェック【check】
チェッリーニ【Benvenuto Cellini】
イタリアの彫金師・彫刻家。波瀾の生涯を綴った「自伝」は有名。(1500〜1571)
ちえ‐なみ【千重波】‥ヘ‥
幾重にもかさなって寄せてくる波。万葉集6「朝なぎに―寄り」
⇒ちえなみ‐しき‐に【千重波頻に】
ちえなみ‐しき‐に【千重波頻に】‥ヘ‥
千重波の寄せるように頻繁なさま。万葉集3「ひと日には―思へども」
⇒ちえ‐なみ【千重波】
チェ‐ナムソン【崔南善】
(Ch‘oe Nam-sŏn)朝鮮の詩人・評論家・出版人。ソウル生れ。号は六堂。自由詩「海から少年へ」は朝鮮近代詩の嚆矢。三‐一独立宣言文を起草。(1890〜1957)
ちえ‐ねつ【知恵熱】‥ヱ‥
乳児が知恵づきはじめる頃、不意に出る熱。ちえぼとり。
ちえ‐の‐いた【知恵の板】‥ヱ‥
江戸中期以降流行した、種々の形の小さい板を集めてさまざまな形をつくる遊具。中国で考案され、19世紀以降ヨーロッパで流行したタングラムも同類。
ちえ‐の‐うみ【智慧の海】‥ヱ‥
智慧の深いことを海にたとえていう語。
ちえ‐の‐かがみ【智慧の鏡】‥ヱ‥
智慧の明らかなことを鏡にたとえていう語。毛吹草2「―も曇る」
ちえ‐の‐けん【智慧の剣】‥ヱ‥
智慧がよく煩悩ぼんのうを断ち、生死の絆きずなを断つことを鋭利な剣にたとえていう語。智慧の利剣。
ちえ‐の‐こま【知恵の駒】‥ヱ‥
正方形の浅い箱に、番号を記した正方形の駒15個を置き、駒1個だけの空地を利用して、駒を動かし、番号順に並べるゲーム。
ちえ‐の‐ひ【智慧の火】‥ヱ‥
智慧が煩悩ぼんのうを焼き尽くすことを火にたとえていう語。智火。慧火。
ちえ‐がゆ【知恵粥】‥ヱ‥🔗⭐🔉
ちえ‐がゆ【知恵粥】‥ヱ‥
(→)大師粥だいしがゆに同じ。
ちえ‐くらべ【知恵競べ】‥ヱ‥🔗⭐🔉
ちえ‐くらべ【知恵競べ】‥ヱ‥
知恵の優劣をきそうこと。
ちえ‐しゃ【知恵者】‥ヱ‥🔗⭐🔉
ちえ‐しゃ【知恵者】‥ヱ‥
知恵のすぐれた人。
ちえ‐の‐いた【知恵の板】‥ヱ‥🔗⭐🔉
ちえ‐の‐いた【知恵の板】‥ヱ‥
江戸中期以降流行した、種々の形の小さい板を集めてさまざまな形をつくる遊具。中国で考案され、19世紀以降ヨーロッパで流行したタングラムも同類。
ちえ‐の‐こま【知恵の駒】‥ヱ‥🔗⭐🔉
ちえ‐の‐こま【知恵の駒】‥ヱ‥
正方形の浅い箱に、番号を記した正方形の駒15個を置き、駒1個だけの空地を利用して、駒を動かし、番号順に並べるゲーム。
○知恵の持ち腐れちえのもちぐされ🔗⭐🔉
○知恵の持ち腐れちえのもちぐされ
知恵を持ちながら実際に活用し得ないこと。
⇒ち‐え【知恵・智慧】
ちえ‐の‐や【智慧の矢】‥ヱ‥
智慧の働きがはやいことを矢にたとえていう語。
ちえ‐の‐りけん【智慧の利剣】‥ヱ‥
(→)「智慧の剣」に同じ。
ちえ‐の‐わ【知恵の輪】‥ヱ‥
①種々の形の輪を工夫してつなぎ合わせたり抜き放したりして遊ぶ玩具。九連環。
②九つの輪ちがいの文様。浄瑠璃、女殺油地獄「濃柿に―の大紋」
③文殊もんじゅを祀った寺院にある円形の石輪。また、祭日に草などで作ったものをもいう。くぐれば知恵を得るという。
ちえ‐ば【知恵歯】‥ヱ‥
(→)知歯ちしに同じ。
ちえ‐の‐わ【知恵の輪】‥ヱ‥🔗⭐🔉
ちえ‐の‐わ【知恵の輪】‥ヱ‥
①種々の形の輪を工夫してつなぎ合わせたり抜き放したりして遊ぶ玩具。九連環。
②九つの輪ちがいの文様。浄瑠璃、女殺油地獄「濃柿に―の大紋」
③文殊もんじゅを祀った寺院にある円形の石輪。また、祭日に草などで作ったものをもいう。くぐれば知恵を得るという。
ちえ‐ば【知恵歯】‥ヱ‥🔗⭐🔉
ちえ‐ば【知恵歯】‥ヱ‥
(→)知歯ちしに同じ。
○知恵は小出しにせよちえはこだしにせよ
あるだけの知恵を一時に出せばあとで困るから、時に応じて少しずつ出す方がよい。
⇒ち‐え【知恵・智慧】
○知恵は小出しにせよちえはこだしにせよ🔗⭐🔉
○知恵は小出しにせよちえはこだしにせよ
あるだけの知恵を一時に出せばあとで困るから、時に応じて少しずつ出す方がよい。
⇒ち‐え【知恵・智慧】
チェビシェフ【Pafnutii L'vovich Chebyshev】
ロシアの数学者。関数の最良近似、直交多項式の理論、補間論、曲面論、連分数の研究、計算機の製作、数論などに業績がある。(1821〜1894)
ちえ‐ぶくろ【知恵袋】‥ヱ‥
頭脳。知恵のありったけ。また、仲間のうちの知恵者。「―をしぼる」「宰相の―」
ちえ‐ぼとり【知恵熱】‥ヱ‥
(→)「ちえねつ」に同じ。
ちえ‐まけ【知恵負け】‥ヱ‥
知恵が多いため、考え過ぎてかえって失敗すること。
ちえ‐もうで【知恵詣】‥ヱマウデ
(→)「十三参り」に同じ。
ちえ‐もんじゅ【智慧文殊】‥ヱ‥
(諸尊の中で智慧が最も秀れているというので)文殊菩薩の俗称。
チェリー【cherry】
桜。桜の実。さくらんぼう。
チェリオ【cheerio】
(くだけた言い方)
①さよなら。ご機嫌よう。
②乾杯するときの掛け声。
チェリスト【cellist】
チェロ奏者。
チェリビダッケ【Sergiu Celibidache】
ルーマニア出身の指揮者。ベルリン‐フィル・ミュンヘン‐フィルなどを指揮。(1912〜1996)
チェリャビンスク【Chelyabinsk】
ロシア西部、ウラル地方の都市。鉄鋼業・機械工業など重工業地帯の中心。シベリア鉄道の起点。人口109万5千(2004)。
チェルニー【Carl Czerny】
オーストリアのピアノ奏者・教師・作曲家。ベートーヴェンに師事し、その教則本は、今日も広く用いられる。その門からリストが出た。(1791〜1857)
チェルヌイシェフスキー【Nikolai G. Chernyshevskii】
ロシアの批評家・経済学者。急進的思想家として知識人に大きな影響力をもった。1862年逮捕され、獄中で小説「何をなすべきか」を執筆、のちシベリアへ流刑。(1828〜1889)
チェルネンコ【Konstantin U. Chernenko】
ソ連の政治家。1984年アンドロポフのあとを受けて党書記長。翌年病死。(1911〜1985)
チェルノーゼム【chernozem】
レス(黄土)を母材とし半乾燥気候下の草原に発達する土壌。腐植と石灰とによって水もちのよい団粒構造ができており、肥沃で、小麦などの主要生産地となっている。ウクライナから西シベリア低地南部にかけて帯状に広く分布するほか北アメリカ・中央アジアにも見られる。チェルノジョーム。黒土。黒色土。
チェルノブイリ【Chernobyl'】
ウクライナの首都キエフ北方の地名。1986年4月、同地の原子力発電所4号炉で、炉心の爆発・溶融破壊、建屋破壊事故が起き、多数の死傷者が出、欧州諸国など広い範囲に放射能汚染をもたらした。
チェルノブイリ原子力発電所(1991年)
撮影:桐生広人
 チェレスタ【celesta イタリア】
(「天国的な」の意)ピアノに似た有鍵打楽器。弦の代りに鋼鉄製音板をハンマーで打って鳴らすもの。音色は明るく鋭い。19世紀末にフランスのオルガン製作者ミュステル(A. Mustel1842〜1919)が考案し、管弦楽の装飾効果に使用。
チェレンコフ‐こうか【チェレンコフ効果】‥カウクワ
荷電粒子が物質中を運動するとき、その速度が物質中の光速(真空中の光の速さを、その物質の屈折率で割った値)よりも大きい場合には、一様な運動であっても光を放射する現象。1937年ソ連の物理学者チェレンコフ(P. A. Cherenkov1904〜1990)が発見。
チェロ【cello】
(violoncello イタリアの略)バイオリン属の弦楽器。大型で、バイオリンの約2倍の長さがあり、椅子にかけ両膝の間に胴体を抱いて演奏する。4弦で、美しく柔らかい音色を発し、独奏・室内楽・管弦楽などに重用。セロ。
チェロキー【Cherokee】
北アメリカ先住民の一部族。
チェレスタ【celesta イタリア】
(「天国的な」の意)ピアノに似た有鍵打楽器。弦の代りに鋼鉄製音板をハンマーで打って鳴らすもの。音色は明るく鋭い。19世紀末にフランスのオルガン製作者ミュステル(A. Mustel1842〜1919)が考案し、管弦楽の装飾効果に使用。
チェレンコフ‐こうか【チェレンコフ効果】‥カウクワ
荷電粒子が物質中を運動するとき、その速度が物質中の光速(真空中の光の速さを、その物質の屈折率で割った値)よりも大きい場合には、一様な運動であっても光を放射する現象。1937年ソ連の物理学者チェレンコフ(P. A. Cherenkov1904〜1990)が発見。
チェロ【cello】
(violoncello イタリアの略)バイオリン属の弦楽器。大型で、バイオリンの約2倍の長さがあり、椅子にかけ両膝の間に胴体を抱いて演奏する。4弦で、美しく柔らかい音色を発し、独奏・室内楽・管弦楽などに重用。セロ。
チェロキー【Cherokee】
北アメリカ先住民の一部族。
 チェレスタ【celesta イタリア】
(「天国的な」の意)ピアノに似た有鍵打楽器。弦の代りに鋼鉄製音板をハンマーで打って鳴らすもの。音色は明るく鋭い。19世紀末にフランスのオルガン製作者ミュステル(A. Mustel1842〜1919)が考案し、管弦楽の装飾効果に使用。
チェレンコフ‐こうか【チェレンコフ効果】‥カウクワ
荷電粒子が物質中を運動するとき、その速度が物質中の光速(真空中の光の速さを、その物質の屈折率で割った値)よりも大きい場合には、一様な運動であっても光を放射する現象。1937年ソ連の物理学者チェレンコフ(P. A. Cherenkov1904〜1990)が発見。
チェロ【cello】
(violoncello イタリアの略)バイオリン属の弦楽器。大型で、バイオリンの約2倍の長さがあり、椅子にかけ両膝の間に胴体を抱いて演奏する。4弦で、美しく柔らかい音色を発し、独奏・室内楽・管弦楽などに重用。セロ。
チェロキー【Cherokee】
北アメリカ先住民の一部族。
チェレスタ【celesta イタリア】
(「天国的な」の意)ピアノに似た有鍵打楽器。弦の代りに鋼鉄製音板をハンマーで打って鳴らすもの。音色は明るく鋭い。19世紀末にフランスのオルガン製作者ミュステル(A. Mustel1842〜1919)が考案し、管弦楽の装飾効果に使用。
チェレンコフ‐こうか【チェレンコフ効果】‥カウクワ
荷電粒子が物質中を運動するとき、その速度が物質中の光速(真空中の光の速さを、その物質の屈折率で割った値)よりも大きい場合には、一様な運動であっても光を放射する現象。1937年ソ連の物理学者チェレンコフ(P. A. Cherenkov1904〜1990)が発見。
チェロ【cello】
(violoncello イタリアの略)バイオリン属の弦楽器。大型で、バイオリンの約2倍の長さがあり、椅子にかけ両膝の間に胴体を抱いて演奏する。4弦で、美しく柔らかい音色を発し、独奏・室内楽・管弦楽などに重用。セロ。
チェロキー【Cherokee】
北アメリカ先住民の一部族。
ちえ‐もうで【知恵詣】‥ヱマウデ🔗⭐🔉
ちえ‐もうで【知恵詣】‥ヱマウデ
(→)「十三参り」に同じ。
○知恵を借りるちえをかりる🔗⭐🔉
○知恵を借りるちえをかりる
人に相談していい考えや方法を教えてもらう。「多くの人の―」
⇒ち‐え【知恵・智慧】
○知恵を絞るちえをしぼる🔗⭐🔉
○知恵を絞るちえをしぼる
(名案などを求めて)ありったけの知恵を出す。「無い―」
⇒ち‐え【知恵・智慧】
○知恵を付けるちえをつける🔗⭐🔉
○知恵を付けるちえをつける
傍から知恵や策略を授ける。入れ知恵をする。「余計な―」
⇒ち‐え【知恵・智慧】
ち‐えん【地縁】
住む土地に基づく縁故関係。↔血縁けつえん。
⇒ちえん‐しゅうだん【地縁集団】
ち‐えん【遅延】
物事が予定の期日・時刻より遅れて、のびること。長びくこと。「工事が―する」「―証明」
⇒ちえん‐ばいしょう【遅延賠償】
⇒ちえん‐りそく【遅延利息】
チェンジ【change】
①変えること。変化。変更。「イメージ‐―」
②交替。特に、野球の攻守交替。また、チェンジ‐コートの略。
③両替。また、釣銭。
⇒チェンジ‐アップ【change-up】
⇒チェンジ‐オーバー【change-over】
⇒チェンジ‐オブ‐ペース【change of pace】
⇒チェンジ‐コート
⇒チェンジ‐レバー
チェンジ‐アップ【change-up】
野球で、投手の投球の一種。速球と同じフォームで投げる緩い球。打者のタイミングをはずす。
⇒チェンジ【change】
チェンジ‐オーバー【change-over】
為替の売買契約が満期となった場合、実際の受渡しをせず、さらに先物の売買契約に変更すること。乗替。繰越。
⇒チェンジ【change】
チェンジ‐オブ‐ペース【change of pace】
(「調子を変える」の意)野球で、投手がボールの速度・コースなどを多様に変化させて投球すること。
⇒チェンジ【change】
チェンジ‐コート
(和製語change court)テニス・卓球・バレーボールなどで、各セット終了時などにコートを交替すること。
⇒チェンジ【change】
チェンジャン‐どうぶつ‐ぐん【澄江動物群】
(Chengjiang fauna)「バージェス動物群」参照。
ちえん‐しゅうだん【地縁集団】‥シフ‥
一定地域での居住に基づく社会集団。地縁社会。↔血縁集団
⇒ち‐えん【地縁】
チェンジ‐レバー
(和製語change lever)歯車などを切り換えるてこ。変速桿かん。
⇒チェンジ【change】
チェンナイ【Chennai】
インド南部、タミル‐ナドゥ州の州都。ベンガル湾に面する港湾都市。17世紀以来イギリス植民地支配の一中心。貿易港としても重要。人口421万6千(2001)。旧称マドラス。
チェンバー【chamber】
室。会議室。
⇒チェンバー‐オルガン【chamber organ】
⇒チェンバー‐ミュージック【chamber music】
チェンバー‐オルガン【chamber organ】
(→)「ポジティブ‐オルガン」に同じ。
⇒チェンバー【chamber】
チェンバー‐ミュージック【chamber music】
(→)室内楽。
⇒チェンバー【chamber】
ちえん‐ばいしょう【遅延賠償】‥シヤウ
〔法〕履行遅滞による損害の賠償。
⇒ち‐えん【遅延】
チェンバリン【Edward Hastings Chamberlin】
アメリカの経済学者。ハーヴァード大教授。主著「独占的競争の理論」によって、新古典派の完全競争に代わる理論を提示し、後の寡占論や産業組織論の基礎を築いた。(1899〜1967)
チェンバレン【Arthur Neville Chamberlain】
イギリスの政治家。J.チェンバレンの次男。保健相・蔵相を経て、1937〜40年首相。ミュンヘン会談での譲歩など対独宥和政策を採ったが、39年ドイツに対して宣戦。(1869〜1940)
チェンバレン【Austen Chamberlain】
イギリスの政治家。J.チェンバレンの長男。外相として1925年ロカルノ条約を締結。国際連盟の強力な支持者。ノーベル賞。(1863〜1937)
チェンバレン【Basil Hall Chamberlain】
イギリスの言語学者。王堂と号す。1873年(明治6)来日、86〜90年東大で講じ、近代国語学の樹立に貢献、また東洋比較言語学を開拓。著「アイノ研究より見たる日本の言語神話及地名」「日本国語提要」「琉球語文典及び字彙」など。(1850〜1935)
チェンバレン【Joseph Chamberlain】
イギリスの政治家。自由党急進派を領導、1886年グラッドストンに反対して自由統一党を組織、95年植民地相、南ア戦争に深く関与。(1836〜1914)
チェンバロ【cembalo イタリア】
(→)ハープシコードに同じ。
チェンマイ【Chiang Mai】
タイ北部の都市。13世紀ラーンナータイ王国の首都として建設。古い寺院が多く、観光地として知られる。農産物・チーク材の集散地で、手工業も活発。人口39万(2002)。
チエンマイ ドイ‐ステープ寺
撮影:小松義夫
 チエンマイ ドイ‐ステープ寺入口
撮影:小松義夫
チエンマイ ドイ‐ステープ寺入口
撮影:小松義夫
 ちえん‐りそく【遅延利息】
債務者が遅延賠償として債権者に支払うべき金銭。旧民法上の用語に由来するもので、本来の意味での利息ではない。
⇒ち‐えん【遅延】
チオ【thio】
硫黄を表す接頭語。チオ硫酸・チオシアン酸などのように化合物名に付ける。
ちお‐あき【千百秋】チホ‥
千百年。また、かぎりなく続く年月。ちいほあき。日本紀竟宴歌「―の国をさめたるあとをのみよろづよ今もわすれやはする」
チオール【thiol】
メルカプト基‐SHをもつ化合物の総称。一般式R‐SH(Rはアルキル基など炭化水素基)。一般に揮発しやすい不快臭のある液体。代表例はエタンチオールで、都市ガスの臭気付与剤などに用いる。
チオクト‐さん【チオクト酸】
(thioctic acid)(→)リポ酸に同じ。
チオシアン‐さん【チオシアン酸】
(thiocyanic acid)刺激臭のある不安定な気体。分子式HSCN カリウム塩(チオシアン酸カリウム)は無色の結晶。その水溶液は鉄(Ⅲ)イオンを含む水溶液と反応して血赤色を呈し、鉄(Ⅲ)イオンの検出・定量に用いる。ロダン酸。
ち‐おち【血落ち】
(→)「血下ろし」に同じ。
ち‐おととい【乳兄弟】
⇒ちきょうだい。〈日葡辞書〉
チオフェン【thiophene】
分子式C4H4S 硫黄原子1個を含む五員環の複素環式化合物。芳香族性を持つ。無色の液体。コールタールから得たベンゼン中に少量含まれる。工業的にはブタンと硫黄を加熱してつくる。イサチンと濃硫酸を加えると青色を呈する反応(インドフェニン反応)により検出される。樹脂・染料・医薬の合成原料。
ち‐おも【乳母】
うば。めのと。神代紀下「彦火火出見尊ひこほほでみのみこと、婦人を取りて―・湯母…としたまふ」
ち‐おや【乳親】
①乳を飲ませて育てる女。うば。
②乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。
チオ‐りゅうさん‐ナトリウム【チオ硫酸ナトリウム】‥リウ‥
(sodium thiosulfate)化学式Na2S2O3 普通には五水和物で、無色の結晶。水に溶けやすい。水溶液はハロゲン化銀を溶かすので写真の定着液に用いる。漂白後の除塩素剤にも利用。次亜硫酸ナトリウムは誤称。ハイポ。
ち‐おろし【血下ろし】
子をおろすこと。堕胎だたい。ちおち。好色二代男「夜は男狂ひ、誰とも定めがたき―」
ち‐おん【地温】‥ヲン
地面または地中の温度。
⇒ちおん‐こうばい【地温勾配】
ちおん‐いん【知恩院】‥ヰン
京都市東山区にある浄土宗総本山。大谷寺知恩教院。法然が念仏をひろめ、また没した吉水御房・大谷禅房の跡に1234年(文暦1)弟子源智が再興した堂宇に始まる。16世紀に浄土宗総本山としての地位を確立し、徳川家康の菩提所ともなった。「法然上人絵伝」48巻などを所蔵。
ちおん‐こうばい【地温勾配】‥ヲン‥
地球内部で深さとともに温度の上昇する割合。通常は30メートルについて1度高くなるが、場所・深さにより変わる。この勾配のため熱が内部より地表へ伝わる。地下増温率。地温上昇率。
⇒ち‐おん【地温】
ちおん‐じ【知恩寺】
京都市左京区百万遍にある浄土宗の本山。法然の住した賀茂の河原屋に始まり、たびたび移転。1331年(元徳3)疫病流行に際し、8世善阿(空円)が百万遍念仏を修し効あったことから、寺号の百万遍を下賜。1662年(寛文2)から現在地。
ち‐か【地下】
①大地の下。「―街」「―に眠る」
②社会運動・政治運動などにおける非合法面。「―活動」「―出版物」
③⇒じげ(地下)
⇒地下に潜る
ち‐か【地価】
①土地の売買価格。「―の高騰」
②課税標準となる土地の価格で、公簿に登録されたもの。
ち‐か【知化】‥クワ
知力がよくはたらくこと。太平記1「深慮―の老臣」
ち‐か【治下】
ある政権の支配下にあること。統治下。
ちかい【誓い】チカヒ
①神仏に、ある事をそむくまいと約束すること。願がん。がんかけ。源氏物語夕霧「深き―にて今は命を限りける山ごもりを」。「―を立てる」
②衆生しゅじょうを救おうとする神仏の誓願。源氏物語若菜下「不動尊の御もとの―あり。その日数をだにかけ留め奉り給へ」
③ある事を将来必ず履行しようと他人や自分自身に固く約束すること。また、その言葉。「―を交わす」
⇒ちかい‐ごと【誓い言】
⇒ちかい‐だて【誓い立て】
⇒ちかい‐の‐あみ【誓の網】
⇒ちかい‐の‐うみ【誓の海】
⇒ちかい‐の‐ふね【誓の船】
⇒ちかい‐ぶみ【誓文】
ち‐かい【地界】
①土地の境界。また、土地。
②地上の世界。↔天界
ち‐かい【地階】
建物で、地盤面以下の階。
ち‐かい【地塊】‥クワイ
四方が断層面によって限られた陸地の塊。
⇒ちかい‐うんどう【地塊運動】
ち‐かい【知解】
知識の力でさとること。
ちか・い【近い】
〔形〕[文]ちか・し(ク)
①距離のへだたりが小さい。遠くない。古事記下「其の老媼の住める屋は―・く宮の辺に作りて日毎に必ず召しき」。日葡辞書「ホドチカイ」。「駅から―・い」
②時間のへだたりが小さい。万葉集19「わが思へる君に別れむ日―・くなりぬ」。源氏物語夕顔「明方も―・うなりにけり」。日葡辞書「チカイコロ・チカイホド」。「―・いうちに」「終りに―・い」
③よく見知っている。源氏物語早蕨「世のはかなさを目に―・く見しに」。世間胸算用1「皆人かしこすぎて結句―・き事にはまりぬ」
④心と心とのへだたりが少ない。親しい。万葉集15「遠くとも心を―・くおもほせ吾妹」
⑤血縁が遠くない。身寄りである。身内である。源氏物語蛍「―・きよすがにて見むは飽かぬ事にやあらむ」。「―・い親戚」
⑥物事の形状・内容・性質が似ている。徒然草「人倫にとほく禽獣に―・きふるまひ」。「紫に―・い赤」
⑦ある数量にもう少しで届く。「五十に―・い」
⑧近視である。「目が―・い」
ちがい【違い】チガヒ
ちがうこと。同じでないこと。また、その程度。〈日葡辞書〉。「―を見つける」
⇒ちがい‐さいふ【違割符】
⇒ちがい‐だか【違鷹】
⇒ちがい‐たかのは【違鷹羽】
⇒ちがい‐だな【違い棚】
⇒ちがい‐づけ【違付】
⇒ちがい‐め【違い目】
ち‐がい【地外】‥グワイ
ある地域のそと。
ち‐がい【痴騃】
経験が足らず適切に判断するだけの知識がないこと。愚かであること。森鴎外、舞姫「われ等二人の間にはまだ―なる歓楽のみ存じたりしを」
ち‐がい【稚貝】‥ガヒ
幼生の時期を終わって、砂泥または岩石上などに定着して間もない、幼い微小な貝類。
ちかい‐うんどう【地塊運動】‥クワイ‥
地塊が周囲の断層を境に、一体となって傾いたり隆起・沈降を起こしたりする地殻変動。
⇒ち‐かい【地塊】
ちか‐いえか【地下家蚊】‥イヘ‥
カ科の昆虫。アカイエカの一亜種で、形態的にはそれに酷似するが、無吸血でも産卵できるなど、生理的に異なる。地下の水溜りから発生し、特に都市部に多く、成虫は年中見られる。
ちかい‐ごと【誓い言】チカヒ‥
誓って言うことば。ちかごと。誓詞せいし。せいごん。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐さいふ【違割符】チガヒ‥
中世の為替手形で、割符屋で支払いを拒否されたもの。信用制度の不備による。
⇒ちがい【違い】
ちがいそ
褐藻類の海藻。ワカメに似るが、中肋ちゅうろくは著しく厚く、全体が細長い。1メートルに達し、成熟するとナイフ状の胞子葉をつける。北海道・東北地方の干潮線付近の岩上に自生。若いものは食用。エゾワカメ。サルメン。
ちがいそ
ちえん‐りそく【遅延利息】
債務者が遅延賠償として債権者に支払うべき金銭。旧民法上の用語に由来するもので、本来の意味での利息ではない。
⇒ち‐えん【遅延】
チオ【thio】
硫黄を表す接頭語。チオ硫酸・チオシアン酸などのように化合物名に付ける。
ちお‐あき【千百秋】チホ‥
千百年。また、かぎりなく続く年月。ちいほあき。日本紀竟宴歌「―の国をさめたるあとをのみよろづよ今もわすれやはする」
チオール【thiol】
メルカプト基‐SHをもつ化合物の総称。一般式R‐SH(Rはアルキル基など炭化水素基)。一般に揮発しやすい不快臭のある液体。代表例はエタンチオールで、都市ガスの臭気付与剤などに用いる。
チオクト‐さん【チオクト酸】
(thioctic acid)(→)リポ酸に同じ。
チオシアン‐さん【チオシアン酸】
(thiocyanic acid)刺激臭のある不安定な気体。分子式HSCN カリウム塩(チオシアン酸カリウム)は無色の結晶。その水溶液は鉄(Ⅲ)イオンを含む水溶液と反応して血赤色を呈し、鉄(Ⅲ)イオンの検出・定量に用いる。ロダン酸。
ち‐おち【血落ち】
(→)「血下ろし」に同じ。
ち‐おととい【乳兄弟】
⇒ちきょうだい。〈日葡辞書〉
チオフェン【thiophene】
分子式C4H4S 硫黄原子1個を含む五員環の複素環式化合物。芳香族性を持つ。無色の液体。コールタールから得たベンゼン中に少量含まれる。工業的にはブタンと硫黄を加熱してつくる。イサチンと濃硫酸を加えると青色を呈する反応(インドフェニン反応)により検出される。樹脂・染料・医薬の合成原料。
ち‐おも【乳母】
うば。めのと。神代紀下「彦火火出見尊ひこほほでみのみこと、婦人を取りて―・湯母…としたまふ」
ち‐おや【乳親】
①乳を飲ませて育てる女。うば。
②乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。
チオ‐りゅうさん‐ナトリウム【チオ硫酸ナトリウム】‥リウ‥
(sodium thiosulfate)化学式Na2S2O3 普通には五水和物で、無色の結晶。水に溶けやすい。水溶液はハロゲン化銀を溶かすので写真の定着液に用いる。漂白後の除塩素剤にも利用。次亜硫酸ナトリウムは誤称。ハイポ。
ち‐おろし【血下ろし】
子をおろすこと。堕胎だたい。ちおち。好色二代男「夜は男狂ひ、誰とも定めがたき―」
ち‐おん【地温】‥ヲン
地面または地中の温度。
⇒ちおん‐こうばい【地温勾配】
ちおん‐いん【知恩院】‥ヰン
京都市東山区にある浄土宗総本山。大谷寺知恩教院。法然が念仏をひろめ、また没した吉水御房・大谷禅房の跡に1234年(文暦1)弟子源智が再興した堂宇に始まる。16世紀に浄土宗総本山としての地位を確立し、徳川家康の菩提所ともなった。「法然上人絵伝」48巻などを所蔵。
ちおん‐こうばい【地温勾配】‥ヲン‥
地球内部で深さとともに温度の上昇する割合。通常は30メートルについて1度高くなるが、場所・深さにより変わる。この勾配のため熱が内部より地表へ伝わる。地下増温率。地温上昇率。
⇒ち‐おん【地温】
ちおん‐じ【知恩寺】
京都市左京区百万遍にある浄土宗の本山。法然の住した賀茂の河原屋に始まり、たびたび移転。1331年(元徳3)疫病流行に際し、8世善阿(空円)が百万遍念仏を修し効あったことから、寺号の百万遍を下賜。1662年(寛文2)から現在地。
ち‐か【地下】
①大地の下。「―街」「―に眠る」
②社会運動・政治運動などにおける非合法面。「―活動」「―出版物」
③⇒じげ(地下)
⇒地下に潜る
ち‐か【地価】
①土地の売買価格。「―の高騰」
②課税標準となる土地の価格で、公簿に登録されたもの。
ち‐か【知化】‥クワ
知力がよくはたらくこと。太平記1「深慮―の老臣」
ち‐か【治下】
ある政権の支配下にあること。統治下。
ちかい【誓い】チカヒ
①神仏に、ある事をそむくまいと約束すること。願がん。がんかけ。源氏物語夕霧「深き―にて今は命を限りける山ごもりを」。「―を立てる」
②衆生しゅじょうを救おうとする神仏の誓願。源氏物語若菜下「不動尊の御もとの―あり。その日数をだにかけ留め奉り給へ」
③ある事を将来必ず履行しようと他人や自分自身に固く約束すること。また、その言葉。「―を交わす」
⇒ちかい‐ごと【誓い言】
⇒ちかい‐だて【誓い立て】
⇒ちかい‐の‐あみ【誓の網】
⇒ちかい‐の‐うみ【誓の海】
⇒ちかい‐の‐ふね【誓の船】
⇒ちかい‐ぶみ【誓文】
ち‐かい【地界】
①土地の境界。また、土地。
②地上の世界。↔天界
ち‐かい【地階】
建物で、地盤面以下の階。
ち‐かい【地塊】‥クワイ
四方が断層面によって限られた陸地の塊。
⇒ちかい‐うんどう【地塊運動】
ち‐かい【知解】
知識の力でさとること。
ちか・い【近い】
〔形〕[文]ちか・し(ク)
①距離のへだたりが小さい。遠くない。古事記下「其の老媼の住める屋は―・く宮の辺に作りて日毎に必ず召しき」。日葡辞書「ホドチカイ」。「駅から―・い」
②時間のへだたりが小さい。万葉集19「わが思へる君に別れむ日―・くなりぬ」。源氏物語夕顔「明方も―・うなりにけり」。日葡辞書「チカイコロ・チカイホド」。「―・いうちに」「終りに―・い」
③よく見知っている。源氏物語早蕨「世のはかなさを目に―・く見しに」。世間胸算用1「皆人かしこすぎて結句―・き事にはまりぬ」
④心と心とのへだたりが少ない。親しい。万葉集15「遠くとも心を―・くおもほせ吾妹」
⑤血縁が遠くない。身寄りである。身内である。源氏物語蛍「―・きよすがにて見むは飽かぬ事にやあらむ」。「―・い親戚」
⑥物事の形状・内容・性質が似ている。徒然草「人倫にとほく禽獣に―・きふるまひ」。「紫に―・い赤」
⑦ある数量にもう少しで届く。「五十に―・い」
⑧近視である。「目が―・い」
ちがい【違い】チガヒ
ちがうこと。同じでないこと。また、その程度。〈日葡辞書〉。「―を見つける」
⇒ちがい‐さいふ【違割符】
⇒ちがい‐だか【違鷹】
⇒ちがい‐たかのは【違鷹羽】
⇒ちがい‐だな【違い棚】
⇒ちがい‐づけ【違付】
⇒ちがい‐め【違い目】
ち‐がい【地外】‥グワイ
ある地域のそと。
ち‐がい【痴騃】
経験が足らず適切に判断するだけの知識がないこと。愚かであること。森鴎外、舞姫「われ等二人の間にはまだ―なる歓楽のみ存じたりしを」
ち‐がい【稚貝】‥ガヒ
幼生の時期を終わって、砂泥または岩石上などに定着して間もない、幼い微小な貝類。
ちかい‐うんどう【地塊運動】‥クワイ‥
地塊が周囲の断層を境に、一体となって傾いたり隆起・沈降を起こしたりする地殻変動。
⇒ち‐かい【地塊】
ちか‐いえか【地下家蚊】‥イヘ‥
カ科の昆虫。アカイエカの一亜種で、形態的にはそれに酷似するが、無吸血でも産卵できるなど、生理的に異なる。地下の水溜りから発生し、特に都市部に多く、成虫は年中見られる。
ちかい‐ごと【誓い言】チカヒ‥
誓って言うことば。ちかごと。誓詞せいし。せいごん。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐さいふ【違割符】チガヒ‥
中世の為替手形で、割符屋で支払いを拒否されたもの。信用制度の不備による。
⇒ちがい【違い】
ちがいそ
褐藻類の海藻。ワカメに似るが、中肋ちゅうろくは著しく厚く、全体が細長い。1メートルに達し、成熟するとナイフ状の胞子葉をつける。北海道・東北地方の干潮線付近の岩上に自生。若いものは食用。エゾワカメ。サルメン。
ちがいそ
 ちがい‐だか【違鷹】チガヒ‥
違鷹羽ちがいたかのはの略。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐たかのは【違鷹羽】チガヒ‥
紋所の名。鷹の羽を斜めに交差させたもの。→鷹の羽(図)。
⇒ちがい【違い】
ちかい‐だて【誓い立て】チカヒ‥
誓いを立てること。誓文立せいもんだて。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐だな【違い棚】チガヒ‥
2枚の棚板を左右から上下2段に食い違いに釣り、間に蝦束えびづかを入れた棚。天袋・池袋・地板を含めていう。床の間・書院などの脇に設ける。ちがえだな。
違い棚
ちがい‐だか【違鷹】チガヒ‥
違鷹羽ちがいたかのはの略。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐たかのは【違鷹羽】チガヒ‥
紋所の名。鷹の羽を斜めに交差させたもの。→鷹の羽(図)。
⇒ちがい【違い】
ちかい‐だて【誓い立て】チカヒ‥
誓いを立てること。誓文立せいもんだて。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐だな【違い棚】チガヒ‥
2枚の棚板を左右から上下2段に食い違いに釣り、間に蝦束えびづかを入れた棚。天袋・池袋・地板を含めていう。床の間・書院などの脇に設ける。ちがえだな。
違い棚
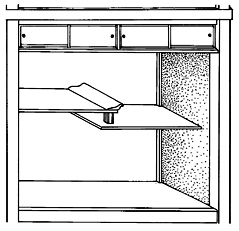 ⇒ちがい【違い】
ちがい‐づけ【違付】チガヒ‥
連歌の付け方の一つ。「春」に「秋」、「憂し」に「嬉し」など、前句と反対の意の語をつける類。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐ない【違いない】チガヒ‥
①(「に―」の形で)確実にそうだ。きまっている。「来るに―」「それに―」
②相手の言うことを受けて肯定する語。そのとおりだ。
ちかい‐の‐あみ【誓の網】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの網」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐の‐うみ【誓の海】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの海」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐の‐ふね【誓の船】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの船」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐ぶみ【誓文】チカヒ‥
誓いの言葉を記した文。せいもん。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐ほうけん【治外法権】‥グワイハフ‥
①外国の領域内にいてその国の法律、特に裁判権の支配を受けない特権。この特権を享有する主要なものは元首と外交使節であるが、軍艦・軍用航空機または軍隊もこれを認められる。
②領事裁判権の俗称。
ちがい‐め【違い目】チガヒ‥
①ちがったところ。
②筋かいに組んだところ。
⇒ちがい【違い】
ちか・う【誓う・盟う】チカフ
〔他五〕
①神仏や他人・自分自身などに対して、ある事を必ず守ると固く約束する。日本霊異記中「母の奉為みために法華経を写して、―・ひて曰はく」。「天地神明に―・う」「将来を―・った仲」
②神仏が国家鎮護・衆生済度などの誓願をする。増鏡「久かたの天地あめつちともにかぎりなき天つ日つぎを―・ひてし神もろともにまもれとて」
ちが・う【違う・交う】チガフ
[一]〔自五〕
二つ以上のものの動きが一つの点に合わない意。
①互いに行きはずれる。すれちがう。ゆきちがう。大鏡伊尹「書きていそぎ奉り給へど―・ひていととく参り給ひにけり」。平家物語11「判官もさきに心得て面に立つやうにはしけれどもとかく―・ひて能登殿には組まれず」
②合わない。相違する。誤る。たがう。天草本伊曾保物語「イソポが申したに―・はず」。「意見が―・う」「いつもと―・う」「答えが―・う」「約束が―・う」
③人の気持に合わない。機嫌をそこねる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「父つさまは殿さまのお気に―・うて」
④普通と異なる。狂う。「気が―・う」
[二]〔他下二〕
⇒ちがえる(下一)
ちか‐うんどう【地下運動】
(→)地下活動に同じ。
ちがえ【違え】チガヘ
①ちがえること。ちがえたさま。
②鹿が狩人にあった時、狩人の方を向いて立ち上がり、前足を交叉させて突き出すしぐさ。
⇒ちがえ‐だな【違え棚】
⇒ちがえ‐やりど【違え遣戸】
ちがえ‐だな【違え棚】チガヘ‥
⇒ちがいだな。
⇒ちがえ【違え】
ちがえ‐やりど【違え遣戸】チガヘ‥
二つの溝にはめて、入りちがわせて開閉する遣戸。
⇒ちがえ【違え】
ちが・える【違える・交える】チガヘル
〔他下一〕[文]ちが・ふ(下二)
①互いに行き合わないようにする。交錯させる。源氏物語蜻蛉「几帳どもの、立て―・へたるあはひより、見通されてあらはなり」
②交叉させる。続古今和歌集恋「鵲の―・ふるはしの間遠にて隔つる中に霜や置くらむ」
③相違させる。他と異なるものにする。「色を―・えて目立たせる」
④悪い夢を良い夢にかえる。大鏡道長「―・へさせ祈りなどをもすべかりけることを」
⑤正常の位置からはずす。「足の筋を―・える」
⑥まちがえる。「人を―・えた」
⑦違背する。日葡辞書「ヤクソク(約束)ヲチガユル」
ちか‐おとり【近劣り】
近寄って見ると、遠くから見るより劣って見えること。源氏物語総角「さりとも―しては思はずやあらむ」↔近優まさり
ちか‐がい【地下街】
公共の地下通路に面して作られた商店街。広義には、それに接続するビルの地下階、地下駐車場、地下広場、地下鉄駅などの総称。
ちかがく‐たんさ【地化学探査】‥クワ‥
(→)化学探鉱に同じ。
ちか‐かせん【地下河川】
道路の下など地下空間に設けた放水路。
ちか‐がつえ【近餓え】‥ガツヱ
飲食の後、すぐにまた食欲を催すこと。また、その人。転じて、色欲にもいう。浄瑠璃、神霊矢口渡「この長蔵は―、手附けにちよつと口々と」
ちか‐かつどう【地下活動】‥クワツ‥
秘密に行う非合法の社会運動・政治運動など。地下運動。潜行運動。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐づけ【違付】チガヒ‥
連歌の付け方の一つ。「春」に「秋」、「憂し」に「嬉し」など、前句と反対の意の語をつける類。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐ない【違いない】チガヒ‥
①(「に―」の形で)確実にそうだ。きまっている。「来るに―」「それに―」
②相手の言うことを受けて肯定する語。そのとおりだ。
ちかい‐の‐あみ【誓の網】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの網」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐の‐うみ【誓の海】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの海」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐の‐ふね【誓の船】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの船」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐ぶみ【誓文】チカヒ‥
誓いの言葉を記した文。せいもん。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐ほうけん【治外法権】‥グワイハフ‥
①外国の領域内にいてその国の法律、特に裁判権の支配を受けない特権。この特権を享有する主要なものは元首と外交使節であるが、軍艦・軍用航空機または軍隊もこれを認められる。
②領事裁判権の俗称。
ちがい‐め【違い目】チガヒ‥
①ちがったところ。
②筋かいに組んだところ。
⇒ちがい【違い】
ちか・う【誓う・盟う】チカフ
〔他五〕
①神仏や他人・自分自身などに対して、ある事を必ず守ると固く約束する。日本霊異記中「母の奉為みために法華経を写して、―・ひて曰はく」。「天地神明に―・う」「将来を―・った仲」
②神仏が国家鎮護・衆生済度などの誓願をする。増鏡「久かたの天地あめつちともにかぎりなき天つ日つぎを―・ひてし神もろともにまもれとて」
ちが・う【違う・交う】チガフ
[一]〔自五〕
二つ以上のものの動きが一つの点に合わない意。
①互いに行きはずれる。すれちがう。ゆきちがう。大鏡伊尹「書きていそぎ奉り給へど―・ひていととく参り給ひにけり」。平家物語11「判官もさきに心得て面に立つやうにはしけれどもとかく―・ひて能登殿には組まれず」
②合わない。相違する。誤る。たがう。天草本伊曾保物語「イソポが申したに―・はず」。「意見が―・う」「いつもと―・う」「答えが―・う」「約束が―・う」
③人の気持に合わない。機嫌をそこねる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「父つさまは殿さまのお気に―・うて」
④普通と異なる。狂う。「気が―・う」
[二]〔他下二〕
⇒ちがえる(下一)
ちか‐うんどう【地下運動】
(→)地下活動に同じ。
ちがえ【違え】チガヘ
①ちがえること。ちがえたさま。
②鹿が狩人にあった時、狩人の方を向いて立ち上がり、前足を交叉させて突き出すしぐさ。
⇒ちがえ‐だな【違え棚】
⇒ちがえ‐やりど【違え遣戸】
ちがえ‐だな【違え棚】チガヘ‥
⇒ちがいだな。
⇒ちがえ【違え】
ちがえ‐やりど【違え遣戸】チガヘ‥
二つの溝にはめて、入りちがわせて開閉する遣戸。
⇒ちがえ【違え】
ちが・える【違える・交える】チガヘル
〔他下一〕[文]ちが・ふ(下二)
①互いに行き合わないようにする。交錯させる。源氏物語蜻蛉「几帳どもの、立て―・へたるあはひより、見通されてあらはなり」
②交叉させる。続古今和歌集恋「鵲の―・ふるはしの間遠にて隔つる中に霜や置くらむ」
③相違させる。他と異なるものにする。「色を―・えて目立たせる」
④悪い夢を良い夢にかえる。大鏡道長「―・へさせ祈りなどをもすべかりけることを」
⑤正常の位置からはずす。「足の筋を―・える」
⑥まちがえる。「人を―・えた」
⑦違背する。日葡辞書「ヤクソク(約束)ヲチガユル」
ちか‐おとり【近劣り】
近寄って見ると、遠くから見るより劣って見えること。源氏物語総角「さりとも―しては思はずやあらむ」↔近優まさり
ちか‐がい【地下街】
公共の地下通路に面して作られた商店街。広義には、それに接続するビルの地下階、地下駐車場、地下広場、地下鉄駅などの総称。
ちかがく‐たんさ【地化学探査】‥クワ‥
(→)化学探鉱に同じ。
ちか‐かせん【地下河川】
道路の下など地下空間に設けた放水路。
ちか‐がつえ【近餓え】‥ガツヱ
飲食の後、すぐにまた食欲を催すこと。また、その人。転じて、色欲にもいう。浄瑠璃、神霊矢口渡「この長蔵は―、手附けにちよつと口々と」
ちか‐かつどう【地下活動】‥クワツ‥
秘密に行う非合法の社会運動・政治運動など。地下運動。潜行運動。
 チエンマイ ドイ‐ステープ寺入口
撮影:小松義夫
チエンマイ ドイ‐ステープ寺入口
撮影:小松義夫
 ちえん‐りそく【遅延利息】
債務者が遅延賠償として債権者に支払うべき金銭。旧民法上の用語に由来するもので、本来の意味での利息ではない。
⇒ち‐えん【遅延】
チオ【thio】
硫黄を表す接頭語。チオ硫酸・チオシアン酸などのように化合物名に付ける。
ちお‐あき【千百秋】チホ‥
千百年。また、かぎりなく続く年月。ちいほあき。日本紀竟宴歌「―の国をさめたるあとをのみよろづよ今もわすれやはする」
チオール【thiol】
メルカプト基‐SHをもつ化合物の総称。一般式R‐SH(Rはアルキル基など炭化水素基)。一般に揮発しやすい不快臭のある液体。代表例はエタンチオールで、都市ガスの臭気付与剤などに用いる。
チオクト‐さん【チオクト酸】
(thioctic acid)(→)リポ酸に同じ。
チオシアン‐さん【チオシアン酸】
(thiocyanic acid)刺激臭のある不安定な気体。分子式HSCN カリウム塩(チオシアン酸カリウム)は無色の結晶。その水溶液は鉄(Ⅲ)イオンを含む水溶液と反応して血赤色を呈し、鉄(Ⅲ)イオンの検出・定量に用いる。ロダン酸。
ち‐おち【血落ち】
(→)「血下ろし」に同じ。
ち‐おととい【乳兄弟】
⇒ちきょうだい。〈日葡辞書〉
チオフェン【thiophene】
分子式C4H4S 硫黄原子1個を含む五員環の複素環式化合物。芳香族性を持つ。無色の液体。コールタールから得たベンゼン中に少量含まれる。工業的にはブタンと硫黄を加熱してつくる。イサチンと濃硫酸を加えると青色を呈する反応(インドフェニン反応)により検出される。樹脂・染料・医薬の合成原料。
ち‐おも【乳母】
うば。めのと。神代紀下「彦火火出見尊ひこほほでみのみこと、婦人を取りて―・湯母…としたまふ」
ち‐おや【乳親】
①乳を飲ませて育てる女。うば。
②乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。
チオ‐りゅうさん‐ナトリウム【チオ硫酸ナトリウム】‥リウ‥
(sodium thiosulfate)化学式Na2S2O3 普通には五水和物で、無色の結晶。水に溶けやすい。水溶液はハロゲン化銀を溶かすので写真の定着液に用いる。漂白後の除塩素剤にも利用。次亜硫酸ナトリウムは誤称。ハイポ。
ち‐おろし【血下ろし】
子をおろすこと。堕胎だたい。ちおち。好色二代男「夜は男狂ひ、誰とも定めがたき―」
ち‐おん【地温】‥ヲン
地面または地中の温度。
⇒ちおん‐こうばい【地温勾配】
ちおん‐いん【知恩院】‥ヰン
京都市東山区にある浄土宗総本山。大谷寺知恩教院。法然が念仏をひろめ、また没した吉水御房・大谷禅房の跡に1234年(文暦1)弟子源智が再興した堂宇に始まる。16世紀に浄土宗総本山としての地位を確立し、徳川家康の菩提所ともなった。「法然上人絵伝」48巻などを所蔵。
ちおん‐こうばい【地温勾配】‥ヲン‥
地球内部で深さとともに温度の上昇する割合。通常は30メートルについて1度高くなるが、場所・深さにより変わる。この勾配のため熱が内部より地表へ伝わる。地下増温率。地温上昇率。
⇒ち‐おん【地温】
ちおん‐じ【知恩寺】
京都市左京区百万遍にある浄土宗の本山。法然の住した賀茂の河原屋に始まり、たびたび移転。1331年(元徳3)疫病流行に際し、8世善阿(空円)が百万遍念仏を修し効あったことから、寺号の百万遍を下賜。1662年(寛文2)から現在地。
ち‐か【地下】
①大地の下。「―街」「―に眠る」
②社会運動・政治運動などにおける非合法面。「―活動」「―出版物」
③⇒じげ(地下)
⇒地下に潜る
ち‐か【地価】
①土地の売買価格。「―の高騰」
②課税標準となる土地の価格で、公簿に登録されたもの。
ち‐か【知化】‥クワ
知力がよくはたらくこと。太平記1「深慮―の老臣」
ち‐か【治下】
ある政権の支配下にあること。統治下。
ちかい【誓い】チカヒ
①神仏に、ある事をそむくまいと約束すること。願がん。がんかけ。源氏物語夕霧「深き―にて今は命を限りける山ごもりを」。「―を立てる」
②衆生しゅじょうを救おうとする神仏の誓願。源氏物語若菜下「不動尊の御もとの―あり。その日数をだにかけ留め奉り給へ」
③ある事を将来必ず履行しようと他人や自分自身に固く約束すること。また、その言葉。「―を交わす」
⇒ちかい‐ごと【誓い言】
⇒ちかい‐だて【誓い立て】
⇒ちかい‐の‐あみ【誓の網】
⇒ちかい‐の‐うみ【誓の海】
⇒ちかい‐の‐ふね【誓の船】
⇒ちかい‐ぶみ【誓文】
ち‐かい【地界】
①土地の境界。また、土地。
②地上の世界。↔天界
ち‐かい【地階】
建物で、地盤面以下の階。
ち‐かい【地塊】‥クワイ
四方が断層面によって限られた陸地の塊。
⇒ちかい‐うんどう【地塊運動】
ち‐かい【知解】
知識の力でさとること。
ちか・い【近い】
〔形〕[文]ちか・し(ク)
①距離のへだたりが小さい。遠くない。古事記下「其の老媼の住める屋は―・く宮の辺に作りて日毎に必ず召しき」。日葡辞書「ホドチカイ」。「駅から―・い」
②時間のへだたりが小さい。万葉集19「わが思へる君に別れむ日―・くなりぬ」。源氏物語夕顔「明方も―・うなりにけり」。日葡辞書「チカイコロ・チカイホド」。「―・いうちに」「終りに―・い」
③よく見知っている。源氏物語早蕨「世のはかなさを目に―・く見しに」。世間胸算用1「皆人かしこすぎて結句―・き事にはまりぬ」
④心と心とのへだたりが少ない。親しい。万葉集15「遠くとも心を―・くおもほせ吾妹」
⑤血縁が遠くない。身寄りである。身内である。源氏物語蛍「―・きよすがにて見むは飽かぬ事にやあらむ」。「―・い親戚」
⑥物事の形状・内容・性質が似ている。徒然草「人倫にとほく禽獣に―・きふるまひ」。「紫に―・い赤」
⑦ある数量にもう少しで届く。「五十に―・い」
⑧近視である。「目が―・い」
ちがい【違い】チガヒ
ちがうこと。同じでないこと。また、その程度。〈日葡辞書〉。「―を見つける」
⇒ちがい‐さいふ【違割符】
⇒ちがい‐だか【違鷹】
⇒ちがい‐たかのは【違鷹羽】
⇒ちがい‐だな【違い棚】
⇒ちがい‐づけ【違付】
⇒ちがい‐め【違い目】
ち‐がい【地外】‥グワイ
ある地域のそと。
ち‐がい【痴騃】
経験が足らず適切に判断するだけの知識がないこと。愚かであること。森鴎外、舞姫「われ等二人の間にはまだ―なる歓楽のみ存じたりしを」
ち‐がい【稚貝】‥ガヒ
幼生の時期を終わって、砂泥または岩石上などに定着して間もない、幼い微小な貝類。
ちかい‐うんどう【地塊運動】‥クワイ‥
地塊が周囲の断層を境に、一体となって傾いたり隆起・沈降を起こしたりする地殻変動。
⇒ち‐かい【地塊】
ちか‐いえか【地下家蚊】‥イヘ‥
カ科の昆虫。アカイエカの一亜種で、形態的にはそれに酷似するが、無吸血でも産卵できるなど、生理的に異なる。地下の水溜りから発生し、特に都市部に多く、成虫は年中見られる。
ちかい‐ごと【誓い言】チカヒ‥
誓って言うことば。ちかごと。誓詞せいし。せいごん。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐さいふ【違割符】チガヒ‥
中世の為替手形で、割符屋で支払いを拒否されたもの。信用制度の不備による。
⇒ちがい【違い】
ちがいそ
褐藻類の海藻。ワカメに似るが、中肋ちゅうろくは著しく厚く、全体が細長い。1メートルに達し、成熟するとナイフ状の胞子葉をつける。北海道・東北地方の干潮線付近の岩上に自生。若いものは食用。エゾワカメ。サルメン。
ちがいそ
ちえん‐りそく【遅延利息】
債務者が遅延賠償として債権者に支払うべき金銭。旧民法上の用語に由来するもので、本来の意味での利息ではない。
⇒ち‐えん【遅延】
チオ【thio】
硫黄を表す接頭語。チオ硫酸・チオシアン酸などのように化合物名に付ける。
ちお‐あき【千百秋】チホ‥
千百年。また、かぎりなく続く年月。ちいほあき。日本紀竟宴歌「―の国をさめたるあとをのみよろづよ今もわすれやはする」
チオール【thiol】
メルカプト基‐SHをもつ化合物の総称。一般式R‐SH(Rはアルキル基など炭化水素基)。一般に揮発しやすい不快臭のある液体。代表例はエタンチオールで、都市ガスの臭気付与剤などに用いる。
チオクト‐さん【チオクト酸】
(thioctic acid)(→)リポ酸に同じ。
チオシアン‐さん【チオシアン酸】
(thiocyanic acid)刺激臭のある不安定な気体。分子式HSCN カリウム塩(チオシアン酸カリウム)は無色の結晶。その水溶液は鉄(Ⅲ)イオンを含む水溶液と反応して血赤色を呈し、鉄(Ⅲ)イオンの検出・定量に用いる。ロダン酸。
ち‐おち【血落ち】
(→)「血下ろし」に同じ。
ち‐おととい【乳兄弟】
⇒ちきょうだい。〈日葡辞書〉
チオフェン【thiophene】
分子式C4H4S 硫黄原子1個を含む五員環の複素環式化合物。芳香族性を持つ。無色の液体。コールタールから得たベンゼン中に少量含まれる。工業的にはブタンと硫黄を加熱してつくる。イサチンと濃硫酸を加えると青色を呈する反応(インドフェニン反応)により検出される。樹脂・染料・医薬の合成原料。
ち‐おも【乳母】
うば。めのと。神代紀下「彦火火出見尊ひこほほでみのみこと、婦人を取りて―・湯母…としたまふ」
ち‐おや【乳親】
①乳を飲ませて育てる女。うば。
②乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。
チオ‐りゅうさん‐ナトリウム【チオ硫酸ナトリウム】‥リウ‥
(sodium thiosulfate)化学式Na2S2O3 普通には五水和物で、無色の結晶。水に溶けやすい。水溶液はハロゲン化銀を溶かすので写真の定着液に用いる。漂白後の除塩素剤にも利用。次亜硫酸ナトリウムは誤称。ハイポ。
ち‐おろし【血下ろし】
子をおろすこと。堕胎だたい。ちおち。好色二代男「夜は男狂ひ、誰とも定めがたき―」
ち‐おん【地温】‥ヲン
地面または地中の温度。
⇒ちおん‐こうばい【地温勾配】
ちおん‐いん【知恩院】‥ヰン
京都市東山区にある浄土宗総本山。大谷寺知恩教院。法然が念仏をひろめ、また没した吉水御房・大谷禅房の跡に1234年(文暦1)弟子源智が再興した堂宇に始まる。16世紀に浄土宗総本山としての地位を確立し、徳川家康の菩提所ともなった。「法然上人絵伝」48巻などを所蔵。
ちおん‐こうばい【地温勾配】‥ヲン‥
地球内部で深さとともに温度の上昇する割合。通常は30メートルについて1度高くなるが、場所・深さにより変わる。この勾配のため熱が内部より地表へ伝わる。地下増温率。地温上昇率。
⇒ち‐おん【地温】
ちおん‐じ【知恩寺】
京都市左京区百万遍にある浄土宗の本山。法然の住した賀茂の河原屋に始まり、たびたび移転。1331年(元徳3)疫病流行に際し、8世善阿(空円)が百万遍念仏を修し効あったことから、寺号の百万遍を下賜。1662年(寛文2)から現在地。
ち‐か【地下】
①大地の下。「―街」「―に眠る」
②社会運動・政治運動などにおける非合法面。「―活動」「―出版物」
③⇒じげ(地下)
⇒地下に潜る
ち‐か【地価】
①土地の売買価格。「―の高騰」
②課税標準となる土地の価格で、公簿に登録されたもの。
ち‐か【知化】‥クワ
知力がよくはたらくこと。太平記1「深慮―の老臣」
ち‐か【治下】
ある政権の支配下にあること。統治下。
ちかい【誓い】チカヒ
①神仏に、ある事をそむくまいと約束すること。願がん。がんかけ。源氏物語夕霧「深き―にて今は命を限りける山ごもりを」。「―を立てる」
②衆生しゅじょうを救おうとする神仏の誓願。源氏物語若菜下「不動尊の御もとの―あり。その日数をだにかけ留め奉り給へ」
③ある事を将来必ず履行しようと他人や自分自身に固く約束すること。また、その言葉。「―を交わす」
⇒ちかい‐ごと【誓い言】
⇒ちかい‐だて【誓い立て】
⇒ちかい‐の‐あみ【誓の網】
⇒ちかい‐の‐うみ【誓の海】
⇒ちかい‐の‐ふね【誓の船】
⇒ちかい‐ぶみ【誓文】
ち‐かい【地界】
①土地の境界。また、土地。
②地上の世界。↔天界
ち‐かい【地階】
建物で、地盤面以下の階。
ち‐かい【地塊】‥クワイ
四方が断層面によって限られた陸地の塊。
⇒ちかい‐うんどう【地塊運動】
ち‐かい【知解】
知識の力でさとること。
ちか・い【近い】
〔形〕[文]ちか・し(ク)
①距離のへだたりが小さい。遠くない。古事記下「其の老媼の住める屋は―・く宮の辺に作りて日毎に必ず召しき」。日葡辞書「ホドチカイ」。「駅から―・い」
②時間のへだたりが小さい。万葉集19「わが思へる君に別れむ日―・くなりぬ」。源氏物語夕顔「明方も―・うなりにけり」。日葡辞書「チカイコロ・チカイホド」。「―・いうちに」「終りに―・い」
③よく見知っている。源氏物語早蕨「世のはかなさを目に―・く見しに」。世間胸算用1「皆人かしこすぎて結句―・き事にはまりぬ」
④心と心とのへだたりが少ない。親しい。万葉集15「遠くとも心を―・くおもほせ吾妹」
⑤血縁が遠くない。身寄りである。身内である。源氏物語蛍「―・きよすがにて見むは飽かぬ事にやあらむ」。「―・い親戚」
⑥物事の形状・内容・性質が似ている。徒然草「人倫にとほく禽獣に―・きふるまひ」。「紫に―・い赤」
⑦ある数量にもう少しで届く。「五十に―・い」
⑧近視である。「目が―・い」
ちがい【違い】チガヒ
ちがうこと。同じでないこと。また、その程度。〈日葡辞書〉。「―を見つける」
⇒ちがい‐さいふ【違割符】
⇒ちがい‐だか【違鷹】
⇒ちがい‐たかのは【違鷹羽】
⇒ちがい‐だな【違い棚】
⇒ちがい‐づけ【違付】
⇒ちがい‐め【違い目】
ち‐がい【地外】‥グワイ
ある地域のそと。
ち‐がい【痴騃】
経験が足らず適切に判断するだけの知識がないこと。愚かであること。森鴎外、舞姫「われ等二人の間にはまだ―なる歓楽のみ存じたりしを」
ち‐がい【稚貝】‥ガヒ
幼生の時期を終わって、砂泥または岩石上などに定着して間もない、幼い微小な貝類。
ちかい‐うんどう【地塊運動】‥クワイ‥
地塊が周囲の断層を境に、一体となって傾いたり隆起・沈降を起こしたりする地殻変動。
⇒ち‐かい【地塊】
ちか‐いえか【地下家蚊】‥イヘ‥
カ科の昆虫。アカイエカの一亜種で、形態的にはそれに酷似するが、無吸血でも産卵できるなど、生理的に異なる。地下の水溜りから発生し、特に都市部に多く、成虫は年中見られる。
ちかい‐ごと【誓い言】チカヒ‥
誓って言うことば。ちかごと。誓詞せいし。せいごん。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐さいふ【違割符】チガヒ‥
中世の為替手形で、割符屋で支払いを拒否されたもの。信用制度の不備による。
⇒ちがい【違い】
ちがいそ
褐藻類の海藻。ワカメに似るが、中肋ちゅうろくは著しく厚く、全体が細長い。1メートルに達し、成熟するとナイフ状の胞子葉をつける。北海道・東北地方の干潮線付近の岩上に自生。若いものは食用。エゾワカメ。サルメン。
ちがいそ
 ちがい‐だか【違鷹】チガヒ‥
違鷹羽ちがいたかのはの略。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐たかのは【違鷹羽】チガヒ‥
紋所の名。鷹の羽を斜めに交差させたもの。→鷹の羽(図)。
⇒ちがい【違い】
ちかい‐だて【誓い立て】チカヒ‥
誓いを立てること。誓文立せいもんだて。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐だな【違い棚】チガヒ‥
2枚の棚板を左右から上下2段に食い違いに釣り、間に蝦束えびづかを入れた棚。天袋・池袋・地板を含めていう。床の間・書院などの脇に設ける。ちがえだな。
違い棚
ちがい‐だか【違鷹】チガヒ‥
違鷹羽ちがいたかのはの略。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐たかのは【違鷹羽】チガヒ‥
紋所の名。鷹の羽を斜めに交差させたもの。→鷹の羽(図)。
⇒ちがい【違い】
ちかい‐だて【誓い立て】チカヒ‥
誓いを立てること。誓文立せいもんだて。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐だな【違い棚】チガヒ‥
2枚の棚板を左右から上下2段に食い違いに釣り、間に蝦束えびづかを入れた棚。天袋・池袋・地板を含めていう。床の間・書院などの脇に設ける。ちがえだな。
違い棚
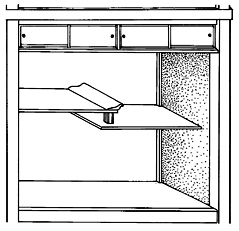 ⇒ちがい【違い】
ちがい‐づけ【違付】チガヒ‥
連歌の付け方の一つ。「春」に「秋」、「憂し」に「嬉し」など、前句と反対の意の語をつける類。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐ない【違いない】チガヒ‥
①(「に―」の形で)確実にそうだ。きまっている。「来るに―」「それに―」
②相手の言うことを受けて肯定する語。そのとおりだ。
ちかい‐の‐あみ【誓の網】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの網」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐の‐うみ【誓の海】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの海」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐の‐ふね【誓の船】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの船」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐ぶみ【誓文】チカヒ‥
誓いの言葉を記した文。せいもん。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐ほうけん【治外法権】‥グワイハフ‥
①外国の領域内にいてその国の法律、特に裁判権の支配を受けない特権。この特権を享有する主要なものは元首と外交使節であるが、軍艦・軍用航空機または軍隊もこれを認められる。
②領事裁判権の俗称。
ちがい‐め【違い目】チガヒ‥
①ちがったところ。
②筋かいに組んだところ。
⇒ちがい【違い】
ちか・う【誓う・盟う】チカフ
〔他五〕
①神仏や他人・自分自身などに対して、ある事を必ず守ると固く約束する。日本霊異記中「母の奉為みために法華経を写して、―・ひて曰はく」。「天地神明に―・う」「将来を―・った仲」
②神仏が国家鎮護・衆生済度などの誓願をする。増鏡「久かたの天地あめつちともにかぎりなき天つ日つぎを―・ひてし神もろともにまもれとて」
ちが・う【違う・交う】チガフ
[一]〔自五〕
二つ以上のものの動きが一つの点に合わない意。
①互いに行きはずれる。すれちがう。ゆきちがう。大鏡伊尹「書きていそぎ奉り給へど―・ひていととく参り給ひにけり」。平家物語11「判官もさきに心得て面に立つやうにはしけれどもとかく―・ひて能登殿には組まれず」
②合わない。相違する。誤る。たがう。天草本伊曾保物語「イソポが申したに―・はず」。「意見が―・う」「いつもと―・う」「答えが―・う」「約束が―・う」
③人の気持に合わない。機嫌をそこねる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「父つさまは殿さまのお気に―・うて」
④普通と異なる。狂う。「気が―・う」
[二]〔他下二〕
⇒ちがえる(下一)
ちか‐うんどう【地下運動】
(→)地下活動に同じ。
ちがえ【違え】チガヘ
①ちがえること。ちがえたさま。
②鹿が狩人にあった時、狩人の方を向いて立ち上がり、前足を交叉させて突き出すしぐさ。
⇒ちがえ‐だな【違え棚】
⇒ちがえ‐やりど【違え遣戸】
ちがえ‐だな【違え棚】チガヘ‥
⇒ちがいだな。
⇒ちがえ【違え】
ちがえ‐やりど【違え遣戸】チガヘ‥
二つの溝にはめて、入りちがわせて開閉する遣戸。
⇒ちがえ【違え】
ちが・える【違える・交える】チガヘル
〔他下一〕[文]ちが・ふ(下二)
①互いに行き合わないようにする。交錯させる。源氏物語蜻蛉「几帳どもの、立て―・へたるあはひより、見通されてあらはなり」
②交叉させる。続古今和歌集恋「鵲の―・ふるはしの間遠にて隔つる中に霜や置くらむ」
③相違させる。他と異なるものにする。「色を―・えて目立たせる」
④悪い夢を良い夢にかえる。大鏡道長「―・へさせ祈りなどをもすべかりけることを」
⑤正常の位置からはずす。「足の筋を―・える」
⑥まちがえる。「人を―・えた」
⑦違背する。日葡辞書「ヤクソク(約束)ヲチガユル」
ちか‐おとり【近劣り】
近寄って見ると、遠くから見るより劣って見えること。源氏物語総角「さりとも―しては思はずやあらむ」↔近優まさり
ちか‐がい【地下街】
公共の地下通路に面して作られた商店街。広義には、それに接続するビルの地下階、地下駐車場、地下広場、地下鉄駅などの総称。
ちかがく‐たんさ【地化学探査】‥クワ‥
(→)化学探鉱に同じ。
ちか‐かせん【地下河川】
道路の下など地下空間に設けた放水路。
ちか‐がつえ【近餓え】‥ガツヱ
飲食の後、すぐにまた食欲を催すこと。また、その人。転じて、色欲にもいう。浄瑠璃、神霊矢口渡「この長蔵は―、手附けにちよつと口々と」
ちか‐かつどう【地下活動】‥クワツ‥
秘密に行う非合法の社会運動・政治運動など。地下運動。潜行運動。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐づけ【違付】チガヒ‥
連歌の付け方の一つ。「春」に「秋」、「憂し」に「嬉し」など、前句と反対の意の語をつける類。
⇒ちがい【違い】
ちがい‐ない【違いない】チガヒ‥
①(「に―」の形で)確実にそうだ。きまっている。「来るに―」「それに―」
②相手の言うことを受けて肯定する語。そのとおりだ。
ちかい‐の‐あみ【誓の網】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの網」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐の‐うみ【誓の海】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの海」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐の‐ふね【誓の船】チカヒ‥
(→)「弘誓ぐぜいの船」に同じ。
⇒ちかい【誓い】
ちかい‐ぶみ【誓文】チカヒ‥
誓いの言葉を記した文。せいもん。
⇒ちかい【誓い】
ちがい‐ほうけん【治外法権】‥グワイハフ‥
①外国の領域内にいてその国の法律、特に裁判権の支配を受けない特権。この特権を享有する主要なものは元首と外交使節であるが、軍艦・軍用航空機または軍隊もこれを認められる。
②領事裁判権の俗称。
ちがい‐め【違い目】チガヒ‥
①ちがったところ。
②筋かいに組んだところ。
⇒ちがい【違い】
ちか・う【誓う・盟う】チカフ
〔他五〕
①神仏や他人・自分自身などに対して、ある事を必ず守ると固く約束する。日本霊異記中「母の奉為みために法華経を写して、―・ひて曰はく」。「天地神明に―・う」「将来を―・った仲」
②神仏が国家鎮護・衆生済度などの誓願をする。増鏡「久かたの天地あめつちともにかぎりなき天つ日つぎを―・ひてし神もろともにまもれとて」
ちが・う【違う・交う】チガフ
[一]〔自五〕
二つ以上のものの動きが一つの点に合わない意。
①互いに行きはずれる。すれちがう。ゆきちがう。大鏡伊尹「書きていそぎ奉り給へど―・ひていととく参り給ひにけり」。平家物語11「判官もさきに心得て面に立つやうにはしけれどもとかく―・ひて能登殿には組まれず」
②合わない。相違する。誤る。たがう。天草本伊曾保物語「イソポが申したに―・はず」。「意見が―・う」「いつもと―・う」「答えが―・う」「約束が―・う」
③人の気持に合わない。機嫌をそこねる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「父つさまは殿さまのお気に―・うて」
④普通と異なる。狂う。「気が―・う」
[二]〔他下二〕
⇒ちがえる(下一)
ちか‐うんどう【地下運動】
(→)地下活動に同じ。
ちがえ【違え】チガヘ
①ちがえること。ちがえたさま。
②鹿が狩人にあった時、狩人の方を向いて立ち上がり、前足を交叉させて突き出すしぐさ。
⇒ちがえ‐だな【違え棚】
⇒ちがえ‐やりど【違え遣戸】
ちがえ‐だな【違え棚】チガヘ‥
⇒ちがいだな。
⇒ちがえ【違え】
ちがえ‐やりど【違え遣戸】チガヘ‥
二つの溝にはめて、入りちがわせて開閉する遣戸。
⇒ちがえ【違え】
ちが・える【違える・交える】チガヘル
〔他下一〕[文]ちが・ふ(下二)
①互いに行き合わないようにする。交錯させる。源氏物語蜻蛉「几帳どもの、立て―・へたるあはひより、見通されてあらはなり」
②交叉させる。続古今和歌集恋「鵲の―・ふるはしの間遠にて隔つる中に霜や置くらむ」
③相違させる。他と異なるものにする。「色を―・えて目立たせる」
④悪い夢を良い夢にかえる。大鏡道長「―・へさせ祈りなどをもすべかりけることを」
⑤正常の位置からはずす。「足の筋を―・える」
⑥まちがえる。「人を―・えた」
⑦違背する。日葡辞書「ヤクソク(約束)ヲチガユル」
ちか‐おとり【近劣り】
近寄って見ると、遠くから見るより劣って見えること。源氏物語総角「さりとも―しては思はずやあらむ」↔近優まさり
ちか‐がい【地下街】
公共の地下通路に面して作られた商店街。広義には、それに接続するビルの地下階、地下駐車場、地下広場、地下鉄駅などの総称。
ちかがく‐たんさ【地化学探査】‥クワ‥
(→)化学探鉱に同じ。
ちか‐かせん【地下河川】
道路の下など地下空間に設けた放水路。
ちか‐がつえ【近餓え】‥ガツヱ
飲食の後、すぐにまた食欲を催すこと。また、その人。転じて、色欲にもいう。浄瑠璃、神霊矢口渡「この長蔵は―、手附けにちよつと口々と」
ちか‐かつどう【地下活動】‥クワツ‥
秘密に行う非合法の社会運動・政治運動など。地下運動。潜行運動。
ちおん‐いん【知恩院】‥ヰン🔗⭐🔉
ちおん‐いん【知恩院】‥ヰン
京都市東山区にある浄土宗総本山。大谷寺知恩教院。法然が念仏をひろめ、また没した吉水御房・大谷禅房の跡に1234年(文暦1)弟子源智が再興した堂宇に始まる。16世紀に浄土宗総本山としての地位を確立し、徳川家康の菩提所ともなった。「法然上人絵伝」48巻などを所蔵。
ちおん‐じ【知恩寺】🔗⭐🔉
ちおん‐じ【知恩寺】
京都市左京区百万遍にある浄土宗の本山。法然の住した賀茂の河原屋に始まり、たびたび移転。1331年(元徳3)疫病流行に際し、8世善阿(空円)が百万遍念仏を修し効あったことから、寺号の百万遍を下賜。1662年(寛文2)から現在地。
ち‐か【知化】‥クワ🔗⭐🔉
ち‐か【知化】‥クワ
知力がよくはたらくこと。太平記1「深慮―の老臣」
ち‐かい【知解】🔗⭐🔉
ち‐かい【知解】
知識の力でさとること。
ち‐かく【知覚】🔗⭐🔉
ち‐かく【知覚】
①〔仏〕知り覚ること。分別すること。
②〔心〕(perception)感覚器官への刺激を通じてもたらされた情報をもとに、外界の対象の性質・形態・関係および身体内部の状態を把握するはたらき。→感覚→認知1
⇒ちかく‐しんけい【知覚神経】
⇒ちかく‐まひ【知覚麻痺】
ちかくのげんしょうがく【知覚の現象学】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
ちかくのげんしょうがく【知覚の現象学】‥シヤウ‥
(Phénoménologie de la perception フランス)メルロ=ポンティの主著。1945年刊。世界を構成する主体を、意識ではなく知覚し運動する身体に求め、主知主義と経験主義をともに乗り越えることを目指す。
ちかく‐まひ【知覚麻痺】🔗⭐🔉
ちかく‐まひ【知覚麻痺】
神経系統や精神作用の障害により知覚が麻痺すること。知覚鈍麻。
⇒ち‐かく【知覚】
ち‐ぎょう【知暁】‥ゲウ🔗⭐🔉
ち‐ぎょう【知暁】‥ゲウ
知ってさとること。
ち‐ぐ【知愚・智愚】🔗⭐🔉
ち‐ぐ【知愚・智愚】
かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。
ち‐ぐう【知遇】🔗⭐🔉
ち‐ぐう【知遇】
人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」
ち‐けい【知契】🔗⭐🔉
ち‐けい【知契】
男色などで、きわめて深い交わり。親密なつきあい。浮世草子、風流比翼鳥「其身は兄分に任せ、―のわりなきを、外より見るも心よし」
ち‐けじ【知家事】🔗⭐🔉
ち‐けじ【知家事】
①親王・摂関・大臣家などの政所まんどころの職員。その家の家務を統べる。
②鎌倉幕府の政所の職員。案主あんじゅに次いで、文案に官職・氏名を連署したもの。
③伊勢神宮の祭主家・大宮司家などの職員。
ちちぶ【知知武】🔗⭐🔉
ちちぶ【知知武】
ハゼ科の硬骨魚。全長約10センチメートル。日本全土の淡水・汽水域に分布。ヌマチチブは近縁種。ダボハゼ。
○知は力なりちはちからなり🔗⭐🔉
○知は力なりちはちからなり
自然を正しく認識することで自然を支配することを説いたF.ベーコンの言葉。
⇒ち【智・知】
ち‐はつ【遅発】
①遅れて出発すること。
②〔医〕遅れて発症すること。
③銃の発火装置が不良のため、引き金を引いて少したって発火する現象。
ち‐はつ【薙髪】
①頭髪をそること。僧となること。落飾。剃髪ていはつ。
②もとどりを切ること。
ち‐ばな【茅花】
チガヤの花。つばな。〈日葡辞書〉
ち‐ばなれ【乳離れ】
①乳児が生長して、乳以外の食物をとるようになること。離乳。また、その時期。
②比喩的に、成長して保護を必要としない一人前の人間になること。「―していない青年」
ちば‐の【千葉の】
〔枕〕
「かづの(葛野)」(地名)にかかる。
[漢]知🔗⭐🔉
知 字形
 筆順
筆順
 〔矢部3画/8画/教育/3546・434E〕
〔音〕チ(呉)(漢)
〔訓〕しる (名)とも・さと・さとし・さとる
[意味]
①心に感じとる。道理をわきまえる。わかる。しる。しらせる。「知覚・知見・感知・認知・通知・告知」
②よくしっている。親しい交わりがある(人)。しりあい。「知人・知友・旧知」
③つかさどる。治める。「知事・知行ちぎょう」
④真理をさとる心のはたらき。ちえ。(同)智。「知恵・英知・機知・故知」
[解字]
形声。音符「矢」(=まっすぐに飛ぶ)+「口」。よく理解してずばりと言いあてる意。
[下ツキ
一知半解・叡知・英知・格物致知・奸知・感知・関知・奇知・機知・窺知・既知・旧知・下知・公知・巧知・狡知・告知・故知・才知・察知・邪知・周知・衆知・熟知・主知・小知・承知・上知・辱知・新知・神知・人知・推知・世知弁・全知・存知・大知・探知・通知・認知・風知草・不可知・聞知・報知・未知・無知・明知・予知・理知・了知・良知・霊知
〔矢部3画/8画/教育/3546・434E〕
〔音〕チ(呉)(漢)
〔訓〕しる (名)とも・さと・さとし・さとる
[意味]
①心に感じとる。道理をわきまえる。わかる。しる。しらせる。「知覚・知見・感知・認知・通知・告知」
②よくしっている。親しい交わりがある(人)。しりあい。「知人・知友・旧知」
③つかさどる。治める。「知事・知行ちぎょう」
④真理をさとる心のはたらき。ちえ。(同)智。「知恵・英知・機知・故知」
[解字]
形声。音符「矢」(=まっすぐに飛ぶ)+「口」。よく理解してずばりと言いあてる意。
[下ツキ
一知半解・叡知・英知・格物致知・奸知・感知・関知・奇知・機知・窺知・既知・旧知・下知・公知・巧知・狡知・告知・故知・才知・察知・邪知・周知・衆知・熟知・主知・小知・承知・上知・辱知・新知・神知・人知・推知・世知弁・全知・存知・大知・探知・通知・認知・風知草・不可知・聞知・報知・未知・無知・明知・予知・理知・了知・良知・霊知
 筆順
筆順
 〔矢部3画/8画/教育/3546・434E〕
〔音〕チ(呉)(漢)
〔訓〕しる (名)とも・さと・さとし・さとる
[意味]
①心に感じとる。道理をわきまえる。わかる。しる。しらせる。「知覚・知見・感知・認知・通知・告知」
②よくしっている。親しい交わりがある(人)。しりあい。「知人・知友・旧知」
③つかさどる。治める。「知事・知行ちぎょう」
④真理をさとる心のはたらき。ちえ。(同)智。「知恵・英知・機知・故知」
[解字]
形声。音符「矢」(=まっすぐに飛ぶ)+「口」。よく理解してずばりと言いあてる意。
[下ツキ
一知半解・叡知・英知・格物致知・奸知・感知・関知・奇知・機知・窺知・既知・旧知・下知・公知・巧知・狡知・告知・故知・才知・察知・邪知・周知・衆知・熟知・主知・小知・承知・上知・辱知・新知・神知・人知・推知・世知弁・全知・存知・大知・探知・通知・認知・風知草・不可知・聞知・報知・未知・無知・明知・予知・理知・了知・良知・霊知
〔矢部3画/8画/教育/3546・434E〕
〔音〕チ(呉)(漢)
〔訓〕しる (名)とも・さと・さとし・さとる
[意味]
①心に感じとる。道理をわきまえる。わかる。しる。しらせる。「知覚・知見・感知・認知・通知・告知」
②よくしっている。親しい交わりがある(人)。しりあい。「知人・知友・旧知」
③つかさどる。治める。「知事・知行ちぎょう」
④真理をさとる心のはたらき。ちえ。(同)智。「知恵・英知・機知・故知」
[解字]
形声。音符「矢」(=まっすぐに飛ぶ)+「口」。よく理解してずばりと言いあてる意。
[下ツキ
一知半解・叡知・英知・格物致知・奸知・感知・関知・奇知・機知・窺知・既知・旧知・下知・公知・巧知・狡知・告知・故知・才知・察知・邪知・周知・衆知・熟知・主知・小知・承知・上知・辱知・新知・神知・人知・推知・世知弁・全知・存知・大知・探知・通知・認知・風知草・不可知・聞知・報知・未知・無知・明知・予知・理知・了知・良知・霊知
広辞苑に「知」で始まるの検索結果 1-78。もっと読み込む