複数辞典一括検索+![]()
![]()
処 ところ🔗⭐🔉
【処】
 5画 几部 [六年]
区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88
【處】旧字旧字
5画 几部 [六年]
区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88
【處】旧字旧字
 11画 虍部
区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C
《常用音訓》ショ
《音読み》 ショ
11画 虍部
区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C
《常用音訓》ショ
《音読み》 ショ
 〈ch
〈ch ・ch
・ch 〉
《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ
《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす
《意味》
〉
《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ
《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす
《意味》
 {動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕
{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕
 {動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕
{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕
 ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」
ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」
 ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」
ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」
 {名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕
{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕
 {単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕
〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」
《解字》
{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕
〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」
《解字》
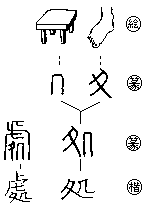 会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。
《単語家族》
居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。
《類義》
→居
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。
《単語家族》
居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。
《類義》
→居
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 5画 几部 [六年]
区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88
【處】旧字旧字
5画 几部 [六年]
区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88
【處】旧字旧字
 11画 虍部
区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C
《常用音訓》ショ
《音読み》 ショ
11画 虍部
区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C
《常用音訓》ショ
《音読み》 ショ
 〈ch
〈ch ・ch
・ch 〉
《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ
《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす
《意味》
〉
《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ
《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす
《意味》
 {動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕
{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕
 {動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕
{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕
 ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」
ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」
 ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」
ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」
 {名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕
{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕
 {単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕
〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」
《解字》
{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕
〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」
《解字》
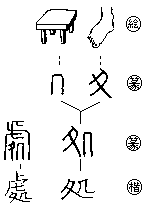 会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。
《単語家族》
居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。
《類義》
→居
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。
《単語家族》
居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。
《類義》
→居
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
所 ところ🔗⭐🔉
【所】
 8画 戸部 [三年]
区点=2974 16進=3D6A シフトJIS=8F8A
《常用音訓》ショ/ところ
《音読み》 ショ
8画 戸部 [三年]
区点=2974 16進=3D6A シフトJIS=8F8A
《常用音訓》ショ/ところ
《音読み》 ショ /ソ
/ソ 〈su
〈su 〉
《訓読み》 ところ/ところの/ばかり
《名付け》 ところ・ど・のぶ
《意味》
〉
《訓読み》 ところ/ところの/ばかり
《名付け》 ところ・ど・のぶ
《意味》
 {名}ところ。場所。また、地位。〈類義語〉→処。「住所」「居其所=ソノ所ニ居ル」〔→論語〕
{名}ところ。場所。また、地位。〈類義語〉→処。「住所」「居其所=ソノ所ニ居ル」〔→論語〕
 {助}ところ。ある動作を受けるそのもの、そのこと、その場所などをさし示す。「所在=在ル所」「叟之所知也=叟ノ知ルトコロナリ」〔→孟子〕
{助}ところ。ある動作を受けるそのもの、そのこと、その場所などをさし示す。「所在=在ル所」「叟之所知也=叟ノ知ルトコロナリ」〔→孟子〕
 {助}ところの。…するその、という修飾成分をつくる。「取舞陽所持地図=舞陽ノ持ツトコロノ地図ヲ取ル」〔→史記〕
{助}ところの。…するその、という修飾成分をつくる。「取舞陽所持地図=舞陽ノ持ツトコロノ地図ヲ取ル」〔→史記〕
 「所以…ショイ・ユエン・モッテ…スルトコロ」とは、…するわけ・理由、…する手段、の意をあらわす。▽「ゆえん」という訓読法は、「ゆえに」のなまったもの。「此心之所以合於王者、何也=コノ心ノ王ニ合フユ
「所以…ショイ・ユエン・モッテ…スルトコロ」とは、…するわけ・理由、…する手段、の意をあらわす。▽「ゆえん」という訓読法は、「ゆえに」のなまったもの。「此心之所以合於王者、何也=コノ心ノ王ニ合フユ ンハ、ナンゾヤ」〔→孟子〕
ンハ、ナンゾヤ」〔→孟子〕
 「所以ユエニ」とは、故に、の意をあらわす接続詞。「偸本非礼、所以不拝=偸ハモト礼ニアラズ、ユ
「所以ユエニ」とは、故に、の意をあらわす接続詞。「偸本非礼、所以不拝=偸ハモト礼ニアラズ、ユ ニ拝セズ」〔→世説〕
ニ拝セズ」〔→世説〕
 「為A所B」とは、「AのBする所と為る」と読んで、だれかに何かをされる、との受身の意味をあらわす。「為盗所殺=盗ノ殺ス所ト為ル」〔→謝小娥〕
「為A所B」とは、「AのBする所と為る」と読んで、だれかに何かをされる、との受身の意味をあらわす。「為盗所殺=盗ノ殺ス所ト為ル」〔→謝小娥〕
 「所謂イワユル・イウトコロノ」とは、人々にそういわれるところの、との意をあらわす。「所謂大臣者以道事君不可則止=イハユル大臣ナル者ハ、道ヲモッテ君ニ事ヘ、不可ナレバスナハチ止ム」〔→論語〕
「所謂イワユル・イウトコロノ」とは、人々にそういわれるところの、との意をあらわす。「所謂大臣者以道事君不可則止=イハユル大臣ナル者ハ、道ヲモッテ君ニ事ヘ、不可ナレバスナハチ止ム」〔→論語〕
 「所有アラユル」とは、おのずとそこに存在するかぎりのとの意をあらわす。▽訓読で「ゆ(ゆる)」をつけるのは「見ゆ」「泣かゆ」の「ゆ」と同じで、自発・受身の意味を含ませたもの。
「所有アラユル」とは、おのずとそこに存在するかぎりのとの意をあらわす。▽訓読で「ゆ(ゆる)」をつけるのは「見ゆ」「泣かゆ」の「ゆ」と同じで、自発・受身の意味を含ませたもの。
 {助}ばかり。数量をあらわすことばのあとにつけ、それくらい、の意をあらわす。〈同義語〉→許バカリ。「父去里所、復還曰=父去ルコト里バカリニシテ、マタ還リテ曰ハク」〔→史記〕
{助}ばかり。数量をあらわすことばのあとにつけ、それくらい、の意をあらわす。〈同義語〉→許バカリ。「父去里所、復還曰=父去ルコト里バカリニシテ、マタ還リテ曰ハク」〔→史記〕
 「幾所イクバク」とは、どれくらい、の意をあらわす。〈同義語〉幾許イクバク。
〔国〕ところ。…したところ、その場合に。「門を出た所が」
《解字》
形声。「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔→詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「幾所イクバク」とは、どれくらい、の意をあらわす。〈同義語〉幾許イクバク。
〔国〕ところ。…したところ、その場合に。「門を出た所が」
《解字》
形声。「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔→詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 戸部 [三年]
区点=2974 16進=3D6A シフトJIS=8F8A
《常用音訓》ショ/ところ
《音読み》 ショ
8画 戸部 [三年]
区点=2974 16進=3D6A シフトJIS=8F8A
《常用音訓》ショ/ところ
《音読み》 ショ /ソ
/ソ 〈su
〈su 〉
《訓読み》 ところ/ところの/ばかり
《名付け》 ところ・ど・のぶ
《意味》
〉
《訓読み》 ところ/ところの/ばかり
《名付け》 ところ・ど・のぶ
《意味》
 {名}ところ。場所。また、地位。〈類義語〉→処。「住所」「居其所=ソノ所ニ居ル」〔→論語〕
{名}ところ。場所。また、地位。〈類義語〉→処。「住所」「居其所=ソノ所ニ居ル」〔→論語〕
 {助}ところ。ある動作を受けるそのもの、そのこと、その場所などをさし示す。「所在=在ル所」「叟之所知也=叟ノ知ルトコロナリ」〔→孟子〕
{助}ところ。ある動作を受けるそのもの、そのこと、その場所などをさし示す。「所在=在ル所」「叟之所知也=叟ノ知ルトコロナリ」〔→孟子〕
 {助}ところの。…するその、という修飾成分をつくる。「取舞陽所持地図=舞陽ノ持ツトコロノ地図ヲ取ル」〔→史記〕
{助}ところの。…するその、という修飾成分をつくる。「取舞陽所持地図=舞陽ノ持ツトコロノ地図ヲ取ル」〔→史記〕
 「所以…ショイ・ユエン・モッテ…スルトコロ」とは、…するわけ・理由、…する手段、の意をあらわす。▽「ゆえん」という訓読法は、「ゆえに」のなまったもの。「此心之所以合於王者、何也=コノ心ノ王ニ合フユ
「所以…ショイ・ユエン・モッテ…スルトコロ」とは、…するわけ・理由、…する手段、の意をあらわす。▽「ゆえん」という訓読法は、「ゆえに」のなまったもの。「此心之所以合於王者、何也=コノ心ノ王ニ合フユ ンハ、ナンゾヤ」〔→孟子〕
ンハ、ナンゾヤ」〔→孟子〕
 「所以ユエニ」とは、故に、の意をあらわす接続詞。「偸本非礼、所以不拝=偸ハモト礼ニアラズ、ユ
「所以ユエニ」とは、故に、の意をあらわす接続詞。「偸本非礼、所以不拝=偸ハモト礼ニアラズ、ユ ニ拝セズ」〔→世説〕
ニ拝セズ」〔→世説〕
 「為A所B」とは、「AのBする所と為る」と読んで、だれかに何かをされる、との受身の意味をあらわす。「為盗所殺=盗ノ殺ス所ト為ル」〔→謝小娥〕
「為A所B」とは、「AのBする所と為る」と読んで、だれかに何かをされる、との受身の意味をあらわす。「為盗所殺=盗ノ殺ス所ト為ル」〔→謝小娥〕
 「所謂イワユル・イウトコロノ」とは、人々にそういわれるところの、との意をあらわす。「所謂大臣者以道事君不可則止=イハユル大臣ナル者ハ、道ヲモッテ君ニ事ヘ、不可ナレバスナハチ止ム」〔→論語〕
「所謂イワユル・イウトコロノ」とは、人々にそういわれるところの、との意をあらわす。「所謂大臣者以道事君不可則止=イハユル大臣ナル者ハ、道ヲモッテ君ニ事ヘ、不可ナレバスナハチ止ム」〔→論語〕
 「所有アラユル」とは、おのずとそこに存在するかぎりのとの意をあらわす。▽訓読で「ゆ(ゆる)」をつけるのは「見ゆ」「泣かゆ」の「ゆ」と同じで、自発・受身の意味を含ませたもの。
「所有アラユル」とは、おのずとそこに存在するかぎりのとの意をあらわす。▽訓読で「ゆ(ゆる)」をつけるのは「見ゆ」「泣かゆ」の「ゆ」と同じで、自発・受身の意味を含ませたもの。
 {助}ばかり。数量をあらわすことばのあとにつけ、それくらい、の意をあらわす。〈同義語〉→許バカリ。「父去里所、復還曰=父去ルコト里バカリニシテ、マタ還リテ曰ハク」〔→史記〕
{助}ばかり。数量をあらわすことばのあとにつけ、それくらい、の意をあらわす。〈同義語〉→許バカリ。「父去里所、復還曰=父去ルコト里バカリニシテ、マタ還リテ曰ハク」〔→史記〕
 「幾所イクバク」とは、どれくらい、の意をあらわす。〈同義語〉幾許イクバク。
〔国〕ところ。…したところ、その場合に。「門を出た所が」
《解字》
形声。「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔→詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「幾所イクバク」とは、どれくらい、の意をあらわす。〈同義語〉幾許イクバク。
〔国〕ところ。…したところ、その場合に。「門を出た所が」
《解字》
形声。「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔→詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
攸 ところ🔗⭐🔉
【攸】
 7画 攴部
区点=5833 16進=5A41 シフトJIS=9DBF
《音読み》 ユウ(イウ)
7画 攴部
区点=5833 16進=5A41 シフトJIS=9DBF
《音読み》 ユウ(イウ) /ユ
/ユ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 ところ
《意味》
u〉
《訓読み》 ところ
《意味》
 {助}ところ。動詞の前について、その所、そのものなどをさし示すことをあらわす古代のことば。〈類義語〉→所。「攸関=関スルトコロ」「彝倫攸叙=彝倫ノ叙スルトコロ」〔→書経〕
{助}ところ。動詞の前について、その所、そのものなどをさし示すことをあらわす古代のことば。〈類義語〉→所。「攸関=関スルトコロ」「彝倫攸叙=彝倫ノ叙スルトコロ」〔→書経〕
 {形}のびやかなさま。また、はるかなさま。▽悠ユウに当てた用法。「攸然而逝=攸然トシテ逝ケリ」〔→孟子〕
{形}のびやかなさま。また、はるかなさま。▽悠ユウに当てた用法。「攸然而逝=攸然トシテ逝ケリ」〔→孟子〕
 {形}細く長く伸びるさま。また、固定せずにゆらゆら揺れるさま。〈類義語〉→揺。「攸乎ユウコ」
《解字》
{形}細く長く伸びるさま。また、固定せずにゆらゆら揺れるさま。〈類義語〉→揺。「攸乎ユウコ」
《解字》
 会意。攸は「人+:(水のたれるさま)+攴(動詞の記号)」からなるもので、長く細く水をたらすさま。洗滌センデキの滌の原字。また、遊(たゆとう)や揺(固定せずにゆれる)などの意味にも当てて用いる。また、その音を借りて、古代の指さすことば(それ、そのもの)にも当てる。
《単語家族》
條(=条。細長い)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。攸は「人+:(水のたれるさま)+攴(動詞の記号)」からなるもので、長く細く水をたらすさま。洗滌センデキの滌の原字。また、遊(たゆとう)や揺(固定せずにゆれる)などの意味にも当てて用いる。また、その音を借りて、古代の指さすことば(それ、そのもの)にも当てる。
《単語家族》
條(=条。細長い)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 7画 攴部
区点=5833 16進=5A41 シフトJIS=9DBF
《音読み》 ユウ(イウ)
7画 攴部
区点=5833 16進=5A41 シフトJIS=9DBF
《音読み》 ユウ(イウ) /ユ
/ユ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 ところ
《意味》
u〉
《訓読み》 ところ
《意味》
 {助}ところ。動詞の前について、その所、そのものなどをさし示すことをあらわす古代のことば。〈類義語〉→所。「攸関=関スルトコロ」「彝倫攸叙=彝倫ノ叙スルトコロ」〔→書経〕
{助}ところ。動詞の前について、その所、そのものなどをさし示すことをあらわす古代のことば。〈類義語〉→所。「攸関=関スルトコロ」「彝倫攸叙=彝倫ノ叙スルトコロ」〔→書経〕
 {形}のびやかなさま。また、はるかなさま。▽悠ユウに当てた用法。「攸然而逝=攸然トシテ逝ケリ」〔→孟子〕
{形}のびやかなさま。また、はるかなさま。▽悠ユウに当てた用法。「攸然而逝=攸然トシテ逝ケリ」〔→孟子〕
 {形}細く長く伸びるさま。また、固定せずにゆらゆら揺れるさま。〈類義語〉→揺。「攸乎ユウコ」
《解字》
{形}細く長く伸びるさま。また、固定せずにゆらゆら揺れるさま。〈類義語〉→揺。「攸乎ユウコ」
《解字》
 会意。攸は「人+:(水のたれるさま)+攴(動詞の記号)」からなるもので、長く細く水をたらすさま。洗滌センデキの滌の原字。また、遊(たゆとう)や揺(固定せずにゆれる)などの意味にも当てて用いる。また、その音を借りて、古代の指さすことば(それ、そのもの)にも当てる。
《単語家族》
條(=条。細長い)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。攸は「人+:(水のたれるさま)+攴(動詞の記号)」からなるもので、長く細く水をたらすさま。洗滌センデキの滌の原字。また、遊(たゆとう)や揺(固定せずにゆれる)などの意味にも当てて用いる。また、その音を借りて、古代の指さすことば(それ、そのもの)にも当てる。
《単語家族》
條(=条。細長い)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
許 ところ🔗⭐🔉
【許】
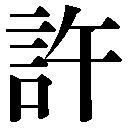 11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ
11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ /コ
/コ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
 {動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
 {動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
 {名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
 {助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
 {名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
 {助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
 「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
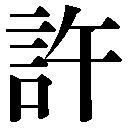 11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ
11画 言部 [五年]
区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96
《常用音訓》キョ/ゆる…す
《音読み》 キョ /コ
/コ 〈x
〈x 〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
〉
《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり
《名付け》 もと・ゆく
《意味》
 {動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕
 {動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」
 {名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」
 {助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕
 {名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。
 {助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」
 「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕
〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」
《解字》
会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午
《類義》
→釈
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
漢字源に「ところ」で完全一致するの検索結果 1-4。