複数辞典一括検索+![]()
![]()
不一 フイツ🔗⭐🔉
【不一】
フイツ  イツナラズ同じでない。ふぞろい。
イツナラズ同じでない。ふぞろい。 手紙の末尾に書くあいさつのことば。▽一つ一つ詳しくはしるさないの意。読書を途中でやめるとき、「乙」というしるしをつけたことから。『不乙フイツ・不尽フジン・不悉フシツ・不具フグ・不宣フセン・不備フビ』
手紙の末尾に書くあいさつのことば。▽一つ一つ詳しくはしるさないの意。読書を途中でやめるとき、「乙」というしるしをつけたことから。『不乙フイツ・不尽フジン・不悉フシツ・不具フグ・不宣フセン・不備フビ』
 イツナラズ同じでない。ふぞろい。
イツナラズ同じでない。ふぞろい。 手紙の末尾に書くあいさつのことば。▽一つ一つ詳しくはしるさないの意。読書を途中でやめるとき、「乙」というしるしをつけたことから。『不乙フイツ・不尽フジン・不悉フシツ・不具フグ・不宣フセン・不備フビ』
手紙の末尾に書くあいさつのことば。▽一つ一つ詳しくはしるさないの意。読書を途中でやめるとき、「乙」というしるしをつけたことから。『不乙フイツ・不尽フジン・不悉フシツ・不具フグ・不宣フセン・不備フビ』
不変 フイ🔗⭐🔉
【不易】
 フエキ 物事が永久にかわらないこと。『不変フヘン』「万古不易」
フエキ 物事が永久にかわらないこと。『不変フヘン』「万古不易」 フイ・ヤスカラズ
フイ・ヤスカラズ  容易でない。困難であること。
容易でない。困難であること。 土地の耕作がじゅうぶんになされない。▽「易」は治。
土地の耕作がじゅうぶんになされない。▽「易」は治。
 フエキ 物事が永久にかわらないこと。『不変フヘン』「万古不易」
フエキ 物事が永久にかわらないこと。『不変フヘン』「万古不易」 フイ・ヤスカラズ
フイ・ヤスカラズ  容易でない。困難であること。
容易でない。困難であること。 土地の耕作がじゅうぶんになされない。▽「易」は治。
土地の耕作がじゅうぶんになされない。▽「易」は治。
付倚 フイ🔗⭐🔉
【付倚】
フイ =附倚。たよりにしてよりすがる。
傅育 フイク🔗⭐🔉
【傅育】
フイク そばについていて身分の高い人の子を守り育てる。
吹聴 フイチョウ🔗⭐🔉
【吹聴】
フイチョウ〔国〕人々の間にいい広める。いいふらす。
呎 フィート🔗⭐🔉
【呎】
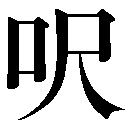 7画 口部 〔国〕
区点=5072 16進=5268 シフトJIS=99E6
《訓読み》 フィート
《意味》
フィート。長さの単位。一フィートは一二インチで、約三〇・四センチメートル。
《解字》
会意。「口+尺」。
7画 口部 〔国〕
区点=5072 16進=5268 シフトJIS=99E6
《訓読み》 フィート
《意味》
フィート。長さの単位。一フィートは一二インチで、約三〇・四センチメートル。
《解字》
会意。「口+尺」。
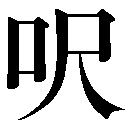 7画 口部 〔国〕
区点=5072 16進=5268 シフトJIS=99E6
《訓読み》 フィート
《意味》
フィート。長さの単位。一フィートは一二インチで、約三〇・四センチメートル。
《解字》
会意。「口+尺」。
7画 口部 〔国〕
区点=5072 16進=5268 シフトJIS=99E6
《訓読み》 フィート
《意味》
フィート。長さの単位。一フィートは一二インチで、約三〇・四センチメートル。
《解字》
会意。「口+尺」。
孚育 フイク🔗⭐🔉
【孚育】
フイク 養い育てること。『孚養フヨウ』
富溢 フウイツ🔗⭐🔉
【富溢】
フウイツ ありあまるほど金がある。『富衍フエン』
封印 フウイン🔗⭐🔉
【封印】
フウイン 封じめに印をおすこと。また、その印。
布衣 フイ🔗⭐🔉
【布衣】
 フイ
フイ  一般庶民の着る麻や綿の服。
一般庶民の着る麻や綿の服。 官位のない人。庶民のこと。「三十在布衣=三十ニシテ布衣ニ在リ」〔→白居易〕
官位のない人。庶民のこと。「三十在布衣=三十ニシテ布衣ニ在リ」〔→白居易〕 ホイ・ホウイ〔国〕
ホイ・ホウイ〔国〕 六位以下のものが着る無紋の狩衣カリギヌ。
六位以下のものが着る無紋の狩衣カリギヌ。 六位以下の官吏。
六位以下の官吏。 江戸時代、武士の第四級の礼服。
江戸時代、武士の第四級の礼服。
 フイ
フイ  一般庶民の着る麻や綿の服。
一般庶民の着る麻や綿の服。 官位のない人。庶民のこと。「三十在布衣=三十ニシテ布衣ニ在リ」〔→白居易〕
官位のない人。庶民のこと。「三十在布衣=三十ニシテ布衣ニ在リ」〔→白居易〕 ホイ・ホウイ〔国〕
ホイ・ホウイ〔国〕 六位以下のものが着る無紋の狩衣カリギヌ。
六位以下のものが着る無紋の狩衣カリギヌ。 六位以下の官吏。
六位以下の官吏。 江戸時代、武士の第四級の礼服。
江戸時代、武士の第四級の礼服。
布衣之交 フイノマジワリ🔗⭐🔉
【布衣之交】
フイノマジワリ〈故事〉庶民のつきあい。〔→史記〕
布衣之極 フイノキョク🔗⭐🔉
【布衣之極】
フイノキョク〈故事〉庶民としての最高の出世。〔→史記〕
府 ふ🔗⭐🔉
【府】
 8画 广部 [四年]
区点=4160 16進=495C シフトJIS=957B
《常用音訓》フ
《音読み》 フ
8画 广部 [四年]
区点=4160 16進=495C シフトJIS=957B
《常用音訓》フ
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 くら/みやこ/ふ
《名付け》 あつ・くら・もと
《意味》
〉
《訓読み》 くら/みやこ/ふ
《名付け》 あつ・くら・もと
《意味》
 {名}くら。宝物や文書をしまう建物。〈類義語〉→庫。「府庫」「内府(宮中の金蔵)」
{名}くら。宝物や文書をしまう建物。〈類義語〉→庫。「府庫」「内府(宮中の金蔵)」
 {名}役所。「政府」「大宰府ダザイフ」
{名}役所。「政府」「大宰府ダザイフ」
 {名}みやこ。政府のある町。また、地方政府のある町。
{名}みやこ。政府のある町。また、地方政府のある町。
 {名}唐から清シン代にかけての行政区画の一つ。州の上位に位置し、州・県を統轄する。「知府(府の長官)」「府治(府の行政庁のある町)」
{名}唐から清シン代にかけての行政区画の一つ。州の上位に位置し、州・県を統轄する。「知府(府の長官)」「府治(府の行政庁のある町)」
 {名}邸宅。やしき。「府君(他人の家長を尊んでいうことば)」「王府(親王の屋敷)」
{名}邸宅。やしき。「府君(他人の家長を尊んでいうことば)」「王府(親王の屋敷)」
 {名}集まる所。「怨府エンプ(多くの人の怨ウラみの集まる所)」
{名}集まる所。「怨府エンプ(多くの人の怨ウラみの集まる所)」
 {名}胃や腸などの消化器官のこと。▽「臓腑ゾウフ」の腑に当てた用法。「六府(=六腑)」
〔国〕ふ。地方公共団体の一つ。「大阪府」
《解字》
会意兼形声。付フは、人の背に手をぴたりとひっつけるさま。府は「广(いえ)+音符付」で物をびっしりとひっつけて入れるくら。→付
《単語家族》
富フ(物をびっしり詰めこむ→とむ)
{名}胃や腸などの消化器官のこと。▽「臓腑ゾウフ」の腑に当てた用法。「六府(=六腑)」
〔国〕ふ。地方公共団体の一つ。「大阪府」
《解字》
会意兼形声。付フは、人の背に手をぴたりとひっつけるさま。府は「广(いえ)+音符付」で物をびっしりとひっつけて入れるくら。→付
《単語家族》
富フ(物をびっしり詰めこむ→とむ) 腑フ(食べ物のはいるくらに似た内臓)
腑フ(食べ物のはいるくらに似た内臓) 腐フ(肉がくさって、ぴったりひっつく)などと同系。
《類義》
→倉
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
腐フ(肉がくさって、ぴったりひっつく)などと同系。
《類義》
→倉
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 广部 [四年]
区点=4160 16進=495C シフトJIS=957B
《常用音訓》フ
《音読み》 フ
8画 广部 [四年]
区点=4160 16進=495C シフトJIS=957B
《常用音訓》フ
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 くら/みやこ/ふ
《名付け》 あつ・くら・もと
《意味》
〉
《訓読み》 くら/みやこ/ふ
《名付け》 あつ・くら・もと
《意味》
 {名}くら。宝物や文書をしまう建物。〈類義語〉→庫。「府庫」「内府(宮中の金蔵)」
{名}くら。宝物や文書をしまう建物。〈類義語〉→庫。「府庫」「内府(宮中の金蔵)」
 {名}役所。「政府」「大宰府ダザイフ」
{名}役所。「政府」「大宰府ダザイフ」
 {名}みやこ。政府のある町。また、地方政府のある町。
{名}みやこ。政府のある町。また、地方政府のある町。
 {名}唐から清シン代にかけての行政区画の一つ。州の上位に位置し、州・県を統轄する。「知府(府の長官)」「府治(府の行政庁のある町)」
{名}唐から清シン代にかけての行政区画の一つ。州の上位に位置し、州・県を統轄する。「知府(府の長官)」「府治(府の行政庁のある町)」
 {名}邸宅。やしき。「府君(他人の家長を尊んでいうことば)」「王府(親王の屋敷)」
{名}邸宅。やしき。「府君(他人の家長を尊んでいうことば)」「王府(親王の屋敷)」
 {名}集まる所。「怨府エンプ(多くの人の怨ウラみの集まる所)」
{名}集まる所。「怨府エンプ(多くの人の怨ウラみの集まる所)」
 {名}胃や腸などの消化器官のこと。▽「臓腑ゾウフ」の腑に当てた用法。「六府(=六腑)」
〔国〕ふ。地方公共団体の一つ。「大阪府」
《解字》
会意兼形声。付フは、人の背に手をぴたりとひっつけるさま。府は「广(いえ)+音符付」で物をびっしりとひっつけて入れるくら。→付
《単語家族》
富フ(物をびっしり詰めこむ→とむ)
{名}胃や腸などの消化器官のこと。▽「臓腑ゾウフ」の腑に当てた用法。「六府(=六腑)」
〔国〕ふ。地方公共団体の一つ。「大阪府」
《解字》
会意兼形声。付フは、人の背に手をぴたりとひっつけるさま。府は「广(いえ)+音符付」で物をびっしりとひっつけて入れるくら。→付
《単語家族》
富フ(物をびっしり詰めこむ→とむ) 腑フ(食べ物のはいるくらに似た内臓)
腑フ(食べ物のはいるくらに似た内臓) 腐フ(肉がくさって、ぴったりひっつく)などと同系。
《類義》
→倉
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
腐フ(肉がくさって、ぴったりひっつく)などと同系。
《類義》
→倉
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
府尹 フイン🔗⭐🔉
【府尹】
フイン 官名。府の長官。▽漢代の京兆尹ケイチョウノインに始まり、唐代には西都・東都・北都などの都市に置いた。明ミン・清シン代は特に重要な都会(応天府・順天府)の長官をいった。
怖畏 フイ🔗⭐🔉
【怖懼】
フク びくびく恐れる。『怖慴フショウ・怖畏フイ』
拊愛 フアイ🔗⭐🔉
【拊愛】
フアイ なでるようにかわいがる。〈類義語〉撫愛ブアイ。
歩 ふ🔗⭐🔉
【歩】
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
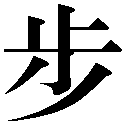 8画 止部 [二年]
区点=4266 16進=4A62 シフトJIS=95E0
《常用音訓》フ/ブ/ホ/あゆ…む/ある…く
《音読み》 ホ
8画 止部 [二年]
区点=4266 16進=4A62 シフトJIS=95E0
《常用音訓》フ/ブ/ホ/あゆ…む/ある…く
《音読み》 ホ /ブ
/ブ /フ
/フ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 あるく/あゆむ/あゆみ/はかる/ぶ/ふ
《名付け》 あゆみ・あゆむ・すすむ
《意味》
〉
《訓読み》 あるく/あゆむ/あゆみ/はかる/ぶ/ふ
《名付け》 あゆみ・あゆむ・すすむ
《意味》
 {動}あるく。あゆむ。右足と左足をふみ出してあるく。徒歩で行く。〈類義語〉→走・→進。「進歩」「歩行」
{動}あるく。あゆむ。右足と左足をふみ出してあるく。徒歩で行く。〈類義語〉→走・→進。「進歩」「歩行」
 {名}あゆみ。進み方。また、運命やおかれた境遇。「学歩=歩ヲ学ブ」「地歩(達した地位)」「天歩(天体の運行のしかた)」
{名}あゆみ。進み方。また、運命やおかれた境遇。「学歩=歩ヲ学ブ」「地歩(達した地位)」「天歩(天体の運行のしかた)」
 {動}はかる。天体のあゆみをはかる。「推歩」
{動}はかる。天体のあゆみをはかる。「推歩」
 {単位}長さの単位。一歩とは左足と右足をふみ出した長さのことで、手尺で計って六尺。昔の一歩は今の一三五センチにあたる。昔の一里の三百分の一。唐代以降は三百六十分の一。▽半歩(左足だけ、または右足だけをふみだした長さ)を[キ]といい、三尺。また、足をふたあしふみ出した長さ(手尺の六尺)を一歩といい、それが長さや面積の単位となった。
{単位}長さの単位。一歩とは左足と右足をふみ出した長さのことで、手尺で計って六尺。昔の一歩は今の一三五センチにあたる。昔の一里の三百分の一。唐代以降は三百六十分の一。▽半歩(左足だけ、または右足だけをふみだした長さ)を[キ]といい、三尺。また、足をふたあしふみ出した長さ(手尺の六尺)を一歩といい、それが長さや面積の単位となった。
 {単位}面積の単位。一歩は昔の一畝の十分の一。唐代以降には二百四十分の一。
{単位}面積の単位。一歩は昔の一畝の十分の一。唐代以降には二百四十分の一。
 {名}水ぎわのこと。〈同義語〉→浦ホ。
〔国〕
{名}水ぎわのこと。〈同義語〉→浦ホ。
〔国〕 ぶ。もうけの割合。また、物事の優劣・勝敗などの形勢。「歩が悪い」「歩止まり」
ぶ。もうけの割合。また、物事の優劣・勝敗などの形勢。「歩が悪い」「歩止まり」 ぶ。分配の比率や利率をあらわすときのことば。一歩は一割の十分の一。「日歩ヒブ」
ぶ。分配の比率や利率をあらわすときのことば。一歩は一割の十分の一。「日歩ヒブ」 ぶ。土地の面積の単位。一歩は六尺平方(約三・三平方メートル)。坪。
ぶ。土地の面積の単位。一歩は六尺平方(約三・三平方メートル)。坪。 ふ。将棋の駒コマの一つ。「歩兵フヒョウ」
《解字》
ふ。将棋の駒コマの一つ。「歩兵フヒョウ」
《解字》
 会意。「右の足+左の足」で、左と右の足をふみ出すことを示す。足の面を地面に近づけてぱたぱたあるくこと。
《単語家族》
拍(ぱたと手の面でうつ)
会意。「右の足+左の足」で、左と右の足をふみ出すことを示す。足の面を地面に近づけてぱたぱたあるくこと。
《単語家族》
拍(ぱたと手の面でうつ) 迫(面と面を近づける)
迫(面と面を近づける) 搏ハク(ぱたぱたとうつ)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
搏ハク(ぱたぱたとうつ)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 人名に使える旧字
人名に使える旧字
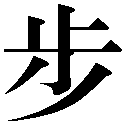 8画 止部 [二年]
区点=4266 16進=4A62 シフトJIS=95E0
《常用音訓》フ/ブ/ホ/あゆ…む/ある…く
《音読み》 ホ
8画 止部 [二年]
区点=4266 16進=4A62 シフトJIS=95E0
《常用音訓》フ/ブ/ホ/あゆ…む/ある…く
《音読み》 ホ /ブ
/ブ /フ
/フ 〈b
〈b 〉
《訓読み》 あるく/あゆむ/あゆみ/はかる/ぶ/ふ
《名付け》 あゆみ・あゆむ・すすむ
《意味》
〉
《訓読み》 あるく/あゆむ/あゆみ/はかる/ぶ/ふ
《名付け》 あゆみ・あゆむ・すすむ
《意味》
 {動}あるく。あゆむ。右足と左足をふみ出してあるく。徒歩で行く。〈類義語〉→走・→進。「進歩」「歩行」
{動}あるく。あゆむ。右足と左足をふみ出してあるく。徒歩で行く。〈類義語〉→走・→進。「進歩」「歩行」
 {名}あゆみ。進み方。また、運命やおかれた境遇。「学歩=歩ヲ学ブ」「地歩(達した地位)」「天歩(天体の運行のしかた)」
{名}あゆみ。進み方。また、運命やおかれた境遇。「学歩=歩ヲ学ブ」「地歩(達した地位)」「天歩(天体の運行のしかた)」
 {動}はかる。天体のあゆみをはかる。「推歩」
{動}はかる。天体のあゆみをはかる。「推歩」
 {単位}長さの単位。一歩とは左足と右足をふみ出した長さのことで、手尺で計って六尺。昔の一歩は今の一三五センチにあたる。昔の一里の三百分の一。唐代以降は三百六十分の一。▽半歩(左足だけ、または右足だけをふみだした長さ)を[キ]といい、三尺。また、足をふたあしふみ出した長さ(手尺の六尺)を一歩といい、それが長さや面積の単位となった。
{単位}長さの単位。一歩とは左足と右足をふみ出した長さのことで、手尺で計って六尺。昔の一歩は今の一三五センチにあたる。昔の一里の三百分の一。唐代以降は三百六十分の一。▽半歩(左足だけ、または右足だけをふみだした長さ)を[キ]といい、三尺。また、足をふたあしふみ出した長さ(手尺の六尺)を一歩といい、それが長さや面積の単位となった。
 {単位}面積の単位。一歩は昔の一畝の十分の一。唐代以降には二百四十分の一。
{単位}面積の単位。一歩は昔の一畝の十分の一。唐代以降には二百四十分の一。
 {名}水ぎわのこと。〈同義語〉→浦ホ。
〔国〕
{名}水ぎわのこと。〈同義語〉→浦ホ。
〔国〕 ぶ。もうけの割合。また、物事の優劣・勝敗などの形勢。「歩が悪い」「歩止まり」
ぶ。もうけの割合。また、物事の優劣・勝敗などの形勢。「歩が悪い」「歩止まり」 ぶ。分配の比率や利率をあらわすときのことば。一歩は一割の十分の一。「日歩ヒブ」
ぶ。分配の比率や利率をあらわすときのことば。一歩は一割の十分の一。「日歩ヒブ」 ぶ。土地の面積の単位。一歩は六尺平方(約三・三平方メートル)。坪。
ぶ。土地の面積の単位。一歩は六尺平方(約三・三平方メートル)。坪。 ふ。将棋の駒コマの一つ。「歩兵フヒョウ」
《解字》
ふ。将棋の駒コマの一つ。「歩兵フヒョウ」
《解字》
 会意。「右の足+左の足」で、左と右の足をふみ出すことを示す。足の面を地面に近づけてぱたぱたあるくこと。
《単語家族》
拍(ぱたと手の面でうつ)
会意。「右の足+左の足」で、左と右の足をふみ出すことを示す。足の面を地面に近づけてぱたぱたあるくこと。
《単語家族》
拍(ぱたと手の面でうつ) 迫(面と面を近づける)
迫(面と面を近づける) 搏ハク(ぱたぱたとうつ)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
搏ハク(ぱたぱたとうつ)などと同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
覆甕 フウオウ🔗⭐🔉
【覆甕】
フウオウ 著述などが世間に広まらず、その書物でかめのふたをする。重んずるほどの価値のない著述のこと。また、自分の著述の謙称。▽「漢書」揚雄伝・賛から。『覆醤フウショウ』
覆蓋 フウガイ🔗⭐🔉
【覆蓋】
フウガイ おおいかぶさる。また、おおいかぶせる。「枝枝相覆蓋=枝枝アヒ覆蓋ス」〔古楽府〕
訃音 フイン🔗⭐🔉
【訃告】
フコク 死んだというしらせ。『訃音フイン・訃報フホウ・訃信フシン・訃聞フブン』
諷詠 フウエイ🔗⭐🔉
【諷詠】
フウエイ 詩歌を節をつけてうたう。
諷意 フウイ🔗⭐🔉
【諷意】
フウイ  思っていることをそれとなく遠まわしにいう。
思っていることをそれとなく遠まわしにいう。 それとなくほのめかしていった意味。
それとなくほのめかしていった意味。
 思っていることをそれとなく遠まわしにいう。
思っていることをそれとなく遠まわしにいう。 それとなくほのめかしていった意味。
それとなくほのめかしていった意味。
鞴 ふいごう🔗⭐🔉
【鞴】
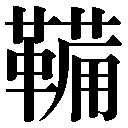 19画 革部
区点=8070 16進=7066 シフトJIS=E8E4
《音読み》 ビ
19画 革部
区点=8070 16進=7066 シフトJIS=E8E4
《音読み》 ビ /ヒ
/ヒ /フク
/フク /ブク
/ブク /ホ
/ホ /ブ
/ブ 〈b
〈b i〉
《訓読み》 ふいごう(ふいがう)
《意味》
i〉
《訓読み》 ふいごう(ふいがう)
《意味》
 {名}飾りとして張りつけるかわ。車につけたかわの飾り。
{名}飾りとして張りつけるかわ。車につけたかわの飾り。
 {名}かわぶくろ。うつぼ。「鞴靫ホサイ(かわ製の矢入れ)」
{名}かわぶくろ。うつぼ。「鞴靫ホサイ(かわ製の矢入れ)」
 {名}ふいごう(フイガウ)。ふいご。風を送りだして火をおこすかわ製のふくろ。▽訓の「ふいがう」は「吹き皮」の転じたもの。
《解字》
会意兼形声。右側の字は、ぴったりとそえる意を含む。鞴はそれを音符とし、革(かわ)を加えたもの。
《単語家族》
服(ぴったりとくっつく)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
{名}ふいごう(フイガウ)。ふいご。風を送りだして火をおこすかわ製のふくろ。▽訓の「ふいがう」は「吹き皮」の転じたもの。
《解字》
会意兼形声。右側の字は、ぴったりとそえる意を含む。鞴はそれを音符とし、革(かわ)を加えたもの。
《単語家族》
服(ぴったりとくっつく)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
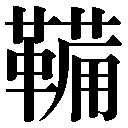 19画 革部
区点=8070 16進=7066 シフトJIS=E8E4
《音読み》 ビ
19画 革部
区点=8070 16進=7066 シフトJIS=E8E4
《音読み》 ビ /ヒ
/ヒ /フク
/フク /ブク
/ブク /ホ
/ホ /ブ
/ブ 〈b
〈b i〉
《訓読み》 ふいごう(ふいがう)
《意味》
i〉
《訓読み》 ふいごう(ふいがう)
《意味》
 {名}飾りとして張りつけるかわ。車につけたかわの飾り。
{名}飾りとして張りつけるかわ。車につけたかわの飾り。
 {名}かわぶくろ。うつぼ。「鞴靫ホサイ(かわ製の矢入れ)」
{名}かわぶくろ。うつぼ。「鞴靫ホサイ(かわ製の矢入れ)」
 {名}ふいごう(フイガウ)。ふいご。風を送りだして火をおこすかわ製のふくろ。▽訓の「ふいがう」は「吹き皮」の転じたもの。
《解字》
会意兼形声。右側の字は、ぴったりとそえる意を含む。鞴はそれを音符とし、革(かわ)を加えたもの。
《単語家族》
服(ぴったりとくっつく)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
{名}ふいごう(フイガウ)。ふいご。風を送りだして火をおこすかわ製のふくろ。▽訓の「ふいがう」は「吹き皮」の転じたもの。
《解字》
会意兼形声。右側の字は、ぴったりとそえる意を含む。鞴はそれを音符とし、革(かわ)を加えたもの。
《単語家族》
服(ぴったりとくっつく)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
風花 フウカ🔗⭐🔉
【風花】
フウカ  風に吹かれて散る花。
風に吹かれて散る花。 風の吹く前にみなぎりわたる霧。
風の吹く前にみなぎりわたる霧。 まだら雲。
まだら雲。
 風に吹かれて散る花。
風に吹かれて散る花。 風の吹く前にみなぎりわたる霧。
風の吹く前にみなぎりわたる霧。 まだら雲。
まだら雲。
風音 フウイン🔗⭐🔉
【風信】
フウシン  風が季節の変化につれて吹くこと。
風が季節の変化につれて吹くこと。 人のたより。手紙。おとずれ。『風音フウイン』〈類義語〉音信。
人のたより。手紙。おとずれ。『風音フウイン』〈類義語〉音信。
 風が季節の変化につれて吹くこと。
風が季節の変化につれて吹くこと。 人のたより。手紙。おとずれ。『風音フウイン』〈類義語〉音信。
人のたより。手紙。おとずれ。『風音フウイン』〈類義語〉音信。
風華 フウカ🔗⭐🔉
【風華】
フウカ  すぐれた人がらと才能。
すぐれた人がらと才能。 外見・姿の美しさ。
外見・姿の美しさ。
 すぐれた人がらと才能。
すぐれた人がらと才能。 外見・姿の美しさ。
外見・姿の美しさ。
風雲 フウウン🔗⭐🔉
【風雲】
 フウウン
フウウン  風と雲。「墨花五色風雲浮=墨花五色ニシテ風雲浮カブ」〔→呉偉業〕
風と雲。「墨花五色風雲浮=墨花五色ニシテ風雲浮カブ」〔→呉偉業〕 竜が風や雲に乗って天にのぼるといわれるところから、すぐれた人物が活躍することのできる機運のたとえ。また、世の中が大きく変動しようとする形勢のたとえ。「風雲急」
竜が風や雲に乗って天にのぼるといわれるところから、すぐれた人物が活躍することのできる機運のたとえ。また、世の中が大きく変動しようとする形勢のたとえ。「風雲急」 人の才気や行動のすぐれているたとえ。
人の才気や行動のすぐれているたとえ。 地勢が高いことのたとえ。
地勢が高いことのたとえ。 カザグモ〔国〕強風の吹く前ぶれの雲。
カザグモ〔国〕強風の吹く前ぶれの雲。
 フウウン
フウウン  風と雲。「墨花五色風雲浮=墨花五色ニシテ風雲浮カブ」〔→呉偉業〕
風と雲。「墨花五色風雲浮=墨花五色ニシテ風雲浮カブ」〔→呉偉業〕 竜が風や雲に乗って天にのぼるといわれるところから、すぐれた人物が活躍することのできる機運のたとえ。また、世の中が大きく変動しようとする形勢のたとえ。「風雲急」
竜が風や雲に乗って天にのぼるといわれるところから、すぐれた人物が活躍することのできる機運のたとえ。また、世の中が大きく変動しようとする形勢のたとえ。「風雲急」 人の才気や行動のすぐれているたとえ。
人の才気や行動のすぐれているたとえ。 地勢が高いことのたとえ。
地勢が高いことのたとえ。 カザグモ〔国〕強風の吹く前ぶれの雲。
カザグモ〔国〕強風の吹く前ぶれの雲。
風雲児 フウウンジ🔗⭐🔉
【風雲児】
フウウンジ 世の中の急変にさいして、活躍する英雄的人物。
風煙 フウエン🔗⭐🔉
【風煙】
フウエン  風と煙。風ともや。
風と煙。風ともや。 風に流れているかすみ。
風に流れているかすみ。 戦乱のたとえ。『風烟フウエン』
戦乱のたとえ。『風烟フウエン』
 風と煙。風ともや。
風と煙。風ともや。 風に流れているかすみ。
風に流れているかすみ。 戦乱のたとえ。『風烟フウエン』
戦乱のたとえ。『風烟フウエン』
風雅 フウガ🔗⭐🔉
風概 フウガイ🔗⭐🔉
【風概】
フウガイ  けだかい人品。
けだかい人品。 みさお。節操。
みさお。節操。 おもむき。ようす。
おもむき。ようす。
 けだかい人品。
けだかい人品。 みさお。節操。
みさお。節操。 おもむき。ようす。
おもむき。ようす。
風鳶 フウエン🔗⭐🔉
【風鳶】
フウエン 空にあげるたこ。〈類義語〉紙鳶シエン。『風箏フウソウ』
風懐 フウカイ🔗⭐🔉
【風懐】
フウカイ  風流を愛する気持ち。風流な思い。
風流を愛する気持ち。風流な思い。 ゆかしい心。
ゆかしい心。
 風流を愛する気持ち。風流な思い。
風流を愛する気持ち。風流な思い。 ゆかしい心。
ゆかしい心。
風韻 フウイン🔗⭐🔉
【風韻】
フウイン  風の音。『風声フウセイ・風籟フウライ』
風の音。『風声フウセイ・風籟フウライ』 みやびやかな趣や、けだかい人がら。
みやびやかな趣や、けだかい人がら。 ゆかしい詩や文章。
ゆかしい詩や文章。
 風の音。『風声フウセイ・風籟フウライ』
風の音。『風声フウセイ・風籟フウライ』 みやびやかな趣や、けだかい人がら。
みやびやかな趣や、けだかい人がら。 ゆかしい詩や文章。
ゆかしい詩や文章。
風偃 フウエン🔗⭐🔉
【風靡】
フウビ  風が雲や草木などを吹きなびかせる。
風が雲や草木などを吹きなびかせる。 いっせいになびき従う。服従する。『風偃フウエン』
いっせいになびき従う。服従する。『風偃フウエン』 広く流行する。
広く流行する。
 風が雲や草木などを吹きなびかせる。
風が雲や草木などを吹きなびかせる。 いっせいになびき従う。服従する。『風偃フウエン』
いっせいになびき従う。服従する。『風偃フウエン』 広く流行する。
広く流行する。
馮異 フウイ🔗⭐🔉
【馮異】
フウイ〈人名〉後漢の武将。父城(河南省平頂山市)の人。字アザナは公孫。はじめ王莽オウモウに従って漢にそむいたが、のちに光武帝に属した。自分の戦功を誇らず、諸将が各自の武功を論じあうときには、常にその席を離れて、大樹の下にすわっていたという。そのため大樹将軍と呼ばれた。
馮延巳 フウエンシ🔗⭐🔉
【馮延巳】
フウエンシ〈人名〉903〜60 五代十国の南唐の文人。広陵(江蘇コウソ省江都県)の人。字アザナは正中。政治家であり、詞の作者としても有名。著に『陽春集』がある。
馮媛 フウエン🔗⭐🔉
【馮媛】
フウエン・フウショウヨ〈人名〉ショウヨは官名。前漢代、元帝の后。元帝のとき、後宮に入る。熊クマが檻オリを破って元帝に迫ったとき、身を挺テイして帝を守り、帝の寵愛チョウアイを受けた。子の興が中山王に封ぜられてから、中山太后と呼ばれた。のち、傅フ太后の計略にかかって自殺した。
麩 ふ🔗⭐🔉
【麩】
 15画 麥部
区点=8347 16進=734F シフトJIS=EA6E
【麸】異体字異体字
15画 麥部
区点=8347 16進=734F シフトJIS=EA6E
【麸】異体字異体字
 11画 麥部
区点=8348 16進=7350 シフトJIS=EA6F
《音読み》 フ
11画 麥部
区点=8348 16進=7350 シフトJIS=EA6F
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 ふすま/ふ
《意味》
{名}ふすま。小麦から麦粉をとったかす。むぎかす。
〔国〕ふ。小麦粉の麩質でつくった食品。
《解字》
形声。「麥+音符夫」で、平らに散りしく穀皮の意か。
《単語家族》
敷フ(平らにのばしひく)と同系。
〉
《訓読み》 ふすま/ふ
《意味》
{名}ふすま。小麦から麦粉をとったかす。むぎかす。
〔国〕ふ。小麦粉の麩質でつくった食品。
《解字》
形声。「麥+音符夫」で、平らに散りしく穀皮の意か。
《単語家族》
敷フ(平らにのばしひく)と同系。
 15画 麥部
区点=8347 16進=734F シフトJIS=EA6E
【麸】異体字異体字
15画 麥部
区点=8347 16進=734F シフトJIS=EA6E
【麸】異体字異体字
 11画 麥部
区点=8348 16進=7350 シフトJIS=EA6F
《音読み》 フ
11画 麥部
区点=8348 16進=7350 シフトJIS=EA6F
《音読み》 フ
 〈f
〈f 〉
《訓読み》 ふすま/ふ
《意味》
{名}ふすま。小麦から麦粉をとったかす。むぎかす。
〔国〕ふ。小麦粉の麩質でつくった食品。
《解字》
形声。「麥+音符夫」で、平らに散りしく穀皮の意か。
《単語家族》
敷フ(平らにのばしひく)と同系。
〉
《訓読み》 ふすま/ふ
《意味》
{名}ふすま。小麦から麦粉をとったかす。むぎかす。
〔国〕ふ。小麦粉の麩質でつくった食品。
《解字》
形声。「麥+音符夫」で、平らに散りしく穀皮の意か。
《単語家族》
敷フ(平らにのばしひく)と同系。
黼帷 フイ🔗⭐🔉
【黼帳】
フチョウ・ホチョウ 斧オノの形をぬいとりしたとばり。『黼帷フイ・ホイ』
漢字源に「ふ」で始まるの検索結果 1-46。もっと読み込む