複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (26)
とう‐せん【刀山】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【刀山】タウ‥
地獄の四面にあるという、剣を植えた山。つるぎの山。
とう‐せん【刀尖】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【刀尖】タウ‥
かたなのきっさき。
とう‐せん【刀銭】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【冬扇】🔗⭐🔉
とう‐せん【冬扇】
冬扇夏炉の略。
⇒とうせん‐かろ【冬扇夏炉】
とう‐せん【灯船】🔗⭐🔉
とう‐せん【灯船】
航路標識用の船。灯台の構築困難な箇所などに碇置ていちして、船上に高く灯火を掲げて航路を示すもの。灯台船。灯明船。浮うき灯台。
とう‐せん【当千】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【当千】タウ‥
(古くはトウゼンとも)一人で千人に匹敵すること。また、それほどに勇気・武力があること。日葡辞書「イチニンタウゼンノモノナリ」。「一騎―」
とう‐せん【当選】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【当選】タウ‥
①選にあたること。選抜されること。「懸賞に―する」
②議員候補者の選出が確定すること。「―人」↔落選。
⇒とうせん‐しょうしょ【当選証書】
⇒とうせん‐そしょう【当選訴訟】
とう‐せん【当籤】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【当籤】タウ‥
くじに当たること。
とう‐せん【投扇】🔗⭐🔉
とう‐せん【投扇】
(→)投扇興に同じ。
⇒とうせん‐きょう【投扇興】
とう‐せん【投銭】🔗⭐🔉
とう‐せん【投銭】
①ぜにを投げ入れること。
②ぜにを与えること。
⇒とうせん‐ぎ【投銭戯】
とう‐せん【東遷】🔗⭐🔉
とう‐せん【東遷】
東方にうつること。
とう‐せん【唐扇】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【唐扇】タウ‥
中国製のおうぎ。とううちわ。
とう‐せん【唐船】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【唐船】タウ‥
中国の船。中国風の船。からふね。平家物語11「平家の舟は千余艘、―少々あひまじれり」
とうせん【唐船】タウ‥(作品名)🔗⭐🔉
とうせん【唐船】タウ‥
能。唐船の乗員祖慶官人は日本に抑留されたが、唐土から二人の子が迎えに来る。日本でもうけた子は同行を許されないので官人は投身しようとするが、後に許されて船出する。
とう‐せん【盗泉】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【盗泉】タウ‥
中国山東省泗水県にある泉。孔子はその名が悪いのでその水を飲まなかったという。転じて、不義の意に用いる。「渇すれども―の水を飲まず」→渇する(成句)
とう‐せん【陶潜】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せん【陶潜】タウ‥
⇒とうえんめい(陶淵明)
とう‐せん【登仙】🔗⭐🔉
とう‐せん【登仙】
①仙人となって天にのぼること。「羽化―」
②貴人の死去の尊敬語。上僊。
とう‐せん【登船】🔗⭐🔉
とう‐せん【登船】
船に乗ること。
とう‐せん【闘戦】🔗⭐🔉
とう‐せん【闘戦】
たたかうこと。いくさをすること。
とうせん‐かろ【冬扇夏炉】🔗⭐🔉
とうせん‐かろ【冬扇夏炉】
(→)「かろとうせん」に同じ。
⇒とう‐せん【冬扇】
とうせん‐ぎ【投銭戯】🔗⭐🔉
とうせん‐ぎ【投銭戯】
(→)穴一あないちに同じ。
⇒とう‐せん【投銭】
とうせん‐きょう【投扇興】🔗⭐🔉
とうせん‐きょう【投扇興】
江戸時代の遊戯の一つ。台の上に蝶と呼ぶいちょう形の的を立て、1メートルほど離れた所にすわり、開いた扇を投げてこれを落とし、扇と的の落ちた形を源氏五十四帖になぞらえた図式に照らして採点し、優劣を競う。1773年(安永2)頃から盛行。明治期に衰退したが、近年復興。扇落おうぎおとし。なげおうぎ。〈[季]新年〉
投扇興
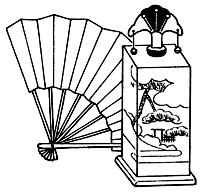 ⇒とう‐せん【投扇】
⇒とう‐せん【投扇】
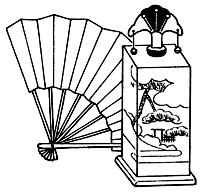 ⇒とう‐せん【投扇】
⇒とう‐せん【投扇】
とうせん‐しょうしょ【当選証書】タウ‥🔗⭐🔉
とうせん‐しょうしょ【当選証書】タウ‥
当選したことを証明するため、選挙管理委員会が当選人に交付する証書。
⇒とう‐せん【当選】
とうせん‐そしょう【当選訴訟】タウ‥🔗⭐🔉
とうせん‐そしょう【当選訴訟】タウ‥
当選人の決定を違法として当選の効力を争う訴訟。→選挙訴訟
⇒とう‐せん【当選】
とう‐せんだん【唐栴檀】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐せんだん【唐栴檀】タウ‥
〔植〕イイギリの異称。
とうせんぷろん【東潜夫論】🔗⭐🔉
とうせんぷろん【東潜夫論】
経済論書。帆足ほあし万里著。3編。1844年(弘化1)頃成る。「潜夫論」に触発され、弊政を批判し、文教と国防の充実を主張。
大辞林の検索結果 (28)
とう-せん【刀山】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― [0] 【刀山】
〔仏〕 地獄にあるという剣を植えた山。つるぎの山。
とう-せん【刀尖】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― [0] 【刀尖】
刀のきっさき。
とう-せん【刀銭】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― [0] 【刀銭】
中国古代の青銅貨幣の一種。刀子(トウス)にかたどり,戦国時代を中心に燕・斉など主に河北・山東で使われた。刀貨。刀幣。刀。
とう-せん【灯船】🔗⭐🔉
とう-せん [0] 【灯船】
船上高く灯火を掲げ,灯台の役目を果たす船。灯台の設置が困難な浅州などに定置する。灯台船。灯明船。浮き灯台。
とう-せん【当千】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― 【当千】
〔「とうぜん」とも〕
千に相当すること。一人で千人に匹敵するほど強いこと。一騎当千。「―と頼みをかけし小早川/浄瑠璃・吉野忠信」
とうせん-かくじつ【当選確実】🔗⭐🔉
とうせん-かくじつ タウ― [0] 【当選確実】
選挙前の予想または開票の途中で当選が確実視されること。当確。
とうせん-しょうしょ【当選証書】🔗⭐🔉
とうせん-しょうしょ タウ― [5] 【当選証書】
選挙管理委員会が当選人に交付する証書。
とうせん-そしょう【当選訴訟】🔗⭐🔉
とうせん-そしょう タウ― [5] 【当選訴訟】
当選の効力に関する訴訟。高等裁判所の専属管轄。
→選挙訴訟
とう-せん【当籤】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― [0] 【当籤】 (名)スル
くじに当たること。
とう-せん【投扇】🔗⭐🔉
とう-せん [0] 【投扇】
「投扇興(トウセンキヨウ)」の略。
とうせん-きょう【投扇興】🔗⭐🔉
とうせん-きょう [3][0] 【投扇興】
1メートルほど離れた距離に座り,開いた扇の要(カナメ)を親指が上になるようにつまんで投げ,台の上にある蝶と呼ばれる的を落とす室内遊戯。的の落ち方,扇の開き具合で点数を争う。江戸後期頃から流行。扇落とし。なげおうぎ。投扇。[季]新年。
投扇興
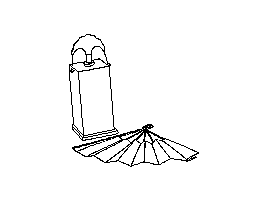 [図]
[図]
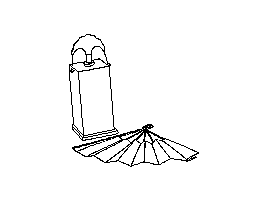 [図]
[図]
とう-せん【東遷】🔗⭐🔉
とう-せん [0] 【東遷】 (名)スル
東の方へ移ること。
とう-せん【唐扇】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― [0] 【唐扇】
中国製のおうぎ。
とう-せん【唐船】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― [0] 【唐船】
(1)中国の船。中国式の船。からふね。
(2)鎌倉時代から室町時代に対中国貿易に従事した日本船を,その船型に関係なく呼んだもの。
とうせん【唐船】🔗⭐🔉
とうせん タウセン 【唐船】
能の一。四番目物。作者未詳。祖慶官人という中国人が船軍(フナイクサ)に負けて箱崎の領主に捕らえられていたが,中国から二人の子供が迎えにくる。日本でもうけた二人の子供の同行が許されないため,投身しようとするが,人情にほだされた領主が日本の子も連れていくことを許したので喜び船出する。
とう-せん【唐銭】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― [0] 【唐銭】
中国から渡来した銭貨の総称。江戸初期まで通貨として広く流通した。
とう-せん【盗泉】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― [0] 【盗泉】
中国山東省泗水(シスイ)県の東北にある泉。孔子はその泉の名が悪いとして飲まなかったという。
→渇(カツ)しても盗泉の水を飲まず
とう-せん【登山】🔗⭐🔉
とう-せん [0] 【登山】
〔「せん」は呉音〕
(1)修行のために,僧・修験者などが山に入ること。
(2)山上の寺社に参詣すること。「先横川へ御―有しかども/太平記 2」
とう-せん【登船】🔗⭐🔉
とう-せん [0] 【登船】 (名)スル
船に乗ること。乗船。とせん。
とう-せん【闘戦】🔗⭐🔉
とう-せん [0] 【闘戦】 (名)スル
たたかうこと。「勇気を奮ひ,これと―せざるべからず/西国立志編(正直)」
とう-せん【陶潜】🔗⭐🔉
とう-せん タウ― 【陶潜】
⇒陶淵明(トウエンメイ)
とうせん-かろ【冬扇夏炉】🔗⭐🔉
とうせん-かろ [5] 【冬扇夏炉】
⇒夏炉冬扇(カロトウセン)
とう-せんせき【透閃石】🔗⭐🔉
とう-せんせき [3] 【透閃石】
角閃石類の一。単斜晶系に属し,淡灰色のガラス状光沢がある。透角閃石。
とう-せんだん【唐楝】🔗⭐🔉
とう-せんだん タウ― [3] 【唐楝】
センダン科センダンの一変種。果実は大きく六〜八本の縦の溝(ミゾ)がある。樹皮を条虫駆除などの薬用とする。
とうせんぷろん【東潜夫論】🔗⭐🔉
とうせんぷろん 【東潜夫論】
経世書。三巻。帆足万里(ホアシバンリ)著。1844年頃成立。王室・覇府・諸侯の三編よりなり,幕藩体制に関する諸改革案を述べる。
広辞苑+大辞林に「とうせん」で始まるの検索結果。