複数辞典一括検索+![]()
![]()
は【歯】🔗⭐🔉
は【歯】
①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」
歯(臼歯)
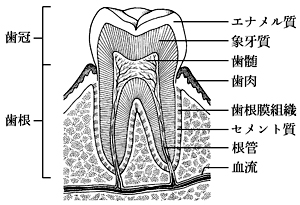 歯冠
歯根
エナメル質
象牙質
歯髄
歯肉
セメント質
根管
②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」
⇒歯が浮く
⇒歯が立たない
⇒歯に合う
⇒歯に衣着せぬ
⇒歯の抜けたよう
⇒歯の根が合わぬ
⇒歯の根も食い合う
⇒歯の根を鳴らす
⇒歯亡び舌存す
⇒歯を噛む
⇒歯を食いしばる
⇒歯を切す
⇒歯を出す
歯冠
歯根
エナメル質
象牙質
歯髄
歯肉
セメント質
根管
②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」
⇒歯が浮く
⇒歯が立たない
⇒歯に合う
⇒歯に衣着せぬ
⇒歯の抜けたよう
⇒歯の根が合わぬ
⇒歯の根も食い合う
⇒歯の根を鳴らす
⇒歯亡び舌存す
⇒歯を噛む
⇒歯を食いしばる
⇒歯を切す
⇒歯を出す
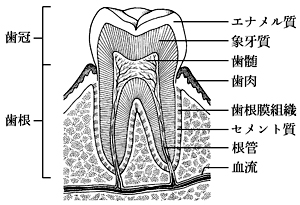 歯冠
歯根
エナメル質
象牙質
歯髄
歯肉
セメント質
根管
②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」
⇒歯が浮く
⇒歯が立たない
⇒歯に合う
⇒歯に衣着せぬ
⇒歯の抜けたよう
⇒歯の根が合わぬ
⇒歯の根も食い合う
⇒歯の根を鳴らす
⇒歯亡び舌存す
⇒歯を噛む
⇒歯を食いしばる
⇒歯を切す
⇒歯を出す
歯冠
歯根
エナメル質
象牙質
歯髄
歯肉
セメント質
根管
②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」
⇒歯が浮く
⇒歯が立たない
⇒歯に合う
⇒歯に衣着せぬ
⇒歯の抜けたよう
⇒歯の根が合わぬ
⇒歯の根も食い合う
⇒歯の根を鳴らす
⇒歯亡び舌存す
⇒歯を噛む
⇒歯を食いしばる
⇒歯を切す
⇒歯を出す
よわい【齢・歯】ヨハヒ🔗⭐🔉
よわい【齢・歯】ヨハヒ
①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」
②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」
⇒よわい‐ぐさ【齢草】
⇒よわい‐びと【齢人】
[漢]歯🔗⭐🔉
歯 字形
 筆順
筆順
 〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕
[齒] 字形
〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕
[齒] 字形
 〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕
〔音〕シ(呉)(漢)
〔訓〕は・よわい
[意味]
①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」
②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」
③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。
④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」
[解字]
解字
〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕
〔音〕シ(呉)(漢)
〔訓〕は・よわい
[意味]
①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」
②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」
③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。
④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」
[解字]
解字 形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。
[下ツキ
齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯
形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。
[下ツキ
齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯
 筆順
筆順
 〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕
[齒] 字形
〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕
[齒] 字形
 〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕
〔音〕シ(呉)(漢)
〔訓〕は・よわい
[意味]
①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」
②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」
③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。
④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」
[解字]
解字
〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕
〔音〕シ(呉)(漢)
〔訓〕は・よわい
[意味]
①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」
②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」
③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。
④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」
[解字]
解字 形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。
[下ツキ
齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯
形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。
[下ツキ
齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯
広辞苑に「歯」で完全一致するの検索結果 1-4。