複数辞典一括検索+![]()
![]()
かじ【梶・楫・舵】カヂ(道具)🔗⭐🔉
かじ【梶・楫・舵】カヂ
①水をかいて船を進めるのに用いる道具。櫓ろ・櫂かいなどの類。万葉集20「堀江漕ぐいづての船の―つくめ」
②船尾などにつけて船の針路を定める板状の船具。
③車の梶棒。
④紋所の名。舟の舵の形を描いたもの。
⇒舵を取る
かじ【梶・構・楮・穀】カヂ🔗⭐🔉
かじ【梶・構・楮・穀】カヂ
①カジノキのこと。〈類聚名義抄〉
②襲かさねの色目。表裏とも萌葱もえぎ。(桃華蘂葉)
③紋所の名。梶の木の葉を表したもの。
かじ【梶】カヂ(姓氏)🔗⭐🔉
かじ【梶】カヂ
姓氏の一つ。
⇒かじ‐つねきち【梶常吉】
かじ【鍛冶】カヂ🔗⭐🔉
かじ【鍛冶】カヂ
(カヌチ(金打)の約転。「鍛冶」は当て字)金属を打ちきたえて種々の器物を作ること。また、それを業とする人。「刀―」
か‐じ【火事】クワ‥🔗⭐🔉
か‐じ【火事】クワ‥
建物・船・山林などの焼けること。ひごと。火災。〈[季]冬〉
⇒火事と喧嘩は江戸の華
か‐じ【加持】‥ヂ🔗⭐🔉
か‐じ【加持】‥ヂ
〔仏〕(梵語adhiṣṭhāna)
①仏が不可思議な力で衆生しゅじょうを加護すること。
②真言密教で、仏と行者の行為が一体となること。災いを除き願いをかなえるため、仏の加護を祈ること。印を結び真言を唱える。源氏物語若紫「わらはやみにわづらひ給ひて、よろづに、まじなひ・―などまゐらせ給へど」
③供物・香水・念珠などを清めはらう作法。
か‐じ【花時】クワ‥🔗⭐🔉
か‐じ【花時】クワ‥
花の咲く時。はなどき。
か‐じ【夏時】🔗⭐🔉
か‐じ【夏時】
夏の時季。夏季。夏。
か‐じ【家事】🔗⭐🔉
か‐じ【家事】
①家庭内のいろいろな事柄。「―の都合により」
②家庭生活を営むための大小いろいろの用事。掃除・洗濯・炊事など。「―を手伝う」「―労働」
か‐じ【家慈】🔗⭐🔉
か‐じ【家慈】
自分の母の称。↔家厳
か‐じ【華字・花字】クワ‥🔗⭐🔉
か‐じ【華字・花字】クワ‥
①書判かきはん。花押かおう。
②中国の文字。また、華字紙の略。
か‐じ【遐邇】🔗⭐🔉
か‐じ【遐邇】
遠い所と近い所。遠近。
か‐じ【嘉事】🔗⭐🔉
か‐じ【嘉事】
めでたい事柄。慶事。
かじい【梶井】カヂヰ(地名)🔗⭐🔉
かじい【梶井】カヂヰ
京都市上京区の地名。もと三千院(梶井門跡)があった。
かじい【梶井】カヂヰ(姓氏)🔗⭐🔉
かじい【梶井】カヂヰ
姓氏の一つ。
⇒かじい‐もとじろう【梶井基次郎】
かじ‐いちご【梶苺】カヂ‥🔗⭐🔉
かじ‐いちご【梶苺】カヂ‥
バラ科の落葉小低木。高さ1〜2メートルで、根もとから分枝。葉は大形掌状で長柄がある。初夏に5弁の白花を付ける。海岸付近の陽地に群生。淡黄色の木苺状の果実は甘酸味があり食用として栽植。トウイチゴ。オオモミジバイチゴ。
カジイチゴ
提供:OPO


かじい‐もとじろう【梶井基次郎】カヂヰ‥ラウ🔗⭐🔉
かじい‐もとじろう【梶井基次郎】カヂヰ‥ラウ
小説家。大阪市生れ。東大英文科中退。志賀直哉の影響を受け、簡潔な描写で詩情豊かな小品をのこす。作「檸檬レモン」「城のある町にて」など。(1901〜1932)
梶井基次郎
提供:毎日新聞社
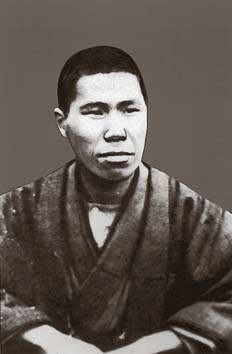 ⇒かじい【梶井】
⇒かじい【梶井】
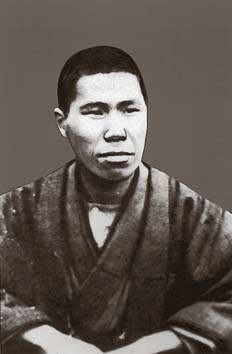 ⇒かじい【梶井】
⇒かじい【梶井】
かじ‐お【楫緒】カヂヲ🔗⭐🔉
かじ‐お【楫緒】カヂヲ
楫を船にとりつける縄。新古今和歌集恋「ゆらのとを渡るふな人―絶えゆくへも知らぬ恋の道かも」
かじ‐おと【楫音】カヂ‥🔗⭐🔉
かじ‐おと【楫音】カヂ‥
船を漕ぐ楫の音。
かじか【鰍・杜父魚】🔗⭐🔉
かじか【鰍・杜父魚】
カジカ科の淡水産の硬骨魚。全長約15センチメートル。体は一見ハゼ型で細長い。暗灰色で、背部に雲形斑紋がある。河川の清冽な水を好む。美味。川鰍かわかじか。マゴリ。チチンコ。〈[季]秋〉
カジカ
提供:東京動物園協会


か‐じか【河鹿】🔗⭐🔉
か‐じか【河鹿】
(→)カジカガエルに同じ。〈[季]夏〉
⇒かじか‐がえる【河鹿蛙・金襖子】
かじか‐がえる【河鹿蛙・金襖子】‥ガヘル🔗⭐🔉
かじか‐がえる【河鹿蛙・金襖子】‥ガヘル
カエルの一種。谷川の岩間にすむ。体色は暗褐色で四肢の各指端に吸盤がある。雄は美声を発するので飼養される。カジカ。〈[季]夏〉
かじかがえる
 カジカガエル
提供:東京動物園協会
カジカガエル
提供:東京動物園協会
 ⇒か‐じか【河鹿】
⇒か‐じか【河鹿】
 カジカガエル
提供:東京動物園協会
カジカガエル
提供:東京動物園協会
 ⇒か‐じか【河鹿】
⇒か‐じか【河鹿】
かじかざわ【鰍沢】‥ザハ🔗⭐🔉
かじかざわ【鰍沢】‥ザハ
①山梨県の西部、南巨摩こま郡にある町。富士川水運の河港・宿場町として発達。
②落語。三遊亭円朝作。身延山参りの男が雪道に迷い、宿を求めた家で所持金と命をねらわれるが、鰍沢へ飛び込んで助かる。
かじ‐かぶり【鍛冶被り】カヂ‥🔗⭐🔉
かじ‐かぶり【鍛冶被り】カヂ‥
鍛冶工の手拭のかぶりかた。作業中四つに折って頭の上に載せておくもの。
かじか・む【悴む】🔗⭐🔉
かじか・む【悴む】
〔自五〕
(古くは清音)
①疲れ痩やせる。〈享和本新撰字鏡〉
②手足がこごえて思うように動かなくなる。かじける。〈[季]冬〉。樋口一葉、にごりえ「寒さの身にしみて手も足も亀かじかみたれば」
かじ‐から【梶柄】カヂ‥🔗⭐🔉
かじ‐から【梶柄】カヂ‥
(一説に、カヂツカと読む)梶1の柄え。万葉集8「君がみ船の―にもが」
かじかわ‐まきえ【梶川蒔絵】カヂカハ‥ヱ🔗⭐🔉
かじかわ‐まきえ【梶川蒔絵】カヂカハ‥ヱ
江戸時代、徳川家御用の蒔絵師、梶川家代々の作品。印籠蒔絵に優れる。
か‐じき【加敷】🔗⭐🔉
か‐じき【加敷】
和船で、船体の最下部にある棚板。敷しき2( かわら)の両側に取り付け、
かわら)の両側に取り付け、 とともに箱型の強い構造物をなす。ねだな。そばがわら。梶木。
とともに箱型の強い構造物をなす。ねだな。そばがわら。梶木。
 かわら)の両側に取り付け、
かわら)の両側に取り付け、 とともに箱型の強い構造物をなす。ねだな。そばがわら。梶木。
とともに箱型の強い構造物をなす。ねだな。そばがわら。梶木。
かじ‐き【梶木・旗魚】カヂ‥🔗⭐🔉
かじ‐き【梶木・旗魚】カヂ‥
マカジキ科とメカジキ科の硬骨魚の総称。体はマグロに似るが、上顎は剣状に延びている。背部は青黒く、腹部は淡色。熱帯・温帯の外洋に分布。美味。かじきまぐろ。
⇒かじき‐ざ【旗魚座】
⇒かじき‐とおし【梶木通し】
⇒かじき‐まぐろ【梶木鮪】
かじき‐ざ【旗魚座】カヂ‥🔗⭐🔉
かじき‐ざ【旗魚座】カヂ‥
南天の星座。日本からは見えない。この星座の南部に、テーブル山座にまたがって大マゼラン雲がある。
⇒かじ‐き【梶木・旗魚】
かじ‐きとう【加持祈祷】‥ヂ‥タウ🔗⭐🔉
かじ‐きとう【加持祈祷】‥ヂ‥タウ
仏の力を信者に加え保たせる「祈祷」が「加持」とも言われ、並称されるようになった言葉。→加持
かじき‐とおし【梶木通し】カヂ‥トホシ🔗⭐🔉
かじき‐とおし【梶木通し】カヂ‥トホシ
メカジキの方言。とがった顎で船の加敷かじきを突き通すという意からきた語。かじとおし。
⇒かじ‐き【梶木・旗魚】
かじき‐まぐろ【梶木鮪】カヂ‥🔗⭐🔉
かじき‐まぐろ【梶木鮪】カヂ‥
(→)カジキに同じ。
⇒かじ‐き【梶木・旗魚】
か‐じく【花軸】クワヂク🔗⭐🔉
か‐じく【花軸】クワヂク
花梗をつける花序の枝。
かじ‐くろ・しカヂ‥🔗⭐🔉
かじ‐くろ・しカヂ‥
〔形シク〕
堅苦しく窮屈である。好色一代男5「よろづ―・しく、あたら夜終よもすがら新三十石に乗合のここちするなり」
かじ・ける【悴ける】🔗⭐🔉
かじ・ける【悴ける】
〔自下一〕[文]かじ・く(下二)
(古くはカシクとも)
①やつれる。生気を失う。やせ衰える。法華経玄賛平安中期点「痟カジケ痩せたらむ」
②手足がこごえて思うように動かなくなる。かじかむ。
かじ‐こ【楫子】カヂ‥🔗⭐🔉
かじ‐こ【楫子】カヂ‥
かじとり。水夫。船頭。かこ。
か‐じこ【加地子】‥ヂ‥🔗⭐🔉
か‐じこ【加地子】‥ヂ‥
⇒かじし
かじ‐こうずい【加持香水】‥ヂカウ‥🔗⭐🔉
かじ‐こうずい【加持香水】‥ヂカウ‥
密教で修法しゅほうの際、香水を加持し、それを行者や壇場に注いで浄化すること。また、その香水。徒然草「―を見侍りしに」
か‐じし【加地子】‥ヂ‥🔗⭐🔉
か‐じし【加地子】‥ヂ‥
①国衙こくがや荘園領主のとる本年貢に対して、その下で私領主や名主などの地主的中間層がとる追加の地代。片子かたこ。→地子。
②江戸時代、小作米の異称。加地子米。かじこ。
かじ‐し【華字紙】クワ‥🔗⭐🔉
かじ‐し【華字紙】クワ‥
中国語で書かれた新聞。
かじ‐しょうぞく【火事装束】クワ‥シヤウ‥🔗⭐🔉
かじ‐しょうぞく【火事装束】クワ‥シヤウ‥
消火に当たる人の服装。江戸時代は、火事頭巾・火事羽織・野袴などを着けた。
かじ‐しんぱん【家事審判】🔗⭐🔉
かじ‐しんぱん【家事審判】
家庭裁判所が家事審判法に定められた後見開始・財産分与その他の家庭事件について行う審判。
⇒かじしんぱん‐ほう【家事審判法】
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】‥ハフ🔗⭐🔉
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】‥ハフ
家庭裁判所が管轄する家庭事件(審判と調停)およびその取扱方法について定めた法律。1947年制定。
⇒かじ‐しんぱん【家事審判】
かじ‐ずきん【火事頭巾】クワ‥ヅ‥🔗⭐🔉
かじ‐ずきん【火事頭巾】クワ‥ヅ‥
江戸時代の火事装束用の頭巾。一般には革・羅紗ラシャ・刺子さしこなどで作り、武家は兜かぶと頭巾を用いた。
かじた【梶田】カヂ‥🔗⭐🔉
かじた【梶田】カヂ‥
姓氏の一つ。
⇒かじた‐はんこ【梶田半古】
かじた‐はんこ【梶田半古】カヂ‥🔗⭐🔉
かじた‐はんこ【梶田半古】カヂ‥
日本画家。本名、錠次郎。東京生れ。風俗画を得意とし、小説の挿絵にも活躍。門人に小林古径・奥村土牛ら。(1870〜1917)
⇒かじた【梶田】
か‐じち【家質】🔗⭐🔉
か‐じち【家質】
江戸時代、家屋敷を抵当に入れること。また、その家屋敷。いえじち。浮世風呂前「金が子を産んで―が流れ込む」
⇒かじち‐こう【家質講】
広辞苑に「かじ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む