複数辞典一括検索+![]()
![]()
そう【僧】🔗⭐🔉
そう【僧】
(梵語saṃghaの音写「僧伽そうぎゃ」の略。和合衆・衆と訳す)
①仏教の修行者の集団。
②1に属する修行者。特に中国・日本では、仏門に入って仏道修行する各個人の称。沙門。出家。比丘びく。法師。
そう‐あん【僧庵】🔗⭐🔉
そう‐あん【僧庵】
僧の住むいおり。
そう‐い【僧位】‥ヰ🔗⭐🔉
そう‐い【僧位】‥ヰ
学徳のすぐれた僧に授ける位階。8世紀末には、伝灯・修学・修行の3系列に、それぞれ大法師位・法師位・満位・住位・入位の5位が整備された。864年(貞観6)僧綱の位階として大法師位の上に、法印大和尚位・法眼和上位・法橋上人位が設置され、それぞれ僧正・僧都・律師の階位とした。なお中世以降、仏師・医師なども法印・法眼・法橋に叙された。
そう‐いん【僧院】‥ヰン🔗⭐🔉
そう‐いん【僧院】‥ヰン
①僧の住居たる建物。てら。寺院。
②修道院。
そう‐う【僧宇】🔗⭐🔉
そう‐う【僧宇】
(「宇」は家の意)僧のいる所。寺。
そう‐えん【僧園】‥ヱン🔗⭐🔉
そう‐えん【僧園】‥ヱン
寺院の建物。伽藍がらん。
そう‐か【僧家】🔗⭐🔉
そう‐か【僧家】
(ソウケとも)
①僧の住む家。寺院。仏家。↔俗家ぞっか。
②僧侶。出家。
そう‐かい【僧戒】🔗⭐🔉
そう‐かい【僧戒】
僧尼の守るべき戒律。沙弥しゃみ・沙弥尼の十戒、比丘びく・比丘尼の具足戒を指す。
そう‐がら【僧柄】🔗⭐🔉
そう‐がら【僧柄】
僧としての品位。僧の人柄。
そう‐がらん【僧伽藍】🔗⭐🔉
そう‐がらん【僧伽藍】
(→)伽藍がらんに同じ。
そうかり【僧伽梨】🔗⭐🔉
そうかり【僧伽梨】
(梵語saṃghāṭī)三衣さんえの一つ。三衣のうち最も大きく、9〜25条の袈裟けさ。説法・托鉢のときに用いる。大衣。そうぎゃりえ。さんがり。
そう‐かん【僧官】‥クワン🔗⭐🔉
そう‐かん【僧官】‥クワン
朝廷から僧侶に与える官。僧正・僧都そうず・律師など。
そうぎ【僧祇】🔗⭐🔉
そうぎ【僧祇】
〔仏〕
①(梵語saṃgha)(→)僧伽そうぎゃに同じ。
②阿僧祇あそうぎの略。
⇒そうぎ‐こ【僧祇戸】
そうぎ‐こ【僧祇戸】🔗⭐🔉
そうぎ‐こ【僧祇戸】
北魏における僧曹(宗教行政官庁)所属の人戸。沙門統曇曜の奏請によって設置。僧院維持と備荒貯蔵のため、毎年粟60石を納入させた(僧祇粟という)。
⇒そうぎ【僧祇】
そうぎゃ【僧伽】🔗⭐🔉
そうぎゃ【僧伽】
〔仏〕(梵語saṃgha 和合衆・衆と訳)仏教の修行者の集まり。仏教の教団。略して「僧」とも。
そうぎゃり‐え【僧伽梨衣】🔗⭐🔉
そうぎゃり‐え【僧伽梨衣】
(→)僧伽梨そうかりに同じ。今昔物語集3「仏の―及び錫杖を右手に取りて」
そう‐ぎょう【僧形】‥ギヤウ🔗⭐🔉
そう‐ぎょう【僧形】‥ギヤウ
僧のすがた。僧のみなり。↔俗形ぞくぎょう。
⇒そうぎょう‐はちまん【僧形八幡】
そうぎょう‐はちまん【僧形八幡】‥ギヤウ‥🔗⭐🔉
そうぎょう‐はちまん【僧形八幡】‥ギヤウ‥
僧形をとった八幡神。神仏習合思想に基づき、その作例は平安初期にまでさかのぼる。東寺・薬師寺に古い作品があり、また、東大寺には快慶の優作がある。
⇒そう‐ぎょう【僧形】
○創業は易く守成は難しそうぎょうはやすくしゅせいはかたし
[貞観政要君道](唐の太宗の下問に答えた魏徴の語に由来)創業はたやすいが、その事業を受け継いで維持してゆくことはむずかしい。
⇒そう‐ぎょう【創業】
そう‐ぐ【僧供】🔗⭐🔉
そう‐ぐ【僧供】
僧侶への供物。
そう‐くよう【僧供養】‥ヤウ🔗⭐🔉
そう‐くよう【僧供養】‥ヤウ
僧に供養すること。
そう‐ごう【僧号】‥ガウ🔗⭐🔉
そう‐ごう【僧号】‥ガウ
僧となって後、俗名を改めてつける名。
そう‐ごう【僧綱】‥ガウ🔗⭐🔉
そう‐ごう【僧綱】‥ガウ
①僧尼を統領し、法務を統轄する僧官。624年に僧正そうじょう・僧都そうず・法頭ほうずが設けられたことに始まる。後に僧正・僧都・律師となり、佐官(後に威儀師・従儀師となる)が置かれた。→僧位。
②「そうごうくび」の略。
⇒そうごう‐えり【僧綱襟】
⇒そうごう‐くび【僧綱領・僧綱頸】
⇒そうごう‐しょ【僧綱所】
そうごう‐えり【僧綱襟】‥ガウ‥🔗⭐🔉
そうごう‐えり【僧綱襟】‥ガウ‥
僧綱の位にある僧が、衣のえりに着けるもの。
僧綱襟
 ⇒そう‐ごう【僧綱】
⇒そう‐ごう【僧綱】
 ⇒そう‐ごう【僧綱】
⇒そう‐ごう【僧綱】
そうごう‐くび【僧綱領・僧綱頸】‥ガウ‥🔗⭐🔉
そうごう‐くび【僧綱領・僧綱頸】‥ガウ‥
①(→)僧綱襟そうごうえりに同じ。
②小袖の襟を折らずに三角形にして着ること。僧綱。坊主襟。
⇒そう‐ごう【僧綱】
そうごう‐しょ【僧綱所】‥ガウ‥🔗⭐🔉
そうごう‐しょ【僧綱所】‥ガウ‥
僧綱の事務所。奈良時代は薬師寺。平安遷都後は東寺または西寺に置かれた。綱所。
⇒そう‐ごう【僧綱】
そう‐さい【僧斎】🔗⭐🔉
そう‐さい【僧斎】
〔仏〕死者の追善などのため、僧尼に食事を供養すること。
そう‐ざん【僧残】🔗⭐🔉
そう‐ざん【僧残】
〔仏〕僧尼の守るべき具足戒の一部。波羅夷はらいに次ぐ重罪。大衆だいしゅの前に懺悔すれば、滅罪して僧団に残りうるところから名づける。十三項目あるので十三僧残と称する。
そう‐じ【僧寺】🔗⭐🔉
そう‐じ【僧寺】
僧のいる寺。寺。↔尼寺
そう‐じき【僧食】🔗⭐🔉
そう‐じき【僧食】
僧の食べる食事。正法眼蔵行持上「なんぢすでに年老なり、―を食じきすべし」
そう‐しゃ【僧舎】🔗⭐🔉
そう‐しゃ【僧舎】
てら。寺院。僧家。
そう‐しゅう【僧衆】🔗⭐🔉
そう‐しゅう【僧衆】
多くの僧侶。僧徒。衆徒。
そう‐じょう【僧正】‥ジヤウ🔗⭐🔉
そう‐じょう【僧正】‥ジヤウ
僧官の最上級。のちに大僧正・僧正・権僧正に分けた。現在、各宗で僧階の一つ。
そうじょう【僧肇】‥デウ🔗⭐🔉
そうじょう【僧肇】‥デウ
中国、後秦の学僧。鳩摩羅什くまらじゅうの弟子。什門の四哲(僧肇・僧叡・道生・僧融)の一人。長安で師の訳経を助ける。(384〜414頃)→肇論じょうろん
そうじょう‐が‐たに【僧正谷】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
そうじょう‐が‐たに【僧正谷】‥ジヤウ‥
京都市左京区鞍馬山にある谷。源義経が兵法を学んだ所と伝えられる。
そう‐しょく【僧職】🔗⭐🔉
そう‐しょく【僧職】
①僧の職務。法会・授戒・灌頂かんじょうなどの儀式および寺院の経営をつかさどる者。
②一宗の教師(住職)。
そう‐ず【僧都】‥ヅ🔗⭐🔉
そう‐ず【僧都】‥ヅ
僧綱そうごうの一つ。僧正に次ぐ僧官。のちに大僧都・権大僧都・少僧都・権少僧都に分けた。現在、各宗派で僧階の一つ。
そう‐せき【僧籍】🔗⭐🔉
そう‐せき【僧籍】
僧の宗籍。僧・尼となった者が、所属宗派で登録された籍。「―に入る」
⇒そうせき‐ぼ【僧籍簿】
そうせき‐ぼ【僧籍簿】🔗⭐🔉
そうせき‐ぼ【僧籍簿】
各宗宗務所で、僧尼の名称・得度などを記録する帳簿。僧帳。
⇒そう‐せき【僧籍】
そう‐ぜん【僧膳】🔗⭐🔉
そう‐ぜん【僧膳】
僧をもてなす食膳。宇治拾遺物語13「堂を飾りて―を設けて」
そう‐ぞく【僧俗】🔗⭐🔉
そう‐ぞく【僧俗】
僧侶と俗人。
そう‐たい【僧体】🔗⭐🔉
そう‐たい【僧体】
僧侶のすがた。法体ほうたい。僧形そうぎょう。
そう‐だん【僧団】🔗⭐🔉
そう‐だん【僧団】
信仰のために特別の修行をする僧侶の団体。
そう‐と【僧徒】🔗⭐🔉
そう‐と【僧徒】
僧のともがら。僧侶。
そう‐どう【僧堂】‥ダウ🔗⭐🔉
そう‐どう【僧堂】‥ダウ
禅宗寺院の建物の一つで、坐禅修行の根本道場。もとは坐禅を中心に食事から睡眠までの一切がなされた。禅堂。雲堂。撰仏場。
そう‐に【僧尼】🔗⭐🔉
そう‐に【僧尼】
僧と尼。男女の出家。
⇒そうに‐りょう【僧尼令】
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ🔗⭐🔉
そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ
仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。
⇒そう‐に【僧尼】
そう‐ふく【僧服】🔗⭐🔉
そう‐ふく【僧服】
僧侶の着る衣服。ころも。
そう‐へい【僧兵】🔗⭐🔉
そう‐へい【僧兵】
寺院の私兵。平安後期以後、延暦寺・興福寺など諸大寺の下級僧徒で、仏法保護を名として武芸を練り戦闘に従事した。悪僧。
僧兵


そう‐ぼう【僧坊・僧房】‥バウ🔗⭐🔉
そう‐ぼう【僧坊・僧房】‥バウ
僧尼の起居する寺院付属の家屋。
そう‐ぼう【僧帽】🔗⭐🔉
そう‐ぼう【僧帽】
僧のかぶる帽子。
⇒そうぼう‐きん【僧帽筋】
⇒そうぼう‐べん【僧帽弁】
そうぼう‐きん【僧帽筋】🔗⭐🔉
そうぼう‐きん【僧帽筋】
〔医〕(形がカトリック僧の頭巾に似るからいう)項部から背部の上半分にわたって浅層にある大きな三角形の筋肉。肩胛けんこう骨を動かし、また固定する。→筋肉(図)。
⇒そう‐ぼう【僧帽】
そう‐ほうし【僧法師】‥ホフ‥🔗⭐🔉
そう‐ほうし【僧法師】‥ホフ‥
(同意の「僧」と「法師」とを重ねた語)僧。
そうぼう‐べん【僧帽弁】🔗⭐🔉
そうぼう‐べん【僧帽弁】
心臓の左心房から左心室への入口にある僧帽形の2枚の弁膜。心収縮の際、血液が左心房へ逆流するのを防ぐ。二尖弁。
⇒そう‐ぼう【僧帽】
そう‐みん【僧旻】🔗⭐🔉
そう‐みん【僧旻】
飛鳥時代の学僧、旻みんのこと。
そう‐もつ【僧物】🔗⭐🔉
そう‐もつ【僧物】
僧伽そうぎゃに帰属する共有資財。四方僧物(堂舎・団地など)と現前僧物(衣食などの生活物資)の2種がある。僧祇そうぎ物。僧伽物。太平記35「―施料を貪る事を業とす」
そう‐もん【僧門】🔗⭐🔉
そう‐もん【僧門】
僧家。仏門。仏家。
そう‐りょ【僧侶】🔗⭐🔉
そう‐りょ【僧侶】
出家して僧門に帰した人。また、その集団。僧徒。「―の読経」↔俗衆
そう‐りん【僧林】🔗⭐🔉
そう‐りん【僧林】
大きな寺。住僧の多いことを林にたとえた語。
そう‐ろく【僧録】🔗⭐🔉
そう‐ろく【僧録】
禅宗の僧職。五山十刹およびその諸流の禅寺を統轄、人事をつかさどった。1379年(康暦1)足利義満が春屋妙葩しゅんおくみょうはを任じたのに始まり、後には鹿苑院の院主が任ぜられるようになった。室町時代には権勢をふるったが、江戸時代に廃され、1619年(元和5)以降は南禅寺金地院の院主が僧録に任ぜられた。
⇒そうろく‐し【僧録司】
そうろく‐し【僧録司】🔗⭐🔉
そうろく‐し【僧録司】
僧録が事務を執った所。
⇒そう‐ろく【僧録】
そう‐わき【僧脇】🔗⭐🔉
そう‐わき【僧脇】
能の中に僧の姿で出るワキ。「―物」
[漢]僧🔗⭐🔉
僧 字形
 筆順
筆順
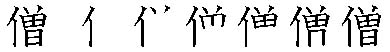 〔人(亻・
〔人(亻・ )部11画/13画/常用/3346・414E〕
[
)部11画/13画/常用/3346・414E〕
[ ] 字形
] 字形
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部12画/14画〕
〔音〕ソウ(呉)(漢)
[意味]
仏門に入って道を修める男子。沙門しゃもん。比丘びく。広く、聖職者。「僧侶そうりょ・僧院・僧俗・尼僧・仏法僧」
▷saṃghaサンスクリットの音訳「僧伽そうぎゃ」の略。和合衆の意で、本来、三人ないし四人以上の比丘の集団をさす。
[解字]
形声。「人」+音符「曾」。
[下ツキ
悪僧・学僧・客僧・愚僧・高僧・虚無僧・山僧・師僧・住僧・雛僧・拙僧・俗僧・尼僧・伴僧・番僧・普化僧・仏法僧・売僧まいす・名僧・役僧
)部12画/14画〕
〔音〕ソウ(呉)(漢)
[意味]
仏門に入って道を修める男子。沙門しゃもん。比丘びく。広く、聖職者。「僧侶そうりょ・僧院・僧俗・尼僧・仏法僧」
▷saṃghaサンスクリットの音訳「僧伽そうぎゃ」の略。和合衆の意で、本来、三人ないし四人以上の比丘の集団をさす。
[解字]
形声。「人」+音符「曾」。
[下ツキ
悪僧・学僧・客僧・愚僧・高僧・虚無僧・山僧・師僧・住僧・雛僧・拙僧・俗僧・尼僧・伴僧・番僧・普化僧・仏法僧・売僧まいす・名僧・役僧
 筆順
筆順
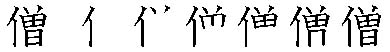 〔人(亻・
〔人(亻・ )部11画/13画/常用/3346・414E〕
[
)部11画/13画/常用/3346・414E〕
[ ] 字形
] 字形
 〔人(亻・
〔人(亻・ )部12画/14画〕
〔音〕ソウ(呉)(漢)
[意味]
仏門に入って道を修める男子。沙門しゃもん。比丘びく。広く、聖職者。「僧侶そうりょ・僧院・僧俗・尼僧・仏法僧」
▷saṃghaサンスクリットの音訳「僧伽そうぎゃ」の略。和合衆の意で、本来、三人ないし四人以上の比丘の集団をさす。
[解字]
形声。「人」+音符「曾」。
[下ツキ
悪僧・学僧・客僧・愚僧・高僧・虚無僧・山僧・師僧・住僧・雛僧・拙僧・俗僧・尼僧・伴僧・番僧・普化僧・仏法僧・売僧まいす・名僧・役僧
)部12画/14画〕
〔音〕ソウ(呉)(漢)
[意味]
仏門に入って道を修める男子。沙門しゃもん。比丘びく。広く、聖職者。「僧侶そうりょ・僧院・僧俗・尼僧・仏法僧」
▷saṃghaサンスクリットの音訳「僧伽そうぎゃ」の略。和合衆の意で、本来、三人ないし四人以上の比丘の集団をさす。
[解字]
形声。「人」+音符「曾」。
[下ツキ
悪僧・学僧・客僧・愚僧・高僧・虚無僧・山僧・師僧・住僧・雛僧・拙僧・俗僧・尼僧・伴僧・番僧・普化僧・仏法僧・売僧まいす・名僧・役僧
広辞苑に「僧」で始まるの検索結果 1-67。