複数辞典一括検索+![]()
![]()
うぬ【汝・己】🔗⭐🔉
うぬ【汝・己】
〔代〕
①自分自身。誹風柳多留16「暗い晩―が声色通るなり」
②相手を卑しめていう語。おのれ。なんじ。浄瑠璃、心中天の網島「畜生め、狐め、太兵衛より先―を踏みたい」
うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】🔗⭐🔉
うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】
うぬぼれること。自負。「―が強い」
⇒うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】
うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】🔗⭐🔉
うぬぼれ‐かがみ【己惚鏡・自惚鏡】
(容貌を実際よりもよく見せる鏡、また、うぬぼれて絶えず見る鏡の意とも)江戸時代、それまでの和鏡に対し、ガラスに水銀を塗った洋鏡を指したとも、また一説に懐中鏡の一種で、人の居ない所でひとりで見たり、化粧をなおすのに用いたりした故の名ともいう。
⇒うぬ‐ぼれ【己惚れ・自惚れ】
うら【己】🔗⭐🔉
うら【己】
〔代〕
(一人称)おのれ。われ。おれ。おら。好色二代男「―がといふた言葉つきもなほりて」
おい‐ら【己等】🔗⭐🔉
おい‐ら【己等】
〔代〕
(一人称)おれら。われら。おれ。主に男性が用いる語。
おどれ【己】🔗⭐🔉
おどれ【己】
〔代〕
(オノレの転)相手をののしっていう語。きさま。おんどれ。おどりゃ。狂言、花子「やい―さへ花子さまとぬかすか」
おの【己】🔗⭐🔉
おの【己】
[一]〔名〕
その人自身。自分。おのれ。万葉集5「―が身しいたはしければ」
[二]〔代〕
①(一人称)われ。あれ。おのれ。
②(二人称。相手をののしっていう)きさま。宇治拾遺物語9「―、後に会はざらんやは」
おの‐が【己が】🔗⭐🔉
おの‐が【己が】
①(主格として)自分が。私が。
②(連体格として)自分の。私の。
⇒おのが‐いろいろ【己が色色】
⇒おのが‐さまざま【己が様様】
⇒おのが‐じし【己がじし】
⇒おのが‐しなじな【己が品品】
⇒おのが‐ちりぢり【己が散り散り】
⇒おのが‐でに【己がでに】
⇒おのが‐どち【己がどち】
⇒おのが‐むきむき【己が向き向き】
⇒おのが‐よよ【己が世世】
おのが‐いろいろ【己が色色】🔗⭐🔉
おのが‐いろいろ【己が色色】
それぞれ異なったさま。おもいおもい。続古今和歌集釈教「雲しきてふる春雨はわかねども秋の垣根は―」
⇒おの‐が【己が】
おのが‐さまざま【己が様様】🔗⭐🔉
おのが‐さまざま【己が様様】
(→)「おのがいろいろ」に同じ。伊勢物語「―年のへぬれば」
⇒おの‐が【己が】
おのが‐じし【己がじし】🔗⭐🔉
おのが‐じし【己がじし】
めいめい。それぞれ。各自。万葉集12「―人死にすらし」。「―新しきを開かんと思へるぞ、若き人のつとめなる」(藤村)
⇒おの‐が【己が】
おのが‐しなじな【己が品品】🔗⭐🔉
おのが‐しなじな【己が品品】
(→)「おのがいろいろ」に同じ。
⇒おの‐が【己が】
おのが‐ちりぢり【己が散り散り】🔗⭐🔉
おのが‐ちりぢり【己が散り散り】
めいめいばらばら。古今和歌集雑体「秋の紅葉と人々は―わかれなば」
⇒おの‐が【己が】
おのが‐でに【己がでに】🔗⭐🔉
おのが‐でに【己がでに】
自分で。みずから。
⇒おの‐が【己が】
おのが‐どち【己がどち】🔗⭐🔉
おのが‐どち【己がどち】
自分たち同士。各自お互いに。源氏物語少女「更に思ひ寄らざりけることと―嘆く」
⇒おの‐が【己が】
おのが‐むきむき【己が向き向き】🔗⭐🔉
おのが‐むきむき【己が向き向き】
めいめいの心の向いた方。おもいおもい。万葉集9「はふ蔦の―天雲の別れし往けば」
⇒おの‐が【己が】
おのが‐よよ【己が世世】🔗⭐🔉
おのが‐よよ【己が世世】
(男女が)めいめい別の生活を送ること。後撰和歌集恋「笛竹のもとの古音ふるねはかはるとも―にはならずもあらなむ」
⇒おの‐が【己が】
おの‐さま【己様】🔗⭐🔉
おの‐さま【己様】
〔代〕
(二人称)あなた。そなた。おまえさま。おのさん。浄瑠璃、卯月潤色「いやわれよりも―の」
おの‐づま【己妻・己夫】🔗⭐🔉
おの‐づま【己妻・己夫】
自分の妻。また、自分の夫。万葉集14「―を人の里に置き」
おの‐ぼれ【己惚れ】🔗⭐🔉
おの‐ぼれ【己惚れ】
(→)「うぬぼれ」に同じ。
おの‐ら【己等】🔗⭐🔉
おの‐ら【己等】
〔代〕
①(一人称)われら。舒明紀「―が父子かぞこ並に蘇我より出でたり」
②(二人称)同輩以下を卑しめていう。おまえら。うぬら。狂言、二人大名「―がぬぎをつて、つくばうてをるなりは」
おのれ【己】🔗⭐🔉
おのれ【己】
[一]〔名〕
自分自身。万葉集16「伊夜彦は―神さび」。「士は―を知る者の為に死す」
[二]〔代〕
①(一人称)わたくし。われ。宇津保物語俊蔭「―は天上より来り給ひし人の御子供なり」
②(二人称)目下の者に、または人をののしる時にいう。きさま。こいつ。宇治拾遺物語1「―はまがまがしかりける心もちたる者かな」。日葡辞書「ヲノレメ」。狂言、河原新市「なんの―、人の飲まうといふ時は飲まさいで」
[三]〔副〕
自然と。ひとりでに。おのずから。源氏物語末摘花「松の木の―起きかへり」
[四]〔感〕
物事に激して自ら励ます時に発する声。「―、何のこれしき」
⇒おのれ‐おい【己生い】
⇒おのれ‐がお【己顔】
⇒おのれ‐ざき【己咲き】
⇒おのれ‐と【己と】
⇒おのれ‐やれ【己やれ】
⇒おのれ‐ら【己等】
⇒己達せんと欲すれば人を達せしむ
⇒己に克ち礼に復る
⇒己に如かざる者を友とするなかれ
⇒己の欲せざる所は人に施すなかれ
⇒己を枉げる
⇒己を虚しうす
おのれ‐おい【己生い】‥オヒ🔗⭐🔉
おのれ‐おい【己生い】‥オヒ
自然に生い出ること。自生。
⇒おのれ【己】
おのれ‐がお【己顔】‥ガホ🔗⭐🔉
おのれ‐がお【己顔】‥ガホ
自分こそはと思う自慢らしい顔つき。われはがお。俊成女集「―なる風の音かな」
⇒おのれ【己】
おのれ‐ざき【己咲き】🔗⭐🔉
おのれ‐と【己と】🔗⭐🔉
おのれ‐と【己と】
〔副〕
①自分から。われと。続千載和歌集夏「人とはで―名のるほととぎす」
②ひとりでに。自然に。徒然草「―枯るるだにこそあるを」
⇒おのれ【己】
○己に克ち礼に復るおのれにかちれいにかえる
[論語顔淵]私欲をおさえて、人間生活の基本である礼の道にたちかえる。
⇒おのれ【己】
○己に如かざる者を友とするなかれおのれにしかざるものをともとするなかれ
[論語学而・子罕]自分より劣った者は、善を求め道を修める上の助けとならないから、友としてはならない。
⇒おのれ【己】
○己の欲せざる所は人に施すなかれおのれのほっせざるところはひとにほどこすなかれ
[論語顔淵・衛霊公]自分が欲しないことは人も欲しないのだから、これを人にしてはならない。
⇒おのれ【己】
○己に克ち礼に復るおのれにかちれいにかえる🔗⭐🔉
○己に克ち礼に復るおのれにかちれいにかえる
[論語顔淵]私欲をおさえて、人間生活の基本である礼の道にたちかえる。
⇒おのれ【己】
○己に如かざる者を友とするなかれおのれにしかざるものをともとするなかれ🔗⭐🔉
○己に如かざる者を友とするなかれおのれにしかざるものをともとするなかれ
[論語学而・子罕]自分より劣った者は、善を求め道を修める上の助けとならないから、友としてはならない。
⇒おのれ【己】
おのれ‐やれ【己やれ】🔗⭐🔉
おのれ‐やれ【己やれ】
〔感〕
他人が自分に無念なことをした時に発する発憤や決意を表す語。なにくそ。今にみていろ。
⇒おのれ【己】
おのれ‐ら【己等】🔗⭐🔉
○己を枉げるおのれをまげる🔗⭐🔉
○己を枉げるおのれをまげる
[孟子万章上]自分の信念を捨て節を曲げる。自己の主張を捨てる。
⇒おのれ【己】
○己を虚しうすおのれをむなしうす🔗⭐🔉
○己を虚しうすおのれをむなしうす
[漢書五行志上]私情を全く捨ててわだかまりのない気持になる。
⇒おのれ【己】
おのろけ‐まめ【御惚気豆】
煎いったピーナッツを塩味の寒梅粉でくるんだ豆菓子。
お‐の‐わらわ【男童】ヲノワラハ
①男の子。童子。少年。
②召使の男の子。
オノン【Onon・斡難】
黒竜江上流のシルカ川の支流。モンゴルのヘンティーン山脈に発源し、北東流してシベリアに入り、シルカ川に注ぐ。長さ1032キロメートル。
お‐は【尾羽】ヲ‥
鳥の尾と羽。
⇒尾羽打ち枯らす
お‐ば【小母】ヲ‥
⇒おばさん2
お‐ば【老婆・姥】
(「おほば」の略)年取った女。おうな。ろうば。ばば。
お‐ば【伯母・叔母】ヲ‥
①父・母の姉妹。また、おじの妻。父・母の姉には「伯母」、妹には「叔母」と書く。
②㋐(東北・関東・中部地方などで)妹。次女以下。
㋑(北陸地方・西日本で)独身の女。
お‐ば【祖母】
(「おほば」の略)父・母の母。そぼ。
お‐ばあ‐さん【御祖母さん・御婆さん】
①祖母を敬っていう語。
②年とった女性を敬い、また親しんでいう語。
オパーリン【Aleksandr Ivanovich Oparin】
ソ連の生化学者。モスクワ大学教授。バッハ生化学研究所長。主著「生命の起源」。(1894〜1980)
オパール【opal】
(→)蛋白石たんぱくせきに同じ。
オハイオ【Ohio】
①アメリカ合衆国中央北東部の州。交通網が発達し、各種製造業が盛ん。州都コロンバス。→アメリカ合衆国(図)。
②アメリカ東部、アパラチア山脈に発し、オハイオ州南縁を流れて、ミシシッピ川に注ぐ川。
おら【己】🔗⭐🔉
おら【己】
〔代〕
(一人称)おれ。おいら。江戸時代、男性が用いるのがふつうであったが、女性も使った。狂言、苞山伏「―がひるめしはよそへずい」
おら‐っち【己っち】🔗⭐🔉
おら‐っち【己っち】
(「おらたち」の訛)男性の卑俗な自称語。多く江戸の下町で使われた。「おいらっち」とも。歌舞伎、東海道四谷怪談「風が悪いと思つて、―には、隠すの隠すの」
おれ【己】🔗⭐🔉
おれ【己】
〔代〕
①(二人称)相手を卑しめて呼ぶ語。おのれ。古事記中「―熊曾建くまそたける二人、伏まつろはず礼いや無しと聞しめして、―を取殺とれと詔りたまひて」。枕草子226「ほととぎす、―、かやつよ。―鳴きてこそ」
②(一人称)男女ともに、また目上にも目下にも用いたが、現代では主として男が同輩以下の者に対して用いる、荒っぽい言い方。「俺」「乃公」とも書く。狂言、金岡「―は狂気はせぬ」。「お前と―の仲」
おれ‐さま【己様・俺様】🔗⭐🔉
おれ‐さま【己様・俺様】
〔代〕
自分のことを尊大にいう語。
おれ‐め【己奴】🔗⭐🔉
おれ‐め【己奴】
〔代〕
(二人称の「おれ」に、ののしる意を加えていう語)おのれめ。きさま。狂言、清水「―は身共をおくびやうものにするか」
おれ‐ら【己等】🔗⭐🔉
おれ‐ら【己等】
〔代〕
①(二人称)おまえら。相手をののしっていう。平家物語5「さらば―書け」
②(一人称)われら。われ。俺等。讃岐典侍日記「―知らぬに、教へよ」
おん‐ども【己共】🔗⭐🔉
おん‐ども【己共】
〔代〕
(オレドモの訛)われら。我々。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―が二十七の年薩摩者と喧嘩した咄」
おん‐ら【己等】🔗⭐🔉
おん‐ら【己等】
〔代〕
(一人称)おれ。おいら。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―が在所はの」
き【己】🔗⭐🔉
き【己】
(呉音はコ)十干じっかんの第6。つちのと。
きゆう‐やくじょう【己酉約条】‥イウ‥デウ🔗⭐🔉
きゆう‐やくじょう【己酉約条】‥イウ‥デウ
1609年(慶長14年己酉)朝鮮国王が対馬島主宗氏に与えた文書。通交の対象を将軍・宗氏に限り、また貿易船の数を限るなど、朝鮮側の鎖国政策を明確に示す。
○己心の弥陀こしんのみだ🔗⭐🔉
○己心の弥陀こしんのみだ
弥陀は浄土にあるのではなくて、却って自分の心(身)にそなわっているということ。
⇒こ‐しん【己心】
○己身の弥陀こしんのみだ🔗⭐🔉
○己身の弥陀こしんのみだ
「己心の弥陀」に同じ。→己心(成句)
⇒こ‐しん【己身】
ごしん‐ふ【護身符】
護符ごふ。おふだ。
⇒ご‐しん【護身】
ご‐しんぷ【御親父】
相手の父の尊敬語。狂言、武悪「中にも―にあうて御ざる」
ごしん‐ぶつ【護身仏】
護身とする持仏。
⇒ご‐しん【護身】
こじん‐プレー【個人プレー】
集団で行うスポーツや仕事で、全体の利益を顧みず、個人の成績や名誉だけを重んずる行動。「―に走る」↔チームプレー。
⇒こ‐じん【個人】
こ‐しんぶん【小新聞】
明治前期の新聞の一形態。市井の出来事や花柳界の艶聞、通俗的読み物などを中心とした、紙面の寸法が小さい新聞。総ふりがなの平易な文章で綴られた大衆紙。当時の読売新聞・朝日新聞など。→大おお新聞→中ちゅう新聞
ご‐しんぺい【御親兵】
(→)親兵2に同じ。
ごしん‐ぼう【護身法】‥ボフ
〔仏〕密教で、行法を修する前に、衆生済度しゅじょうさいどのための慈悲心を甲冑のごとく身につけ身心を堅固に守護すると観想して修行の完成を祈る修法。印を結び、真言を誦する。
⇒ご‐しん【護身】
こじん‐メドレー【個人メドレー】
競泳の一種目。一人がバタフライ・背泳・平泳・自由形の順に泳ぎ、所要時間を競うもの。200メートルと400メートルとがある。
⇒こ‐じん【個人】
ごしん‐もじ【御心文字】
(女房詞)「おこころ」の意を表す文字詞。
ごしん‐もじ【御親文字】
(女房詞)「御親切」の意を表す文字詞。松の落葉「今の嬉しき―」
こじん‐りんり【個人倫理】
個人的生活に適用される道徳原理。個人主義の倫理説を指すこともある。↔社会倫理
⇒こ‐じん【個人】
こ‐す【小簾】
(オスの誤読)みす。すだれ。謡曲、遊行柳ゆぎょうやなぎ「―のひま漏りくる風のにほひより」
こ‐す【庫主】
〔仏〕
①延暦寺の僧職。仏供ぶくなどを調える下級の僧。
②禅寺の僧職。副寺ふうすに属して、出納をつかさどる。庫主の行者あんじゃ。
こ・す【居す】
〔自サ変〕
(コは「居」の呉音)いる。ある地位にある。きょす。太平記37「執事の職に―・して」
こ・す【越す・超す】
[一]〔自五〕
境界などを越えて進む意。
①行く。来る。去る。後拾遺和歌集雑「あづまぢのそのはらからは来たりともあふさかまでは―・さじとぞおもふ」。御伽草子、唐糸草子「御身たちは鎌倉へ―・すべきなり」。「宅へもお―・し下さい」
②引っ越す。移転する。「隣町に―・す」
[二]〔他五〕
障害や限界をなすものなどをのりこえる意。
①(ある領域にあるものを他所に)渡す。越えさせる。崇神紀「大坂に継ぎのぼれる石群を手越しに―・さば―・しかてむかも」
②(あるものの上を)通過する。万葉集14「広橋を馬―・しがねて」。古今和歌集冬「浦ちかく降りくる雪は白浪のすゑのまつやま―・すかとぞみる」
③前にあるものを抜いて先行する。追い越す。宇津保物語楼上下「大将を人より―・して大臣になして」。「先を―・す」
④時間・時節などを過ぎる。経過する。日葡辞書「トシヲコス」。世間胸算用2「こなたは若いが思案は一越し―・した年の暮」。「冬を―・す」
⑤障害となるものを通り過ぎる。困難なところを切りぬける。奥の細道「関守にあやしめられてやうやうとして関を―・す」。「難関を―・す」
⑥ある標準より上に出る。…以上になる。超過する。平家物語10「馬のくさわき、むながいづくし、太腹につくところもあり、鞍壺―・すところもあり」。「50を―・す」「1万人を―・す大観衆」
⑦ぬきんでる。まさる。ひいでる。「それに―・したことはない」
◇[二]6は「超す」と書くことが多い。
こ・す【遣す】
〔他四〕
(「おこす」の略)よこす。兼澄集「筑紫より来たる人に、すだれがはを乞ふを、今々とて―・さねば」→こす(助動)
こ・す【濾す・漉す】
〔他五〕
滓かすなどを取りわけるため細かい目を通す。濾過する。「味噌を―・す」
こ・す【挙す】
〔他サ変〕
①持ちあげる。日本霊異記上「礠石じしゃくの鉄山を―・して鉄を嘘すふ」
②推挙する。沙石集(一本)「老体の身ものうく侍り。―・し申さん」
こ・す【扈す】
〔自サ変〕
つき従う。ともをする。
こ・す【錮す】
〔他サ変〕
つなぎとどめる。禁錮する。
こ・す【餬す・糊す】
〔他サ変〕
口にのりする。口すぎをする。生活をする。
こす
〔助動〕
(活用は下二段型。用例は、未然形「こせ」・終止形「こす」・命令形「こせ」だけ。誂えの終助詞「こそ」を命令形とする説もある)動詞の連用形に付き、その動作が自分に係わり及ぶ意を表す。自分のために…する。…てくれる。万葉集5「梅の花今咲ける如散り過ぎず我が家の園にありこせぬかも」。万葉集11「我が後に生まれむ人は我が如く恋する道にあひこすなゆめ」。催馬楽、我が駒「いで我が駒早く行きこせ」。伊勢物語「ゆく蛍雲の上までいぬべくは秋風吹くと雁に告げこせ」
こ・ず【抉ず】
〔他上二〕
⇒こじる(上一)
こ・ず【掘ず】
〔他〕
(用例は連用形のみ、活用は上二段か四段か不明)根付きのまま引き抜く。根こそぎにする。万葉集8「去年こぞの春い―・じてうゑし」→根こじ
ご‐す【呉須】
①磁器の染付に用いる藍色顔料。中国に天然に産する唐呉須という多量の酸化コバルト・マンガン・鉄などを含む黒褐色の粘土を用いたが、近来は合成呉須を使用。呉州。呉須土。
②呉須手の略。
ご・す【期す】
〔他サ変〕
①かねてその時と定める。期待する。十訓抄「さしたる所作もなくて、そらに果報を―・せんこと」
②覚悟する。謡曲、安宅「かねて―・したることなれば惜しき命にあらねども」
ごす
〔助動〕
(「ごっす」の転)「ある」の丁寧な言い方。ございます。誹風柳多留41「あんで―なあなあとみつ物や」
ご‐ず【牛頭】‥ヅ
〔仏〕地獄にいるという牛頭人身の獄卒。→牛頭馬頭ごずめず
ごす‐あおえ【呉須青絵】‥アヲヱ
呉須赤絵で、赤絵具の代りに青を基本とした上絵付が施されたもの。青呉須。
ごす‐あかえ【呉須赤絵】‥ヱ
呉須手の一種。明末清初の頃に福建省漳州しょうしゅう付近で作られた、赤を基調とする色絵磁器。大皿など多くを輸出。赤絵呉須。
こ‐すい【巨水】
大海の水。大水。謡曲、白楽天「―漫々として碧浪天を浸し」
こ‐すい【胡荽】
〔植〕コエンドロの漢名。〈伊呂波字類抄〉
こ‐すい【湖水】
みずうみ。森鴎外、うたかたの記「―の畔なる漁師の家にて」
⇒こすい‐ちほう【湖水地方】
こ‐すい【鼓吹】
①鼓と笛とを主な楽器とする軍用の楽。また、鼓を打ち笛を吹くこと。くすい。
②勢いをつけはげますこと。鼓舞。
③意見・思想を盛んに主張して他の共鳴を得ようとすること。「軍国主義を―する」
⇒こすい‐し【鼓吹司】
こす・い【狡い】
〔形〕[文]こす・し(ク)
①わるがしこい。ずるい。狂言、馬口労ばくろう「をのれは―・い事をしおる」。「やり方が―・い」
②けちである。吝嗇りんしょくである。炭俵「年の暮互ひに―・き銭遣ひ」
ご‐すい【五衰】
〔仏〕欲界の天人が命尽きようとする時に現れるという五種の衰亡の相。涅槃経によると、衣服垢穢・頭上華萎・身体臭穢・腋下汗流・不楽本座の五相。経によって諸説があり、倶舎論では五種の大衰相と小衰相があるという。天人の五衰。
ご‐すい【午睡】
昼ねること。ひるね。〈[季]夏〉。「―をとる」
ご‐ずい【五瑞】
五つのめでたいもの。
㋐黄竜・白虎・喜楽・甘露・木連理。
㋑文人画の5種の画題。葵・菖蒲・蓮・柘榴・枇杷。
㋒[書経舜典]天子が五爵の諸侯に賜るしるしの玉。桓圭(公)・信圭(侯)・躬圭(伯)・穀璧(子)・蒲璧(男)。
コスイギン【Aleksei Nikolaevich Kosygin】
ソ連の政治家。ブレジネフ時代の首相(1964〜1980)。経済改革を推進。(1904〜1980)
こすい‐し【鼓吹司】
⇒くすいし
⇒こ‐すい【鼓吹】
こ‐ずいじん【小随身】
近衛の中・少将、左・右衛門、左・右兵衛に仕える随身。
こすい‐ちほう【湖水地方】‥ハウ
(Lake District)イングランドの北西部、ウェストモーランド・カンバーランド・ランカシャー地方にまたがる地域。国立公園に指定。渓谷沿いに小さな湖が無数に連なり、古くからリゾート地。
⇒こ‐すい【湖水】
ごすい‐もじ【御推文字】
「御推量」の文字詞。ごすもじ。おすいもじ。浄瑠璃、鎌倉三代記「三浦の助と―の上は名乗るに及ばず」
こ‐すう【戸数】
家の数。やかず。
⇒こすう‐わり【戸数割】
こ‐すう【個数】
物の数。員数。
⇒こすう‐ちんぎん【個数賃金】
ご‐すう【語数】
ことばの数。単語数。
ごすう‐せい【五数性】
〔生〕植物の花で、花弁・萼片がくへんがそれぞれ5枚あるもの。ウツギ・ノイバラ・キキョウの花はその例。
こすう‐ちんぎん【個数賃金】
(→)出来高給に同じ。
⇒こ‐すう【個数】
こすう‐わり【戸数割】
一戸を構える者または一戸を構えなくても独立の生計を営む者を単位として、これに賦課した市町村の特別税。1878年(明治11)定められ、1940年廃止。
⇒こ‐すう【戸数】
こ‐ずえ【梢・杪】‥ズヱ
(「木末」の意)幹や枝の先の部分。
⇒こずえ‐の‐あき【梢の秋】
⇒こずえ‐の‐とこ【梢の床】
⇒こずえ‐の‐ゆき【梢の雪】
こずえ‐の‐あき【梢の秋】‥ズヱ‥
(梢の色づく秋に末をかけていう語)秋の末。陰暦9月の異称。八雲御抄「九月、ながつき、―」
⇒こ‐ずえ【梢・杪】
こずえ‐の‐とこ【梢の床】‥ズヱ‥
梢にかけた鳥の巣。正治百首「むら烏―をあらそひて」
⇒こ‐ずえ【梢・杪】
こずえ‐の‐ゆき【梢の雪】‥ズヱ‥
梢の花を降りつもる雪に見たてていう語。続後拾遺和歌集春「見るままに―はかつはれて散りかひくもる山桜かな」
⇒こ‐ずえ【梢・杪】
こずえ‐ばば【子ずえ婆】
(九州地方で)産婆。コズイババとも。「すえる」は「添える」の転か。人間の仲間に加える義という。
こ‐すおう【小素襖】‥アヲ
小形の素襖。鰭袖はたそでをつけずに、四幅よのの短い小袴を用いる。小素袍。
こ‐ずか‥ヅカ
(カミヅカ(髪束)の音便カウヅカの約)たぶさ。もとどり。
こす‐から・い【狡辛い】
〔形〕
⇒こすっからい
こ‐すき【木鋤・杴】
全体が木製の鋤。〈倭名類聚鈔15〉
こ‐すき【樹透】
樹木の間のすきま。源平盛衰記36「伏木、磯道をも嫌はず―を守りて」
こ‐すぎ【小杉】
①小さい杉。
②小杉原こすぎわらの略。日本永代蔵5「鼻紙に―入れしを見て」
こすぎ【小杉】
姓氏の一つ。
⇒こすぎ‐てんがい【小杉天外】
⇒こすぎ‐ほうあん【小杉放庵】
こ‐すぎごけ【小杉苔】
蘚類スギゴケ科の一種。茎葉体は直立し、高さ1〜5センチメートル。葉は乾くと縮れる。頂端細胞は台形で中央がへこむ。雌雄同株。低地に密な群落をつくる。
こすぎ‐てんがい【小杉天外】‥グワイ
小説家。名は為蔵。秋田県生れ。国民英学会卒。斎藤緑雨の知遇を得て作家として出発、ゾラの自然主義に学んで「はつ姿」「はやり唄」などを書く。新風俗の女子学生を描いた「魔風恋風」で人気を博した。(1865〜1952)
小杉天外
撮影:石井幸之助
 ⇒こすぎ【小杉】
こすぎ‐ばら【子過ぎ腹】
子を多く産み過ぎた腹。
こすぎ‐ほうあん【小杉放庵】‥ハウ‥
洋画家。名は国太郎。別号、未醒。栃木県生れ。院展洋画部、のち春陽会に属し、装飾的な独自の画風をもち、日本画もよくした。作「水郷」など。(1881〜1964)
⇒こすぎ【小杉】
こ‐すぎわら【小杉原】‥ハラ
小判の杉原紙。鼻紙などに用いる。小杉。
こすげ【小菅】
東京都葛飾区北西部の地名。1877年(明治10)以来、小菅監獄(現、東京拘置所)が置かれた。
ごず‐こう【牛頭香】‥ヅカウ
(→)牛頭栴檀ごずせんだんに同じ。
ごすこう‐いん【後崇光院】‥クワウヰン
伏見宮栄仁よしひと親王の子。名は貞成さだふさ。後花園天皇の父。剃髪して道欽と号。太上天皇の尊号を受けた。著「看聞御記かんもんぎょき」「椿葉記」など。(1372〜1456)
ごすざく‐てんのう【後朱雀天皇】‥ワウ
平安中期の天皇。一条天皇の第3皇子。名は敦良あつなが。母は藤原彰子。(在位1036〜1045)(1009〜1045)→天皇(表)
ごす‐さま【御所様】
摂家・大臣などの子女が、その父を呼ぶ語。ごすさん。
こ‐すずめ【小雀】
春に生まれた、小さい雀。雀の子。〈[季]春〉
こ‐すずり【小硯】
小形の硯。箱に入れて懐中して用いるものもあり、懐硯ふところすずりという。平家物語1「懐より―畳紙を取り出し」
ごず‐せんだん【牛頭栴檀】‥ヅ‥
(南天竺の牛頭山(摩羅耶山)に産する栴檀から製したという)熱帯地方産の麝香じゃこうの香のする香料。万病を除くという。牛頭香ごずこう。
ごす‐そめつけ【呉須染付】
呉須手の磁器で、白地に藍だけで文様を描いたもの。明末清初の頃、福建省漳州しょうしゅう付近から産出。
コスタ‐デル‐ソル【Costa del Sol】
(「太陽の海岸」の意)スペイン南部、アンダルシア地方の地中海沿岸地域。マラガ・トレモリーノス・マルベージャなどの都市を中心とする保養地。
コスタ‐デル‐ソルの海
撮影:小松義夫
⇒こすぎ【小杉】
こすぎ‐ばら【子過ぎ腹】
子を多く産み過ぎた腹。
こすぎ‐ほうあん【小杉放庵】‥ハウ‥
洋画家。名は国太郎。別号、未醒。栃木県生れ。院展洋画部、のち春陽会に属し、装飾的な独自の画風をもち、日本画もよくした。作「水郷」など。(1881〜1964)
⇒こすぎ【小杉】
こ‐すぎわら【小杉原】‥ハラ
小判の杉原紙。鼻紙などに用いる。小杉。
こすげ【小菅】
東京都葛飾区北西部の地名。1877年(明治10)以来、小菅監獄(現、東京拘置所)が置かれた。
ごず‐こう【牛頭香】‥ヅカウ
(→)牛頭栴檀ごずせんだんに同じ。
ごすこう‐いん【後崇光院】‥クワウヰン
伏見宮栄仁よしひと親王の子。名は貞成さだふさ。後花園天皇の父。剃髪して道欽と号。太上天皇の尊号を受けた。著「看聞御記かんもんぎょき」「椿葉記」など。(1372〜1456)
ごすざく‐てんのう【後朱雀天皇】‥ワウ
平安中期の天皇。一条天皇の第3皇子。名は敦良あつなが。母は藤原彰子。(在位1036〜1045)(1009〜1045)→天皇(表)
ごす‐さま【御所様】
摂家・大臣などの子女が、その父を呼ぶ語。ごすさん。
こ‐すずめ【小雀】
春に生まれた、小さい雀。雀の子。〈[季]春〉
こ‐すずり【小硯】
小形の硯。箱に入れて懐中して用いるものもあり、懐硯ふところすずりという。平家物語1「懐より―畳紙を取り出し」
ごず‐せんだん【牛頭栴檀】‥ヅ‥
(南天竺の牛頭山(摩羅耶山)に産する栴檀から製したという)熱帯地方産の麝香じゃこうの香のする香料。万病を除くという。牛頭香ごずこう。
ごす‐そめつけ【呉須染付】
呉須手の磁器で、白地に藍だけで文様を描いたもの。明末清初の頃、福建省漳州しょうしゅう付近から産出。
コスタ‐デル‐ソル【Costa del Sol】
(「太陽の海岸」の意)スペイン南部、アンダルシア地方の地中海沿岸地域。マラガ・トレモリーノス・マルベージャなどの都市を中心とする保養地。
コスタ‐デル‐ソルの海
撮影:小松義夫
 コスタ‐リカ【Costa Rica】
(「豊かな海岸」の意)中米南部の共和国。1821年スペインから独立。パナマの西端に接する。住民はヨーロッパ系が主で、言語はスペイン語。憲法で非武装中立を規定。面積5万1000平方キロメートル。人口425万(2004)。首都サンホセ。→中央アメリカ(図)。
⇒コスタリカ‐ほうしき【コスタリカ方式】
コスタリカ‐ほうしき【コスタリカ方式】‥ハウ‥
(国会議員の連続再選を禁止するコスタリカの制度を参考にしたところからという)同一政党に属する複数の候補者が、選挙ごとに小選挙区と比例代表区とに交代で立候補する方式。
⇒コスタ‐リカ【Costa Rica】
こ‐すだれ【小簾】
小形のすだれ。多く、車輿くるまごしにかける。
コスチューム【costume】
①特定の民族・階級・時代・地方の服装。髪型・装身具も含めていう。
②仮装・演劇などの衣装。
③上下揃いの婦人服。
⇒コスチューム‐プレー【costume play】
コスチューム‐プレー【costume play】
①俳優の衣装の視覚的効果をねらった劇。特に歴史劇や歴史映画をいう。衣装劇。時代劇。
②(日本での用法)漫画・アニメの登場人物などの扮装をして楽しむこと。コスプレ。
⇒コスチューム【costume】
こすっ‐から・い【狡っ辛い】
〔形〕
(コスカライの転)うまく立ち回って利を得ようとするたちである。ずるくて抜け目がない。
ごす‐で【呉須手】
中国南部、福建・広東地方で明末清初の頃に焼かれた磁器。粗製で奔放な絵模様を描くが、日本の茶人が呉須赤絵・呉須染付などと称し珍重。呉州手。呉須。
ごず‐てんのう【牛頭天王】‥ヅ‥ワウ
〔仏〕もとインドの祇園精舎の守護神で、薬師如来の垂迹すいじゃくとされる。除疫神として、京都祇園社(八坂神社)などに祀られる。頭上に牛の頭を持つ忿怒相に表される。
コスト【cost】
①値段。費用。
②原価。生産費。
⇒コスト‐アップ【cost up】
⇒コスト‐インフレ
⇒コスト‐ダウン【cost down】
⇒コスト‐パフォーマンス【cost performance】
⇒コスト‐プッシュ‐インフレーション【cost-push inflation】
⇒コスト‐われ【コスト割れ】
コスト‐アップ【cost up】
生産費が上昇すること。
⇒コスト【cost】
コスト‐インフレ
(cost inflation)(→)コスト‐プッシュ‐インフレーションに同じ。
⇒コスト【cost】
コスト‐ダウン【cost down】
生産費が減少すること。
⇒コスト【cost】
コスト‐パフォーマンス【cost performance】
①投入される費用や作業量に対する成果の割合。
②機械などで、性能と価格との比。
⇒コスト【cost】
コスト‐プッシュ‐インフレーション【cost-push inflation】
賃金や原材料費などのコストの上昇が生産性の伸びを上回ったために生ずるインフレーション。売手インフレーション。コスト‐インフレ。↔デマンド‐プル‐インフレーション。
⇒コスト【cost】
コストレ【Guillaume Costeley】
フランスの作曲家。100曲以上の多声シャンソンを作曲。コトレ。(1530頃〜1606)
コスト‐われ【コスト割れ】
実際の売値が原価を下回ること。
⇒コスト【cost】
こすのと【小簾の戸】
地歌。端歌物。峰崎勾当作曲。癪がきっかけで生まれた恋を歌ったもの。小簾の外。
ゴスバンク【Gosbank ロシア】
ソ連の国立中央銀行。1922年営業を開始。92年ロシア中央銀行に改組。
ゴスプラン【Gosplan ロシア】
ソ連の国家計画委員会。1921年創設。5カ年計画など経済計画を作成。
ゴスペル【gospel】
①福音。
②福音書。新約聖書に収めた4福音書の総称。
③ゴスペル‐ソングの略。
⇒ゴスペル‐ソング【gospel song】
ゴスペル‐ソング【gospel song】
黒人霊歌・ジャズ・ブルースなどの影響を受けた福音歌。アメリカの黒人教会で1920年代からさかんになった。現在は教会の外でも広くうたわれる。ゴスペル。
⇒ゴスペル【gospel】
こすみ【尖】
囲碁で、盤上の石から斜めに連ねて打つ手。こすみつけ。
こ‐すみ【小隅・小角】
かたすみ。すみっこ。
こ‐ずみ【小炭】
最初小さく切った木を燃やし、急に沢山の木片を覆い、ある程度焼き、水をかけて消して作った炭。古い製炭法。
こ‐ずみ【粉炭】
炭が砕けて粉となったもの。こなずみ。
こ‐ずみ【濃墨】
墨色の濃いもの。源氏物語少女「―、うすずみ、さうがちにうちまぜ乱れたるも」
ご‐ずみ【後炭】
茶道で濃茶がすんで薄茶に移るまでに、再び炭をついで湯が沸き立つようにすること。のちのすみ。
こず・む【偏む】コヅム
〔自五〕
①かたよる。傾く。特に、馬がつまずいて倒れかかる。古今著聞集10「ふまへられて、馬かい―・みて、やすやすととどまりにけり」
②一つ所にかたよって集まる。ぎっしりと詰まる。混む。
③筋肉が凝こる。「肩が―・む」
④気持が暗くなる。心持ちがねじれてくる。
コスメ
コスメチックの略。化粧品全般を指す。
ごず‐めず【牛頭馬頭】‥ヅ‥ヅ
〔仏〕地獄の獄卒で、牛頭人身のものと馬頭人身のもの。
牛頭馬頭
コスタ‐リカ【Costa Rica】
(「豊かな海岸」の意)中米南部の共和国。1821年スペインから独立。パナマの西端に接する。住民はヨーロッパ系が主で、言語はスペイン語。憲法で非武装中立を規定。面積5万1000平方キロメートル。人口425万(2004)。首都サンホセ。→中央アメリカ(図)。
⇒コスタリカ‐ほうしき【コスタリカ方式】
コスタリカ‐ほうしき【コスタリカ方式】‥ハウ‥
(国会議員の連続再選を禁止するコスタリカの制度を参考にしたところからという)同一政党に属する複数の候補者が、選挙ごとに小選挙区と比例代表区とに交代で立候補する方式。
⇒コスタ‐リカ【Costa Rica】
こ‐すだれ【小簾】
小形のすだれ。多く、車輿くるまごしにかける。
コスチューム【costume】
①特定の民族・階級・時代・地方の服装。髪型・装身具も含めていう。
②仮装・演劇などの衣装。
③上下揃いの婦人服。
⇒コスチューム‐プレー【costume play】
コスチューム‐プレー【costume play】
①俳優の衣装の視覚的効果をねらった劇。特に歴史劇や歴史映画をいう。衣装劇。時代劇。
②(日本での用法)漫画・アニメの登場人物などの扮装をして楽しむこと。コスプレ。
⇒コスチューム【costume】
こすっ‐から・い【狡っ辛い】
〔形〕
(コスカライの転)うまく立ち回って利を得ようとするたちである。ずるくて抜け目がない。
ごす‐で【呉須手】
中国南部、福建・広東地方で明末清初の頃に焼かれた磁器。粗製で奔放な絵模様を描くが、日本の茶人が呉須赤絵・呉須染付などと称し珍重。呉州手。呉須。
ごず‐てんのう【牛頭天王】‥ヅ‥ワウ
〔仏〕もとインドの祇園精舎の守護神で、薬師如来の垂迹すいじゃくとされる。除疫神として、京都祇園社(八坂神社)などに祀られる。頭上に牛の頭を持つ忿怒相に表される。
コスト【cost】
①値段。費用。
②原価。生産費。
⇒コスト‐アップ【cost up】
⇒コスト‐インフレ
⇒コスト‐ダウン【cost down】
⇒コスト‐パフォーマンス【cost performance】
⇒コスト‐プッシュ‐インフレーション【cost-push inflation】
⇒コスト‐われ【コスト割れ】
コスト‐アップ【cost up】
生産費が上昇すること。
⇒コスト【cost】
コスト‐インフレ
(cost inflation)(→)コスト‐プッシュ‐インフレーションに同じ。
⇒コスト【cost】
コスト‐ダウン【cost down】
生産費が減少すること。
⇒コスト【cost】
コスト‐パフォーマンス【cost performance】
①投入される費用や作業量に対する成果の割合。
②機械などで、性能と価格との比。
⇒コスト【cost】
コスト‐プッシュ‐インフレーション【cost-push inflation】
賃金や原材料費などのコストの上昇が生産性の伸びを上回ったために生ずるインフレーション。売手インフレーション。コスト‐インフレ。↔デマンド‐プル‐インフレーション。
⇒コスト【cost】
コストレ【Guillaume Costeley】
フランスの作曲家。100曲以上の多声シャンソンを作曲。コトレ。(1530頃〜1606)
コスト‐われ【コスト割れ】
実際の売値が原価を下回ること。
⇒コスト【cost】
こすのと【小簾の戸】
地歌。端歌物。峰崎勾当作曲。癪がきっかけで生まれた恋を歌ったもの。小簾の外。
ゴスバンク【Gosbank ロシア】
ソ連の国立中央銀行。1922年営業を開始。92年ロシア中央銀行に改組。
ゴスプラン【Gosplan ロシア】
ソ連の国家計画委員会。1921年創設。5カ年計画など経済計画を作成。
ゴスペル【gospel】
①福音。
②福音書。新約聖書に収めた4福音書の総称。
③ゴスペル‐ソングの略。
⇒ゴスペル‐ソング【gospel song】
ゴスペル‐ソング【gospel song】
黒人霊歌・ジャズ・ブルースなどの影響を受けた福音歌。アメリカの黒人教会で1920年代からさかんになった。現在は教会の外でも広くうたわれる。ゴスペル。
⇒ゴスペル【gospel】
こすみ【尖】
囲碁で、盤上の石から斜めに連ねて打つ手。こすみつけ。
こ‐すみ【小隅・小角】
かたすみ。すみっこ。
こ‐ずみ【小炭】
最初小さく切った木を燃やし、急に沢山の木片を覆い、ある程度焼き、水をかけて消して作った炭。古い製炭法。
こ‐ずみ【粉炭】
炭が砕けて粉となったもの。こなずみ。
こ‐ずみ【濃墨】
墨色の濃いもの。源氏物語少女「―、うすずみ、さうがちにうちまぜ乱れたるも」
ご‐ずみ【後炭】
茶道で濃茶がすんで薄茶に移るまでに、再び炭をついで湯が沸き立つようにすること。のちのすみ。
こず・む【偏む】コヅム
〔自五〕
①かたよる。傾く。特に、馬がつまずいて倒れかかる。古今著聞集10「ふまへられて、馬かい―・みて、やすやすととどまりにけり」
②一つ所にかたよって集まる。ぎっしりと詰まる。混む。
③筋肉が凝こる。「肩が―・む」
④気持が暗くなる。心持ちがねじれてくる。
コスメ
コスメチックの略。化粧品全般を指す。
ごず‐めず【牛頭馬頭】‥ヅ‥ヅ
〔仏〕地獄の獄卒で、牛頭人身のものと馬頭人身のもの。
牛頭馬頭
 コスメチック【cosmetic イギリス・cosmétique フランス】
①化粧品。
②白蝋・牛脂・パラフィンなどに香料を加え、練り固めた整髪用の化粧品。チック。泉鏡花、黒百合「島野は総すべてコスメチツク、香水、巻莨シガレット、洋杖ステッキ、護謨ゴム靴といふ才子肌」
コスメッツ【COSMETS】
(Computer System for Meteorological Services)気象資料総合処理システム。気象庁に設置される。国内外との情報交換とその資料の情報処理を総合的にオンライン‐リアルタイム方式で行うコンピューター‐システム。→アデス→ナプス
こ‐ずもう【小相撲・小角力】‥ズマフ
①相撲取りの弟子。地位の低い力士。
②本相撲にまねて相撲を取ること。また、その相撲。しろうと相撲。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「若い時は―の一番もひねつた俺ぢや」
⇒こずもう‐とり【小相撲取】
こずもう‐とり【小相撲取】‥ズマフ‥
しろうとの相撲取り。狂言、飛越「それが―からとりあがつて、大相撲になつて後」
⇒こ‐ずもう【小相撲・小角力】
コスモス【kosmos ギリシア・cosmos イギリス】
①美しい秩序。転じて、それ自身のうちに秩序と調和とをもつ宇宙または世界の意。「ミクロ‐―」↔カオス。
②〔植〕キク科の一年草。メキシコ原産。高さ約1.5メートルに達する。葉は線状に細裂。秋、大形の頭状花を開く。色は白・淡紅・深紅など。秋桜。おおハルシャぎく。〈[季]秋〉
コスモス
撮影:関戸 勇
コスメチック【cosmetic イギリス・cosmétique フランス】
①化粧品。
②白蝋・牛脂・パラフィンなどに香料を加え、練り固めた整髪用の化粧品。チック。泉鏡花、黒百合「島野は総すべてコスメチツク、香水、巻莨シガレット、洋杖ステッキ、護謨ゴム靴といふ才子肌」
コスメッツ【COSMETS】
(Computer System for Meteorological Services)気象資料総合処理システム。気象庁に設置される。国内外との情報交換とその資料の情報処理を総合的にオンライン‐リアルタイム方式で行うコンピューター‐システム。→アデス→ナプス
こ‐ずもう【小相撲・小角力】‥ズマフ
①相撲取りの弟子。地位の低い力士。
②本相撲にまねて相撲を取ること。また、その相撲。しろうと相撲。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「若い時は―の一番もひねつた俺ぢや」
⇒こずもう‐とり【小相撲取】
こずもう‐とり【小相撲取】‥ズマフ‥
しろうとの相撲取り。狂言、飛越「それが―からとりあがつて、大相撲になつて後」
⇒こ‐ずもう【小相撲・小角力】
コスモス【kosmos ギリシア・cosmos イギリス】
①美しい秩序。転じて、それ自身のうちに秩序と調和とをもつ宇宙または世界の意。「ミクロ‐―」↔カオス。
②〔植〕キク科の一年草。メキシコ原産。高さ約1.5メートルに達する。葉は線状に細裂。秋、大形の頭状花を開く。色は白・淡紅・深紅など。秋桜。おおハルシャぎく。〈[季]秋〉
コスモス
撮影:関戸 勇
 コスモポリス【cosmopolis】
(→)国際都市。
コスモポリタニズム【cosmopolitanism】
国家や民族を超越して、全人類を同胞と見なし、世界市民としての個人によって世界社会を実現しようとする思想。古くはキニク学派・ストア学派などがこの考えを唱えた。国民主義思想の勃興とともに諸国家の協同をめざす国際主義に代わったが、第二次大戦後に再び提唱。世界(市民)主義。四海同胞主義。万民主義。公民主義。
⇒コスモポリタニズム‐ひはん【コスモポリタニズム批判】
コスモポリタニズム‐ひはん【コスモポリタニズム批判】
ソ連のユダヤ人攻撃のキャンペーン。1949年ユダヤ人の学者・文化人を「根なしのコスモポリタン」と非難、多数の逮捕・投獄者を出した。
⇒コスモポリタニズム【cosmopolitanism】
コスモポリタン【cosmopolitan】
①コスモポリタニズムを信奉する人。世界主義者。
②国境や国籍にとらわれず、世界を股にかける人。国際人。
コスモロジー【cosmology】
宇宙論。
こすり【擦り・錯】
①こすること。ざらざらしたものをすりみがくこと。狂言、太刀奪たちばい「まづおのれ此縄に―をかけて」
②やすりをかけること。
③鑢やすりの異称。新撰字鏡6「錯、鑢也、己須利、又也須利、又乃保支利」
④木片に木賊とくさの枯茎を貼り付け、木などを磨くもの。
こすり‐つ・く【擦り付く】
[一]〔自五〕
こするように近寄る。
[二]〔他下二〕
⇒こすりつける(下一)
こすり‐つ・ける【擦り付ける】
〔他下一〕[文]こすりつ・く(下二)
押しつけてなすりつける。力を入れてこする。「靴の泥を石に―・ける」
こす・る【擦る・錯る】
〔他五〕
①おしつけて摩擦する。すりみがく。夏目漱石、三四郎「寐てゐた男がむつくり起きて眼を―・りながら下りて行つた」
②あてこする。いやみをいう。誹風柳多留23「どうるいがあると母親―・られる」
こ・する【鼓する】
〔他サ変〕[文]鼓す(サ変)
①うちならす。かきならす。
②ふるわす。おこす。「勇を―・する」
ご・する【伍する】
〔自サ変〕[文]伍す(サ変)
仲間に入る。同等の位置にならぶ。肩を並べる。「先輩に―・して活躍する」
こす・れる【擦れる】
〔自下一〕
互いにすれあう。
コスロー【Khosrō】
⇒ホスロー
コズロフ【Petr Kuzimich Kozlov】
ロシアの軍人・探検家。カラホトで西夏の古都市を、のち北モンゴルのノインウラで匈奴王の墓を発掘。(1863〜1935)
ご‐すん【五寸】
①1寸の5倍。
②五寸局ごすんつぼねの略。
⇒ごすん‐くぎ【五寸釘】
⇒ごすん‐つぼね【五寸局】
⇒ごすん‐もよう【五寸模様】
ごすん‐くぎ【五寸釘】
大形の釘。長さ曲尺かねじゃく5寸位(約15センチメートル)の釘。
⇒ご‐すん【五寸】
ごすん‐つぼね【五寸局】
一切りの揚代、銀5匁の局女郎。
⇒ご‐すん【五寸】
ごすん‐もよう【五寸模様】‥ヤウ
宝暦(1751〜1764)の頃流行した、着物の裾模様で、裾から5寸ほどの範囲に模様を置いたもの。
⇒ご‐すん【五寸】
こせ【巨勢】
姓氏の一つ。大和の古代豪族。高市郡巨勢郷(今、奈良県御所市古瀬)を本拠とする。武内宿祢の後裔と称す。許勢。
⇒こせ‐の‐かなおか【巨勢金岡】
こせ【瘡】
「こせがさ」の略。散木奇歌集「怪しさはみなもととこそ思ひつれ膚はだえは―のうちにぞありける」
ご‐せ【後世】
〔仏〕
①三世の一つ。死後に生まれ変わる世界。あの世。来世。ごせい。
②(→)後生善処ごしょうぜんじょに同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「最期に心乱れては人の譏り―のため」
⇒後世を弔う
ごせ【御所】
奈良県西部、大阪府に接する市。葛城地方の中心都市。製薬・繊維工業が盛ん。古代史跡が多い。人口3万2千。
ご‐ぜ【御前】
①(御前駆ごぜんくの略)(→)「みさきおい」に同じ。今昔物語集31「指貫さしぬき姿の―ども十余人」
②貴婦人の尊敬語。今昔物語集31「わが―たちの御あたりには」
③(接尾語的に用いる)女性の尊敬語。「姫―」→ごぜん
ご‐ぜ【瞽女】
(「御前ごぜ」から)三味線を弾き、唄を歌いなどして米や金銭を得た盲目の女。めくらごぜ。
こ‐せい【古生】
⇒こせい‐かい【古生界】
⇒こせい‐そう【古生層】
⇒こせい‐だい【古生代】
こ‐せい【古制】
古い時代の制度。昔のおきて。
こ‐せい【古製】
古い時代のつくり。昔の製作。
こ‐せい【呼声】
呼ばわる声。よびごえ。
こ‐せい【個性】
①(individuality)個人に具わり、他の人とはちがう、その個人にしかない性格・性質。「―を伸ばす」
②個物または個体に特有な特徴あるいは性格。
⇒こせい‐てき【個性的】
こ‐せい【糊精】
〔化〕(→)デキストリンに同じ。
こ‐ぜい【小勢】
①人数の少ない軍勢。太平記4「思ふには似ず、―なりけりと」
②少ない人数。小人数。↔大勢
こ‐ぜい【挙税】
奈良・平安時代、稲穀・銭貨を貸し出して利息を取ったこと。出挙稲すいことう。出挙銭。
ご‐せい【五声】
〔音〕
①日本・中国の音楽で、低音から宮きゅう・商しょう・角かく・徴ち・羽うの5音。また、その構成する音階。五音ごいん。→七声。
②(→)五音ごおん音階に同じ。
ご‐せい【五星】
①五つの星。
②[左伝襄公28年、注]中国で古代から知られている五惑星、すなわち歳星(木星)・熒惑けいごく(火星)・鎮星(土星)・太白(金星)・辰星(水星)の総称。五緯。
⇒ごせい‐こうき【五星紅旗】
ご‐せい【五牲】
[左伝昭公、注]いけにえに用いる5種の動物、すなわち牛・羊・豕いのこ・犬・鶏。また、麏くじか・鹿・熊・狼・野豕の総称。
ご‐せい【五清】
(画題)文人画で五つの清いものを描くこと。松・竹・梅・蘭・石。あるいは松・竹・蘭・芭蕉・石。また、梅・菊・竹・芭蕉・石。
ご‐せい【五聖】
中国古代の5人の聖人。通説では、尭ぎょう・舜しゅん・禹う・湯とう・文王をいう。
ご‐せい【互生】
〔植〕茎や枝に交互に1枚ずつ葉を生じること。サクラ・アサガオの類。互生葉序。→葉序(図)
ご‐せい【後世】
⇒ごせ。
⇒ごせい‐ほう【後世方】
ご‐せい【悟性】
〔哲〕(intellect イギリス・Verstand ドイツ)
①広義には、思考の能力。
②カントにおいては、感性に与えられる所与を認識へと構成する概念能力・判断能力で、理性と感性の中間にあり、科学的思考の主体。
③ヘーゲルにおいては、弁証法的思考能力としての理性に対して、対象を固定的にとらえ、他との区別に固執する思考能力。
⇒ごせい‐がいねん【悟性概念】
ご‐せい【碁聖】
傑出した囲碁の名手。棋聖きせい。
ご‐せい【語勢】
語ることばのいきおい。語気。語調。「―を強める」
こせい‐かい【古生界】
古生代に形成された堆積岩と火成岩。変成岩に関しては、原岩が古生代に作られたもの。
⇒こ‐せい【古生】
ごせい‐がいねん【悟性概念】
(→)範疇はんちゅう1に同じ。
⇒ご‐せい【悟性】
ごせい‐こうき【五星紅旗】
中華人民共和国の国旗。長方形紅地の左上方に、大きい1個の星と、これを弧状に囲む4個の小さい星とを黄色に染め抜く。
⇒ご‐せい【五星】
こせい‐せん【湖西線】
琵琶湖西岸を走り、東海道・北陸両本線を結ぶJR線。山科・近江塩津間、全長74.1キロメートル。
こせい‐そう【古生層】
古生代に堆積した地層。日本列島には、古生代にできた岩塊が中生層の中にとりこまれている所が多く、このような中生層は20世紀前半に秩父古生層の名でよばれていた。
⇒こ‐せい【古生】
こせい‐だい【古生代】
(Pal(a)eozoic Era)地質年代中、原生代の後、中生代の前の時代。約5億4000万年前から2億5000万年前までの時代。カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀に分ける。この時代には植物は主に隠花植物(藻類・シダ類など)、動物は主に海生の無脊椎動物(筆石・珊瑚類・海百合・腕足類など)が栄えた。古生代中頃のシルル紀末に、生物は初めて陸上に進出。→地質年代(表)
⇒こ‐せい【古生】
こ‐せいたいがく【個生態学】
動物の各種につき、その食性・繁殖その他一切の生活様式を研究する学問。種生態学とほぼ同義。↔群集生態学
こせい‐てき【個性的】
個性が表れているさま。独特なさま。「―な文章」「―な顔立ち」
⇒こ‐せい【個性】
ごせいばい‐しきもく【御成敗式目】
鎌倉幕府の基本的法典。1232年(貞永1)北条泰時が承久の乱後の当面する政治・法制の諸問題に対処するために編纂。51カ条から成り、室町幕府も武家の根本法として継承。江戸時代には手習手本として民間に普及。貞永じょうえい式目。
→文献資料[御成敗式目]
こ‐せいぶつ【古生物】
地質時代に生息していた生物の総称。マンモス・恐竜・アンモナイト・三葉虫さんようちゅう・蘆木ろぼくなどの類。
⇒こせいぶつ‐がく【古生物学】
⇒こせいぶつ‐ちりがく【古生物地理学】
こせいぶつ‐がく【古生物学】
(pal(a)eontology)古生物の系統・分類・進化・構造・生理・生態・地理的分布などを研究する学問分野。
⇒こ‐せいぶつ【古生物】
こせいぶつ‐ちりがく【古生物地理学】
化石を用いて地球史における生物の地理的分布を研究する学問分野。→生物地理学
⇒こ‐せいぶつ【古生物】
ごせい‐ほう【後世方】‥ハウ
鎌倉時代末期以降伝えられた中国の金・元の医家の処方を祖述する医家の一派。これを奉ずる医家を後世家とよび、田代三喜・曲直瀬まなせ道三・曲直瀬玄朔(1549〜1631)はその代表者。こうせいほう。↔古医方
⇒ご‐せい【後世】
ごぜ‐うた【瞽女歌】
瞽女のうたう歌。門口でうたう門付け歌のほか、段物と口説くどきを語った。山椒太夫などの段物は瞽女節とも呼んだ。越後口説も知られる。
ごぜえ・す
〔自サ変〕
「ある」「居る」を丁寧にいう語。ございます。(遊里語であるが、一般の人にも使われた)浮世床初「大学ぢやあ―・せんねえ」
こせ‐がさ
「がんがさ(雁瘡)」の異称。こせ。
こせがさわ‐いせき【小瀬ヶ沢遺跡】‥サハヰ‥
新潟県東蒲原郡阿賀町にある縄文時代草創期から早期の洞穴遺跡。縄文草創期を代表する土器・石器が出土。
こ‐せがれ【小倅】
①自分の息子の謙称。
②青年・少年をののしっていう語。
コセカント【cosecant】
〔数〕三角関数の一つ。サインの逆数。余割よかつ。記号cosec →三角関数
こせき【小関】
姓氏の一つ。
⇒こせき‐さんえい【小関三英】
こ‐せき【戸籍】
①戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にはほぼ廃絶。明治維新後復活した。へじゃく。→庚午年籍→壬申戸籍。
②国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書。
⇒こせき‐げんぽん【戸籍原本】
⇒こせき‐しょうほん【戸籍抄本】
⇒こせき‐とうほん【戸籍謄本】
⇒こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
⇒こせき‐ぼ【戸籍簿】
⇒こせき‐ほう【戸籍法】
こ‐せき【古昔】
むかし。いにしえ。
こ‐せき【古跡・古蹟】
歴史上有名な出来事や建物のあった跡。旧跡。
こせき【古関】
姓氏の一つ。
⇒こせき‐ゆうじ【古関裕而】
こ‐ぜき【小関】
要所に設けて敵の出入を防ぐ小さい関所。特に、山城国宇治郡四宮に通ずる道をいう。平家物語4「宮いらせ給ひてのちは、大関―掘りきつて」
ご‐せき【五石】
[抱朴子金丹]中国の古代に道士が長生薬を練るのに用いた5種の薬石、すなわち丹砂・雄黄・白礬石・曾青・慈石の総称。
こせき‐げんぽん【戸籍原本】
戸籍事務を管掌する市町村長が最初に作成した戸籍。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐さんえい【小関三英】
江戸後期の蘭学者・医学者。名は好義。出羽庄内鶴岡の人。江戸へ出て蘭医吉田長淑に学び、岸和田藩医を経て幕府の天文台訳員となる。渡辺崋山の依頼で、高野長英とともに蘭書を翻訳。蛮社の獄の際、自殺。著「西医原病略」、訳「那波列翁ナポレオン伝」など。(1787〜1839)
⇒こせき【小関】
こせき‐しょうほん【戸籍抄本】‥セウ‥
戸籍のうち請求者の指定した部分だけを転写した文書。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐とうほん【戸籍謄本】
戸籍原本の全部を謄写した文書。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
戸籍の冒頭に記載されている者。戸主とは異なり、特別の権利関係を示すものではない。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ぼ【戸籍簿】
同一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ほう【戸籍法】‥ハフ
戸籍制度を規定した法律。1871年(明治4)に太政官布告で定め、1914年(大正3)に全文改正、第二次大戦後民法の親族・相続編の改正に伴って47年に全面的改正。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ゆうじ【古関裕而】
作曲家。本名、勇治。福島県生れ。歌謡曲・応援歌・軍歌など約5000曲を作る。作「紺碧の空」「長崎の鐘」「とんがり帽子」「君の名は」など。(1909〜1989)
古関裕而
提供:毎日新聞社
コスモポリス【cosmopolis】
(→)国際都市。
コスモポリタニズム【cosmopolitanism】
国家や民族を超越して、全人類を同胞と見なし、世界市民としての個人によって世界社会を実現しようとする思想。古くはキニク学派・ストア学派などがこの考えを唱えた。国民主義思想の勃興とともに諸国家の協同をめざす国際主義に代わったが、第二次大戦後に再び提唱。世界(市民)主義。四海同胞主義。万民主義。公民主義。
⇒コスモポリタニズム‐ひはん【コスモポリタニズム批判】
コスモポリタニズム‐ひはん【コスモポリタニズム批判】
ソ連のユダヤ人攻撃のキャンペーン。1949年ユダヤ人の学者・文化人を「根なしのコスモポリタン」と非難、多数の逮捕・投獄者を出した。
⇒コスモポリタニズム【cosmopolitanism】
コスモポリタン【cosmopolitan】
①コスモポリタニズムを信奉する人。世界主義者。
②国境や国籍にとらわれず、世界を股にかける人。国際人。
コスモロジー【cosmology】
宇宙論。
こすり【擦り・錯】
①こすること。ざらざらしたものをすりみがくこと。狂言、太刀奪たちばい「まづおのれ此縄に―をかけて」
②やすりをかけること。
③鑢やすりの異称。新撰字鏡6「錯、鑢也、己須利、又也須利、又乃保支利」
④木片に木賊とくさの枯茎を貼り付け、木などを磨くもの。
こすり‐つ・く【擦り付く】
[一]〔自五〕
こするように近寄る。
[二]〔他下二〕
⇒こすりつける(下一)
こすり‐つ・ける【擦り付ける】
〔他下一〕[文]こすりつ・く(下二)
押しつけてなすりつける。力を入れてこする。「靴の泥を石に―・ける」
こす・る【擦る・錯る】
〔他五〕
①おしつけて摩擦する。すりみがく。夏目漱石、三四郎「寐てゐた男がむつくり起きて眼を―・りながら下りて行つた」
②あてこする。いやみをいう。誹風柳多留23「どうるいがあると母親―・られる」
こ・する【鼓する】
〔他サ変〕[文]鼓す(サ変)
①うちならす。かきならす。
②ふるわす。おこす。「勇を―・する」
ご・する【伍する】
〔自サ変〕[文]伍す(サ変)
仲間に入る。同等の位置にならぶ。肩を並べる。「先輩に―・して活躍する」
こす・れる【擦れる】
〔自下一〕
互いにすれあう。
コスロー【Khosrō】
⇒ホスロー
コズロフ【Petr Kuzimich Kozlov】
ロシアの軍人・探検家。カラホトで西夏の古都市を、のち北モンゴルのノインウラで匈奴王の墓を発掘。(1863〜1935)
ご‐すん【五寸】
①1寸の5倍。
②五寸局ごすんつぼねの略。
⇒ごすん‐くぎ【五寸釘】
⇒ごすん‐つぼね【五寸局】
⇒ごすん‐もよう【五寸模様】
ごすん‐くぎ【五寸釘】
大形の釘。長さ曲尺かねじゃく5寸位(約15センチメートル)の釘。
⇒ご‐すん【五寸】
ごすん‐つぼね【五寸局】
一切りの揚代、銀5匁の局女郎。
⇒ご‐すん【五寸】
ごすん‐もよう【五寸模様】‥ヤウ
宝暦(1751〜1764)の頃流行した、着物の裾模様で、裾から5寸ほどの範囲に模様を置いたもの。
⇒ご‐すん【五寸】
こせ【巨勢】
姓氏の一つ。大和の古代豪族。高市郡巨勢郷(今、奈良県御所市古瀬)を本拠とする。武内宿祢の後裔と称す。許勢。
⇒こせ‐の‐かなおか【巨勢金岡】
こせ【瘡】
「こせがさ」の略。散木奇歌集「怪しさはみなもととこそ思ひつれ膚はだえは―のうちにぞありける」
ご‐せ【後世】
〔仏〕
①三世の一つ。死後に生まれ変わる世界。あの世。来世。ごせい。
②(→)後生善処ごしょうぜんじょに同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「最期に心乱れては人の譏り―のため」
⇒後世を弔う
ごせ【御所】
奈良県西部、大阪府に接する市。葛城地方の中心都市。製薬・繊維工業が盛ん。古代史跡が多い。人口3万2千。
ご‐ぜ【御前】
①(御前駆ごぜんくの略)(→)「みさきおい」に同じ。今昔物語集31「指貫さしぬき姿の―ども十余人」
②貴婦人の尊敬語。今昔物語集31「わが―たちの御あたりには」
③(接尾語的に用いる)女性の尊敬語。「姫―」→ごぜん
ご‐ぜ【瞽女】
(「御前ごぜ」から)三味線を弾き、唄を歌いなどして米や金銭を得た盲目の女。めくらごぜ。
こ‐せい【古生】
⇒こせい‐かい【古生界】
⇒こせい‐そう【古生層】
⇒こせい‐だい【古生代】
こ‐せい【古制】
古い時代の制度。昔のおきて。
こ‐せい【古製】
古い時代のつくり。昔の製作。
こ‐せい【呼声】
呼ばわる声。よびごえ。
こ‐せい【個性】
①(individuality)個人に具わり、他の人とはちがう、その個人にしかない性格・性質。「―を伸ばす」
②個物または個体に特有な特徴あるいは性格。
⇒こせい‐てき【個性的】
こ‐せい【糊精】
〔化〕(→)デキストリンに同じ。
こ‐ぜい【小勢】
①人数の少ない軍勢。太平記4「思ふには似ず、―なりけりと」
②少ない人数。小人数。↔大勢
こ‐ぜい【挙税】
奈良・平安時代、稲穀・銭貨を貸し出して利息を取ったこと。出挙稲すいことう。出挙銭。
ご‐せい【五声】
〔音〕
①日本・中国の音楽で、低音から宮きゅう・商しょう・角かく・徴ち・羽うの5音。また、その構成する音階。五音ごいん。→七声。
②(→)五音ごおん音階に同じ。
ご‐せい【五星】
①五つの星。
②[左伝襄公28年、注]中国で古代から知られている五惑星、すなわち歳星(木星)・熒惑けいごく(火星)・鎮星(土星)・太白(金星)・辰星(水星)の総称。五緯。
⇒ごせい‐こうき【五星紅旗】
ご‐せい【五牲】
[左伝昭公、注]いけにえに用いる5種の動物、すなわち牛・羊・豕いのこ・犬・鶏。また、麏くじか・鹿・熊・狼・野豕の総称。
ご‐せい【五清】
(画題)文人画で五つの清いものを描くこと。松・竹・梅・蘭・石。あるいは松・竹・蘭・芭蕉・石。また、梅・菊・竹・芭蕉・石。
ご‐せい【五聖】
中国古代の5人の聖人。通説では、尭ぎょう・舜しゅん・禹う・湯とう・文王をいう。
ご‐せい【互生】
〔植〕茎や枝に交互に1枚ずつ葉を生じること。サクラ・アサガオの類。互生葉序。→葉序(図)
ご‐せい【後世】
⇒ごせ。
⇒ごせい‐ほう【後世方】
ご‐せい【悟性】
〔哲〕(intellect イギリス・Verstand ドイツ)
①広義には、思考の能力。
②カントにおいては、感性に与えられる所与を認識へと構成する概念能力・判断能力で、理性と感性の中間にあり、科学的思考の主体。
③ヘーゲルにおいては、弁証法的思考能力としての理性に対して、対象を固定的にとらえ、他との区別に固執する思考能力。
⇒ごせい‐がいねん【悟性概念】
ご‐せい【碁聖】
傑出した囲碁の名手。棋聖きせい。
ご‐せい【語勢】
語ることばのいきおい。語気。語調。「―を強める」
こせい‐かい【古生界】
古生代に形成された堆積岩と火成岩。変成岩に関しては、原岩が古生代に作られたもの。
⇒こ‐せい【古生】
ごせい‐がいねん【悟性概念】
(→)範疇はんちゅう1に同じ。
⇒ご‐せい【悟性】
ごせい‐こうき【五星紅旗】
中華人民共和国の国旗。長方形紅地の左上方に、大きい1個の星と、これを弧状に囲む4個の小さい星とを黄色に染め抜く。
⇒ご‐せい【五星】
こせい‐せん【湖西線】
琵琶湖西岸を走り、東海道・北陸両本線を結ぶJR線。山科・近江塩津間、全長74.1キロメートル。
こせい‐そう【古生層】
古生代に堆積した地層。日本列島には、古生代にできた岩塊が中生層の中にとりこまれている所が多く、このような中生層は20世紀前半に秩父古生層の名でよばれていた。
⇒こ‐せい【古生】
こせい‐だい【古生代】
(Pal(a)eozoic Era)地質年代中、原生代の後、中生代の前の時代。約5億4000万年前から2億5000万年前までの時代。カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀に分ける。この時代には植物は主に隠花植物(藻類・シダ類など)、動物は主に海生の無脊椎動物(筆石・珊瑚類・海百合・腕足類など)が栄えた。古生代中頃のシルル紀末に、生物は初めて陸上に進出。→地質年代(表)
⇒こ‐せい【古生】
こ‐せいたいがく【個生態学】
動物の各種につき、その食性・繁殖その他一切の生活様式を研究する学問。種生態学とほぼ同義。↔群集生態学
こせい‐てき【個性的】
個性が表れているさま。独特なさま。「―な文章」「―な顔立ち」
⇒こ‐せい【個性】
ごせいばい‐しきもく【御成敗式目】
鎌倉幕府の基本的法典。1232年(貞永1)北条泰時が承久の乱後の当面する政治・法制の諸問題に対処するために編纂。51カ条から成り、室町幕府も武家の根本法として継承。江戸時代には手習手本として民間に普及。貞永じょうえい式目。
→文献資料[御成敗式目]
こ‐せいぶつ【古生物】
地質時代に生息していた生物の総称。マンモス・恐竜・アンモナイト・三葉虫さんようちゅう・蘆木ろぼくなどの類。
⇒こせいぶつ‐がく【古生物学】
⇒こせいぶつ‐ちりがく【古生物地理学】
こせいぶつ‐がく【古生物学】
(pal(a)eontology)古生物の系統・分類・進化・構造・生理・生態・地理的分布などを研究する学問分野。
⇒こ‐せいぶつ【古生物】
こせいぶつ‐ちりがく【古生物地理学】
化石を用いて地球史における生物の地理的分布を研究する学問分野。→生物地理学
⇒こ‐せいぶつ【古生物】
ごせい‐ほう【後世方】‥ハウ
鎌倉時代末期以降伝えられた中国の金・元の医家の処方を祖述する医家の一派。これを奉ずる医家を後世家とよび、田代三喜・曲直瀬まなせ道三・曲直瀬玄朔(1549〜1631)はその代表者。こうせいほう。↔古医方
⇒ご‐せい【後世】
ごぜ‐うた【瞽女歌】
瞽女のうたう歌。門口でうたう門付け歌のほか、段物と口説くどきを語った。山椒太夫などの段物は瞽女節とも呼んだ。越後口説も知られる。
ごぜえ・す
〔自サ変〕
「ある」「居る」を丁寧にいう語。ございます。(遊里語であるが、一般の人にも使われた)浮世床初「大学ぢやあ―・せんねえ」
こせ‐がさ
「がんがさ(雁瘡)」の異称。こせ。
こせがさわ‐いせき【小瀬ヶ沢遺跡】‥サハヰ‥
新潟県東蒲原郡阿賀町にある縄文時代草創期から早期の洞穴遺跡。縄文草創期を代表する土器・石器が出土。
こ‐せがれ【小倅】
①自分の息子の謙称。
②青年・少年をののしっていう語。
コセカント【cosecant】
〔数〕三角関数の一つ。サインの逆数。余割よかつ。記号cosec →三角関数
こせき【小関】
姓氏の一つ。
⇒こせき‐さんえい【小関三英】
こ‐せき【戸籍】
①戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にはほぼ廃絶。明治維新後復活した。へじゃく。→庚午年籍→壬申戸籍。
②国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書。
⇒こせき‐げんぽん【戸籍原本】
⇒こせき‐しょうほん【戸籍抄本】
⇒こせき‐とうほん【戸籍謄本】
⇒こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
⇒こせき‐ぼ【戸籍簿】
⇒こせき‐ほう【戸籍法】
こ‐せき【古昔】
むかし。いにしえ。
こ‐せき【古跡・古蹟】
歴史上有名な出来事や建物のあった跡。旧跡。
こせき【古関】
姓氏の一つ。
⇒こせき‐ゆうじ【古関裕而】
こ‐ぜき【小関】
要所に設けて敵の出入を防ぐ小さい関所。特に、山城国宇治郡四宮に通ずる道をいう。平家物語4「宮いらせ給ひてのちは、大関―掘りきつて」
ご‐せき【五石】
[抱朴子金丹]中国の古代に道士が長生薬を練るのに用いた5種の薬石、すなわち丹砂・雄黄・白礬石・曾青・慈石の総称。
こせき‐げんぽん【戸籍原本】
戸籍事務を管掌する市町村長が最初に作成した戸籍。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐さんえい【小関三英】
江戸後期の蘭学者・医学者。名は好義。出羽庄内鶴岡の人。江戸へ出て蘭医吉田長淑に学び、岸和田藩医を経て幕府の天文台訳員となる。渡辺崋山の依頼で、高野長英とともに蘭書を翻訳。蛮社の獄の際、自殺。著「西医原病略」、訳「那波列翁ナポレオン伝」など。(1787〜1839)
⇒こせき【小関】
こせき‐しょうほん【戸籍抄本】‥セウ‥
戸籍のうち請求者の指定した部分だけを転写した文書。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐とうほん【戸籍謄本】
戸籍原本の全部を謄写した文書。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
戸籍の冒頭に記載されている者。戸主とは異なり、特別の権利関係を示すものではない。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ぼ【戸籍簿】
同一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ほう【戸籍法】‥ハフ
戸籍制度を規定した法律。1871年(明治4)に太政官布告で定め、1914年(大正3)に全文改正、第二次大戦後民法の親族・相続編の改正に伴って47年に全面的改正。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ゆうじ【古関裕而】
作曲家。本名、勇治。福島県生れ。歌謡曲・応援歌・軍歌など約5000曲を作る。作「紺碧の空」「長崎の鐘」「とんがり帽子」「君の名は」など。(1909〜1989)
古関裕而
提供:毎日新聞社
 ⇒こせき【古関】
こせ‐こせ
①つまらないことにこだわって言動に余裕や落着きのないさま。夏目漱石、坊つちやん「蔭で―生意気な悪いたづらをして」。「―した態度」
②場所が狭くゆとりのないさま。「―した裏通り」
こせ‐ごと【こせ言】
しゃれ。秀句。狂言、今参「秀句―を御存じかと申す事でおりやる」
ごぜざとう【瞽女座頭】
狂言。(→)「清水きよみず座頭」に同じ。
こせ‐ざむらい【悴侍】‥ザムラヒ
(→)「かせざむらい」に同じ。
ごせ‐しゃ【後世者】
〔仏〕念仏をとなえて極楽往生を願う人。発心集「劣らぬ―なりければ」
ごせだ【五姓田】
姓氏の一つ。
⇒ごせだ‐ほうりゅう【五姓田芳柳】
⇒ごせだ‐よしまつ【五姓田義松】
ごせだ‐ほうりゅう【五姓田芳柳】‥ハウリウ
(初世)画家。本名、浅田岩吉。江戸生れ。初め歌川国芳に浮世絵を学び、のち長崎で洋画に志す。幕末、横浜に移り住み、外国人などの求めに応じて肖像画・風俗画を描いた。(1827〜1892)
⇒ごせだ【五姓田】
ごせだ‐よしまつ【五姓田義松】
洋画家。江戸生れ。初世芳柳の次子。ワーグマンに学び、工部美術学校入学。渡仏してボナに師事。パリのサロンに入選。明治美術会に参加。作「操り人形」など。(1855〜1915)
⇒ごせだ【五姓田】
ご‐せち【五節】
(遅・速・本・末・中声の五声の節の意)
①古代から朝廷で新嘗会しんじょうえ・大嘗会だいじょうえに行われた少女楽の行事。儀式は毎年11月の中の丑・寅・卯・辰の4日にわたり、丑の日に舞姫参入、その夜は帳台の試こころみ、寅の日に殿上の淵酔えんずい、その夜は御前の試(清涼殿で舞楽を天覧)、卯の日に清涼殿で童女わらわ御覧、辰の日に豊明の節会とよのあかりのせちえが行われ、群臣の前で五節の舞が奏される。
②五節の舞姫。枕草子24「受領の―いだすをりなど」
⇒ごせち‐さだめ【五節定め】
⇒ごせち‐どころ【五節所】
⇒ごせち‐どの【五節殿】
⇒ごせち‐の‐えんずい【五節の淵酔】
⇒ごせち‐の‐つぼね【五節の局】
⇒ごせち‐の‐まい【五節の舞】
⇒ごせち‐の‐まいひめ【五節の舞姫】
⇒ごせち‐の‐まいり【五節の参り】
⇒ごせち‐の‐わらわ【五節の童女】
ご‐せちえ【五節会】‥ヱ
古代より宮中で行われた五つの節会、すなわち元日・白馬あおうま・踏歌とうか・端午・豊明とよのあかり。
ご‐せちく【五節供】
⇒ごせっく(五節句)
ごせち‐さだめ【五節定め】
その年の五節の舞姫を献上すべき公卿・国司を選定すること。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐どころ【五節所】
五節の舞姫の控室。常寧殿の四隅にあり、中央に舞台が設けられた。五節の局つぼね。紫式部日記「ただ―のをかしきことを語る」
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐どの【五節殿】
(五節の舞の試演が行われたところから)常寧殿の異称。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐えんずい【五節の淵酔】‥ヱン‥
五節の寅の日に清涼殿の殿上で催される宴会。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐つぼね【五節の局】
(→)「ごせちどころ」に同じ。枕草子90「―を…みなこぼちすかして」
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まい【五節の舞】‥マヒ
五節に大歌おおうたを伴って奏する少女の舞。中世に廃絶。近代に改訂して復活。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まいひめ【五節の舞姫】‥マヒ‥
五節の舞を舞う舞姫。新嘗会しんじょうえでは四人で、二人(あるいは三人)は公卿の家、二人(あるいは一人)は国司の家から出す。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まいり【五節の参り】‥マヰリ
五節の舞姫が丑の日に五節所に参入すること。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐わらわ【五節の童女】‥ワラハ
五節の舞姫に二人ずつ付き従う童女。
⇒ご‐せち【五節】
こ‐せつ【古拙】
古風で技巧はつたないが、趣のあること。「―の美」「―な壺」
こ‐せつ【古説】
古く言われている説。ふるい説。
こ‐ぜつ【孤絶】
他とのつながりがなく、一つだけかけ離れていること。
ご‐せつ【五節】
①五節句ごせっくの略。
②(→)「ごせち(五節)」に同じ。謡曲、国栖くず「―の始めこれなれや」
ご‐ぜつ【五絶】
①五つの死の原因、すなわち縊・溺・圧・凍・驚の称。
②五つのすぐれたこと。
③漢詩の五言絶句の略。
ご‐せっきょう【五説経】‥キヤウ
説経節の代表的な五つの曲目。「山椒太夫」「苅萱かるかや」「信田妻しのだづま」「梅若」「愛護若あいごのわか」。また、「山椒太夫」「苅萱」「俊徳(信徳)丸」「小栗判官」「梵天国」の五つなど。
こせ‐つ・く
〔自五〕
こせこせする。人情本、春色辰巳園「世界中の女を―・く癖に、他ひとの事をば恋しらずだ」
ご‐せっく【五節句・五節供】
毎年5度の節句。正月7日(人日
⇒こせき【古関】
こせ‐こせ
①つまらないことにこだわって言動に余裕や落着きのないさま。夏目漱石、坊つちやん「蔭で―生意気な悪いたづらをして」。「―した態度」
②場所が狭くゆとりのないさま。「―した裏通り」
こせ‐ごと【こせ言】
しゃれ。秀句。狂言、今参「秀句―を御存じかと申す事でおりやる」
ごぜざとう【瞽女座頭】
狂言。(→)「清水きよみず座頭」に同じ。
こせ‐ざむらい【悴侍】‥ザムラヒ
(→)「かせざむらい」に同じ。
ごせ‐しゃ【後世者】
〔仏〕念仏をとなえて極楽往生を願う人。発心集「劣らぬ―なりければ」
ごせだ【五姓田】
姓氏の一つ。
⇒ごせだ‐ほうりゅう【五姓田芳柳】
⇒ごせだ‐よしまつ【五姓田義松】
ごせだ‐ほうりゅう【五姓田芳柳】‥ハウリウ
(初世)画家。本名、浅田岩吉。江戸生れ。初め歌川国芳に浮世絵を学び、のち長崎で洋画に志す。幕末、横浜に移り住み、外国人などの求めに応じて肖像画・風俗画を描いた。(1827〜1892)
⇒ごせだ【五姓田】
ごせだ‐よしまつ【五姓田義松】
洋画家。江戸生れ。初世芳柳の次子。ワーグマンに学び、工部美術学校入学。渡仏してボナに師事。パリのサロンに入選。明治美術会に参加。作「操り人形」など。(1855〜1915)
⇒ごせだ【五姓田】
ご‐せち【五節】
(遅・速・本・末・中声の五声の節の意)
①古代から朝廷で新嘗会しんじょうえ・大嘗会だいじょうえに行われた少女楽の行事。儀式は毎年11月の中の丑・寅・卯・辰の4日にわたり、丑の日に舞姫参入、その夜は帳台の試こころみ、寅の日に殿上の淵酔えんずい、その夜は御前の試(清涼殿で舞楽を天覧)、卯の日に清涼殿で童女わらわ御覧、辰の日に豊明の節会とよのあかりのせちえが行われ、群臣の前で五節の舞が奏される。
②五節の舞姫。枕草子24「受領の―いだすをりなど」
⇒ごせち‐さだめ【五節定め】
⇒ごせち‐どころ【五節所】
⇒ごせち‐どの【五節殿】
⇒ごせち‐の‐えんずい【五節の淵酔】
⇒ごせち‐の‐つぼね【五節の局】
⇒ごせち‐の‐まい【五節の舞】
⇒ごせち‐の‐まいひめ【五節の舞姫】
⇒ごせち‐の‐まいり【五節の参り】
⇒ごせち‐の‐わらわ【五節の童女】
ご‐せちえ【五節会】‥ヱ
古代より宮中で行われた五つの節会、すなわち元日・白馬あおうま・踏歌とうか・端午・豊明とよのあかり。
ご‐せちく【五節供】
⇒ごせっく(五節句)
ごせち‐さだめ【五節定め】
その年の五節の舞姫を献上すべき公卿・国司を選定すること。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐どころ【五節所】
五節の舞姫の控室。常寧殿の四隅にあり、中央に舞台が設けられた。五節の局つぼね。紫式部日記「ただ―のをかしきことを語る」
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐どの【五節殿】
(五節の舞の試演が行われたところから)常寧殿の異称。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐えんずい【五節の淵酔】‥ヱン‥
五節の寅の日に清涼殿の殿上で催される宴会。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐つぼね【五節の局】
(→)「ごせちどころ」に同じ。枕草子90「―を…みなこぼちすかして」
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まい【五節の舞】‥マヒ
五節に大歌おおうたを伴って奏する少女の舞。中世に廃絶。近代に改訂して復活。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まいひめ【五節の舞姫】‥マヒ‥
五節の舞を舞う舞姫。新嘗会しんじょうえでは四人で、二人(あるいは三人)は公卿の家、二人(あるいは一人)は国司の家から出す。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まいり【五節の参り】‥マヰリ
五節の舞姫が丑の日に五節所に参入すること。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐わらわ【五節の童女】‥ワラハ
五節の舞姫に二人ずつ付き従う童女。
⇒ご‐せち【五節】
こ‐せつ【古拙】
古風で技巧はつたないが、趣のあること。「―の美」「―な壺」
こ‐せつ【古説】
古く言われている説。ふるい説。
こ‐ぜつ【孤絶】
他とのつながりがなく、一つだけかけ離れていること。
ご‐せつ【五節】
①五節句ごせっくの略。
②(→)「ごせち(五節)」に同じ。謡曲、国栖くず「―の始めこれなれや」
ご‐ぜつ【五絶】
①五つの死の原因、すなわち縊・溺・圧・凍・驚の称。
②五つのすぐれたこと。
③漢詩の五言絶句の略。
ご‐せっきょう【五説経】‥キヤウ
説経節の代表的な五つの曲目。「山椒太夫」「苅萱かるかや」「信田妻しのだづま」「梅若」「愛護若あいごのわか」。また、「山椒太夫」「苅萱」「俊徳(信徳)丸」「小栗判官」「梵天国」の五つなど。
こせ‐つ・く
〔自五〕
こせこせする。人情本、春色辰巳園「世界中の女を―・く癖に、他ひとの事をば恋しらずだ」
ご‐せっく【五節句・五節供】
毎年5度の節句。正月7日(人日
 ⇒こすぎ【小杉】
こすぎ‐ばら【子過ぎ腹】
子を多く産み過ぎた腹。
こすぎ‐ほうあん【小杉放庵】‥ハウ‥
洋画家。名は国太郎。別号、未醒。栃木県生れ。院展洋画部、のち春陽会に属し、装飾的な独自の画風をもち、日本画もよくした。作「水郷」など。(1881〜1964)
⇒こすぎ【小杉】
こ‐すぎわら【小杉原】‥ハラ
小判の杉原紙。鼻紙などに用いる。小杉。
こすげ【小菅】
東京都葛飾区北西部の地名。1877年(明治10)以来、小菅監獄(現、東京拘置所)が置かれた。
ごず‐こう【牛頭香】‥ヅカウ
(→)牛頭栴檀ごずせんだんに同じ。
ごすこう‐いん【後崇光院】‥クワウヰン
伏見宮栄仁よしひと親王の子。名は貞成さだふさ。後花園天皇の父。剃髪して道欽と号。太上天皇の尊号を受けた。著「看聞御記かんもんぎょき」「椿葉記」など。(1372〜1456)
ごすざく‐てんのう【後朱雀天皇】‥ワウ
平安中期の天皇。一条天皇の第3皇子。名は敦良あつなが。母は藤原彰子。(在位1036〜1045)(1009〜1045)→天皇(表)
ごす‐さま【御所様】
摂家・大臣などの子女が、その父を呼ぶ語。ごすさん。
こ‐すずめ【小雀】
春に生まれた、小さい雀。雀の子。〈[季]春〉
こ‐すずり【小硯】
小形の硯。箱に入れて懐中して用いるものもあり、懐硯ふところすずりという。平家物語1「懐より―畳紙を取り出し」
ごず‐せんだん【牛頭栴檀】‥ヅ‥
(南天竺の牛頭山(摩羅耶山)に産する栴檀から製したという)熱帯地方産の麝香じゃこうの香のする香料。万病を除くという。牛頭香ごずこう。
ごす‐そめつけ【呉須染付】
呉須手の磁器で、白地に藍だけで文様を描いたもの。明末清初の頃、福建省漳州しょうしゅう付近から産出。
コスタ‐デル‐ソル【Costa del Sol】
(「太陽の海岸」の意)スペイン南部、アンダルシア地方の地中海沿岸地域。マラガ・トレモリーノス・マルベージャなどの都市を中心とする保養地。
コスタ‐デル‐ソルの海
撮影:小松義夫
⇒こすぎ【小杉】
こすぎ‐ばら【子過ぎ腹】
子を多く産み過ぎた腹。
こすぎ‐ほうあん【小杉放庵】‥ハウ‥
洋画家。名は国太郎。別号、未醒。栃木県生れ。院展洋画部、のち春陽会に属し、装飾的な独自の画風をもち、日本画もよくした。作「水郷」など。(1881〜1964)
⇒こすぎ【小杉】
こ‐すぎわら【小杉原】‥ハラ
小判の杉原紙。鼻紙などに用いる。小杉。
こすげ【小菅】
東京都葛飾区北西部の地名。1877年(明治10)以来、小菅監獄(現、東京拘置所)が置かれた。
ごず‐こう【牛頭香】‥ヅカウ
(→)牛頭栴檀ごずせんだんに同じ。
ごすこう‐いん【後崇光院】‥クワウヰン
伏見宮栄仁よしひと親王の子。名は貞成さだふさ。後花園天皇の父。剃髪して道欽と号。太上天皇の尊号を受けた。著「看聞御記かんもんぎょき」「椿葉記」など。(1372〜1456)
ごすざく‐てんのう【後朱雀天皇】‥ワウ
平安中期の天皇。一条天皇の第3皇子。名は敦良あつなが。母は藤原彰子。(在位1036〜1045)(1009〜1045)→天皇(表)
ごす‐さま【御所様】
摂家・大臣などの子女が、その父を呼ぶ語。ごすさん。
こ‐すずめ【小雀】
春に生まれた、小さい雀。雀の子。〈[季]春〉
こ‐すずり【小硯】
小形の硯。箱に入れて懐中して用いるものもあり、懐硯ふところすずりという。平家物語1「懐より―畳紙を取り出し」
ごず‐せんだん【牛頭栴檀】‥ヅ‥
(南天竺の牛頭山(摩羅耶山)に産する栴檀から製したという)熱帯地方産の麝香じゃこうの香のする香料。万病を除くという。牛頭香ごずこう。
ごす‐そめつけ【呉須染付】
呉須手の磁器で、白地に藍だけで文様を描いたもの。明末清初の頃、福建省漳州しょうしゅう付近から産出。
コスタ‐デル‐ソル【Costa del Sol】
(「太陽の海岸」の意)スペイン南部、アンダルシア地方の地中海沿岸地域。マラガ・トレモリーノス・マルベージャなどの都市を中心とする保養地。
コスタ‐デル‐ソルの海
撮影:小松義夫
 コスタ‐リカ【Costa Rica】
(「豊かな海岸」の意)中米南部の共和国。1821年スペインから独立。パナマの西端に接する。住民はヨーロッパ系が主で、言語はスペイン語。憲法で非武装中立を規定。面積5万1000平方キロメートル。人口425万(2004)。首都サンホセ。→中央アメリカ(図)。
⇒コスタリカ‐ほうしき【コスタリカ方式】
コスタリカ‐ほうしき【コスタリカ方式】‥ハウ‥
(国会議員の連続再選を禁止するコスタリカの制度を参考にしたところからという)同一政党に属する複数の候補者が、選挙ごとに小選挙区と比例代表区とに交代で立候補する方式。
⇒コスタ‐リカ【Costa Rica】
こ‐すだれ【小簾】
小形のすだれ。多く、車輿くるまごしにかける。
コスチューム【costume】
①特定の民族・階級・時代・地方の服装。髪型・装身具も含めていう。
②仮装・演劇などの衣装。
③上下揃いの婦人服。
⇒コスチューム‐プレー【costume play】
コスチューム‐プレー【costume play】
①俳優の衣装の視覚的効果をねらった劇。特に歴史劇や歴史映画をいう。衣装劇。時代劇。
②(日本での用法)漫画・アニメの登場人物などの扮装をして楽しむこと。コスプレ。
⇒コスチューム【costume】
こすっ‐から・い【狡っ辛い】
〔形〕
(コスカライの転)うまく立ち回って利を得ようとするたちである。ずるくて抜け目がない。
ごす‐で【呉須手】
中国南部、福建・広東地方で明末清初の頃に焼かれた磁器。粗製で奔放な絵模様を描くが、日本の茶人が呉須赤絵・呉須染付などと称し珍重。呉州手。呉須。
ごず‐てんのう【牛頭天王】‥ヅ‥ワウ
〔仏〕もとインドの祇園精舎の守護神で、薬師如来の垂迹すいじゃくとされる。除疫神として、京都祇園社(八坂神社)などに祀られる。頭上に牛の頭を持つ忿怒相に表される。
コスト【cost】
①値段。費用。
②原価。生産費。
⇒コスト‐アップ【cost up】
⇒コスト‐インフレ
⇒コスト‐ダウン【cost down】
⇒コスト‐パフォーマンス【cost performance】
⇒コスト‐プッシュ‐インフレーション【cost-push inflation】
⇒コスト‐われ【コスト割れ】
コスト‐アップ【cost up】
生産費が上昇すること。
⇒コスト【cost】
コスト‐インフレ
(cost inflation)(→)コスト‐プッシュ‐インフレーションに同じ。
⇒コスト【cost】
コスト‐ダウン【cost down】
生産費が減少すること。
⇒コスト【cost】
コスト‐パフォーマンス【cost performance】
①投入される費用や作業量に対する成果の割合。
②機械などで、性能と価格との比。
⇒コスト【cost】
コスト‐プッシュ‐インフレーション【cost-push inflation】
賃金や原材料費などのコストの上昇が生産性の伸びを上回ったために生ずるインフレーション。売手インフレーション。コスト‐インフレ。↔デマンド‐プル‐インフレーション。
⇒コスト【cost】
コストレ【Guillaume Costeley】
フランスの作曲家。100曲以上の多声シャンソンを作曲。コトレ。(1530頃〜1606)
コスト‐われ【コスト割れ】
実際の売値が原価を下回ること。
⇒コスト【cost】
こすのと【小簾の戸】
地歌。端歌物。峰崎勾当作曲。癪がきっかけで生まれた恋を歌ったもの。小簾の外。
ゴスバンク【Gosbank ロシア】
ソ連の国立中央銀行。1922年営業を開始。92年ロシア中央銀行に改組。
ゴスプラン【Gosplan ロシア】
ソ連の国家計画委員会。1921年創設。5カ年計画など経済計画を作成。
ゴスペル【gospel】
①福音。
②福音書。新約聖書に収めた4福音書の総称。
③ゴスペル‐ソングの略。
⇒ゴスペル‐ソング【gospel song】
ゴスペル‐ソング【gospel song】
黒人霊歌・ジャズ・ブルースなどの影響を受けた福音歌。アメリカの黒人教会で1920年代からさかんになった。現在は教会の外でも広くうたわれる。ゴスペル。
⇒ゴスペル【gospel】
こすみ【尖】
囲碁で、盤上の石から斜めに連ねて打つ手。こすみつけ。
こ‐すみ【小隅・小角】
かたすみ。すみっこ。
こ‐ずみ【小炭】
最初小さく切った木を燃やし、急に沢山の木片を覆い、ある程度焼き、水をかけて消して作った炭。古い製炭法。
こ‐ずみ【粉炭】
炭が砕けて粉となったもの。こなずみ。
こ‐ずみ【濃墨】
墨色の濃いもの。源氏物語少女「―、うすずみ、さうがちにうちまぜ乱れたるも」
ご‐ずみ【後炭】
茶道で濃茶がすんで薄茶に移るまでに、再び炭をついで湯が沸き立つようにすること。のちのすみ。
こず・む【偏む】コヅム
〔自五〕
①かたよる。傾く。特に、馬がつまずいて倒れかかる。古今著聞集10「ふまへられて、馬かい―・みて、やすやすととどまりにけり」
②一つ所にかたよって集まる。ぎっしりと詰まる。混む。
③筋肉が凝こる。「肩が―・む」
④気持が暗くなる。心持ちがねじれてくる。
コスメ
コスメチックの略。化粧品全般を指す。
ごず‐めず【牛頭馬頭】‥ヅ‥ヅ
〔仏〕地獄の獄卒で、牛頭人身のものと馬頭人身のもの。
牛頭馬頭
コスタ‐リカ【Costa Rica】
(「豊かな海岸」の意)中米南部の共和国。1821年スペインから独立。パナマの西端に接する。住民はヨーロッパ系が主で、言語はスペイン語。憲法で非武装中立を規定。面積5万1000平方キロメートル。人口425万(2004)。首都サンホセ。→中央アメリカ(図)。
⇒コスタリカ‐ほうしき【コスタリカ方式】
コスタリカ‐ほうしき【コスタリカ方式】‥ハウ‥
(国会議員の連続再選を禁止するコスタリカの制度を参考にしたところからという)同一政党に属する複数の候補者が、選挙ごとに小選挙区と比例代表区とに交代で立候補する方式。
⇒コスタ‐リカ【Costa Rica】
こ‐すだれ【小簾】
小形のすだれ。多く、車輿くるまごしにかける。
コスチューム【costume】
①特定の民族・階級・時代・地方の服装。髪型・装身具も含めていう。
②仮装・演劇などの衣装。
③上下揃いの婦人服。
⇒コスチューム‐プレー【costume play】
コスチューム‐プレー【costume play】
①俳優の衣装の視覚的効果をねらった劇。特に歴史劇や歴史映画をいう。衣装劇。時代劇。
②(日本での用法)漫画・アニメの登場人物などの扮装をして楽しむこと。コスプレ。
⇒コスチューム【costume】
こすっ‐から・い【狡っ辛い】
〔形〕
(コスカライの転)うまく立ち回って利を得ようとするたちである。ずるくて抜け目がない。
ごす‐で【呉須手】
中国南部、福建・広東地方で明末清初の頃に焼かれた磁器。粗製で奔放な絵模様を描くが、日本の茶人が呉須赤絵・呉須染付などと称し珍重。呉州手。呉須。
ごず‐てんのう【牛頭天王】‥ヅ‥ワウ
〔仏〕もとインドの祇園精舎の守護神で、薬師如来の垂迹すいじゃくとされる。除疫神として、京都祇園社(八坂神社)などに祀られる。頭上に牛の頭を持つ忿怒相に表される。
コスト【cost】
①値段。費用。
②原価。生産費。
⇒コスト‐アップ【cost up】
⇒コスト‐インフレ
⇒コスト‐ダウン【cost down】
⇒コスト‐パフォーマンス【cost performance】
⇒コスト‐プッシュ‐インフレーション【cost-push inflation】
⇒コスト‐われ【コスト割れ】
コスト‐アップ【cost up】
生産費が上昇すること。
⇒コスト【cost】
コスト‐インフレ
(cost inflation)(→)コスト‐プッシュ‐インフレーションに同じ。
⇒コスト【cost】
コスト‐ダウン【cost down】
生産費が減少すること。
⇒コスト【cost】
コスト‐パフォーマンス【cost performance】
①投入される費用や作業量に対する成果の割合。
②機械などで、性能と価格との比。
⇒コスト【cost】
コスト‐プッシュ‐インフレーション【cost-push inflation】
賃金や原材料費などのコストの上昇が生産性の伸びを上回ったために生ずるインフレーション。売手インフレーション。コスト‐インフレ。↔デマンド‐プル‐インフレーション。
⇒コスト【cost】
コストレ【Guillaume Costeley】
フランスの作曲家。100曲以上の多声シャンソンを作曲。コトレ。(1530頃〜1606)
コスト‐われ【コスト割れ】
実際の売値が原価を下回ること。
⇒コスト【cost】
こすのと【小簾の戸】
地歌。端歌物。峰崎勾当作曲。癪がきっかけで生まれた恋を歌ったもの。小簾の外。
ゴスバンク【Gosbank ロシア】
ソ連の国立中央銀行。1922年営業を開始。92年ロシア中央銀行に改組。
ゴスプラン【Gosplan ロシア】
ソ連の国家計画委員会。1921年創設。5カ年計画など経済計画を作成。
ゴスペル【gospel】
①福音。
②福音書。新約聖書に収めた4福音書の総称。
③ゴスペル‐ソングの略。
⇒ゴスペル‐ソング【gospel song】
ゴスペル‐ソング【gospel song】
黒人霊歌・ジャズ・ブルースなどの影響を受けた福音歌。アメリカの黒人教会で1920年代からさかんになった。現在は教会の外でも広くうたわれる。ゴスペル。
⇒ゴスペル【gospel】
こすみ【尖】
囲碁で、盤上の石から斜めに連ねて打つ手。こすみつけ。
こ‐すみ【小隅・小角】
かたすみ。すみっこ。
こ‐ずみ【小炭】
最初小さく切った木を燃やし、急に沢山の木片を覆い、ある程度焼き、水をかけて消して作った炭。古い製炭法。
こ‐ずみ【粉炭】
炭が砕けて粉となったもの。こなずみ。
こ‐ずみ【濃墨】
墨色の濃いもの。源氏物語少女「―、うすずみ、さうがちにうちまぜ乱れたるも」
ご‐ずみ【後炭】
茶道で濃茶がすんで薄茶に移るまでに、再び炭をついで湯が沸き立つようにすること。のちのすみ。
こず・む【偏む】コヅム
〔自五〕
①かたよる。傾く。特に、馬がつまずいて倒れかかる。古今著聞集10「ふまへられて、馬かい―・みて、やすやすととどまりにけり」
②一つ所にかたよって集まる。ぎっしりと詰まる。混む。
③筋肉が凝こる。「肩が―・む」
④気持が暗くなる。心持ちがねじれてくる。
コスメ
コスメチックの略。化粧品全般を指す。
ごず‐めず【牛頭馬頭】‥ヅ‥ヅ
〔仏〕地獄の獄卒で、牛頭人身のものと馬頭人身のもの。
牛頭馬頭
 コスメチック【cosmetic イギリス・cosmétique フランス】
①化粧品。
②白蝋・牛脂・パラフィンなどに香料を加え、練り固めた整髪用の化粧品。チック。泉鏡花、黒百合「島野は総すべてコスメチツク、香水、巻莨シガレット、洋杖ステッキ、護謨ゴム靴といふ才子肌」
コスメッツ【COSMETS】
(Computer System for Meteorological Services)気象資料総合処理システム。気象庁に設置される。国内外との情報交換とその資料の情報処理を総合的にオンライン‐リアルタイム方式で行うコンピューター‐システム。→アデス→ナプス
こ‐ずもう【小相撲・小角力】‥ズマフ
①相撲取りの弟子。地位の低い力士。
②本相撲にまねて相撲を取ること。また、その相撲。しろうと相撲。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「若い時は―の一番もひねつた俺ぢや」
⇒こずもう‐とり【小相撲取】
こずもう‐とり【小相撲取】‥ズマフ‥
しろうとの相撲取り。狂言、飛越「それが―からとりあがつて、大相撲になつて後」
⇒こ‐ずもう【小相撲・小角力】
コスモス【kosmos ギリシア・cosmos イギリス】
①美しい秩序。転じて、それ自身のうちに秩序と調和とをもつ宇宙または世界の意。「ミクロ‐―」↔カオス。
②〔植〕キク科の一年草。メキシコ原産。高さ約1.5メートルに達する。葉は線状に細裂。秋、大形の頭状花を開く。色は白・淡紅・深紅など。秋桜。おおハルシャぎく。〈[季]秋〉
コスモス
撮影:関戸 勇
コスメチック【cosmetic イギリス・cosmétique フランス】
①化粧品。
②白蝋・牛脂・パラフィンなどに香料を加え、練り固めた整髪用の化粧品。チック。泉鏡花、黒百合「島野は総すべてコスメチツク、香水、巻莨シガレット、洋杖ステッキ、護謨ゴム靴といふ才子肌」
コスメッツ【COSMETS】
(Computer System for Meteorological Services)気象資料総合処理システム。気象庁に設置される。国内外との情報交換とその資料の情報処理を総合的にオンライン‐リアルタイム方式で行うコンピューター‐システム。→アデス→ナプス
こ‐ずもう【小相撲・小角力】‥ズマフ
①相撲取りの弟子。地位の低い力士。
②本相撲にまねて相撲を取ること。また、その相撲。しろうと相撲。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「若い時は―の一番もひねつた俺ぢや」
⇒こずもう‐とり【小相撲取】
こずもう‐とり【小相撲取】‥ズマフ‥
しろうとの相撲取り。狂言、飛越「それが―からとりあがつて、大相撲になつて後」
⇒こ‐ずもう【小相撲・小角力】
コスモス【kosmos ギリシア・cosmos イギリス】
①美しい秩序。転じて、それ自身のうちに秩序と調和とをもつ宇宙または世界の意。「ミクロ‐―」↔カオス。
②〔植〕キク科の一年草。メキシコ原産。高さ約1.5メートルに達する。葉は線状に細裂。秋、大形の頭状花を開く。色は白・淡紅・深紅など。秋桜。おおハルシャぎく。〈[季]秋〉
コスモス
撮影:関戸 勇
 コスモポリス【cosmopolis】
(→)国際都市。
コスモポリタニズム【cosmopolitanism】
国家や民族を超越して、全人類を同胞と見なし、世界市民としての個人によって世界社会を実現しようとする思想。古くはキニク学派・ストア学派などがこの考えを唱えた。国民主義思想の勃興とともに諸国家の協同をめざす国際主義に代わったが、第二次大戦後に再び提唱。世界(市民)主義。四海同胞主義。万民主義。公民主義。
⇒コスモポリタニズム‐ひはん【コスモポリタニズム批判】
コスモポリタニズム‐ひはん【コスモポリタニズム批判】
ソ連のユダヤ人攻撃のキャンペーン。1949年ユダヤ人の学者・文化人を「根なしのコスモポリタン」と非難、多数の逮捕・投獄者を出した。
⇒コスモポリタニズム【cosmopolitanism】
コスモポリタン【cosmopolitan】
①コスモポリタニズムを信奉する人。世界主義者。
②国境や国籍にとらわれず、世界を股にかける人。国際人。
コスモロジー【cosmology】
宇宙論。
こすり【擦り・錯】
①こすること。ざらざらしたものをすりみがくこと。狂言、太刀奪たちばい「まづおのれ此縄に―をかけて」
②やすりをかけること。
③鑢やすりの異称。新撰字鏡6「錯、鑢也、己須利、又也須利、又乃保支利」
④木片に木賊とくさの枯茎を貼り付け、木などを磨くもの。
こすり‐つ・く【擦り付く】
[一]〔自五〕
こするように近寄る。
[二]〔他下二〕
⇒こすりつける(下一)
こすり‐つ・ける【擦り付ける】
〔他下一〕[文]こすりつ・く(下二)
押しつけてなすりつける。力を入れてこする。「靴の泥を石に―・ける」
こす・る【擦る・錯る】
〔他五〕
①おしつけて摩擦する。すりみがく。夏目漱石、三四郎「寐てゐた男がむつくり起きて眼を―・りながら下りて行つた」
②あてこする。いやみをいう。誹風柳多留23「どうるいがあると母親―・られる」
こ・する【鼓する】
〔他サ変〕[文]鼓す(サ変)
①うちならす。かきならす。
②ふるわす。おこす。「勇を―・する」
ご・する【伍する】
〔自サ変〕[文]伍す(サ変)
仲間に入る。同等の位置にならぶ。肩を並べる。「先輩に―・して活躍する」
こす・れる【擦れる】
〔自下一〕
互いにすれあう。
コスロー【Khosrō】
⇒ホスロー
コズロフ【Petr Kuzimich Kozlov】
ロシアの軍人・探検家。カラホトで西夏の古都市を、のち北モンゴルのノインウラで匈奴王の墓を発掘。(1863〜1935)
ご‐すん【五寸】
①1寸の5倍。
②五寸局ごすんつぼねの略。
⇒ごすん‐くぎ【五寸釘】
⇒ごすん‐つぼね【五寸局】
⇒ごすん‐もよう【五寸模様】
ごすん‐くぎ【五寸釘】
大形の釘。長さ曲尺かねじゃく5寸位(約15センチメートル)の釘。
⇒ご‐すん【五寸】
ごすん‐つぼね【五寸局】
一切りの揚代、銀5匁の局女郎。
⇒ご‐すん【五寸】
ごすん‐もよう【五寸模様】‥ヤウ
宝暦(1751〜1764)の頃流行した、着物の裾模様で、裾から5寸ほどの範囲に模様を置いたもの。
⇒ご‐すん【五寸】
こせ【巨勢】
姓氏の一つ。大和の古代豪族。高市郡巨勢郷(今、奈良県御所市古瀬)を本拠とする。武内宿祢の後裔と称す。許勢。
⇒こせ‐の‐かなおか【巨勢金岡】
こせ【瘡】
「こせがさ」の略。散木奇歌集「怪しさはみなもととこそ思ひつれ膚はだえは―のうちにぞありける」
ご‐せ【後世】
〔仏〕
①三世の一つ。死後に生まれ変わる世界。あの世。来世。ごせい。
②(→)後生善処ごしょうぜんじょに同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「最期に心乱れては人の譏り―のため」
⇒後世を弔う
ごせ【御所】
奈良県西部、大阪府に接する市。葛城地方の中心都市。製薬・繊維工業が盛ん。古代史跡が多い。人口3万2千。
ご‐ぜ【御前】
①(御前駆ごぜんくの略)(→)「みさきおい」に同じ。今昔物語集31「指貫さしぬき姿の―ども十余人」
②貴婦人の尊敬語。今昔物語集31「わが―たちの御あたりには」
③(接尾語的に用いる)女性の尊敬語。「姫―」→ごぜん
ご‐ぜ【瞽女】
(「御前ごぜ」から)三味線を弾き、唄を歌いなどして米や金銭を得た盲目の女。めくらごぜ。
こ‐せい【古生】
⇒こせい‐かい【古生界】
⇒こせい‐そう【古生層】
⇒こせい‐だい【古生代】
こ‐せい【古制】
古い時代の制度。昔のおきて。
こ‐せい【古製】
古い時代のつくり。昔の製作。
こ‐せい【呼声】
呼ばわる声。よびごえ。
こ‐せい【個性】
①(individuality)個人に具わり、他の人とはちがう、その個人にしかない性格・性質。「―を伸ばす」
②個物または個体に特有な特徴あるいは性格。
⇒こせい‐てき【個性的】
こ‐せい【糊精】
〔化〕(→)デキストリンに同じ。
こ‐ぜい【小勢】
①人数の少ない軍勢。太平記4「思ふには似ず、―なりけりと」
②少ない人数。小人数。↔大勢
こ‐ぜい【挙税】
奈良・平安時代、稲穀・銭貨を貸し出して利息を取ったこと。出挙稲すいことう。出挙銭。
ご‐せい【五声】
〔音〕
①日本・中国の音楽で、低音から宮きゅう・商しょう・角かく・徴ち・羽うの5音。また、その構成する音階。五音ごいん。→七声。
②(→)五音ごおん音階に同じ。
ご‐せい【五星】
①五つの星。
②[左伝襄公28年、注]中国で古代から知られている五惑星、すなわち歳星(木星)・熒惑けいごく(火星)・鎮星(土星)・太白(金星)・辰星(水星)の総称。五緯。
⇒ごせい‐こうき【五星紅旗】
ご‐せい【五牲】
[左伝昭公、注]いけにえに用いる5種の動物、すなわち牛・羊・豕いのこ・犬・鶏。また、麏くじか・鹿・熊・狼・野豕の総称。
ご‐せい【五清】
(画題)文人画で五つの清いものを描くこと。松・竹・梅・蘭・石。あるいは松・竹・蘭・芭蕉・石。また、梅・菊・竹・芭蕉・石。
ご‐せい【五聖】
中国古代の5人の聖人。通説では、尭ぎょう・舜しゅん・禹う・湯とう・文王をいう。
ご‐せい【互生】
〔植〕茎や枝に交互に1枚ずつ葉を生じること。サクラ・アサガオの類。互生葉序。→葉序(図)
ご‐せい【後世】
⇒ごせ。
⇒ごせい‐ほう【後世方】
ご‐せい【悟性】
〔哲〕(intellect イギリス・Verstand ドイツ)
①広義には、思考の能力。
②カントにおいては、感性に与えられる所与を認識へと構成する概念能力・判断能力で、理性と感性の中間にあり、科学的思考の主体。
③ヘーゲルにおいては、弁証法的思考能力としての理性に対して、対象を固定的にとらえ、他との区別に固執する思考能力。
⇒ごせい‐がいねん【悟性概念】
ご‐せい【碁聖】
傑出した囲碁の名手。棋聖きせい。
ご‐せい【語勢】
語ることばのいきおい。語気。語調。「―を強める」
こせい‐かい【古生界】
古生代に形成された堆積岩と火成岩。変成岩に関しては、原岩が古生代に作られたもの。
⇒こ‐せい【古生】
ごせい‐がいねん【悟性概念】
(→)範疇はんちゅう1に同じ。
⇒ご‐せい【悟性】
ごせい‐こうき【五星紅旗】
中華人民共和国の国旗。長方形紅地の左上方に、大きい1個の星と、これを弧状に囲む4個の小さい星とを黄色に染め抜く。
⇒ご‐せい【五星】
こせい‐せん【湖西線】
琵琶湖西岸を走り、東海道・北陸両本線を結ぶJR線。山科・近江塩津間、全長74.1キロメートル。
こせい‐そう【古生層】
古生代に堆積した地層。日本列島には、古生代にできた岩塊が中生層の中にとりこまれている所が多く、このような中生層は20世紀前半に秩父古生層の名でよばれていた。
⇒こ‐せい【古生】
こせい‐だい【古生代】
(Pal(a)eozoic Era)地質年代中、原生代の後、中生代の前の時代。約5億4000万年前から2億5000万年前までの時代。カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀に分ける。この時代には植物は主に隠花植物(藻類・シダ類など)、動物は主に海生の無脊椎動物(筆石・珊瑚類・海百合・腕足類など)が栄えた。古生代中頃のシルル紀末に、生物は初めて陸上に進出。→地質年代(表)
⇒こ‐せい【古生】
こ‐せいたいがく【個生態学】
動物の各種につき、その食性・繁殖その他一切の生活様式を研究する学問。種生態学とほぼ同義。↔群集生態学
こせい‐てき【個性的】
個性が表れているさま。独特なさま。「―な文章」「―な顔立ち」
⇒こ‐せい【個性】
ごせいばい‐しきもく【御成敗式目】
鎌倉幕府の基本的法典。1232年(貞永1)北条泰時が承久の乱後の当面する政治・法制の諸問題に対処するために編纂。51カ条から成り、室町幕府も武家の根本法として継承。江戸時代には手習手本として民間に普及。貞永じょうえい式目。
→文献資料[御成敗式目]
こ‐せいぶつ【古生物】
地質時代に生息していた生物の総称。マンモス・恐竜・アンモナイト・三葉虫さんようちゅう・蘆木ろぼくなどの類。
⇒こせいぶつ‐がく【古生物学】
⇒こせいぶつ‐ちりがく【古生物地理学】
こせいぶつ‐がく【古生物学】
(pal(a)eontology)古生物の系統・分類・進化・構造・生理・生態・地理的分布などを研究する学問分野。
⇒こ‐せいぶつ【古生物】
こせいぶつ‐ちりがく【古生物地理学】
化石を用いて地球史における生物の地理的分布を研究する学問分野。→生物地理学
⇒こ‐せいぶつ【古生物】
ごせい‐ほう【後世方】‥ハウ
鎌倉時代末期以降伝えられた中国の金・元の医家の処方を祖述する医家の一派。これを奉ずる医家を後世家とよび、田代三喜・曲直瀬まなせ道三・曲直瀬玄朔(1549〜1631)はその代表者。こうせいほう。↔古医方
⇒ご‐せい【後世】
ごぜ‐うた【瞽女歌】
瞽女のうたう歌。門口でうたう門付け歌のほか、段物と口説くどきを語った。山椒太夫などの段物は瞽女節とも呼んだ。越後口説も知られる。
ごぜえ・す
〔自サ変〕
「ある」「居る」を丁寧にいう語。ございます。(遊里語であるが、一般の人にも使われた)浮世床初「大学ぢやあ―・せんねえ」
こせ‐がさ
「がんがさ(雁瘡)」の異称。こせ。
こせがさわ‐いせき【小瀬ヶ沢遺跡】‥サハヰ‥
新潟県東蒲原郡阿賀町にある縄文時代草創期から早期の洞穴遺跡。縄文草創期を代表する土器・石器が出土。
こ‐せがれ【小倅】
①自分の息子の謙称。
②青年・少年をののしっていう語。
コセカント【cosecant】
〔数〕三角関数の一つ。サインの逆数。余割よかつ。記号cosec →三角関数
こせき【小関】
姓氏の一つ。
⇒こせき‐さんえい【小関三英】
こ‐せき【戸籍】
①戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にはほぼ廃絶。明治維新後復活した。へじゃく。→庚午年籍→壬申戸籍。
②国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書。
⇒こせき‐げんぽん【戸籍原本】
⇒こせき‐しょうほん【戸籍抄本】
⇒こせき‐とうほん【戸籍謄本】
⇒こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
⇒こせき‐ぼ【戸籍簿】
⇒こせき‐ほう【戸籍法】
こ‐せき【古昔】
むかし。いにしえ。
こ‐せき【古跡・古蹟】
歴史上有名な出来事や建物のあった跡。旧跡。
こせき【古関】
姓氏の一つ。
⇒こせき‐ゆうじ【古関裕而】
こ‐ぜき【小関】
要所に設けて敵の出入を防ぐ小さい関所。特に、山城国宇治郡四宮に通ずる道をいう。平家物語4「宮いらせ給ひてのちは、大関―掘りきつて」
ご‐せき【五石】
[抱朴子金丹]中国の古代に道士が長生薬を練るのに用いた5種の薬石、すなわち丹砂・雄黄・白礬石・曾青・慈石の総称。
こせき‐げんぽん【戸籍原本】
戸籍事務を管掌する市町村長が最初に作成した戸籍。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐さんえい【小関三英】
江戸後期の蘭学者・医学者。名は好義。出羽庄内鶴岡の人。江戸へ出て蘭医吉田長淑に学び、岸和田藩医を経て幕府の天文台訳員となる。渡辺崋山の依頼で、高野長英とともに蘭書を翻訳。蛮社の獄の際、自殺。著「西医原病略」、訳「那波列翁ナポレオン伝」など。(1787〜1839)
⇒こせき【小関】
こせき‐しょうほん【戸籍抄本】‥セウ‥
戸籍のうち請求者の指定した部分だけを転写した文書。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐とうほん【戸籍謄本】
戸籍原本の全部を謄写した文書。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
戸籍の冒頭に記載されている者。戸主とは異なり、特別の権利関係を示すものではない。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ぼ【戸籍簿】
同一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ほう【戸籍法】‥ハフ
戸籍制度を規定した法律。1871年(明治4)に太政官布告で定め、1914年(大正3)に全文改正、第二次大戦後民法の親族・相続編の改正に伴って47年に全面的改正。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ゆうじ【古関裕而】
作曲家。本名、勇治。福島県生れ。歌謡曲・応援歌・軍歌など約5000曲を作る。作「紺碧の空」「長崎の鐘」「とんがり帽子」「君の名は」など。(1909〜1989)
古関裕而
提供:毎日新聞社
コスモポリス【cosmopolis】
(→)国際都市。
コスモポリタニズム【cosmopolitanism】
国家や民族を超越して、全人類を同胞と見なし、世界市民としての個人によって世界社会を実現しようとする思想。古くはキニク学派・ストア学派などがこの考えを唱えた。国民主義思想の勃興とともに諸国家の協同をめざす国際主義に代わったが、第二次大戦後に再び提唱。世界(市民)主義。四海同胞主義。万民主義。公民主義。
⇒コスモポリタニズム‐ひはん【コスモポリタニズム批判】
コスモポリタニズム‐ひはん【コスモポリタニズム批判】
ソ連のユダヤ人攻撃のキャンペーン。1949年ユダヤ人の学者・文化人を「根なしのコスモポリタン」と非難、多数の逮捕・投獄者を出した。
⇒コスモポリタニズム【cosmopolitanism】
コスモポリタン【cosmopolitan】
①コスモポリタニズムを信奉する人。世界主義者。
②国境や国籍にとらわれず、世界を股にかける人。国際人。
コスモロジー【cosmology】
宇宙論。
こすり【擦り・錯】
①こすること。ざらざらしたものをすりみがくこと。狂言、太刀奪たちばい「まづおのれ此縄に―をかけて」
②やすりをかけること。
③鑢やすりの異称。新撰字鏡6「錯、鑢也、己須利、又也須利、又乃保支利」
④木片に木賊とくさの枯茎を貼り付け、木などを磨くもの。
こすり‐つ・く【擦り付く】
[一]〔自五〕
こするように近寄る。
[二]〔他下二〕
⇒こすりつける(下一)
こすり‐つ・ける【擦り付ける】
〔他下一〕[文]こすりつ・く(下二)
押しつけてなすりつける。力を入れてこする。「靴の泥を石に―・ける」
こす・る【擦る・錯る】
〔他五〕
①おしつけて摩擦する。すりみがく。夏目漱石、三四郎「寐てゐた男がむつくり起きて眼を―・りながら下りて行つた」
②あてこする。いやみをいう。誹風柳多留23「どうるいがあると母親―・られる」
こ・する【鼓する】
〔他サ変〕[文]鼓す(サ変)
①うちならす。かきならす。
②ふるわす。おこす。「勇を―・する」
ご・する【伍する】
〔自サ変〕[文]伍す(サ変)
仲間に入る。同等の位置にならぶ。肩を並べる。「先輩に―・して活躍する」
こす・れる【擦れる】
〔自下一〕
互いにすれあう。
コスロー【Khosrō】
⇒ホスロー
コズロフ【Petr Kuzimich Kozlov】
ロシアの軍人・探検家。カラホトで西夏の古都市を、のち北モンゴルのノインウラで匈奴王の墓を発掘。(1863〜1935)
ご‐すん【五寸】
①1寸の5倍。
②五寸局ごすんつぼねの略。
⇒ごすん‐くぎ【五寸釘】
⇒ごすん‐つぼね【五寸局】
⇒ごすん‐もよう【五寸模様】
ごすん‐くぎ【五寸釘】
大形の釘。長さ曲尺かねじゃく5寸位(約15センチメートル)の釘。
⇒ご‐すん【五寸】
ごすん‐つぼね【五寸局】
一切りの揚代、銀5匁の局女郎。
⇒ご‐すん【五寸】
ごすん‐もよう【五寸模様】‥ヤウ
宝暦(1751〜1764)の頃流行した、着物の裾模様で、裾から5寸ほどの範囲に模様を置いたもの。
⇒ご‐すん【五寸】
こせ【巨勢】
姓氏の一つ。大和の古代豪族。高市郡巨勢郷(今、奈良県御所市古瀬)を本拠とする。武内宿祢の後裔と称す。許勢。
⇒こせ‐の‐かなおか【巨勢金岡】
こせ【瘡】
「こせがさ」の略。散木奇歌集「怪しさはみなもととこそ思ひつれ膚はだえは―のうちにぞありける」
ご‐せ【後世】
〔仏〕
①三世の一つ。死後に生まれ変わる世界。あの世。来世。ごせい。
②(→)後生善処ごしょうぜんじょに同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「最期に心乱れては人の譏り―のため」
⇒後世を弔う
ごせ【御所】
奈良県西部、大阪府に接する市。葛城地方の中心都市。製薬・繊維工業が盛ん。古代史跡が多い。人口3万2千。
ご‐ぜ【御前】
①(御前駆ごぜんくの略)(→)「みさきおい」に同じ。今昔物語集31「指貫さしぬき姿の―ども十余人」
②貴婦人の尊敬語。今昔物語集31「わが―たちの御あたりには」
③(接尾語的に用いる)女性の尊敬語。「姫―」→ごぜん
ご‐ぜ【瞽女】
(「御前ごぜ」から)三味線を弾き、唄を歌いなどして米や金銭を得た盲目の女。めくらごぜ。
こ‐せい【古生】
⇒こせい‐かい【古生界】
⇒こせい‐そう【古生層】
⇒こせい‐だい【古生代】
こ‐せい【古制】
古い時代の制度。昔のおきて。
こ‐せい【古製】
古い時代のつくり。昔の製作。
こ‐せい【呼声】
呼ばわる声。よびごえ。
こ‐せい【個性】
①(individuality)個人に具わり、他の人とはちがう、その個人にしかない性格・性質。「―を伸ばす」
②個物または個体に特有な特徴あるいは性格。
⇒こせい‐てき【個性的】
こ‐せい【糊精】
〔化〕(→)デキストリンに同じ。
こ‐ぜい【小勢】
①人数の少ない軍勢。太平記4「思ふには似ず、―なりけりと」
②少ない人数。小人数。↔大勢
こ‐ぜい【挙税】
奈良・平安時代、稲穀・銭貨を貸し出して利息を取ったこと。出挙稲すいことう。出挙銭。
ご‐せい【五声】
〔音〕
①日本・中国の音楽で、低音から宮きゅう・商しょう・角かく・徴ち・羽うの5音。また、その構成する音階。五音ごいん。→七声。
②(→)五音ごおん音階に同じ。
ご‐せい【五星】
①五つの星。
②[左伝襄公28年、注]中国で古代から知られている五惑星、すなわち歳星(木星)・熒惑けいごく(火星)・鎮星(土星)・太白(金星)・辰星(水星)の総称。五緯。
⇒ごせい‐こうき【五星紅旗】
ご‐せい【五牲】
[左伝昭公、注]いけにえに用いる5種の動物、すなわち牛・羊・豕いのこ・犬・鶏。また、麏くじか・鹿・熊・狼・野豕の総称。
ご‐せい【五清】
(画題)文人画で五つの清いものを描くこと。松・竹・梅・蘭・石。あるいは松・竹・蘭・芭蕉・石。また、梅・菊・竹・芭蕉・石。
ご‐せい【五聖】
中国古代の5人の聖人。通説では、尭ぎょう・舜しゅん・禹う・湯とう・文王をいう。
ご‐せい【互生】
〔植〕茎や枝に交互に1枚ずつ葉を生じること。サクラ・アサガオの類。互生葉序。→葉序(図)
ご‐せい【後世】
⇒ごせ。
⇒ごせい‐ほう【後世方】
ご‐せい【悟性】
〔哲〕(intellect イギリス・Verstand ドイツ)
①広義には、思考の能力。
②カントにおいては、感性に与えられる所与を認識へと構成する概念能力・判断能力で、理性と感性の中間にあり、科学的思考の主体。
③ヘーゲルにおいては、弁証法的思考能力としての理性に対して、対象を固定的にとらえ、他との区別に固執する思考能力。
⇒ごせい‐がいねん【悟性概念】
ご‐せい【碁聖】
傑出した囲碁の名手。棋聖きせい。
ご‐せい【語勢】
語ることばのいきおい。語気。語調。「―を強める」
こせい‐かい【古生界】
古生代に形成された堆積岩と火成岩。変成岩に関しては、原岩が古生代に作られたもの。
⇒こ‐せい【古生】
ごせい‐がいねん【悟性概念】
(→)範疇はんちゅう1に同じ。
⇒ご‐せい【悟性】
ごせい‐こうき【五星紅旗】
中華人民共和国の国旗。長方形紅地の左上方に、大きい1個の星と、これを弧状に囲む4個の小さい星とを黄色に染め抜く。
⇒ご‐せい【五星】
こせい‐せん【湖西線】
琵琶湖西岸を走り、東海道・北陸両本線を結ぶJR線。山科・近江塩津間、全長74.1キロメートル。
こせい‐そう【古生層】
古生代に堆積した地層。日本列島には、古生代にできた岩塊が中生層の中にとりこまれている所が多く、このような中生層は20世紀前半に秩父古生層の名でよばれていた。
⇒こ‐せい【古生】
こせい‐だい【古生代】
(Pal(a)eozoic Era)地質年代中、原生代の後、中生代の前の時代。約5億4000万年前から2億5000万年前までの時代。カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀に分ける。この時代には植物は主に隠花植物(藻類・シダ類など)、動物は主に海生の無脊椎動物(筆石・珊瑚類・海百合・腕足類など)が栄えた。古生代中頃のシルル紀末に、生物は初めて陸上に進出。→地質年代(表)
⇒こ‐せい【古生】
こ‐せいたいがく【個生態学】
動物の各種につき、その食性・繁殖その他一切の生活様式を研究する学問。種生態学とほぼ同義。↔群集生態学
こせい‐てき【個性的】
個性が表れているさま。独特なさま。「―な文章」「―な顔立ち」
⇒こ‐せい【個性】
ごせいばい‐しきもく【御成敗式目】
鎌倉幕府の基本的法典。1232年(貞永1)北条泰時が承久の乱後の当面する政治・法制の諸問題に対処するために編纂。51カ条から成り、室町幕府も武家の根本法として継承。江戸時代には手習手本として民間に普及。貞永じょうえい式目。
→文献資料[御成敗式目]
こ‐せいぶつ【古生物】
地質時代に生息していた生物の総称。マンモス・恐竜・アンモナイト・三葉虫さんようちゅう・蘆木ろぼくなどの類。
⇒こせいぶつ‐がく【古生物学】
⇒こせいぶつ‐ちりがく【古生物地理学】
こせいぶつ‐がく【古生物学】
(pal(a)eontology)古生物の系統・分類・進化・構造・生理・生態・地理的分布などを研究する学問分野。
⇒こ‐せいぶつ【古生物】
こせいぶつ‐ちりがく【古生物地理学】
化石を用いて地球史における生物の地理的分布を研究する学問分野。→生物地理学
⇒こ‐せいぶつ【古生物】
ごせい‐ほう【後世方】‥ハウ
鎌倉時代末期以降伝えられた中国の金・元の医家の処方を祖述する医家の一派。これを奉ずる医家を後世家とよび、田代三喜・曲直瀬まなせ道三・曲直瀬玄朔(1549〜1631)はその代表者。こうせいほう。↔古医方
⇒ご‐せい【後世】
ごぜ‐うた【瞽女歌】
瞽女のうたう歌。門口でうたう門付け歌のほか、段物と口説くどきを語った。山椒太夫などの段物は瞽女節とも呼んだ。越後口説も知られる。
ごぜえ・す
〔自サ変〕
「ある」「居る」を丁寧にいう語。ございます。(遊里語であるが、一般の人にも使われた)浮世床初「大学ぢやあ―・せんねえ」
こせ‐がさ
「がんがさ(雁瘡)」の異称。こせ。
こせがさわ‐いせき【小瀬ヶ沢遺跡】‥サハヰ‥
新潟県東蒲原郡阿賀町にある縄文時代草創期から早期の洞穴遺跡。縄文草創期を代表する土器・石器が出土。
こ‐せがれ【小倅】
①自分の息子の謙称。
②青年・少年をののしっていう語。
コセカント【cosecant】
〔数〕三角関数の一つ。サインの逆数。余割よかつ。記号cosec →三角関数
こせき【小関】
姓氏の一つ。
⇒こせき‐さんえい【小関三英】
こ‐せき【戸籍】
①戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にはほぼ廃絶。明治維新後復活した。へじゃく。→庚午年籍→壬申戸籍。
②国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書。
⇒こせき‐げんぽん【戸籍原本】
⇒こせき‐しょうほん【戸籍抄本】
⇒こせき‐とうほん【戸籍謄本】
⇒こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
⇒こせき‐ぼ【戸籍簿】
⇒こせき‐ほう【戸籍法】
こ‐せき【古昔】
むかし。いにしえ。
こ‐せき【古跡・古蹟】
歴史上有名な出来事や建物のあった跡。旧跡。
こせき【古関】
姓氏の一つ。
⇒こせき‐ゆうじ【古関裕而】
こ‐ぜき【小関】
要所に設けて敵の出入を防ぐ小さい関所。特に、山城国宇治郡四宮に通ずる道をいう。平家物語4「宮いらせ給ひてのちは、大関―掘りきつて」
ご‐せき【五石】
[抱朴子金丹]中国の古代に道士が長生薬を練るのに用いた5種の薬石、すなわち丹砂・雄黄・白礬石・曾青・慈石の総称。
こせき‐げんぽん【戸籍原本】
戸籍事務を管掌する市町村長が最初に作成した戸籍。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐さんえい【小関三英】
江戸後期の蘭学者・医学者。名は好義。出羽庄内鶴岡の人。江戸へ出て蘭医吉田長淑に学び、岸和田藩医を経て幕府の天文台訳員となる。渡辺崋山の依頼で、高野長英とともに蘭書を翻訳。蛮社の獄の際、自殺。著「西医原病略」、訳「那波列翁ナポレオン伝」など。(1787〜1839)
⇒こせき【小関】
こせき‐しょうほん【戸籍抄本】‥セウ‥
戸籍のうち請求者の指定した部分だけを転写した文書。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐とうほん【戸籍謄本】
戸籍原本の全部を謄写した文書。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】
戸籍の冒頭に記載されている者。戸主とは異なり、特別の権利関係を示すものではない。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ぼ【戸籍簿】
同一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ほう【戸籍法】‥ハフ
戸籍制度を規定した法律。1871年(明治4)に太政官布告で定め、1914年(大正3)に全文改正、第二次大戦後民法の親族・相続編の改正に伴って47年に全面的改正。
⇒こ‐せき【戸籍】
こせき‐ゆうじ【古関裕而】
作曲家。本名、勇治。福島県生れ。歌謡曲・応援歌・軍歌など約5000曲を作る。作「紺碧の空」「長崎の鐘」「とんがり帽子」「君の名は」など。(1909〜1989)
古関裕而
提供:毎日新聞社
 ⇒こせき【古関】
こせ‐こせ
①つまらないことにこだわって言動に余裕や落着きのないさま。夏目漱石、坊つちやん「蔭で―生意気な悪いたづらをして」。「―した態度」
②場所が狭くゆとりのないさま。「―した裏通り」
こせ‐ごと【こせ言】
しゃれ。秀句。狂言、今参「秀句―を御存じかと申す事でおりやる」
ごぜざとう【瞽女座頭】
狂言。(→)「清水きよみず座頭」に同じ。
こせ‐ざむらい【悴侍】‥ザムラヒ
(→)「かせざむらい」に同じ。
ごせ‐しゃ【後世者】
〔仏〕念仏をとなえて極楽往生を願う人。発心集「劣らぬ―なりければ」
ごせだ【五姓田】
姓氏の一つ。
⇒ごせだ‐ほうりゅう【五姓田芳柳】
⇒ごせだ‐よしまつ【五姓田義松】
ごせだ‐ほうりゅう【五姓田芳柳】‥ハウリウ
(初世)画家。本名、浅田岩吉。江戸生れ。初め歌川国芳に浮世絵を学び、のち長崎で洋画に志す。幕末、横浜に移り住み、外国人などの求めに応じて肖像画・風俗画を描いた。(1827〜1892)
⇒ごせだ【五姓田】
ごせだ‐よしまつ【五姓田義松】
洋画家。江戸生れ。初世芳柳の次子。ワーグマンに学び、工部美術学校入学。渡仏してボナに師事。パリのサロンに入選。明治美術会に参加。作「操り人形」など。(1855〜1915)
⇒ごせだ【五姓田】
ご‐せち【五節】
(遅・速・本・末・中声の五声の節の意)
①古代から朝廷で新嘗会しんじょうえ・大嘗会だいじょうえに行われた少女楽の行事。儀式は毎年11月の中の丑・寅・卯・辰の4日にわたり、丑の日に舞姫参入、その夜は帳台の試こころみ、寅の日に殿上の淵酔えんずい、その夜は御前の試(清涼殿で舞楽を天覧)、卯の日に清涼殿で童女わらわ御覧、辰の日に豊明の節会とよのあかりのせちえが行われ、群臣の前で五節の舞が奏される。
②五節の舞姫。枕草子24「受領の―いだすをりなど」
⇒ごせち‐さだめ【五節定め】
⇒ごせち‐どころ【五節所】
⇒ごせち‐どの【五節殿】
⇒ごせち‐の‐えんずい【五節の淵酔】
⇒ごせち‐の‐つぼね【五節の局】
⇒ごせち‐の‐まい【五節の舞】
⇒ごせち‐の‐まいひめ【五節の舞姫】
⇒ごせち‐の‐まいり【五節の参り】
⇒ごせち‐の‐わらわ【五節の童女】
ご‐せちえ【五節会】‥ヱ
古代より宮中で行われた五つの節会、すなわち元日・白馬あおうま・踏歌とうか・端午・豊明とよのあかり。
ご‐せちく【五節供】
⇒ごせっく(五節句)
ごせち‐さだめ【五節定め】
その年の五節の舞姫を献上すべき公卿・国司を選定すること。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐どころ【五節所】
五節の舞姫の控室。常寧殿の四隅にあり、中央に舞台が設けられた。五節の局つぼね。紫式部日記「ただ―のをかしきことを語る」
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐どの【五節殿】
(五節の舞の試演が行われたところから)常寧殿の異称。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐えんずい【五節の淵酔】‥ヱン‥
五節の寅の日に清涼殿の殿上で催される宴会。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐つぼね【五節の局】
(→)「ごせちどころ」に同じ。枕草子90「―を…みなこぼちすかして」
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まい【五節の舞】‥マヒ
五節に大歌おおうたを伴って奏する少女の舞。中世に廃絶。近代に改訂して復活。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まいひめ【五節の舞姫】‥マヒ‥
五節の舞を舞う舞姫。新嘗会しんじょうえでは四人で、二人(あるいは三人)は公卿の家、二人(あるいは一人)は国司の家から出す。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まいり【五節の参り】‥マヰリ
五節の舞姫が丑の日に五節所に参入すること。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐わらわ【五節の童女】‥ワラハ
五節の舞姫に二人ずつ付き従う童女。
⇒ご‐せち【五節】
こ‐せつ【古拙】
古風で技巧はつたないが、趣のあること。「―の美」「―な壺」
こ‐せつ【古説】
古く言われている説。ふるい説。
こ‐ぜつ【孤絶】
他とのつながりがなく、一つだけかけ離れていること。
ご‐せつ【五節】
①五節句ごせっくの略。
②(→)「ごせち(五節)」に同じ。謡曲、国栖くず「―の始めこれなれや」
ご‐ぜつ【五絶】
①五つの死の原因、すなわち縊・溺・圧・凍・驚の称。
②五つのすぐれたこと。
③漢詩の五言絶句の略。
ご‐せっきょう【五説経】‥キヤウ
説経節の代表的な五つの曲目。「山椒太夫」「苅萱かるかや」「信田妻しのだづま」「梅若」「愛護若あいごのわか」。また、「山椒太夫」「苅萱」「俊徳(信徳)丸」「小栗判官」「梵天国」の五つなど。
こせ‐つ・く
〔自五〕
こせこせする。人情本、春色辰巳園「世界中の女を―・く癖に、他ひとの事をば恋しらずだ」
ご‐せっく【五節句・五節供】
毎年5度の節句。正月7日(人日
⇒こせき【古関】
こせ‐こせ
①つまらないことにこだわって言動に余裕や落着きのないさま。夏目漱石、坊つちやん「蔭で―生意気な悪いたづらをして」。「―した態度」
②場所が狭くゆとりのないさま。「―した裏通り」
こせ‐ごと【こせ言】
しゃれ。秀句。狂言、今参「秀句―を御存じかと申す事でおりやる」
ごぜざとう【瞽女座頭】
狂言。(→)「清水きよみず座頭」に同じ。
こせ‐ざむらい【悴侍】‥ザムラヒ
(→)「かせざむらい」に同じ。
ごせ‐しゃ【後世者】
〔仏〕念仏をとなえて極楽往生を願う人。発心集「劣らぬ―なりければ」
ごせだ【五姓田】
姓氏の一つ。
⇒ごせだ‐ほうりゅう【五姓田芳柳】
⇒ごせだ‐よしまつ【五姓田義松】
ごせだ‐ほうりゅう【五姓田芳柳】‥ハウリウ
(初世)画家。本名、浅田岩吉。江戸生れ。初め歌川国芳に浮世絵を学び、のち長崎で洋画に志す。幕末、横浜に移り住み、外国人などの求めに応じて肖像画・風俗画を描いた。(1827〜1892)
⇒ごせだ【五姓田】
ごせだ‐よしまつ【五姓田義松】
洋画家。江戸生れ。初世芳柳の次子。ワーグマンに学び、工部美術学校入学。渡仏してボナに師事。パリのサロンに入選。明治美術会に参加。作「操り人形」など。(1855〜1915)
⇒ごせだ【五姓田】
ご‐せち【五節】
(遅・速・本・末・中声の五声の節の意)
①古代から朝廷で新嘗会しんじょうえ・大嘗会だいじょうえに行われた少女楽の行事。儀式は毎年11月の中の丑・寅・卯・辰の4日にわたり、丑の日に舞姫参入、その夜は帳台の試こころみ、寅の日に殿上の淵酔えんずい、その夜は御前の試(清涼殿で舞楽を天覧)、卯の日に清涼殿で童女わらわ御覧、辰の日に豊明の節会とよのあかりのせちえが行われ、群臣の前で五節の舞が奏される。
②五節の舞姫。枕草子24「受領の―いだすをりなど」
⇒ごせち‐さだめ【五節定め】
⇒ごせち‐どころ【五節所】
⇒ごせち‐どの【五節殿】
⇒ごせち‐の‐えんずい【五節の淵酔】
⇒ごせち‐の‐つぼね【五節の局】
⇒ごせち‐の‐まい【五節の舞】
⇒ごせち‐の‐まいひめ【五節の舞姫】
⇒ごせち‐の‐まいり【五節の参り】
⇒ごせち‐の‐わらわ【五節の童女】
ご‐せちえ【五節会】‥ヱ
古代より宮中で行われた五つの節会、すなわち元日・白馬あおうま・踏歌とうか・端午・豊明とよのあかり。
ご‐せちく【五節供】
⇒ごせっく(五節句)
ごせち‐さだめ【五節定め】
その年の五節の舞姫を献上すべき公卿・国司を選定すること。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐どころ【五節所】
五節の舞姫の控室。常寧殿の四隅にあり、中央に舞台が設けられた。五節の局つぼね。紫式部日記「ただ―のをかしきことを語る」
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐どの【五節殿】
(五節の舞の試演が行われたところから)常寧殿の異称。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐えんずい【五節の淵酔】‥ヱン‥
五節の寅の日に清涼殿の殿上で催される宴会。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐つぼね【五節の局】
(→)「ごせちどころ」に同じ。枕草子90「―を…みなこぼちすかして」
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まい【五節の舞】‥マヒ
五節に大歌おおうたを伴って奏する少女の舞。中世に廃絶。近代に改訂して復活。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まいひめ【五節の舞姫】‥マヒ‥
五節の舞を舞う舞姫。新嘗会しんじょうえでは四人で、二人(あるいは三人)は公卿の家、二人(あるいは一人)は国司の家から出す。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐まいり【五節の参り】‥マヰリ
五節の舞姫が丑の日に五節所に参入すること。
⇒ご‐せち【五節】
ごせち‐の‐わらわ【五節の童女】‥ワラハ
五節の舞姫に二人ずつ付き従う童女。
⇒ご‐せち【五節】
こ‐せつ【古拙】
古風で技巧はつたないが、趣のあること。「―の美」「―な壺」
こ‐せつ【古説】
古く言われている説。ふるい説。
こ‐ぜつ【孤絶】
他とのつながりがなく、一つだけかけ離れていること。
ご‐せつ【五節】
①五節句ごせっくの略。
②(→)「ごせち(五節)」に同じ。謡曲、国栖くず「―の始めこれなれや」
ご‐ぜつ【五絶】
①五つの死の原因、すなわち縊・溺・圧・凍・驚の称。
②五つのすぐれたこと。
③漢詩の五言絶句の略。
ご‐せっきょう【五説経】‥キヤウ
説経節の代表的な五つの曲目。「山椒太夫」「苅萱かるかや」「信田妻しのだづま」「梅若」「愛護若あいごのわか」。また、「山椒太夫」「苅萱」「俊徳(信徳)丸」「小栗判官」「梵天国」の五つなど。
こせ‐つ・く
〔自五〕
こせこせする。人情本、春色辰巳園「世界中の女を―・く癖に、他ひとの事をば恋しらずだ」
ご‐せっく【五節句・五節供】
毎年5度の節句。正月7日(人日つち‐の‐と【己】🔗⭐🔉
つち‐の‐と【己】
(「土の弟おと」の意)十干じっかんの第6。
な【己・汝】🔗⭐🔉
な【己・汝】
〔代〕
①自分。おのれ。万葉集9「―が心から鈍おそやこの君」
②転じて、おまえ。なんじ。なれ。いまし。古事記上「―こそは男おにいませば」
[漢]己🔗⭐🔉
己 字形
 筆順
筆順
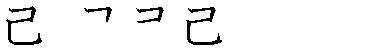 〔己部0画/3画/教育/2442・384A〕
〔音〕コ(呉) キ(漢)
〔訓〕おのれ・つちのと
[意味]
①自分。おのれ。「知己ちき・克己こっき・自己・利己・一己」
②十干の第六。つちのと。「己丑きちゅう」
[解字]
解字
〔己部0画/3画/教育/2442・384A〕
〔音〕コ(呉) キ(漢)
〔訓〕おのれ・つちのと
[意味]
①自分。おのれ。「知己ちき・克己こっき・自己・利己・一己」
②十干の第六。つちのと。「己丑きちゅう」
[解字]
解字 象形。古代の土器の模様の一部。人の目をひく模様であることから、「おのれ」の意に用いられた。一説に、先端を引き出した糸の形で、「はじめ」の意を示したとする。
[難読]
己惚うぬぼれ
象形。古代の土器の模様の一部。人の目をひく模様であることから、「おのれ」の意に用いられた。一説に、先端を引き出した糸の形で、「はじめ」の意を示したとする。
[難読]
己惚うぬぼれ
 筆順
筆順
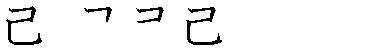 〔己部0画/3画/教育/2442・384A〕
〔音〕コ(呉) キ(漢)
〔訓〕おのれ・つちのと
[意味]
①自分。おのれ。「知己ちき・克己こっき・自己・利己・一己」
②十干の第六。つちのと。「己丑きちゅう」
[解字]
解字
〔己部0画/3画/教育/2442・384A〕
〔音〕コ(呉) キ(漢)
〔訓〕おのれ・つちのと
[意味]
①自分。おのれ。「知己ちき・克己こっき・自己・利己・一己」
②十干の第六。つちのと。「己丑きちゅう」
[解字]
解字 象形。古代の土器の模様の一部。人の目をひく模様であることから、「おのれ」の意に用いられた。一説に、先端を引き出した糸の形で、「はじめ」の意を示したとする。
[難読]
己惚うぬぼれ
象形。古代の土器の模様の一部。人の目をひく模様であることから、「おのれ」の意に用いられた。一説に、先端を引き出した糸の形で、「はじめ」の意を示したとする。
[難読]
己惚うぬぼれ
広辞苑に「己」で始まるの検索結果 1-51。