複数辞典一括検索+![]()
![]()
いた・む【炒む・煠む】🔗⭐🔉
いた・む【炒む・煠む】
〔他下二〕
⇒いためる(下一)
いため‐じお【撓塩・炒め塩】‥ジホ🔗⭐🔉
いため‐じお【撓塩・炒め塩】‥ジホ
やきしお。枕草子一本4「心えぬもの、―、あこめ、かたびら」
いため‐に【炒め煮】🔗⭐🔉
いため‐に【炒め煮】
材料を油で炒め、出し汁と調味料を加えて煮ること。また、その料理。「ヒジキの―」
いため‐もの【炒め物】🔗⭐🔉
いため‐もの【炒め物】
野菜・魚肉類などを油で炒めた料理。
いた・める【炒める・煠める】🔗⭐🔉
いた・める【炒める・煠める】
〔他下一〕[文]いた・む(下二)
食品を少量の油を使って加熱・調理する。「ほうれん草を―・める」
いり‐あられ【炒霰】🔗⭐🔉
いり‐あられ【炒霰】
采の目に切った青・赤・白の餅を炒って砂糖をまぶしたもの。雛祭に供える。
いり‐がし【炒菓子】‥グワ‥🔗⭐🔉
いり‐がし【炒菓子】‥グワ‥
米・豆などに砂糖を加えて炒った菓子。
いり‐かや【炒榧】🔗⭐🔉
いり‐かや【炒榧】
カヤの果実を炒って作った菓子。
いり‐がら【炒殻】🔗⭐🔉
いり‐がら【炒殻】
①クジラの脂身を細く切り、炒って脂を取り、乾かした食品。
②おからを炒って、味を添えたもの。
いり‐がわら【炒瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉
いり‐がわら【炒瓦】‥ガハラ
いりなべ。ほうろく。
いり‐こ【炒子】🔗⭐🔉
いり‐こ【炒子】
小さな雑魚ざこを炒って干したもの。いりじゃこ。いりぼし。
いり‐こ【炒粉】🔗⭐🔉
いり‐こ【炒粉】
①米の粉を炒ったもの。菓子だねにする。
②むぎこがし。
いり‐こぶ【炒昆布】🔗⭐🔉
いり‐こぶ【炒昆布】
炒るか油で揚げるかした昆布。
いり‐ごま【炒胡麻】🔗⭐🔉
いり‐ごま【炒胡麻】
炒った胡麻。
いり‐ごめ【炒米】🔗⭐🔉
いり‐ごめ【炒米】
炒った米。
いり‐じお【炒塩】‥ジホ🔗⭐🔉
いり‐じお【炒塩】‥ジホ
いった塩。焼き塩。
いり‐ずみ【炒炭】🔗⭐🔉
いり‐ずみ【炒炭】
火にあぶって湿気を去り、火のつきやすいようにした炭。
いり‐だね【炒種】🔗⭐🔉
いり‐だね【炒種】
米・糯粟もちあわなどを蒸して挽き割って炒った粒種。おめで糖・おこしなどの材料。
いり‐たまご【煎玉子・炒卵】🔗⭐🔉
いり‐たまご【煎玉子・炒卵】
溶きほぐして調味した鶏卵を煎りつけた料理。
いり‐なべ【炒鍋】🔗⭐🔉
いり‐なべ【炒鍋】
肉・豆・野菜などを炒るのに用いる浅い鉄製の鍋。土製のものもある。ほうろく。
いり‐に【炒煮】🔗⭐🔉
いり‐に【炒煮】
油でいためてから煮る調理法。
いり‐ふね【炒船】🔗⭐🔉
いり‐ふね【炒船】
瀬戸内海の鰯網いわしあみ漁業などに付随し、船中に釜を据え、とれた鰯をゆがいた加工船。いりやぶね。
いり‐ぼし【熬乾・炒干】🔗⭐🔉
いり‐ぼし【熬乾・炒干】
小魚を炒ってほしたもの。いりこ。だしこ。こわいじゃこ。いりじゃこ。
いり‐まめ【炒豆】🔗⭐🔉
いり‐まめ【炒豆】
①大豆を炒ったもの。
②まめいり。
⇒炒豆に花
○炒豆に花いりまめにはな
あるはずのないことが実現すること。めったにないことのたとえ。「いり豆に花が咲く」とも。毛吹草6「―のためしか除夜の雪」
⇒いり‐まめ【炒豆】
○炒豆に花いりまめにはな🔗⭐🔉
○炒豆に花いりまめにはな
あるはずのないことが実現すること。めったにないことのたとえ。「いり豆に花が咲く」とも。毛吹草6「―のためしか除夜の雪」
⇒いり‐まめ【炒豆】
いり‐み【入身】
①相撲で、相手の身に自分の身を入れ込むこと。相手に接近して攻撃するわざ。
②武道の試合などで、攻撃をしかける側。武道伝来記「次に竹刀ちくとう、其の―には、小石与四郎とて家中若手の内の達者なるが出たるに」
いり‐みだ・れる【入り乱れる】
〔自下一〕[文]いりみだ・る(下二)
入りまじり混乱する。「敵味方―・れて戦う」「情報が―・れる」
いり‐むぎ【炒麦】
大麦を炒り焦がし、碾ひいて粉にしたもの。砂糖をまぜて食べ、また、菓子種などにする。むぎこがし。〈字鏡集〉→糗はったい→香煎こうせん
いり‐むこ【入り婿】
他家に入ってその家の娘の婿となること。また、その人。婿養子。入夫。好色一代男2「世之介是非に―」
いり‐め【入目】
①費用。入費。〈日葡辞書〉
②控えめなこと。気弱なさま。吾妻問答「―にもなく又さし出でても見えぬ様に」
いり‐め・く【炒りめく】
〔自四〕
物が炒られたように、ひしめきさわぐ。今昔物語集25「―・きあひて、ののしる」
いり‐めし【炒飯】
炒った飯。やきめし。チャーハン。
いり‐もの【炒物・煎物・熬物】
①肉類・野菜などを鍋の中で炒って水分を去り、または油でいためた料理。
②豆・米などを炒ったもの。
いり‐も・む【いり揉む】
〔自他四〕
①はげしく揉む。風などが吹き荒れる。源氏物語明石「ひねもすに―・みつる風のさわぎに」
②はげしく気をいらだたせる。身をもむ。宇治拾遺物語11「―・み申して御前にうつぶし」
③是非願いを叶え給えと祈る。栄華物語鶴林「仏を―・み奉る」
いり‐もや【入母屋】
上部は切妻きりづまのように2方へ勾配を有し、下部は寄棟造のように4方へ勾配を有する屋根形。
入母屋
 ⇒いりもや‐づくり【入母屋造】
⇒いりもや‐はふ【入母屋破風】
いりもや‐づくり【入母屋造】
入母屋に造る屋根の様式。法隆寺金堂の屋根の類。また、広くはこの屋根をもつ建築の様式をさす。
⇒いり‐もや【入母屋】
いりもや‐はふ【入母屋破風】
入母屋屋根の破風。
⇒いり‐もや【入母屋】
いりや【入谷】
東京都台東区北部の地名。毎年7月の朝顔市は有名。「恐れ―の鬼子母神」
いり‐やき【熬焼】
うすめに切った鳥獣の肉を空鍋で焼いた料理。
いり‐やまがた【入山形】
①紋所の名。「入」の字の形にした山形。
入山形
⇒いりもや‐づくり【入母屋造】
⇒いりもや‐はふ【入母屋破風】
いりもや‐づくり【入母屋造】
入母屋に造る屋根の様式。法隆寺金堂の屋根の類。また、広くはこの屋根をもつ建築の様式をさす。
⇒いり‐もや【入母屋】
いりもや‐はふ【入母屋破風】
入母屋屋根の破風。
⇒いり‐もや【入母屋】
いりや【入谷】
東京都台東区北部の地名。毎年7月の朝顔市は有名。「恐れ―の鬼子母神」
いり‐やき【熬焼】
うすめに切った鳥獣の肉を空鍋で焼いた料理。
いり‐やまがた【入山形】
①紋所の名。「入」の字の形にした山形。
入山形
 ②遊女の階級を示す記号。吉原細見に使用。「入山形に星(後には二つ星)」を最高級とした。
いり‐ゆ【炒湯】
炒米を湯に入れ、その香を移したもの。
い‐りゅう【移流】‥リウ
〔理〕(advection)流体中に分散した物質やエネルギーが流れによって運ばれること。多くは水平方向の移動に用いる。
⇒いりゅう‐ぎり【移流霧】
い‐りゅう【慰留】ヰリウ
なだめて、辞任などを思いとどまらせること。「辞表を出したが―された」
い‐りゅう【遺留】ヰリウ
①死後にのこすこと。
②置き忘れること。
⇒いりゅう‐ひん【遺留品】
⇒いりゅう‐ぶん【遺留分】
いりゅう‐ぎり【移流霧】‥リウ‥
湿った暖かい気団が冷たい地表や海面上を移動するとき、その下層部が冷やされて発生する霧。→蒸気霧
⇒い‐りゅう【移流】
イリュージョン【illusion】
幻影。幻覚。幻想。錯覚。
いりゅう‐ひん【遺留品】ヰリウ‥
①死後にのこした品。
②持ち主が立ち去ったあとに残された品。「犯人の―を探す」
⇒い‐りゅう【遺留】
いりゅう‐ぶん【遺留分】ヰリウ‥
〔法〕被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者のために保障される相続財産の割合。この割合を超える遺贈や贈与は減殺げんさい請求によって効力を失う。
⇒い‐りゅう【遺留】
い‐りょ【倚閭】
(「閭」は村里の門、「倚」はよるの意)母が村の入口の門によりかかって子の帰るのを待ちわびること。「―の望」→倚門
い‐りょう【井料】ヰレウ
中世、用水の使用料または維持費。井料米(堰料米)・井料田の形で、領主側が負担する場合と農民側が負担する場合とがある。
い‐りょう【衣料】‥レウ
衣服、また、その材料である布地などの総称。
⇒いりょう‐きっぷ【衣料切符】
⇒いりょう‐ひん【衣料品】
い‐りょう【衣糧】‥リヤウ
衣類と食糧。
い‐りょう【医料】‥レウ
医師の治療に対して支払う料金。
い‐りょう【医療】‥レウ
医術で病気をなおすこと。療治。治療。
⇒いりょう‐かご【医療過誤】
⇒いりょうぎじゅつ‐たんきだいがく【医療技術短期大学】
⇒いりょう‐くみあい【医療組合】
⇒いりょう‐ソーシャル‐ワーク【医療ソーシャルワーク】
⇒いりょうひよう‐ほけん【医療費用保険】
⇒いりょう‐ふくし【医療福祉】
⇒いりょう‐ふじょ【医療扶助】
⇒いりょう‐ほう【医療法】
⇒いりょう‐ほうじん【医療法人】
⇒いりょう‐ほけん【医療保険】
⇒いりょうほしょう‐ほけん【医療保障保険】
い‐りょう【違令】ヰリヤウ
令の規定にそむくこと。
い‐りょう【遺令】ヰリヤウ
死後に遺した命令。いれい。
⇒いりょう‐の‐そう【遺令の奏】
い‐りょう【遺領】ヰリヤウ
死後に残された領地。
いり‐よう【入り用】
①入費。費用。色道大鏡「万事の―家主より調へてわたす法なり」
②ある用事のために必要なこと。にゅうよう。「―な品」「金が―になる」
いりょう‐かご【医療過誤】‥レウクワ‥
診断・治療の不適正、施設の不備等によって医療上の事故を起こすこと。誤診・誤療などがその例。刑事上・民事上の責任を問われうる。
⇒い‐りょう【医療】
いりょうぎじゅつ‐たんきだいがく【医療技術短期大学】‥レウ‥
看護師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士などの育成を目的とした短期大学。所定の課程を修了すれば国家試験の受験資格を取得できる。近年4年制への再編が進む。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐きっぷ【衣料切符】‥レウ‥
配給制度のもとで、衣料の分配のため官公庁が発行する切符。1942年から51年まで実施。
⇒い‐りょう【衣料】
いりょう‐くみあい【医療組合】‥レウ‥アヒ
医療利用組合の略。特に農村地域において組合員の出資により診療所を設け、低料金で診療をうけることを目的としたもの。1922年(大正11)長野県に始まり、全国に広まった。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ソーシャル‐ワーク【医療ソーシャルワーク】‥レウ‥
(medical social work)医療機関において行われる、疾病や心身障害などによって起こる患者と家族の精神的・社会的・経済的な問題についての相談・援助。MSW
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐の‐そう【遺令の奏】ヰリヤウ‥
古代、皇后・中宮・女院などの死去した際、その遺言を奏聞する儀式。
⇒い‐りょう【遺令】
いりょうひよう‐ほけん【医療費用保険】‥レウ‥
損害保険の一種。健康保険の自己負担分などのほか、同保険対象外の高度医療の費用の支払が目的。掛け捨て型。→医療保障保険。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ひん【衣料品】‥レウ‥
商品としての、衣類やその素材などの総称。
⇒い‐りょう【衣料】
いりょう‐ふくし【医療福祉】‥レウ‥
保健・医療・福祉の連携による総合的な社会福祉サービス。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ふじょ【医療扶助】‥レウ‥
生活困窮者の疾病・負傷に対して行われる医療のための給付。生活保護法に規定。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほう【医療法】‥レウハフ
医療施設のあり方を定める法律。診療所・助産所・病院・総合病院・公的医療機関などの構造設備・人的構成・管理体制・適正配置、医療法人に関する規則を規定。1942年公布の国民医療法に代えて、48年制定。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほうじん【医療法人】‥レウハフ‥
医療法に基づき、私的医療機関に与えられる法人格。利益追求を否定されている医療機関の継続性と資金の集積、また医療の普及向上をはかるため、1950年導入された。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほけん【医療保険】‥レウ‥
健康保険・国民健康保険など医療保障を扱う社会保険の総称。→疾病しっぺい保険。
⇒い‐りょう【医療】
いりょうほしょう‐ほけん【医療保障保険】‥レウ‥シヤウ‥
生命保険の一種。健康保険の自己負担分、差額ベッド代などの支払が目的。掛け捨て型。→医療費用保険
⇒い‐りょう【医療】
い‐りょく【威力】ヰ‥
①他を圧倒して服従させる強い力。「―を発揮する」「金の―」
②〔法〕人の意思を制圧するに足りる威圧的な行為。威力業務妨害罪・競売入札妨害罪を構成する行為などがこれにあたる。
い‐りょく【偉力】ヰ‥
すぐれて大きな力。
い‐りょく【意力】
意志の力。精神力。
いり‐よね【入米・糴】
(→)「かいよね(買米)」に同じ。
いり‐わけ【入り訳】
いりくんだ事情。浄瑠璃、八百屋お七「此の―をとつくりと云ひ聞かせたら」
い‐りん【彝倫】
(「彝」は常、「倫」は道の意)人として常に守るべき道。
い・る【入る】
[一]〔自五〕
①外から中に移動する。はいる。万葉集4「わが背子が着けせる衣の針目落ちず―・りにけらしもわが情こころさへ」。万葉集12「出づる日の―・る別わき知らぬわれし苦しも」。日葡辞書「イエニイル」。「思いがけず手に―・る」「仏門に―・る」「念が―・った仕事をする」
▷現代ではふつう「はいる」を使う。
②時間が経ち、ある区切られた時間・期間の内になる。また、年月が重なる。老境に達する。源氏物語若菜上「としまかり―・り侍りて」。大鏡道隆「夜に―・りぬれば御前の松の光にとほりて」。無名抄「いかにもさかひに―・らずしてよみいでがたきさまなり」。「寒に―・る」
③進んで行き、ある段階に達する。「技わざ神しんに―・る」「話が佳境に―・る」
④果実の内部がいっぱいになる。みのる。熟する。はいる。「稲の実が―・る」
⑤物の間に生じる。はいる。狂言、枕物狂「天目ほどの靨えくぼが七八十―・つた」。「ひびが―・る」
⑥(「要る」とも書く)必要とする。入用である。かかる。源氏物語梅枝「これは暇いとま―・りぬべきものかな」。「根気が―・る」
⑦他の動詞の連用形に付いて意味を強める。
㋐完全にその状態になったことを表す。伊勢物語「死に―・りたりければ」。竹取物語「絶え―・り給ひぬ」。「恥じ―・る」
㋑その動作をひたすら行うことを表す。源氏物語夕霧「いみじう泣き―・りつつ」。源氏物語玉鬘「額に手をあてて念じ―・りて居り」。「拝み―・る」
[二]〔他下二〕
⇒いれる(下一)
⇒入るを量りて出ずるを為す
い・る【炒る・煎る・熬る】
〔他五〕
水気のなくなるまで煮つめる。また、乾いたものを、土鍋などで熱する。西大寺本最勝王経平安初期点「王…倍増ますます憂の火に煎イラれ」。「豆を―・る」「卵を―・る」
い・る【要る】
〔自五〕
⇒いる(入る)[一]6
い・る【齭る】ヰル
〔自四〕
酸いものを食べて歯がうく。〈倭名類聚鈔2〉
いる【沃る】
〔他上一〕
注ぐ。浴びせる。蜻蛉日記中「おもてに水なむいるべき」
いる【居る】ヰル
〔自上一〕
(動くものが一つの場所に存在する意。現代語では動くと意識したものが存在する意で用い、意識しないものが存在する意の「ある」と使い分ける)
①一つの場所を、動かないでいる。とどまる。とまる。孝徳紀「山川に鴛鴦おし二つゐて」。万葉集12「みさごゐる渚すにゐる舟の」。万葉集14「霞ゐる富士の山傍やまびに」。万葉集3「三船の山にゐる雲の常にあらむと」。源氏物語若紫「このゐたる大人」。源氏物語若菜下「蓮葉に玉ゐる露の」。「ここにいなさい」
②すわる。万葉集10「立ちてもゐても君をしそ思ふ」。伊勢物語「立ちて見、ゐて見れど」
③動くものが存在する。主に、人・動物に用いる。「彼は東京にいる」「家には妻がいる」「前にバスがいる」
④出来てある時間そこにある。生じる。金葉和歌集春「つららゐし細谷川のとけゆくは」。千載和歌集冬「やどりし水も氷ゐにけり」
⑤草などが、生える。源氏物語幻「よるべの水に水草みくさゐめ」
⑥ある地位につく。大鏡師輔「式部卿の宮帝にゐさせ給ひなば西宮殿の族ぞうに世の中移りて」
⑦居住する。住み着く。徒然草「第一に食ひ物、第二に着るもの、第三にゐる所なり」
⑧動揺した気がおさまる。落ちつく。平家物語9「梶原この詞に腹がゐて」
⑨動詞の連用形、またはそれに助詞「て」(撥音を受ける時は「で」)の付いたものなどに接続して、動作の継続や、動作・事象の変化した状態が存続している意を表す。…し続ける。ずっと…する。万葉集17「籠りゐて君に恋ふるに心神こころどもなし」。伊勢物語「住吉の浜をゆくにいと面白ければおりゐつつゆく」。猿蓑「鳥共も寝入りてゐるか余吾の海」(路通)。「よく知っている」「本を読んでいる」「彼とは一度会っている」
⇒居ても立っても居られない
いる【射る】
〔他上一〕
(近世後期からラ行五段にも活用)
①弓につがえて、矢を放つ。万葉集1「大夫ますらおのさつ矢手挿み立ち向ひ射る円方まとかたは見るにさやけし」
②矢や弾丸を目標にあてる。平家物語7「馬をも射させ、かちだちになり」。木下尚江、良人の自白「拙者を射らずして却て君を撃つた」。「的まとを射る」
③(光が)鋭くあたる。森鴎外、舞姫「何等の光彩ぞ、我目を射むとするは」。江見水蔭、船頭大将「眉毛濃く眼鋭くして人を射りぬ」
④ねらって取る。「利を射る」
いる【率る・将る】ヰル
〔他上一〕
①連れて行く。ひきいる。南海寄帰内法伝平安後期点「請して将ヰて内に入れて供養す」
②身につけて行く。携帯する。増鏡「内侍所・神璽・宝剣ばかりをぞ、忍びてゐて渡させ給ふ」
いる【鋳る】
〔他上一〕
金属をとかして鋳型に流し込み、固めて器物を造る。鋳造する。三蔵法師伝永久点「宮中に於て金像一躯を鋳イル」
い‐るい【衣類】
身に着る物の総称。着物類。「冬の―をしまう」
い‐るい【異類】
①類を異にするもの。異種。
②人間でないもの。禽獣または変化へんげの類。太平記5「―・異形いぎょうのばけものども」
⇒いるい‐こんいん‐たん【異類婚姻譚】
い‐るい【彙類】ヰ‥
①同じたぐい。同類。
②分類。
いるい‐こんいん‐たん【異類婚姻譚】
説話類型の一つ。動物・精霊などと人間との結婚を主題とする話。異類が男性の場合(蛇聟入り・猿聟入りなど)と女性の場合(鶴女房・蛤女房など)とがある。
⇒い‐るい【異類】
いるか【海豚】
歯クジラ類のうちの小形種の総称。体長1〜5メートル。両顎に歯があり、体形は紡錘状で頭部は長く延びる。背びれはふつう鎌形で大きい。前肢はひれとなり、後肢を欠く。群をなして遊泳。種類が多い。しばしば船舶に平行して走る。マイルカは背部藍黒色、腹部白色。大西洋・インド洋、その他日本近海にも産。〈[季]冬〉。新撰字鏡9「鮪、伊留加」
まいるか
②遊女の階級を示す記号。吉原細見に使用。「入山形に星(後には二つ星)」を最高級とした。
いり‐ゆ【炒湯】
炒米を湯に入れ、その香を移したもの。
い‐りゅう【移流】‥リウ
〔理〕(advection)流体中に分散した物質やエネルギーが流れによって運ばれること。多くは水平方向の移動に用いる。
⇒いりゅう‐ぎり【移流霧】
い‐りゅう【慰留】ヰリウ
なだめて、辞任などを思いとどまらせること。「辞表を出したが―された」
い‐りゅう【遺留】ヰリウ
①死後にのこすこと。
②置き忘れること。
⇒いりゅう‐ひん【遺留品】
⇒いりゅう‐ぶん【遺留分】
いりゅう‐ぎり【移流霧】‥リウ‥
湿った暖かい気団が冷たい地表や海面上を移動するとき、その下層部が冷やされて発生する霧。→蒸気霧
⇒い‐りゅう【移流】
イリュージョン【illusion】
幻影。幻覚。幻想。錯覚。
いりゅう‐ひん【遺留品】ヰリウ‥
①死後にのこした品。
②持ち主が立ち去ったあとに残された品。「犯人の―を探す」
⇒い‐りゅう【遺留】
いりゅう‐ぶん【遺留分】ヰリウ‥
〔法〕被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者のために保障される相続財産の割合。この割合を超える遺贈や贈与は減殺げんさい請求によって効力を失う。
⇒い‐りゅう【遺留】
い‐りょ【倚閭】
(「閭」は村里の門、「倚」はよるの意)母が村の入口の門によりかかって子の帰るのを待ちわびること。「―の望」→倚門
い‐りょう【井料】ヰレウ
中世、用水の使用料または維持費。井料米(堰料米)・井料田の形で、領主側が負担する場合と農民側が負担する場合とがある。
い‐りょう【衣料】‥レウ
衣服、また、その材料である布地などの総称。
⇒いりょう‐きっぷ【衣料切符】
⇒いりょう‐ひん【衣料品】
い‐りょう【衣糧】‥リヤウ
衣類と食糧。
い‐りょう【医料】‥レウ
医師の治療に対して支払う料金。
い‐りょう【医療】‥レウ
医術で病気をなおすこと。療治。治療。
⇒いりょう‐かご【医療過誤】
⇒いりょうぎじゅつ‐たんきだいがく【医療技術短期大学】
⇒いりょう‐くみあい【医療組合】
⇒いりょう‐ソーシャル‐ワーク【医療ソーシャルワーク】
⇒いりょうひよう‐ほけん【医療費用保険】
⇒いりょう‐ふくし【医療福祉】
⇒いりょう‐ふじょ【医療扶助】
⇒いりょう‐ほう【医療法】
⇒いりょう‐ほうじん【医療法人】
⇒いりょう‐ほけん【医療保険】
⇒いりょうほしょう‐ほけん【医療保障保険】
い‐りょう【違令】ヰリヤウ
令の規定にそむくこと。
い‐りょう【遺令】ヰリヤウ
死後に遺した命令。いれい。
⇒いりょう‐の‐そう【遺令の奏】
い‐りょう【遺領】ヰリヤウ
死後に残された領地。
いり‐よう【入り用】
①入費。費用。色道大鏡「万事の―家主より調へてわたす法なり」
②ある用事のために必要なこと。にゅうよう。「―な品」「金が―になる」
いりょう‐かご【医療過誤】‥レウクワ‥
診断・治療の不適正、施設の不備等によって医療上の事故を起こすこと。誤診・誤療などがその例。刑事上・民事上の責任を問われうる。
⇒い‐りょう【医療】
いりょうぎじゅつ‐たんきだいがく【医療技術短期大学】‥レウ‥
看護師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士などの育成を目的とした短期大学。所定の課程を修了すれば国家試験の受験資格を取得できる。近年4年制への再編が進む。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐きっぷ【衣料切符】‥レウ‥
配給制度のもとで、衣料の分配のため官公庁が発行する切符。1942年から51年まで実施。
⇒い‐りょう【衣料】
いりょう‐くみあい【医療組合】‥レウ‥アヒ
医療利用組合の略。特に農村地域において組合員の出資により診療所を設け、低料金で診療をうけることを目的としたもの。1922年(大正11)長野県に始まり、全国に広まった。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ソーシャル‐ワーク【医療ソーシャルワーク】‥レウ‥
(medical social work)医療機関において行われる、疾病や心身障害などによって起こる患者と家族の精神的・社会的・経済的な問題についての相談・援助。MSW
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐の‐そう【遺令の奏】ヰリヤウ‥
古代、皇后・中宮・女院などの死去した際、その遺言を奏聞する儀式。
⇒い‐りょう【遺令】
いりょうひよう‐ほけん【医療費用保険】‥レウ‥
損害保険の一種。健康保険の自己負担分などのほか、同保険対象外の高度医療の費用の支払が目的。掛け捨て型。→医療保障保険。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ひん【衣料品】‥レウ‥
商品としての、衣類やその素材などの総称。
⇒い‐りょう【衣料】
いりょう‐ふくし【医療福祉】‥レウ‥
保健・医療・福祉の連携による総合的な社会福祉サービス。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ふじょ【医療扶助】‥レウ‥
生活困窮者の疾病・負傷に対して行われる医療のための給付。生活保護法に規定。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほう【医療法】‥レウハフ
医療施設のあり方を定める法律。診療所・助産所・病院・総合病院・公的医療機関などの構造設備・人的構成・管理体制・適正配置、医療法人に関する規則を規定。1942年公布の国民医療法に代えて、48年制定。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほうじん【医療法人】‥レウハフ‥
医療法に基づき、私的医療機関に与えられる法人格。利益追求を否定されている医療機関の継続性と資金の集積、また医療の普及向上をはかるため、1950年導入された。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほけん【医療保険】‥レウ‥
健康保険・国民健康保険など医療保障を扱う社会保険の総称。→疾病しっぺい保険。
⇒い‐りょう【医療】
いりょうほしょう‐ほけん【医療保障保険】‥レウ‥シヤウ‥
生命保険の一種。健康保険の自己負担分、差額ベッド代などの支払が目的。掛け捨て型。→医療費用保険
⇒い‐りょう【医療】
い‐りょく【威力】ヰ‥
①他を圧倒して服従させる強い力。「―を発揮する」「金の―」
②〔法〕人の意思を制圧するに足りる威圧的な行為。威力業務妨害罪・競売入札妨害罪を構成する行為などがこれにあたる。
い‐りょく【偉力】ヰ‥
すぐれて大きな力。
い‐りょく【意力】
意志の力。精神力。
いり‐よね【入米・糴】
(→)「かいよね(買米)」に同じ。
いり‐わけ【入り訳】
いりくんだ事情。浄瑠璃、八百屋お七「此の―をとつくりと云ひ聞かせたら」
い‐りん【彝倫】
(「彝」は常、「倫」は道の意)人として常に守るべき道。
い・る【入る】
[一]〔自五〕
①外から中に移動する。はいる。万葉集4「わが背子が着けせる衣の針目落ちず―・りにけらしもわが情こころさへ」。万葉集12「出づる日の―・る別わき知らぬわれし苦しも」。日葡辞書「イエニイル」。「思いがけず手に―・る」「仏門に―・る」「念が―・った仕事をする」
▷現代ではふつう「はいる」を使う。
②時間が経ち、ある区切られた時間・期間の内になる。また、年月が重なる。老境に達する。源氏物語若菜上「としまかり―・り侍りて」。大鏡道隆「夜に―・りぬれば御前の松の光にとほりて」。無名抄「いかにもさかひに―・らずしてよみいでがたきさまなり」。「寒に―・る」
③進んで行き、ある段階に達する。「技わざ神しんに―・る」「話が佳境に―・る」
④果実の内部がいっぱいになる。みのる。熟する。はいる。「稲の実が―・る」
⑤物の間に生じる。はいる。狂言、枕物狂「天目ほどの靨えくぼが七八十―・つた」。「ひびが―・る」
⑥(「要る」とも書く)必要とする。入用である。かかる。源氏物語梅枝「これは暇いとま―・りぬべきものかな」。「根気が―・る」
⑦他の動詞の連用形に付いて意味を強める。
㋐完全にその状態になったことを表す。伊勢物語「死に―・りたりければ」。竹取物語「絶え―・り給ひぬ」。「恥じ―・る」
㋑その動作をひたすら行うことを表す。源氏物語夕霧「いみじう泣き―・りつつ」。源氏物語玉鬘「額に手をあてて念じ―・りて居り」。「拝み―・る」
[二]〔他下二〕
⇒いれる(下一)
⇒入るを量りて出ずるを為す
い・る【炒る・煎る・熬る】
〔他五〕
水気のなくなるまで煮つめる。また、乾いたものを、土鍋などで熱する。西大寺本最勝王経平安初期点「王…倍増ますます憂の火に煎イラれ」。「豆を―・る」「卵を―・る」
い・る【要る】
〔自五〕
⇒いる(入る)[一]6
い・る【齭る】ヰル
〔自四〕
酸いものを食べて歯がうく。〈倭名類聚鈔2〉
いる【沃る】
〔他上一〕
注ぐ。浴びせる。蜻蛉日記中「おもてに水なむいるべき」
いる【居る】ヰル
〔自上一〕
(動くものが一つの場所に存在する意。現代語では動くと意識したものが存在する意で用い、意識しないものが存在する意の「ある」と使い分ける)
①一つの場所を、動かないでいる。とどまる。とまる。孝徳紀「山川に鴛鴦おし二つゐて」。万葉集12「みさごゐる渚すにゐる舟の」。万葉集14「霞ゐる富士の山傍やまびに」。万葉集3「三船の山にゐる雲の常にあらむと」。源氏物語若紫「このゐたる大人」。源氏物語若菜下「蓮葉に玉ゐる露の」。「ここにいなさい」
②すわる。万葉集10「立ちてもゐても君をしそ思ふ」。伊勢物語「立ちて見、ゐて見れど」
③動くものが存在する。主に、人・動物に用いる。「彼は東京にいる」「家には妻がいる」「前にバスがいる」
④出来てある時間そこにある。生じる。金葉和歌集春「つららゐし細谷川のとけゆくは」。千載和歌集冬「やどりし水も氷ゐにけり」
⑤草などが、生える。源氏物語幻「よるべの水に水草みくさゐめ」
⑥ある地位につく。大鏡師輔「式部卿の宮帝にゐさせ給ひなば西宮殿の族ぞうに世の中移りて」
⑦居住する。住み着く。徒然草「第一に食ひ物、第二に着るもの、第三にゐる所なり」
⑧動揺した気がおさまる。落ちつく。平家物語9「梶原この詞に腹がゐて」
⑨動詞の連用形、またはそれに助詞「て」(撥音を受ける時は「で」)の付いたものなどに接続して、動作の継続や、動作・事象の変化した状態が存続している意を表す。…し続ける。ずっと…する。万葉集17「籠りゐて君に恋ふるに心神こころどもなし」。伊勢物語「住吉の浜をゆくにいと面白ければおりゐつつゆく」。猿蓑「鳥共も寝入りてゐるか余吾の海」(路通)。「よく知っている」「本を読んでいる」「彼とは一度会っている」
⇒居ても立っても居られない
いる【射る】
〔他上一〕
(近世後期からラ行五段にも活用)
①弓につがえて、矢を放つ。万葉集1「大夫ますらおのさつ矢手挿み立ち向ひ射る円方まとかたは見るにさやけし」
②矢や弾丸を目標にあてる。平家物語7「馬をも射させ、かちだちになり」。木下尚江、良人の自白「拙者を射らずして却て君を撃つた」。「的まとを射る」
③(光が)鋭くあたる。森鴎外、舞姫「何等の光彩ぞ、我目を射むとするは」。江見水蔭、船頭大将「眉毛濃く眼鋭くして人を射りぬ」
④ねらって取る。「利を射る」
いる【率る・将る】ヰル
〔他上一〕
①連れて行く。ひきいる。南海寄帰内法伝平安後期点「請して将ヰて内に入れて供養す」
②身につけて行く。携帯する。増鏡「内侍所・神璽・宝剣ばかりをぞ、忍びてゐて渡させ給ふ」
いる【鋳る】
〔他上一〕
金属をとかして鋳型に流し込み、固めて器物を造る。鋳造する。三蔵法師伝永久点「宮中に於て金像一躯を鋳イル」
い‐るい【衣類】
身に着る物の総称。着物類。「冬の―をしまう」
い‐るい【異類】
①類を異にするもの。異種。
②人間でないもの。禽獣または変化へんげの類。太平記5「―・異形いぎょうのばけものども」
⇒いるい‐こんいん‐たん【異類婚姻譚】
い‐るい【彙類】ヰ‥
①同じたぐい。同類。
②分類。
いるい‐こんいん‐たん【異類婚姻譚】
説話類型の一つ。動物・精霊などと人間との結婚を主題とする話。異類が男性の場合(蛇聟入り・猿聟入りなど)と女性の場合(鶴女房・蛤女房など)とがある。
⇒い‐るい【異類】
いるか【海豚】
歯クジラ類のうちの小形種の総称。体長1〜5メートル。両顎に歯があり、体形は紡錘状で頭部は長く延びる。背びれはふつう鎌形で大きい。前肢はひれとなり、後肢を欠く。群をなして遊泳。種類が多い。しばしば船舶に平行して走る。マイルカは背部藍黒色、腹部白色。大西洋・インド洋、その他日本近海にも産。〈[季]冬〉。新撰字鏡9「鮪、伊留加」
まいるか
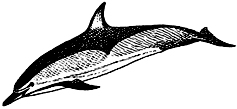 イロワケイルカ
撮影:小宮輝之
イロワケイルカ
撮影:小宮輝之
 シロイルカ
撮影:小宮輝之
シロイルカ
撮影:小宮輝之
 バンドウイルカ
撮影:小宮輝之
バンドウイルカ
撮影:小宮輝之
 イルカ
提供:NHK
⇒いるか‐ざ【海豚座】
いるか‐ざ【海豚座】
(Delphinus ラテン)白鳥座の南、鷲座わしざの北東にある星座。晩秋の夕刻に南中。
⇒いるか【海豚】
いるかせ【忽せ】
(→)「ゆるがせ」に同じ。三蔵法師伝承徳点「梵本零落して忽諸イルカセになりなむとす」
いる‐かわ【入側】‥カハ
⇒いりがわ
イルクーツク【Irkutsk】
東シベリア、ロシア中部の同名州の州都。バイカル湖の南西、アンガラ川のほとりにある。17世紀に建設。東シベリアの政治・経済・文化の中心地。人口58万3千(2004)。
いる‐さ【入るさ】
(サは接尾語)入る方向。入る時。和歌では、「入佐山」とかけて用いることが多い。源氏物語末摘花「行く月の―の山を誰か尋ぬる」
いるさ‐の‐やま【入佐山】
兵庫県豊岡市出石町の北にある此隅このすみ山の嶺つづきかという。(歌枕)
い‐るす【居留守】ヰ‥
家に居るのに、不在をよそおうこと。「―をつかう」
イル‐ハンこく【イル汗国】
(Il-khan)モンゴル四ハン国の一つ。ジンギス汗の孫のフラグが建てた国。イラン北西のタブリーズに首府を置き、領土はアム河から地中海まで、またカフカスからインド洋に及んだ。チャガタイ・キプチャク両ハン国と争った。伊児汗国。(1258〜1353)→モンゴル帝国
いるま【入間】
①武蔵国の大郡。往古は多摩郡とつらなる原野で、武蔵野と呼ばれた。
②埼玉県南部の市。日光脇往還の宿場町・市場町から発達。狭山茶の産地。東京の衛星都市化が進む。人口14万9千。
⇒いるま‐がわ【入間川】
⇒いるま‐ことば【入間詞】
⇒いるま‐よう【入間様】
いる‐まい【入舞】‥マヒ
⇒いりまい
いるま‐がわ【入間川】‥ガハ
①埼玉県南西部の川。入間郡名栗村に発し、荒川に入る。長さ51キロメートル。
②狂言。入間川を渡る大名が入間詞いるまことばを面白がり、入間の某に持物を残らず与えるが、最後に欺いて取り返す。
⇒いるま【入間】
いるま‐ことば【入間詞】
埼玉県入間地方にあったとされる、言葉の順序を逆にし、また、意味を反対にする言葉遣い。入間様よう。
⇒いるま【入間】
いるま‐よう【入間様】‥ヤウ
入間風の言葉遣い。入間詞ことば。狂言、入間川「昔から―と言うて、逆言葉さかことばを遣ふと聞いた」
⇒いるま【入間】
イルマン【irmão ポルトガル】
(キリシタン用語。兄弟の意。「入満」「伊留満」「由婁漫」と当てた)近世初期、キリシタン布教時代に、バテレン(パアデレ・神父)の次に位する宣教師。修道士。ヒイデスの導師「新しくこの国へ渡海のパアデレ、―、この書のたよりを以て日本の言葉を習はるべき為」
イルミネーション【illumination】
多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾。田村俊子、あきらめ「有楽座前の―が遠くの方でちらちらしてゐる」
イルリガートル【Irrigator ドイツ】
点滴・灌腸・洗腸・膣洗浄・輸血などに用いる灌注器具。薬液等を容れる容器、導管、先端の嘴管しかんまたは注射針を備え、容器を高所において液圧を調節する。
イルカ
提供:NHK
⇒いるか‐ざ【海豚座】
いるか‐ざ【海豚座】
(Delphinus ラテン)白鳥座の南、鷲座わしざの北東にある星座。晩秋の夕刻に南中。
⇒いるか【海豚】
いるかせ【忽せ】
(→)「ゆるがせ」に同じ。三蔵法師伝承徳点「梵本零落して忽諸イルカセになりなむとす」
いる‐かわ【入側】‥カハ
⇒いりがわ
イルクーツク【Irkutsk】
東シベリア、ロシア中部の同名州の州都。バイカル湖の南西、アンガラ川のほとりにある。17世紀に建設。東シベリアの政治・経済・文化の中心地。人口58万3千(2004)。
いる‐さ【入るさ】
(サは接尾語)入る方向。入る時。和歌では、「入佐山」とかけて用いることが多い。源氏物語末摘花「行く月の―の山を誰か尋ぬる」
いるさ‐の‐やま【入佐山】
兵庫県豊岡市出石町の北にある此隅このすみ山の嶺つづきかという。(歌枕)
い‐るす【居留守】ヰ‥
家に居るのに、不在をよそおうこと。「―をつかう」
イル‐ハンこく【イル汗国】
(Il-khan)モンゴル四ハン国の一つ。ジンギス汗の孫のフラグが建てた国。イラン北西のタブリーズに首府を置き、領土はアム河から地中海まで、またカフカスからインド洋に及んだ。チャガタイ・キプチャク両ハン国と争った。伊児汗国。(1258〜1353)→モンゴル帝国
いるま【入間】
①武蔵国の大郡。往古は多摩郡とつらなる原野で、武蔵野と呼ばれた。
②埼玉県南部の市。日光脇往還の宿場町・市場町から発達。狭山茶の産地。東京の衛星都市化が進む。人口14万9千。
⇒いるま‐がわ【入間川】
⇒いるま‐ことば【入間詞】
⇒いるま‐よう【入間様】
いる‐まい【入舞】‥マヒ
⇒いりまい
いるま‐がわ【入間川】‥ガハ
①埼玉県南西部の川。入間郡名栗村に発し、荒川に入る。長さ51キロメートル。
②狂言。入間川を渡る大名が入間詞いるまことばを面白がり、入間の某に持物を残らず与えるが、最後に欺いて取り返す。
⇒いるま【入間】
いるま‐ことば【入間詞】
埼玉県入間地方にあったとされる、言葉の順序を逆にし、また、意味を反対にする言葉遣い。入間様よう。
⇒いるま【入間】
いるま‐よう【入間様】‥ヤウ
入間風の言葉遣い。入間詞ことば。狂言、入間川「昔から―と言うて、逆言葉さかことばを遣ふと聞いた」
⇒いるま【入間】
イルマン【irmão ポルトガル】
(キリシタン用語。兄弟の意。「入満」「伊留満」「由婁漫」と当てた)近世初期、キリシタン布教時代に、バテレン(パアデレ・神父)の次に位する宣教師。修道士。ヒイデスの導師「新しくこの国へ渡海のパアデレ、―、この書のたよりを以て日本の言葉を習はるべき為」
イルミネーション【illumination】
多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾。田村俊子、あきらめ「有楽座前の―が遠くの方でちらちらしてゐる」
イルリガートル【Irrigator ドイツ】
点滴・灌腸・洗腸・膣洗浄・輸血などに用いる灌注器具。薬液等を容れる容器、導管、先端の嘴管しかんまたは注射針を備え、容器を高所において液圧を調節する。
 ⇒いりもや‐づくり【入母屋造】
⇒いりもや‐はふ【入母屋破風】
いりもや‐づくり【入母屋造】
入母屋に造る屋根の様式。法隆寺金堂の屋根の類。また、広くはこの屋根をもつ建築の様式をさす。
⇒いり‐もや【入母屋】
いりもや‐はふ【入母屋破風】
入母屋屋根の破風。
⇒いり‐もや【入母屋】
いりや【入谷】
東京都台東区北部の地名。毎年7月の朝顔市は有名。「恐れ―の鬼子母神」
いり‐やき【熬焼】
うすめに切った鳥獣の肉を空鍋で焼いた料理。
いり‐やまがた【入山形】
①紋所の名。「入」の字の形にした山形。
入山形
⇒いりもや‐づくり【入母屋造】
⇒いりもや‐はふ【入母屋破風】
いりもや‐づくり【入母屋造】
入母屋に造る屋根の様式。法隆寺金堂の屋根の類。また、広くはこの屋根をもつ建築の様式をさす。
⇒いり‐もや【入母屋】
いりもや‐はふ【入母屋破風】
入母屋屋根の破風。
⇒いり‐もや【入母屋】
いりや【入谷】
東京都台東区北部の地名。毎年7月の朝顔市は有名。「恐れ―の鬼子母神」
いり‐やき【熬焼】
うすめに切った鳥獣の肉を空鍋で焼いた料理。
いり‐やまがた【入山形】
①紋所の名。「入」の字の形にした山形。
入山形
 ②遊女の階級を示す記号。吉原細見に使用。「入山形に星(後には二つ星)」を最高級とした。
いり‐ゆ【炒湯】
炒米を湯に入れ、その香を移したもの。
い‐りゅう【移流】‥リウ
〔理〕(advection)流体中に分散した物質やエネルギーが流れによって運ばれること。多くは水平方向の移動に用いる。
⇒いりゅう‐ぎり【移流霧】
い‐りゅう【慰留】ヰリウ
なだめて、辞任などを思いとどまらせること。「辞表を出したが―された」
い‐りゅう【遺留】ヰリウ
①死後にのこすこと。
②置き忘れること。
⇒いりゅう‐ひん【遺留品】
⇒いりゅう‐ぶん【遺留分】
いりゅう‐ぎり【移流霧】‥リウ‥
湿った暖かい気団が冷たい地表や海面上を移動するとき、その下層部が冷やされて発生する霧。→蒸気霧
⇒い‐りゅう【移流】
イリュージョン【illusion】
幻影。幻覚。幻想。錯覚。
いりゅう‐ひん【遺留品】ヰリウ‥
①死後にのこした品。
②持ち主が立ち去ったあとに残された品。「犯人の―を探す」
⇒い‐りゅう【遺留】
いりゅう‐ぶん【遺留分】ヰリウ‥
〔法〕被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者のために保障される相続財産の割合。この割合を超える遺贈や贈与は減殺げんさい請求によって効力を失う。
⇒い‐りゅう【遺留】
い‐りょ【倚閭】
(「閭」は村里の門、「倚」はよるの意)母が村の入口の門によりかかって子の帰るのを待ちわびること。「―の望」→倚門
い‐りょう【井料】ヰレウ
中世、用水の使用料または維持費。井料米(堰料米)・井料田の形で、領主側が負担する場合と農民側が負担する場合とがある。
い‐りょう【衣料】‥レウ
衣服、また、その材料である布地などの総称。
⇒いりょう‐きっぷ【衣料切符】
⇒いりょう‐ひん【衣料品】
い‐りょう【衣糧】‥リヤウ
衣類と食糧。
い‐りょう【医料】‥レウ
医師の治療に対して支払う料金。
い‐りょう【医療】‥レウ
医術で病気をなおすこと。療治。治療。
⇒いりょう‐かご【医療過誤】
⇒いりょうぎじゅつ‐たんきだいがく【医療技術短期大学】
⇒いりょう‐くみあい【医療組合】
⇒いりょう‐ソーシャル‐ワーク【医療ソーシャルワーク】
⇒いりょうひよう‐ほけん【医療費用保険】
⇒いりょう‐ふくし【医療福祉】
⇒いりょう‐ふじょ【医療扶助】
⇒いりょう‐ほう【医療法】
⇒いりょう‐ほうじん【医療法人】
⇒いりょう‐ほけん【医療保険】
⇒いりょうほしょう‐ほけん【医療保障保険】
い‐りょう【違令】ヰリヤウ
令の規定にそむくこと。
い‐りょう【遺令】ヰリヤウ
死後に遺した命令。いれい。
⇒いりょう‐の‐そう【遺令の奏】
い‐りょう【遺領】ヰリヤウ
死後に残された領地。
いり‐よう【入り用】
①入費。費用。色道大鏡「万事の―家主より調へてわたす法なり」
②ある用事のために必要なこと。にゅうよう。「―な品」「金が―になる」
いりょう‐かご【医療過誤】‥レウクワ‥
診断・治療の不適正、施設の不備等によって医療上の事故を起こすこと。誤診・誤療などがその例。刑事上・民事上の責任を問われうる。
⇒い‐りょう【医療】
いりょうぎじゅつ‐たんきだいがく【医療技術短期大学】‥レウ‥
看護師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士などの育成を目的とした短期大学。所定の課程を修了すれば国家試験の受験資格を取得できる。近年4年制への再編が進む。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐きっぷ【衣料切符】‥レウ‥
配給制度のもとで、衣料の分配のため官公庁が発行する切符。1942年から51年まで実施。
⇒い‐りょう【衣料】
いりょう‐くみあい【医療組合】‥レウ‥アヒ
医療利用組合の略。特に農村地域において組合員の出資により診療所を設け、低料金で診療をうけることを目的としたもの。1922年(大正11)長野県に始まり、全国に広まった。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ソーシャル‐ワーク【医療ソーシャルワーク】‥レウ‥
(medical social work)医療機関において行われる、疾病や心身障害などによって起こる患者と家族の精神的・社会的・経済的な問題についての相談・援助。MSW
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐の‐そう【遺令の奏】ヰリヤウ‥
古代、皇后・中宮・女院などの死去した際、その遺言を奏聞する儀式。
⇒い‐りょう【遺令】
いりょうひよう‐ほけん【医療費用保険】‥レウ‥
損害保険の一種。健康保険の自己負担分などのほか、同保険対象外の高度医療の費用の支払が目的。掛け捨て型。→医療保障保険。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ひん【衣料品】‥レウ‥
商品としての、衣類やその素材などの総称。
⇒い‐りょう【衣料】
いりょう‐ふくし【医療福祉】‥レウ‥
保健・医療・福祉の連携による総合的な社会福祉サービス。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ふじょ【医療扶助】‥レウ‥
生活困窮者の疾病・負傷に対して行われる医療のための給付。生活保護法に規定。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほう【医療法】‥レウハフ
医療施設のあり方を定める法律。診療所・助産所・病院・総合病院・公的医療機関などの構造設備・人的構成・管理体制・適正配置、医療法人に関する規則を規定。1942年公布の国民医療法に代えて、48年制定。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほうじん【医療法人】‥レウハフ‥
医療法に基づき、私的医療機関に与えられる法人格。利益追求を否定されている医療機関の継続性と資金の集積、また医療の普及向上をはかるため、1950年導入された。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほけん【医療保険】‥レウ‥
健康保険・国民健康保険など医療保障を扱う社会保険の総称。→疾病しっぺい保険。
⇒い‐りょう【医療】
いりょうほしょう‐ほけん【医療保障保険】‥レウ‥シヤウ‥
生命保険の一種。健康保険の自己負担分、差額ベッド代などの支払が目的。掛け捨て型。→医療費用保険
⇒い‐りょう【医療】
い‐りょく【威力】ヰ‥
①他を圧倒して服従させる強い力。「―を発揮する」「金の―」
②〔法〕人の意思を制圧するに足りる威圧的な行為。威力業務妨害罪・競売入札妨害罪を構成する行為などがこれにあたる。
い‐りょく【偉力】ヰ‥
すぐれて大きな力。
い‐りょく【意力】
意志の力。精神力。
いり‐よね【入米・糴】
(→)「かいよね(買米)」に同じ。
いり‐わけ【入り訳】
いりくんだ事情。浄瑠璃、八百屋お七「此の―をとつくりと云ひ聞かせたら」
い‐りん【彝倫】
(「彝」は常、「倫」は道の意)人として常に守るべき道。
い・る【入る】
[一]〔自五〕
①外から中に移動する。はいる。万葉集4「わが背子が着けせる衣の針目落ちず―・りにけらしもわが情こころさへ」。万葉集12「出づる日の―・る別わき知らぬわれし苦しも」。日葡辞書「イエニイル」。「思いがけず手に―・る」「仏門に―・る」「念が―・った仕事をする」
▷現代ではふつう「はいる」を使う。
②時間が経ち、ある区切られた時間・期間の内になる。また、年月が重なる。老境に達する。源氏物語若菜上「としまかり―・り侍りて」。大鏡道隆「夜に―・りぬれば御前の松の光にとほりて」。無名抄「いかにもさかひに―・らずしてよみいでがたきさまなり」。「寒に―・る」
③進んで行き、ある段階に達する。「技わざ神しんに―・る」「話が佳境に―・る」
④果実の内部がいっぱいになる。みのる。熟する。はいる。「稲の実が―・る」
⑤物の間に生じる。はいる。狂言、枕物狂「天目ほどの靨えくぼが七八十―・つた」。「ひびが―・る」
⑥(「要る」とも書く)必要とする。入用である。かかる。源氏物語梅枝「これは暇いとま―・りぬべきものかな」。「根気が―・る」
⑦他の動詞の連用形に付いて意味を強める。
㋐完全にその状態になったことを表す。伊勢物語「死に―・りたりければ」。竹取物語「絶え―・り給ひぬ」。「恥じ―・る」
㋑その動作をひたすら行うことを表す。源氏物語夕霧「いみじう泣き―・りつつ」。源氏物語玉鬘「額に手をあてて念じ―・りて居り」。「拝み―・る」
[二]〔他下二〕
⇒いれる(下一)
⇒入るを量りて出ずるを為す
い・る【炒る・煎る・熬る】
〔他五〕
水気のなくなるまで煮つめる。また、乾いたものを、土鍋などで熱する。西大寺本最勝王経平安初期点「王…倍増ますます憂の火に煎イラれ」。「豆を―・る」「卵を―・る」
い・る【要る】
〔自五〕
⇒いる(入る)[一]6
い・る【齭る】ヰル
〔自四〕
酸いものを食べて歯がうく。〈倭名類聚鈔2〉
いる【沃る】
〔他上一〕
注ぐ。浴びせる。蜻蛉日記中「おもてに水なむいるべき」
いる【居る】ヰル
〔自上一〕
(動くものが一つの場所に存在する意。現代語では動くと意識したものが存在する意で用い、意識しないものが存在する意の「ある」と使い分ける)
①一つの場所を、動かないでいる。とどまる。とまる。孝徳紀「山川に鴛鴦おし二つゐて」。万葉集12「みさごゐる渚すにゐる舟の」。万葉集14「霞ゐる富士の山傍やまびに」。万葉集3「三船の山にゐる雲の常にあらむと」。源氏物語若紫「このゐたる大人」。源氏物語若菜下「蓮葉に玉ゐる露の」。「ここにいなさい」
②すわる。万葉集10「立ちてもゐても君をしそ思ふ」。伊勢物語「立ちて見、ゐて見れど」
③動くものが存在する。主に、人・動物に用いる。「彼は東京にいる」「家には妻がいる」「前にバスがいる」
④出来てある時間そこにある。生じる。金葉和歌集春「つららゐし細谷川のとけゆくは」。千載和歌集冬「やどりし水も氷ゐにけり」
⑤草などが、生える。源氏物語幻「よるべの水に水草みくさゐめ」
⑥ある地位につく。大鏡師輔「式部卿の宮帝にゐさせ給ひなば西宮殿の族ぞうに世の中移りて」
⑦居住する。住み着く。徒然草「第一に食ひ物、第二に着るもの、第三にゐる所なり」
⑧動揺した気がおさまる。落ちつく。平家物語9「梶原この詞に腹がゐて」
⑨動詞の連用形、またはそれに助詞「て」(撥音を受ける時は「で」)の付いたものなどに接続して、動作の継続や、動作・事象の変化した状態が存続している意を表す。…し続ける。ずっと…する。万葉集17「籠りゐて君に恋ふるに心神こころどもなし」。伊勢物語「住吉の浜をゆくにいと面白ければおりゐつつゆく」。猿蓑「鳥共も寝入りてゐるか余吾の海」(路通)。「よく知っている」「本を読んでいる」「彼とは一度会っている」
⇒居ても立っても居られない
いる【射る】
〔他上一〕
(近世後期からラ行五段にも活用)
①弓につがえて、矢を放つ。万葉集1「大夫ますらおのさつ矢手挿み立ち向ひ射る円方まとかたは見るにさやけし」
②矢や弾丸を目標にあてる。平家物語7「馬をも射させ、かちだちになり」。木下尚江、良人の自白「拙者を射らずして却て君を撃つた」。「的まとを射る」
③(光が)鋭くあたる。森鴎外、舞姫「何等の光彩ぞ、我目を射むとするは」。江見水蔭、船頭大将「眉毛濃く眼鋭くして人を射りぬ」
④ねらって取る。「利を射る」
いる【率る・将る】ヰル
〔他上一〕
①連れて行く。ひきいる。南海寄帰内法伝平安後期点「請して将ヰて内に入れて供養す」
②身につけて行く。携帯する。増鏡「内侍所・神璽・宝剣ばかりをぞ、忍びてゐて渡させ給ふ」
いる【鋳る】
〔他上一〕
金属をとかして鋳型に流し込み、固めて器物を造る。鋳造する。三蔵法師伝永久点「宮中に於て金像一躯を鋳イル」
い‐るい【衣類】
身に着る物の総称。着物類。「冬の―をしまう」
い‐るい【異類】
①類を異にするもの。異種。
②人間でないもの。禽獣または変化へんげの類。太平記5「―・異形いぎょうのばけものども」
⇒いるい‐こんいん‐たん【異類婚姻譚】
い‐るい【彙類】ヰ‥
①同じたぐい。同類。
②分類。
いるい‐こんいん‐たん【異類婚姻譚】
説話類型の一つ。動物・精霊などと人間との結婚を主題とする話。異類が男性の場合(蛇聟入り・猿聟入りなど)と女性の場合(鶴女房・蛤女房など)とがある。
⇒い‐るい【異類】
いるか【海豚】
歯クジラ類のうちの小形種の総称。体長1〜5メートル。両顎に歯があり、体形は紡錘状で頭部は長く延びる。背びれはふつう鎌形で大きい。前肢はひれとなり、後肢を欠く。群をなして遊泳。種類が多い。しばしば船舶に平行して走る。マイルカは背部藍黒色、腹部白色。大西洋・インド洋、その他日本近海にも産。〈[季]冬〉。新撰字鏡9「鮪、伊留加」
まいるか
②遊女の階級を示す記号。吉原細見に使用。「入山形に星(後には二つ星)」を最高級とした。
いり‐ゆ【炒湯】
炒米を湯に入れ、その香を移したもの。
い‐りゅう【移流】‥リウ
〔理〕(advection)流体中に分散した物質やエネルギーが流れによって運ばれること。多くは水平方向の移動に用いる。
⇒いりゅう‐ぎり【移流霧】
い‐りゅう【慰留】ヰリウ
なだめて、辞任などを思いとどまらせること。「辞表を出したが―された」
い‐りゅう【遺留】ヰリウ
①死後にのこすこと。
②置き忘れること。
⇒いりゅう‐ひん【遺留品】
⇒いりゅう‐ぶん【遺留分】
いりゅう‐ぎり【移流霧】‥リウ‥
湿った暖かい気団が冷たい地表や海面上を移動するとき、その下層部が冷やされて発生する霧。→蒸気霧
⇒い‐りゅう【移流】
イリュージョン【illusion】
幻影。幻覚。幻想。錯覚。
いりゅう‐ひん【遺留品】ヰリウ‥
①死後にのこした品。
②持ち主が立ち去ったあとに残された品。「犯人の―を探す」
⇒い‐りゅう【遺留】
いりゅう‐ぶん【遺留分】ヰリウ‥
〔法〕被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者のために保障される相続財産の割合。この割合を超える遺贈や贈与は減殺げんさい請求によって効力を失う。
⇒い‐りゅう【遺留】
い‐りょ【倚閭】
(「閭」は村里の門、「倚」はよるの意)母が村の入口の門によりかかって子の帰るのを待ちわびること。「―の望」→倚門
い‐りょう【井料】ヰレウ
中世、用水の使用料または維持費。井料米(堰料米)・井料田の形で、領主側が負担する場合と農民側が負担する場合とがある。
い‐りょう【衣料】‥レウ
衣服、また、その材料である布地などの総称。
⇒いりょう‐きっぷ【衣料切符】
⇒いりょう‐ひん【衣料品】
い‐りょう【衣糧】‥リヤウ
衣類と食糧。
い‐りょう【医料】‥レウ
医師の治療に対して支払う料金。
い‐りょう【医療】‥レウ
医術で病気をなおすこと。療治。治療。
⇒いりょう‐かご【医療過誤】
⇒いりょうぎじゅつ‐たんきだいがく【医療技術短期大学】
⇒いりょう‐くみあい【医療組合】
⇒いりょう‐ソーシャル‐ワーク【医療ソーシャルワーク】
⇒いりょうひよう‐ほけん【医療費用保険】
⇒いりょう‐ふくし【医療福祉】
⇒いりょう‐ふじょ【医療扶助】
⇒いりょう‐ほう【医療法】
⇒いりょう‐ほうじん【医療法人】
⇒いりょう‐ほけん【医療保険】
⇒いりょうほしょう‐ほけん【医療保障保険】
い‐りょう【違令】ヰリヤウ
令の規定にそむくこと。
い‐りょう【遺令】ヰリヤウ
死後に遺した命令。いれい。
⇒いりょう‐の‐そう【遺令の奏】
い‐りょう【遺領】ヰリヤウ
死後に残された領地。
いり‐よう【入り用】
①入費。費用。色道大鏡「万事の―家主より調へてわたす法なり」
②ある用事のために必要なこと。にゅうよう。「―な品」「金が―になる」
いりょう‐かご【医療過誤】‥レウクワ‥
診断・治療の不適正、施設の不備等によって医療上の事故を起こすこと。誤診・誤療などがその例。刑事上・民事上の責任を問われうる。
⇒い‐りょう【医療】
いりょうぎじゅつ‐たんきだいがく【医療技術短期大学】‥レウ‥
看護師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士などの育成を目的とした短期大学。所定の課程を修了すれば国家試験の受験資格を取得できる。近年4年制への再編が進む。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐きっぷ【衣料切符】‥レウ‥
配給制度のもとで、衣料の分配のため官公庁が発行する切符。1942年から51年まで実施。
⇒い‐りょう【衣料】
いりょう‐くみあい【医療組合】‥レウ‥アヒ
医療利用組合の略。特に農村地域において組合員の出資により診療所を設け、低料金で診療をうけることを目的としたもの。1922年(大正11)長野県に始まり、全国に広まった。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ソーシャル‐ワーク【医療ソーシャルワーク】‥レウ‥
(medical social work)医療機関において行われる、疾病や心身障害などによって起こる患者と家族の精神的・社会的・経済的な問題についての相談・援助。MSW
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐の‐そう【遺令の奏】ヰリヤウ‥
古代、皇后・中宮・女院などの死去した際、その遺言を奏聞する儀式。
⇒い‐りょう【遺令】
いりょうひよう‐ほけん【医療費用保険】‥レウ‥
損害保険の一種。健康保険の自己負担分などのほか、同保険対象外の高度医療の費用の支払が目的。掛け捨て型。→医療保障保険。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ひん【衣料品】‥レウ‥
商品としての、衣類やその素材などの総称。
⇒い‐りょう【衣料】
いりょう‐ふくし【医療福祉】‥レウ‥
保健・医療・福祉の連携による総合的な社会福祉サービス。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ふじょ【医療扶助】‥レウ‥
生活困窮者の疾病・負傷に対して行われる医療のための給付。生活保護法に規定。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほう【医療法】‥レウハフ
医療施設のあり方を定める法律。診療所・助産所・病院・総合病院・公的医療機関などの構造設備・人的構成・管理体制・適正配置、医療法人に関する規則を規定。1942年公布の国民医療法に代えて、48年制定。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほうじん【医療法人】‥レウハフ‥
医療法に基づき、私的医療機関に与えられる法人格。利益追求を否定されている医療機関の継続性と資金の集積、また医療の普及向上をはかるため、1950年導入された。
⇒い‐りょう【医療】
いりょう‐ほけん【医療保険】‥レウ‥
健康保険・国民健康保険など医療保障を扱う社会保険の総称。→疾病しっぺい保険。
⇒い‐りょう【医療】
いりょうほしょう‐ほけん【医療保障保険】‥レウ‥シヤウ‥
生命保険の一種。健康保険の自己負担分、差額ベッド代などの支払が目的。掛け捨て型。→医療費用保険
⇒い‐りょう【医療】
い‐りょく【威力】ヰ‥
①他を圧倒して服従させる強い力。「―を発揮する」「金の―」
②〔法〕人の意思を制圧するに足りる威圧的な行為。威力業務妨害罪・競売入札妨害罪を構成する行為などがこれにあたる。
い‐りょく【偉力】ヰ‥
すぐれて大きな力。
い‐りょく【意力】
意志の力。精神力。
いり‐よね【入米・糴】
(→)「かいよね(買米)」に同じ。
いり‐わけ【入り訳】
いりくんだ事情。浄瑠璃、八百屋お七「此の―をとつくりと云ひ聞かせたら」
い‐りん【彝倫】
(「彝」は常、「倫」は道の意)人として常に守るべき道。
い・る【入る】
[一]〔自五〕
①外から中に移動する。はいる。万葉集4「わが背子が着けせる衣の針目落ちず―・りにけらしもわが情こころさへ」。万葉集12「出づる日の―・る別わき知らぬわれし苦しも」。日葡辞書「イエニイル」。「思いがけず手に―・る」「仏門に―・る」「念が―・った仕事をする」
▷現代ではふつう「はいる」を使う。
②時間が経ち、ある区切られた時間・期間の内になる。また、年月が重なる。老境に達する。源氏物語若菜上「としまかり―・り侍りて」。大鏡道隆「夜に―・りぬれば御前の松の光にとほりて」。無名抄「いかにもさかひに―・らずしてよみいでがたきさまなり」。「寒に―・る」
③進んで行き、ある段階に達する。「技わざ神しんに―・る」「話が佳境に―・る」
④果実の内部がいっぱいになる。みのる。熟する。はいる。「稲の実が―・る」
⑤物の間に生じる。はいる。狂言、枕物狂「天目ほどの靨えくぼが七八十―・つた」。「ひびが―・る」
⑥(「要る」とも書く)必要とする。入用である。かかる。源氏物語梅枝「これは暇いとま―・りぬべきものかな」。「根気が―・る」
⑦他の動詞の連用形に付いて意味を強める。
㋐完全にその状態になったことを表す。伊勢物語「死に―・りたりければ」。竹取物語「絶え―・り給ひぬ」。「恥じ―・る」
㋑その動作をひたすら行うことを表す。源氏物語夕霧「いみじう泣き―・りつつ」。源氏物語玉鬘「額に手をあてて念じ―・りて居り」。「拝み―・る」
[二]〔他下二〕
⇒いれる(下一)
⇒入るを量りて出ずるを為す
い・る【炒る・煎る・熬る】
〔他五〕
水気のなくなるまで煮つめる。また、乾いたものを、土鍋などで熱する。西大寺本最勝王経平安初期点「王…倍増ますます憂の火に煎イラれ」。「豆を―・る」「卵を―・る」
い・る【要る】
〔自五〕
⇒いる(入る)[一]6
い・る【齭る】ヰル
〔自四〕
酸いものを食べて歯がうく。〈倭名類聚鈔2〉
いる【沃る】
〔他上一〕
注ぐ。浴びせる。蜻蛉日記中「おもてに水なむいるべき」
いる【居る】ヰル
〔自上一〕
(動くものが一つの場所に存在する意。現代語では動くと意識したものが存在する意で用い、意識しないものが存在する意の「ある」と使い分ける)
①一つの場所を、動かないでいる。とどまる。とまる。孝徳紀「山川に鴛鴦おし二つゐて」。万葉集12「みさごゐる渚すにゐる舟の」。万葉集14「霞ゐる富士の山傍やまびに」。万葉集3「三船の山にゐる雲の常にあらむと」。源氏物語若紫「このゐたる大人」。源氏物語若菜下「蓮葉に玉ゐる露の」。「ここにいなさい」
②すわる。万葉集10「立ちてもゐても君をしそ思ふ」。伊勢物語「立ちて見、ゐて見れど」
③動くものが存在する。主に、人・動物に用いる。「彼は東京にいる」「家には妻がいる」「前にバスがいる」
④出来てある時間そこにある。生じる。金葉和歌集春「つららゐし細谷川のとけゆくは」。千載和歌集冬「やどりし水も氷ゐにけり」
⑤草などが、生える。源氏物語幻「よるべの水に水草みくさゐめ」
⑥ある地位につく。大鏡師輔「式部卿の宮帝にゐさせ給ひなば西宮殿の族ぞうに世の中移りて」
⑦居住する。住み着く。徒然草「第一に食ひ物、第二に着るもの、第三にゐる所なり」
⑧動揺した気がおさまる。落ちつく。平家物語9「梶原この詞に腹がゐて」
⑨動詞の連用形、またはそれに助詞「て」(撥音を受ける時は「で」)の付いたものなどに接続して、動作の継続や、動作・事象の変化した状態が存続している意を表す。…し続ける。ずっと…する。万葉集17「籠りゐて君に恋ふるに心神こころどもなし」。伊勢物語「住吉の浜をゆくにいと面白ければおりゐつつゆく」。猿蓑「鳥共も寝入りてゐるか余吾の海」(路通)。「よく知っている」「本を読んでいる」「彼とは一度会っている」
⇒居ても立っても居られない
いる【射る】
〔他上一〕
(近世後期からラ行五段にも活用)
①弓につがえて、矢を放つ。万葉集1「大夫ますらおのさつ矢手挿み立ち向ひ射る円方まとかたは見るにさやけし」
②矢や弾丸を目標にあてる。平家物語7「馬をも射させ、かちだちになり」。木下尚江、良人の自白「拙者を射らずして却て君を撃つた」。「的まとを射る」
③(光が)鋭くあたる。森鴎外、舞姫「何等の光彩ぞ、我目を射むとするは」。江見水蔭、船頭大将「眉毛濃く眼鋭くして人を射りぬ」
④ねらって取る。「利を射る」
いる【率る・将る】ヰル
〔他上一〕
①連れて行く。ひきいる。南海寄帰内法伝平安後期点「請して将ヰて内に入れて供養す」
②身につけて行く。携帯する。増鏡「内侍所・神璽・宝剣ばかりをぞ、忍びてゐて渡させ給ふ」
いる【鋳る】
〔他上一〕
金属をとかして鋳型に流し込み、固めて器物を造る。鋳造する。三蔵法師伝永久点「宮中に於て金像一躯を鋳イル」
い‐るい【衣類】
身に着る物の総称。着物類。「冬の―をしまう」
い‐るい【異類】
①類を異にするもの。異種。
②人間でないもの。禽獣または変化へんげの類。太平記5「―・異形いぎょうのばけものども」
⇒いるい‐こんいん‐たん【異類婚姻譚】
い‐るい【彙類】ヰ‥
①同じたぐい。同類。
②分類。
いるい‐こんいん‐たん【異類婚姻譚】
説話類型の一つ。動物・精霊などと人間との結婚を主題とする話。異類が男性の場合(蛇聟入り・猿聟入りなど)と女性の場合(鶴女房・蛤女房など)とがある。
⇒い‐るい【異類】
いるか【海豚】
歯クジラ類のうちの小形種の総称。体長1〜5メートル。両顎に歯があり、体形は紡錘状で頭部は長く延びる。背びれはふつう鎌形で大きい。前肢はひれとなり、後肢を欠く。群をなして遊泳。種類が多い。しばしば船舶に平行して走る。マイルカは背部藍黒色、腹部白色。大西洋・インド洋、その他日本近海にも産。〈[季]冬〉。新撰字鏡9「鮪、伊留加」
まいるか
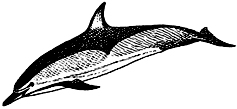 イロワケイルカ
撮影:小宮輝之
イロワケイルカ
撮影:小宮輝之
 シロイルカ
撮影:小宮輝之
シロイルカ
撮影:小宮輝之
 バンドウイルカ
撮影:小宮輝之
バンドウイルカ
撮影:小宮輝之
 イルカ
提供:NHK
⇒いるか‐ざ【海豚座】
いるか‐ざ【海豚座】
(Delphinus ラテン)白鳥座の南、鷲座わしざの北東にある星座。晩秋の夕刻に南中。
⇒いるか【海豚】
いるかせ【忽せ】
(→)「ゆるがせ」に同じ。三蔵法師伝承徳点「梵本零落して忽諸イルカセになりなむとす」
いる‐かわ【入側】‥カハ
⇒いりがわ
イルクーツク【Irkutsk】
東シベリア、ロシア中部の同名州の州都。バイカル湖の南西、アンガラ川のほとりにある。17世紀に建設。東シベリアの政治・経済・文化の中心地。人口58万3千(2004)。
いる‐さ【入るさ】
(サは接尾語)入る方向。入る時。和歌では、「入佐山」とかけて用いることが多い。源氏物語末摘花「行く月の―の山を誰か尋ぬる」
いるさ‐の‐やま【入佐山】
兵庫県豊岡市出石町の北にある此隅このすみ山の嶺つづきかという。(歌枕)
い‐るす【居留守】ヰ‥
家に居るのに、不在をよそおうこと。「―をつかう」
イル‐ハンこく【イル汗国】
(Il-khan)モンゴル四ハン国の一つ。ジンギス汗の孫のフラグが建てた国。イラン北西のタブリーズに首府を置き、領土はアム河から地中海まで、またカフカスからインド洋に及んだ。チャガタイ・キプチャク両ハン国と争った。伊児汗国。(1258〜1353)→モンゴル帝国
いるま【入間】
①武蔵国の大郡。往古は多摩郡とつらなる原野で、武蔵野と呼ばれた。
②埼玉県南部の市。日光脇往還の宿場町・市場町から発達。狭山茶の産地。東京の衛星都市化が進む。人口14万9千。
⇒いるま‐がわ【入間川】
⇒いるま‐ことば【入間詞】
⇒いるま‐よう【入間様】
いる‐まい【入舞】‥マヒ
⇒いりまい
いるま‐がわ【入間川】‥ガハ
①埼玉県南西部の川。入間郡名栗村に発し、荒川に入る。長さ51キロメートル。
②狂言。入間川を渡る大名が入間詞いるまことばを面白がり、入間の某に持物を残らず与えるが、最後に欺いて取り返す。
⇒いるま【入間】
いるま‐ことば【入間詞】
埼玉県入間地方にあったとされる、言葉の順序を逆にし、また、意味を反対にする言葉遣い。入間様よう。
⇒いるま【入間】
いるま‐よう【入間様】‥ヤウ
入間風の言葉遣い。入間詞ことば。狂言、入間川「昔から―と言うて、逆言葉さかことばを遣ふと聞いた」
⇒いるま【入間】
イルマン【irmão ポルトガル】
(キリシタン用語。兄弟の意。「入満」「伊留満」「由婁漫」と当てた)近世初期、キリシタン布教時代に、バテレン(パアデレ・神父)の次に位する宣教師。修道士。ヒイデスの導師「新しくこの国へ渡海のパアデレ、―、この書のたよりを以て日本の言葉を習はるべき為」
イルミネーション【illumination】
多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾。田村俊子、あきらめ「有楽座前の―が遠くの方でちらちらしてゐる」
イルリガートル【Irrigator ドイツ】
点滴・灌腸・洗腸・膣洗浄・輸血などに用いる灌注器具。薬液等を容れる容器、導管、先端の嘴管しかんまたは注射針を備え、容器を高所において液圧を調節する。
イルカ
提供:NHK
⇒いるか‐ざ【海豚座】
いるか‐ざ【海豚座】
(Delphinus ラテン)白鳥座の南、鷲座わしざの北東にある星座。晩秋の夕刻に南中。
⇒いるか【海豚】
いるかせ【忽せ】
(→)「ゆるがせ」に同じ。三蔵法師伝承徳点「梵本零落して忽諸イルカセになりなむとす」
いる‐かわ【入側】‥カハ
⇒いりがわ
イルクーツク【Irkutsk】
東シベリア、ロシア中部の同名州の州都。バイカル湖の南西、アンガラ川のほとりにある。17世紀に建設。東シベリアの政治・経済・文化の中心地。人口58万3千(2004)。
いる‐さ【入るさ】
(サは接尾語)入る方向。入る時。和歌では、「入佐山」とかけて用いることが多い。源氏物語末摘花「行く月の―の山を誰か尋ぬる」
いるさ‐の‐やま【入佐山】
兵庫県豊岡市出石町の北にある此隅このすみ山の嶺つづきかという。(歌枕)
い‐るす【居留守】ヰ‥
家に居るのに、不在をよそおうこと。「―をつかう」
イル‐ハンこく【イル汗国】
(Il-khan)モンゴル四ハン国の一つ。ジンギス汗の孫のフラグが建てた国。イラン北西のタブリーズに首府を置き、領土はアム河から地中海まで、またカフカスからインド洋に及んだ。チャガタイ・キプチャク両ハン国と争った。伊児汗国。(1258〜1353)→モンゴル帝国
いるま【入間】
①武蔵国の大郡。往古は多摩郡とつらなる原野で、武蔵野と呼ばれた。
②埼玉県南部の市。日光脇往還の宿場町・市場町から発達。狭山茶の産地。東京の衛星都市化が進む。人口14万9千。
⇒いるま‐がわ【入間川】
⇒いるま‐ことば【入間詞】
⇒いるま‐よう【入間様】
いる‐まい【入舞】‥マヒ
⇒いりまい
いるま‐がわ【入間川】‥ガハ
①埼玉県南西部の川。入間郡名栗村に発し、荒川に入る。長さ51キロメートル。
②狂言。入間川を渡る大名が入間詞いるまことばを面白がり、入間の某に持物を残らず与えるが、最後に欺いて取り返す。
⇒いるま【入間】
いるま‐ことば【入間詞】
埼玉県入間地方にあったとされる、言葉の順序を逆にし、また、意味を反対にする言葉遣い。入間様よう。
⇒いるま【入間】
いるま‐よう【入間様】‥ヤウ
入間風の言葉遣い。入間詞ことば。狂言、入間川「昔から―と言うて、逆言葉さかことばを遣ふと聞いた」
⇒いるま【入間】
イルマン【irmão ポルトガル】
(キリシタン用語。兄弟の意。「入満」「伊留満」「由婁漫」と当てた)近世初期、キリシタン布教時代に、バテレン(パアデレ・神父)の次に位する宣教師。修道士。ヒイデスの導師「新しくこの国へ渡海のパアデレ、―、この書のたよりを以て日本の言葉を習はるべき為」
イルミネーション【illumination】
多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾。田村俊子、あきらめ「有楽座前の―が遠くの方でちらちらしてゐる」
イルリガートル【Irrigator ドイツ】
点滴・灌腸・洗腸・膣洗浄・輸血などに用いる灌注器具。薬液等を容れる容器、導管、先端の嘴管しかんまたは注射針を備え、容器を高所において液圧を調節する。
いり‐め・く【炒りめく】🔗⭐🔉
いり‐め・く【炒りめく】
〔自四〕
物が炒られたように、ひしめきさわぐ。今昔物語集25「―・きあひて、ののしる」
いり‐めし【炒飯】🔗⭐🔉
いり‐めし【炒飯】
炒った飯。やきめし。チャーハン。
いり‐もの【炒物・煎物・熬物】🔗⭐🔉
いり‐もの【炒物・煎物・熬物】
①肉類・野菜などを鍋の中で炒って水分を去り、または油でいためた料理。
②豆・米などを炒ったもの。
いり‐ゆ【炒湯】🔗⭐🔉
いり‐ゆ【炒湯】
炒米を湯に入れ、その香を移したもの。
い・る【炒る・煎る・熬る】🔗⭐🔉
い・る【炒る・煎る・熬る】
〔他五〕
水気のなくなるまで煮つめる。また、乾いたものを、土鍋などで熱する。西大寺本最勝王経平安初期点「王…倍増ますます憂の火に煎イラれ」。「豆を―・る」「卵を―・る」
い・れる【炒れる】🔗⭐🔉
い・れる【炒れる】
〔自下一〕
①いらだつ。怒りもだえる。浮世風呂2「ほんにほんに肝の―・れたことよ」
②炒られる。炒られた状態となる。「豆が―・れる」
チャーハン【炒飯】🔗⭐🔉
チャーハン【炒飯】
(中国語)中国料理。米飯を油でいため、肉・卵・野菜などを混ぜあわせたもの。やきめし。
チャオ【炒】🔗⭐🔉
チャオ【炒】
(中国語)中国料理で、油でいためること。
[漢]炒🔗⭐🔉
炒 字形
 〔火(灬)部4画/8画/6354・5F56〕
〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)
〔訓〕いる・いためる
[意味]
なべで肉・野菜などをあぶってさっとこがす。油でいためる。いる。「煎炒せんしょう・炒飯チャーハン」
〔火(灬)部4画/8画/6354・5F56〕
〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)
〔訓〕いる・いためる
[意味]
なべで肉・野菜などをあぶってさっとこがす。油でいためる。いる。「煎炒せんしょう・炒飯チャーハン」
 〔火(灬)部4画/8画/6354・5F56〕
〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)
〔訓〕いる・いためる
[意味]
なべで肉・野菜などをあぶってさっとこがす。油でいためる。いる。「煎炒せんしょう・炒飯チャーハン」
〔火(灬)部4画/8画/6354・5F56〕
〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)
〔訓〕いる・いためる
[意味]
なべで肉・野菜などをあぶってさっとこがす。油でいためる。いる。「煎炒せんしょう・炒飯チャーハン」
広辞苑に「炒」で始まるの検索結果 1-35。