複数辞典一括検索+![]()
![]()
こと‐わり【理】🔗⭐🔉
こと‐わり【理】
(物事の理非を分かち定める意から。→断り)
①道理。条理。万葉集5「世間よのなかはかくぞ―」。平家物語1「盛者必衰の―をあらはす」
②格式・礼儀にかなっていること。欽明紀「新羅―無し」
③理由。わけ。源氏物語須磨「その―をあらはにえ承り給はねば」
④当然のこと。もっともなこと。源氏物語桐壺「人の御心を尽し給ふも、げに―と見えたり」
⑤(副詞的に用いて)もちろん。無論。枕草子262「わが得たらむは―、人の許なるさへ憎くこそあれ」
⇒ことわり‐の‐いくさ【理の兵】
⇒ことわり‐の‐よそい【理の装い】
⇒理過ぎて
⇒理迫めて
⇒理無し
○理過ぎてことわりすぎて🔗⭐🔉
○理過ぎてことわりすぎて
常軌を逸して。極端に。
⇒こと‐わり【理】
ことわり‐の‐いくさ【理の兵】🔗⭐🔉
ことわり‐の‐いくさ【理の兵】
正義の兵。崇神紀「―を挙げて」
⇒こと‐わり【理】
ことわり‐の‐よそい【理の装い】‥ヨソヒ🔗⭐🔉
ことわり‐の‐よそい【理の装い】‥ヨソヒ
礼にかなった儀式。継体紀「―を備へて」
⇒こと‐わり【理】
り【理】🔗⭐🔉
り‐あい【理合い】‥アヒ🔗⭐🔉
り‐あい【理合い】‥アヒ
わけあい。筋道。梅暦「込み入つた腹に―のあることだけれど」
り‐うん【理運・利運】🔗⭐🔉
り‐うん【理運・利運】
①道理にかなっていること。平家物語1「今度山門の御訴訟、―の条勿論に候ふ」
②天理にかなった幸運。
③よいめぐりあわせ。好運。天草本伊曾保物語「あまたの人大きな事には―を開けども、聊かの事には負くる事が多い」
④勝手気ままにふるまうこと。高慢なさま。中華若木詩抄「―に案内なしに打入て」
り‐か【理科】‥クワ🔗⭐🔉
り‐か【理科】‥クワ
①学校教育で、自然界の事物および現象を学ぶ教科。
②自然科学の学問。また、大学などでそれを専攻する部門。理学部・工学部・医学部・農学部などの総称。また特に、理学部。「―系」↔文科
り‐かい【理会】‥クワイ🔗⭐🔉
り‐かい【理会】‥クワイ
事の道理を会得えとくすること。理解。
り‐かい【理解】🔗⭐🔉
り‐かい【理解】
①物事の道理をさとり知ること。意味をのみこむこと。物事がわかること。了解。「文意を―する」
②人の気持や立場がよくわかること。「―のある先生」「関係者の―を求める」
③〔哲〕(→)了解2に同じ。
り‐がい【理外】‥グワイ🔗⭐🔉
り‐がい【理外】‥グワイ
道理から外れていること。〈日葡辞書〉
⇒理外の理
○理外の理りがいのり🔗⭐🔉
○理外の理りがいのり
普通の道理では推定することのできない不思議な道理。
⇒り‐がい【理外】
リカオン【Lycaon ラテン】
イヌ科の哺乳類。体長70センチメートルほど。毛色は黒褐色に白または茶の不規則な斑。立ち耳、垂れ尾。アフリカの草原地帯に分布、巣穴で生活し、夜に数十頭の群れでインパラなどの有蹄類を捕食。
リカオン
提供:東京動物園協会
 り‐か‐がく【理化学】‥クワ‥
物理学と化学。
⇒りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】
りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】‥クワ‥キウ‥
物理・化学の研究およびその産業への応用を目的とする研究機関。1917年(大正6)に財団法人として設立。第二次大戦後、研究機関が分離し、一時、株式会社科学研究所と称したが、58年政府出資による特殊法人、2003年独立行政法人となる。本部は埼玉県和光市。略称、理研。
⇒り‐か‐がく【理化学】
りか‐かでん【李下瓜田】‥クワ‥
(→)瓜田李下に同じ。
り‐かく【釐革】
治め改めること。改革。
り‐かく【離角】
〔天〕(elongation)天球上で、1天体または1定点からある天体までの角距離。
り‐かく【離隔】
はなれへだたること。また、はなしへだてること。隔離。
⇒りかく‐がいねん【離隔概念】
り‐がく【理学】
①中国、宋代に唱えられた性理学に始まり、陽明学までを含む宋・明代儒学の総称。宋明理学。
②陰陽師おんようじなどが方位や星象を見て吉凶を定めること。
③(明治期の用語)哲学。
④㋐自然科学の基礎研究諸分野の称。
㋑特に、物理学。→窮理学。
⇒りがく‐しんとう【理学神道】
⇒りがく‐りょうほう【理学療法】
⇒りがくりょうほう‐し【理学療法士】
りかく‐がいねん【離隔概念】
〔哲〕類と種の関係もなく、同一類概念に包摂もできない二つの概念の相互の関係をいう。例えば、「徳」と「三角形」。乖離概念。不等概念。異類概念。
⇒り‐かく【離隔】
りがく‐しんとう【理学神道】‥タウ
(→)吉川よしかわ神道に同じ。
⇒り‐がく【理学】
りがく‐りょうほう【理学療法】‥レウハフ
マッサージ・温熱・電気などを用いる物理療法と、筋力増強・機能訓練・歩行訓練などの運動療法とを組み合わせて、運動障害の回復・改善をはかる治療法。
⇒り‐がく【理学】
りがくりょうほう‐し【理学療法士】‥レウハフ‥
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもとに、理学療法を行うことを業とする者。
⇒り‐がく【理学】
りか‐じょし‐だいがく【梨花女子大学】‥クワヂヨ‥
韓国ソウルにあるキリスト教系私立総合大学。1886年、宣教師メアリー=スクラントン(M. Scranton1832〜1909)が設立。翌年、高宗が「梨花学堂」の名を下賜。1925年梨花女子専門学校となり、46年総合大学となる。
り‐かた【利方】
利益のある方法。便利なやり方。浮世風呂2「手がかからねえで貧乏人にはいい―だ」
り‐かた【理方】
理屈。原理。心学早染草「その―、子供のもてあそぶシヤボンのごとし」
り‐か‐がく【理化学】‥クワ‥
物理学と化学。
⇒りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】
りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】‥クワ‥キウ‥
物理・化学の研究およびその産業への応用を目的とする研究機関。1917年(大正6)に財団法人として設立。第二次大戦後、研究機関が分離し、一時、株式会社科学研究所と称したが、58年政府出資による特殊法人、2003年独立行政法人となる。本部は埼玉県和光市。略称、理研。
⇒り‐か‐がく【理化学】
りか‐かでん【李下瓜田】‥クワ‥
(→)瓜田李下に同じ。
り‐かく【釐革】
治め改めること。改革。
り‐かく【離角】
〔天〕(elongation)天球上で、1天体または1定点からある天体までの角距離。
り‐かく【離隔】
はなれへだたること。また、はなしへだてること。隔離。
⇒りかく‐がいねん【離隔概念】
り‐がく【理学】
①中国、宋代に唱えられた性理学に始まり、陽明学までを含む宋・明代儒学の総称。宋明理学。
②陰陽師おんようじなどが方位や星象を見て吉凶を定めること。
③(明治期の用語)哲学。
④㋐自然科学の基礎研究諸分野の称。
㋑特に、物理学。→窮理学。
⇒りがく‐しんとう【理学神道】
⇒りがく‐りょうほう【理学療法】
⇒りがくりょうほう‐し【理学療法士】
りかく‐がいねん【離隔概念】
〔哲〕類と種の関係もなく、同一類概念に包摂もできない二つの概念の相互の関係をいう。例えば、「徳」と「三角形」。乖離概念。不等概念。異類概念。
⇒り‐かく【離隔】
りがく‐しんとう【理学神道】‥タウ
(→)吉川よしかわ神道に同じ。
⇒り‐がく【理学】
りがく‐りょうほう【理学療法】‥レウハフ
マッサージ・温熱・電気などを用いる物理療法と、筋力増強・機能訓練・歩行訓練などの運動療法とを組み合わせて、運動障害の回復・改善をはかる治療法。
⇒り‐がく【理学】
りがくりょうほう‐し【理学療法士】‥レウハフ‥
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもとに、理学療法を行うことを業とする者。
⇒り‐がく【理学】
りか‐じょし‐だいがく【梨花女子大学】‥クワヂヨ‥
韓国ソウルにあるキリスト教系私立総合大学。1886年、宣教師メアリー=スクラントン(M. Scranton1832〜1909)が設立。翌年、高宗が「梨花学堂」の名を下賜。1925年梨花女子専門学校となり、46年総合大学となる。
り‐かた【利方】
利益のある方法。便利なやり方。浮世風呂2「手がかからねえで貧乏人にはいい―だ」
り‐かた【理方】
理屈。原理。心学早染草「その―、子供のもてあそぶシヤボンのごとし」
 り‐か‐がく【理化学】‥クワ‥
物理学と化学。
⇒りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】
りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】‥クワ‥キウ‥
物理・化学の研究およびその産業への応用を目的とする研究機関。1917年(大正6)に財団法人として設立。第二次大戦後、研究機関が分離し、一時、株式会社科学研究所と称したが、58年政府出資による特殊法人、2003年独立行政法人となる。本部は埼玉県和光市。略称、理研。
⇒り‐か‐がく【理化学】
りか‐かでん【李下瓜田】‥クワ‥
(→)瓜田李下に同じ。
り‐かく【釐革】
治め改めること。改革。
り‐かく【離角】
〔天〕(elongation)天球上で、1天体または1定点からある天体までの角距離。
り‐かく【離隔】
はなれへだたること。また、はなしへだてること。隔離。
⇒りかく‐がいねん【離隔概念】
り‐がく【理学】
①中国、宋代に唱えられた性理学に始まり、陽明学までを含む宋・明代儒学の総称。宋明理学。
②陰陽師おんようじなどが方位や星象を見て吉凶を定めること。
③(明治期の用語)哲学。
④㋐自然科学の基礎研究諸分野の称。
㋑特に、物理学。→窮理学。
⇒りがく‐しんとう【理学神道】
⇒りがく‐りょうほう【理学療法】
⇒りがくりょうほう‐し【理学療法士】
りかく‐がいねん【離隔概念】
〔哲〕類と種の関係もなく、同一類概念に包摂もできない二つの概念の相互の関係をいう。例えば、「徳」と「三角形」。乖離概念。不等概念。異類概念。
⇒り‐かく【離隔】
りがく‐しんとう【理学神道】‥タウ
(→)吉川よしかわ神道に同じ。
⇒り‐がく【理学】
りがく‐りょうほう【理学療法】‥レウハフ
マッサージ・温熱・電気などを用いる物理療法と、筋力増強・機能訓練・歩行訓練などの運動療法とを組み合わせて、運動障害の回復・改善をはかる治療法。
⇒り‐がく【理学】
りがくりょうほう‐し【理学療法士】‥レウハフ‥
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもとに、理学療法を行うことを業とする者。
⇒り‐がく【理学】
りか‐じょし‐だいがく【梨花女子大学】‥クワヂヨ‥
韓国ソウルにあるキリスト教系私立総合大学。1886年、宣教師メアリー=スクラントン(M. Scranton1832〜1909)が設立。翌年、高宗が「梨花学堂」の名を下賜。1925年梨花女子専門学校となり、46年総合大学となる。
り‐かた【利方】
利益のある方法。便利なやり方。浮世風呂2「手がかからねえで貧乏人にはいい―だ」
り‐かた【理方】
理屈。原理。心学早染草「その―、子供のもてあそぶシヤボンのごとし」
り‐か‐がく【理化学】‥クワ‥
物理学と化学。
⇒りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】
りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】‥クワ‥キウ‥
物理・化学の研究およびその産業への応用を目的とする研究機関。1917年(大正6)に財団法人として設立。第二次大戦後、研究機関が分離し、一時、株式会社科学研究所と称したが、58年政府出資による特殊法人、2003年独立行政法人となる。本部は埼玉県和光市。略称、理研。
⇒り‐か‐がく【理化学】
りか‐かでん【李下瓜田】‥クワ‥
(→)瓜田李下に同じ。
り‐かく【釐革】
治め改めること。改革。
り‐かく【離角】
〔天〕(elongation)天球上で、1天体または1定点からある天体までの角距離。
り‐かく【離隔】
はなれへだたること。また、はなしへだてること。隔離。
⇒りかく‐がいねん【離隔概念】
り‐がく【理学】
①中国、宋代に唱えられた性理学に始まり、陽明学までを含む宋・明代儒学の総称。宋明理学。
②陰陽師おんようじなどが方位や星象を見て吉凶を定めること。
③(明治期の用語)哲学。
④㋐自然科学の基礎研究諸分野の称。
㋑特に、物理学。→窮理学。
⇒りがく‐しんとう【理学神道】
⇒りがく‐りょうほう【理学療法】
⇒りがくりょうほう‐し【理学療法士】
りかく‐がいねん【離隔概念】
〔哲〕類と種の関係もなく、同一類概念に包摂もできない二つの概念の相互の関係をいう。例えば、「徳」と「三角形」。乖離概念。不等概念。異類概念。
⇒り‐かく【離隔】
りがく‐しんとう【理学神道】‥タウ
(→)吉川よしかわ神道に同じ。
⇒り‐がく【理学】
りがく‐りょうほう【理学療法】‥レウハフ
マッサージ・温熱・電気などを用いる物理療法と、筋力増強・機能訓練・歩行訓練などの運動療法とを組み合わせて、運動障害の回復・改善をはかる治療法。
⇒り‐がく【理学】
りがくりょうほう‐し【理学療法士】‥レウハフ‥
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもとに、理学療法を行うことを業とする者。
⇒り‐がく【理学】
りか‐じょし‐だいがく【梨花女子大学】‥クワヂヨ‥
韓国ソウルにあるキリスト教系私立総合大学。1886年、宣教師メアリー=スクラントン(M. Scranton1832〜1909)が設立。翌年、高宗が「梨花学堂」の名を下賜。1925年梨花女子専門学校となり、46年総合大学となる。
り‐かた【利方】
利益のある方法。便利なやり方。浮世風呂2「手がかからねえで貧乏人にはいい―だ」
り‐かた【理方】
理屈。原理。心学早染草「その―、子供のもてあそぶシヤボンのごとし」
り‐か‐がく【理化学】‥クワ‥🔗⭐🔉
り‐か‐がく【理化学】‥クワ‥
物理学と化学。
⇒りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】
りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】‥クワ‥キウ‥🔗⭐🔉
りかがく‐けんきゅうじょ【理化学研究所】‥クワ‥キウ‥
物理・化学の研究およびその産業への応用を目的とする研究機関。1917年(大正6)に財団法人として設立。第二次大戦後、研究機関が分離し、一時、株式会社科学研究所と称したが、58年政府出資による特殊法人、2003年独立行政法人となる。本部は埼玉県和光市。略称、理研。
⇒り‐か‐がく【理化学】
り‐がく【理学】🔗⭐🔉
り‐がく【理学】
①中国、宋代に唱えられた性理学に始まり、陽明学までを含む宋・明代儒学の総称。宋明理学。
②陰陽師おんようじなどが方位や星象を見て吉凶を定めること。
③(明治期の用語)哲学。
④㋐自然科学の基礎研究諸分野の称。
㋑特に、物理学。→窮理学。
⇒りがく‐しんとう【理学神道】
⇒りがく‐りょうほう【理学療法】
⇒りがくりょうほう‐し【理学療法士】
りがく‐しんとう【理学神道】‥タウ🔗⭐🔉
りがく‐しんとう【理学神道】‥タウ
(→)吉川よしかわ神道に同じ。
⇒り‐がく【理学】
りがく‐りょうほう【理学療法】‥レウハフ🔗⭐🔉
りがく‐りょうほう【理学療法】‥レウハフ
マッサージ・温熱・電気などを用いる物理療法と、筋力増強・機能訓練・歩行訓練などの運動療法とを組み合わせて、運動障害の回復・改善をはかる治療法。
⇒り‐がく【理学】
りがくりょうほう‐し【理学療法士】‥レウハフ‥🔗⭐🔉
りがくりょうほう‐し【理学療法士】‥レウハフ‥
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもとに、理学療法を行うことを業とする者。
⇒り‐がく【理学】
○理が非でもりがひでも🔗⭐🔉
○理が非でもりがひでも
ぜひとも。むりにでも。是が非でも。
⇒り【理】
○理が非になるりがひになる🔗⭐🔉
○理が非になるりがひになる
理論上は正しいのに、口不調法などのために却って非とされる。狂言、内沙汰「―は公事のならひで御座る」
⇒り【理】
り‐かん【利勘】
利益を打算してかかること。勘定高いこと。日葡辞書「リカン。即ち、リトク(利得)ヲカンガユル」。日本永代蔵2「これも―にて大仏の前へあつらへ」
り‐かん【罹患】‥クワン
病気にかかること。罹病。「―率」
り‐かん【離間】
相互の仲をさくこと。仲たがいさせること。「―策」
り‐かん【離艦】‥クワン
乗組員あるいは艦載機が、その軍艦から離れること。
り‐がん【離岸】
船などが、岸を離れること。
⇒りがん‐てい【離岸堤】
りがん‐てい【離岸堤】
海岸線に平行に設置された沖合いの堤防。海浜に打ち寄せる波を減衰し、浸食防止や魚介類の養殖などを目的とする。
⇒り‐がん【離岸】
りき【力】
(呉音)
①ちから。日葡辞書「リキノアルモノヂャ」。「―を出す」
②力者法師の略。
③車力しゃりきの略。また、その賃銭。
り‐き【利器】
①よく切れる刃物。するどい兵器・武器。
②便利な器具。すぐれた性能の機械。「文明の―」
③役に立つ才能。
り‐き【理気】
宇宙の生成されるべき根本の理すなわち太極と、これから生ずる陰陽の気。→理気説
り‐ぎ【理義】
道理と正義。
りき‐えい【力泳】
力いっぱい泳ぐこと。また、その泳ぎ。
り‐きえい【李箕永】
⇒イ=ギヨン
りき‐えき【力役】
①力わざのかせぎ。あらしごと。力仕事。
②官から課せられて勤める労役。えだち。りょくえき。
りき‐えん【力演】
力いっぱい演技すること。「悲劇の主人公を―する」
りき‐がく【力学】
①物体の運動や力の釣合に関する物理法則を研究する物理学の一部門。古典力学と同義。
②物理の基礎となる完成度の高い理論体系であることを示す語。熱力学・量子力学など。
③転じて、社会集団・人間心理などの運動にみられる一般的傾向。ダイナミックス。「政治の―」
⇒りきがくてき‐エネルギー【力学的エネルギー】
りきがくてき‐エネルギー【力学的エネルギー】
物体の位置エネルギーと運動エネルギーとの和。保存力だけが働いている系では一定となる。機械的エネルギー。
⇒りき‐がく【力学】
りき‐かん【力感】
力強い感じ。「―あふれる像」
りき‐こう【力行】‥カウ
⇒りっこう
りき‐さく【力作】
①力をこめて製作した作品。労作。
②⇒りょくさく
りき‐し【力士】
(古くはリキジとも)
①力の強い人。
②相撲取り。力者。力人。「ひいきの―」
③金剛力士こんごうりきしの略。古今著聞集10「鬼王のかたちをあらはして、―のたちまちに来るかとおぼえたり」
⇒りきし‐だち【力士立ち】
⇒りきし‐まい【力士舞】
りきし‐だち【力士立ち】
金剛力士の像のように猛々しく突っ立つこと。仁王立ち。浄瑠璃、栬狩剣本地「思ひの外に金剛兵衛が―」
⇒りき‐し【力士】
りきし‐まい【力士舞】‥マヒ
伎楽ぎがくの一つ。金剛力士に仮装し、煩悩打破のさまを演じた舞。万葉集16「池神の―かも」
⇒りき‐し【力士】
りき‐しゃ【力車】
①荷車。ちからぐるま。
②人力車の略。
りき‐しゃ【力者】
①力の強い人。また、力士。力人。相撲取り。
②力者法師の略。平家物語3「金行といふ御―ばかりぞまゐりける」
⇒りきしゃ‐ほうし【力者法師】
りきしゃ‐ほうし【力者法師】‥ホフ‥
中世、法師のように剃髪した、一種の中間ちゅうげん。かごをかき、馬の口取りをし、長刀を持って貴人の供をするなど、力仕事をした。三帖和讃「輿かく僧達―」
⇒りき‐しゃ【力者】
りき‐しょっき【力織機】‥シヨク‥
動力を使用する織機の総称。
りき‐じん【力人】
力の強い人。また、力士。力者。相撲取り。十訓抄「五人の―をして山を掘り、牛を引くに」
りき‐せき【力積】
〔理〕(impulse)力とその力が働いた時間との積。運動量の変化量に等しく、瞬間的な力の働きの大きさを表すのに用いる。
りき‐せつ【力説】
力をつくして説くこと。一所懸命に説明すること。「必要性を―する」
りき‐せつ【理気説】
太極・気・陰陽などの伝統的な概念を改めて体系化した朱子学の宇宙論。朱熹しゅきの説は、万物の生成を気の陰陽の働きによるとしながら、一方その働きの根拠に太極としての理があるとした。そのためこの説は理気二元論と見られ、明代に入ると、理を気の条理とする羅欽順らきんじゅんらの一元論が現れる。
りき‐せん【力戦】
[史記馮唐伝]力を尽くして戦うこと。力闘。りょくせん。「―奮闘」
りき‐せん【力線】
〔理〕力の場を直観的に表す曲線群。それぞれの曲線上の各点における接線の方向が、場における力の向きと一致する。→電気力線→磁力線じりょくせん
りき‐そう【力走】
力のかぎり走ること。また、その走り。
りき‐そう【力漕】‥サウ
ボートなどを力いっぱい漕ぐこと。
リキッド【liquid】
①液体。
②ヘア‐リキッドの略。
りき‐てん【力点】
①梃子てこで物を動かす時、力を加える点。
②重点のおかれている箇所。物事や論旨の主眼とする箇所。「新製品の開発に―をおく」
りき‐とう【力投】
全力をこめて投げること。
りき‐とう【力闘】
力いっぱい戦うこと。力戦。
りき‐どう【力道】‥ダウ
①芸道における力量。遊楽習道風見「一身他風に所持する―これなり」
②功徳の力。謡曲、盛久「定業亦能転は菩薩の―とかや」
りきどうざん【力道山】‥ダウ‥
プロレスラー。朝鮮の生れ。本名、金信洛。日本名、百田光浩。1950年相撲力士を廃業し、翌年プロレスラーに転身。協会設立やインターナショナル選手権獲得など、プロレス界の第一人者として活躍。(1924〜1963)
りきどう‐ふう【力動風】
「砕動風さいどうふう」参照。二曲三体人形図「―勢形心鬼」
りき‐にげんろん【理気二元論】
「理気説」参照。
りき‐ふ【力婦】
①力の強い女。
②女の仕丁してい。女丁じょちょう。
りき‐へん【力編】
力をこめて作った小説・映画などの作品。
りきほん‐せつ【力本説】
〔哲〕(→)ダイナミズムに同じ。
りき‐み【力み】
①力を入れること。また、体に力の入ったさま。西鶴諸国ばなし「仁王の形を作りて、手足の―迄を、細縄がらみの細工」
②気負い。「―のある表現」
③負けん気。強がり。洒落本、辰巳婦言「まき舌をまじへて、―をならべた処が」
りきみ‐かえ・る【力み返る】‥カヘル
〔自五〕
必要以上にりきむ。ひどく強がる。
りき・む【力む】
〔自五〕
①力をこめる。気ばる。また、うまくやろうと気負う。浮世風呂前「ぬの字を―・んで書けば奴と読むは」。「―・んで失敗する」
②力のありそうなさまをする。勢いを誇る。いばる。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「裾からげ、胸を叩いて―・みける」
りきゅう【利休】‥キウ
⇒せんのりきゅう(千利休)。
⇒りきゅう‐いろ【利休色】
⇒りきゅう‐がた【利休形】
⇒りきゅう‐き【利休忌】
⇒りきゅう‐げた【利休下駄】
⇒りきゅう‐ごのみ【利休好み】
⇒りきゅう‐ちゃ【利休茶】
⇒りきゅう‐ねずみ【利休鼠】
⇒りきゅう‐ばし【利休箸】
⇒りきゅう‐やき【利休焼】
り‐きゅう【離宮】
皇居や王宮以外の地に定められた宮殿。外とつ宮。
り‐ぎゅう【犂牛】‥ギウ
毛色のまだらな牛。日葡辞書「リギュウ。マダラウシ」
りきゅう‐いろ【利休色】‥キウ‥
緑色を帯びた灰色。
Munsell color system: 5.5Y5.5/2.5
⇒りきゅう【利休】
りきゅう‐がた【利休形】‥キウ‥
①平棗ひらなつめの別称。
②浅い形の櫛。
③印籠の形の一つ。
⇒りきゅう【利休】
りきゅう‐き【利休忌】‥キウ‥
利休の忌日。陰暦2月28日。茶道の表千家では3月27日に、裏千家では3月28日に、追善茶会を催す。〈[季]春〉
⇒りきゅう【利休】
りきゅう‐げた【利休下駄】‥キウ‥
日和ひより下駄の一種。木地のままで、薄い二枚歯を入れたもの。
⇒りきゅう【利休】
りきゅう‐こうじゅう【裏急後重】‥キフ‥ヂユウ
大腸カタル・赤痢などの患者が、疼痛を伴って便意を催すが、肛門筋肉の痙攣けいれんによって排便がほとんど行われず、便意のみがたびたび繰り返される状態。しぶりばら。結痢。
りきゅう‐ごのみ【利休好み】‥キウ‥
①利休の好んだ作法・道具・色彩。利休箸・利休鼠の類。
②茶人風。物ずき。
⇒りきゅう【利休】
りきゅう‐ちゃ【利休茶】‥キウ‥
利休色の茶がかったもの。
⇒りきゅう【利休】
りきゅう‐ねずみ【利休鼠】‥キウ‥
利休色のねずみ色を帯びたもの。
Munsell color system: 2.5G5/1
⇒りきゅう【利休】
りきゅう‐ばし【利休箸】‥キウ‥
中央をやや太く両端を細く削って面を取った赤杉製の箸。
⇒りきゅう【利休】
りきゅう‐はちまんぐう【離宮八幡宮】
石清水いわしみず八幡宮の別宮。元府社。京都府乙訓おとくに郡大山崎町にあり、室町時代に繁栄した大山崎油座が所属。
離宮八幡宮
撮影:的場 啓
 りきゅう‐やき【利休焼】‥キウ‥
①天正(1573〜1592)年間、利休が信楽しがらきなどの茶器を選択して愛玩したもの。利休名物。
②醤油たれの中に白胡麻を加え、魚などに塗って焼いた料理。利休に因んだ料理であるが、「休」を忌み字として「久」と書くこともある。
⇒りきゅう【利休】
リキュール【liqueur フランス】
混成酒の一種。醸造酒・蒸留酒・アルコールに果実・香草・甘味料・香料などを加えて造る。ペパーミント・アブサン・キュラソーなど。
⇒リキュール‐グラス【liqueur glass】
リキュール‐グラス【liqueur glass】
リキュール用の、小型で脚付きのグラス。→グラス(図)
⇒リキュール【liqueur フランス】
り‐きょ【離居】
はなれて住むこと。
り‐ぎょ【李漁】
中国、明末・清初の戯曲作者・小説家。号は笠翁。浙江の人。戯曲「笠翁十種曲」、小説「十二楼」「無声戯」の他「笠翁一家言」「閑情偶寄」など。(1611〜1680)
り‐ぎょ【鯉魚】
コイのこと。
り‐きょう【李喬】‥ケウ
(Li Qiao)台湾の作家。台湾苗栗生れの客家ハッカ人。台湾ペンクラブ会長。総統府国策顧問。作「寒夜」。(1934〜)
り‐きょう【離京】‥キヤウ
みやこを離れること。特に、東京あるいは京都を離れること。
り‐きょう【離郷】‥キヤウ
郷里を離れること。
りき‐りつ【力率】
〔電〕交流の電圧と電流との位相差の余弦。交流の電力は実効電圧・実効電流・力率の積に等しい。
りき‐りょう【力量】‥リヤウ
人の能力の大きさの度合。また、その大きいこと。日葡辞書「リキリャウナモノ」。「―が問われる」
⇒りきりょう‐けい【力量計】
⇒りきりょう‐もの【力量者】
りきりょう‐けい【力量計】‥リヤウ‥
筋肉の運動を反復または持続して、筋肉の仕事量を計算したり疲労の状況を調べたりするための装置。
⇒りき‐りょう【力量】
りきりょう‐もの【力量者】‥リヤウ‥
力量のある者。力の強い人。
⇒りき‐りょう【力量】
り‐きん【利金】
①利息の金。利子。好色二代男「―は然も八割の算用」
②もうけた金銭。
り‐ぎん【利銀】
(→)利金に同じ。好色一代女2「二割三割の―に出しあげ」
りきん‐ぜい【釐金税】
中国で、太平天国の乱以後施行した国内関税。各省内通過の商品に価格の100分の1を賦課。1931年廃止。
りく【陸】
①地表の水におおわれない部分。地球面積の約30パーセントで、岩石および土壌から構成される。くが。おか。
②陸奥国むつのくにの略。
→ろく(陸)
り‐く【離苦】
〔仏〕苦悩を離れること。
り‐く【離垢】
〔仏〕煩悩ぼんのうを離れること。
りく‐あげ【陸揚げ】
船舶の荷物を陸上に運び揚げること。荷あげ。河岸あげ。「漁獲物を―する」「―港」
⇒りくあげ‐さんばし【陸揚げ桟橋】
りくあげ‐さんばし【陸揚げ桟橋】
陸揚げのために特に設けた桟橋。
⇒りく‐あげ【陸揚げ】
りく‐い【陸尉】‥ヰ
陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸佐と准陸尉との間。
り‐ぐい【利食い】‥グヒ
(取引用語)相場の変動によって利益勘定となった買玉かいぎょくまたは売玉うりぎょくを、転売または買戻しをして利益を収得すること。
りく‐う【陸羽】
陸奥むつ国と出羽でわ国。奥羽地方。
⇒りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】
⇒りくう‐せん【陸羽線】
りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】‥ガウ
水稲粳うるちの育成品種。1921年(大正10)寺尾博(1883〜1961)が育成。昭和初期に多収・良質で冷害に強い品種として東北・北陸・関東などに普及。
⇒りく‐う【陸羽】
リグ‐ヴェーダ【Ṛg-veda 梵】
「ヴェーダ(吠陀)」参照。
りくう‐せん【陸羽線】
JR線の一つ。陸羽東線(小牛田こごた・新庄間)94.1キロメートル、陸羽西線(新庄・余目あまるめ間)43.0キロメートル、石巻線(小牛田・女川おながわ間)44.9キロメートルの総称で、東北地方を横断し、縦走する東北本線・奥羽本線・羽越本線を連絡する。
⇒りく‐う【陸羽】
リクール【Paul Ricoeur】
フランスの哲学者。人間を歴史的状況の不随意性と価値希求の随意性との緊張関係の中で自由を求める存在者としてとらえ、それに必要な言語を単なる記号変換ではなく、生ける隠喩とみなし、新しい解釈学的哲学を構想。晩年は記憶と忘却の視点から歴史を考察した。著「意志の哲学」「生ける隠喩」「時間と物語」など。(1913〜2005)
りく‐うん【陸運】
旅客・貨物の陸上運送。
りく‐えい【陸影】
遠い海上から見る陸地の姿。
リクエスト【request】
①要求。請求。注文。
②ラジオ・テレビなどで、聴視者から出す希望。「―曲」
りく‐えふ【六衛府】‥ヱ‥
⇒ろくえふ
りくえん‐たい【陸援隊】‥ヱン‥
幕末期の浪士隊。1867年(慶応3)中岡慎太郎が京都で組織、倒幕活動を行なった。68年親兵に編入。
りく‐おう‐がくは【陸王学派】‥ワウ‥
陸象山と王陽明との学に対する呼称。ともに心即理を標榜したことから、両者を一つの学派とみなしていう。現実にこういう学派があったわけではない。
りく‐か【六花】‥クワ
⇒りっか
りく‐か【六科】‥クワ
中国、唐初の科挙(官吏登用試験)の六つの科目。すなわち秀才・明経・進士・明法・明書・明算の総称。
りく‐か【陸賈】
中国、前漢初期の政治家。楚の人。高祖に仕え、南越王趙佗ちょうだを諭して漢に臣従させ、その功により太中大夫に任ぜられた。著「新語」12編。
りく‐かい【陸海】
①陸と海。
②陸軍と海軍。
⇒りくかい‐くう【陸海空】
りくかい‐くう【陸海空】
①陸と海と空。
②陸軍と海軍と空軍。「―合同演習」
⇒りく‐かい【陸海】
りく‐かぜ【陸風】
⇒りくふう
りく‐がっしゃく【六合釈】
サンスクリット語の名詞複合語の前分と後分との関係を解釈する6種の方法。中国・日本では、相違釈・依主釈えしゅしゃく・持業釈じごつしゃく・帯数釈・有財釈うざいしゃく・隣近釈りんごんしゃくを総称していう。六離合釈。
りく‐かん【六官】‥クワン
周代の六中央行政機関。すなわち天官・地官・春官・夏官・秋官・冬官の総称。→六卿りくけい
りく‐き【六気】
⇒ろっき
りく‐き【陸機】
中国、西晋の詩人。字は士衡。呉の名族の出身。呉の滅亡後、弟の陸雲(262〜303)と共に洛陽へ赴き、晋に仕えた。修辞に意を用いた華麗な詩風で、六朝修辞主義の路を開いた。陸雲と共に二陸と称される。著「陸士衡集」。(261〜303)
りく‐ぎ【六義】
①詩経大序にいう詩の6種の分類。すなわち賦・比・興・風・雅・頌。賦は感想そのままを述べたもの、比はたとえを採って感想を述べたもの、興は外物に触れて感想を述べたもの、風は民間に行われる歌謡、雅は朝廷でうたわれる雅正の詞藻、頌は宗廟頌徳の詞藻。
②紀貫之が詩の六義を転用して古今集序において述べた、和歌の6種の風体。そえ歌・かぞえ歌・なずらえ歌・たとえ歌・ただこと歌・いわい歌。転じて、和歌。「―の道」
③書道で、筆法・風情・字象・去病・骨目・感徳の6種の法。
④(→)六書りくしょ1に同じ。
りく‐ぎ【六儀】
①周代、祭祀さいし・賓客・朝廷・喪紀・軍旅・車馬の6事に関する儀式。
②転じて、ものの道理・筋道。浄瑠璃、今宮の心中「善悪ふたつをかみ分けて、―をただす柴崎に」
③唐代後宮の六つの女官名。淑儀など。
りく‐ぎ【六議】
律に規定された刑法上の特典を受くべき6種の資格。議親ぎしん・議故ぎこ・議賢ぎけん・議能ぎのう・議功ぎくう・議貴ぎきの総称。天皇の親族・縁故者、国家の賢者や能・功ある者、貴族などは裁判に際し律を機械的に適用されず、特に情状酌量され、また流罪以下ならば最初から一等減刑される。唐律の八議に由来。→八議
りくぎ‐えん【六義園】‥ヱン
東京都文京区本駒込にある回遊式庭園。元禄(1688〜1704)年間、柳沢吉保がその別邸に造った江戸時代の名園。
りく‐きゅう【六宮】
中国で、皇后のいる六つの宮殿。後宮。太平記39「―の美人」
りく‐きゅうえん【陸九淵】‥キウヱン
(→)陸象山りくしょうざんの別称。
りく‐ぐ【六具】
⇒ろくぐ
りく‐ぐん【六軍】
周代の兵制で、天子が統率した6個の軍の称。一軍は1万2500人、したがって総計7万5000人。六師りくし。
りく‐ぐん【陸軍】
陸上戦闘を任務とする軍備・軍隊。明治維新後の日本では天皇に直属し、海軍と協同して国防に任じた。1945年(昭和20)11月廃止。渡辺崋山、外国事情書「軍官は海陸相分け候得共、―尤も多く」
⇒りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】
⇒りくぐん‐きょう【陸軍卿】
⇒りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】
⇒りくぐん‐しょう【陸軍省】
⇒りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】
⇒りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】
⇒りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】
⇒りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】
⇒りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】
⇒りくぐん‐はじめ【陸軍始】
⇒りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】
⇒りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】
⇒りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】
りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】
1905年(明治38)の奉天大会戦の勝利を記念した3月10日。第二次大戦後廃止。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐きょう【陸軍卿】‥キヤウ
1885年(明治18)官制改革以前の陸軍省の長官。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】‥クワンガクカウ
陸軍の士官候補生および准士官・下士官を教育した学校。1874年(明治7)東京市ヶ谷に設置、敗戦時は神奈川県座間にあった。略称、陸士。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐しょう【陸軍省】‥シヤウ
もと内閣各省の一つ。陸軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→参謀本部。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】
江戸幕府の職名。幕府の陸軍を総轄した。1862年(文久2)設置。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】‥ザウ‥シヤウ
陸軍の兵器・弾薬・器具・材料などを製造・修理した所。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】‥ガクカウ
陸軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行う学校。東京赤坂にあった。略称、陸大。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】
旧陸軍省の長官。陸軍行政を管理し、陸軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては内閣を経て天皇を輔弼ほひつする責任を負ったが、軍機・軍令に関しては直接天皇に上奏・裁可を求める帷幄いあく上奏権が認められていた。陸相。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】‥ガクカウ
陸軍の秘密戦(情報収集・防諜・謀略など)の要員を養成するための学校。1938年(昭和13)に創設され、東京中野にあった。参謀総長直轄。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐はじめ【陸軍始】
旧日本陸軍で毎年1月8日の仕事始めの日に行なった観兵式などの儀式。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】
1934年(昭和9)に陸軍省新聞班が発表した小冊子「国防の本義と其の強化の提唱」の通称。総力戦を遂行できる「高度国防国家」の構築と軍備の急速な拡充を主張。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。歩兵・騎兵・砲兵を統括した。1862年(文久2)設置。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】‥エウ‥ガクカウ
陸軍将校を志願する少年に対して陸軍士官学校の予備教育を行う学校。東京・仙台・名古屋・大阪・広島・熊本にあった。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りく‐けい【六経】
中国における6種の経書。すなわち易経・書経・詩経・礼らい・楽経(佚書)・春秋の総称。六芸。六籍。
りく‐けい【六卿】
周代の六官りくかんの長。すなわち冢宰ちょうさい・司徒・宗伯・司馬・司寇・司空。
りく‐げい【六芸】
①周代に士以上が必ず学ぶべき科目と定められた6種の技芸。すなわち礼・楽・射・御・書・数。
②(→)六経りくけいに同じ。
りくけい‐とう【陸繋島】‥タウ
砂州によって陸地とつながった島。潮岬・函館山など。
りく‐けん【陸圏】
⇒りっけん
りく‐こ【陸弧】
大陸の縁辺につらなる山脈とそれに平行な海溝との組合せ。アンデス山脈とペルー‐チリ海溝との組が好例。地学的現象が弧状列島と同類であるため、島弧にならって名づけられた。
りく‐ごう【六合】‥ガフ
天地と四方。宇宙全体。謡曲、内外詣「日月は―を照らせども」
りくごう‐ざっし【六合雑誌】‥ガフ‥
1880年(明治13)キリスト教徒の小崎弘道・植村正久らが創刊した評論雑誌。政治・思想・社会問題などについて、キリスト教社会主義など進歩的立場から論じた。1921年(大正10)終刊。
りく‐こく【六国】
⇒りっこく
りく‐さ【陸佐】
陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸将補と陸尉との間。
りく‐さん【陸産】
陸産物の略。
⇒りくさん‐ぶつ【陸産物】
りくさん‐ぶつ【陸産物】
陸上に産する物。陸産。
⇒りく‐さん【陸産】
りく‐し【六師】
(→)六軍りくぐんに同じ。
りく‐し【陸士】
①陸軍士官学校の略称。
②陸上自衛官の最下位の階級。陸士長および一・二・三等がある。
りく‐じ【六事】
慈・倹・勤・慎・誠・明の六つの徳。
りく‐じ【陸自】
陸上自衛隊の略。
りく‐じ【陸路】‥ヂ
陸上の道。りくろ。〈日葡辞書〉
りく‐しゅうふ【陸秀夫】‥シウ‥
南宋末の忠臣。宰相。字は君実。張世傑とともに広東厓山で元軍と最後の戦闘をして敗れ、幼君衛王昺へいを抱いて入水。(1236〜1279)
りく‐しゅつ【六出】
(雪の結晶を花に見立て、6弁があるとして)雪の異称。六花。むつのはな。
⇒りくしゅつ‐か【六出花】
りくしゅつ‐か【六出花】‥クワ
(→)六出に同じ。
⇒りく‐しゅつ【六出】
りく‐しょ【六書】
①漢字の字形の構成および用法に関する6種の原則。象形しょうけい・指事・会意・形声・転注・仮借かしゃ。
②(→)六体りくたい1に同じ。
りく‐しょう【陸相】‥シヤウ
陸軍大臣の略称。
りく‐しょう【陸将】‥シヤウ
①陸軍の将官。
②陸上自衛官の最高位の階級。陸佐との間に陸将補がある。
りく‐じょう【陸上】‥ジヤウ
①陸地の上。
②陸上競技の略。
⇒りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】
⇒りくじょう‐き【陸上機】
⇒りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】
⇒りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】
⇒りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】
りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】‥ジヤウ‥
(→)運送保険に同じ。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくじょう‐き【陸上機】‥ジヤウ‥
車輪・スキーなどにより地上を滑走して離着陸を行う飛行機の総称。陸上飛行機。↔水上機。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】‥ジヤウキヤウ‥
トラック1・フィールドおよび道路などで行われる歩・走・跳・投の競技。→トラック競技→フィールド競技。
⇒りく‐じょう【陸上】
りく‐しょうざん【陸象山】‥シヤウ‥
南宋の大儒。名は九淵。字は子静。象山・存斎と号。江西金渓の人。程顥ていこうの哲学を発展させて、心即理を主張、朱熹の主知的哲学に対抗。文安と諡おくりなす。(1139〜1192)
りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥
自衛隊の一つ。5個の方面隊および防衛大臣直轄部隊から成る。陸上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。保安隊の後身として1954年(昭和29)設置。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくしょう‐じっきく【六菖十菊】‥シヤウ‥
「六日むいかの菖蒲あやめ、十日の菊」に同じ。→六日(成句)
りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】‥ジヤウ‥
緑藻類から進化して、陸上に生育するようになった一群の植物の総称。コケ植物・シダ植物・種子植物をいう。陸生植物。
⇒りく‐じょう【陸上】
りく‐しん【六親】
父・母・兄・弟・妻・子の総称。また、父・子・兄・弟・夫・婦の総称。ろくしん。平家物語2「―を皆罪せらる」
りく・す【戮す】
〔他サ変〕
①罪ある者を殺す。
②(力を)合わせる。
りく‐ず【陸図】‥ヅ
(→)地形図に同じ。
りく‐すい【陸水】
(内陸にある水域の意)地球上に分布する水のうち、海水を除いたものの総称。湖沼・河川・地下水・温泉・雪氷など。
⇒りくすい‐がく【陸水学】
りくすい‐がく【陸水学】
(昭和初期の造語)陸水の物理的・化学的・生物学的研究を行う学問。淡水漁業・稚魚養殖・水道事業・工場用水および排水などに寄与する。→水文学すいもんがく
⇒りく‐すい【陸水】
りく‐せい【陸生・陸棲】
陸地に生ずること。また、陸地で生活すること。↔水生。
⇒りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】
⇒りくせい‐どうぶつ【陸生動物】
りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】
陸地に生育する植物。系統分類上は陸上植物とは異なる。↔水生植物。
⇒りく‐せい【陸生・陸棲】
りくせい‐そう【陸成層】
湖沼・河川または風の作用によって陸上に堆積・生成した地層。淡水成層・風成層など。
りくせい‐どうぶつ【陸生動物】
陸地に生活する動物の総称。陸上生活に適応して、空気呼吸、卵や子の保護、体の保持・運動などの機構を備える。
⇒りく‐せい【陸生・陸棲】
りく‐せき【六籍】
(→)六経りくけいに同じ。
りく‐せん【陸戦】
陸上の戦闘。
⇒りくせん‐たい【陸戦隊】
りくぜん【陸前】
旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。大部分は今の宮城県、一部は岩手県に属する。
⇒りくぜん‐たかた【陸前高田】
⇒りくぜん‐はまかいどう【陸前浜街道】
りくせん‐たい【陸戦隊】
海軍陸戦隊の略称。
⇒りく‐せん【陸戦】
りくぜん‐たかた【陸前高田】
岩手県南東部、広田湾に臨む市。遠洋漁業の基地。湾内ではホタテガイ・ワカメなどの養殖も盛ん。人口2万5千。
⇒りくぜん【陸前】
りくぜん‐はまかいどう【陸前浜街道】‥ダウ
(→)浜街道2に同じ。
⇒りくぜん【陸前】
りく‐そう【陸送】
①陸上の輸送。「―のトラック」
②未登録車両を運転して輸送すること。
りく‐そう【陸曹】‥サウ
陸上自衛官の階級の一つ。陸曹長および一・二・三等がある。准陸尉と陸士との間。
りく‐ぞく【陸続】
ひっきりなしに続くさま。「避難民が―とやって来る」
りく‐たい【六体】
①漢字の6種の書体、すなわち大篆だいてん・小篆・八分はっぷん・隷書・行書・草書。また、古文・奇字・篆書・隷書・繆篆びゅうてん・虫書の総称。
②(→)六書1に同じ。
③書経の6種の文体、すなわち典・謨・誓・命・訓・誥の称。
りく‐だな【陸棚】
(→)大陸棚に同じ。
りく‐たんび【陸探微】
宋2の画家。呉(江蘇省)の人。一筆画による人物画に長じる。顧愷之こがいし・張僧繇ちょうそうようとともに六朝三大家の一人。生没年未詳。
りく‐ち【陸地】
地球表面の、水におおわれない所。ろくち。→陸。
⇒りくち‐そくりょう‐ひょう【陸地測量標】
⇒りくち‐めん【陸地綿・陸地棉】
りく‐ちく【六畜】
六つの家畜、すなわち牛・馬・羊・犬・鶏・豚の総称。ろくちく。
りくち‐そくりょう‐ひょう【陸地測量標】‥リヤウヘウ
陸地測量のために設置した標識。三角点標石・水準点標石・測標・標杭・測旗・仮杭の6種。
⇒りく‐ち【陸地】
りくち‐めん【陸地綿・陸地棉】
ワタの一種。中米の原産とされ、アメリカ合衆国を中心に世界のワタの栽培面積の7割を占める。海島綿かいとうめんに対していう。→わた
⇒りく‐ち【陸地】
りくちゅう【陸中】
旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。大部分は今の岩手県、一部は秋田県に属する。
⇒りくちゅうかいがん‐こくりつこうえん【陸中海岸国立公園】
りくちゅうかいがん‐こくりつこうえん【陸中海岸国立公園】‥ヱン
岩手県東部の典型的リアス海岸地帯の国立公園。壮大な海食崖、深く入りこんだ湾・入江などが多く、ウミツバメの繁殖地日出島、ウミネコで知られる佐賀部さかべかもめ島、崎山の潮吹穴、八戸穴などの奇景も少なくない。
⇒りくちゅう【陸中】
りく‐ちょう【六朝】‥テウ
①中国で、後漢滅亡から隋の統一まで建業・建康(南京)に都した、呉・東晋・宋・斉・梁・陳の6王朝の総称。
②六朝時代に行われた書風。
⇒りくちょう‐みんか【六朝民歌】
りくちょう‐みんか【六朝民歌】‥テウ‥
中国六朝時代の半ば頃に南北でそれぞれ勃興した民歌。南朝楽府がふ・北朝楽府と呼ばれる。
⇒りく‐ちょう【六朝】
り‐くつ【理屈・理窟】
(理のつまる所の意)
①物事のすじみち。道理。ことわり。「―に合う」「―ではわかっている」
②こじつけの理由。現実を無視した条理。また、それを言い張ること。「―をこねる」「―を付ける」
③色事。情事。黄表紙、御存商売物「青本は妹柱かくしと一枚絵が―を知り」
④やりくり。金の工面。また、心づもり。手はず。花暦八笑人「そこで今夜下見分をしようといふ―だ」
⇒りくつ‐ぜめ【理屈責め】
⇒りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
⇒りくつ‐づめ【理屈詰め】
⇒りくつ‐ぬき【理屈抜き】
⇒りくつ‐や【理屈屋】
⇒理屈と膏薬はどこへでも付く
りくつ‐ぜめ【理屈責め】
理屈一方で人を責めなじること。理責め。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りく‐つづき【陸続き】
二つの地が海などに隔てられず、陸地でつながっていること。地続き。
りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
〔形〕
何事についてもすぐに理屈を言い出しがちである。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐づめ【理屈詰め】
理屈を言い立てること。理詰め。好色一代女1「―なるつめひらき、少し勿体もつけ」
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りきゅう‐やき【利休焼】‥キウ‥
①天正(1573〜1592)年間、利休が信楽しがらきなどの茶器を選択して愛玩したもの。利休名物。
②醤油たれの中に白胡麻を加え、魚などに塗って焼いた料理。利休に因んだ料理であるが、「休」を忌み字として「久」と書くこともある。
⇒りきゅう【利休】
リキュール【liqueur フランス】
混成酒の一種。醸造酒・蒸留酒・アルコールに果実・香草・甘味料・香料などを加えて造る。ペパーミント・アブサン・キュラソーなど。
⇒リキュール‐グラス【liqueur glass】
リキュール‐グラス【liqueur glass】
リキュール用の、小型で脚付きのグラス。→グラス(図)
⇒リキュール【liqueur フランス】
り‐きょ【離居】
はなれて住むこと。
り‐ぎょ【李漁】
中国、明末・清初の戯曲作者・小説家。号は笠翁。浙江の人。戯曲「笠翁十種曲」、小説「十二楼」「無声戯」の他「笠翁一家言」「閑情偶寄」など。(1611〜1680)
り‐ぎょ【鯉魚】
コイのこと。
り‐きょう【李喬】‥ケウ
(Li Qiao)台湾の作家。台湾苗栗生れの客家ハッカ人。台湾ペンクラブ会長。総統府国策顧問。作「寒夜」。(1934〜)
り‐きょう【離京】‥キヤウ
みやこを離れること。特に、東京あるいは京都を離れること。
り‐きょう【離郷】‥キヤウ
郷里を離れること。
りき‐りつ【力率】
〔電〕交流の電圧と電流との位相差の余弦。交流の電力は実効電圧・実効電流・力率の積に等しい。
りき‐りょう【力量】‥リヤウ
人の能力の大きさの度合。また、その大きいこと。日葡辞書「リキリャウナモノ」。「―が問われる」
⇒りきりょう‐けい【力量計】
⇒りきりょう‐もの【力量者】
りきりょう‐けい【力量計】‥リヤウ‥
筋肉の運動を反復または持続して、筋肉の仕事量を計算したり疲労の状況を調べたりするための装置。
⇒りき‐りょう【力量】
りきりょう‐もの【力量者】‥リヤウ‥
力量のある者。力の強い人。
⇒りき‐りょう【力量】
り‐きん【利金】
①利息の金。利子。好色二代男「―は然も八割の算用」
②もうけた金銭。
り‐ぎん【利銀】
(→)利金に同じ。好色一代女2「二割三割の―に出しあげ」
りきん‐ぜい【釐金税】
中国で、太平天国の乱以後施行した国内関税。各省内通過の商品に価格の100分の1を賦課。1931年廃止。
りく【陸】
①地表の水におおわれない部分。地球面積の約30パーセントで、岩石および土壌から構成される。くが。おか。
②陸奥国むつのくにの略。
→ろく(陸)
り‐く【離苦】
〔仏〕苦悩を離れること。
り‐く【離垢】
〔仏〕煩悩ぼんのうを離れること。
りく‐あげ【陸揚げ】
船舶の荷物を陸上に運び揚げること。荷あげ。河岸あげ。「漁獲物を―する」「―港」
⇒りくあげ‐さんばし【陸揚げ桟橋】
りくあげ‐さんばし【陸揚げ桟橋】
陸揚げのために特に設けた桟橋。
⇒りく‐あげ【陸揚げ】
りく‐い【陸尉】‥ヰ
陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸佐と准陸尉との間。
り‐ぐい【利食い】‥グヒ
(取引用語)相場の変動によって利益勘定となった買玉かいぎょくまたは売玉うりぎょくを、転売または買戻しをして利益を収得すること。
りく‐う【陸羽】
陸奥むつ国と出羽でわ国。奥羽地方。
⇒りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】
⇒りくう‐せん【陸羽線】
りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】‥ガウ
水稲粳うるちの育成品種。1921年(大正10)寺尾博(1883〜1961)が育成。昭和初期に多収・良質で冷害に強い品種として東北・北陸・関東などに普及。
⇒りく‐う【陸羽】
リグ‐ヴェーダ【Ṛg-veda 梵】
「ヴェーダ(吠陀)」参照。
りくう‐せん【陸羽線】
JR線の一つ。陸羽東線(小牛田こごた・新庄間)94.1キロメートル、陸羽西線(新庄・余目あまるめ間)43.0キロメートル、石巻線(小牛田・女川おながわ間)44.9キロメートルの総称で、東北地方を横断し、縦走する東北本線・奥羽本線・羽越本線を連絡する。
⇒りく‐う【陸羽】
リクール【Paul Ricoeur】
フランスの哲学者。人間を歴史的状況の不随意性と価値希求の随意性との緊張関係の中で自由を求める存在者としてとらえ、それに必要な言語を単なる記号変換ではなく、生ける隠喩とみなし、新しい解釈学的哲学を構想。晩年は記憶と忘却の視点から歴史を考察した。著「意志の哲学」「生ける隠喩」「時間と物語」など。(1913〜2005)
りく‐うん【陸運】
旅客・貨物の陸上運送。
りく‐えい【陸影】
遠い海上から見る陸地の姿。
リクエスト【request】
①要求。請求。注文。
②ラジオ・テレビなどで、聴視者から出す希望。「―曲」
りく‐えふ【六衛府】‥ヱ‥
⇒ろくえふ
りくえん‐たい【陸援隊】‥ヱン‥
幕末期の浪士隊。1867年(慶応3)中岡慎太郎が京都で組織、倒幕活動を行なった。68年親兵に編入。
りく‐おう‐がくは【陸王学派】‥ワウ‥
陸象山と王陽明との学に対する呼称。ともに心即理を標榜したことから、両者を一つの学派とみなしていう。現実にこういう学派があったわけではない。
りく‐か【六花】‥クワ
⇒りっか
りく‐か【六科】‥クワ
中国、唐初の科挙(官吏登用試験)の六つの科目。すなわち秀才・明経・進士・明法・明書・明算の総称。
りく‐か【陸賈】
中国、前漢初期の政治家。楚の人。高祖に仕え、南越王趙佗ちょうだを諭して漢に臣従させ、その功により太中大夫に任ぜられた。著「新語」12編。
りく‐かい【陸海】
①陸と海。
②陸軍と海軍。
⇒りくかい‐くう【陸海空】
りくかい‐くう【陸海空】
①陸と海と空。
②陸軍と海軍と空軍。「―合同演習」
⇒りく‐かい【陸海】
りく‐かぜ【陸風】
⇒りくふう
りく‐がっしゃく【六合釈】
サンスクリット語の名詞複合語の前分と後分との関係を解釈する6種の方法。中国・日本では、相違釈・依主釈えしゅしゃく・持業釈じごつしゃく・帯数釈・有財釈うざいしゃく・隣近釈りんごんしゃくを総称していう。六離合釈。
りく‐かん【六官】‥クワン
周代の六中央行政機関。すなわち天官・地官・春官・夏官・秋官・冬官の総称。→六卿りくけい
りく‐き【六気】
⇒ろっき
りく‐き【陸機】
中国、西晋の詩人。字は士衡。呉の名族の出身。呉の滅亡後、弟の陸雲(262〜303)と共に洛陽へ赴き、晋に仕えた。修辞に意を用いた華麗な詩風で、六朝修辞主義の路を開いた。陸雲と共に二陸と称される。著「陸士衡集」。(261〜303)
りく‐ぎ【六義】
①詩経大序にいう詩の6種の分類。すなわち賦・比・興・風・雅・頌。賦は感想そのままを述べたもの、比はたとえを採って感想を述べたもの、興は外物に触れて感想を述べたもの、風は民間に行われる歌謡、雅は朝廷でうたわれる雅正の詞藻、頌は宗廟頌徳の詞藻。
②紀貫之が詩の六義を転用して古今集序において述べた、和歌の6種の風体。そえ歌・かぞえ歌・なずらえ歌・たとえ歌・ただこと歌・いわい歌。転じて、和歌。「―の道」
③書道で、筆法・風情・字象・去病・骨目・感徳の6種の法。
④(→)六書りくしょ1に同じ。
りく‐ぎ【六儀】
①周代、祭祀さいし・賓客・朝廷・喪紀・軍旅・車馬の6事に関する儀式。
②転じて、ものの道理・筋道。浄瑠璃、今宮の心中「善悪ふたつをかみ分けて、―をただす柴崎に」
③唐代後宮の六つの女官名。淑儀など。
りく‐ぎ【六議】
律に規定された刑法上の特典を受くべき6種の資格。議親ぎしん・議故ぎこ・議賢ぎけん・議能ぎのう・議功ぎくう・議貴ぎきの総称。天皇の親族・縁故者、国家の賢者や能・功ある者、貴族などは裁判に際し律を機械的に適用されず、特に情状酌量され、また流罪以下ならば最初から一等減刑される。唐律の八議に由来。→八議
りくぎ‐えん【六義園】‥ヱン
東京都文京区本駒込にある回遊式庭園。元禄(1688〜1704)年間、柳沢吉保がその別邸に造った江戸時代の名園。
りく‐きゅう【六宮】
中国で、皇后のいる六つの宮殿。後宮。太平記39「―の美人」
りく‐きゅうえん【陸九淵】‥キウヱン
(→)陸象山りくしょうざんの別称。
りく‐ぐ【六具】
⇒ろくぐ
りく‐ぐん【六軍】
周代の兵制で、天子が統率した6個の軍の称。一軍は1万2500人、したがって総計7万5000人。六師りくし。
りく‐ぐん【陸軍】
陸上戦闘を任務とする軍備・軍隊。明治維新後の日本では天皇に直属し、海軍と協同して国防に任じた。1945年(昭和20)11月廃止。渡辺崋山、外国事情書「軍官は海陸相分け候得共、―尤も多く」
⇒りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】
⇒りくぐん‐きょう【陸軍卿】
⇒りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】
⇒りくぐん‐しょう【陸軍省】
⇒りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】
⇒りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】
⇒りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】
⇒りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】
⇒りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】
⇒りくぐん‐はじめ【陸軍始】
⇒りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】
⇒りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】
⇒りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】
りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】
1905年(明治38)の奉天大会戦の勝利を記念した3月10日。第二次大戦後廃止。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐きょう【陸軍卿】‥キヤウ
1885年(明治18)官制改革以前の陸軍省の長官。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】‥クワンガクカウ
陸軍の士官候補生および准士官・下士官を教育した学校。1874年(明治7)東京市ヶ谷に設置、敗戦時は神奈川県座間にあった。略称、陸士。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐しょう【陸軍省】‥シヤウ
もと内閣各省の一つ。陸軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→参謀本部。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】
江戸幕府の職名。幕府の陸軍を総轄した。1862年(文久2)設置。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】‥ザウ‥シヤウ
陸軍の兵器・弾薬・器具・材料などを製造・修理した所。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】‥ガクカウ
陸軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行う学校。東京赤坂にあった。略称、陸大。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】
旧陸軍省の長官。陸軍行政を管理し、陸軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては内閣を経て天皇を輔弼ほひつする責任を負ったが、軍機・軍令に関しては直接天皇に上奏・裁可を求める帷幄いあく上奏権が認められていた。陸相。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】‥ガクカウ
陸軍の秘密戦(情報収集・防諜・謀略など)の要員を養成するための学校。1938年(昭和13)に創設され、東京中野にあった。参謀総長直轄。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐はじめ【陸軍始】
旧日本陸軍で毎年1月8日の仕事始めの日に行なった観兵式などの儀式。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】
1934年(昭和9)に陸軍省新聞班が発表した小冊子「国防の本義と其の強化の提唱」の通称。総力戦を遂行できる「高度国防国家」の構築と軍備の急速な拡充を主張。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。歩兵・騎兵・砲兵を統括した。1862年(文久2)設置。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】‥エウ‥ガクカウ
陸軍将校を志願する少年に対して陸軍士官学校の予備教育を行う学校。東京・仙台・名古屋・大阪・広島・熊本にあった。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りく‐けい【六経】
中国における6種の経書。すなわち易経・書経・詩経・礼らい・楽経(佚書)・春秋の総称。六芸。六籍。
りく‐けい【六卿】
周代の六官りくかんの長。すなわち冢宰ちょうさい・司徒・宗伯・司馬・司寇・司空。
りく‐げい【六芸】
①周代に士以上が必ず学ぶべき科目と定められた6種の技芸。すなわち礼・楽・射・御・書・数。
②(→)六経りくけいに同じ。
りくけい‐とう【陸繋島】‥タウ
砂州によって陸地とつながった島。潮岬・函館山など。
りく‐けん【陸圏】
⇒りっけん
りく‐こ【陸弧】
大陸の縁辺につらなる山脈とそれに平行な海溝との組合せ。アンデス山脈とペルー‐チリ海溝との組が好例。地学的現象が弧状列島と同類であるため、島弧にならって名づけられた。
りく‐ごう【六合】‥ガフ
天地と四方。宇宙全体。謡曲、内外詣「日月は―を照らせども」
りくごう‐ざっし【六合雑誌】‥ガフ‥
1880年(明治13)キリスト教徒の小崎弘道・植村正久らが創刊した評論雑誌。政治・思想・社会問題などについて、キリスト教社会主義など進歩的立場から論じた。1921年(大正10)終刊。
りく‐こく【六国】
⇒りっこく
りく‐さ【陸佐】
陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸将補と陸尉との間。
りく‐さん【陸産】
陸産物の略。
⇒りくさん‐ぶつ【陸産物】
りくさん‐ぶつ【陸産物】
陸上に産する物。陸産。
⇒りく‐さん【陸産】
りく‐し【六師】
(→)六軍りくぐんに同じ。
りく‐し【陸士】
①陸軍士官学校の略称。
②陸上自衛官の最下位の階級。陸士長および一・二・三等がある。
りく‐じ【六事】
慈・倹・勤・慎・誠・明の六つの徳。
りく‐じ【陸自】
陸上自衛隊の略。
りく‐じ【陸路】‥ヂ
陸上の道。りくろ。〈日葡辞書〉
りく‐しゅうふ【陸秀夫】‥シウ‥
南宋末の忠臣。宰相。字は君実。張世傑とともに広東厓山で元軍と最後の戦闘をして敗れ、幼君衛王昺へいを抱いて入水。(1236〜1279)
りく‐しゅつ【六出】
(雪の結晶を花に見立て、6弁があるとして)雪の異称。六花。むつのはな。
⇒りくしゅつ‐か【六出花】
りくしゅつ‐か【六出花】‥クワ
(→)六出に同じ。
⇒りく‐しゅつ【六出】
りく‐しょ【六書】
①漢字の字形の構成および用法に関する6種の原則。象形しょうけい・指事・会意・形声・転注・仮借かしゃ。
②(→)六体りくたい1に同じ。
りく‐しょう【陸相】‥シヤウ
陸軍大臣の略称。
りく‐しょう【陸将】‥シヤウ
①陸軍の将官。
②陸上自衛官の最高位の階級。陸佐との間に陸将補がある。
りく‐じょう【陸上】‥ジヤウ
①陸地の上。
②陸上競技の略。
⇒りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】
⇒りくじょう‐き【陸上機】
⇒りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】
⇒りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】
⇒りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】
りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】‥ジヤウ‥
(→)運送保険に同じ。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくじょう‐き【陸上機】‥ジヤウ‥
車輪・スキーなどにより地上を滑走して離着陸を行う飛行機の総称。陸上飛行機。↔水上機。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】‥ジヤウキヤウ‥
トラック1・フィールドおよび道路などで行われる歩・走・跳・投の競技。→トラック競技→フィールド競技。
⇒りく‐じょう【陸上】
りく‐しょうざん【陸象山】‥シヤウ‥
南宋の大儒。名は九淵。字は子静。象山・存斎と号。江西金渓の人。程顥ていこうの哲学を発展させて、心即理を主張、朱熹の主知的哲学に対抗。文安と諡おくりなす。(1139〜1192)
りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥
自衛隊の一つ。5個の方面隊および防衛大臣直轄部隊から成る。陸上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。保安隊の後身として1954年(昭和29)設置。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくしょう‐じっきく【六菖十菊】‥シヤウ‥
「六日むいかの菖蒲あやめ、十日の菊」に同じ。→六日(成句)
りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】‥ジヤウ‥
緑藻類から進化して、陸上に生育するようになった一群の植物の総称。コケ植物・シダ植物・種子植物をいう。陸生植物。
⇒りく‐じょう【陸上】
りく‐しん【六親】
父・母・兄・弟・妻・子の総称。また、父・子・兄・弟・夫・婦の総称。ろくしん。平家物語2「―を皆罪せらる」
りく・す【戮す】
〔他サ変〕
①罪ある者を殺す。
②(力を)合わせる。
りく‐ず【陸図】‥ヅ
(→)地形図に同じ。
りく‐すい【陸水】
(内陸にある水域の意)地球上に分布する水のうち、海水を除いたものの総称。湖沼・河川・地下水・温泉・雪氷など。
⇒りくすい‐がく【陸水学】
りくすい‐がく【陸水学】
(昭和初期の造語)陸水の物理的・化学的・生物学的研究を行う学問。淡水漁業・稚魚養殖・水道事業・工場用水および排水などに寄与する。→水文学すいもんがく
⇒りく‐すい【陸水】
りく‐せい【陸生・陸棲】
陸地に生ずること。また、陸地で生活すること。↔水生。
⇒りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】
⇒りくせい‐どうぶつ【陸生動物】
りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】
陸地に生育する植物。系統分類上は陸上植物とは異なる。↔水生植物。
⇒りく‐せい【陸生・陸棲】
りくせい‐そう【陸成層】
湖沼・河川または風の作用によって陸上に堆積・生成した地層。淡水成層・風成層など。
りくせい‐どうぶつ【陸生動物】
陸地に生活する動物の総称。陸上生活に適応して、空気呼吸、卵や子の保護、体の保持・運動などの機構を備える。
⇒りく‐せい【陸生・陸棲】
りく‐せき【六籍】
(→)六経りくけいに同じ。
りく‐せん【陸戦】
陸上の戦闘。
⇒りくせん‐たい【陸戦隊】
りくぜん【陸前】
旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。大部分は今の宮城県、一部は岩手県に属する。
⇒りくぜん‐たかた【陸前高田】
⇒りくぜん‐はまかいどう【陸前浜街道】
りくせん‐たい【陸戦隊】
海軍陸戦隊の略称。
⇒りく‐せん【陸戦】
りくぜん‐たかた【陸前高田】
岩手県南東部、広田湾に臨む市。遠洋漁業の基地。湾内ではホタテガイ・ワカメなどの養殖も盛ん。人口2万5千。
⇒りくぜん【陸前】
りくぜん‐はまかいどう【陸前浜街道】‥ダウ
(→)浜街道2に同じ。
⇒りくぜん【陸前】
りく‐そう【陸送】
①陸上の輸送。「―のトラック」
②未登録車両を運転して輸送すること。
りく‐そう【陸曹】‥サウ
陸上自衛官の階級の一つ。陸曹長および一・二・三等がある。准陸尉と陸士との間。
りく‐ぞく【陸続】
ひっきりなしに続くさま。「避難民が―とやって来る」
りく‐たい【六体】
①漢字の6種の書体、すなわち大篆だいてん・小篆・八分はっぷん・隷書・行書・草書。また、古文・奇字・篆書・隷書・繆篆びゅうてん・虫書の総称。
②(→)六書1に同じ。
③書経の6種の文体、すなわち典・謨・誓・命・訓・誥の称。
りく‐だな【陸棚】
(→)大陸棚に同じ。
りく‐たんび【陸探微】
宋2の画家。呉(江蘇省)の人。一筆画による人物画に長じる。顧愷之こがいし・張僧繇ちょうそうようとともに六朝三大家の一人。生没年未詳。
りく‐ち【陸地】
地球表面の、水におおわれない所。ろくち。→陸。
⇒りくち‐そくりょう‐ひょう【陸地測量標】
⇒りくち‐めん【陸地綿・陸地棉】
りく‐ちく【六畜】
六つの家畜、すなわち牛・馬・羊・犬・鶏・豚の総称。ろくちく。
りくち‐そくりょう‐ひょう【陸地測量標】‥リヤウヘウ
陸地測量のために設置した標識。三角点標石・水準点標石・測標・標杭・測旗・仮杭の6種。
⇒りく‐ち【陸地】
りくち‐めん【陸地綿・陸地棉】
ワタの一種。中米の原産とされ、アメリカ合衆国を中心に世界のワタの栽培面積の7割を占める。海島綿かいとうめんに対していう。→わた
⇒りく‐ち【陸地】
りくちゅう【陸中】
旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。大部分は今の岩手県、一部は秋田県に属する。
⇒りくちゅうかいがん‐こくりつこうえん【陸中海岸国立公園】
りくちゅうかいがん‐こくりつこうえん【陸中海岸国立公園】‥ヱン
岩手県東部の典型的リアス海岸地帯の国立公園。壮大な海食崖、深く入りこんだ湾・入江などが多く、ウミツバメの繁殖地日出島、ウミネコで知られる佐賀部さかべかもめ島、崎山の潮吹穴、八戸穴などの奇景も少なくない。
⇒りくちゅう【陸中】
りく‐ちょう【六朝】‥テウ
①中国で、後漢滅亡から隋の統一まで建業・建康(南京)に都した、呉・東晋・宋・斉・梁・陳の6王朝の総称。
②六朝時代に行われた書風。
⇒りくちょう‐みんか【六朝民歌】
りくちょう‐みんか【六朝民歌】‥テウ‥
中国六朝時代の半ば頃に南北でそれぞれ勃興した民歌。南朝楽府がふ・北朝楽府と呼ばれる。
⇒りく‐ちょう【六朝】
り‐くつ【理屈・理窟】
(理のつまる所の意)
①物事のすじみち。道理。ことわり。「―に合う」「―ではわかっている」
②こじつけの理由。現実を無視した条理。また、それを言い張ること。「―をこねる」「―を付ける」
③色事。情事。黄表紙、御存商売物「青本は妹柱かくしと一枚絵が―を知り」
④やりくり。金の工面。また、心づもり。手はず。花暦八笑人「そこで今夜下見分をしようといふ―だ」
⇒りくつ‐ぜめ【理屈責め】
⇒りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
⇒りくつ‐づめ【理屈詰め】
⇒りくつ‐ぬき【理屈抜き】
⇒りくつ‐や【理屈屋】
⇒理屈と膏薬はどこへでも付く
りくつ‐ぜめ【理屈責め】
理屈一方で人を責めなじること。理責め。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りく‐つづき【陸続き】
二つの地が海などに隔てられず、陸地でつながっていること。地続き。
りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
〔形〕
何事についてもすぐに理屈を言い出しがちである。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐づめ【理屈詰め】
理屈を言い立てること。理詰め。好色一代女1「―なるつめひらき、少し勿体もつけ」
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
 りきゅう‐やき【利休焼】‥キウ‥
①天正(1573〜1592)年間、利休が信楽しがらきなどの茶器を選択して愛玩したもの。利休名物。
②醤油たれの中に白胡麻を加え、魚などに塗って焼いた料理。利休に因んだ料理であるが、「休」を忌み字として「久」と書くこともある。
⇒りきゅう【利休】
リキュール【liqueur フランス】
混成酒の一種。醸造酒・蒸留酒・アルコールに果実・香草・甘味料・香料などを加えて造る。ペパーミント・アブサン・キュラソーなど。
⇒リキュール‐グラス【liqueur glass】
リキュール‐グラス【liqueur glass】
リキュール用の、小型で脚付きのグラス。→グラス(図)
⇒リキュール【liqueur フランス】
り‐きょ【離居】
はなれて住むこと。
り‐ぎょ【李漁】
中国、明末・清初の戯曲作者・小説家。号は笠翁。浙江の人。戯曲「笠翁十種曲」、小説「十二楼」「無声戯」の他「笠翁一家言」「閑情偶寄」など。(1611〜1680)
り‐ぎょ【鯉魚】
コイのこと。
り‐きょう【李喬】‥ケウ
(Li Qiao)台湾の作家。台湾苗栗生れの客家ハッカ人。台湾ペンクラブ会長。総統府国策顧問。作「寒夜」。(1934〜)
り‐きょう【離京】‥キヤウ
みやこを離れること。特に、東京あるいは京都を離れること。
り‐きょう【離郷】‥キヤウ
郷里を離れること。
りき‐りつ【力率】
〔電〕交流の電圧と電流との位相差の余弦。交流の電力は実効電圧・実効電流・力率の積に等しい。
りき‐りょう【力量】‥リヤウ
人の能力の大きさの度合。また、その大きいこと。日葡辞書「リキリャウナモノ」。「―が問われる」
⇒りきりょう‐けい【力量計】
⇒りきりょう‐もの【力量者】
りきりょう‐けい【力量計】‥リヤウ‥
筋肉の運動を反復または持続して、筋肉の仕事量を計算したり疲労の状況を調べたりするための装置。
⇒りき‐りょう【力量】
りきりょう‐もの【力量者】‥リヤウ‥
力量のある者。力の強い人。
⇒りき‐りょう【力量】
り‐きん【利金】
①利息の金。利子。好色二代男「―は然も八割の算用」
②もうけた金銭。
り‐ぎん【利銀】
(→)利金に同じ。好色一代女2「二割三割の―に出しあげ」
りきん‐ぜい【釐金税】
中国で、太平天国の乱以後施行した国内関税。各省内通過の商品に価格の100分の1を賦課。1931年廃止。
りく【陸】
①地表の水におおわれない部分。地球面積の約30パーセントで、岩石および土壌から構成される。くが。おか。
②陸奥国むつのくにの略。
→ろく(陸)
り‐く【離苦】
〔仏〕苦悩を離れること。
り‐く【離垢】
〔仏〕煩悩ぼんのうを離れること。
りく‐あげ【陸揚げ】
船舶の荷物を陸上に運び揚げること。荷あげ。河岸あげ。「漁獲物を―する」「―港」
⇒りくあげ‐さんばし【陸揚げ桟橋】
りくあげ‐さんばし【陸揚げ桟橋】
陸揚げのために特に設けた桟橋。
⇒りく‐あげ【陸揚げ】
りく‐い【陸尉】‥ヰ
陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸佐と准陸尉との間。
り‐ぐい【利食い】‥グヒ
(取引用語)相場の変動によって利益勘定となった買玉かいぎょくまたは売玉うりぎょくを、転売または買戻しをして利益を収得すること。
りく‐う【陸羽】
陸奥むつ国と出羽でわ国。奥羽地方。
⇒りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】
⇒りくう‐せん【陸羽線】
りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】‥ガウ
水稲粳うるちの育成品種。1921年(大正10)寺尾博(1883〜1961)が育成。昭和初期に多収・良質で冷害に強い品種として東北・北陸・関東などに普及。
⇒りく‐う【陸羽】
リグ‐ヴェーダ【Ṛg-veda 梵】
「ヴェーダ(吠陀)」参照。
りくう‐せん【陸羽線】
JR線の一つ。陸羽東線(小牛田こごた・新庄間)94.1キロメートル、陸羽西線(新庄・余目あまるめ間)43.0キロメートル、石巻線(小牛田・女川おながわ間)44.9キロメートルの総称で、東北地方を横断し、縦走する東北本線・奥羽本線・羽越本線を連絡する。
⇒りく‐う【陸羽】
リクール【Paul Ricoeur】
フランスの哲学者。人間を歴史的状況の不随意性と価値希求の随意性との緊張関係の中で自由を求める存在者としてとらえ、それに必要な言語を単なる記号変換ではなく、生ける隠喩とみなし、新しい解釈学的哲学を構想。晩年は記憶と忘却の視点から歴史を考察した。著「意志の哲学」「生ける隠喩」「時間と物語」など。(1913〜2005)
りく‐うん【陸運】
旅客・貨物の陸上運送。
りく‐えい【陸影】
遠い海上から見る陸地の姿。
リクエスト【request】
①要求。請求。注文。
②ラジオ・テレビなどで、聴視者から出す希望。「―曲」
りく‐えふ【六衛府】‥ヱ‥
⇒ろくえふ
りくえん‐たい【陸援隊】‥ヱン‥
幕末期の浪士隊。1867年(慶応3)中岡慎太郎が京都で組織、倒幕活動を行なった。68年親兵に編入。
りく‐おう‐がくは【陸王学派】‥ワウ‥
陸象山と王陽明との学に対する呼称。ともに心即理を標榜したことから、両者を一つの学派とみなしていう。現実にこういう学派があったわけではない。
りく‐か【六花】‥クワ
⇒りっか
りく‐か【六科】‥クワ
中国、唐初の科挙(官吏登用試験)の六つの科目。すなわち秀才・明経・進士・明法・明書・明算の総称。
りく‐か【陸賈】
中国、前漢初期の政治家。楚の人。高祖に仕え、南越王趙佗ちょうだを諭して漢に臣従させ、その功により太中大夫に任ぜられた。著「新語」12編。
りく‐かい【陸海】
①陸と海。
②陸軍と海軍。
⇒りくかい‐くう【陸海空】
りくかい‐くう【陸海空】
①陸と海と空。
②陸軍と海軍と空軍。「―合同演習」
⇒りく‐かい【陸海】
りく‐かぜ【陸風】
⇒りくふう
りく‐がっしゃく【六合釈】
サンスクリット語の名詞複合語の前分と後分との関係を解釈する6種の方法。中国・日本では、相違釈・依主釈えしゅしゃく・持業釈じごつしゃく・帯数釈・有財釈うざいしゃく・隣近釈りんごんしゃくを総称していう。六離合釈。
りく‐かん【六官】‥クワン
周代の六中央行政機関。すなわち天官・地官・春官・夏官・秋官・冬官の総称。→六卿りくけい
りく‐き【六気】
⇒ろっき
りく‐き【陸機】
中国、西晋の詩人。字は士衡。呉の名族の出身。呉の滅亡後、弟の陸雲(262〜303)と共に洛陽へ赴き、晋に仕えた。修辞に意を用いた華麗な詩風で、六朝修辞主義の路を開いた。陸雲と共に二陸と称される。著「陸士衡集」。(261〜303)
りく‐ぎ【六義】
①詩経大序にいう詩の6種の分類。すなわち賦・比・興・風・雅・頌。賦は感想そのままを述べたもの、比はたとえを採って感想を述べたもの、興は外物に触れて感想を述べたもの、風は民間に行われる歌謡、雅は朝廷でうたわれる雅正の詞藻、頌は宗廟頌徳の詞藻。
②紀貫之が詩の六義を転用して古今集序において述べた、和歌の6種の風体。そえ歌・かぞえ歌・なずらえ歌・たとえ歌・ただこと歌・いわい歌。転じて、和歌。「―の道」
③書道で、筆法・風情・字象・去病・骨目・感徳の6種の法。
④(→)六書りくしょ1に同じ。
りく‐ぎ【六儀】
①周代、祭祀さいし・賓客・朝廷・喪紀・軍旅・車馬の6事に関する儀式。
②転じて、ものの道理・筋道。浄瑠璃、今宮の心中「善悪ふたつをかみ分けて、―をただす柴崎に」
③唐代後宮の六つの女官名。淑儀など。
りく‐ぎ【六議】
律に規定された刑法上の特典を受くべき6種の資格。議親ぎしん・議故ぎこ・議賢ぎけん・議能ぎのう・議功ぎくう・議貴ぎきの総称。天皇の親族・縁故者、国家の賢者や能・功ある者、貴族などは裁判に際し律を機械的に適用されず、特に情状酌量され、また流罪以下ならば最初から一等減刑される。唐律の八議に由来。→八議
りくぎ‐えん【六義園】‥ヱン
東京都文京区本駒込にある回遊式庭園。元禄(1688〜1704)年間、柳沢吉保がその別邸に造った江戸時代の名園。
りく‐きゅう【六宮】
中国で、皇后のいる六つの宮殿。後宮。太平記39「―の美人」
りく‐きゅうえん【陸九淵】‥キウヱン
(→)陸象山りくしょうざんの別称。
りく‐ぐ【六具】
⇒ろくぐ
りく‐ぐん【六軍】
周代の兵制で、天子が統率した6個の軍の称。一軍は1万2500人、したがって総計7万5000人。六師りくし。
りく‐ぐん【陸軍】
陸上戦闘を任務とする軍備・軍隊。明治維新後の日本では天皇に直属し、海軍と協同して国防に任じた。1945年(昭和20)11月廃止。渡辺崋山、外国事情書「軍官は海陸相分け候得共、―尤も多く」
⇒りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】
⇒りくぐん‐きょう【陸軍卿】
⇒りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】
⇒りくぐん‐しょう【陸軍省】
⇒りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】
⇒りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】
⇒りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】
⇒りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】
⇒りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】
⇒りくぐん‐はじめ【陸軍始】
⇒りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】
⇒りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】
⇒りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】
りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】
1905年(明治38)の奉天大会戦の勝利を記念した3月10日。第二次大戦後廃止。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐きょう【陸軍卿】‥キヤウ
1885年(明治18)官制改革以前の陸軍省の長官。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】‥クワンガクカウ
陸軍の士官候補生および准士官・下士官を教育した学校。1874年(明治7)東京市ヶ谷に設置、敗戦時は神奈川県座間にあった。略称、陸士。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐しょう【陸軍省】‥シヤウ
もと内閣各省の一つ。陸軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→参謀本部。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】
江戸幕府の職名。幕府の陸軍を総轄した。1862年(文久2)設置。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】‥ザウ‥シヤウ
陸軍の兵器・弾薬・器具・材料などを製造・修理した所。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】‥ガクカウ
陸軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行う学校。東京赤坂にあった。略称、陸大。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】
旧陸軍省の長官。陸軍行政を管理し、陸軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては内閣を経て天皇を輔弼ほひつする責任を負ったが、軍機・軍令に関しては直接天皇に上奏・裁可を求める帷幄いあく上奏権が認められていた。陸相。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】‥ガクカウ
陸軍の秘密戦(情報収集・防諜・謀略など)の要員を養成するための学校。1938年(昭和13)に創設され、東京中野にあった。参謀総長直轄。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐はじめ【陸軍始】
旧日本陸軍で毎年1月8日の仕事始めの日に行なった観兵式などの儀式。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】
1934年(昭和9)に陸軍省新聞班が発表した小冊子「国防の本義と其の強化の提唱」の通称。総力戦を遂行できる「高度国防国家」の構築と軍備の急速な拡充を主張。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。歩兵・騎兵・砲兵を統括した。1862年(文久2)設置。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】‥エウ‥ガクカウ
陸軍将校を志願する少年に対して陸軍士官学校の予備教育を行う学校。東京・仙台・名古屋・大阪・広島・熊本にあった。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りく‐けい【六経】
中国における6種の経書。すなわち易経・書経・詩経・礼らい・楽経(佚書)・春秋の総称。六芸。六籍。
りく‐けい【六卿】
周代の六官りくかんの長。すなわち冢宰ちょうさい・司徒・宗伯・司馬・司寇・司空。
りく‐げい【六芸】
①周代に士以上が必ず学ぶべき科目と定められた6種の技芸。すなわち礼・楽・射・御・書・数。
②(→)六経りくけいに同じ。
りくけい‐とう【陸繋島】‥タウ
砂州によって陸地とつながった島。潮岬・函館山など。
りく‐けん【陸圏】
⇒りっけん
りく‐こ【陸弧】
大陸の縁辺につらなる山脈とそれに平行な海溝との組合せ。アンデス山脈とペルー‐チリ海溝との組が好例。地学的現象が弧状列島と同類であるため、島弧にならって名づけられた。
りく‐ごう【六合】‥ガフ
天地と四方。宇宙全体。謡曲、内外詣「日月は―を照らせども」
りくごう‐ざっし【六合雑誌】‥ガフ‥
1880年(明治13)キリスト教徒の小崎弘道・植村正久らが創刊した評論雑誌。政治・思想・社会問題などについて、キリスト教社会主義など進歩的立場から論じた。1921年(大正10)終刊。
りく‐こく【六国】
⇒りっこく
りく‐さ【陸佐】
陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸将補と陸尉との間。
りく‐さん【陸産】
陸産物の略。
⇒りくさん‐ぶつ【陸産物】
りくさん‐ぶつ【陸産物】
陸上に産する物。陸産。
⇒りく‐さん【陸産】
りく‐し【六師】
(→)六軍りくぐんに同じ。
りく‐し【陸士】
①陸軍士官学校の略称。
②陸上自衛官の最下位の階級。陸士長および一・二・三等がある。
りく‐じ【六事】
慈・倹・勤・慎・誠・明の六つの徳。
りく‐じ【陸自】
陸上自衛隊の略。
りく‐じ【陸路】‥ヂ
陸上の道。りくろ。〈日葡辞書〉
りく‐しゅうふ【陸秀夫】‥シウ‥
南宋末の忠臣。宰相。字は君実。張世傑とともに広東厓山で元軍と最後の戦闘をして敗れ、幼君衛王昺へいを抱いて入水。(1236〜1279)
りく‐しゅつ【六出】
(雪の結晶を花に見立て、6弁があるとして)雪の異称。六花。むつのはな。
⇒りくしゅつ‐か【六出花】
りくしゅつ‐か【六出花】‥クワ
(→)六出に同じ。
⇒りく‐しゅつ【六出】
りく‐しょ【六書】
①漢字の字形の構成および用法に関する6種の原則。象形しょうけい・指事・会意・形声・転注・仮借かしゃ。
②(→)六体りくたい1に同じ。
りく‐しょう【陸相】‥シヤウ
陸軍大臣の略称。
りく‐しょう【陸将】‥シヤウ
①陸軍の将官。
②陸上自衛官の最高位の階級。陸佐との間に陸将補がある。
りく‐じょう【陸上】‥ジヤウ
①陸地の上。
②陸上競技の略。
⇒りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】
⇒りくじょう‐き【陸上機】
⇒りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】
⇒りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】
⇒りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】
りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】‥ジヤウ‥
(→)運送保険に同じ。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくじょう‐き【陸上機】‥ジヤウ‥
車輪・スキーなどにより地上を滑走して離着陸を行う飛行機の総称。陸上飛行機。↔水上機。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】‥ジヤウキヤウ‥
トラック1・フィールドおよび道路などで行われる歩・走・跳・投の競技。→トラック競技→フィールド競技。
⇒りく‐じょう【陸上】
りく‐しょうざん【陸象山】‥シヤウ‥
南宋の大儒。名は九淵。字は子静。象山・存斎と号。江西金渓の人。程顥ていこうの哲学を発展させて、心即理を主張、朱熹の主知的哲学に対抗。文安と諡おくりなす。(1139〜1192)
りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥
自衛隊の一つ。5個の方面隊および防衛大臣直轄部隊から成る。陸上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。保安隊の後身として1954年(昭和29)設置。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくしょう‐じっきく【六菖十菊】‥シヤウ‥
「六日むいかの菖蒲あやめ、十日の菊」に同じ。→六日(成句)
りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】‥ジヤウ‥
緑藻類から進化して、陸上に生育するようになった一群の植物の総称。コケ植物・シダ植物・種子植物をいう。陸生植物。
⇒りく‐じょう【陸上】
りく‐しん【六親】
父・母・兄・弟・妻・子の総称。また、父・子・兄・弟・夫・婦の総称。ろくしん。平家物語2「―を皆罪せらる」
りく・す【戮す】
〔他サ変〕
①罪ある者を殺す。
②(力を)合わせる。
りく‐ず【陸図】‥ヅ
(→)地形図に同じ。
りく‐すい【陸水】
(内陸にある水域の意)地球上に分布する水のうち、海水を除いたものの総称。湖沼・河川・地下水・温泉・雪氷など。
⇒りくすい‐がく【陸水学】
りくすい‐がく【陸水学】
(昭和初期の造語)陸水の物理的・化学的・生物学的研究を行う学問。淡水漁業・稚魚養殖・水道事業・工場用水および排水などに寄与する。→水文学すいもんがく
⇒りく‐すい【陸水】
りく‐せい【陸生・陸棲】
陸地に生ずること。また、陸地で生活すること。↔水生。
⇒りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】
⇒りくせい‐どうぶつ【陸生動物】
りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】
陸地に生育する植物。系統分類上は陸上植物とは異なる。↔水生植物。
⇒りく‐せい【陸生・陸棲】
りくせい‐そう【陸成層】
湖沼・河川または風の作用によって陸上に堆積・生成した地層。淡水成層・風成層など。
りくせい‐どうぶつ【陸生動物】
陸地に生活する動物の総称。陸上生活に適応して、空気呼吸、卵や子の保護、体の保持・運動などの機構を備える。
⇒りく‐せい【陸生・陸棲】
りく‐せき【六籍】
(→)六経りくけいに同じ。
りく‐せん【陸戦】
陸上の戦闘。
⇒りくせん‐たい【陸戦隊】
りくぜん【陸前】
旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。大部分は今の宮城県、一部は岩手県に属する。
⇒りくぜん‐たかた【陸前高田】
⇒りくぜん‐はまかいどう【陸前浜街道】
りくせん‐たい【陸戦隊】
海軍陸戦隊の略称。
⇒りく‐せん【陸戦】
りくぜん‐たかた【陸前高田】
岩手県南東部、広田湾に臨む市。遠洋漁業の基地。湾内ではホタテガイ・ワカメなどの養殖も盛ん。人口2万5千。
⇒りくぜん【陸前】
りくぜん‐はまかいどう【陸前浜街道】‥ダウ
(→)浜街道2に同じ。
⇒りくぜん【陸前】
りく‐そう【陸送】
①陸上の輸送。「―のトラック」
②未登録車両を運転して輸送すること。
りく‐そう【陸曹】‥サウ
陸上自衛官の階級の一つ。陸曹長および一・二・三等がある。准陸尉と陸士との間。
りく‐ぞく【陸続】
ひっきりなしに続くさま。「避難民が―とやって来る」
りく‐たい【六体】
①漢字の6種の書体、すなわち大篆だいてん・小篆・八分はっぷん・隷書・行書・草書。また、古文・奇字・篆書・隷書・繆篆びゅうてん・虫書の総称。
②(→)六書1に同じ。
③書経の6種の文体、すなわち典・謨・誓・命・訓・誥の称。
りく‐だな【陸棚】
(→)大陸棚に同じ。
りく‐たんび【陸探微】
宋2の画家。呉(江蘇省)の人。一筆画による人物画に長じる。顧愷之こがいし・張僧繇ちょうそうようとともに六朝三大家の一人。生没年未詳。
りく‐ち【陸地】
地球表面の、水におおわれない所。ろくち。→陸。
⇒りくち‐そくりょう‐ひょう【陸地測量標】
⇒りくち‐めん【陸地綿・陸地棉】
りく‐ちく【六畜】
六つの家畜、すなわち牛・馬・羊・犬・鶏・豚の総称。ろくちく。
りくち‐そくりょう‐ひょう【陸地測量標】‥リヤウヘウ
陸地測量のために設置した標識。三角点標石・水準点標石・測標・標杭・測旗・仮杭の6種。
⇒りく‐ち【陸地】
りくち‐めん【陸地綿・陸地棉】
ワタの一種。中米の原産とされ、アメリカ合衆国を中心に世界のワタの栽培面積の7割を占める。海島綿かいとうめんに対していう。→わた
⇒りく‐ち【陸地】
りくちゅう【陸中】
旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。大部分は今の岩手県、一部は秋田県に属する。
⇒りくちゅうかいがん‐こくりつこうえん【陸中海岸国立公園】
りくちゅうかいがん‐こくりつこうえん【陸中海岸国立公園】‥ヱン
岩手県東部の典型的リアス海岸地帯の国立公園。壮大な海食崖、深く入りこんだ湾・入江などが多く、ウミツバメの繁殖地日出島、ウミネコで知られる佐賀部さかべかもめ島、崎山の潮吹穴、八戸穴などの奇景も少なくない。
⇒りくちゅう【陸中】
りく‐ちょう【六朝】‥テウ
①中国で、後漢滅亡から隋の統一まで建業・建康(南京)に都した、呉・東晋・宋・斉・梁・陳の6王朝の総称。
②六朝時代に行われた書風。
⇒りくちょう‐みんか【六朝民歌】
りくちょう‐みんか【六朝民歌】‥テウ‥
中国六朝時代の半ば頃に南北でそれぞれ勃興した民歌。南朝楽府がふ・北朝楽府と呼ばれる。
⇒りく‐ちょう【六朝】
り‐くつ【理屈・理窟】
(理のつまる所の意)
①物事のすじみち。道理。ことわり。「―に合う」「―ではわかっている」
②こじつけの理由。現実を無視した条理。また、それを言い張ること。「―をこねる」「―を付ける」
③色事。情事。黄表紙、御存商売物「青本は妹柱かくしと一枚絵が―を知り」
④やりくり。金の工面。また、心づもり。手はず。花暦八笑人「そこで今夜下見分をしようといふ―だ」
⇒りくつ‐ぜめ【理屈責め】
⇒りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
⇒りくつ‐づめ【理屈詰め】
⇒りくつ‐ぬき【理屈抜き】
⇒りくつ‐や【理屈屋】
⇒理屈と膏薬はどこへでも付く
りくつ‐ぜめ【理屈責め】
理屈一方で人を責めなじること。理責め。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りく‐つづき【陸続き】
二つの地が海などに隔てられず、陸地でつながっていること。地続き。
りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
〔形〕
何事についてもすぐに理屈を言い出しがちである。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐づめ【理屈詰め】
理屈を言い立てること。理詰め。好色一代女1「―なるつめひらき、少し勿体もつけ」
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りきゅう‐やき【利休焼】‥キウ‥
①天正(1573〜1592)年間、利休が信楽しがらきなどの茶器を選択して愛玩したもの。利休名物。
②醤油たれの中に白胡麻を加え、魚などに塗って焼いた料理。利休に因んだ料理であるが、「休」を忌み字として「久」と書くこともある。
⇒りきゅう【利休】
リキュール【liqueur フランス】
混成酒の一種。醸造酒・蒸留酒・アルコールに果実・香草・甘味料・香料などを加えて造る。ペパーミント・アブサン・キュラソーなど。
⇒リキュール‐グラス【liqueur glass】
リキュール‐グラス【liqueur glass】
リキュール用の、小型で脚付きのグラス。→グラス(図)
⇒リキュール【liqueur フランス】
り‐きょ【離居】
はなれて住むこと。
り‐ぎょ【李漁】
中国、明末・清初の戯曲作者・小説家。号は笠翁。浙江の人。戯曲「笠翁十種曲」、小説「十二楼」「無声戯」の他「笠翁一家言」「閑情偶寄」など。(1611〜1680)
り‐ぎょ【鯉魚】
コイのこと。
り‐きょう【李喬】‥ケウ
(Li Qiao)台湾の作家。台湾苗栗生れの客家ハッカ人。台湾ペンクラブ会長。総統府国策顧問。作「寒夜」。(1934〜)
り‐きょう【離京】‥キヤウ
みやこを離れること。特に、東京あるいは京都を離れること。
り‐きょう【離郷】‥キヤウ
郷里を離れること。
りき‐りつ【力率】
〔電〕交流の電圧と電流との位相差の余弦。交流の電力は実効電圧・実効電流・力率の積に等しい。
りき‐りょう【力量】‥リヤウ
人の能力の大きさの度合。また、その大きいこと。日葡辞書「リキリャウナモノ」。「―が問われる」
⇒りきりょう‐けい【力量計】
⇒りきりょう‐もの【力量者】
りきりょう‐けい【力量計】‥リヤウ‥
筋肉の運動を反復または持続して、筋肉の仕事量を計算したり疲労の状況を調べたりするための装置。
⇒りき‐りょう【力量】
りきりょう‐もの【力量者】‥リヤウ‥
力量のある者。力の強い人。
⇒りき‐りょう【力量】
り‐きん【利金】
①利息の金。利子。好色二代男「―は然も八割の算用」
②もうけた金銭。
り‐ぎん【利銀】
(→)利金に同じ。好色一代女2「二割三割の―に出しあげ」
りきん‐ぜい【釐金税】
中国で、太平天国の乱以後施行した国内関税。各省内通過の商品に価格の100分の1を賦課。1931年廃止。
りく【陸】
①地表の水におおわれない部分。地球面積の約30パーセントで、岩石および土壌から構成される。くが。おか。
②陸奥国むつのくにの略。
→ろく(陸)
り‐く【離苦】
〔仏〕苦悩を離れること。
り‐く【離垢】
〔仏〕煩悩ぼんのうを離れること。
りく‐あげ【陸揚げ】
船舶の荷物を陸上に運び揚げること。荷あげ。河岸あげ。「漁獲物を―する」「―港」
⇒りくあげ‐さんばし【陸揚げ桟橋】
りくあげ‐さんばし【陸揚げ桟橋】
陸揚げのために特に設けた桟橋。
⇒りく‐あげ【陸揚げ】
りく‐い【陸尉】‥ヰ
陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸佐と准陸尉との間。
り‐ぐい【利食い】‥グヒ
(取引用語)相場の変動によって利益勘定となった買玉かいぎょくまたは売玉うりぎょくを、転売または買戻しをして利益を収得すること。
りく‐う【陸羽】
陸奥むつ国と出羽でわ国。奥羽地方。
⇒りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】
⇒りくう‐せん【陸羽線】
りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】‥ガウ
水稲粳うるちの育成品種。1921年(大正10)寺尾博(1883〜1961)が育成。昭和初期に多収・良質で冷害に強い品種として東北・北陸・関東などに普及。
⇒りく‐う【陸羽】
リグ‐ヴェーダ【Ṛg-veda 梵】
「ヴェーダ(吠陀)」参照。
りくう‐せん【陸羽線】
JR線の一つ。陸羽東線(小牛田こごた・新庄間)94.1キロメートル、陸羽西線(新庄・余目あまるめ間)43.0キロメートル、石巻線(小牛田・女川おながわ間)44.9キロメートルの総称で、東北地方を横断し、縦走する東北本線・奥羽本線・羽越本線を連絡する。
⇒りく‐う【陸羽】
リクール【Paul Ricoeur】
フランスの哲学者。人間を歴史的状況の不随意性と価値希求の随意性との緊張関係の中で自由を求める存在者としてとらえ、それに必要な言語を単なる記号変換ではなく、生ける隠喩とみなし、新しい解釈学的哲学を構想。晩年は記憶と忘却の視点から歴史を考察した。著「意志の哲学」「生ける隠喩」「時間と物語」など。(1913〜2005)
りく‐うん【陸運】
旅客・貨物の陸上運送。
りく‐えい【陸影】
遠い海上から見る陸地の姿。
リクエスト【request】
①要求。請求。注文。
②ラジオ・テレビなどで、聴視者から出す希望。「―曲」
りく‐えふ【六衛府】‥ヱ‥
⇒ろくえふ
りくえん‐たい【陸援隊】‥ヱン‥
幕末期の浪士隊。1867年(慶応3)中岡慎太郎が京都で組織、倒幕活動を行なった。68年親兵に編入。
りく‐おう‐がくは【陸王学派】‥ワウ‥
陸象山と王陽明との学に対する呼称。ともに心即理を標榜したことから、両者を一つの学派とみなしていう。現実にこういう学派があったわけではない。
りく‐か【六花】‥クワ
⇒りっか
りく‐か【六科】‥クワ
中国、唐初の科挙(官吏登用試験)の六つの科目。すなわち秀才・明経・進士・明法・明書・明算の総称。
りく‐か【陸賈】
中国、前漢初期の政治家。楚の人。高祖に仕え、南越王趙佗ちょうだを諭して漢に臣従させ、その功により太中大夫に任ぜられた。著「新語」12編。
りく‐かい【陸海】
①陸と海。
②陸軍と海軍。
⇒りくかい‐くう【陸海空】
りくかい‐くう【陸海空】
①陸と海と空。
②陸軍と海軍と空軍。「―合同演習」
⇒りく‐かい【陸海】
りく‐かぜ【陸風】
⇒りくふう
りく‐がっしゃく【六合釈】
サンスクリット語の名詞複合語の前分と後分との関係を解釈する6種の方法。中国・日本では、相違釈・依主釈えしゅしゃく・持業釈じごつしゃく・帯数釈・有財釈うざいしゃく・隣近釈りんごんしゃくを総称していう。六離合釈。
りく‐かん【六官】‥クワン
周代の六中央行政機関。すなわち天官・地官・春官・夏官・秋官・冬官の総称。→六卿りくけい
りく‐き【六気】
⇒ろっき
りく‐き【陸機】
中国、西晋の詩人。字は士衡。呉の名族の出身。呉の滅亡後、弟の陸雲(262〜303)と共に洛陽へ赴き、晋に仕えた。修辞に意を用いた華麗な詩風で、六朝修辞主義の路を開いた。陸雲と共に二陸と称される。著「陸士衡集」。(261〜303)
りく‐ぎ【六義】
①詩経大序にいう詩の6種の分類。すなわち賦・比・興・風・雅・頌。賦は感想そのままを述べたもの、比はたとえを採って感想を述べたもの、興は外物に触れて感想を述べたもの、風は民間に行われる歌謡、雅は朝廷でうたわれる雅正の詞藻、頌は宗廟頌徳の詞藻。
②紀貫之が詩の六義を転用して古今集序において述べた、和歌の6種の風体。そえ歌・かぞえ歌・なずらえ歌・たとえ歌・ただこと歌・いわい歌。転じて、和歌。「―の道」
③書道で、筆法・風情・字象・去病・骨目・感徳の6種の法。
④(→)六書りくしょ1に同じ。
りく‐ぎ【六儀】
①周代、祭祀さいし・賓客・朝廷・喪紀・軍旅・車馬の6事に関する儀式。
②転じて、ものの道理・筋道。浄瑠璃、今宮の心中「善悪ふたつをかみ分けて、―をただす柴崎に」
③唐代後宮の六つの女官名。淑儀など。
りく‐ぎ【六議】
律に規定された刑法上の特典を受くべき6種の資格。議親ぎしん・議故ぎこ・議賢ぎけん・議能ぎのう・議功ぎくう・議貴ぎきの総称。天皇の親族・縁故者、国家の賢者や能・功ある者、貴族などは裁判に際し律を機械的に適用されず、特に情状酌量され、また流罪以下ならば最初から一等減刑される。唐律の八議に由来。→八議
りくぎ‐えん【六義園】‥ヱン
東京都文京区本駒込にある回遊式庭園。元禄(1688〜1704)年間、柳沢吉保がその別邸に造った江戸時代の名園。
りく‐きゅう【六宮】
中国で、皇后のいる六つの宮殿。後宮。太平記39「―の美人」
りく‐きゅうえん【陸九淵】‥キウヱン
(→)陸象山りくしょうざんの別称。
りく‐ぐ【六具】
⇒ろくぐ
りく‐ぐん【六軍】
周代の兵制で、天子が統率した6個の軍の称。一軍は1万2500人、したがって総計7万5000人。六師りくし。
りく‐ぐん【陸軍】
陸上戦闘を任務とする軍備・軍隊。明治維新後の日本では天皇に直属し、海軍と協同して国防に任じた。1945年(昭和20)11月廃止。渡辺崋山、外国事情書「軍官は海陸相分け候得共、―尤も多く」
⇒りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】
⇒りくぐん‐きょう【陸軍卿】
⇒りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】
⇒りくぐん‐しょう【陸軍省】
⇒りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】
⇒りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】
⇒りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】
⇒りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】
⇒りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】
⇒りくぐん‐はじめ【陸軍始】
⇒りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】
⇒りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】
⇒りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】
りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】
1905年(明治38)の奉天大会戦の勝利を記念した3月10日。第二次大戦後廃止。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐きょう【陸軍卿】‥キヤウ
1885年(明治18)官制改革以前の陸軍省の長官。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】‥クワンガクカウ
陸軍の士官候補生および准士官・下士官を教育した学校。1874年(明治7)東京市ヶ谷に設置、敗戦時は神奈川県座間にあった。略称、陸士。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐しょう【陸軍省】‥シヤウ
もと内閣各省の一つ。陸軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→参謀本部。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】
江戸幕府の職名。幕府の陸軍を総轄した。1862年(文久2)設置。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】‥ザウ‥シヤウ
陸軍の兵器・弾薬・器具・材料などを製造・修理した所。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】‥ガクカウ
陸軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行う学校。東京赤坂にあった。略称、陸大。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】
旧陸軍省の長官。陸軍行政を管理し、陸軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては内閣を経て天皇を輔弼ほひつする責任を負ったが、軍機・軍令に関しては直接天皇に上奏・裁可を求める帷幄いあく上奏権が認められていた。陸相。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】‥ガクカウ
陸軍の秘密戦(情報収集・防諜・謀略など)の要員を養成するための学校。1938年(昭和13)に創設され、東京中野にあった。参謀総長直轄。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐はじめ【陸軍始】
旧日本陸軍で毎年1月8日の仕事始めの日に行なった観兵式などの儀式。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】
1934年(昭和9)に陸軍省新聞班が発表した小冊子「国防の本義と其の強化の提唱」の通称。総力戦を遂行できる「高度国防国家」の構築と軍備の急速な拡充を主張。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。歩兵・騎兵・砲兵を統括した。1862年(文久2)設置。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】‥エウ‥ガクカウ
陸軍将校を志願する少年に対して陸軍士官学校の予備教育を行う学校。東京・仙台・名古屋・大阪・広島・熊本にあった。
⇒りく‐ぐん【陸軍】
りく‐けい【六経】
中国における6種の経書。すなわち易経・書経・詩経・礼らい・楽経(佚書)・春秋の総称。六芸。六籍。
りく‐けい【六卿】
周代の六官りくかんの長。すなわち冢宰ちょうさい・司徒・宗伯・司馬・司寇・司空。
りく‐げい【六芸】
①周代に士以上が必ず学ぶべき科目と定められた6種の技芸。すなわち礼・楽・射・御・書・数。
②(→)六経りくけいに同じ。
りくけい‐とう【陸繋島】‥タウ
砂州によって陸地とつながった島。潮岬・函館山など。
りく‐けん【陸圏】
⇒りっけん
りく‐こ【陸弧】
大陸の縁辺につらなる山脈とそれに平行な海溝との組合せ。アンデス山脈とペルー‐チリ海溝との組が好例。地学的現象が弧状列島と同類であるため、島弧にならって名づけられた。
りく‐ごう【六合】‥ガフ
天地と四方。宇宙全体。謡曲、内外詣「日月は―を照らせども」
りくごう‐ざっし【六合雑誌】‥ガフ‥
1880年(明治13)キリスト教徒の小崎弘道・植村正久らが創刊した評論雑誌。政治・思想・社会問題などについて、キリスト教社会主義など進歩的立場から論じた。1921年(大正10)終刊。
りく‐こく【六国】
⇒りっこく
りく‐さ【陸佐】
陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸将補と陸尉との間。
りく‐さん【陸産】
陸産物の略。
⇒りくさん‐ぶつ【陸産物】
りくさん‐ぶつ【陸産物】
陸上に産する物。陸産。
⇒りく‐さん【陸産】
りく‐し【六師】
(→)六軍りくぐんに同じ。
りく‐し【陸士】
①陸軍士官学校の略称。
②陸上自衛官の最下位の階級。陸士長および一・二・三等がある。
りく‐じ【六事】
慈・倹・勤・慎・誠・明の六つの徳。
りく‐じ【陸自】
陸上自衛隊の略。
りく‐じ【陸路】‥ヂ
陸上の道。りくろ。〈日葡辞書〉
りく‐しゅうふ【陸秀夫】‥シウ‥
南宋末の忠臣。宰相。字は君実。張世傑とともに広東厓山で元軍と最後の戦闘をして敗れ、幼君衛王昺へいを抱いて入水。(1236〜1279)
りく‐しゅつ【六出】
(雪の結晶を花に見立て、6弁があるとして)雪の異称。六花。むつのはな。
⇒りくしゅつ‐か【六出花】
りくしゅつ‐か【六出花】‥クワ
(→)六出に同じ。
⇒りく‐しゅつ【六出】
りく‐しょ【六書】
①漢字の字形の構成および用法に関する6種の原則。象形しょうけい・指事・会意・形声・転注・仮借かしゃ。
②(→)六体りくたい1に同じ。
りく‐しょう【陸相】‥シヤウ
陸軍大臣の略称。
りく‐しょう【陸将】‥シヤウ
①陸軍の将官。
②陸上自衛官の最高位の階級。陸佐との間に陸将補がある。
りく‐じょう【陸上】‥ジヤウ
①陸地の上。
②陸上競技の略。
⇒りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】
⇒りくじょう‐き【陸上機】
⇒りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】
⇒りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】
⇒りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】
りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】‥ジヤウ‥
(→)運送保険に同じ。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくじょう‐き【陸上機】‥ジヤウ‥
車輪・スキーなどにより地上を滑走して離着陸を行う飛行機の総称。陸上飛行機。↔水上機。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】‥ジヤウキヤウ‥
トラック1・フィールドおよび道路などで行われる歩・走・跳・投の競技。→トラック競技→フィールド競技。
⇒りく‐じょう【陸上】
りく‐しょうざん【陸象山】‥シヤウ‥
南宋の大儒。名は九淵。字は子静。象山・存斎と号。江西金渓の人。程顥ていこうの哲学を発展させて、心即理を主張、朱熹の主知的哲学に対抗。文安と諡おくりなす。(1139〜1192)
りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥
自衛隊の一つ。5個の方面隊および防衛大臣直轄部隊から成る。陸上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。保安隊の後身として1954年(昭和29)設置。
⇒りく‐じょう【陸上】
りくしょう‐じっきく【六菖十菊】‥シヤウ‥
「六日むいかの菖蒲あやめ、十日の菊」に同じ。→六日(成句)
りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】‥ジヤウ‥
緑藻類から進化して、陸上に生育するようになった一群の植物の総称。コケ植物・シダ植物・種子植物をいう。陸生植物。
⇒りく‐じょう【陸上】
りく‐しん【六親】
父・母・兄・弟・妻・子の総称。また、父・子・兄・弟・夫・婦の総称。ろくしん。平家物語2「―を皆罪せらる」
りく・す【戮す】
〔他サ変〕
①罪ある者を殺す。
②(力を)合わせる。
りく‐ず【陸図】‥ヅ
(→)地形図に同じ。
りく‐すい【陸水】
(内陸にある水域の意)地球上に分布する水のうち、海水を除いたものの総称。湖沼・河川・地下水・温泉・雪氷など。
⇒りくすい‐がく【陸水学】
りくすい‐がく【陸水学】
(昭和初期の造語)陸水の物理的・化学的・生物学的研究を行う学問。淡水漁業・稚魚養殖・水道事業・工場用水および排水などに寄与する。→水文学すいもんがく
⇒りく‐すい【陸水】
りく‐せい【陸生・陸棲】
陸地に生ずること。また、陸地で生活すること。↔水生。
⇒りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】
⇒りくせい‐どうぶつ【陸生動物】
りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】
陸地に生育する植物。系統分類上は陸上植物とは異なる。↔水生植物。
⇒りく‐せい【陸生・陸棲】
りくせい‐そう【陸成層】
湖沼・河川または風の作用によって陸上に堆積・生成した地層。淡水成層・風成層など。
りくせい‐どうぶつ【陸生動物】
陸地に生活する動物の総称。陸上生活に適応して、空気呼吸、卵や子の保護、体の保持・運動などの機構を備える。
⇒りく‐せい【陸生・陸棲】
りく‐せき【六籍】
(→)六経りくけいに同じ。
りく‐せん【陸戦】
陸上の戦闘。
⇒りくせん‐たい【陸戦隊】
りくぜん【陸前】
旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。大部分は今の宮城県、一部は岩手県に属する。
⇒りくぜん‐たかた【陸前高田】
⇒りくぜん‐はまかいどう【陸前浜街道】
りくせん‐たい【陸戦隊】
海軍陸戦隊の略称。
⇒りく‐せん【陸戦】
りくぜん‐たかた【陸前高田】
岩手県南東部、広田湾に臨む市。遠洋漁業の基地。湾内ではホタテガイ・ワカメなどの養殖も盛ん。人口2万5千。
⇒りくぜん【陸前】
りくぜん‐はまかいどう【陸前浜街道】‥ダウ
(→)浜街道2に同じ。
⇒りくぜん【陸前】
りく‐そう【陸送】
①陸上の輸送。「―のトラック」
②未登録車両を運転して輸送すること。
りく‐そう【陸曹】‥サウ
陸上自衛官の階級の一つ。陸曹長および一・二・三等がある。准陸尉と陸士との間。
りく‐ぞく【陸続】
ひっきりなしに続くさま。「避難民が―とやって来る」
りく‐たい【六体】
①漢字の6種の書体、すなわち大篆だいてん・小篆・八分はっぷん・隷書・行書・草書。また、古文・奇字・篆書・隷書・繆篆びゅうてん・虫書の総称。
②(→)六書1に同じ。
③書経の6種の文体、すなわち典・謨・誓・命・訓・誥の称。
りく‐だな【陸棚】
(→)大陸棚に同じ。
りく‐たんび【陸探微】
宋2の画家。呉(江蘇省)の人。一筆画による人物画に長じる。顧愷之こがいし・張僧繇ちょうそうようとともに六朝三大家の一人。生没年未詳。
りく‐ち【陸地】
地球表面の、水におおわれない所。ろくち。→陸。
⇒りくち‐そくりょう‐ひょう【陸地測量標】
⇒りくち‐めん【陸地綿・陸地棉】
りく‐ちく【六畜】
六つの家畜、すなわち牛・馬・羊・犬・鶏・豚の総称。ろくちく。
りくち‐そくりょう‐ひょう【陸地測量標】‥リヤウヘウ
陸地測量のために設置した標識。三角点標石・水準点標石・測標・標杭・測旗・仮杭の6種。
⇒りく‐ち【陸地】
りくち‐めん【陸地綿・陸地棉】
ワタの一種。中米の原産とされ、アメリカ合衆国を中心に世界のワタの栽培面積の7割を占める。海島綿かいとうめんに対していう。→わた
⇒りく‐ち【陸地】
りくちゅう【陸中】
旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。大部分は今の岩手県、一部は秋田県に属する。
⇒りくちゅうかいがん‐こくりつこうえん【陸中海岸国立公園】
りくちゅうかいがん‐こくりつこうえん【陸中海岸国立公園】‥ヱン
岩手県東部の典型的リアス海岸地帯の国立公園。壮大な海食崖、深く入りこんだ湾・入江などが多く、ウミツバメの繁殖地日出島、ウミネコで知られる佐賀部さかべかもめ島、崎山の潮吹穴、八戸穴などの奇景も少なくない。
⇒りくちゅう【陸中】
りく‐ちょう【六朝】‥テウ
①中国で、後漢滅亡から隋の統一まで建業・建康(南京)に都した、呉・東晋・宋・斉・梁・陳の6王朝の総称。
②六朝時代に行われた書風。
⇒りくちょう‐みんか【六朝民歌】
りくちょう‐みんか【六朝民歌】‥テウ‥
中国六朝時代の半ば頃に南北でそれぞれ勃興した民歌。南朝楽府がふ・北朝楽府と呼ばれる。
⇒りく‐ちょう【六朝】
り‐くつ【理屈・理窟】
(理のつまる所の意)
①物事のすじみち。道理。ことわり。「―に合う」「―ではわかっている」
②こじつけの理由。現実を無視した条理。また、それを言い張ること。「―をこねる」「―を付ける」
③色事。情事。黄表紙、御存商売物「青本は妹柱かくしと一枚絵が―を知り」
④やりくり。金の工面。また、心づもり。手はず。花暦八笑人「そこで今夜下見分をしようといふ―だ」
⇒りくつ‐ぜめ【理屈責め】
⇒りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
⇒りくつ‐づめ【理屈詰め】
⇒りくつ‐ぬき【理屈抜き】
⇒りくつ‐や【理屈屋】
⇒理屈と膏薬はどこへでも付く
りくつ‐ぜめ【理屈責め】
理屈一方で人を責めなじること。理責め。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りく‐つづき【陸続き】
二つの地が海などに隔てられず、陸地でつながっていること。地続き。
りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
〔形〕
何事についてもすぐに理屈を言い出しがちである。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐づめ【理屈詰め】
理屈を言い立てること。理詰め。好色一代女1「―なるつめひらき、少し勿体もつけ」
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
り‐ぎ【理義】🔗⭐🔉
り‐ぎ【理義】
道理と正義。
りき‐せつ【理気説】🔗⭐🔉
りき‐せつ【理気説】
太極・気・陰陽などの伝統的な概念を改めて体系化した朱子学の宇宙論。朱熹しゅきの説は、万物の生成を気の陰陽の働きによるとしながら、一方その働きの根拠に太極としての理があるとした。そのためこの説は理気二元論と見られ、明代に入ると、理を気の条理とする羅欽順らきんじゅんらの一元論が現れる。
りき‐にげんろん【理気二元論】🔗⭐🔉
りき‐にげんろん【理気二元論】
「理気説」参照。
り‐くつ【理屈・理窟】🔗⭐🔉
り‐くつ【理屈・理窟】
(理のつまる所の意)
①物事のすじみち。道理。ことわり。「―に合う」「―ではわかっている」
②こじつけの理由。現実を無視した条理。また、それを言い張ること。「―をこねる」「―を付ける」
③色事。情事。黄表紙、御存商売物「青本は妹柱かくしと一枚絵が―を知り」
④やりくり。金の工面。また、心づもり。手はず。花暦八笑人「そこで今夜下見分をしようといふ―だ」
⇒りくつ‐ぜめ【理屈責め】
⇒りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
⇒りくつ‐づめ【理屈詰め】
⇒りくつ‐ぬき【理屈抜き】
⇒りくつ‐や【理屈屋】
⇒理屈と膏薬はどこへでも付く
りくつ‐ぜめ【理屈責め】🔗⭐🔉
りくつ‐ぜめ【理屈責め】
理屈一方で人を責めなじること。理責め。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】🔗⭐🔉
りくつ‐っぽ・い【理屈っぽい】
〔形〕
何事についてもすぐに理屈を言い出しがちである。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐づめ【理屈詰め】🔗⭐🔉
りくつ‐づめ【理屈詰め】
理屈を言い立てること。理詰め。好色一代女1「―なるつめひらき、少し勿体もつけ」
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
○理屈と膏薬はどこへでも付くりくつとこうやくはどこへでもつく
理屈は、つけようと思えばどんなことにでもつけることができる。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
○理屈と膏薬はどこへでも付くりくつとこうやくはどこへでもつく🔗⭐🔉
○理屈と膏薬はどこへでも付くりくつとこうやくはどこへでもつく
理屈は、つけようと思えばどんなことにでもつけることができる。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐ぬき【理屈抜き】
わざわざ理屈を述べ立てる必要のないこと。「―のおもしろさ」
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐や【理屈屋】
理屈っぽい人。理屈をすぐ言い立てる癖のある人。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りく‐てん【六典】
①中国周代の、国を治める6種の法典。治典・教典・礼典・政典・刑典・事典の総称で、それぞれが六官に対応。
②(→)唐六典とうりくてんに同じ。
りく‐でん【陸田】
①はたけ。↔水田。
②律令制で、雑穀を栽培する畑。
③もと畑であった所にポンプで水を揚げ、水田として水稲を栽培する農地。第二次大戦後、地下水を得やすい関東平野中南部で普及。
りく‐とう【六韜】‥タウ
周の太公望の撰と称する兵法書。文韜・武韜・竜韜・虎韜・豹韜・犬韜の6巻60編の総称。魏晋時代の偽作と考えられる。
⇒りくとう‐さんりゃく【六韜三略】
りく‐とう【陸島】‥タウ
(→)大陸島に同じ。
りく‐とう【陸稲】‥タウ
(→)「おかぼ」に同じ。
りく‐どう【六道】‥ダウ
⇒ろくどう
りくとう‐さんりゃく【六韜三略】‥タウ‥
①「六韜」と「三略」。「三略」は上略・中略・下略の3巻で、黄石公の撰と称せられるが、後代の偽作。ともに中国兵法の古典。
②兵法の極意。虎の巻。奥の手。
⇒りく‐とう【六韜】
りく‐とく【六徳】
6種の徳目。「周礼しゅらい」では知・仁・聖・義・忠・和、「小学」では礼・仁・信・義・勇・知。
りく‐なんぷう【陸軟風】
(→)陸風に同じ。↔海軟風
りくにょ【六如】
江戸中期の僧侶・漢詩人。法名、慈周。六如は号。近江の人。天台宗の学僧として仏学を学び、また宋詩を範にした新詩風をもたらした。著「六如庵詩鈔」「葛原詩話」など。(1734〜1801)
リグニン【lignin】
高等植物の導管・繊維などの細胞壁間に蓄積される高分子重合体。これによって細胞は木化し、硬くなる。製紙の際、セルロースを利用したあとの不要副産物。木質素。
りく‐の‐ことう【陸の孤島】‥タウ
交通の便がひどく悪い、周囲から隔絶した内陸の地方や場所。
りく‐はんきゅう【陸半球】‥キウ
地球の、陸地を多く含む半球。イギリス海峡を極とした北半球。全面積の47パーセントが陸地で、ユーラシア・アフリカおよびアメリカ大陸の大部分を含み、世界の陸地面積の約9割を含む。↔水半球すいはんきゅう
りく‐ぶ【六部】
(ロクブとも)中国の中央行政官庁。吏部・戸部・礼部・兵部・刑部・工部の総称。周の六官りくかんに基づき、初め隋・唐に設けられ、尚書省に隷属し、それぞれの政務を分担。元では中書省に属し、明初、天子に直属。清末に廃止。
りく‐ふう【陸封】
〔生〕遡河そか回遊魚のように生活史中に海水中の生活と淡水中の生活とを持つものが、地形の変化などによって淡水中に閉じこめられ、一生そこで生活するようになる現象。「―魚」
⇒りくふう‐しゅ【陸封種】
りく‐ふう【陸風】
陸から海へ向かって吹く風。夜間、陸地は海よりも早く冷えるために吹く。陸軟風。りくかぜ。↔海風
りくふう‐しゅ【陸封種】
陸封により生じた種。
⇒りく‐ふう【陸封】
りく‐ふく【六服】
中国で、王畿の外にあって各500里を1区とする六つの地域。九服のうち侯服・甸服でんぷく・男服・采服・衛服・蛮服を指す。→五服→九服
りく‐へい【陸兵】
①陸上の兵。
②陸軍の兵。
りく‐ほう【陸棚】‥ハウ
⇒りくだな
りく‐ほうおう【陸放翁】‥ハウヲウ
陸游りくゆうの別名。
りく‐む【六夢】
[周礼春官、占夢]六つの夢。正夢(安らかな夢)・噩夢がくむ(驚く夢)・思夢(思うことの夢)・寤夢ごむ(現実の夢)・喜夢(よろこぶ夢)・懼夢くむ(おそれる夢)をいう。
りく‐やね【陸屋根】
⇒ろくやね
りく‐ゆ【六諭】
明の太祖(洪武帝)が1397年、民衆教化の目的で発布した教訓。父母に孝順なれ、長上を恭敬せよ、郷里と和睦せよ、子孫を教訓せよ、おのおの生理(職業)に安んぜよ、非為をなすなかれ、の6カ条。
⇒りくゆ‐えんぎ【六諭衍義】
りく‐ゆう【陸游】‥イウ
南宋前期の詩人。字は務観、号は放翁。浙江山陰(紹興)の人。金に対する抗戦を唱え、当局者に嫌われて不遇の生涯を送る。詩は慷慨の気に満ちた愛国詩人の面と、農村の日常を愛する田園詩人の面とに特色を見る。范成大・楊万里・尤袤ゆうぼうとともに南宋四大家と称される。著「剣南詩稿」「渭南文集」「老学庵筆記」「入蜀記」など。(1125〜1209)
りくゆ‐えんぎ【六諭衍義】
清初の范鋐はんこうが「六諭」を解説した書。琉球から島津家へ伝わり、島津氏が8代将軍吉宗に献じ、1722年(享保7)室鳩巣むろきゅうそうが命を受けて「六諭衍義大意」を作る。
⇒りく‐ゆ【六諭】
リクライニング‐シート【reclining seat】
乗物などで背もたれの傾斜角度を変えられる座席。
りく‐り【陸離】
①光の分散するさま。光の入り乱れて美しいさま。「光彩―」
②入りまじって多く盛んなさま。
リグリア‐かい【リグリア海】
(Mare Ligure イタリア)イタリア北西部、ジェノヴァ湾とコルシカ島北岸とに囲まれた海域。
リクリエーション【recreation】
⇒レクリエーション
りくりく‐ぎょ【六六魚】
[続博物志2「鯉魚大小並三十六鱗」]鯉の異称。
りく‐りょう【陸梁】‥リヤウ
ほしいままなさま。おどりまわるさま。あれまわるさま。跳梁。
りく‐りょく【戮力】
力をあわせること。協力。
リクルート【recruit】
求人。人材募集。転じて、学生の就職運動。「―‐ファッション」
リクルート‐じけん【リクルート事件】
情報関連企業リクルート社が、政財官界に巨額の贈賄を行なった事件。1988年に表面化し、竹下内閣崩壊につながった。
リクルート社の捜査 1988年
提供:毎日新聞社
 りく‐れい【六礼】
①[礼記王制]士たるものの六つの大礼、すなわち冠・婚・喪・祭・郷・相見の総称。
②[儀礼士昏礼、疏]婚姻の6種の大礼、すなわち納采・問名・納吉・納徴・請期しょうき・親迎の総称。
りく‐ろ【陸路】
陸上のみち。また、陸上の交通機関を利用して行くこと。くがじ。→海路→空路
リグロイン【ligroin】
石油を蒸留して得られる液体。留出温度がセ氏70〜125度のもの。溶剤に使用。
り‐けい【理系】
理科の系統。理・工・農・医・薬などの学部を指す。↔文系
リケッチア【Rickettsia ラテン】
(最初に発見したアメリカの医学者H. T. Ricketts1871〜1910の名に因む)通常の細菌より小さく、ウイルスより大きい微生物。リケッチア目として細菌に分類される。グラム陰性の小型の球桿菌で、一部のものを除いては細胞内寄生性で、無細胞培地では増殖しない。発疹チフス・発疹熱・恙虫つつがむし病・Q熱・紅斑熱などの病原体。
リゲル【Rigel】
(足の意のアラビア語から)オリオン座のベータ(β)星。青白色の光度0.1等の星。オリオンの左足にある。
り‐けん【利剣】
①鋭利なつるぎ。
②煩悩ぼんのうを破りくだく仏智をたとえていう語。「弥陀の―」
り‐けん【利権】
利益を専有する権利。業者が公的機関などと結託して得る権益。「―がからむ」
⇒りけん‐や【利権屋】
り‐けん【理研】
理化学研究所の略称。
り‐けん【離見】
(世阿弥の用語)自己(演者)の目を離れて客観的に見ること。花鏡「見所より見る所の風姿は我が―也」
り‐げん【俚言】
①俗間のさとびたことば。
②共通語とは異なる、その地方特有のことば。土地のなまりことば。俗言。俚語。↔雅言
り‐げん【俚諺】
俗間のことわざ。民間で言いならわされてきたことわざ。
り‐げんこう【李元昊】‥カウ
西夏の初代皇帝。景宗。唐の夏州節度使の後裔。国を大夏と号し、宋・遼と対抗しながら国力の充実を図った。諡おくりなは武烈。(在位1038〜1048)(1003〜1048)
りげんしゅうらん【俚言集覧】‥シフ‥
国語辞書。26巻。太田全斎編、村田了阿ら補。「諺苑」を基礎にして江戸時代の方言・俗語・俗諺を集め、五十音図の横列順に配し、語釈を施したもの。1900年(明治33)井上頼圀よりくに・近藤瓶城みかきが増訂、通行の五十音順に改編。
りげん‐だいし【理源大師】
聖宝しょうぼうの諡号しごう。
りけん‐や【利権屋】
①利権をあさる人。
②特許的権利を得ようとする人のために、各種の仲介運動をして手数料を取る周旋屋。
⇒り‐けん【利権】
り‐こ【利子】
⇒りし。太平記8「頸を借りたる人―をつけて返すべし」
り‐こ【利己】
自分一人だけの利益を計ること。自利。主我。「―心」「―的」「―主義」↔利他
り‐ご【俚語】
(→)俚言りげん2に同じ。
り‐こう【李昂】‥カウ
(Li Ang)台湾の作家。本名、施淑端。両親とも本省人。フェミニズム文学「夫殺し」「迷いの園」「自伝の小説」など。(1952〜)
り‐こう【利口】
①たくみに言うこと。口さきのうまいこと。巧言。今昔物語集28「まことにわ君行きて―に云ひ聞せよ」
②頭がよいこと。かしこいこと。また、要領がよく抜け目がないこと。利巧。狂言、長光「さてさて―なやつちや。これはだまされまい」。「―な人」「―に立ちまわる」
③冗談じょうだんを言うこと。興言。古今著聞集16「それにも懲りず、なほ―し歩きけるほどに」
④(多く「お―」の形で)聞きわけのよいこと。「お―にしていなさい」
⇒りこう‐ぶ・る【利口ぶる】
り‐こう【利巧】‥カウ
(→)利口2に同じ。
り‐こう【里甲】‥カフ
明代の郷村統治機構。1381年制定。110戸を1里とし、そのうち10人を里長、他の100戸を甲首とし、毎年里長1人、甲首10人が服役して、租税の徴収・治安の維持などに当たった。
り‐こう【里堠】
(→)一里塚に同じ。
り‐こう【理工】
理学と工学。「―系」
り‐こう【犂耕】‥カウ
犂すきを用いた耕作、または農業。↔耨耕じょっこう
り‐こう【履行】‥カウ
①実際に行うこと。言葉どおりに実行すること。
②〔法〕債務者が債権の目的(内容)たる給付を実行すること。弁済と同義であるが、履行は債権の効力の面からいうのに対し、弁済は債権の消滅の面からいう。
⇒りこう‐ちたい【履行遅滞】
⇒りこう‐ふのう【履行不能】
り‐ごう【離合】‥ガフ
はなれたり集まったりすること。
⇒りごう‐し【離合詩】
⇒りごう‐しゅうさん【離合集散】
りごう‐し【離合詩】‥ガフ‥
漢詩の雑体詩の一種。字の偏へんや旁つくりを分けた文字を組み合わせて詩を作る文字遊び。例えば、「呂公釣磯盍口渭傍」で「呂」から「口」の字を離し、「九域有聖無土不王」で「域」から「土」の字を離して「或」とし、「口」と合わせて、「國」の字とするもの。
⇒り‐ごう【離合】
り‐こうじゅ【李光珠】‥クワウ‥
⇒イ=グヮンス
りごう‐しゅうさん【離合集散】‥ガフシフ‥
はなれたり集まったりすること。分離したり合併したりすること。「―を繰り返す」
⇒り‐ごう【離合】
り‐こうしょう【李鴻章】‥シヤウ
清末の政治家。字は少荃、号は儀叟。安徽合肥の人。曾国藩に従って太平天国の乱を平定。以来、日清戦争(下関条約)・義和団事件(北京議定書)などの外交に貢献するとともに軍隊の近代化、近代工業の育成、招商局の設立などにつとめた。直隷総督・北洋大臣・内閣大学士などを歴任。(1823〜1901)
りこう‐ちたい【履行遅滞】‥カウ‥
債務不履行の一類型。履行不能の場合を除き、債務者が履行期に債務を履行しないこと。債務者遅滞。
⇒り‐こう【履行】
りこう‐ふのう【履行不能】‥カウ‥
債務不履行の一類型。債務者の責めに帰すべき事由によって債務の履行が不可能となること。
⇒り‐こう【履行】
りこう‐ぶ・る【利口ぶる】
〔自五〕
利口らしくふるまう。
⇒り‐こう【利口】
り‐こうり【李広利】‥クワウ‥
前漢の将軍。武帝の寵妃李夫人の兄。大宛遠征を指揮した。( 〜前90)
り‐こうりん【李公麟】
北宋の画家。字は伯時。号は竜眠居士。安徽舒城の人。諸官を歴任後、竜眠山に隠棲。唐の呉道子流の白画を復活させた。(1049?〜1106)
リコーダー【recorder】
木管楽器。16〜18世紀、ヨーロッパで用いた縦笛。日本では、第二次大戦後、竹製・プラスチック製のものを主に初等教育用楽器として使用。ブロックフレーテ。
リゴーニ‐ステルン【Mario Rigoni Stern】
イタリアのネオレアリズモの作家。庶民・歴史・自然の3要素が融合した作風。作「雪の中の軍曹」「雷鳥の森」。(1921〜)
リコール【recall】
①国または地方自治体の公職者を国民または住民の意思によって罷免する制度。直接民主制の一つ。解職請求。「市長を―する」
②自動車などで、製品に欠陥がある場合、生産者が公表して、製品を回収し無料で修理すること。
り‐こくよう【李克用】
五代の後唐の実質的創始者。追号、太祖。突厥とっけつ沙陀部首長。父祖以来、唐に服属。振武節度使。黄巣の乱に唐を助け、河東節度使となる。朱全忠と政権を争って敗れ戦没したが、その子存勗そんきょくが後唐を建国。(856〜908)
りこ‐しゅぎ【利己主義】
(egoism)
①自己の利害だけを行為の規準とし、社会一般の利害を念頭に置かない考え方。主我主義。自己主義。↔利他主義。
②人間の利己心から出発して道徳の原理や観念を説明しようとする倫理学の立場。必ずしも1の意味での利己主義を主張するものではない。
りこ‐しん【利己心】
自己の利害だけを念頭に置いて、他人の迷惑を考えようとしない心。「―から出た振舞」
リコッタ【ricotta イタリア】
ホエーを加熱して作るイタリアのフレッシュ‐チーズ。料理や菓子によく使う。原料乳は牛・羊など様々で、塩を加えて熟成させたものもある。
りこ‐てき【利己的】
他人の迷惑を顧みず、自己の利益だけを追求するさま。「―な態度」
⇒りこてき‐いでんし【利己的遺伝子】
りこてき‐いでんし【利己的遺伝子】‥ヰ‥
(selfish genes)イギリスの動物行動学者ドーキンス(Richard Dawkins1941〜)による1976年の著書。「個体ではなく、遺伝子にとって有利な性質が進化する」という説を、遺伝子が利己的に振る舞っていると表現した語。
⇒りこ‐てき【利己的】
リコピン【lycopene】
分子式C40H50 カロテンの異性体。結晶性炭化水素。トマトなどの赤色色素で、優れた抗酸化作用がある。
リコリス【Licoris】
ヒガンバナ科ヒガンバナ属の球根植物数種の総称。園芸品種が多い。秋に花茎を伸ばし先端にヒガンバナに似た美花を多数放射状に咲かせる。広くはヒガンバナ属の属名。
リゴリスト【rigorist】
厳格な人。厳粛主義者。
リゴリズム【rigorism】
厳粛主義。厳格主義。
リゴレット【Rigoletto】
ヴェルディ作曲の歌劇。3幕。ユゴーの戯曲「王は楽しむ」(1832年作)に取材。1851年ヴェネツィアで初演。「女心の歌」で有名。
ヴェルディ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
りく‐れい【六礼】
①[礼記王制]士たるものの六つの大礼、すなわち冠・婚・喪・祭・郷・相見の総称。
②[儀礼士昏礼、疏]婚姻の6種の大礼、すなわち納采・問名・納吉・納徴・請期しょうき・親迎の総称。
りく‐ろ【陸路】
陸上のみち。また、陸上の交通機関を利用して行くこと。くがじ。→海路→空路
リグロイン【ligroin】
石油を蒸留して得られる液体。留出温度がセ氏70〜125度のもの。溶剤に使用。
り‐けい【理系】
理科の系統。理・工・農・医・薬などの学部を指す。↔文系
リケッチア【Rickettsia ラテン】
(最初に発見したアメリカの医学者H. T. Ricketts1871〜1910の名に因む)通常の細菌より小さく、ウイルスより大きい微生物。リケッチア目として細菌に分類される。グラム陰性の小型の球桿菌で、一部のものを除いては細胞内寄生性で、無細胞培地では増殖しない。発疹チフス・発疹熱・恙虫つつがむし病・Q熱・紅斑熱などの病原体。
リゲル【Rigel】
(足の意のアラビア語から)オリオン座のベータ(β)星。青白色の光度0.1等の星。オリオンの左足にある。
り‐けん【利剣】
①鋭利なつるぎ。
②煩悩ぼんのうを破りくだく仏智をたとえていう語。「弥陀の―」
り‐けん【利権】
利益を専有する権利。業者が公的機関などと結託して得る権益。「―がからむ」
⇒りけん‐や【利権屋】
り‐けん【理研】
理化学研究所の略称。
り‐けん【離見】
(世阿弥の用語)自己(演者)の目を離れて客観的に見ること。花鏡「見所より見る所の風姿は我が―也」
り‐げん【俚言】
①俗間のさとびたことば。
②共通語とは異なる、その地方特有のことば。土地のなまりことば。俗言。俚語。↔雅言
り‐げん【俚諺】
俗間のことわざ。民間で言いならわされてきたことわざ。
り‐げんこう【李元昊】‥カウ
西夏の初代皇帝。景宗。唐の夏州節度使の後裔。国を大夏と号し、宋・遼と対抗しながら国力の充実を図った。諡おくりなは武烈。(在位1038〜1048)(1003〜1048)
りげんしゅうらん【俚言集覧】‥シフ‥
国語辞書。26巻。太田全斎編、村田了阿ら補。「諺苑」を基礎にして江戸時代の方言・俗語・俗諺を集め、五十音図の横列順に配し、語釈を施したもの。1900年(明治33)井上頼圀よりくに・近藤瓶城みかきが増訂、通行の五十音順に改編。
りげん‐だいし【理源大師】
聖宝しょうぼうの諡号しごう。
りけん‐や【利権屋】
①利権をあさる人。
②特許的権利を得ようとする人のために、各種の仲介運動をして手数料を取る周旋屋。
⇒り‐けん【利権】
り‐こ【利子】
⇒りし。太平記8「頸を借りたる人―をつけて返すべし」
り‐こ【利己】
自分一人だけの利益を計ること。自利。主我。「―心」「―的」「―主義」↔利他
り‐ご【俚語】
(→)俚言りげん2に同じ。
り‐こう【李昂】‥カウ
(Li Ang)台湾の作家。本名、施淑端。両親とも本省人。フェミニズム文学「夫殺し」「迷いの園」「自伝の小説」など。(1952〜)
り‐こう【利口】
①たくみに言うこと。口さきのうまいこと。巧言。今昔物語集28「まことにわ君行きて―に云ひ聞せよ」
②頭がよいこと。かしこいこと。また、要領がよく抜け目がないこと。利巧。狂言、長光「さてさて―なやつちや。これはだまされまい」。「―な人」「―に立ちまわる」
③冗談じょうだんを言うこと。興言。古今著聞集16「それにも懲りず、なほ―し歩きけるほどに」
④(多く「お―」の形で)聞きわけのよいこと。「お―にしていなさい」
⇒りこう‐ぶ・る【利口ぶる】
り‐こう【利巧】‥カウ
(→)利口2に同じ。
り‐こう【里甲】‥カフ
明代の郷村統治機構。1381年制定。110戸を1里とし、そのうち10人を里長、他の100戸を甲首とし、毎年里長1人、甲首10人が服役して、租税の徴収・治安の維持などに当たった。
り‐こう【里堠】
(→)一里塚に同じ。
り‐こう【理工】
理学と工学。「―系」
り‐こう【犂耕】‥カウ
犂すきを用いた耕作、または農業。↔耨耕じょっこう
り‐こう【履行】‥カウ
①実際に行うこと。言葉どおりに実行すること。
②〔法〕債務者が債権の目的(内容)たる給付を実行すること。弁済と同義であるが、履行は債権の効力の面からいうのに対し、弁済は債権の消滅の面からいう。
⇒りこう‐ちたい【履行遅滞】
⇒りこう‐ふのう【履行不能】
り‐ごう【離合】‥ガフ
はなれたり集まったりすること。
⇒りごう‐し【離合詩】
⇒りごう‐しゅうさん【離合集散】
りごう‐し【離合詩】‥ガフ‥
漢詩の雑体詩の一種。字の偏へんや旁つくりを分けた文字を組み合わせて詩を作る文字遊び。例えば、「呂公釣磯盍口渭傍」で「呂」から「口」の字を離し、「九域有聖無土不王」で「域」から「土」の字を離して「或」とし、「口」と合わせて、「國」の字とするもの。
⇒り‐ごう【離合】
り‐こうじゅ【李光珠】‥クワウ‥
⇒イ=グヮンス
りごう‐しゅうさん【離合集散】‥ガフシフ‥
はなれたり集まったりすること。分離したり合併したりすること。「―を繰り返す」
⇒り‐ごう【離合】
り‐こうしょう【李鴻章】‥シヤウ
清末の政治家。字は少荃、号は儀叟。安徽合肥の人。曾国藩に従って太平天国の乱を平定。以来、日清戦争(下関条約)・義和団事件(北京議定書)などの外交に貢献するとともに軍隊の近代化、近代工業の育成、招商局の設立などにつとめた。直隷総督・北洋大臣・内閣大学士などを歴任。(1823〜1901)
りこう‐ちたい【履行遅滞】‥カウ‥
債務不履行の一類型。履行不能の場合を除き、債務者が履行期に債務を履行しないこと。債務者遅滞。
⇒り‐こう【履行】
りこう‐ふのう【履行不能】‥カウ‥
債務不履行の一類型。債務者の責めに帰すべき事由によって債務の履行が不可能となること。
⇒り‐こう【履行】
りこう‐ぶ・る【利口ぶる】
〔自五〕
利口らしくふるまう。
⇒り‐こう【利口】
り‐こうり【李広利】‥クワウ‥
前漢の将軍。武帝の寵妃李夫人の兄。大宛遠征を指揮した。( 〜前90)
り‐こうりん【李公麟】
北宋の画家。字は伯時。号は竜眠居士。安徽舒城の人。諸官を歴任後、竜眠山に隠棲。唐の呉道子流の白画を復活させた。(1049?〜1106)
リコーダー【recorder】
木管楽器。16〜18世紀、ヨーロッパで用いた縦笛。日本では、第二次大戦後、竹製・プラスチック製のものを主に初等教育用楽器として使用。ブロックフレーテ。
リゴーニ‐ステルン【Mario Rigoni Stern】
イタリアのネオレアリズモの作家。庶民・歴史・自然の3要素が融合した作風。作「雪の中の軍曹」「雷鳥の森」。(1921〜)
リコール【recall】
①国または地方自治体の公職者を国民または住民の意思によって罷免する制度。直接民主制の一つ。解職請求。「市長を―する」
②自動車などで、製品に欠陥がある場合、生産者が公表して、製品を回収し無料で修理すること。
り‐こくよう【李克用】
五代の後唐の実質的創始者。追号、太祖。突厥とっけつ沙陀部首長。父祖以来、唐に服属。振武節度使。黄巣の乱に唐を助け、河東節度使となる。朱全忠と政権を争って敗れ戦没したが、その子存勗そんきょくが後唐を建国。(856〜908)
りこ‐しゅぎ【利己主義】
(egoism)
①自己の利害だけを行為の規準とし、社会一般の利害を念頭に置かない考え方。主我主義。自己主義。↔利他主義。
②人間の利己心から出発して道徳の原理や観念を説明しようとする倫理学の立場。必ずしも1の意味での利己主義を主張するものではない。
りこ‐しん【利己心】
自己の利害だけを念頭に置いて、他人の迷惑を考えようとしない心。「―から出た振舞」
リコッタ【ricotta イタリア】
ホエーを加熱して作るイタリアのフレッシュ‐チーズ。料理や菓子によく使う。原料乳は牛・羊など様々で、塩を加えて熟成させたものもある。
りこ‐てき【利己的】
他人の迷惑を顧みず、自己の利益だけを追求するさま。「―な態度」
⇒りこてき‐いでんし【利己的遺伝子】
りこてき‐いでんし【利己的遺伝子】‥ヰ‥
(selfish genes)イギリスの動物行動学者ドーキンス(Richard Dawkins1941〜)による1976年の著書。「個体ではなく、遺伝子にとって有利な性質が進化する」という説を、遺伝子が利己的に振る舞っていると表現した語。
⇒りこ‐てき【利己的】
リコピン【lycopene】
分子式C40H50 カロテンの異性体。結晶性炭化水素。トマトなどの赤色色素で、優れた抗酸化作用がある。
リコリス【Licoris】
ヒガンバナ科ヒガンバナ属の球根植物数種の総称。園芸品種が多い。秋に花茎を伸ばし先端にヒガンバナに似た美花を多数放射状に咲かせる。広くはヒガンバナ属の属名。
リゴリスト【rigorist】
厳格な人。厳粛主義者。
リゴリズム【rigorism】
厳粛主義。厳格主義。
リゴレット【Rigoletto】
ヴェルディ作曲の歌劇。3幕。ユゴーの戯曲「王は楽しむ」(1832年作)に取材。1851年ヴェネツィアで初演。「女心の歌」で有名。
ヴェルディ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
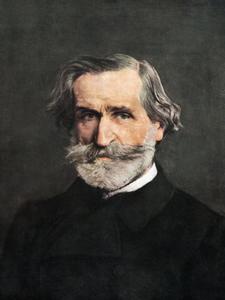 り‐こん【利根】
かしこい性質。利口。利発。特に仏教で、宗教的素質・能力がすぐれていること。謡曲、丹後物狂「この人―第一の人にて」
⇒りこん‐そう【利根草】
り‐こん【離恨】
人と離れるかなしみ。別離の恨み。
り‐こん【離婚】
夫婦が婚姻を解消すること。
⇒りこん‐とどけ【離婚届】
リコンストラクション【reconstruction】
改造。再建。
りこん‐そう【利根草】‥サウ
蓼たでの異称。狂言、鈍根草「これは―と云うて、これを食へば利根になるになあ」
⇒り‐こん【利根】
りこん‐とどけ【離婚届】
夫婦がその協議で離婚をする場合に、市区町村長に対してする届出。
⇒り‐こん【離婚】
りこん‐びょう【離魂病】‥ビヤウ
①魂が肉体から抜け出し、もう一人同じ人間が現れると考えられていた病気。浄瑠璃、蘆屋道満大内鑑「退いて分別するに―といふ病あり。俗には影の煩ひと言ひ」
②(→)夢中遊行むちゅうゆうこう症に同じ。
リコンファーム【reconfirm】
航空機の予約済み座席の再確認。
リサーチ【research】
調査。研究。「マーケット‐―」
リザーブ【reserve】
①部屋や座席を予約すること。「船室を―する」
②留保。保留。
リサール【José Rizal】
フィリピンの民族英雄。言論活動でスペインの行政・宗教政策を攻撃。フィリピン革命の勃発に際して扇動者と疑われ、銃殺。小説「我に触れるなかれ」「反逆」など。(1861〜1896)
り‐さい【里宰】
むらおさ。庄屋。里長。
り‐さい【罹災】
災害をうけること。被災。「―した人々」「―地」
り‐ざい【李在】
明代の画家。字は以政。福建莆田の人。山水画を得意とし、郭
り‐こん【利根】
かしこい性質。利口。利発。特に仏教で、宗教的素質・能力がすぐれていること。謡曲、丹後物狂「この人―第一の人にて」
⇒りこん‐そう【利根草】
り‐こん【離恨】
人と離れるかなしみ。別離の恨み。
り‐こん【離婚】
夫婦が婚姻を解消すること。
⇒りこん‐とどけ【離婚届】
リコンストラクション【reconstruction】
改造。再建。
りこん‐そう【利根草】‥サウ
蓼たでの異称。狂言、鈍根草「これは―と云うて、これを食へば利根になるになあ」
⇒り‐こん【利根】
りこん‐とどけ【離婚届】
夫婦がその協議で離婚をする場合に、市区町村長に対してする届出。
⇒り‐こん【離婚】
りこん‐びょう【離魂病】‥ビヤウ
①魂が肉体から抜け出し、もう一人同じ人間が現れると考えられていた病気。浄瑠璃、蘆屋道満大内鑑「退いて分別するに―といふ病あり。俗には影の煩ひと言ひ」
②(→)夢中遊行むちゅうゆうこう症に同じ。
リコンファーム【reconfirm】
航空機の予約済み座席の再確認。
リサーチ【research】
調査。研究。「マーケット‐―」
リザーブ【reserve】
①部屋や座席を予約すること。「船室を―する」
②留保。保留。
リサール【José Rizal】
フィリピンの民族英雄。言論活動でスペインの行政・宗教政策を攻撃。フィリピン革命の勃発に際して扇動者と疑われ、銃殺。小説「我に触れるなかれ」「反逆」など。(1861〜1896)
り‐さい【里宰】
むらおさ。庄屋。里長。
り‐さい【罹災】
災害をうけること。被災。「―した人々」「―地」
り‐ざい【李在】
明代の画家。字は以政。福建莆田の人。山水画を得意とし、郭 から馬遠・夏珪様式まで広くとりいれた。雪舟は入明中、李在らに学ぶ。
り‐ざい【理財】
貨財を有利に運用すること。経済。「―にたける」
⇒りざい‐か【理財家】
⇒りざい‐がく【理財学】
⇒りざい‐きょく【理財局】
りざい‐か【理財家】
理財の道に長じた人。経済家。北村透谷、二宮尊徳翁「翁は希代の―にして而して独得の大信仰を有し」
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐がく【理財学】
(political economyの井上哲次郎による訳語)経済学の旧称。
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐きょく【理財局】
国庫・国債・財政投融資・国有財産・たばこ塩行政その他の事項を取り扱う財務省の内局。
⇒り‐ざい【理財】
リサイクル【recycle】
資源の節約や環境汚染防止などのために、不用品・廃棄物などを再利用すること。
⇒リサイクル‐ショップ
リサイクル‐ショップ
(和製語recycle shop)中古品や不要品を買い取り、販売する店。
⇒リサイクル【recycle】
リサイタル【recital】
独唱会。独奏会。
りさく‐りょう【離作料】‥レウ
(→)作離料に同じ。
り‐さげ【利下げ】
利息を安くすること。↔利上げ
リサジュー‐ずけい【リサジュー図形】‥ヅ‥
互いに垂直な方向の単振動を合成して得られる2次元運動の軌道が描く図形。フランスの科学者リサジュー(J. A. Lissajous1822〜1880)が1855年に考案。
り‐さつ【利札】
公債証書・債券などにつける利子支払保証の札。クーポン。りふだ。
り‐ざや【利鞘】
(取引用語)売買をして得られる差額の利益。マージン。
り‐さん【離散】
ちりぢりに離れること。「一家―」
⇒りさん‐すうがく【離散数学】
⇒りさん‐てき【離散的】
り‐ざん【離山】
①ただ一つ離れた山。孤山。
②僧が寺を去ること。平家物語2「―しける僧の坊の柱に」
り‐ざん【驪山】
中国陝西省西安市臨潼区の南東郊にある山。古来、西北麓の温泉で名高く、秦の始皇帝は瘡そうを治療し、唐の玄宗は華清宮で楊貴妃に浴せしめた。
⇒りざん‐きゅう【驪山宮】
りざん‐きゅう【驪山宮】
驪山にあった華清宮の別称。
⇒り‐ざん【驪山】
りさん‐すうがく【離散数学】
(discrete mathematics)有限個の対象、あるいは連続でない対象を研究する数学の一分野。組合せ数学とほぼ同義。
⇒り‐さん【離散】
りさん‐てき【離散的】
〔理〕ある変量が特定のとびとびの値しか取りえないさま。物理量の値が離散的になることが量子力学の特色。
⇒り‐さん【離散】
り‐さんぺい【李参平】
江戸初期の陶工。文禄・慶長の役の際、朝鮮から渡来。日本名、金ヶ江三兵衛。佐賀県の有田泉山で良質の土を発見し、日本磁器の端緒を開く。( 〜1655)
り‐し【利子】
債務者が貨幣使用料として債権者に一定の割合で支払う金銭。金利。利息。「―が付く」
り‐し【李斯】
秦の宰相。楚の上蔡の人。荀子に学び、始皇帝に仕え、宰相となり、焚書を行なった。最後は讒ざんせられて刑死。( 〜前210)
り‐し【李詩】
唐の李白の詩。
り‐し【李贄】
明末の儒者。陽明学左派。字は卓吾。福建晋江の人。自ら儒教叛徒と称す。1580年官を辞し、やがて剃髪し在家居士として世俗の交わりを絶ち、著述に専心。過激な言説によって異端視され76歳で下獄、自殺。吉田松陰が獄中でその著書を愛読、抄写した。著「焚書」「蔵書」など。(1527〜1602)
り‐し【律師】
⇒りっし。源氏物語夕霧「物のけなど祓ひ捨てける―」
り‐じ【俚耳】
世間の人々の耳。俗耳。「―に入りやすい」
り‐じ【理事】
①法人の事務を処理し、これを代表し、権利を行使する機関。株式会社などでは特に取締役という。「―会」
②〔仏〕(→)事理に同じ。
りしうみ‐しほん【利子生み資本】
(→)貸付資本に同じ。
リシエ【Germaine Richier】
フランスの女性彫刻家。ブールデルの門人。独自の塑造そぞう法によって人体を表現。(1904〜1959)
りじ‐かん【理事官】‥クワン
①旧制で、内閣各省に属した官名。多くは古参判任官の優遇のためにおかれた奏任官。
②もと台湾総督府の事務官。
り‐しくん【李思訓】
唐の画家。字は建見。唐の宗室の一族。大李将軍と呼ばれた。その子の李昭道も小李将軍と称せられ、共に細密な着色山水画をよくし、金碧山水の創始者。また、北宗画の祖といわれる。(653〜718)
りじ‐こく【理事国】
国際機関の理事会の一員たる国。
りじ‐しゃ【理事者】
法人などの理事の職にある人。
り‐じせい【李自成】
明末の農民反乱の首領。飢民・流民らを組織して各地を荒らし、1644年に明を滅ぼす。北京で帝を称したが、清軍に破れ敗走し、自殺。(1606〜1645)
りし‐ちょうせん【李氏朝鮮】‥テウ‥
(→)李朝りちょう2に同じ。
り‐じちん【李時珍】
明の自然科学者。湖北蘄春の人。本草・医学に通じ、1578年「本草綱目」を完成、本草学を集大成した。(1518〜1593)
りしつき‐しほん【利子付き資本】
(→)貸付資本に同じ。
リジッド【rigid】
①厳格なこと。厳密なこと。
②固定していること。動かないこと。
リシノール‐さん【リシノール酸】
(ricinoleic acid)ヒドロキシ酸の一つ。分子式C17H32(OH)COOH オレイン酸の水素1原子を水酸基で置換したもの。グリセリン‐エステルとしてひまし油に含まれる。
りし‐ほきゅう【利子補給】‥キフ
借入金の利子支払に要する経費の一部または全部を補助すること。特定の事業・産業を援助するためなどに行う。
り‐しゅ【理趣】
事のわけ。物の道理。駿台雑話「文辞訓話を僉議して―の深きに及ばず」
り‐しゅ【離朱】
中国古伝説上の人物。百歩離れた所からでも毛の先が見えるほど視力がすぐれていたと伝えられる。離婁りろう。
り‐しゅう【履修】‥シウ
きめられた学科・課程などを習い修めること。「全課程を―する」「―科目」
り‐しゅう【離愁】‥シウ
別離のかなしみ。
りしゅ‐きょう【理趣経】‥キヤウ
仏典の一つ。不空の訳。1巻。真言宗の常用経典。大日如来が金剛薩埵さったのために般若理趣の自性清浄なることを説いたもの。般若理趣経。
リシュリュー【Armand Jean du Plessis, Duc de Richelieu】
フランスの政治家・枢機卿。1624〜42年ルイ13世の宰相。反王権的な貴族やユグノーの反乱を抑え、中央集権制と絶対王政の確立に努め、外ではスペインと抗争、三十年戦争に介入。アカデミー‐フランセーズを創立。(1585〜1642)
り‐じゅん【利潤】
①利益。もうけ。
②〔経〕(profit)企業の総売上額から生産費を控除した余剰で、企業家の所得となるもの。生産過程で生みだされる剰余価値の転化した形態。
⇒りじゅん‐ぶんぱい‐せいど【利潤分配制度】
⇒りじゅん‐りつ【利潤率】
り‐しゅんしん【李舜臣】
(Yi Sun-shin)朝鮮、李朝中期の水軍の将。亀甲船をつくり、秀吉による日本の侵攻軍を破った。のち戦死。救国の英雄的将軍とたたえられる。イ=スンシン。(1545〜1598)
りじゅん‐ぶんぱい‐せいど【利潤分配制度】
経営参加の一形態。利潤の一部を従業員に分配することによって、勤労意欲の向上を期待する制度。
⇒り‐じゅん【利潤】
りじゅん‐りつ【利潤率】
資本に対する利潤の割合。総資本で剰余価値を割った比率。
⇒り‐じゅん【利潤】
り‐じょ【犂鋤】
からすきとくわ。農具。また、すきやくわで耕地をたがやすこと。
り‐しょう【利生】‥シヤウ
〔仏〕仏が衆生しゅじょうを利益りやくすること。また、その利益。仏の冥加。利物りもつ。今昔物語集1「王宮を出でて―の道に入れり」
⇒りしょう‐おとこ【利生男】
⇒りしょう‐とう【利生塔】
⇒りしょう‐ほうべん【利生方便】
り‐しょう【理性】‥シヤウ
〔仏〕一切存在の本性。真如。法性。
り‐しょう【離生】‥シヤウ
〔仏〕生死を離れること。
り‐しょう【離床】‥シヤウ
ねどこを離れること。起床。
り‐しょう【離昇】
航空機が空中に浮揚し始めること。
り‐しょう【離礁】‥セウ
暗礁に乗り上げた船が暗礁を離れて浮かぶこと。
り‐しょういん【李商隠】‥シヤウ‥
晩唐の詩人。字は義山。懐州河内(河南沁陽)の人。生涯を落魄の中に送る。典故を多用して修辞に技巧を凝らす詩風は、宋初の西崑体せいこんたいの祖となる。著「李義山詩集」「樊南文集」。(812?〜858)
りしょういん‐りゅう【理性院流】‥シヤウヰンリウ
真言宗の事相の一派。醍醐理性院の賢覚を祖とし、京都市伏見区の理性院を本寺とする。小野六流・醍醐三流の一つ。
りしょう‐おとこ【利生男】‥シヤウヲトコ
利生を受けた男。幸福な男。
⇒り‐しょう【利生】
りしょう‐とう【利生塔】‥シヤウタフ
「安国寺あんこくじ」参照。
⇒り‐しょう【利生】
り‐しょうばん【李承晩】
⇒イ=スンマン。
⇒りしょうばん‐ライン【李承晩ライン】
りしょうばん‐ライン【李承晩ライン】
李承晩が1952年に発した海洋主権宣言において設定された漁船立入禁止線。済州島付近から対馬海峡にわたる漁場での日本の漁船の操業が禁止された。65年日韓漁業協定の成立とともに撤廃。
⇒り‐しょうばん【李承晩】
りしょう‐ほうべん【利生方便】‥シヤウハウ‥
衆生を利益りやくする仏の巧みなてだて。太平記26「―を施し給ひし天神の社壇」
⇒り‐しょう【利生】
り‐しょく【利殖】
利子または利益を得て財産の増殖を図ること。「―の才にたける」
り‐しょく【離職】
①職務から離れること。
②職業から離れること。失業。
りしり【利尻】
北海道北部、稚内わっかない市の南西方40キロメートル、礼文れぶん島と並ぶ日本海中の火山島。ウニ・コンブを産する。
利尻岳
撮影:山梨勝弘
から馬遠・夏珪様式まで広くとりいれた。雪舟は入明中、李在らに学ぶ。
り‐ざい【理財】
貨財を有利に運用すること。経済。「―にたける」
⇒りざい‐か【理財家】
⇒りざい‐がく【理財学】
⇒りざい‐きょく【理財局】
りざい‐か【理財家】
理財の道に長じた人。経済家。北村透谷、二宮尊徳翁「翁は希代の―にして而して独得の大信仰を有し」
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐がく【理財学】
(political economyの井上哲次郎による訳語)経済学の旧称。
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐きょく【理財局】
国庫・国債・財政投融資・国有財産・たばこ塩行政その他の事項を取り扱う財務省の内局。
⇒り‐ざい【理財】
リサイクル【recycle】
資源の節約や環境汚染防止などのために、不用品・廃棄物などを再利用すること。
⇒リサイクル‐ショップ
リサイクル‐ショップ
(和製語recycle shop)中古品や不要品を買い取り、販売する店。
⇒リサイクル【recycle】
リサイタル【recital】
独唱会。独奏会。
りさく‐りょう【離作料】‥レウ
(→)作離料に同じ。
り‐さげ【利下げ】
利息を安くすること。↔利上げ
リサジュー‐ずけい【リサジュー図形】‥ヅ‥
互いに垂直な方向の単振動を合成して得られる2次元運動の軌道が描く図形。フランスの科学者リサジュー(J. A. Lissajous1822〜1880)が1855年に考案。
り‐さつ【利札】
公債証書・債券などにつける利子支払保証の札。クーポン。りふだ。
り‐ざや【利鞘】
(取引用語)売買をして得られる差額の利益。マージン。
り‐さん【離散】
ちりぢりに離れること。「一家―」
⇒りさん‐すうがく【離散数学】
⇒りさん‐てき【離散的】
り‐ざん【離山】
①ただ一つ離れた山。孤山。
②僧が寺を去ること。平家物語2「―しける僧の坊の柱に」
り‐ざん【驪山】
中国陝西省西安市臨潼区の南東郊にある山。古来、西北麓の温泉で名高く、秦の始皇帝は瘡そうを治療し、唐の玄宗は華清宮で楊貴妃に浴せしめた。
⇒りざん‐きゅう【驪山宮】
りざん‐きゅう【驪山宮】
驪山にあった華清宮の別称。
⇒り‐ざん【驪山】
りさん‐すうがく【離散数学】
(discrete mathematics)有限個の対象、あるいは連続でない対象を研究する数学の一分野。組合せ数学とほぼ同義。
⇒り‐さん【離散】
りさん‐てき【離散的】
〔理〕ある変量が特定のとびとびの値しか取りえないさま。物理量の値が離散的になることが量子力学の特色。
⇒り‐さん【離散】
り‐さんぺい【李参平】
江戸初期の陶工。文禄・慶長の役の際、朝鮮から渡来。日本名、金ヶ江三兵衛。佐賀県の有田泉山で良質の土を発見し、日本磁器の端緒を開く。( 〜1655)
り‐し【利子】
債務者が貨幣使用料として債権者に一定の割合で支払う金銭。金利。利息。「―が付く」
り‐し【李斯】
秦の宰相。楚の上蔡の人。荀子に学び、始皇帝に仕え、宰相となり、焚書を行なった。最後は讒ざんせられて刑死。( 〜前210)
り‐し【李詩】
唐の李白の詩。
り‐し【李贄】
明末の儒者。陽明学左派。字は卓吾。福建晋江の人。自ら儒教叛徒と称す。1580年官を辞し、やがて剃髪し在家居士として世俗の交わりを絶ち、著述に専心。過激な言説によって異端視され76歳で下獄、自殺。吉田松陰が獄中でその著書を愛読、抄写した。著「焚書」「蔵書」など。(1527〜1602)
り‐し【律師】
⇒りっし。源氏物語夕霧「物のけなど祓ひ捨てける―」
り‐じ【俚耳】
世間の人々の耳。俗耳。「―に入りやすい」
り‐じ【理事】
①法人の事務を処理し、これを代表し、権利を行使する機関。株式会社などでは特に取締役という。「―会」
②〔仏〕(→)事理に同じ。
りしうみ‐しほん【利子生み資本】
(→)貸付資本に同じ。
リシエ【Germaine Richier】
フランスの女性彫刻家。ブールデルの門人。独自の塑造そぞう法によって人体を表現。(1904〜1959)
りじ‐かん【理事官】‥クワン
①旧制で、内閣各省に属した官名。多くは古参判任官の優遇のためにおかれた奏任官。
②もと台湾総督府の事務官。
り‐しくん【李思訓】
唐の画家。字は建見。唐の宗室の一族。大李将軍と呼ばれた。その子の李昭道も小李将軍と称せられ、共に細密な着色山水画をよくし、金碧山水の創始者。また、北宗画の祖といわれる。(653〜718)
りじ‐こく【理事国】
国際機関の理事会の一員たる国。
りじ‐しゃ【理事者】
法人などの理事の職にある人。
り‐じせい【李自成】
明末の農民反乱の首領。飢民・流民らを組織して各地を荒らし、1644年に明を滅ぼす。北京で帝を称したが、清軍に破れ敗走し、自殺。(1606〜1645)
りし‐ちょうせん【李氏朝鮮】‥テウ‥
(→)李朝りちょう2に同じ。
り‐じちん【李時珍】
明の自然科学者。湖北蘄春の人。本草・医学に通じ、1578年「本草綱目」を完成、本草学を集大成した。(1518〜1593)
りしつき‐しほん【利子付き資本】
(→)貸付資本に同じ。
リジッド【rigid】
①厳格なこと。厳密なこと。
②固定していること。動かないこと。
リシノール‐さん【リシノール酸】
(ricinoleic acid)ヒドロキシ酸の一つ。分子式C17H32(OH)COOH オレイン酸の水素1原子を水酸基で置換したもの。グリセリン‐エステルとしてひまし油に含まれる。
りし‐ほきゅう【利子補給】‥キフ
借入金の利子支払に要する経費の一部または全部を補助すること。特定の事業・産業を援助するためなどに行う。
り‐しゅ【理趣】
事のわけ。物の道理。駿台雑話「文辞訓話を僉議して―の深きに及ばず」
り‐しゅ【離朱】
中国古伝説上の人物。百歩離れた所からでも毛の先が見えるほど視力がすぐれていたと伝えられる。離婁りろう。
り‐しゅう【履修】‥シウ
きめられた学科・課程などを習い修めること。「全課程を―する」「―科目」
り‐しゅう【離愁】‥シウ
別離のかなしみ。
りしゅ‐きょう【理趣経】‥キヤウ
仏典の一つ。不空の訳。1巻。真言宗の常用経典。大日如来が金剛薩埵さったのために般若理趣の自性清浄なることを説いたもの。般若理趣経。
リシュリュー【Armand Jean du Plessis, Duc de Richelieu】
フランスの政治家・枢機卿。1624〜42年ルイ13世の宰相。反王権的な貴族やユグノーの反乱を抑え、中央集権制と絶対王政の確立に努め、外ではスペインと抗争、三十年戦争に介入。アカデミー‐フランセーズを創立。(1585〜1642)
り‐じゅん【利潤】
①利益。もうけ。
②〔経〕(profit)企業の総売上額から生産費を控除した余剰で、企業家の所得となるもの。生産過程で生みだされる剰余価値の転化した形態。
⇒りじゅん‐ぶんぱい‐せいど【利潤分配制度】
⇒りじゅん‐りつ【利潤率】
り‐しゅんしん【李舜臣】
(Yi Sun-shin)朝鮮、李朝中期の水軍の将。亀甲船をつくり、秀吉による日本の侵攻軍を破った。のち戦死。救国の英雄的将軍とたたえられる。イ=スンシン。(1545〜1598)
りじゅん‐ぶんぱい‐せいど【利潤分配制度】
経営参加の一形態。利潤の一部を従業員に分配することによって、勤労意欲の向上を期待する制度。
⇒り‐じゅん【利潤】
りじゅん‐りつ【利潤率】
資本に対する利潤の割合。総資本で剰余価値を割った比率。
⇒り‐じゅん【利潤】
り‐じょ【犂鋤】
からすきとくわ。農具。また、すきやくわで耕地をたがやすこと。
り‐しょう【利生】‥シヤウ
〔仏〕仏が衆生しゅじょうを利益りやくすること。また、その利益。仏の冥加。利物りもつ。今昔物語集1「王宮を出でて―の道に入れり」
⇒りしょう‐おとこ【利生男】
⇒りしょう‐とう【利生塔】
⇒りしょう‐ほうべん【利生方便】
り‐しょう【理性】‥シヤウ
〔仏〕一切存在の本性。真如。法性。
り‐しょう【離生】‥シヤウ
〔仏〕生死を離れること。
り‐しょう【離床】‥シヤウ
ねどこを離れること。起床。
り‐しょう【離昇】
航空機が空中に浮揚し始めること。
り‐しょう【離礁】‥セウ
暗礁に乗り上げた船が暗礁を離れて浮かぶこと。
り‐しょういん【李商隠】‥シヤウ‥
晩唐の詩人。字は義山。懐州河内(河南沁陽)の人。生涯を落魄の中に送る。典故を多用して修辞に技巧を凝らす詩風は、宋初の西崑体せいこんたいの祖となる。著「李義山詩集」「樊南文集」。(812?〜858)
りしょういん‐りゅう【理性院流】‥シヤウヰンリウ
真言宗の事相の一派。醍醐理性院の賢覚を祖とし、京都市伏見区の理性院を本寺とする。小野六流・醍醐三流の一つ。
りしょう‐おとこ【利生男】‥シヤウヲトコ
利生を受けた男。幸福な男。
⇒り‐しょう【利生】
りしょう‐とう【利生塔】‥シヤウタフ
「安国寺あんこくじ」参照。
⇒り‐しょう【利生】
り‐しょうばん【李承晩】
⇒イ=スンマン。
⇒りしょうばん‐ライン【李承晩ライン】
りしょうばん‐ライン【李承晩ライン】
李承晩が1952年に発した海洋主権宣言において設定された漁船立入禁止線。済州島付近から対馬海峡にわたる漁場での日本の漁船の操業が禁止された。65年日韓漁業協定の成立とともに撤廃。
⇒り‐しょうばん【李承晩】
りしょう‐ほうべん【利生方便】‥シヤウハウ‥
衆生を利益りやくする仏の巧みなてだて。太平記26「―を施し給ひし天神の社壇」
⇒り‐しょう【利生】
り‐しょく【利殖】
利子または利益を得て財産の増殖を図ること。「―の才にたける」
り‐しょく【離職】
①職務から離れること。
②職業から離れること。失業。
りしり【利尻】
北海道北部、稚内わっかない市の南西方40キロメートル、礼文れぶん島と並ぶ日本海中の火山島。ウニ・コンブを産する。
利尻岳
撮影:山梨勝弘
 利尻島
撮影:関戸 勇
利尻島
撮影:関戸 勇
 ⇒りしり‐こんぶ【利尻昆布】
⇒りしり‐ざん【利尻山】
⇒りしり‐れぶん‐サロベツ‐こくりつこうえん【利尻礼文サロベツ国立公園】
りしり‐こんぶ【利尻昆布】
褐藻コンブ科の一種。帯状、黒褐色。長さ3メートルに達する。利尻・礼文両島付近を主産地に、日本海北部・オホーツク海などに分布。乾して食用。
⇒りしり【利尻】
りしり‐ざん【利尻山】
利尻島を形成する円錐状成層火山。標高1721メートル。利尻富士。
⇒りしり【利尻】
りし‐りつ【利子率】
元金に対する利子の割合。
りしり‐れぶん‐サロベツ‐こくりつこうえん【利尻礼文サロベツ国立公園】‥ヱン
利尻・礼文両島および対岸のサロベツ原野を中心とする国立公園。高山植物・湿原・海食崖が特色。
⇒りしり【利尻】
り‐しん【離心】
①そむき離れる心。また、そむくこと。「主君に―する」
②中心から離れていること。
⇒りしん‐えん【離心円】
⇒りしん‐りつ【離心率】
リシン【lysine】
必須アミノ酸の一つ。ほとんどの蛋白質の成分で、特にヒストン・アルブミン・筋肉蛋白質などに多い。食物に添加して栄養価を高めるのに用いる。リジン。ライシン。
リシン【ricin】
トウゴマの種子などに含まれる糖蛋白質。細胞のリボソームに作用し、蛋白質合成を阻害し、微量で猛毒。リチン。
り‐じん【吏人】
役人。官吏。公吏。
り‐じん【利刃】
よく切れる刀。
り‐じん【里人】
村の人。さとびと。
りしん‐えん【離心円】‥ヱン
(eccentric circle)天動説で、惑星の動きをより精確に説明するために想定された、地球から離れたところにある点を中心とする円。惑星はその上を周転するとされた。プトレマイオスが提唱。→周転円。
⇒り‐しん【離心】
りじん‐しょう【離人症】‥シヤウ
自己・他人・外部世界の具体的な存在感・生命感が失われ、対象は完全に知覚しながらも、それらと自己との有機的なつながりを実感しえない精神状態。人格感喪失。有情感喪失。
りしん‐りつ【離心率】
〔数〕円錐曲線(二次曲線)の持つ定数の一つ。離心率が1より小さいか、1に等しいか、1より大きいかに従い、楕円・放物線・双曲線となる。円の離心率は0と定める。心差率。→円錐曲線
⇒り‐しん【離心】
りしん‐ろん【理神論】
〔宗〕(deism)世界の根源として神の存在を認めはするが、これを人格的な主宰者とは考えず、従って奇跡や啓示の存在を否定する説。啓示宗教に対する理性宗教。17〜18世紀のヨーロッパに現れ、代表者はイギリスのトーランド(John Toland1670〜1722)・ヴォルテール・レッシングら。自然神論。自然神教。↔有神論↔汎神論
り‐す【栗鼠】
(リスは漢字の音読み)ネズミ目リス科の哺乳類の総称。また特にニホンリスのことで、頭胴長20センチメートル、尾長15センチメートルほど。夏毛は赤褐色、冬毛は黄褐色で、腹は白い。森林に生息し、木の実や木の葉、昆虫などを食べる。小枝や葉を集め、枝の間に巣を作る。日本特産。北海道には類似種のキタリスがいる。また各地で、より大形のタイワンリスが野生化。キネズミ。〈日葡辞書〉
タイワンリス
提供:東京動物園協会
⇒りしり‐こんぶ【利尻昆布】
⇒りしり‐ざん【利尻山】
⇒りしり‐れぶん‐サロベツ‐こくりつこうえん【利尻礼文サロベツ国立公園】
りしり‐こんぶ【利尻昆布】
褐藻コンブ科の一種。帯状、黒褐色。長さ3メートルに達する。利尻・礼文両島付近を主産地に、日本海北部・オホーツク海などに分布。乾して食用。
⇒りしり【利尻】
りしり‐ざん【利尻山】
利尻島を形成する円錐状成層火山。標高1721メートル。利尻富士。
⇒りしり【利尻】
りし‐りつ【利子率】
元金に対する利子の割合。
りしり‐れぶん‐サロベツ‐こくりつこうえん【利尻礼文サロベツ国立公園】‥ヱン
利尻・礼文両島および対岸のサロベツ原野を中心とする国立公園。高山植物・湿原・海食崖が特色。
⇒りしり【利尻】
り‐しん【離心】
①そむき離れる心。また、そむくこと。「主君に―する」
②中心から離れていること。
⇒りしん‐えん【離心円】
⇒りしん‐りつ【離心率】
リシン【lysine】
必須アミノ酸の一つ。ほとんどの蛋白質の成分で、特にヒストン・アルブミン・筋肉蛋白質などに多い。食物に添加して栄養価を高めるのに用いる。リジン。ライシン。
リシン【ricin】
トウゴマの種子などに含まれる糖蛋白質。細胞のリボソームに作用し、蛋白質合成を阻害し、微量で猛毒。リチン。
り‐じん【吏人】
役人。官吏。公吏。
り‐じん【利刃】
よく切れる刀。
り‐じん【里人】
村の人。さとびと。
りしん‐えん【離心円】‥ヱン
(eccentric circle)天動説で、惑星の動きをより精確に説明するために想定された、地球から離れたところにある点を中心とする円。惑星はその上を周転するとされた。プトレマイオスが提唱。→周転円。
⇒り‐しん【離心】
りじん‐しょう【離人症】‥シヤウ
自己・他人・外部世界の具体的な存在感・生命感が失われ、対象は完全に知覚しながらも、それらと自己との有機的なつながりを実感しえない精神状態。人格感喪失。有情感喪失。
りしん‐りつ【離心率】
〔数〕円錐曲線(二次曲線)の持つ定数の一つ。離心率が1より小さいか、1に等しいか、1より大きいかに従い、楕円・放物線・双曲線となる。円の離心率は0と定める。心差率。→円錐曲線
⇒り‐しん【離心】
りしん‐ろん【理神論】
〔宗〕(deism)世界の根源として神の存在を認めはするが、これを人格的な主宰者とは考えず、従って奇跡や啓示の存在を否定する説。啓示宗教に対する理性宗教。17〜18世紀のヨーロッパに現れ、代表者はイギリスのトーランド(John Toland1670〜1722)・ヴォルテール・レッシングら。自然神論。自然神教。↔有神論↔汎神論
り‐す【栗鼠】
(リスは漢字の音読み)ネズミ目リス科の哺乳類の総称。また特にニホンリスのことで、頭胴長20センチメートル、尾長15センチメートルほど。夏毛は赤褐色、冬毛は黄褐色で、腹は白い。森林に生息し、木の実や木の葉、昆虫などを食べる。小枝や葉を集め、枝の間に巣を作る。日本特産。北海道には類似種のキタリスがいる。また各地で、より大形のタイワンリスが野生化。キネズミ。〈日葡辞書〉
タイワンリス
提供:東京動物園協会
 ニホンリス
提供:東京動物園協会
ニホンリス
提供:東京動物園協会
 り‐す【離洲】
洲に乗り上げた船が、その洲を離れて浮かぶこと。
リス【Riss ドイツ】
(登山用語)岩の割れ目。通常、ハーケンが打てる程度の細いものをいう。
り・す【理す】
〔他サ変〕
ととのえる。また、おさめる。太平記23「民を安んじ国を―・するを本となす」
リスアニア【Lithuania】
⇒リトアニア
り‐すい【利水】
①水をよく流通させること。また、水をよく利用すること。
②漢方で、体内の水の偏在を改善すること。
⇒りすい‐ざい【利水剤】
り‐すい【離水】
水上飛行機が水面から飛び上がること。↔着水。
⇒りすい‐かいがん【離水海岸】
りすい‐かいがん【離水海岸】
地盤の隆起または海水面の下降によって陸地が相対的に海面より上昇した海岸。
⇒り‐すい【離水】
りすい‐ざい【利水剤】
利水2の目的で用いる漢方方剤。五苓散・真武湯など。
⇒り‐すい【利水】
り‐すう【里数】
道程を里ではかった数。
り‐すう【理数】
理科と数学。
⇒りすう‐か【理数科】
りすう‐か【理数科】‥クワ
①理科と数学とを統合した教科。旧制の国民学校では算数・理科、中等学校では数学・物象・生物の各科目に分かれていた。
②高等学校の学科の一つ。
⇒り‐すう【理数】
リスキー【risky】
危険を伴うさま。冒険的なこと。
リスク【RISC】
(reduced instruction set computer)CPUを制御する基本命令を簡素化し、直接ハードウェアで機械語の処理を行うコンピューター。CISC(シスク)に比べて高速で演算処理を行える。
リスク【risk】
①危険。「―を伴う」
②保険者の担保責任。被保険物。
⇒リスク‐しゃかい【リスク社会】
⇒リスク‐プレミアム【risk premium】
⇒リスク‐ぶんせき【リスク分析】
⇒リスク‐ヘッジ
⇒リスク‐マネージメント【risk management】
リスク‐しゃかい【リスク社会】‥クワイ
産業と科学が環境や健康に与えるリスクの負担をめぐる争いが主要な対立点となった、後期の産業社会。ドイツの社会学者ベック(Ulrich Beck1944〜)の用語。
⇒リスク【risk】
リスク‐プレミアム【risk premium】
リスクの大きい資産の収益率が、長期国債など安全な資産の収益率を上回る分。
⇒リスク【risk】
リスク‐ぶんせき【リスク分析】
リスクを低減するための方法論。リスクの科学的な判定(リスク評価)、具体的な措置(リスク管理)、情報・意見交換(リスク‐コミュニケーション)から構成される。リスク学。特に、リスク評価での危険度分析をいう。
⇒リスク【risk】
リスク‐ヘッジ
(和製語risk hedge)〔経〕(→)ヘッジに同じ。
⇒リスク【risk】
リスク‐マネージメント【risk management】
企業活動に伴うさまざまな危険を最小限に抑える管理運営方法。RM
⇒リスク【risk】
リスケジューリング【re-scheduling】
〔経〕債務国からの要請を受けて、既存の返済計画の見直し、返済額の減額などによって債務返済の繰延べを行うこと。リスケ。
りす‐ざる【栗鼠猿】
オマキザル科リスザル属のサル3〜5種の総称。また、そのうちのコモンリスザルを指す。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。毛色は明るい褐色で、顔から胸にかけて白い。アマゾン流域からコロンビアの森林に分布し、集団で生活。ペット・実験動物としても飼育。
リスザル
提供:東京動物園協会
り‐す【離洲】
洲に乗り上げた船が、その洲を離れて浮かぶこと。
リス【Riss ドイツ】
(登山用語)岩の割れ目。通常、ハーケンが打てる程度の細いものをいう。
り・す【理す】
〔他サ変〕
ととのえる。また、おさめる。太平記23「民を安んじ国を―・するを本となす」
リスアニア【Lithuania】
⇒リトアニア
り‐すい【利水】
①水をよく流通させること。また、水をよく利用すること。
②漢方で、体内の水の偏在を改善すること。
⇒りすい‐ざい【利水剤】
り‐すい【離水】
水上飛行機が水面から飛び上がること。↔着水。
⇒りすい‐かいがん【離水海岸】
りすい‐かいがん【離水海岸】
地盤の隆起または海水面の下降によって陸地が相対的に海面より上昇した海岸。
⇒り‐すい【離水】
りすい‐ざい【利水剤】
利水2の目的で用いる漢方方剤。五苓散・真武湯など。
⇒り‐すい【利水】
り‐すう【里数】
道程を里ではかった数。
り‐すう【理数】
理科と数学。
⇒りすう‐か【理数科】
りすう‐か【理数科】‥クワ
①理科と数学とを統合した教科。旧制の国民学校では算数・理科、中等学校では数学・物象・生物の各科目に分かれていた。
②高等学校の学科の一つ。
⇒り‐すう【理数】
リスキー【risky】
危険を伴うさま。冒険的なこと。
リスク【RISC】
(reduced instruction set computer)CPUを制御する基本命令を簡素化し、直接ハードウェアで機械語の処理を行うコンピューター。CISC(シスク)に比べて高速で演算処理を行える。
リスク【risk】
①危険。「―を伴う」
②保険者の担保責任。被保険物。
⇒リスク‐しゃかい【リスク社会】
⇒リスク‐プレミアム【risk premium】
⇒リスク‐ぶんせき【リスク分析】
⇒リスク‐ヘッジ
⇒リスク‐マネージメント【risk management】
リスク‐しゃかい【リスク社会】‥クワイ
産業と科学が環境や健康に与えるリスクの負担をめぐる争いが主要な対立点となった、後期の産業社会。ドイツの社会学者ベック(Ulrich Beck1944〜)の用語。
⇒リスク【risk】
リスク‐プレミアム【risk premium】
リスクの大きい資産の収益率が、長期国債など安全な資産の収益率を上回る分。
⇒リスク【risk】
リスク‐ぶんせき【リスク分析】
リスクを低減するための方法論。リスクの科学的な判定(リスク評価)、具体的な措置(リスク管理)、情報・意見交換(リスク‐コミュニケーション)から構成される。リスク学。特に、リスク評価での危険度分析をいう。
⇒リスク【risk】
リスク‐ヘッジ
(和製語risk hedge)〔経〕(→)ヘッジに同じ。
⇒リスク【risk】
リスク‐マネージメント【risk management】
企業活動に伴うさまざまな危険を最小限に抑える管理運営方法。RM
⇒リスク【risk】
リスケジューリング【re-scheduling】
〔経〕債務国からの要請を受けて、既存の返済計画の見直し、返済額の減額などによって債務返済の繰延べを行うこと。リスケ。
りす‐ざる【栗鼠猿】
オマキザル科リスザル属のサル3〜5種の総称。また、そのうちのコモンリスザルを指す。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。毛色は明るい褐色で、顔から胸にかけて白い。アマゾン流域からコロンビアの森林に分布し、集団で生活。ペット・実験動物としても飼育。
リスザル
提供:東京動物園協会
 リスター【Joseph Lister】
イギリスの外科医。石炭酸溶液による消毒法の開発で近代外科手術に貢献。(1827〜1912)
リスト【list】
目録。名簿。一覧表。
⇒リスト‐アップ
リスト【wrist】
手首。特にスポーツでいう。「―の強いバッター」
⇒リスト‐カット
⇒リスト‐バンド【wristband】
リスト【Friedrich List】
ドイツの経済学者。歴史学派の先駆。経済発展段階説を展開し、国民主義の立場から保護貿易政策を主張。主著「経済学の国民的体系」。(1789〜1846)
リスト【Franz Liszt】
ハンガリーの作曲家・ピアノ奏者。標題音楽でベルリオーズを継承し、交響詩の形式を確立。ピアノ演奏では超絶技巧を誇り、その表現能力を拡大。作「ファウスト交響曲」、交響詩「前奏曲」、ピアノ協奏曲など。(1811〜1886)
リスト
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
リスター【Joseph Lister】
イギリスの外科医。石炭酸溶液による消毒法の開発で近代外科手術に貢献。(1827〜1912)
リスト【list】
目録。名簿。一覧表。
⇒リスト‐アップ
リスト【wrist】
手首。特にスポーツでいう。「―の強いバッター」
⇒リスト‐カット
⇒リスト‐バンド【wristband】
リスト【Friedrich List】
ドイツの経済学者。歴史学派の先駆。経済発展段階説を展開し、国民主義の立場から保護貿易政策を主張。主著「経済学の国民的体系」。(1789〜1846)
リスト【Franz Liszt】
ハンガリーの作曲家・ピアノ奏者。標題音楽でベルリオーズを継承し、交響詩の形式を確立。ピアノ演奏では超絶技巧を誇り、その表現能力を拡大。作「ファウスト交響曲」、交響詩「前奏曲」、ピアノ協奏曲など。(1811〜1886)
リスト
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
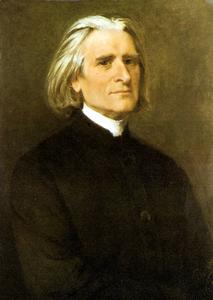 →愛の夢
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
リスト【Franz von Liszt】
ドイツの刑法学者。作曲家リストの従弟。ベルリン大学教授。近代刑法学の確立に貢献。著「ドイツ刑法教科書」など。(1851〜1919)
リスト‐アップ
(和製語list up)多くの事物の中から基準に合うものを選び出すこと。また、その一覧表を作ること。
⇒リスト【list】
リスト‐カット
(wrist-cutting syndrome)手首自傷症候群。刃物で自分の手首の内側や腕などを切創する自傷行為。
⇒リスト【wrist】
リスト‐バンド【wristband】
手首の保護と汗ふきとをかねて、運動時に手首にはめる布製の輪。
⇒リスト【wrist】
リストラ
(→)リストラクチュアリング2の略。
リストラクチュアリング【restructuring】
〔経〕(再建の意)
①短期債務を長期債務で置き換える債務の再構成。
②企業の買収・合併、不採算部門の整理、人員削減などの手段によって、事業内容を再編成すること。リストラ。
リストロサウルス【Lystrosaurus ラテン】
単弓類のうち比較的進歩した仲間の一つ。三畳紀前期に生息。水陸両生で、植物食性。体長約1メートル。化石はアフリカ・南極・インド・中国・東欧などで発見。
リスナー【listener】
ラジオの聴取者。
リスプ【LISP】
(list processor)コンピューターのプログラム言語の一種。人工知能・数式処理などの記号処理の分野で広く用いる。
リスボン【Lisbon】
ポルトガル共和国の首都。タホ川河口の港湾都市。1256年コインブラより遷都。旧王宮・美術博物館などがある。人口53万5千(2004)。ポルトガル語名リジュボア。
リスボン(1)
撮影:田沼武能
→愛の夢
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
リスト【Franz von Liszt】
ドイツの刑法学者。作曲家リストの従弟。ベルリン大学教授。近代刑法学の確立に貢献。著「ドイツ刑法教科書」など。(1851〜1919)
リスト‐アップ
(和製語list up)多くの事物の中から基準に合うものを選び出すこと。また、その一覧表を作ること。
⇒リスト【list】
リスト‐カット
(wrist-cutting syndrome)手首自傷症候群。刃物で自分の手首の内側や腕などを切創する自傷行為。
⇒リスト【wrist】
リスト‐バンド【wristband】
手首の保護と汗ふきとをかねて、運動時に手首にはめる布製の輪。
⇒リスト【wrist】
リストラ
(→)リストラクチュアリング2の略。
リストラクチュアリング【restructuring】
〔経〕(再建の意)
①短期債務を長期債務で置き換える債務の再構成。
②企業の買収・合併、不採算部門の整理、人員削減などの手段によって、事業内容を再編成すること。リストラ。
リストロサウルス【Lystrosaurus ラテン】
単弓類のうち比較的進歩した仲間の一つ。三畳紀前期に生息。水陸両生で、植物食性。体長約1メートル。化石はアフリカ・南極・インド・中国・東欧などで発見。
リスナー【listener】
ラジオの聴取者。
リスプ【LISP】
(list processor)コンピューターのプログラム言語の一種。人工知能・数式処理などの記号処理の分野で広く用いる。
リスボン【Lisbon】
ポルトガル共和国の首都。タホ川河口の港湾都市。1256年コインブラより遷都。旧王宮・美術博物館などがある。人口53万5千(2004)。ポルトガル語名リジュボア。
リスボン(1)
撮影:田沼武能
 リスボン(2)
撮影:小松義夫
リスボン(2)
撮影:小松義夫
 ⇒リスボン‐じょうやく【リスボン条約】
リスボン‐じょうやく【リスボン条約】‥デウ‥
1887年ポルトガルと中国との間に結ばれた、澳門マカオの永代租借・最恵国待遇に関する条約。
⇒リスボン【Lisbon】
リズミカル【rhythmical】
リズムのあるさま。調子のよいさま。律動的。音律的。「―な運動」
リズム【rhythm】
①周期的な動き。進行の調子。律動。「―に乗る」「生活の―が狂う」
②詩の韻律。
③音楽におけるあらゆる時間的な諸関係。西洋音楽では旋律・和声と並んで基本要素の一つで、一般に音量・音高・音色などと結びついてアクセントが生じ、それが周期的に現れると拍子が成立する。拍子がなくてもリズムは存在する。節奏。
⇒リズム‐アンド‐ブルース【rhythm and blues】
⇒リズム‐ギター【rhythm guitar】
リズム‐アンド‐ブルース【rhythm and blues】
アメリカ黒人音楽の一種。バンド演奏に合わせて歌う都会的なブルース音楽、特にアフター‐ビートを強調し、叫ぶような調子で歌うものを1940年代末からこう呼ぶようになった。R&B →ロックン‐ロール。
⇒リズム【rhythm】
リズム‐ギター【rhythm guitar】
リード‐ギターに対して、伴奏を担当するギター。
⇒リズム【rhythm】
リスリン
グリセリンの略訛。
り・する【利する】
〔自他サ変〕[文]利す(サ変)
①ためになる。また、ためになるようにする。利益・便益があるようにする。また、利益・便益を与える。「敵を―・する」
②利用する。応用する。「高官の地位を―・して」
③(罪から)救済する。〈日葡辞書〉
リセ【lycée フランス】
フランスの中等教育機関。修業年限は7年であったが、1975年以降は4年制のコレージュに続く3年制の後期中等学校をいう。アリストテレスが学校を開いた地、リュケイオンに由来する語。
り‐せい【李成】
五代・北宋初期の画家。李営丘と称。唐の宗室の末裔。華北系山水様式の大成者の一人。広大な空間を表現した「平遠山水」で知られる。(919〜967)
り‐せい【里正】
村長。庄屋。黄葉夕陽村舎詩「連日―が宅に珍羞は厨くりやに満ちて堆うづたかしと」
り‐せい【理世】
世をおさめること。治世。
⇒りせい‐ぶみん【理世撫民】
り‐せい【理性】
〔哲〕(reason イギリス・Vernunft ドイツ)
①概念的思考の能力。実践的には感性的欲求に左右されず思慮的に行動する能力。古来、人間と動物とを区別するものとされた。「―を保つ」「―を失う」
②真偽・善悪を識別する能力。
③超自然的啓示に対し、人間の自然的な認識能力。→自然の光。
④パルメニデスやアリストテレスにおいては、絶対者を認識する能力。
⑤特にカントの用法として、ア‐プリオリな原理の能力の総称。カントは理性が認識に関わる場合を理論理性、行為の原理となる場合を実践理性と呼んだ。狭義には感性や悟性から区別され、理念によって認識を統一する能力。
⑥ヘーゲルの用法で、悟性と区別された弁証法的思考の能力。
⑦宇宙的原理。世界理性・絶対的理性などのようにいわれる。
⑧ロゴスとしての言語能力。
⇒りせい‐がいねん【理性概念】
⇒りせい‐てき【理性的】
⇒りせい‐ろん【理性論】
り‐せい【理政】
政まつりごとを治めること。治世。源平盛衰記27「百官を百王の
⇒リスボン‐じょうやく【リスボン条約】
リスボン‐じょうやく【リスボン条約】‥デウ‥
1887年ポルトガルと中国との間に結ばれた、澳門マカオの永代租借・最恵国待遇に関する条約。
⇒リスボン【Lisbon】
リズミカル【rhythmical】
リズムのあるさま。調子のよいさま。律動的。音律的。「―な運動」
リズム【rhythm】
①周期的な動き。進行の調子。律動。「―に乗る」「生活の―が狂う」
②詩の韻律。
③音楽におけるあらゆる時間的な諸関係。西洋音楽では旋律・和声と並んで基本要素の一つで、一般に音量・音高・音色などと結びついてアクセントが生じ、それが周期的に現れると拍子が成立する。拍子がなくてもリズムは存在する。節奏。
⇒リズム‐アンド‐ブルース【rhythm and blues】
⇒リズム‐ギター【rhythm guitar】
リズム‐アンド‐ブルース【rhythm and blues】
アメリカ黒人音楽の一種。バンド演奏に合わせて歌う都会的なブルース音楽、特にアフター‐ビートを強調し、叫ぶような調子で歌うものを1940年代末からこう呼ぶようになった。R&B →ロックン‐ロール。
⇒リズム【rhythm】
リズム‐ギター【rhythm guitar】
リード‐ギターに対して、伴奏を担当するギター。
⇒リズム【rhythm】
リスリン
グリセリンの略訛。
り・する【利する】
〔自他サ変〕[文]利す(サ変)
①ためになる。また、ためになるようにする。利益・便益があるようにする。また、利益・便益を与える。「敵を―・する」
②利用する。応用する。「高官の地位を―・して」
③(罪から)救済する。〈日葡辞書〉
リセ【lycée フランス】
フランスの中等教育機関。修業年限は7年であったが、1975年以降は4年制のコレージュに続く3年制の後期中等学校をいう。アリストテレスが学校を開いた地、リュケイオンに由来する語。
り‐せい【李成】
五代・北宋初期の画家。李営丘と称。唐の宗室の末裔。華北系山水様式の大成者の一人。広大な空間を表現した「平遠山水」で知られる。(919〜967)
り‐せい【里正】
村長。庄屋。黄葉夕陽村舎詩「連日―が宅に珍羞は厨くりやに満ちて堆うづたかしと」
り‐せい【理世】
世をおさめること。治世。
⇒りせい‐ぶみん【理世撫民】
り‐せい【理性】
〔哲〕(reason イギリス・Vernunft ドイツ)
①概念的思考の能力。実践的には感性的欲求に左右されず思慮的に行動する能力。古来、人間と動物とを区別するものとされた。「―を保つ」「―を失う」
②真偽・善悪を識別する能力。
③超自然的啓示に対し、人間の自然的な認識能力。→自然の光。
④パルメニデスやアリストテレスにおいては、絶対者を認識する能力。
⑤特にカントの用法として、ア‐プリオリな原理の能力の総称。カントは理性が認識に関わる場合を理論理性、行為の原理となる場合を実践理性と呼んだ。狭義には感性や悟性から区別され、理念によって認識を統一する能力。
⑥ヘーゲルの用法で、悟性と区別された弁証法的思考の能力。
⑦宇宙的原理。世界理性・絶対的理性などのようにいわれる。
⑧ロゴスとしての言語能力。
⇒りせい‐がいねん【理性概念】
⇒りせい‐てき【理性的】
⇒りせい‐ろん【理性論】
り‐せい【理政】
政まつりごとを治めること。治世。源平盛衰記27「百官を百王の
 りく‐れい【六礼】
①[礼記王制]士たるものの六つの大礼、すなわち冠・婚・喪・祭・郷・相見の総称。
②[儀礼士昏礼、疏]婚姻の6種の大礼、すなわち納采・問名・納吉・納徴・請期しょうき・親迎の総称。
りく‐ろ【陸路】
陸上のみち。また、陸上の交通機関を利用して行くこと。くがじ。→海路→空路
リグロイン【ligroin】
石油を蒸留して得られる液体。留出温度がセ氏70〜125度のもの。溶剤に使用。
り‐けい【理系】
理科の系統。理・工・農・医・薬などの学部を指す。↔文系
リケッチア【Rickettsia ラテン】
(最初に発見したアメリカの医学者H. T. Ricketts1871〜1910の名に因む)通常の細菌より小さく、ウイルスより大きい微生物。リケッチア目として細菌に分類される。グラム陰性の小型の球桿菌で、一部のものを除いては細胞内寄生性で、無細胞培地では増殖しない。発疹チフス・発疹熱・恙虫つつがむし病・Q熱・紅斑熱などの病原体。
リゲル【Rigel】
(足の意のアラビア語から)オリオン座のベータ(β)星。青白色の光度0.1等の星。オリオンの左足にある。
り‐けん【利剣】
①鋭利なつるぎ。
②煩悩ぼんのうを破りくだく仏智をたとえていう語。「弥陀の―」
り‐けん【利権】
利益を専有する権利。業者が公的機関などと結託して得る権益。「―がからむ」
⇒りけん‐や【利権屋】
り‐けん【理研】
理化学研究所の略称。
り‐けん【離見】
(世阿弥の用語)自己(演者)の目を離れて客観的に見ること。花鏡「見所より見る所の風姿は我が―也」
り‐げん【俚言】
①俗間のさとびたことば。
②共通語とは異なる、その地方特有のことば。土地のなまりことば。俗言。俚語。↔雅言
り‐げん【俚諺】
俗間のことわざ。民間で言いならわされてきたことわざ。
り‐げんこう【李元昊】‥カウ
西夏の初代皇帝。景宗。唐の夏州節度使の後裔。国を大夏と号し、宋・遼と対抗しながら国力の充実を図った。諡おくりなは武烈。(在位1038〜1048)(1003〜1048)
りげんしゅうらん【俚言集覧】‥シフ‥
国語辞書。26巻。太田全斎編、村田了阿ら補。「諺苑」を基礎にして江戸時代の方言・俗語・俗諺を集め、五十音図の横列順に配し、語釈を施したもの。1900年(明治33)井上頼圀よりくに・近藤瓶城みかきが増訂、通行の五十音順に改編。
りげん‐だいし【理源大師】
聖宝しょうぼうの諡号しごう。
りけん‐や【利権屋】
①利権をあさる人。
②特許的権利を得ようとする人のために、各種の仲介運動をして手数料を取る周旋屋。
⇒り‐けん【利権】
り‐こ【利子】
⇒りし。太平記8「頸を借りたる人―をつけて返すべし」
り‐こ【利己】
自分一人だけの利益を計ること。自利。主我。「―心」「―的」「―主義」↔利他
り‐ご【俚語】
(→)俚言りげん2に同じ。
り‐こう【李昂】‥カウ
(Li Ang)台湾の作家。本名、施淑端。両親とも本省人。フェミニズム文学「夫殺し」「迷いの園」「自伝の小説」など。(1952〜)
り‐こう【利口】
①たくみに言うこと。口さきのうまいこと。巧言。今昔物語集28「まことにわ君行きて―に云ひ聞せよ」
②頭がよいこと。かしこいこと。また、要領がよく抜け目がないこと。利巧。狂言、長光「さてさて―なやつちや。これはだまされまい」。「―な人」「―に立ちまわる」
③冗談じょうだんを言うこと。興言。古今著聞集16「それにも懲りず、なほ―し歩きけるほどに」
④(多く「お―」の形で)聞きわけのよいこと。「お―にしていなさい」
⇒りこう‐ぶ・る【利口ぶる】
り‐こう【利巧】‥カウ
(→)利口2に同じ。
り‐こう【里甲】‥カフ
明代の郷村統治機構。1381年制定。110戸を1里とし、そのうち10人を里長、他の100戸を甲首とし、毎年里長1人、甲首10人が服役して、租税の徴収・治安の維持などに当たった。
り‐こう【里堠】
(→)一里塚に同じ。
り‐こう【理工】
理学と工学。「―系」
り‐こう【犂耕】‥カウ
犂すきを用いた耕作、または農業。↔耨耕じょっこう
り‐こう【履行】‥カウ
①実際に行うこと。言葉どおりに実行すること。
②〔法〕債務者が債権の目的(内容)たる給付を実行すること。弁済と同義であるが、履行は債権の効力の面からいうのに対し、弁済は債権の消滅の面からいう。
⇒りこう‐ちたい【履行遅滞】
⇒りこう‐ふのう【履行不能】
り‐ごう【離合】‥ガフ
はなれたり集まったりすること。
⇒りごう‐し【離合詩】
⇒りごう‐しゅうさん【離合集散】
りごう‐し【離合詩】‥ガフ‥
漢詩の雑体詩の一種。字の偏へんや旁つくりを分けた文字を組み合わせて詩を作る文字遊び。例えば、「呂公釣磯盍口渭傍」で「呂」から「口」の字を離し、「九域有聖無土不王」で「域」から「土」の字を離して「或」とし、「口」と合わせて、「國」の字とするもの。
⇒り‐ごう【離合】
り‐こうじゅ【李光珠】‥クワウ‥
⇒イ=グヮンス
りごう‐しゅうさん【離合集散】‥ガフシフ‥
はなれたり集まったりすること。分離したり合併したりすること。「―を繰り返す」
⇒り‐ごう【離合】
り‐こうしょう【李鴻章】‥シヤウ
清末の政治家。字は少荃、号は儀叟。安徽合肥の人。曾国藩に従って太平天国の乱を平定。以来、日清戦争(下関条約)・義和団事件(北京議定書)などの外交に貢献するとともに軍隊の近代化、近代工業の育成、招商局の設立などにつとめた。直隷総督・北洋大臣・内閣大学士などを歴任。(1823〜1901)
りこう‐ちたい【履行遅滞】‥カウ‥
債務不履行の一類型。履行不能の場合を除き、債務者が履行期に債務を履行しないこと。債務者遅滞。
⇒り‐こう【履行】
りこう‐ふのう【履行不能】‥カウ‥
債務不履行の一類型。債務者の責めに帰すべき事由によって債務の履行が不可能となること。
⇒り‐こう【履行】
りこう‐ぶ・る【利口ぶる】
〔自五〕
利口らしくふるまう。
⇒り‐こう【利口】
り‐こうり【李広利】‥クワウ‥
前漢の将軍。武帝の寵妃李夫人の兄。大宛遠征を指揮した。( 〜前90)
り‐こうりん【李公麟】
北宋の画家。字は伯時。号は竜眠居士。安徽舒城の人。諸官を歴任後、竜眠山に隠棲。唐の呉道子流の白画を復活させた。(1049?〜1106)
リコーダー【recorder】
木管楽器。16〜18世紀、ヨーロッパで用いた縦笛。日本では、第二次大戦後、竹製・プラスチック製のものを主に初等教育用楽器として使用。ブロックフレーテ。
リゴーニ‐ステルン【Mario Rigoni Stern】
イタリアのネオレアリズモの作家。庶民・歴史・自然の3要素が融合した作風。作「雪の中の軍曹」「雷鳥の森」。(1921〜)
リコール【recall】
①国または地方自治体の公職者を国民または住民の意思によって罷免する制度。直接民主制の一つ。解職請求。「市長を―する」
②自動車などで、製品に欠陥がある場合、生産者が公表して、製品を回収し無料で修理すること。
り‐こくよう【李克用】
五代の後唐の実質的創始者。追号、太祖。突厥とっけつ沙陀部首長。父祖以来、唐に服属。振武節度使。黄巣の乱に唐を助け、河東節度使となる。朱全忠と政権を争って敗れ戦没したが、その子存勗そんきょくが後唐を建国。(856〜908)
りこ‐しゅぎ【利己主義】
(egoism)
①自己の利害だけを行為の規準とし、社会一般の利害を念頭に置かない考え方。主我主義。自己主義。↔利他主義。
②人間の利己心から出発して道徳の原理や観念を説明しようとする倫理学の立場。必ずしも1の意味での利己主義を主張するものではない。
りこ‐しん【利己心】
自己の利害だけを念頭に置いて、他人の迷惑を考えようとしない心。「―から出た振舞」
リコッタ【ricotta イタリア】
ホエーを加熱して作るイタリアのフレッシュ‐チーズ。料理や菓子によく使う。原料乳は牛・羊など様々で、塩を加えて熟成させたものもある。
りこ‐てき【利己的】
他人の迷惑を顧みず、自己の利益だけを追求するさま。「―な態度」
⇒りこてき‐いでんし【利己的遺伝子】
りこてき‐いでんし【利己的遺伝子】‥ヰ‥
(selfish genes)イギリスの動物行動学者ドーキンス(Richard Dawkins1941〜)による1976年の著書。「個体ではなく、遺伝子にとって有利な性質が進化する」という説を、遺伝子が利己的に振る舞っていると表現した語。
⇒りこ‐てき【利己的】
リコピン【lycopene】
分子式C40H50 カロテンの異性体。結晶性炭化水素。トマトなどの赤色色素で、優れた抗酸化作用がある。
リコリス【Licoris】
ヒガンバナ科ヒガンバナ属の球根植物数種の総称。園芸品種が多い。秋に花茎を伸ばし先端にヒガンバナに似た美花を多数放射状に咲かせる。広くはヒガンバナ属の属名。
リゴリスト【rigorist】
厳格な人。厳粛主義者。
リゴリズム【rigorism】
厳粛主義。厳格主義。
リゴレット【Rigoletto】
ヴェルディ作曲の歌劇。3幕。ユゴーの戯曲「王は楽しむ」(1832年作)に取材。1851年ヴェネツィアで初演。「女心の歌」で有名。
ヴェルディ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
りく‐れい【六礼】
①[礼記王制]士たるものの六つの大礼、すなわち冠・婚・喪・祭・郷・相見の総称。
②[儀礼士昏礼、疏]婚姻の6種の大礼、すなわち納采・問名・納吉・納徴・請期しょうき・親迎の総称。
りく‐ろ【陸路】
陸上のみち。また、陸上の交通機関を利用して行くこと。くがじ。→海路→空路
リグロイン【ligroin】
石油を蒸留して得られる液体。留出温度がセ氏70〜125度のもの。溶剤に使用。
り‐けい【理系】
理科の系統。理・工・農・医・薬などの学部を指す。↔文系
リケッチア【Rickettsia ラテン】
(最初に発見したアメリカの医学者H. T. Ricketts1871〜1910の名に因む)通常の細菌より小さく、ウイルスより大きい微生物。リケッチア目として細菌に分類される。グラム陰性の小型の球桿菌で、一部のものを除いては細胞内寄生性で、無細胞培地では増殖しない。発疹チフス・発疹熱・恙虫つつがむし病・Q熱・紅斑熱などの病原体。
リゲル【Rigel】
(足の意のアラビア語から)オリオン座のベータ(β)星。青白色の光度0.1等の星。オリオンの左足にある。
り‐けん【利剣】
①鋭利なつるぎ。
②煩悩ぼんのうを破りくだく仏智をたとえていう語。「弥陀の―」
り‐けん【利権】
利益を専有する権利。業者が公的機関などと結託して得る権益。「―がからむ」
⇒りけん‐や【利権屋】
り‐けん【理研】
理化学研究所の略称。
り‐けん【離見】
(世阿弥の用語)自己(演者)の目を離れて客観的に見ること。花鏡「見所より見る所の風姿は我が―也」
り‐げん【俚言】
①俗間のさとびたことば。
②共通語とは異なる、その地方特有のことば。土地のなまりことば。俗言。俚語。↔雅言
り‐げん【俚諺】
俗間のことわざ。民間で言いならわされてきたことわざ。
り‐げんこう【李元昊】‥カウ
西夏の初代皇帝。景宗。唐の夏州節度使の後裔。国を大夏と号し、宋・遼と対抗しながら国力の充実を図った。諡おくりなは武烈。(在位1038〜1048)(1003〜1048)
りげんしゅうらん【俚言集覧】‥シフ‥
国語辞書。26巻。太田全斎編、村田了阿ら補。「諺苑」を基礎にして江戸時代の方言・俗語・俗諺を集め、五十音図の横列順に配し、語釈を施したもの。1900年(明治33)井上頼圀よりくに・近藤瓶城みかきが増訂、通行の五十音順に改編。
りげん‐だいし【理源大師】
聖宝しょうぼうの諡号しごう。
りけん‐や【利権屋】
①利権をあさる人。
②特許的権利を得ようとする人のために、各種の仲介運動をして手数料を取る周旋屋。
⇒り‐けん【利権】
り‐こ【利子】
⇒りし。太平記8「頸を借りたる人―をつけて返すべし」
り‐こ【利己】
自分一人だけの利益を計ること。自利。主我。「―心」「―的」「―主義」↔利他
り‐ご【俚語】
(→)俚言りげん2に同じ。
り‐こう【李昂】‥カウ
(Li Ang)台湾の作家。本名、施淑端。両親とも本省人。フェミニズム文学「夫殺し」「迷いの園」「自伝の小説」など。(1952〜)
り‐こう【利口】
①たくみに言うこと。口さきのうまいこと。巧言。今昔物語集28「まことにわ君行きて―に云ひ聞せよ」
②頭がよいこと。かしこいこと。また、要領がよく抜け目がないこと。利巧。狂言、長光「さてさて―なやつちや。これはだまされまい」。「―な人」「―に立ちまわる」
③冗談じょうだんを言うこと。興言。古今著聞集16「それにも懲りず、なほ―し歩きけるほどに」
④(多く「お―」の形で)聞きわけのよいこと。「お―にしていなさい」
⇒りこう‐ぶ・る【利口ぶる】
り‐こう【利巧】‥カウ
(→)利口2に同じ。
り‐こう【里甲】‥カフ
明代の郷村統治機構。1381年制定。110戸を1里とし、そのうち10人を里長、他の100戸を甲首とし、毎年里長1人、甲首10人が服役して、租税の徴収・治安の維持などに当たった。
り‐こう【里堠】
(→)一里塚に同じ。
り‐こう【理工】
理学と工学。「―系」
り‐こう【犂耕】‥カウ
犂すきを用いた耕作、または農業。↔耨耕じょっこう
り‐こう【履行】‥カウ
①実際に行うこと。言葉どおりに実行すること。
②〔法〕債務者が債権の目的(内容)たる給付を実行すること。弁済と同義であるが、履行は債権の効力の面からいうのに対し、弁済は債権の消滅の面からいう。
⇒りこう‐ちたい【履行遅滞】
⇒りこう‐ふのう【履行不能】
り‐ごう【離合】‥ガフ
はなれたり集まったりすること。
⇒りごう‐し【離合詩】
⇒りごう‐しゅうさん【離合集散】
りごう‐し【離合詩】‥ガフ‥
漢詩の雑体詩の一種。字の偏へんや旁つくりを分けた文字を組み合わせて詩を作る文字遊び。例えば、「呂公釣磯盍口渭傍」で「呂」から「口」の字を離し、「九域有聖無土不王」で「域」から「土」の字を離して「或」とし、「口」と合わせて、「國」の字とするもの。
⇒り‐ごう【離合】
り‐こうじゅ【李光珠】‥クワウ‥
⇒イ=グヮンス
りごう‐しゅうさん【離合集散】‥ガフシフ‥
はなれたり集まったりすること。分離したり合併したりすること。「―を繰り返す」
⇒り‐ごう【離合】
り‐こうしょう【李鴻章】‥シヤウ
清末の政治家。字は少荃、号は儀叟。安徽合肥の人。曾国藩に従って太平天国の乱を平定。以来、日清戦争(下関条約)・義和団事件(北京議定書)などの外交に貢献するとともに軍隊の近代化、近代工業の育成、招商局の設立などにつとめた。直隷総督・北洋大臣・内閣大学士などを歴任。(1823〜1901)
りこう‐ちたい【履行遅滞】‥カウ‥
債務不履行の一類型。履行不能の場合を除き、債務者が履行期に債務を履行しないこと。債務者遅滞。
⇒り‐こう【履行】
りこう‐ふのう【履行不能】‥カウ‥
債務不履行の一類型。債務者の責めに帰すべき事由によって債務の履行が不可能となること。
⇒り‐こう【履行】
りこう‐ぶ・る【利口ぶる】
〔自五〕
利口らしくふるまう。
⇒り‐こう【利口】
り‐こうり【李広利】‥クワウ‥
前漢の将軍。武帝の寵妃李夫人の兄。大宛遠征を指揮した。( 〜前90)
り‐こうりん【李公麟】
北宋の画家。字は伯時。号は竜眠居士。安徽舒城の人。諸官を歴任後、竜眠山に隠棲。唐の呉道子流の白画を復活させた。(1049?〜1106)
リコーダー【recorder】
木管楽器。16〜18世紀、ヨーロッパで用いた縦笛。日本では、第二次大戦後、竹製・プラスチック製のものを主に初等教育用楽器として使用。ブロックフレーテ。
リゴーニ‐ステルン【Mario Rigoni Stern】
イタリアのネオレアリズモの作家。庶民・歴史・自然の3要素が融合した作風。作「雪の中の軍曹」「雷鳥の森」。(1921〜)
リコール【recall】
①国または地方自治体の公職者を国民または住民の意思によって罷免する制度。直接民主制の一つ。解職請求。「市長を―する」
②自動車などで、製品に欠陥がある場合、生産者が公表して、製品を回収し無料で修理すること。
り‐こくよう【李克用】
五代の後唐の実質的創始者。追号、太祖。突厥とっけつ沙陀部首長。父祖以来、唐に服属。振武節度使。黄巣の乱に唐を助け、河東節度使となる。朱全忠と政権を争って敗れ戦没したが、その子存勗そんきょくが後唐を建国。(856〜908)
りこ‐しゅぎ【利己主義】
(egoism)
①自己の利害だけを行為の規準とし、社会一般の利害を念頭に置かない考え方。主我主義。自己主義。↔利他主義。
②人間の利己心から出発して道徳の原理や観念を説明しようとする倫理学の立場。必ずしも1の意味での利己主義を主張するものではない。
りこ‐しん【利己心】
自己の利害だけを念頭に置いて、他人の迷惑を考えようとしない心。「―から出た振舞」
リコッタ【ricotta イタリア】
ホエーを加熱して作るイタリアのフレッシュ‐チーズ。料理や菓子によく使う。原料乳は牛・羊など様々で、塩を加えて熟成させたものもある。
りこ‐てき【利己的】
他人の迷惑を顧みず、自己の利益だけを追求するさま。「―な態度」
⇒りこてき‐いでんし【利己的遺伝子】
りこてき‐いでんし【利己的遺伝子】‥ヰ‥
(selfish genes)イギリスの動物行動学者ドーキンス(Richard Dawkins1941〜)による1976年の著書。「個体ではなく、遺伝子にとって有利な性質が進化する」という説を、遺伝子が利己的に振る舞っていると表現した語。
⇒りこ‐てき【利己的】
リコピン【lycopene】
分子式C40H50 カロテンの異性体。結晶性炭化水素。トマトなどの赤色色素で、優れた抗酸化作用がある。
リコリス【Licoris】
ヒガンバナ科ヒガンバナ属の球根植物数種の総称。園芸品種が多い。秋に花茎を伸ばし先端にヒガンバナに似た美花を多数放射状に咲かせる。広くはヒガンバナ属の属名。
リゴリスト【rigorist】
厳格な人。厳粛主義者。
リゴリズム【rigorism】
厳粛主義。厳格主義。
リゴレット【Rigoletto】
ヴェルディ作曲の歌劇。3幕。ユゴーの戯曲「王は楽しむ」(1832年作)に取材。1851年ヴェネツィアで初演。「女心の歌」で有名。
ヴェルディ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
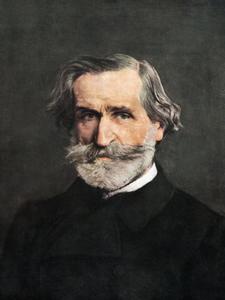 り‐こん【利根】
かしこい性質。利口。利発。特に仏教で、宗教的素質・能力がすぐれていること。謡曲、丹後物狂「この人―第一の人にて」
⇒りこん‐そう【利根草】
り‐こん【離恨】
人と離れるかなしみ。別離の恨み。
り‐こん【離婚】
夫婦が婚姻を解消すること。
⇒りこん‐とどけ【離婚届】
リコンストラクション【reconstruction】
改造。再建。
りこん‐そう【利根草】‥サウ
蓼たでの異称。狂言、鈍根草「これは―と云うて、これを食へば利根になるになあ」
⇒り‐こん【利根】
りこん‐とどけ【離婚届】
夫婦がその協議で離婚をする場合に、市区町村長に対してする届出。
⇒り‐こん【離婚】
りこん‐びょう【離魂病】‥ビヤウ
①魂が肉体から抜け出し、もう一人同じ人間が現れると考えられていた病気。浄瑠璃、蘆屋道満大内鑑「退いて分別するに―といふ病あり。俗には影の煩ひと言ひ」
②(→)夢中遊行むちゅうゆうこう症に同じ。
リコンファーム【reconfirm】
航空機の予約済み座席の再確認。
リサーチ【research】
調査。研究。「マーケット‐―」
リザーブ【reserve】
①部屋や座席を予約すること。「船室を―する」
②留保。保留。
リサール【José Rizal】
フィリピンの民族英雄。言論活動でスペインの行政・宗教政策を攻撃。フィリピン革命の勃発に際して扇動者と疑われ、銃殺。小説「我に触れるなかれ」「反逆」など。(1861〜1896)
り‐さい【里宰】
むらおさ。庄屋。里長。
り‐さい【罹災】
災害をうけること。被災。「―した人々」「―地」
り‐ざい【李在】
明代の画家。字は以政。福建莆田の人。山水画を得意とし、郭
り‐こん【利根】
かしこい性質。利口。利発。特に仏教で、宗教的素質・能力がすぐれていること。謡曲、丹後物狂「この人―第一の人にて」
⇒りこん‐そう【利根草】
り‐こん【離恨】
人と離れるかなしみ。別離の恨み。
り‐こん【離婚】
夫婦が婚姻を解消すること。
⇒りこん‐とどけ【離婚届】
リコンストラクション【reconstruction】
改造。再建。
りこん‐そう【利根草】‥サウ
蓼たでの異称。狂言、鈍根草「これは―と云うて、これを食へば利根になるになあ」
⇒り‐こん【利根】
りこん‐とどけ【離婚届】
夫婦がその協議で離婚をする場合に、市区町村長に対してする届出。
⇒り‐こん【離婚】
りこん‐びょう【離魂病】‥ビヤウ
①魂が肉体から抜け出し、もう一人同じ人間が現れると考えられていた病気。浄瑠璃、蘆屋道満大内鑑「退いて分別するに―といふ病あり。俗には影の煩ひと言ひ」
②(→)夢中遊行むちゅうゆうこう症に同じ。
リコンファーム【reconfirm】
航空機の予約済み座席の再確認。
リサーチ【research】
調査。研究。「マーケット‐―」
リザーブ【reserve】
①部屋や座席を予約すること。「船室を―する」
②留保。保留。
リサール【José Rizal】
フィリピンの民族英雄。言論活動でスペインの行政・宗教政策を攻撃。フィリピン革命の勃発に際して扇動者と疑われ、銃殺。小説「我に触れるなかれ」「反逆」など。(1861〜1896)
り‐さい【里宰】
むらおさ。庄屋。里長。
り‐さい【罹災】
災害をうけること。被災。「―した人々」「―地」
り‐ざい【李在】
明代の画家。字は以政。福建莆田の人。山水画を得意とし、郭 から馬遠・夏珪様式まで広くとりいれた。雪舟は入明中、李在らに学ぶ。
り‐ざい【理財】
貨財を有利に運用すること。経済。「―にたける」
⇒りざい‐か【理財家】
⇒りざい‐がく【理財学】
⇒りざい‐きょく【理財局】
りざい‐か【理財家】
理財の道に長じた人。経済家。北村透谷、二宮尊徳翁「翁は希代の―にして而して独得の大信仰を有し」
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐がく【理財学】
(political economyの井上哲次郎による訳語)経済学の旧称。
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐きょく【理財局】
国庫・国債・財政投融資・国有財産・たばこ塩行政その他の事項を取り扱う財務省の内局。
⇒り‐ざい【理財】
リサイクル【recycle】
資源の節約や環境汚染防止などのために、不用品・廃棄物などを再利用すること。
⇒リサイクル‐ショップ
リサイクル‐ショップ
(和製語recycle shop)中古品や不要品を買い取り、販売する店。
⇒リサイクル【recycle】
リサイタル【recital】
独唱会。独奏会。
りさく‐りょう【離作料】‥レウ
(→)作離料に同じ。
り‐さげ【利下げ】
利息を安くすること。↔利上げ
リサジュー‐ずけい【リサジュー図形】‥ヅ‥
互いに垂直な方向の単振動を合成して得られる2次元運動の軌道が描く図形。フランスの科学者リサジュー(J. A. Lissajous1822〜1880)が1855年に考案。
り‐さつ【利札】
公債証書・債券などにつける利子支払保証の札。クーポン。りふだ。
り‐ざや【利鞘】
(取引用語)売買をして得られる差額の利益。マージン。
り‐さん【離散】
ちりぢりに離れること。「一家―」
⇒りさん‐すうがく【離散数学】
⇒りさん‐てき【離散的】
り‐ざん【離山】
①ただ一つ離れた山。孤山。
②僧が寺を去ること。平家物語2「―しける僧の坊の柱に」
り‐ざん【驪山】
中国陝西省西安市臨潼区の南東郊にある山。古来、西北麓の温泉で名高く、秦の始皇帝は瘡そうを治療し、唐の玄宗は華清宮で楊貴妃に浴せしめた。
⇒りざん‐きゅう【驪山宮】
りざん‐きゅう【驪山宮】
驪山にあった華清宮の別称。
⇒り‐ざん【驪山】
りさん‐すうがく【離散数学】
(discrete mathematics)有限個の対象、あるいは連続でない対象を研究する数学の一分野。組合せ数学とほぼ同義。
⇒り‐さん【離散】
りさん‐てき【離散的】
〔理〕ある変量が特定のとびとびの値しか取りえないさま。物理量の値が離散的になることが量子力学の特色。
⇒り‐さん【離散】
り‐さんぺい【李参平】
江戸初期の陶工。文禄・慶長の役の際、朝鮮から渡来。日本名、金ヶ江三兵衛。佐賀県の有田泉山で良質の土を発見し、日本磁器の端緒を開く。( 〜1655)
り‐し【利子】
債務者が貨幣使用料として債権者に一定の割合で支払う金銭。金利。利息。「―が付く」
り‐し【李斯】
秦の宰相。楚の上蔡の人。荀子に学び、始皇帝に仕え、宰相となり、焚書を行なった。最後は讒ざんせられて刑死。( 〜前210)
り‐し【李詩】
唐の李白の詩。
り‐し【李贄】
明末の儒者。陽明学左派。字は卓吾。福建晋江の人。自ら儒教叛徒と称す。1580年官を辞し、やがて剃髪し在家居士として世俗の交わりを絶ち、著述に専心。過激な言説によって異端視され76歳で下獄、自殺。吉田松陰が獄中でその著書を愛読、抄写した。著「焚書」「蔵書」など。(1527〜1602)
り‐し【律師】
⇒りっし。源氏物語夕霧「物のけなど祓ひ捨てける―」
り‐じ【俚耳】
世間の人々の耳。俗耳。「―に入りやすい」
り‐じ【理事】
①法人の事務を処理し、これを代表し、権利を行使する機関。株式会社などでは特に取締役という。「―会」
②〔仏〕(→)事理に同じ。
りしうみ‐しほん【利子生み資本】
(→)貸付資本に同じ。
リシエ【Germaine Richier】
フランスの女性彫刻家。ブールデルの門人。独自の塑造そぞう法によって人体を表現。(1904〜1959)
りじ‐かん【理事官】‥クワン
①旧制で、内閣各省に属した官名。多くは古参判任官の優遇のためにおかれた奏任官。
②もと台湾総督府の事務官。
り‐しくん【李思訓】
唐の画家。字は建見。唐の宗室の一族。大李将軍と呼ばれた。その子の李昭道も小李将軍と称せられ、共に細密な着色山水画をよくし、金碧山水の創始者。また、北宗画の祖といわれる。(653〜718)
りじ‐こく【理事国】
国際機関の理事会の一員たる国。
りじ‐しゃ【理事者】
法人などの理事の職にある人。
り‐じせい【李自成】
明末の農民反乱の首領。飢民・流民らを組織して各地を荒らし、1644年に明を滅ぼす。北京で帝を称したが、清軍に破れ敗走し、自殺。(1606〜1645)
りし‐ちょうせん【李氏朝鮮】‥テウ‥
(→)李朝りちょう2に同じ。
り‐じちん【李時珍】
明の自然科学者。湖北蘄春の人。本草・医学に通じ、1578年「本草綱目」を完成、本草学を集大成した。(1518〜1593)
りしつき‐しほん【利子付き資本】
(→)貸付資本に同じ。
リジッド【rigid】
①厳格なこと。厳密なこと。
②固定していること。動かないこと。
リシノール‐さん【リシノール酸】
(ricinoleic acid)ヒドロキシ酸の一つ。分子式C17H32(OH)COOH オレイン酸の水素1原子を水酸基で置換したもの。グリセリン‐エステルとしてひまし油に含まれる。
りし‐ほきゅう【利子補給】‥キフ
借入金の利子支払に要する経費の一部または全部を補助すること。特定の事業・産業を援助するためなどに行う。
り‐しゅ【理趣】
事のわけ。物の道理。駿台雑話「文辞訓話を僉議して―の深きに及ばず」
り‐しゅ【離朱】
中国古伝説上の人物。百歩離れた所からでも毛の先が見えるほど視力がすぐれていたと伝えられる。離婁りろう。
り‐しゅう【履修】‥シウ
きめられた学科・課程などを習い修めること。「全課程を―する」「―科目」
り‐しゅう【離愁】‥シウ
別離のかなしみ。
りしゅ‐きょう【理趣経】‥キヤウ
仏典の一つ。不空の訳。1巻。真言宗の常用経典。大日如来が金剛薩埵さったのために般若理趣の自性清浄なることを説いたもの。般若理趣経。
リシュリュー【Armand Jean du Plessis, Duc de Richelieu】
フランスの政治家・枢機卿。1624〜42年ルイ13世の宰相。反王権的な貴族やユグノーの反乱を抑え、中央集権制と絶対王政の確立に努め、外ではスペインと抗争、三十年戦争に介入。アカデミー‐フランセーズを創立。(1585〜1642)
り‐じゅん【利潤】
①利益。もうけ。
②〔経〕(profit)企業の総売上額から生産費を控除した余剰で、企業家の所得となるもの。生産過程で生みだされる剰余価値の転化した形態。
⇒りじゅん‐ぶんぱい‐せいど【利潤分配制度】
⇒りじゅん‐りつ【利潤率】
り‐しゅんしん【李舜臣】
(Yi Sun-shin)朝鮮、李朝中期の水軍の将。亀甲船をつくり、秀吉による日本の侵攻軍を破った。のち戦死。救国の英雄的将軍とたたえられる。イ=スンシン。(1545〜1598)
りじゅん‐ぶんぱい‐せいど【利潤分配制度】
経営参加の一形態。利潤の一部を従業員に分配することによって、勤労意欲の向上を期待する制度。
⇒り‐じゅん【利潤】
りじゅん‐りつ【利潤率】
資本に対する利潤の割合。総資本で剰余価値を割った比率。
⇒り‐じゅん【利潤】
り‐じょ【犂鋤】
からすきとくわ。農具。また、すきやくわで耕地をたがやすこと。
り‐しょう【利生】‥シヤウ
〔仏〕仏が衆生しゅじょうを利益りやくすること。また、その利益。仏の冥加。利物りもつ。今昔物語集1「王宮を出でて―の道に入れり」
⇒りしょう‐おとこ【利生男】
⇒りしょう‐とう【利生塔】
⇒りしょう‐ほうべん【利生方便】
り‐しょう【理性】‥シヤウ
〔仏〕一切存在の本性。真如。法性。
り‐しょう【離生】‥シヤウ
〔仏〕生死を離れること。
り‐しょう【離床】‥シヤウ
ねどこを離れること。起床。
り‐しょう【離昇】
航空機が空中に浮揚し始めること。
り‐しょう【離礁】‥セウ
暗礁に乗り上げた船が暗礁を離れて浮かぶこと。
り‐しょういん【李商隠】‥シヤウ‥
晩唐の詩人。字は義山。懐州河内(河南沁陽)の人。生涯を落魄の中に送る。典故を多用して修辞に技巧を凝らす詩風は、宋初の西崑体せいこんたいの祖となる。著「李義山詩集」「樊南文集」。(812?〜858)
りしょういん‐りゅう【理性院流】‥シヤウヰンリウ
真言宗の事相の一派。醍醐理性院の賢覚を祖とし、京都市伏見区の理性院を本寺とする。小野六流・醍醐三流の一つ。
りしょう‐おとこ【利生男】‥シヤウヲトコ
利生を受けた男。幸福な男。
⇒り‐しょう【利生】
りしょう‐とう【利生塔】‥シヤウタフ
「安国寺あんこくじ」参照。
⇒り‐しょう【利生】
り‐しょうばん【李承晩】
⇒イ=スンマン。
⇒りしょうばん‐ライン【李承晩ライン】
りしょうばん‐ライン【李承晩ライン】
李承晩が1952年に発した海洋主権宣言において設定された漁船立入禁止線。済州島付近から対馬海峡にわたる漁場での日本の漁船の操業が禁止された。65年日韓漁業協定の成立とともに撤廃。
⇒り‐しょうばん【李承晩】
りしょう‐ほうべん【利生方便】‥シヤウハウ‥
衆生を利益りやくする仏の巧みなてだて。太平記26「―を施し給ひし天神の社壇」
⇒り‐しょう【利生】
り‐しょく【利殖】
利子または利益を得て財産の増殖を図ること。「―の才にたける」
り‐しょく【離職】
①職務から離れること。
②職業から離れること。失業。
りしり【利尻】
北海道北部、稚内わっかない市の南西方40キロメートル、礼文れぶん島と並ぶ日本海中の火山島。ウニ・コンブを産する。
利尻岳
撮影:山梨勝弘
から馬遠・夏珪様式まで広くとりいれた。雪舟は入明中、李在らに学ぶ。
り‐ざい【理財】
貨財を有利に運用すること。経済。「―にたける」
⇒りざい‐か【理財家】
⇒りざい‐がく【理財学】
⇒りざい‐きょく【理財局】
りざい‐か【理財家】
理財の道に長じた人。経済家。北村透谷、二宮尊徳翁「翁は希代の―にして而して独得の大信仰を有し」
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐がく【理財学】
(political economyの井上哲次郎による訳語)経済学の旧称。
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐きょく【理財局】
国庫・国債・財政投融資・国有財産・たばこ塩行政その他の事項を取り扱う財務省の内局。
⇒り‐ざい【理財】
リサイクル【recycle】
資源の節約や環境汚染防止などのために、不用品・廃棄物などを再利用すること。
⇒リサイクル‐ショップ
リサイクル‐ショップ
(和製語recycle shop)中古品や不要品を買い取り、販売する店。
⇒リサイクル【recycle】
リサイタル【recital】
独唱会。独奏会。
りさく‐りょう【離作料】‥レウ
(→)作離料に同じ。
り‐さげ【利下げ】
利息を安くすること。↔利上げ
リサジュー‐ずけい【リサジュー図形】‥ヅ‥
互いに垂直な方向の単振動を合成して得られる2次元運動の軌道が描く図形。フランスの科学者リサジュー(J. A. Lissajous1822〜1880)が1855年に考案。
り‐さつ【利札】
公債証書・債券などにつける利子支払保証の札。クーポン。りふだ。
り‐ざや【利鞘】
(取引用語)売買をして得られる差額の利益。マージン。
り‐さん【離散】
ちりぢりに離れること。「一家―」
⇒りさん‐すうがく【離散数学】
⇒りさん‐てき【離散的】
り‐ざん【離山】
①ただ一つ離れた山。孤山。
②僧が寺を去ること。平家物語2「―しける僧の坊の柱に」
り‐ざん【驪山】
中国陝西省西安市臨潼区の南東郊にある山。古来、西北麓の温泉で名高く、秦の始皇帝は瘡そうを治療し、唐の玄宗は華清宮で楊貴妃に浴せしめた。
⇒りざん‐きゅう【驪山宮】
りざん‐きゅう【驪山宮】
驪山にあった華清宮の別称。
⇒り‐ざん【驪山】
りさん‐すうがく【離散数学】
(discrete mathematics)有限個の対象、あるいは連続でない対象を研究する数学の一分野。組合せ数学とほぼ同義。
⇒り‐さん【離散】
りさん‐てき【離散的】
〔理〕ある変量が特定のとびとびの値しか取りえないさま。物理量の値が離散的になることが量子力学の特色。
⇒り‐さん【離散】
り‐さんぺい【李参平】
江戸初期の陶工。文禄・慶長の役の際、朝鮮から渡来。日本名、金ヶ江三兵衛。佐賀県の有田泉山で良質の土を発見し、日本磁器の端緒を開く。( 〜1655)
り‐し【利子】
債務者が貨幣使用料として債権者に一定の割合で支払う金銭。金利。利息。「―が付く」
り‐し【李斯】
秦の宰相。楚の上蔡の人。荀子に学び、始皇帝に仕え、宰相となり、焚書を行なった。最後は讒ざんせられて刑死。( 〜前210)
り‐し【李詩】
唐の李白の詩。
り‐し【李贄】
明末の儒者。陽明学左派。字は卓吾。福建晋江の人。自ら儒教叛徒と称す。1580年官を辞し、やがて剃髪し在家居士として世俗の交わりを絶ち、著述に専心。過激な言説によって異端視され76歳で下獄、自殺。吉田松陰が獄中でその著書を愛読、抄写した。著「焚書」「蔵書」など。(1527〜1602)
り‐し【律師】
⇒りっし。源氏物語夕霧「物のけなど祓ひ捨てける―」
り‐じ【俚耳】
世間の人々の耳。俗耳。「―に入りやすい」
り‐じ【理事】
①法人の事務を処理し、これを代表し、権利を行使する機関。株式会社などでは特に取締役という。「―会」
②〔仏〕(→)事理に同じ。
りしうみ‐しほん【利子生み資本】
(→)貸付資本に同じ。
リシエ【Germaine Richier】
フランスの女性彫刻家。ブールデルの門人。独自の塑造そぞう法によって人体を表現。(1904〜1959)
りじ‐かん【理事官】‥クワン
①旧制で、内閣各省に属した官名。多くは古参判任官の優遇のためにおかれた奏任官。
②もと台湾総督府の事務官。
り‐しくん【李思訓】
唐の画家。字は建見。唐の宗室の一族。大李将軍と呼ばれた。その子の李昭道も小李将軍と称せられ、共に細密な着色山水画をよくし、金碧山水の創始者。また、北宗画の祖といわれる。(653〜718)
りじ‐こく【理事国】
国際機関の理事会の一員たる国。
りじ‐しゃ【理事者】
法人などの理事の職にある人。
り‐じせい【李自成】
明末の農民反乱の首領。飢民・流民らを組織して各地を荒らし、1644年に明を滅ぼす。北京で帝を称したが、清軍に破れ敗走し、自殺。(1606〜1645)
りし‐ちょうせん【李氏朝鮮】‥テウ‥
(→)李朝りちょう2に同じ。
り‐じちん【李時珍】
明の自然科学者。湖北蘄春の人。本草・医学に通じ、1578年「本草綱目」を完成、本草学を集大成した。(1518〜1593)
りしつき‐しほん【利子付き資本】
(→)貸付資本に同じ。
リジッド【rigid】
①厳格なこと。厳密なこと。
②固定していること。動かないこと。
リシノール‐さん【リシノール酸】
(ricinoleic acid)ヒドロキシ酸の一つ。分子式C17H32(OH)COOH オレイン酸の水素1原子を水酸基で置換したもの。グリセリン‐エステルとしてひまし油に含まれる。
りし‐ほきゅう【利子補給】‥キフ
借入金の利子支払に要する経費の一部または全部を補助すること。特定の事業・産業を援助するためなどに行う。
り‐しゅ【理趣】
事のわけ。物の道理。駿台雑話「文辞訓話を僉議して―の深きに及ばず」
り‐しゅ【離朱】
中国古伝説上の人物。百歩離れた所からでも毛の先が見えるほど視力がすぐれていたと伝えられる。離婁りろう。
り‐しゅう【履修】‥シウ
きめられた学科・課程などを習い修めること。「全課程を―する」「―科目」
り‐しゅう【離愁】‥シウ
別離のかなしみ。
りしゅ‐きょう【理趣経】‥キヤウ
仏典の一つ。不空の訳。1巻。真言宗の常用経典。大日如来が金剛薩埵さったのために般若理趣の自性清浄なることを説いたもの。般若理趣経。
リシュリュー【Armand Jean du Plessis, Duc de Richelieu】
フランスの政治家・枢機卿。1624〜42年ルイ13世の宰相。反王権的な貴族やユグノーの反乱を抑え、中央集権制と絶対王政の確立に努め、外ではスペインと抗争、三十年戦争に介入。アカデミー‐フランセーズを創立。(1585〜1642)
り‐じゅん【利潤】
①利益。もうけ。
②〔経〕(profit)企業の総売上額から生産費を控除した余剰で、企業家の所得となるもの。生産過程で生みだされる剰余価値の転化した形態。
⇒りじゅん‐ぶんぱい‐せいど【利潤分配制度】
⇒りじゅん‐りつ【利潤率】
り‐しゅんしん【李舜臣】
(Yi Sun-shin)朝鮮、李朝中期の水軍の将。亀甲船をつくり、秀吉による日本の侵攻軍を破った。のち戦死。救国の英雄的将軍とたたえられる。イ=スンシン。(1545〜1598)
りじゅん‐ぶんぱい‐せいど【利潤分配制度】
経営参加の一形態。利潤の一部を従業員に分配することによって、勤労意欲の向上を期待する制度。
⇒り‐じゅん【利潤】
りじゅん‐りつ【利潤率】
資本に対する利潤の割合。総資本で剰余価値を割った比率。
⇒り‐じゅん【利潤】
り‐じょ【犂鋤】
からすきとくわ。農具。また、すきやくわで耕地をたがやすこと。
り‐しょう【利生】‥シヤウ
〔仏〕仏が衆生しゅじょうを利益りやくすること。また、その利益。仏の冥加。利物りもつ。今昔物語集1「王宮を出でて―の道に入れり」
⇒りしょう‐おとこ【利生男】
⇒りしょう‐とう【利生塔】
⇒りしょう‐ほうべん【利生方便】
り‐しょう【理性】‥シヤウ
〔仏〕一切存在の本性。真如。法性。
り‐しょう【離生】‥シヤウ
〔仏〕生死を離れること。
り‐しょう【離床】‥シヤウ
ねどこを離れること。起床。
り‐しょう【離昇】
航空機が空中に浮揚し始めること。
り‐しょう【離礁】‥セウ
暗礁に乗り上げた船が暗礁を離れて浮かぶこと。
り‐しょういん【李商隠】‥シヤウ‥
晩唐の詩人。字は義山。懐州河内(河南沁陽)の人。生涯を落魄の中に送る。典故を多用して修辞に技巧を凝らす詩風は、宋初の西崑体せいこんたいの祖となる。著「李義山詩集」「樊南文集」。(812?〜858)
りしょういん‐りゅう【理性院流】‥シヤウヰンリウ
真言宗の事相の一派。醍醐理性院の賢覚を祖とし、京都市伏見区の理性院を本寺とする。小野六流・醍醐三流の一つ。
りしょう‐おとこ【利生男】‥シヤウヲトコ
利生を受けた男。幸福な男。
⇒り‐しょう【利生】
りしょう‐とう【利生塔】‥シヤウタフ
「安国寺あんこくじ」参照。
⇒り‐しょう【利生】
り‐しょうばん【李承晩】
⇒イ=スンマン。
⇒りしょうばん‐ライン【李承晩ライン】
りしょうばん‐ライン【李承晩ライン】
李承晩が1952年に発した海洋主権宣言において設定された漁船立入禁止線。済州島付近から対馬海峡にわたる漁場での日本の漁船の操業が禁止された。65年日韓漁業協定の成立とともに撤廃。
⇒り‐しょうばん【李承晩】
りしょう‐ほうべん【利生方便】‥シヤウハウ‥
衆生を利益りやくする仏の巧みなてだて。太平記26「―を施し給ひし天神の社壇」
⇒り‐しょう【利生】
り‐しょく【利殖】
利子または利益を得て財産の増殖を図ること。「―の才にたける」
り‐しょく【離職】
①職務から離れること。
②職業から離れること。失業。
りしり【利尻】
北海道北部、稚内わっかない市の南西方40キロメートル、礼文れぶん島と並ぶ日本海中の火山島。ウニ・コンブを産する。
利尻岳
撮影:山梨勝弘
 利尻島
撮影:関戸 勇
利尻島
撮影:関戸 勇
 ⇒りしり‐こんぶ【利尻昆布】
⇒りしり‐ざん【利尻山】
⇒りしり‐れぶん‐サロベツ‐こくりつこうえん【利尻礼文サロベツ国立公園】
りしり‐こんぶ【利尻昆布】
褐藻コンブ科の一種。帯状、黒褐色。長さ3メートルに達する。利尻・礼文両島付近を主産地に、日本海北部・オホーツク海などに分布。乾して食用。
⇒りしり【利尻】
りしり‐ざん【利尻山】
利尻島を形成する円錐状成層火山。標高1721メートル。利尻富士。
⇒りしり【利尻】
りし‐りつ【利子率】
元金に対する利子の割合。
りしり‐れぶん‐サロベツ‐こくりつこうえん【利尻礼文サロベツ国立公園】‥ヱン
利尻・礼文両島および対岸のサロベツ原野を中心とする国立公園。高山植物・湿原・海食崖が特色。
⇒りしり【利尻】
り‐しん【離心】
①そむき離れる心。また、そむくこと。「主君に―する」
②中心から離れていること。
⇒りしん‐えん【離心円】
⇒りしん‐りつ【離心率】
リシン【lysine】
必須アミノ酸の一つ。ほとんどの蛋白質の成分で、特にヒストン・アルブミン・筋肉蛋白質などに多い。食物に添加して栄養価を高めるのに用いる。リジン。ライシン。
リシン【ricin】
トウゴマの種子などに含まれる糖蛋白質。細胞のリボソームに作用し、蛋白質合成を阻害し、微量で猛毒。リチン。
り‐じん【吏人】
役人。官吏。公吏。
り‐じん【利刃】
よく切れる刀。
り‐じん【里人】
村の人。さとびと。
りしん‐えん【離心円】‥ヱン
(eccentric circle)天動説で、惑星の動きをより精確に説明するために想定された、地球から離れたところにある点を中心とする円。惑星はその上を周転するとされた。プトレマイオスが提唱。→周転円。
⇒り‐しん【離心】
りじん‐しょう【離人症】‥シヤウ
自己・他人・外部世界の具体的な存在感・生命感が失われ、対象は完全に知覚しながらも、それらと自己との有機的なつながりを実感しえない精神状態。人格感喪失。有情感喪失。
りしん‐りつ【離心率】
〔数〕円錐曲線(二次曲線)の持つ定数の一つ。離心率が1より小さいか、1に等しいか、1より大きいかに従い、楕円・放物線・双曲線となる。円の離心率は0と定める。心差率。→円錐曲線
⇒り‐しん【離心】
りしん‐ろん【理神論】
〔宗〕(deism)世界の根源として神の存在を認めはするが、これを人格的な主宰者とは考えず、従って奇跡や啓示の存在を否定する説。啓示宗教に対する理性宗教。17〜18世紀のヨーロッパに現れ、代表者はイギリスのトーランド(John Toland1670〜1722)・ヴォルテール・レッシングら。自然神論。自然神教。↔有神論↔汎神論
り‐す【栗鼠】
(リスは漢字の音読み)ネズミ目リス科の哺乳類の総称。また特にニホンリスのことで、頭胴長20センチメートル、尾長15センチメートルほど。夏毛は赤褐色、冬毛は黄褐色で、腹は白い。森林に生息し、木の実や木の葉、昆虫などを食べる。小枝や葉を集め、枝の間に巣を作る。日本特産。北海道には類似種のキタリスがいる。また各地で、より大形のタイワンリスが野生化。キネズミ。〈日葡辞書〉
タイワンリス
提供:東京動物園協会
⇒りしり‐こんぶ【利尻昆布】
⇒りしり‐ざん【利尻山】
⇒りしり‐れぶん‐サロベツ‐こくりつこうえん【利尻礼文サロベツ国立公園】
りしり‐こんぶ【利尻昆布】
褐藻コンブ科の一種。帯状、黒褐色。長さ3メートルに達する。利尻・礼文両島付近を主産地に、日本海北部・オホーツク海などに分布。乾して食用。
⇒りしり【利尻】
りしり‐ざん【利尻山】
利尻島を形成する円錐状成層火山。標高1721メートル。利尻富士。
⇒りしり【利尻】
りし‐りつ【利子率】
元金に対する利子の割合。
りしり‐れぶん‐サロベツ‐こくりつこうえん【利尻礼文サロベツ国立公園】‥ヱン
利尻・礼文両島および対岸のサロベツ原野を中心とする国立公園。高山植物・湿原・海食崖が特色。
⇒りしり【利尻】
り‐しん【離心】
①そむき離れる心。また、そむくこと。「主君に―する」
②中心から離れていること。
⇒りしん‐えん【離心円】
⇒りしん‐りつ【離心率】
リシン【lysine】
必須アミノ酸の一つ。ほとんどの蛋白質の成分で、特にヒストン・アルブミン・筋肉蛋白質などに多い。食物に添加して栄養価を高めるのに用いる。リジン。ライシン。
リシン【ricin】
トウゴマの種子などに含まれる糖蛋白質。細胞のリボソームに作用し、蛋白質合成を阻害し、微量で猛毒。リチン。
り‐じん【吏人】
役人。官吏。公吏。
り‐じん【利刃】
よく切れる刀。
り‐じん【里人】
村の人。さとびと。
りしん‐えん【離心円】‥ヱン
(eccentric circle)天動説で、惑星の動きをより精確に説明するために想定された、地球から離れたところにある点を中心とする円。惑星はその上を周転するとされた。プトレマイオスが提唱。→周転円。
⇒り‐しん【離心】
りじん‐しょう【離人症】‥シヤウ
自己・他人・外部世界の具体的な存在感・生命感が失われ、対象は完全に知覚しながらも、それらと自己との有機的なつながりを実感しえない精神状態。人格感喪失。有情感喪失。
りしん‐りつ【離心率】
〔数〕円錐曲線(二次曲線)の持つ定数の一つ。離心率が1より小さいか、1に等しいか、1より大きいかに従い、楕円・放物線・双曲線となる。円の離心率は0と定める。心差率。→円錐曲線
⇒り‐しん【離心】
りしん‐ろん【理神論】
〔宗〕(deism)世界の根源として神の存在を認めはするが、これを人格的な主宰者とは考えず、従って奇跡や啓示の存在を否定する説。啓示宗教に対する理性宗教。17〜18世紀のヨーロッパに現れ、代表者はイギリスのトーランド(John Toland1670〜1722)・ヴォルテール・レッシングら。自然神論。自然神教。↔有神論↔汎神論
り‐す【栗鼠】
(リスは漢字の音読み)ネズミ目リス科の哺乳類の総称。また特にニホンリスのことで、頭胴長20センチメートル、尾長15センチメートルほど。夏毛は赤褐色、冬毛は黄褐色で、腹は白い。森林に生息し、木の実や木の葉、昆虫などを食べる。小枝や葉を集め、枝の間に巣を作る。日本特産。北海道には類似種のキタリスがいる。また各地で、より大形のタイワンリスが野生化。キネズミ。〈日葡辞書〉
タイワンリス
提供:東京動物園協会
 ニホンリス
提供:東京動物園協会
ニホンリス
提供:東京動物園協会
 り‐す【離洲】
洲に乗り上げた船が、その洲を離れて浮かぶこと。
リス【Riss ドイツ】
(登山用語)岩の割れ目。通常、ハーケンが打てる程度の細いものをいう。
り・す【理す】
〔他サ変〕
ととのえる。また、おさめる。太平記23「民を安んじ国を―・するを本となす」
リスアニア【Lithuania】
⇒リトアニア
り‐すい【利水】
①水をよく流通させること。また、水をよく利用すること。
②漢方で、体内の水の偏在を改善すること。
⇒りすい‐ざい【利水剤】
り‐すい【離水】
水上飛行機が水面から飛び上がること。↔着水。
⇒りすい‐かいがん【離水海岸】
りすい‐かいがん【離水海岸】
地盤の隆起または海水面の下降によって陸地が相対的に海面より上昇した海岸。
⇒り‐すい【離水】
りすい‐ざい【利水剤】
利水2の目的で用いる漢方方剤。五苓散・真武湯など。
⇒り‐すい【利水】
り‐すう【里数】
道程を里ではかった数。
り‐すう【理数】
理科と数学。
⇒りすう‐か【理数科】
りすう‐か【理数科】‥クワ
①理科と数学とを統合した教科。旧制の国民学校では算数・理科、中等学校では数学・物象・生物の各科目に分かれていた。
②高等学校の学科の一つ。
⇒り‐すう【理数】
リスキー【risky】
危険を伴うさま。冒険的なこと。
リスク【RISC】
(reduced instruction set computer)CPUを制御する基本命令を簡素化し、直接ハードウェアで機械語の処理を行うコンピューター。CISC(シスク)に比べて高速で演算処理を行える。
リスク【risk】
①危険。「―を伴う」
②保険者の担保責任。被保険物。
⇒リスク‐しゃかい【リスク社会】
⇒リスク‐プレミアム【risk premium】
⇒リスク‐ぶんせき【リスク分析】
⇒リスク‐ヘッジ
⇒リスク‐マネージメント【risk management】
リスク‐しゃかい【リスク社会】‥クワイ
産業と科学が環境や健康に与えるリスクの負担をめぐる争いが主要な対立点となった、後期の産業社会。ドイツの社会学者ベック(Ulrich Beck1944〜)の用語。
⇒リスク【risk】
リスク‐プレミアム【risk premium】
リスクの大きい資産の収益率が、長期国債など安全な資産の収益率を上回る分。
⇒リスク【risk】
リスク‐ぶんせき【リスク分析】
リスクを低減するための方法論。リスクの科学的な判定(リスク評価)、具体的な措置(リスク管理)、情報・意見交換(リスク‐コミュニケーション)から構成される。リスク学。特に、リスク評価での危険度分析をいう。
⇒リスク【risk】
リスク‐ヘッジ
(和製語risk hedge)〔経〕(→)ヘッジに同じ。
⇒リスク【risk】
リスク‐マネージメント【risk management】
企業活動に伴うさまざまな危険を最小限に抑える管理運営方法。RM
⇒リスク【risk】
リスケジューリング【re-scheduling】
〔経〕債務国からの要請を受けて、既存の返済計画の見直し、返済額の減額などによって債務返済の繰延べを行うこと。リスケ。
りす‐ざる【栗鼠猿】
オマキザル科リスザル属のサル3〜5種の総称。また、そのうちのコモンリスザルを指す。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。毛色は明るい褐色で、顔から胸にかけて白い。アマゾン流域からコロンビアの森林に分布し、集団で生活。ペット・実験動物としても飼育。
リスザル
提供:東京動物園協会
り‐す【離洲】
洲に乗り上げた船が、その洲を離れて浮かぶこと。
リス【Riss ドイツ】
(登山用語)岩の割れ目。通常、ハーケンが打てる程度の細いものをいう。
り・す【理す】
〔他サ変〕
ととのえる。また、おさめる。太平記23「民を安んじ国を―・するを本となす」
リスアニア【Lithuania】
⇒リトアニア
り‐すい【利水】
①水をよく流通させること。また、水をよく利用すること。
②漢方で、体内の水の偏在を改善すること。
⇒りすい‐ざい【利水剤】
り‐すい【離水】
水上飛行機が水面から飛び上がること。↔着水。
⇒りすい‐かいがん【離水海岸】
りすい‐かいがん【離水海岸】
地盤の隆起または海水面の下降によって陸地が相対的に海面より上昇した海岸。
⇒り‐すい【離水】
りすい‐ざい【利水剤】
利水2の目的で用いる漢方方剤。五苓散・真武湯など。
⇒り‐すい【利水】
り‐すう【里数】
道程を里ではかった数。
り‐すう【理数】
理科と数学。
⇒りすう‐か【理数科】
りすう‐か【理数科】‥クワ
①理科と数学とを統合した教科。旧制の国民学校では算数・理科、中等学校では数学・物象・生物の各科目に分かれていた。
②高等学校の学科の一つ。
⇒り‐すう【理数】
リスキー【risky】
危険を伴うさま。冒険的なこと。
リスク【RISC】
(reduced instruction set computer)CPUを制御する基本命令を簡素化し、直接ハードウェアで機械語の処理を行うコンピューター。CISC(シスク)に比べて高速で演算処理を行える。
リスク【risk】
①危険。「―を伴う」
②保険者の担保責任。被保険物。
⇒リスク‐しゃかい【リスク社会】
⇒リスク‐プレミアム【risk premium】
⇒リスク‐ぶんせき【リスク分析】
⇒リスク‐ヘッジ
⇒リスク‐マネージメント【risk management】
リスク‐しゃかい【リスク社会】‥クワイ
産業と科学が環境や健康に与えるリスクの負担をめぐる争いが主要な対立点となった、後期の産業社会。ドイツの社会学者ベック(Ulrich Beck1944〜)の用語。
⇒リスク【risk】
リスク‐プレミアム【risk premium】
リスクの大きい資産の収益率が、長期国債など安全な資産の収益率を上回る分。
⇒リスク【risk】
リスク‐ぶんせき【リスク分析】
リスクを低減するための方法論。リスクの科学的な判定(リスク評価)、具体的な措置(リスク管理)、情報・意見交換(リスク‐コミュニケーション)から構成される。リスク学。特に、リスク評価での危険度分析をいう。
⇒リスク【risk】
リスク‐ヘッジ
(和製語risk hedge)〔経〕(→)ヘッジに同じ。
⇒リスク【risk】
リスク‐マネージメント【risk management】
企業活動に伴うさまざまな危険を最小限に抑える管理運営方法。RM
⇒リスク【risk】
リスケジューリング【re-scheduling】
〔経〕債務国からの要請を受けて、既存の返済計画の見直し、返済額の減額などによって債務返済の繰延べを行うこと。リスケ。
りす‐ざる【栗鼠猿】
オマキザル科リスザル属のサル3〜5種の総称。また、そのうちのコモンリスザルを指す。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。毛色は明るい褐色で、顔から胸にかけて白い。アマゾン流域からコロンビアの森林に分布し、集団で生活。ペット・実験動物としても飼育。
リスザル
提供:東京動物園協会
 リスター【Joseph Lister】
イギリスの外科医。石炭酸溶液による消毒法の開発で近代外科手術に貢献。(1827〜1912)
リスト【list】
目録。名簿。一覧表。
⇒リスト‐アップ
リスト【wrist】
手首。特にスポーツでいう。「―の強いバッター」
⇒リスト‐カット
⇒リスト‐バンド【wristband】
リスト【Friedrich List】
ドイツの経済学者。歴史学派の先駆。経済発展段階説を展開し、国民主義の立場から保護貿易政策を主張。主著「経済学の国民的体系」。(1789〜1846)
リスト【Franz Liszt】
ハンガリーの作曲家・ピアノ奏者。標題音楽でベルリオーズを継承し、交響詩の形式を確立。ピアノ演奏では超絶技巧を誇り、その表現能力を拡大。作「ファウスト交響曲」、交響詩「前奏曲」、ピアノ協奏曲など。(1811〜1886)
リスト
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
リスター【Joseph Lister】
イギリスの外科医。石炭酸溶液による消毒法の開発で近代外科手術に貢献。(1827〜1912)
リスト【list】
目録。名簿。一覧表。
⇒リスト‐アップ
リスト【wrist】
手首。特にスポーツでいう。「―の強いバッター」
⇒リスト‐カット
⇒リスト‐バンド【wristband】
リスト【Friedrich List】
ドイツの経済学者。歴史学派の先駆。経済発展段階説を展開し、国民主義の立場から保護貿易政策を主張。主著「経済学の国民的体系」。(1789〜1846)
リスト【Franz Liszt】
ハンガリーの作曲家・ピアノ奏者。標題音楽でベルリオーズを継承し、交響詩の形式を確立。ピアノ演奏では超絶技巧を誇り、その表現能力を拡大。作「ファウスト交響曲」、交響詩「前奏曲」、ピアノ協奏曲など。(1811〜1886)
リスト
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
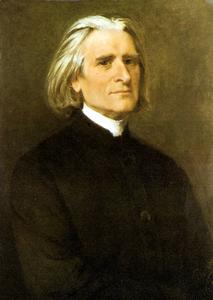 →愛の夢
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
リスト【Franz von Liszt】
ドイツの刑法学者。作曲家リストの従弟。ベルリン大学教授。近代刑法学の確立に貢献。著「ドイツ刑法教科書」など。(1851〜1919)
リスト‐アップ
(和製語list up)多くの事物の中から基準に合うものを選び出すこと。また、その一覧表を作ること。
⇒リスト【list】
リスト‐カット
(wrist-cutting syndrome)手首自傷症候群。刃物で自分の手首の内側や腕などを切創する自傷行為。
⇒リスト【wrist】
リスト‐バンド【wristband】
手首の保護と汗ふきとをかねて、運動時に手首にはめる布製の輪。
⇒リスト【wrist】
リストラ
(→)リストラクチュアリング2の略。
リストラクチュアリング【restructuring】
〔経〕(再建の意)
①短期債務を長期債務で置き換える債務の再構成。
②企業の買収・合併、不採算部門の整理、人員削減などの手段によって、事業内容を再編成すること。リストラ。
リストロサウルス【Lystrosaurus ラテン】
単弓類のうち比較的進歩した仲間の一つ。三畳紀前期に生息。水陸両生で、植物食性。体長約1メートル。化石はアフリカ・南極・インド・中国・東欧などで発見。
リスナー【listener】
ラジオの聴取者。
リスプ【LISP】
(list processor)コンピューターのプログラム言語の一種。人工知能・数式処理などの記号処理の分野で広く用いる。
リスボン【Lisbon】
ポルトガル共和国の首都。タホ川河口の港湾都市。1256年コインブラより遷都。旧王宮・美術博物館などがある。人口53万5千(2004)。ポルトガル語名リジュボア。
リスボン(1)
撮影:田沼武能
→愛の夢
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
リスト【Franz von Liszt】
ドイツの刑法学者。作曲家リストの従弟。ベルリン大学教授。近代刑法学の確立に貢献。著「ドイツ刑法教科書」など。(1851〜1919)
リスト‐アップ
(和製語list up)多くの事物の中から基準に合うものを選び出すこと。また、その一覧表を作ること。
⇒リスト【list】
リスト‐カット
(wrist-cutting syndrome)手首自傷症候群。刃物で自分の手首の内側や腕などを切創する自傷行為。
⇒リスト【wrist】
リスト‐バンド【wristband】
手首の保護と汗ふきとをかねて、運動時に手首にはめる布製の輪。
⇒リスト【wrist】
リストラ
(→)リストラクチュアリング2の略。
リストラクチュアリング【restructuring】
〔経〕(再建の意)
①短期債務を長期債務で置き換える債務の再構成。
②企業の買収・合併、不採算部門の整理、人員削減などの手段によって、事業内容を再編成すること。リストラ。
リストロサウルス【Lystrosaurus ラテン】
単弓類のうち比較的進歩した仲間の一つ。三畳紀前期に生息。水陸両生で、植物食性。体長約1メートル。化石はアフリカ・南極・インド・中国・東欧などで発見。
リスナー【listener】
ラジオの聴取者。
リスプ【LISP】
(list processor)コンピューターのプログラム言語の一種。人工知能・数式処理などの記号処理の分野で広く用いる。
リスボン【Lisbon】
ポルトガル共和国の首都。タホ川河口の港湾都市。1256年コインブラより遷都。旧王宮・美術博物館などがある。人口53万5千(2004)。ポルトガル語名リジュボア。
リスボン(1)
撮影:田沼武能
 リスボン(2)
撮影:小松義夫
リスボン(2)
撮影:小松義夫
 ⇒リスボン‐じょうやく【リスボン条約】
リスボン‐じょうやく【リスボン条約】‥デウ‥
1887年ポルトガルと中国との間に結ばれた、澳門マカオの永代租借・最恵国待遇に関する条約。
⇒リスボン【Lisbon】
リズミカル【rhythmical】
リズムのあるさま。調子のよいさま。律動的。音律的。「―な運動」
リズム【rhythm】
①周期的な動き。進行の調子。律動。「―に乗る」「生活の―が狂う」
②詩の韻律。
③音楽におけるあらゆる時間的な諸関係。西洋音楽では旋律・和声と並んで基本要素の一つで、一般に音量・音高・音色などと結びついてアクセントが生じ、それが周期的に現れると拍子が成立する。拍子がなくてもリズムは存在する。節奏。
⇒リズム‐アンド‐ブルース【rhythm and blues】
⇒リズム‐ギター【rhythm guitar】
リズム‐アンド‐ブルース【rhythm and blues】
アメリカ黒人音楽の一種。バンド演奏に合わせて歌う都会的なブルース音楽、特にアフター‐ビートを強調し、叫ぶような調子で歌うものを1940年代末からこう呼ぶようになった。R&B →ロックン‐ロール。
⇒リズム【rhythm】
リズム‐ギター【rhythm guitar】
リード‐ギターに対して、伴奏を担当するギター。
⇒リズム【rhythm】
リスリン
グリセリンの略訛。
り・する【利する】
〔自他サ変〕[文]利す(サ変)
①ためになる。また、ためになるようにする。利益・便益があるようにする。また、利益・便益を与える。「敵を―・する」
②利用する。応用する。「高官の地位を―・して」
③(罪から)救済する。〈日葡辞書〉
リセ【lycée フランス】
フランスの中等教育機関。修業年限は7年であったが、1975年以降は4年制のコレージュに続く3年制の後期中等学校をいう。アリストテレスが学校を開いた地、リュケイオンに由来する語。
り‐せい【李成】
五代・北宋初期の画家。李営丘と称。唐の宗室の末裔。華北系山水様式の大成者の一人。広大な空間を表現した「平遠山水」で知られる。(919〜967)
り‐せい【里正】
村長。庄屋。黄葉夕陽村舎詩「連日―が宅に珍羞は厨くりやに満ちて堆うづたかしと」
り‐せい【理世】
世をおさめること。治世。
⇒りせい‐ぶみん【理世撫民】
り‐せい【理性】
〔哲〕(reason イギリス・Vernunft ドイツ)
①概念的思考の能力。実践的には感性的欲求に左右されず思慮的に行動する能力。古来、人間と動物とを区別するものとされた。「―を保つ」「―を失う」
②真偽・善悪を識別する能力。
③超自然的啓示に対し、人間の自然的な認識能力。→自然の光。
④パルメニデスやアリストテレスにおいては、絶対者を認識する能力。
⑤特にカントの用法として、ア‐プリオリな原理の能力の総称。カントは理性が認識に関わる場合を理論理性、行為の原理となる場合を実践理性と呼んだ。狭義には感性や悟性から区別され、理念によって認識を統一する能力。
⑥ヘーゲルの用法で、悟性と区別された弁証法的思考の能力。
⑦宇宙的原理。世界理性・絶対的理性などのようにいわれる。
⑧ロゴスとしての言語能力。
⇒りせい‐がいねん【理性概念】
⇒りせい‐てき【理性的】
⇒りせい‐ろん【理性論】
り‐せい【理政】
政まつりごとを治めること。治世。源平盛衰記27「百官を百王の
⇒リスボン‐じょうやく【リスボン条約】
リスボン‐じょうやく【リスボン条約】‥デウ‥
1887年ポルトガルと中国との間に結ばれた、澳門マカオの永代租借・最恵国待遇に関する条約。
⇒リスボン【Lisbon】
リズミカル【rhythmical】
リズムのあるさま。調子のよいさま。律動的。音律的。「―な運動」
リズム【rhythm】
①周期的な動き。進行の調子。律動。「―に乗る」「生活の―が狂う」
②詩の韻律。
③音楽におけるあらゆる時間的な諸関係。西洋音楽では旋律・和声と並んで基本要素の一つで、一般に音量・音高・音色などと結びついてアクセントが生じ、それが周期的に現れると拍子が成立する。拍子がなくてもリズムは存在する。節奏。
⇒リズム‐アンド‐ブルース【rhythm and blues】
⇒リズム‐ギター【rhythm guitar】
リズム‐アンド‐ブルース【rhythm and blues】
アメリカ黒人音楽の一種。バンド演奏に合わせて歌う都会的なブルース音楽、特にアフター‐ビートを強調し、叫ぶような調子で歌うものを1940年代末からこう呼ぶようになった。R&B →ロックン‐ロール。
⇒リズム【rhythm】
リズム‐ギター【rhythm guitar】
リード‐ギターに対して、伴奏を担当するギター。
⇒リズム【rhythm】
リスリン
グリセリンの略訛。
り・する【利する】
〔自他サ変〕[文]利す(サ変)
①ためになる。また、ためになるようにする。利益・便益があるようにする。また、利益・便益を与える。「敵を―・する」
②利用する。応用する。「高官の地位を―・して」
③(罪から)救済する。〈日葡辞書〉
リセ【lycée フランス】
フランスの中等教育機関。修業年限は7年であったが、1975年以降は4年制のコレージュに続く3年制の後期中等学校をいう。アリストテレスが学校を開いた地、リュケイオンに由来する語。
り‐せい【李成】
五代・北宋初期の画家。李営丘と称。唐の宗室の末裔。華北系山水様式の大成者の一人。広大な空間を表現した「平遠山水」で知られる。(919〜967)
り‐せい【里正】
村長。庄屋。黄葉夕陽村舎詩「連日―が宅に珍羞は厨くりやに満ちて堆うづたかしと」
り‐せい【理世】
世をおさめること。治世。
⇒りせい‐ぶみん【理世撫民】
り‐せい【理性】
〔哲〕(reason イギリス・Vernunft ドイツ)
①概念的思考の能力。実践的には感性的欲求に左右されず思慮的に行動する能力。古来、人間と動物とを区別するものとされた。「―を保つ」「―を失う」
②真偽・善悪を識別する能力。
③超自然的啓示に対し、人間の自然的な認識能力。→自然の光。
④パルメニデスやアリストテレスにおいては、絶対者を認識する能力。
⑤特にカントの用法として、ア‐プリオリな原理の能力の総称。カントは理性が認識に関わる場合を理論理性、行為の原理となる場合を実践理性と呼んだ。狭義には感性や悟性から区別され、理念によって認識を統一する能力。
⑥ヘーゲルの用法で、悟性と区別された弁証法的思考の能力。
⑦宇宙的原理。世界理性・絶対的理性などのようにいわれる。
⑧ロゴスとしての言語能力。
⇒りせい‐がいねん【理性概念】
⇒りせい‐てき【理性的】
⇒りせい‐ろん【理性論】
り‐せい【理政】
政まつりごとを治めること。治世。源平盛衰記27「百官を百王のりくつ‐ぬき【理屈抜き】🔗⭐🔉
りくつ‐ぬき【理屈抜き】
わざわざ理屈を述べ立てる必要のないこと。「―のおもしろさ」
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
りくつ‐や【理屈屋】🔗⭐🔉
りくつ‐や【理屈屋】
理屈っぽい人。理屈をすぐ言い立てる癖のある人。
⇒り‐くつ【理屈・理窟】
り‐けい【理系】🔗⭐🔉
り‐けい【理系】
理科の系統。理・工・農・医・薬などの学部を指す。↔文系
り‐けん【理研】🔗⭐🔉
り‐けん【理研】
理化学研究所の略称。
りげん‐だいし【理源大師】🔗⭐🔉
りげん‐だいし【理源大師】
聖宝しょうぼうの諡号しごう。
り‐こう【理工】🔗⭐🔉
り‐こう【理工】
理学と工学。「―系」
り‐ざい【理財】🔗⭐🔉
りざい‐か【理財家】🔗⭐🔉
りざい‐か【理財家】
理財の道に長じた人。経済家。北村透谷、二宮尊徳翁「翁は希代の―にして而して独得の大信仰を有し」
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐がく【理財学】🔗⭐🔉
りざい‐がく【理財学】
(political economyの井上哲次郎による訳語)経済学の旧称。
⇒り‐ざい【理財】
りざい‐きょく【理財局】🔗⭐🔉
りざい‐きょく【理財局】
国庫・国債・財政投融資・国有財産・たばこ塩行政その他の事項を取り扱う財務省の内局。
⇒り‐ざい【理財】
りじ‐かん【理事官】‥クワン🔗⭐🔉
りじ‐かん【理事官】‥クワン
①旧制で、内閣各省に属した官名。多くは古参判任官の優遇のためにおかれた奏任官。
②もと台湾総督府の事務官。
りじ‐こく【理事国】🔗⭐🔉
りじ‐こく【理事国】
国際機関の理事会の一員たる国。
りじ‐しゃ【理事者】🔗⭐🔉
りじ‐しゃ【理事者】
法人などの理事の職にある人。
り‐しゅ【理趣】🔗⭐🔉
り‐しゅ【理趣】
事のわけ。物の道理。駿台雑話「文辞訓話を僉議して―の深きに及ばず」
りしゅ‐きょう【理趣経】‥キヤウ🔗⭐🔉
りしゅ‐きょう【理趣経】‥キヤウ
仏典の一つ。不空の訳。1巻。真言宗の常用経典。大日如来が金剛薩埵さったのために般若理趣の自性清浄なることを説いたもの。般若理趣経。
り‐しょう【理性】‥シヤウ🔗⭐🔉
り‐しょう【理性】‥シヤウ
〔仏〕一切存在の本性。真如。法性。
りしょういん‐りゅう【理性院流】‥シヤウヰンリウ🔗⭐🔉
りしょういん‐りゅう【理性院流】‥シヤウヰンリウ
真言宗の事相の一派。醍醐理性院の賢覚を祖とし、京都市伏見区の理性院を本寺とする。小野六流・醍醐三流の一つ。
りしん‐ろん【理神論】🔗⭐🔉
りしん‐ろん【理神論】
〔宗〕(deism)世界の根源として神の存在を認めはするが、これを人格的な主宰者とは考えず、従って奇跡や啓示の存在を否定する説。啓示宗教に対する理性宗教。17〜18世紀のヨーロッパに現れ、代表者はイギリスのトーランド(John Toland1670〜1722)・ヴォルテール・レッシングら。自然神論。自然神教。↔有神論↔汎神論
り・す【理す】🔗⭐🔉
り・す【理す】
〔他サ変〕
ととのえる。また、おさめる。太平記23「民を安んじ国を―・するを本となす」
り‐すう【理数】🔗⭐🔉
り‐すう【理数】
理科と数学。
⇒りすう‐か【理数科】
りすう‐か【理数科】‥クワ🔗⭐🔉
りすう‐か【理数科】‥クワ
①理科と数学とを統合した教科。旧制の国民学校では算数・理科、中等学校では数学・物象・生物の各科目に分かれていた。
②高等学校の学科の一つ。
⇒り‐すう【理数】
り‐せい【理世】🔗⭐🔉
り‐せい【理世】
世をおさめること。治世。
⇒りせい‐ぶみん【理世撫民】
り‐せい【理性】🔗⭐🔉
り‐せい【理性】
〔哲〕(reason イギリス・Vernunft ドイツ)
①概念的思考の能力。実践的には感性的欲求に左右されず思慮的に行動する能力。古来、人間と動物とを区別するものとされた。「―を保つ」「―を失う」
②真偽・善悪を識別する能力。
③超自然的啓示に対し、人間の自然的な認識能力。→自然の光。
④パルメニデスやアリストテレスにおいては、絶対者を認識する能力。
⑤特にカントの用法として、ア‐プリオリな原理の能力の総称。カントは理性が認識に関わる場合を理論理性、行為の原理となる場合を実践理性と呼んだ。狭義には感性や悟性から区別され、理念によって認識を統一する能力。
⑥ヘーゲルの用法で、悟性と区別された弁証法的思考の能力。
⑦宇宙的原理。世界理性・絶対的理性などのようにいわれる。
⑧ロゴスとしての言語能力。
⇒りせい‐がいねん【理性概念】
⇒りせい‐てき【理性的】
⇒りせい‐ろん【理性論】
り‐せい【理政】🔗⭐🔉
り‐せい【理政】
政まつりごとを治めること。治世。源平盛衰記27「百官を百王の―に任ぜざるの間」
り‐せい【理勢】🔗⭐🔉
り‐せい【理勢】
世の中のなりゆき。世の中の情勢。主として明治期に用いた語。
りせい‐てき【理性的】🔗⭐🔉
りせい‐てき【理性的】
理性に従って判断・行動するさま。
⇒り‐せい【理性】
りせい‐ぶみん【理世撫民】🔗⭐🔉
りせい‐ぶみん【理世撫民】
世をおさめ民をいたわること。帝王の政治。新古今和歌集序「誠にこれ―の鴻徽こうき」
⇒り‐せい【理世】
りせい‐ろん【理性論】🔗⭐🔉
り‐ぜめ【理責め】🔗⭐🔉
り‐ぜめ【理責め】
理屈で人をやりこめること。理屈責め。日葡辞書「ヒトヲリゼメニスル」
り‐そ【理訴】🔗⭐🔉
り‐そ【理訴】
道理にかなった訴訟。また、そうした訴訟として認められること。源平盛衰記4「―を極めずして下向の条謂れなし」
り‐そう【理想】‥サウ🔗⭐🔉
り‐そう【理想】‥サウ
〔哲〕(ideal)行為・性質・状態などに関して、考え得る最高の状態。未だ現実には存在しないが、実現可能なものとして行為の目的であり、その意味で行為の起動力である。「―は高く持て」
⇒りそう‐か【理想化】
⇒りそう‐か【理想家】
⇒りそう‐きたい【理想気体】
⇒りそう‐きょう【理想郷】
⇒りそう‐けい【理想型】
⇒りそう‐しゅぎ【理想主義】
⇒りそう‐せい【理想性】
⇒りそう‐てき【理想的】
⇒りそう‐は【理想派】
⇒りそう‐ろん【理想論】
りそう‐か【理想化】‥サウクワ🔗⭐🔉
りそう‐か【理想化】‥サウクワ
現実をありのままに見ず、理想の姿に近づけて見たり考えたりすること。
⇒り‐そう【理想】
りそう‐か【理想家】‥サウ‥🔗⭐🔉
りそう‐か【理想家】‥サウ‥
理想を追求してやまない人。また、現実を無視して理想ばかりいう人。
⇒り‐そう【理想】
りそう‐きたい【理想気体】‥サウ‥🔗⭐🔉
りそう‐きたい【理想気体】‥サウ‥
ボイル‐シャルルの法則に従う仮想的な気体。分子の大きさも分子間の相互作用もないと考える。内部エネルギーは体積によらず温度だけで決まることが導かれる。実在気体は、温度が高く圧力が低いときに理想気体に近づく。完全気体。
⇒り‐そう【理想】
りそう‐きょう【理想郷】‥サウキヤウ🔗⭐🔉
りそう‐きょう【理想郷】‥サウキヤウ
想像上の、理想的で完全な社会。ユートピア。
⇒り‐そう【理想】
りそう‐せい【理想性】‥サウ‥🔗⭐🔉
りそう‐せい【理想性】‥サウ‥
現実に対し理想の意義を強調する性質。↔現実性。
⇒り‐そう【理想】
りそう‐てき【理想的】‥サウ‥🔗⭐🔉
りそう‐てき【理想的】‥サウ‥
事物の状態が理想に合致しているさま。
⇒り‐そう【理想】
り‐づめ【理詰め】🔗⭐🔉
り‐づめ【理詰め】
どこまでも理屈でおしすすめること。理を言い立てて責めること。理屈詰め。「―で行く」
り‐づよ【理強】🔗⭐🔉
り‐づよ【理強】
理屈の強いこと。理屈を強く言い張ること。源平盛衰記46「この人心猛く―におはしければ」
○理に当たるりにあたる🔗⭐🔉
○理に落ちるりにおちる🔗⭐🔉
○理に落ちるりにおちる
話が理屈っぽくなる。梅暦「今日はおめへのお蔭で酒が理に落ちていけねへ」
⇒り【理】
○理に勝って非に落ちるりにかってひにおちる🔗⭐🔉
○理に勝って非に落ちるりにかってひにおちる
道理の上では勝ちながら、事実においては負けとなる。理を以て非に落ちる。理に勝って非に負ける。
⇒り【理】
り‐にち【離日】
外来者が日本を離れて他に向かうこと。
○理に詰まるりにつまる🔗⭐🔉
○理に詰まるりにつまる
理屈にかなった主張をされて行き詰まる。
⇒り【理】
○理の当然りのとうぜん🔗⭐🔉
○理の当然りのとうぜん
理屈からいって必ずそうなるはずのこと。
⇒り【理】
リノベーション【renovation】
修理・修復すること。また、改善すること。
リノリウム【linoleum】
亜麻仁油あまにゆの酸化物リノキシンに樹脂・コルク粉・顔料などを混合し、麻布などに塗って薄板状に成形したもの。床敷・壁張材料に用いる。高い抗菌力がある。
リノレン‐さん【リノレン酸】
(linolenic acid)必須脂肪酸の一つ。分子式C17H29COOH 二重結合を3個含む不飽和脂肪酸。無色の液体。亜麻仁油あまにゆのような乾性油にグリセリン‐エステルとして含まれる。
リバー【river】
川。河川。
⇒リバー‐サイド【riverside】
リバー‐サイド【riverside】
川のほとり。川辺。
⇒リバー【river】
リハーサル【rehearsal】
劇・音楽・放送などの下稽古。舞台総稽古をもいう。試演。
リバーサル‐フィルム【reversal film】
(写真用語)露光後、反転現像によりポジ画像を得るフィルム。
リバーシブル【reversible】
布地や衣服などが表裏ともに使えること。両面兼用。「―‐コート」
⇒リバーシブル‐レーン【reversible lane】
リバーシブル‐レーン【reversible lane】
3車線以上ある道路の中央部の、時間帯によって進行方向を逆にする車線。
⇒リバーシブル【reversible】
リバース【reverse】
裏。逆。反対にすること。「―‐ターン」「オート‐―」
⇒リバース‐ロール【reverse roll】
リバース‐ロール【reverse roll】
パーマをかけた髪を整える際、毛先を内側へ巻き込むもの。内巻き。
⇒リバース【reverse】
リパーゼ【Lipase ドイツ】
中性脂肪を脂肪酸とグリセリンとに加水分解する酵素。エステラーゼの一種。動物の肺や脂肪組織、血清、特に膵臓すいぞう・膵液に多く、消化酵素として働く。植物では唐胡麻とうごまの種子中や小麦・大豆などに含まれる。
リバータリアニズム【libertarianism】
徹底した個人主義、自由市場の擁護、国家の役割の最小化などを特徴とする思想。ハイエク・ノージックらが代表。政府の市場介入と財の再分配を求めるリベラリズムや、共同体の伝統や慣行を重視するコミュニタリアニズムと対立する。自由至上主義。完全自由主義。
り‐はい【離杯・離盃】
別離の時にくみかわす杯。また、その酒。別杯。
り‐はい【離背】
はなれそむくこと。離反。
り‐ばい【利売】
利益を得て売ること。もうけて売ること。
り‐ばい【利倍】
利子が利子を生んで、元金がふえること。日葡辞書「リバイヲスル」
⇒りばい‐じん【利倍人】
りばい‐じん【利倍人】
(→)高利貸に同じ。〈日葡辞書〉
⇒り‐ばい【利倍】
リバイバル【revival】
(「生き返ること」の意)
①〔宗〕主にキリスト教で、大衆の信仰心が再び活性化する現象。また、それを目的とする運動。信仰復興。
②古い劇・映画・流行歌などの再演・再上映・再録音。また、昔の風俗・流行などの復活・再評価。
リバウンド【rebound】
①はねかえること。特に、球技でボールがはねかえること。また、そのボール。
②治療や投薬をやめたあとに、急激に症状が悪化すること。
③ダイエットをやめたために、一旦減少した体重が前より増加すること。
り‐はく【李白】
盛唐の詩人。四川の人、また砕葉(キルギス共和国のトクマク付近)の生れともいう。母が太白星(金星)を夢みて生んだので太白を字としたと伝える。号は青蓮(居士)。謫仙人とも称された。酒を好み奇行多く、玄宗の宮廷詩人に招かれたが、高力士らに嫌われて追放される。晩年、王子の反乱に座して流罪となったが途中で恩赦。最後は酔って水中の月を捕らえようとして溺死したという。その詩は天馬行空と称され、絶句と長編古詩を得意とした。杜甫と共に李杜と併称され、詩仙とも呼ばれる。詩文集「李太白集」30巻がある。(701〜762)
り‐はつ【利発】
①(利口発明の意)かしこいこと。怜悧。「―な子供」
②役に立つこと。
⇒りはつ‐だて【利発立て】
り‐はつ【理髪】
①元服または裳着もぎの時、頭髪を剪そったり結んだりして成人の髪型に整えること。また、その役。
②頭髪を刈り整えること。散髪。調髪。「―店」
⇒りはつ‐し【理髪師】
りはつ‐し【理髪師】
(→)理髪2を職業とする人。床屋。
⇒り‐はつ【理髪】
りはつ‐だて【利発立て】
利発らしく振る舞うこと。
⇒り‐はつ【利発】
り‐はっ‐ちゃく【離発着】
(離着陸と発着との混交語)飛行機の出発と到着。
リバティー【liberty】
自由。解放。
リバノール【Rivanol ドイツ】
(→)アクリノールのこと。
り‐はば【利幅】
利益の大きさ。マージン。「―が小さい」
リハビリ
リハビリテーションの略。
リハビリテーション【rehabilitation】
治療段階を終えた疾病や外傷の後遺症を持つ人に対して、医学的・心理学的な指導や機能訓練を施し、機能回復・社会復帰をはかること。更生指導。リハビリ。
リバプール【Liverpool】
⇒リヴァプール
リパブリック【republic】
共和政体。共和制。共和国。
り‐ばらい【利払い】‥バラヒ
利息の支払い。
り‐はん【離反・離叛】
はなれそむくこと。「人心が―する」
りはん‐いん【理藩院】‥ヰン
清代の官庁。藩部を統括した清代固有の機関。長官の尚書には満州人をあてた。
り‐はんりょう【李攀竜】
明代後期の詩人。字は于鱗、号は滄溟。山東歴城の人。盛唐詩を尊重。七言絶句に長じ、王世貞らとともに七子と称される。著「滄溟集」「古今詩刪」。「唐詩選」は彼の編と称するが疑わしい。(1514〜1570)
り‐ひ【理非】
道理と非理。道理にかなっていることとはずれていること。是非。大鏡時平「王威の限りなくおはしますによりて―を示させ給へるなり」。「―曲直」
リビア【Libya】
(ギリシア・ローマ時代のアフリカの称)アフリカ北部、地中海に面する国。正称は、大リビア‐アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国。1912年イタリア植民地、51年立憲王国として独立、69年共和国となる。住民の大多数はイスラム教徒のアラブ人・ベルベル人。油田開発が進む。面積176万平方キロメートル。人口548万4千(2002)。首都トリポリ。→アフリカ(図)。
⇒リビア‐さばく【リビア砂漠】
⇒リビア‐ねこ【リビア猫】
リビア‐さばく【リビア砂漠】
アフリカ北部の砂漠。ナイル川以西エジプト南西部、リビア南東部、スーダン北西部にまたがる。面積約170万平方キロメートル。
⇒リビア【Libya】
リビア‐ねこ【リビア猫】
ネコ科の一種。体長50センチメートルほどの野生猫で、アフリカからインドにかけて分布。家猫の先祖とされるが、最近ではヨーロッパヤマネコと同じ種と考えられている。リビアヤマネコ。
⇒リビア【Libya】
リビー【Willard Frank Libby】
アメリカの化学者。炭素14法を確立。水素の放射性同位体トリチウムによる年代決定法も考案。ノーベル賞。(1908〜1980)
リピーター【repeater】
ある事を何度も繰り返し行う人。「海外旅行の―」「―の多い店」
リピート【repeat】
①繰り返すこと。「後について―する」
②〔音〕(→)反復記号。
りひ‐か【離被架】
病人の患部や手術部に直接布団などが触れないように保護する器具。
りひ‐きょくちょく【理非曲直】
道理や道徳にかなっていることと反していること。「―を明らかにする」
リヒター【Gerhard Richter】
ドイツの画家。ピントの甘い写真を基にした写実的絵画と抽象絵画とを交互に制作。「エマ」など。(1932〜)
リヒテル【Svyatoslav Rikhter】
ロシアのピアニスト。ウクライナ生れ。1960年以後、欧米でも活動。リフテル。(1915〜1997)
リヒテンシュタイン【Liechtenstein】
スイスとオーストリアとの国境にある立憲公国。住民はゲルマン系、旧教を信奉。観光・郵政事業で著名。公用語はドイツ語。面積160平方キロメートル。人口3万4千(2004)。首都ファドーツ。→ヨーロッパ(図)
リヒテンシュタイン
撮影:田沼武能
 リピド【lipid】
(→)脂質ししつ。
リビドー【Libido ドイツ】
(本来はラテン語で欲望の意)精神分析の主要概念の一つ。フロイトは、生の本能としての性的エネルギーと定義し、それが阻害されると様々な発達障害や神経症が生じるとする。また、ユングは、すべての本能のエネルギーの本体とする。
り‐びょう【利平】‥ビヤウ
利息。利子。また、高い利子による儲け。〈日葡辞書〉。建武以来追加「―においては廿一箇年を過ぎずは一倍たるべし」
り‐びょう【痢病】‥ビヤウ
腹痛・下痢が激しく、飴状の排泄物を出す病気。赤痢の類。日葡辞書「リビャウ。シボリハラ」
り‐びょう【罹病】‥ビヤウ
病気にかかること。「―率」
リビング【living】
①生きていること。生活。暮し。また、住まい。「モダン‐―」
②リビング‐ルームの略。
⇒リビング‐ウィル【living will】
⇒リビング‐ルーム【living room】
リビング‐ウィル【living will】
(willは意思・遺言の意)あらかじめ自らの延命措置等に関して意思表示しておく文書。
⇒リビング【living】
リビング‐シアター【Living Theatre】
アメリカの劇団。1947年結成。オフ‐ブロードウェーで注目されるが、反体制色の強い活動が妨害を受け64年にヨーロッパに移転。代表作「パラダイス‐ナウ」。
リビングストン【D. Livingstone】
⇒リヴィングストン
リビング‐ルーム【living room】
洋風の居間。リビング。
⇒リビング【living】
り‐ふ【嫠婦】
夫をなくした女。やもめ。
り‐ぶ【吏部】
(リホウとも)
①中国の六部りくぶの一つ。官吏の任免および功過の考査、勲爵の賜与をつかさどる。隋・唐に設けられ、清末に廃止。
②式部省の唐名。
リブ【lib】
(liberation(解放)の略)ウーマン‐リブの略。
リブ【rib】
(肋骨の意)リブ‐ロースの略。
リファイン【refine】
洗練すること。上品にすること。
リファレンス【reference】
⇒レファレンス
リファレンダム【referendum】
⇒レファレンダム
リブ‐ヴォールト【ribbed vault】
ヴォールトの一種。交差するヴォールトの稜線の下側に太いアーチ(リブ)を架け渡して補強したもの。ゴシック式の重要な特徴の一つ。
リフォーム【reform】
改良すること。作り直すこと。特に、衣服の仕立て直しや建物の改築・改装。
り‐ふく【利福】
利益と幸福。福利。
リプシッツ【Jacques Lipchitz】
フランス、立体派の代表的彫刻家。リトアニアの生れ。(1891〜1973)
りぶ‐しょうしょ【吏部尚書】‥シヤウ‥
中国の吏部の長官。
り‐ふじん【理不尽】
①道理を尽くさないこと。東鑑6「頼朝の申状たりといへども、―の裁許有るべからず候」
②道理にあわないこと。無理無体。こんてむつすむん地「―なる事を言ひかけらるる時」。「―な要求」
り‐ふだ【利札】
⇒りさつ
り‐ぶっしょう【理仏性】‥シヤウ
〔仏〕一切衆生しゅじょうのもつ仏となるべき性質。↔行仏性ぎょうぶっしょう
リフティング【lifting】
サッカー‐ボールを、地面に落とさないように手を使わないで打ち上げ続けること。
リフト【lift】
①昇降機。エレベーター。
②スキー場などの、架空ケーブルに椅子を吊した登山用装置。
③起重機。
④ポンプの揚程。
⑤ダンスやフィギュア‐スケートで、男性が女性を持ち上げること。
⇒リフトアップ‐こうほう【リフトアップ工法】
⇒リフト‐バルブ【lift valve】
リフトアップ‐こうほう【リフトアップ工法】‥ハフ
屋根組などを低所で組み立ててから所定の位置まで引き上げて設置する工法。
⇒リフト【lift】
リフト‐バルブ【lift valve】
昇降によって弁座の開閉する弁の総称。持上げ弁。
⇒リフト【lift】
リプリント【reprint】
①写真などの複写。
②復刻。翻刻。また、再版。
リフレイン【refrain】
詩や楽曲の中で、各節の後に同じ部分を繰り返すこと。また、その部分。折返し。畳句。ルフラン。
リプレー【replay】
①試合や演劇などを再び行うこと。
②録音・録画を再生すること。
リフレーション【reflation】
景気循環の過程で、デフレーションから脱し、しかもインフレーションにまで至っていない状態。不況における物価下落を正常水準まで引き上げて生産を刺激し、景気を回復させることを目的とした計画的な通貨の膨張。↔ディスインフレーション
リプレース【replace】
ゴルフで、規則に従って拾い上げた球を、元あった場所に置き戻すこと。
リフレクソロジー【reflexology】
掌てのひらや足裏などに身体の各器官の調子を反映した箇所があるという考えに基づき、それらを刺激して健康を維持・増進する療法。反射療法。
リフレクター【reflector】
反射器。反射鏡。反射板。レフレクター。
リフレックス【reflex】
⇒レフレックス
リプレッサー【repressor】
特定の遺伝子群の形質発現を抑制する蛋白質。レプレッサー。→オペロン説
リフレッシュ【refresh】
気分をさわやかに一新すること。元気を取り戻すこと。
⇒リフレッシュ‐きゅうか【リフレッシュ休暇】
リフレッシュ‐きゅうか【リフレッシュ休暇】‥キウ‥
気持をリフレッシュするために取る休暇。また、一定の勤続期間を経た者に与える休暇。
⇒リフレッシュ【refresh】
リフレッシュメント【refreshment】
①気分を新たにすること。
②爽快な気分を起こさせる飲物。
リブ‐ロース
(rib roast)牛肉の部位のうち背中の肩寄りの部分。霜降り状で柔らかい。ロースト‐ビーフ・ステーキなどに用いる。リブ。→牛肉(図)
リプロダクション【reproduction】
①模写。複写。複製。
②〔経〕(→)再生産。
③書籍の翻刻。
リプロダクティブ‐ヘルス【reproductive health】
性と生殖に関する健康。安全な性生活を営む権利が女性に認められるべきだとする理念。
リプロダクティブ‐ライツ【reproductive rights】
性と生殖に関する権利。妊娠・出産についての基本的な決定権が女性にあるとする立場からいう。
り‐ぶん【利分】
①利益となる分。利得。もうけ。浮世物語「今の商人は…米の直ねを上げんと―を守る程に」
②(→)利子に同じ。太平記35「本物ばかりを借り主に返納すべし。―は我添へて返すべし」
り‐ぶん【理分】
道理にかなう方。道理があり利益になる方。狂言、内沙汰「随分―になるやうに云はつしやれい」
り‐へい【利平】
⇒りびょう
り‐へい【利兵】
するどい刃物。鋭利な兵器。
リベート【rebate】
①支払代金の一部を支払者に謝礼として与えること。また、その金。割戻し。
②手数料。また、わいろ。
り‐べつ【離別】
①人に別れること。別離。
②夫婦の関係を断つこと。離婚。「―状」
リベッター【riveter】
(→)鋲締機びょうじめき。
リベッテッド‐ジョイント【riveted joint】
(→)リベット継手つぎてに同じ。
リベット【rivet】
頭の大きな釘くぎ。鋲びょう。締釘しめくぎ。
⇒リベット‐つぎて【リベット継手】
リベット‐つぎて【リベット継手】
金属板接続部をリベットで固定する接合法。重ね継手・突合せ継手などがある。鋲びょう継手。リベッテッド‐ジョイント。
⇒リベット【rivet】
リベラ【José de Ribera】
スペインの画家。イタリア各地で過ごし、ナポリに永住。厳格な写実を心掛け、カラヴァッジオの影響を受けた。明暗の対比の強い宗教画に佳作を残す。作「聖バルトロメオの殉教」など。(1591〜1652)
リベラ【Diego Rivera】
メキシコの画家。シケイロスに出会い、壁画運動に参加。作「社会主義と資本主義の岐路にある男」など。(1886〜1957)
リベラ
提供:ullstein bild/APL
リピド【lipid】
(→)脂質ししつ。
リビドー【Libido ドイツ】
(本来はラテン語で欲望の意)精神分析の主要概念の一つ。フロイトは、生の本能としての性的エネルギーと定義し、それが阻害されると様々な発達障害や神経症が生じるとする。また、ユングは、すべての本能のエネルギーの本体とする。
り‐びょう【利平】‥ビヤウ
利息。利子。また、高い利子による儲け。〈日葡辞書〉。建武以来追加「―においては廿一箇年を過ぎずは一倍たるべし」
り‐びょう【痢病】‥ビヤウ
腹痛・下痢が激しく、飴状の排泄物を出す病気。赤痢の類。日葡辞書「リビャウ。シボリハラ」
り‐びょう【罹病】‥ビヤウ
病気にかかること。「―率」
リビング【living】
①生きていること。生活。暮し。また、住まい。「モダン‐―」
②リビング‐ルームの略。
⇒リビング‐ウィル【living will】
⇒リビング‐ルーム【living room】
リビング‐ウィル【living will】
(willは意思・遺言の意)あらかじめ自らの延命措置等に関して意思表示しておく文書。
⇒リビング【living】
リビング‐シアター【Living Theatre】
アメリカの劇団。1947年結成。オフ‐ブロードウェーで注目されるが、反体制色の強い活動が妨害を受け64年にヨーロッパに移転。代表作「パラダイス‐ナウ」。
リビングストン【D. Livingstone】
⇒リヴィングストン
リビング‐ルーム【living room】
洋風の居間。リビング。
⇒リビング【living】
り‐ふ【嫠婦】
夫をなくした女。やもめ。
り‐ぶ【吏部】
(リホウとも)
①中国の六部りくぶの一つ。官吏の任免および功過の考査、勲爵の賜与をつかさどる。隋・唐に設けられ、清末に廃止。
②式部省の唐名。
リブ【lib】
(liberation(解放)の略)ウーマン‐リブの略。
リブ【rib】
(肋骨の意)リブ‐ロースの略。
リファイン【refine】
洗練すること。上品にすること。
リファレンス【reference】
⇒レファレンス
リファレンダム【referendum】
⇒レファレンダム
リブ‐ヴォールト【ribbed vault】
ヴォールトの一種。交差するヴォールトの稜線の下側に太いアーチ(リブ)を架け渡して補強したもの。ゴシック式の重要な特徴の一つ。
リフォーム【reform】
改良すること。作り直すこと。特に、衣服の仕立て直しや建物の改築・改装。
り‐ふく【利福】
利益と幸福。福利。
リプシッツ【Jacques Lipchitz】
フランス、立体派の代表的彫刻家。リトアニアの生れ。(1891〜1973)
りぶ‐しょうしょ【吏部尚書】‥シヤウ‥
中国の吏部の長官。
り‐ふじん【理不尽】
①道理を尽くさないこと。東鑑6「頼朝の申状たりといへども、―の裁許有るべからず候」
②道理にあわないこと。無理無体。こんてむつすむん地「―なる事を言ひかけらるる時」。「―な要求」
り‐ふだ【利札】
⇒りさつ
り‐ぶっしょう【理仏性】‥シヤウ
〔仏〕一切衆生しゅじょうのもつ仏となるべき性質。↔行仏性ぎょうぶっしょう
リフティング【lifting】
サッカー‐ボールを、地面に落とさないように手を使わないで打ち上げ続けること。
リフト【lift】
①昇降機。エレベーター。
②スキー場などの、架空ケーブルに椅子を吊した登山用装置。
③起重機。
④ポンプの揚程。
⑤ダンスやフィギュア‐スケートで、男性が女性を持ち上げること。
⇒リフトアップ‐こうほう【リフトアップ工法】
⇒リフト‐バルブ【lift valve】
リフトアップ‐こうほう【リフトアップ工法】‥ハフ
屋根組などを低所で組み立ててから所定の位置まで引き上げて設置する工法。
⇒リフト【lift】
リフト‐バルブ【lift valve】
昇降によって弁座の開閉する弁の総称。持上げ弁。
⇒リフト【lift】
リプリント【reprint】
①写真などの複写。
②復刻。翻刻。また、再版。
リフレイン【refrain】
詩や楽曲の中で、各節の後に同じ部分を繰り返すこと。また、その部分。折返し。畳句。ルフラン。
リプレー【replay】
①試合や演劇などを再び行うこと。
②録音・録画を再生すること。
リフレーション【reflation】
景気循環の過程で、デフレーションから脱し、しかもインフレーションにまで至っていない状態。不況における物価下落を正常水準まで引き上げて生産を刺激し、景気を回復させることを目的とした計画的な通貨の膨張。↔ディスインフレーション
リプレース【replace】
ゴルフで、規則に従って拾い上げた球を、元あった場所に置き戻すこと。
リフレクソロジー【reflexology】
掌てのひらや足裏などに身体の各器官の調子を反映した箇所があるという考えに基づき、それらを刺激して健康を維持・増進する療法。反射療法。
リフレクター【reflector】
反射器。反射鏡。反射板。レフレクター。
リフレックス【reflex】
⇒レフレックス
リプレッサー【repressor】
特定の遺伝子群の形質発現を抑制する蛋白質。レプレッサー。→オペロン説
リフレッシュ【refresh】
気分をさわやかに一新すること。元気を取り戻すこと。
⇒リフレッシュ‐きゅうか【リフレッシュ休暇】
リフレッシュ‐きゅうか【リフレッシュ休暇】‥キウ‥
気持をリフレッシュするために取る休暇。また、一定の勤続期間を経た者に与える休暇。
⇒リフレッシュ【refresh】
リフレッシュメント【refreshment】
①気分を新たにすること。
②爽快な気分を起こさせる飲物。
リブ‐ロース
(rib roast)牛肉の部位のうち背中の肩寄りの部分。霜降り状で柔らかい。ロースト‐ビーフ・ステーキなどに用いる。リブ。→牛肉(図)
リプロダクション【reproduction】
①模写。複写。複製。
②〔経〕(→)再生産。
③書籍の翻刻。
リプロダクティブ‐ヘルス【reproductive health】
性と生殖に関する健康。安全な性生活を営む権利が女性に認められるべきだとする理念。
リプロダクティブ‐ライツ【reproductive rights】
性と生殖に関する権利。妊娠・出産についての基本的な決定権が女性にあるとする立場からいう。
り‐ぶん【利分】
①利益となる分。利得。もうけ。浮世物語「今の商人は…米の直ねを上げんと―を守る程に」
②(→)利子に同じ。太平記35「本物ばかりを借り主に返納すべし。―は我添へて返すべし」
り‐ぶん【理分】
道理にかなう方。道理があり利益になる方。狂言、内沙汰「随分―になるやうに云はつしやれい」
り‐へい【利平】
⇒りびょう
り‐へい【利兵】
するどい刃物。鋭利な兵器。
リベート【rebate】
①支払代金の一部を支払者に謝礼として与えること。また、その金。割戻し。
②手数料。また、わいろ。
り‐べつ【離別】
①人に別れること。別離。
②夫婦の関係を断つこと。離婚。「―状」
リベッター【riveter】
(→)鋲締機びょうじめき。
リベッテッド‐ジョイント【riveted joint】
(→)リベット継手つぎてに同じ。
リベット【rivet】
頭の大きな釘くぎ。鋲びょう。締釘しめくぎ。
⇒リベット‐つぎて【リベット継手】
リベット‐つぎて【リベット継手】
金属板接続部をリベットで固定する接合法。重ね継手・突合せ継手などがある。鋲びょう継手。リベッテッド‐ジョイント。
⇒リベット【rivet】
リベラ【José de Ribera】
スペインの画家。イタリア各地で過ごし、ナポリに永住。厳格な写実を心掛け、カラヴァッジオの影響を受けた。明暗の対比の強い宗教画に佳作を残す。作「聖バルトロメオの殉教」など。(1591〜1652)
リベラ【Diego Rivera】
メキシコの画家。シケイロスに出会い、壁画運動に参加。作「社会主義と資本主義の岐路にある男」など。(1886〜1957)
リベラ
提供:ullstein bild/APL
 リベラリスト【liberalist】
自由主義者。
リベラリズム【liberalism】
(→)自由主義。
リベラル【liberal】
①個人の自由、個性を重んずるさま。自由主義的。
②自由主義者。
⇒リベラル‐アーツ【liberal arts】
リベラル‐アーツ【liberal arts】
①(→)自由学芸に同じ。
②自由な心や批判的知性の育成、また自己覚醒を目的にした大学の教養教育の課程。
⇒リベラル【liberal】
リベリア【Liberia】
アフリカ西部、大西洋に面する共和国。1820年アメリカの解放奴隷が移住・建国、47年独立。便宜置籍船制度により、世界一の商船保有国。面積11万平方キロメートル。人口287万9千(1997)。首都モンロヴィア。→アフリカ(図)
リベル【Liber】
ローマの古神。生産と豊穣の神。ギリシア神話のディオニュソスと同一視された。
リベロ【libero イタリア】
(「自由な」の意)
①サッカーで、通常はゴール前を守るが、自由に攻撃にも参加する選手。
②バレーボールで、守備専門の選手。他の選手とは異なるユニフォームを着用する。
り‐べん【利便】
便利。便宜。「―をはかる」
り‐べん【離弁・離瓣】
(花弁の分離している意)
⇒りべん‐か【離弁花】
⇒りべん‐かかん【離弁花冠】
⇒りべんか‐るい【離弁花類】
りべん‐か【離弁花】‥クワ
離弁花冠をもつ花。↔合弁花。
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
りべん‐かかん【離弁花冠】‥クワクワン
一つの花にある全花弁が互いに分離している花冠。ウメ・サクラの花の類。↔合弁花冠。
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
りべんか‐るい【離弁花類】‥クワ‥
双子葉植物のうち、花冠が全く無いかまたは離弁花冠をもつ群。ブナ科・ナデシコ科・バラ科・マメ科など。↔合弁花類
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
リベンジ【revenge】
復讐。雪辱戦。
リポイド【lipoid】
(→)類脂質。
り‐ほう【吏部】
(ホウは漢音)
⇒りぶ
り‐ほう【李鵬】
(Li Peng)中国の政治家。上海生れ。1948年モスクワ留学。電力工業部部長・中共中央政治局委員などを経て88〜98年国務院総理。(1928〜)
り‐ほう【理法】‥ハフ
のっとるべき道理。規則。法則。
り‐ぼうよう【李夢陽】‥ヤウ
(リムヨウとも)明の詩文家。字は献吉。号は空同子。甘粛慶陽の人。明代古文辞派の首唱者、前七子の一人。著「空同子集」。(1472〜1529)→七子しちし
リボー【Théodule Armand Ribot】
フランスの心理学者。病態心理学や感情研究の分野で活躍。著「感情の心理学」など。(1839〜1916)
リボース【ribose】
分子式C5H10O5 ペントースの一つ。白色の結晶。リボ核酸や種々の補酵素の構成成分として広く生体に分布。
リポーター【reporter】
⇒レポーター
リポート【report】
⇒レポート
リボ‐かくさん【リボ核酸】
(ribonucleic acid)リボースを含む核酸。RNAと略記。デオキシリボ核酸とともに蛋白質生合成に関与、またRNAウイルスでは遺伝情報の保存・複製を行う。リボソームの重要成分をなす。メッセンジャーRNA、転移RNAなどがある。
リポ‐さん【リポ酸】
(lipoic acid)ビタミン様作用物質の一つで、微生物の発育に必要な因子。人では、必要量は腸内細菌が合成。チオクト酸。
リポジショニング【repositioning】
競合商品に対して自社商品を位置づけ直し、差異を明確にして宣伝すること。
リボソーム【ribosome】
細胞質中に遊離するか、または小胞体や核膜と結合して存在する小顆粒。蛋白質の生合成、すなわち翻訳が行われる。ミトコンドリア・葉緑体は独自のものをもつ。
リポソーム【liposome】
生体膜と同じくリン脂質の二分子膜の構造からなる微少なカプセル。薬剤投与の目的で開発されたが、細胞生物学研究のモデルとしても用いる。
リポ‐たんぱくしつ【リポ蛋白質】
(lipoprotein)複合蛋白質の一種で、蛋白質と脂質とが結合したものの総称。血漿・卵黄などに含まれる。
リボヌクレアーゼ【ribonuclease】
RNAを分解する酵素の総称。動植物・微生物に広く分布。作用機序、基質の特異性の異なる多数の種類が存在する。
リボ‐ばらい【リボ払い】‥バラヒ
リボルビング方式による支払い。
リボフラビン【riboflavin】
(→)ビタミンB2に同じ。
リボルバー【revolver】
回転式の連発拳銃。
リボルビング【revolving】
(回転の意)クレジット‐カード等による分割払いの一つ。総借入れ限度額を設定し、予め定めた一定額ずつ毎月返済していく方式。
リボン【ribbon】
絹・合成繊維などで織った細幅のひも。衣服・帽子・頭髪や贈り物の装飾として用いる。夏目漱石、坊つちやん「花月巻、白い―のハイカラ頭、乗るは自転車、弾くは
リベラリスト【liberalist】
自由主義者。
リベラリズム【liberalism】
(→)自由主義。
リベラル【liberal】
①個人の自由、個性を重んずるさま。自由主義的。
②自由主義者。
⇒リベラル‐アーツ【liberal arts】
リベラル‐アーツ【liberal arts】
①(→)自由学芸に同じ。
②自由な心や批判的知性の育成、また自己覚醒を目的にした大学の教養教育の課程。
⇒リベラル【liberal】
リベリア【Liberia】
アフリカ西部、大西洋に面する共和国。1820年アメリカの解放奴隷が移住・建国、47年独立。便宜置籍船制度により、世界一の商船保有国。面積11万平方キロメートル。人口287万9千(1997)。首都モンロヴィア。→アフリカ(図)
リベル【Liber】
ローマの古神。生産と豊穣の神。ギリシア神話のディオニュソスと同一視された。
リベロ【libero イタリア】
(「自由な」の意)
①サッカーで、通常はゴール前を守るが、自由に攻撃にも参加する選手。
②バレーボールで、守備専門の選手。他の選手とは異なるユニフォームを着用する。
り‐べん【利便】
便利。便宜。「―をはかる」
り‐べん【離弁・離瓣】
(花弁の分離している意)
⇒りべん‐か【離弁花】
⇒りべん‐かかん【離弁花冠】
⇒りべんか‐るい【離弁花類】
りべん‐か【離弁花】‥クワ
離弁花冠をもつ花。↔合弁花。
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
りべん‐かかん【離弁花冠】‥クワクワン
一つの花にある全花弁が互いに分離している花冠。ウメ・サクラの花の類。↔合弁花冠。
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
りべんか‐るい【離弁花類】‥クワ‥
双子葉植物のうち、花冠が全く無いかまたは離弁花冠をもつ群。ブナ科・ナデシコ科・バラ科・マメ科など。↔合弁花類
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
リベンジ【revenge】
復讐。雪辱戦。
リポイド【lipoid】
(→)類脂質。
り‐ほう【吏部】
(ホウは漢音)
⇒りぶ
り‐ほう【李鵬】
(Li Peng)中国の政治家。上海生れ。1948年モスクワ留学。電力工業部部長・中共中央政治局委員などを経て88〜98年国務院総理。(1928〜)
り‐ほう【理法】‥ハフ
のっとるべき道理。規則。法則。
り‐ぼうよう【李夢陽】‥ヤウ
(リムヨウとも)明の詩文家。字は献吉。号は空同子。甘粛慶陽の人。明代古文辞派の首唱者、前七子の一人。著「空同子集」。(1472〜1529)→七子しちし
リボー【Théodule Armand Ribot】
フランスの心理学者。病態心理学や感情研究の分野で活躍。著「感情の心理学」など。(1839〜1916)
リボース【ribose】
分子式C5H10O5 ペントースの一つ。白色の結晶。リボ核酸や種々の補酵素の構成成分として広く生体に分布。
リポーター【reporter】
⇒レポーター
リポート【report】
⇒レポート
リボ‐かくさん【リボ核酸】
(ribonucleic acid)リボースを含む核酸。RNAと略記。デオキシリボ核酸とともに蛋白質生合成に関与、またRNAウイルスでは遺伝情報の保存・複製を行う。リボソームの重要成分をなす。メッセンジャーRNA、転移RNAなどがある。
リポ‐さん【リポ酸】
(lipoic acid)ビタミン様作用物質の一つで、微生物の発育に必要な因子。人では、必要量は腸内細菌が合成。チオクト酸。
リポジショニング【repositioning】
競合商品に対して自社商品を位置づけ直し、差異を明確にして宣伝すること。
リボソーム【ribosome】
細胞質中に遊離するか、または小胞体や核膜と結合して存在する小顆粒。蛋白質の生合成、すなわち翻訳が行われる。ミトコンドリア・葉緑体は独自のものをもつ。
リポソーム【liposome】
生体膜と同じくリン脂質の二分子膜の構造からなる微少なカプセル。薬剤投与の目的で開発されたが、細胞生物学研究のモデルとしても用いる。
リポ‐たんぱくしつ【リポ蛋白質】
(lipoprotein)複合蛋白質の一種で、蛋白質と脂質とが結合したものの総称。血漿・卵黄などに含まれる。
リボヌクレアーゼ【ribonuclease】
RNAを分解する酵素の総称。動植物・微生物に広く分布。作用機序、基質の特異性の異なる多数の種類が存在する。
リボ‐ばらい【リボ払い】‥バラヒ
リボルビング方式による支払い。
リボフラビン【riboflavin】
(→)ビタミンB2に同じ。
リボルバー【revolver】
回転式の連発拳銃。
リボルビング【revolving】
(回転の意)クレジット‐カード等による分割払いの一つ。総借入れ限度額を設定し、予め定めた一定額ずつ毎月返済していく方式。
リボン【ribbon】
絹・合成繊維などで織った細幅のひも。衣服・帽子・頭髪や贈り物の装飾として用いる。夏目漱石、坊つちやん「花月巻、白い―のハイカラ頭、乗るは自転車、弾くは イオリン」。「―を結ぶ」「―を掛ける」
⇒リボン‐グラス【ribbon-grass】
⇒リボン‐ししゅう【リボン刺繍】
リボン‐グラス【ribbon-grass】
イネ科の多年草。ヨーロッパ原産。地下茎はチョロギに似た白色の念珠状。葉は長さ約30センチメートルで、縦に白縞がある。夏の末に枯れ、初冬にまた芽を出す。花壇のへり植えなどに栽培。リボンガヤ。
リボン-グラス
イオリン」。「―を結ぶ」「―を掛ける」
⇒リボン‐グラス【ribbon-grass】
⇒リボン‐ししゅう【リボン刺繍】
リボン‐グラス【ribbon-grass】
イネ科の多年草。ヨーロッパ原産。地下茎はチョロギに似た白色の念珠状。葉は長さ約30センチメートルで、縦に白縞がある。夏の末に枯れ、初冬にまた芽を出す。花壇のへり植えなどに栽培。リボンガヤ。
リボン-グラス
 ⇒リボン【ribbon】
リボン‐ししゅう【リボン刺繍】‥シウ
細いリボンを用いて刺す刺繍の総称。服飾のほか室内の装飾品や小物などに応用する。
⇒リボン【ribbon】
リマ【Lima】
南米、ペルー共和国の首都。1535年ピサロの創建した植民地都市。太平洋岸に位置し、外港はカヤオ。人口707万5千(2003)。
リマ
撮影:田沼武能
⇒リボン【ribbon】
リボン‐ししゅう【リボン刺繍】‥シウ
細いリボンを用いて刺す刺繍の総称。服飾のほか室内の装飾品や小物などに応用する。
⇒リボン【ribbon】
リマ【Lima】
南米、ペルー共和国の首都。1535年ピサロの創建した植民地都市。太平洋岸に位置し、外港はカヤオ。人口707万5千(2003)。
リマ
撮影:田沼武能
 り‐まい【利米】
借米の利息として払う米。
り‐まとう【利瑪竇】
マテオ=リッチの漢名。
り‐まわし【利回し】‥マハシ
利息を得るために金銭を他に貸し出すこと。利殖をはかること。
り‐まわり【利回り】‥マハリ
利益配当または利息の元金に対する割合。「―が良い」
リマン‐かいりゅう【リマン海流】‥リウ
(リマン(liman ロシア)は「河口の潟」の意)日本近海の寒流の一つ。日本海北隅に発し、大陸沿岸を経て朝鮮半島東岸に達する。→海流(図)
リミット【limit】
限度。限界。範囲。極限。
⇒リミット‐ゲージ【limit gauge】
リミット‐ゲージ【limit gauge】
〔機〕(→)限界ゲージに同じ。
⇒リミット【limit】
り‐みん【里民】
村里の民。その里の人。
り‐みん【理民】
民を治めること。治民。
り‐む【吏務】
役人としての職務。
リム【rim】
車の外周をなす環状部分。自動車などの車輪では、この部分にタイヤを固定する。
リムーバー【remover】
ペンキやマニキュアを除去する溶剤。→除光液
リムジン【limousine フランス】
①運転席と座席との間に仕切りがある公式用の豪華な箱型乗用車。→自動車(図)。
②空港などの送迎用バス。リムジン‐バス。
リムスキー‐コルサコフ【Nikolai Rimskii-Korsakov】
ロシアの作曲家。ロシア国民楽派の一人。色彩的な管弦楽法と楽想とで著名。交響組曲「シェエラザード」、管弦楽曲「スペイン奇想曲」、歌劇「金鶏」など。(1844〜1908)
リムスキー‐コルサコフ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
り‐まい【利米】
借米の利息として払う米。
り‐まとう【利瑪竇】
マテオ=リッチの漢名。
り‐まわし【利回し】‥マハシ
利息を得るために金銭を他に貸し出すこと。利殖をはかること。
り‐まわり【利回り】‥マハリ
利益配当または利息の元金に対する割合。「―が良い」
リマン‐かいりゅう【リマン海流】‥リウ
(リマン(liman ロシア)は「河口の潟」の意)日本近海の寒流の一つ。日本海北隅に発し、大陸沿岸を経て朝鮮半島東岸に達する。→海流(図)
リミット【limit】
限度。限界。範囲。極限。
⇒リミット‐ゲージ【limit gauge】
リミット‐ゲージ【limit gauge】
〔機〕(→)限界ゲージに同じ。
⇒リミット【limit】
り‐みん【里民】
村里の民。その里の人。
り‐みん【理民】
民を治めること。治民。
り‐む【吏務】
役人としての職務。
リム【rim】
車の外周をなす環状部分。自動車などの車輪では、この部分にタイヤを固定する。
リムーバー【remover】
ペンキやマニキュアを除去する溶剤。→除光液
リムジン【limousine フランス】
①運転席と座席との間に仕切りがある公式用の豪華な箱型乗用車。→自動車(図)。
②空港などの送迎用バス。リムジン‐バス。
リムスキー‐コルサコフ【Nikolai Rimskii-Korsakov】
ロシアの作曲家。ロシア国民楽派の一人。色彩的な管弦楽法と楽想とで著名。交響組曲「シェエラザード」、管弦楽曲「スペイン奇想曲」、歌劇「金鶏」など。(1844〜1908)
リムスキー‐コルサコフ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 →交響組曲「シェエラザード」王子と王女
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
リムセ
アイヌの伝承歌舞。輪座して歌ううちに興が乗ると立って歌い踊る。歌は掛声や囃子詞はやしことばの反復が多く、踊りは描写的な動作が多い。→ウポポ
リメーク【remake】
作り直すこと。「昔の映画の―」
り‐めん【裏面】
①うら。うらがわ。
②物事の外部には現れない面。内情。「政界の―を探る」
⇒りめん‐こうさく【裏面工作】
⇒りめん‐し【裏面史】
りめん‐こうさく【裏面工作】
物事を思いどおりに運ぶために、ひそかに交渉し準備すること。
⇒り‐めん【裏面】
りめん‐し【裏面史】
外部に現れない方面、裏話などを叙述した歴史。
⇒り‐めん【裏面】
リメンバー【remember】
①思い出すこと。
②覚えていること。
リモート【remote】
(遠隔の意)
⇒リモート‐コントロール【remote control】
⇒リモート‐センシング【remote sensing】
⇒リモート‐ターミナル【remote terminal】
リモート‐コントロール【remote control】
(→)遠隔操作。リモコン。
⇒リモート【remote】
リモート‐センシング【remote sensing】
遠隔測定または遠隔計測。特に、人工衛星・航空機などにより地表からの各種波長の電磁波エネルギーを測定し、そのデータや画像を伝送させて観測すること。
⇒リモート【remote】
リモート‐ターミナル【remote terminal】
コンピューター‐ネットワークに接続された端末装置。
⇒リモート【remote】
リモ‐コン
リモート‐コントロールの略。
り‐もつ【利物】
①稲・粟などを貸して得た利息分と貸した分。元利。令義解「―は並に糺たださむ人にたまへ」
②もうけ。利益。成果。〈日葡辞書〉
③〔仏〕(「物」は一切衆生をいう)(→)利生りしょうに同じ。平家物語1「慈悲具足の山王―の方便にてましませば」
⇒利物の垂迹
→交響組曲「シェエラザード」王子と王女
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
リムセ
アイヌの伝承歌舞。輪座して歌ううちに興が乗ると立って歌い踊る。歌は掛声や囃子詞はやしことばの反復が多く、踊りは描写的な動作が多い。→ウポポ
リメーク【remake】
作り直すこと。「昔の映画の―」
り‐めん【裏面】
①うら。うらがわ。
②物事の外部には現れない面。内情。「政界の―を探る」
⇒りめん‐こうさく【裏面工作】
⇒りめん‐し【裏面史】
りめん‐こうさく【裏面工作】
物事を思いどおりに運ぶために、ひそかに交渉し準備すること。
⇒り‐めん【裏面】
りめん‐し【裏面史】
外部に現れない方面、裏話などを叙述した歴史。
⇒り‐めん【裏面】
リメンバー【remember】
①思い出すこと。
②覚えていること。
リモート【remote】
(遠隔の意)
⇒リモート‐コントロール【remote control】
⇒リモート‐センシング【remote sensing】
⇒リモート‐ターミナル【remote terminal】
リモート‐コントロール【remote control】
(→)遠隔操作。リモコン。
⇒リモート【remote】
リモート‐センシング【remote sensing】
遠隔測定または遠隔計測。特に、人工衛星・航空機などにより地表からの各種波長の電磁波エネルギーを測定し、そのデータや画像を伝送させて観測すること。
⇒リモート【remote】
リモート‐ターミナル【remote terminal】
コンピューター‐ネットワークに接続された端末装置。
⇒リモート【remote】
リモ‐コン
リモート‐コントロールの略。
り‐もつ【利物】
①稲・粟などを貸して得た利息分と貸した分。元利。令義解「―は並に糺たださむ人にたまへ」
②もうけ。利益。成果。〈日葡辞書〉
③〔仏〕(「物」は一切衆生をいう)(→)利生りしょうに同じ。平家物語1「慈悲具足の山王―の方便にてましませば」
⇒利物の垂迹
 リピド【lipid】
(→)脂質ししつ。
リビドー【Libido ドイツ】
(本来はラテン語で欲望の意)精神分析の主要概念の一つ。フロイトは、生の本能としての性的エネルギーと定義し、それが阻害されると様々な発達障害や神経症が生じるとする。また、ユングは、すべての本能のエネルギーの本体とする。
り‐びょう【利平】‥ビヤウ
利息。利子。また、高い利子による儲け。〈日葡辞書〉。建武以来追加「―においては廿一箇年を過ぎずは一倍たるべし」
り‐びょう【痢病】‥ビヤウ
腹痛・下痢が激しく、飴状の排泄物を出す病気。赤痢の類。日葡辞書「リビャウ。シボリハラ」
り‐びょう【罹病】‥ビヤウ
病気にかかること。「―率」
リビング【living】
①生きていること。生活。暮し。また、住まい。「モダン‐―」
②リビング‐ルームの略。
⇒リビング‐ウィル【living will】
⇒リビング‐ルーム【living room】
リビング‐ウィル【living will】
(willは意思・遺言の意)あらかじめ自らの延命措置等に関して意思表示しておく文書。
⇒リビング【living】
リビング‐シアター【Living Theatre】
アメリカの劇団。1947年結成。オフ‐ブロードウェーで注目されるが、反体制色の強い活動が妨害を受け64年にヨーロッパに移転。代表作「パラダイス‐ナウ」。
リビングストン【D. Livingstone】
⇒リヴィングストン
リビング‐ルーム【living room】
洋風の居間。リビング。
⇒リビング【living】
り‐ふ【嫠婦】
夫をなくした女。やもめ。
り‐ぶ【吏部】
(リホウとも)
①中国の六部りくぶの一つ。官吏の任免および功過の考査、勲爵の賜与をつかさどる。隋・唐に設けられ、清末に廃止。
②式部省の唐名。
リブ【lib】
(liberation(解放)の略)ウーマン‐リブの略。
リブ【rib】
(肋骨の意)リブ‐ロースの略。
リファイン【refine】
洗練すること。上品にすること。
リファレンス【reference】
⇒レファレンス
リファレンダム【referendum】
⇒レファレンダム
リブ‐ヴォールト【ribbed vault】
ヴォールトの一種。交差するヴォールトの稜線の下側に太いアーチ(リブ)を架け渡して補強したもの。ゴシック式の重要な特徴の一つ。
リフォーム【reform】
改良すること。作り直すこと。特に、衣服の仕立て直しや建物の改築・改装。
り‐ふく【利福】
利益と幸福。福利。
リプシッツ【Jacques Lipchitz】
フランス、立体派の代表的彫刻家。リトアニアの生れ。(1891〜1973)
りぶ‐しょうしょ【吏部尚書】‥シヤウ‥
中国の吏部の長官。
り‐ふじん【理不尽】
①道理を尽くさないこと。東鑑6「頼朝の申状たりといへども、―の裁許有るべからず候」
②道理にあわないこと。無理無体。こんてむつすむん地「―なる事を言ひかけらるる時」。「―な要求」
り‐ふだ【利札】
⇒りさつ
り‐ぶっしょう【理仏性】‥シヤウ
〔仏〕一切衆生しゅじょうのもつ仏となるべき性質。↔行仏性ぎょうぶっしょう
リフティング【lifting】
サッカー‐ボールを、地面に落とさないように手を使わないで打ち上げ続けること。
リフト【lift】
①昇降機。エレベーター。
②スキー場などの、架空ケーブルに椅子を吊した登山用装置。
③起重機。
④ポンプの揚程。
⑤ダンスやフィギュア‐スケートで、男性が女性を持ち上げること。
⇒リフトアップ‐こうほう【リフトアップ工法】
⇒リフト‐バルブ【lift valve】
リフトアップ‐こうほう【リフトアップ工法】‥ハフ
屋根組などを低所で組み立ててから所定の位置まで引き上げて設置する工法。
⇒リフト【lift】
リフト‐バルブ【lift valve】
昇降によって弁座の開閉する弁の総称。持上げ弁。
⇒リフト【lift】
リプリント【reprint】
①写真などの複写。
②復刻。翻刻。また、再版。
リフレイン【refrain】
詩や楽曲の中で、各節の後に同じ部分を繰り返すこと。また、その部分。折返し。畳句。ルフラン。
リプレー【replay】
①試合や演劇などを再び行うこと。
②録音・録画を再生すること。
リフレーション【reflation】
景気循環の過程で、デフレーションから脱し、しかもインフレーションにまで至っていない状態。不況における物価下落を正常水準まで引き上げて生産を刺激し、景気を回復させることを目的とした計画的な通貨の膨張。↔ディスインフレーション
リプレース【replace】
ゴルフで、規則に従って拾い上げた球を、元あった場所に置き戻すこと。
リフレクソロジー【reflexology】
掌てのひらや足裏などに身体の各器官の調子を反映した箇所があるという考えに基づき、それらを刺激して健康を維持・増進する療法。反射療法。
リフレクター【reflector】
反射器。反射鏡。反射板。レフレクター。
リフレックス【reflex】
⇒レフレックス
リプレッサー【repressor】
特定の遺伝子群の形質発現を抑制する蛋白質。レプレッサー。→オペロン説
リフレッシュ【refresh】
気分をさわやかに一新すること。元気を取り戻すこと。
⇒リフレッシュ‐きゅうか【リフレッシュ休暇】
リフレッシュ‐きゅうか【リフレッシュ休暇】‥キウ‥
気持をリフレッシュするために取る休暇。また、一定の勤続期間を経た者に与える休暇。
⇒リフレッシュ【refresh】
リフレッシュメント【refreshment】
①気分を新たにすること。
②爽快な気分を起こさせる飲物。
リブ‐ロース
(rib roast)牛肉の部位のうち背中の肩寄りの部分。霜降り状で柔らかい。ロースト‐ビーフ・ステーキなどに用いる。リブ。→牛肉(図)
リプロダクション【reproduction】
①模写。複写。複製。
②〔経〕(→)再生産。
③書籍の翻刻。
リプロダクティブ‐ヘルス【reproductive health】
性と生殖に関する健康。安全な性生活を営む権利が女性に認められるべきだとする理念。
リプロダクティブ‐ライツ【reproductive rights】
性と生殖に関する権利。妊娠・出産についての基本的な決定権が女性にあるとする立場からいう。
り‐ぶん【利分】
①利益となる分。利得。もうけ。浮世物語「今の商人は…米の直ねを上げんと―を守る程に」
②(→)利子に同じ。太平記35「本物ばかりを借り主に返納すべし。―は我添へて返すべし」
り‐ぶん【理分】
道理にかなう方。道理があり利益になる方。狂言、内沙汰「随分―になるやうに云はつしやれい」
り‐へい【利平】
⇒りびょう
り‐へい【利兵】
するどい刃物。鋭利な兵器。
リベート【rebate】
①支払代金の一部を支払者に謝礼として与えること。また、その金。割戻し。
②手数料。また、わいろ。
り‐べつ【離別】
①人に別れること。別離。
②夫婦の関係を断つこと。離婚。「―状」
リベッター【riveter】
(→)鋲締機びょうじめき。
リベッテッド‐ジョイント【riveted joint】
(→)リベット継手つぎてに同じ。
リベット【rivet】
頭の大きな釘くぎ。鋲びょう。締釘しめくぎ。
⇒リベット‐つぎて【リベット継手】
リベット‐つぎて【リベット継手】
金属板接続部をリベットで固定する接合法。重ね継手・突合せ継手などがある。鋲びょう継手。リベッテッド‐ジョイント。
⇒リベット【rivet】
リベラ【José de Ribera】
スペインの画家。イタリア各地で過ごし、ナポリに永住。厳格な写実を心掛け、カラヴァッジオの影響を受けた。明暗の対比の強い宗教画に佳作を残す。作「聖バルトロメオの殉教」など。(1591〜1652)
リベラ【Diego Rivera】
メキシコの画家。シケイロスに出会い、壁画運動に参加。作「社会主義と資本主義の岐路にある男」など。(1886〜1957)
リベラ
提供:ullstein bild/APL
リピド【lipid】
(→)脂質ししつ。
リビドー【Libido ドイツ】
(本来はラテン語で欲望の意)精神分析の主要概念の一つ。フロイトは、生の本能としての性的エネルギーと定義し、それが阻害されると様々な発達障害や神経症が生じるとする。また、ユングは、すべての本能のエネルギーの本体とする。
り‐びょう【利平】‥ビヤウ
利息。利子。また、高い利子による儲け。〈日葡辞書〉。建武以来追加「―においては廿一箇年を過ぎずは一倍たるべし」
り‐びょう【痢病】‥ビヤウ
腹痛・下痢が激しく、飴状の排泄物を出す病気。赤痢の類。日葡辞書「リビャウ。シボリハラ」
り‐びょう【罹病】‥ビヤウ
病気にかかること。「―率」
リビング【living】
①生きていること。生活。暮し。また、住まい。「モダン‐―」
②リビング‐ルームの略。
⇒リビング‐ウィル【living will】
⇒リビング‐ルーム【living room】
リビング‐ウィル【living will】
(willは意思・遺言の意)あらかじめ自らの延命措置等に関して意思表示しておく文書。
⇒リビング【living】
リビング‐シアター【Living Theatre】
アメリカの劇団。1947年結成。オフ‐ブロードウェーで注目されるが、反体制色の強い活動が妨害を受け64年にヨーロッパに移転。代表作「パラダイス‐ナウ」。
リビングストン【D. Livingstone】
⇒リヴィングストン
リビング‐ルーム【living room】
洋風の居間。リビング。
⇒リビング【living】
り‐ふ【嫠婦】
夫をなくした女。やもめ。
り‐ぶ【吏部】
(リホウとも)
①中国の六部りくぶの一つ。官吏の任免および功過の考査、勲爵の賜与をつかさどる。隋・唐に設けられ、清末に廃止。
②式部省の唐名。
リブ【lib】
(liberation(解放)の略)ウーマン‐リブの略。
リブ【rib】
(肋骨の意)リブ‐ロースの略。
リファイン【refine】
洗練すること。上品にすること。
リファレンス【reference】
⇒レファレンス
リファレンダム【referendum】
⇒レファレンダム
リブ‐ヴォールト【ribbed vault】
ヴォールトの一種。交差するヴォールトの稜線の下側に太いアーチ(リブ)を架け渡して補強したもの。ゴシック式の重要な特徴の一つ。
リフォーム【reform】
改良すること。作り直すこと。特に、衣服の仕立て直しや建物の改築・改装。
り‐ふく【利福】
利益と幸福。福利。
リプシッツ【Jacques Lipchitz】
フランス、立体派の代表的彫刻家。リトアニアの生れ。(1891〜1973)
りぶ‐しょうしょ【吏部尚書】‥シヤウ‥
中国の吏部の長官。
り‐ふじん【理不尽】
①道理を尽くさないこと。東鑑6「頼朝の申状たりといへども、―の裁許有るべからず候」
②道理にあわないこと。無理無体。こんてむつすむん地「―なる事を言ひかけらるる時」。「―な要求」
り‐ふだ【利札】
⇒りさつ
り‐ぶっしょう【理仏性】‥シヤウ
〔仏〕一切衆生しゅじょうのもつ仏となるべき性質。↔行仏性ぎょうぶっしょう
リフティング【lifting】
サッカー‐ボールを、地面に落とさないように手を使わないで打ち上げ続けること。
リフト【lift】
①昇降機。エレベーター。
②スキー場などの、架空ケーブルに椅子を吊した登山用装置。
③起重機。
④ポンプの揚程。
⑤ダンスやフィギュア‐スケートで、男性が女性を持ち上げること。
⇒リフトアップ‐こうほう【リフトアップ工法】
⇒リフト‐バルブ【lift valve】
リフトアップ‐こうほう【リフトアップ工法】‥ハフ
屋根組などを低所で組み立ててから所定の位置まで引き上げて設置する工法。
⇒リフト【lift】
リフト‐バルブ【lift valve】
昇降によって弁座の開閉する弁の総称。持上げ弁。
⇒リフト【lift】
リプリント【reprint】
①写真などの複写。
②復刻。翻刻。また、再版。
リフレイン【refrain】
詩や楽曲の中で、各節の後に同じ部分を繰り返すこと。また、その部分。折返し。畳句。ルフラン。
リプレー【replay】
①試合や演劇などを再び行うこと。
②録音・録画を再生すること。
リフレーション【reflation】
景気循環の過程で、デフレーションから脱し、しかもインフレーションにまで至っていない状態。不況における物価下落を正常水準まで引き上げて生産を刺激し、景気を回復させることを目的とした計画的な通貨の膨張。↔ディスインフレーション
リプレース【replace】
ゴルフで、規則に従って拾い上げた球を、元あった場所に置き戻すこと。
リフレクソロジー【reflexology】
掌てのひらや足裏などに身体の各器官の調子を反映した箇所があるという考えに基づき、それらを刺激して健康を維持・増進する療法。反射療法。
リフレクター【reflector】
反射器。反射鏡。反射板。レフレクター。
リフレックス【reflex】
⇒レフレックス
リプレッサー【repressor】
特定の遺伝子群の形質発現を抑制する蛋白質。レプレッサー。→オペロン説
リフレッシュ【refresh】
気分をさわやかに一新すること。元気を取り戻すこと。
⇒リフレッシュ‐きゅうか【リフレッシュ休暇】
リフレッシュ‐きゅうか【リフレッシュ休暇】‥キウ‥
気持をリフレッシュするために取る休暇。また、一定の勤続期間を経た者に与える休暇。
⇒リフレッシュ【refresh】
リフレッシュメント【refreshment】
①気分を新たにすること。
②爽快な気分を起こさせる飲物。
リブ‐ロース
(rib roast)牛肉の部位のうち背中の肩寄りの部分。霜降り状で柔らかい。ロースト‐ビーフ・ステーキなどに用いる。リブ。→牛肉(図)
リプロダクション【reproduction】
①模写。複写。複製。
②〔経〕(→)再生産。
③書籍の翻刻。
リプロダクティブ‐ヘルス【reproductive health】
性と生殖に関する健康。安全な性生活を営む権利が女性に認められるべきだとする理念。
リプロダクティブ‐ライツ【reproductive rights】
性と生殖に関する権利。妊娠・出産についての基本的な決定権が女性にあるとする立場からいう。
り‐ぶん【利分】
①利益となる分。利得。もうけ。浮世物語「今の商人は…米の直ねを上げんと―を守る程に」
②(→)利子に同じ。太平記35「本物ばかりを借り主に返納すべし。―は我添へて返すべし」
り‐ぶん【理分】
道理にかなう方。道理があり利益になる方。狂言、内沙汰「随分―になるやうに云はつしやれい」
り‐へい【利平】
⇒りびょう
り‐へい【利兵】
するどい刃物。鋭利な兵器。
リベート【rebate】
①支払代金の一部を支払者に謝礼として与えること。また、その金。割戻し。
②手数料。また、わいろ。
り‐べつ【離別】
①人に別れること。別離。
②夫婦の関係を断つこと。離婚。「―状」
リベッター【riveter】
(→)鋲締機びょうじめき。
リベッテッド‐ジョイント【riveted joint】
(→)リベット継手つぎてに同じ。
リベット【rivet】
頭の大きな釘くぎ。鋲びょう。締釘しめくぎ。
⇒リベット‐つぎて【リベット継手】
リベット‐つぎて【リベット継手】
金属板接続部をリベットで固定する接合法。重ね継手・突合せ継手などがある。鋲びょう継手。リベッテッド‐ジョイント。
⇒リベット【rivet】
リベラ【José de Ribera】
スペインの画家。イタリア各地で過ごし、ナポリに永住。厳格な写実を心掛け、カラヴァッジオの影響を受けた。明暗の対比の強い宗教画に佳作を残す。作「聖バルトロメオの殉教」など。(1591〜1652)
リベラ【Diego Rivera】
メキシコの画家。シケイロスに出会い、壁画運動に参加。作「社会主義と資本主義の岐路にある男」など。(1886〜1957)
リベラ
提供:ullstein bild/APL
 リベラリスト【liberalist】
自由主義者。
リベラリズム【liberalism】
(→)自由主義。
リベラル【liberal】
①個人の自由、個性を重んずるさま。自由主義的。
②自由主義者。
⇒リベラル‐アーツ【liberal arts】
リベラル‐アーツ【liberal arts】
①(→)自由学芸に同じ。
②自由な心や批判的知性の育成、また自己覚醒を目的にした大学の教養教育の課程。
⇒リベラル【liberal】
リベリア【Liberia】
アフリカ西部、大西洋に面する共和国。1820年アメリカの解放奴隷が移住・建国、47年独立。便宜置籍船制度により、世界一の商船保有国。面積11万平方キロメートル。人口287万9千(1997)。首都モンロヴィア。→アフリカ(図)
リベル【Liber】
ローマの古神。生産と豊穣の神。ギリシア神話のディオニュソスと同一視された。
リベロ【libero イタリア】
(「自由な」の意)
①サッカーで、通常はゴール前を守るが、自由に攻撃にも参加する選手。
②バレーボールで、守備専門の選手。他の選手とは異なるユニフォームを着用する。
り‐べん【利便】
便利。便宜。「―をはかる」
り‐べん【離弁・離瓣】
(花弁の分離している意)
⇒りべん‐か【離弁花】
⇒りべん‐かかん【離弁花冠】
⇒りべんか‐るい【離弁花類】
りべん‐か【離弁花】‥クワ
離弁花冠をもつ花。↔合弁花。
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
りべん‐かかん【離弁花冠】‥クワクワン
一つの花にある全花弁が互いに分離している花冠。ウメ・サクラの花の類。↔合弁花冠。
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
りべんか‐るい【離弁花類】‥クワ‥
双子葉植物のうち、花冠が全く無いかまたは離弁花冠をもつ群。ブナ科・ナデシコ科・バラ科・マメ科など。↔合弁花類
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
リベンジ【revenge】
復讐。雪辱戦。
リポイド【lipoid】
(→)類脂質。
り‐ほう【吏部】
(ホウは漢音)
⇒りぶ
り‐ほう【李鵬】
(Li Peng)中国の政治家。上海生れ。1948年モスクワ留学。電力工業部部長・中共中央政治局委員などを経て88〜98年国務院総理。(1928〜)
り‐ほう【理法】‥ハフ
のっとるべき道理。規則。法則。
り‐ぼうよう【李夢陽】‥ヤウ
(リムヨウとも)明の詩文家。字は献吉。号は空同子。甘粛慶陽の人。明代古文辞派の首唱者、前七子の一人。著「空同子集」。(1472〜1529)→七子しちし
リボー【Théodule Armand Ribot】
フランスの心理学者。病態心理学や感情研究の分野で活躍。著「感情の心理学」など。(1839〜1916)
リボース【ribose】
分子式C5H10O5 ペントースの一つ。白色の結晶。リボ核酸や種々の補酵素の構成成分として広く生体に分布。
リポーター【reporter】
⇒レポーター
リポート【report】
⇒レポート
リボ‐かくさん【リボ核酸】
(ribonucleic acid)リボースを含む核酸。RNAと略記。デオキシリボ核酸とともに蛋白質生合成に関与、またRNAウイルスでは遺伝情報の保存・複製を行う。リボソームの重要成分をなす。メッセンジャーRNA、転移RNAなどがある。
リポ‐さん【リポ酸】
(lipoic acid)ビタミン様作用物質の一つで、微生物の発育に必要な因子。人では、必要量は腸内細菌が合成。チオクト酸。
リポジショニング【repositioning】
競合商品に対して自社商品を位置づけ直し、差異を明確にして宣伝すること。
リボソーム【ribosome】
細胞質中に遊離するか、または小胞体や核膜と結合して存在する小顆粒。蛋白質の生合成、すなわち翻訳が行われる。ミトコンドリア・葉緑体は独自のものをもつ。
リポソーム【liposome】
生体膜と同じくリン脂質の二分子膜の構造からなる微少なカプセル。薬剤投与の目的で開発されたが、細胞生物学研究のモデルとしても用いる。
リポ‐たんぱくしつ【リポ蛋白質】
(lipoprotein)複合蛋白質の一種で、蛋白質と脂質とが結合したものの総称。血漿・卵黄などに含まれる。
リボヌクレアーゼ【ribonuclease】
RNAを分解する酵素の総称。動植物・微生物に広く分布。作用機序、基質の特異性の異なる多数の種類が存在する。
リボ‐ばらい【リボ払い】‥バラヒ
リボルビング方式による支払い。
リボフラビン【riboflavin】
(→)ビタミンB2に同じ。
リボルバー【revolver】
回転式の連発拳銃。
リボルビング【revolving】
(回転の意)クレジット‐カード等による分割払いの一つ。総借入れ限度額を設定し、予め定めた一定額ずつ毎月返済していく方式。
リボン【ribbon】
絹・合成繊維などで織った細幅のひも。衣服・帽子・頭髪や贈り物の装飾として用いる。夏目漱石、坊つちやん「花月巻、白い―のハイカラ頭、乗るは自転車、弾くは
リベラリスト【liberalist】
自由主義者。
リベラリズム【liberalism】
(→)自由主義。
リベラル【liberal】
①個人の自由、個性を重んずるさま。自由主義的。
②自由主義者。
⇒リベラル‐アーツ【liberal arts】
リベラル‐アーツ【liberal arts】
①(→)自由学芸に同じ。
②自由な心や批判的知性の育成、また自己覚醒を目的にした大学の教養教育の課程。
⇒リベラル【liberal】
リベリア【Liberia】
アフリカ西部、大西洋に面する共和国。1820年アメリカの解放奴隷が移住・建国、47年独立。便宜置籍船制度により、世界一の商船保有国。面積11万平方キロメートル。人口287万9千(1997)。首都モンロヴィア。→アフリカ(図)
リベル【Liber】
ローマの古神。生産と豊穣の神。ギリシア神話のディオニュソスと同一視された。
リベロ【libero イタリア】
(「自由な」の意)
①サッカーで、通常はゴール前を守るが、自由に攻撃にも参加する選手。
②バレーボールで、守備専門の選手。他の選手とは異なるユニフォームを着用する。
り‐べん【利便】
便利。便宜。「―をはかる」
り‐べん【離弁・離瓣】
(花弁の分離している意)
⇒りべん‐か【離弁花】
⇒りべん‐かかん【離弁花冠】
⇒りべんか‐るい【離弁花類】
りべん‐か【離弁花】‥クワ
離弁花冠をもつ花。↔合弁花。
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
りべん‐かかん【離弁花冠】‥クワクワン
一つの花にある全花弁が互いに分離している花冠。ウメ・サクラの花の類。↔合弁花冠。
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
りべんか‐るい【離弁花類】‥クワ‥
双子葉植物のうち、花冠が全く無いかまたは離弁花冠をもつ群。ブナ科・ナデシコ科・バラ科・マメ科など。↔合弁花類
⇒り‐べん【離弁・離瓣】
リベンジ【revenge】
復讐。雪辱戦。
リポイド【lipoid】
(→)類脂質。
り‐ほう【吏部】
(ホウは漢音)
⇒りぶ
り‐ほう【李鵬】
(Li Peng)中国の政治家。上海生れ。1948年モスクワ留学。電力工業部部長・中共中央政治局委員などを経て88〜98年国務院総理。(1928〜)
り‐ほう【理法】‥ハフ
のっとるべき道理。規則。法則。
り‐ぼうよう【李夢陽】‥ヤウ
(リムヨウとも)明の詩文家。字は献吉。号は空同子。甘粛慶陽の人。明代古文辞派の首唱者、前七子の一人。著「空同子集」。(1472〜1529)→七子しちし
リボー【Théodule Armand Ribot】
フランスの心理学者。病態心理学や感情研究の分野で活躍。著「感情の心理学」など。(1839〜1916)
リボース【ribose】
分子式C5H10O5 ペントースの一つ。白色の結晶。リボ核酸や種々の補酵素の構成成分として広く生体に分布。
リポーター【reporter】
⇒レポーター
リポート【report】
⇒レポート
リボ‐かくさん【リボ核酸】
(ribonucleic acid)リボースを含む核酸。RNAと略記。デオキシリボ核酸とともに蛋白質生合成に関与、またRNAウイルスでは遺伝情報の保存・複製を行う。リボソームの重要成分をなす。メッセンジャーRNA、転移RNAなどがある。
リポ‐さん【リポ酸】
(lipoic acid)ビタミン様作用物質の一つで、微生物の発育に必要な因子。人では、必要量は腸内細菌が合成。チオクト酸。
リポジショニング【repositioning】
競合商品に対して自社商品を位置づけ直し、差異を明確にして宣伝すること。
リボソーム【ribosome】
細胞質中に遊離するか、または小胞体や核膜と結合して存在する小顆粒。蛋白質の生合成、すなわち翻訳が行われる。ミトコンドリア・葉緑体は独自のものをもつ。
リポソーム【liposome】
生体膜と同じくリン脂質の二分子膜の構造からなる微少なカプセル。薬剤投与の目的で開発されたが、細胞生物学研究のモデルとしても用いる。
リポ‐たんぱくしつ【リポ蛋白質】
(lipoprotein)複合蛋白質の一種で、蛋白質と脂質とが結合したものの総称。血漿・卵黄などに含まれる。
リボヌクレアーゼ【ribonuclease】
RNAを分解する酵素の総称。動植物・微生物に広く分布。作用機序、基質の特異性の異なる多数の種類が存在する。
リボ‐ばらい【リボ払い】‥バラヒ
リボルビング方式による支払い。
リボフラビン【riboflavin】
(→)ビタミンB2に同じ。
リボルバー【revolver】
回転式の連発拳銃。
リボルビング【revolving】
(回転の意)クレジット‐カード等による分割払いの一つ。総借入れ限度額を設定し、予め定めた一定額ずつ毎月返済していく方式。
リボン【ribbon】
絹・合成繊維などで織った細幅のひも。衣服・帽子・頭髪や贈り物の装飾として用いる。夏目漱石、坊つちやん「花月巻、白い―のハイカラ頭、乗るは自転車、弾くは イオリン」。「―を結ぶ」「―を掛ける」
⇒リボン‐グラス【ribbon-grass】
⇒リボン‐ししゅう【リボン刺繍】
リボン‐グラス【ribbon-grass】
イネ科の多年草。ヨーロッパ原産。地下茎はチョロギに似た白色の念珠状。葉は長さ約30センチメートルで、縦に白縞がある。夏の末に枯れ、初冬にまた芽を出す。花壇のへり植えなどに栽培。リボンガヤ。
リボン-グラス
イオリン」。「―を結ぶ」「―を掛ける」
⇒リボン‐グラス【ribbon-grass】
⇒リボン‐ししゅう【リボン刺繍】
リボン‐グラス【ribbon-grass】
イネ科の多年草。ヨーロッパ原産。地下茎はチョロギに似た白色の念珠状。葉は長さ約30センチメートルで、縦に白縞がある。夏の末に枯れ、初冬にまた芽を出す。花壇のへり植えなどに栽培。リボンガヤ。
リボン-グラス
 ⇒リボン【ribbon】
リボン‐ししゅう【リボン刺繍】‥シウ
細いリボンを用いて刺す刺繍の総称。服飾のほか室内の装飾品や小物などに応用する。
⇒リボン【ribbon】
リマ【Lima】
南米、ペルー共和国の首都。1535年ピサロの創建した植民地都市。太平洋岸に位置し、外港はカヤオ。人口707万5千(2003)。
リマ
撮影:田沼武能
⇒リボン【ribbon】
リボン‐ししゅう【リボン刺繍】‥シウ
細いリボンを用いて刺す刺繍の総称。服飾のほか室内の装飾品や小物などに応用する。
⇒リボン【ribbon】
リマ【Lima】
南米、ペルー共和国の首都。1535年ピサロの創建した植民地都市。太平洋岸に位置し、外港はカヤオ。人口707万5千(2003)。
リマ
撮影:田沼武能
 り‐まい【利米】
借米の利息として払う米。
り‐まとう【利瑪竇】
マテオ=リッチの漢名。
り‐まわし【利回し】‥マハシ
利息を得るために金銭を他に貸し出すこと。利殖をはかること。
り‐まわり【利回り】‥マハリ
利益配当または利息の元金に対する割合。「―が良い」
リマン‐かいりゅう【リマン海流】‥リウ
(リマン(liman ロシア)は「河口の潟」の意)日本近海の寒流の一つ。日本海北隅に発し、大陸沿岸を経て朝鮮半島東岸に達する。→海流(図)
リミット【limit】
限度。限界。範囲。極限。
⇒リミット‐ゲージ【limit gauge】
リミット‐ゲージ【limit gauge】
〔機〕(→)限界ゲージに同じ。
⇒リミット【limit】
り‐みん【里民】
村里の民。その里の人。
り‐みん【理民】
民を治めること。治民。
り‐む【吏務】
役人としての職務。
リム【rim】
車の外周をなす環状部分。自動車などの車輪では、この部分にタイヤを固定する。
リムーバー【remover】
ペンキやマニキュアを除去する溶剤。→除光液
リムジン【limousine フランス】
①運転席と座席との間に仕切りがある公式用の豪華な箱型乗用車。→自動車(図)。
②空港などの送迎用バス。リムジン‐バス。
リムスキー‐コルサコフ【Nikolai Rimskii-Korsakov】
ロシアの作曲家。ロシア国民楽派の一人。色彩的な管弦楽法と楽想とで著名。交響組曲「シェエラザード」、管弦楽曲「スペイン奇想曲」、歌劇「金鶏」など。(1844〜1908)
リムスキー‐コルサコフ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
り‐まい【利米】
借米の利息として払う米。
り‐まとう【利瑪竇】
マテオ=リッチの漢名。
り‐まわし【利回し】‥マハシ
利息を得るために金銭を他に貸し出すこと。利殖をはかること。
り‐まわり【利回り】‥マハリ
利益配当または利息の元金に対する割合。「―が良い」
リマン‐かいりゅう【リマン海流】‥リウ
(リマン(liman ロシア)は「河口の潟」の意)日本近海の寒流の一つ。日本海北隅に発し、大陸沿岸を経て朝鮮半島東岸に達する。→海流(図)
リミット【limit】
限度。限界。範囲。極限。
⇒リミット‐ゲージ【limit gauge】
リミット‐ゲージ【limit gauge】
〔機〕(→)限界ゲージに同じ。
⇒リミット【limit】
り‐みん【里民】
村里の民。その里の人。
り‐みん【理民】
民を治めること。治民。
り‐む【吏務】
役人としての職務。
リム【rim】
車の外周をなす環状部分。自動車などの車輪では、この部分にタイヤを固定する。
リムーバー【remover】
ペンキやマニキュアを除去する溶剤。→除光液
リムジン【limousine フランス】
①運転席と座席との間に仕切りがある公式用の豪華な箱型乗用車。→自動車(図)。
②空港などの送迎用バス。リムジン‐バス。
リムスキー‐コルサコフ【Nikolai Rimskii-Korsakov】
ロシアの作曲家。ロシア国民楽派の一人。色彩的な管弦楽法と楽想とで著名。交響組曲「シェエラザード」、管弦楽曲「スペイン奇想曲」、歌劇「金鶏」など。(1844〜1908)
リムスキー‐コルサコフ
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
 →交響組曲「シェエラザード」王子と王女
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
リムセ
アイヌの伝承歌舞。輪座して歌ううちに興が乗ると立って歌い踊る。歌は掛声や囃子詞はやしことばの反復が多く、踊りは描写的な動作が多い。→ウポポ
リメーク【remake】
作り直すこと。「昔の映画の―」
り‐めん【裏面】
①うら。うらがわ。
②物事の外部には現れない面。内情。「政界の―を探る」
⇒りめん‐こうさく【裏面工作】
⇒りめん‐し【裏面史】
りめん‐こうさく【裏面工作】
物事を思いどおりに運ぶために、ひそかに交渉し準備すること。
⇒り‐めん【裏面】
りめん‐し【裏面史】
外部に現れない方面、裏話などを叙述した歴史。
⇒り‐めん【裏面】
リメンバー【remember】
①思い出すこと。
②覚えていること。
リモート【remote】
(遠隔の意)
⇒リモート‐コントロール【remote control】
⇒リモート‐センシング【remote sensing】
⇒リモート‐ターミナル【remote terminal】
リモート‐コントロール【remote control】
(→)遠隔操作。リモコン。
⇒リモート【remote】
リモート‐センシング【remote sensing】
遠隔測定または遠隔計測。特に、人工衛星・航空機などにより地表からの各種波長の電磁波エネルギーを測定し、そのデータや画像を伝送させて観測すること。
⇒リモート【remote】
リモート‐ターミナル【remote terminal】
コンピューター‐ネットワークに接続された端末装置。
⇒リモート【remote】
リモ‐コン
リモート‐コントロールの略。
り‐もつ【利物】
①稲・粟などを貸して得た利息分と貸した分。元利。令義解「―は並に糺たださむ人にたまへ」
②もうけ。利益。成果。〈日葡辞書〉
③〔仏〕(「物」は一切衆生をいう)(→)利生りしょうに同じ。平家物語1「慈悲具足の山王―の方便にてましませば」
⇒利物の垂迹
→交響組曲「シェエラザード」王子と王女
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
リムセ
アイヌの伝承歌舞。輪座して歌ううちに興が乗ると立って歌い踊る。歌は掛声や囃子詞はやしことばの反復が多く、踊りは描写的な動作が多い。→ウポポ
リメーク【remake】
作り直すこと。「昔の映画の―」
り‐めん【裏面】
①うら。うらがわ。
②物事の外部には現れない面。内情。「政界の―を探る」
⇒りめん‐こうさく【裏面工作】
⇒りめん‐し【裏面史】
りめん‐こうさく【裏面工作】
物事を思いどおりに運ぶために、ひそかに交渉し準備すること。
⇒り‐めん【裏面】
りめん‐し【裏面史】
外部に現れない方面、裏話などを叙述した歴史。
⇒り‐めん【裏面】
リメンバー【remember】
①思い出すこと。
②覚えていること。
リモート【remote】
(遠隔の意)
⇒リモート‐コントロール【remote control】
⇒リモート‐センシング【remote sensing】
⇒リモート‐ターミナル【remote terminal】
リモート‐コントロール【remote control】
(→)遠隔操作。リモコン。
⇒リモート【remote】
リモート‐センシング【remote sensing】
遠隔測定または遠隔計測。特に、人工衛星・航空機などにより地表からの各種波長の電磁波エネルギーを測定し、そのデータや画像を伝送させて観測すること。
⇒リモート【remote】
リモート‐ターミナル【remote terminal】
コンピューター‐ネットワークに接続された端末装置。
⇒リモート【remote】
リモ‐コン
リモート‐コントロールの略。
り‐もつ【利物】
①稲・粟などを貸して得た利息分と貸した分。元利。令義解「―は並に糺たださむ人にたまへ」
②もうけ。利益。成果。〈日葡辞書〉
③〔仏〕(「物」は一切衆生をいう)(→)利生りしょうに同じ。平家物語1「慈悲具足の山王―の方便にてましませば」
⇒利物の垂迹
○理も非もないりもひもない🔗⭐🔉
○理も非もないりもひもない
道理に合っていようがいまいが、かまわない。事を進めるのに精一杯で、道理を考える余裕がない。
⇒り【理】
リヤ【rear】
⇒リア
リヤ‐カー
(和製語rear car)自転車の後尾につけたり、人が引いたりして物を運ぶのに用いる二輪車。
りゃく【掠】
永字八法の一つ。「永」の第3画の左下払い。
りゃく【略】
はぶくこと。簡単にすること。あらまし。「以下、―」
り‐やく【利益】
①〔仏〕ためになること。法力によって恩恵を与えること。自らを益するのを功徳くどく、他を益するのを利益という。
②神仏の力によって授かる利福。利生りしょう。「ご―」
りゃく‐い【略意】
あらましの意味。
りゃく‐おう【略押】‥アフ
「花押かおう」参照。
りゃくおう【暦応】
(レキオウとも)[帝王代記]南北朝時代の北朝、光明こうみょう天皇朝の年号。建武5年8月28日(1338年10月11日)改元、暦応5年4月27日(1342年6月1日)康永に改元。
りゃく‐が【略画】‥グワ
細かい部分を省略して描いた絵。
りゃく‐ぎ【略儀】
(→)略式に同じ。「―ながら書面を以て」
りゃく‐げ【略解】
簡単な解釈。また、その書物。りゃっかい。「万葉集―」
りゃく‐げん【略言】
①全体を要約して簡略に言うこと。
②語中の音を省略してできたことば。「あさあけ」を「あさけ」、「うらうら」を「うらら」という類。約言。
りゃく‐ご【略語】
語形の一部を省略して簡略にした語。「国民体育大会」を「国体」、「ストライキ」を「スト」という類。
りゃく‐こう【歴劫】‥コフ
〔仏〕(リャッコウとも)多くの劫を経ること。
⇒りゃくこう‐しゅぎょう【歴劫修行】
⇒りゃくこう‐ふしぎ【歴劫不思議】
りゃく‐ごう【略号】‥ガウ
簡略に表すために定めた記号。
りゃくこう‐しゅぎょう【歴劫修行】‥コフ‥ギヤウ
菩薩が成仏するまで、多くの劫を経て修行すること。
⇒りゃく‐こう【歴劫】
りゃくこう‐ふしぎ【歴劫不思議】‥コフ‥
永久にわからないこと。平家物語1「―力及ばず」
⇒りゃく‐こう【歴劫】
りゃく‐さい【略載】
(明治期の語)要点を簡単に記載すること。おおまかに述べ記すこと。
りゃく‐じ【略字】
字画の複雑な漢字について、その点・画かくを省いて簡略にした文字。また、その漢字に代用される字形の簡略な文字。「應」を「応」、「學」を「学」、「釋」を「釈」と書く類。
りゃく‐しき【略式】
正式の手続や様式を省略して簡単にした方式。略儀。「―の礼服」
⇒りゃくしき‐きそ【略式起訴】
⇒りゃくしき‐てつづき【略式手続】
⇒りゃくしき‐ひきうけ【略式引受】
りゃくしき‐きそ【略式起訴】
〔法〕略式手続で検察官が請求する起訴。
⇒りゃく‐しき【略式】
りゃくしき‐てつづき【略式手続】
〔法〕公判手続を開かず書面審理で罰金・科料を決定する刑事特別手続。簡易裁判所で行われ、これによる裁判を略式命令という。
⇒りゃく‐しき【略式】
りゃくしき‐ひきうけ【略式引受】
引受の旨の表示がなく、支払人の署名だけによる手形引受。
⇒りゃく‐しき【略式】
りゃく‐しゅ【略取】
奪い取ること。かすめとること。脅迫または暴力を以て取ること。
⇒りゃくしゅ‐ゆうかい‐ざい【略取誘拐罪】
りゃく‐じゅ【略頌】
⇒りゃくしょう
りゃく‐じゅ【略綬】
勲章・記章などの略式の綬。
りゃく‐じゅつ【略述】
あらましを述べること。概略を述べること。略叙。
りゃくしゅ‐ゆうかい‐ざい【略取誘拐罪】‥イウ‥
他人を一定の保護状態から離して自己または第三者の支配内に移す罪。暴行脅迫によるのが略取罪、偽計・甘言を用いるのが誘拐罪。
⇒りゃく‐しゅ【略取】
りゃく‐じょ【略叙】
(→)略述に同じ。
りゃく‐しょう【略称】
名前を省略して呼ぶこと。また、省略して呼ぶ名前。「国際連合」を「国連」と呼ぶ類。
りゃく‐しょう【略章】‥シヤウ
勲章の略式のもの。
りゃく‐しょう【略頌】
(「頌」は詩経の詩の一体。短い詩の形式の意)人物・物名などを印象づけるために詩歌の形式に読み込んだもの。古今著聞集7「美福門は田広し、朱雀門は米雀門と―に作りて嘲り」
りゃく‐じょう【略定】‥ヂヤウ
簡単にした儀式。略儀。略式。大鏡伊尹「御葬送の沙汰をむげに―に書き置かせ給へりければ」
りゃく・す【略す】
[一]〔他五〕
(→)「略する」(サ変)に同じ。
[二]〔他サ変〕
⇒りゃくする
りゃく‐ず【略図】‥ヅ
簡略な図。細部をはぶき、主要な点だけを書いた図。
りゃく・する【略する】
〔他サ変〕[文]略す(サ変)
①はぶく。簡単にする。「敬称を―・する」
②(「掠する」とも)かすめとる。攻めとる。
りゃく‐せつ【略説】
概略を説くこと。また、そのもの。
りゃく‐そう【略装】‥サウ
略式の服装。↔正装
りゃく‐たい【略体】
正式のものを略した姿や形。特に字体などにいう。「―字」
りゃく‐だつ【略奪・掠奪】
かすめうばうこと。むりやり奪い取ること。「大金を―する」
⇒りゃくだつ‐こん【略奪婚】
⇒りゃくだつ‐のうぎょう【略奪農業】
りゃくだつ‐こん【略奪婚】
女性を他民族や他親族集団から略奪して妻とすること。
⇒りゃく‐だつ【略奪・掠奪】
りゃくだつ‐のうぎょう【略奪農業】‥ゲフ
原始的農法の一つ。作物に肥料をやらずに収穫する農業。一定年限後には同一耕地での耕作を放棄する。焼畑はその一例。奪略農業。
⇒りゃく‐だつ【略奪・掠奪】
りゃく‐でん【略伝】
経歴の概略を書いた伝記。簡略な伝記。
りゃく‐どく【略読】
ざっと読むこと。
りゃくにん【暦仁】
(レキニンとも)[隋書音楽志]鎌倉中期、四条天皇朝の年号。嘉禎4年11月23日(1238年12月30日)改元、暦仁2年2月7日(1239年3月13日)延応に改元。
りゃく‐ひつ【略筆】
①主要な点以外を省略して書くこと。また、その文章。略文。
②文字の筆画ひっかくを略して書くこと。略字。
りゃく‐ひょう【略表】‥ヘウ
簡単な表。大略を示した表。
りゃく‐ふ【略譜】
〔音〕(→)数字譜に同じ。
りゃく‐ふく【略服】
略儀の衣服。正式でない服装。略装。
りゃく‐ぶん【略文】
主要な点以外を省略して書いた文章。
りゃく‐ほう【略法】‥ハフ
簡略な方法。手軽な方法。
りゃく‐ぼう【略帽】
①略式の帽子。
②軍隊で、戦闘・訓練の場合などに用いた帽子。戦闘帽。戦帽。
りゃく‐ほん【略本】
①内容の一部を省略した書籍。抄本。
②同一作品の伝本のうち、省略や欠脱のために、他に比して内容の少ないもの。↔広本こうほん
りゃく‐ほんれき【略本暦】
本暦を基準とし、一般の人に便利な事柄だけを抜き出したこよみ。略暦。
りゃく‐みょう【歴名】‥ミヤウ
氏名を順次に列記すること。れきめい。
りゃく‐めい【略名】
正式の名前の一部を省略した名称。
りゃく‐りょ【掠虜】
かすめとってとりことすること。
りゃく‐りょう【掠領】‥リヤウ
掠奪し領有すること。平家物語9「隣境・遠境数国を―して」
りゃく‐れいふく【略礼服】
略式の礼服。
りゃく‐れき【略暦】
(→)略本暦に同じ。
りゃく‐れき【略歴】
簡略な経歴。また、それを書きしるしたもの。
りゃく‐ろん【略論】
簡略に論ずること。概略を論ずること。また、その論議。
リャザーノフ【David Borisovich Ryazanov】
ソ連のマルクス学者。「マルクス‐エンゲルス全集(初版)」などを編集。(1870〜1938)
りゃっ‐か【略訛】リヤククワ
語の省略となまり。
りゃっ‐かい【略解】リヤク‥
⇒りゃくげ
りゃっ‐き【略記】リヤク‥
簡略に記すこと。また、その記したもの。「いきさつを―する」
りゃっ‐くん【略訓】リヤク‥
万葉集における用字法の一つ。漢字の訓を一部省略して用いるもの。「足」をアまたはシに当てる類。
りゃっ‐こう【歴劫】リヤクコフ
⇒りゃくこう。日葡辞書「リャッコウ、コウヲフル」
リヤド【Riyadh】
サウジ‐アラビア王国の首都。オアシスを基礎に発展、ネジド地方の中心地。人口272万3千(1992)。
リャノス【Llanos スペイン】
(大平原の意)南アメリカ北部、ベネズエラとコロンビア東部にわたる、オリノコ川流域の高原性の熱帯草原。リャノ。
リャマ【llama スペイン・羊駝】
ラクダ科の哺乳類。背に肉瘤がなく、体長約2メートル。毛色は白か白地に茶または黒の斑。グアナコを家畜化したものといわれ、肉は食用、乳汁は美味。アンデス山地で使役に供される。ラマ。アメリカらくだ。
リャマ
 リャマ
提供:東京動物園協会
リャマ
提供:東京動物園協会
 リヤル【riyal】
サウジ‐アラビアの貨幣単位。1リヤルは20クルーシュ(qurush)。
りゃん【両】
(唐音)
①数の「2」。特に拳けんでの呼称。
②(→)両個りゃんこ2の略。
→りょう(両)
リャンガン‐ド【両江道】
(Ryanggang-do)朝鮮民主主義人民共和国北部の内陸の道。1949年咸鏡南道から分離して設置。北は豆満江・鴨緑江を隔てて中国と接する。林産資源に富む。道都は恵山ヘサン。→朝鮮(図)
りゃん‐こ【両個】
(リャンは唐音)
①2個。二つ。
②(両刀を佩おびたからいう)武士をあざけっていう語。りゃん。花暦八笑人「何処の侍か知らねえが、しかつべらしい―が腰をかけて居る」
りゅう【六】リウ
(唐音)清楽しんがくの音譜、または拳けんで、数の「6」をいう語。むつ。浮世風呂3「―や五ごうやと、ヤの字を付けるのがや拳さ」
りゅう【柳】リウ
二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざに当たる。柳宿。ぬりこぼし。
りゅう【流】リウ
(呉音はル)
①ながれること。ながすこと。ながれ。謡曲、安宅「面白や、山水に杯を浮かめては、―に牽かるる曲水の」
②血筋。系統。学術・芸能などで、その人・家の特有な方式。固有なやり方。「御家―」
③仲間。たぐい。社会の階層。「二―」
④(「旒」の通用字)旗を数える語。
→る(流)
りゅう【留】リウ
(呉音はル)〔天〕惑星が天球上で順行と逆行との境目に一時停って見える現象。また、その時刻・位置。
りゅう【竜】
(慣用音。漢音はリョウ)
①想像上の動物。たつ。
㋐〔仏〕(梵語nāga)インド神話で、蛇を神格化した人面蛇身の半神。大海や地底に住し、雲雨を自在に支配する力を持つとされる。仏教では古くから仏伝に現れ、また仏法守護の天竜八部衆の一つとされた。
㋑中国で、神霊視される鱗虫の長。鳳ほう・麟りん・亀きとともに四瑞の一つ。よく雲を起こし雨を呼ぶという。竹取物語「はやても―の吹かする也」
㋒ドラゴンのこと。
②化石時代の、大形の爬虫類を表す語。「首長―」
③すぐれた人物のたとえ。
④天子に関する物事に冠する語。
⑤将棋で、飛車の成ったもの。
⇒竜吟ずれば雲起こる
⇒竜の雲を得る如し
⇒竜の髭を蟻がねらう
⇒竜は一寸にして昇天の気あり
りゅう【粒】リフ
つぶ。穀物の種子。小さな固体。また、それを数える語。
りゅう【笠】リフ
姓氏の一つ。
⇒りゅう‐しんたろう【笠信太郎】
⇒りゅう‐ちしゅう【笠智衆】
りゅう【硫】リウ
①非金属元素の一つ。いおう。
②硫酸の略。
り‐ゆう【理由】‥イウ
①物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
②〔哲〕一般には存在や生成の根拠となるもの。論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。↔帰結。
⇒りゆう‐の‐げんり【理由の原理】
りゅう‐あ【流亜】リウ‥
(→)亜流ありゅうに同じ。
りゅう‐あん【硫安】リウ‥
(→)硫酸アンモニウムの俗称。重要な窒素肥料の一つ。
りゅう‐あん【劉安】リウ‥
漢の学者。高祖劉邦の孫。淮南わいなん王に封じられ、のち謀叛を企て自殺。編著「淮南子えなんじ」。( 〜前122)
りゅう‐あん【劉晏】リウ‥
唐の政治家。河北南華の人。安史の乱後、塩の専売業によって財政再建に尽くし、宰相。(715頃〜780)
りゅうあん‐かめい【柳暗花明】リウ‥クワ‥
①柳は繁って暗く、花は咲いて明るいこと。春の野の美しいながめ。
②転じて、花柳街。色町。色里。
りゅうあん‐じ【竜安寺】
⇒りょうあんじ
りゅう‐い【留意】リウ‥
ある物事に心を留めること。気をつけること。注意。「服装に―する」「―点」
りゅう‐いき【流域】リウヰキ
河川の流れ行く地域。また、その河川の四囲にある分水界によって囲まれた区域。「信濃川の―」
りゅう‐いちょう【劉以鬯】リウ‥チヤウ
(Liu Yichang)香港の作家。本名、劉同繹。代表作「酒徒」は意識の流れの手法で売文業暮しの文化人の苦悩と孤独を描く。(1918〜)
りゅう‐いん【溜飲】リウ‥
胃の具合が悪く、酸性のおくびを生ずること。胸焼け。浮世風呂前「五十韻百韻などとくると、―で又わざをなすて」
⇒溜飲が下がる
リヤル【riyal】
サウジ‐アラビアの貨幣単位。1リヤルは20クルーシュ(qurush)。
りゃん【両】
(唐音)
①数の「2」。特に拳けんでの呼称。
②(→)両個りゃんこ2の略。
→りょう(両)
リャンガン‐ド【両江道】
(Ryanggang-do)朝鮮民主主義人民共和国北部の内陸の道。1949年咸鏡南道から分離して設置。北は豆満江・鴨緑江を隔てて中国と接する。林産資源に富む。道都は恵山ヘサン。→朝鮮(図)
りゃん‐こ【両個】
(リャンは唐音)
①2個。二つ。
②(両刀を佩おびたからいう)武士をあざけっていう語。りゃん。花暦八笑人「何処の侍か知らねえが、しかつべらしい―が腰をかけて居る」
りゅう【六】リウ
(唐音)清楽しんがくの音譜、または拳けんで、数の「6」をいう語。むつ。浮世風呂3「―や五ごうやと、ヤの字を付けるのがや拳さ」
りゅう【柳】リウ
二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざに当たる。柳宿。ぬりこぼし。
りゅう【流】リウ
(呉音はル)
①ながれること。ながすこと。ながれ。謡曲、安宅「面白や、山水に杯を浮かめては、―に牽かるる曲水の」
②血筋。系統。学術・芸能などで、その人・家の特有な方式。固有なやり方。「御家―」
③仲間。たぐい。社会の階層。「二―」
④(「旒」の通用字)旗を数える語。
→る(流)
りゅう【留】リウ
(呉音はル)〔天〕惑星が天球上で順行と逆行との境目に一時停って見える現象。また、その時刻・位置。
りゅう【竜】
(慣用音。漢音はリョウ)
①想像上の動物。たつ。
㋐〔仏〕(梵語nāga)インド神話で、蛇を神格化した人面蛇身の半神。大海や地底に住し、雲雨を自在に支配する力を持つとされる。仏教では古くから仏伝に現れ、また仏法守護の天竜八部衆の一つとされた。
㋑中国で、神霊視される鱗虫の長。鳳ほう・麟りん・亀きとともに四瑞の一つ。よく雲を起こし雨を呼ぶという。竹取物語「はやても―の吹かする也」
㋒ドラゴンのこと。
②化石時代の、大形の爬虫類を表す語。「首長―」
③すぐれた人物のたとえ。
④天子に関する物事に冠する語。
⑤将棋で、飛車の成ったもの。
⇒竜吟ずれば雲起こる
⇒竜の雲を得る如し
⇒竜の髭を蟻がねらう
⇒竜は一寸にして昇天の気あり
りゅう【粒】リフ
つぶ。穀物の種子。小さな固体。また、それを数える語。
りゅう【笠】リフ
姓氏の一つ。
⇒りゅう‐しんたろう【笠信太郎】
⇒りゅう‐ちしゅう【笠智衆】
りゅう【硫】リウ
①非金属元素の一つ。いおう。
②硫酸の略。
り‐ゆう【理由】‥イウ
①物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
②〔哲〕一般には存在や生成の根拠となるもの。論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。↔帰結。
⇒りゆう‐の‐げんり【理由の原理】
りゅう‐あ【流亜】リウ‥
(→)亜流ありゅうに同じ。
りゅう‐あん【硫安】リウ‥
(→)硫酸アンモニウムの俗称。重要な窒素肥料の一つ。
りゅう‐あん【劉安】リウ‥
漢の学者。高祖劉邦の孫。淮南わいなん王に封じられ、のち謀叛を企て自殺。編著「淮南子えなんじ」。( 〜前122)
りゅう‐あん【劉晏】リウ‥
唐の政治家。河北南華の人。安史の乱後、塩の専売業によって財政再建に尽くし、宰相。(715頃〜780)
りゅうあん‐かめい【柳暗花明】リウ‥クワ‥
①柳は繁って暗く、花は咲いて明るいこと。春の野の美しいながめ。
②転じて、花柳街。色町。色里。
りゅうあん‐じ【竜安寺】
⇒りょうあんじ
りゅう‐い【留意】リウ‥
ある物事に心を留めること。気をつけること。注意。「服装に―する」「―点」
りゅう‐いき【流域】リウヰキ
河川の流れ行く地域。また、その河川の四囲にある分水界によって囲まれた区域。「信濃川の―」
りゅう‐いちょう【劉以鬯】リウ‥チヤウ
(Liu Yichang)香港の作家。本名、劉同繹。代表作「酒徒」は意識の流れの手法で売文業暮しの文化人の苦悩と孤独を描く。(1918〜)
りゅう‐いん【溜飲】リウ‥
胃の具合が悪く、酸性のおくびを生ずること。胸焼け。浮世風呂前「五十韻百韻などとくると、―で又わざをなすて」
⇒溜飲が下がる
 リャマ
提供:東京動物園協会
リャマ
提供:東京動物園協会
 リヤル【riyal】
サウジ‐アラビアの貨幣単位。1リヤルは20クルーシュ(qurush)。
りゃん【両】
(唐音)
①数の「2」。特に拳けんでの呼称。
②(→)両個りゃんこ2の略。
→りょう(両)
リャンガン‐ド【両江道】
(Ryanggang-do)朝鮮民主主義人民共和国北部の内陸の道。1949年咸鏡南道から分離して設置。北は豆満江・鴨緑江を隔てて中国と接する。林産資源に富む。道都は恵山ヘサン。→朝鮮(図)
りゃん‐こ【両個】
(リャンは唐音)
①2個。二つ。
②(両刀を佩おびたからいう)武士をあざけっていう語。りゃん。花暦八笑人「何処の侍か知らねえが、しかつべらしい―が腰をかけて居る」
りゅう【六】リウ
(唐音)清楽しんがくの音譜、または拳けんで、数の「6」をいう語。むつ。浮世風呂3「―や五ごうやと、ヤの字を付けるのがや拳さ」
りゅう【柳】リウ
二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざに当たる。柳宿。ぬりこぼし。
りゅう【流】リウ
(呉音はル)
①ながれること。ながすこと。ながれ。謡曲、安宅「面白や、山水に杯を浮かめては、―に牽かるる曲水の」
②血筋。系統。学術・芸能などで、その人・家の特有な方式。固有なやり方。「御家―」
③仲間。たぐい。社会の階層。「二―」
④(「旒」の通用字)旗を数える語。
→る(流)
りゅう【留】リウ
(呉音はル)〔天〕惑星が天球上で順行と逆行との境目に一時停って見える現象。また、その時刻・位置。
りゅう【竜】
(慣用音。漢音はリョウ)
①想像上の動物。たつ。
㋐〔仏〕(梵語nāga)インド神話で、蛇を神格化した人面蛇身の半神。大海や地底に住し、雲雨を自在に支配する力を持つとされる。仏教では古くから仏伝に現れ、また仏法守護の天竜八部衆の一つとされた。
㋑中国で、神霊視される鱗虫の長。鳳ほう・麟りん・亀きとともに四瑞の一つ。よく雲を起こし雨を呼ぶという。竹取物語「はやても―の吹かする也」
㋒ドラゴンのこと。
②化石時代の、大形の爬虫類を表す語。「首長―」
③すぐれた人物のたとえ。
④天子に関する物事に冠する語。
⑤将棋で、飛車の成ったもの。
⇒竜吟ずれば雲起こる
⇒竜の雲を得る如し
⇒竜の髭を蟻がねらう
⇒竜は一寸にして昇天の気あり
りゅう【粒】リフ
つぶ。穀物の種子。小さな固体。また、それを数える語。
りゅう【笠】リフ
姓氏の一つ。
⇒りゅう‐しんたろう【笠信太郎】
⇒りゅう‐ちしゅう【笠智衆】
りゅう【硫】リウ
①非金属元素の一つ。いおう。
②硫酸の略。
り‐ゆう【理由】‥イウ
①物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
②〔哲〕一般には存在や生成の根拠となるもの。論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。↔帰結。
⇒りゆう‐の‐げんり【理由の原理】
りゅう‐あ【流亜】リウ‥
(→)亜流ありゅうに同じ。
りゅう‐あん【硫安】リウ‥
(→)硫酸アンモニウムの俗称。重要な窒素肥料の一つ。
りゅう‐あん【劉安】リウ‥
漢の学者。高祖劉邦の孫。淮南わいなん王に封じられ、のち謀叛を企て自殺。編著「淮南子えなんじ」。( 〜前122)
りゅう‐あん【劉晏】リウ‥
唐の政治家。河北南華の人。安史の乱後、塩の専売業によって財政再建に尽くし、宰相。(715頃〜780)
りゅうあん‐かめい【柳暗花明】リウ‥クワ‥
①柳は繁って暗く、花は咲いて明るいこと。春の野の美しいながめ。
②転じて、花柳街。色町。色里。
りゅうあん‐じ【竜安寺】
⇒りょうあんじ
りゅう‐い【留意】リウ‥
ある物事に心を留めること。気をつけること。注意。「服装に―する」「―点」
りゅう‐いき【流域】リウヰキ
河川の流れ行く地域。また、その河川の四囲にある分水界によって囲まれた区域。「信濃川の―」
りゅう‐いちょう【劉以鬯】リウ‥チヤウ
(Liu Yichang)香港の作家。本名、劉同繹。代表作「酒徒」は意識の流れの手法で売文業暮しの文化人の苦悩と孤独を描く。(1918〜)
りゅう‐いん【溜飲】リウ‥
胃の具合が悪く、酸性のおくびを生ずること。胸焼け。浮世風呂前「五十韻百韻などとくると、―で又わざをなすて」
⇒溜飲が下がる
リヤル【riyal】
サウジ‐アラビアの貨幣単位。1リヤルは20クルーシュ(qurush)。
りゃん【両】
(唐音)
①数の「2」。特に拳けんでの呼称。
②(→)両個りゃんこ2の略。
→りょう(両)
リャンガン‐ド【両江道】
(Ryanggang-do)朝鮮民主主義人民共和国北部の内陸の道。1949年咸鏡南道から分離して設置。北は豆満江・鴨緑江を隔てて中国と接する。林産資源に富む。道都は恵山ヘサン。→朝鮮(図)
りゃん‐こ【両個】
(リャンは唐音)
①2個。二つ。
②(両刀を佩おびたからいう)武士をあざけっていう語。りゃん。花暦八笑人「何処の侍か知らねえが、しかつべらしい―が腰をかけて居る」
りゅう【六】リウ
(唐音)清楽しんがくの音譜、または拳けんで、数の「6」をいう語。むつ。浮世風呂3「―や五ごうやと、ヤの字を付けるのがや拳さ」
りゅう【柳】リウ
二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざに当たる。柳宿。ぬりこぼし。
りゅう【流】リウ
(呉音はル)
①ながれること。ながすこと。ながれ。謡曲、安宅「面白や、山水に杯を浮かめては、―に牽かるる曲水の」
②血筋。系統。学術・芸能などで、その人・家の特有な方式。固有なやり方。「御家―」
③仲間。たぐい。社会の階層。「二―」
④(「旒」の通用字)旗を数える語。
→る(流)
りゅう【留】リウ
(呉音はル)〔天〕惑星が天球上で順行と逆行との境目に一時停って見える現象。また、その時刻・位置。
りゅう【竜】
(慣用音。漢音はリョウ)
①想像上の動物。たつ。
㋐〔仏〕(梵語nāga)インド神話で、蛇を神格化した人面蛇身の半神。大海や地底に住し、雲雨を自在に支配する力を持つとされる。仏教では古くから仏伝に現れ、また仏法守護の天竜八部衆の一つとされた。
㋑中国で、神霊視される鱗虫の長。鳳ほう・麟りん・亀きとともに四瑞の一つ。よく雲を起こし雨を呼ぶという。竹取物語「はやても―の吹かする也」
㋒ドラゴンのこと。
②化石時代の、大形の爬虫類を表す語。「首長―」
③すぐれた人物のたとえ。
④天子に関する物事に冠する語。
⑤将棋で、飛車の成ったもの。
⇒竜吟ずれば雲起こる
⇒竜の雲を得る如し
⇒竜の髭を蟻がねらう
⇒竜は一寸にして昇天の気あり
りゅう【粒】リフ
つぶ。穀物の種子。小さな固体。また、それを数える語。
りゅう【笠】リフ
姓氏の一つ。
⇒りゅう‐しんたろう【笠信太郎】
⇒りゅう‐ちしゅう【笠智衆】
りゅう【硫】リウ
①非金属元素の一つ。いおう。
②硫酸の略。
り‐ゆう【理由】‥イウ
①物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
②〔哲〕一般には存在や生成の根拠となるもの。論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。↔帰結。
⇒りゆう‐の‐げんり【理由の原理】
りゅう‐あ【流亜】リウ‥
(→)亜流ありゅうに同じ。
りゅう‐あん【硫安】リウ‥
(→)硫酸アンモニウムの俗称。重要な窒素肥料の一つ。
りゅう‐あん【劉安】リウ‥
漢の学者。高祖劉邦の孫。淮南わいなん王に封じられ、のち謀叛を企て自殺。編著「淮南子えなんじ」。( 〜前122)
りゅう‐あん【劉晏】リウ‥
唐の政治家。河北南華の人。安史の乱後、塩の専売業によって財政再建に尽くし、宰相。(715頃〜780)
りゅうあん‐かめい【柳暗花明】リウ‥クワ‥
①柳は繁って暗く、花は咲いて明るいこと。春の野の美しいながめ。
②転じて、花柳街。色町。色里。
りゅうあん‐じ【竜安寺】
⇒りょうあんじ
りゅう‐い【留意】リウ‥
ある物事に心を留めること。気をつけること。注意。「服装に―する」「―点」
りゅう‐いき【流域】リウヰキ
河川の流れ行く地域。また、その河川の四囲にある分水界によって囲まれた区域。「信濃川の―」
りゅう‐いちょう【劉以鬯】リウ‥チヤウ
(Liu Yichang)香港の作家。本名、劉同繹。代表作「酒徒」は意識の流れの手法で売文業暮しの文化人の苦悩と孤独を描く。(1918〜)
りゅう‐いん【溜飲】リウ‥
胃の具合が悪く、酸性のおくびを生ずること。胸焼け。浮世風呂前「五十韻百韻などとくると、―で又わざをなすて」
⇒溜飲が下がる
○理を曲げるりをまげる🔗⭐🔉
○理を曲げるりをまげる
道理のある正しいことを無理に誤りとする。
⇒り【理】
○理を以て非に落ちるりをもってひにおちる🔗⭐🔉
○理を以て非に落ちるりをもってひにおちる
「理に勝って非に落ちる」と同意。狂言、右近左近おこさこ「惣て公事と申物は、いひ様に依て―物で御座る」
⇒り【理】
○理を分けるりをわける🔗⭐🔉
○理を分けるりをわける
筋道を立てて道理を説明する。
⇒り【理】
りん【厘】
①貨幣の単位。円の1000分の1。銭の10分の1。
②尺度の単位。尺の1000分の1。
③目方の単位。貫の10万分の1。
④1の100分の1。
⑤歩合・利率等の単位。1割の100分の1。
りん【淋】
(「痳」の通用字)性病の一つ。
りん【鈴】
①何かの合図に振ったりして鳴らすすず。
②ベル。また、その音。「電話の―が鳴る」
③読経のときなどにたたく小さな椀形の仏具。れい。→れい(鈴)
りん【綸】
印のひも。また、太い糸。
りん【輪】
①車のわ。わ状のもの。また、それを数える語。「四―駆動」
②二輪車の略。「駐―場」
③〔仏〕(→)輪宝りんぼうに同じ。
④襟・袖または裾などに別のきれでへりを取ったもの。平家物語4「大臣おとどの指貫の左の―」
⑤花の大きさ。また、花を数える語。「梅一―一―程のあたたかさ」(嵐雪)
りん【燐・リン】
(phosphorus)窒素族元素の一種。元素記号P 原子番号15。原子量30.97。単体として天然に産することなく、燐酸塩、殊に燐酸カルシウムとなって鉱物界に存在し、また、動植物の体内にも含まれている。淡黄色・半透明・蝋ろう状の同素体を黄燐という。常温では徐々に酸化されて暗所で青白色の微光を放ち、50度になれば発火する。空気の供給を絶って熱すると赤燐になる。主な用途はマッチ・農薬・燐化合物の製造など。→黄燐→赤燐
りん【隣】
となり。となりあうこと。「徳孤ならず必ず―あり」
りんあん【臨安】
南宋の首都。今の浙江省杭州市。1129年臨安府と改称。臨時の都という意味で、「行在あんざい」とも称した。
りん‐いん【廩院】‥ヰン
平安時代、田租や庸の米を収蔵した、民部省の倉庫。
りん‐う【霖雨】
幾日も降りつづく雨。ながあめ。淫雨。
りんうち‐どけい【鈴打時計】
鈴りんが時を打つ仕掛けの時計。自鳴鐘。
りん‐うん【鱗雲】
うろこ状の雲。うろこぐも。いわしぐも。
りん‐えん【林縁】
森林の周縁部分。
りん‐おう【輪王】‥ワウ
(→)転輪王に同じ。
りん‐か【林下】
禅の修行道場のこと。また日本の禅宗で、五山の系統に入らない寺院。叢林下。沙石集序「―の貧士無住」
りん‐か【林家】
①林業を営む世帯。ふつう10アール以上の林地をもつもの。
②⇒りんけ
りん‐か【輪禍】‥クワ
電車・自動車などに、ひかれたりはねられたりする災難。
りん‐か【燐火】‥クワ
墓地・沼沢などの陰湿の地に自然に発生する青白い火光。おにび。きつねび。ひだま。
りん‐か【隣家】
となりのいえ。
りんか【臨夏】
(Linxia)中国甘粛省西南部の都市。旧称、河州。黄土高原と青蔵高原が接する位置にあり、古くから交易が盛ん。人口20万2千(2000)。
りんが【林歌・臨河】
雅楽。高麗楽こまがくでは高麗平調こまひょうじょうに属する舞楽曲。四人舞。唐楽では平調に属する管弦曲。
りん‐が【臨画】‥グワ
手本を見て絵を習うこと。また、その絵。↔自由画
りん‐が【臨臥】‥グワ
就寝の時刻。〈日葡辞書〉
りん‐が【鱗芽】
オニユリやヤマノイモなどにある腋芽で、養分を蓄えて肥厚し、地に落ちて発芽繁殖するもの。
リンガ【liṅga 梵】
インドのヒンドゥー教で崇拝される男根形の石柱。シヴァ祠に祀られる。シヴァ神の象徴。陽石。
リンガー‐えき【リンガー液】
⇒リンゲルえき
リンカーン【Abraham Lincoln】
アメリカ合衆国第16代大統領(1861〜1865)。共和党出身。ケンタッキー州生れ。初め弁護士。1863年南北戦争下に奴隷解放を宣言、64年再選。翌年南部人によって暗殺された。「人民の人民による人民のための政治」という民主主義の理念を説いたことで著名。リンカン。(1809〜1865)
りん‐かい【臨海】
海にのぞむこと。海辺にあること。
⇒りんかい‐がっこう【臨海学校】
⇒りんかい‐こうぎょう‐ちたい【臨海工業地帯】
⇒りんかい‐じっけんしょ【臨海実験所】
りん‐かい【臨界】
①さかい。境界。
②〔理〕物理的性質が不連続的に変わる境界。特に原子炉で、核分裂連鎖反応が一定の割合で維持されている状態。
⇒りんかい‐あつりょく【臨界圧力】
⇒りんかい‐おんど【臨界温度】
⇒りんかい‐かく【臨界角】
⇒りんかい‐げんしょう【臨界現象】
⇒りんかい‐じょうたい【臨界状態】
⇒りんかい‐てん【臨界点】
⇒りんかい‐りょう【臨界量】
りん‐かい【鱗介】
魚類と貝類。魚介。
りんかい‐あつりょく【臨界圧力】
臨界温度で気体に圧力を加えていく時、その気体が初めて液化する際の圧力。臨界圧。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐ウラン‐せき【燐灰ウラン石】‥クワイ‥
カルシウム・ウランを含む燐酸塩鉱物。黄色から黄緑色を呈し、鱗片状の集合体をつくる。ウラン鉱床から産出。
りんかい‐おんど【臨界温度】‥ヲン‥
①臨界における温度。
②㋐圧縮によって気体を液化する場合、ある温度以下でないと圧力をいかに大きくしても液体にならない。この限界の温度をいう。空気の臨界温度は約セ氏マイナス141度。
㋑超伝導体で、超伝導状態が破れて常伝導状態に転移する温度。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐かく【臨界角】
光線が屈折率の大きい物質から小さい物質に進む場合に、それ以上では全反射を起こすような入射角の値。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐がっこう【臨海学校】‥ガクカウ
夏期に海辺で、健康の増進、水泳訓練、その他特別の教育計画のもとに開設される教育プログラム、およびそのための施設。
⇒りん‐かい【臨海】
りんかい‐げんしょう【臨界現象】‥シヤウ
巨視的な物理系の性質が、ある温度を境に不連続的に変わること。また、その近辺で起こるさまざまな異常現象。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐こうぎょう‐ちたい【臨海工業地帯】‥ゲフ‥
海に面して発達した工業地帯。日本では主に、原料輸送、工場用地取得の条件などによって精油・石油化学・製鉄・造船・電力などの大工場を中心に形成される。↔内陸工業地帯。
⇒りん‐かい【臨海】
りんかい‐じっけんしょ【臨海実験所】
海産動植物の研究のため、臨海地につくられた実験所。日本では、1886年(明治19)三浦半島の三崎町に東京帝国大学付属臨海実験所を初めて設置。
⇒りん‐かい【臨海】
りんかい‐じょうたい【臨界状態】‥ジヤウ‥
①臨界に達した状態。
②臨界温度・臨界圧力における物質の状態。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐せき【燐灰石】‥クワイ‥
フッ素・塩素・水酸基を含むカルシウムの燐酸塩鉱物の一群。六方晶系で、柱状・板状あるいは稀に塊状。無色透明であるが、時に淡青色・黄色を帯び、ガラス光沢をもつ。火成岩中に産出するほか、ペグマタイトや変成岩中にも多い。燐酸肥料のほか、クリーム・歯磨原料となる。
燐灰石
撮影:松原 聰
 りんかい‐てん【臨界点】
気体の液化が起こる最高の温度・圧力の点。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐ど【燐灰土】‥クワイ‥
燐酸石灰に不純物が混じった白色または灰褐色の土。脊椎動物の骨格・排泄物などが堆積したもの。リン分の多いものは人造肥料の原料となる。能登・小笠原諸島に産。また、塊状の燐灰石。
りんかい‐りょう【臨界量】‥リヤウ
核分裂反応で、臨界状態における核燃料の量。
⇒りん‐かい【臨界】
りん‐かく【輪郭・輪廓】‥クワク
①物の外形を形づくっている線。「顔の―」
②物事の概観。概要。アウトライン。「話の―」
りん‐かく【麟角】
麒麟きりんのつの。きわめてまれな物事にたとえていう語。太平記39「撓たわまざる志は―よりも稀なり」
りん‐がく【林学】
森林および林業に関する技術や経済を研究する学問。森林科学。
りん‐がく【臨岳】
琴きんの首部の称。↔焦尾
りんか‐ぼん【輪花盆】‥クワ‥
車輪のような平らな花形にかたどった朱漆塗の盆。
輪花盆
りんかい‐てん【臨界点】
気体の液化が起こる最高の温度・圧力の点。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐ど【燐灰土】‥クワイ‥
燐酸石灰に不純物が混じった白色または灰褐色の土。脊椎動物の骨格・排泄物などが堆積したもの。リン分の多いものは人造肥料の原料となる。能登・小笠原諸島に産。また、塊状の燐灰石。
りんかい‐りょう【臨界量】‥リヤウ
核分裂反応で、臨界状態における核燃料の量。
⇒りん‐かい【臨界】
りん‐かく【輪郭・輪廓】‥クワク
①物の外形を形づくっている線。「顔の―」
②物事の概観。概要。アウトライン。「話の―」
りん‐かく【麟角】
麒麟きりんのつの。きわめてまれな物事にたとえていう語。太平記39「撓たわまざる志は―よりも稀なり」
りん‐がく【林学】
森林および林業に関する技術や経済を研究する学問。森林科学。
りん‐がく【臨岳】
琴きんの首部の称。↔焦尾
りんか‐ぼん【輪花盆】‥クワ‥
車輪のような平らな花形にかたどった朱漆塗の盆。
輪花盆
 りん‐かん【林冠】‥クワン
森林で樹冠が連続している部分。
りん‐かん【林間】
はやしのあいだ。林中。
⇒りんかん‐がっこう【林間学校】
⇒林間に酒を煖めて紅葉を焼く
りん‐かん【輪奐】‥クワン
(「輪」は曲折して広大の意、「奐」は大きく盛んの意)建物の広大・壮麗なこと。「―の美」
りん‐かん【輪姦】
多人数の男が次々に一人の女を強姦すること。念仏講。
りん‐かん【臨監】
その場に臨んで、監督・監視をすること。また、その人。「―の警官が演説を制止する」
りんかん‐がっこう【林間学校】‥ガクカウ
主として夏期に、健康の増進、自主活動その他特別の教育計画のもとに、高原などで実施される教育プログラムおよびそのための施設。
⇒りん‐かん【林間】
りん‐かん【林冠】‥クワン
森林で樹冠が連続している部分。
りん‐かん【林間】
はやしのあいだ。林中。
⇒りんかん‐がっこう【林間学校】
⇒林間に酒を煖めて紅葉を焼く
りん‐かん【輪奐】‥クワン
(「輪」は曲折して広大の意、「奐」は大きく盛んの意)建物の広大・壮麗なこと。「―の美」
りん‐かん【輪姦】
多人数の男が次々に一人の女を強姦すること。念仏講。
りん‐かん【臨監】
その場に臨んで、監督・監視をすること。また、その人。「―の警官が演説を制止する」
りんかん‐がっこう【林間学校】‥ガクカウ
主として夏期に、健康の増進、自主活動その他特別の教育計画のもとに、高原などで実施される教育プログラムおよびそのための施設。
⇒りん‐かん【林間】
 りんかい‐てん【臨界点】
気体の液化が起こる最高の温度・圧力の点。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐ど【燐灰土】‥クワイ‥
燐酸石灰に不純物が混じった白色または灰褐色の土。脊椎動物の骨格・排泄物などが堆積したもの。リン分の多いものは人造肥料の原料となる。能登・小笠原諸島に産。また、塊状の燐灰石。
りんかい‐りょう【臨界量】‥リヤウ
核分裂反応で、臨界状態における核燃料の量。
⇒りん‐かい【臨界】
りん‐かく【輪郭・輪廓】‥クワク
①物の外形を形づくっている線。「顔の―」
②物事の概観。概要。アウトライン。「話の―」
りん‐かく【麟角】
麒麟きりんのつの。きわめてまれな物事にたとえていう語。太平記39「撓たわまざる志は―よりも稀なり」
りん‐がく【林学】
森林および林業に関する技術や経済を研究する学問。森林科学。
りん‐がく【臨岳】
琴きんの首部の称。↔焦尾
りんか‐ぼん【輪花盆】‥クワ‥
車輪のような平らな花形にかたどった朱漆塗の盆。
輪花盆
りんかい‐てん【臨界点】
気体の液化が起こる最高の温度・圧力の点。
⇒りん‐かい【臨界】
りんかい‐ど【燐灰土】‥クワイ‥
燐酸石灰に不純物が混じった白色または灰褐色の土。脊椎動物の骨格・排泄物などが堆積したもの。リン分の多いものは人造肥料の原料となる。能登・小笠原諸島に産。また、塊状の燐灰石。
りんかい‐りょう【臨界量】‥リヤウ
核分裂反応で、臨界状態における核燃料の量。
⇒りん‐かい【臨界】
りん‐かく【輪郭・輪廓】‥クワク
①物の外形を形づくっている線。「顔の―」
②物事の概観。概要。アウトライン。「話の―」
りん‐かく【麟角】
麒麟きりんのつの。きわめてまれな物事にたとえていう語。太平記39「撓たわまざる志は―よりも稀なり」
りん‐がく【林学】
森林および林業に関する技術や経済を研究する学問。森林科学。
りん‐がく【臨岳】
琴きんの首部の称。↔焦尾
りんか‐ぼん【輪花盆】‥クワ‥
車輪のような平らな花形にかたどった朱漆塗の盆。
輪花盆
 りん‐かん【林冠】‥クワン
森林で樹冠が連続している部分。
りん‐かん【林間】
はやしのあいだ。林中。
⇒りんかん‐がっこう【林間学校】
⇒林間に酒を煖めて紅葉を焼く
りん‐かん【輪奐】‥クワン
(「輪」は曲折して広大の意、「奐」は大きく盛んの意)建物の広大・壮麗なこと。「―の美」
りん‐かん【輪姦】
多人数の男が次々に一人の女を強姦すること。念仏講。
りん‐かん【臨監】
その場に臨んで、監督・監視をすること。また、その人。「―の警官が演説を制止する」
りんかん‐がっこう【林間学校】‥ガクカウ
主として夏期に、健康の増進、自主活動その他特別の教育計画のもとに、高原などで実施される教育プログラムおよびそのための施設。
⇒りん‐かん【林間】
りん‐かん【林冠】‥クワン
森林で樹冠が連続している部分。
りん‐かん【林間】
はやしのあいだ。林中。
⇒りんかん‐がっこう【林間学校】
⇒林間に酒を煖めて紅葉を焼く
りん‐かん【輪奐】‥クワン
(「輪」は曲折して広大の意、「奐」は大きく盛んの意)建物の広大・壮麗なこと。「―の美」
りん‐かん【輪姦】
多人数の男が次々に一人の女を強姦すること。念仏講。
りん‐かん【臨監】
その場に臨んで、監督・監視をすること。また、その人。「―の警官が演説を制止する」
りんかん‐がっこう【林間学校】‥ガクカウ
主として夏期に、健康の増進、自主活動その他特別の教育計画のもとに、高原などで実施される教育プログラムおよびそのための施設。
⇒りん‐かん【林間】
○理を言うわりをいう🔗⭐🔉
○理を言うわりをいう
道理を言う。理屈を言う。弁解する。不平を言う。誹風柳多留3「もてぬやつ舟宿へ来てわりを言ひ」
⇒わり【理】
[漢]理🔗⭐🔉
理 字形
 筆順
筆順
 〔玉(王)部7画/11画/教育/4593・4D7D〕
〔音〕リ(呉)(漢)
〔訓〕おさめる・ことわり (名)おさむ・まさ
[意味]
①すじ。すじめ。
㋐物の表面に見えるすじ。きめ。「木理・肌理きり・節理」
㋑物事のすじみち。ことわり。「理の当然」「理が非でも」(ぜひとも)「理論・理由・道理・条理・物理」
②物事のすじをたてる。ただす。おさめる。ととのえる。「理事・理財・管理・料理・修理・理髪」
③宇宙の根源的本性。「理学・理気二元論」▶中国哲学で用いる概念。
④「物理学」の略。広く、自然科学系の学問。「理化学・文理学部・理科」
[解字]
形声。「玉」+音符「里」(=すじめをつけた土地)。玉の表面に見えるすじめの意。
[下ツキ
一理・学理・監理・管理・逆理・究理・窮理・教理・肌理・義理・空理・経理・計理・原理・公理・合理・実理・修理・受理・掌理・情理・条理・処理・至理・事理・審理・心理・真理・推理・数理・性理・整理・生理・税理士・摂理・節理・総理・代理・大理石・調理・地理・定理・哲理・天理・董理・道理・悖理・背理・病理・非理・物理・辧理・弁理・法理・妙理・無理・木理・薬理・有理・料理・倫理・連理・論理
〔玉(王)部7画/11画/教育/4593・4D7D〕
〔音〕リ(呉)(漢)
〔訓〕おさめる・ことわり (名)おさむ・まさ
[意味]
①すじ。すじめ。
㋐物の表面に見えるすじ。きめ。「木理・肌理きり・節理」
㋑物事のすじみち。ことわり。「理の当然」「理が非でも」(ぜひとも)「理論・理由・道理・条理・物理」
②物事のすじをたてる。ただす。おさめる。ととのえる。「理事・理財・管理・料理・修理・理髪」
③宇宙の根源的本性。「理学・理気二元論」▶中国哲学で用いる概念。
④「物理学」の略。広く、自然科学系の学問。「理化学・文理学部・理科」
[解字]
形声。「玉」+音符「里」(=すじめをつけた土地)。玉の表面に見えるすじめの意。
[下ツキ
一理・学理・監理・管理・逆理・究理・窮理・教理・肌理・義理・空理・経理・計理・原理・公理・合理・実理・修理・受理・掌理・情理・条理・処理・至理・事理・審理・心理・真理・推理・数理・性理・整理・生理・税理士・摂理・節理・総理・代理・大理石・調理・地理・定理・哲理・天理・董理・道理・悖理・背理・病理・非理・物理・辧理・弁理・法理・妙理・無理・木理・薬理・有理・料理・倫理・連理・論理
 筆順
筆順
 〔玉(王)部7画/11画/教育/4593・4D7D〕
〔音〕リ(呉)(漢)
〔訓〕おさめる・ことわり (名)おさむ・まさ
[意味]
①すじ。すじめ。
㋐物の表面に見えるすじ。きめ。「木理・肌理きり・節理」
㋑物事のすじみち。ことわり。「理の当然」「理が非でも」(ぜひとも)「理論・理由・道理・条理・物理」
②物事のすじをたてる。ただす。おさめる。ととのえる。「理事・理財・管理・料理・修理・理髪」
③宇宙の根源的本性。「理学・理気二元論」▶中国哲学で用いる概念。
④「物理学」の略。広く、自然科学系の学問。「理化学・文理学部・理科」
[解字]
形声。「玉」+音符「里」(=すじめをつけた土地)。玉の表面に見えるすじめの意。
[下ツキ
一理・学理・監理・管理・逆理・究理・窮理・教理・肌理・義理・空理・経理・計理・原理・公理・合理・実理・修理・受理・掌理・情理・条理・処理・至理・事理・審理・心理・真理・推理・数理・性理・整理・生理・税理士・摂理・節理・総理・代理・大理石・調理・地理・定理・哲理・天理・董理・道理・悖理・背理・病理・非理・物理・辧理・弁理・法理・妙理・無理・木理・薬理・有理・料理・倫理・連理・論理
〔玉(王)部7画/11画/教育/4593・4D7D〕
〔音〕リ(呉)(漢)
〔訓〕おさめる・ことわり (名)おさむ・まさ
[意味]
①すじ。すじめ。
㋐物の表面に見えるすじ。きめ。「木理・肌理きり・節理」
㋑物事のすじみち。ことわり。「理の当然」「理が非でも」(ぜひとも)「理論・理由・道理・条理・物理」
②物事のすじをたてる。ただす。おさめる。ととのえる。「理事・理財・管理・料理・修理・理髪」
③宇宙の根源的本性。「理学・理気二元論」▶中国哲学で用いる概念。
④「物理学」の略。広く、自然科学系の学問。「理化学・文理学部・理科」
[解字]
形声。「玉」+音符「里」(=すじめをつけた土地)。玉の表面に見えるすじめの意。
[下ツキ
一理・学理・監理・管理・逆理・究理・窮理・教理・肌理・義理・空理・経理・計理・原理・公理・合理・実理・修理・受理・掌理・情理・条理・処理・至理・事理・審理・心理・真理・推理・数理・性理・整理・生理・税理士・摂理・節理・総理・代理・大理石・調理・地理・定理・哲理・天理・董理・道理・悖理・背理・病理・非理・物理・辧理・弁理・法理・妙理・無理・木理・薬理・有理・料理・倫理・連理・論理
広辞苑に「理」で始まるの検索結果 1-84。もっと読み込む